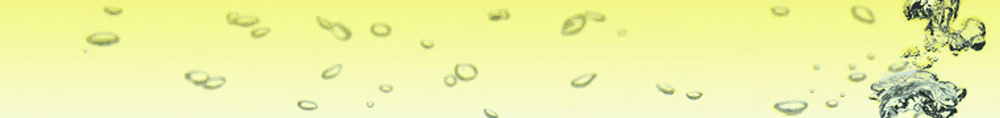BLACK POST 3
「秋。」
秋はこっちを向いた。目が隠れる程の長い前髪が秋の孤独感を倍にさせた。わたしは訊ねた。
「友達の様子は?」
「・・・・・死んだ。」
秋は冷たい声で答えた。その目は涙で輝いていた。わたしはその言葉を聞いたとき、驚きはしなかった。なんとなく予感していたからだ。
「死因は頭部の強打だってよ・・・。」
・・・・兄と同じ死因だ。そう思った。秋はその言葉が嫌なのかもしれない。秋だって兄の死因ぐらいわかっている。わたしがそう思っていると、秋はなぜか部屋に入らず、戸を閉め、その戸に頭を当てた。
「俺、あいつが落ちていくのをただ見ていただけなんだ。」
心臓が締め付けられるような激痛が走った。秋は友達が死んだのは自分のせいだと思い込んでいる。
「あいつ、ベランダの縁に座っていたんだ。俺はあいつのベッドの上に座って、話していたんだ。そしたら、急に信志が俺の近くに来いって言って、そこに行ったらあいつは彼女の写真を見せたんだ。俺はその写真を貸してもらって見ていた。その時だった。急にあいつがバランスを崩して、そのまま落ちてしまったんだ。落ちる直前、俺は信志に話しかけようと信志を見たんだ。そしたら、あいつが落ちそうになっていて、、、普通なら手を出すだろ?でも俺は出せなかった。ただ、俺はあいつが落ちていくのを見ているだけだった。」
秋は鼻声でそう言うと部屋に入っていった。ちらりと秋の右手に小さい白い紙が見えた気がした。
その日、わたしは寝られなくて、ただ椅子に座って窓はカーテンを閉めずに、月が沈んで、太陽が昇っていくのをずっと見ていた。
秋の友達が死んだ・・・。
いつもわたしは家族や知り合いが死んでしまったのを知った日には寝られなくなってしまう。まだ二歳くらいのとき、いとこのおおばあちゃんが死んだ。おおばあちゃんはただ和室で寝かされていて、他のみんなはその隣で食事をしていた。わたしはそのおおばあちゃんの遺体を何度も見ながら、食事をしていた。たった一人ぼっちで、和室に取り残されているその姿が寂しく思えて、見ずにはいられなかった。
それから何度も死を見たことあったけど、いつも、魂が抜けた肉体がとても寂しく見える。まるで、魂に捨てられたみたいに、裏切られたみたいに・・・。
わたしはまた死に出会い、今まで見てきた死を思い出してしまって寝られなくなっている。別に死を振り返るのは怖くない。ただ、もう慣れているんだ。「死」に。
朝になった空を見た直後、わたしは眠りについた。
目を開けると、目の前に秋が立っていた。秋は背広を着、大人っぽく見えた。
「どうしたの?その格好。」
「信志の葬式に行くんだよ。」
わたしはそれを聞いた時、やっと気づいた。そうか、信志、死んでいたんだ。そして、ある言葉が喉から滑って出てきた。
「・・・わたしも行ったほうがいいかなぁ?」
秋はわたしに寂しい笑みを見せてこう言った。
「昨日、寝てないんだろ?無理しなくていいよ。」
秋はそう言うと、行ってきます。と言って出て行った。またわたしは眠気に襲われて、眠りについた。
ぼやけた空間。わたしはアパートの前にいて、アパートを見ていた。なぜかそれはぼやけて見えた。アパートだけじゃない。全部がぼやけて見える。人さえも。わたしは学校とは反対方向に歩いた。ただまっすぐに歩いた。途中、道があってもそこには行かず、ただずっとまっすぐ歩いた。十分くらいで行き止まりになった。そこには見たこともない、黒いポストがポツンと立っていた。なぜかそのポストだけはっきりと見えた。すると、そのポストの隣で黒い煙が出た。その煙が消えるとそこにはゴスファッションみたいな服を着た、十五歳くらいの少女が立っていた。その少女はこんな事を言った。
「このブラックポストは、特定の人間にしか見えないポスト。このポストを使うと、あの世に行った者と、手紙の交換が出来る。」
わたしはそれを聞いて驚いた。そんなわたしの顔を見た少女は、にやりと笑って話を続けた。
「でもね、これを使うには「条件」があるのよ。それは、じゅ・・・」
わたしは少女の話を最後まで聞くことが出来ず、気を失った。
~つづく~
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-

- 田原俊彦さん・としちゃん・トシちゃ…
- KING of IDOL 踊るパワースポット!
- (2025-10-05 15:16:43)
-
-
-

- 今日聴いた音楽
- ☆乃木坂46♪久保史緒里、エッセイ『LO…
- (2025-11-27 13:13:29)
-
© Rakuten Group, Inc.