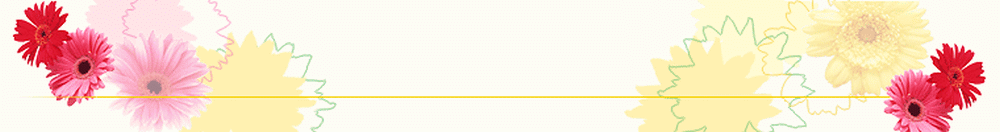論苑 その2
さて、臨終には“多年の臨終”と“刹那の臨終”とがあります。
“多年の臨終”とは、今日という日は今日一日しかない、臨終はただいまなりと思って、いついかなる時もお題目を心のなかで唱えて、精進しようとすることであります。
“刹那の臨終”とは、いわゆる命の終わる時で、これが最も肝心であります。
人間はだれしも生きているときに好きなことをやって人生を大いに謳歌し、死ぬ時にはスウッと眠るように死にたいと思っているわけであります。しかしながら、現実はそうはいきません。“臨終の一念は多年の行功”といいますように、常日ごろからの心掛けがないと、その時だけ良くなろうとしても流されてしまいます。毎日毎日の一生の行動が積もって、臨終の一念に顕われてくるのであります。
例えば、まっすぐな松の木は切る人によって、どの方向にも切り倒すことができますが、右に曲がった松の木はどこから切っても右にしか倒れません。これは外的な原因と、木そのものに右に曲がる要因を、生きているうちにもっていたからです。これは人間も同様で、その人が一生のうちにやってきた牛命が、臨終の一念になって顕われてくるのであります。
“臨終に報を受くるは強きに従って引く”といいますように、臨終に報いを受けるのは、その人の一番強い性格や癖に引っ張られていくということです。その人の癖の一番強い方向の一生を送った報い、結果が臨終の一念として顕われ、この一念が来世を決めてしまうのであります。
★ 心の乱れる原因
臨終に注意しなければならないのは心が乱れることで、これが悪い果報を得る原因となるのであります。日寛上人は『臨終用心抄』の中に、心の乱れる原因を三つ挙げておられます。即ち
一、断末魔の苦しみの故に心が乱れる
二、魔のために心が乱れる
三、執着のために心が乱れる
との三つであります。
一、の断末魔の苦しみとは、断末魔の風が体内に現われたとき、骨と肉とが離れるときの激痛であります。人間の体は五大、妙法蓮華経の五字から成っております。丁度私達の住んでいる家が柱や床や畳や板等で造られているのと同じです。人間が死ねば、体の体温が無くなって冷えるのは火大が去るからであり、何日も生身のまま放って置くと、嗅気を放って腐ってくるのは地大が去るからであり、体を切っても血が出ないのは水大の去る故であり、死んだ人の体が全く動かないのは風大が去ったからで、この四大がばらばらになるときに激痛が生じるのであります。正法念経には“臨終のときには千本の鋭い刀が身体を刺す如くである”と説かれ、このときは指一本触れただけでも大きな石が投げ置かれたように重く感じるといわれております。臨終には、人目から見てさほどでもないように思われても肉身の痛みは計り知れないものがあるとされており、このため断末魔の苦痛によって心が乱れてくるわけです。
二、に魔のために心が乱れるとは、弘安六年(一二八三年)に無住法師の著わした『沙石集』の中に
“ある山寺の法師が山を下りて世俗のなかで生活することとなり妻帯した。この僧は年をとって病気になったが妻の看病で回復し、意が落ち着いたので臨終が近いことを悟った。もうこれで最後と思い、端座合掌して西方に向かって高声に念仏を称えたところ、妻がそれを見て、私を捨てていずこへ行くのか、別れるのは悲しいと言って法師の首に抱きつきました。法師は心安らかに臨終させてくれと言って念仏を称えますと、また妻は別れるのがいやだといって首にしがみついて法師を引き倒してしまい、法師はそのまま死んでしまった”
という説話があります。臨終正念を妨げるのは魔の致すところであり、これによって、心が散乱するのであります。
三、に執着の故に心が乱れるとは、『沙石集』の中に“一生の間、五戒を持って清廉潔白に生きた在家の御主人が、妻を残して死ぬのがかわいそうになって、妻を思って死んでしまったら、奥さんの鼻の中に虫となって生まれた”と書かれております。また『致悔集』という本には“盧山寺の明道上人がお経を頭に思い浮かべて死んだら、経典の上に小蛇となって現われた”とあります。また臨終のときに花を愛した人は蝶になって生まれるとか、鳥に執着した人は畜生に生まれる等といわれております。これらはすべて説話にすぎませんが、臨終には執着心を捨て去ることを教えて、心の散乱を防ごうとしたのであります。
では、どのようにすれば心の乱れを防げるのでしょうか。日寛上人は、まず一、の断末魔による乱心を防ぐには、平生から臨終には断末魔が起こることを覚悟し、また他人を謗らず、傷つけず、つとめて善業を積み、さらに御本尊と自分は一体であると思って、信心に励むことが大切であると言われております。
二、の魔による乱心を防ぐには、平生から魔が現われることを覚悟しておく必要があります。『持病大小権実違目』に
「三障・四魔と申すは権経を行ずる行人の障りにはあらず今日蓮が時具さに起れり……御臨終の御時は御心へ有るべく候」(全集九九八p)
とあります。つまり一生涯、三障四魔が起こるから、前もって用心しておきなさいということであります。
三、の執着による乱心を防ぐには、実は執着するに値しないと考えることが、執着心をなくすことになると説かれております。ともかく、臨終には心を乱さないようにし、また乱させるような原因をつくらないようにしなければなりません。
★ 悪業を転換
さて、人間が死んだら何も来世に持っていける物はなく、すべて失ってしまいますが、それでも無くならないものがあります。それは業です。現在の果は過去の因によるのであり、未来の果は現在の因によるといわれるように、因果は三世にわたって永久に引き続いていきます。
宿業というものがありますが、私達の現在の幸、不幸は過去世の業によるものだという意味です。過去の善業があれば現在の善果があり、悪業があれば悪果があるように、業は相続されて消えることがないのであります。人が何かの理由で自殺したとしても、すべてがなくなってしまうわけではありません。私達は業から逃げられません。まじめに生きなければならないわけです。
信徒の方々が御供養を真心でされ、折伏した立派な功徳は、来世に善業として持続されてゆくのであります。“釈尊の三不能”と申しまして、万能であったはずの釈尊にも三つのできないことがありました。その一つは、釈尊は衆生の業を代わりにつぐなってあげることができないというものです。自分でしたことは何度生まれ変わってでも、自分で報いを受けなければならないのです。ですから釈尊の時代に悪業をおさえ、善業をこつこつと長い生にわたって積み重ね、成仏を願ったのであります。その点、大聖人の仏法は過去遠々劫から持続して来た悪業を、毒を変じて薬となす如く、善業に転換することができるのであります。まことに偉大な仏法であります。
★ 成仏は長年の行功
ところで、大聖人は臨終の相によって後生を知ることができると仰せになっております。『妙法尼御前御返事』に
「臨終の時色黒き者は地獄に堕つ」(全集一四〇四p)
とあります。また『千日尼御前御返事』に
「人は臨終の時地獄に堕つる者は黒色となる上其の身重き事千引の石の如し善人は設ひ七尺八尺の女人なれども色黒き者なれども臨終に色変じて白色となる又軽き事鵞毛の如しなる事兜羅緜の如し」(同一三一六p)
と仰せです。臨終に地獄に堕ちる者は黒色となり、身体は極度に重く硬くなる。しかし、妙法を信仰する人は、十方の諸仏、諸菩薩を供養する功徳と等しく、色の黒い人でも白色と変じ、身は鵞鳥の毛のように軽く、膚の軟らかさは綿のようになると説かれております。
総本山第六十世日開上人は、昭和十八年十一月二十一日に七十一歳で、蓮葉奄において御遷化されております。その相貌はたいへん立派で、顔立ちは柔和で、目鼻は端正であったため、七日間、坐棺にして居間に御安置申し上げられました。上人の仏身の相貌を拝見した人は、合掌しお題目を唱えたと聞いております。仏様の顔立ちは常に柔和であり、私達の命が尽きて成仏すれば、半眼半口の穏やかな相になるといえるわけです。
また臨終で、なかには重病にあい、苦痛のあまりお題目を唱えることができず、多少、相が悪くなるともいいますが、ひとたび妙法を真実に信じて謗法を犯さなかったならば、無量億劫にわたって地獄に堕ちることはないのであります。これを涅槃経に
「我涅槃の後、若しかくの如き大乗微妙の経典を聞くことを得、信敬の心を生ずることあらん。まさに知るべし、是等、来世百千億劫に於いて悪道に堕ちず」
とあります。また『法華経提婆達多品第十二』に
「浄心に信敬して、疑惑を生ぜざらん者は、地獄、餓鬼、畜生に堕ちずして、十方の仏前に生ぜん」(開結四二六p)
とあります。御本尊を信じ敬い疑惑を生じなければ、三悪道に堕ちることなく仏国に生まれると説かれております。『法華経題目抄』には
「只南無妙法蓮華経と計り五字七字に限りて一日に一遍一月乃至一年十年一期生の間に只一遍なんど唱えても軽重の悪に引かれずして四悪趣におもむかずついに不退の位にいたるべしや、答えて云くしかるべきなり」(全集九四〇p)
と仰せのように、ただ一遍たりとも真のお題目であれば、悪道には堕ちないと説かれております。
ともかく、人間は死ぬときは一人です。孤独です。そのときに様々な悪夢が交錯するでしょうが、信心を持っている人は、悪い相が現われても決して恐れない、喜ばしい相が現われてもうきうきせず、ただ平らな心をもって南無妙法蓮華経と唱えることが大事であります。
他宗の行者は、たとえ善相が臨終に現われても地獄に堕ちるのであります。日寛上人が
「たとい、正念称名にして死すとも、法華経謗法の大罪在る故に阿鼻獄に入る事疑いなし」
と仰せられておりますように、他宗教を信仰する人の成仏は、決して有り得ないのであります。
禅の三階禅師は声が出なくなって死に、真言の善無畏三蔵は皮膚が黒色となり、浄土の善導は転倒狂乱して死んでいったのであります。師がそうであれば、その弟子・檀那もしかるべきでありますから、臨終に弥陀の名号をいくら称えても、弥陀は迎えに来てくれません。むしろ悪趣に誘引されて苦しまなければならないのであります。
そこで、本当に仏になるためには、長年の行功によるわけです。臨終にお題目を唱えられるか唱えられないかは、常々の修行の在り方によるのであり、常々の信心の無い人はお題目を唱えられないのでありますから、必ず唱題できるように自ら常に心掛ける必要があります。
臨終のお題目は計り知れない功徳があります。これを『妙法尼御前御返事』に
「はた又法華経の名号を臨終に二反となう……しかれば故聖霊・最後臨終に南無妙法蓮華経と・となへさせ給いしかば、一生乃至無始の悪業変じて仏の種となり給う」(全集一四〇四p)
と仰せです。いかに臨終にお題目を唱えることが大切かが分かります。
★ 臨終の題目
世の中には、まだまだ浄土宗とか神道とかキリスト教とか新興宗教を信じている人が沢山おり、また無神論者もおりますから、一度や二度の折伏ではなかなか聞き入れようとはしません。しかし、この多くの人達が一度折伏を受け御本尊の偉大さを聞いていれば、臨終に苦しみのあまり、溺れた人がワラにもすがるような気持ちで、苦しいときの神頼み式に南無妙法蓮華経と唱えるかもしれません。その時では遅いのですけれども、その人達は“こんなに苦しむのなら、もっと早くから信仰していればよかった”と後悔するでしょう。その意味では折伏、下種活動は活かされてくると確信いたします。
現実に、猛烈に反対した御主人が臨終をさとり、一緒にお題目を唱えてくれと妻に頼んで安らかに息を引きとる人が多いのであります。臨終の題目がいかに大切か、そして御本尊の法力がいかに大きいかを、如実に物語るものであります。
日寛上人は『臨終用心抄』に『大智度論』を引かれ
「臨終の一念は百年の行力に勝れたり、心力決定して猛利なること火の如く毒の如し、少なりと雖も大事を成す。人の陣に入りて身命を惜まざるを名て健と為すが如し」
とあります。百年の修行より臨終の一念は真剣であり、勝れております。ですから臨終にお題目を唱えられない人は、まことに哀れな人です。百年ぐらいの長い修行があって、常々信心に励んでいるからこそ、臨終にお題目を唱えることができるのです。その題目だから尊いのであります。
これは、小火であっても大きな被害をもたらし、わずかな毒であっても生きものを殺すほどの力があるように、また戦で豪傑が身命を惜しまず戦うように、この強烈な一念は、臨終の一念の信力と同じで、百年の修行にも越えていきます。信力が深まれば深まるほど、仏力、法力がますます強くなって行者を成仏に導くのであります。
それは丁度、昔、火打ち石と火打金とを打ち合わせて生じた火を、火口で移して役立てた如く、信力と仏力、法力が具わって成仏が可能になるのです。『四条金吾殿御返事』に
「いかに日蓮いのり申すとも不信ならばぬれたる・ほくちに・火をうちかくるが・ごとくなるべし」(全集一一九一p)
と仰せです。ともかく、火口のぬれた信心のない人は、どうしようもありません。
例えば、乾電池には電気が充電され、豆電球があっても、これをつなぐ銅線がなければ電気はつきません。どんなに勝れた法があっても、信心がなければ意味がないのです。逆に線があっても球が切れ、電池が空っぽであれば電気はつきません。どんなに強盛な信心を興しても、法と仏に力がなければ無意味な信心であります。
人間は自分だけでは成仏できません。法と仏への帰命があってこそ成仏できるのです。人が石を海の上に置こうとしても必ず沈みます。ところが、船を造ってこの上に石を置けば、船の大きさに応じていくら積んでも沈みません。同じように、我々の生命はこのままでいけば、臨終に悪念を起こして地獄に堕ちてしまいます。しかし、正しい信心を持って臨終正念すれば、仏力、法力をかりて成仏の大願を成就することができるのです。
私達は自分の力だけで成仏できると思ってはいけません。大聖人が禅宗を“天魔”と仰せになったのは、彼らが自力で仏に成れると言うからです。煩悩が充満し争いの絶えない凡夫が、自分で仏身を成就することは不可能です。もし自分が仏であるとすれば、仏様もいらなくなり、信心もなくなってしまいます。常に臨終を心掛けて、本当の信心を貫き通さなければいけません。『顕立正意抄』に
「我弟子等の中にも信心薄淡き者は臨終の時阿鼻獄の相を現ず可し其の時我を恨む可からず」(全集五三七p)
と、まことに厳しいお言葉があります。よくよく信心に励まなければなりません。
★ 信心をもって題目を唱える
大聖人の御書の各所に“お題目を一遍唱えれば成仏する”という御文があることから、安易に解釈する人もありますが、これは単に初心者に仏教は困難でなく、成仏が困難でないことを示して、信心を勧奨するだけのものでなく、真実の信心であれば、一遍のお題目でも成仏するということです。御先師日達上人は次のように御指南されております。
「本宗の元来のお題目の唱え方は信心である。信心において唱えるときは、一遍も少なからず、百万遍も多からず、とこれが本宗の昔からの教えです。信心のないお題目を朝から晩まで唱えても、馬の耳に念仏ということわざがあるように、そんなことではだめなんです。忙しくて働いている人、また一生懸命に働いている人が、たった一遍のお題目でも、信心をもって唱えるお題目こそ、立派な、有難い我々の成仏すべきところの題目であります。また、信心がありながら、用もないのに何もしない。お題目も唱えないでぐうたらしているというのも、これはまただめなんです。それは本当の信心じゃない。やはり、用がなければお題目を唱えればいい。年をとって針仕事をしながらお題目を唱える。これは信心から出るところのお題目であるからして有難いのです。その心が常に唱うるお題目である。一遍のお題目でも常に唱うる、すなわち信心が根本であるからそうなるのであります。よく聞きますが、私は百万遍唱えたとか、十万遍唱えたとか自慢する人がおりますが、それは本宗の信心ではない。信心なくして何万遍唱えてもしようがない。それよりも信心をもって、御本尊様にむかって、本当の心からの題目を唱えることこそ、最も大切であります」
と御指南されておられます。あるいは大聖人が『生死一大事血脈抄』に
「信心の血脈なくんば法華経を持つとも無益なり」(全集一三三八p)
と念誡されているとおり、この「信心の血脈」なくんば、また否定せば、いかに強弁をなすとも、無益の信心、邪義の信心といわなければなりません。
想うに、宗祖日蓮大聖人の救世済民の御精神は、ことごとく御開山日興上人に付嘱せられ、以来、金口嫡々の御相承により、御当代日顕上人に相承せられているのであります。故に一切衆生の盲目を開き、無間地獄の道をふさぐ大聖人の大慈悲は、御当代御法主上人の御振る舞いのうちにあるのであります。
されば私達は今後ともいよいよ、御法主上人猊下の御指南、御教導に信伏随順し、もって仏道修行に精進してこそ、成仏の直道、真の臨終正念ありと思うものであります。
(たけうち ようどう・久修寺住職)
(大日蓮昭和57年11月号)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 今日のこと★☆
- - 20. NOVEMBER * Hubble *
- (2025-11-20 07:10:57)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 2025年11月20日の運勢ランキング「お…
- (2025-11-20 07:50:08)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- ファジーについて考察します。
- (2025-11-20 07:39:53)
-
© Rakuten Group, Inc.