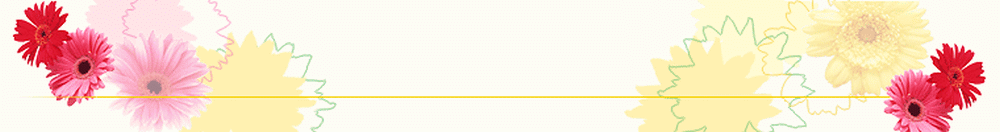全797件 (797件中 1-50件目)
-
やっぱりお山です。
先日、7日に支部総登山会がありました。猊下様との広布唱題会にも参加させていただきました。久しぶりのお山はやはり心が洗われます。朝は雨でしたが、昼前には上がり、ご開扉の時は青空も見えていました。支部の仲のいい方々と中華を食べに行ったりして。なんだかとっても楽しいご登山になりました。お山にいるとみんなが笑顔なんですよ。目がつりあがって、カリカリしてる人は見かけないです。一度、清浄な空気にふれてみてください。そこの顕正会員さんこちらも見てね。焦らず・気負わず・一歩ずつ
2012年10月10日
コメント(4)
-
心機一転で・・・
こちらでお世話になって6年でございます。その間にいろいろありまして、ずいぶん更新もしなかったんですが・・・更新しない間にメッセージ機能がなくなって、内緒でご連絡をいただけなくなっていまして・・・どうしよう????と、思っていたら。お引越しされているのを知って、私もそちらに・・・・心機一転、再始動できるといいんですが。こちらはこのままボチボチと。。。。。でおいておきます。引っ越し先は・・・・・諸先輩方がこぞっていらっしゃるところなので恥ずかしいのですが・・・http://hottkori.blog.fc2.com/お時間がある方は一度覗いてくださいませ。
2012年09月24日
コメント(0)
-
中・高校生の講習会に~(^O^)
昨日・今日と暑かったですね~ うちの三男坊も今年から高校1年になりました~ 早いものです。 で、今年から始まりました、中・高校生の講習会に参加させていただきました~ 私は運転手二号で、合宿には三男坊と付添に夫が行きました~ はっきり言って昨日はヒマな時間があって、四男坊と白糸の滝を見てきました。 滝の側は涼しかったですが、そこまでの道程が嫌になるぐらいあつい~ フェイスタオルがビショビショでした~ でも四男坊と夏のいい思い出が出来ました(^O^) 夕は六壺の勤行に参加でしましたし~ 六壺は風が良く入り、涼しかったですo(^-^)o 今日は広布唱題会に参加でき、ご開扉をいただいて帰ってきました。 ありがたい二日間でした。 来年は私が付き添いだそうですが~(夫の希望) 今から言ってたら鬼に笑われますかね・・・
2012年08月05日
コメント(1)
-
桜満開o(^-^)o
8日は日差しがあり、暖かな一日でした。 私の母が桜と富士山を見たいと言っていたので、連れてきました。 子供に勧められるものは、どんなに良いものでも拒む母なので、御住職様のお話しは『説得力がある』と好感触でしたが、本山見学で終わってしまいました。 身内の中でも親は難しいです。 でもしっかり、破折して下種できたので、ぼちぼち勧めていこうかな~と思ってます。 そうそう お花見にこられていたかたもすご~く大勢いらっしゃてました。 あちらこちらで折伏の花も満開でした~ 皆様方も 桜を見に来て、良い御縁をいただいてくださいね
2012年04月08日
コメント(2)
-
ぼちぼち頑張ってます(O_O)
最近ご無沙汰しております。 3月末の法華講総会にも無事に参加でき、懐かしい方々や新しい方とお会いでき、元気をいただけました。 次回、お会いできる時はもう少しゆっくりお話ししたいです。宜しくお願いします。 私の所は、何とか無事に三男が高校生になれました。 今度の月曜が入学式です。(全国的に同じですよねきっと) 四男は年長さんになります。 早いものです。 御宗門で御受戒をさせていただいた時は、まだハイハイでした。 今は、二人目の孫がスタスタ歩き始めてます。 私もすっかりおばあちゃん?ですねぇ~ 本山では明日、明後日が御虫払い会ですね。 お虫払いの時には桜が見ごろと言われていますが、今年はどうかなぁ~ 私は参加できなかったので、参加された方、桜の様子を教えてくださ~い。 さて、明日も仕事なので、そろそろ寝ます~ おやすみなさ~い
2012年04月05日
コメント(0)
-
謹賀新年・・・2012
新年明けましておめでとうございます。昨年は仕事と私生活の時間配分がうまくいかず・・・ここも2年連続の半放置状態・・・皆様方には御心配いただいていて、本当にありがとうございます。なんだか、正宗に縁をして、親身に心配をしてくださる方にとてもたくさん巡り合えるようになったと感じています。ー深謝ー 今年は、もう少し時間の使い方を工夫して、ここの更新も今よりはいいペースで頑張りたいと思っておりますので・・・・(昨年も同じことを書いたかも(^^ゞ) どうぞ今年もよろしくお願いいたします。ここを訪ねてくださる皆様の今年1年のご多幸を心より御祈念しております。 平成24年 元旦
2012年01月01日
コメント(5)
-

今年も~花火が綺麗でした~o(^-^ )o
昨日はお天気も良くて、富士山もくっきりと姿を見せてくれておりました~寛師会の飾り付けも整って、寛師会の提灯が飾られて・・・とにもかくにも・・・今年も子どもたちと参詣がかない、ありがたかったです。 罪障と魔と・・・どちらなのか、どちらもなのか・・・いろんな事が次から次から~罪障消滅は半端な心構えでは乗り越えられないなぁ~なんて思う今日この頃f^_^;更新もままならない~そんな日々はまだ続きそうですがぁー今年も子どもの笑顔を見たくて、でっかい花火と縁日を満喫してきました~ 4番目は光る銃を買うのが楽しみで、今年も新たな光る銃が増えました。本山に着くなり、『バンバン買う』を連呼~手に持つまで言い続けておりました。花火が、とても近くで上がっているので、音も大きさも半端なくでかい!上がるたびに『お~』とか『わぁ~』とか言ってたので喉が痛いかも~帰りはみんな爆睡してくれてました。今は帰り着いて、チビちゃんたちが光るおもちゃを鳴らしまくっております~(結構うるさいです)元顕正会の方々で、今年初めて寛師会に来た方々も『すごかったっす~』とコメントしてくれました。やることの桁が違う~とほんと、大違いだよね~顕正会の方々は、一度、総本山に来て、ご自身の目で、しっかり確かめた方がいいと思います。戒壇の大御本尊様がまします、御本仏がお住まいの地が清浄でないなんて言うのは、御本仏に力が無いと言ってる事になるんですよ。道理を通すとね・・・(^_^)
2011年09月19日
コメント(2)
-

春は桜だねぇ~
客殿のところにひときは鮮やかな花がありました~ やはりきれいですぅ~今年もかわらず桜は咲いてくれました。観光で来られてる方が非常に多くて、あちこちで立ち止まり、花を愛でていらっしゃいました~法華講の方が、お声をかけられて、熱心に仏法のお話を聞いていらっしゃる方を何人もみました。たゆまぬ信心ですよね。大石寺に桜を見物に来られた方々も足の底に日蓮大聖人様とのご縁をしっかり付けて帰られるんですよ~
2011年04月10日
コメント(0)
-
お見舞い申し上げます。
東北・関東にお住まいの方々被災された方々お見舞い申し上げます。東北の友達とは震災後すぐに無事の確認が取れたんですが・・・その後は連絡が取れません。何かできる事をと思っても・・・自分の無力を感じるばかりです。全く使えない奴になっております(T_T)本当に申し訳ない。原発もえらい事になっているし・・・津波被害も・・・言葉がなくて・・・稚拙な文章ですいません。一日も早い復旧を御祈念し、御冥福を祈っております。『一切を開く鍵は唱題にあり』負けないで・・・・
2011年03月15日
コメント(0)
-
本日のお菓子( ゜▽゜)
イチゴクリ~ムのロ~ルケ~キ(^O^) クリ~ムに使ったイチゴジャムもフレッシュイチゴをコトコト煮込んで作りましたぁ~(^O^)v 最近、手作りお菓子にはまってますぅ。 このブログの最初の方に書き込んでいますがぁ~ 顕正会に入る前は子どものおやつは殆ど手作り(^_^) ポテチもキャラメルもアイスクリームも肉まんなんかもね(^_-)-☆ 夏には自家製のイチゴシロップをかき氷にかけたり、冷たい水で薄めてジュ~スにしたり~ 長男・次男がお菓子を前にして『思い出すよなぁ』なんていいながら美味しいと食べてくれてますぅ~ 見た目はイマイチなんですがぁ(^^ゞ 夫や三男もパクパクと~ 四男は主食になってるかも~ こんな事に時間を使えるほど心に余裕が戻ってきたんだなぁ~ そんな風に思うこのごろです~ だからって折伏をしてないとかぁ~ 勤行をしてないとかぁ~ 唱題をしてないとかぁ~ てなことはありませ~ん ギスギス、イライラしていいことないと言うことですよー そうそう~ 日曜日に唱題会をさせていただいたんですがぁ~ その時にお嫁ちゃんのお友達が来てくれてお話で来ましたし~ 唱題会の時に話してたんですがぁ~ 顕正会は未だに待ち伏せ勧誘をしてるんだそうですねぇ~ それと~今更~と言われそうですが・・・ 京都事務所の管理をしてらしたN岡元区長さんの姿が最近見えないとか・・・ 京都事務所でお世話になったのですご~く気になります~。 合わせて、O家元区長は旦那さんに引っ張られて今もバリバリなのかなぁ~ なんだかとっても気になるお二人なんですぅ~ というところで~ 明日から仕事ですので、本日はこれにて~ おやすみなさいませ~m(__)m
2011年01月24日
コメント(0)
-
食べますぅ~(^_-)- ☆
作ってみました~ いかがでしょう? すいませ~ん 続きはまた明日にさせていただきますぅ~ おやすみなさいませ~
2011年01月23日
コメント(0)
-
ホットでど~ぞ( #^.^#)
昨日、コトコトと作りましたゆずジャムでございますぅ~それをお湯でわりましてぇ~ゆず湯にしてみましたぁ~皆様、相変わらずご無沙汰を重ねてしまい、申し訳ございませんm(__)m新年のご挨拶をいただきました☆山門入り口様~☆raiden様~☆ただじろう様~☆たくチャンのパパさん様~☆トチロ~様~本当に、本当にありがとうございます。今年もあいかわりませず、どうぞよろしくお願いいたします。で~続きはのちほどぉ~続きですぅ~最近思うんですよねぇ~正宗に御縁を頂いた瞬間に罪障が消えちゃわないかしらって・・・顕正会から御帰依した人の中には正宗に御縁を頂いた瞬間に罪障が無くなって、性格も暮らしもすごく立派になると思ってる方々もいるようで・・・・正宗の信心は罪障消滅から始まりますから、最初はつらい事が多いかな。それを乗り越えていける生命力を頂いていくわけですが・・・・これまた厳しくて、朝夕の勤行唱題の修行を基本としてのことなので、それなくして罪障消滅は出来ないんですよね。まずは、朝夕にお題目を自分の口で唱え出し、勤行の姿勢が整うように祈る事が生活を守る事につながるんですが・・・・お題目を三回唱える事すらしてない方がいるんですよねぇ~そんな状態で、いろんな事を否定されても・・・・ねぇ~・・・・答えようがなくて・・・・自分自身の気のすむようにするしかないよね。。。。。。。冷たいかもしれませんが、間違った事は勧められませんからねぇ~。。。。。。。。。。そういう方々を見ていると、御帰依と同時に罪障がすべてなくなって、非の打ちどころがないような人格者になれると思っているのかなぁ~って。いろんなところで正宗を否定してるのを目にしますが、どれもこれも感情論で、道理が通る内容には思えず・・・否定できるほどしっかりと正宗の信心修行をしたわけじゃあないのにね。そして、最後は自己保身で締めくくる感じ・・・・それっておかしいと思うんですが・・・・そういう事に最近よく出会うんですよ。(;一_一)新年早々に湿っぽい内容で申し訳ありません。正宗の信心は厳しいということんなんですよね。なんだか支離滅裂な文書、、、、、正宗の信心は本当にきびしいもんです~~そんな思いで新年が明けました~~またまた含みを持たせて・・・・じかいにつづけましょう。
2011年01月17日
コメント(2)
-
謹賀新年・・・遅れましたがぁ~
明けました~ おめでとうございますぅ~ 今日はと~ても天気が良くて素晴らしい富士山をみれました~ 今日は初登山の一日目でした。 人がいっぱいでした~ 空気も澄んでいてホントに気持ちいいありがたい一日でした。 お戒壇様にお会いできる事がこんなにありがたいなんて~ 三世常住のご本仏様のお側にいられるなんて・・・ そんな事を思いながら~ ただ今、帰路の車のなかです。 昨年の宿題も残したままで新年のご挨拶なんて、本当に申し訳ありません。 昨年はいろいろと生活環境も信心の環境も大きくかわり、体も頭もついていくのに四苦八苦で・・・ 今年はもう少し更新も頑張りたいです。 お返事をお待たせしてる方々にも深くお詫びしたいです。 新年早々、お詫びから始まった更新ですが、今年も皆様方の暖かな励ましをいただけるとうれしいです。 今年もよろしくお願いいたします。
2011年01月03日
コメント(6)
-
寛師会の花火~
久方ぶりで更新ですぅ~ 今年も寛師会に行ってきました~ 今年は人も多くて、法要にはまったく参加は出来なかったんですが、屋台と花火を楽しんできました~ 4番目くんも四歳になり、 去年とは違い、自己意思をはっきり主張しまて、屋台で楽しくスーパーボールすくいとかぁ かき氷はブルーハワイ~ りんごあめをほうばって~ 満足気におちょけまくっておりました~ 花火が頭の真上で開くように感じますので、大きな花が開いた時は・・・ 『熱いかも~怖いかも~』と頭を手で隠す仕草をしながら落ちる火の粉をよけるようなポーズをしたりして~ あまりの可愛さに愛おしさ何倍増!! こういう一つひとつの場面が有り難いってしみじみと、ジンワリと感じられて・・・ こういう何気ない日々に有り難さや感謝を感じる事を求めて顕正会に入って、頑張っていたけど・・・ 全然違ったし~ 日々、イライラ~ギスギスして子どもと過ごしてたなぁ~ 一泊で出かける余裕がなかったしねぇ~ 顕正会で積んだ罪障は深くて、いろんな嫌な罪障消滅も起こるけど、家族の(とくに夫の)支えを感じながら乗り越えて行けてるし~ 信心をしていてよかったなぁ~って・・・ 寛師会の縁日に行くたびに思っちゃいます。 京都の祇園祭なんかと比べると小さな小さな縁日だけど、心に残る感謝は計り知れない縁日なんですよねぇ~ 来年は日月だろうし~ 来年も家族みんなで行きたいなぁ~ とおもいつつ~ 家路についた昨日のお話しで~す。 コメントレスもせずに更新しちゃってすいません。
2010年09月20日
コメント(0)
-
二人目誕生~
相変わらず、放置ですいません。 前の日記にコメントをいただいてお返事ができていない【ポテンヒットさん】【デミアンさん】【リンダさん】【秋田のマイケルさん】本当にすいません。 7月末に長男夫婦が引っ越し~ 8月始めに私たち家族が引っ越し~ その荷物詰めや掃除などでてんてこ舞いをしておりました~ そして、荷解きにも四苦八苦してる今日この頃・・・ 今朝早くに二人目の孫も誕生しまして~ またまたバタバタの日々に拍車がかかりそうです~ 孫は予定日より18日早いのですが、すでに体重は2700グラムを越えておりまして、元気な女の子でございました~ ますます賑やかになるわが家でございます。 引っ越しは同居の為なんです~ 田舎なんで大きな中古住宅がありまして~ まるで私たちに住んで下さいと言う感じで話しがまとまり~ 家のこともまたの機会に書き込んで見ようと思います。 気ままブログにお付き合い下さる皆様方。 本当にありがとうございます。 落ち着きましたら必ずお返事いたします。 よろしくおねがいします~
2010年08月10日
コメント(4)
-
午前様~
つい最近のことなんですがぁ~ 久しぶりに御前様で帰宅~ 何をしてたかってぇ~~ じ・つ・わぁ~ 顕正会時代を彷彿とさせる・・・地区員さんのお知り合いの現役バリバリ顕正会員を破折させていただいていて、自宅に帰り着いたのが深夜0時を回っていたというわけぇ~ 合コンかぁ・・・オフ会かぁなどなどと期待をしてくださった方々~ 申し訳ない=^_^= 顕正会員くんも、お仕事帰りにわざわざ途中下車して6時30分からお店の閉店10時過ぎまでお付き合い頂いて、本当にありがたかったです。そのうえぇ~~ものすご~~く楽しかったですぅ。久しぶりに燃えましたぁ~折伏楽しいよぉ(^○^) 最初にぃこ:日蓮大聖人様を本当に信じていらっしゃいますか? 信じていれば血脈の否定は日蓮大聖人様をあなずってる行為なんですよ。け:血脈が断絶してないと思い込まされて、言ってるんですよ。 御相承の授受が行われた日はいつですか?こ:日達上人様から御隠尊猊下へは昭和53年4月15日です。 御隠尊猊下様から御当座様へのお座替わり式は平成17年12月16日です。け:時間は何時からですか?何時間あったんですか?こ:え?時間?式典の時間でちゃんとしたとか決まるんですか?け:そうですよ~。副長だったら大きな大会に出たでしょ。大切な時は時間長いでしょ!(勝ち誇ったように・・・)こ・地:(思わず顔を見合わせて・・・)時間って・・・・???け:何時に始まったか、何時間行われたか解らないんですか!(ますます勝ち誇って) では、解る方に今すぐ聞いてください!(中座して先輩にヘルプ~電話・・・しっかり良いお話を聞いて席に戻りましたぁ(^^)v)こ:御隠尊猊下様から御当座様のお時間は解りますよ。 日達上人様から日顕上人様の事は日付だけしか解らないですけど・・・け:そうでしょ。そこが大事なんだ!4月15日は何の日か知ってますか?(めちゃくち得 意げに) 日達上人様(本当は呼び捨て)の誕生日なんだ。この人は自分の誕生日が物すごく大切だから、毎年、誕生日には○○ホテルで盛大に自分の大切な誕生日パーティをしてるんだよ。そんな日に御相承の授受があるわけないでしょ。大勢の前で!!(勝った!という感じで) こ:そのお誕生会って情報源はどこですかぁ~? 当然、裏どりして確認してあるんですよね。け:そんなものネットを見れば書いてあるじゃないかぁ!こ:学会の受け売りなんだぁ~ 学会ネタでしょ。ホテルに確認したわけじゃないんでしょ。 そんな事うのみにして話してたら恥ずかしいですよ。 浅井さんは【「学会・宗門」抗争の根本原因】のP225の最後から5行目(では、もしこの付嘱相承の儀が省略されるようなことがあったらどうなるのか---。そのような非常事態が万一あったとしても、血脈が断絶するようなことは断じてあり得ない。御本仏の下種仏法は金剛不壊である。法体たる戒壇の大御本尊は厳然とましまし、金口の相承(御大事)また厳然である。) とP226の最初の1行目(万一相承の儀式が省略されたとしても、大聖人の御意に叶う法器だにあれば、法水また不断である。)に血脈の不断を書いてるのに、なんで今になって否定するの? それが自語相違でしょ。それを説明して下さい。 け:世界の客観情勢を見て時が来たから真実を話されたんですよ。 いま、中国の脅威もせまってるじゃないですかぁ。最新の講演集は読まれましたか? こ:以前はソ連の脅威だったでしょ。それがなぜ中国に変わるんですか? け:それは世界の客観情勢を見てです。 こ:顕正会はすでに平成19年には確か広宣流布してないといけないんじゃないの?それは? 平成11年に100万になってから1000万の誓願が300万に下降したじゃない。 け:今は200万ですよ。 こ・地:えっ?また、減ったの? け:客観情勢を見て、200万顕正会員が立たなければ日本がもたないということですよ。 こ:法華講は50万だけど、小さな子ども(小3以下)を抜いて7万8千名が大石寺に集結したよ。 未入信者はいないしね。顕正会は法華講の3倍近くいるけど、3万も集まらないよね。 しかも、退転者やお亡くなりになった方の人数は減らしてないでしょ。ご宗門は何年か毎に、ちゃんと確認しなおしされてるよ。 け:男子精鋭だけで3万集まりましたよ。そっちは全部集めてでしょ。 こ:それって長野の男子部大会?公共機関に2万3千人しか集まらないから消防法を守ってるって顕正会が伝えたの知ってる?公共機関のところが公表してたよ。 け:公共機関にそのように伝えても来る者は仕方ないでしょ。 こ:その中には未入信者はいないんだね。壮年や女子・婦人も入ってないんだね。知り合いが小学生の息子を連れて行ったって言ってたけど。。。。。。 け:女子婦人はメイン会場には入れませんし。未入信は・・・・・小学生もいたけど・・・・ こ・地:小学生がいたんだ~。顕正会って、16歳からだよね。小学生を数に入れるのまずいんじゃないの。それで3万人はおかしいよぉ~(だいたい、メイン会場に入らなくても出席票書いてるんだから、女子婦人も数に入って3万なんだよって思いながら・・・) け:・・・・・ てな感じで第一ラウンドが終わり・・・ 長いので続くぅ<m(__)m>
2010年07月17日
コメント(17)
-
【信仰を持たない人へ】9・宗教が社会に評(ひょう)価(か)されるのは福祉(ふくし)活動だけではないか
3 正しい宗教と信仰【信仰を持たない人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 9・宗教が社会に評(ひょう)価(か)されるのは福祉(ふくし)活動だけではないか 「福祉」という言葉は、“幸福”の意味ですから、広くいえば宗教の目的とも考えられます。しかし、ここでいう「福祉」は、困窮(こんきゅう)している人に物を恵(めぐ)み、飢(う)えた人に食(しょく)を与え、不自由な人の手助けとなり、なぐさめるという、一般的な意味であろうと思います。 たしかに極端(きょくたん)な個人主義と利己(りこ)主義によるぎすぎすした現代にあって、他人の幸せを願い福祉活動に奉仕(ほうし)することはきわめて尊いことであり、さらに広く深く社会に定着(ていちゃく)させてゆかねばなりません。政治や行政(ぎょうせい)の面からも福祉政策(せいさく)を協力に推進(すいしん)してほしいと願わずにはいられません。 しかし宗教の存在価値(かち)や目的が福祉活動への奉仕(ほうし)だけであると考えるのは、大(おお)いなる誤解(ごかい)です。なぜならば、宗教とりわけ仏法では、正法によって生(しょう)老(ろう)病(びょう)死(し)の四苦(しく)を解決し、成仏という確固(かっこ)不動(ふどう)の安穏(あんのん)な境地に至ることを真実の救済とし、本来の目的としているのに対し、一般的な福祉活動はあくまで表面的一時的な救済措置(そち)だからです。 またもし宗教の存在価値が、人々に物を与え、不自由な人の手助けをし、悩める人を慰(なぐさ)めるだけで事(こと)足りるというならば、仏がこの世界に出現し、苦難と迫害(はくがい)の中で身命を賭(と)して法を説く必要があったのでしょうか。私たちも本尊を礼拝(らいはい)し、修行を積み、教義の研鑽(けんさん)をすることもすべて不要となってしまうではありませんか。 真実の宗教とは正しい法を信仰することによって、生命の根源(こんげん)に光をあて、活力にみちた仏の働きを涌(わ)きあがらせて、力強い人生を確立(かくりつ)することにその目的があるのです。 他人への親切や親への孝養といっても具体的な形態(けいたい)はさまざまです。仏法では人間を深く観達(かんたつ)したうえで、孝養に三種ありと次のように説いています。「孝養に三種あり。衣食(えじき)を施(ほどこ)すを下品(げぼん)とし、父母の意に違(たが)わざるを中品(ちゅうぼん)とし、功徳(くどく)を回向(えこう)するを上品(じょうぼん)とす」 ここにも、物を与える孝養は下品であり、意にかなうことが中品、仏法によって功徳を回向(自ら修行した果報(かほう)を他に回(めぐ)らし向かわせること)することがもっとも尊(とうと)いことであり上品であると明かしています。 物を与え、慰労(いろう)するところの福祉活動が正しく実践(じっせん)され、持続し、実効(じっこう)を生むためにも、原点となる個々の人間に正しい智慧(ちえ)と活力を与える真実の仏法が必要なのです。 言い換(か)えれば、福祉活動をはじめ文化・社会・教育・政治などの各方面における活動、そして人間がなすすべての営(いとな)みの基盤(きばん)となり、根底にあって善導(ぜんどう)し、活力を与えてゆくのが正しい宗教なのです。
2010年07月09日
コメント(0)
-
【信仰を持たない人へ】8・宗教は思考をマヒさせ、人間を無知にするのではないか
3 正しい宗教と信仰【信仰を持たない人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 8・宗教は思考をマヒさせ、人間を無知にするのではないか 宗教を信ずると、その宗教に没頭(ぼっとう)するあまり冷静(れいせい)な思考(しこう)能力や批判(ひはん)力、判断(はんだん)力がマヒして、自分なりの理性を持(も)てなくなるのではないか、という危惧(きぐ)をもつ人がいます。 たしかに、なんらの教義をもたない低級な新興宗教をはじめ、数多くの宗教は、たんに忘我(ぼうが)の境(きょう)地(ち)や、あきらめることのみを教え、人間の思考能力をマヒさせています。ここに邪(よこしま)な宗教の恐(おそ)ろしさがあります。 しかし、正しい因果(いんが)の道理(どうり)を説く仏教、なかでも法華経の教えにおいては、“聞(もん)思(し)修(しゅう)の三慧(さんね)”といって、仏道(ぶつどう)を成就(じょうじゅ)するためには正法をよく聞き、思惟(しゆい)し、修行しなければならないと説いてます。日蓮大聖人は、「行学(ぎょうがく)の二道をはげみ候べし。行学た(絶)へなば仏法はあるべからず」(諸法実相抄・御書668頁)と教(きょう)示(じ)されるように、正しい教えに則(のっと)り、修行と研学(けんがく)によって仏法の精神を求めることの大切さを説かれています。 また法華経を持(たも)つ者の功徳(くどく)の姿を示して、「日蓮等(ら)の類(たぐい)南無妙法蓮華経と唱へ奉る者は明鏡(めいきょう)に万像(ばんぞう)を浮かぶるが如(ごと)く知見(ちけん)するなり。此(こ)の明鏡とは法華経なり」(御義口伝・御書1776頁)と説かれています。すなわち正しい仏法を信ずることによって、生命の本源が活動し、物ごとを正しく知見(ちけん)できるというのです。反対に間違った宗教を信ずる者や正しい仏法を持たない者は迷える心、煩悩(ぼんのう)の生命から物を見、考えているために、すべてを正しく見ることができないのです。まさに本心を失っているようなものです。 これについて、大聖人は、「本心と云ふは法華経の信心の事なり。失(しつ)と申すは謗法(ほうぼう)の人にすかされて、法華経を捨(す)つる心出来(しゅったい)するを云ふなり」(御講聞書・御書1857頁)とも説かれています。ここでいう本心とは、世間的な迷いの凡智(ぼんち)ではなく、本仏本法によってもたらされる仏智(ぶっち)であり、人生においてもっとも大切な真実の幸福を確立(かくりつ)する仏界の心を指しているのです。 ですから、真実の仏法とは、本心たる智慧(ちえ)の眼(まなこ)を開かせ、正しい人生を歩ませるための英知(えいち)を、生命の根源から涌現(ゆげん)させるものであることを知るべきでしょう。
2010年06月22日
コメント(4)
-
【信仰を持たない人へ】7・いまが楽しければそれでよいではないか
3 正しい宗教と信仰【信仰を持たない人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 7・いまが楽しければそれでよいではないか 「いまが楽しければ」という言葉のひびきには、まったく将来(しょうらい)のことを考えず、苦しみを避(さ)けて、いまの楽しみばかりを追い求(もと)めるというニュアンスが感じられます。 それは、おそらく、若いときの楽しみは若い時にしか味わえないという考えから、オートバイの爆音(ばくおん)や、ロックの喧噪(けんそう)のなかに我(われ)を忘れ、酒や歌、そしてダンスに陶酔(とうすい)のひとときを過ごす若者たちに共通した考えかたであると思います。 その反面、いまの楽しみより将来の楽しみを目指(めざ)して、つらさに耐(た)え、少しでも自分のもてる能力や才能を伸(の)ばそうと、懸命(けんめい)な努力を重(かさ)ねている若者たちも、けっして少(すく)なくありません。 安易(あんい)に目前の快楽のみを求める若者たちの行きかたは、蟻(あり)とキリギリスの寓話(ぐうわ)の教訓をまつまでもなく、苦労を続けながらも真剣に生きている多くの人たちに比(くら)べて、あまりにも人間として分別(ふんべつ)のない、しかも後(あと)に必ず苦しみと後悔(こうかい)をともなう生きかたではないかと思います。 だからといって、人間は若いときには何が何でも苦労ばかりをして、楽しみなどを求めてはいけない、というのではありません。 青年の時代こそ、人生を真に楽しんで生きていくための基盤(きばん)を、しっかりと築き上げる時であると言いたいのです。 「楽しみ」というものの本質について、仏教では、五官(ごかん)から起る欲望を五識(ごしき)によって満たし、意識(心)にここちよく感ずることであると明かしています。 五官とは、眼(げん)(視官(しかん))・耳(に)(聴官(ちょうかん))・鼻(び)(嗅官(しゅうかん))・口(こう)(味官(みかん))・皮膚(ひふ)(触官(しょっかん))をさします。すなわち、眼にあざやかな色形(いろかたち)を見る楽しみ、耳にここちよい音や響(ひびき)を聞く楽しみ、鼻にかおりのよいものを嗅(か)ぐ楽しみ、口中の舌においしいものを味わう楽しみ、皮膚(ひふ)(身体)にここちよいものが触(ふ)れる楽しみを欲(ほっ )するところを五欲(ごよく)といい、五官によって判断することを五識といいます。 要するに、人間の楽しみのほとんどは、この五欲の一つ一つが満たされるか、そのいくつかが同時に満たされるかの度合(どあい)に応じて起こる、情感(じょうかん)であることがわかると思います。 したがって、五欲そのものは、けっして悪いものではありません。しかしそこに、人間の煩悩(ぼんのう)(貪(とん)・瞋(じん)・癡(ち)などの迷い)が働きかけた時、はじめて五欲は、無謀性(むぼうせい)を発揮(はっき)し、欲望の暴走(ぼうそう)となってあらわれたり、意(こころ)のままに満たされない不満がつのって、怒(いか)りを感じたり、落胆(らくたん)のあまり、自暴(じぼう)自棄(じき)になったりして、自分や社会を破壊(はかい)してしまうことにもなりかねないのです。 五欲とは、ちょうど火のようなものだといえます。火そのものは悪でも善でもありませんが、私たちの使いかた如何(いかん)によっては、生活に欠かせない便利なものにもなる半面、不始末(ふしまつ)などがあれば、すべてのものを一瞬のうちに灰燼(かいじん)にしてしまう、ということにたとえられるでしょう。 いわば、一時の快楽を飽(あ)きることなく求める若者たちは、煩悩(ぼんのう)の働きがそれだけ旺盛(おうせい)だともいえましょう。その旺盛な煩悩の猛火(もうか)をそのまま自分の将来の幸福と社会に役立つ有益(ゆうえき)な火に転換(てんかん)させるところに、正しい宗教と信仰のもつ大きな意義があるのです。
2010年06月02日
コメント(0)
-
【信仰を持たない人へ】6・学歴(がくれき)や社会的地位こそ幸福の要件ではないか
3 正しい宗教と信仰【信仰を持たない人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 6・学歴(がくれき)や社会的地位こそ幸福の要件ではないか レッテル社会といわれる現代では、より安定した生活を送るためには有名校を卒業して大(だい)企(き)業(ぎょう)や官公庁(かんこうちょう)に入り、重要ポストにつくことが幸福の要件と考えている人があります。 これについて二点から考えてみましょう。 第一の点は、はたして社会的な地位につくことが幸福の条件なのか、ということです。 最近、四十代、五十代の、いわば社会的に重要な地位にある年代のエリートが、仕事上の行きづまりや人間関係の悩みによってノイローゼになったり、自殺に走るケースが頻繁(ひんぱん)に起こっています。 現代の熾烈(しれつ)な競争社会の中で責任のある地位につくことは、それだけ大きな負担(ふたん)となり、身心ともに苦労も多くなることは当然です。 ではなぜ人々は苦労の多い地位を望(のぞ)むのでしょうか。その理由は、ひとつには人に負けたくない、人の上に立ちたいという本能的な願望(がんぼう)であり、もうひとつには地位が向上すれば経済的に豊かになる、周囲から敬(うやま)われることなどが挙(あ)げられると思います。 もし願いどおりの地位についたとしても、それに適合(てきごう)しない性格であったり、負担に堪(た)える人間的な能力がなければ、その人は苦痛(くつう)の毎日を送ることになるのです。 第二の点は、学歴(がくれき)至(し)上(じょう)主義(しゅぎ)がもたらす弊害(へいがい)と不幸がいかに大きいか、ということです。 たしかに一流大学を卒業した人は、それだけ幼(おさな)いころから勉学に励(はげ)んできた努力によって、能力的に優(すぐ)れています。深い学識と幅(はば)広い教養による英知(えいち)はいずこの社会や職場にあっても、知的(ちてき)資源(しげん)、人的(じんてき)資材(しざい)として重要視されることは当然でしょう。 しかし誰もが一流校には入(はい)れるわけではなく、ごく一にぎりの人だけが許(ゆる)される狭(せま)き門を目指(めざ)して、過酷(かこく)な受験戦争がくり広げられ、子供は友情を育(はぐく)むどころか、同級生を敵視(てきし)する状態(じょうたい)に追いやられています。 毎年受験シーズンになると受験に失敗して自殺するという悲惨(ひさん)な事件が相(あい)つぎますが、幼いころから親や先生の「有名校に入る人は優秀、入れない人は敗北者(はいぼくしゃ)」という言葉を聞いて育ったならば、受験の失敗がそのまま人生の破滅(はめつ)になると考えるのは当然です。 まさに誤(あやま)った学歴偏重(へんちょう)の風潮(ふうちょう)が生む不幸の一面であり、その風潮の中で育った子供は、またさらに学歴偏重の人生観を増幅(ぞうふく)していくのです。 このような教育制度や教育行政(ぎょうせい)のゆがみは教育の部分だけをとり上げて改革(かいかく)しようとしても根本的な解決にはなりません。 なぜならば、教育問題は時代や社会機構(きこう)全体と深く関(かか)わっており、さらには人生観・価値(かち)観(かん)ともつながっている事柄(ことがら)だからです。 釈尊は現代を予言して、末法は五(ご)濁(じょく)の時代であると喝破(かっぱ)されています。五濁とは時代が濁(にご)り、社会が乱(みだ)れ、人間の生命も思想も狂(くる)うことを指(さ)しており、その原因は誤った宗教にあると説いています。 したがって健全な人生観や社会思想は、ひとりひとりが正しい宗教に帰依(きえ)し、しかも正法が社会に広く深く定着(ていちゃく)したときに醸成(じょうせい)されるのであり、真実の幸福は表面的な学歴や肩書きによってもたらされるのではなく、真実の仏法を信仰し修行することによってもたらされるのです。 以上の二点だけを取り上げてみても、学歴や社会的地位がそのまま個人の幸福の絶対的条件になるわけでもなく、社会の福祉(ふくし)につながるわけでもないことがわかるでしょう。 真実の幸福とは、いかなる負担や困難をも悠々(ゆうゆう)と解決して乗り越えていくところにあります。 個々の人間に生命力を与え、勇気と希望と智慧(ちえ)をもたらす道は、真実にして最勝の仏法を信仰し修行することに尽(つ)きるのです。 身につけた学識(がくしき)と教養、そして大きな責任をもつ社会的な地位、それらをより充実したものとし、より価値あるものとするために、正しい信仰が絶対に必要なことを知るべきです。
2010年05月31日
コメント(0)
-
【信仰を持たない人へ】5・現実生活の幸福条件はお金が第一ではないか
3 正しい宗教と信仰【信仰を持たない人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 5・現実生活の幸福条件はお金が第一ではないか 私たちが日常生活を営(いとな)むうえで、衣・食・住の全般(ぜんぱん)にわたってお金がたいへん重要で便利な役割(やくわり)を果(は)たしています。物品(ぶっぴん)の価値(かち)がお金に換算(かんさん)できることはもちろん、人間や機械の労力・能力そして生命までが金銭で贖(あがな)われています。 そのためにお金をすべてに先行して価値あるもののように思い、幸福条件の第一に挙(あ)げる考えの人は少なくありません。 しかしどんなに貴(き)重(ちょう)なお金であっても、所詮(しょせん)は人間社会によって産(う)み出された“物”であり、生活上の手段のひとつにすぎないのです。言い換(か)えれば、生きている人間そのものが主体者(しゅたいしゃ)で、金銭は人間によって考え出された流通(りゅうつう)上の約束(やくそく)ごとのひとつであるということです。 これを間違(まちが)えて、人間がお金に使われたり振(ふ)り回(まわ)されるところにとんでもない悲劇(ひげき)が生ずるのです。たとえば、お金をけちけちとためて満足な食事もせず、結局ためたお金を使うことなく餓死(がし)した老人がいました。また遺産(いさん)をめぐる親族間の争いが高(こう)じて殺人事件に発展した例、サラ金苦においつめられて殺人や強盗(ごうとう)に走る例もあれば、一家心中の例などお金をめぐる悲惨(ひさん)な事件は毎日のように報道されています。これはお金というものが、私たちの生活に大きな比(ひ)重(じゅう)を占(し)めている証(あか)しでもありますし、生死(せいし)にかかわるほど大きな影響力をもっている証(しょう)左(さ)でもあります。 と同時にこれらの事例から、同じお金であってもそれを使う人間によって幸にも不幸にもなることがわかります。 つまり、お金は生活する上に必要なものですが、またお金によって不幸を招(まね)くこともあるということなのです。 ここに主体者(しゅたいしゃ)である人間を確立しなければ、真実にお金も財産も正しく生かされないという道理を知るべきなのです。 日蓮大聖人は、「蔵(くら)の財(たから)よりも身の財すぐれたり。身の財より心の財第一なり」(崇峻天皇御書・御書1173頁)と仰(おお)せられています。 私たちにとって大切な財宝(ざいほう)はいくつかありますが、お金などの蔵の財よりも、健康な身体が大切であり、それよりも大切な宝が人間の根本ともなる心の財なのです。 お金は、現代の幸福になる条件のひとつであることに違いはありませんが、それが幸福のすべてではありません。根本にある心の財を正しい信仰によって磨(みが)き、福徳(ふくとく)に満ちみちた人間になったとき、はじめて蔵の財(お金)にも恵(めぐ)まれ、それを正しく自在に使いこなしていけるのです。 せっかくためたお金や財産を不幸や悲劇の種にするか、幸福の種にするかは、その人の心と福徳によって決(き)まります。 物心両面にわたる幸福な人生を築くためにも、まず正しい仏法に帰依(きえ)し、信仰に励むことから出発しなければならないことを知るべきでしょう。
2010年05月22日
コメント(0)
-
【信仰を持たない人へ】4・「さわらぬ神にたたりなし」で、宗教に近づかない方(ほう)がよいと思うが
3 正しい宗教と信仰【信仰を持たない人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 4・「さわらぬ神にたたりなし」で、宗教に近づかない方(ほう)がよいと思うが 「さわらぬ神にたたりなし」」とか「参(まい)らぬ仏に罰(ばち)は当たらぬ」ということわざは、信仰とかかわりを持(も)たなければ、利益(りやく)も罰も受けることはないとの意味ですが、一般には広くなにごとも近づかなければ無難(ぶなん)であるという意味に使われています。 たしかに間違(まちが)った宗教には近づかない方が無難ですが、こと正しい仏法に対して、このような考えを持つことは誤(あやま)りです。 釈尊は、「今(いま)此(こ)の三界は皆(みな)是(こ)れ我(わ)が有(う)なり。其(そ)の中(なか)の衆生は悉(ことごと)く是(こ)れ吾(わ)が子なり。」(譬喩品第三・開結一六八)と説かれ、世の中のすべては仏の所有(しょゆう)するところであり、人々はすべて仏の子供であるといわれています。いいかえると、仏法とは文字(もじ)通(どお)り仏が悟(さと)られた真理(しんり)の法則(ほうそく)ということであり、私たちは誰ひとりとしてこの真理の法則(ほうそく)から逃(のが)れることはできません。 仏教では宇(う)宙(ちゅう)全体を指して法界(ほうかい)といいますが、日蓮大聖人は、「法界一法として漏(も)るゝ事無き」(御義口伝・御書1798頁)と仰(おお)せられ、仏が開悟(かいご)した法は宇宙法界に漏(も)れなくゆきわたっていると教えられています。 ですから信仰を持たなければ罰も当たらないというのは、警察署(けいさつしょ)に近づかなければ罰(ばっ)せられることもないということと同じで幼稚(ようち)な理屈(りくつ)であることがわかるでしょう。 もし正しい仏法に近づかなければ、真実の幸福をもたらす教えを知ることができないわけですから、それこそ日々の生活が、仏に背(そむ)き、法を破(やぶ)る悪業(あくごう)の積(つ)み重(かさ)ねとなっていくのです。 ましてや仏の慈悲(じひ)は人を救(すく)い善導(ぜんどう)するところにあり、たたりなどあるわけがありませんし、罰といっても、親が我が子を導(みちび)く手段(しゅだん)として叱(しか)ることと同じで、それも親の愛情の一分(いちぶん)であることを知らなければなりません。 その意味から考えても、罰が当たるから仏法に近づかないというのは、親や教師がうるさいからといってこそこそ逃(に)げ回(まわ)っている子供と同じことで、およそ健全(けんぜん)な人間に育(そだ)つはずはないのです。 いかに自分では信仰と無縁(むえん)のつもりでいても、この世に生きている人はすべて、正しい教えによらなければ真の幸福を得られない存在(そんざい)であり、また仏の掌(たなごころ)の上で生きていることに違(ちが)いはないのですから、自(みずか)らの人生をより爽快(そうかい)なものとし、充実(じゅうじつ)したものとするため一日も早く正しい仏法に帰依(きえ)することが大切なのです。
2010年05月21日
コメント(0)
-
【信仰を持たない人へ】3・宗教は精神修養にすぎないのではないか
3 正しい宗教と信仰【信仰を持たない人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 3・宗教は精神修養にすぎないのではないか 精神修養(せいしんしゅうよう)とは、精神を錬磨(れんま)し品性(ひんせい)を養(やしな)い人格(じんかく)を高めることですが、一般には心を静(しず)め精神を集中することをいうようです。 芸術やスポーツなどを通(とお)して精神を磨(みが)き、人格を高めるならば、それは立派(りっぱ)な精神修養です。 数多い宗教のなかには、精神修養の美名(びめい)を看板(かんばん)にして布(ふ)教(きょう)するものがあります。その代表的なものとして禅宗(ぜんしゅう)があげられます。 煩雑(はんざつ)な毎日(まいにち)に明けくれている現代人にとって、心を静めて精神を集中する機会(きかい)が少ないためか、管理(かんり)職者(しょくしゃ)や運動選手の精神統一の場として、あるいは社員教育の場として、座禅(ざぜん)が取り入れられ、ブームになっているようです。 では宗教の目的は精神修養にあるのかという点ですが、仏教では、精神を統一し心を定(さだ)めて動(どう)じないことを禅定(ぜんじょう)とか三昧(さんまい)といい、仏道(ぶつどう)修行(しゅぎょう)のための初歩的な心構(こころがま)えとして教えており、これが仏教の目的でないことはいうまでもありません。 また人格品位(ひんい)の修養についていえば、仏教の中の小(しょう)乗(じょう)教(きょう)では、悪心(あくしん)悪業(あくごう)の原因は煩悩(ぼんのう)にあり、煩悩を断滅(だんめつ)して身も心も正(ただ)された聖者(せいじゃ)になることがもっとも大切であると説き、戒律(かいりつ)を守り智慧(ちえ)を磨くことを教えました。これを二(に)乗(じょう)(声聞(しょうもん)・縁覚(えんがく))の教えといいます。しかし大(だい)乗(じょう)教(きょう)では、自分だけが聖者になっても他(た)を救おうとしないのは狭(きょう)小(しょう)な考えであり、思考(しこう)や感情に誤(あやま)りのない聖者でも、それだけでは真実の悟(さと)りではないと、小乗教を排斥(はいせき)し、自他(じた)ともに成仏(じょうぶつ)を目指(めざ)す菩薩の道を示(しめ)しました。 そして究極(きゅうきょく)の法華経では、さらに進めて、仏が法を説く目的は、二乗や菩薩になることではなく、一仏(いちぶつ)乗(じょう)といって衆生(しゅじょう)を仏の境界(きょうがい)に導(みちび)くことに尽(つ)きるのであると教えられたのです。これを開三顕一(かいさんけんいち)(三乗を開いて一仏乗を顕(あら)わす)といいます。 もちろん宗教で説く二乗や菩薩の道が直(ただ)ちに現今(げんこん)の精神修養とまったく同じということではありませんが、少なくとも二乗や菩薩の教えの一部分に人格と品性(ひんせい)の向上(こうじょう)を計(はか)る精神修養の意義(いぎ)が含(ふく)まれているということができましょう。 釈尊は、「如来(にょらい)は但一仏乗(ただいちぶつじょう)を以(もっ )ての故に、衆生(しゅじょう)の為に法を説きたもう」(方便品第二・開結一〇三)と説かれ、日蓮大聖人も、「智者(ちしゃ)・学匠(がくしょう)の身と為(な)りても地獄(じごく)に墜(お)ちて何(なん)の詮(せん)か有(あ)るべき」(十八円満抄・御書1519頁)と仰(おお)せられるように、仏法の目的は精神修養などに止(とど)まらず、成仏(じょぶつ)すなわち三世(さんぜ)にわたる絶対的(ぜったいてき)な幸福境界(きょうがい)の確立(かくりつ)にあるのです。 したがって、禅宗などで精神修養を売りものにしていることは、教義的に誤(あやま)っているだけでなく、仏教本来(ほんらい)の目的からも大きな逸脱(いつだつ)を犯(おか)す結果になっているのです。
2010年05月17日
コメント(0)
-
りんごの花ぁ~
桜が終わって寂しくなったなぁ~て時に家の近くでりんごの花が満開でした~ と言ってもこれは二週間ほど前の話しなんですがぁ~ ヒメリンゴの仲間で、アメリカンチェリーぐらいの大きさの実が秋に実ります~ この間~お山に行きましたが、毎年ならつつじやさつきが満開の時期なのにまだまだ蕾がいっぱいでしたぁ~ これからご登山の皆様は~つつじを楽しんでくださいねぇ~。 どうしてもりんごの花を見ていただきたくて~ ちょっとトボケタタイミングで~載せちゃいましたぁ~
2010年05月13日
コメント(2)
-
【信仰を持たない人へ】2・現実に神や仏がいるとは思わない
3 正しい宗教と信仰【信仰を持たない人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 2・現実に神や仏がいるとは思わない はじめに、神についていいますと、キリスト教やイスラム教で立てる天地(てんち)創造(そうぞう)の神ゴッドやアラーは、予言者と称(しょう)されるキリストやマホメットが経典(きょうてん)に説示(せつじ)しただけのことで、現実にこの地上に姿(すがた)を現わしたことはありません。 天理(てんり)教(きょう)の天理(てんり)王(おうの)命(みこと)や金光(こんこう)教(きょう)の天地(てんち)金乃神(かねのかみ)なども、教祖がある日思いついたように言い出したもので、この世に現われたことはありません。 また神社の中には、天満宮(てんまんぐう)や明治神宮などのように菅原道真(すがわらのみちざね)とか明治天皇などの歴史上の人物を祭(まつ)っているところもありますが、これらは偉人(いじん)を敬慕(けいぼ)する感情や時の政治的配慮(はいりょ)などによって、人間を神にまで祭(まつ)りあげてしまっただけのことで、神本来の働きをもっているわけではないのです。 本来、神とは原始的時代の自然崇拝(すうはい)の産物(さんぶつ)であり、宇宙に存在するさまざまな自然の作用(はたらき)には、それぞれ神秘的な生命すなわち神が宿っているという思想に端(たん)を発しています。 したがって真実の神とは、ひとつの人格や個性を指すものではありませんし、神社などに祭られて礼拝(らいはい)の対象(たいしょう)となるものでもありません。あくまでもすべての生き物を守り育(はぐ)くむことに神の意義があるのです。この神の力が強ければ人々は平和で豊かに暮(くら)らせるわけですが、仏法においては、神の作用は正しい法の功徳を原動力とし、これを法味(ほうみ)といい、諸天諸神が正法を味わうとき、仏の威光(いこう)と法の力を得て善神(ぜんじん)として人間を守り、社会を護(まも)る力を発揮(はっき)すると説いています。 次に仏についていいますと、仏典に説かれるたくさんの仏や菩薩(ぼさつ)たちも、ほとんどは歴史的に地上に出現したことはありません。身近(みぢか)なところでは、念仏(ねんぶつ)宗(しゅう)の阿弥陀(あみだ)如来(にょらい)や真言(しんごん)宗(しゅう)の大日(だいにち)如来(にょらい)なども実在したことのない仏です。 ではなぜ架空(かくう)ともいえる仏や菩薩が経典に説かれたのかというと、インドに出現した釈尊は法界(ほうかい)の真理と生命の根源を説き明かすために生命に備(そな)わる働きや仏の徳を具(ぐ)象(しょう)的(てき)・擬(ぎ)人(じん)的(てき)に仏・菩薩の名を付けて表現されたのです。たとえば智慧(ちえ)を文殊(もんじゅ)菩薩(ぼさつ)、慈悲(じひ)を弥勒(みろく)菩薩(ぼさつ)、病(やま)いを防(ふせ)ぎ、癒(い)やす働きを薬師(やくし)如来(にょらい)・薬王(やくおう)菩薩(ぼさつ)、美しい声を妙音(みょうおん)菩薩(ぼさつ)というように、それぞれに名を付(つ)けられました。 これらの仏・菩薩は教主である釈尊の力用(りきゆう)を示すために説かれたわけですが、釈尊は厳然(げんぜん)とインドに誕生され、宇宙(うちゅう)の真理を悟り、人々に多くの教えを遺(のこ)されました。釈尊の出現と経典に説かれる深義(じんぎ)に疑いをもつ人はいないでしょう。 この釈尊が究極(きゅうきょく)の教えとして説かれた法華経の中に、末法に出現する本仏を予(よ)証(しょう)されました。その予証とは、法華経を行ずる故に刀(かたな)や杖(つえ)あるいは瓦(が)石(しゃく)で迫害(はくがい)されること、悪口(あっく)罵詈(めり)されること、しばしば所払(ところばら)いの難に遭(あ)うこと、迫害者(はくがいしゃ)の刀が折(お)れて斬(き)ることができないなどのことですが、この予言どおりに、うち続く大難の中で民衆救済のために究極の本法たる文底(もんてい)の法華経を説き、未来(みらい)永劫(えいごう)の人々のために大御本尊を顕(あら)わされた御本仏こそ日蓮大聖人です。 日蓮大聖人はひとりの人間としての人格の上に本仏の境界(きょうがい)を現実に示されたのです。 もしあなたが、仏は人間の姿をしたものではなく、金ピカの仏像や大仏そのものと考えて「そのような仏など実在しない」というならば、それはあまりにも幼稚(ようち)な考えであり、ためにする言(い)い掛(がか)りというべきです。
2010年05月13日
コメント(2)
-
【信仰を持たない人へ】1・宗教の必要性を認めない
3 正しい宗教と信仰【信仰を持たない人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 1・宗教の必要性を認めない 宗教を否定し、信仰の必要性を認めないという人の中には、感覚的に信仰を嫌(きら)う人もあれば、今までまったく無関心に生きてきたことによって、その必要性に気づかない人もあることでしょう。 しかし、ほとんどの人々は自分なりの信念を持って、日々努力を重ねて自分の一生を生きていけばよいと思っているようです。 確(たし)かに自分の信念と、毎日の努力によって一家をささえ、子供を育て、それなりの財産を築き、社会的な地位を得(う)るということは、尊(とうと)い一生の仕事であり、これとても、並(なみ)たいていの努力でできるものではありません。 真実の宗教は、人間の生命を説き明かし、人生に指針(ししん)を与えるもっとも勝れた教えですから、これを信ずることは仏の正しい教えによって、心の中に秘められた願いを成就(じょうじゅ)し、私たちの持つ信念を、より崇高(すうこう)な信念へと高め、人間性をより豊かに、より充実したものに育(はぐ)くむことになるのです。 たとえば、山の中の小さな谷川をわたるのには、航海(こうかい)術(じゅつ)を学ぶ必要はないでしょう。けれども、太平洋などの大海原(おおうなばら)を渡るには、正しい航路を知り、進路を定(さだ)め、航海するための知識や技術が、どうしても必要なのです。 私たちの人生にとっても、一生という長い航海には、仏の正しい教えによって航路を正(ただ)し、自分を見きわめ、真実の幸せな人生という目標に到達(とうたつ)するための知識や訓練(くんれん)ともいうべき、正しい信仰と修行が必要なのです。 真実の宗教を持(も)たず、正しい信仰を知らない人は、あたかも航海の知識もなく、進路を見定める羅針盤(らしんばん)も持たずに大海原に乗り出した船のように、人生をさまよわなければなりません。 釈尊は涅槃(ねはん)経(ぎょう)というお経の中で、信仰のない人のことを、「主(しゅ)無く、親(おや)無く、救(く)無く、護(ご)無く、趣(しゅ)無く、貧(びん)窮(ぐ)飢(き)困(こん)ならん」と説いています。 すなわち、正しい宗教を持たない人は、仏という人生における根本の師を知らず、もっとも慈愛の深い親を持たず、したがって、仏の救済(きゅうさい)もなく、護られることもなく、何を目的として生きるのかということを知らず、正法の財宝(功徳(くどく))に恵(めぐ)まれない、心の貧(まず)しい人だというのです。 さらに長い一生の間には、経済苦や家庭不和や社会不安の影響などによって、深刻な悩みや苦しみが押し寄せてくる時もありましょう。少なくとも病苦(びょうく)・老苦(ろうく)・死苦(しく)などは、誰もが必ず直面しなければならないことなのです。 実際に自分がこうした苦悩(くのう)に遭遇(そうぐう)した時のことを想像(そうぞう)してみて下さい。はたして本当に自分の信念と努力で、このような悩みや苦しみを乗り越えることができるのでしょうか。少なくとも自分一人の力で、その苦しみのどん底からはい上がり、我が身の不幸を真実の幸せな人生へと転換(てんかん)させることは容易(ようい)なことではありません。 まして一切の苦悩に打ち勝って、安穏(あんのん)な、しかも行きづまりのない自在の境涯(きょうがい)を開拓(かいたく)して生きるなどということは、できるものではありません。 ここに、正しい信仰によっていかなる障(しょう)魔(ま)にも負けない不屈(ふくつ)の闘志(とうし)と、仕事や家庭など人生におけるすべての苦難(くなん)に打ち勝つ力を養うために、宗教の必要性があるのです。
2010年05月12日
コメント(0)
-
【他の信仰をしている人へ】15・邪(じゃ)宗(しゅう)という呼び方が気に入らない
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 15・邪(じゃ)宗(しゅう)という呼び方が気に入らない 邪宗という言葉は、日蓮正宗の人が、やみくもに他宗を攻撃(こうげき)するために勝手に使っているのではありません。 釈尊は法華経に、「正直(しょうじき)に方便(ほうべん)を捨(す)てて但(ただ)無(む)上道(じょうどう)を説く」(方便品第二・開結一二四)と、四十余年にわたって説き続けてきた方便の経々(きょうぎょう)を捨てることを説き、これ以後に説示(せつじ)する法華経こそ最高唯一(ゆいいつ)の無上道であると言われています。また方便の経々に執着(しゅうちゃく)していた弟子の舎利弗(しゃりほつ)は自(みずか)ら、「世尊(せそん)我(わ)が心(こころ)を知(し)ろしめて、邪(じゃ)を抜(ぬ)き涅槃(ねはん)を説(と)きたまいしかば、我(われ)悉(ことごと)く邪見(じゃけん)を除(のぞ)いて空法(くうほう)に於(おい)て證(しょう)を得たり」(譬喩品第三・開結一三二)と述懐(じゅつかい)していますが、ここにも低級な教えによる考えを「邪見」と称(しょう)しています。 また、日蓮大聖人は末法の教主として、「正直に権教(ごんぎょう)の邪法(じゃほう)邪師(じゃし)の邪義(じゃぎ)を捨てゝ、正直に正法(しょうぼう)正(しょう)師(し)の正(しょう)義(ぎ)を信ずる」(当体義抄・御書701頁)ことが、もっとも大切であると教えています。 これらのことからも、邪宗・邪法などの言葉は仏の経説にしたがって使用していることがわかると思います。 ではなぜ他の宗派に対して、攻撃的(こうげきてき)なしかも刺激(しげき)の強い邪宗という呼び方をするのかといいますと、個人の苦しみや社会の不幸はすべて邪(よこし)まな宗教が元凶(げんきょう)となっているからであり、言いかえると誤った宗教、低劣な教えがこの世の不幸のたねだからです。 昭和二十年に広島市と長崎市に投下された原爆は一瞬のうちに何十万人という市民、それもなんの罪もない子供や老人まで無差別に殺戮(さつりく)しました。いま私たちが、核兵器の行使(こうし)が悪魔(あくま)の所業(しょぎょう)であると叫(さけ)び、この憎(にく)むべき不幸を二度とくり返してはならないと訴(うった)えるのは当然でしょう。そしてその不幸の原因が戦争であり、戦争は人間社会の誤った思想によって誘発(ゆうはつ)されたことを考えますと、誤った思想が何十万人、いな世界大戦で戦死した人を含めると何百万人、何千万人の命を奪ったことになるのです。このような殺人思想に対して、邪教・魔説と指弾(しだん)することは言いすぎでしょうか。失礼に当たるから控(ひか)えるべきなのでしょうか。 涅槃(ねはん)経(ぎょう)に、「悪象のために殺されては三趣(さんしゅ)に至らず、悪友のために殺されては必ず三趣に至る」と説かれています。この意味は災害や事故によって命を失っても地獄・餓鬼(がき)・畜生(ちくしょう)というもっとも苦しむ状態にはならないが、誤った教えを信ずるものは死して後に必ず三悪道(さんなくどう)に堕(お)ちて永劫(えいごう)に苦しみ続けるということです。 一切の不幸の元凶となる誤った宗教は、あたかも覚醒剤(かくせいざい)や麻薬(まやく)のように、本人も気付(きづ)かないまま、いつしか次第に身も心もむしばみ人生を狂(くる)わせていくのです。 正しい仏法に目醒(めざ)めた私たちが、誤った宗教を不幸の根源であると破折(はしゃく)し、邪宗と称することは、悪法に対する憤(いか)りであり、いまなお知らずに毒を飲んでいる人に対する警告(けいこく)の表(あら)われでもあるのです。
2010年05月05日
コメント(0)
-
【他の信仰をしている人へ】14・歴史のある有名な神社やお寺の方がありがたいと思うが
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 14・歴史のある有名な神社やお寺の方がありがたいと思うが 奈良や京都の歴史的に名高い神社や寺々は、今もなお多くの観光客が訪(おとず)れています。 たしかに年月を経(へ)た建物や、静かな庭園のたたずまいには、いかにも心をなごませる落ち着いたふんい気があります。 しかし、よくよく考えてみなければならないことは、宗教の本来の役割(やくわり)は物見遊山(ものみゆさん)や観光のためではなく、民衆を法によって救うことにあるということです。 歴史的に有名であったり、大ぜいの観光客が訪れるということと、実際にその寺院が人々の救済(きゅうさい)に役立っているか、また参詣者(さんけいしゃ)に功徳(くどく)を与えているかということとは別の問題なのです。 昔の人の川柳(せんりゅう)に「大仏は見る物にして尊ばず」という一句がありますように、奈良の大仏を見に行く人や、見上げてその大きさに感心する人はあっても、心から信じて礼拝(らいはい)合掌(がっしょう)する人はいないものです。 信仰心をもって行くというよりは、観光のために訪れるというのが本心でしょう。 古都(こと)の神社や寺々は、もはや宗教本来の目的を失い、拝観(はいかん)料(りょう)などの観光による財源(ざいげん)で建物を維持(いじ)することに窮々(きゅうきゅう)としているというのが現状です。 そのほか、正月や縁日(えんにち)に大ぜいの参詣者でにぎわう有名な寺社も、宗旨の根本である本尊と教義を調べてみると、まったく根拠(こんきょ)のない本尊であったり、仮りの教えであるなど、今日の人々の救済(きゅうさい)になんら役立つものではなく、むしろ正法流布のさまたげとなっているのです。 ところが宗教の正邪を判断できない人々は、開運(かいうん)・交通安全・商売繁盛(はんじょう)・厄除(やくよ)けなどの宣伝文句にさそわれ、これら有害(ゆうがい)無益(むえき)の寺社におしかけ、自(みずか)ら悪道の原因を積(つ)み重ねているのです。 日蓮大聖人は、「汝(なんじ)只(ただ)正理(しょうり)を以て前(さき)とすべし。別して人の多きを以て本とすることなかれ」(聖愚問答抄・御書402頁)と説かれているように、正しい本尊と、勝れた教法によって、民衆救済の実(じつ)をあげていくところに宗教の本質があるのであって、ただ歴史が古い、名が通っている、多くの参詣者でにぎわっているということをもって、その寺社を尊んだり勝れていると考えてはならないのです。 歴史的な建物や、庭園・遺跡(いせき)などには、それなりの価値(かち)はあるのでしょうが、人々を救済するという宗教本来の目的から見れば、これら有名な寺社にはなんらの価値(かち)もないばかりか、むしろ人生の苦悩(くのう)の根源となる悪法と、社会をむしばむ害毒(がいどく)のみがうずまいていることを知るべきです。
2010年04月28日
コメント(0)
-
【他の信仰をしている人へ】13・信仰は必要なときだけすればよいのではないか
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 13・信仰は必要なときだけすればよいのではないか “信仰を必要とする時”とは、どのような時を指(さ)すのでしょうか。苦境(くきょう)に立ってわらにもすがりたくなる時なのでしょうか。それとも慣例的(かんれいてき)に神社仏閣(ぶっかく)に参詣(さんけい)する正月や盆、彼岸(ひがん)を指すのでしょうか。あるいは冠婚(かんこん)葬祭(そうさい)の時でしょうか。または人生のなかで老境(ろうきょう)に至った時という意味でしょうか。 こうしてみると、“信仰を必要とする”といっても、受けとり方によって意味がまったく異(こと)なりますから、一部分のみをとらえて、そのよし悪(あ)しを論ずることはできませんが、いま質問の内容について、わかりやすく説明するために、“信仰をしなくともよい時”があるかどうかを考えてみましょう。 そのためには、まず信仰にどのような意義があるかを知る必要があります。 信仰の意義として大要(たいよう)次の三点が挙(あ)げられます。 第一に正しい宗教は、人間の生命を含む時間空間を超(こ)えた宇宙(うちゅう)法界(ほうかい)の真理を悟(さと)った本仏が、私たち衆生(しゅじょう)に対して人間のもっとも大切な根本の道を教え示されたものなのです。それはあたかも人生という草木を生育(せいいく)している大地のようなものであり、人間という電車を幸せに向って快適(かいてき)に走らせるためのレールのようなものです。私たちの人生は老(お)いも若きも平等に時々(じじ)刻々(こくこく)と過ぎ去って行きます。誰(だれ)もが毎日毎日が、生きた草木であり、走りつつある電車なのです。はたして生きた草木にとって大地がなくてもよい時があるのでしょうか。また走りつつある電車にレールがなくてもよい時があるのでしょうか。宗教とは人間の根本となる教えということであり、宗教のない人生は人間としての根本の指針(ししん)を欠落(けつらく)した、さまよえる人生というべきなのです。 第二に正しい宗教を信ずることは、成仏という人間としてもっとも崇高(すうこう)な境界(きょうがい)を目標として修行することです。成仏とは、個々の生命に仏の力と智慧(ちえ)を涌現(ゆげん)させ、何ものにも崩(くず)れることのない絶対的に安穏(あんのん)で自在(じざい)の境地(きょうち)を築(きず)くことであり、この高い目的地に至るためには、たゆまぬ努力と精進(しょうじん)が必要です。どんな世界でも、高い目標を目指し、ひとつの道を極(きわ)めるためには、正しい指導とたゆまぬ修行鍛錬(たんれん)がなければならないことはいうまでもありません。思いついた時、気が向いた時だけ一時的に信仰するというのは、学生が気が向いた時だけ学校に行くということと同じであり、真の目的をなしとげることはできません。 第三に正しい宗教とは人生の苦悩(くのう)を根本的に解決するためのものであり、これを実践(じっせん)(信仰)すれば自(おの)ずと苦悩を乗り越える勇気と智慧などの生命力が備(そな)わるのです。それのみならず正法を信ずることによって、日常生活が仏天(ぶってん)の加護(かご)を受けることも厳然(げんぜん)たる事実です。自分の将来に対する不安や性格的な悩み、さらには家族や職場での問題など、誰もが多くの解決すべき難問や悩みを抱(かか)えながら生きているのではないでしょうか。また明日どころか一時間さきに何が起きるかわからない私たちは、自分の人生がいつ、どこで幕を閉(と)じるかもわからないのです。“必要な時が来れば信仰する”などと言って、今日一日を自分勝手な思いつきで過ごすことは、かけがいのない人生の時間を無駄(むだ)にしているといわざるをえません。 あなたにとって“信仰が必要な時”、それはいまを置(お)いてないのです。
2010年04月22日
コメント(4)
-
【他の信仰をしている人へ】12・信仰の自由は憲法でも保障されているのだから、なにを信じてもよいはずだ
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 12・信仰の自由は憲法でも保障されているのだから、なにを信じてもよいはずだ 日本国憲法の第二十条に、「信教(しんきょう)の自由は、何人(なんびと)に対してもこれを保障する」と、明確に信教の自由が保障されています。 この条目は、かって古代、中世より近世にいたる長い国家権力による、宗教統制(とうせい)の歴史の反省から、信教の自由が国民の一人ひとりに始めて保障されたものです。 朝廷(ちょうてい)による宗教への保護と規制(きせい)、また、江戸幕府の寺請制度(てらうけせいど)と転宗(てんしゅう)の禁制(きんせい)、近代国家主義下の神道(しんとう)の強制などの歴史を経(へ)て、今こそ自由にみずからの意志で宗教を選び、弾圧(だんあつ)、迫害(はくがい)の恐れもなく、堂々と信仰ができる時代となったのです。 しかし、ここで私たちが注意しなくてはならないことは、どのような信仰を持(たも)とうとも、確(たし)かに法律の上では自由を保障される時代を迎えたとはいえ、信教の自由の意味を単(たん)に、宗教の正邪、善悪(ぜんあく)を無視(むし)して、何をどう信じてもいいと、安易(あんい)にとらえてはならないということです。 信教の自由は、個人個人が自分の意志で、宗教の正邪・浅深を判断し、より正しく勝れたものを選び取る権利を持つということであり、その権利の行使(こうし)には、それを正しく役立てていく、主権者(しゅけんしゃ)としての責任もあるのです。 法律の上では宗派の持つ教義の正邪の判断を下(くだ)し、規制することはできませんが、実際に宗教を選ぶという時には、一人ひとりが正邪を厳(きび)しく判定して、唯一(ゆいいつ)の正法を選ぶことが肝要(かんよう)です。 信教に限らず、尊い自由の保障を受けた私たちは、この自由の基本的な権利を積極的に生かし、自(みずか)らの責任において、立派(りっぱ)にその恩恵(おんけい)を行使していく意志を持たなくてはなりません。 せっかく憲法で保障された信教の自由を、放逸(ほういつ)(わがまま)の意味に曲解(きょっかい)するのは、あまりにも無責任に過(す)ぎます。
2010年04月20日
コメント(0)
-
【他の信仰をしている人へ】11・自分は先祖の位牌を祭っているので、それで充分だ
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 11・自分は先祖の位牌を祭っているので、それで充分だ 位牌(いはい)とは昔(むかし)中国において、存命(ぞんめい)中(ちゅう)に受けた官位(かんい)や姓名(せいめい)を記(しる)した木牌(もくはい)に始まるといわれています。 日本では、葬儀(そうぎ)のときに白木(しらき)の位牌に法名(ほうみょう)、俗名(ぞくみょう)、死亡年月日、年齢(ねんれい)を記して、祭壇(さいだん)に安置します。これは、回向(えこう)のためと、参列者(さんれつしゃ)に法名などを披露(ひろう)するためのならわしといえます。 したがって位牌そのものを、礼拝(らいはい)の対象(たいしょう)にしたり、死者の霊が宿(やど)っているなどと考え、それに執着(しゅうちゃく)するのは誤りです。 位牌はけっして本尊のような信仰の対象物ではなく、位牌を拝(おが)んだからといって、死者の霊を慰(なぐさ)めることができるというものではありません。 世間(せけん)の多くの人々が白木の位牌を、のちに金箔(きんぱく)などの位牌に改(あらた)め、その位牌を守ることがいかにも尊い大事な意味を持っているように考えていますが、これも本来の死者の成仏、死者に対する回向、供養とは何の相関(そうかん)関係(かんけい)もないことなのです。 真実の死者に対する供養のためには、なによりも一切の人々を救済(きゅうさい)成仏(じょうぶつ)させうる力と働きと法門の備(そな)わった本門の本尊を安置し、本門の題目を唱えて、凡身(ぼんしん)を仏身(ぶっしん)へ、生死(しょうじ)を涅槃(ねはん)へと導くことに尽(つ)きるのです。 日蓮大聖人は、「今末法は南無妙法蓮華経の七字を弘めて利生得益(りしょうとくやく)有るべき時なり。されば此(こ)の題目には余事(よじ)を交へば僻事(ひがごと)なるべし。此(こ)の妙法の大(だい)曼(まん)荼(だ)羅(ら)を身に持(たも)ち心に念じ口に唱へ奉るべき時なり」(御講聞書・御書1818頁)とも、また、「但(ただ)南無妙法蓮華経の七字のみこそ仏になる種には候へ」(九郎太郎殿御返事・御書1293頁)と説かれています。 父母の成仏や、我が身の成仏を願い、一家の幸せを築くためには、一閻浮提(いちえんぶだい)第一の本門の本尊を持ち、その御本尊に整足(せいそく)する成仏の種子(しゅし)たる南無妙法蓮華経の本門の題目を唱える以外には絶対にありえないのです。 したがって位牌も塔婆(とうば)も、この本門の本尊のもとにあって、しかも題目をしたためてこそ、死者の当体を回向する十界(じっかい)互具(ごぐ)一念三千(いちねんさんぜん)の法門の原理が具(そな)わるのです。梵字(ぼんじ)や新寂(しんじゃく)・空(くう)などの字が刻(きざ)まれた他宗の位牌や塔婆を建てることは、仏の本意にもとづく供養の仕方(しかた)ではありませんから、先祖のためには、かえってあだとなり、実際には先祖を苦しめ正法不信の罪過(ざいか)を重ねる結果となってしまうのです。
2010年04月18日
コメント(6)
-
【他の信仰をしている人へ】10・自分の気に入った宗教が一番よいと思う
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 10・自分の気に入った宗教が一番よいと思う 近年、世間を騒がせたオウム真理教の信徒たちは、麻原教祖に洗脳されて、ある者は殺人者となり、ある者は見せしめのために殺されました。 またアメリカにおいては、人民寺院を標榜(ひょうぼう)(主張)する新興宗教の教祖の教えによって、集団生活をしていた千名近い信者が、ことごとく自殺して果(は)てるというすさまじい事件もありました。 こうしたことは、極端(きょくたん)な例ですが、誤った思想や宗教の恐しさを如実(にょじつ)に象徴(しょうちょう)したものといえます。 人はかたよった思想や邪宗教にとりつかれてしまいますと、その教えに熱中するあまり、人を人とも思わず、人の命すら自分たちの集団の論理で平気で葬(ほうむ)ってしまうのです。 思想や信条、ことに宗教という人間の生活規範(きはん)にかかわる大切なものは、何よりも明るく清々(すがすが)しく健康的な理念で、うら打ちされていることが必要です。人々を心の底から躍動(やくどう)させる歓(よろこ)びにあふれたものでなければなりません。 洋服や食べ物ならば、自分の好きなものを選べばよいのですが、自分の人生や家庭、生活に重大な影響(えいきょう)を持つ宗教の場合は、その根本たる本尊や教義の内容を正しく取捨(しゅしゃ)選択(せんたく)することが大切です。 宗教の正邪・勝劣を知るためには、少なくともその宗旨が何を本尊とし、何を信仰の対象(たいしょう)としているかということを、まず尋(たず)ねる必要があります。 また、本尊とともに、その宗教の教義が正しいと判断されるためには、一切の人々が過去・現在・未来の三世(さんぜ)にわたって救済(きゅうさい)されるのみならず、地獄界から仏界(ぶっかい)に至る十界(じっかい)のことごとく生きとし生けるもののすべてが、根本的に救われる道理と法門が解き明かされていなければなりません。 日蓮大聖人は、「同じく信を取るならば、又大小権実(ごんじつ)のある中に、諸仏出世の本意(ほんい)、衆生成仏の直道(じきどう)の一乗をこそ信ずべけれ。持(たも)つ処(ところ)の御経の諸経に勝(すぐ)れてましませば、能(よ)く持(たも)つ人も亦(また)諸人にまされり」(持妙法華問答抄・御書297頁)と仰せられています。 信仰を志(こころざ)すならば、好ききらいで判断するのではなく、もっとも勝れた本尊と教義のもとに誓願(せいがん)の尊(とうと)さと修行の正しさを教示された宗教を求めるべきです。そして永遠性や普遍性(ふへんせい)にとみ、広大(こうだい)無辺(むへん)の功徳の備(そな)わった世界一の宗教を持(たも)つべきです。
2010年04月14日
コメント(2)
-
【他の信仰をしている人へ】9・先祖が代々守ってきた宗教を捨てることはできない
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 9・先祖が代々守ってきた宗教を捨てることはできない 誰(だれ)しも先祖代々長く守ってきた宗教に愛着(あいちゃく)があり、その宗(しゅう)旨(し)を捨てることは先祖の意に背(そむ)くように思い、一種の恐れのような感情を抱(いだ)くのは、無理からぬことです。 しかし、先祖がいったい、どうしてそうした宗教を持(たも)ち、その寺の檀家(だんか)になったかということを、昔にさかのぼって、考えてみますと、その多くは、慶長(けいちょう)十七年(一六一二年)に始まる徳川幕府の寺請(てらうけ)制度(せいど)によって、強制的に菩提寺(ぼだいじ)が定められ、宗門(しゅうもん)人別(にんべつ)帳(ちょう)(戸籍(こせき))をもって、長く管理統制(とうせい)されてきた名残(なご)りによるものと思われます。 江戸時代は信仰しているかどうかにかかわらず、旅行するにも、移(い)住(じゅう)するのにも、養子(ようし)縁組(えんぐみ)するにも、すべて寺請(てらうけ)の手形(てがた)の下付(かふ)が必要だったのです。もちろん宗旨を変えたり檀家(だんか)をやめることは許(ゆる)されませんでした。 したがって、庶民は宗教に正邪浅深があり、浅い方便(ほうべん)の教え(仮りの教え)を捨てて、真実の正法につくなどという化導(けどう)を受ける機会もありませんでした。せいぜい現世(げんぜ)利益(りやく)を頼(たの)んで、檀家制度とは別に、有名な神社仏閣(ぶっかく)の縁日(えんにち)や祭礼(さいれい)に出かけたり、物見(ものみ)遊山(ゆさん)を楽しむぐらいのものでした。 しかし現代は、明治から昭和にかけての国家権力による宗教統制もようやく解(と)けて、真に信教の自由が保(ほ)障(しょう)され、みずからの意志で正しい宗教を選び、過去の悪法や制度に左右されることなく、堂々と正道を求めることができる時代になったのです。 言葉をかえて言えば、今こそ先祖代々の人々をも正法の功力(くりき)によって、真の成仏に導(みちび)くことができる時がきたのです。 釈尊の本懐(ほんがい)である法華経には、 「此(こ)の経(きょう)は持(たも)ち難(がた)し、若(も)し暫(しばら)くも持(たも)つ者(もの)は我(われ)即(すなわ)ち歓喜(かんぎ)す諸仏(しょぶつ)も亦(また)然(しか)なり」(宝塔品第十一・開結三五四)と説かれています。 すなわち、世間の人々の中(ちゅう)傷(しょう)や妨害(ぼうがい)のなかで、妙法蓮華経の大法を信じ持つことは、なまやさしいことではありません。しかし、持(たも)ち難(がた)く行じ難いからこそ、三世(さんぜ)十方(じっぽう)の諸仏は歓喜して、その妙法の持者を守るのだと説かれているのです。 また日蓮大聖人は、「今(いま)日蓮等(ら)の類(たぐい)聖(しょう)霊(りょう)を訪(とぶら)ふ時、法華経を読誦(どくじゅ)し、南無妙法蓮華経と唱へ奉(たてまつ)る時、題目の光無間(むけん)に至って即身(そくしん)成仏(じょうぶつ)せしむ」(御義口伝・御書1724頁)と仰(おお)せられています。 ほんとうに先祖累代(るいだい)の父母を救おうと思うならば、日蓮大聖人の仰せのように、一乗の妙法蓮華経の題目の功徳を供(そな)え、真実の孝養をつくすことが肝心(かんじん)なのです。 今のあなたが、先祖が長い間誤(あやま)りをおかしてきた宗教を、そのまま踏襲(とうしゅう)することは、あまりにもおろかなことです。 自分のあさはかな意(こころ)にしたがうのではなく、正法にめざめてこそ、始めて先祖累代の人々を救い、我が家の幸せを開拓(かいたく)し、未来の人々をも救いうるのだということを知るべきです。
2010年04月13日
コメント(0)
-
【他の信仰をしている人へ】8・他の宗教によって現実に願いがかなったので信じているが
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 8・他の宗教によって現実に願いがかなったので信じているが 日蓮正宗以外の宗教を信じ、“商売がうまくいった”とか、“病気が直(なお)った”という人がいます。また日蓮正宗に入信しても、初めは周囲の反対や人間関係などで苦労する人もいるかもしれません。 しかし、正しい仏法とは私たちに正しい本尊と修行を教え、身心両面にわたって育成(いくせい)錬磨(れんま)し、究(きゅう)極(きょく)の目的である仏の道を成就(じょうじゅ)させることを目的としています。 正しい仏道修行をすることによって、いかなる苦難(くなん)や障害(しょうがい)がおきてもそれを乗り越えていける人こそ真に幸せな人なのです。困った時だけ拝(おが)み屋のような宗教にすがって一時しのぎの解決をしても、それは人生の本質的な幸福につながるものではありません。たとえば、勉強をしない子供に試験の時に答(こた)えだけを教えて、よい点数をとらせたからといって、その子供の学力が向上(こうじょう)することにならないと同様(どうよう)なのです。 もし現在、悩みがあったとしても、善因(ぜんいん)を積んで善果(ぜんか)を生ずるように、その原因をよく知って、正法(しょうぼう)正(しょう)義(ぎ)に帰依(きえ)しなければ真の解決にならないことを知るべきです。 また、低俗な宗教によって悩みが一時的に解決したからといって、それが人生のすべてに通用し、人生の苦を根本から解決できることになるわけではありません。むしろ苦難に遭(あ)った時に努力することを忘れて一時の神だのみに走ることだけが身についてしまうでしょう。それはその人にとって決してよい結果とはいえません。 悩みや問題はひとそれぞれにさまざまですが、その人の生(お)い立ちや周囲の縁(えん)、年齢や心がけなどによって解決のかたちもまた異(こと)なっています。 たとえば、種(たね)をまいても直(ただ)ちに花を開かせることはできませんが、時が至れば必ず開花するように、時(とき)と機(き)が熟(じゅく)さなければ解決しない場合もあるのです。 また誤った宗教に縁することによって、願いがかなったこと以上に生命が汚染(おせん)され、将来大きな苦しみを生ずる業因(ごういん)となることをよく認識(にんしき)すべきです。 日蓮大聖人は、「現在に一分(いちぶん)のしるしある様なりとも、天地の知る程(ほど)の祈(いの)りとは成るべからず。魔王(まおう)・魔民(まみん)等(ら)守護(しゅご)を加へて法に験(しるし)の有(あ)る様(よう)なりとも、終(つい)には其(そ)の身(み)も檀那(だんな)も安穏(あんのん)なるべからず」(諌暁八幡抄・御書1531頁)と仰(おお)せられ、一時的に祈りがかなったように見えても、邪宗教によるものは、正法を隠蔽(いんぺい)しようとする魔の所為(しょい)(行(おこ)ない)にすぎないと説かれています。 そして正法による祈りについて、「大地はさゝばはづるゝとも、虚空(おおぞら)をつなぐ者はありとも、潮(しお)のみ(満)ちひ(干)ぬ事はありとも、日は西より出づるとも、法華経の行者の祈りのかな(叶)はぬ事はあるべからず」(祈祷抄・御書630頁)とものべられ、人生根本の大願(だいがん)たる成仏も、強い信心によって必ずかなうと教示(きょうじ)されています。 また日寛上人も、日蓮大聖人建立(こんりゅう)の大御本尊の利益(りやく)について、「この本尊を信じて南無妙法蓮華経と唱うれば、則(すなわ)ち祈りとして叶(かな)わざるなく、罪(つみ)として滅(めっ)せざるなく、福として来(き)たらざるなく、理として顕(あら)われざるなきなり」(観心本尊抄文段・文段集四四三)と仰せられています。 真実の祈りは、正法正義による仏道修行によってかなうのであり、低俗な宗教によるならば、かえって苦業(くごう)をますことを知るべきでありましょう。
2010年04月12日
コメント(0)
-
【他の信仰をしている人へ】7・他の宗教で幸福になった人もいるのではないか
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 7・他の宗教で幸福になった人もいるのではないか 私たちの周囲には、さまざまな宗教や信仰によってそれなりの幸せを感じて暮(くら)している人もいるようです。 しかし人は幸福そうに見えていても、その実体(じったい)はわからないものです。 外見(がいけん)は大邸宅(だいていたく)に住み、社会的にも恵まれた地位にありながら、非行や障害(しょうがい)のある子供を持って、苦労している人もあり、家庭内の不和や、親族間の財産争(あらそ)いに明けくれている家もあります。 また、現在は一時的に満足できても、明日(あす)の確(たし)かなる保(ほ)障(しょう)は、どこにもないのです。 したがって、他の宗教を信じて確かに幸せになったなどと軽々(けいけい)に結論を下(くだ)すことはできません。 また、「積善(せきぜん)の家には余慶(よけい)あり」ということわざがあるように、その家の過去の人々の善業(ぜんごう)が、今の人々の身の上に余徳(よとく)となって現(あら)われている場合もありましょう。 信仰には、確かに現世(げんせ)の利益(りやく)がなくてはなりませんが、反面、その一時の小さな利益のみに眼がくらんではならないのです。 たとえば、ある宗教を信じ、高名(こうめい)な霊能者(れいのうしゃ)などに相談を持ちかけ、少しばかりよいことがあったり、商売が上向(うわむ)いたことがあったばかりに、その宗教や霊能者に執心(しゅうしん)して、真実の仏法の正邪(せいじゃ)や、正しい因果(いんが)の道理に則(のっと)った判断ができなくなってしまうようなものです。 他の宗教で幸福になったと思う人も、大概(たいがい)はこうした人々であって、いわば一時の低い利益に酔(よ)いしれているようなものです。厳(きび)しい言い方をすれば、浅薄(せんぱく)な宗教を信ずるということは、より勝(すぐ)れた根本の教えを知らず、結果的には最勝の教えに背(そむ)くということであり、その背信(はいしん)の罰(ばち)をのがれることはできません。 ちょうど、悩みや苦しみを、お酒によってまぎらわしたり、麻薬(まやく)の世界に一時の楽しみを求めた人たちが、その悦楽(えつらく)から抜け出せず、結局、アルコール中毒や、取り返しのつかない廃人(はいじん)となってしまうように、他宗の小利益に執(しゅう)する末路(まつろ)には、大きな不幸、すなわち、最高・最善の仏法に背く大罰(だいばち)が待ちうけているということを知らなければなりません。 つまり、いつとはなしに身心ともにむしばまれた、地獄(じごく)のような生活に堕してしまうのです。 日蓮大聖人は、「当(まさ)に知るべし、彼の威徳(いとく)有りといへども、猶(なお)阿鼻(あび)の炎(ほのお)をまぬか(免)れず。況(いわ)んやわづかの変化(へんげ)にをいてをや。況(いわ)んや大乗誹謗(ひぼう)にをいてをや。是(これ)一切衆生の悪知識なり。近付くべからず。畏(おそ)るべし畏るべし」(星名五郎太郎殿御返事・御書366頁)と説かれており、他宗を信ずることによってもたらされる現象(げんしょう)は、けっして功徳とはならず、むしろ、正法への帰依(きえ)を妨(さまた)げ、不幸へと導く悪知識(あくちしき)であると仰(おお)せです。 幸福の条件のひとつには、現在の生活の上におけるさまざまな願望(がんぼう)の充足(じゅうそく)が挙(あ)げられますが、人間にとって、最高の幸せはなんといっても、過去・現在・未来の三世(さんぜ)にわたる、ゆるぎない成仏の境界(きょうがい)であって、真の幸福とはここに極(きわ)まるものなのです。 そして、この三世にわたる成仏は、日蓮大聖人の南無妙法蓮華経の大法を離れては、絶対にありえないのです。
2010年04月05日
コメント(2)
-
【他の信仰をしている人へ】6・先祖を崇拝することがまちがっているのか
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 6・先祖を崇拝することがまちがっているのか 先祖を敬い、崇めることは、仏法の教義に照して、決してまちがいではありません。むしろ人間としてたいへん立派な行為といえます。 しかし先祖を神として祭ったり、「仏」と呼んで祈願や礼拝の対象とすることは誤りです。なぜならば先祖といっても、私たちと同じようにひとりの人間として苦しんだり悩んだり、失敗したり泣いたりしながら生きた人たちであり、生前も死後も悪縁によれば苦を感じ、善縁すなわち正法によれば安楽の果 報を受ける凡夫であることに変わりがないからなのです。言いかえれば人間は死ぬことによって、正しい悟りが得られるわけではありませんし、子孫を守ったり苦悩から救ったりできるわけでもないということです。 世間では先祖や故人を「仏」と呼ぶ場合がありますが、これは仏教の精神から見て正しい用法ではありません。 仏とは仏陀(ぶっだ)とも如来(にょらい)ともいい、この世の一切の真実の相(すがた)と真理を一分のくもりもなく悟り極めた覚者という意味です。仏教の経典には阿弥陀仏や薬師仏、大日如来などたくさんの仏が説かれておりますが、これらの仏について、法華経には、 「此の大乗経典は諸仏の宝蔵なり。十方三世の諸仏の眼目なり。三世の諸の如来を出生する種なり」(観普賢経・開結六二四) と説かれ、日蓮大聖人も、 「三世の諸仏も妙法蓮華経の五字を以て仏になり給ひしなり」(法華初心成仏抄・新編一三二一) とのべられているように、多くの仏はすべて大乗経典たる妙法蓮華経という本法を種として仏となることができたのです。 この原理は私たちや先祖が何によって真に救われるかをはっきり示しています。 すなわち本当に先祖を敬い、先祖の恩に報いる気持ちがあるならば、生者死者をともに根本から成仏せしめる本仏本法に従って正しく回向(えこう)供養しなければなりません。 また先祖の意志を考えてみますと、先祖の多くはわが家の繁栄と子孫の幸せを願って苦労されたことでしょう。急病の子供を背負って医者を探し求めたこともあったでしょうし、妻子を助けるために我が身を犠牲にされた方もいたことと思います。このように一家の繁栄と幸福を願う先祖がもし、自分の子孫のひとりが、真実の仏法によって先祖を回向し、自らも幸せになるために信仰を始めたことを知ったならば、家代々の宗教を改めたことを悲しむどころか、「宿願(しゅくがん)ここに成れり」と大いに喜ぶはずです。 先祖を救うという尊い真心を正しく生かすためには、先祖の写真や位牌を拝むことではなく、三世諸仏の本種(ほんしゅ)である南無妙法蓮華経の御本尊を安置し、読経唱題して回向供養することがもっとも大切なのです。 大聖人は、 「父母に御孝養の意あらん人々は法華経を贈り給ふべし。(中略)定めて過去聖霊(しょうりょう)も忽(たちま)ちに六道の垢穢(くえ)を離れて霊山浄土へ御参り候らん」(刑部左衛門尉女房御返事・新編一五〇六) と、妙法によって先祖を供養するよう教えられています。
2010年04月03日
コメント(0)
-

28日はさむかったよぉ~
逆光で見にくいかなぁ~ 法華講春季総登山に参加して来ました~(^O^)/ 寒くてぇ~ 桜の蕾も固い感じでした~ しだれ桜と三門からの参道の桜は綺麗に咲いてました~ 今年は4月に入ってもしばらく持ちそうですよぉ~ 私は有り難いことに今年~はじめてぇ~大法要のお虫払い会に参加させていただきますぅ~o(^-^o)(o^-^)o その時に満開かなぁ~ あ~ 桜も持ちそうだから~桜を見に来ませんかぁ~ 4月11日(日)も行ってます~(^_-)-☆ポテ~
2010年03月30日
コメント(4)
-
【他の信仰をしている人へ】5・仏教はすべて釈尊(しゃくそん)から出ているのだから、どれを信じてもおなじではないか
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 5・仏教はすべて釈尊(しゃくそん)から出ているのだから、どれを信じてもおなじではないか 今から三千年前にインド北部のカピラ城の王子として誕生(たんじょう)した釈尊は、十九歳のとき修行者となり、三十歳の時にガヤ城の近くで悟(さと)りを開きました。その後八十歳で入滅するまで五十年の間、人々に悟りの法を教えるためにさまざまな教えを説きました。 中国の天台大師は、釈尊の五十年間の説法を深く検討(けんとう)して、その内容から説法の時期を五つに区分しました。これが「五時(ごじ)」といわれるものです。また「八教(はっきょう)」という区分けもしていますが、ここでは「五時」によって説明しましょう。 第一は華厳時(けごんじ)といって、釈尊は開悟(かいご)の後(のち)、直(ただ)ちに二十一日間にわたって哲学的な十玄(じゅうげん)六相(ろくそう)などの教理を説きましたが、聴衆(ちょうしゅう)はまったく理解できませんでした。 第二は阿含時(あごんじ)といって戒律(かいりつ)を中心とした教えを十二年間説きました。これは三蔵(さんぞう)教(きょう)あるいは小(しょう)乗(じょう)教(きょう)といわれ、仏教の中でもっとも低い教義です。 第三は方等時(ほうどうじ)といって幅(はば)広い内容の教えを十六年間説きました。これは弾訶(だんか)といって小乗教に執着(しゅうちゃく)する人を叱責(しっせき)し、大乗教(だいじょうきょう)すなわち自分のみでなく他人をも内面から救う教えに帰(き)入(にゅう)させるものです。 第四は般若時(はんにゃじ)といって十四年間、空(くう)すなわちこの世のものは何(なに)ひとつとして定(さだ)まった実体(じったい)などなく、執着(しゅうちゃく)すべきものはないという教えを説きました。この般若と第一華厳・第三方等は大乗教ですが、いまだ釈尊が久遠(くおん)の仏であることを明さず、人生の目的は三乗(さんじょう)(声聞(しょうもん)・縁覚(えんがく)・菩薩(ぼさつ))にあるとして、真実を示さない仮(か)りの教えでした。釈尊は第五時の法華経を説法するために、まず無(む)量(りょう)義(ぎ)経(きょう)を説きましたがその中で、“仏の眼(まなこ)をもって衆生の根性(こんじょう)を見るに、人々は種々様々(さまざま)の心(こころ)根(ね)だったので、まずそれを調(ととの)えるために種々の方便の力を用(もち)いたり、仮りの法を説いたのである”と説明し、「四(し)十(じゅう)余(よ)年(ねん)には未(いま)だ真実(しんじつ)を顕(あらわ)さず」(無量義経・開結二三)と説いています。そして法華経八年間の説法で、はじめて真実の教えとして、いかなる人もその身のままで仏の境界(きょうがい)に至る一仏乗の法を説きあらわしたのです。 現在、東大寺(とうだいじ)を本山とする華厳宗は第一華厳時の教義を所依(しょえ)とし、タイやビルマなどに残っている戒律仏教や、律宗(りっしゅう)などは第二阿含時の経典を教義としています。また浄土宗、禅宗、真言宗、法相宗などは第三方等時の経典からそれぞれ宗義を立てており、天台宗や日蓮宗各派のように法華経を依経(えきょう)としていても迹門(しゃくもん)の観念的(かんねんてき)教理を中心としているなど、いずれの宗派も、末法現時に適した究極(きゅうきょく)の教えである法華経本門の法を依(え)教(きょう)としていません。法華経本門の教えとは、釈尊が久遠の昔(むかし)に成仏するために修行した根本の原因となる一法であり、それは日蓮大聖人が唱えあらわされた南無妙法蓮華経に尽(つ)きるのです。 このように同じ仏教といっても、教義の内容や目的、そして修行もまったく違うのですから仏の本意に基(もと)づく真実の教えに帰依(きえ)しなくてはなりません。
2010年03月30日
コメント(0)
-
【他の信仰をしている人へ】4・どんな宗教にも、それなりの利益(りやく)があるのではないか
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 4・どんな宗教にも、それなりの利益(りやく)があるのではないか すべての宗教かどうかはわかりませんが、低級宗教や教義もないような宗教、あるいは宗教ともいえない精神統一などにも一分(いちぶん)の利益というべき結果が見られる場合があります。人によってはこの一分の結果や様相(ようそう)が御(ご)利益(りやく)のように感じられるのでしょう。しかし、人間の生命には一念三千といって三千種類の生命状態が可能性として潜在(せんざい)しており、それが縁(えん)にふれて様々(さまざま)な作用をするわけですから、周囲の状態(縁(えん))を変えることによって今までとは違った心境や状態になることもありうるのです。生活と仕事に追われていた人が、心を鎮(しず)めて何(なに)かを拝(おが)み祈ることによって、今までとは違った心境になるでしょうし、時には精神の変化が肉体に影響して病気が好転(こうてん)することも不思議なことではありません。 また、祈祷師(きとうし)や占(うらな)い師(し)などのように利根(りこん)や通力(つうりき)という一種の超能力(ちょうのうりょく)をもって、他人の願いごとを祈ったり、将来を占(うらな)い、それが時にはかなったり当たったりすることもあるでしょう。これなども人間生命の潜在的(せんざいてき)可能性の一分が現(あら)われたものであり、あっても不思議ではありません。 しかし日蓮大聖人は、「利根(りこん)と通力(つうりき)とにはよるべからず。」(唱法華題目抄・御書233頁) と説かれ、人間の真の幸福は仏の境界(きょうがい)に至ることであり、このような超能力によってはいけないと戒(いまし)めています。 ともあれ、宗教の高低・正邪をとわず、いずれの宗教にも一部分の利益ともいうべきものがあるかも知れませんが、私たちの真実の幸福は一時的な神だのみや、目先(めさき)の急(きゅう)場(ば)しのぎによって得(え)られるものではなく、宇(う)宙(ちゅう)法界(ほうかい)を悟(さと)った仏の教えにしたがい、正しい本尊を信仰することによって得られるものなのです。すなわち本仏の慈悲によって仏天(ぶってん)の加護(かご)を受け、正しい信心と修行によって人間としての福徳を備(そな)え、清浄(せいじょう)にして自在な仏の境界を現実生活の中で生かしていくことが仏教の目的であり、真実の大利益なのです。 たとえば、ここに幸福に到達する正しい道と不幸に至る邪(よこしま)な道があるとします。正しい道は向上(こうじょう)するものですから、険(けわ)しい坂道や困難な壁(かべ)にぶつかることもありましょう。反対に邪な道は下降(かこう)する道ですから、快適(かいてき)な下り坂があり途中には美しい花が咲いているかもしれません。しかし一輪の花や下り坂に魅(み)せられて不幸な破滅の道を選ぶべきではありません。邪な宗教によって一分の利益がもたらされるのは、あたかも詐欺師(さぎし)がはじめに正直者(しょうじきもの)を装(よそお)い、おいしい餌(えさ)を相手に与えるようなものであり、正しい宗教に帰依(きえ)することを妨(さまた)げようとする魔(ま)の働きなのです。 一時的、表面的な結果のみにとらわれることなく、正しい教理と経文、そして現実の証拠(しょうこ)がそなわっている正しい宗教によって、正しい人生を歩(あゆ)むことこそ人間としてもっとも大切なことなのです。
2010年03月26日
コメント(0)
-
【他の信仰をしている人へ】3・どんな宗教にもよい教えが説かれていると思うが
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 3・どんな宗教にもよい教えが説かれていると思うが これについて二点から考えてみましょう。 その第一は、教義の善(よ)し悪(あ)しとは何(なに)によって決められるかということであり、第二には宗教とは観念的(かんねんてき)な理論のみではなく、実践(じっせん)がともなうものであるということです。 まず第一の教義の善し悪しですが、もし一般的な道徳や常識という見地(けんち)に立てば、人殺しや盗みを奨励(しょうれい)する宗教でないかぎり、よい教えを説いているようにみえます。 しかし、宗教は個人の身体(しんたい)と精神を含(ふく)む全人格が帰(き)命(みょう)し、よりどころとするものですから、高い教えと低い教え、部分的な教えと大局的(たいきょくてき)な教えの相違は、信ずる人間性に対して敏感(びんかん)に影響(えいきょう)します。したがってひとりの人間をより根本から蘇生(そせい)させ本源的に救済するためには低級で部分的なものではなく、高度で大局的な教えに帰依しなければなりません。 日蓮大聖人は、「所詮(しょせん)成仏(じょうぶつ)の大綱(たいこう)を法華に之(これ)を説き、其(そ)の余の網目(もうもく)は衆典(しゅうてん)に明かす。法華の為の網目なるが故に」(観心本尊得意抄・御書915頁)と仰(おお)せられ、法華経という大綱があって、はじめて法華経以前に説かれた諸々(もろもろ)の教えが生かされると説かれています。 仏教以外のキリスト教やマホメット教、儒教(じゅきょう)、神道(しんとう)、なども一見すると人倫(じんりん)の道が説かれており道徳的にはよい教えのようですが、人間の三世(さんぜ)にわたる生命論や、人間が具有(ぐゆう)する十界三千の実相(じっそう)が説かれていませんし、これらを仏教とりわけ法華経と比(くら)べるとまったく低級な宗教であることがわかります。また、「無量義(むりょうぎ)とは一法(いっぽう)より生(しょう)ず」(無量義経・開結一九) ともいわれますように、唯一(ゆいいつ)無二(むに)の大綱たる一法を信受するとき、種々の経々に説かれている功徳利益(りやく)のすべてがはじめて生きてくるのです。 この一法こそ仏法の上からいうところの真実の一法であり、もっとも正しい教えなのです。 次に宗教には必ず実践(じっせん)がともないますから、理論的にはいかに立派な教えであっても、それが現実に生かされないものであれば、なんの役にも立ちません。 その理論的教義を現実に証明し民衆を救済する教主(きょうしゅ)が出現するかしないかは、その宗教が真実か空想かという違いでもあります。教主がみずから出現し、正(しょう)法(ぼう)正(しょう)義(ぎ)を説いてそれを実践し証明したとき、はじめてその宗教は信憑性(しんぴょうせい)のある宗教といえるのです。 たとえば新興宗教のなかにモラロジー(最高道徳)という宗教がありますが、その教義は“釈迦・キリスト・孔子などの教えの中からそれぞれよいところだけを取り出して実践する”というものです。しかし、同じ釈尊の教えの中でも、二百五十戒、五百戒という戒律(かいりつ)の実践を説く教えもあれば六度(ろくど)の修行(布施(ふせ)・持戒(じかい)・忍辱(にんにく)・精進(しょうじん)・禅定(ぜんじょう)・智慧(ちえ))もあり、以(い)信得入(しんとくにゅう)すなわち信ずることが悟りに入ることであるとも説いています。このなかのどこをよい教えとして用いたり、反対に切り捨(す)てたりするのでしょうか。 これを靴(くつ)にたとえれば、雨の時はゴムの長靴が最適(さいてき)であり、登山には登山靴、野球・テニス・サッカーなどにはそれぞれ目的にかなった靴があります。また海水浴の時はだれでも、はだしになるわけです。 これらをすべてがよいからといって、すべての靴のよいところと、はだしをいっしょに用いることなどはできるわけがありませんし、そんなことを言えば狂人(きょうじん)と笑われるでしょう。 このモラロジーという宗教が犯(おか)している誤りのひとつは、大綱(たいこう)と網目(もうもく)の相違、すなわち大局的・総合的な教義と部分的な善悪(ぜんあく)との判断がつけられず、無(む)節操(せっそう)にどれでもよいと考えていることであり、もうひとつは生きた例証(れいしょう)もなく、実践も不可能な空想論をかってに教義と称して信者に押しつけることにあります。一見するとよい教えのように思われる宗教でも、よく検討(けんとう)するならば、低級宗教や、邪悪(じゃあく)な宗教であると気がつくでしょう。
2010年03月25日
コメント(0)
-
【他の信仰をしている人へ】2・宗派は分かれているが、到達(とうたつ)する目的はおなじではないか
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 2・宗派は分かれているが、到達(とうたつ)する目的はおなじではないか 宗派は別でも宗教の目的は同じなのだから、どの宗派でもよいのだ、と主張する人の中には、「分(わ)け登(のぼ)る 麓(ふもと)の道は多けれど 同じ雲井(くもい)の月をこそ見れ」という歌を引き合いに出すことがあります。しかし、これはあくまでもひとつの古歌(こか)であって、実際は同じ麓の道でもひとつは他の嶺(みね)に至るもの、別な道は山ではなく池に至る道かもしれません。なかには命を落とすような危険な谷に通じている道であるかもしれません。ですから歌やことわざにあるからといって、それを証(しょう)拠(こ)に宗教を論ずることはできません。 いま各(かく)宗派の教義をみると、教主も本尊も修行も経典も、それぞれまったく異(こと)なっています。 キリスト教はイエスキリストによって神(ゴッド)が説かれ、バイブルを教典としておりますし、イスラム教はマホメットによってアラーの神への帰依(きえ)が説かれ、コーランを所依(しょえ)の教典としています。儒教(じゅきょう)は孔子(こうし)によって道徳が説かれており、仏教は釈尊によって三世(さんぜ)の因果律(いんがりつ)という正当な原理を根本として、人間の生命とその救済(きゅうさい)を説かれたものです。しかも同じ仏教の中でも、小(しょう)乗(じょう)教(きょう)は劣応身(れっとうじん)という仏を教主として戒律(かいりつ)を説き、一切の煩悩(ぼんのう)を断じ尽(つく)した阿羅漢(あらかん)という聖者(せいじゃ)になることを目的としています。これに対して大(だい)乗(じょう)教(きょう)の中でも、華厳(けごん)経(きょう)を所依とする華厳宗、方等(ほうどう)部(ぶ)から発した真言宗、淨土宗、禅宗など、般若(はんにゃ)部(ぶ)の教理をもとにした三論(さんろん)宗(しゅう)など、これらは経典がそれぞれ違うわけですから、当然教義や修行、目的、教主がすべて異(こと)なっているのです。 まして「唯(ゆい)有(う)一(いち)仏(ぶつ)乗(じょう)」といわれる法華経は今までの四十二年間の教えとは比較(ひかく)にならない深遠(しんえん)な教理と偉大な仏の利益(りやく)、そして真実の仏身(ぶっしん)が説き現(あら)わされたものです。その目的も、今までの経教(きょうぎょう)では、三乗(さんじょう)すなわち声聞(しょうもん)を目的とする者、縁覚(えんがく)を目的とする者、菩薩(ぼさつ)になることを目指(めざ)す者をそれぞれ認めて、それに見合った教義と修行を別々に説いていたのですが、法華経に至ると、今までの三乗を目的とする教えは方便であり仮(か)りのものなので、すべてこれを捨てよ、信じてはならないと釈尊自(みずか)らが戒(いまし)められ、一仏(いちぶつ)乗(じょう)すなわちすべての人が仏の境界(きょうがい)に至ることこそ真実の目的であると教示されました。 このように宗教と言っても宗派によって本尊も教義も目的もまったく異なっているのです。もしあなたが“宗教”という大きな意味で、目的が“救済”ということだから、どれでも同じだというならば、それはあまりに大雑把(おおざっぱ)な考え方だというべきでしょう。それはあたかも“学校”はどこも“教育”を目的にしていることは同じだからといって、小学校でも大学でも自動車学校あるいは料理学校でも、どこへ通(かよ)っても同じだということと同じです。 宗教の選択(せんたく)が人間の幸・不幸にかかわる大事であることを知れば知るほど、このような無責任で粗雑(そざつ)な判断は当(とう)を得(え)たものでないことがわかると思います。
2010年03月24日
コメント(0)
-
【他の信仰をしている人へ】1・神仏を礼拝(らいはい)することが尊いのであるから、何宗(なにしゅう)でもよいのではないか
2 正しい宗教と信仰【他の信仰をしている人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 1・神仏を礼拝(らいはい)することが尊いのであるから、何宗(なにしゅう)でもよいのではないか 宗教に限(かぎ)らず、人間にとって敬(うやま)い、信ずるということは大切なことです。日常生活においても信頼する心がなかったならば、食事もできませんし、乗(の)り物(もの)はおろか、道を歩くことも、家に住むことさえできないでしょう。 では反対になんでも無(む)節操(せっそう)に信ずればよいかというと、それもいけません。道に迷ったときは道をよく知っている人に尋(たず)ねれば、間違いなく目的地に着くことができます。私たちは目的地に正しく導(みちび)いてくれるものを信用したときには、所期(しょき)の目的が達成されるわけですし、反対にいつわりのものや目的と違ったものを信じたときには、思い通 りにならず、不満(ふまん)や不幸を感ずるのです。 質問のように、神仏を信ずる心が尊(とうと)い、神仏を礼拝(らいはい)する姿が美しい、だから何宗(なにしゅう)でもよいというのは、詐欺師(さぎし)の言葉でもそれを信ずることが尊(とうと)く、ブレーキのこわれた車でも信じて乗ることがよいということと同じです。 私たちの生命は周囲の環境に応じて、さまざまな状態やはたらきをします。ちょうど透明(とうめい)な水の入ったコップが周囲の物や光によって色が変化するようなものです。「朱(しゅ)に交(まじ)われば赤くなる」という言葉も、周囲の縁(えん)によって感応(かんのう)する私たちの生命のはたらきを指したものでありましょう。信仰は“信ずること”であり、“礼拝すること”なのですから、単に交わるとか尊敬する状態よりさらに強い影響を受け、それによってもたらされる結果や報(むく)いは、人生に大きな影響(えいきょう)を与えることになります。 いいかえれば、信仰における礼拝は、その対象(たいしょう)たる本尊に衆生(しゅじょう)の生命が強く感化(かんか)されるのであり、人間の生命と生活の全体に、これほど強烈(きょうれつ)に働きかけ、影響を与えるものはないのです。ですからいかに信ずることが尊いといっても、人間に悪影響を与える低劣(ていれつ)な本尊や、誤った宗教を信ずるならば、その本尊や教えに感応(かんのう)して、次第にその人は濁(にご)った生命となり、不幸な人生を歩むことになるわけです。たとえば「稻荷(いなり)」と称(しょう)してキツネを拝んでいると、本尊のキツネの生命に、その人の畜生界(ちくしょうかい)の生命が感応して、その人の性格や行動、さらには人相まで似(に)てきます。本来ならば過去と将来を考え、理性をもって生きるはずの人間が、畜生を拝むことによって計画性や道徳心が欠落(けつらく)し、人間失格の人生に変わってゆくのです。もし架空(かくう)の本尊や架空の教義を信仰すれば、同じように人間も、人生も、生活も実(みの)りのない浮(う)き草のようなものになってしまいます。 せっかく信仰心に目覚(めざ)めたのですから、理論的にも正しく、経典によってその正しさが証明され、現実に人々を幸福に導く真実の本尊と真実の教えを説き明す宗教に帰依(きえ)すべきでありましょう。
2010年03月23日
コメント(0)
-
プッツゥ~~ンと音がするぅ~~(;一_一)
三世の諸仏の世に出でさせ給ひても、皆々四恩を報ぜよと説き、三皇(さんこう)・五帝(ごてい)・孔子(こうし)・老子(ろうし)・顔回(がんかい)等の古(いにしえ)の賢人は四恩を修せよとなり。四徳とは、一には父母に孝あるべし、二には主に忠あるべし、三には友に合って礼あるべし、四には劣れるに逢ふて慈悲あれとなり。(上野殿御消息 御書921~頁) 【通解】三世十方の諸仏は世に出現されたならば、必ず皆な四恩(父母の恩・国主の恩・一切衆生への恩・三宝の恩)を報じなさいと説かれている。また、三皇・五帝・孔子・老子・顔回など中国の昔の賢人は四徳を修しなさいと教えている。四徳とは、一に父母に孝養を尽くしなさい。二に主君には忠義を尽くしなさい。三には友に会ったならば礼儀をもって接しなさい。四には自分より力量や地位が劣る人に対しては慈悲を与えなさいということである。 この御聖訓を拝読して、人としての道徳をしっかりと御教示してくださってると思いました。 親孝行することや会社での心構え。親しい友に礼儀をもって接するという事。そして慈悲の思いを持つこと。 顕正会の時を振り返ると・・・・・ 親の頼み事よりも顕正活動優先で親のところに寄り付きもしなかったよね~ 仕事をしてた時も、営業の合間に人をビデオにつれて行ったり、折伏したりで、全然営業してなかったしね。顕正会員は残業なんてお断りの人多いよね。事あるごとに休む人も多いよね。それって会社からみると大迷惑だよね。 親しい友だちとも礼儀をもって接するって、顕正会の話ばかりで、友達の近況なんて知らん顔だったなぁ~ 顕正会からご宗門に来た人たちもこれがなかなかできない人がいるよね。言いたいことだけ言って、礼儀とか持てない人。 私だって生身の人間だからね、人の言葉に傷つくんだからね。 でも、平気で人を傷つける事を言う人おおいよ~顕正会からの人・・・自分も顕正会からなんだけどね。 売り言葉に買い言葉ならお互い様だけどね。そうじゃない事も多いじゃない。 あとさぁ~電話しても本人が出てるのに、声聞いてぶちって電話切る人もいるんだよ。無視して連絡先を変えて知らせてこない人とかね。 これがさぁ~10代の若い子ならまだ「はいはい」ってな感じなんだけれども・・・ 40過ぎや50前の大人にやられた時には正直ショックで泣きそうでしたわ。『・・・・』 私も含めて、自分が正しいと思ってるんだろうね。人を大きく傷つけてるのに、自分が傷ついた事だけ主張してさ。 私だって・・・・・ 大人だったら礼儀を以て感謝して日蓮大聖人様の仰せのままの信行に励んで、我見で信心しないでください。と連絡の取れない人たちに言いたい。 1回2回どころじゃないんだよぉ~~私はほんとにあまりの仕打ちに言葉もなかったし・・・・・・・・・・・・ 『友に会って礼あるべし』・・・これができない人ほど・・・『劣れるに逢ふて慈悲あれ』を盾にして、自分は未熟やし、何をしてもいい!何を言っても許される!と勘違いしてるんだよね。 これって世間一般の道徳だよ。親への恩や孝養をつくすことも、仕事を真面目にしていくことも、友達や知り合いに礼を尽くす事もさ。 ほんとにさ~ こういう風な事も仏法の道理に照らすと因果因縁なんで、私がやってきたことが因果応報で自分の身に降りかかってるんだろうけどね。 私って、そうとう礼儀知らずだったんだろうねぇ~(ToT)/~~~ ほんとに厳しいよねぇ~因果応報だからねぇ・・・・人に対して自分が取った行動や振舞いは結局自分自身に返ってくるんだよねぇ~ そこをよくよく考えて・・・四の『劣れるに逢ふて慈悲あれ』を心掛けないといけないんだよね。 最近、こういうことが多くって・・・・(>_<)(T_T) ついつい愚痴ってしまいましたぁ~<m(__)m>いけない・・・いけない・・・・・
2010年03月23日
コメント(0)
-
【信仰に反対する人へ】15・信仰はなぜ必要なのか
1・ 正しい宗教と信仰【信仰に反対する人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 15・信仰はなぜ必要なのか 一般に信仰とは、お年寄りが一種の精神修養や先祖を敬(うやま)いつつ、なごやかな楽しみの場を持つために、お寺へ参詣(さんけい)し、時には団体旅行をすることぐらいの認識(にんしき)しか持ち合わせていない人が多いようです。 あるいはまた困(こま)った時に、神仏の加護(かご)を求めて参詣し、手を合わせ、願(がん)をかけ、守(まも)り札(ふだ)などを大事にすることが、信仰だと思っている人もあります。 しかし、正しい宗教を信仰する目的は、一人ひとりの人間の生命の救済、つまり、生(しょう)・老(ろう)・病(びょう)・死(し)の四苦(しく)や、経済的な苦しみや対人(たいじん)関係の悩みなどを含(ふく)む、人のいかなる苦悩にも打ち勝つ活力を与え、すべての人々に真実の幸福を築かせ、尊い人生を全(まっと)うするための生き方を教えるところにあります。 したがって、正しい宗教の持つ働きは、単(たん)なる精神修養(しゅうよう)や気安めではないのです。 正しい信仰は、何よりも人間の全生命の問題と、その生き方、人の幸・不幸にかかわる、実に重大な意義と働きと大きな価値(かち)を持っているのだということを知ってください。 数(かず)ある宗教の中にあって、一時の気安めや現実からの逃避(とうひ)ではなく、真に一切(いっさい)の人間の苦悩を喜びに変え、大難を乗り越えて、煩悩(ぼんのう)を菩提(ぼだい)へ、生(しょう)死(じ)を涅槃(ねはん)へ、裟婆(しゃば)の忍土(にんど)を寂光(じゃっこう)の楽土(らくど)へと転換(てんかん)させうる仏法こそ、日蓮大聖人の教えなのです。 では、正しい信仰に、どのような功徳がそなわるかといいますと、 (一)世界中の一切の人々を、真に幸せな即身成仏の境界(きょうがい)に導(みちび)くことができる。(二)強盛(ごじょう)な信仰を通して、御本尊に託(たく)する願いや希望を成就(じょうじゅ)し、また、悩みや苦しみに打ち勝つ金剛心(こんごうしん)を育てることができる。(三)御本尊にそなわる題目の功徳によって、父母を救い、先祖代々の人々を成仏させ、また、未来の子孫(しそん)をも救済する福徳(ふくとく)を得(う)ることができる。などがあり、そのほかにも正しい信仰の功徳は数(かず)多くあります。 日蓮大聖人は、妙法を信受する功徳について、 「南無妙法蓮華経とだにも唱へ奉(たてまつ)らば滅(めっ)せぬ罪(つみ)や有るべき、来たらぬ福(さいわい)や有るべき。真実なり甚深(じんじん)なり、是(これ)を信受(しんじゅ)すべし」(聖愚問答抄・御書406頁)と教えられています。
2010年03月21日
コメント(0)
-
【信仰に反対する人へ】14・信仰をしなくても立派な人がいるではないか
1・ 正しい宗教と信仰【信仰に反対する人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 14・信仰をしなくても立派な人がいるではないか まず「立派(りっぱ)な人」とはどういう人を指(さ)すのでしょうか。 一般に「立派な人」という場合は、社会的に指導的地位にある人、名誉(めいよ)のある人、財(ざい)をなした人、学識(がくしき)豊かな人、福祉(ふくし)活動や救済事業に貢献(こうけん)する人、社会的な悪と闘(たたか)う人などが挙げられます。 さらに広くいえば、名誉や地位はなくても毎日を正直にまじめに努力しながら過(すご)している人々も“立派な人”といえるのではないでしょうか。 こうしてみると、“立派な人”といっても一定の規(き)準(じゅん)があるわけではなく、他人を評(ひょう)価(か)する時に主観的見地(けんち)から用いる漠然(ばくぜん)とした言葉にすぎないことがおわかりでしょう。 では信仰は立派な人間になるためにするのでしょうか。それとも立派な人間になることとは違うところに目的があるのでしょうか。 結論からいえば、正しい信仰とは、成仏という人間にとって最高究(きゅう)極(きょく)の境涯(きょうがい)に到達(とうたつ)することを大目的として修行精進(しょうじん)することであり、その仏道を修行することによって、ひとりひとりが人間性を開発し、錬磨(れんま)し、身に福徳を具えていきますので、その過程の中でおのずと“立派な人間”が培(つち)かわれていくのです。日蓮大聖人は、「されば持(たも)たるゝ法だに第一ならば、持つ人随(したが)って第一なるべし」(持妙法華問答抄・御書298頁)と仰(おお)せられ、信ずる法が正しいゆえに人も立派になるのであると説かれています。 ですから正しい信仰を持(も)たずに、単(たん)に眼前(がんぜん)の名誉や地位、あるいは財産、学歴などをもって、それで仏の御意(ぎょい)に叶(かな)う人生になるわけではありませんし、そのような表面的な要件が備わっているからといっても真実の絶対的幸福が得られるわけではありません。 大聖人は、賢人(けんじん)について、「賢人は八風(はっぷう)と申して八つのかぜにをかされぬを賢人と申すなり。利(うるおい)・衰(おとろえ)・毀(やぶれ)・誉(ほまれ)・称(たたえ)・譏(そしり)・苦(くるしみ)・楽(たのしみ)なり」(四条金吾殿御返事・御書1117頁)と仰(おお)せです。財産(利)や名誉(誉)、地位(称)、悦楽(えつらく)(楽)などによって喜んだり、落胆(らくたん)したりすることは世の常ですが、これらは世間の一時的な八風であって、この八風に侵(おか)されない賢人になるためには、より高い理想と教え、すなわち身心に強い信仰を体(たい)して仏道精進を志(こころざ)す以外にないと示唆(しさ)されています。 この八風に侵(おか)されない賢人こそ“立派な人”というべきではないでしょうか。そのためには生命の奥底(おうてい)から浄化し活力を与える正しい仏法をもつべきなのです。 大聖人は、「地獄に堕(お)ちて炎(ほのお)にむせぶ時は、願はくは今度人間に生まれて諸事を閣(さしお)いて三宝(さんぼう)を供養し、後(ご)世(せ)菩(ぼ)提(だい)をたす(助)からんと願へども、たまたま人間に来たる時は、名(みょう)聞(もん)名(みょう)利(り)の風はげしく、仏道修行の灯(ともしび)は消えやすし」(新池御書・御書1457頁)と戒(いまし)められています。
2010年03月20日
コメント(0)
-
【信仰に反対する人へ】13・利益や罰はその人の心の持ち方によるのであって、客観的にあるものではない
1・ 正しい宗教と信仰【信仰に反対する人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 13・利益や罰はその人の心の持ち方によるのであって、客観的にあるものではない 人間の幸福と不幸を、線を引いて区分(くぶん)することはできません。まったく同じ条件のなかにあって、ある人は自分は不幸だと思う人もいれば、別な人は自分は幸福だと思う場合もあります。ひとつの結果を利益とみるか、罰とみるかはその人の心や考え方によって決定されるといっても間違いではありません。 「心頭滅却(しんとうめっきゃく)すれば火もまた涼(すず)し」という言葉がありますが、どこまで心頭を滅却(無念無想(むねんむそう)の境地)できるか、どの程度の火熱(かねつ)を涼しく感ずるかという限界点は個人差がありましょう。しかし普通の人で、真っ赤に焼けた鉄にふれても何も感じない人はいません。また食事をとらないで一日二日は我慢(がまん)できても、十日も二十日も絶食して平常と変わらない人はいません。どんな人でも体に激痛(げきつう)を感ずれば心も落着(おちつ)かなくなるのは当然です。 これらの事実から見ても、現実の結果や物事(ものごと)の評(ひょう)価(か)は人間の心によって決定されるものですが、心はまた現実の物質世界に支えられていることがわかるでしょう。 これらの原理を仏法では「色心(しきしん)不二(ふに)」といって物質や肉体(色)と精神(心)はたがいに離(はな)れることなく一体であると説いています。 この色心不二の生命に根本的な影響を与えるものが宗教です。 日蓮大聖人の教えによりますと、妙法を信受(しんじゅ)する者について、「身は是(これ)安全にして、心は是禅定(ぜんじょう)ならん」(立正安国論・御書250頁)と仰(おお)せられ、心に禅定を得(う)るばかりでなく、身体も安穏(あんのん)になると説かれています。 また、正法に背(そむ)く者について、経文を引用して、「人(ひと)仏教を壊(やぶ)らば復(また)孝(こう)子(し)無く、六親(ろくしん)不和(ふわ)にして天神も祐(たす)けず、疾疫(しつえき)悪(あっ)鬼(き)日(ひび)に来(き)たりて侵害(しんがい)し、災(さい)怪(け)首(しゅ)尾(び)し、連(れん)禍(か)縦横(じゅうおう)し、死して地獄(じごく)・餓鬼(がき)・畜生(ちくしょう)に入らん。若し出(い)でて人と為(な)らば兵(ひょう)奴(ぬ)の果報(かほう)ならん」(立正安国論・御書249頁)と説かれています。この文の意味は、“正法を信ぜず、信仰を壊(やぶ)る者は福徳(ふくとく)が尽(つ)きて、孝養心のある子供に恵(めぐ)まれず、親子・兄弟・親戚(しんせき)が仲たがいをしていがみあう。天候不順で作物(さくもつ)が実らず、悪病が流行し、悪い思想もはやって生活をおびやかす。奇怪(きかい)な事件やわざわいが次々に起こり、死後は苦しみの地獄、飢渇(けかち)の餓鬼、互いに殺し合う畜生などの世界に落ちる。その後(のち)もし人間に再び生まれてくるならば兵隊として戦場にかり出されたり、奴隷(どれい)となって酷使(こくし)されるであろう”というのです。 これらの教えは因果(いんが)の道理、すなわち善因(ぜんいん)を積めば善果(ぜんか)を得(え)、悪因(あくいん)には悪果(あっか)を生じるという当然の姿を記(しる)したものであり、正法を信受する者には大利益(だいりやく)が、不信(ふしん)毀謗(きぼう)の者には厳然(げんぜん)とした罪(ばち)が、身心両面に現れることを説いているのです。 真実の幸福と安穏な境涯は、凡俗(ぼんぞく)の私たちが心でどのように受けとめるか、あるいは一時的な感情でどのように考えるか、というところにあるのではなく、正しい仏法をいかに余念(よねん)なく信受(しんじゅ)し、行じうるかにかかっていることを知るべきでしょう。
2010年03月18日
コメント(0)
-
【信仰に反対する人へ】12・現在は信仰するほどの悩みはない、いまの生活で満足だ
1・ 正しい宗教と信仰【信仰に反対する人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 12・現在は信仰するほどの悩みはない、いまの生活で満足だ 「信仰するほどの悩(なや)みはない」という言葉は、言い換(か)えると「悩みのない人は信仰の必要がない」ということであり、信仰を正しく理解していないようです。 仏さまが、この世に出られた目的は、仏知見(ぶっちけん)すなわちいかなるものにも壊(こわ)れることのない清浄(せいじょう)で自在(じざい)の境地と、深く正しい智慧(ちえ)を、衆生に対して開き示し、悟(さと)り入(い)らしめるためであると法華経に説かれています。 そして法華経宝塔品(ほうとうほん)には、「此(こ)の経(きょう)を読(よ)み持(たも)たんは是(こ)れ真(しん)の仏子(ぶっし) 淳善(じゅんぜん)の地(じ)に住(じゅう)するなり」(開結三五五)と説かれ、正しい仏法に帰依(きえ)する者は真実の仏の子であり、清浄で安穏(あんのん)な境(きょう)地(ち)に住することができると教えています。 日蓮大聖人も、「法華経は現世(げんぜ)安隠(あんのん)・後(ご)生(しょう)善処(ぜんしょ)の御経なり」(弥源太殿御返事・御書723頁)と仰(おお)せられているように、安穏な境地とは現在ばかりでなく、未来にわたるものでなければなりません。楽しいはずの家族旅行が一瞬にして悲惨(ひさん)な事故にあったり、順調(じゅんちょう)に出世コースを歩んできた人が一時の迷(まよ)いから人生の破滅(はめつ)を招(まね)いたりすることはしばしば耳にすることです。いまが幸せだからそれでよいという人は、よほど自分だけの世界に閉(と)じ込(こも)っているか、直面している問題や障壁(しょうへき)を認識(にんしき)できない人といわざるをえません。 私たちの周囲を見ても、世界では毎年(まいとし)何百万人もの戦争による死(し)傷(しょう)者(しゃ)が出ており、私たちが戦乱の渦(か)中(ちゅう)に巻き込まれないという保(ほ)障(しょう)はどこにもありません。また、家族や親戚(しんせき)の悩みはまったくないのでしょうか。子供の教育問題や親または自分の老後の問題などを考えても、「今の生活で満足だ」とのんびりしているわけにはいかないと思います。 大聖人は、「賢人(けんじん)は安(やす)きに居(い)て危(あや)ふきを欲(おも)ひ、佞人(ねいじん)は危ふきに居て安きを欲(おも)ふ」(富木殿御書・御書1168頁)と仰(おお)せられ、賢人は安穏な時でも常に危険に心を砕(くだ)いているが、考えが浅くへつらうことばかり考えている人は、危険な状態になっても安逸(あんいつ)をむさぼろうとするだけであると説かれています。 今が幸せだということは、譬(たと)えていえば平坦(へいたん)な舗装(ほそう)道路をなんの苦労もなく歩いているようなものです。しかし長い人生には険(けわ)しい登り坂もあれば泥沼(どろぬま)の道もあります。その時にはより強い体力と精神力、そして適正(てきせい)な智慧(ちえ)がなければなりません。難所(なんしょ)にきてから「自分は平坦な道しか歩いたことがない」という人はむしろ不幸な人というべきです。どんな険難(けんなん)悪(あく)路(ろ)に遭遇(そうぐう)しても、それを楽しみながら悠々(ゆうゆう)と乗り越えてゆく力を持つ人こそ真に幸せな人というべきでしょう。 強い生命力と深く正しい智慧は、真実の仏法に帰依して信心修行を積(つ)まなければ決して開発されるものではありません。 どうか目先の世界や自己満足に閉(と)じこもることなく、一日も早く正しい仏法を信じ、真に賢(かしこ)い人間となり、幸福な人生を築いて下さい。
2010年03月16日
コメント(0)
-
【信仰に反対する人へ】11・宗教は狂信、盲信のすすめではないか
1・ 正しい宗教と信仰【信仰に反対する人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 11・宗教は狂信、盲信のすすめではないか ここでいう「狂信(きょうしん)」とは、理性(りせい)を失い我(われ)を忘れて狂ったように信ずることであり、「盲信(もうしん)」とは、ひとつの信仰に埋没(まいぼつ)し、わけもわからずむやみに信ずることです。 この狂信・盲信について三つの点から考えてみましょう。 まずはじめに数多い宗教、信仰のなかには明らかに教義として狂信・盲信をすすめているものがあります。たとえば霊媒信仰(れいばいしんこう)や修験道(しゅげんどう)、あるいは踊(おど)る宗教などは忘我(ぼうが)の境(きょう)地(ち)に至(いた)ることが救いであり、理想であると説いています。また、キリスト教やイスラム教のなかには自宗に執着(しゅうちゃく)するあまり、教義の正邪ではなく、暴力やテロに訴(うった)える場合もあり、これも狂信のひとつといえましょう。 さらに念仏(ねんぶつ)宗(しゅう)などは「他の教典はすべて捨(す)てよ、閉(と)じよ、閣(さしお)け、抛(なげう)て」と、他(た)の教典を読むことを禁じ、禅宗なども不立文字(ふりゅうもんじ)・只管(しかん)打坐(たざ)と称(しょう)して文字による教義理解を否定し、他宗の善悪(ぜんあく)を知ることさえ、きらいます。 また、密教(みっきょう)やキリスト教のなかには、社会との交渉(こうしょう)を断(た)って、山奥(やまおく)や閉鎖(へいさ)集団の中で生きることを至(し)上(じょう)の目的とするものもあります。 このように、他の宗派や社会と隔絶(かくぜつ)することを説く宗教を信ずるならば、他の宗教と比較することもできず、独善(どくぜん)的な信仰となります。 日蓮大聖人は、「迷妄(めいもう)の法に著(ちゃく)するが故に本心を失ふなり」(御講聞書・御書1858頁)と説かれ、誤った教えによって本心たる理性が失(うしな)われ、狂信になると教えています。また、「若(も)し先(ま)づ国土を安(やす)んじて現当(げんとう)を祈らんと欲(ほっ)せば、速(すみ)やかに情慮(じょうりょ)を廻(めぐ)らし怱(いそ)いで対治(たいじ)を加へよ」(立正安国論・御書248頁)と仰(おお)せられ、社会の平和を実現させるためには、正法と邪法とをよくよく糾明(きゅうめい)して対応(たいおう)救(きゅう)治(じ)しなければならないと説かれています。 第二には、信仰修行の上での狂信・盲信についていえば、日蓮正宗の信仰修行は理性(りせい)を失(うしな)う狂信でもなく、わけもなく信ずる盲信でもありません。 大聖人は、 「行学の二道をはげみ候べし。行学た(絶)へなば仏法はあるべからず」(諸法実相抄・御書668頁)と、修行とともに教学、すなわち教義の研鑽(けんさん)が大切であると説かれています。また、「酔(すい)とは不信なり、覚(かく)とは信なり。今日蓮等(ら)の類(たぐい)南無妙法蓮華経と唱へ奉る時無(む)明(みょう)の酒醒(さ)めたり」(御義口伝・御書1747頁)と仰せられ、真実の正法を信じ唱題する時、無(む)明(みょう)という迷いの霧(きり)が晴れて真理に目覚(めざ)めるのであると教示されています。 第三には、現実の例証(れいしょう)をもっていえば、大聖人は、「仏法を習ふ身には、必ず四恩(しおん)を報ずべきに候(そうろう)か。」(四恩抄・御書267頁)と、信仰者(しんこうしゃ)は人間の道として父母・衆生(しゅじょう)・国土、そして三宝(さんぼう)の四つの大恩を常に感じ、報(むく)いるように教えられています。 又、職(しょく)場(ば)での心(こころ)得(え)として、「御みや(仕)づかい(官)を法華経とをぼしめせ」(檀越某御返事・御書1220頁)と諭(さと)されています。このように常識をもち、社会人としての勤(つと)めに励(はげ)むことが信仰者(しんこうしゃ)の道であると教えています。 日蓮大聖人の願いとするところは、正しい仏法によって個人も社会もともに健全に発展し幸福境涯を築くことであり、日蓮正宗を信仰する者は邪法に迷う人々を目覚(めざ)めさせるために正邪を説き、自(みずか)らの姿をもって信仰の尊さを示しているのです。 しかも正法を信ずるならば仏力(ぶつりき)・法力(ほうりき)によって、おのずと円満な人格と福徳(ふくとく)が備(そな)わり、社会人としても多くの人々の信頼と尊敬を受けていることはまぎれもない事実なのです。 もしあなたが、信仰者の真剣な礼拝(らいはい)唱題の姿をとらえて、それを狂信だ盲信だと非難(ひなん)するならばそれは妄断(もうだん)であり、誤(あやま)りです。なぜならばそれはあたかも、職人(しょくにん)が一心不乱(いっしんふらん)に仕事に打ち込み、運動会で子供が一所懸命(いっしょけんめい)に走っているところだけをとらえて、「気違いだ」「狂っている」と、はやしたてているようなものだからです。
2010年03月15日
コメント(0)
-
【信仰に反対する人へ】10・信仰をしていても悪い人がいるのではないか
1・ 正しい宗教と信仰【信仰に反対する人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 10・信仰をしていても悪い人がいるのではないか 信仰していない人は、よく「信仰をしていても、こんなに悪い人がいるから信仰する気にならない」と言います。 「悪い人」といっても、悪い考えに染(そ)まった人、悪い癖(くせ)を持った人、自分で気付かずに悪業(あくごう)を犯(おか)す人などさまざまです。 釈尊は、現代の世相を「五(ご)濁(じょく)悪世(あくせ)」と予言(よげん)しました。五濁とは(1)劫濁(こうじょく)(社会・環境に悪い現象が起きる)(2)煩悩(ぼんのう)濁(じょく)(瞋(いか)りや貪(むさぼ)りなどの悪心にとらわれた本能の迷(まよ)い)(3)衆生濁(しゅじょうじょく)(人間そのものの濁(にご)り)(4)見濁(けんじょく)(思想や考えの乱(みだ)れ)(5)命濁(みょうじょく)(生命自体の濁(にご)り、人命軽視(けいし)など)をいいます。 たしかに現代社会は科学技術の発展とは逆に、人間性は歪曲(わいきょく)され、貧困(ひんこん)になっていますし、社会全体の混迷(こんめい)と汚染(おせん)はますます深刻(しんこく)になっています。まさしく釈尊の予言どおりの世相になっています。 社会も時代も、そして個々の人間まで汚染されつつある現代は、悪で充満しているといっても過言(かごん)ではありません。そのような中で、健全な人生を築くために発心(ほっしん)して信仰の道に入っても、始めのうちは過去からの宿習(しゅくじゅう)や因縁(いんねん)によって、また縁にふれて悪心を起こしたり、他人に迷惑をかける人もいるかもしれません。 また世間で罪(つみ)を犯(おか)した人が、最後の更正(こうせい)のよりどころとして信仰を持(たも)ち、努力することも宗教の世界なればこそ当然であります。 このような場合でも、正しい宗教によって信仰を実践(じっせん)していくうちに、悪い性(さが)を断(た)ち切り、煩悩を浄化(じょうか)し、六根(ろっこん)清浄(しょうじょう)になっていくのです。日蓮大聖人は信心の功徳(くどく)について、 「功徳とは六根清浄(ろっこんしょうじょう)の果報(かほう)なり。所詮(しょせん)今(いま)日蓮等(ら)の類(たぐい)南無妙法蓮華経と唱へ奉る者は六根清浄なり」(御義口伝・御書1775頁)と仰せです、すなわち正しい教えである南無妙法蓮華経を信じ唱える者は、必ず六根〔眼(げん)・耳(に)・鼻(び)・舌(ぜつ)・身(しん)・意(い)〕のすべてが清浄な働きになると教えているのです。 信仰の正当性を知るために大切なことは、それを信ずる人の姿を見て判断するのではなく、信仰の対象(たいしょう)である本尊や教義の正邪をもってその価値(かち)を決しなければならないのです。釈尊は、「法に依(よ)りて人に依らざれ、義(ぎ)に依りて語(ご)に依らざれ」〔涅槃経(ねはんぎょう)〕と説いています。 信仰をしている人を部分的な表面や風評(ふうひょう)をもって批判することは誰(だれ)にでもできるでしょう。しかし批判者(ひはんしゃ)にはそれ以上に得(う)るものはなにもないのです。むしろ、正法の信者を誹謗(ひぼう)するという大きな罪を作っているかもしれません。 一方、正しい信仰を根本として、過去の悪業や弱い自分と闘(たたか)いながら仏道に精進(しょうじん)している人は、当初(とうしょ)は恥(はずか)しい思いをするかもしれませんが、将来必ず目標に到達し、真実の幸福境涯を築き、周囲の信頼(しんらい)と尊敬を集めることができるのです。 もし万が一にも、正しい信仰を持ちながら平気で悪事をなすならば、その人は仏法に疵(きず)をつける罪によって仏罰(ぶつばち)を受けるでしょう。しかしそれもまた、その人を善導(ぜんどう)するための仏の慈悲(じひ)のあらわれであり、いかなる人も必ず正しい人生を歩(あゆ)むようになるのです。
2010年03月13日
コメント(0)
-
【信仰に反対する人へ】9・信仰は老人がするものではないのか
1・ 正しい宗教と信仰【信仰に反対する人へ】 ※日蓮正宗公式HPより転載http://www.nichirenshoshu.or.jp/index.htm 9・信仰は老人がするものではないのか 「信仰は年寄(としよ)りがしていればよい」という意見には、信仰に対する無理解(むりかい)と老人に対する偏見(へんけん)が潜(ひそ)んでいるように思われます。 正しい信仰が人生にもたらす作用はさまざまなものがあります。その中の主なものを挙(あ)げてみますと、1 正しい教えを信ずることによって、考え方や人生観が広く正しいものになる。2 日々の信仰修行によって身心ともに健全(けんぜん)な人間として鍛錬(たんれん)される。3 精進心(しょうじんしん)すなわちこつこつとたゆまぬ努力を積(つ)み重ねる心が培(つちか)われる。4 敬虔(けいけん)な心・感謝の心・思いやりの心が養(やしな)われる。5 日常生活が信仰の功徳力(くどくりき)によって仏天(ぶってん)に加護(かご)される。などがあります。 このように人生に大きな意義をもつ信仰が、若い人と無縁(むえん)であるというのはまったく的(まと)はずれな暴論(ぼうろん)というべきです。 むしろ、「鉄は熱(あつ)いうちに鍛(きた)えよ」という言葉どおりに、人生の基礎(きそ)となり土台(どだい)となる若い時こそ、正しい宗教を信仰し修練(しゅうれん)を積(つ)むべきなのです。 ビルを建てる場合でも地中(ちちゅう)深く打ち込まれた盤石(ばんじゃく)な基礎があれば、その上に立派(りっぱ)な高層建築を建てても微動(びどう)だもしません。これと同じように、若い時に目先の欲得(よくとく)や表面的な楽しみに流されることなく、信仰を根本としてしっかりした人生観と人間性を養うことが将来の大きな力になるのです。 また本人がいかにまじめな努力家でも、いつ不慮(ふりょ)の災難(さいなん)にまき込まれるかわかりません。一瞬の事故によって一生を台(だい)なしにするような事件がいたるところで起きていることを考えると、やはり仏天の大きな力によって日々(ひび)守られることも、若い人が充実した生活を築くための大切な要件(ようけん)といえましょう。 たしかに低級思想や迷信(めいしん)に走る宗教、あるいは形骸化(けいがいか)した既成(きせい)宗教の姿に対して、若い人だけでなくすべての人々が失望し、むしろそれらを忌避(きひ)しているというのが現実です。 しかし真実の生きた宗教は、老若男女(ろうにゃくなんにょ)、人種などの差別なく、すべての人に生きる力を与え、何ものにも崩(くず)れない安穏(あんのん)にして自由な境涯(きょうがい)を確立させるところに、その目的があるのです。また、道を志(こころざ)すことに遅(おそ)いということはありません。青年・壮年(そうねん)・熟年(じゅくねん)を問(と)わず正法に帰依(きえ)することは幸福の絶対条件ですが、健全な苗木(なえぎ)が大木(たいぼく)・名木(めいぼく)に成長していくように、伸びゆく青年時代に信仰に励むならば、それだけ人生の大きな力となり、強(きょう)固(こ)な礎(いしずえ)となるのです。 現在日蓮正宗には、何万名もの青年が自己(じこ)の確立と社会平和のために情熱をもって信心修行に励んでいます。
2010年03月12日
コメント(0)
全797件 (797件中 1-50件目)