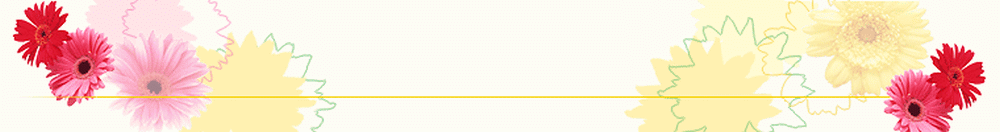臨終の大事(上)
臨終の大事(上)
大聖人様は『妙法尼御前御返事』に、
「人の寿命は無常なり、出る気は入る気を待つ事なし・風の前の露尚譬えにあらず、かしこきもはかなきも老いたるも若きも定め無き習いなり、されば先臨終の事を習うて後に他事を習うべし」(全集一四〇四p)
と仰せになられ、人と生まれた以上、誰にでも臨終というものは必ず訪れるのであるから、まず臨終(成仏の法)について学ぶことが大切であると御指南されておられます。
人間は何人たりとも、我が身の臨終から逃れることはできないものです。
昔、あるバラモンが自分の死から逃れようと、山や海や空や市の中を逃げ回ったという話がありますが、どこに逃げようと、我が身の臨終から逃れることは絶対にできません。
釈尊の逸話にもこんな話があります。
「ある裕福な家の若い嫁が、大事な一人息子を病気で亡くしました。若い嫁は気が狂い、冷たくなった骸を抱いて巷に出、子供の病気を治してくれる者はいないかと尋ね回りました。町の人はどうすることもできず、ただ哀れみ、見守るだけでした。これを見かねたある信者が釈尊の所へ連れて行き、教えを乞うたのであります。釈尊は静かにその様子を見て『汝よ、この子の病を治すには、芥子の実がいる。町に出て四・五粒もらってくるがよい。しかし、その芥子の実は、まだ一度も死者を出して無い家からもらってこなければいけない』と言われたのです。
狂った母親は町に出て、一生懸命探すのですが、芥子の実は見つかっても、死者を出したことのない家は一軒もありません。必ず身内の誰かが亡くなっているのです。母親はついにその芥子の実を見つけることはできず、釈尊のもとへ帰ってきたのですが、釈尊の静かな姿に接し、その言葉の意味をさとり、我が子を墓所に埋め、心から供義しました」
この話の要点の一つは、誰人にも、どこの家庭にも、必ず臨終は訪れるのだということですが、もう一つ重要なポイントが隠されています。それは、悲しみに狂った母親が釈尊の教えを受け、自分で家々を歩き回り、自分の体験から「死」というものの無常を悟ったところにあります。嘆き悲しむ母親にいくらそれらしき法を説いたところで、その悲しみを真にいやすことはできなかったことでしょう。ここに「臨終」の重要な点があるように思います。
「死」はだれもその体験を話すことはできません。もちろん聞くことも不可能です。自分の「死」は自分で解決していかなくてはならないのであります。そのためには当宗の正しい臨終の在り方を聞き、それに向かって精進を続けるべきであります。
臨終はその人の人生における総決算であり、生前になした言行の善悪一切が裁かれる時でもあります。
古言にも“死は人の大故なり”といって、臨終はその人の生涯にわたる一大事であります。臨終に際し、その時だけいくら取り繕おうとしてもそれはできません。何故ならば、我が身の臨終がいつ来るのかは、誰にもわかりませんし、そのとき魔が競い起ることが種々の経文に示されているからです。
この一大事たる臨終について学ぶべき事を第二十六世日寛上人は「臨終用心抄」(富士宗学要集三巻)に詳しく教えられています。その中からいくつか大事な所を挙げてみましょう。
一、多念の臨終・刹那の臨終
多念の臨終とは、「日は今日、時は唯今と意に懸けて行住坐臥に題目を唱ふるを云ふ也」と仰せのように、常に「臨終只今にあり」との念をもって、日々唱題修行に励むことです。
また、刹那の臨終というのは、まさに今世一期生の最期の臨終の時のことで、これが最も肝心であるとされています。この時に題目が唱えられれば、成仏は疑いのないところとなります。
大聖人様が『妙法尼御前御返事』で、
「最後臨終に南無妙法蓮華経と・となへさせ給いしかば、一生乃至無始の悪業変じて仏の種となり給う、煩悩即菩提・生死即涅槃・即身成仏と申す法門なり」(全集一四〇五p)
と仰せのとおりであります。
その人の一生の信心修行の総決算が、身・口・意の三業にわたる一遍の唱題となれば、生死即涅槃にして、即身成仏は疑いのないところとなるでありましょう。しかし、これも日頃の唱題を重ねていなければ、簡単にできるものではありません。日寛上人は、このことについて、「臨終の一念は多年の行功による」と仰せであります。
例えば木が倒れるときは、どうしても傾いた方向に倒れるものです。それと同じように、人は臨終のときに、その人が生前になしてきた報いを受けます。日頃、瞋恚の強い者は、その強きに引かれて地獄界の方に引っ張られるのです。貪欲の強い者は、欲の曲がりに引かれて餓鬼道に堕ちるでありましょう。愚癡多き者は、畜生道に引かれていくのです。このことを思いますとき、『南條殿女房御返事』の、
「夫れ水は寒積れば氷と為る・雪は年累つて水精と為る・悪積れば地獄と為る・善積れば仏となる云云」(同 一五四七p)
との御文を心肝に染めるべきでありましょう。
妙法の信者たる者、日々多念の臨終を積み重ね、今生の最期には、たとえ声ならずとも一念を込めた題目を唱え、刹那の臨終正念を遂げたいものです。
一、臨終の時心乱るるに三の子細あること…
一には断末魔の苦の故。(臨終の時、断末魔の風といって、千の尖き刀のような風が其の身を刺すようにふきぬける)
二には魔の所以。(種々の魔が競い起こり、臨終正念を妨げる)
三には妻子従類の嘆きの声、財宝等に執着するの故。(財産や肉親に対する執着心、未練などをもってしまい、心が動く)
臨終には以上のような種々の妨げにより、臨終正念が遂げられない場合があることを示されています。
ですから、この時に臨終正念を扶けてくれる善知識が必要となるのです。
同抄に、
「臨終は勧むる人が肝要なり。乃至病苦、死苦に責められて、臨終の一大事を失念するをば、側よりよく勧むるが肝要なり。その勧め様は唯だ題目を唱るなり」
とありますが、その唱え様について、総本山第五十五世日布上人は、
「病人が次第によはってゆけば、よはるに随って題目をしづかに唱へ、ゆるやかでなく、またすみやかでなく、病人のたましいに徹る様に題目をすすむべきであります。これ則ち臨終の」大事であって、常にわすれず心にかけるべきであります。」
と御指南あそばされております。
延命治療の発逹した現在、日本人の平均寿命は八十歳近くまで伸び、随分生きながらえるようにも見えますが、仏法より見れば、朝夕の一日に生死があり、たった一呼吸の出入にも生死が存しているのであります。この生死生死の連続が、五十年乃至八十年の人生ともなっていくわけでありますから、毎日毎日の信心修行を決して疎かに考えることはできません。
臨終の大事を自覚するということは、いかに生きるかを考えることでもあります。必ず迎えくる我が身の臨終をしっかりと心にとめ、その問題を解決し、憂い無き人生を悠々と生きていくことが、臨終の大事を真に知る人といえましょう。
「御臨終のきざみ生死の中間に日蓮かならず・むかいにまいり候べし」(上野殿御返事 全集一五五八p)
とのありがたいお言葉を心して拝してまいりたいものであります。
(大白法平成4年11月16日号)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…
- (2025-11-20 02:23:55)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「グラビア界最強ボディ」の28歳・榎…
- (2025-11-20 03:00:10)
-
© Rakuten Group, Inc.