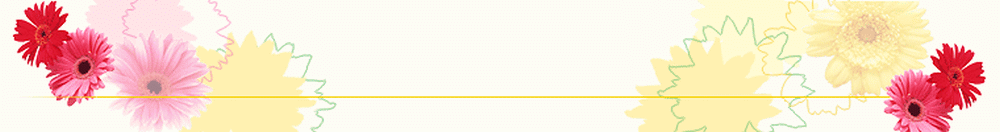臨終の大事(下)
臨終の大事(下)
イギリスの人名学者フレーザーは、呪術の根本を「共感呪術」とし、更にそれを「類感呪術」と「感染呪術」の二つに分解して考察しています。
この中の「類感呪術」は「模倣呪術」ともいわれるように、ある動作を正確に模倣擦れば、それに相応する効果があらわれるという信念――「擬き好き」にもとづく呪術であり、フレーザーは「類似は類似を生む」と表現しています。
日蓮正宗の信仰における「化儀」を考えるとき、この捉え方はよき参考になると思います。だからといって、この“もどき”は、偽物という意味ではありません。御本仏の御振る舞いを、凡夫である私たちの立場で実践することを言っているのです。
たとえば、「日蓮が如くなりたくば、日蓮が如くせさせ給へ」とあっても、私たちには直ちに、「わが身は地水火風空の五大なり…」とはできませんから、必ず御本尊を安置して題目を唱えるという三大秘法を修して、久遠の即座開悟を“もどく”ことができるのです。数珠、その体相は、妙法五字、無作本有の当体でありますから、これを手に掛けて胸の上で合わせ、題目を唱えれば大聖人様の悟りであり御魂である御本尊と、私たちの身が即一体となって成仏の功徳を得るのです。
このことを大聖人様は、
「日蓮は過去の不軽の如く当世の人人は彼の軽毀の四衆の如し人は替れども因は是一なり、(中略)いかなれば不軽の因を行じて日蓮一人釈迦仏とならざるべき」(佐渡御書 全集九六〇p)
と仰せになり、日蓮と同じ因を行ずる弟子・旦那らか、どうして日蓮と同じ境涯を得ることができないことがあろうか、必ず成仏するに違いない、と断言されているのです。このように
“化儀”とは、仏が仏になられた方法を、最も簡便な、しかも確実な、更に照準を仏法における初心の人にあわせて提示くだされた我々弟子・且那らの実践法ですから、これを単なる形式と軽んすることは、厳に慎まなければならないのです。
さて、臨終の大事の話にもどりますが、人はその死に際して、一生の出来事が走馬灯のように、瞬時に頭の中を駆け巡ると言います。まさに臨終のときは、人生の総決算のときであり、その人の生きざまが隠れもなく現れるときでもありますから、その姿もいろいろです。
四十二才のときに浄土宗をひらき、「ただ極楽往生のために南無阿弥陀仏と申せば、疑いなく往生する」として、おびただしい信者を生みだした法然は、建暦二年一月二十五日、庭まで雲集した信者たちの念仏の声の中、正午過ぎに死去しました。『愚管抄』の中で天台宗の僧・慈円は言っています。「終に大谷という東山にて入滅してけり、それも往生往生といいなしてて、人あつまりけれど、さるたしかなる事もなし」
念仏聖の死に、何か瑞相の起こることを期待して野次馬どもが集まったが、何の変わったことも起こらなかったというのです。
現在残っている美術品としての阿弥陀来迎図の中に、弥陀が結ぶ手の印の部分に、穴が二つ開いているのを見ることができます。これは、死の間際に阿弥陀仏が必ず迎えに来ると信じて疑わぬ人々が、かの仏画の手に五色の紐を結わえ、その端を自分の手としっかり結んで、離れてしまわないようにした名残であるといいます。見るものをして、哀れみさえ感じさせます。
善導は「酒肉五辛を手に取らざれ口にかまざれ、手にとり口にもかみて念仏申さば手と口に悪瘡付くべし」と禁め、法然は「洒肉五辛を服して念仏申さば予が門弟にあらず」と厳命しています。易行といわれながら、信者は更に一日に六万回の念仏と阿弥陀経十五巻の読経の課題を果たしても、その結果は顔の色は黒くなり、錯乱状態に陥るばかりであります。これが本当に極楽往生の姿でありましょうか。すると彼らは「往生に四つある。その中の第四は狂乱往生といい、観経の下品下生にある」とうそぶくのです。大聖人様は『妙法尼御前御返事』に、
「大論に云く『臨終の時色黒き者は地獄に堕つ』等云云、守護経に云く『地獄に堕つるに十五の相・餓鬼に八種の相・畜生に五種の相』等云云、天台大師の摩訶止観に云く『身の黒色は地獄の陰譬う」等云云」(全集 一四〇四p)
と仰せになり、狂乱と顔の相が黒く変化したのは、まぎれもなく堕地獄の姿であるとされているのです。
そうとは知らず、一日六万回の念仏のノルマを間違えすに実行するため、ある江戸時代の信者などは、あらかじめ一升枡に小豆が何粒入るか数えておき、念仏一回ごとに一粒の小豆を枡の中に放り込むという画期的?な方法を考案しました。こうすれば一升枡に何杯で、念仏何回、と数えることができ、念仏にうちこめるというものです。こうしてこの信者は、小豆一千万石分(一石は一升の百倍)の念仏を毎日唱えて過ごしたといいます。なんという無駄、なんという難行苦行でしょうか。その結果が、地獄行きでは、嘆いても余りあるものがあります。
M市にTさんという人がいました。八十歳を越えていますが、一つの悩みがありました。子供やお孫さんたちが、信心をしないのです。そこでお婆さんは、お寺の住職に指導を受けました。どうしたら折伏できるでしょうかと。住職は考えた末に「息を引き取るときに、題目を唱えてごらんなさい」と答えられました。そして、それはどんなに困難なことか、またどれほど大功徳を受けることができるか、懇切に指導されたといいます。お婆さんは、一つ一つの指導にうなずきながら、胸にしっかりと決意しました。
いよいよその日がきました。お婆さんは、「皆んなとお別れのときです。最後のお願いだから、私の題目に皆も合わせて、題目を唱えておくれ」そう言って「なん、みょう、ほう、れん、げ、きょう」と、一字一字、全身の力をふりしぼって題目をあげました。最初皆んなは、また婆さん、たわいもないことを言っている、と思っていたそうです。でも、最期とは思えない、その力強さに引きずられるように、思わず皆んな題目を唱えたそうです。後で子供さんやお孫さんが述懐されてました。「あのときほど、人間が神々しく見えたことはありません。あれから私たちは信心するようになりました」と。
水の絶えざる流れのように、清らかで真剣な日々の実践を積み重ねることにより、このように素晴らしい臨終が訪れるのです。
《参考資科》
「日本古代宗教の謎」佐治芳彦者(日本文芸社)
「数の不思義」博学こだわり倶楽部編(青春出版社)
「人間臨終図巻」山田風太郎著(徳間書店)
(大白法平成5年1月16日号)
© Rakuten Group, Inc.