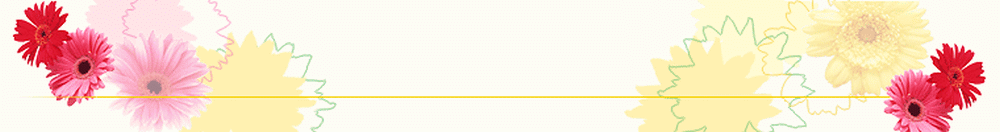御書編纂について
教学部長 大村寿顕
このたび、『平成新編日蓮大聖人御書』(以下、『平成新編御書』と略す)を発刊するに当たっては、実に二百六十五名もの教師僧侶の尊い御尽力を頂きました。ここに御協力を頂いた全国の教師僧侶各位に対して厚く御礼申し上げます。まことに有り難うございました。
昭和四十一年四月二十八日、『昭和新定日蓮大聖人御書』(以下、『昭和新定』と略す)が宗門において初めて出版され、僧侶必携の御書として使われてまいりました。この御書の特徴は、日蓮大聖人の御書といわれるものは、『日朗譲り状』を除いて、すべて網羅したというところにあります。しかし、それは逆に、「定見のない御書」との謗(そし)りを免れません。
そこで、宗門においては、宗祖日蓮大聖人第七百遠忌の記念出版事業の一つとして、『昭和新定』の見直しをすべく、昭和六十二年の春、御書真偽検討委貝会、御書系年対告衆検討委員会が設置され、藤本総監を委員長として、約八年の長きにわたって検討が加えられてまいりました。委員各位の並々ならない努力によって、このたび、一往の決着を見ることができたのであります。
ここに『昭和新定』を改訂し、『平成新定御書(仮称)』の編纂出版作業も佳境に入ってまいりましたが、平成二年に創価学会の大謗法問題が勃発(ぼっぱつ)し、『平成新定御書』の出版よりも、従来の『日蓮大聖人御書全集』(以下、『御書全集』と略す) に替わる、法華議員が使える御書の作製が急務となり、こうした経緯のもとに『平成新編御書』が出版されたのであります。
偽書として削除した御書
『平成新編御書』は、『昭和新定』から、六十二篇の御書を削除し、別に断簡を正篇に加えるなどして、計四百九十一篇の御書を収録しております。
その内訳は、真偽委員会において検討した結果、「新編御書不収録一覧」の「偽書」の項(57頁に掲載)に示しましたように、『垂迹法門』以下の三十二篇が完全な偽書と決定されましたので、これを削除いたしました。
次に、真偽未決の御書は、二十四篇ありますが、そのなかから『女人成仏抄』『土篭御書』『真言見聞』『上野殿御書』『法華初心成仏抄』『三沢御房御返事』『華果成就御書』の七篇は、真偽未決ではありますが、真書に近いものとして、本文に収録いたしました。
この七篇を除く『師子頬王抄』以下の十七篇は、真偽未決のうちでも偽書の可能性が濃厚でありますので不収録といたしました。それが「真偽未決書」の項(57頁に掲載)に示した十七篇の御書です。
重複書として不収録とした御書
次に、重複書として収録しなかった御書は、「重複書」の項(58頁に掲載)に示しました。まず『寿量品得意抄』は、真偽未決書であると同時に『開目抄』の一部と同文の重複書でありますので、不収録といたしました。
次の『立正安国論』の広本は、正本と重複しますので、不収録といたしました。また、『南条平七郎殿御返事』は、『種々御振舞御書』の末文と同じであります。『阿育王御書』は前半が『高橋殿御返事』、後半が『南条殿女房御返事』と同じで、本文が重複しております。
また、『来臨曇華御書』は『内記左近入道殿御返事』の断簡であることが明らかになりましたので、不収録といたしました。
また、『衣食御書』は既に『昭和新定』において『上野殿尼御前御返事』の一部として収録しておりますが、『平成新編御書』もこれにならい、『上野殿尼御前御返事』に編入しておりますので、重複書として不収録といたしました。
不収録とした真書
次に、『六因四縁事』ほか八篇の御書は、御真蹟ではありますが、図録等で、信徒向けの御書には、どうしてもこの御書がなければならないという特別な必要性も認められませんので、これを不収録といたしました。
『御書全集』収録分で不収録とした御書
また、『御書全集』に収録されているもので、『平成新編御書』に収録しなかった御書が三篇あります。まず、四五三『兵衛志殿御返事』と一八四『遠藤左衛門尉御書』の二篇は、偽書一覧に記載してありますように、真偽委員会によって偽書と決まりましたので、不収録といたしました。また、『寿量品得意抄』は、先程、重複書のところで申し上げたような理由で不収録といたしました。
このように『昭和新定』からは、偽書の可能性の強い六十二篇の御書を不収録としましたが、『御書全集』に比べれば、七十八篇もの多くの御書が収録されております。
系年を変更した御書
次に、系年を新たに変更した御書七十二篇を、「御書系年変更一覧」(59頁に掲載)に示しました。一番上の番号は『昭和新定』の番号です。題名の下の系年は従来のものであり、その下の「新編の系年」とありますのが、新しく決定した系年です。
これについての詳細な説明は、時間の都合上できませんので、そのうちの一、二について申し上げます。
まず、二四『三八教』ですが、この御書の内容は、天台の図録的なもので、今まで正嘉元年(聖寿三六歳)とする説が濃厚でありました。しかし、御筆跡を検討した結果、一〇〇『金吾殿御返事』(文永六年と決定)に最も近い御筆と判断し、従来の正嘉元年三月十六日から文永六年三月十六日に変更いたしました。
このように、御筆跡・書風から系年を変更した御書は、ほかに十二篇あります。
また、御署名・花押により系年を変更した御書は、六二『御輿振御書』ほか十八篇あります。
このうち、四六八『桟敷女房御返事』は、和歌山了法寺に御真蹟が現存しており、それには「二月十七日」と、月日のみあって年号はありません。古来、建治四年の御書とされておりましたが、それは本文の末尾に、「あらあら申すべく候へども、身にいたわる事候聞こまかならず候」の御文から、大聖人の御病状が重かった建治三年末より建治四年(弘安元年)五、六月までの御書と推定したためと考えられます。
しかし、大聖人の御病気は、四七〇『八幡宮造営事』の御文から、弘安四年にも窺(うかが)えるとして、御署名・花押の形態より『昭和定本日蓮大聖人遺文』(以下、『昭和定本』と略す)『昭和新定』は、弘安四年に系(か)け、『富士年表』もこの説を採っております。
ただし、大聖人の御病気は弘安四年のみならず、弘安五年三月の四九八『筵三枚御書』にも窺われるように、弘安五年二、三月ごろまで続いたことが明らかです。そこで御署名・花押について、さらに詳細に検討した結果、日蓮の「蓮」の字の「しんにゅう」の形が、弘安四年三月二十一日と目される、断簡五七『稻河入道殿御返事』以降は、右上に跳ね上がる特徴があり、本書にもこの特徴が見られ、特に本書の「蓮」の字は、そのなかでも後期に属するものと判断できますので、むしろ弘安四年よりも、弘安五年に系けるべきであると決定いたしました。
文字の誤読・誤記による系年の変更
次に、文字の誤読や誤記によって、系年を誤って掲載していた御書について申し上げます。
これに関しては、九九『六郎恒長御消息』・二一〇『三沢御房御返事』・二八三『曽谷殿御返事』の三篇が挙げられます。
まず、九九『六郎恒長御消息』は、従来、文永元年説でありましたが、宮崎英修が『波木井南部氏事跡考』という論文において、「元」は「六」を誤写したものであるとの説を立てて以来、文永六年説が定説になり、『昭和新定』もこれに倣(なら)ってまいりました。
しかし、日達上人は『富士学報』の二号に、この御書は内容的には佐前の、念仏破折の一連のなかに入るものであり、文永元年九月とすべきであると御指南されております。しかも、最も古い文献である『本満寺録外』にも文永元年とあるところから、委員会では日達上人の御指南のとおり、文永元年といたしました。
また、二一〇『三沢御房御返事』は、従来、文永十二年二月十一日でありましたが、『縮刷遺文』(霊艮閣版)で「二月二十一日」としたため、以後の『昭和定本』『御書全集』『昭和新定』等がこれに倣って、「二月二十一日」としております。
しかし、「二十一日」と改めた理由は全く不明で、筆写の際の誤記であると思われます。故に、本書は御真蹟はありませんが、御真蹟と対照したとする写本の説(高祖遺文録註)を採り、文永十二年二月十一日といたしました。
このほか、委員会においては、御遺文中の「御本尊」と「法華経の御宝前」という語の用い方を系年推定の一つの基準といたしました。
つまり、大聖人は、弘安二年十月以前は「御本尊」と言われ、それ以後は「法華経の御宝前」という言い方をされております。これを考慮して検討した結果、三一五『日女御前御返事』・三六八『初穂御書』・三七五『十字御書』の三篇の御書の系年が変更されました。
特に三一五『日女御前御返事』は、従来、建治三年八月二十三日の書とされておりましたが、日顕上人が平成四年九月二十一日、法観寺の御親修の折に御説法され、昨日もまた御講義を賜りましたように、本書は、日女御前に授与された御本尊(現存はしない)の体相を述べられたものであり、現存する大聖人の御本尊百三十二幅のうち、提婆達多が記されているのは、文永十一年七月二十五日の一幅を除き、弘安二年二月の目師授与の御本尊以後、弘安五年に至る御本尊に限定されるのであります。
本書は従来、建治三年に系けられておりましたが、同年の他の御本尊には提婆達多はありません。
また、本書には竜女の名が見えますが、竜女が記されている御本尊は、弘安二年二月の目師授与の御本尊のみであります。
これらの理由により、本書の系年は弘安二年八月二十三日に系けるのが妥当であると考えたのであります。
対告衆を変更した御書
次に、対告衆を変更した御書は、「対告衆変更一覧」(62頁に掲載)に示しましたように、一一四『月満御前御書』以下の十二篇であります。
一一四『月満御前御書』は、四条金吾宛ての御書とするのが定説となって現在に至っております。しかし、そうすると、本書の「若童生まれさせ給由承候」の文が、同年同月の御書である、一一三『四条金吾女房御書』の「懐妊のよし承條畢」と時期的に合わなくなります。
故に対告衆は四条金吾ではなく、それ以外の鎌倉在住の檀越と見るほうが穏当であります。
本抄の初見となる『他受用御書』には「月満御前」とのみで、四条氏の名前はありません。したがって、委員会においては、この書の対告衆を月満御前としたわけです。
断簡に命名した御書
また、このたぴの『平成新編御書』を編纂するに当たり、今まで無名であった断簡をそれぞれ一書として、それに当編纂委員会において初めて、「断簡御書一覧」(63頁に掲載)に記載してありますような題名を付けましたので、御承知ください。
題名を変更した御書
次に、題名を変更した御書について申し上げます。
従来、宗内で使用されてきた『御書全集』収録の御書で、対告衆の変更などにより題名が変わったものは四十七篇あります。便宜上、変更以前の題名は、『平成新編御書』の目次の異称・略称の欄に記載してあります。
『御書全集』の御書名を変更した御書一覧は資料(63頁に掲載)に示したとおりです。
なお、細かい部分の変更は、『昭和新定』の題名に合わせたものでありますので、これを省略し、主なものについて申し上げます。
まず、表の一の『十住毘婆沙論尋出御書』ですが、本書には宛て名があり、「武蔵公御房」となっております。故に、わざわざ『十住毘婆沙論尋出御書』とする必要性もないことから、本来の宛て名を題名として、『武蔵公御房御書』といたしました。
次に、二の『念仏者・追放せしむる宣旨・御教書・五篇に集列する勘文状』であります。この書は題名が長いために、通常、略称をもって『念仏者追放宣状事』などと称されております。
『平賀本』では、本文末尾にある『念仏者追放宣旨御教書事』を題名としており、今回、検討の結果、これを採用いたしました。
次に、四の『六郎恒長御消息』ですが、本書は昭和四十七年の教師講習会で日達上人が、対告衆を六郎恒長とする根拠はどこにもなく、この御書は門下一般に下されたものであるとされました。故にこの説を採り入れ、最も古い文献である『本満寺録外』の題名を採用し、『念仏無間地獄事』といたしました。
次に、二一の『一谷入道御書』ですが、この『一谷入道御書』との題名が、『御書全集』を含めた既刊御書のなかで最も多いのであります。しかし、本書を頂いたのは一谷入道の妻であることから「女房」を付すのが適当であると思われます。『昭和新定』では、『録内御書』を踏襲して『一谷入道百姓女房御返事』としておりますが、委員会としては強(し)いて「百姓」を付ける必要はないと判断し、題名を『一谷入道女房御書』と訂正いたしました。
次に、二七の『高橋殿御返事』ですが、本書は日達上人が昭和四十三年の教師講習会において、既に対告衆を南条時光に変更されております。よって、『高橋殿御返事』との題名はふさわしくないので、別名を採用して『米穀御書』といたしました。
次に、二八の『妙法尼御前御返事』ですが、本書には御真蹟がなく、古来から写本、刊本、目録等、すべてにおいて『六難九易抄』として収録されていたものであります。『他受用御書』で初めて『妙法尼御前御消息』と改められましたが、本書の内容からは対告衆を妙法尼とする材料は何も見当たりませんので、古来からの題名である『六難九易抄』に戻す形を採りました。
また、『昭和新定』番号四四六の『大尼御前御返事』についてですが、本書は第十九紙と第二十二紙の断簡二紙を合わせた御書で、従来、独立した二篇の御書として扱われてきたものですが、『昭和新定』で、これを一書として扱ったために、本文の内容から見て脈絡のないものとなっておりました。
そこで今回、従来どおり前半の第十九紙と後半の第二十二紙を分離して扱うことにし、前半の第十九紙を『大学殿事』とし、後半の第二十二紙を『大尼御前御返事』として収録しました。
編纂に当たって解明された御書
『平成新編御書』は、御真蹟、古写本等の伝承本を重視しつつ、既刊の御書およぴ御書講義類等を参照して編纂いたしました。
その結果、『昭和定本』『御書全集』『昭和新定』等の従来の御書の誤りが発見され、それを訂正した箇所がいくつかあります。
今、そのなかの代表的なものを紹介いたします。初めに、御真蹟が西山本門寺に蔵されている『浄土九品の事』について申し上げます。これは資料(66頁に掲載) を参照していただきます。
従来の御書では、後半の「下輩・中輩・上輩」等の文字が逆さまになって表記されており、その意味するところが不明瞭でありました。
それが、このたぴ、当抄を校正した若手編纂委員より、「下輩・中輩・上輩」は、本抄前半の「上品・中品・下品」に関連するのではないか、との指摘があり、御真蹟を拝して検討したところ、『日蓮聖人真蹟集成』(以下、『真蹟集成』と略す)に収録された当御書の「下輩・中輩・上輩」等の後半の一紙を逆さまにし、「上品・中品・下品」等が書かれた前半一紙に合わせてみたところ、後半一紙の文字の欠けた所と、前半一紙の文字の欠けた所とがピツタリと一致して、「三」と「品」の字が、はっきりと顕れたのであります。
しかも、それによって、「上品」は「上三品」、「中品」は「中三品」、「下品」は「下三品」となっていたことが判り、また、それぞれに、「上輩」「中輩」「下輩」が関連した図となっていたことが明らかになったのであります。
たしかに浄土宗では、「上輩・中輩・下輩」の三輩と、「上三品・中三品・下三品」の九品は、共に念仏によって往生する人の機根と行位を示す教義であり、御真蹟を上下に合わせると、そのことが説明づけられるのであります。
現在の御真蹟は、元の御真蹟が過去に何かの理由で上下に切られてしまい、上半部が逆さまに表装されてしまったものと思われます。そして、従来の御書は、この切り離されたままの状態で収録されていたことが判明したのであります。
次に、『昭和新定』に収録されている断簡御書を改めて一つひとつ検討したことにより、『昭和新定』では断簡一四九として扱われていたものが、『依法不依人御書』(平成新編御書八〇五頁)という題名で新たに独立した御書として編纂することができました。
いわゆる『昭和新定』では、『真蹟集成』に収録された玉沢の妙法華寺ほか三ヵ所に蔵されている断簡七紙を、『真蹟集成』の収録順に一篇の書として編纂していますが、『昭和定本』や『日蓮大聖人御真蹟対照録』では収録順が異なって編纂されており、研究の余地が充分にあったのであります。
そこで、今回、当断簡を検討してみたところ、『昭和新定』二六〇六頁に収録されている、池上本門寺蔵の「行ありて学生ならざるは国の用なり」以下「一仏の名号には諸仏の功徳」までの御文と、同二六〇二頁に収録されている玉沢妙法華寺蔵の「をさまらず。法華経の五字には諸経をさまるというか」以下「法相宗・三論宗等も皆我が依経を本として諸経を」までの御文が、その文体と内容から見て、一書として差し支えないことが確認されたのであります。
すなわち、「問うて云く」「答えて云く」の構文の関連、「一仏の名号には諸仏の功徳をさまらず」と「法華経の五字には諸経をさまるというか」の両御文の文脈と内容の関連、さらには御真蹟の両紙の御筆跡は同一であると認められることから、両紙の首末の字の欠けた部分を繋ぎ合わせるとき、「華」「経」「に」「は」等の字が合致して、当断簡が続いていた御文であることが明らかになったのであります。
さらには、「問うて云く一仏の名号には諸仏の功徳」の次に来る解読不明の文字を「は」と判読したことにより、「諸仏の功徳はをさまらず」というように御文が繋がりました。以上の観点より、両紙は同一の繋がった御書であると判定したのであります。
この御書に、さらに、『昭和新定』二六〇三頁に収録された「よするなり。されば華厳宗に人多しといえども澄観等の心をいでず」以下の断簡二紙が繋がるのであります。
つまり、『昭和新定』二六〇二頁に収録されている玉沢妙法華寺蔵の、
「をさまらず。法華経の五字には諸経をさまるというか。答て云く、爾なり(乃至)華厳宗と申す宗は華厳経を本として一切経をすべたり。法相宗・三論宗等も皆我が依経を本として諸経を」
の御文に、『昭和新定』二六〇三頁収録の「よするなり。されば華厳宗に人多しといえども澄観等の心をいでず」云々との御文が繋がるのであります。
もともと、『日蓮大聖人御真蹟対照録』では、両方の断簡を一篇として編纂していましたが、今回、当委員会では、華厳宗に関する同一の記述、および依法不依人に関する首尾一貫した内容、そして「よするなり」の「よ」の字を「釈」(『昭和定本』では「釈」と判読している)と解読したことによって前後の文脈が通り、同一の御書であることを認めたのであります。
このように、玉沢妙法華寺に蔵される断簡三紙と、池上本門寺に蔵される断簡一紙は、同一の接続する御書であると判定し、その内容から『依法不依人御書』と名を付けたのであります。
このように、『平成新編御書』の発刊に伴い、従来の御書に欠けていたところや、編集のミスを訂正することができましたのも、編纂委員各位のひたむさな研鑚の賜物であると深く感謝申し上げます。
以上、御真蹟のある御書の内、代表的な三書を選び、その校訂について述べました。
また、『平成新編御書』においては、古来の伝承、すなわち、御真蹟、写本、刊本に本来なかった年月日は、本文から削りました。御書の系年は推定によったとしても、本文に置〈ことは、大聖人のお筆による本来の姿ではないと考えたからであります。
このほか、『平成新編御書』は、『高祖遺文録』以来そのままにされてきた御文も、改めて古来の御書と突き合わせ、元に戻したほうがよいところは戻すようにいたしました。
これらの意味でも『平成新編御書』は、従来、出版された諸御書よりも、大聖人の御真意をより正しく伝えていると言えましょう。
ルビについて
最後に、御書のルビについて申しますと、『平成新編御書』には、今まで使用してきた『御書全集』にはないルビがいくつか付いています。
例えば、『御書全集』等には、「一・」との文字に「いったい」とルビが付けられていましたが、これを今回、「いってい」と読み方を変えました。その理由は、『南条殿御返事』(平成新編御書一五二二頁)の御真蹟を見ますと、そこには「大海の一・」と漢字で書かれていますが、その四行後には、「一」と漢字で書かれ、続いて平仮名で「てい」とあり、その後、同様の表記が三ヵ所にわたって書かれております。このことから、大聖人は、「いったい」ではなく「いってい」と読まれていたものと判断し、そのようにルビを付けたのであります。
また、従来、「えきびょう」(疫病)と読んでいたものを、今回は、「やくびょう」とルビを付けました。これは、御真蹟が総本山大石寺に現存している『上野殿御返事』(竜門御書) に、大聖人の御筆で「やくびやう」と平仮名で書かれておりますので、それを重んじて、このようなルビを付けたのであります。
また、「けんざん」(見参)を「げんざん」、「けさん」を「げざん」として、ルビまたは漢ルビを振りました。これは、各種の国語辞典または古語辞典によったのであります。
また、「まほる」、つまり「守る」は、「まぼる」と表記して漢ルビを振りました。これは、明治までは、濁音・半濁音の表記法がないためにすべて清音で表記されておりました。この「まほる」は、守護・警護の意味であります。これは、国語辞典(新潮国語辞典・大言海) によりますと、「まぼる」と発音しなければ「守る」の意味にならないとあります。そこで、『平成新編御書』では、現代の表記法に従って、発音どおり「まぼる」と表記いたしました。
なおまた、絶待妙または相待妙は、各辞典ではそれぞれ「ぜつだいみょう」「そうだいみょう」と読んでいますが、宗門伝統の読み万を尊重して、従来どおりに「ぜったいみょう」「そうたいみょう」と振り仮名を付けました。
また、御会式の際、捧読する『立正安国論』で、かつては「客の曰く、今生後生誰か慎まざらん誰か恐れざらん」と読んでいた箇所がありますが、この「恐れ」という字は、御真蹟は「和」という字になっております。したがって、今後は「誰か慎まざらん誰か和(したがは)ざらん」と読みますので、捧読に際しては充分御注意いただきたいと思います。
なお、『平成新編御書』について誤字・脱字等その他、お気付きの点がありましたら、教学部までお知らせくださるようお願いいたします。
本年は、地涌六万大総会を開催して、いよいよ僧俗一致して真の広宣流布に向かって大前進を開始する大事な時を迎えました。この時に、宗門において初の『平成新編御書』が刊行されましたことは、まさに宗門主導の広宣流布の時が来たと、歓喜に身の引き締まる思いであります。
これひとえに御本尊の御威光と、御法主上人の尊い御慈悲の賜物であります。
それに加えて、宗門を担う若手教師各位の並々ならない努力があったればこそであります。ここに重ねて厚く御礼申し上げますとともに、教学の推進に、今後一層の御協賛を賜りますようお願い申し上げ、編纂委員会を代表しての「『平成新編日蓮大聖人御書』の編纂について」の話を終了させていただきます。
※ 読者の教学研鑚に資するため、昨年の八月二十五日に開講された全国教師講習会における大村教学部長の発表を、資料と共に掲載しました。
大日蓮編集室
『平成新篇日蓮大聖人御書』の編纂について
―補足― 『日女御前御返事』の系年について
教学部長 大村寿顕
先月号に、「『平成新編日蓮大聖人御書』の編纂について」と題し、その経緯を御紹介いたしました。そのなかで、三一五『日女御前御返事』の系年を、従来の建治三年八月二十三日から弘安二年に変更した理由について、次の二点を挙げました。
すなわち、一点は、同抄に「悪逆の達多・愚癡の竜女云云」と、提婆達多と竜女が示されておりますが、現存する大聖人の百三十二幅の御本尊中、提婆達多が示されるのは、文永十一年七月二十五日の御本尊の一幅を除いて、弘安二年二月の日目上人授与の御本尊以後、弘安五年に至る弘安年中の御本尊に限定されているということであります。
また、もう一点は、竜女が示されている御本尊は弘安二年二月の日目上人授与の御本尊のみであるということです。
以上を弘安二年に変更する理由といたしましたが、さらにもう一点、建治年中の御本尊には、「善徳仏」と「十方分身仏」が勧請(かんじょう)されておりますが、弘安元年以降の御本尊からは、全く見ることができないということです。
すなわち、御本尊の相貌(そうみょう)について、建治二年に確定されている『報恩抄』には、
「日本乃至一閻浮提一同に本門の教主釈尊を本尊とすべし。所謂宝塔の内の釈迦・多宝、外(そのほか)の諸仏並びに上行等の四菩薩脇士となるべし」(平成新編御書一〇三六頁)
とあります。ここに「外の諸仏」とあるのは、建治年中の御本尊の相貌と同じく、十方分身の諸仏を示されたものです。ところが、『日女御前御返事』における御本尊の相貌を教示されたところには、
「されば首題の五字は中央にかゝり、四大天王は宝塔の四方に坐し、釈迦・多宝・本化の四菩薩肩を並べ、普賢・文殊等、舎利弗・目連等座を屈し、日天・月天・第六天の魔王・竜王・阿修羅・其の外(ほか)不動・愛染は南北の二方に陣を取り、悪逆の達多・愚癡の竜女一座をはり云云」(同一三八七頁)
とあるように、「善徳仏」や「十方分身仏」を表示する部分は全く見ることができません。
このことは、『日女御前御返事』が建治年中の御書ではなく、弘安元年以降の御書だからであると思われます。したがって、これも『日女御前御返事』を弘安二年にした大きな理由であります。
この点が欠けておりましたので、補足いたします。
© Rakuten Group, Inc.