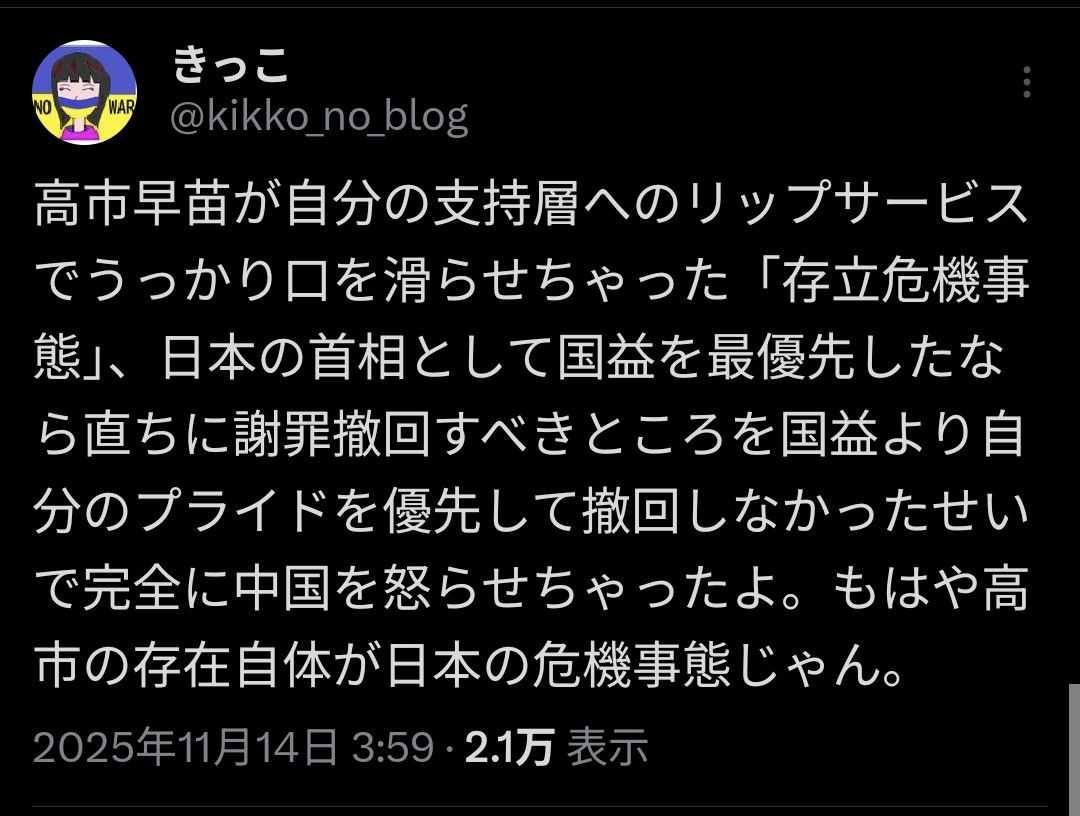全53件 (53件中 1-50件目)
-
日本人であること
自国以外で生活したことのある人は、何人であっても、多かれ少なかれ「母国の代表」として扱われた経験があるのではないだろうか?「母国」を「部族」「民族」「(一定の宗教の)信徒」に置き換えても良い。人は誰でも、自分のアイデンティティーを確立するために何らかの拠り所を必要とする。私の場合は「日本人であること」だった。両親や兄と海外で暮らした期間は約12年。滞在先は4カ国。その間、私たち家族以外の日本人は一人もいない国なんていうのもあった。続きはこちらをクリック
2009.05.05
コメント(1)
-
私にとってのフランス語
中学の卒業アルバムに書いた将来の夢は「外国語を使った仕事」だった。その考えは中学1年で西アフリカから帰国した時から持っていたものであり、それ以降も自分の未来にそれ以外の選択肢はなかった。美術も音楽も運動も、人並みにはこなせたと思うし、演劇も好きだったけれど、将来それで生計を立てたいと思う程ではなかった。父から「カウンセラーとか向いてるんじゃないか」と言われ、確かに心理学にも興味を持ったことはあったが、あくまでも趣味としてだった。空想することも文章を書くこともわりと好きなので、小説を書いてみたりもしたけれど、あくまでも手遊びにすぎない。まぁ、現状を省みれば夢は叶ったと言って差し支えないと思う。卒業アルバムが作られた時と違うことがあるとすれば、当時の私にとって第一外国語はフランス語だったのに対し、今は英語に換わっていることだろう。喋り言葉だけを比較するならば、得意な順に日本語→フランス語→英語→スペイン語・・・となるが、書き言葉となると、2番目と3番目の順序が逆になる。何故「外国語」にこだわったのか?続きを読む
2009.05.05
コメント(0)
-
外国人であること
私たちは出会ってから今まで、ずっと日本で暮らしています。5年前のその日は私の誕生日。「待ち合わせしよう」そう提案したのは夫でした。続きはこちらをクリック。転載元はこちらです。
2006.11.29
コメント(0)
-
君はこの国を好きか
何年か前に読んだ鷺沢萠氏の著作である。「君はこの国を好きか」読んだあとから「韓国」とか「日本」とか「北朝鮮」とかって置き換えて今もずっと考えている。 続きはこちらでどうぞ。
2006.10.10
コメント(0)
-
I hate it!?
うちは基本的に80%を英語に頼ってます。 仕事でも使うし、やはり言葉ができないとイギリスでは生きていきにくい。 その上でもあんまりテレビを見る習慣のない私たちにとってこの80%は、職業生活にとって非常に重要かなぁと思います。あとの20%はビジネスで使うような日本語。 基本的に私は友人に語りかけるような口調では相方に話しかけないように努力しています。 理由はいつか日本に住むときになったときに、仕事で「でもぉ~ それじゃぁダメだよ」という言葉が相方の口から出るのを恐れているため。 この人は結婚式のときに、友人に何か聞かれて「それでいいと思うわ!」と叫んで(日本語でです!)周囲の大爆笑をかった人ですから・・・続きはこちら。
2006.09.18
コメント(0)
-
外人な日本人
久しぶりに昔の事なんか思い出して凹んでいる。私は小さい頃にずっと、外人!外国帰れ!っていじめられてたんだ。続きはこちら。
2006.03.12
コメント(0)
-
クナリ・オミョン【その日が来たら】
韓国で製作された平和と南北統一祈願プロジェクトCDの中のメインタイトル曲になってる歌なのだそうだ。韓国のトップ歌手達が一緒に歌ってる珍しい歌。セブンとかイ・ジョンヒョンとか私でも知ってる有名所が出演してる!最初この歌を聞いたとき意外にサラッと聞けてびっくりした。平和と南北統一祈願なんていかにもって感じで聞く前からいろいろ思うところがあったけど、そんな事を考える暇もないままに、心に直接響いてくる歌だった。やっぱり、歌は偉大だよなと思う。朝鮮学校に通ってた時。<続き>
2006.01.19
コメント(0)
-
国籍とステータス
私はまぎれもない日本人だ。たぶん、もしかすると最後までアメリカに住むことになるかもしれないけど、でも心は死ぬまで日本人だ。ひょっとしたら、どこかの段階でアメリカ市民になってしまうかもしれない。その可能性も最近は考えている。でもそれは単にステータスだけの問題なのだけど、今はまだ踏ん切りがつかない。続く・・・
2005.11.02
コメント(0)
-
家族の絆
私の家族はすごく仲がいい。家族全体としての仲もよいけど、ひとりひとり同士の仲もよいのだ。反抗期らしい反抗期も遅めに経験した。それでも程度は軽かった。なんでか・・・続きはこちら。
2005.06.26
コメント(0)
-
国際結婚2代目
これ、アタシのことです。まあ、「国際結婚」という言葉の字面どおりに行けば確かに2代目です。でもね、じつはアタシ、越境結婚3代目なんですよ、どっちから数えても。そういう家族なんでしょうね。でもアタシは「越境」してると言っても・・・<続き>
2005.06.10
コメント(0)
-
フィアンセは何人?
有吉佐和子の『非色』を読んだ。全てが主人公の「私」の視点から描かれた一人称の物語なのだけれど、その主人公笑子のあまりに正直な自己内省の声に触発され、書き留めてみたくなったことがある。自分でも嫌になる、自分の嫌な部分についてだ。私がフィアンセAの話をすると、Aに会ったことのない人はたいてい、「それで彼は何(人)なの?」と聞いてくる。その瞬間に私はいつも戸惑う。そして答えるときには、いつも何か大変な秘密を白状している気になる。日本人に「やっぱり」と思われるのも、アメリカ人に「あー、ありがち」と思われるのもいやだ。続きはここ!
2005.06.09
コメント(1)
-
親としての課題
「自分は一体何者なのか?」という問いは(2004年11月10日の日記)『悩んだ』、『苦労した』と同時に『自分のアイデンティティーを考えさせてくれる 大変良い機会』でもあったわけです。『人と違う自分』と『合わせていく自分』(2004年11月9日の日記)このバランスをとるというのはTCKでなくても誰もがしていることではあるけれどTCKはそのプロセスに普通の人より時間がかかる場合があるかもしれません。続きはここ。転載元はこっち。
2005.04.19
コメント(0)
-
マイノリティー同士のバトル――台湾系・中国系・韓国系の場合
最近の日本の学校では、中国帰国の子どもと在日の子どもの摩擦が当たり前のように起きている。マジョリティーにやられてもやり返せないが、身近なマイノリティーになら、やり返せるというわけだ。ここ日本で起きている中国系と韓国系の子どもの敵対については、少なくない日本人が想像するような「中国人と韓国人の仲の悪さ」とは違う。続きを読む!
2005.04.10
コメント(0)
-
マイノリティー同士の連帯が大事だという理由で、
私は、基本的には、ハーフや帰国子女と、中国系や韓国系・琉球系の人々を引き合わせようとはまったく考えない。大和系と非大和系を紹介するのは、私自身がハラハラするからだ。実際、私はしたことがない。当事者の意思によるマイノリティー同士の連帯ではない限り、私にはとうてい責任を負えない感情的な摩擦が起きる可能性があるからだ。大和系が、非大和系の感情を無視するのは自然なことだ。当事者の意思と感情をめぐっての責任を覚悟のうえ、連帯したい人だけが連帯しようというのでなければ、無理が大きい。コメントをどうぞ
2005.04.10
コメント(0)
-
マイノリティのいがみ合い
「一般人」と呼ばれる社会のマジョリティと見かけの違うマイノリティと見かけが「同じ」マイノリティの間には亀裂が生じることが良くある。理由はもちろん多岐にわたってるわけだけど、ひとつはお互い、相手が「羨ましい」「そんなんで済むんだったらいいじゃん」と思ってることにあるかもしれない、と思う。見かけの「違う」人は・・・続きはここをクリック。
2005.04.08
コメント(0)
-
海外経験を隠すことについて
インターネットで偶然、そのトピックを見つけたとき、目がテンになった。読みすすむうちに、私の気持ちは激しくヘコんだ。なぜか涙も出た。続きを読む
2005.03.18
コメント(0)
-
どの日本人が「在日」について本当のことを言ってるんだ?
ある日本人曰く。「在日って、優秀だよねえ」別の日本人曰く。「在日って、怠惰で暴力的だよねえ」また別の日本人曰く。「在日って、お金持ちが多いから」さらに別の日本人曰く。「在日は貧乏人が多いから」等々、等々。言っているとキリがない。在日って、一人何役やってるわけ???コメント欄
2005.03.09
コメント(0)
-
帰属意識に関する悩みから、社交に関する悩みへ
(1)私はある時期まで、「私は韓国人? それとも日本人?」と悩み続けたっス(笑)。それねえ、つまり従うべき規範を求めていたという要素も大きくて。(2)「日本人になる」という意識はなかったけれど、ただし「日本の規範に従う」という意識はめちゃ強かった! でも規範にかかわらず、どーせ「“完全な”日本人ではない」から、「そうしたらしたで、しないならしないで」ゴチャゴチャ言われるので、葛藤だらけの日々。(3)私は自分が本場韓国人でないという意識があったので、だから自分は日本人だとすっかり思いこんでいた。でも自分と他、という意識はとにかく強かった。当たり前だよねー。ははは。(4)自分がどうあるか、とは別のレベルで、人とどうやってコミュニケートするか、という課題があることに気がついた(爆)。問題は……!私はここでは、ナニ人なのかしらぁ~?私はここでは、どういう立場の人間なのかしらぁ~? 何を言うのはよくて、何を言うのはいけないのかしらぁ~?って、いまだに迷います(苦笑)。つまり社交に迷いがでるンす。私と一緒にいる人も迷っていますからね(笑)。コメントはこちら。
2005.03.09
コメント(0)
-
バイリンガル&バイカルチャー教育されてコケた私
小学校4年生半ばくらいまでの記憶が本当に少ないんだよね。ぜんぜんないわけじゃないよ。覚えていることもあるけれど、それが周囲の人々とは比較にならないくらい少ないんだよ(涙)。ただねえ、面白いこともあってねえ。体で覚えたことは、体が覚えているんだよ。ピアノとか、鉄棒とか、編み物とか、ピンクレディーの振り付けとか(泣笑)。忘れたと思っていても、体が勝手に動いちゃうんだよ~(号泣)。ピンクレディーとかキャンディーズとか、これほど覚えている人間って、私はほかに一人しか知らない(涙)。こんなことになってるのって、親がバイリンガル教育を私にしちゃったってだけじゃないよ。日本語では日本の常識を教え、韓国語では韓国の常識を教えるみたいなことをしちゃったのよ。続きはここ!
2005.03.09
コメント(0)
-
名前が二つ
私には「かぐや」という日本名があるとすれば、「う~や」と言う英語名がある。どっちも物心ついたときから呼ばれていた名前で、どちらのほうがより本物、ってことはない。しいて言えば、続きはここ。
2005.03.06
コメント(0)
-
リンク集
やっとリンク集の整理をちょっとしました。ふう~。見てやってくださいね。あと、このページもいいよ、ってお勧めがあったらどんどん教えてください。リンク集に貼る際には事前に承諾をもらわなかったので、ここで自分のリンクを見つけてびっくりって方、ごめんなさい。リンクをはずして欲しかったら、私書箱のほうに連絡ください。
2005.02.25
コメント(0)
-
立場の変化と感じ方
私は、アメリカにいるとき「外国人」だったのだが、自分自身を「みんなと違う」とか「よそもの」だと思うことはあまりなかった。年齢的に成人していなかったこともあるが、周辺の人々に多様性があったことが主な要因だろう。実にさまざまな人がいた。さまざまな外見の、さまざまな宗教の、さまざまな祖先を持つ人々。英語を話せない人もいた。英語は話せても外国語のアクセントが強く残る人もいた。私のような外国人もたくさんいた。当時のアメリカの大人たちは、アメリカの中に多様性が存在する事実を認め、お互いがお互いを差別なく大切にするべきだと子供に教え、多様性を誇りにしていた。しかし実際にはまだまだだった。続きはここ。
2005.02.17
コメント(0)
-
名前って何?
去年韓国にブラッと遊びに行ったときに鐘路のでっかい本屋で韓国語版"GO"が平積みされてるのを見つけて思わず買ってしまいました。オリジナルを読んだから別に買う必要もなかったのですが、ここんとこ韓国語でどう訳してるんだろう~とか気になりだして、まあ、韓国語の勉強にもなるし。いいやと。訳しで特に気になったのがここ。主人公が在日"朝鮮人"から在日"韓国人"になる経緯及び朝鮮学校・総連の説明。果たしてどう訳すのだ!?続きby みょんしる
2005.02.16
コメント(0)
-
「国際結婚」をして日本で暮らしている女性たちに、
私はそうとう親切にしてもらってきているんだよね。まあ、この場合は、まず私より年長者ばかりなんだけれどさ。戦後焼け野原で、というほど古い話でなくても、60年代70年代でも、かなり大変な思いをした人がいるんだよね。ある女性は、白人の夫と一緒に道を歩いているだけで、「あんなパンパン、朝鮮人に決まっている」って、日本人男性たちに怒鳴られたんだって。彼女はボロボロ泣きながら、「あなたも大変でしょう。がんばってね、がんばってね。いつでも私に相談してね」とか、力強く言ってくれたしねえ。だから、私は、今度は「国際結婚」をして日本でつらい思いをしている日本人女性たちがいたら、彼女たちを励ましたい、とそう思っているんだよね。「恩返し」なんて、偽善的に思われちゃうかな。それでもね、こんな「恩」という連続性があってもいいじゃないか、って思っているんだよね、私は。。。コメントはこちら。リールーさんのサイトはこちら。
2005.02.15
コメント(0)
-
もう泣きたくないから
私はこういう活動をしている。私が「なにかがおかしい」と言ったときに「でもそれは相手の立場も理解してあげなきゃ」と言ってそこからは私をひたさら諭そうとするだけで、私の言うことを聞いてくれなかった人たちがいっぱいいた。親身になって聞いてくれるのは家族と家族同然の幼なじみのみ。それがあっただけでも私は幸せものだったが、家族だけが社会生活の中心ではなかったから、特に学校生活中心にものごとを捉えがちな思春期に周りに「わたし」という人間を認めてもらえていない、と感じていたのは非常に辛かった。この場は、「マイノリティ」として共通点も相違点もある人たちがお互いの経験を通して、思ったことや感じたことを書いていける場にしていきたいと思って始めた。続き。
2005.02.14
コメント(0)
-
私が泣くとき ~ 日本語
昔感じた気持ちがまた思い出されてしまうとき。ものごころついた時からついて回ったあの気持ち。「わたし、日本人なのに。どうして日本人じゃないって言われるの?」今でもたまにはあるのは、誰でもするような簡単な文法ミスでも「ああ~、やっぱり・・・」としたり顔で言われたり、「やっぱりね」という態度を取られたりすること。逆にもっと多いのは、続きはクリック。
2005.02.13
コメント(0)
-
ハーフという言葉が嫌いなわけ
私には保育園からの幼なじみがたくさんいる。みんなとてもいい子が多くて、私も学ぶところがたくさんある。小学校3年生のころにある幼なじみAちゃんがテレビででも見たのか、私の真ん中にツーと線を引く手振りをして、「ハーフって英語の半分って意味なんだよね。だからかぐやはこっちからこっちがアメリカ人でこっちからこっちが日本人なの?」と冗談半分で言ってきた。続きはこちら。
2005.02.09
コメント(0)
-
「韓国系日本人」と「日韓ブレンド」
わたしの義理の兄弟やイトコ(ちなみに私にとってイトコとは兄弟と同じだ)には、韓国系日本人もいれば、日韓のブレンドもいる。外見がどうやっても変わらないせいだけれど、日本人アイデンティティーの兄弟もいれば、韓国人アイデンティティーの兄弟もいる。だが韓国人アイデンティティーといっても、日本人に対して、なのであって、本場?韓国人だとはまったく考えてないところがミソ。でもさ、韓国人二世でアメリカに留学して、その後カナダ人と結婚してアメリカで暮らしているとか、同じく韓国人二世でアメリカに留学して、その後メキシコ人と結婚してアメリカで暮らしているとか、またしても同じく韓国人二世でアメリカに留学して、その後イタリア人と結婚してイギリスで暮らしているとか等々、そういうハトコ(私にとっては兄弟みたいなもんだ)の子どもはどう考えればいいんだ? ・・・続きはこちら
2005.01.29
コメント(0)
-
「日米ハーフ」と言われて違和感を感じるわけ
私は一応、日米ハーフらしい。理由は簡単。日本国籍と米国籍の親が片方ずついるから。建前はそうだ。でも本当にそうだろうか?・・・続きはここをクリック
2005.01.28
コメント(0)
-
中学生時代
私が最初に在日コリアンの子と仲良しになったのは中学生のときだった。部員も少なく、その中でも圧倒的に女子生徒の少ない部活で、私たちは共に「はっきりしていて、パワーのある女子」と評価されていた。とにかく人数の少ない部活だったし、更衣室での着替えももちろん一緒だったので、先輩・後輩の別けなく、みんな仲が良かったのだが、この子とは、性格の一致以外にもいろいろ共通点があった。・・・(続きはココ)
2005.01.13
コメント(0)
-
中学生時代
私が最初に在日コリアンの子と仲良しになったのは中学生のときだった。部員も少なく、その中でも圧倒的に女子生徒の少ない部活で、私たちは共に「はっきりしていて、パワーのある女子」と評価されていた。とにかく人数の少ない部活だったし、更衣室での着替えももちろん一緒だったので、先輩・後輩の別けなく、みんな仲が良かったのだが、この子とは、性格の一致以外にもいろいろ共通点があった。・・・(続きを読む)
2005.01.06
コメント(0)
-
帰国子女という言葉-学校の選択
日本で帰国子女という言葉が知られるようになって久しい。日本以外の場所に親の都合で移り住み、そこで教育を受けて、成人前に帰国した日本人を指すようだが、実はとても曖昧な言葉で、私はあまり好きではない。どこに何歳でどのくらい住んだか、母語(第一言語)として日本語を習得しているか、第二言語を習得しているか、どんな学校教育を受けたか、両親の教育方針はどうだったか、文化の多様性を重んじる環境で育ったか等、、、ひとりひとりが千差万別なので、たったひとつの帰国子女というカテゴリーに放り込むのは如何か、と思いたくなるのである。しかし、帰国子女という言葉が誕生する必然性があった。・・・(続き)
2005.01.05
コメント(0)
-
カテゴリーの効用――文化圏によって異なる「成熟」や「大人」の意味
私自身は、自分が韓国系だから、日本人だから、女性だから、このように行動しようと考えることはしない。けれども、自分のカテゴリーを思い出し、カテゴリーとして自分自身を見つめなおしてみることは、割合に役に立つものだ。カテゴリーとしての自分を考えてみるということは、自己相対化することでもある。「だから男性は」「だから日本人は」「だから韓国人は」……等々。そんなふうにふと思ってしまうことは、もちろん私にもある。・・・
2005.01.04
コメント(0)
-
「固着」に起因する“暴言”には要注意。――その場を離れろ!
来日したくて、来日したアメリカ人男性がいた。彼は日本語を話せたけれど、コミュニケートするのには不十分だった。なまじ流暢な日本語を話すものだから、彼の“失言”は意図的なものだと受け止められた。そのため彼は、日本人と関わっては仲たがいしていた。ある日、とうとう彼はブチ切れ、叫び出した。・・・
2005.01.03
コメント(0)
-
ある「国際」結婚カップルたちの年末の受難
年末になると、「国際」結婚した夫婦たちが険悪になることがある。時に、それは離婚も辞さない状態だ。昨年同様、今年も知り合いたちがてんてこ舞いをしたのであった。このようなことが起きてしまう状況は、限定されているらしい。・・・
2005.01.02
コメント(0)
-
日本人にありがちな言語感覚――「英語ができない劣等感」「二ヶ国語以上できる優越感」
韓国人なら、日本生まれで韓国語ができない「在日」に、「なぜ、親が教えなかったのか?」と言う。――みんな、いろいろ忙しいのだ。日本人なら、日本生まれで韓国語ができない「在日」に、「韓国人の血が流れているのだから話せるはずだ」と言う。――血が話す言語を決定することはない。また日本人は、「親が韓国語を話せれば、子どもも韓国語を話せるはずだ」とも言う。――それを言うなら、むしろ逆だ。・・・
2004.12.21
コメント(0)
-
加齢のありがたみ
私は年齢的に、“もう”中年だ。こう言うと、“もう”という言葉の響きも手伝って、なにか悲惨な感じがするだろう。けれども、私は若い頃よりも、うんと自由だ。元気だし、うんと楽しい。若い頃のように、みじめな私ではないのだ。若い頃。女性の私は、性的対象として見られていた。韓国系であることが、それに拍車をかけていた。モノとして見られていたと言い換えてもいい。不自由で窮屈だった。若い頃。私は、自分と同質の誰かを求めていた。同質の誰かがいないことが原因で、私は孤独だった。女性が生きる大変さとともに、韓国系が生きる大変さを共有できる人はいなかった。若い頃。・・・
2004.12.17
コメント(0)
-
気にし過ぎ?
「じゅうにひとえ」のことを異人種結婚をした海外在住の日本人の親に紹介するとよく言われるのが「自分の生い立ちを気にしすぎなんじゃない?そんなことにとらわれずにもっとのびのびと生きたほうがいいよ。あなたはあなたなんだから。」それを言われると、「この人は『自分』が誰であるかで真剣に悩んだ思春期を雑音に犯されずに自分と向かい合えたんだな。」と羨ましく思う。そして、私にそれは可能だったろうか、とまた思いをはせる。・・・
2004.12.16
コメント(0)
-
故郷のまち
私の母は、今は日本のある町に住んでいる。父の故郷に近い場所なのだが、父はそこに家を建てた後すぐに亡くなってしまった。母はその町の出身ではないが、父の建ててくれたその家に愛着を持って暮らしている。私もその家そのものは好きだ、しかし、私はその町がとても苦手だ。私はそこでは暮らせない。親が根をおろして住む家を実家だとすると、そこは私の現在の実家、でもそれが私の故郷なのだろうか。郷土愛を持つべき場所が自分の故郷だとしたら、私の故郷はどこになるのだろうか?・・・
2004.12.15
コメント(0)
-
見る人 見られる人
ある日、昔の友人に会うために東京都内で待ち合わせをした。表通りから少し離れたおしゃれな感じの広々としたカフェで、天気が良かったので私たちはテラスにあるテーブルについた。友人は、子供を連れてきた。歩きだしたばかりの可愛い女の子だ。私たちが食事を楽しむ間、その子は退屈してテラスをよちよちと歩き回った。しばらくすると人々が注目し始めた。「見て!可愛い!ハーフの赤ちゃんがいるよ!」「ほんとだ。可愛いね。日本人と全然違うね」・・・
2004.12.10
コメント(0)
-
ハーフだったらバイリンガルなのは当たり前?
ある日、日米ブレンドで東京のインターナショナルスクールに通う15歳ぐらいの子と在日何年かのアメリカ人と食事の場で同席することがあった。名前も知らないもの同士、名前と今どこ在住なのか、そしてどこ出身なのかを言う。その子は英語を流暢に話すのに、東京出身の東京在住だと言うので、そのアメリカ人の男性は「じゃあ、インターナショナル・スクールにでも通ってるの?」と聞き、その子は、そうだ、と答えていた。そこで「じゃあ、日本語は?」と聞いた。・・・
2004.12.07
コメント(0)
-
「国際」結婚・越境結婚のメリット
どんな結婚でも、お互いに違うという前提を持っていることは必要だろう。けれども「国際」・越境結婚のメリットとは、あきらかに、違うことを前提として出発する機会に恵まれたことにある。「違うから大変だ」と思えるところから出発できる機会。夫婦の公用語は何か、ではなくて、夫婦の共通言語は何か、という問題。同国人・同系人同士なら、持ちにくい問題意識かもしれない。共通言語を作ろう!という意識をお互いに持てる幸運って、あるものだと思う。コメントはこちらへどうぞ。
2004.12.06
コメント(0)
-
架け橋になんかなるな
私は小学校だか中学校のころだかに、親に「将来は通訳者になりたい」と言ったことがある。周り、特に先生方に「かぐやは将来アメリカと日本の架け橋になるんだな」と言われ続け、それを包括した職業といったら何だろうか・・・と考えた末の結論だった。ところが両親の猛反対にあった。・・・
2004.12.02
コメント(0)
-
大人同士の関係。親子という関係。
「国際」結婚でも越境結婚でもしている仲間に対して言いたいこともあります。私は「国際」結婚や越境結婚している人にありがちのように見えるのは、「国際」なり越境なりの結婚だからだというので、自分にできる以上の我慢をしていることです。まずは自分の生き方を考え直してもいいと思います。「あなたとの結婚生活は修行なので、この分だと死ぬまでに悟りが開けそうです」。そんなことを言われて相手は嬉しいのか。それとも自分は嬉しいのか。こういったことは、なにも「国際」だの越境だのに関係ないことです。ここまでは夫婦の問題であり、大人同士のことなのでむしろどうでもいい。親子の問題のほうが、比べるまでもなく重要です。(続き)
2004.12.01
コメント(0)
-
「悩む」という能力
マイノリティーであることや、またカルチャーショックで悩むというのは、外界に対し、異文化に対し、敏感であるということです。このような才能は誰にでもあるわけではないと私は思います。だから、その悩みが身体症状や精神病になってあらわれたとすれば、素晴らしいっ! でかしたぞ。もちろん万歳三唱です。文化によって悩みがどのような病となって出るかが違うのはもちろんです。現在の日本の十代であれば、ひきこもりは主に息子の、拒食症は主に娘の病です。これらには、アイデンティティーの問題が関わっていることが珍しくない。ひきこもり。拒食症。その他。もちろん大変です。でも、ちゃんと悩んで病気になったのです。偉いぞっ!それ、第三者の介入だ。しっかりしてくれ、第三者役の人たち。ひきこもった息子の、拒食症になった娘の、母親だけを罰するのはやめてくれ。悩める子らの言葉を聞かず、マニュアル通りの理解に熱中するのはやめてくれ。マニュアルはないと困る。けれどもマニュアル通りの人間なんて一人も存在していない。そんな人間は、マニュアルの中にのみ存在するに過ぎないのだから。さあ、病気になれば、あとは治癒の、回復の過程を進むだけ。治癒し、回復した時は、以前と同じその人ではありません。一回りも二回りも成長したその人の登場です。将来は明るいぞお~!コメントはこちらへどうぞ。
2004.11.25
コメント(0)
-
話し合い方―「You」を使わず「I」を使え
どんな種類の人間関係でもすれ違いのない人間関係はないでしょう。その度に話し合うものです。その時の話し合い方は重要なこと。できるだけ「You」を主語にして話さないこと。「あなたが○○人だから~」「お前が悪い」「あなたは~という考え方だから」等々。自分のストーリーを相手に押しつけて従属を強いないこと。私は、自分以外は「隣人」なのだと思っています。「隣人」がどんなストーリーを持っているか、わかるわけがないのです。想像力が大事だとは言えども、想像してわかるなら話し合いは必要ない。わからないから話し合う。どんな人間関係でも同じことだと思います。話し合う時は、できるだけ「I」を主語にして話すこと。「私はいやだ」「俺はこうしたい」「私はこうしてほしい」等々。自分の要求がはっきりしないのに、人にケチをつけてもしかたがない。あるいは自分の要求がはっきりしているなら、それだけ言えばすむ。まずは状態をよく観察すること。次に“私”はどうしたいのか、どのようなことができるか、要求できるか等々、現実に照らし合わせて考えること。そして、実行するにあたって、適切な実行のしかたや時期を考え、それから実行することです。たとえばイギリス人とフランス人が一緒に生活している。 ・・・
2004.11.24
コメント(0)
-
相手をどのように理解するか――他者の人間性を信頼せよ
90年代前半だったでしょうか。私はロンドンとパリを往復していました。ロンドンで飲む紅茶はとても美味しいのに、コーヒーはひどくまずい。パリで飲むカフェ・オレはとても美味しいのに、紅茶はひどくまずい。私は考えました。いや待てよ。私の主観に過ぎないのか、これは。イギリス人はロンドンの紅茶もコーヒーも美味しいと思っているんじゃないか。フランス人はパリのカフェオレも紅茶も美味しいと思っているんじゃないか。このように私が考えようとした背景には、人間は正しいことをしようとしている、言おうとしているものとして、できる限り好意的な姿勢で相手を理解しようとすべきだという信念があります。だからフランス人もイギリス人も正しいことをしようとしているのではないか、とまあ、そのように考えてみたわけです。しかし、これだけではとうとう行き詰まりました。・・・
2004.11.23
コメント(0)
-
抽象的な個人は実在するか――他者に対して好意的であれ
「国籍や民族なんか関係ない。結局は個人だ」。(この場合の国籍は国民文化を指すのでしょう)「性別なんか関係ない。結局は個人だ」。この決まり文句を文字通り受け止めると、「国籍や民族や性別とは無関係な、独立した個人がいる」ということになります。けれども、そのような“抽象的な個人”は実在するのか?“抽象的な個人”とは、法律等々においてのみ存在しているだけです。“抽象的な個人”など実在しない。(続き)
2004.11.22
コメント(0)
-
悩む、ということ
ある友人が言ってたこと。「病気の症状っていうのは万国共通だけど病気の捉われかたは(そもそも病気であるかどうかも含め)文化によって違う」ほほう~~~、なるほどねぇ~。って授業で先生が言ってたことらしいんだが。で、精神病についても同じことが言えると。これについては興味津々。なぜかと言うと、「アイデンティティの悩み」系のことって言うのはある程度、生活が安定していて自分の精神状態のことなんかに気を使ってられる贅沢ものの悩みなのかなぁ・・・(続き)
2004.11.21
コメント(0)
-
あるカップルの話
結婚においての文化の違い、個々の性格の違い、とかそういうものを考えるうえで一番参考になると思うあるカップルの話がある。長年連れ添った夫婦。妻が日本人で夫がアメリカ人。二人ともお互いの母語は話すしお互いの国にも長いこと住んだことがある。今はアメリカ在住だが夫は、妻がそれほど社交好きでもないので妻も誘ってみてから一人でパーティーや社交の場に出て行くと家でアジア人の妻を言いなりにしている、ありがちな白人上位主義の男に見られることがあると不愉快そうに言う。そんな二人がしてくれたある話。夫はもう何年も朝のコーヒーをベッドで飲む習慣にしていた。もちろん自分のための朝のコーヒーは淹れてるけれどもしかして妻もコーヒーを淹れて欲しくても日本人だから、僕がコーヒーを淹れて隣で飲むのを見ててもそう言いだし辛いかもしれない・・・、と思った夫は毎朝「コーヒーは飲む?」と妻に聞くようにしていた。もし考えが変わってコーヒーが飲みたくなったときにも言い出せるように、と。しばらくすると妻がだんだんイライラしてきた様子を察知した夫は怪訝に思いながら妻にどうしたのかと聞いてみると、妻は毎朝コーヒーが欲しいのか聞かれるのが嫌だと言う。・・・
2004.11.16
コメント(0)
全53件 (53件中 1-50件目)