全45件 (45件中 1-45件目)
1
-
「スウィングガールズ」 谷啓までおいしい青春コメディー
「ウォーター・ボーイズ」の矢口史靖監督による、女子高校生ジャズバンド青春映画の登場である。東北の片田舎の高校。補習組のぐーたら落ちこぼれ女子たちは、野球部の応援ブラスバンド用の弁当を届けるべく言われ電車で出発したが、なにぶんいいかげんないまどきの女子高校生の集まり。異様に時間がかかったせいで、それを食べたブラスバンド部員が皆食中毒になるという事件を引き起こしてしまう。 一人難を逃れた男子部員の中村は、お前たちのせいだ、と次の試合までに即席ブラスバンドを作り、応援演奏をしろとつめよる。補習がさぼれるとばかりいい加減な気持ちで参加を決めた補習組女子ときわめて真剣な中村で、人数的に足りるビッグバンドを結成することになるが・・・ こう書くと、ああ、それでちょろちょろっと苦労して、最後には嘘みたいに短期間で上手になって終わりね、と簡単に想像されるかもしれないが、この作品はその期待をいい意味で裏切ってくれる。 いろいろな伏せんが張り巡らされる中で、、補習を逃げられた(?)数学教師竹中直人ももちろん絡んで、イマドキの女子高校生たち(その冒頭の弁当運搬のシーンはあまりのダメ人間ぶりで、見ていて腹が立つほどである)が、紆余曲折しながらも、「自分の力で吹いて」音を出さねばならない管楽器を17人一丸となってプレイするようになるまでを、この映画は「お決まりであってお決まりでない展開」でユーモアたっぷりに見せてくれるのである。単純なようで案外盛りだくさん、それがこの映画のおいしいところなのだ。(ここが、ダメ部員が成長する様を描く点でテーマがかぶる、「ロボコン」とは違う点だろう) また、「ウォーターボーイズ」よりも、その笑いのセンスに磨きがかかっているのも見逃せない。私がここ数年に見た映画で最も笑ったと断言できる「イノシシ」がからむシーンは、あきらかに安い大道具に、最新の画像技術という組み合わせの、あ、っと思わせる手法と、バックグラウンドミュージックとの抜群な相乗効果でまさにスタンディングオベーション(スタンディング大笑いでも良いが)に値する。 この映画のコメディセンスは、とにかく一言で言って、「センスが良い」のだ。ジャズのリズムにのって歩く生徒たちの上でたたかれる布団に、「そんなわけないだろ!」と思わず突っ込むほどの転げ落ち方の高校生・・・そういった小さなユーモアがストーリーの中に組み込まれるテンポの巧妙さ、軽快さは、今までの日本映画にはあまり見出せないものだ。(頭に浮かぶとしたら、岡本喜八監督の「大誘拐」くらいのものか) 以前、「ゲロッパ!」で、井筒監督がハリウッド娯楽を(無意識に?)やろうとして失敗した、と書いたことがあるが、「スィングガールズ」は、むしろ、ハリウッド娯楽とともに育ったからこそ無意識にテンポの良さを身に着けた、という表現が当てはまるかと思う。それは、最近のジャパニーズポップスの若手たちが、明らかにかつての「歌謡界」よりも(メロウさは薄くなったが)リズム感で優れていることと同じであるのかもしれない。 欲を言えば、多少映画としての「感動」が薄いことだろうか。もう少し笑いの前フリ部分を減らし、登場人物たちの内面の葛藤を深く織り込めば、最高に笑えて、最高に感動できて、最高にスィングできる映画になったのに、とだけ辛口で評しておこう。ちなみに、モデルとなったのは兵庫県のこちらの高校。部員が少ないことからビッグバンドに転向、成功を収めている有名ジャズ高校バンドである。また、 「スウィングガールズ」のオフィサルサイトには、映画の登場人物たちのキャラクター紹介が映画を超えて事細かに書き記されているので、すでにご覧の方は必ずチェックのほどを。映画として 8/10コメディとして 9/10俳優たちが練習して演奏するまでになったことをたたえて 10/10
2005.03.25
コメント(83)
-
「シャーク・テイル」 内輪受けのセレブ嗜好映画
かの職人集団 ドリームワークスによるフルCGアニメ。豪華な声優たちのキャスティングで話題を呼んだ作品である。海底に広がる大都会リーフシティ。ここに暮らすオスカー(ウィル・スミス)は「いつかnobodyでなく大物somebodyになるんだ」が口癖の、洗鯨場で働く小さな魚。受付嬢のアンジー(レニー・ゼルウィガー)は、いい加減なところはあるが心優しいオスカーに夢中だし、社長のサイクス(マーティン・スコセッシ)にとっても、眼の上のたんこぶながらなんとなく憎めない存在だ。 一方、サメ・マフィアのドン(ロバート・デ・ニーロ)の次男レニー(ジャック・ブラック)は気が優しくすぎて殺しも出来ず、兄と父親の悩みの種。そんなある日、オスカーとレニーの人生を一変させる出来事が起きる・・・。 上にあげたキャストの他に、オスカーを誘惑する美魚(びぎょ)にアンジェリーナ・ジョリー、クラゲの片割れにボブ・マーレーの息子ジギー・マーレー、ヨボヨボマフィアにピーター・フォーク、など、声優たちはまさに豪華としか言いようが無い。2004年アメリカ公開時、3週連続でボックスオフィスの首位を守り、1億6000万ドルに迫る興収を記録したというのも、この豪華なキャスティング、それぞれの声優を模した魚たちのアニメーション、 乗りのよい音楽、といったものを大大的に宣伝したプロモーションに惹かれて観客が足を運んだからであろう。 映画の中では、ウィルスミス魚やスコセッシ魚、デニーロ鮫が海に置き換えられた人間の街を歩き(泳ぎ?)まわり、随所に「ゴッドファーザー」や「グッドフェローズ」といった映画のパロディなどが散りばめられていたりする。 が、しかし、So what?-だからどうだっていうんだ?と声を上げたくなるのが、この映画である。上にあげた三つ以外には何の魅力も無いのだ。 キャラクターの豪華声優陣とビジュアルの模倣具合はおもしろいが、キャラクターそのものには魅力が無い。上昇志向の強いオスカーは、確かに憎めない奴かもしれないが、いい加減でだらしない嘘つきで、ラストで多少の成長は見せるものの、その過程は極めて短絡的に描かれる。マフィアのドンは息子が「男らしく」ないことを受け入れられないのが、これもきわめて深み無く、受けいるにいたる。合間合間のつじつまがあっていないとか、そういことを言いたいのではない。とにかく、二流テレビアニメ以下の、プロットの薄さなのだ。 もちろんクスっと笑えるシーンもあるが、パロディ系の笑い大元を知らないと笑えないものばかりともいえる。これは、アメリカ人でも100パーセントというわけにはいかない笑いのはずだ。 そして何より疑問に思ったのは、いったいどんな客層をターゲットにした映画なのか、ということだ。お魚が楽しいの~という年代の幼児には良いかもしれないが(しかし、メリハリが少ないし妙に人間臭いのが足を引っ張って、たいていの幼児は匙を投げるはずだ)、もう少し年齢が上の子供には、セリフに微妙なセックスや暴力のニュアンスが多いため、親としてはお勧めできない気分になる。それでは大人が、となると、筋が薄いため、最初は、「へぇ、この魚ウィルにそっくり」で喜べても、徐々に退屈になってくる。 こう考えていくと、この映画で心底楽しめるのは、二つの人種しかいないのではないかと思えるのだ。 ひとつは、セレブ礼賛の庶民たち。セレブが声をやっているというだけで、二時間過ごせる方々である。 そしてもうひとつは、作り手側本人たちだ。私はこの映画を見終わった瞬間に、二つの言葉が思い浮かんだ。「後期のおれたちひょうきん族」と、「とんねるずの生でだらだらいかせて」である。娯楽の作り手がビッグになっていき、その名前だけで視聴者を集めることが出来るようになると、そこに必ずといっていいほど起こる現象がある。視聴者のため、を意識しなくなり、作り手たちの中で「おもしろい」ことを優先して番組を作るようになっていくのだ。その「娯楽」はすでに視聴者のものではなく、作り手たちの「内輪」のものとなる。笑いは「内輪」の中で閉じ、それをみるたいていの視聴者にはさっぱりわからない。「内輪ねた」で回るようになった番組は、精彩を欠き、面白みを失う。 私は「シャーク・テイル」に、この現象が起こっているように思う。ハリウッド内にいる人物(セレブ)には、きっとすべてが「あれあれ!」という感じでおもしろいのだろう。「あいつこの声なんだぜ!」から、「あのセリフあの映画からだぜ!」「この音楽○○の替え歌だぜ!」までだ。一般人で、たとえアメリカ人でも、そのすべてを業界人と同じほど知っていて楽しめる人物は、きっと、少ないはずだ。ましてや、日本人大衆には・・・。 セレブへの憧れとその真実を描こうとしながら(全くの失敗であるが)、セレブに閉じてしまっているこの作品を作ったドリームワークが、「ひょうきん族」や「生ダラ」の二の舞にならないことを、せつにせつに願うのみである。映画として 5/10セレブで回れる人 8/10ハリウッド・アメリカ音楽業界情報通 8/10
2005.03.22
コメント(2)
-
トスカーナの休日
ベストセラー小説、フランシス・メイズの『イタリア・トスカーナの休日』を、「写真家の女たち」のオードリー・ウェルズ監督で映画化したのが、この「トスカーナの休日」(Under the Tuscan Sun)である。 サンフランシスコ。フランシス(ダイアン・レイン)は作家だが、最近は書評で評判を得ていた。が、突然の夫の浮気発覚、離婚。家を明け渡した失意の彼女に、友達のパティは妊娠でいけなくなった「ゲイツアー・トスカーナの旅」をフランシスにプレゼントする。 迷いながらも旅に出たフランシスは運命的なものを感じ、一軒の古い家を購入し、トスカーナにとどまることを決意する・・・。 いわゆる「女性の成長物語」である。しかし、この映画最大の魅力は、その再生の過程でも、もちろん魅力的ではあるものの、ダイアン・レインのかわいい中年女性ぶりでも、また、美しいイタリアの景色でもない。この映画の魅力は、その「気楽さ」にある。 死語となってしまったが、かつて、「カウチポテト」という言葉がはやったことがある。カウチでのんべんだらりとポテトチップスでも食べながらビデオ鑑賞を楽しむ、というあれだ。「トスカーナの休日」は、まさにこの「カウチポテト」にうってつけの「気楽な」映画なのだ。 一人の女性の再生の物語でありながら、その語り口はあくまでも軽快だ。浮気をされた側であるのに家を追い出され、単身者用のアパートに移り住んだフランシスの惨めさはコメディタッチで描かれ、「ゲイ・ツアー」で戸惑う様子もまたおもしろい。そして、トスカーナの美しい景色。随所に出てくる美しいイタリアの田舎の景色は、叙情的でも芸術的でもなく、さらりと、ある意味セットのようなさりげなさで、それでいて登場人物の振る舞いや会話の中でロマンチックに描き出される。じっと胸に響く景色というよりも、あくまでもイタリアらしいロマンを演出するためのイタリア、であるのだ。 登場人物にしてもそうだ。高校時代、友人と「待ち合わせ、イタリア男ならどうやって待つと思うか?」という笑い話をしたことがあるが、右手にジェラート左手にパスタを持って噴水の前に立ち、女が前を通ると「ベニッシモ!プレーゴ!アマコルド!(意味不明)」と口笛を吹いている、と想像したイメージ、そのままのイタリア人が目白押しである。自称フェリーニの知り合いで、いつもジェラートを食べながら現れる女性キャサリンや、くどき文句も名前も典型的なイタリア男のマルチェロ、といった、アメリカ人が、そしてわれわれ日本人が、想像するとおりのイタリア人ばかり登場するのである。 これを紋切り型で深みが無い、ととらえる真面目な視聴者もいるであろう。しかし私は逆に、この、悪く言えば深みのなさが、「気楽に」見れる娯楽映画としての最高の魅力なのではないかと思う。見ている側に自己を深く考えさせたり、心にずしんとのしかかるのではなくて、風がさっと通り過ぎたような、そんな軽妙さ、さわやかさ。ダイアン・レインはこの軽妙さをそこなわない程よいコメディエンヌぶりを発揮している点で、ゴールデン・グローブ賞をとるのも納得である。ちなみに、パティ役のサンドラ・オーは、「アバウト・シュミット」のアレクサンダー・ペイン監督の奥さんである。 軽妙で気楽、濃すぎず重すぎず―単純なアメリカ娯楽映画として、「カウチポテト」でもするか、な気分の女性たちにお勧めしたい一品である。映画として 7,5/10単純お気楽娯楽映画(女性用)として 10/10
2005.03.21
コメント(7)
-
「ビヨンド the シー」 スペイシー監督に才能あり
ビヨンド the シー ~夢見るように歌えば~ スペイシー監督の才能を感じさせるエンターテイメント作品 アカデミー俳優ケヴィン・スペイシーが、製作・監督・主演の3役を努め、一切の吹き替えなしに歌い踊ってみせる、1960年代の大スター、ボビー・ダーリンの生涯の映画化である。 ボビー・ダーリン(ケヴィン・スペイシー)は、自分の人生を映画にしようと考えていた。若いころのアナタを演じるには年をとりすぎなのではないですか、という記者たちの批判をよそに、子役の少年と会話を交わしつつ、「思い出を月光のように」つづっていく。 リウマチ熱で15までの命と宣言されながらも、音楽好きの母親と、シナトラをめざし歌い踊ったブロンクスでの少年時代。歌手としての成功、女優サンドラ・ディー(ケイト・ボズワース)と結婚…。しかし、もちろん、すべての思い出が月光のように美しかったわけではなかった・・・ たとえボビー・ダーリンの名前をご存じなくても、「マック・ザ・ナイフ」(クルト・ヴァイルの「三文オペラ」からのアレンジであるのは意外と知られていない)「ビヨンド・ザ・シー」(最近では、ディズニー映画「ファインディング・ニモ」のエンドクレジット曲として記憶に新しい)を聴いたことのある方は多いかと思う。いや、それとも、サンドラ・ディー位はご存知であろうか。「グリース」で歌われる、"Good bye, Sandra Dee"の、サンドラ・ディーである・・・ボビー・ダーリンは、彼女の夫でもあった。 映画内で10曲以上披露されるケビン・スペイシーの歌の上手さ(踊りは微妙)、ボビー・ダーリンへのなりきり加減についての賛辞は、どのページを見ても見つかるものであるから、ここでは割愛しよう。歌のうまさはとにかく、書くまでも無い。10年構想を暖めながら練習した、というのもさもありなんのできばえである。 さて、実はこの映画のおもしろいところは、その「作り」だ。ボビー・ダーリンが、自伝映画を作っている、という設定で物語りははじまる。若いころのアナタを演じるには年をとりすぎなのではないですか、という記者からのボビーへの質問は、実はケビン本人に実際に言われた批判だったという。そんな質問をさらっとかわし、子役の子供と言葉を交わしながら映画はすすむ。 素晴らしい思い出は歌と踊りでつづられ、そのミュージカル場面は、ブロンクス時代はまるでそのセットや衣装そのまま「ウェストサイド物語」を見るかのようだし、ディーとの恋愛のエピソードは、「ローマの休日」をも意識した「パリのアメリカ人」風である。合間合間に子供との会話や撮影シーンが差し挟まれ、ああ、そうか、映画を作っている設定だったな、と思っているうちに、いつの間にかダーリンの結婚生活などリアルな私生活が描かれ、一時間も見るころには、「映画を作っているという設定」だったことはすっかり忘れてしまうような展開だ。このへんの匙加減、進め加減は、スペイシーの監督としての才能を感じさせる。 女優サンドラ・ディーとの結婚生活のエピソードは、ユーモアも交えて描かれ、最近みた「喧嘩シーン」では、一番のできばえのように思う。笑わせておいて、ケンカの最後では、ほろっとさせる。その辺の描き方も、うまい。 サンドラ・ディー役のケイト・ボズワースの使い方も実に上手である。彼女はそっくり、というわけではないが、雰囲気がそのまま、私たちが想像したとおりのサンドラ・ディーなのだ。その可憐さ、かわいらしさ。当時の風物や実在の人物たちを引き立てる衣装やメイク、セットにも何の手抜かりも無い。 難を言えば、確かにスペイシーが年をとりすぎていて、登場人物たちの年齢がどうも分かりづらいところであるが、(ボビー・ダーリンは38歳で死去)細部まで手を抜かず、構成もよく練りぬかれた作品であるといえよう。 大御所「レイ」の陰に隠れてしまったのが残念だが、(映画の中には、なんとレイ・チャールズについての言及もある。伝記映画が目白押しのハリウッドを意識してのことだろう)ボビー・ダーリンの劇的な人生ともあいまって、歌に踊りに酔い、ドラマに泣け、そしてラストまでスィングを忘れない、素晴らしいエンターテインメント作品だと、太鼓判を押しておこう。そして、歌と踊りばかり取りざたされているスペイシーの監督としてのこれからに、大いに期待したい。 映画として 9/10ボビー・ダーリン=スペイシー 10/10サンドラ・ディー=ボズワース 10/10
2005.03.19
コメント(5)
-
「ゲロッパ!」 井筒監督の深層心理を見た?
数日後に収監されることになったヤクザの組長・羽原(西田敏行)には心残りなことが2つあった。1つは25年前に生き別れた娘かおり(常盤貴子)と再会を果たすこと。そしてもう1つは大ファンであるキング・オブ・ソウル、ジェームス・ブラウンの公演に行くこと。彼の心中を察した弟分・金山(萩原一徳)は子分たちに“いますぐJBをさらいに行って来い”ととんでもない命令を下すのだが・・・。井筒監督といえば、日ごろのマスメディアでの辛口映画評が思い浮かぶ。歯に衣着せぬその言いっぷりは、ならあんたどんな映画を撮るんか、と言いたくなる口ぶりであったが、その、井筒監督の作品である。 正直に言おう。井筒監督は、「かわいいね~」の一言に尽きる。 実はこの映画は、そのストーリー展開、合間に差し挟まれるミュージック・パフォーマンス、テンポといい、まさにハリウッド映画の要素をすべて取り入れているのだ。いつもあんなに辛口を聞かされていたから、こんなにハリウッド映画に影響を受けているとは思わなかった、というのが本音だ。そう、井筒監督はハリウッド映画が好きすぎて、あんなに辛口になっていたのである。(ご本人がこれを認めるかどうかは知らないが) ハリウッド娯楽映画をハリウッド娯楽映画にしている醍醐味といえば、ホロっとさせたり、ハラハラさせたりしながらも失われない、そのウィット、コメディーセンスにある。たとえば、「隣のヒットマン」や「花嫁のパパ」でもいい。ホロっとさせたり、ハラハラさせたりしながらも、いつもウィットと笑える要素を失わないのだ。そして、皆がいつも陽気で明るい。井筒監督は、この醍醐味を、日本映画に入れ込もうとした。 JBを誘拐しようとドタバタとする子分たち、エアロビの先生?をしている元やくざ、かおりを狙う取引先上司のいやらしさ、JBのパフォーマンスをしてみせる組長に、「ブツ」をめぐって繰り広げられるドタバタ活劇・・・そういったパーツが、まるでハリウッド娯楽映画そのものなのだ。パーツを上手くストーリーに組み込んだことは、この映画を先の読めない面白いものにしているし、俳優達も、なかなかいい演技を見せている。もちろん西田に岸辺はどんな演技子お手の物だし、山本太郎他脇を固める役者陣も精一杯小気味よく演じていると思う。娯楽映画としては、まずまず楽しめる仕上がりだろう。が、いかんせん、いくつか残念な点がある。ひとつは、「ハリウッド娯楽映画的」にするのなら、他の点もハリウッド的にするべきだった、という点だ。それは何も、お金を掛けろといっているのではない。この映画のハリウッド的な最大の難点は、その「色」だ。井筒映画にはその独自の色がある。どちらかといえば、砂埃でもかぶったような、もったりとした、ある意味日本的な色だ。これが、力強い描写と重なると、なんともいえない重厚感や迫力を生み出すわけだが、いかんせん、「ゲロッパ」は、娯楽ハリウッド風作品である。 そうなると、このもったり色が、テンポをそぐことになってしまうのだ。もったりとした色合いの中で、テンポのよいパーツが次々と展開しても、垢抜けないのである。衣装・舞台セットといった基本的な色合い―これがもっとビビッドで、気を使ったものであれば、そのビビッドな色が画面をドタバタと動き回ることで、余計にテンポが小気味よく感じられるはずである。ハリウッド映画というのは、その辺までも十分計算し尽くされたものであるのだ。 もう一点は、上と逆説的になるのだが、井筒監督が「ハリウッド風」を、意識的か無意識的か、作り出そうとしていることにある。ハリウッド娯楽のおもしろさがどこにあるかをこれだけ理解している井筒監督なら、日本独特のしっとりと静かな笑いの情感を、上手い具合にあのハリウッド娯楽のもりだくさんなウィットと混合し、消化し、新しいジャパネスク娯楽が作れるのではないか、と思えるのだ。その世界観であれば、井筒監督の独特な「色」もまた味わい深いウィットの一部分となると思えるのである。井筒監督がこれから、そのどちらを選択し、映画を作り続けていくのか―それが気になる、映画であった。最後に、もちろん「ゲロッパ」とは、JBのGet Upの呼び声のカタカナ表記である。(なにをどおやってもそうとしか、聞こえない)映画として 7/10娯楽として 8/10ゲロッパ 10/10
2005.03.17
コメント(0)
-
「アイ, ロボット」
ロボットが人々の生活に溶け込み始めた、西暦2035年シカゴ。新型ロボットの発売を控えたUSロボティック社で、ロボット工学の第一人者ラニング博士が謎の死を遂げる。大のロボット嫌い、スプーナー刑事(ウィル・スミス)は、ラニング博士のホログラムに導かれ、その捜査を担当することになる・・・ 大々的にスポットが流されていたら、映像をご覧になった方もおいだろう。人間風の半透明の顔がついた、すこしロボットらしからぬロボットとウィル・スミスの、派手なアクション・シーンなどだ。これからご覧になる方は自宅で見ることになるだろうから、よほどの大画面TVか、ホームシアターでなければ、この映画をCGの迫力だけで「最高!」と言い切るのは難しいかもしれない。ロボットのデザインをはじめとして派手な爆発シーンといったものも、テレビの画面に音だと、CG臭さが見えすぎてしまうのも、興をそぐ。 が、CGを除いた「アイ、ロボット」には、まだ見所がある。 サスペンスとしても「最高!」というほどではないが、通常の(SFでない)サスペンス映画と同じぐらいのひねりや謎解きはある。いや、逆に、SF映画としてはめずらしく、そこそこヒネリのきいたサスペンス魂を持っている。そして何より、実はそのウィットに富んだセリフに、この映画の魅力はある。脱力系クールガイ、ウィル・スミスと同僚や、さまざまな登場人物とのやり取りは、時にニヤリとおもしろく、また、ああ、うまいこと言うな、と納得させられたりするセリフが多い。案外ウィル・スミス本人のアドリブも入っているのかもしれないが、ストーリーに絡んだところにも垣間見えるウィットは、やはり脚本家アキヴァ・ゴールズマン(実は、彼はかのアカデミー受賞作「ビューティフル・マインド」や「依頼人」の脚本家であり、スピルバーグ製作の芸者映画「SAYURI」の脚本は彼の手による)と、この映画の原案者でもあるジェフ・ヴィンターによるところが大きいのだろう。変に知的ではない小粋さを楽しめるSFとして、推薦しておこう。 ところで、「アイ、ロボット」と聞くと、あのSF文学の巨頭、アイザック・アシモフが1950年に発表した短編集を思い出す人も多いだろうが、この映画はアシモフを映画化したものではまったくない。原作に着想を得た、インスパイア映画(?)の類である。アシモフの「われはロボット」に出てくるロボット三原則、第一条:ロボットは人間に危害を加えてはならない.また,その危険を看過することによって,人間に危害を及ぼしてはならない.第二条:ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない.ただし,あたえられた命令が,第一条に反する場合は,この限りでない.第三条:ロボットは,前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり,自己をまもらなければならない.を大前提としてロボットが活躍する近未来社会をリアルに映像化して見せたことが、同じアシモフからのインスパイア映画「アンドリューNDR114」などのセンチメンタリズムとは違った醍醐味であろう。映画として 7/10サスペンスアクションとして 7.5/10CGの醍醐味 6.8/10以下、結末も含むネタバレがふくまれますので、ご注意ください 実はこの映画は、アシモフのロボット三原則の使い方が悪いと、SFファンたちからは評判が悪いらしい。あの金字塔を全く無視した展開だ、というのがその理由だ。なんといっても、映画ではアシモフを題材にとっているにもかかわらず、人間の危害を与えるはずのないロボットが、バンバン危害を与えまくる。しかも、この三原則をプログラムされていないロボットまで登場するのだ。アシモフにインスパイアされながら、全くそれを反対に使っているというのが、酷評の理由のひとつだろう。 しかし、あるいは私には、この映画はあの金字塔をしっかりとベースに映像化した上で、そこに新しい物語を作ったところを、評価するべきではないかと思うのだ。それはいわゆる「やおい」に近い発想である。大好きだからこそ、それをベースに新しい物語を作ったのだ。私たちが子供のころ、読んだ本や漫画の世界を、床で夢想したように、である。その原作への愛は、侮辱ではなく、限りなく純粋な愛であるように思う。そもそも、「アイ、ロボット」なんてタイトルなしで、ロボット三原則も引用することなしに、凶暴なロボットが出現する未来社会を描く映画であっても、全く良かったのだから。 主人公?のロボットサニーが、いわゆる救世主としてロボット世界を切り開くであろう、というラストもまたさわやかだ。ロボットと一騒動あった後の、「人間が完全にロボットを淘汰する社会」で終わるのではなく、ロボットによるロボットのための平和社会が示唆されているラストはなかなか新しい視点だなと思わされた。 予告編を見たときは、つまらない三文映画なのではないかと思っていたが、そのウィットと、原作への子供心を忘れない愛情に、評価を置いてあげたい作品であった。
2005.03.15
コメント(4)
-
CODE46
「ひかりのまち」のマイケル・ウィンターボトム監督の2003年度作品である。 近未来、上海。ウィリアム(ティム・ロビンス)は、パペルと呼ばれる都市間通行許可証の偽造事件の調査に訪れた先で、マリア(サマンサ・モートン)に出会う。出会った瞬間から彼女に惹かれるウィリアム。そして、二人の運命がつながり、新たな人生がはじまる・・・ この映画に関して何よりもまず賞賛せねばならないのは、ウィンターボトムの映し出す「近未来」だ。それは、SFXを多用することによって未来を描く現代のハリウッド映画の多くへのアンティテーゼともいえる。彼自身ゴダールの白黒SF作品「アルファビル」のような近未来を描きたいと語っていたとおり、上海という(監督にとっての)異空間の中に「未来」を見出し、そこを切り取り、そして監督独特のビビッドでありながら澄んだ色彩を、流れる光を取り込むことによって、まるでSFXで描かれたのと同じ色合いの近未来を映像化してみせる。 遺伝子操作が可能な未来に普通車が走っている―といった点を、SF好きの観客は不満たっぷりにつついてみせるかもしれない。しかし、逆に、普通車が走っているフツウの現代を、何のSFXも無しに未来のように映し出してみせた、という監督の手腕を賞賛してほしい。そしてなにより、現代で近未来を描き、近未来で現代を描くというこのトリックに浸ってほしい・・というのが私の言い分である。 ストーリーに対しても同様だ。それを通常のSFとして「つじつまを合わせて」考えていくと、しっくりとはいかないだろう。しかし、これを人類の大きな寓話と考えれば、また、その悲しいラブストーリーの叙情にだけでもひたっていただければ、それだけでもこの映画の真価はわかってもらえるのではないだろうか。これからご覧になる方には、「SFサスペンスラブロマンスー!」というレッテルだけははらずに、どちらかといえば現代美術を鑑賞するような心持で見ていただきたいといっておこう。以下結末も含めてネタバレがふくまれます。ご注意ください。 CODE46とは、同一、または高いパーセンテージで重なる遺伝子を持つ男女の生殖行為を禁じる法律である。クローンが日常となった世界では、確かにありうる話である。 この映画の世界では、人々は「内」とよばれる都市部に密集して暮らし、「外」は砂漠化し、同時にさまざまな伝染病がはびこる世界である。都市間移動の許可証パペルは厳しい審査のうえでのみ発行され、発行されないのにはかならず「理由がある」といわれるほどの代物だ。 マリアとウィリアムは、遺伝子上では親子に当たる存在でありながら、生殖行為を行ってしまう。一度目は、避けがたいほどマリアに魅力を感じたウィリアムと、夢で彼を運命だと感じたマリアという間柄で。そして二度目は、おそらく消しきれなかった愛の記憶に突き動かされるマリアと、遺伝子上の母と知りながらその願いを聞き入れる、ウィリアムの間で。マリアの記憶も、ウィリアムの記憶も、それは消され、書き換えられ、それでもなおかつ彼らは互いを探し、愛し合う。愛の記憶は、繰り返され、消され、繰り返され、そして永遠に続く。それがCODE46であろうと、だ。 そもそもわれわれは元はアフリカの一人のイブではなかったか。イブと、その息子ではなかったのか。 現代に生きるわれわれすべてが彼女の子孫であるなら、私たちは皆、マリアとウィリアムの二人のように、親子であり、また兄弟であるのだ。私たちはその中で、引き裂かれ、出会い、愛し合い、死ぬ。そしてまた繰り返し、繰り返し出会い、愛し合う。新しい記憶を持って、新しい場所で、新しい体で、私たちは生まれ変わり、愛し合う。マリアとウィリアムは、私たちを二人に集約したにすぎない。古典「オイディプス」(知らずに父親を殺し母親を娶るも、後に悟り眼をつぶして荒野へ出る、永遠のさまよえる人間像である)で荒野へと出るのは男オイディプスであり、残されるのは母親であるが、この映画では、「内」へと戻っていくのはウィリアムであり、「外」の荒野をさまようのは女性であるマリアのほうだ。偽のパペルを渡したことで死ぬにいたった友人を幸せと言い、「内」から「外」に戻ることを夢に見る彼女は、記憶を抹消されながらでも人の手による社会には制御不能な存在である―そんな最初の一人の「女」、マリア=イブが、荒野で「あなたに会いたい」とつぶやくとき、私たちはまた生の営みをはじめからたどり、くりかえすのである。映画として 7/10映像作品として 8.5/10追記:あちこちで、サマンサ・モートンはよかったがティム・ロビンスがミスキャストという声が聞かれた。しかし、この二人が並んだ場面を見てみてほしい。二人の身長の差の大きさ―モートンが小柄なため二人は父親と娘のように背が違うが、実際はその間柄は逆である。これが母親と息子との永遠のラブストーリーであるなら、そして私たちの愛がイブとその息子から永遠に続いているなら、この「身長差」は明らかに監督の意図したものといわざるを得ない。 ちなみにティム演じるウィリアムの妻役の女優は非常に背の高い役者を選んでいること(ティム・ロビンスは相当な長身であるので、それに並ぶ女優を探すのはたとえ西洋でも難しいことである)も、これを裏付けているように私は思う。
2005.03.10
コメント(2)
-
「砂と霧の家」 アメリカが砂の国を覆い尽くす
House of Sand and Fog アンドレ・デュバス三世原作による、ひとつの家を巡る物語である。 キャシー(ジェニファー・コネリー)は、夫が出て行った精神的ショックからうつ状態に陥り郵便物を放置した結果、ささいな税金滞納で亡き父の唯一の財産を郡から差し押さえられ、競売に掛けられてしまう。 物件を手に入れたのは、イランからの政治亡命者、ベリーニ(ベン・キングスレー)。軍の幹部であった祖国での暮らしを捨てきれない妻と思春期の息子のために、家族に隠れて昼夜肉体労働をしている彼は、この昔持っていた別荘に似た家を元手に、転売で資金を得ようと考えていた。 ひとつの家に、二人の思いが交差したそのとき、悲劇のストーリーが始まった・・。 舞台はサンフランシスコ、そう、霧のサンフランシスコ、である。キャシーはそこで生まれ育った。一方、ベリーニはイランからの亡命者である―その祖国は砂の国、だ。霧は、キャシーを、そしてアメリカを意味し、砂は、ベリーニを、そしてアメリカの他の国(それはアメリカが侵攻し続ける砂の土地といえるかもしれない)を意味する。霧と砂の家とは、キャシーとベリーニの家であり、そしてそのどちらも、くずれやすくもろいのだ。以下批評となりますので、ネタバレがふくまれます。また、ストーリーの結末も含まれますので、ご注意ください。「霧」であるキャシーはアルコール中毒で、精神が不安定であり、夫に捨てられ、家を失った傷を、他人の夫で、そしてアルコールで癒そうとする。彼女の家への執着もまた、父親への思い出のみならず、離れて暮らす母親へ事実を話すことが出来ないという「事実」を隠そうとする結果でもある。彼女は実体のない「霧」の中で自分を保とうとする。それは彼女がいつもタバコの煙の向こうで話をすることにも、あらわれている。彼女が「家」を訪れるとき―そこには深い「霧」がたちこめているのだ。「砂」であるベリーニは、日雇い労働の中で「砂」にまみれながらも、それを駐車場のトイレで洗い流すと、スーツを着て我が家に戻るーという生活を送っている。妻はイラン時代と同じ暮らしを送ろうとし、彼もまたそれを支えようとするが、嘘の上に成り立った家庭は、足元から崩れていく海岸の「砂」の城のようなものだ。妻を承諾させ、かつて持っていたビーチ沿いの別荘に良く似た家を安く手に入れ転売することで資金を得ようとするその発想自体も「砂」のようにもろく、景気の動向もあり上手くいかない。 郡から家の返還命令が来ていることも家族に隠す彼の「砂」の「家」に飾られるのは、「砂」の国での要人たちとの写真だ。アメリカに住みながら、アメリカに暮らしていない―それがベリーニである。 互いが互いの理由のためにひとつの家に執着するとき、そしてその「理由」がどちらも実体のない、もろくくずれやすいものであるとき、失われるのは、本当に大切な「実体」、魂の家たる「血肉」である。そしてこの映画では、本当に失われる「血肉」は、ベリーニ側だ。 失われる瞬間になって初めてベリーニは「砂」よりも「血肉」が大事であることに気づくが、時はすでに遅い。そしてもっとも大切なものを失った彼は、妻も、そして彼自身も「砂」のまま死ぬことを選ぶのである。なぜなら彼の生きる世界にはもう、本当に大切な「家=血肉=家族」はいないからだ。 一方最後の一連の悲劇をひきおこす原因は不安定なキャシーの言動にある。キャシーの「霧」はベリーニ一家を覆いつくし、そして結局は彼らを皆破滅させてしまうのである。ラストシーンで遺体を引き取りに来た警察に「あなたの家ですか?」と聞かれた彼女は、「いいえ」と応える。彼女の涙とも言える雨の中で、けれどいつものようにタバコの煙の向こうで。 これは、実体のないものに突き動かされる二組の現代人たちの話であるのと同時に、アメリカのマジョリティーたちとマイノリティー(移民たち)の寓話のようにも私には思える。 弁護士事務所でベリーニが見かける差別に関するポスターや、キャシーの恋人の副保安官による移民に対する暴言や偏見、そういったものがしっかりと描きこまれているからだ。 典型的なアメリカ白人であるキャシーと、政治難民であり、アメリカに馴染めない存在であるベリーニ一家。そのベリーニ一家はキャシーというアメリカの「霧」におおわれて破滅してしまう。双方が納得のいく方法もあったのに、そうはならないのだ。※1 ひとつの「家」をマジョリティーとマイノリティー(しかも「砂」の国からきたというのもまた示唆的だ)がとりあい、法がからみ、銃が絡み、そしてマイノリティーが破滅する。その破滅を引き起こしたのを目の当たりにして初めて、「私の家ではありません」というキャシーは本当に何かを悟ったのか―彼女のタバコの「霧」の中では、その答えは謎のままだというほかないのである。映画として 10/10 (原作の意図を非常に上手く抽出し映像化していると思われる)演技 10/10※1納得のいく解決策をつぶしてしまうのは、直接的に保安官が脅しに使う「銃」であることは、興味深い。映画の中には「銃を使うものは弱者だ」というセリフまである。
2005.03.07
コメント(4)
-
オペラ座の怪人 (フツウのレビュー)
意外なことだが、アンドリュー・ロイド・ウェバーが「オペラ座の怪人」を映画化しようと思い立ったのは、そのブロードウェイ初演のときからだったという。ジョエル・シューマッカーに声をかけたものの、当時のウェーバーのパートナー、「オペラ座の怪人」の初代クリスティーヌであったかのサラ・ブライトマンとのごたごたによって頓挫、中断。それが15年のときを経てやっと結実したのが今回の映画化であった。 「吹き替えなし」という前情報以外出演者などをまったく知らずに映画館入りした私は、そのキャストの多彩さにまず驚いた。クリスティーヌは、「ミスティック・リバー」でショーン・ペンの娘役を演じた少女であるし、ファントムはどうも「ドラキュリア」、だし、キンキン声のプリマ・カルロッタは「グッド・ウィル・ハンティング」のミニー・ドライヴァーだし、マダム・ジリーは「スリーピー・ホロー」の悪役奥様でおなじみのミランダ・リチャードソンだし・・・。「きっと、歌も演技も一枚上手の舞台俳優たちを使って映画を作ったのであろう」という私の想像を、見事に裏切った配役だったのだ。 ふたを開けてみれば、クリスティーヌ役のエミー・ロッサムは実は幼少のころからメトロポリタンオペラに出演しており、演技だけで終わらせるのがもったいないほどの人材であったようだ。 ラウル役のパトリック・ウィルソンはもともと舞台の出だからそつなつこなすとして、ジェラルド・バトラーはすこしばかりだみ声ながら、それを上手に生かしたテノールで歌い上げるし、ましてやミランダ・リチャードソンの歌声まで聴くことになるとは・・。 が、キンキン声がすごいな、と思っていたミニー・ドライヴァーの歌だけは葺き替えであるらしい。しかしラストに流れるポップス曲を歌っているのが彼女なことを考えると、キンキン声くらいだせたのではないか、とも思ったのだが。 彼らの歌唱力、演技力、ダンス。そのどれをとっても、文句の付け所のない出来である。 そして、それをひきたてる、本物のオペラ・ガルニエよりも数段まがまがしく、絢爛豪華なセットと、「エリザベス」も手がけたアレキサンドラ・バーンのモダンで斬新でありながらロマンチックな衣装。また、「マスカレード」で見ることの出来る、美しく迫力のあるッダンサーたちの踊り。 舞台でミュージカルをみるのとはまた違う、きらびやかさ、豪勢さといったものがこの映画の要となっていることは間違いない。 ストーリーとしては、ビデオでみても差し支えはないのかもしれないが、「絢爛豪華さ」だけは映画館で見ないと失われてしまうから、やはり映画観で見ていただきたい作品である。 最後に、ひとつだけ。それは、ちまたでも言われているが、字幕のぞんざいさである。戸田奈津子さんの訳は、超訳の域であるのはもう仕方がないとしても、今回は特に「超・超訳」であったかに思う。 歌が前面に出ているから仕方がないにしろ、できればもう少し、ストーリー性を考えてつけてほしかった。ファントム・フリークでない私ですらそう思うのだから、ファンはそれはご立腹であろうと思う。いつかのビデオ化の際には、ぜひどうにかならないかと思うしだいである。追記:歌は少しだけならここで数曲聴ける。歌詞はこちらで。なんかあのへん変じゃなかった?と思うところがあれば、確認していただきたい。映画として 7/10絢爛豪華ミュージカルとして10/10ストーリー性 6/10ドラマチック性 8/10
2005.03.04
コメント(6)
-
「オペラ座の怪人」 エロスとアガペー
1870年代パリ、オペラ座。プリマドンナのカルロッタ(ミニー・ドライヴァー)に幕が落ちてきたりと奇怪な事件が続くのに腹を立てた彼女が降板。代役は「秘密の先生」に歌の指導を受けたというバレエダンサーのクリスティーヌ(エミー・ロッサム)となった。その彼女を見つめていたのは、実は幼馴染のラウル子爵(パトリック・ウィルソン)。しかしもう一人、彼女をその黒い目で見つめるものがいた。彼こそがファントム・オブ・ジ・オペラ(ジェラルド・バトラー)・・・・ いわずと知れた大話題作、「オペラ座の怪人」である。実は筆者はNYでも日本でもチケットが取れず、この舞台を一度も目にした事が無い。そのため、舞台との比較といったものはできないことを最初にお断りしておきたいと思う。しかし同時に先入観・思い入れといったものも無縁であるから、この映画を、単純に芸術作品として評価できるのではないかと思う。 さて、知り合いに「小学三年生の息子ともう四回も映画を見に行った」という怪人フリークがいる。私はこの映画を見て真っ先にこう感じた-「これはけっして子供には見せるべき映画ではない、ましてや繰り返しなど!」それは、あまりにも「官能的」だからだ。 そもそも「オペラ座の怪人」というのは、ガストン・ルルーの原作では、ゴシック色の強い推理物(エドガー・アラン・ポーなどがそうだ)といういでたちで、後半はオペラ座の怪の謎解き、といったつくりであったように思う。が、ミュージカルは「愛の物語」だけを抽出し、そこに色を加えた-その色が、「官能」であることを、私は今回初めて知ったのである。そしてこの映画は、その「官能」を、よりひきたてるように演出してあるのだ。 三島由紀夫の「音楽」という小品がある。妻が「音楽が聞こえないんです」と男が精神科医のところを訪れる話だが、それはそのまま性の隠喩だ。最後には「音楽が聞こえるようになりました、ありがとうございました」とストーリーは閉じるのだが、これで夫と妻が性(すなわち生の、でもある)の喜びを知った、ということを現している。では、「オペラ座の怪人」はどうだろう。Silently the senses abandon their defences . . .Slowly, gently night unfurls its splendour . . . 翻訳には思い入れのある方もいるようなので、あえて訳はつけずに置く。しかし、初めてファントムの元に連れてこられたクリスティーンにささやかれる歌Music of the Night は、まさに「音楽」そのままの歌なのだ。Purge your thoughts of the life you knew before!Open up your mind, let your fantasies unwind, in this darkness which you know you cannot fight -the darkness of the music of the night . . ..君の今まで知らなかったこの「夜の世界」で「音楽」を紡ごう、といういわばプロポーズを繰り返すこの歌詞は、実に官能的で扇情的だ。そしてその歌詞を裏付けるべく、どちらかといえば清純な感じのクリスティーンがいつのまにかアイメイクの強い夜の顔に変貌していて、太もものガーターベルトもあらわに小船を降りると、うっとりと怪人に身を任せ唇を開く。その後ろの幕の後ろには下着姿にガーターベルトをつけたクリスティーンの木彫りの像が隠されている・・・・また、後半においてファントムとクリスティーンで歌われるThe Point of No Return も、上の歌を受けてのより官能的な歌だ。no second thoughts, you've decided, decided . . .Past the point of no return -no backward glances:the games we've played till now are at an end . . .no use resisting: abandon thought, and let the dream descend . . .私に、夢に身を任せよ、と歌うファントムと、絡み合いながら袖を落とし肩をあらわに歌うクリスティーンは、やはり最高にセクシーに演出されている。クリスティーンはこの、官能的なファントムの「夜の音楽」とラウルの純粋な愛情の狭間で揺れる。ファントムがストーカー的であるとか(笑)クリスティーンが尻軽に思えるとか(笑)、そんな声を映画以前から聞いたこともあった(※私の意見ではありません)。 しかし、生身の女性=クリスティーンが、いわば「夜の愛」と「昼の愛」―夜の愛は実は一方的な所有によるエロス愛(=パッション・受難の意でもある)であり、昼の愛は互いに必要としあうアガペー愛である―の狭間で揺れているのだ、と思えば、そしてファントムが男性の願望を背負った存在であると思えば(自分好みの女性を育てるというそれは光源氏と育ての娘紫の上を髣髴とさせる―しかしこの二人は最終的には結ばれることを考えれば、ファントムはあまりに哀れでもある)、そういった見方も薄まるかもしれない。 そして同時に、これが作曲家(演出家でもよい・ロイド=ウェーバー本人でも)と、彼が手塩にかけた歌姫との物語だと単純化してもいい。歌姫はその一曲でスターダムにのしあがり、そして作曲家の手を離れ、時の人となり、誰か他の者の歌姫となってしまうのである・・・。 芸術作品として、その「美」ではなく内容に関して私が言えるのはこれくらいしかない。明日はその美しさ、出演人の素晴らしさについて語ろうと思う。
2005.03.01
コメント(3)
-
モナリザ・スマイル 女性必見の好感度映画
ヒラリー・クリントンの自伝に記されたアメリカの名門女子大ウィズリー校での話しをもとに、ジュリア・ロバーツ、キルスティン・ダンストといった有力キャストで描かれる、先駆的な美術講師と、生徒達の心の交流の物語である。1953年、東部の名門女子大学ウィズリー校に、カリフォルニアから一人の若い女性美術講師が赴任する。キャサリン・ワトソン(ジュリア・ロバーツ)、UCLAで学んだ彼女は、志願してウィズリーに来たと言う。 生徒達(キルスティン・ダンスト、マギー・ギレンホール他)は、最高レベルの教育環境の中で学ぶ優秀なものたちであるが、その一方で、「大学を卒業した後はすぐに結婚をし、夫に尽くすのが女たるもの」という保守的な考え方の中で、自らの才能を開花させる事の無い人生を送ろうとしていた。キャサリンはその静かなたたずまいながら、そんな彼女たちに、美術を通して新しい道を教えようとするのだが…。「モナリザ・スマイル」というタイトルは、「モナリザは微笑んでいるけれど、本当に幸せだったの?」という劇中の問いかけから来ている。 1950年代は、アットホームな家庭を舞台にしたコメディ「アイ・ラブ・ルーシー」が放映され、郊外型の住宅が次々と建てられた時代である。同時に、訪問販売やスーパー形式のストアなどが台頭しはじめた時代もあり、女性達は、郊外型住宅によって社会と孤立し、同時に、大量消費をすすめるテレビや雑誌広告で描かれる「理想的な女性像」(当時はいわゆる家電が売りに出され始めた頃でもある)に憧れ、縛られていた時代であった。夫と子供のために尽くし、素晴らしい家庭を作ることこそが女のつとめ-その価値感が主流の中では、名門女子大で最高峰の教育を受けた生徒達に必要とされるのは「夫の上司が家に来た時の応対の仕方」であり、卒業と同時に結婚、出産する事であった。 実は筆者はこのウィズリー大の姉妹校の出身である。映画を見ながら、「母校と教育方針が似ているなぁ」と思っていたら(姉妹校がヒラリーの出身校であることは知っていたが、校名を覚えていなかったのである)なんのことはない、系列校であった。母校の学部や院を卒業してすぐに結婚していったクラスメイトたちをふと、思い起こさせる登場人物たちもいた-リッチな一家出身の才女で在学中にいち早く結婚しながら、プライドと押し付けられた女性像の狭間で苦悩するベティ(ダンスト)や、イエールの法学部に合格を果たしながら婚約者との間で悩むもの、「理想とされる女性像」を追い求めないがために男性の欲望の対象となって「ふしだら」のレッテルを貼られてしまうもの・・・押さえつけられた小さな空間の中で、快活な若さを、ぬきんでた知性を、縛り押し殺して生きていたのだ。 ジュリア演じる美術教師キャサリンは、現代美術を彼女たちに見せることで、「価値観」というものが実は「時代によって作られた」ものにしかすぎず「真実」は別にあること、そして、ポロックに代表されるアクションペインティングから、生きることの躍動と自由を生徒たちに教えようとする。このへんの作品のテーマと絵画の絡ませ方は、モナリザからゴッホ、現代広告にいたるまで非常に巧みである。 また、キャサリンが動というよりもむしろ静の教師であり、彼女が学校全体をすべてを変えてしまいハッピーエンド、という終わり方を見せないのもハリウッドらしからず、大変好感が持てる。生徒がキャサリンを通じて、女性でも「選択」があることを知ると同時に、キャサリン本人もそれを学び、成長する。主人公が「全てを改革する熱血漢」といった通り一辺倒な女性像でないのが、この映画をもっとも、そして主演のジュリア・ロバーツをもっとも魅力的にしているといえるだろう。 地味な作品で、カメラアングルやカットが多少テレビドラマくさい安っぽさを持っているのは否めないが、よく練られた小品として、特に女性にお勧めしたい一品である。そう、これはなにも、1950年代アメリカでの話とは限らないのだから。映画として 7/10ジュリア・ロバーツ 9/10キルスティン・ダンスト他若手女優 10/10
2005.02.26
コメント(4)
-
「呪怨」日本版-ライミの心を捉えたもの
怪物と戦うものは、その過程で自分も怪物とならないよう気をつけねばならない。深淵を覗き込むときその深淵もこちらをみつめているのである。-ニーチェ サム・ライミがほれ込んで清水監督本人にメガホンを取らせリメイクした「呪怨」-サム・ライミの心を捉えたものはなんだったのか、と考えをはせながら、テレビ放映版を見た。合間にCMをはさむこともあって、ホラー映画的な怖さは半減したが、何が日本人の心を捉え、サム・ライミの心を捉えたのかが見えたような気がした。「呪怨」にはストーリー的なアラは多いけれど、確実に貫いているテーマがある。それは、「覗くこと」と恐怖の関係だ。 主人公のリカはボランティアに来て聞いた物音で、(わざわざ上がっていく必要すらないにもかかわらず)二階を覗いてしまう。そこに住んでいた家族の妻は、二階を、そして押入れを覗いてしまい死んだ。夫勝也の妹は、ドアののぞき穴から兄の姿(を借りた怨霊)を覗き、布団の中を覗いて恐怖を呼び込むし、リカはラストで、指の隙間から覗くことで、すべての恐怖を理解してしまう。閉じられている何かを、見ずに済まされる何かを「覗くこと」-それが恐怖の基本概念なのだ。※1 それは私たちが子供のころホラー映画を見るときに、そしてお化け屋敷に入るときにかならずといっていいほどやっていたことだ。両手で顔を覆い隠し、さも「怖くて見たくない」という様を呈しながら、指の隙間から薄目を開けて見ている、あれである。 恐ろしいと思っているのに、わざわざ覗いてしまう。それは、私たちが猟奇殺人の本やサイトを見てしまったり、オカルト番組をからかい半分に見てしまったりするのと、本質的には同じことだ。 この映画はまた、私たちが指の隙間から覗いているときに、「かれら」もまたこちらを覗いていることをも描いている。ドアの覗き穴からまっすぐに見据える勝也=悪霊、階段の上の手すりの隙間から下を覗き込むトシオ・・・そして恐怖が「覗くこと」で実態を表すことを理解したリカの下に、「かれら」は降りてくるのだ。怪物と戦うものは、その過程で自分も怪物とならないよう気をつけねばならない。深淵を覗き込むときその深淵もこちらをみつめているのである。 これはケスラーの「快楽殺人の心理」にも引用された有名な言葉であるが、リカはまさにこの禁忌を犯し、降りてきた彼らに摂り殺されることで、彼女もまた「かれら」の一人と成り果てるのである。 おわかりだろうか。これは、決してなにかオカルト的な物語というだけでは終わらない。私たちが「猟奇殺人サイト」を見て「怖いね」といっているそのとき、「惨い死体」を見ているそのとき、その恐怖もまたこちらを覗いているのだ。その恐怖は猟奇殺人者その人であり、われわれの心の中の闇の深淵でもあり、死や痛みそのものでもある。「かれら」の方がわれわれを覗いているのだ。 この覗くこと、からの恐怖感というある意味恐怖の真髄のようなものが描かれていることに、ライミは反応したのではないか・・と思いつつ、もうひとつ「アメリカ的な」ホラー要素にも思い当たった。それは、映画を声を上げながら、ポップコーンを投げつつ見る、アメリカ人特有のお祭り的ホラー映画の見方である。ジェイソンしかり、フレディしかり、テキサスチェーンソーしかり。アメリカ人は、静かに息を凝らしてみるだけではない。「ほら!うしろ!そこにいる!そこ!そこ!いっちゃだめ!あーー!!」 急に出てきてドッキリ、やじわじわ恐怖をもリあげるタイプでなく、観客にはわかっているのに主人公にはわかっていない、思わず声が出てしまう!というアレである。日本版「呪怨」はまさにこの多様であった。鏡やガラス、エレベーターの外にうつる悪霊の姿を、日本人はただ固唾を呑んで見つめるだろうけれど、アメリカ人なら間違いなく「オーノー!イッツカミング!」と声を上げるに違いない。それは最近のアメリカホラー映画では見かけなかった、(じわじわ型やドッキリ型が多いように思う)ホラー映画(しかも、B級の、もしかしたら懐かしき80年代ホラーかもしれない)の基本形である。ライミはその懐かしい基本形を、そこに見たのではないか。 「覗くこと」から来る本質的な恐怖と、何か懐かしさを覚える白塗りで「そこ!そこ!」な登場の仕方を見せる怨霊。その二つがライミの心をわしづかみにしたに違いない-そんなことを考えた二時間であった。そしてライミのエッセンスを取り入れ、あの白塗りをよりリアルにしたであろう特殊効果で作り直されたハリウッド版「呪怨」が、ますます見たくなったのである。※1 ライミ映画では「閉じられたものを開くこと」というのがやはり恐怖の一様式として定着している気がする。それは「覗く」ということと、同一視できるように思われる。
2005.02.23
コメント(4)
-
「ステップフォード・ワイフ」 ヨーダの送る豪華「コメディ」
「ステップフォード・ワイフ」 ヨーダの送る豪華「コメディ」「ステップフォードワイフ」は、ニコール・キッドマン、クリストファー・ウォーケン、マシュー・ブロドリック、ベッド・ミドラー、そしてグレン・クロース、と主役級をまさに豪華にそろえた新作映画。 原作は、かの「ローズマリーの赤ちゃん」のアイラ・レヴィンによるもの。本国ではテレビ化、続編化されたこともあるらしく、なにかしら「アメリカ」の心を捉えるものであるらしい。 どうも日本では「サスペンス」として宣伝をしているような気がするのだが、前評判を全く知らずに見た私からのジャンルわけは、あきらかなる「コメディ」であるとここで明記しておく。 ストーリーは・・・ ジョアンナ(キッドマン)はテレビ会社の重役であり、人気番組のホステスも務めるいわゆる「仕事の出来るいい女」。ところがそのえげつないやり方が出演者の殺意をあおり、公開録画で殺されかける羽目に。 この出来事で職を追われたジョアンナは、夫(ブロドリック)や子供たちとコネチカットの美しい郊外町ステップフォードに引っ越してきた。そこにはその町を取り仕切るてきぱきとした中年女性(クロース)と、街の男性たちの「クラブ」のドンを勤めるその夫(ウォーケン)、そして、皆一様に美しいが、精気にかける「妻たち」がいた。 ウーマンリブ作家(ベッド・ミドラー)とともに、どうにかその町になじもうとするジョアンナなのだが・・。 「永遠に美しく」(ゴールディー・ホーン&メリル・ストリープ)をご覧になった方がいるだろうか。テレビで繰り返し放映されているから、見た方も多いと思う。 さて、「永遠に美しく」、当時としては度肝を抜いたあのSFXはおいておいて、あなたは、ストーリー的に楽しめる人でしたか?私は大好きな映画なのですが、あの、「ちょっとブラックはいったコメディーだよね、でもなんだかくだんないような、もしかしたら俳優がいいからどうにかなってんじゃない?いやでも、豪華俳優陣がこういうアホな話やるのって、楽しいよね」なノリ(説明長くてすんまそん)、これを楽しめるあなたなら、映画館に行くか否かは別として、きっと楽しめる映画。それが「ステップ・フォードワイフ」です。逆に、この「あの豪華俳優でこんな映画?!」的な楽しみが出来ない人には、ちっとも喜べない映画であることも、しっかりとつけくわえておきましょう。 ですがですが、やはりなんといっても俳優陣がとてつもなく豪華!「運命の逆転」で昏睡していても演技が上手だったグレン・クロースが、「101」ばりの怪演ぶりだし、主役のキッドマンは細くてながぁい体と手足をジタバタと動かし、髪を黒髪に染めての登場だし、ベッド・ミドラーはさすが彼女!と思わせるコメディエンヌぶりをいかんなく発揮するし、とにかく「ちょっとおふざけ入ったストーリー展開」の中で見せる俳優陣のおちゃらけぶり、なりきりぶりは見事の一言。年をとってもやっぱり胡散臭い男NO1のウォーケンや、オロオロさせたら右に出るものがいないブロドリックなども、なかなかの配役。 ただ、本当は、「ジョン・キューザックとジョーン・キューザック姉妹」(「マルコビッチの穴」と「アダムスファミリー2」の看護婦の姉弟)が出るはずだったらしいけど、ちょっとした騒動で降板したという話を聞くと、多少残念だけどね。この二人、だって実力派うさんくさくさ姉弟だもん・・ ストーリーはいたってシンプル。「ステップフォードの妻たちには秘密がある」んです。 さて、監督は「スター・ウォーズ」のマスター・ヨーダのマペット師、「ダーククリスタル」が基本形で、最近では「スコア」なんか撮ってどーしたん?と思ってたフランク・オズ。 しかししかし、この映画最高のおふざけは、まさにこのストーリーを、かの伝説のマペット師、フランク・オズが自ら選び、メガホンをとっていること。この映画最高の「しかけ」は何か?それを、是非ぜひ、楽しんでやってください。結論でも、映画館で絶対に見てねー!!!!!というほどではない。のでレンタルになるのを待ちましょう。400円以内でね。ニコールキッドマンの美しさを堪能したいあなただけは、映画館でどうぞ。しかし彼女、コメディエンヌの才能はあまりなさそう。残念!(ざくっ)
2005.02.18
コメント(4)
-
「キューティーハニー」 劇団演技陣の素晴らしさと「ハニー不足」
1973年にアニメ放送されカリスマ的人気で伝説となった、あの永井豪アニメを、「ハニメーション」と名づけられた、アニメ+子供実写番組の風味を残したVFXで実写して見せたのが、本作品である。 タチバナ総合商事で働く如月ハニー(佐藤江梨子)はオニギリ大好きの明るい女の子。だが実は父親の手によって再生された、キューティーハニーという名の特殊なサイボーグ・「愛の戦士」。そんなハニーの特殊な能力に目をつけた秘密結社パンサークローは、次々と刺客を差し向けてくる。 冷静沈着がモットーの警察庁公安8課の秋夏子警部(市川実日子)や、なにか怪しい自称新聞記者の早見青児(村上淳)と友情を深めたハニーは、彼らを、そして人類を守るため、パンサークローに戦いを挑む・・・! 「ハニメーション」は、そのキャラクター設定・演出の上手さとの相乗効果でこの映画の要である。たとえば、「少林サッカー」のVFXは、あの「ワイヤーアクション」がわかっているからこそ楽しめるし、「ヴァン・ヘルシング」や「ハルク」のVFX-つまりあの妙にリアルでないキャラクターたちである-はそれが「アメコミ由来」のものであるとわかっているからこそ、アメリカ人は興奮をする。(日本人は微妙かもしれないが)「ハニメーション」が作って見せたのは、日本アニメ+子供実写ヒーロー番組の、うさんくささと、毒々しさ、そしてそれが奇妙にマッチしたスタイリッシュさだ。海外で、一度も日本で目にした事が無いのに「あれ、これ日本アニメでしょ」とわかることがある。その日本くささを、VFXと合体させたのが、「ハニメーション」なのだ。「よくできてるぅ~」「超リアル~」というのではないから、好き嫌いは別れるかもしれないが、これが、アメリカで好まれる「アメコミのVFXバージョン」と同じように、「日本アニメ+子供実写ヒーロー番組のVFXバージョン」だと思ってみていただければ、その価値はわかっていただけるのではないかと思う。 しかし、この映画の最大の魅力は、「ハニメーション」でも、ましてや佐藤江梨子演じるハニーでもない。映画を見た後に最も心に残るのは、悪役たちのその卓越した演技力である。 パンサークロウを率いるシスター・ジル役の篠井英介と執事役の手塚とおるには、いくらスタンディングオベーションをしても足りない程だ。ほとんど動かず表情も無い役どころながら、独特の威圧感と気品を、眼だけで表現してみせる篠井。独白の台詞回しで思わず涙を誘うほどの手塚。劇団で活躍をしている二人を見ていると、ぽっと出の芸能人やタレントの演技というものが、どれほど浅薄で味気ないものであるのか、つくづく思い知らされる。 また、役者としてよりも声優として知られている新谷真弓の独特のはじけぶりは「ハニメーション」に色を添えるし、片桐はいりはまさに子供番組から抜け出てきたかのようだ。不思議さが魅力の小日向しえ。そして、「CASSHERN」同様、こういったファンタジックな世界だと強烈な魅力を放つ及川光博。悪役のメンバーは、まさに史上最高である。主役を食ってしまう魅力的な悪役というのはなかなかいないのだが(たとえば「ブレードランナー」のルトガー・ハウアー、「ダイハード」のアラン・リックマン)、このメンバーは、(ハニーのダメさ故でもあるのだが)まさに、ハニーが足元にも及ばない悪役軍団であった。また、よくこれだけ漫画っぽくできたな、と思わず感心してしまう市川実日子、村上淳の両人も、適役というほか無い。さて、最後にこの映画最大の欠点がある。それは、他でもないキューティー・ハニーその人・佐藤江梨子である。彼女はかわいいし、元気もある。スタイルは確かに、現在活躍中の芸能人では彼女以上の手足の長さと、ナイスバディはいないであろう。下着姿で走ったりと、とにかくがんばっているし、かわいらしい。だが、なぜ彼女をもっと美しく撮ってやらなかったか、と私はそれが本当に悔やまれるのだ。彼女の「体」はそれはそれは美しく撮ってある。長い足、きゅっとひきしまったヒップ、きれいな胸。ハニーの衣装があれだけ似合う人は、もういないかもしれない。 けれど、「顔」は、私がいつもテレビで眼にするサトエリよりも、数段かわいくなく、写っているのだ。それはメイクのせいであり、カメラアングルのせいでもあろう。演技自体は、あんなものであろうし、しゃべり方自体は問題は無い。けれど、なぜもっと、彼女を「演出」してやらなかったのか。なぜもっと彼女を「ハニー」へと導いてやらなかったのか。とにかく、なぜもっと、彼女を体だけでなく、すべてを「美しく」作ってやらなかったのか。他の部分が非常に良くできた作品だからこそ、「ハニー」本人の出来がとにかく悔やまれる、そんな映画であった。え?これはサトエリ映画?だとしたらなおさら、サトエリをもっともっとかわいく写せるはずだと思います・・・。映画として 7/10実写アニメとして 9/10サトエリ映画として (体目当て) 10/10 (全体像目当て) 5.5/10悪役映画として 10/10
2005.02.17
コメント(8)
-
「コールドマウンテン」
全米図書賞を受賞したチャールズ・フレイジャーのベストセラー小説を「イングリッシュ・ペイシェント」のアンソニー・ミンゲラ監督で映画化したのがこの作品である。 1860年代、アメリカ。コールドマウンテンという名の美しい田舎で出会った、土地の青年インマン(ジュード・ロウ)と、牧師令嬢エイダ(ニコール・キッドマン)。しかし、インマンはほどなく南北戦争の兵士として借り出され、エイダは彼の帰りを待つと誓う。壮絶な戦場で瀕死の重傷を負うインマン。一方、父の急死で生活の糧を失ったエイダは、流れ者の女ルビー(レニー・ゼルヴィガー)に生きるすべを教えてもらいながら、インマンの帰りを待っていた・・・・。 ニコール・キッドマンと、ジュード・ロウという美男美女を主役にすえ、南北戦争を背景に壮大な純愛物語をつむぎだしたのは、アカデミーの受賞もした監督アンソニー・ミンゲラである。ミンゲラの演出力は、ハンサムだが田舎者で無骨なインマンと、都会から来た牧師令嬢エイダが、初めて会った瞬間から惹かれ合い、少ない会話の中で愛を静かに燃え上がらせていくさまを描くとき、もっとも発揮されているように思える。二人の互いへの気持ちを、瞬間に交わす視線や、出征間際までキスさえしない二人の何気ない立ち姿ですら際立たせて見せるのは、ミンゲラの腕の見せ所といったところか。 また、彼の「スケールの壮大さ」は「イングリッシュペイシェント」でも証明済みで、重傷の兵士でごった返す病院を差し挟みながら映像化される、山盛りの死体が連なる南北戦争の悲惨な実態(その戦場の描き方はまるでベトナム戦争を髣髴とさせる)などは、さすがと言う他無い。南北戦争に参戦すると大喜びする若者たちが、一転地獄の戦場でおいつめられる様や、戦争に赴かなかったならず者たちが牛耳る寂れた町の様子、戦争とは無関係なところで略奪を繰り返す兵士たち、と、「戦争の実態」を普遍的に描いて見せるところに、ミンゲラの主張が見えるように思える。 お嬢様育ちのエイダに一から生活の知恵を教えるルビー演じるゼルヴィガーの演技は、アカデミー助演女優賞ももっともだとうなずけるできである。サザンベル(南部美人)=エイダとサザントンボイ(おてんば娘)=ルビー・コンビはユーモラスでたくましく、暗い画面に傾きがちなこの映画に生き生きとした色彩を与えている。このへんもミンゲラの演技指導と演出の賜物であろう。 一方、インマンが脱走しエイダに会いに行く道のりでさまざまな人々に出会い・・といったエピソードは、フィリップ・シーモア・ホフマンやナタリー・ポートマンといった有力キャストを迎えながらも、どうもぱっとしない印象が否めない。だらだらと続き、見せ場が無いというべきか。また、もちろん二人は再び出会うわけだが、その盛り上げ方、も、二人の恋の盛り上げ方や戦争の陰惨な描き方といった卓越した演出力からすると、どうしたの?と聞きたくなる様な精彩の欠け方である。ラブシーンも美しくはあるが、心には残らない。ミンゲラ監督の弱い部分が一気に噴出してしまうのが、後半だともいえる。多くから出たであろうこういった批判をうまく料理したときこそ、ミンゲラが真の名監督となる時なのかもしれない。長編であるので、時間の無い人にはあまりおすすめできない作品である。映画として 6.7/10美男美女映画として 9/10
2005.02.14
コメント(6)
-
「息子のまなざし」
Le Fils「ロゼッタ」のジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ監督の、2002年作品である。主役のオリヴィエ・グルメは、ほとんどセリフの無い役柄ながら、その確かな演技力でカンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞した。 職業訓練所で木工を教える中年講師、オリヴィエ。寡黙で真面目な仕事ぶりであるが、どことなくとっつきにくい男だ。彼には別れた妻がおり、また、数年前に殺人で息子を失ったらしい。 そんなある日、彼は新入生名簿を見て愕然とする。他のクラスに定員オーバーで入れなかったその青年を、オリヴィエは自分のクラスへと招き入れる。人気の無い教室で毎晩腹筋をし、体を鍛えるオリヴィエ。彼は何をしようとしているのか、そしてその青年は誰なのか・・・・。 淡々と日常の小さな事柄を、登場人物の行動で見せていくダルデンヌ兄弟の「ロゼッタ」同様の手法は、社会に埋もれた、または隠された「日常の裏側の暗い部分」と、登場人物たちの心の動きを見事に映像で描写してみせる。 ダルデンヌ兄弟の映画には、俗に言う「見せ場」もないし、「大団円」もない。それは、現実は映画のように派手ではないし、終わりよければすべてよし、というような単純な瞬間も無いからだ。 しかし、人生には真実が露呈する瞬間、がある。心の何かがスイッチし、地味ながら何かが変わる、そんな瞬間がある。 ダルデンヌ監督は、グルメの寡黙で実直な雰囲気をうまく生かし、実直な講師であるオリヴィエの苦悶や怒りを静かに映し出す。また、青年フランシスの「何をすべきかがわからない」といった危うげなたたずまいから、徐々にオリヴィエの後姿に「なすべきこと」を学んでいく様子が、その幼い表情や言葉に見て取れるのも、監督の細やかな演出の賜物であろう。(以下、批評となりますが、ネタバレが含まれます。) オリヴィエの職業は「大工仕事」を教える講師である、というのが、この映画の一番の象徴的な事柄であろう。それは、かの「すべての人の罪を許し、背負って死んだ」キリストの職業だ。 また、映像で細かに描写される「大工仕事」は、実はそのイメージとは裏腹に、非常に緻密で精密な仕事である。木材について正確な知識が必要であるし、それを運ぶにもしっかりとしたバランス感覚が無ければならない。すべてを正確に測ってから木材を切断し、測量したとおりに緻密に打ち付ける。 そのバランス感覚の、そして「正確に把握すること」の大切さは、すなわち人生においても同じなのだ。フランシスがオリヴィエの「見ただけで正確に距離を測れる」という特技に尊敬の念を抱く場面がある。フランシスは彼のそれまでの成長の過程で「正確に把握すること」を学ばなかった青年だ。殺すつもりは無かったのに、力を入れたら死んでしまった、とフランシスは言う。 「正確に把握すること」は実はとても大切なことであり、彼はそれをオリヴィエから初めて学んだ。だからこそ彼に後見人に頼むほど尊敬するようになるのである。 一方オリヴィエの苦悩は深く、彼の静かな怒りは部屋で静かに腹筋を鍛える彼の動かない表情に刻まれる。が、彼はものを「創造する」大工なのだ。物事を「正確に把握する」大工なのである。真実を知りおびえて逃げ出すフランシスにも、オリヴィエが「破壊するもの・距離のわからないもの」ではなく、「正確に把握をする大工」であることがわかっている。だから彼はまたオリヴィエの元に戻るのだ。 いつものように、淡々と、バランスよく木材をかかえる大工仕事に戻っていく二人の姿は、けして明るくも、にこやかでもない。けれど、そこに目に見えない絆と、神でもあり人間でもあるキリストの姿が、見える気がするのだ。
2005.02.08
コメント(4)
-
「ミッシング」 リアルで冗漫な開拓劇
監督は「ビューティフル・マインド」「アポロ13」のロン・ハワード。トミー・リー・ジョーンズとケイト・ブランシェットを主役に迎えた、手堅いアメリカ開拓時代劇である。 1885年、アメリカ・ニューメキシコ州。医術師として生計を立てている中年女性マギー(ブランシェット)は、夫はいないものの二人の娘と、信頼できる愛人ブレイクとの簡素ながら幸せな日々を過ごしていた。そんなある日、20年前にアパッチ族との生活を選び妻子を捨てた父親(リー・ジョーンズ)が治療に立ち寄る。父親を許せないまま帰すマギーだったが、ブレイクと娘二人がインディアンに襲われ、ブレイクは死亡、娘の一人が誘拐されるという事件が起こる。マギーはしぶしぶ父親に手助けを求めることになる・・・。 さすがロン・ハワードというべきか、その「西部劇」的背景は、美しく、そしてリアルである。えてして「セット臭く」なりがちな西部劇を、衣装からそのたたずまいから、明暗をうまく際立たせることで(部屋や町、荒野が「明るすぎる」ことが一番西部劇をアンリアルにする)、開拓時代の「簡素で質素な暮らし」を再現してみせたのは、まさにロン・ハワードの手腕ならではだ。 また、インディアンに魅せられ妻子を捨てた過去を持つ「白人インディアン」のリー・ジョーンズの渋さ、「癒すこと」だけを行っていたマギーが、「守るために戦うこと」を学んでいくそのりんとブランシェットの表情、立ち姿。インディアンにさらわれながら機知と勇気を失わない娘リリーの力強さ、泥まみれの美しさ。悪役インディアンたちの「清潔すぎない」恐ろしさ。そういったキャラクターそれぞれの描きこみは、まさに名人芸というしかない。 また、原作からのものであるだろうが、娘たちを誘拐し殺戮をくりかえすインディアンたちは、元はアメリカ軍隊のために働いていたインディアン部隊の脱走者たち、という設定である。そして、追う側のアメリカ軍にも、それに協力するインディアン達がいる。インディアン対インディアンの構図である。 そこに見え隠れするのは、アメリカという国のご都合主義である。殖民してきた国の原住民を追い出し、彼らが白人と、そして同族同志とすら戦わねばならぬ状況を作りだしたのは、他でもないアメリカ人本人なのである。また、正義であるはずのアメリカ軍隊は、殺戮を受けた家を略奪するような有様の酷い部隊であり、一方、白人の生活を捨てた父親は、中途半端な存在でありながらも、意思と知恵、力を兼ね備えた者として描かれている。 インディアンの精神世界への憧れ、というものは、ここ数年とくに顕著にアメリカでは現れているように思われるが、モラルの無いアメリカ軍隊に、呪術を使うインディアンのおどろおどろしい悪と、インディアンから良い面のみを学んだ「白人のインディアン」の対比が、アメリカ人の目指すべき姿を提示しているようにも、思われる。 さて、それぞれのキャラクター描写の素晴らしさについて先ほどは賛辞を述べたが、ストーリー展開としては、やけに細かく描いたシーンがあれば、やけにささっとすんでしまった場面もある、といった具合で、幾分かあらがめだつ。ラストの一連の展開も、見せ場であるはずなのに「力が尽きた」ようなスカスカな描写となっていて、どうも山場としてはぱっとしない。そのため、「あぁおもしろかった」と手放しでおすすめできる出来とはいえないのが、残念である。映画として 6.8/10西部開拓劇として 8/10
2005.02.07
コメント(0)
-
「エレファント」
エレファントコロンバイン高校で1999年に起きた高校生乱射事件をご記憶の方は多いと思う。最近ではでかのマイケル・ムーア監督が、この事件を引き起こした原因を「悪影響を与えるゲームやテレビ、音楽」ではなく、「銃を容認するアメリカ社会そのもの」であると主張する「ボーリング・フォー・コロンバイン」が話題となった。「エレファント」は、「グッド・ウィル・ハンティング」のガス・ヴァン・サントがこの事件を題材に作り上げた映画である。 映画は乱射事件が起こるまでの数時間を、犯人の二人の少年を含めて、その場に居合わせた生徒達の行動をそれぞれに区切りながら、追って行く手法を取っていく。彼らが殺される、または犯行に及ぶに至る場所にたどりつくまでを、一人づつ描き、そして事件が起こる、という構造である。 実はこの作品は脚本と言うものはいくつかのキーワード以外は存在せず、全て俳優達(ほとんどがオーディションで選ばれた子供たちである)のアドリブで補われている。流れは説明してあるものの、演技そのものがアドリブ(犯人の少年が自室で弾くピアノのシーンが印象的なのだが、それすらも)らしい。 これは、それだけ演技者の「現実」を引き出し、アメリカのティーンエージャーの「真実」を映像に映し出すのに成功しているが、同時に、監督ガス・ヴァン・サントが伝えようとしているのは何か、をぼやかす意図も感じられる。ヴァン・サント自身は、「それはこの映画を見た観客にゆだねられる」と言っているが、その意図の中で、こぼれでてしまった監督本人の心情、これについて少し語ってみたいと思う。 それはなによりもまず、その映像における「構図」にある。たとえば、高校のグラウンドのあちこちで授業や球技をしている、しかしその真ん中がぽっかりと開いている。内気な少女がたどりつく、一人ぼっちの体育館のがらんとした冷たい空間。アル中の親をもつ青年が一人で涙をこぼす、使われていない教室のだだっ広さ。たくさん人がいるはずの学校で、歩く生徒を追うカメラがほとんど他の生徒の姿を捕らえない。 「がらんとした空洞」-hollow という表現があるが、まさにそれを象徴したかのような構図の連続である。その空洞は、社会のミクロコスモスであるといわれている小さな社会「学校」が実は空洞であり、虚無であり、それゆえに無防備であることを象徴しているのと同時に、生徒たちが実は学校というさも社交的な場にいながら、実は孤独である、ということを示しているように思える。 Hollowな場所に集う、hollowな子供たち-アダルトチルドレンの担わされる役割の中で、「隅の子供」と呼ばれる、いつも部屋の隅に立ちまわりのものと本当にはかかわりを持たないことで自分を守る、というのがあるが、この生徒たちが、実は皆、「隅の子供」なのではないのか・・・そう、思わせる構図なのである。 また、演技や脚本ではなく、登場人物たちの設定そのものに見ることのできるものもある。 アル中の親を世話するのに忙しく、学業がままならない子。美しく、それを維持するために食べては吐くを繰り返す少女たち。「異性愛と同性愛」について話し合う会。友達のいない孤独な少女。学校ではいじめられている少年が銃を手に見る「力の象徴」ナチの映像。燃え盛り人が血まみれで逃げ惑う中をまるで「普通のこと」のように歩き回る黒人の少年。 その設定そのものの中に、アメリカへの疑問が投げかけられているように思えるのだ。それはムーアのような直接的な表現ではなく、「これはすべてがアドリブの映画なんです」ということで、きれいに隠されてしまっている。 けれど、やはりそこに、病んだアメリカを真っ直ぐに見ているガス・ヴァン・サントがいる。私にはそう思えた。映画として 8/10映像作品として 9/10手法として 10/10追記:「エレファント」のタイトルは、製作時に会社側に「銃乱射事件を扱うのなら、こういうつくりの映画ならよい」と例に出された映画のタイトルである。1989年のアメリカテレビ映画「エレファント」で、北アイルランド紛争を扱ったもので、できはあまりいいものではないらしい。 「象」は普遍的には「力への欲求」のシンボルで使われることが多く、案外この映画の真実を言い表しているのかもしれない。
2005.02.05
コメント(6)
-
「ウォルター少年と夏の休日」 2
(批評ですのでネタバレがふくまれます) アーサー・ミラーの「セールスマンの死」、では、父親であるセールスマンが、その夢を熱く語るシーンがあるが、そこでその「夢物語」を象徴する人物がいる。彼の「おじさん」である。このおじは、主人公の話によれば、アフリカに渡り(舞台でこのおじが実体化されると、たいていサファリの服装を着ているらしい)そこでアフリカを切り開き、巨万の富を築いた、というのである。もちろんこの話が真実かどうかというのは描かれず、どちらかといえば、この夢物語を信じて生きてきた主人公ウィリーが人生を誤ってしまうのであるから、うそ臭い話であるといえる。アフリカのサファリ、といえばヘミングウェイをはじめとして、「男らしさ」の最たる象徴のひとつだ。ウィリーの夢は、この「男らしさ」の夢とアメリカ資本主義の夢を併せ持つ形で、増殖したのである。 これが「ウォルター少年と夏の休日」と、見事に一致する。ウォルター少年が預けられる「おじ」達は、アフリカで活躍し、猛獣たちと戦い、そして巨万の富を築いた、と自らを語る。そしてそのすべては、案の定、真実なのである。「ビッグフィッシュ」ではセールスマンの父の夢物語が、真実であった。「ウォルター少年」では アフリカのおじの話、が真実であった。そう、この二つの映画は、「セールスマンの死」のうそ臭い夢物語が二つに分離し、そしてその夢双方を見事にかなえた物語なのである。 ビッグフィッシュにおいても、ウォルター少年においても、その夢物語が真実であったことがラストではっきりと明らかになり、「アメリカンドリーム」も「男らしさの幻想」も現実であったことが強められてラストとなる。しかし、私は個人的には、ウォルター少年のほうが、気に入っている。よりできがよく、強く感動するのは「ビッグフィッシュ」であるにもかかわらず、だ。 なぜかといえば、ウォルター少年は、母のもとを離れ、おじたちに、自分が大きくなるまで「男らしさを封印する」=保護者として少年を育てる ことを要求し、おじたちはこれを飲むからだ(女性抜きの男性だけで成長する少年、というスタンスは「男らしさ幻想」とあいまった微妙さではあるが)。つまり、おじたちは、それまでにはなかった、いわゆる「女性的な」要素=育児・庇護を、その性質に付け加え、ただの「男らしい男」ではない、女性的面をも兼ね備えた「完璧な人間」へと変貌するからである。 ウォルターがひとり立ちしてからやっと、おじたちは「靴をはいて」男らしく、死んでいくのである。(宗教的には、確か靴は死に際して脱がせてやるものだったかと記憶している)成長したウォルター少年は、漫画家という「夢を売る」商売となっていて、あきらかに資本主義に組み込まれた人間にはなっていないようであるのが、また、私にはほほえましく感じられた。 女性の影は「ビッグフィッシュ」と比べてもあまりに薄いが(母親はあまりにひどい人間であるし)、「男性的な男」が女性性をもかねそなえる、という成長までも描いているから、というだけで、私はウォルター少年に思わず軍配をあげてしまうのだ。いや、それとも、「女性抜きで育つ男なんて!」と、声を上げるフェミニストであるべきなのかも、しれない。
2005.01.29
コメント(0)
-
ウォルター少年と夏の休日 Secondhand Lions
監督・脚本はティム・マッキャンリーズ。実はこの映画、どうやら、かの感動作ティム・バートンの「ビッグ・フィッシュ」へのいわば対抗馬、いや、二匹目のどじょう映画であるようだ。マッキャンリーズは「アイアン・ジャイアント」の監督。感動ならお手の物、ということで、「ティム」バートンの対抗馬として担ぎ出されたのかもしれない。 父親がいない14才の少年ウォルター(ハーレイ・ジョエル・オスメント)は、「大金を隠し持っているらしいから、とにかく見つけてきて!」と興奮気味の母親に、今までまったく付き合いのない母方のおじ二人の住む家へおきざりにされる。 おじ二人は、最近このテキサスに戻ってきたらしいのだが、その「億万長者」のうわさとは裏腹に、粗末な暮らし振りだ。無愛想なハブ(ロバート・デュヴァル)とガース(マイケル・ケイン)の2人に馴染めないウォルター。しかし、屋根裏部屋のトランクケースからエスニックな美女の写真を見つけたウォルターに、ガースが意外な物語を語り始めたことから、三人は心を通わせていく・・。(以下「ビッグ・フィッシュ」も含めたねたばれが多数含まれますので、ご注意ください。また、以下にかかれたものはあくまでも筆者の観点であり、皆さんの感動を損なおうという他意はありません。) さて、この映画の何が「二匹目のどじょう映画」であるのかといえば、その基本構造そのままである。 「ビッグ・フィッシュ」(原作のある、文学作品でもある・原作者はその後同じテーマで違う物語を書いているが、ここでは、ウソのように話した父親を責めている)では父親が生涯にわたって息子に聞かせ続けた夢のような話が、実は多少の誇張はあるもののすべて真実であった、という物語であった。 かつてアーサー・ミラーの「セールスマンの死」で暴き出した、「人によく知られること」・「リッチになること」=「アメリカンドリーム」をすばらしいとする価値観が(これはアメリカのマスメディアのつくったものだ)実ははかなく、非現実的でありむなしいものであること・・を、きれいにひっくりかえし、現代においては「アメリカンドリームを信じよ」と、ストーリーのすべてをまるごと裏返しにしたのが、この原作であった。( 左・ビッグ・フィッシュ 右 セールスマン) 「息子たちに語ったままの凄腕セールスマン」⇔「実際は解雇寸前のセールスマン」「浮気をしていそうでしていなかった父」⇔「真面目なようで浮気をしていた父」「町中すべてが知り合い」⇔「町中すべてが知り合いという、ウソ・夢」といった具合である。そこに対立しているのは、「アメリカンドリーム」の構図だけでなく、セールスマンの父親が、「信じられない父親」(死で愛を示すほかない)のに対し、ビッグ・フィッシュの父親は、「本当は信じるべき父親」であったという点でもある。ここに、原作者の(そして出版社、仕掛け人たちの)アメリカにおいての「父親を信じよ」というメッセージが(それは同時に、現在の父権崩壊を示唆するものでもある)読み取れる、と以前実はもう消してしまった批評で書いたことがある。くれぐれもいっておくが、これは感動作を批判しているわけではない。「ビッグ・フィッシュ」はすばらしい感動作である。ただ、この物語の登場・評価に、アメリカのそういう傾向が見える、というだけの話である。 さて、「ウォルター少年と夏の休日」は、なぜこの「ビッグ・フィッシュ」の二匹目であるのかといえば、その基本構図が同じであるからだ。そして、上に同じく「セールスマンの死」をひっくりかえした部分が存在するからだ。明日はそれについて、書いてみようと思う。
2005.01.27
コメント(4)
-
「ターミナル」 2 風刺コメディの香り
(映画を見ての批評・気づきをしたためているので、ネタばれが含まれます。また、以下に書かれているのは眺望本人の主観であり、映画をご覧になった皆さんの感動をなんら否定するものではありません) ターミナル、の基本構造は、東欧からの素朴で純粋な男が、こりかたまったアメリカ(の縮図空港)にさわやかな風をふかす、というものだ。このヨーロッパ・アメリカ間での「新しい風・さわやかな風」という図式は、「エイジ・オブ・イノセンス」(イーディス・ウォートン原作 ヨーロッパに長年住んでいた女性が、NY社交界に新しい風を吹かせるも偏見に縛られる話)や、「鳩の翼」(ヘンリー・ジェームズ原作 イギリス人・ヨーロッパの中に新しい風を吹かせる不治の病に冒されたアメリカ人女性)など、文学・芸術の世界では繰り返し使われている構図である。 また、広く言えば、「どこからか誰かが現れて、みなを変えて去っていく」というのは、スピルバーグのE.T.であり、もちろんアメリカお得意のウェスタン「シェーン」の構図でもある。 これは、常に「すばらしい魅力を持つ誰か」が「何か腐敗したもの」を変え、何かを教えて去っていく、という「アメリカン・ヒーロー・(ヒロインでもよいが)ファンタジー」の基本構造である。それでは「ターミナル」では、誰が何を変え、何を教えたのだろうか。そして、何が腐敗していたのか。 主人公のビクターがまず周囲を驚かせるのは、彼が「空港で待つように」言われたままに、「空港でいつまでも待っていること」だ。局長代理ディクソンは「逃げようと思えば逃げられるのに、なぜ逃げない?」と本音を漏らし、ビクターをわざと逃がそうとまでする。何かといえば二言目に「法が・・」と難しい法律用語を並べ立て、法をつかさどる側のディクソンが、保身のためには法を破らせようとする。そしてまた、彼が「人間み無く」法に固執する一方で、ビクターが法の抜け穴をうまく使って、人助けをしてみせる。 「ターミナル」というミクロコスモスの中で描かれるアメリカは、「道で転んだからその道を作った市を訴える」ような事が日常茶飯事の、超司法国家アメリカの暗部でもあるのだ。 ビクターが友情を育むメンバーは、インドで犯罪を犯し、アメリカに逃亡して二十年以上になる「インディアン」(インド人)グプタや、メキシコ系のエンリケ、黒人の荷物係など、いわゆるWASPではない「移民」たちだ。 そもそも、空港で働く登場人物の中には、ディクソンと、局長本人以外ほとんど白人がキャスティングされていない。ターミナルが、アメリカのミクロコスモスであるなら、これは、そのまま多くが有色人種の「移民」でなりたっていながら、その統治にあたっているのは白人である、というアメリカの不自然さを映す鏡でもある。 ビクターは当然白人であるのだが、国籍から不確かな状態の彼をはじめに受け入れてくれるのは、法の番人たち白人ではなく、有色人種の移民たち=庶民たちなのだ。そして同時に、彼をスパイだと疑ってみたり、また、「人が転ぶのを喜ぶ」といったことに象徴される「庶民」たちのささくれだった心を癒すのもまた、ビクターの優しさと純朴な明るさなのである。 「買い物だけしかできない」ターミナル・・それは、そのまま「資本主義大国」アメリカを揶揄しているが・・・を支えているのは、彼ら「庶民」であるのだ。 さて、この映画の感想で、よく目にするものがある。それは、ヒロイン役アメリア(キャスリーン・ゼタ・ジョーンズ)が、ビクターと心を通わせるのに、なぜ不倫相手の元へ戻ってしまうのか、というものだ。映画としては、おそらくビクターとアメリアがめでたしめでたし、といったほうが数倍盛り上がるのだろうが、なぜ、そうしないのか。それは、アメリアが、「典型的なアメリカ女」の役割を担っているからだ。それはヘミングウェイにも通じる、アメリカ女性への痛烈な批判でもある。 強く美しく知的であり、奔放で、そして不幸な愛を抜けられない-そんなアメリアは、アメリカの男性たちが時に恐れてきた、気位が高く気が強いアメリカ女性であり、同時に、アメリカの男性たちがもてはやしうまく弄んできた、その奔放さとと精神的なもろさをも、象徴している。他のみなが、あのディクソンでさえ変化の兆しを見せるのに、アメリアだけは、変わらない。 そこにスピルバーグや、ニコルの、アメリカ人女性への理解不能さ、恐れ、といったものを見て取ることもできるのだろうか。アメリカ女性のイメージは、あのヘミングウェイのころから本質的に変わってはいないのかもしれない。 こうしてみると、「ターミナル」は「ファンタジックなヒーロー物語」でありながら、アメリカをターミナルになぞらえての、そこはかとない「風刺」の香りがするように思う。そこで腐敗していたのは、「自由の国」でありながら、法律にがちがちに縛られ、庶民と上層部が完全に分離した、「メルティングポット」(融合したもの)でなく「サラダボウル」(さまざまな人種が別々の場所にいる)な社会であり、そしてビクターが教え、変えたのは、「なによりもまず、人間であること」「希望」「0から作り上げること」「待つだけでなく、行動すること」などだ。 そしてなにより「何かを教え去っていく」のがアメリカ人ではない未知の国の人間であること、また、モデルのメーハンがどちらかといえば「とどまってしまったこと」で有名になったのに対してこのストーリーが「とどまった中で回りを変えていくこと」に焦点を置いたことが、私にはなにか少し「アメリカ批判」的なものを感じたように思う。 おもしろいことに、原案のニコルは、ニュージーランド人であって、アメリカ人ではない。スピルバーグの常套構図を用いながら、ハリウッドに「缶詰」になってしまったニコルの、いつものさりげない風刺コメディのひとつとして、この「ターミナル」も数えることができるのかもしれない。 最後にひとつ、さりげない「風刺」を感じさせつつ、今までのアメリカの国としてのあり方を完全には批判していないのだな、と思わされた点がある。それは、ディクソンがさんざんの失態(しかし法を守った上での失態である)の末にもかかわらず、昇進している点だ。問題点はあるものの、その「あり方」はアメリカを守ってもいる・・・そんなメッセージを、感じたラストであった。追記として、小さなきづきを。1. アメリアの不倫相手マックスは、「ヒドゥン」のマイケル・ヌーリー。すっかりロマンスグレーの、しかし品のいいおじ様となった。2. ビクターがかばんを閉じてやる少女ルーシー、はスピルバーグとケイトキャプショーの間の娘、サーシャである。映画として 8/10コメディー・ファンタジーとして 9/10
2005.01.25
コメント(4)
-
「ターミナル」 1 まずは背景を簡単に
いまさらながら、「ターミナル」である。詳しいことをご存じない方がいないとも限らないので、少しばかりこの映画の背景について説明することから今日は始めようかと思う。このトム・ハンクス主演の、大々的なハリウッド映画は、実話に基づいたわけではないにしろ、モデルとなった人物がいる。アルフレッド・メーハンというイラン人男性である。 彼は、その自伝「Terminal man」(アマゾンでももちろん販売中)をそのまま信じるならば、イランからの奨学生としてイギリスにきたものの、反イラン運動に加わったことが本国にばれ、イラン帰国後投獄・追放を受ける。そのため、英国へ亡命者として入国の申請をしたものの、英国政府はこれを拒否。しかたなく難民申請のためにヨーロッパ各国を転々としている間に、亡命者許可証や一切の書類の入った鞄の盗難に合い、どこの国への入国もできないという状況に陥り、1988年、降り立ったフランスのシャルル・ド・ゴール空港に腰を落ち着けることとなった。 彼はその後フランスへの入国許可を得たものの、あえて入国せず、以来16年間、(筆者の知る限り昨年11月までは確実に)ド・ゴール空港を住処とし続けている。メーハンは「ターミナル」映画化に際して300万ドルを手にしたものの、その後も暮らしぶりは変わらず、ド・ゴール空港のいわばシンボルとしてそれまでと同じ生活を続けているという。 さて、この逸話が、原案アンドリューニコル(「ガタカ」「トルーマン・ショー」)にして、スピルバーグ監督で映画化され、名作曲家ジョン・ウィリアムスの音楽をふんだんに使ってハリウッドに行くと、どうなるか。それが、「ターミナル」である。 東欧の政治的に不安定な小国、クラコウジアからNYの空港に降り立った中年の男、ビクター・ナボルフスキー(トム・ハンクス)。ピーナッツの缶を大事に抱え、数冊のガイドブックとともにNYに降り立った彼は、満面の笑みでパスポートを入国審査に出すが、入国拒否とされ管理局へとまわされる。担当は管理職候補の野心家ディクソン。英語の説明がよくわからないまま食事券とポケットベルを渡され、ターミナルに戻されたビクターが目にしたのは、ターミナル内のテレビニュースが伝える、祖国クラコウジアのクーデターのニュースだった。 入国拒否の理由を悟ったビクターは、いつか許可が下りる日を待って、ターミナルでの暮らしを始める。なぜなら、彼には果たさねばならない約束があるのだ・・。 ストーリーは、不倫で悩む美人フライトアテンダントのアメリア(キャスリーン・ゼタ・ジョーンズ)との恋や、インド人掃除夫、機内食運搬の青年やラゲージ担当など、管理局のディクソンも含め空港内で働くさまざまな人々とビクターの交流を軸にすすめられる。ヨーロッパからさわやかでピュアな風が吹いてきて、人々を正しいほうに導く、というのが最も簡単な説明であろう。 それでは明日は、批評というよりもむしろ、感じたことをつれづれなるまま、という観点から、この「ターミナル」について書いてみようと思う。
2005.01.24
コメント(2)
-
「ワン・コイン・ヘブン」 快笑傑作ショートフィルム
「ワン・コイン・ヘブン」 In god We Trust 原題:In God We Trustとは、アメリカのコインに刻まれている言葉。われわれは(お金ではなく)神に信心をおき神に集います といったところだろうか。 道端に落ちていた 10 セント銀貨を拾ったばかりにトラックにひき殺されてしまうロバート。次の瞬間、彼は「三途の川事務所」に辿りつき、隣人の庭芝に「ケツの穴」と文字を刻んだ、元カノにゲロ入りボックスを送りつけた、などなど小さな悪事の合計で、なんと地獄行きを宣告されてしまうのだが・・・・ 今日ご紹介するのは現在ネット上のここで公開中の16分のショートフィルムである。 監督・脚本はジェイソン・ライトマン。この名字に覚えはないだろうか。そう、「ゴーストバスターズ」や「ツインズ」の製作や監督で知られる、あのアイヴァン・ライトマンの実の息子である。 実はこの作品、まるで漫画的なくだらなぁぁいストーリーながら、そのすばらしいテンポとコメディセンスで、さまざまなショートフィルム賞を総なめにした傑作。「三途の川事務所」から命からがら逃げ出した主人公と、それをおう事務員(?)たちを中心に、次から次へと予期せぬ展開へと転がっていくストーリーは、もちろんものすごいCGがあるわけでも、長い脚本があるわけでもない。が、その娯楽性の高さ、シンプルだからこそのおもしろさは、まるでごてごてにお金をかけたハリウッド映画へのアンチテーゼのようである。 現在はThank You For Smoking という新作を準備中のライトマン、彼がハリウッド映画のデビューを飾るのも、遠い話ではなさそうだ。 ただで視聴できるので、これを読んだらすぐに、コーヒーでも用意して見ていただきたい逸品である。 ワン・コイン・ヘブン
2005.01.18
コメント(3)
-
「ロスト・イン・トランスレーション」 失うことの価値
マルチに活躍するソフィア・コッポラの、「ヴァージン・スーサイズ」につぐ映画作品である。もちろん今回も脚本、メガホンともにソフィア・コッポラ本人。彼女が目にした日本を舞台に繰り広げられるラブストーリーということで、相当な話題を呼んだ。 全盛期を過ぎた中年ハリウッド俳優のボブ(ビル・マーレー)。サントリーのCM撮影に東京にやってきた彼は、日本人スタッフたちに気を使われる日々をすごしながらも、異国の環境になじめず、仕事とホテルのバーの往復を繰り返しながら、孤独感を深めていた。 一方新婚の夫の仕事で同行したシャーロット(スカーレット・ヨハンソン)は、多忙な夫に取り残され、異国に、そしてまた夫の生きる社会との間に疎外感を感じていた。そんな二人がホテルで繰り返し顔をあわせるうちに、心を寄り添わせていく・・。 言葉のよく通じない異国に旅行したことがあるだろうか。見るものすべてが新しくエキサイティングであるのと同時に、すべてが本当に異世界で、自分だけが「違う」・・そんな感覚に陥るあの瞬間を、思い出してもらいたい。 ボブとシャーロットの二人が目にする日本では、よくわからない漢字が氾濫し、「ブレードランナー」さながらのけばけばしいネオンが光り、聴く言葉はまったくの意味を成さず、「通訳」(トランスレーション)はまるで曖昧に感じられる。何を信じ、何を頼るべきなのか・・・このTOKYOという未知の都会で、二人は完全に迷い子(ロスト)となってしまう。初めはホテルという要塞に閉じこもっていた二人が、互いの中にある「同じなにか」に惹かれあい、そっとホテルを抜け出し、そして夜の東京に足を踏み出していく様子は、もどかしく、またほほえましい。 当然外国の目から見た目の日本であるから、妙な描写もあるが(映像の反転のために着物の襟が逆になってしまった、というおまけつきでもある)、その西欧から見たときの日本:東京という街の「妙ちきりんさ」が、二人が心を寄せ合い、「どこかに属する誰か」から「自分に属する自分であること」を発見する過程(トランスレーション)にしたがって、普遍的なただの街となり、雑踏となっていく。 ソフィア・コッポラの監督としての力が最も上手に現れるのは、その、東京という街の「特定の場所から普遍的な場所への移行(トランレーション)」であり、また、アカデミー脚本賞を受賞したその脚本は、ボブとシャーロットという年齢もその職業もまったく重なり合わない二人の「自己発見」を、二人の言葉すくななやり取りの中でしっかりと描いてみせている。 ロスト・イン・トランスレーション の元の意味は、Something is lost in translation-通訳・翻訳の途中で本来の文章にあったものが失われていくこと であるらしい。ボブがラストでシャーロットにささやくセリフは、われわれの耳には届かない。(ロスト)けれど、私たちは彼の言葉を自分の耳で聞くことができる。失われたことで補足されるものがあり、失われたことで新しくなるものがある。移行の過程で何かを失うことは、決して悪いだけではない。 東京という街が、それをソフイア・コッポラに教えた街であるのなら、素敵なことではないか。映画として 7.5/10ラブストーリーとして 7.8/10
2005.01.17
コメント(4)
-
「10億分の1の男」 Intacto 傑作ミステリアス・サスペンス
監督・脚本はスペインの新鋭、ファン・カルロス・フレナディージョ。スペイン・ゴヤ賞の最優秀新人監督賞を受賞した、傑作である。荒涼とした砂漠にある一軒のカジノ。フェデリコはそこで「運」を操る仕事をする男。何不自由ない生活をしていたが、ある日、自分を育ててくれた恩人でもある経営者サムのもとを去ろうと決意する。それを知ったサムは、フェデリコを訪れると熱い抱擁をする-彼の必死の抵抗にもかかわらず・・・。 7年後、旅客機の墜落事故があり、ただひとり生き残った逃亡中の銀行強盗犯トマスがいた。フェディリコはトマスに、あるゲームにエントリーすれば警察の手からお前を逃がしてやる、ともちかける・・。 美しいだけの映画というのがある。ストーリーだけが突出した映画、俳優だけが目立つ映画、脚本のよさだけが妙に浮いてしまう映画、奇想ばかりが一人歩きする映画。映像も、ストーリーも、演技も、脚本も・・そういった全てがバランスよく組み合わさることでできあがる傑作、というのは意外に少ないものだ。が、この「10億分の一の男」は間違いなくその「バランスの良い」傑作のひとつである。 ゴヤの絵のように陰影の美しい映像、「運」が人々の間をまるで実体があるかのように行きかうというその発想・ストーリー、あくまでも静かで、存在感だけをかもしだす俳優たちの演技に、ミステリー・サスペンスでありながら、ホラー的な要素も兼ね備え、同時に「父と子」の関係までも描いた脚本・・・そういったものが全てバランスよく組み合わさり、見ているものをその世界に完全に引き込んでしまう、そんな映画なのだ。「ゲーム」とは、そのものたちの「運」を試すものなのだが、その数々のゲームも見所のひとつである。森の中を目隠しして全速力で走り、樹にあたらなかったものを勝ちとし、「運」を交換する・・・・など、その内容はまさに奇想天外だ。 フェデリコやトマスを追う女刑事とのいたちごっこもスリリングである。よくあるハリウッド映画にありがちな「美人でナイスバディ」な女刑事でもなく、ありがちな「ロマンス」の匂いもなく、リアルに描かれるのだが、そこにまた、「運」が絡む。 美しい原色とコントラストの中で、登場人物たちのリアルさと「運」の不可思議さが交錯した、ミステリアスでサスペンスフルなストーリーが展開する。 ハリウッドリメイクも決まっていると聞いているが、おそらくこの「バランスの素晴らしさ」は「バニラスカイ」の時のようにハリウッドの大仕掛けの中で消えてしまうに違いない。リメイク版が話題になる前に、是非見ておいていただきたい逸品である。映画として 9.9/10 (ストーリーが「運」を扱っているため、「大槻教授」な人には受け入れてもらえないこと、ラストがわかりづらいこと、にー0.2)発想として 100/10サム役フォン・シドーに 10/10
2005.01.07
コメント(10)
-
来年もよろしくお願いいたします
皆さんご訪問ありがとうございました私本人のチョイスでは、今年発売・ロードショーの映画では、「ソウ」「10億分の1の男」「華氏9・11」「ドッグ・ヴィル」「パッション」になるかとおもいます。総合評価としてですが。もちろん新作旧作あわせ、年間150本ほどしか見ておりませんので、個人的な意見ですが。それではよいお年をお迎えください。眺望
2004.12.30
コメント(6)
-
「昭和歌謡大全集」 悪意のあるブラック・コメディー
村上龍の同名小説の映画化である。 東京都・調布。専門学校生で、友人たち(松田龍平/池内博之/斉藤陽一郎/村田充)と昭和歌謡を舞台風に歌うことを趣味としている青年(安藤政信)が、町で通りがかりのおばさん(内田春菊)をからかった末、大声を出されてふと、手持ちのナイフで頚動脈を切り殺してしまう。なんだかスカっとした気分になった彼は、ほとばしる血が「チャンチキおけさ」だったと友人たちに吹聴したりしている。 一方殺された「おばさん」にはあと5人のカラオケ大好きな仲間(樋口可南子/岸本加世子/森尾由美/細川ふみえ/鈴木砂羽)がいた。現場に落ちていたバッジから犯人を突き止めた彼女たちは、犯人殺害を綿密に計画、見事復讐に成功する。 そしてこれが壮絶な闘いの幕開けだった・・! 村上龍は難解だ。若い頃に本人が好きで(RYU'S BARのようにセンスのよい会話を聞かせてくれるTV番組は今はもうない)ずいぶんと読んだけれど、そのにごっていながら澄んだ私的で感覚的な文章の裏に、その淡々と現代を(または現代を模した未来を)描写する言葉の裏に、明らかな「批判」やウィットある「悪意」を感じるからだ。ここ数年はもう彼のかくものは読んでいないから、「昭和歌謡全集」も原作は未読であるが、この、ナンセンスなまでのバイオレンス・コメディーの背後にも、あの青いバーのカウンターに座る鋭い村上龍の目が見える気がしたのである。 監督は「深呼吸の必要」の篠原哲雄。カラっとしたアメリカン・ブラック・コメディー(「ローズ家の戦争」に代表されるか)にも仕立てられたであろうに、そうはしていないところが、彼もまた村上龍の「裏」をしっかりと読み取って映像化したのだということが読み取れる。 全ての章は「錆びたナイフ」など昭和の歌謡をタイトルとして区切られ(小説のままらしい)、その中で「復讐」という形で一人、又一人と殺しあいが続く。その殺し方がエスカレートする様は、「りんごの歌」に始まり笠置シズコ、美空ひばり・・と発展した日本の昭和歌謡が、ピンキーとキラーズ、へとすすみ、ジュリーの「TOKIO」にいたるまでどんどんとその形態をエスカレートさせていったのに重なるし、またそれと同時に、ひとつの時代(歌)が終わるたび、そこで得た刺激(ここでは殺人)以上のものを求めて行くという人間社会そのものの縮図でもある。 おばさんグループと青年グループは、お互い「差別」し合っていながら実はその「虚無感」が非常に似たものとして描かれているし、殺人という強烈な刺激を通して初めて、それぞれのグループに足りなかったもの-おばさんにとってはそれは「人の話を聞くこと」であり、青年たちにとってはそれは「心」である―が得られるようになる、というアイロニーも上手に描かれている。 もちろん原作譲りの軽妙な会話と絶妙な合いの手(殺しの後のそれぞれの自慢話の部分など、噴出したほどだ)も健在で、ブラックで笑えるコメディーとしてもしっかり成立している。 ストーリー自体が一見荒唐無稽であるから、映画の冒頭の歌のシーンから「なんじゃこりゃ?」な感は否めないが、これが村上龍原作で、いつもその裏に何かあること、ウィットに富んだ「悪意」がとてつもなく上手な作家であること、を思い出してもらえれば、充分に楽しめる映画だと太鼓判を押しておこう。 ちなみに、殺人シーンは強烈であるから、血しぶきに弱い人にはお奨めできないことを付け加えておこう。映画として 7/10ブラック・コメディーとして 9/10
2004.12.27
コメント(0)
-
「女はみんな生きている」 女はそこに何を見るのか
普通の中年主婦エレーヌと、夫ポール。知人との約束に遅れると車を飛ばす彼らの前に、怪しげな男たちに追われた血まみれの若い有色人種の女が助けを求めて駆け寄ってくる。しかし、面倒に巻き込まれたくないポールは無情にも走り去り、血が車についた、と愚痴を言う始末。一方助けなかったことを後悔するエレーヌは、救急病院で瀕死の彼女をなんとか探し当てる。女はノエミという名で、どうやら半分植物状態で口も利けない彼女を付けねらう人物がまだいるらしい。エレーヌは家事も仕事もなげうって献身的に介護をはじめ、彼女を守ろうと決意する。やがて、口が利けるまでに回復したノエミが語った物語は、むごくすさまじい彼女の人生であった・・。 コリーヌ・セロー監督・脚本の代表作といえば、かの「赤ちゃんに乾杯!」である(ハリウッドリメイク「スリーメン&ベビー」も作られた)。軽妙な語り口が身上の女性監督であるが、実は彼女はしっかりとした社会派監督でもある。もちろん特にジェンダー論的な問題点を中心におく監督であるから、この作品も女性たちを中心に、身勝手で他人を慮ろうとしない男たちとのさまざまな関係を描いたものである。(ちなみに原題はCHAOS、神が人間を作る前、ORDER-秩序- の無い世界のことである)しかし、彼女の語り口はそれにとどまらない。 ノエミの口から語られるイスラム社会での女性の生活は、まさに衝撃的だ。娘は商品であって、ある一定の年齢に達したらお金と引き換えに嫁に出される。ノエミはその後娼婦となるのだが、その搾取のされ方もすさまじい。ヤク漬け、反抗、ヤク漬け、の繰り返しであり、たとえ映画としてデフォルメされているにしろ、どこの都会でも必ず行われている「裏社会」の風景が伺われる。ノエミはこの男たちからの搾取と従属を、知力と行動力で切り抜け、妹が自分と同じ生き方をするのをどうにか防ぐために命がけで尽力するわけだが、彼女の物語は、普通のフランスを生きるエレーヌとは、あまりにも対照的だ。 しかし、仕事は持っているものの、夫と息子の世話に追われながらないがしろにされる主婦エレーヌの日常は、ノエミのような生命の危機はないにしろ、やはり男性による精神的な搾取と従属の連続である。ストーリーで重要な役割を果たすことになる夫ポールの母親もまたそうで、年に一回か二回息子に会いにパリのホテルに滞在までする年老いた母親は、成長した息子にまったくとりあってもらえない。 男性たちにないがしろにされ、さげすまれ、従属を強いられ、搾取されてきた彼女たちが命がけで抵抗するとき、神の作った秩序ーそれはまずアダムを作って、そのあばらからイブをつくった秩序である-は混乱し、カオスとなるのだ。 カオスの果てに、新しい秩序を見出そうとする女性たちの顔は、強く美い。けれど、「Angry Young Woman」そのままのノエミと、微笑を満面に称えているポールの母親とは対照的に、なにか当惑したままで、憂い気なエレーヌの表情が、セロー本人の、現代社会への意見をそのまま表しているような気がしてならないのである。映画として 8/10軽快なフレンチ・クライム・サスペンスとして 8/10社会派映画として 8/10
2004.12.25
コメント(2)
-
「エイリアンVSプレデター」 「第五惑星」でもよかったのに
2004年、巨大企業ウェイランド社に謎の熱源が南極大陸の地下深くで発生しているという衛星データが送られてくる。この企業の経営者で億万長者のチャールズ・ビショップ・ウェイランド(ランス・ヘンリクセン)は現地調査を決断、さっそく若手女性登山家レックスを筆頭に、各分野の専門家を招集する。 熱源にたどり着くためには厚い氷に穴を開けることからはじめねばならない-と、そんな矢先、まっすぐに氷をくりぬかれた穴を発見した彼らがそこを降りると、かつての古代文明の全ての要素を兼ね備えた、動く迷路でもある巨大ピラミッドが。しかしそこに現れたのは、なぞの生物(エイリアン)と、なぞの異星人(プレデター)であった・・・!「ジェイソンVSフレディ」があるのだから、もちろん、「エイリアンVSプレデター」も、ありである。なんといってもプレデターの前作では、彼らの収集した狩りの獲物の中に、エイリアンの頭蓋骨があった。それなら・・と企画されたのが、本作品だ。 さいころから出たこま、であるから、これは最高傑作!というわけにはいかないが、個人的な感慨はとりあえずおいておけば(これについては後で)アンダーソン監督(「バイオハザード」)は、「B級SFアクション」としては合格点の仕事をこなしているように思う。「エイリアン」はそのギガーによるあまりにも美しいデザインから(私は子供のときに映画館で見た「エイリアン」の衝撃を一生忘れはしない)、常に美意識の高い監督をその続編に選んできたが(3はこれがデビューであったデビッド・フィンチャー「ファイト・クラブ」、4はジャン・ピエール・ジュネ「アメリ」である)、なんといっても相手は、あの、B級異星人の王道、プレデターである。最高に美しいクリーチャーと、最高に昔の特撮の面影を残した異星人のヴァーサスB級SFとしては、この監督はまさに適役だったといえよう。 内容的には、人間たちの見せ場があり、プレデターの見せ場があり、エイリアンの見せ場があり、ととにかくめまぐるしい。どれか一点に絞るというわけには趣旨的にいかないから、これは仕方がないことだろう。が、なんといってもエイリアンとプレデターの「関係」(これについては、見ていない方のために説明は敢えてしないが)から設定せねばならないから、めまぐるしさとあいまって、多少分かりづらいものとなっている。しかし、エイリアンとプレデターの迫力ある見せ場はしっかりあるし、楽しめはする。 が、画面としてあまりにも暗すぎる。「ヴァン・ヘルシング」もそうであったように記憶しているが、夜の場面が多い映画というのは、登場人物たちの色がはっきりとしていないと非常に見づらい。ましてや今回はあの「半透明」なプレデターと、「ぬるツヤ」のエイリアンである。残念ながら、その派手な闘いの場面ほど、画面が分かりづらい、というのが一番の難点かもしれない。 さて、最後に私的な感慨で言えば-やはり、エイリアンの扱いだ。「エイリアン」では、マザーは宇宙船を操縦してきたように見えたし、あのときのエイリアンは、獰猛で狡猾、その肉体までも完全な武器である上に知的という、史上最高のクリーチャーであった。それが、2,3と進む上で、なんというか、知能が低下していって、ただの「動物」になりさがっていたのだ。「エイリアンVSプレデター」も、まさにこの「知能の悲しい低下」を受け継いでいる。プレデターにはプレデターの、エイリアンにはエイリアンの知力を見せてほしかったのだが・・「動物の勘」だけで行動しているように見えるエイリアンはもう見たくない、というのがエイリアンファンの私としての感想である。 ストーリーは途中から、「え?」という展開をみせる。「これは、もしかして「第五惑星」か・・?」そんなことを期待しながらラストを見守ったのだが・・。ハリウッドでも、異星人相手でも、人間とはなんと都合のいい生き物であることか。そんなことを考えさせてくれる、映画であった。映画として 6/10B級SFとして 8/10
2004.12.20
コメント(12)
-
「デボラ・ウィンガーを探して」 自分探しで社会批判
TOTOという1980年代を風靡したアメリカのバンドがいる。彼らの代表曲は「ロザーナ」で、当時TOTOファンだった私は、それが、キーボードのメンバーの彼女の名前から取られた歌だと知っていた。ロサンゼルスの新進女優で、ロザーナ・アークエット、という名前だと。 その後彼女は「アフター・アワーズ」「マドンナのスーザンを探して」などでコケティッシュな魅力を振りまいたものの、なんだかパっとせず、「グラン・ブルー」で、"Go, go and see my love"なんてセリフを聞くまでは、彼女が力のある女優だということすら忘れてしまっていたほどだった。 その彼女もいつのまにか40代になり、ドキュメンタリー映画のメガホンを撮ったと聞いたときには、びっくりしたものだ。そしてそれが、この映画「デボラ・ウィンガーを探して」である。 女優は40代になるとハリウッドで急に仕事がなくなる、という。子供にも、パートナーにも、もちろん時間は割きたい。けれど、いい仕事はしたい。ここで仕事を捨てれば、平穏な暮らしが待っているけれど、今まで築いたものも失いたくない。けれど、何の仕事でも、というまでには気持ちを持っていけない-デボラ・ウィンガーは、ある日急に女優を引退した。彼女はなにを捨て、なにを選んだのかーそれを、総勢35人の女優たちの生の声とともに探って行く。それがこの映画でのロザナ・アークエットの「旅」だ。 登場する女優達は、もちろんデボラ・ウィンガー(「愛と青春の旅立ち」のヒロイン役で一世を風靡した)をはじめとして、メグ・ライアン、ホリー・ハンター(「ピアノ・レッスン」)、メラニー・グリフィスやグイネス・パルトロウに、妹のパトリシア・アークエット(「トゥルー・ロマンス」)、ジェーン・フォンダ、シャロン・ストーンなど、主役級の女優たちに加え、どこかで見たことのある準主役級の女優たち(個人的には、テリー・ガーやテレサ・ラッセルを見て声を上げてしまったが)など、とにかく豪華である。女優業を長く続けているからこそ、彼女たちから生の声を聞くことが出来た(そして、それを映画とする許可を得ることが出来た・・こちらのほうの功績が大きいのかもしれない)のであろう。 これは、たとえば、リンダ・マッカートニー(ポール・マッカートニーの故妻で、写真家)の写真が、イギリス音楽陣のそうそうたる顔ぶれの素顔をとらえていることで評価が高いこと、リー・ミラー(写真家)の初期の写真がシュールリアリスムを語る上での大切な資料となっていること、などと同じ、その場にともにいることの出来る人間(この場合は同じ女優であること、だ)の特権を最大限に利用した芸術作品である。 われわれが女優たちの生の声を聞くとき-特にそれが女性であればあるほど、彼女たちがハリウッドをしょって立つ存在でありながら、まるで日本に住んでいる普通の女性と同じ悩みをかかえていることがわかる。そして同時に、女性が男性に「こうあってほしい」と投影されるのと同種でもっと強力なもの-スターであるために投影されるイメージーとの狭間にも苦しんでいるのだ、と。アークエットは、自分という一女優の悩みが、実は全ての女性に共通の悩みであることを暴き出していく。「全ての女性は女優だ」・・「オール・アバウト・マイ・マザー」のアルモドヴァルの言葉が、新たな意味を持つ瞬間だ。 これは、アークエットの自分探しの旅であり、われわれ観客の自分探しであり、そして同時に、「自分探しの旅」の形を借りた、一方的に女性のイメージを決め付けて映画を製作しようとする(女性は若い、か年寄りか、の二つの範疇でしか描かれない)ハリウッドへの、そして社会への、痛烈な批判映画でもある。 ねぇねぇ、あの有名女優さんが、私生活を語ってるー!そういった視点のみではなく、女性全体に共通する問題と、そのさりげなくも痛烈な社会批判のほうに、是非耳を傾けてみてほしい映画である。
2004.12.19
コメント(8)
-
「ドグマ」 聖書でやおい?
「やおい」とは、「ヤマなし、オチなし、イミなし」の、アニメや小説、映画など既存の作品を主に同性愛を中心にパロディ化したものと記憶している。映画「ドグマ」は、同性愛ではないにしろ、この、「やおい」の基本体質をまさに兼ね備えたB級映画-しかも、ベン・アフレック、マット・デイモン、サルマ・ハエックにアラニス・モリセット、アラン・リックマンといった豪華メンバーをそろえてのだ-であり、そして、その元となった既存作品は、あの、世界で一番のベストセラー、「聖書」なのである。 ニュージャージー州のカトリック教会。教会のイメチェンにと、枢機卿は、教会の門をくぐればどんな罪でも許されるという「特別の日」イヴェントを発表。 これを知った、神に逆らって2000年間ウィスコンシンに追放されていた、天使のバートルビー(ベン・アフレック)とロキ(マット・デイモン)は、このチャンスを利用し自分の罪を清めて、天国へ帰還しようと企む。 が、これが成功すると、キリスト教の教義(ドグマ)は根底から覆されてしまう。神は天使(アラン・リックマン)をつかわし、ある女性を選ぶと、彼女や予言者、女神(サルマ・ハエック)とともに、二人を阻止しようとするが・・。 基本は天使と聖書のパロディだ。聖書からの引用もふんだんにあるし、なんといっても「ドグマ」であるから、それを最大限に利用したストーリーである。「聖書」をもとにとことんパロディしたこのB級やおい風映画は、冒頭に夢のように長いお笑い「おことわり」がある。キリスト教に悪意を持っているのではないこと。神を冒涜しようとしているのではないこと・・とせつせつとひょうひょうとえんえんと続くおことわりは、おそらくこの映画最大の山場だ。 そして、あとは御気楽な登場人物たちに、御気楽なストーリー展開。くだらないけれどそこそこ笑える御気楽コメディ、といったところだろうか。 しかしこの映画は私に、非常に興味深い感慨を抱かせてくれた。 日本ではキリスト教は、それを宗教としているのが人口の約2パーセント以下であり、しかも、その学歴の平均値は、一般の日本人よりも高く、どちらかといえば「高学歴の宗教」なのだそうだ。また、2パーセント以外の人間がキリスト教についてしっているという場合、そのほとんどは学問として、知識と知っているということになるし、特に詳しく、「ドグマ」まで知っている、となれば、これはもう非常に詳しくキリスト教を「学んだ」(自分でにしろ、どこかでにしろ、だ)人、ということになる。ということは、日本人でこの映画を、既存の作品を軸とする本当の「パロディ・やおい」として楽しめる人というのは、おそらく日本の人口の一割程度というところだ。 けれど、この映画「ドグマ」は、B級娯楽映画で、アメリカの一般的な庶民派コメディ映画なのだ。「ドグマ」で語られる宗教についてのセリフは、私にはときに知的にすら聞こえるが、それは、「毎週教会になんとなく行く」キリスト教が主要な世界では、非常に一般的で、日常の普通の会話なのである。彼らにとっての聖書は、「やおい」になるほど、馴染みのある、よく知っている物語なのだ。 もちろん上に書いたようなことは、私も分かっていたつもりであったのだが、この映画を見てつくづく、その「浸透」具合に感心した・・・・と、そんなことばかりが心に残った、この映画であった。映画として 5/10やおいとして 7/10
2004.12.17
コメント(10)
-
「ルナ・パパ」 奇想天外・荒唐無稽・抱腹絶倒
1999年のドイツ=オーストリア=日本合作の、東京国際映画祭最優秀芸術貢献賞受賞作品である。舞台はタジキスタン、砂漠に囲まれた典型的な田舎町である。戦争で頭がおかしくなった兄(モーリッツ・ブライブトロイ・ラン・ローラ・ラン」「ES」のドイツ人俳優)の面倒を見ながら女優を夢見る、歌と踊りが大好きな少女マラムカットは、満月の夜、お互い顔も見えない中で俳優と名乗る男と幻想的に結ばれる。ほどなくして妊娠に気づいた彼女は村の医師を訪ねたものの、医師は偶然にも流れ弾に当たって死亡。仕方なく父親に妊娠を打ち明けると、「父なし子」は恥だから「父親をさがしゃいいんだ!」と息巻いた父親先導に、家族三人車でほうぼうを「父親」探しで奔走することになるが・・・・奇想天外・荒唐無稽・抱腹絶倒-このそれぞれがあてはまる映画なら、またこの中の二つがあてはまる映画なら、いくらでも思いつくかもしれないが、この三つが同時に、となると、真っ先に思い浮かべる映画がこの、「ルナ・パパ」である。 もちろん香港映画やインド映画のあの「びっくり箱」的なおもしろさの映画はいくらでもあげられるかもしれないが、そのドタバタと矢継ぎ早におこる出来事の中に、さりげない多くのテーマ-戦争や、紛争や、村共同体の狭い価値観、女性差別など-を盛り込みつつ、ファンタジー性を軸としながら、上の三つを満たす映画、となると、まず「ルナ・パパ」しかないのではないか、と思わせられるほどだ。 これだけの盛りだくさんであるから、映画のまとまりであるとか、統一感であるとか、そういったものは確かにかける。私もはじめてみたときは、偶然につけたBSで口をあんぐりとあけたまま、最後まで目を離せずに見てしまった。なんでそこまで次々といろいろなことが起こらなければならないの?この人たちどうしたの?そして何より、このラストは、ぶっ飛びすぎだろう・・と。けれど全編そのどたばたを笑いながら、そして手に汗を握りながら見ていると、この映画にちりばめられたテーマははっきりとした色彩をはなってくるし、ラストもより意味のあるものとなってくるのだ。紛争地帯でありながらイキイキと過ごす人々。その中でも夢を見る少女。戦争で精神を病みながらも、「真実」を見抜く力がある兄に、愛情深いながら典型的な男性中心の村社会意識を持つ父親。「差異」や共同体のルールから少しでも逸脱するものを決して許そうとしない村社会の人々、そしてそれにはまろうとしてもどうしてもはまれない少女と、その兄・・。これを美しくも暗く重くしようとおもえば、いくらでも映像化出来る。けれど、「ルナ・パパ」は、このテーマをあくまでも「荒唐無稽・奇想天外・抱腹絶倒」に料理した。タジキスタンをバックに映像はひたすらに美しく、テンポは信じられないほど軽快で(これは、先日書いたカンピオン監督に見習ってもらいたいほどだ)俳優たちはイキイキと演技をしている。先の三つだけにとどまらないこの映画の「びっくり箱」は、パンドラ・ボックスよろしく、箱から全てが出てしまった後でも、そこになにか大事なものが残っている・・そんな観を抱かせる、映画なのである。レンタル店で借りるもので悩んだときには、是非お奨めしたい一品である。映画として 7/10実のあるビックリ箱として 10/10
2004.12.15
コメント(3)
-
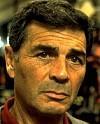
「ジャッキー・ブラウン」 役者の輝きとは
クエンティン・タランティーノ1997年の作品である。 黒人スチュワーデスのジャッキー・ブラウン(パム・グリア)は、密売人の売上金をメキシコからアメリカに運ぶ副業を持っていた。だが、ひょんなことから逮捕され、捜査官レイ(マイケル・キートン)に密売人オデール(サミュエル・L・ジャクソン)の逮捕に協力するよう強要されることになる。保釈金業者(ロバート・フォスター)を巻き込んで、げんナマをめぐってのだましあいが幕を開けた・・・ジャッキー・ブラウンを演じるのは、アメリカで70年代にカルト的B級女優として人気を博したという、パム・グリア。私も若い頃の動く彼女はまだ未見であるが、写真でみても、スタイルから何から本当に美しい、超B級女優さんであった。当時の作品「フォクシー・ブラウン」や「コフィー」では、これでもかというほどのお色気を、彼女中心に展開する話の中で振りまいていたらしい。 40をすぎた彼女には、その魅力は、もはやない。タランティーノが成功をしたからこそこの企画も通すことができたのだろう、と言いたくなるほどだ。 が、ストーリーはエルモア・レナード原作であるから、手の込んだ物語であるし、もちろんタランティーノぶしも光っていて、楽しめる。 脇を固める俳優陣もまたすばらしい。密売人役のL・ジャクソンは、怖いだけではなく「少し頭が悪い」風の悪人を軽妙に演じているし、その相棒を演じるロバート・デ・ニーロは、もちろん顔の表情ひとつで刑務所あがりのこの男の「びびり」を完璧に演じてみせる。ジャクソンの愛人役のブリジット・フォンダは、父親の出ている映画を見ながら(この辺がタランティーノのにくい演出だ)、あくまでも「安い」女ぶりをあますことなく発揮している。キートンの捜査官も、「あまちゃん」な雰囲気を実にうまくかもしだしている。 しかしこの映画の脇役で最も輝いているのは、なんといってもロバート・フォスターという熟年の俳優である。彼はどちらかといえばB級映画の脇を固めてきた長いキャリアのある俳優であるが、その、たたずまいがいい。まなざしがいい。セリフがたくさんあるわけではないのだが、さも物腰の柔らかい保釈金業者(保釈金金融業・保釈人が逃げないよう監視まで行うハードな仕事である)でありながら、危険を冒してきた男のハードボイルドな輝きを瞳の奥に、ふと、垣間見せる。同時に、失った若さや恋への憧れ、といった淋しい熟年男の日常をそのシワの中にただよわせる。この存在感は、圧巻である。 作品を見終わったあとにしったのだが、この作品で彼は、オスカーの助演男優賞にノミネートもされたのだという。この映画最大の見物はロバート・フォスターだ、といっても過言ではないように思う。 さてこういった俳優たちに囲まれると、パム・グリアの見所は全くといっていいほどない。タランティーノはいつものオマージュで、ひときわ彼女を際立たせようと演出をするけれど、いかんせんかつての彼女の輝きはもう失われているのだ。それは彼女が年をとって醜くなったからではない。彼女は今でも美しいのだが、輝きがない。たとえば年をとってからのほうがずっと輝いている女優・・ウーピー・ゴールドバーグでもいい、ダイアン・キートンでも、ヘレン・ハントでもいい・・・そういった女優たちにあって彼女には無いものがあるのだ。その物悲しさ。それがこの映画の第二の見所なのかもしれない。ロバート・フォスターがパム・グリアを見初め、その後姿をそっと見つめるその目・・・それがタランティーノ本人の、現在の彼女への答えであったのかもしれない。クライム・アクションとして 6/7タランティーノ・ムービーとして 7/7
2004.12.12
コメント(2)
-
「イン・ザ・カット」 サスペンスにフェミニズムを
(批評ですが、ネタバレはしていそうでしていません)In The Cut-ホームページによれば、語源は女性器であり、転じて、秘密の部分、安全な隠れ場所の意味であり、また、ギャンブラーが他人のカードを盗み見るときに使う言葉でもあるらしい。 タイトルどおり、のっけから女性器のスラングの話で始まるこの映画は、「フェミニズム」の映画である。 たとえば、フェミニズムの先導的学者アドリエンヌ・リッチ。彼女が女性器を語るとき、それは男性に闘いを挑むときだ。男性は非常にしばしば自らの生殖器について口にするが女性はめったにそれを口にしない。(同時に、男はそれを字義通り口にするよう要求するが、女性はめったに要求しない、という意味でもある) また、フェミニズムでしばし語られるのは、男性器なしで女性は容易に快感を得ることができるということだ。女性にとっての男性器は、男性がしばし女性に言うような「不可欠」なものではないという事実。これは実はフェミニズムでしばしば取りざたされることである。 このフェミニズムの性的な一面を知っていると、このサスペンスはそれだけでおのずと犯人が、わからないまでも、そうでない人間を非常に最初から除外できる。つまり、上で書いたことを知っている男性は犯人ではない、ということだ。 そして、また、そういったことを念頭においてみれば、この映画が単純なサスペンスではなく(もちろん、勘の鋭い人はフェミニズムについて全く知らなくても容易にその真意が分かると思うが)、連続猟奇殺人や、サスペンスの構図の中に、男女の格差を見出したがためにその体裁を借りた作品であることもすぐにわかるであろう。 映画は「ケセラセラ」という古いポップスからはじまるが、この歌詞は少女が大きくなったときに、かわいく、また愛される人になるかしら?(そうなりたいわ)という、一般に女性に押し付けられがちな「理想的女性像」を歌っている。そこに登場するのは、主人公の妹だ。彼女は性的に奔放な女性だが、愛し下手で、結婚願望も強い、まさに「ケセラセラ」の歌の通りであり、またどこかでその歌にたどり着くはずの道を踏み外してしまった人間である。 その彼女が「結婚への憧れ」をモチーフとしたブレスレット(乳母車や教会、赤ちゃんの飾りなどがついている)をプレゼントするのは、大学で国語(これを「英語」と訳す字幕は私はいただけないと思う。黒板に書いてあるのは文学的事項であって、英語という語法ではない。日本の国語の授業と同じ、読解の授業である・ちなみに内容はヴァージニア・ウルフの「灯台へ」と意識の流れについてであった)を教える姉フラニー(メグ・ライアン)である。ちなみに、英文学で「エブリマン」という人間そのものを描いた古典があるが、この、対照的な二姉妹の名字はエブリーという、二人で全女性を示唆する名前となっている。 姉のほうはタイトルそのままの、自分を外界から、また自分の無意識の欲望ーそれは性的なものとして比ゆされるがーから隔離し、「言葉」という隠れ家に逃げ込んでいる女性である。結婚や子供を作るということはもちろんのこと、数度寝た相手も彼女には用のない相手だ。彼女は全てから、そして自分からも自分を遠ざけている存在だ。その彼女が偶然居合わせたバーで見た女性が殺され、その容疑者らしき男性を見ていることから話は始まり、絡んでくるのが、彼女に「イン・ザ・カット」してくる刑事、次々と続く連続殺人と、刑事と彼女の性的な駆け引き、やりとり・・といった、プロットだけ書くとお決まりのサスペンスの構図である。「モンスター」の主人公は実在の連続殺人犯であったが、世界的に怨恨からではない連続殺人犯、ましてや猟奇殺人犯となると、女性の犯人というのはめったにいないそうである。 それは映画の世界でも同じだ。そこそこ映画を見ている私が思い浮かぶ連続殺人の女性犯は、「モンスター」と「シリアルママ」、レベッカ・デモーネイの某作品くらいしかぱっとは思い浮かばない。一方現実にも映画にも、膨大な数の男性の連続殺人犯がいて、彼らの殺害対象は女性であり、少女であり、そしてしばしば彼女たちはこれでもかというほど切り刻まれる。 ジェーン・カンピオンは、この犯罪の構図、ひいてはサスペンス・ホラー映画の構図に、男性と女性の「性の絡んだ日常的光景」の象徴を見たのだろう。性行為は時に結婚や愛をちらつかせながら男性が主導で行われ、女性の欲望よりも常に男性の欲望が優先される。使われるだけ使われた女性は、女性が「いるべき場所」、洗濯機や、庭いじりの場や、娼館へと取り残される。そして女性の欲望は口にされることのないまま、葬り去られる。 もちろん現代はそんな時代ではないという反論が出そうではある。女性も性的に男性同様奔放だし、強い女性も多くて家庭では男性を組み敷いているのが普通だ、と。ある部分では確かにそうかもしれない。が、たとえば性的に奔放な女性は「ふしだら」という蔑称があるのに、それが男性に使われないのはなぜか?女性が大勢の人の前で女性器についての話をしても、冷たい目で見られることはなく、男性がそうするときと同じように、「あいつ、おもしろいよなぁ」と言われるだけで果たしてすむだろうか?と問うたら、どうであろうか。「そう」でない時代は、まだ来ていない。だからこそこの映画のために、メグ・ライアンは脱ぐことを決めたし、ニコール・キッドマンは製作を買って出たのだ。 映画の中ではさまざまな象徴が入り混じって使われる。主人公の後ろを通り過ぎる「母の日の花束」、「何かから逃げる女性たち」、さしはさまれる主人公の両親による「恋愛と結婚の夢物語」や、地下鉄の中の詩。 「めぐり合う時間たち」の中のあの深い川であり、「テルマ&ルイーズ」ででてくるあの断崖でもある「カット」の中に入り込み、その中を模索することで男女間の新たな関係を模索しようとする、フェミニズム映画としてのこの作品は、そのテーマを汲み取るべき佳作であり、及第点であろう。 が、残念なのは、そのストーリー展開のキレと、カンピオンの「都会を撮る技術」の下手さである。脚本段階では本当にすばらしい作品であったのかもしれない。が、カンピオンの映像化への力量不足(大自然はあんなに上手にとっていた彼女であるのに!)が足を引っ張ってしまった。その点が「サスペンス」として見た場合のどうしようもなさ(しかし普通に見た場合散漫ではあるものの犯人はそこそこわかりづらいとは思う)や、映画としての散漫さとなってしまったようである。 せめてサスペンス映画の「テンポ」だけでも学んでくれていたら、一流のサスペンス映画であり一流のフェミニズム映画でもあるものが出来上がっていたかもしれない、と思うと、本当に残念でならない。 フラニーが、ウルフ作品の主人公がたどり着けなかった「灯台へ」いくとき、何を見つけ、どう結末を付けるのか。女性には、どうか途中で投げてしまわずに、その真意を汲み取ってほしい映画である。追記: 主人公が愛する刑事役がセクシーでないのが一番の失敗に思えるのだが・・・。
2004.12.09
コメント(14)
-
「ポーラー・エクスプレス」 動く油絵式ジェットコースター・ムービー!
「ポーラー・エクスプレス」は絵本作家クリス・ヴァン・オールズバーグ原作(彼は映画「ジュマンジ」の原作者でもある)の「特急北極号」の映画化である。ハリー・ポッターが実写で(もちろんCG合成だが)できる時代であるから、実写でもゆうに可能な映画化であったのを、トム・ハンクスとロバート・ゼメキス監督が、「原作の幻想的な雰囲気をそのまま残したい」(原作はパステル画の実に不思議な世界観を持った絵本である)と、登場人物にいたるまで全編フル・CGで臨んだ、目を奪うほどの意欲作である。 使われた技術は、ディズニー映画などが最近とりいれている「モーション・キャプチャー」という技術。これは、ボディースーツに球体(これで光=動きの方向を感知)がたくさんついたものを着用し、ハメコミのブルーバックで演技をすると、パソコンがその動きの全てを3Dで取り込み、原画にインプット、原画が俳優のした動きどおりに動くようになる、といういわば新しい形の「アニメーション」である。このやりかたであれば、撮影用の(映画には反映されない)セットさえ大きくすれば、大人が子供を演じることも可能である--ということで、今回はトム・ハンクス本人が主人公の少年に車掌、サンタクロースなど5役を演じるという離れ業を見せている。 ディズニー映画などの省略化された戯画風のマンガではなく、リアルな油絵風の人物画にこのモーションキャプシャーを利用しているため、登場人物たちは絵でありながら本当に生きているかのような動きや表情を見せているのが、この映画の見所のひとつである。また、もちろん「北極号」はまさに目の前を駆け抜ける機関車の風格そのままに所狭しとスクリーンをかけめぐるし、しんしんと降る雪の情感などは実写さながらである。この映画の最大の魅力は、ファンタジーやSFに必須の、その「リアルなアンリアルさ-アンリアルなリアルさ」である。実物のようでありながら絵であると言うその映像は、必見である。 最も楽しいシーンは「ホットチョコレート」が車内の子供たちに振舞われるシーンだが、これももちろんモーション・キャプチャーでとられたもの。実際にダンサーたちがやった動きだとおもって見ると、ただのCGではない迫力が余計に楽しめると思う。ストーリーは・・サンタを疑い始めた10歳の少年。イブにつきもののサンタさんへのお夜食の準備も妹に任せ、猜疑心一杯で床に就いた。サンタなんていないんだ・・・・と、そこへ機関車独特のあのシューシューという轟音が。あわてて外に出てみると、そこにいたのは黒くて大きな機関車「ポーラー・エキスプレス」と、口ひげの車掌。すでに中にはサンタに会いに行くためのこの列車に乗り込んだ、たくさんの子供たちがいた・・・。 私個人の話をすれば、始めてみた映画が「恐竜百万年」(世界で最初の特撮映画のひとつである)であり、「シンドバッドトラの目大冒険」が生涯の一本の人間であるから、CGやSFXものというのは見逃せない映画だ。しかし実は、あまりアニメ系CG作品に興味がないから、「ロジャーラビット」も見に行かなかった。「シュレック」は、よくできているけれど、やはり絵がね・・・と思ったものだったが、この「ポーラー・エクスプレス」には、文句のつけようがないようにおもう。いや、もちろん、来年かさ来年に映画化されれば、おそらく表情までまるで完璧な生きた人でありながら油絵風である、というこの雰囲気をより正確に、より美しくCG化していたのではないかという欲は残るが、それを押さえれば、これ以上の作品は今までに見たことがないほどのできばえであるように思う。 幻想的で美しく、絵であると分かるのに、次の瞬間には忘れてしまう・・そんな映像世界なのだ。登場人物たちはどうしてもCGくさいところがあるのだが(そこに私の欲がうずくのだが)、少し離れてみたときのたたずまいは生きた人間そのままである。 そういったCG/映像的すばらしさに加えて、もちろん原作から引き継がれたテーマ(これについては弱めにさっぱりと主張されていて、そこがごり押しになっていないところはある意味評価していいのかもしれない)も描かれているし、ロバート・ゼメキス監督作品ならではのほのぼのとしていながら少しハラハラさせる盛り上げ方(「フォレスト・ガンプの羽が好例か)、ポーラー・エキスプレスが巻き起こす波乱万丈のジェットコースタームービーさながらの展開、など、他の見所もしっかりと作られている。大好きな絵本を動かしてみた・・そんな大人たちの子供心が泣かせる、作品である。クリスマスのこの時期に、大人が見ても、子供が見ても、楽しめる「美しく楽しい」一本であり、「MR.インクレディブル」の陰に隠れてしまうにはあまりにももったいない作品だと太鼓判を押しておこう。映画として 8/10子供映画として 7/10CG映画として 9.9/10................................追記: モーションキャプチャーで撮られたエルフの中に、スティーブン・タイラー(エアロスミス)がいます。ちなみに、黒人の少女を演じたのは、マービン・ゲイの娘、ノーラ(マトリックスリローデッド等の女優)
2004.12.06
コメント(6)
-
「白いカラス」 表現者からの控えめな意見
原作は、アメリカの誇る文豪フィリップ・ロス原作で、フォークナー賞も受賞している[Human Stain] (映画の原題も同じである)である。 1998年、アメリカ・ニューイングランド。大学の学部長コールマン・シルク(アンソニー・ホプキンス)は、新学期以来一度も自分の授業に顔を出さない見たこともない生徒を「彼らはそもそも存在するのかね?幽霊(spooks 俗語では黒人の蔑称)なんじゃないのか?」と皮肉ったことが、PC (Political Correctness 政治的・道徳的正確さ)に反するとして糾弾を受け、辞職。その顛末を聞いた妻は憤慨から心臓麻痺で死に、孤独な身の上となる。 スランプ中の作家ザッカーマン(ゲイリー・シニーズ)と知り合いになった彼は男の友情を深めて行く一方、車の故障から乗せた郵便局のアルバイト女性フォーニア(ニコール・キッドマン)と知り合い、彼女を愛するようになる。しかし彼女にはつきまとう前夫(エド・ハリス)や、隠された過去が、そしてコールマン本人にも、誰にもいえない秘密があった・・・ 映画としてのつくりは、なぜそのシーンにそれだけの時間を割かねばならないのか?や、なぜそんな演技をさせねばならないのか?といった多少の疑問を抱かせる点もある。エピソードとエピソードの連結も弱く、特にフォーニアの行動は、見て少し考えただけでは理解できない点が多いなど、映画としての弱点はここそこに見える。 ホプキンスとキッドマンの演技は、すばらしいのだが、キッドマンの「なりきった」演技は、賛否両論の分かれるところかもしれない。 しかし、この映画にはしっかりとした原作があるのだ。なぜこの映画がいい映画であるのかといえば、それは原作がすばらしいからに他ならない。それが弱いエピソード連結や分かりづらさといったものの全てを凌駕してしまうのである。 原題であるHuman Stainとは、人間のしみ、すなわち人間に一度ついたら消えない傷であり、過去のことである。邦題の白いカラス(センスはないが、言いえて妙ではある)とは、なぜ「白い」なのかはレビューであるから伏せておくにしろ、フォーニアが時節語りかけに行くもとは野生で今は人に飼われているカラスからくる。漆黒であるカラスには、しみのつくことがなく、小さな囲いの中で暮らすそのからすは、汚れることがない。傷を受けることがない。 事故で二人の子供を焼死させた罪を、自分を大切に扱わないことで償おうとしているフォーニアと、ある理由で過去に生まれ育った場所と家族を捨てたコールマンは、もともとアメリカの両端に住む出会うことのない二人であったが、肉欲から関係をはじめ、お互いの傷をすりよせることで徐々にお互いの傷を癒していく。 この作品で描かれるのは、肉欲であり、老人の性であり、愛であり、人種問題であり、DVであり、犯罪であり、社会的な格差である。現代アメリカに巣食う全ての問題が、このストーリーの中凝縮されているのだ。そしてその全てが1998年という年-マスコミはクリントン大統領の「不適切な関係」に終始し、一方PCについて騒ぎ始めた頃であった-を舞台としているのである。以前、親交のあった絵本作家からこんな話を聞いたことがある。- 絵本原稿に「魚屋さん」と書いたら、出版社から、PCにひっかかり問題となる可能性があるので、「鮮魚店」にするよう言われたよ。子供たちにも、僕にも、「魚屋さん」は、親しみを込めた呼び方でしかないのにね。-その後彼がどうしたのかは残念ながら知らない。しかし私は、映画にも登場し、他のロス作品にも登場する作家、ザッカーマンに、ロスと、その絵本作家と、そしてたくさんの表現者たちを見たように思う。ロスは言う。クリントンのスキャンダルにあけくれ、それに湧き上がる人々たち。そして同じ人々が、PCについて常に目を光らせ、つねに語意的政治的「正しさ」を追求しようとする。けれど、アメリカには、そしておそらく世界には、クリントンのスキャンダルや、PCなどよりも、これだけ多くの語るべき問題がある。私(=ザッカーマン)は、書きたくても書けない。PCという検閲に近い了解が、私の書こうとしているこの本当に大切な、人間の問題を、ありのままに、そのムードそのままに書かせてはくれないからだ・・・その彼の心のうちを、そして「表現者」全ての心のうちを、ロスの作家としての類まれな手腕でひとつの物語にした。私はそれが、[Human Stain] ではないかと、思っている。映画として 7/10原作も含めた作品として 10/10追記: stainは、「染まる」と言う意味もある。PCによって一様の色に「染まってしまう」Human、の意味もあるのではないかと思っている。
2004.12.01
コメント(6)
-
「下妻物語」 たいへんよくできました
嶽本野ばら原作の不思議小説の映画化である。 レースのパラソルにボンネット、ロリータファッションに身を包むロココ命の少女、桃子(深田恭子)。彼女はコテコテのチンピラ家庭出身だが、「心はいつもお仏蘭西」とばかり、現在は茨城県下妻というど田舎で暮らしている。 大好きなロココ服を買うために彼女は父親がかつて売っていたベル○ーチのばった物を売ることにするが、そこに現れた客は、バリバリのヤンキー少女、いちこ(土屋アンナ)。嬉々として買い物していったいちこであったが、なぜかその後も、いちこは桃子の家を訪れるようになる・・・。 姿も考え方も正反対の二人が親交を深めていく、簡単に言ってしまえば青春物語なのだが、なんといってもロココ少女とヤンキー少女の出会いは、ミシンとこうもり傘の出会いほどの衝撃である。 原作どおりの極端で細かなキャラクター設定に(それは姿だけでなく、二人の生育暦にまで及ぶ)ミュージカル風、お仏蘭西風、アニメ、ビデオカメラ風、といったさまざまな形態をさしはさんで展開するテンポの良いストーリー、そしてパチンコ屋だろうが田んぼだろうが、美しい色と洒落たアングルの映像。映画として、多少冗漫なところはあるものの、非常に良く出来た作品である。もちろんいたるところに笑うところあり、(いちこの頭突き、ジャスコ!など)ハラハラあり、感動あり、とにかくなんでもありで、またそれが、おいしくてお得なお菓子の詰め合わせ(マドレーヌとうまか棒が一緒に入った箱ではあるが)のようにうまく詰まった作品なのだ。 主人公の二人も良くがんばっている。深田恭子は、その「語り」の下手さがこの作品一番の欠点となっているのだが、ラストの山場は、やはり彼女のあの「目」あってのものだと思うから、何も言うまい。それに、ロリータファッションと、「超個人主義」をイヤミ無く演じられるのは屈託の無いアイドルならではだ。土屋アンナのヤンキーはこの上なくすごみがあって、おそろしいほど三白眼で、そしてかわいらしい。話し方からつばの吐き方まで、見事になりきったということで、この映画最大の見物だろう。 ゲスでどうしようもない世界(と桃子が思っていた)からの逃避のためにロココという夢の世界に浸り、超個人主義を貫き何者にも心を動かされないももこと、普通の家出身でありながらヤンキーへと身を投じ、何事にもあつくなり恩義を重んじるいちこの二人は、両極端であるからこそお互いから何かを学び、成長して行く。その様を、涙と笑いと、たくさんの「はぁ?(笑)」で見せてくれるこの作品は、いくつかの欠点はあれど、本当に「よくできました」な映画だと太鼓判を押そう。中島監督の、次作に期待である。映画として 8/10コメディーとして 10/10
2004.11.28
コメント(6)
-
「恋愛適齢期」 一筋縄ではいかない恋の行方
ダイアン・キートンにジャック・ニコルソン、脇役にキアヌ・リーブスという豪華メンバーで話題を呼んだ、「恋愛適齢期」(Something's gotta give)である。 ハリー(ニコルソン)はすっかり熟年の男性だが、いまだに未婚のまま、若い女性としか付き合わないのをモットーとするプレイボーイ。新しい彼女マリンと彼女の母親の持つ海辺の別荘で甘い週末を過ごすべくいそいそとやってきたのもつかの間、仕事に来ていたマリンの母エリカ(キートン)と遭遇、ともに週末を過ごすことになるが・・・。 ハリーとエリカがお互いの「作った顔」への嫌悪感から「素の顔」に興味を抱き、最終的に愛情をはぐくんで行く様子を、洒落た会話と軽妙な笑いを通して、ニコルソンとキートンの「老いらくの」さらっとしていながらも熟練したコメディアン・コメディエンヌぶりで魅せてくれるのが、この映画である。 この映画は、二人の有名俳優が海辺の家でさっさと恋に落ちそのままハッピーエンド、という単純なストーリーではない。劇作家エリカのファンであったことから彼女を愛し始める青年医師ジュリアン(キアヌ・リーブス)や両親の離婚の心の傷が大人になってからの恋愛にまで影響している娘のマリンなどをからめつつ、嫌悪と惹かれあいを繰り返す紆余曲折の末、それぞれへの「思い」によって主人公たちが大人の成長を遂げる、という、非常によく練られたプロットをもつ一級の「劇」なのだ。 脚本・監督・製作をかねたのは、「プライベート・ベンジャミン」「赤ちゃんはトップレディーがお好き」「花嫁のパパ」「ハート・オブ・ウーマン」などの脚本で知られるナンシー・マイヤーズ。今回の作品は、「女性であること」や、「男性と女性の感情的な行き違い」などを常にテーマにしてきた彼女のそれまでの集大成ともいえる。劇作家であるエリカが自分の周りの人間を、ハリーへの腹いせから舞台にしてしまうエピソードなどは、まるで現実と虚構が交錯するようだ。 映画のラストには、実際の名前や実在の人物と類似した点があっても、この物語はフィクションであり・・といったことがつらつらと出てくることを考えても、この作品がマイヤーズ(もちろんエリカとほぼ同い年である)の実人生とかぶるのではないかと思うと、なかなか違う意味でも楽しめる作品ではないかと思う。 また、この映画のもうひとつの楽しみは、娘マリンの勤め先があのオークションの老舗クリスティーズであり、エリカやハリーの家に飾られた美術品が美術館や個人蔵の一流品であることなど、そのラブコメディーの必須条件である「センスのよさ」もまた大人味に手を抜いていないことであろう。 残念なのは、マイヤーズ本人がセレブだからなのか、非常に「リッチ」な世界での恋物語であるということか・・・いや、だからこそ、大人の夢物語としても人気の高い作品なのかもしれない。いずれにせよ、そのよく練り上げられたプロットと、俳優陣の軽妙な演技にと、注目すべき作品であるのは間違いない。映画として 8/10
2004.11.26
コメント(6)
-
「僕は怖くない」 映像と音楽で語る社会派叙事詩映画
ガブリエーレ・サルヴァトーレス監督(「エーゲ海の天使」1991でアカデミー外国語映画賞を受賞)の2003年監督イタリア作品である。原作は同名のニコロ・アンマニーティーの小説で、脚本も本人が担当した。 70年代イタリア南部。美しい麦畑に囲まれた5軒からなる小さな集落で暮らす黒髪の少年ミケーレ。彼はふとしたことから、村のはずれの高台に深い穴を見つける。そしてそこにいる、脚輪をはめられた少年を・・・。 これは映像と音楽で見せる(魅せる でもある)映画である。原作のテーマとしてある「穴」の、70年代に特に増大したというイタリアの社会の穴、人間存在そのものの「穴」といった思想的な意味は、その映像を見ているときには思い起こされない。美しい草原と、ぬかるんだ暗い穴や、無邪気ながら大人社会をどことなく模倣した子供たちの遊ぶ風景と、なにかうらぶれたやりきれなさを抱えた大人たち、穴の外にいるミケーレと中にいる少年、といった意図された対比や、主人公の母親や父親のセリフに細かにちりばめられた深い意味に気が付くのは、ラストで一気に見せる衝撃的な展開が過ぎ、そのあまりにも美しい映像と音楽が終わってからである。 主人公の二人を演じるのはオーディションで選ばれた少年たちで、彼らが実に自然に呼吸をするような演技を見せてくれている。特にミケーレを演じるジュゼッペ・クリスチアーノは、大人の社会を垣間見てしまったために子供の無邪気な世界へと戻れなくなってしまうミケーレの心境を、遠くを見るその視線ひとつで語る逸材であり、将来が期待される。 音楽はイタリア音楽の新鋭エツィオ・ボッツオ。ペルトとナイマン、グレツキなどの現代音楽を優しく解釈したようなその聴きやすくもミニマルな音楽は、黄金色がどこまでも続くイタリア南部の風景や、少年たちの無邪気な笑い顔と溶け込み、この映画をひきたてている。一度目はその映像と音楽に身を任せて主人公の優しさとストーリーの意外な展開を楽しみ、二度目にその背後のイタリアにおける社会的な意味をじんわりと考えながら鑑賞する。そんな楽しみ方を薦めたい映画である。映画として 7/10原作として 8/10映像と音楽として 10/10
2004.11.25
コメント(9)
-
SAW 「ソウ」 無痛社会の激痛映画
サンダンス映画祭で セブン meets CUBE として話題をさらい、オーストラリアの脚本・監督のマイナー作品でありながら、全米2000館公開の大ヒット作品となった作品である。 薄汚れた白タイルの老朽化したバスルーム。医師のゴードンと、ごく普通の若者アダム(脚本家本人)は、そこで覚醒した。どちらも片足を太い鎖でパイプに繋がれ、身動きがとれない。部屋のほぼ中央には、頭部を撃ち抜いた死体が転がっている。 全くの不可解な状況で、ポケットから見つけたテープを再生すると、生き残りたければ、6時間以内に相手を殺さなくてはならないと告げる声が。張り巡らされた死の策略。しかし、医師には、犯人の心当たりがあった・・。 この映画の何よりも上手なのは、この、監禁されたバスルームの撮り方である。薄汚れた白いタイル。今にでもにおいだしそうなヘドロでいっぱいの便器や、バスタブ。この部屋に監禁された男たちへ、テープや手紙で命令が下る。タイムリミットのあるそれに従わねば自分たちはおろか身近なものたちまで死に至るというその脅迫は、薄気味が悪くナンセンスである。 たとえば糸のこぎり。彼らは鉄の足輪でつながれているが、この足輪はのこぎりでは切れない。逃げたかったら、脚そのものを切り落とさねばならないのだ。残虐な神が支配するこの白い部屋では、肉体的・精神的苦痛こそが愛される。 ストーリーが進むにつれ、観客たちはなんとなくではあるが、なぜ彼らが「選ばれた」のかが見えてくる。(ここがCUBEとは大幅に違う点だ)ある意味で、そしてもうひとつの意味で。合間には、同じ犯人が起こした数々の犯罪風景がさしはさまれる。数分で頭蓋骨がはじきとばされる拘束具をつけられた女引火剤を塗りつけられ、ろうそくのある部屋に監禁された男かみそり状のワイヤーの中に閉じ込められた男 彼らがなぜそこにつれてこられたのかを、犯人を追う刑事(ダニー・グローバー)とともに追うとき、この映画はサスペンスであり、彼らの死に様を目の当たりにするときはホラーであり、強烈な音楽と、際限の無いフラッシュバック映像をこれでもかとみせられるときのこの映画はMTVそのものだ。どこまでも「逃げ場がなく」どこまでも「痛い」この映画は、その隙の無い脚本と、強烈な映像と、斬新な編集で見たものを圧倒する。 ラストまでその「痛み」をずるずると血の跡とともにひきずり、最後まで観客を驚愕させてくれるこの映画、鑑賞後に深く考えてしまうとなぞは残るかもしれないが、それを差し引いても、確かに、サンダンスを熱狂させるだけの作品であると明言しておこう。 痛いもの、辛いものから逃げる-そんな無痛社会(そしてそれは外の世界で起こる戦争との格差をどんどんと広げて行くのだ)へのアンチテーゼとも受け取れるるこの作品を作りあげたのは、脚本家にして主役の一人である(そして「マトリックス・リローデッド」にも出演している)リー・ワネルと、おそらく中国系と思われる監督ジェームズ・ワンの二人。次回作の出来で今後が決まるコンビだろう。 最後に、監督が中国系だからであろうか、犯人および被害者は全て白人であり、それを追う側は黒人や中国人という、一般的に見られる映画とは非常に異なった人種配置であることも、注目すべきではないかと思う。映画(サスペンス・ホラー)として 8/10緊迫感 10/10
2004.11.23
コメント(12)
-
「モンスター」 アメリカの車輪に巻かれて(2)
異常者の客に捕まり、殺されかけたアイリーンが男に向って銃を撃ちはなったとき、彼女の中でなにかが外れた。それまでたまっていたアメリカの塵が、はじけたのである。アメリカン・ドリームの中身とはなんだろう。容姿を認められてスターになり、お金持ちになるなにかアイデアを認められ、有名になり、裕福になるアイリーンはその両方を試し、その双方にあてはまらなかった。社会の底辺出身の彼女には、学をつけて社会に出る、という選択肢も無かった。そして、社会は彼女を拒絶し、彼女もまた社会を拒絶した。彼女はアメリカ全体から「あぶれて」しまった。が、そこに、もうひとつのアメリカンドリームがあった。それは、犯罪者、という範疇だ。厳密にはもちろんよい意味ではないのだが、マスコミがそこにただよわせる「クールさ」簡単に手に入る「キャッシュ」のイメージ銃はその全てを可能にするし、何より簡単に手に入るのだ。これがアメリカ的な夢想でなくして、なんであろうか。いや、呼ぶならば、「アメリカン・ナイトメア」と呼ぶべきなのかもしれない。アイリーンはその中に、居場所を見つけてしまった。生きるための希望を見つけてしまったのである。怨恨以外での殺人犯、とくに連続殺人犯の多くは男性だというのはいわれることであるがアイリーンは男を殺すたびに、男性と同化して行く。言葉遣いはよりあらあらしくなり、その立ち振る舞いはまるで彼女をぞんざいに扱った男たちと同じになって行く。彼女が「なじむことのできる世界」がとうとう、見つかったのだ。警察から追われる恐怖や、罪の意識を、アイリーンはセルビーへの愛と、小さいときから刷り込まれてきた「アメリカンドリーム」と「ポジティブシンキング」で、払拭しようとする。これがうまく廻っているときはよいが、もちろんそうはいかない。歯車が狂いだすと、最後のときが来るのは早い。アイリーンは死刑となって人生を終える。この映画を見て二通りの感想を持つものがいるだろう。アイリーンは社会の犠牲者である。社会の問題にしろ、犯罪を犯すにいたったアイリーンが悪い。映画は前者よりであるとは思うが、私はそのどちらも正しいのではないかと思う。社会から長くはじき出されていたために、その中にもう一度はいる姿勢というものを、どうにか身につけられなかったアイリーンにも責任があるとは思うからだ。しいていえば彼女の孤独ゆえの無知が全ての原因かもしれない。いや、映画は、それを救ってやれない社会に責任があると示唆しているのかもしれないのだが・・。しかしこの映画は、彼女がどうやって作られ、どうやってそのものの考え方、感じ方を持つにいたったのかを、実にうまく描き出している。 最初から社会の底辺に生まれ、レイプされ、売春婦へと落ちるも、常に心には「アメリカン・ドリーム」が、「ポジティブシンキング」がある。けれどその二つは、現実を認識した上でなら正だが、現実を見たくないものにとっては、全くの負なのだ。負が「アメリカン・ドリーム」の対極の夢にすすむのは、当然ではないか。 アイリーンは「プリティ・ウーマン」のジュリア・ロバーツの裏だ。男によって引き上げられる夢からもあぶれ、自分を引き上げることも出来ず(ワーキング・ガール?)、彼女は「アメリカン・ナイトメア」を選択したのである。 アイリーンはアメリカの病理そのものである、とこの映画は言う。アイリーンは連続殺人犯の「モンスター」であり、そのモンスターを作ったのが又、観覧車に象徴される、うそ臭い夢に満ちて回り続ける「モンスター」アメリカである。そう、この映画は訴えているのだ。演じたのはこれでアカデミー主演女優賞を獲得したシャリーズ・セロン。日本人には、ラックス・スパ・モイスト の人形のような人としておなじみのはずだが、メイクと増量によって別人の、アイリーンそのものとなっている。演技には多少おおげさなところがある気もするが、渾身の演技であることには変わりない。セルビーには永遠の少女クリスティーナ・リッチ。helplessなセルビーを自然体に演じている。監督と脚本はこれが初作品のパティ・ジェンキンス。アイリーンの事件にフェミニズムのにおい(フェミニズムでは、シスターフッドといって男性に虐げられたものは女性同士で助け合う、という考え方があるが、セルビーとアイリーンは男性と女性の役割分担で女性同士が生きようとするために悲劇を増殖させる)を嗅ぎ取ったのではないかと思われる、女流監督である。良いテーマに出会えば、またすばらしい作品を作ってくれるのではないかと思う。映画として 8/10思索の元として 9/10
2004.11.21
コメント(8)
-
「モンスター」 アメリカの車輪に巻かれて(1)
(批評ですので、ネタバレが含まれます) かつて「無知の涙」という本があった。永山則夫という死刑囚(少年時代に4人を射殺)が、獄の中で独学、自らの人生を反芻し、その犯罪をするにいたった経緯、心理などを語った作品である。そこに描かれるのは社会からはじきだされた人間がどのように犯罪に手を染めるようになるのかであった。 永山則夫同様実話である「モンスター」はある意味ではこのアメリカ版であるのだが、そこには複雑な、「アメリカ的な、あまりにアメリカ的な」ものが描きこまれている。娼婦であることに疲れきったアイリーン(シャーリーズ・セロン)はある日、酒場でセルビー(クリスティーナ・リッチ)というレズビアンの少女と出会う。少女の純粋さに強くひかれたアイリーンは、彼女と暮らすための金を稼ごうと客をとるが、客に殺されかけ抵抗、逆に客を射殺してしまう。セルビーへの愛と、とがの外れた男たちへの怒り。暗く新たな彼女の人生がはじまった・・・・。 作品は「アメリカン・ドリーム」にどっぷりとつかる少女時代のアイリーンから始まる。男性にとってのそれは、成功したビジネスマンになり大金持ちになることかもしれないが、少女のそれは、まず「美しい女性」になることだ。男性に愛され、もてはやされる「美しい女性」。美しければ、そして少女がその意味をしっかりと理解していないにしろ、性的に魅力的ならば、男性が見出し、ひきあげてくれる。アイリーンはそう信じた。が、現実には美しくない彼女は、もう、とうに最初からあぶれてしまっていたのだ。 後にアイリーンがレイプ被害者であり、貧困家庭の出身で13歳から売春を始めたことなど、生まれもって大国アメリカの底辺に身を置いてしまった彼女の人生が少しづつ明かされるのだが、そんな彼女に学校ですりこまれるのは、「夢は信じればいつかかなう」というメッセージだ。学校の講演会で来た有名人の話、周りの大人たちの語ること。「アメリカン・ドリーム」と、常に前向きな「アメリカン・ポジティブ・シンキング」が、貧困で美しくなく、学もない少女の心に巣食うと何ができあがるのか。実態の無い夢だけを心に抱いた、うつろで疲れきった売春婦である。 そして、売春婦であることでよりさげすまれ、男たちに暴力をふるわれる彼女のうつろな心には、絶望と、アメリカの塵がつみかさなっていたのである。 一方セルビーは、アメリカの中流以上の家庭の出身で、レズビアンであることが露呈しそこからはみだしてしまった存在である。大人、とりわけ厳格で成功者である父親に守られて生きてきた彼女には、「生きる」力が無い。生きるために働き、食べるために何かをする、という生活感が無い。自分で何かをしようという、行動そのものが無い。アメリカの中・上流世界の価値観のうつろさに反発しながらも、それに飲み込まれて生まれ育った彼女は、確かに純粋ではあるが、これまた愛に飢えた、からっぽの存在である。アイリーンはセルビーに自分には縁の無かったものを見出す。こぎれいで、純粋で、片足が折れた小鹿のように、人の助けなしには生きていけないような繊細さ、美しさ。セルビーはアイリーンに 荒々しい感情や、行動力といった、やはりそれまでの自分になかったものを見出し、自分の知らない世界に生きてきた彼女に「格好良さ」を感じる。「男」の傲慢さ、残虐さに嫌気がさしていたアメリカの底辺の売春婦と、「男」の付属物としての「女」になりきれずアメリカの上部からはみ出てしまった少女。この二人の組み合わせは、とてつもなく哀しく、成就などあろうはずがない。なぜなら、二人の出会いは、アメリカの病理の出会いだからだ。作品のタイトルである「モンスター」は、連続殺人犯となるアイリーンをさしてはいるが、そもそもは彼女が少女時代に乗り吐き気をもようしたという大きな観覧車の名前である。 赤と黄色のけばけばしいネオンをつけ、ゆっくりと、回り続ける、美しくも毒々しい観覧車。それは、アメリカという社会そのものだ。 最も高いところからは全てが見渡せるが、その反対側、一番下に乗るものに見えるのは、下を歩く者だけ。一番下が、一番上になることもあるし、一番上が、一番下になることもある。けれど全てが同じ高さになることはけっしてありえないし、そしてなにより、そのきらびやかなネオンは美しくもうそ臭く、毒々しくて、そして吐き気を催させる。その観覧車で、アイリーンとセルビーは、並んで座ろうとした。それぞれの場所を捨て、横に並び、幸せをつかもうとした。けれど彼女たちが乗っているのは同じ観覧車-アメリカなのだ。けして廻るのをやめない、大きな観覧車。彼女たちはどんなにあがこうと、そして帰る場所の無いアイリーンが、どんなにもがこうとも、そこからは降りることが出来ないのだ。 (2へ)
2004.11.20
コメント(2)
-
「ドーン・オブ・ザ・デッド」 会話のきっかけに。
演技力では定評のある女優、サラ・ポーリーを主役に置き、ロメロの最高傑作をタイトルもそのままにリメイクしたのが、この、「ドーン・オブ・ザ・デッド」である。 看護婦アナ(ポーリー)は一日の仕事を終え、夫が待つ自宅へ。ラジオやテレビではなにやら不穏なニュースが流れ始めているが、幸せな一般人の彼女の目にとまらない。そして、朝。目覚めた二人の前に現れたのは、血まみれの近所の少女。何があったんだ?と駆け寄る夫に少女はしまみれの歯をむいて襲い掛かり、夫は死亡。しかしアナには、夫の死を悼む猶予はなかった。なぜなら、夫はすぐさま生き返りアナに襲い掛かってきたからだ。そして外でも、同じ光景が広がっていた・・・。名作であるロメロのオリジナルと比較してこの映画をこき下ろすことはとてつもなく簡単である。オリジナルに勝るリメイクというのは、そう簡単に見つけられないからだ。また、オリジナルのことを忘れ、単純に映画としてのできも、手放しでは褒められるものではない。それは、ゾンビ増殖→ショッピングモールへ→ひたすらに戦う生存者 という単純明快なストーリーでありながら、その統一感の無さが原因だ。主演はサラ・ポーリーであるが、生存者の中のワン・オブ・ゼムに沈んでしまい、せっかくの彼女の卓越した演技力が全く生かされていない。(上に彼女がやけにふけて映っている)音楽は、「アメリカンにクールに」と思うあまり、あまりにミスチョイスで、妙なところでギンギンに流れ始めるため、高揚感どころか、逆にチープ感ばかりかもしだしてしまう。すばらしいセンスの映画のタイトルバック-出演者やキャストの赤文字の名前が風に吹き消され血滴となるーにはじまり、サブリミナルぎりぎりのところのフラッシュバックを上手に取り入れ緊張感を高め、象徴的なニュース映像や、「死者は墓場からあふれたとき地上をさまよいだす」といった聖書の言葉を効果的にさしはさめて、スタイリッシュ・ホラー風に盛り上げておきながら、急にテレビドラマのようなちゃちな展開になって、盛り下げる。そのような統一感の無さ、がそこここに現れるため、なんとなく、まとまりがない。が、しかし、単純にホラーとしてみた場合、製作者側はあるひとつの焦点だけはしっかりとはずしていない。それは、「ゾンビジャンルのホラー映画」である点だ。ゾンビ本人の描き方には、なんの手抜かりもないのである。この映画のゾンビは、とにかく、走る。なにかの化学物質で変異したとかではない、ただの死者の生き返りなのだが、少し鈍いものの(一回死んだのだから体がだるいのだろう)、生肉を求めて、とにかく走る。そっと近寄って後ろから襲うくらいの知恵はあるし、小さな隙間から体を縮めて進入するくらい朝飯前だ。「ちょっと疲れてて今日はぼんやりしてるけど、どうにかね」、そんなたたずまいのゾンビたち-つまり、姿は別としても、この映画のゾンビたちはなにかとても人間的なのだ。アメリカの検閲で人間虐待としてひっかかり、「ゾンビは人間ではない」と説明するのに製作者側が苦労した、とは聞いていたが、そう、確かにこのゾンビは人間そのままなのである。生存者たちが立てこもるショッピングモールは、ロメロの先鋭オリジナルのときから、消費社会の象徴であったが、生前は、消費を楽しみにその中でひしめきあっていた彼ら(今はゾンビ)が、今度はその外を取り囲んで、セール品を並んで待つ客よろしく、安くておいしい生者たちを求めて、ひしめきあっている。そのうつろさ、薄気味の悪さ。 そして「新鮮な生者満載!」のトラックが来たときの興奮のすさまじさ。「象徴的」を通り越して、通常のわれわれそのものである。死して生き返ったときにまず、一番身近な人へと向うのもなんとなく人間らしい。心に残ったもののところにまず向うのだ。そう、幽霊ではなく、ゾンビとして。バタリアン以降のゾンビものにはつきものの、「愛するものがゾンビになる哀しさ」というゾンビメロドラマ、もしっかりと描かれている。この映画で一番上手に描かれている部分ではないだろうか。思わず涙するほどだ。暇をもてあました生者たちが屋上からソンビの撃ちっこをするなどシニカルな部分の描き方やセリフも、小粋である。こうして見てみると、統一感がなくアラもあるものの、ストーリーの明確さと、ゾンビ本人の描き方への熱意から、ホラー映画としてはまずまずの及第点を挙げてもいいのではないかというのが私の結論だ。そして何より、ともに見た人と、こんな会話が出来るのが一番の利点である。「この映画さぁ、いいんだけど、なんか、バタリアンやらバイハザとかさぁ、あーゆーのとおんなじじゃん?ほら、28時間とかさぁ。使い古されてるって感じ?」「なんだよ知らないのー?これ、60~70年代にロメロって監督が始めて作ったゾンビ映画のリメイクなんだぜ!だから、このオリジナル版が、ゾンビ映画の最初の一本で、そのリメイクだから逆に使い古されてる気がするんだよ。本当は、さっき君があげた映画全部が、ここからきてものってことさ!そもそもオリジナルのころは、まだエイズもない時代で、ショッピングモールすらできたばかりの時代だったのに、ロメロって監督が象徴的に・・・・」なぜこの映画が今この時代のアメリカでリメイクされたのか・・?そんなことまで話を広げながら、見てほしい一本である。映画として 6/10会話のきっかけとして 9/10
2004.11.19
コメント(2)
-
「スクール・オブ・ロック」 子供には勝てません
「愛しのローズマリー」でパルトロウとの絶妙なコンビでほのぼのと笑わせてくれた、ジャック・ブラックの、映画公開当時も評判の高かった、コメディである。ロックギタリストのデューイ(ジャック・ブラック)は、ロック!に傾倒しすぎたゆえのはちゃめちゃぶりで、自分のバンドをクビに。そのうえ居候している元パンクロッカーの親友ネッドの家からも、彼の彼女とウマが合わず追い出される寸前。そんな時、たまたま受けた電話はネッドあての代用教員の口の話だった。喉から手が出るほどお金がほしいデューイは、蝶ネクタイに似合わない一張羅を着て「音楽教師ネッド」として厳格で有名な名門私立小学校へもぐりこむのだが・・・。もぐりこんだ先の私立小学校の校長がジョーン・キューザック(アダムス・ファミリー2、トイズなど)。ちょっとピンクルな人をやらせたらぴか一の彼女が、お堅い校長先生を、話し方からジェスチャーまで、なりきって演じている。が、もちろん、それだけなら彼女にこの役は廻ってこなかったのだが・・。実は全米NO1ヒット作でありながら、この映画の脚本とストーリーは実にお粗末である。厳格でそれだけ賢い子供たちが、授業もろくにせずいいかげんなことしか言わないデューイになぜついていくのか疑問に思うほどだし、デューイ本人の人間性における成長というのも、(ワンシーンをのぞいて)あまり描かれていない。彼の生徒への話し方も、愛情があるのかないのかわからないままという感じだ。ちょこちょことした山場はあるような気もするが、盛り上がりは最後のシーンだけといっても過言ではない。たとえば、「天使にラブソングを」の1や2と比べてみても、その出来上がりの薄さは歴然である。主人公は自分と違った価値観を持つものたちの中で、自己を主張し、荒い言葉を使いながらも、少しづつ思いやりを見せ、「皆がよいほうに」向うために、統率力を発揮する。 が、デューイは違う。頭にあるのは「自分がロックをやること」だから、そのためだけに子供を使う。子供を励まし、認めるのだが、目的がそれだから、なにか言葉に愛情がない。後半で結局、騙していたことについて謝ることになるのだが、それでも結局舞台では子供と並んで目立とうとする。ジャック・ブラックという人がバンドまでやっている本物のロックンローラーであるから、見せ場という意味でこれは仕方がないことなのかもしれない。 しかし、「映画」としては、自己中心的なオトナコドモであったデューイが、騙していたことを謝り、恥じ、ラストでは、子供たちのパフォーマンスに少し参加するくらいで、あとはそっと「自分を殺し」子供たちを見守る・・といった、主人公の成長を見せるべきではなかったかと思わずにはいられない。 この映画が「ジャック・ブラック」が出演しているからこそ成り立っている、と製作者が考えているからこそ、映画としての出来よりも、彼の「見せ場」を選んだといえるのだろう。 しかし、そういったことを抜きにしても、何よりもすばらしいのは、子供たちである。「動物と子供には勝てない」はまさに名言で、ジャック・ブラックが鼻に付こうが、ストーリーとキャラクターに不具合があろうが、数千人のオーディションで選ばれたという子供たちのパフォーマンスはまさに最高である。(ジャック・ブラックがいないならいいのに!と思わせるほどだ)ラストのバンドシーンは何度でも繰り返してみたくなるほどの格好よさだし、そのテクニックのみならず、子供が作ったという設定の「スクールオブロック」のロゴのポップさ、楽曲のすばらしさ。文句のつけようがないというできばえだ。(しいていえばキーボードがいけていないのだが。) 主人公のダメ人間デューイを許し、一緒に舞台に出させてあげるのも、子供たち。 ジャック・ブラックが目立とうとするのを大目に見てやっているのも、子供たち。子供のほうが大人より何枚も上手。そんな映画である。コメディ映画として 6/10ラストのパフォーマンス場面 10/10
2004.11.18
コメント(2)
-
「コラテラル」 サスペンスアクションではなく
「ヒート」のマイケル・マン監督に、天下のトム・クルーズが悪役に挑む、と聞けばおのずと期待してしまう「サスペンス・アクション」ムービー、「コラテラル」。ところがどっこい、この映画、「サスペンスアクション」というよりも、いろいろな意味で「ドラマ」そのものであった。まず、ストーリーは・・ マックス(ジェイミー・フォックス/「アリ」なんかに出てるコメディ出身のブラック)は、平凡だがよく気が付くロスのタクシー運転手。乗客の一人女性検事のアニーと心を通わせたことから名刺をもらったりと、いい夜を過ごせそうな予感だ。 彼女の次に乗せた乗客は銀髪にひげを蓄えたクールな面持ちの男。(トム・クルーズ)ヴィンセントと名乗り、不動産業で五人の客のサインをもらうために一晩貸切で走ってもらえないか、と大金をちらつかせ話を持ちかける彼に、マックスはしぶしぶ了解。しかしそれこそが悪夢の始まりであった・・。 マイケル・マンのバックグラウンドとして頭に入れておかねばならないことがある。それは、彼が長年テレビ業界の「刑事物・警察物」で活躍し(スタスキーアンド・ハッチの脚本家であった)、かの刑事物の大御所、「マイアミバイス」の仕掛け人であったことだ。 私は最初にこの映画は「ドラマ」だといったが、そのひとつの答えがまずここにある。目線をさまようようなラフなカメラワークに、ど派手というよりも妙に現実感のあるアクション、ロスのリアルな街並み、そして、はっきりと焦点の合わない登場人物の描き方、などがそれだ。 通常、映画では主要なキャラクター(と、プラスアルファほどの助演者)のみがきちんと描かれるのだが、TVドラマにおいては主要なキャラクター以外の者たちにも多少の焦点が当てられる。(特に、いわゆるサスペンス系・刑事物系のドラマがそうだ。刑事たち以外に犯人やその取り巻く状況なども描かねば話が成立しないからである) これは、映画が二時間程度という短い制限時間なのに対し、ドラマは時間的余裕があるからできることなのだが、マイケル・マンは、これを制限時間の短い映画の中にまで持ち込む。だからそのキャラクター、とりわけ主要登場人物の描き方は少し「手ぶれ」するし、その山場は多少色ざめする。一言で言ってしまえば、「クリアー」ではないのだ。 「ヒート」は2大俳優(デニーロとパチーノ)を配し、その存在感を強調するために山場を大幅に盛り上げたので、この、TVドラマ独特の「手ぶれ」感はだいぶ薄らいでいたのだが(それに、作品自体も長い)、今回はそうではない。「コラテラル」は、マイケル・マンによる、二時間のTV「ドラマ」、「クリアーではないこと」を楽しむべき「ドラマ」なのだ。 また、この映画は映画のジャンルとしても、本来は「ドラマ」に分類されるべきであるように思う。もちろん、「巻き込まれ(=コラテラル)型サスペンス」の形をとってはいるのであるが、これを「サスペンス」「アクション」として評価した場合、それは上にも書いたとおり、「クリアーではない」という点で低い評価とされる可能性が高い。(そのTVドラマ風手法を楽しんでほしいものではあるのだけれども) が、しかし、この映画は「ドラマ」-ヒューマンドラマ、という意味のドラマであるーとしては非常に面白いものを持っている。 夢もハートもあるが、しがないタクシー運転手を続けているマックス。 超現実的で冷徹だが、任務の遂行のためには手段も体裁も選ばないヴィンセント。黒人と白人で、姿も正反対の二人(ひげに白髪⇔めがねに黒髪 スーツ⇔ジャージ など)は、ユングいうところの「シャドー」そのものだ。マックスとヴィンセントはお互いがお互いの影である。 だからこそヴィンセントは安易にマックスを殺しはしないし、マックスも、はじめは語ろうとしなかった自分の夢を、脅されている相手のヴィンセントに語ったりするようになる。マックスは自分の人間的・精神的問題点を指摘されるとヴィンセントに反抗するしヴィンセントもまたマックスに反論されると逆上するお互いがお互いにとってのシャドーであるふたりが、犯罪者と犠牲者、という立場で出会い、それぞれを「壊して」いく。壊れたそれまでの自分を「再び構築」するのはどちらであるのか。そこにいたるまでの二人の駆け引き、会話のやりとりがこの映画の醍醐味であり、最終的なクライマックスとなっていく。 ストーリーは全く違うのだが、「ファイト・クラブ」と、その点では非常に似た構図を持ったストーリーであるように思う。もちろん「コラテラル」はずっと泥臭く、ずっとテレビくさい代物ではあるのだが・・。 自分の「影」といかに対峙するかーマックスとヴィンセントという「サスペンスアクション」映画の登場人物の中に、この問いかけを見つけることが出来れば、作品の途中で現れるある動物や、ラストなどもたやすく理解することが出来るかと思う。「コラテラル」は男の「ヒューマンドラマ」なのだ。 さて最後に、ヴィンセント演じるトム・クルーズ。最初はミスキャストじゃん、と思っていたが、その「hollow man」(空虚な人物)としての気持ちの悪さは、なかなか適役だったのではないかというのが見ての感想だ。「クールで颯爽とした凄腕殺し屋」のかっこよさではなく、「なりふりかまわず任務を遂行する空虚な殺し屋」の気持ちの悪さをかもし出したところに努力賞をあげてよいのではないかと思う。もしあなたが、「泥臭いテレビドラマを映画館で見ること」を楽しめる懐の余裕があるなら、または「クリアーではないサスペンスアクション」の中に男の「ヒューマンドラマ」を見出せるなら映画館で、1000円で。「サスペンスアクション大作~!コラテラル~!!」のイメージがどうしても払拭できない人トム・クルーズXマイケル・マンが、切れのいいハリウッド大作でないと許せない人はビデオでどうぞ。1. スーツ姿(しかも超サラリーマン風)で、「しごと、しごと」となりふりかまわず職務を遂行するヴィンセント。「仕事が優先のビジネスマン」をはっきりと揶揄している。2.戸田奈津子さん、「ハンプティーダンプティー」を「天使の像」と訳すのはどうでしょうか?割れた卵でいいのでは・・?
2004.11.09
コメント(0)
全45件 (45件中 1-45件目)
1
-
-
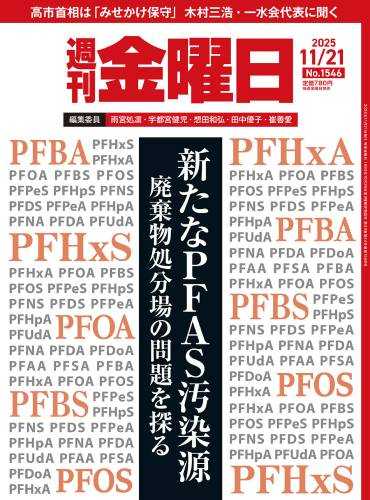
- 【演劇】何か見に行きますか? 行き…
- 劇評:劇団温泉ドラゴン『まだおとず…
- (2025-11-21 13:22:46)
-
-
-

- Youtubeで見つけたイチオシ動画
- 1976学園祭ライブー 中島みゆき
- (2025-11-27 21:45:51)
-
-
-

- 映画館で観た映画
- 映画の話 F1(R) エフワン(映画館)
- (2025-11-29 00:00:13)
-






