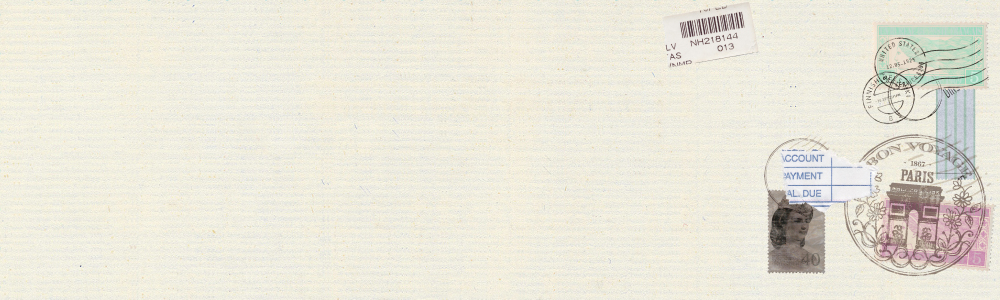PR
X
カレンダー
2025.11
2025.10
2025.09
2025.10
2025.09
2025.08
2025.07
2025.07
カテゴリ
テーマ: ☆留学中☆(2582)
カテゴリ: 留学情報
春学期は授業を4つ受講した。フルタイム学生のステータスを維持するためには最低3つ授業を履修しなくてはならない。私は卒業を急いでいたため最低取らなくてはならない授業3つに加えてもう一つ授業を履修した。このことが後々仇となるなんて履修時には想像もしていなかった。
授業:Second Language Development
Week 1 Introduction
論文2本。
自己紹介、コースシラバスの説明、評価の仕方、課題の説明など。言語のAcquisitionとDevelopmentの違いについてグループで分かれて議論した。
Week 2 First Language Acquisition
教科書(2冊)のチャプターリーディング。論文1本。
第一言語の習得に関する論文を読んでクラス内で議論をした。最近ではinput/interactionの他にもstatistical learningやusage-based learningといった用語が生まれているようである。つまり、脳内で使用頻度や単語と単語の繋がりから意味を推察して言語が習得されていくというアプローチである。言語習得における習慣形成(habit formation)の役割や生得的な能力による言語習得アプローチ(nativist)の根拠などを探った。
Week 3 Bilingualism/Multilingualism
教科書のリーディング(1チャプター)。論文2本。
この週あたりから少しずつ言語の社会における位置付けなどを意識しながら言語習得を考察するようになった。グローバル化していく世の中においてバイリンガリズムやマルティリンガリズムはどのような意味を持つのかクラス内で議論した。また正しくバインがリズムやマルティリンガリズムを育むためにはどのような実践をしていくべきなのか考えさせられた。日本においては外国語といえば英語一辺倒であるが、本来世界が目指すべき姿はplurilingualismであることがこの講義を通じて明らかになった。日本では英語が受験科目に取り入れられ、英語力の有無が高校入試、大学入試、そして入社試験にも影響を及ぼすとされる。しかし、本来言語間に優劣はなく、メジャーな言語であろうとマイナーな言語であろうと対等な立場で語られなければならないというのがアカデミックな世界(特に社会言語学の学者の世界)のスタンダードらしい。現実世界と理想のギャップを感じた週でもあった。改めて社会的通念やイデオロギーのようなものは人々によって構築され、流布していくのだと感じた次第だ。「英語ができれば将来困らない」といった考えもその一つであろう(実際には英語ができても海外で生活すると困ることだらけである)。
Week 4 Age Factor in Language
教科書のチャプターリーディング、論文4本。
この週はリーディングの量が多く非常に大変な週だった。やはり学習開始時期(専門的な用語を使うとage of onsetというらしい)と言語の到達度は学者のみならず多くの人の関心ごとであり、研究も盛んに行われている。日本でも「おうち英語」、「早期英語」が話題になっているが、「早ければ早いほどいい」という考えは沢山の誤解が含まれていることがわかった。臨界期仮説に関してはMunoz (2008)やMunoz(2016)が非常に参考になった。授業内では臨界期仮説に対して支持する肯定側と否定側に分かれ論文の情報をもとにちょっとしたディベートをした。支持するため(反駁するため)の根拠探しは非常に楽しかった。研究で明らかになっていることをどう現場に落とし込むかが今後の課題となりそうだ。
Week 5 Cross-Linguistic Influence
教科書チャプターリーディング、論文2本。
私が学部生の頃は(positive or negative) transfer(転移)と呼ばれていたような気もするが、最近ではcross linguistic influenceと呼ばれることが多くなっているらしい。母語がどれほど第二言語の習得に影響を及ぼすかというものだ。その影響は多岐にわたっており文法、発音などの音声側面、語彙習得など様々だ。また、第二言語の習得が空間認識や時間の観念(time conception)にも影響を及ぼすのか議論をした。この分野は正直全く事前の知識がなく新しい領域であった。スウェーデン語とスペイン語のバイリンガルとスウェーデン語とスペイン語の母語話者のaspectの違いにフォーカスした研究論文を読んだ。
課題:論文を読み込みグループで25分程度プレゼンを行った。非常に難解なトピックであったが、教授のサポートもあり無事終えることができた。私は実験結果の紹介と研究が実生活に与える影響などを話した。
Week 6 Linguistic Environment
教科書チャプターリーディング、論文2本。
年齢、言語間の影響、そして言語の環境は言語習得を語る上で切っても切り離せない。しかし、日本の英語教育では「方法論」に特化しすぎて学者や教員がコントロールできない要因についてはあまり議論がなされていない印象がある。〇〇メソッドとか〇〇ラウンドシステムといったやり方が人気を博しているようだが、言語の習得は全て教授法に起因するものだろうか。環境面も含めて議論する必要性をこの週で学んだ。特に幼い子どもは周囲の影響を(良くも悪くも)受けやすい。こちらでコントロールできない要因をどのように研究のデザインに落とし込む難しさを痛感した週でもあった。
Week 7 Development of Language Learner
教科書のチャプターリーディング、論文3本。
この週はSelinker(1972)が提唱したInterlanguageという概念を中心に扱った。最近ではInterlanguageに代わってmulticompletenceというコンセプトも登場しているらしい。私が学部生の頃はこのinterlanguageと言語の化石化(fossilization)がよく教科書に載っていたが、最近ではこの考えに否定的な考えを示す学者(Larsen-Freeman, 2014等)も登場しているらしい。最近SLAで注目を集め始めているusage-based approachについても学んだ。
Week 8 NO CLASS (spring break)
Week 9 Aptitude and Learning Strategies
論文3本。
言語習得の特性と学習ストラテジーについて学んだ。Aptitude Testは選別テストではなく学習者が持つ学び方の特性を知るために用いられるべきであることを学んだ。また、Howard Gardnerのmultiple intelligence理論を用いた学習方法などについても学んだ。
Week 10 Motivation
教科書チャプターリーディング、論文2本。
Week 11 Affect and Individual differences
教科書チャプターリーディング(2章)、論文2本。
この週では主に情緒と個人の差異が言語学習にどのような影響を及ぼすか学んだ。個々人がターゲット言語に抱いている感情がその言語の習得に大きな影響を及ぼすことを学んだ。よりターゲット言語の文化に親しみを感じるほど言語習得が促進されることをAcculturation Theoryと呼んだりすることもあるようだ。こちらの大学で日本語の授業にお邪魔したことがあるのだが、こちらで日本語を学んでいるアメリカ人は大概日本の文化やサブカルチャーに詳しい。漫画に至っては私が全く知らないタイトルまで登場するほどだ。
Week 12 Social Dimensions of language learning
教科書チャプターリーディング、論文4本。
この週も教科書のチャプターリーディングと論文4本をこなさなくてならず、大変な1週間だった。確かこのあたりに家族も合流したはずなのできっと目が回るほど忙しかったに違いない。嵐のような忙しさも学期が終わってしまえば忘れてしまうから不思議なものだ。自分でもどのように一つ一つのタスクを片付けていたのか思い出せない。きっと無我夢中で駆け抜けていたのだろう。
SLA界で言われるSocial Turnについて扱った。Firth and Wagner(1997)のペーパーが出て以降一大論争が起こったらしい。日本の英語教育史でいう平泉渡部教育論争のようなものだろうか。その後SLAの重鎮であるLong, Gassを巻き込んだ議論の応酬は呼んでいて非常に興味深かった。ネイティブを言語学習の「終着地」として扱う危うさ、社会のコンテキストの中で言語が習得されるとする考え方は一理あるように思えた。統計的有意だけでは捉えきれない言語習得のnuanced messageが含まれているような気がした。
Week 13 Conversation Analysis and Multilingual Theories
論文4本。
この週は談話分析(conversation analysis)の基礎的な手法とEnglish as a Lingua Franca(リンガフランカとしての英語)を学んだ。これらはKachruのThree circlesやJenkinsのWorld Englishesは触れたことがあったが、それに関する研究論文はあまり触れたことがなかったので大変参考になった。リンガフランカとしての英語の理念は共感できたが、ネイティブをモデルとしない場合に教師は何をモデルに英語を教えていくべきなのか疑問が残った。また、文法、音声面においてもどこまでを許容とするかが大きな問題となる。完璧な回答を求める日本の受験英語とも相性が非常に悪い。改めて、理想と実際目の当たりにする現場の間に存在するギャップを目の前に立ち尽くすしかない自分がいた。
Week 14 Sociocultural Theory VS Social Identity Theory
教科書チャプターリーディング、論文2本。
Sociocultural Theoryはざっくり言えばLantolfらが中心になってヴィゴツキーの理論を言語習得理論に応用したものだ。教育心理学で学んだscaffoldingやZone of Proximal Development(ZPD)などが論文を読んでていても登場する。また、動機付けとアイデンティティーを結びつけたNortonらの論文を読んだ。似ているようで決して交わらない両者の考え方を比較検討した。談話分析を含めこの辺りからだんだん質的研究手法を用いた論文が中心となる。
Week 15 Complexity Theory and Transdisciplinarity
論文4本。
Complex Dynamic System Theoryについて扱った。まさに心理学、教育学、言語学、社会学を取り入れながら発展してきたSLAを象徴するような理論である。このままSLAは拡大を続けていくのか、それともどこかの段階で肥大化しすぎて学問領域の分裂が起こるのかはわからない。そのようなtransdisciplinaryな側面も含めてLarsen-Freeman(2012)はComplex, dynamic systemsをたどり着いたのかもしれない。とてもではないが、1週間でこの理論を消化するには期間が短すぎた。どこかまとまった時間ができたら論文を再読したい。
Week 16 Wrap-up
論文3本。
最後の週は今までやってきた内容の総復習をした。
それでは今日も良い一日を。
きたろう
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[留学情報] カテゴリの最新記事
-
米国大学院2年目の学費 2025.06.30
-
アメリカ留学期間中に生活費公開 2025.05.18
-
海外留学を希望されるあなたへ(特に米国) 2025.03.08
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
© Rakuten Group, Inc.