-
1

外資系の支配人のクレーム対応
「お客様は神様です」みたいなことばかり教えるのは簡単。しかし現場が困っていることは、そうではなくて、「この人は客じゃない」と判断し、対応するにはどうしたらいいか?と言うこと。最近は現場のサービスの質が落ちた、、、と言われる背景には「客の質が落ちた」という側面も多々あるからです。先日も、某有名外資系のショッピングセンター?で明らかにスタッフにからんで、クレームを通り越して、「イチャモン」をつけているシーンに遭遇しました。典型的な「あー言えば、こう言う」のクレーマーで、ようするに何だかんだ言って「タダにさせてしまおう」という魂胆が丸見えでした。商品やサービスのクレームを通り越して、スタッフ自身のことを「あれもダメ、これもダメ」と攻めまくります。すると欧州系の支配人が出てきた。どう対応するのだろう?と観察していると、「出て行け!お前は客じゃない!」と物凄い剣幕で怒りだしました。(もう顔面が怒りで真っ赤でした)支配人が出てくれば、あと一押しで「タダになる」と期待していたガラの悪いクレーマーは、ビックリ!そして、「スタッフはお前の奴隷じゃない、謝れ!」とまで言い放ちます。結局、クレーマーが逆に謝罪することに。後に話しを伺うと、「このラインを超えたら客じゃない、というのがある。ラインまではスタッフに精一杯努力させる。しかし、それ以上やらせるとスタッフがいじめられて心に深い傷を負う。そして、この仕事に恐怖を感じるようになってしまう。それは絶対に避けなければならない。だから、私たちはこのラインを超えてくるクレーマーがいたら、その瞬間からスタッフを守るのが義務だ」とのコメント。客も店を選ぶし、店も客を選ぶ、ということでしょう。そして、「日本のお客さんは、商品とサービスの品質に厳しい。それはそれでいい。だけど、時にその限度が超えると、単なるわがまま客に変身してしまうことが多い。これは悲しいことだ。そして、店に断られることに慣れていない。これは、全国的に頭を下げる接客しか教えてこなかったからだろう」というお話しでした。サービスの現場には、「こういう場合はどうしたらいいのか?」というグレーゾーンがたくさんあります。そのグレーゾーンこそ、社員の仕事です。それなのに、朝礼や終礼で、流行りの「感動系の話し」ばかりしていても、問題は解決しませんから要注意です。===★第5回インバウンドセミナーのお知らせ!★ 次回のインバウンドセミナーの開催は4月5日(月)に決定しました!場所:銀座紙パルプ会館1F ラウンジ「パピエ」東京都中央区銀座3-9-11(〒104-8139)時間:19:00~⇒セミナーの詳細はこちらをご覧下さい!
2010/03/24
閲覧総数 112663
-
2

東京ディズニーリゾートは巨大地震にどう対応したのか?
===<WBSより>======現場のスタッフのほとんどはアルバイトで、7万人の来場者で死傷者0人。私の親戚も当日、ディズニーランドにいました。地震の恐怖よりも、従業員の対応に感動してました。ディズニーランドの運営理念「S・C・S・E」が完全に実践されているからこそでしょうね。(何よりも安全第一)まさに「他の追従を許さないブランド力」の真髄が発揮された瞬間です。「なんちゃって防災訓練」しかやってない施設が多い中、いつ役に立つかわからない防災訓練を年に180回、、、。しかも28年間も、、、。全てにおいて「圧倒的」。運営サービスのソフト力の差は、訓練の差ですね。===世界中のリゾートや有名ホテルから、「どのように訓練しているのか?」の問合せがラッシュのようです。中国人観光客にもっと売る新“おもてなし術”価格:1,470円(税込、送料別)
2011/05/02
閲覧総数 480
-
3

中国人経営者に聞いた「絶対にやりたくない仕事トップ3は?」
先日の中国人経営者の訪日遊学ツアーの際、居酒屋談義で聞いた話。「絶対にやりたくない仕事トップ3は?」…の答えは「BYD・SHEIN・TEMU…」の下請け仕事でした(笑)。理由は「全く儲からないから」と、経験者たちの話はまるでドラマのようにリアルな内容で、他国の企業が同じ土俵で勝負するのは不可能なほどブラックで(支払い、納期、契約変更、返品…)、個人的には、ビジネスモデルとしては全く参考になる所は見受けられなかった…と言うのが正直な感想。なので、マスコミの報道に一喜一憂して惑わされることなく「あれは中国式なんだ」と、遠目で眺める程度でいいのかな、と思った次第です。→レジャーサービス研究所のポッドキャスト
2025/01/29
閲覧総数 92
-
4

2つの反日
日本への留学経験者と会食の時、「現在の反日についてどう思いますか?」と聞かれた。いくら留学経験があって、相手は中国人だからどのように答えようか?頭の中でグルグルと考えが巡っていた。その様子を察してか、「では、私の意見ですが…」と口を開いたので、少し構えつつ聞く姿勢をとる。その本人曰く、今振り返れば、やはり反日教育と呼ぶに値する教育はあった、と。詳細を聞くと、ビックリ!だった。今となっては笑えるような大げさな話やウソもあったらしい。けれど、自分で実際に日本に行き、学び働いてみて違う事がわかってきた。日本のいい所は、調べようと思えばいくらでも情報が手に入ることで、これは本当に羨ましいと思った。しかし、一番驚いたのは、日本人が<反日>に写ったこと。何かというと、「いやーもう日本はダメだよ。だいたい…」「あっち(アメリカ)から見るとねぇ…」などなど、よくもまぁ自国のことを否定するなぁとビックリしたらしい。だから日本人も反日がたくさんいるみたいな気がした、と。(あるいは「嫌日」とも)考えてみれば意外に当たっているかもしれない。もしくはそう写ってしまう人が結構多いのかな?と考えた。冷静に見渡しても(過去から)、そういう意見をたくさん聞いてきたし、今も聞くことがある。僕らの世代は明らかにそういう傾向があると思う。(君が代を唄う時、先生は座っている…など不思議だった)日本を評論するのがかっこいいのか?知的に見えるということなのか?小さな頃から少しずつ、けれどしっかり「だいたい日本は…」の視点を植えつけられたのかもしれない。そんなにひどいわけはないのだけど、そうして否定する習慣みたいなのが知らず知らずのうちに身についているのかも?新聞でもメルマガでも、未だそういう視点にお目にかかることがある。相手の国のこともそうだが、まずは自分の国のことも、もう少しニュートラルに眺められる視点を鍛えなければならない、と思った。
2005/04/17
閲覧総数 2
-
5

深夜タクシーのサービス進化論
遅い打合せが終わって、個人タクシーを見つけて帰路につく。なぜ個人タクシーにこだわるのか?というと、ひとつは「深夜割増料金が2割」であること。法人タクシーは3割増しになる。さらに、車種が圧倒的に違う。個人タクシーは、マジェスタ、ティアナ…など、乗り心地のよい車が多い、…などがその理由。乗車してしばらくすると、グッタリしている僕に、運転手さんが「何か音楽でもかけましょうか?」と気を利かせてくれる様子。「おお!いいですね、お願いします」と答える。この約3ヶ月間、何しろ出張の連続で疲労感が一杯なので、うれしい気遣いだぁぁぁぁぁ!と感激。間もなく、何やら昔懐かしいカセットテープを取り出した運転手さん。「ガシャッ!」とセットした音が聞こえた。「どん歌なんだろうか?」少しだけ期待に胸は膨らむ。「シャー・・・・・」っとノイズが聞こえてきた。そして、しばらくすると聞こえてきた歌は…「ウーダダ、ウーダダ、ウダウダよぉー♪」と聞こえた。「????」「この世は私のためにあるぅ~♪」ひょっとして、これって「山本リンダですか?」と聞いてみると、満面な得意そうな笑みで「もちろん!」とあくまでも得意げな運転手さん。タイトルは確か「狙い撃ち」でしたっけ?何しろ、小学生低学年の記憶の彼方で薄っすら覚えている。その後は、「東京ララバイ」とか朱里エイコの歌とか…何しろガッツリ昭和な方だった(汗)。一応、お気遣いに感謝しなければ…と思い、「いつもかけるんですか?」と聞いてみると、「いやー、お客さんが疲れてそうな時はね。うれしいかなと思って…:照」と全く濁りのない、純度の高い笑顔が返ってきた。「こうみえても、色々サービスを考えてるんですよぉー!」とあくまでも明るい。「へぇー素晴らしいですねぇぇぇぇ!」とおだてていると…石原裕次郎のメドレーが流れ出した(涙)。(そんなのがあること自体に驚いた:汗)
2007/04/05
閲覧総数 4
-
6

面接とのギャップの対策
●いよいよ新入社員研修が始まると、人事担当者が凹むのは、「面接とのギャップ」だ。特に中国の場合、自己アピールがうまい人が混ざっている確立が高いから、実際に職場に来た時の「素の姿」を見ると、ショックを受けることがあるようだ。しかし、考えてみれば就職面接は、一生の中でも最も気合の入る瞬間である。ある意味で、その姿はピークと言える。だから、担当者はそのつもりで採用しなければならない。(積極的な姿勢。弾ける笑顔。ハキハキの挨拶…など)●ということで、いつも「面接の5割くらいだろうな」という覚悟が必要だし、そうした視点で面接をしておかないと、ガッカリさせられることになる。(面接通りの場合は、大成果として考えるくらいでちょうどよい)だから「この人が最高の状態の時はこうなる」という確認ができた…、くらいに思っておくべきだ。●または、サッカーのチームを作るように、それぞれのポジションをしっかり頭に入れて選ばなければならない。マルチにできる人なんてそんなにいるもんじゃないから。そういう考えがない人事担当者は…キレちゃうんだな、これが…(笑)。
2007/03/01
閲覧総数 4
-
7

失敗の原因の視点
中国に通うようになって、色々なところで、中国でのビジネスの成功と失敗の話を聞くようになった。(上海にいる時も、東京にいる時も)足掛け4年間そういう話を耳にして、時には議論して感じた事がある。特に失敗例の話では、よく、中国人の習慣や文化の違いから初めって(働かない、自分勝手など)政府の政策、(コロコロ変わる)…果ては反日へと、果てしなくたくさん出てくる。そういう話を聞かされると最初の頃は躊躇ったりしたものだ。ところが最近実務を通して気がついたことがある。もし、それが全部丸ごと本当ならばどの企業も危なくて進出できないはずである。ところが現実は同じ条件化で成功もあれば失敗もある。上記のような失敗の理由は一見それらしく思えるしある程度は当たっているのかもしれないが、ズバリ言って、駐在している、あるいは対中を任されている日本人担当者が必ずしも優秀なビジネスマンではない…という視点が抜けているかもしれない…と。(かなり過激な意見かもしれないが…)もちろん優秀な人もいて、そういう人はしっかり成果を出している。企業が日本から送り出す人材に手抜きがあれば失敗するのは仕方ないこと。それはなめていることに変わりない。ただ、報告として、また敗因の分析が「自分の能力以外」のことを対象にしているから真実がよく見えなくなる。(この辺は、テーマパークやリゾート、第三セクターの例と大変似ている)見方によっては、本当は担当者が優秀でない、人によってはどこかの国の政治家のごとく、毎週ゴルフに小姐のクラブ通いで、おまけに愛人まで囲って、日本では味わえない3ランク上の成金を楽しんでいた…(もちろん経費の使い込みも)という事実は報告書には出てこない。そういうのは関係ないこと…という大前提に勝手に解釈して失敗の原因を「中国人は…」とやるから始末が悪い。散々女遊びだけはしっかりしておいて、それはないだろう…と思っている中国人もたくさんいる。ハッキリ言って、上記のように舞い上がってばかりで実は対して仕事をしていなかった…という事実があるから(あるいは無能だった)失敗の原因は視点をあれこれ変えてみないとわからないというのが正解である。これらは中国に限ったことではない。諸外国でも同様で、成功したいならばやはり精鋭を送り込まなければならない。例えば、20代はたくさん働いて遊んでいた人でそういうことに今さら舞い上がらないという人物も欲しい。ビジネス系の雑誌にはあまり出てこないこんな視点もあるな、と思っている。
2004/08/20
閲覧総数 8
-
8

<中国人 vs 日本人の短所の比較>
とかく「日本人のサービスは良くて、中国人は悪い」とか、「長所と短所」を比較してはしゃいでいる人を見かけますが、それはおかしいと台湾人に教えてもらいました。どちらにも短所はあるし同じ短所を比較することではじめて「違い」がわかるし、ユニークさもわかるから、結果現場で役に立つとのこと。さすがです!ということで、さっそく日本のサービス現場で働く中国人スタッフの方々に療法の短所を上げてもらうようになりました。(最近は毎回やってます:笑その結果は、大体以下に集約されます。ということで現在のところのベスト10。●マナーが悪い中国人、マナーを相手に求める日本人●自分勝手な中国人、意地悪な日本人●声が大きい中国人、何言ってるのか聞こえない日本人●すぐに怒る中国人、後でグズグズ言うネッチーな日本人●感情がすぐ顔に出る中国人、感情を隠す能面な日本人●客と喧嘩する中国人、客になると途端に偉そうな日本人●白黒つけたがる中国人、グレーだからけで結論無き日本人●すぐに値切る中国人、値切り交渉しないで他店に行く日本人●面子にこだわる中国人、プライドにこだわる日本人●他人に関心がない中国人、他人に厳しい日本人その他、なるほどなぁと思ったのが…●すぐに弁償を求める中国人、すぐに上司を出せと叫ぶ日本人これはFacebookで公開したら、中国人からも日本人からも、やっぱり「なるほど!」「的を得てる!」と評判でした。何かの参考になれば幸いです。★レジャーサービス研究所のホームページ★中国人観光客にもっと売る新“おもてなし術”価格:1,470円(税込、送料別)
2013/09/25
閲覧総数 154
-
9

うれしかった@東方欣康サロンセミナー
第3回の東方欣康サロンセミナーに講師として呼んで頂いた。主催のつっちーさんと事務局のセヤさんご夫婦のお世話になってなんとか無事に終えることが出来た。上海にこんな所があるんだ?!とビックリするような、まさに「上海の田園調布」と呼ぶに相応しい優雅な住宅街にある日本庭園が美しいサロン。活きた情報が交換できれば…という想いが主催者の皆さんからヒシヒシと伝わってくる。大変楽しい時間を過ごす事ができた。今後はどんな講師が登場するのだろうか?興味は尽きない。本音で言えば、東京にもこういう所があればいいのに…。中でもうれしかったのは、普段、上海で一緒に飲んだり食事したりの友人たちが有料にも関わらず、あえてゲストをして参加してくれたことである。年齢的には僕よりも10歳も若い人たちだが、時には友人として、時には上海の先輩として、時には、仕事のサポーターとして、そして、このようにゲストとして…と、色んな角度でお付き合いができることが何よりもうれしかった。
2005/04/27
閲覧総数 13
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-
-
-

- 政治について
- 【片山さつき大臣に正念場】※緊急速…
- (2025-11-16 18:49:04)
-
-
-
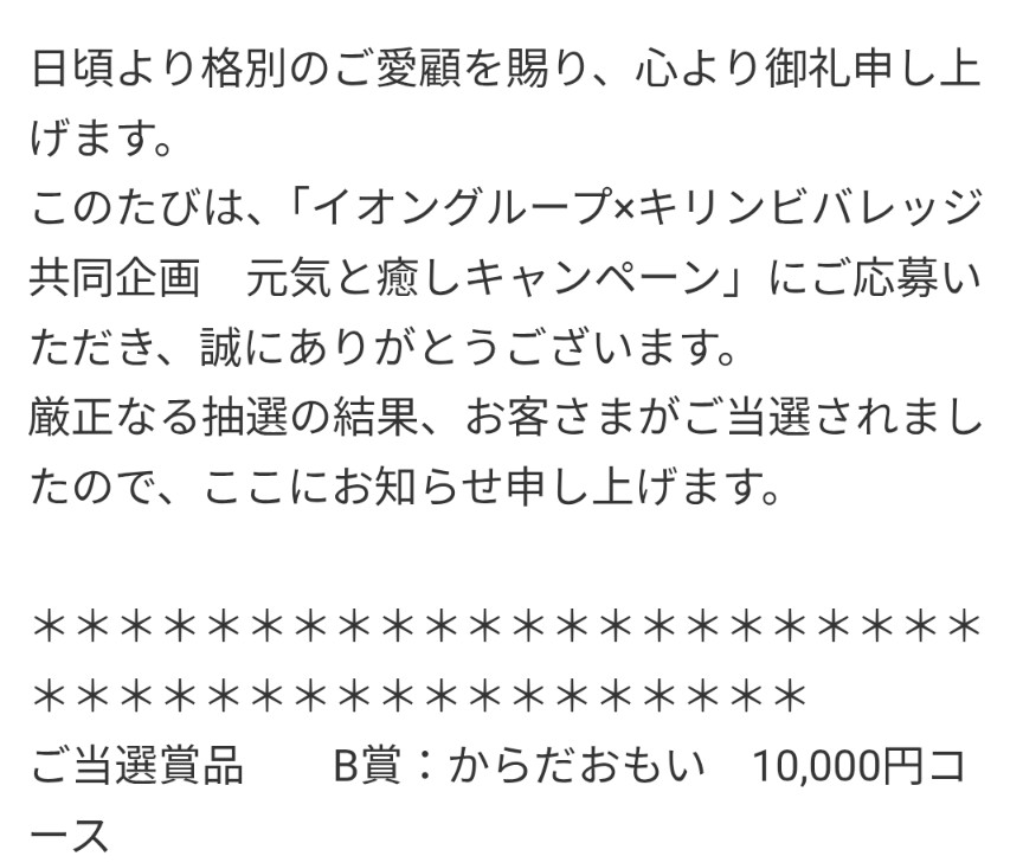
- 懸賞フリーク♪
- からだおもいデジタルカタログギフト
- (2025-11-16 00:56:51)
-







