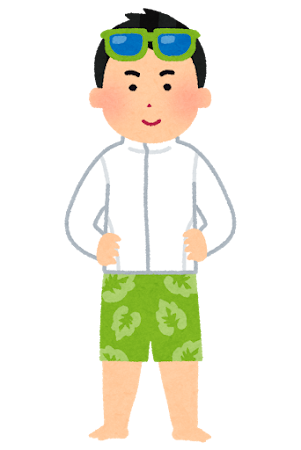全5件 (5件中 1-5件目)
1
-

期待
キャンプも終わり、日常が戻っていた。「帰ったら連絡するよ」そう言って携帯の番号を森に教えてから1週間がたっていた。仕事をしながら森の連絡を待つ時間は忘れていた昔の淡い恋心に酔いしれる時間でもあった。仕事帰り、美咲を迎えに保育園に行く深雪。「ママおかえり~」屈託のない笑顔で迎えられると、仕事の疲れが吹き飛ぶ。「ただいま、今日もおりこうにしてたの?」「うん!きょうはカナちゃんと遊んだんだよ~」「そうかぁ。よかったね。楽しかったんだ」保育園に預けた当初は、大泣きして仕事に行く深雪を困らせていたのに、今ではすっかり慣れ親しんでいるようだ。「じゃあ、学童に寄ってお姉ちゃん迎えに行こうか」「うん!」美咲を車に乗せ、学童にあずけているゆかりを迎えに行く。「進藤さんお帰りなさい。ご苦労様です」迎え出てきたのは学童の指導員の市川だった。年は深雪と同い年で、若いが子供たちをしっかり指導してくれるよき青年だ。「どうですか?ゆかりは慣れてきましたか?」「ええ、少し友達と喧嘩してましたが、大丈夫ですよ」「複雑な事情で家庭が不安定なので・・よろしくお願いします」「わからない事があったら何でも聞いてくださいね」「ありがとうございます。では明日もよろしく」美咲が奥で友達と遊んでいる手を止め、深雪に近づいてきた。「お母さんおかえりなさい!」「ただいま。帰ろうか」「今日はご飯なに?」「今日は二人が大好きなハンバーグかな?」「わ~い!やったね!」二人を車に乗せ、今日合った事を話しながら帰路に着いた。夕飯を済ませ、子供たちが寝入った9時半、部屋の片づけをしながら一人ソファに横になると携帯が鳴った。え?公衆電話?誰からだろう?こんな時間に・・外からかけてくる友人はいない。深雪は首を捻りながら通話ボタンを押した。「もしもし?」「深雪さん?僕です。森ですよ」「え!?」声を聞いた途端、胸が高鳴り、心臓が飛び出してしまいそうなほど驚いた。そして、1週間待ちわびていた自分に気がついた。「お、お久しぶりです」「ごめんね、公衆電話だからびっくりしたでしょ?」「え、ええ。お仕事の帰りですか?」「そうです。今バスから降りたところで」「そうなんですか。お疲れ様です」「実はね・・」「え?」「深雪さんのマンションの近くにいるんですよ」「え!?」「ちょうど下にいるんです」深雪は携帯片手にリビングに走り、窓を明けバルコニーから下を覗き込んだ。暗くてよく見えないが、茶色のスーツにビジネスバッグを持った森が電話ボックスから手を振っていた。「よ、よければあがっていらっしゃいませんか?」「え?でもお子さんがいらっしゃるでしょ?」「いえ、もう二人とも寝ていますから・・」少し戸惑った様子の森だったが、「判りました。じゃあ、少しだけ・・」煙草を足で消して、ボックスから出て森がマンションのロビーに歩き出した。「ど、どうしよう・・・」深雪は誘ってしまった自分自身に驚いていた。別居をしてはいるものの、ここは夫のマンション。罪悪感にかられながらも、もう一度会いたいという気持ちを抑える事が出来なくなっていた。玄関のチャイムがなって、ドアが開いた。森があたりを見回しながら「本当に・・お邪魔してもいいのかな?」と、半ば申し訳なさそうに棒立ちしていた。「いいんです、どうぞこちらへ」玄関から森をリビングに案内し、ソファに腰掛けてもらうように言った。「広いお家ですね」「そうですね。外観より広いかもしれませんね」冷蔵庫からおもむろにビールを出し、テーブルに置いた。「あ、ビールですか?」「え?あ、ごめんなさい。お茶がよかったです?」「いえ、仕事から帰ってビールなんて久しぶりなんで。」目を細めながらビールを明け、美味しそうに飲んでいた。「今日はごめん。突然来てしまって」「いいえ、とんでもない。嬉しかったです」そう、本当に嬉しかったのだ。思いも寄らない出来事に、興奮冷めやらぬ状態であった。森の顔を見た途端、森を好きでいる自分を確認した深雪だった。「電話・・なかなか出来なくて。ごめん。いざ電話しようとすると何故か緊張してしまって」「・・待ってました」深雪は森の横に密着するように腰を下ろした。自分でもどうしたのかと思うほどに積極的になっていた。森の手を握り、いたずらっ子の様に顔を覗き込んだ。「・・会いたかったよ」「・・私も・・」唇が触れ、長い間接吻を交わした後、なだれ込むようにソファに横たわった・・。まだ湿った深雪の髪を繊細な森の指が撫でる。夢のような時間に陶酔しながら、森に抱かれていた。
2006/01/17
-

魅惑
昼間の子供との交流は楽しいものだった。川遊びやあゆの掴みどりなど、都会にいたら経験できない事ばかりで、ゆかりも満足そうだった。森の静けさや穏やかな風が心地いい。深雪の心も、この森の中で癒されていた。夜も更け、子供たちがそれぞれのバンガローで就寝「お母さん、おやすみなさい」初めて親子ばらばらで寝ることに、不安半分、期待半分のゆかり。「おやすみなさい。寒いからちゃんと毛布被ってね」「うん!大丈夫だよ!」ゆかりが布団に入った事を確認し、バンガローを出た。「深雪さん。ゆかりちゃん寝た?」シャワーを浴びて、化粧を落とした博美がそこにいた。「ええ、ちゃんと寝たみたい」「じゃ、行きましょ。あのロッジみたいよ」父兄たちが集まる交流会らしい。深雪は少し急ぎ足でロッジに向かっていた。「深雪さん。今日は旦那様は?」「え?あ、今別居中なんですよ」「そうなの。大変ね。私はいないけど」「いないって・・・」「離婚したのよ。バツイチ。」「そうなんですか・・」「ああ~!もう!ため口でいいわよ!」「え?ふふふ」最初のイメージよりも話しやすい人なんだ、と深雪は少し安堵の表情を見せた。「あ、着いた!ここよ」森の中に丸太で作ったわりと大きいロッジがあった。玄関の前には森が他の父兄と立ち話をしていた。「やあ、進藤さんこんばんわ」「こ、こんばんわ」「ちょっと!森さん、私もいるんですけど」「ああ、ごめんなさい近藤さん。」笑みを浮かべながら少しふざけて深雪達を迎えた。「寒いから中に入りましょう」「ええ、そうですね」ロッジの中は暖炉が炊いてあった。フローリングに無造作におかれた座布団。どこに座ればいいんだろうか?と中をウロウロしていると「進藤さん、近藤さん、こちらにどうぞ」森が暖炉に近い場所を陣取っていた。当然のように、森が進藤の横に座っていた。「ではみなさん!お疲れ様でした。父兄同士仲良くやりましょう!」会長の佐々木の音頭で飲み会が始まった。キッチンでは、肉を焼く匂いや、ラーメンのスープの匂いが立ち込めていた。食欲をそそる。「森さん、深雪さんがお気に入りなのね」ビールを飲みながらまるでいたずらっ子のように森と深雪の間に入り、からかう博美。「ええ、私は嘘はつけないので」「も、森さん!」「あら。いいじゃない。幸せよ深雪さん」「そうですよ。そんなに固くならないで」「ふ、二人で私をからかうんだから・・」いつの間にか3人で円になって酒を飲んでいた。照れくさい事もあったが、それ以上に森に何かを感じる自分を隠すために、急ピッチで飲んでいる深雪。「・・・ちょっと飲みすぎちゃったかな?」「深雪?顔真っ赤よ?大丈夫?」いつの間にか呼び捨てになってる・・でもいいわ。「大丈夫、ちょっと風に当たってくるわ」そう言って、深雪は少しふらつきながら外へ出た。ロッジから少し離れた川原に来ていた。水の音が静かな森に響き渡り、風が深雪の頬に当たる。「進藤さん」え?後ろを振り返ると、森がタオルを持って立っていた。「森さん、どうしたんですか?」「足元がおぼつかなかったみたいだから・・」「大丈夫ですよ。心配かけちゃって・・」「よかった。これで顔冷やして」濡れたタオルがひんやりと深雪の頬を冷やした。「少し座って話しましょうか」「ええ、そうですね」森がハンカチを出し、深雪の腰掛ける場所に敷いた。「ありがとうございます。」少しキザな雰囲気もしたが、嫌味のない紳士的な行動に深雪の鼓動が早くなっていった。「・・深雪さん」「え?は、はい・・」名前で呼ばれる事に戸惑いながらも、嬉しかった。「お仕事なさりながらお子さん二人を育てて大変ですね」「いえ、そんな事ないですよ。森さんこそ・・」言葉途中で口を噤んだ。聞いてはいけない領域だと感じた。しかし森がタバコに火をつけながら語りだした。「妻は医者をしてるんです。忙しくてね・・」「でも、森さんも忙しい仕事じゃないですか」「息子と一緒にいる時が僕が生きてる証なんです。息子のために仕事をしているんですよ。だから息子との行事には何をおいても優先するんです」薄暗い中、煙草の火が蛍のように見える。「・・素敵ですね。一樹くんもきっとお父さんが大好きでしょう」「どうなんでしょうね。僕は家庭ではどの位置にいるのか..必死に取り繕っている自分が惨めになることもありますよ」苦笑しながら、少し寂しそうな横顔で呟いていた。「私も、娘たちがいるから自分が生きている証を持てるんです。きっと一人じゃ・・くだらない人生だったかもしれませんね」「・・あなたが一人なら男は放っておかないでしょう?」「そんな事ないですよ!いつもそうやってからかって・・」「・・からかってるつもりはありませんよ」「え・・・?」「僕は言ってるじゃないですか。貴女のファンだって」「どうして・・?だって私のこと何も知らないじゃないですか」「知らなくても、感じる事は出来ますよ」深雪はお酒のせいで動機がするんだと言い聞かせていた。そうよ・・これは酔ってるせいよ・・「森さん、酔ってるんじゃないですか?」「酔ってますよ・・そういう事にしておきましょう」煙草を消し、森の顔が深雪に近づいてきたあっという間だった・・・森の唇が深雪の唇をふさいでいた。突然の出来事に、深雪の心臓は飛び出しそうなほど動揺を隠せなかった。しかし・・・深雪の手はいつの間にか森の頬を触れていた。川のせせらぎと、木々を揺さぶる風の音だけが二人の間を通り過ぎていた・・
2005/12/23
-

動揺
夏休みに入り、学童のキャンプの日時が迫っていた。ゆかりはとても嬉しそうだ。別居をしてからというもの、ろくに何処かへ連れて行くこともなかったからだろう。朝の7時に学童の前にマイクロバスが止まる。「ママ~!遅刻しちゃうよ!早く早く!」ゆかりはリュックを背負い、靴を履いて玄関先でせかすように深雪を呼んだ。「まって、今いくから。」美咲を実家に預けた後、学童に向かった。マイクロバスには既にほとんどの親子が乗っていた。「遅れてしまって・・申し訳ありません」「あ、進藤さんの席は後ろになりますからね」会長の佐々木さんだ。年のころは40代前半といった所だろうか。髪の毛は淡い栗色、サーファーで膝丈のジーンズが似合う上品な女性だった。・・ふとバスの中を見渡すと、森がいない。「あ、あの、森さんは?」「森さんは他のお父さん方とトラックで来ますよ」なぜそんなことを聞くの?と半ば不思議そうに佐々木は答えていた。自分でも何故そんな言葉が出たのか不思議だった。うかつだったかな?でも現地で会えるんだわ・・・深雪は横でゆかりが声をかけていることも気がつかず心が躍っている自分に驚いていた。1時間半ほど車に揺られ、少しウトウトしかけた頃現地についた。「進藤さん、着きましたよ」声を掛けてくれたのは近藤さんという女性。自分と同じ年のころだろうか?スレンダーで少し男好きする面立ち。「あ、すみません。ありがとう」「ママ~寝てたの?だめだなぁ」ゆかりが微笑みながら深雪に叱咤する。「ごめんね、もう起きたから」バスを降りたら、トラックが停まっていた。すでに到着しているようだ。たくさんの男性がたむろしている中、森の姿を見つけた深雪。あっ!いた!荷物を片付ける傍ら、森達のいる場所へ。「進藤さん!私もこの荷物持って行くわ」近藤が近づいてきた。「ありがとう、あ、深雪でいいですよ」「そう?私は博美。よろしくね」二人で並んでキャンプに必要な荷物を運んだ。タバコをふかしながらふと横目で深雪に気がついた森。「やあ、進藤さん。お疲れ様。」「あ、こんにちは。」たった一言が深雪の気持ちを高ぶらせていた。「何々?二人は知り合いなの?」博美が興味津々で深雪に食らいついてきた。「ち、違いますよ?説明会でお見かけしただけで・・」「いえいえ、私進藤さんのファンなんですよ」森がふざけたような口調で、博美の問いかけに答える。「何?何?おだやかじゃないわね~」含み笑いをしながら、じゃあこれで、と博美がバンガローに向かって歩き出した。「森さん、あんな事言っちゃ駄目ですよ」少しうつむきながら、赤面しながら深雪が言った。「いえ・・私はふざけてるつもりはありませんよ」「・・今日も奥さんは見えないのですか?」「ええ、あなたは?」「・・私は別居中なので・・」「別居中なの?そうなんだ・・」ふかしていたタバコを足で消しながら「夜になったら、親同士の交流会がありますよ。お酒がたくさん出ます。楽しみですね」「そうなんですか?私、お酒強いですよ」「僕は弱いですよ。そういうことにしておきましょう」どうしてなんだろう。森が言う一言一言に動揺してしまう。私・・何を期待しているの?自分の気持ちの動揺を抑えるように、昼は子供たちとの交流に時間を費やした。夜・・まさかあんな事になるとは思いもしないで・・
2005/12/22
-

予感
ゆかりを学童保育に預けるため、説明会に行く深雪。別居しているため、養育費は最低限の金額しかもらえない。仕事をしなければ生活できないのである。「こんにちは。進藤ゆかりの母ですが、こちらで・・」ふと前を見て驚いた。入学式の時、横にいたあの男性の姿があった。「あれ?この前のお母さんですね?」「は、はい。貴方も?」「僕は上の息子が入所していて、役員をやってるんですよ」「そうだったんですか、じゃあ下のお子さんも」「ええ、よろしくお願いします」タバコをふかしながら上機嫌に笑いかけてきた。年のころは30代後半、眼鏡をかけ、落ち着いた雰囲気。入学式の時は気にもしなかったが、理数系的な頭のよさが伺える上品な男性だった。「あ、そういえば、お名前聞いてませんでしたね」「これは失礼。森と申します」タバコを置き、差し出された手は女性のような繊細な雰囲気があった。「進藤です。よろしくお願いします」「こちらこそ」何処か恥じらいながら握手をかわした。入所説明会に来ているのは大半が母親の中森がただ一人、男性であった。「森さん、お仕事は?」「ええ、SEをやってます」「・・森さん、奥様は?」相手の出方を見ながらそう聞いていた。「・・妻も仕事していまして、抜けられないものですから・・」「あ、そうなんですか」共働きなんだ。奥さんも忙しい人なのだろう。「わからない事があれば僕に聞いてくださいね」そう言って森が名刺を差し出した。名刺は、大手のコンピューター会社、情報処理部長の肩書きがあった。・・・こんな多忙な人が何故仕事を休んでまで来ているのか?奥さんはもっと忙しい人なんだろうか・・深雪は気にはなったが、これ以上の詮索はしないほうがよさそうだとあえて言葉をとめた。「進藤さん、私のタイプですよ」からかうような、しかし何処か真剣な瞳で深雪を見つめながら森はそう言った。「からかわないでください」言葉を跳ね返したが女としては嫌なものではなかった。「3ヵ月後にはキャンプがあります。親も参加なので是非一緒に行きましょうね」「あの・・森さんが参加なさるのですか?」「ええ、妻は学童には顔を出さないので」「・・お仕事忙しいのに大変ですね」「いえいえ、ここには母子家庭の人もたくさんいらっしゃいます。そんな方達に比べれば僕なんて大した事ありませんよ」どこまでも謙虚に、自分の立場をひけらかさない森の紳士的な態度に、何処か惹かれる自分がいた。説明会が終わり、帰宅してゆかりに話しをした。「ゆかり、明日から学童に行くのよ。」「学童?」「そう。お母さん仕事で帰りが遅いから」「そっか・・・わかったよ」「同じクラスの○○チャンも一緒だから」「うん!大丈夫だよ!ちゃんと行けるから」少し寂しそうな表情も浮かべたが心配かけまいと必死で笑顔で取り繕うゆかりの姿に申し訳ないと思いつつ、深雪はゆかりを抱きしめた。「そうだ!3ヵ月後にキャンプがあるんだって!」「キャンプ!?」「そう。ママも一緒に行くんだよ」「え!ほんと!?わーい!」無邪気に喜ぶゆかりの姿を見ながら傍ら、森とキャンプに参加できる事への期待感を持つ自分の感情に驚いた深雪。どうしてだろう・・なぜかあの人が気になってしまう・・
2005/12/14
-

序章
「ゆかりー!早く支度しなさいよ」深雪は2人の娘を抱え、今年の初めに別居した。今日は長女の入学式だ。でも、父親の姿はない。ゆかりがワンピースのボタンをはめながら「ねえ、ママ・・パパは?」上目遣いに言葉を選びながら深雪に聞く。「・・・ごめんね。パパはお仕事なんだって」取り繕う言葉もどこかぎこちない。「そうかぁ・・仕方ないよね」心の中で詫びながら、決してそれ以上の言葉をかけずにいた。「ママー!おちっこ!」「もう!美咲ってば!一人で行けるでしょ?」次女の美咲は2歳半。まだ父親との事情を理解できる歳ではない。「ほらほら、時間がないから!」ゆかりと美咲を車に乗せ、入学式へ向かった。車を駐車場に停め、美咲を抱っこしながら会場へ向かう。ゆかりには、父と母に手をつながれた子供が自慢げに歩いている姿ばかりが目に入る。深雪に心配かけまいと、取り繕った笑顔で「ママ、今日から小学生だね。嬉しいな」と、深雪を元気付ける。パパがいなくて・・寂しい?「ううん!ママがいるから大丈夫!」たかが6歳の子供が言うその言葉の奥深さを深雪は切々と胸に刻んでいた。「では、父兄の皆様はこちらへ、お子さんは教室へ」手を離し、親子ばらばらになった時、少し寂しそうに深雪を見ていたゆかり。「入場行進頑張ってね」右手でガッツポーズを送ったら、ゆかりも見真似で返してくれた。会場に入ると、椅子が並んでいた。「いちばんまえ、すわゆー!」美咲が張り切って椅子を陣取っていた。ちょうど二つ椅子が空いていたが横に、男性が一人で座っていた奥さんが来るのだろうか?深雪はその男性に聞いてみる。「あ、あのここ、いいですか?」「ああ、どうぞ、一人ですから」そっか。一人なんだ。奥さんは来てないのだろうか。美咲が横の男性に愛想を振りまいている。思わずその男性が微笑み返して、話しかけてきた。「おたくは何組なんですか?」「うちは1組です」「そうですか、うちも1組ですよ」「そうなんですか」深雪は戸惑いながらも、男性から話しかけられる事に心臓の鼓動が早くなっていた。・・後にこの男性との運命に翻弄されるとも知らず・・
2005/12/13
全5件 (5件中 1-5件目)
1