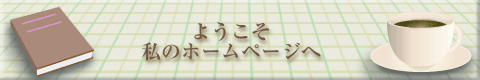幼幻記6 氷水(こおりすい)
氷水(こおりすい)
幼幻記 6
幼幻記 6
小学校に入るにはまだ早い私は祖母が出掛けるときはいつも一緒だった。
暑い夏の日に祖母と出掛けることがあると、祖母は小川屋菓子店に寄って、私に氷水を食べさせるのだった。
当時の小川屋菓子店は店舗から入って南側に入り口があり、そこには東西に長いフロアがあって、そこで氷水やコーヒーなどを楽しめるようにしてあった。
祖母はニコニコしてお店の女主人に
「暑いね~、『こおりすい』をくださいな。ミルクをふたつ!」
といつもの台詞のように言うのだった。
祖母は「氷水」を「こおりすい」と呼んでいた。私はそれが正解なのか、間違いなのかはいまだにわからないが。
祖母と向かい合って椅子に座るのだが、祖母は夏の白っぽい着物がよく似合い、それを引き立たせるように脚を組んで座る。そして汗をハンカチで拭い、扇子を取り出して私に風が来るように扇ぐ。それは幼い私にもとても粋に見えた。
確かお店にはもうおひとり、女主人と姉妹のおばさんがおり、そのおばさんが「こおりすい」を作って、運んで来たように記憶している。
祖母は氷水が運ばれてくるとすぐに財布を取り出して代金を払うのだった。
そして私と自分の膝にハンカチを置く。
グラスにこぼれんばかりに盛られた氷の粉を両手でぎゅっと固め、グラスの脇からスプーンでそっと採って食べていく。
祖母は一口入れると目をつぶり、頭を抱えてしまうのだった。
「ばあちゃん、大丈夫かい?」と私が心配して祖母の顔を探るように見る。祖母は黙って目をつぶったまま、こみかみ辺りを右手でつかんでいる。
私には数分に感じるぐらい沈黙の時間である。
しばらくすると祖母は頭を振りながら頭を上げ、同時にそっと目を開ける。
私が覗き込むようにして祖母の顔を見ていると、祖母の半分開きの目と合う。祖母はそこから思い出したようにやさしい顔で微笑むのだった。
「大丈夫だからね、冷たいものを食べると頭がズズンーと痛くなるんだ」
そして祖母は残りの氷水を私に寄こすのだった。
こんな夏の光景は私が小学校に入学するまで続いた。いまも私は「こおりすい」と呼び、これを食べるとあの祖母の頭痛とやさしい微笑みを想い出す。
2005年8月21日記
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 政治について
- 【高橋洋一×山本期日前】高市総理誕…
- (2025-10-18 11:25:37)
-
-
-

- 楽天市場
- 【マラソン 50%OFFクーポン 21日9:5…
- (2025-10-18 15:41:24)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 【楽天セール】カートに入れたのに値…
- (2025-10-17 22:00:05)
-
© Rakuten Group, Inc.