-
1

建築士の勉強!(法規編第28回)
第28回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 5.耐火・防火 耐火・防火は、性能規定などからの用語の定義を問う問題、法27条や法61条からの構造を問う問題、法61条関連問題、防火区画などから出題されます。近年法改正も多くされているところですので最新の問題で確認したいですね。 今回は、まず用語関連から見ていきましょう!! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 5-1 法2条(耐火性能、準耐火性能、防火性能、遮炎性能) 法23条(準防火性能) 令107条(耐火性能)、令107条の2(準耐火性能)、令108条(防火性能) 令108条の2(不燃性能)、令109条の2(遮炎性能)、令109条の2の2(層間変形角) 令115条(煙突)、令112条 1項(特定防火設備)、令126条 1項(防煙壁) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 1 「耐火性能」とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を 防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう。(1級H17) 2 「準耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために壁、柱、床その他の建築物の部 分に必要とされる性能をいう。 (1級H17) 3 「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために 建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。(1級H17,H21) 4 構造耐力上主要な部分を耐火構造とした建築物は、「耐火建築物」である。(1級H22) 5 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性 能をいう。(1級H17,H26) 6 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能を いう。(1級H30) 7 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周 囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所 定の技術的基準に適合する構造」のいづれかに該当するものでなければならない。 (1級H18,H27,R02) 8 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために 外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。(1級H27,R01) 9 「準防防火性能」とは、建築物の内部において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定 の効果を発揮するために建築物の壁又は天井に必要とされる性能をいう。(1級H17) 10 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動する防火設備を、「特定防火設備」 という。(1級H20) 11 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当 該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、 「特定防火設備」に該当する。(1級H18H,25,R02)12 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当 該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、 「特定防火設備」に該当する。(1級H25,R02)13 天井面から55㎝下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当 する。(1級H20,H25,R01) 14 地上2階建ての建築物に用いる耐火構造の耐力壁に必要とされる耐火性能は、通常の火災 による火熱が1時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損 傷を生じないものであり、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が 可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。(1級H23) 15 主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、所定の技術的基準に適合 するものは、準耐火建築物に該当する。(1級H24) 16 地上2階建ての病院(当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が400㎡で、その部分に 患者の収容施設があるもの)に用いられる準耐火構造の柱にあっては、通常の火災による火 熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の 損傷を生じないものとすることができる。(1級H24) 17 耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障 のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。(1級H26)18 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/120以 内でなければならない。(1級H26)19 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/150以 内でなければならない。(1級H20) 20 耐火建築物の主要構造部は、耐火構造であるか、所定の技術的基準に適合するものである ことについて耐火性能検証法により確かめられたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けた ものであることが求められている。(1級H25) 21 防火性能を有する耐力壁である外壁と準防火性能を有する耐力壁である外壁は、いずれも、 建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、そ れぞれについて定められた時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生 じないものであることが求められている。(1級H25) 22 耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は、いずれも、通常の火災による火熱がそれぞれ について定められた時間加えられた場合に、火熱終了後も構造耐力上支障のある変形、溶融、 破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている。(1級H25)23 通常の火災による火熱が2時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊 その他の損傷を生じないものであること。は、5階建の建築物の1階にある耐力壁である外壁 の「耐火性能」に関する技術基準の一つである。(1級H19)24 建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分 間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない ものであること。は、外壁の「防火性能」に関する技術的基準の一つである。 (1級H19) 25 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、防火上有害な変形、溶融、 き裂その他の損傷を生じないものであること。は、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料の 「不燃性能」に関する技術的基準の一つである。(1級H19)26 建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分 間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。 は、屋根「準耐火性能」に関する技術的基準の一つである。(1級H19) 27 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を 出さないものであること。は、防火設備の「遮炎性能」に関する技術的基準である。 (1級H19) 28 建築物に設ける煙突で天井裏にある部分は、原則として、煙突の上又は周囲にたまるほこり を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものであることが求められる。 (1級H20)29 建築物の屋根に必要とされる性能として、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発 炎をしないものであることが求められる場合がある。(1級H20) 30 準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物で「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は 「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的 基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物に求 められるものと同じ防火設備を有する建築物をいう。(1級H20) 31 屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐火構造及び準耐火構 造の耐力壁である外壁は、いずれも同じ時間、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損 傷を生じないものであることが求められる。(1級H20)32 建築物の立地により異なる防火上の規制が適用される場合として、「特定行政庁が指定す る区域」と「都市計画に定める地域」がある。(1級H20)33 耐火建築物の要件としては、「主要構造部に関する基準」及び「外壁の開口部で延焼のお それのある部分に関する基準」に適合することが求められている。(1級H20) 34 不燃性能は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の 時間、燃焼しないことや防火上有害な変形等を生じないことだけでなく、建築物の外部の仕 上げに用いるものを除き、避難上有害な煙又はガスを発生しないことが求められる。 (1級H20) 35 高さ13mを超える病院においては、主要構造部である柱及び梁に木材を用いることはでき ない。(1級H20) 36 防火上有効な公園、広場、川等の空地又は水面に面する建築物の部分は、延焼のあそれの ある部分から除かれる。(1級H20)37 不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能に関する 技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分 間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生 じないものであること」である。(1級H16) 38 防火構造として、建築物の軒裏の構造が適合すべき防火性能に関する技術的基準は、軒裏 に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30 分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇し ないものであることである。(1級H16) ***************************************************************** 解説 5-1 法2条(耐火性能、準耐火性能、防火性能、遮炎性能) 法23条(準防火性能) 令107条(耐火性能)、令107条の2(準耐火性能)、令108条(防火性能) 令108条の2(不燃性能)、令109条の2(遮炎性能)、令109条の2の2(層間変形角) 令115条(煙突)、令112条 1項(特定防火設備)、令126条 1項(防煙壁) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 耐火・防火に関する用語関連の問題は、ある程度覚えたいところです。用語の定義の問題でも出てくるところですが、あえて同じ問題をここでも紹介しています。用語の意味を理解しておくと、区画や防火の構造等の問題で法令集を確認しなくても解るようになります。 ①耐火性能・準耐火性能・防火性能・準防火性能に関しては、用語の定義1-6にて解説していま すのでそちらをご覧ください。(火事の種類・性能の目的・対象部位は必ず確認して下さい!) ②不燃性性能に関しては、用語の定義1-7にて解説していますのでそちらをご覧ください。 ③耐火建築物・準耐火建築物・遮炎性能に関しては、用語の定義1-8にて解説していますのでそち らをご覧ください。 令107条(耐火性能) 一号(非損傷性):主要構造部に通常の火災による火熱が表に掲げる時間(30分間、1~3時間)加えられた場合、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。(時間を過ぎても変形等しないこと)建物の上部から数えた階数であることに注意!(下階の法が時間が長くなる) 二号(遮熱性):壁及び床に通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面の温度が、可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 三号(遮炎性):外壁及び屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、屋外に火炎を出すき裂その他の損傷生じない。 令107条の2(準耐火性能) 一号(非損傷性):主要構造部に通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後45分間(屋根・階段は30分間)構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。(その時間内変形等しないこと) 二号(遮熱性):壁、床及び軒裏に通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 三号(遮炎性):外壁及び屋根に屋内において発生する通常の火災による火熱加えられた場合、加熱開始後45分間屋外に火炎を出すき裂その他の損傷生じない。 令108条(防火性能) 一号(非損傷性):耐力壁である外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。 二号(遮熱性):外壁及び軒裏に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 令109条の9(準防火性能) 一号(非損傷性):耐力壁である外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。 二号(遮熱性):外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。 令109条の2の2(層間変形角) 主要構造部を準耐火構造とした建築物等の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない 令112条1項(特定防火設備) 令109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの。 令126条の2 1項(防煙壁) 天井面から50㎝下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料造り、又は覆われたもの 。 令115条1項(煙突) 一号:煙突の屋上突出部は、屋根面から垂直距離60㎝以上とすること。 三号:煙突の小屋裏、天井裏等にある部分は、煙突の上部又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる。 1 〇 法2条七号 2 〇 法2条七号の二 3 〇 法2条八号 4 × 法2条九号の二 イ+ロ 耐火構造+外壁の開口部遮炎性能5 〇 法2条九号の二 ロ 6 × 法2条九号の二 ロ 防火設備の性能 7 × 法2条九号の二 イ 当該建築物の屋内において発生する火災8 〇 法23条 9 × 法23条 建築物の周囲の火災に対する外壁の性能10 × 令112条1項 NO.11が正解 11 〇 令112条1項 12 × 令112条1項 1時間 13 〇 令126条 14 〇 令107条一号、二号 15 〇 法2条九号の三 ロに該当 16 〇 法27条1項二号 平27年告示255第11項二号 令107条の2一号17 〇 令107条一号 18 × 令109条の2の2 1/150以内 19 〇 令109条の2の2 20 〇 法2条九号の二 イ 令108条の3 1項 21 〇 令108条一号 令109条の9一号 22 × 令107条一号 令107条の2一号 耐火性能は定められた時間終了後も変形等を生じない ものが求められるが、準耐火性能は定められた時間内変形等を生じないことが求められ ている23 〇 令107条一号 24 〇 令108条二号 25 〇 令108条の2 26 × 令107条の2三号 屋内において発生する通常の火災 27 〇 令109条の2 28 〇 令115条1項三号 イ(1) 29 〇 令109条の8 令136条の2の2 30 〇 法2条九号の三 31 × 令107条三号 令107条の2三号 耐火構造は1時間 準耐火構造は45分32 〇 法22条(22条区域) 法61条(防火地域・準防火地域)33 〇 法2条九号の二 34 〇 令108条の2 35 × 法21条に大規模建築物の主要構造部等の規定はあるが、建築基準法にそんな規定はない36 〇 2条六号 37 〇 令108条の2 38 〇 令108条二号 今年の1級学科が終わりましたが、今年も難しかったですね!過去問だけではも~合格は難しいと言われてはいますが、でもまずは過去問が解けないと始まらないのでやっぱり過去問は大事です。過去問を解くときは、必ず根拠をしっかり理解するようにしてくださいね! 今日はこんな言葉です!! 『基本に忠実であれ。基本とは、困難に直面したとき、志を高く持ち初心を 貫くこと、常に他人に対する思いやりの心を忘れないこと。』 (樋口 廣太郎) 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Jul 13, 2021
閲覧総数 1282
-
2
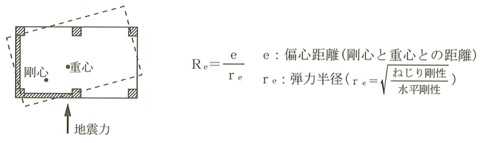
建築士の勉強!第102回(構造文章編第17回 RC造(構造計画-1))
構造文章編第17回(RC造 構造計画-1)構造-23構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)17.RC造(構造計画-1)今回はRC造の文章問題の中から、構造計画・部材の剛性の問題をまとめました。(問題は、一部修正しているものもあります。) *************************************************** 問題 RC造 構造計画-1 □ 鉄筋コンクリート構造計画(2級) 1 部材の曲げモーメントに対する断面算定においては、一般に、コンクリートの引張応 力度は無視する。(2級H14,H19,H22,H23,H25,H27,H29,R01)2 許容応力度設計において、圧縮力の働く部分では、鉄筋に対するコンクリートのかぶ り部分も圧縮力を負担するものとして設計する。(2級H17,H21,H24,H27)3 部材の曲げ破壊は、脆性的な破壊であり、建築物の崩壊につながるおそれがあるので、 せん断破壊よりも先行しないように設計する。(2級H27,R03)4 部材の曲げモーメントに対する断面算定においては、一般に、コンクリートの引張応 力度を考慮する必要がある。(2級R02,R04)5 鉄筋コンクリート造部材の曲げモーメントに対する断面算定は、一般に、曲げ材の各 断面が材の湾曲後も平面を保ち、コンクリートの圧縮応力度が中立軸からの距離に比 例するとの仮定に基づいて行う。(2級R05)6 鉄筋コンクリート構造においては、一般に、「梁又は柱の耐力」より「柱梁接合部の 耐力」のほうが高くなるように設計する。(2級H22)7 鉄筋コンクリート構造においては、偏心率を小さくするために、剛性の高い耐震壁を 建築物外周にバランスよく配置する。(2級H22)8 鉄筋コンクリート構造において、柱や梁に接続する袖壁、腰壁については非耐力壁と して考え、偏心率の算定に当たり、影響はないものとする。(2級H24,H28,R02)9 鉄筋コンクリート造の建築物において、地震力に対して十分な量の耐力壁を設ける場 合であっても、架構を構成する柱については、水平耐力の検討を行うことが必要であ る。(2級H25)10 鉄筋コンクリート造の建築物は、一般に、鉄骨造や木造の建築物より単位床面積当た りの重量が大きいので、構造設計においては地震力より風圧力に対する検討が必要と なる。(2級H30)11 鉄筋コンクリート造の建築物のピロティ階について、単独柱の上下端で曲げ降伏とな るように設計するとともに、ピロティ階の直上、直下の床スラブに十分な剛性と強度 を確保した。(2級R01)12 鉄筋コンクリート造のスラブなどにより床の一体性の確保が図られた剛床仮定のもと では、建築物の各層の地震力は、一般に、柱や耐震壁などの水平剛性に比例して負担 される。(2級R04)13 鉄筋コンクリート造の建築物において、ある階の耐震壁の壁量は、その上階の壁量と 同等以上となるように考慮して配置する。(2級H14)14 鉄筋コンクリートラーメン構造の耐震性の検討において、袖壁、腰壁の影響は無視す る。(2級H15,H22)15 鉄筋コンクリート造の建築物において、柱と腰壁との間に耐震スリットを設けること は、柱の脆性破壊の防止に有効である。(2級H29)16 鉄筋コンクリート構造において、地震力に対して十分な量の耐力壁を配置した場合、 柱については鉛直荷重に対する耐力のみ確認すればよい。(2級H23)□ 鉄筋コンクリート構造計画(1級)1 柱及び梁の靭性を確保するために、部材がせん断破壊する以前に曲げ降伏するように 設計した。(1級H17)2 腰壁が取り付くことにより、柱が短柱となるのを防止するため、柱と腰壁の取り合い 部に、十分なクリアランスを有する完全スリットを設けた。(1級H19)3 許容応力度計算において、コンクリートのひび割れに伴う剛性低下を考慮して構造耐 力上主要な部分に生ずる力を計算した。(1級H23)4 地震時の変形に伴う建築物の損傷を軽減するために、靭性のみに期待せず強度を大き くした。(1級H25)5 細長い平面形状の建築物としたので、地震時に床スラブに生ずる応力が過大にならな いように、張り間方向の耐力壁を外側のみに集中せず均等に配置した。(1級H25)6 1階をピロティとしたので、地震時に1階に応力が集中しないように、1階の水平剛性 を小さくした。(1級H25)7 地震時に単独で抵抗できない屋外階段であったので、建築物本体と一体化し、建築物 本体で屋外階段に作用する地震力に抵抗させた。(1級H25)8 平面形状が細長い建築物において、短辺方向の両妻面にのみ耐力壁が配置されていたの で、剛床仮定に基づいた解析に加えて、床の変形を考慮した解析も行った。(1級H26)9 コンクリートは圧縮力に強く引張力に弱いので、一般に、大きな軸圧縮力を受ける柱の ほうが、靭性は高い。(1級H24)10 鉄筋コンクリートの単位体積重量の算出において、コンクリートの単位体積重量に鉄筋 による重量増分として1kN/㎥を加えた。(1級H24)11 鉄筋コンクリートラーメン構造の応力計算において、柱及び梁を線材に置換し、柱梁接 合部の剛域を考慮した。(1級H27)12 コンクリートのひび割れに伴う部材の剛性低下を考慮して、地震荷重時に構造耐力上主 要な部分に生じる力を計算した。(1級H28)13 建築物の耐震性は、一般に、強度と靭性によって評価され、靭性が低い場合には、強度 を十分に大きくする必要がある。(1級R03)14 構造設計に当たって、建築基準法を遵守して構造計算を行ったので、建築主の要求把握 や目標とする性能の設定は省略した。(1級H24)15 鉄筋コンクリート構造のコア壁を耐震要素とし、外周部を鉄骨造の骨組とした架構形式 は、大スパン化による空間の有効利用に適している。(1級H29)16 平面形状が細長い建築物の応力解析において、短辺方向に地震力を受ける場合には、床 を剛と仮定しなかった。(1級H29)17 外周部の骨組を鉄骨造とし、コア部分の壁を鉄筋コンクリート造とした混合構造形式は、 一般に、外周部の骨組は主に水平力を負担する主要な構造要素とし、コア部分の壁は主 に鉛直荷重を負担する構造形式である。(1級R05)18 鉄筋コンクリート造で、地下部分も含めて別棟とするに当たって、保有水平耐力計算で 用いる大地震時程度の荷重に対しては、簡便的に、それぞれのエキスパンションジョイ ントがある部分の高さをH とし、当該高さにおける間隔がH/50 以上であることを確か めた。(1級R05)19 地下部分(1 階の床・梁を含む。)が一体で地上部分を別棟とするに当たって、1 階床 スラブを一体の剛床と仮定したので、1 階床スラブでの局部的な地震力の伝わり方の検 討は省略した。(1級R05)20 水平力を受ける鉄筋コンクリート構造の柱は、軸方向圧縮力が大きくなるほど、変形能 力が小さくなる。(1級H15,H27)21 境界ばり(耐震壁に接続する梁)は、一般に、耐震壁の回転による基礎の浮き上がりを 抑える効果がある。(1級H15)22 鉄筋コンクリート構造の建築物において、柱・梁と同一構面内の腰壁や袖壁が、建築物 の耐震性能を低下させる場合がある。(1級H17)23 上下層で連続する耐力壁の全高さと幅の比(全高さ/幅)が大きい場合、耐力壁の頂部 を剛性の高い梁で外周の柱とつなぐことによって、一般に、地震時にその耐力壁が負担 する地震力の割合を高める効果がある。(1級H21)24 鉄筋コンクリート造の建築物における垂れ壁や腰壁のついた柱は、垂れ壁や腰壁のつか ない同一構面内の柱と比べて、靭性が高いと判断した。(1級H23)25 鉄筋コンクリート造の柱は、せん断補強筋量が規定値を満足する場合、主筋が多く入っ ているほど変形能力は大きい。(1級H23)26 鉄筋コンクリート造の建築物で壁の多いものは、水平剛性及び水平耐力を大きくするこ とができるが、脆性的な壁のせん断破壊を生じやすい。(1級H24)27 細長い連層耐力壁に接続する梁(境界梁)は、耐震壁の回転による基礎の浮き上がりを 抑える効果がある。(1級H25,R04)28 鉄筋コンクリート造の建築物において、柱及び梁と同一構面内に腰壁やそで壁がある場 合、耐力は大きいが、脆性的な破壊を生じやすい。(1級H26)29 鉄筋コンクリート造の低層建築物において、最上階から基礎まで連続していない壁であっ ても、力の流れを考慮した設計によって、その壁を耐力壁とみなすことができる。 (1級H26)30 鉄筋コンクリート部材の変形能力を大きくするために、コンクリート強度及びせん断補 強筋量を変えることなく主筋量を増やした。(1級H27)31 高強度鉄筋コンクリートや高強度鉄筋の実用化等により、高さ100mを超える鉄筋コン クリート造の建築物が建設されている。(1級H25,H30)32 鉄筋コンクリート造の多層他スパンラーメン架構の建築物の1スパンに連層耐力壁を設 ける場合、連層耐力壁の浮き上がりに対する抵抗力を高めるためには、架構内の中央部 に設けるより、最外端部に設ける方が有効である。(1級H30)33 1階にピロティ階を有する鉄筋コンクリート造建築物において、ピロティ階の独立柱の 曲げ降伏に対する層崩壊を想定する場合、当該階については、地震入力エネルギーの集 中を考慮した十分な保有水平耐力を確保する必要がある。(1級R03)34 鉄筋コンクリート造の建築物の耐久性を向上させる手段として、コンクリートの設計基 準強度を高くする方法、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを大きく設定する方法 等がある。(1級R30)35 鉄筋コンクリート造の建築物において、他の層と比べて剛性が低い層は、大地震時に大 きな変形が集中する恐れがあるので、当該層の柱には十分な強度や人靭性を確保する必 要がある。(1級H24)36 建築物の耐火設計については、火災終了まで、建築物を崩壊・倒壊させないことを目標 とする。(1級H28)37 床の積載荷重や部材断面設計において、適度に余裕を持たせて設計することは、イニシ ャルコスト増となるが、一般に、建築物の寿命を延ばし、ライフサイクルコストの節減 に結びつく。(1級H28)38 平面が不整形な建築物をエキスパンションジョイントを用いて整形な建築物に分割する と、一般に、構造体の地震時の挙動が明確になるが、温度応力やコンクリートの乾燥収 縮に対しては、不利になる。(1級H28)39 建築物の耐震性を向上させる手段として、構造体の強度を大きくする方法、構造体の塑 性変形能力を高める方法、建築物の上部構造を軽量化する方法がある。(1級H30)40 建築物の機能性、安全性、耐久性の設計グレードを高く設定して、高品質を求めるのは 必ずしもよい設計とはいえない。(1級R01)41 建築物に作用する荷重及び外力には性質が異なるいろいろな種類があり、取り扱いが難 しいので、法規及び規基準は、荷重及び外力の数値を扱いやすいように便宜的に提示し ている。(1級R01)42 耐震構造の建築物は、極めて稀に発生する地震に対して、倒壊・崩壊しないことが求め られている。(1級H25)43 建築物の基礎、主要構造部等に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料と して国土交通大臣が定めるものは、「国土交通大臣が指定する日本産業規格又は日本農 業規格に適合するもの」又は「国土交通大臣の認定を受けたもの」でなければならない。 (1級H23)44 地震力作用時における層間変形角の算定時において、耐力壁脚部における地盤の鉛直方 向の変形が大きい場合、耐力壁脚部に鉛直バネを設けた検討を行った。(1級H21)□ 部材の剛性(1級)1 一次設計の応力算定において、スラブ付き梁部材の曲げ剛性として、スラブの協力幅を 考慮したT形断面部材の値を用いた。(1級H21)2 柱部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントはコンクリート断面を用い、ヤ ング係数はコンクリートと鉄筋の平均値を用いた。(1級H21)3 鉄筋コンクリート造の腰壁と柱の間に完全スリットを設けた場合であっても、梁剛性の 算定に当たっては、腰壁部分が梁剛性に与える影響を考慮する。(1級H20)4 柱の剛性評価において、腰壁と柱との接合部に完全スリットを設けたので、腰壁部分の 影響を無視した。(1級H21)5 垂れ壁や腰壁が付く柱が多かったので、当該柱や当該階の耐力を大きくして設計した。 (1級H21)6 柱の設計において、垂れ壁や腰壁のついた柱については、同一構面内の垂れ壁や腰壁の 付かない柱より先に降伏するので、靭性能を持たせるようにした。(1級H21)7 柱の曲げ剛性を大きくするために、引張強度の大きい主筋を用いた。(1級H25)8 鉄筋コンクリート造の建築物の柱の剛性評価において、腰壁と柱とが接する部分に完全 スリットを設ける場合は、腰壁部分の影響を無視してもよい。(1級H25)9 鉄筋コンクリート造の建築物の腰壁と柱との間に完全スリットを設けることにより、柱 の剛性評価において腰壁部分の影響を無視することができる。(1級H30)10 鉄筋コンクリート造の腰壁付き梁の剛性は、腰壁と柱の間との間に完全スリットを設け た場合であっても、腰壁の影響を考慮する必要がある。(1級R01)11 鉄筋コンクリート造の腰壁と柱の間に完全スリットを設けた場合には、梁剛性の算定に 当たっては、腰 壁部分が梁剛性に与える影響を考慮しなくてよい。(1級R04)12 柱及び梁の剛性の算出において、ヤング係数の小さなコンクリートを無視し、ヤング係 数の大きな鉄筋の剛性を用いた。(1級H24)13 鉄筋コンクリート造の腰壁と柱の間に完全スリットを設けた場合には、梁剛性の算定に 当たっては、腰壁部分が梁剛性に与える影響を考慮しなくてよい。(1級R04)************************************************* 解説 RC造 構造計画-1 □ 鉄筋コンクリート構造計画 ① コンクリートの強度の大小関係は、圧縮>曲げ>引張である。コンクリートの引張強 度は非常に小さく圧縮強度の1/10程度であり、構造設計では、許容引張応力度は無視 する。一般に、圧縮強度が大きくなるほど、圧縮強度に対する引張強度の割合は小さく なる。② 鉄筋コンクリート部材の圧縮力に倒する計算では、かぶり部分も含むコンクリート全断 面積で検討する。③ RC造建築物は、靭性破壊(曲げ破壊)を先行させるように計画にする。脆性破壊(せん 断破壊)は、変形を伴わず急激に壊れる脆い破壊で、建築物が倒壊する危険性があるが、 靭性破壊は、粘りのある破壊で、建築物の急激な破壊を回避することが可能である。 柱の変形変形能力を上げるには、せん断破壊させないことが重要でせん断補強筋を適切に 入れること。主筋を多く入れても、付着割裂破壊につながり変形能力向上にはならない。 ④ 建築物は、強度又は靭性(粘り)を高めるようにする。強度指向型が、靭性指向型かを 決める。例えば、靭性に乏しい構造であっても、十分に強度を高めた強度指向型の設計 にすることによって、耐震性の確保ができる。⑤ 鉄筋コンクリート造の建築物で壁の多いもの(同一構面内に腰壁や袖壁が多いもの等) は、水平剛性及び水平耐力は大きくなるが、脆性的な破壊を生じやすい。⑥ 「柱・梁接合部」は、水平荷重時に大きなせん断力がかかる部分であり、大地震の際は、 地震のエネルギーを吸収する重要な構造部位である。従って、「梁又は柱の耐力」より も「柱・梁接合部の耐力」の方が高くなるようにし、「梁又は柱」が「柱・梁接合部」 よりも先に降伏するように設計する。⑦ 地震力は、建築物の重さの中心である重心に作用し、床面の剛性(面内剛性)により、 各柱や耐力壁に伝達され、剛心(各階の硬さの中心)によって地震力に抵抗する。重心 と剛心の距離が大きいと、建築物はねじれ現象を起こしてしまうので、重心と剛心の距 離は、出来るだけ小さくなるように計画する。偏心率(Re)は、次式で求められる。 偏心率の値が大きいほど、その階のねじれ変形の大きい部材に損傷が集中する危険性 が高いことを示す。各階15/100(0.15)以下であることを確かめる。剛性の高い耐 力壁を、建築物の外周にバランスよく配置すると偏心率を小さくすることができる。 ⑧ 建築物は、地震力などの水平力を受け変形しようとするが、柱や壁はこれに抵抗する。 この抵抗の度合いを剛性と言い、水平変形のしにくさ(かたさ)を表す。剛性率(Rs) は次式で求められる。 剛性率の値が小さいほど、その階に損傷が集中する危険性が高いことを示す。各階 について6/10(0.6)以上であることを確かめる。ある階の耐力壁の壁量は上階と 同等以上であることが望ましい。特に、ピロティなどの壁のない(剛性の小さい) 階は、その階だけ変形が大きくなり、破壊する層崩壊の危険性があるので柱の耐力 (強度)、靭性(粘り)を大きくする。(必要保有水平耐力の割増を行う。)⑨ 偏心率や剛性率の算定など、耐震性の検討をする場合、耐力壁だけでなく、袖壁、 腰壁、垂れ壁などの非耐力壁の影響も考慮する必要がある。⑩ 鉄筋コンクリート造においては、柱と梁で構成されるラーメンと、耐震壁の双方に 耐力を分担させる設計とするので、仮に耐震壁が十分であっても、ラーメンにも水 平力を分担させるようにする。⑪ 地震時応力(地震層せん断力)は、建物重量に比例して大きくなるので単位重量の 大きい鉄筋コンクリート造の建築物は、風圧力より地震力に対する検討が重要になる。⑫ 床面や屋根面は、地震力や風圧力などの水平荷重を各階の柱や耐力壁に伝達する働き があるため、構造物の各部分が一体となっいて抵抗できるように、水平構面の剛性を 高くするなど、面内剛性・強度が十分確保されている必要がある。剛床仮定の下では、 同じ層の柱や壁の相対変位は等しくなるため、水平力(地震力)はそれぞれの水平剛 性に比例して負担される。⑬ 細長い平面形状の建築物の場合、地震時に床スラブに生ずる応力が過大とならないよ うに、張り間方向の耐力壁は均等に配置する。また、耐力壁が張り間方向の両妻面の みに配置され、剛床と仮定できない場合、中央部に大きな変形が生じ中央部の柱の負 担せん断力が増すので、両妻面の耐力壁の負担せん断力は剛床と仮定した場合より小 さくなる。⑭ 応力・変形の算定は、原則部材の弾性剛性に基づいて行う。許容応力度計算において は、コンクリートのひび割れに伴う部材の剛性低下を考慮して、構造耐力上主要な部 材に生ずる力を計算することができる。ただし、剛性を低下させて、剛性率、偏心率 を目標値におさめるようなことはしてはならない。⑮ 鉄筋コンクリート柱は、軸方向圧縮力が大きいと、せん断耐力は大きくなるが、圧縮 側コンクリートの破壊により、変形が小さいうちに急激な耐力低下を生じ、脆性破壊 しやすくなるため、靭性能は低下する。⑯ 鉄筋コンクリート構造のコア壁を耐震要素とし、外周部を鉄骨構造の骨組みと架構構 形式は、大スパン化による空間の有効利用に適している。この場合、外周部の鉄骨造 は主に鉛直荷重を負担し、コア部分の壁は水平力を負担する。⑰ エキスパンションジョイントにより分離された構造物は、地震時の衝突等による不具 合を避けるためにクリアランスを設定する。許容応力度計算で用いる中地震程度の荷 重(一次設計用地震力)により生じる変形に対しては、衝突による損傷が生じない事 が求められる。また、保有水平耐力計算レベルの荷重(大地震時の地震力)に対して は、衝突による損傷想定した検討は要求されないが、衝突時の外壁等の落下や、屋外 階段等の損傷など人命にかかわる可能性及び別棟相互の靭性能を損なわないための配 慮が必要である。簡便的に、鉄筋コンクリート造では、エキスパンションジョイント のそれぞれの部分の高さをHとしたときの、当該高さにおける隣等間隔を、H/100以 上とする方法がある。⑱ 地下部分が一体で、地上部分をエキスパンションジョイントにより分離する場合、 1. 地下部分の一次設計については、地下部分及びすべての地上部分を一体として検討 する。この場合の地下部分の検討では、地上部分のルート1やルート2で必要とな る割増規定(S造のCo≧0.3など)は原則適用しなくてもよい。 2. 地上部分がそれぞれ異なる方向の地震力を想定した検討を行う。その場合、2棟に 挟まれた部分の1階床スラブには、局所的な応力集中などの地震力の伝わり方の検 討を行う必要がある。⑲ 連層耐力壁に対する注意点 1. 連層耐力壁に接続する鉄筋コンクリート構造の大梁(境界梁)は、梁が曲げ降伏す る前にせん断破壊が起きないように、せん断補強筋量を多くする。 2. 境界梁の曲げ耐力及びせん断耐力を大きくすると、地震時に連層耐力壁が転倒しに くくなり、耐力壁の負担せん断力は一般に大きくなる。境界梁は、耐力壁の回転に よる基礎の浮き上がりを抑える効果がある。 3. 耐力壁の破壊形式(曲げ降伏、基礎浮き上がり、せん断破壊)は、面内方向の境界 梁や面外方向の直交梁の押さえ効果を評価して決める。 4. 連層耐力壁のように脚部に大きな転倒モーメントが想定される場合は、基礎の浮き 上がりなどによって生じる回転変形を考慮して、壁脚部の固定条件を決める。 5. 多スパンラーメン架構に連層耐力壁を設ける場合は、中央部に配置する方が有効で ある。 6. 上下層で連続する耐力壁の全高さと幅の比(全高さ/幅)が大きい場合、耐力壁の頂 部を剛性の高い梁で外周の柱と繋ぐことによって、地震時にその耐力壁が負担する地 震力の割合を高める効果がある。 7. 鉄筋コンクリート造の建築物の耐力壁脚部のような、地盤の鉛直方向の変形や基礎の 浮き上がりが建築物に及ぼす影響が大きい場合には、地盤ばねを設けるなどして、そ の影響を考慮する。□ 鉄筋コンクリート造構造計画(2級) 1 〇 コンクリートの引張強度は非常に小さく圧縮強度の1/10程度であり、構造設計では、 許容引張応力度は無視する。 正しい2 〇 鉄筋コンクリート部材の圧縮力に倒する計算では、かぶり部分も含むコンクリート 全断面積で検討する。 正しい3 × 曲げ破壊は靭性破壊であり、せん断破壊は脆性破壊である。部材は、せん断破壊よ りも曲げ破壊を先行するように計画する。 誤り4 × コンクリートの引張強度は非常に小さく圧縮強度の1/10程度であり、構造設計で は、許容引張応力度は無視する。 誤り5 〇 曲げ応力度は、曲げモーメントが最大となる最外縁の曲げ応力度を用いて算定する。 正しい6 〇 「梁又は柱の耐力」よりも「柱・梁接合部の耐力」の方が高くなるようにし、「梁 又は柱」が「柱・梁接合部」よりも先に降伏するように設計する。 正しい7 〇 剛性の高い耐力壁を、建築物の外周にバランスよく配置すると偏心率を小さくする ことができる。 正しい8 × 偏心率や剛性率の算定など、耐震性の検討をする場合、耐力壁だけでなく、袖壁、 腰壁、垂れ壁はどの非耐力壁の影響も考慮する必要がある。 誤り9 〇 鉄筋コンクリート造においては、柱と梁で構成されるラーメンと、耐震壁の双方 に耐力を分担させる設計とするので、仮に耐震壁が十分であっても、ラーメンに も水平力を分担させるようにする。 正しい10 × 地震時応力(地震層せん断力)は、建物重量に比例して大きくなるので単位重量 の大きい鉄筋コンクリート造の建築物は、風圧力より地震力に対する検討が重要 になる。 誤り11 〇 ピロティ階は、上下階の床スラブの剛性を上げることで荷重の適切な流れを確保 し、せん断破壊を避け曲げ降伏するように設計する。 正しい12 〇 スラブの水平構面の剛性が高いと、水平荷重を各階の柱や耐力壁の水平剛性に比 例して負担することができる。 正しい13 〇 剛性率の値が小さい階は損傷が集中する危険性が高くなるので、ある階の耐力壁 の壁量は上階と同等以上であることが望ましい。 正しい14 × 偏心率や剛性率の算定など、耐震性の検討をする場合、耐力壁だけでなく、袖壁、 腰壁、垂れ壁などの非耐力壁の影響も考慮する必要がある。 誤り15 〇 柱際にスリットを設けて柱全体の変形能力を上げることは、脆性破壊防止に有効 である。 正しい16 × 鉄筋コンクリート造においては、柱と梁で構成されるラーメンと、耐震壁の双方に 耐力を分担させる設計とするので、仮に耐震壁が十分であっても、ラーメン(柱) にも水平力を分担させるようにする。 誤り□ 鉄筋コンクリート造構造計画(1級) 1 〇 RC造建築物は、脆性破壊(せん断破壊)より靭性破壊(曲げ破壊)を先行させる ように計画にする。 正しい2 〇 柱と腰壁との間にスリットを設けることにより、可撓長さを確保し柱全体の変形 能力を上げ、脆性破壊防止に有効となる。 正しい3 〇 許容応力度計算においては、コンクリートのひび割れに伴う部材の剛性低下を考 慮して、構造耐力上主要な部材に生ずる力を計算することができる。 正しい4 〇 靭性に乏しい構造であっても、十分に強度を高めた強度指向型の設計にすること によって、耐震性の確保ができる。 正しい5 〇 細長い平面形状の建築物の場合、張り間方向の耐力壁は均等に配置することで、 地震時に床スラブに生ずる応力が過大とならないようにすることができる。 正しい6 × ピロティなどの壁のない(剛性の小さい)階は、その階だけ変形が大きくなり、 破壊する層崩壊の危険性があるので柱の耐力(強度)、靭性(粘り)を大きく する。 誤り7 〇 単独で抵抗できない場合は、建築物本体と一体化して地震力に抵抗させる。 正しい8 〇 細長い形状の場合は、均等に耐力壁を入れることが望ましいが、妻側のみにし か耐力壁を入れられない場合は、中央部に大きな変形が生じ中央部の柱の負担 せん断力が増すことを考慮して計画する 正しい9 × 鉄筋コンクリート柱は、軸方向圧縮力が大きいと、圧縮側コンクリートの破壊に より、変形が小さいうちに急激な耐力低下を生じ、脆性破壊しやすくなるため、 靭性能は低下する。 誤り10 〇 鉄筋コンクリートの単位体積重量は、鉄筋の増分1KN/㎥を加算し、概ね24KN/㎥ 以上として算定する。 正しい11 〇 外力を受ける構造物の応力解析では、柱・梁などの部材を線材で表し接合部は剛 節として計算する。 正しい12 〇 許容応力度計算においては、コンクリートのひび割れに伴う部材の剛性低下を考 慮して、構造耐力上主要な部材に生ずる力を計算することができる。 正しい13 〇 建築物は、強度又は靭性(粘り)を高めるようにする。靭性に乏しい構造であっ ても、十分に強度を高めた強度指向型の設計にすることによって、耐震性の確保 ができる。 正しい14 × 構造設計者は建築主の要求を十分把握し、目標とする性能を建築主と設定し、そ れに基づき設計しなければならない。 誤り15 〇 鉄筋コンクリート構造のコア壁を耐震要素とし、外周部を鉄骨構造の骨組みとし た架構構形式は、外周骨組みとコア壁とは両端ピンの鉄骨梁で接合することによ り大スパン化を可能にしている。 正しい16 〇 細長い形状の場合は、中央部に大きな変形が生じ中央部の柱の負担せん断力が増 す。剛床と仮定しないことによりより安全側の設計となる。 正しい17 × 外周部の鉄骨造は主に鉛直荷重を負担し、コア部分の壁は水平力を負担する。誤り18 〇 保有水平耐力計算レベルの荷重に対しては、簡便的に、エキスパンションジョイン トのそれぞれの部分の高さをHとしたときの、当該高さにおける隣等間隔を、H/100 以上とする方法がある。 正しい19 × 2棟に挟まれた部分の1階床スラブには、局所的な応力集中などの地震力の伝わり方 の検討を行う必要がある。 誤り20 〇 鉄筋コンクリート柱は、軸方向圧縮力が大きいと、圧縮側コンクリートの破壊によ り、変形が小さいうちに急激な耐力低下を生じ、脆性破壊しやすくなるため、靭性 能は低下する。 正しい21 〇 境界梁は、耐力壁の回転を抑える効果があるので基礎の浮き上がりを抑える効果 がある。 正しい22 〇 偏心率や剛性率の算定など、耐震性の検討をする場合、耐力壁だけでなく、袖壁、 腰壁、垂れ壁などの非耐力壁の影響も受ける。 正しい23 〇 頂部を固定することにより変形を抑え、耐力壁が負担する地震力の割合を高める ことができる。 正しい24 × 柱に、腰壁や垂れ壁が付くと可撓長さが短くなり短柱となる。靭性は低くなる。誤り25 × 変形能力を上げるには、曲げ破壊する前にせん断破壊させないことが重要であり、 主筋はせん断破壊には有効ではない。せん断補強筋を考慮する。 誤り26 〇 壁の多い建築物は、強度指向であり靭性に乏しいのでせん断破壊を生じやすい。 正しい27 〇 境界梁は、耐力壁の回転を抑える効果があるので基礎の浮き上がりを抑える効果 がある。 正しい28 〇 柱に、腰壁や垂れ壁が付くと可撓長さが短くなり短柱となり脆性破壊しやすくなる。 正しい29 〇 上下連続していな壁でも適切に配置すれば、耐力壁とみなすことができる。正しい30 × 変形能力を上げるには、曲げ破壊する前にせん断破壊させないことが重要であり、 主筋はせん断破壊には有効ではない。せん断補強筋を考慮する。 誤り31 〇 近年では、高強度のコンクリートや鉄筋により、高さ100mを超える鉄筋コンク リート構造の建築物が可能となっている。 正しい32 × 多スパンラーメン架構に連層耐力壁を設ける場合は、中央部に配置する方が有効 である。 誤り33 〇 ピロティなどの壁のない(剛性の小さい)階は、その階だけ変形が大きくなり、 破壊する層崩壊の危険性があるので柱の耐力(強度)、靭性(粘り)を大きくする。 (必要保有水平耐力の割増を行う。) 正しい34 〇 コンクリートの強度を高くする、かぶり厚さを厚くすることは、鉄筋コンクリート 構造物の耐久性の向上につながる。 正しい35 〇 ピロティなどの壁のない(剛性の小さい)階は、その階だけ変形が大きくなり、 破壊する層崩壊の危険性があるので柱の耐力(強度)、靭性(粘り)を大きくする。 (必要保有水平耐力の割増を行う。) 正しい36 〇 火災時に短時間で建築物が崩壊・倒壊すると避難の安全性が確保できない。一定 時間、崩壊・倒壊をさせないことが重要である。 正しい37 〇 部材等に余裕をもって設計することは、耐久性の向上につながり結果として、ラ イフサイクルコストの節減に結びつく。過剰にならないように十分な検討が必要 である。 正しい38 × エキスパンションジョイントは、温度応力やコンクリートの乾燥収縮に対しても 効果がある。 誤り39 〇 耐震性の向上には、耐力の向上、靭性の向上、損傷集中の回避、地震入力の低減、 などがある。上部構造の軽量化は、地震入力の低減につながる。 正しい40 〇 設計グレードを上げて設計することは、耐久性の向上等につながるが、コストの 上昇にもつながる。建築主の要求に応じたうえで十分な検討が必要である。正しい41 〇 建築基準法により、荷重及び外力の数値を便宜的に提示されている。 正しい42 〇 稀に生じる地震に対しては弾性領域にとどめ、損傷しないように設計する。極めて 稀に生じる地震に対しては、塑性変形を許容し倒壊・崩壊を防ぎ人・物品の安全性 を最低限確保する。 正しい43 〇 建築基準法第37条に、指定建築材料は、日本産業規格、日本農林規格、国土交通 大臣の認定を受けたものと規定されている。 正しい44 〇 筋コンクリート造の建築物の耐力壁脚部のような、地盤の鉛直方向の変形や基礎の 浮き上がりが建築物に及ぼす影響が大きい場合には、地盤ばねを設けるなどして、 その影響を考慮する。 正しい□ 部材の剛性 ① 梁に接続する床スラブやハンチ部分・腰壁・垂れ壁が部材に接する部分では、その剛性 を考慮して剛性及び応力の算定を行う。スラブ付き梁、壁付き柱などの曲げ剛性は、ス ラブや壁等板部の協力幅を考慮したT形断面部材の幅を用いる。② 部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントは、コンクリート断面を用い、ヤ ング係数は、コンクリートの値を用いる。鉄筋は無視する。③ 垂れ壁や腰壁により拘束されている柱を短柱という。短柱は、曲げ破壊より先に、せん 断破壊する危険性があるので、柱際にスリットを設けて柱全体の変形能力を上げること や、帯筋を密に配置する等の措置が必要である。柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリッ トを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・垂れ壁部分の影響は無視することができ るが、梁の剛性には関係ない。 □ 部材の剛性(1級) 1 〇 スラブ付き梁、壁付き柱などの曲げ剛性は、スラブや壁等板部の協力幅を考慮した T形断面部材の幅を用いる。 正しい2 × 部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントは、コンクリート断面を用い、 ヤング係数は、コンクリートの値を用いる。鉄筋は無視する。 誤り3 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができるが、梁の剛性には関係ない。 正しい4 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができる。 正しい5 〇 垂れ壁や腰壁が付く柱が多いと当該階全体の剛性が上がり、靭性は低下する。脆性 破壊を防ぐために耐力を上げて対応する。 正しい6 〇 短柱は脆性破壊しやすいので、腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設け可撓範囲 を広げ靭性を持たせるようにする。 正しい7 × 部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントは、コンクリート断面を用い、 ヤング係数は、コンクリートの値を用いる。鉄筋は無視する。主筋は曲げ剛性には 影響しない。 誤り8 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができる。 正しい9 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができる。 正しい10 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができるが、梁の剛性には関係ない。 正しい11 × 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができるが、梁の剛性には関係ないので考慮しな ければならない。 誤り12 × 部材の曲げ剛性の算定において、断面二次モーメントは、コンクリート断面を用い、 ヤング係数は、コンクリートの値を用いる。鉄筋は無視する。 誤り13 〇 柱に腰壁・垂れ壁との間に完全スリットを設けると、柱の剛性評価においては腰壁・ 垂れ壁部分の影響は無視することができるが、梁の剛性には関係ない。 正しい 今回は、RC造の構造計画から構造計画・部材の剛性についてまとめました。次回は、耐震設計についてまとめますが、今回・次回は特に一級ではよく出る所ですので確認してみてください!! 今日はこんな言葉です! 最初から恵まれすぎているより、足りないくらいのほうが、人生からより多くの喜びを引き出せる、ということもあります。成功する可能性はだれにでもあるの。ただ、必要な努力をするかしないかではないかしら。(ターシャ・テューダー)
Dec 31, 2023
閲覧総数 2256
-
3
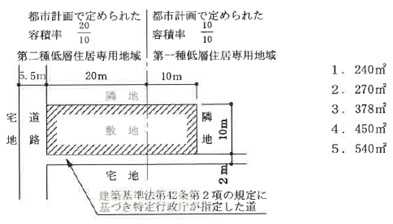
建築士の勉強!(法規編第56回)
第56回建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)法規 13.容積率容積率の問題は、計算問題と文章問題に分けられます。文章問題では、容積対象延べ面積に算入されるかどうかを中心に幅広く問われてきます。計算問題では、2級では用途地域がまたがる場合の計算、特定道路による前面道路の緩和を考慮した計算、容積率対象延べ面積に算入されない部分を考慮する計算など単独で出題されますが、1級ではそれらが複合して問われます。今回は、計算問題を見てみましょう。2級と1級を分けたので、まず2級問題でしっかり理解してから1級を解くと解りやすいかと思います。 (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 13-2 法52条(容積率) 令135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題□ 容積率関連の計算問題(2級)2つの用途地域に渡る場合の延べ面積の最高限度1 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定の基礎と なる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。(2級H16) 2 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H14) 3 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H19) 4 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H20) 5 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H22) 6 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H24) 7 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の 算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H25) 8 図のよな敷地において、建基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、 図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、また、 特定道路の影響はないものとする。(2級H28) 9 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52 条第1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。た だし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとす る。また、特定道路の影響はないものとし、建築物には容積率の算定の基礎となる延べ面積に 算入しない部分及び地階はないものとする。(2級R03) 特定道路を考慮した延べ面積の最高限度1 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定 の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H15) 2 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定 の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H18) 3 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定 の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。 (2級H23) 4 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52 条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただ し、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとす る。(2級H27) 5 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52 条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。た だし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとす る。(2級R02) 地階の住宅部分を考慮した延べ面積1 図のような専用住宅を建築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、 次のうちどれか。ただし、自動車車庫等、備蓄倉庫の用途に供する部分、蓄電池、自家発電設 備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行政庁の指定等は考慮し ないものとする。(2級H15) 2 図のような専用住宅を建築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、 次のうちどれか。ただし、自動車車庫等、備蓄倉庫の用途に供する部分、蓄電池、自家発電設 備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行政庁の指定等は考慮し ないものとする。(2級H17) 3 図のような事務所併用した一戸建住宅を建築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎と なる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等、備蓄倉庫の用途に供する部分、 蓄電池、自家発電設備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行政 庁の指定等は考慮しないものとする。(2級H21) 4 図のような店舗を併用した一戸建住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎と なる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分、エレベーター 、蓄電池、自家発電設備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行 政庁の指定等は考慮しないものとする。(2級H26) 5 図のような事務所を併用した一戸建住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎 となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分、エレベータ ー、蓄電池、自家発電設備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定 行政庁の指定等は考慮しないものとする。(2級R01) 6 図のような エレベーターのない共同住宅を新築する場合、建築基準法上、同法第52条第1項に 規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用 途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとす る。(2級H30) 1級容積率に関する計算問題1 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大の ものは、次のうちどれか。ただし、特定道路の影響はないものとし、建築物には、住宅、自動 車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する 部分はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとする。(1級H16) 2 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率 の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に 記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。 (1級H17) 3 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率 の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に 記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。 (1級H18) 4 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率 の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に 記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。 (1級H22) 5 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率 の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に 記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。 (1級H24) 6 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも のは、次のうちどれか。ただし、建築物の用途は共同住宅とし、地階はないものとする。また 、共用の廊下及び階段の部分の床面積は490㎡であり、建築物内に床面積300㎡の自動車車庫 を設けるものとする。その他には容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供 する部分はないものとする。なお、特定道路の影響はないものとし、図に記載されているもの を除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。(1級H20) 7 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に 規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、 地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級H27) 8 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に 規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、 地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級H28) 9 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に 規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、 地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級R01) 10 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級R03) 11 図のような敷地において、耐火建築物を 築する場合、建築基準法上、建築することができる 「建築物の建築面積の最大値」と「建築物の延べ面積の最大値」との組合せとして、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、特定道路の影響はないものとし、建築物には住宅、自動車車 庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分 はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指 定等はないものとする。(1級H21) 12 図のような敷地において、耐火建築物を 築する場合、建築基準法上、建築することができる建築物の建蔽率(同法53条に規定する建蔽率)建築物の容積率(同法52条に規定する容積率)の最高限度の組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。(1級H30) ***************************************************** 解説 13-2 法52条(容積率) 令135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 法52条(容積率)1項 容積率=容積率算定の基礎となる延べ面積/敷地面積 一号~八号:用途地域による指定容積率(Vs) 容積積率算定の基礎となる延べ面積=敷地面積×容積率 2項 前面道路の幅員が12m未満である場合の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値 に、住居系用途地域は×4/10、住居系以外の用途地域は×6/10を乗じたもの以下としなけ ればならない。(Vd) ∴ VsとVdの小さい方が、その敷地の容積率となる 令135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値) Wa=(12-Wr)(70-L)/703項 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福 祉ホーム(老人ホーム等)の用途に供する部分は、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用 途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度に、容積率算定上の延べ面積には算入しない。 □ 容積率関連の計算問題(2級)2つの用途地域に渡る場合の延べ面積の最高限度 1 4 敷地面積 二低:20m×9m=180㎡ 一低:10m×9m=90㎡ 容積率の検討 二低:Vs=20/10 < Vd=5.5m×4/10=22/10 一低:Vs=10/10 < Vd=22/10 延べ面積検討 二低:180㎡×20/10=360㎡ 一低:90㎡×10/10=90㎡ 合計=450㎡ 2 2 敷地面積 二低:20m×14m=280㎡ 一住:10m×14m=140㎡ 容積率の検討 二低:Vs=10/10 < Vd=4m×4/10=16/10 一住:Vs=20/10 > Vd=16/10 延べ面積検討 二低:280㎡×10/10=280㎡ 一低:140㎡×16/10=224㎡ 合計=504㎡ 3 2 敷地面積 二低:20m×9.5m=190㎡ 一低:10m×9.5m=95㎡ 容積率の検討 二低:Vs=20/10 > Vd=4m×4/10=16/10 一低:Vs=10/10 < Vd=16/10 延べ面積検討 二低:190㎡×16/10=304㎡ 一低:95㎡×10/10=95㎡ 合計=399㎡ 4 3 敷地面積 一住:20m×9m=180㎡ 一低:10m×9m=90㎡ 容積率の検討 一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10 一低:Vs=20/10 < Vd=24/10 延べ面積検討 一住:180㎡×24/10=432㎡ 一低:90㎡×20/10=180㎡ 合計=612㎡ 5 1 敷地面積 二住:20m×10m=200㎡ 一中:20m×4m=80㎡ 容積率の検討 二住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10 一中:Vs=20/10 < Vd=24/10 延べ面積検討 二住:200㎡×24/10=480㎡ 一中:80㎡×20/10=160㎡ 合計=640㎡ 6 1 敷地面積 一住:10m×19m=190㎡ 二低:20m×19m=380㎡ 容積率の検討 一住:Vs=20/10 > Vd=4m×4/10=16/10 二低:Vs=10/10 < Vd=16/10 延べ面積検討 一住:190㎡×16/10=304㎡ 二低:380㎡×10/10=380㎡ 合計=684㎡ 7 2 敷地面積 二住:20m×5m=100㎡ 一中:20m×9m=180㎡ 容積率の検討 一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10 一中:Vs=15/10 < Vd=24/10 延べ面積検討 二住:100㎡×24/10=240㎡ 一中:180㎡×15/10=270㎡ 合計=510㎡ 8 2 敷地面積 一住:20m×9m=180㎡ 一低:10m×9m=90㎡ 容積率の検討 一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10 一低:Vs=10/10 < Vd=24/10 延べ面積検討 一住:180㎡×24/10=432㎡ 一低:90㎡×10/10=90㎡ 合計=522㎡ 9 2 敷地面積 一住:15m×10m=150㎡ 一低:15m×10m=150㎡ 容積率の検討 一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10 一低:Vs=20/10 < Vd=24/10 延べ面積検討 一住:150㎡×24/10=360㎡ 一低:150㎡×20/10=300㎡ 合計=660㎡ 特定道路を考慮した延べ面積の最高限度1 4 敷地面積 10m×20m=200㎡ 特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-21)/70=4.2 容積率の検討 Vs=50/10 > Vd=(6+4.2)m×4/10=40.8/10 延べ面積検討 200㎡×40.8/10=816㎡2 3 敷地面積 10m×15m=150㎡ 特定道路の緩和 Wa=(12-6.5)(70-35)/70=2.75m 容積率の検討 Vs=50/10 > Vd=(6.5+2.75)m×4/10=37/10 延べ面積検討 150㎡×37/10=555㎡ 3 2 敷地面積 10m×10m=100㎡ 特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-49)/70=1.8m 容積率の検討 Vs=50/10 > Vd=(6+1.8)m×4/10=31.2/10 延べ面積検討 100㎡×31.2/10=312㎡4 4 敷地面積 10m×15m=150㎡ 特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-56)/70=1.2m 容積率の検討 Vs=50/10 > Vd=(6+1.2)m×6/10=43.2/10 延べ面積検討 150㎡×43.2/10=648㎡ 5 4 敷地面積 10m×10m=100㎡ 特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-49)/70=1.8m 容積率の検討 Vs=50/10 > Vd=(6+1.8)m×6/10=46.8/10 延べ面積検討 100㎡×46.8/10=468㎡ 地階の住宅部分を考慮した延べ面積1 2 延べ面積:40㎡+50㎡+120㎡+120㎡=330㎡ 地下除外部分:330/3=110㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 40㎡(3F)+50㎡(2F)+120㎡(1F)+10㎡(B1F 120㎡-110㎡)=220㎡ 2 4 延べ面積:60㎡+105㎡+105㎡=270㎡ 地下除外部分:270/3=90㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 60㎡(2F)+105㎡(1F)+15㎡(B1F 105㎡-90㎡)=180㎡ 3 2 住宅部分延べ面積:60㎡+30㎡+60㎡=150㎡ 地下除外部分:150/3=50㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 60㎡(2F)+60㎡(1F)+10㎡(B1F 60㎡-50㎡)=130㎡ 4 4 住宅部分延べ面積:50㎡+70㎡+30㎡=150㎡ 地下除外部分:150/3=50㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 50㎡(2F)+145㎡(1F)+75㎡(B1F 30㎡-50㎡)=270㎡ 5 3 住宅部分延べ面積:60㎡+30㎡+60㎡=150㎡ 地下除外部分:150/3=50㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 60㎡(2F)+120㎡(1F)+70㎡(B1F 60㎡-50㎡)=250㎡ 6 2 住宅部分延べ面積:(90㎡-15㎡)=75㎡,(165㎡-15㎡)=150㎡,(165㎡-15㎡)=150㎡ 合計375㎡ 地下除外部分:375/3=125㎡ 容積率の算定の基礎となる延べ面積: 75㎡(2F)+150㎡(1F)+25㎡(B1F 150㎡-125㎡)=250㎡□1級容積率に関する計算問題1 2 敷地面積 準住:28m×10m=280㎡ 近商:28m×20m=560㎡ 容積率の検討 準住:Vs=20/10<Vd=6m×4/10=24/10 近商:Vs=40/10>Vd=6m×6/10=36/10 延べ面積検討 準住:280㎡×20/10=560㎡ 近商:560㎡×36/10=2016㎡ 合計=2,576㎡2 2 敷地面積 準住:15m×28m=420㎡ 商:20m×28m=560㎡ 容積率の検討 Wa=(12-8.5)(70-30)/70=2m 準住:Vs=40/10<Vd=(8.5m+2m)×4/10=42/10 商:Vs=70/10>Vd=(8.5m+2m)×6/10=63/10 延べ面積検討 準住:420㎡×40/10=1,680㎡ 商:560㎡×63/10=3,528㎡ 合計=5,208㎡3 1 敷地面積 準住:25m×20m=400㎡ 商:15m×20m=300㎡ 容積率の検討 準住:Vs=30/10<Vd=8m×4/10=32/10 商:Vs=60/10>Vd=8m×6/10=48/10 延べ面積検討 準住:400㎡×30/10=1,200㎡ 商:300㎡×48/10=1,440㎡ 合計=2,640㎡4 3 敷地面積 準住:40m×10m=400㎡ 商:40m×15m=600㎡ 容積率の検討 Wa=(12-8)(70-35)/70=2m 準住:Vs=20/10<Vd=(8m+2m)×4/10=40/10 商:Vs=50/10<Vd=(8m+2m)×6/10=60/10 延べ面積検討 準住:400㎡×20/10=800㎡ 商:600㎡×50/10=3,000㎡ 合計=3,800㎡5 1 敷地面積 準住:20m×25m=500㎡ 商:20m×15m=300㎡ 容積率の検討 準住:Vs=30/10>Vd=7m×4/10=28/10 商:Vs=50/10>Vd=7m×6/10=42/10 延べ面積検討 準住:500㎡×28/10=1,400㎡ 商:300㎡×42/10=1,260㎡ 合計=2,660㎡6 3 敷地面積 準住:10m×30m=300㎡ 商:30m×30m=900㎡ 容積率の検討 準住:Vs=20/10<Vd=8m×4/10=32/10 商:Vs=50/10>Vd=8m×6/10=48/10 延べ面積検討 準住:300㎡×20/10=600㎡ 商:900㎡×48/10=4,320㎡ 合計:600㎡+4,320㎡+490㎡+300㎡=5,710㎡ (容積率算定の基礎となる延べ面積は、600㎡+4,320㎡=4,920㎡) 7 3 Wa=(12-8)(70-35)/70=2m Vd=(8m+2m)×6/10=60/10 < Vs=80/10 ∴ 60/10 8 2 敷地面積 一住と商は1,000㎡で同じ面積 容積率の検討 Wa=(12-8.5)(70-20)/70=2.5m 一住:Vs=30/10<Vd=(8.5m+2.5m)×4/10=44/10 商:Vs=70/10>Vd=(8.5m+2.5m)×6/10=66/10 敷地全体の容積率は、敷地面積案分だがおなじ面積なので、 (30/10+66/10)/2=48/10 9 2 敷地面積 準住と商は800㎡で同じ面積 容積率の検討 Wa=(12-8)(70-35)/70=2m 準住:Vs=20/10<Vd=(8m+2m)×4/10=40/10 商:Vs=70/10>Vd=(8m+2m)×6/10=60/10 敷地全体の容積率は、敷地面積案分だがおねじ面積なので、 (20/10+60/10)/2=40/10 10 3 敷地面積 準住と商は200㎡で同じ面積 容積率の検討 Wa=(12-6)(70-35)/70=3m 一住:Vs=20/10<Vd=(6m+3m)×4/10=36/10 商:Vs=60/10>Vd=(6m+3m)×6/10=54/10 敷地全体の容積率は、敷地面積案分だがおねじ面積なので、 (20/10+54/10)/2=37/10 11 4 敷地面積 商:20m×20m=400㎡ 準住:10m×20m=200㎡ 建蔽率の検討 商:8/10→10/10 準住:6/10→8/10(防火耐火+角地) 建築面積 商:400㎡×10/10=400㎡ 準住:200㎡×8/10=160㎡ 合計 560㎡ 容積率の検討 商:Vs=50/10>Vd=8m×6/10=48/10 準住:Vs=30/10<Vd=8m×4/10=32/10 延べ面積検討 商:400㎡×48/10=1,920㎡ 準住:200㎡×30/10=600㎡ 合計=2,520㎡ 12 4 敷地面積 商と準住は600㎡で同じ面積 建蔽率の検討 商:8/10→10/10 準住:6/10→8/10(防火耐火+角地) 敷地全体の建蔽率は、敷地面積が同じなので、(10/10+8/10)/2=9/10 容積率の検討 Wa=(12-10)(70-35)/70=1m 商:Vs=80/10>Vd=(10m+1m)×6/10=66/10 準住:Vs=30/10<Vd=(10m+1m)×4/10=44/10 敷地全体の容積率は、敷地面積がおなじなので、(66/10+30/10)/2=48/10一級の容積率計算問題は、複雑な問題が多いです!まずは、二級問題を使って容積率の基本計算をしっかり覚えて下さい!! 容積率の問題はこれで終わりです。次回からは、高さの問題に入っていきます。容積率以上に難しいですよ! 今日はこんな言葉です。 『いいことばかりが永遠に続かないように、わるいことばかりも 永遠に続かない。 晴天はいつか雨天に変わり、梅雨は必ず送れてもいつか 明けるのである。 変わる日があることを信じて、不運の時は耐えて 努力を忘れないことだ。』 (瀬戸内 寂聴)
Sep 14, 2021
閲覧総数 3271
-
4
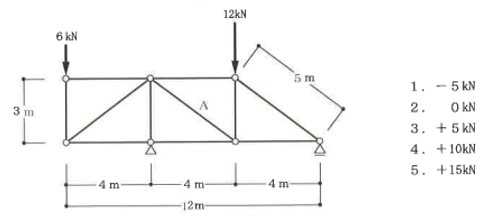
建築士の勉強!第86回(構造力学編第4回トラス)
構造力学編第4回(トラス)建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-8 構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(力学) 4.トラス今回は、力学のトラスです。苦手な方が多い問題ですが、トラスと言っても今までやってきた応力の問題と同じなんです! トラスは軸力しかかからないので、曲げやせん断は考える必要がなく、軸力のみ求めればいいんです。ただ、引張(+)なのか圧縮(-)なのかで迷う人が多いですね。原則、引張(+)方向に仮定して、答えが-と出てきたら圧縮(-)と判断すればいいんです。あと、①0部材、②十字部材、③三角形の先端、この三つの考え方は覚えておくと簡単に解ける問題もあります!!(詳しくは解説で)(問題は、一部修正しているものもあります。)***************************************************************問題 □ トラス1-1 トラス(2級)1 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、斜材Aに生じる軸力として、正しいもの は、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (2級H14)2 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (2級H15)3 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み 合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」 、圧縮力を「-」とする。(2級H16)4 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み 合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」 、圧縮力を「-」とする。(2級H17)5 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み 合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」 、圧縮力を「-」とする。(2級H18)6 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み 合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」 、圧縮力を「-」とする。(2級H19)7 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力NA、NB、 NCの組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力 を「+」、圧縮力を「-」とする。(2級H20)8 図のような下向きの荷重Pを受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる圧縮力・ 引張力の組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。(2級H21)9 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み合 わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、 圧縮力を「-」とする。(2級H22)10 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力として、正しい ものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(2級H23)11 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力として、正しい ものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。なお、接転間距離はすべて2mとする。(2級H24)12 図のような荷重を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力として、正しい ものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。なお、接転間距離はすべて2mとする。(2級H25)13 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力として、正しい ものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(2級H26)14 図のような荷重P受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み合 わせとして、正しいものは、次のうちどれか。(2級H27)15 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力の値として、正 しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」 とする。(2級H28)16 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み合 わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、 圧縮力を「-」とする。(2級H29)17 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み合 わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、 圧縮力を「-」とする。(2級H30)18 図のような荷重P受ける静定トラスにおいて、部材A、B、Cに生じる軸方向力の組み合 わせとして、正しいものは、次のうちどれか。(2級R01)19 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、部材Aに生じる軸方向力の値として、正 しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」 とする。(2級R02)20 図のような荷重条件が異なる静定トラスA、B、Cにおいて、軸方向力が生じない部材の 本数の組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、荷重条件以外の条 件は、同一であるものとする。(2級R03)21 図のような外力を受ける静定トラスにおいて、支点Bに生じる鉛直反力VBと部材AB、 CDにそれぞれ生じる軸方向力NAB、NCDの組み合わせとして、正しいものは、次のう ちどれか。ただし、鉛直反力の方向は上向きを[+]、下向きを[-]とし、軸方向力は、 引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。(2級R04)1-2 トラス(1級)1 図のような荷重を受けるトラスにおいて、上弦材ABに生じる軸方向力として、正しい ものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級H17)2 図のような荷重を受けるトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級H18)3 図のような荷重を受けるトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級H19)4 図のような荷重を受けるトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級H20)5 図のような荷重Pを受けるトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級H23)6 図のような荷重が作用するトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (1級H24)7 図のようなトラスに荷重Pが作用したときの部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (1級H25)8 図のような水平荷重が作用するトラスにおいて、部材A~Eに生じる軸力の組合わせとし て、正しいものは、次のうちどれか。ただし、表中「引」は引張力、「圧」は圧縮力を 示す。(1級H26)9 図のような鉛直荷重Pを受けるトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正し いものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」と する。(1級H27)10 図のような鉛直荷重が作用するトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正し いものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」と する。(1級H28)11 図のような荷重が作用するトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (1級H29)12 図のような水平荷重Pが作用するトラスにおいて、部材A及びBに生じる軸力の組合わせ として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮 力を「-」とする。(1級H30)13 図のような荷重が作用するトラスにおいて、部材ABに生じる軸方向力として、正しいも のは、次のうちどれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。 (1級R01)14 図のような荷重が作用するトラスにおいて、部材A、B、C及びDに生じる軸方向力をそれ ぞれNA、NB、NC及びNDとするとき、それらの値として、誤っているものは、次のうち どれか。ただし、軸方向力は、引張力を「+」、圧縮力を「-」とする。(1級R02)15 図のような荷重が作用するトラスにおいて、部材A、B及びCに生じる軸方向力をそれ ぞれNA、NB及びNCとするとき、それらの大小関係として、正しいものは、次のうちど れか。ただし、 全ての部材は弾性部材とし、自重は無視する。また、軸方向力は、引張 力を「+」、圧縮力を「-」とす る。(1級R04)***************************************************************** 解説 □ トラスの解き方 ① 0部材を見極める!・2コか3コの法則!(接点に対して、角度をもった2つの部材は2つとも軸力は0となる。 接点に対して、3つの部材のうち2つは直線の場合残りの1部材は軸力0となる)② 十字部材を見極める!・接点に対して十字に部材がある場合、ΣX=0、ΣY=0が成り立つ③ 三角形の先端を見極める!・接点に対して角度をもって三つの部材があるとき、一つの力が解れば三角比で求めることが できる。その際、接点を襲ている部材は「圧縮」、接点を引張っている部材は「引張」と判 断する。 ④ 切断法(一般的な応力の求め方と同じ)1) 反力を仮定して、図中に書き入れる。2) 応力を求める位置で構造物を左右(上下)に切断し、何方か一方を選択する。選択する方に 支点があれば、切断する前に反力を求める。3) 切断した図を描き、切断位置に応力を仮定し、図の中に書き入れる。(切断位置より外側 に軸力の方向を仮定する。引張側に仮定)4) つり合い条件式により、応力を求める。・NAは、ΣMO=0より求める。 NBは、X,Yに分解してΣY=0より求め、三角比によりる斜め に戻す。NCは、ΣY=0より求める。5) 応力の向きを検討する。6) 仮定と同じ方向(切断位置から外側向き)は引張、逆は圧縮と判断する1-1 トラス(2級)1 切断法で求める。ΣMB=0より、反力VCを求める。 -6KN×4m+12KN×4m-VC×8m=0 VC=3KN(↑) NAをX,Y成分に分解し、ΣY=0より、NAYを求める。 -12KN+3KN+NAY=0 NAY=9KN(↑) 三角比よりNAを求める。5:NA=3:9KN NA=15KN(引張) 正解 5番2 切断法で求める。ΣMB=0より、反力VCを求める。 -3KN×4m-VC×4m=0 VC=3KN(↓) ΣY=0より、NAを求める。-2KN-3KN-NA=0 NA=-9KN(圧縮) 正解 1番3 切断法で求める。反力VD=1.5P(↑)(式省略) ΣMO=0より、NAを求める。 +1.5P2ℓ-P×ℓ+NA×ℓ=0 NA=-2P(圧縮) NBをX,Y成分に分解し、ΣY=0よりNBYを求める。 +1.5P-P-NBY=0 NBY=0.5P(↓) 三角比よりNBを求める。1:0.5P=√2:NB NB=0.5√2P(引張) ΣMA=0より、NCを求める。+1.5P×ℓ-NC×ℓ=0 NC=1.5P(引張) 正解 4番 4 切断法で求める。ΣMO=0より、NAを求める。 +2KN×3m-NA×3m=0 NA=2KN(引張) ΣX=0よりNBを求める。+2KN-NB=0 NB=2KN(引張) ΣMQ=0より、NCを求める。+2KN×3m+NC×3m=0 NC=-2KN(圧縮) 正解 5番5 切断法で求める。反力VE=1KN(↑)(式省略) ΣMO=0より、NAを求める。 -1KN×4m-NA×2m=0 NA=-2KN(圧縮) NBをX,Y成分に分解し、ΣY=0よりNBYを求める。 +1KN-NBY=0 NBY=1KN(↓) 三角比よりNBを求める。1:1=√2:NB NB=√2P(引張) ΣMQ=0より、NCを求める。-1KN×2m+NC×2m=0 NC=1KN(引張) 正解 1番6 NAは十字部材により、NA=-3KN(圧縮) NCは0部材、NC=0 NBは切断法で求める。NBをX,Y成分に分解し、ΣX=0よりNBXを求める。 +4KN-NBX=0 NBX=4KN(←) 三角比よりNBを求める。4:3=5:NB NB=5KN(引張) 正解 2番7 NCは三角形の先端より、NC=10KN(引張) NA、NBは切断法で求める。ΣMQ=0より、NAを求める。 +6KN×4m+6KN×8m-NA×4.8m(三角比より距離を求める)=0 NA=15KN(引張) ΣMO=0より、NBを求める。 -6KN×4m-NB×4.8m(三角比より距離を求める)=0 NB=5KN(引張) 正解 2番8 NBは十字部材なので、NB=-P(圧縮) NA、NCは切断法で求める。 反力VD=1.5P(↑)(式省略) ΣMO=0より、NAを求める。 +1.5P×2ℓ-P×ℓ+NA×ℓ=0 NA=-2P(圧縮) ΣMQ=0より、NCを求める。+1.5P×ℓ-NC×ℓ=0 NC=1.5P(引張) 正解 2番9 切断法で求める。ΣMO=0より、NAを求める。+1KN×3m-NA×3m=0 NA=1KN(引張) ΣMQ=0より、NCを求める。+1KN×3m+NC×3m=0 NC=-1KN(圧縮) ΣX=0より、NBを求める。+1KN-N=0 NB=1KN(引張) 正解 4番10 切断法で求める。反力VC=3KN(↑)(式省略) NAをX,Y成分に分解して、ΣY=0よりNAYを求める。 -2KN+3KN-NAY=0 NAY=1KN(↓) 三角比よりNAを求める。 1:1=√2:NA NA=√2KN(引張) 正解 2番11 切断法で求める。反力VB=3KN(↑)(式省略) ΣMO=0よりNAを求める。 +3KN×2m+NA×√3=0 NA=-6/√3KN 分母側に√があるので有理化する。 -6/√3×√3/√3=-2√3(圧縮) 正解 4番12 切断法で求める。ΣMO=0よりNBを求める。 -1KN×4m-2KN×2m-NB×2m=0 NB=-4KN(圧縮) NAをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNAYを求める。 -1KN-2KN+NAY=0 NAY=3KN(↑) 三角比よりNAを求める。1:3=√2:NA NA=3√2KN(引張) NCもNAと同様に求める NC=3√2KN(引張) 正解 1番13 切断法で求める。反力VB=2KN(↑)(式省略) NAをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNAYを求める。 +2KN+NAY=0 NAY=-2KN(↓) 三角比よりNAを求める。1:-2=√2:NA NA=-2√2KN(圧縮) 正解 5番14 NBとNCは0部材より、NB=0、NC=0 反力VEは上向き反力(↑) 三角形の先端より、NC=引張 正解 1番15 切断法で求める。NAをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNAYを求める。 -2KN-2KN-NAY=0 NAY=-4KN(↑) 三角比よりNAを求める。1:-4=√2:NA NA=-4√2KN(圧縮) 正解 5番16 切断法で求める。ΣMD=0より、NAを求める。 1KN×6m+2KN×3m-NA×3m=0 NA=4KN(引張) ΣME=0よりNCを求める。1KN×3m+NC×3m=0 NC=-1KN(圧縮) NBをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNBXを求める。 1KN+2KN+NBX=0 NBX=-3KN(←) 三角比よりNBを求める。1:-3=√2:NB NB=-3√2KN(圧縮) 正解 3番17 三角形の先端より、NA=+12KN(引張)、NB=-6√3(圧縮) 0部材より、NC=0 正解 2番18 0部材より、A=3本、B=1本、C=2本 正解 4番19 切断法で求める。反力VC=1KN(↑)(式省略) NAをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNAYを求める。1KN+NAY=0 NAY=-1KN(↓) 三角比よりNAを求める。1:-1=√2:NA NA=-√2KN(圧縮) 正解 2番20 0部材より、A=5本、B=4本、C=2本 正解 4番21 ΣMA=0よりVBを求める。10KN×4m-VB×2m=0 VB=20KN(↑) 切断法によりNABを求める。 ΣMO=0より -20×1m+10KN×2m+NAB×2m=0 NAB=0 NCDは0部材により、NCD=0 正解 1番1-2 トラス(1級) 1 切断法で求める。反力VD=4P(式省略) ΣMC=0よりNABを求める。 -P×2ℓ-2P×ℓ+4P×ℓ+NAB×ℓ=0 NAB=20KN(↑) NAB=0 正解 3番2 切断法で求める。反力VC=1.5P(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 1.5P-P-NABY=0 NABY=1/2P(↓) 三角比よりNABを求める。1:1/2=√2:NAB NAB=+P√2/2(引張) 正解 4番3 NBD、NBEは0部材なので、B点は十字部材となる。NAB=+P(引張) 正解 4番4 切断法で求める。ΣMD=0よりNABを求める。 -P×2ℓ-2P×ℓ+NAB×√2ℓ=0 NAB=+4P/√2 有理化して4P/√2×√2/√2=+2P√2(引張) 正解 5番5 切断法で求める。左側支点の反力V=1P/3(↑)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 +1P/3-NABY=0 NABY=1/3P(↓) 三角比よりNABを求める。√3:1P/3=2:NAB NAB=+2P/3√3(引張) 正解 3番6 切断法で求める。反力VC=5P/2(↑)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 +5P/2-P-NABY=0 NABY=3P/2(↓) 三角比よりNABを求める。1:3P/2=√2:NAB NAB=+3P√2/2(引張) 正解 4番7 切断法で求める。反力VC=P/2(↓)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 -P/2-NABY=0 NABY=-P/2(↑) 三角比よりNABを求める。1:-P/2=√2:NAB NAB=-P√2/2(引張) 正番 1番8 F点で三角形の先端を考えると、NC=圧縮、NB=引張 G点で考えると、反力VGは下向きとなるので、三角形の先端からNA=引張、 NE=圧縮 NDは切断法で考えΣMF=0より、荷重Pが反時計回りなのでNDは 時計回りでないと釣り合わないので仮定の向きと逆になる。ND=圧縮 正番 1番9 切断法で求める。反力VC=P(↓)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 -P+NABY=0 NABY=P(↑) 三角比よりNABを求める。1:P=√2:NAB NAB=+P√2(引張) 正解 3番10 切断法で求める。反力VC=2P(↑)(式省略) ΣMO=0よりNABを求める。 2P×3ℓ/2-P×3ℓ/4-NAB×ℓ√3/2=0 NAB=+18P/4√3 有理化して+3P√3/2(引張) 正解 4番11 切断法で求める。左側支点反力V=2P(↑)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 +2P-P-NABY=0 NABY=P(↑) 三角比よりNABを求める。1:P=√2:NAB NAB=+P√2(引張) 正解 4番12 切断法で求める。NAをX,Y成分に分解、ΣX=0よりNAXを求める。 +P+NAX=0 NAX=-P(←) 三角比よりNAを求める。1:P=√2:NA NAB=-P√2(圧縮) ΣMC=0よりNBを求める。P×3m-NB×3m=0 NB=P(引張) 正解 3番13 切断法で求める。反力VC=6/7P(↑)(式省略) NABをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNABYを求める。 +6P/7-P-NABY=0 NABY=-P/7(↑) 三角比よりNABを求める。√3:-P/7P=2:NAB NAB=-2P/7√3(圧縮) 正解 2番14 反力V=5P/2(↑)(式省略) 三角形の先端よりNAを求める。1:5P/2=√2:NA NA=-5P√2/2(圧縮) 切断法で求める。ΣME=0よりNBを求める。 5P/2×2ℓ-P×ℓ+NB×ℓ=0 NB=-4P(圧縮) NCをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNCYを求める。 +5P/2-P-P+NCY=0 NCY=-P/2(↓) 三角比よりNCを求める。1:-P/2=√2:NC NC=-P√2/2(圧縮) 0部材より、ND=0 正解 2番15 切断法で求める。反力VE=0(式省略) NBをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNBYを求める。 -P+NBY=0 NBY=P(↑) 三角比よりNBを求める。1:P=√2:NB NB=P√2(引張) ΣMF=0よりNAを求める。-P×ℓ+NA×ℓ=0 NA=P(引張) NCをX,Y成分に分解、ΣY=0よりNCYを求める。 -P-P+NCY=0 NCY=2P(↑) 三角比よりNBを求める。1:2P=√2:NC NC=2P√2(引張)∴NA<NB<NC 正解 1番今回は力学のトラスの問題でした。力学の中では苦手な方が多い問題の一つですが、三つのポイント①0部材、②十字部材、③三角形の先端は必ず覚えて下さい。切断法はどんな問題でも使えますが、この三つのポイントを使えばもっと簡単に解ける問題が多くあります。次回は文章問題の各種構造へ入っていきます。RC造・S造。木造が中心ですが文章問題では最もよく出題されている分野です!! 今日はこんな言葉です! 『仕事をする時、この仕事が好きだと思わなければ、 仕事のほうがついてきてくれません。 相手が心を打たれるような情熱がなければ、何事 もうまくいくわけがありません。』 (瀬戸内寂聴)
Sep 16, 2022
閲覧総数 2727
-
5
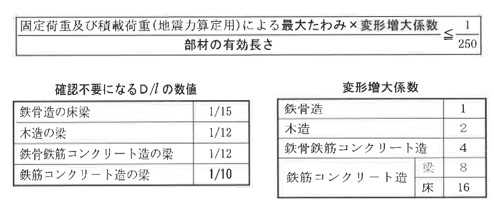
建築士の勉強!第92回(構造文章編第10回 鉄骨造-6(梁の設計・局部座屈))
文章編第10回(鉄骨造-6(梁の設計・局部座屈)) 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-14構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)10.鉄骨造-6(梁の設計・局部座屈) 今回は、鉄骨造の梁の設計と局部座屈に関しての問題です。梁の設計では横座屈が出てきます。鉄骨造においては、柱の圧縮座屈、梁の横座屈、部材の局部座屈と3つの座屈がありますので、特徴をしっかり押さえてください! (問題は、一部修正しているものもあります。) **************************************************** 問題 □ 鉄骨造-梁の設計(横座屈・たわみ) 梁の設計(横座屈・たわみ)2級(1、2は構造計画等で出題) 1 鉄骨造建築物において、大梁は、材端部が十分塑性化するまで、継手で破断が生じな いようにする。(2級R02)2 鋼材のヤング係数は、一般に、引張強さに影響されないことから、引張強さの小さい鋼 材から大きい鋼材に変更しても、梁のたわみは小さくならない。(2級H26)3 はりの設計においては、強度面だけで断面を決定するのではなく、剛性を確保してたわ みを小さくして、震動障害などが生じないように注意する。(2級H14)4 主要な梁材のたわみは、通常の場合、スパンの1/300以下とする。(2級H15)4 座屈を拘束するための補剛材には、剛性と強度が必要である。(2級H18,H27)6 H形断面梁の設計においては、一般に、横座屈の影響を考慮する理必要がある。 (2級H18,H25)7 H形鋼を梁に用いる場合、一般に、曲げモーメントをウエブで、せん断力をフランジで 負担させるものとする。(2級H19,H24,R02)8 荷重面内に対称軸を有し、かつ、弱軸回りに曲げモーメントを受ける溝形鋼について は、横座屈を考慮する必要はない。(2級H19,H22)9 梁の横座屈を防止するために、板要素の幅厚比が制限されている。(2級H21)10 H形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウエブで、曲げモーメントの大部 分をフランジで負担する。(2級H25)11 横座屈のおそれがある曲げ材の許容曲げ応力度は、曲げ材の細長比が大きいものほど小 さい。(2級H27)12 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの1/300以下と し、片持ち梁の場合では1/250以下とする。(2級H29)13 H形断面を有する梁が、強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容 曲げ応力度が小さくなる。(2級H29)14 充腹型の梁の断面係数は、原則として、断面の引張側のボルト孔を控除した断面につ いて算出する。(2級R01)15 鉛直方向に集中荷重が作用するH形鋼梁において、集中荷重の作用点にスチフナを設け る場合、スチフナとその近傍のウエブプレートの有効幅によって構成される部分を圧縮 材とみなして設計する。(2級R01)16 トラスの玄材においては、一般に、構面内の座屈に関する座屈長さを、接点間距離とす ることができる。(2級R02,R04)17 断面の弱軸まわりに曲げモーメントを受けるH形鋼の梁については、横座屈を考慮する 必要はない。(2級R02)18 H形鋼の梁の横座屈を防止するために、圧縮側フランジに補剛材を配置する。 (2級H23)19 長期に作用する荷重に対する梁材のたわみは、通常の場合ではスパンの1/300以下と し、片持ち梁ではスパンの1/150以下とする。(2級H23,H30)20 H形鋼の梁においては、一般に、せん断力の大部分をウエブで負担するように設計する。 (2級H28)21 母屋などに用いる水平材において、長期に作用する荷重に対するたわみは、通常の場 合、仕上 げ材に支障を与えない範囲で、スパンの 1/300 を超えることができる。 (2級R03)22 トラスにおいて、ウェブ材の構面内座屈は、材端支持状態が特に剛である場合を除き、 節点間距離をもって座屈長さとする。(2級R03)23 H形断面を有する梁が強軸まわりに曲げを受ける場合、梁の細長比が大きいほど許容曲 げ応力度は大きくなる。(2級R04)梁の設計(横座屈・たわみ) 1級(1は構造計画等で出題)1 鉄骨造の建築物において、大スパンの梁部材に降伏点の高い鋼材を用いることは、鉛直 荷重による梁の弾性たわみを小さくする効果がある。(1級H26)2 せいの高いⅠ形の断面を有するはりに設ける中間スチフナは、ウエブのせん断座屈に対 する耐力を高める効果がある。(1級H15)3 円形鋼管の許容曲げ応力度は、径厚比の制限に従う場合、許容引張応力度と同じ値とす ることができる。(1級H16)4 H形鋼の梁の横座屈を抑制するための方法として、圧縮側のフランジの横変位を拘束で きるように横補剛材を取り付ける。(1級H16)5 (地上3階建、柱と梁にH形鋼、筋かいに山形鋼、張り間方向をラーメン、けた行方向 を筋かい構造とした建築物において)はりの継手は、せん断力をフランジ継手が負担 し、曲げモーメントをウェブ継手が負担するものとして設計した。(1級H15)6 (地上3階建、柱と梁にH形鋼、筋かいに山形鋼、張り間方向をラーメン、けた行方向 を筋かい構造とした建築物において)小梁と大梁との接合部は、小梁を単純梁として扱 う場合、小梁からのせん断力に対して設計した。(1級H15)7 H型断面の梁において、横座屈を生じないようにするために、この梁に直交する小梁の 本数を増やした。(1級H17,H21)8 応力が許容応力度以下となった梁のたわみを小さくするために、SN400Bから同じ断 面寸法のSN490Bに変更した。(1級H17)9 高張力鋼を使用して梁を設計する場合、長期の設計応力から断面を決定する際に、鉛直 たわみが大きくならないようにした。(1級H19)10 弱軸まわりに曲げを受けるH形鋼の許容曲げ応力度は、幅厚比の制限に従う場合、許容 引張応力度と同じ値とすることができる。(1級H21,H25,R04)11 H型断面梁の変形能力の確保において、梁の長さ、断面の形状・寸法が同じであれば、 等間隔に設置する横補剛の必要箇所数は、梁材が「SN490材の場合」より「SS400材 の場合」の方が少ない。(1級H22)12 H型断面の梁の変形能力の確保において、梁の長さ及び部材断面が同じであれば、等間 隔に設置する横補剛の必要箇所数は、SN490の場合の個所数の方が、SS400の場合の 個所数以上となる。(1級H18)13 剛接架構において、SN400材を用いる代わりに同一断面のSN490材を用いても、弾性 変形を小さくする効果はない。(1級H20)14 H形断面の梁の許容曲げ応力度を、鋼材の基準強度、断面寸法、曲げモーメントの分布 及び圧縮フランジの支点間距離を用いて計算した。(1級H23)15 H形鋼の梁の横座屈を抑制するため、梁の弱軸まわりの細長比を小さくした。 (1級H23)16 梁の弱軸まわりの細長比が200で、梁の全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場 合、梁の鋼種がSN400BよりSN490Bのほうが横補剛の必要箇所は少なくなる。 (1級H25)17 H形鋼を用いた梁に均等間隔で横補剛材を設置して保有耐力横補剛とする場合におい て、梁をSN400Bから同一断面のSN490Bに変更したので、横補剛の数を減らした。 (1級H28,R01)18 曲げ剛性に余裕のあるラーメン構造の梁において、梁せいを小さくするために、建築構 造用圧延鋼材SN400B材の代わりにSN490B材を用いた。(1級H29,R03)19 鉄骨梁のせいがスパンの1/15以下の場合、建築物の使用上の支障が行ないことを確かめ るには、固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値が所定の数値以下であることを確 認すればよい。(1級H25)20 H形鋼の梁の横座屈を抑制するため、圧縮側のフランジの横変位を拘束できるように横 補剛材を取り付けた。(1級H26,R03)21 大梁にH形断面材を用いる場合、梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、 梁端接合部に作用する応力度を減らすことができる。(1級H27)22 トラスの弦材の座屈長さは、清算によらない場合、構面内座屈に対しては接点間距離と し、構面外座屈に対しては横方向に補剛された支点間距離とする。(2級H27)23 ラーメン架構の柱及び梁に、SN400材を用いる代わりに同一断面のSN490材を用いる ことで、弾性変形を小さくすることができる。(1級H27,R02)24 平面計画上、梁の横座屈を防止するための横補剛を梁の全長にわたって均等間隔に設 けることができなかったので、梁の端部に近い部分を主として横補剛する方法を採用 した。(1級H29)25 H型断面の梁の横座屈を防止するための横補剛材は、強度だけではなく、十分な剛性を 有する必要がある。(1級H24,H30)26 梁の横座屈を防止するための横補剛には、「梁全長にわたって均等間隔で横補剛する方 法」、「主として梁端部に近い部分を横補剛する方法」等がある。(1級H30)28 H形鋼等の開断面の梁が曲げを受けたとき、ねじれを伴って圧縮側のフランジが面外に はらみだして座屈する現象を横座屈という。(1級R02)29 梁の横座屈を防止するための横補剛材を梁全長にわたって均等間隔に設けることができ なかったので、梁の端部に近い部分を主として横補剛する方法を採用した。(1級R03)30 小梁として、冷間成形角形鋼管を使用したので、横座屈が生じないものとして曲げモー メントに対する断面検討を行った。(1級R03)31 (露出柱脚、桁行方向は梁をピン接合としたブレース構造、張り間方向は純ラーメン構 造、桁行方向におけるブレースの水平力分担率は100%、耐震計算ルート2の場合)張 り間方向の梁は、横座屈を抑制するために、全長にわたって均等間隔で横補剛を行っ た。(1級H24)32 鉄骨梁のせいがスパンの1/15 以下であったので、固定荷重及び積載荷重によるたわみ の最大値を有効長さで除した値が所定の数値以下であることを確認することにより、建 築物の使用上の支障が起こらないことを確かめた。(1級R04)33 地震時に梁端部が塑性化するH形鋼梁について、一次設計時に許容曲げ応力度を圧縮フ ランジの支点間距離を用いて算定したことにより、十分な塑性変形能力が確保されてい るものと判断した。(1級R04)34 H形鋼を用いた梁の全長にわたって均等間隔で横補剛を設ける場合、梁のせい、断面積 及びウェブ厚さが同一であれば、フランジ幅が大きい梁ほど必要な横補剛の箇所数は多 くなる。(1級R04)□ 鉄骨造-局部座屈(幅厚比)局部座屈(幅厚比) 2級1 鋼管には、局部座屈を起こさないように、管径と管厚の比の限度が定められている。 (2級H14)2 部材がほぼ降伏点に達するまで局部座屈を起こさないようにするため、平板要素の幅厚 比が定められている。(2級H16)3 鉄骨部材は、板厚要素の幅厚比や鋼管の径厚比が小さいものほど、局部座屈を起こしや すい。(2級H18)4 部材の局部座屈を避けるためには、板要素の幅厚比や円形鋼管の径厚比は大きいものと することが望ましい。(2級H20)5 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈を起こしや すい。(2級H22,H24)6 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、板要素の幅厚比が大きいので、ねじれや局部座屈を 起こしやすい。(2級H23,H26)7 H形鋼は、板要素の幅厚比が小さいものほど、局部座屈が生じやすい。(2級H27)8 形鋼の許容応力度設計において、板厚要素の幅厚比が制限値を超える場合は、制限値を 超える部分を無効とした断面で検討する。(2級H21,H23,H29)9 鉄骨部材は、平板要素の幅厚比や鋼管の径厚比が大きいものほど、局部座屈が生じにく い。(2級R01)10 柱及び梁材の断面において、構造耐力上支障のある局部座屈を生じさせないための幅厚 比は、炭素鋼の基準強度(F値)により異なる。(2級R03)局部座屈(幅厚比) 1級1 ラーメン構造において、靭性を高めるために、塑性化が予想される柱又ははりについて は、断面の幅厚比の小さい部材を用いる。(1級H15)2 柱・梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を小さ くした。(1級H17)3 耐震計算ルート2を適用する場合、柱部材を構成する板要素の幅厚比を大きくして、圧 縮応力を受ける部分に局部座屈を生じることがなく、より大きな塑性変形能力が得られ るようにした。(1級H20)4 構造特性係数Dsを算出するための部材種別がFA材であるH形鋼(炭素鋼)の梁につい て、幅厚比の規定値は、フランジよりウエブの方が小さい。(1級H20)5 柱・梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を大き くした。(1級H21)6 H形鋼の柱において、フランジの局部座屈を防ぐため、フランジ厚を薄くし、フラン ジ幅を広げた。(1級H23)7 H形断面梁の設計において、フランジの局部座屈を生じにくくするため、フランジの幅 厚比を小さくした。。(1級H28)8 ラーメン構造において、靭性を高めるために、塑性化が予想される柱又ははりについて は、幅厚比の大きい部材を用いる。(1級H25)9 梁に使用する材料をSN400BからSN490Bに変更したので、幅厚比の制限値を大きくし た。(1級H26)10 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められている柱及び梁の幅厚比の上限値は、 基準強度Fが大きいほど大きくなる。(1級H27)11 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められているH形鋼(炭素鋼)の梁の幅厚比 の上限値は、フランジよりウエブの方が大きい。(1級H27)12 H形鋼の梁の設計において、板厚要素の幅厚比を小さくすると、局部座屈が生じにくく なる。(1級R02)13 柱及び梁に使用する鋼材の幅厚比の上限値は、建築構造用圧延鋼材SN400Bに比べて SN490Bのほうが大きい。(1級R03)14 柱及び梁の種別をFAとするための幅厚比の上限値は、基準強度が大きいほど小さくな る。(1級H24)15 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められているH形鋼(炭素鋼)の柱及び梁の 幅厚比の上限値は、フランジよりウエブの方が大きい。(1級H30,R01)16 柱及び梁に使用する鋼材の幅厚比の上限値は、建築構造用圧延鋼材SN400Bより建築構 造用圧延鋼材SN490Bのほうが大きい。(1級H30)17 骨組みの塑性変形能力を確保するために定められている柱及び梁の幅厚比の上限値は、 基準強度Fが大きいほど小さくなる。(1級R01)*************************************************** 解説 □ 鉄骨造-梁の設計(横座屈・たわみ) ① 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 単純ばり集中荷重のたわみ式(δ=Pℓ³/48EI)の中でヤング係数は一定なので、I(断面二次モーメント=断面形状)を大きくするとたわみは小さくなる。 ② 梁の設計は一次設計において、強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の検討(たわみ(剛性)の検討)を行う。 梁材のたわみは長期に作用する荷重に対して、スパンの1/300以下、片持梁の場合1/250以下とする。ただし、母屋、胴縁等については、その仕上げに支障を与えない範囲でこの限界を超えることができる。(鋼構造許容応力度設計基準) ③ 梁のたわみ(剛性)の検討において、梁せい/有効長さ の値が1/15以下の場合は、下記式にて確認を行う。(平成12年建告1459号) 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリープを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるようにする。 ④ H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、圧縮側がある荷重に達すると、急に構面外(面外方向)にはらみだす横座屈が起こるため、許容曲げ応力度(一次設計における検討)は、横座屈を考慮して与えられている。材幅に比べて材せいが大きい(弱軸まわりの細長比が大きい)ほど、横座屈が生じやすい。鋼管、箱型断面部材、溝形鋼などの弱軸まわりに曲げを受ける対象断面では、横座屈現象が生じない。 ⑤ 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。横補剛材には、曲げモーメントを受ける梁の圧縮側フランジ等が構面外(横)にねじれ、座屈しようとするのを押さえる剛性と強度が必要となる。 梁の許容曲げモーメントは、梁材(曲げ材)の細長比が大きい(縦長形状)ほど横座屈を生じやすくなるので小さくなる。 ⑥ H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定される。 ⑦ 十分に塑性変形が生じるまで横座屈しないようにした横補剛を保有耐力横補剛(二次設計における検討)という。保有耐力横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設ける方法とがある。また、保有耐力横補剛の間隔は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の鋼材によるほうが短くする必要がある。横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。 ⑧ H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 ⑨ 充腹形の梁の断面係数は、断面の引張側のボルトまたは高力ボルトの孔を控除した断面について算出する。 ⑩ スチフナーとは、主に板材が座屈しないように補強する材(補剛材)である。中間スチフナーは、材軸に対して直交方向に設けられ、ウエブのせん断座屈を防止する。水平スチフナーは、材軸に対して平行に設けられ、ウエブの曲げ圧縮座屈を防止する。⑪ H形鋼梁に鉛直方向に集中荷重が加わる場合、ウエブの厚さが比較的薄い場合には、圧壊を防ぐためスチフナーを設ける。この場合、スチフナーとその近傍のウエブプレートの有効幅によって構成される部分を圧縮材とみなして許容圧縮応力度の算定を行う。 ⑫ 大梁と小梁の接合部において、小梁を単純ばりとして扱う場合は、接合部では小梁のウエブのみを接合し、小梁からのせん断力に対して設計する。 ⑬ 大梁にH形鋼断面材を用いる場合、梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、梁端接合部に作用する応力度を減らすことができる。 ⑫ トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計算する。また、トラスのウエブ材における構面内の座屈長さは、材端条件がガセットプレートのようにピン接合と判断できる場合には、接点間距離を座屈長さとする。構面外座屈の場合の座屈長さは、横補剛間隔(支点間距離)とする。 梁の設計(横座屈・たわみ)2級(1、2は構造計画等で出題) 1 〇 大地震により部材の塑性化が予想される場合には、必要に応じた塑性変形をするま で接合部が破断しないように設計する。このように設計された接合部を、保有耐力 接合と言う。 正しい2 〇 鋼材の強度を変えてもたわみは変わらない。 正しい3 〇 梁の設計は一次設計において、強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の 検討(たわみの検討=振動障害に対する検討)を行う。 正しい4 〇 梁材のたわみは通常、スパンの1/300以下とする。 正しい5 〇 横座屈を防止するための補剛材には、座屈を押さえるための強度と剛性が必要とな る。 正しい6 〇 H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、圧縮側がある荷重に達する と、急に構面外(面外方向)にはらみだす横座屈が起こるので、これを考慮して設 計しなければならない。 正しい7 × H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 誤り8 〇 鋼管、箱型断面部材、溝形鋼などの弱軸まわりに曲げを受ける対象断面では、横座 屈現象が生じない。 正しい9 × 幅厚比は局部座屈を防止するために制限されている。横座屈防止ではない。 誤り10 〇 H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 正しい11 〇 曲げ材(梁材)の細長比が大きいほど、許容曲げ応力度は小さくなる。 正しい12 〇 梁材のたわみは通常スパンの1/300以下、片持梁の場合1/250以下とする。 正しい13 〇 曲げ材(梁材)の細長比が大きいほど、許容曲げ応力度は小さくなる。 正しい14 〇 充腹形の梁の断面係数は、断面の引張側のボルトまたは高力ボルトの孔を控除した 断面について算出する。15 〇 H形鋼梁に鉛直方向に集中荷重が加わる場合、スチフナーとその近傍のウエブプレ ートの有効幅によって構成される部分を圧縮材とみなして許容圧縮応力度の算定を 行う。 正しい16 〇 トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計 算する。 正しい17 〇 H形鋼の梁のように強軸回りに曲げを受ける部材には、横座屈があるが、弱軸まわ りに曲げを受ける対象断面では、横座屈現象が生じない。 正しい18 〇 H形鋼の梁に横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい19 × 梁材のたわみは、片持梁の場合1/250以下とする。 誤り20 〇 H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 正しい21 〇 梁材のたわみは長期に作用する荷重に対して、スパンの1/300以下だが、母屋、胴 縁等については、その仕上げに支障を与えない範囲でこの限界を超えることができ る。 正しい22 〇 トラスのウエブ材における構面内の座屈長さは、材端条件がガセットプレートのよ うにピン接合と判断できる場合には、接点間距離を座屈長さとする。 正しい23 × 許容曲げ応力度は、横座屈を考慮して与えられている。梁の細長比が大きいほど横 座屈が生じやすく、許容曲げ応力度は小さくなる。 誤り梁の設計(横座屈・たわみ) 1級(1は構造計画等で出題)1 × 鋼材は、強度を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾 性たわみは変わらない。 誤り2 〇 中間スチフナーは、材軸に対して直交方向に設けられ、ウエブのせん断座屈を防止 する。 正しい3 〇 柱、梁の許容曲げ応力度fbは、角形鋼管や円形鋼管のような横座屈が起こらない形 状のものは、許容引張応力度ftと同じ(fb=ft)とて設計する。 正しい4 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。正しい5 × H形鋼の梁では、曲げモーメントをウフランジで、せん断力をウエブで負担する。 誤り6 〇 大梁と小梁の接合部において、小梁を単純ばりとして扱う場合は、接合部では小梁 のウエブのみを接合し、小梁からのせん断力に対して設計する。 正しい7 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい8 × 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、 同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 誤り9 〇 梁の設計は、強度に関する検討とたわみの検討を行う。高張力鋼の場合は強度が高 く、小さな断面でも大きな荷重に耐えられるが、断面が小さいとたわみが大きくな るので注意する必要がある。 正しい10 〇 弱軸回りに曲げを受けるH形鋼は、横座屈を起こさないので、許容曲げ応力度fbは 許容引張応力度ftと同じとすることができる。 正しい11 〇 横補剛を等間隔に入れる場合の個所数は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の 鋼材によるほうが多くする必要がある。 正しい12 〇 横補剛を等間隔に入れる場合の個所数は、大梁が400N/㎟級に比べ、490N/㎟級の 鋼材によるほうが多くする必要がある。 正しい13 〇 鋼材は、強度(降伏点、引張強さ)を大きくしてもヤング係数は変わらないので、 同じ断面であれば、弾性たわみは変わらない。 正しい14 〇 H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモ ーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定される。 正しい15 〇 H形鋼は、材幅に比べて材せいが大きい(弱軸回りの細長比が大きい)ほど、横座 屈が生じやすい。 正しい16 × 横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。誤り17 × 横補剛を均等間隔に設ける場合は、大梁の強度が高いほど個所数は多くなる。誤り18 〇 梁は強度に関する検討(許容応力度の検討)と使用上の検討(たわみ(剛性)の 検討)を行う。剛性(EI)に余裕がある場合は強度による検討により、より強度の 高い部材を使うことによりサイズを下げることができる。 正しい19 〇 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリー プを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるように検討する。正しい20 〇 横座屈を生じないように、適切な間隔で横補剛材(小梁)を設ける。 正しい21 〇 大梁端部のフランジに水平ハンチを設けることにより、梁端接合部に作用する応力 度を減らすことができる。 正しい22 〇 トラスの玄材の構面内の座屈長さは、略算法として接点間距離を座屈長さとして計 算する。構面外座屈の場合の座屈長さは、横補剛間隔(支点間距離)とする。 正しい23 × 鋼材は、強度を大きくしてもヤング係数は変わらないので、同じ断面であれば、弾 性たわみは変わらない。 誤り24 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい25 〇 横補剛材には、曲げモーメントを受ける梁の圧縮側フランジ等が構面外(横)にね じれ、座屈しようとするのを押さえる剛性と強度が必要となる。 正しい26 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい27 〇 H形鋼の梁の強軸回りに曲げを受ける(開断面に曲げを受ける)部材には、圧縮側 がある荷重に達すると、急に構面外(面外方向)にはらみだす現象を横座屈という。 正しい28 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい29 〇 鋼管は横座屈現象が生じないので、許容曲げ応力度fb=許容引張応力度ftとして計 算することができる。 正しい30 〇 横補剛は梁全長わたり均等間隔に設ける方法と、主として梁端部に近い部分に設け る方法とがある。 正しい31 〇 部材の有効長さに対する、(固定荷重及び積載荷重によるたわみの最大値とクリー プを考慮した変形増大係数の積)の値が1/250以下となるように検討する。正しい32 × H形断面の梁の許容曲げ応力度は、その断面寸法の他に、鋼材の基準強度、曲げモ ーメント分布および圧縮フランジの支点間距離(横補剛間隔)によって決定され る。圧縮フランジの支点間距離のみでは判断できない。 誤り33 × フランジ幅が大きいほど横座屈しにくくなるので、横補剛の個所数は少なくなる。 誤り□ 鉄骨造-局部座屈(幅厚比) ① 鋼材は、降伏するまでの間に局部座屈を起こさないように、幅厚比(幅/厚さ)が決められている。幅厚比が大きくなる(薄くなる)と局部座屈を起こしやすくなる。局部座屈を起こさないように幅厚比の上限が決められていて、基準強度が大きくなるほど小さく(厳しく)なる。またH形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳しい)。鋼管においても、径厚比(管径と管厚の比)が大きくなると局部座屈を起こしやすくなる。② 幅厚比・径厚比が大きくなると、局部座屈が起きやすく、靭性は低下する。② 軽量鉄骨構造に用いる軽量形鋼は、板厚が薄く、幅厚比が大きくなるため局部座屈を起こしやすい。③ 幅厚比の制限を超えた部材断面については、板厚要素ごとに幅厚比の制限を超えた断面の部分を無効とみなして、断面算定を行う。局部座屈(幅厚比) 2級 1 〇 鋼管には、局部座屈を防止するために径厚比(管径と管厚の比)が定められている。 正しい2 〇 鋼材には、降伏するまでに局部座屈を起こさないように幅厚比が佐田園られている。 正しい3 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り4 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすいので、小さい方が望ましい。 誤り5 〇 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 正しい6 〇 軽量形鋼は、板厚が薄く、幅厚比が大きくなるため局部座屈を起こしやすい。 正しい7 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り8 〇 幅厚比の制限を超えた部材断面については、幅厚比の制限を超えた断面の部分を無 効とみなして、許容応力度設計を行う。 正しい9 × 幅厚比や径厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすい。 誤り10 〇 幅厚比の上限は、基準強度が大きくなるほど小さく(厳しく)なる。 正しい局部座屈(幅厚比) 1級1 〇 幅厚比の大きい部材は、局部座屈が起きやすく靭性が低下するので、幅厚比の小さ い部材を用いる。 正しい2 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい3 × 幅厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすくなり、塑性変形能力は得られない。 誤り4 × 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳し い)。 誤り5 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り6 × 幅厚比=幅/厚さ なので、厚みを薄くし幅を広げると、幅厚比は大きくなり局部 座屈しやすくなる。 誤り7 〇 幅厚比を小さくするほど、局部座屈は生じにくくなる。 正しい8 × 幅厚比が大きいほど、局部座屈を起こしやすくなり、靭性(塑性変形能力)は得ら れない。 誤り9 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り10 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り11 〇 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳 しい)。ウエブの方が大きい。 正しい12 〇 幅厚比を小さくするほど、局部座屈は生じにくくなる。 正しい13 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り14 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい15 〇 幅厚比の規定値は、H形鋼のフランジとウエブでは、フランジの方が小さい(厳 しい)。ウエブの方が大きい。 正しい16 × 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 誤り17 〇 基準強度が大きくなるほど、幅厚比の上限値が小さく(厳しく)なる。 正しい今回は、たわみと座屈(横座屈・局部座屈)でしたが、座屈には、前回の柱の設計でよく出る圧縮座屈があります。この3つの座屈(圧縮座屈・横座屈・局部座屈)に関しては必ず出題されますのでしっかり特徴を覚えて下さい!今日はこんな言葉です!『安易な道は効率的だし時間もかからない。困難な道は骨が折れるし時間もかかる。しかし、時計の針が進むにしたがって、容易だった道が困難になり、困難だった道が容易になるものだ。 』 (カーネル・サンダース)
Nov 14, 2022
閲覧総数 4591
-
6
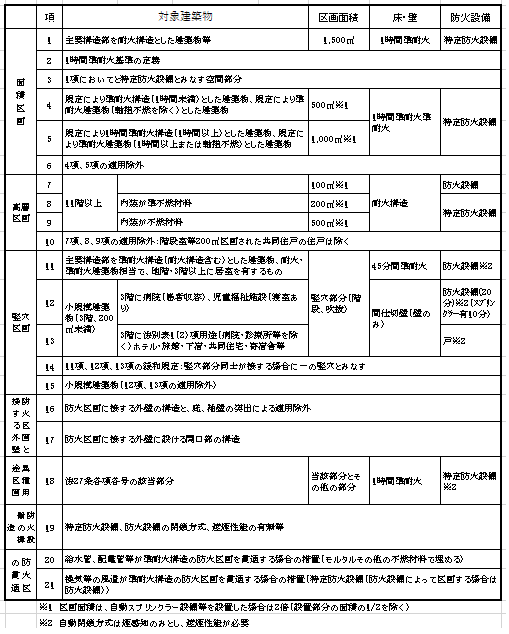
建築士の勉強!(法規編第31回)
第31回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!法規 5.耐火・防火 耐火・防火は、性能規定などからの用語の定義を問う問題、法27条や法61条からの構造を問う問題、法61条関連問題、防火区画などから出題されます。近年法改正も多くされているところですので最新の問題で確認したですね。今回は、防火区画に関する問題について見ていきましょう!! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)5-4 法26条(木造等建築物の防火壁等) 令113条(木造等の建築物の防火壁等) 令112条(防火区画) 令114条(界壁、間仕切壁、隔壁) 法35条の3(無窓居室の主要構造部) 令111条1項(法35条の3における無窓居室) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 区画に関する問題は、自動式のスプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切り壁はないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、区画避難安全検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行われていないものとする。□ 面積区画 1 平家建て、延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床 面積の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければな らない。(2級H30)2 2階建、延べ面積が1,200㎡の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積 の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなけれ ばならない。(2級H25)3 2階建、延べ面積が1,100㎡の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積 の合計1,000㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなけれ ばならない。(2級R02)4 延べ面積1.800㎡の物品販売業の物品販売業を営む店舗で、耐火建築物及び準耐火建築物以 外のものは、床面積1,000㎡以内ごとに防火壁又は防火床で区画しなければならない。 (2級H18)5 主要構造部を耐火構造とした建築物で、自動式のスプリンクラー設備をつけたものについ ては、床面積の合計に応じて区画すべき防火区画の規定が緩和される。(1級H22)6 (防火地域及び準防火地域以外で小学校を計画するに際して)延べ面積1,800㎡、地上2階 建の校舎について、主要構造部を防火構造とし、1,000㎡ごとに防火壁又は防火床によって 区画した。(1級H23)7 (防火地域及び準防火地域以外において)延べ面積1,500㎡、地上3階建ての患者の収容施 設がない診療所において、耐火建築物及び準耐火建築物に該当しない木造の建築物としたの で、準耐火構造の防火壁によって床面積の合計750㎡ごとに区画した。(1級H26)8 延べ面積が1,500㎡、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の2階建の美術館について、 床面積の合計500㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画した。 (1級H27)9 (防火地域及び準防火地域以外で中学校を計画するに際して)延べ面積2,000㎡、地上2階 建としたので、床面積の合計1,000㎡ごとに耐火構造の所定の防火壁(開口部の幅及び高さは、 それぞれ2.5m以下とし、これに所定の特定防火設備を設けたもの)により有効に区画した。 (1級H24) 10 準耐火建築物(主要構造部を準耐火構造としたもの)である延べ面積1,600㎡、平家建て の倉庫は、床面積の合計500㎡又は1,000㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H18) 11 防火区画は、火災の拡大を抑制する等のため、「建築物の用途、構造、階数等に応じた床面 積による区画」、「階段室等の竪穴部分の区画」、「建築物の部分で用途が異なる場合の当 該境界での区画」等について規定されている。(1級H20)□ 高層区画 1 地上11階建ての共同住宅の11階部分で、床面積が100㎡を超えるものは、床面積の合計 100㎡以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。 (1級H27)2 準防火地域内においては、地上15階建ての事務所の12階部分で、当該階の床面積の合計が 500㎡のものは、原則として、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H16,H28)3 地上15階建ての事務所の15階部分で、当該階の床面積の合計が300㎡のものは、原則とし て、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。(1級R01)4 耐火建築物である事務所の15階の部分で、当該階の床面積の合計が500㎡のものは、原則 として、床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の性能を有する防 火設備で区画しなければならない。(1級H15)5 主要構造部を耐火構造とした延べ面積10,000㎡、地上15階建ての事務所のの12階の事務 室で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃 材料で造ったものは、原則として、床面積の500㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H18)6 防火地域内においては、地上12階建の事務所の11階の部分で、床面積の合計が300㎡のも のは、原則として、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画しなければならない。 (1級H17)□ 竪穴区画 1 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積200㎡の一戸建て住宅においては、階段の 部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H22)2 4階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床 面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火 区画しなければならない。(2級H30)3 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積200㎡の一戸建て住宅においては、階段の 部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。(2級H24,H28)4 主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所において、3階部分に事務室を有する場合は、 原則として、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならな い。(2級H25)5 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積220㎡の一戸建て住宅においては、原則とし て、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H26)6 主要構造部を準耐火構造とした3階建の事務所の避難階からその直上階又は直下階のみに通 ずる吹抜きとなっている部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、 かつ、その下地を不燃材料で造った場合、吹抜きとなってる部分とその他の部分を防火区画し なくてもよい。(2級H26)7 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅においては、階段の 部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。(2級H29)8 主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数 が2で、かつ、床面積の合計が130㎡であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他 の部分とを防火区画しなくてもよい。(2級R02)9 主要構造部を準耐火構造とした3階建、延べ面積180㎡の共同住宅においては、原則として、 共用の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H20)10 主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸 でその階数が2以上であるもの)については、当該竪穴部分以外の部分と耐火構造の床若しく は壁又は所定の防火設備により区画した。(1級H25)11 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積800㎡、地上4階建ての事務所であって、3階以上の 階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分については、原則として、当該竪穴部分以外 の部分と防火区画しなければならない。(1級H30)12 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅の吹抜きと なっている部分については、当該竪穴部分以外の部分と防火区画しなければならない。 (1級H30)13 主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡ のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (1級R02)14 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建て住宅において、吹 抜きとなっている部分については、当該竪穴部分以外の部分と防火区画しなくてもよい。 (1級H18,23,27)15 避難階が地上1階であり、地上3階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構 造部を準耐火構造としたものにおいては、原則として、地上2階から地上3階に通ずる吹抜き となってる部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(1級R01)16 主要構造部を準耐火構造とし、3階に居室を有する建築物については、原則として、1階から 3階に通ずる階段の部分とその他の部部とを準耐火構造の床若しくは壁又は所定の性能を有す る防火設備で区画しなければならない。(1級H15)17 主要構造部を耐火構造とした地上5階建のホテル(3階以上の階に客室を有するもの)の昇降 機の昇降路の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければ ならない。(1級H16)18 3階に居室を有するホテルで、主要構造部を準耐火構造としたものにおいて、ダクトスペース の部分とその他の部分とは、不燃材料で造られた床若しくは壁又は防火設備で区画しなければ ならない。(1級H21)19 主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸のうちその階数が2で、かつ、床面積の合計が 150㎡であるものにおける吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくても よい。(1級H21)20 主要構造部を耐火構造とした地下2階、地上5階建の百貨店(各階に売り場を有するもの) の階段の部分については、原則として、当該部分とその他の部分とを防火区画しなければな らない。(1級H17)□ 異種用途区画 1 1階の一部を診療所(患者の収容施設がないもの)、その他の部分を事務所の用途に供する 3階建の建築物においては、診療所の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (2級H22)2 2階建、延べ面積300㎡の事務所の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積が 100㎡)である場合においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくても よい。(2級H24)3 2階建の建築物(各階の床面積が100㎡)で、1階が物品販売業を営む店舗、2階が事務所で あるものは、物品販売業を営む店舗の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (2級H25)4 2階建、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面 積が40㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。 (2級H26)5 1階の一部を床面積50㎡の自動車車庫とし、その他の部分を事務所の用途に供する3階建の 建築物においては、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 (2級H27)6 2階建、延べ面積300㎡の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面 積が60㎡)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。 (2級H29)7 2階建ての建築物(各階の床面積が300㎡)で、1階が幼保連携型認定こども園、2階が事務 所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければな らない。(2級R02)8 3階建ての事務所の一部が自動車車庫(床面積60㎡)である場合においては、自動車車庫の 部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。(2級H20)9 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の各階の床面積の合計がそれ ぞれ1,000㎡)とし、3階以上の階を事務所とする地上8階建の建築物においては、当該店 舗部分と事務所部分とを、原則として、防火区画しなければならない。(1級H30)10 1階から3階までを物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡) とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、原則として、当該店 舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。(1級H27)11 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が200㎡)とし、2階以上の部分を 事務所とする地上5階建の建築物においては、原則として、当該自動車車庫部分と事務所部分 とを防火区画しなければならない。(1級H28)12 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130㎡)とし、2階及び3階を事 務所とする地上3階建ての建築物においては、原則として、当該自動車車庫部分と事務所部分 とを防火区画しなければならない。(1級R01)13 1階及び2階を物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が5,000㎡)と し、3階以上の部分を事務所とする10階建の建築物においては、当該店舗部分と事務所部分と を防火区画しなけれなならない。(1級H17)□ 令114条の区画(界壁・防火上主要な間仕切り・隔壁)1 建築面積200㎡の事務所の小屋組が木造である場合においては、建築基準法施行令第112条 第4項各号のいずれかに該当する部分を除き、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構 造の隔壁を設けなければならない。(2級H22)2 老人福祉施設の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、防火構造とし、建築基準法施 行令第112条第4項各号のいずれかに該当する場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せ締めなけ ればならない。(2級H22)3 建築面積が300㎡の建築物の小屋組みが木造である場合においては、原則として、小屋裏の 直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の 隔壁を設けなければならない。(2級H20,H28,H30)4 共同住宅(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、耐火構造とし小屋裏又は天井裏に 達せしめなければならない。(2級H24)5 寄宿舎の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、天井を強化天井とする場合を除き、 準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(2級H25,H27)6 建築面積が400㎡の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、原則とし て、小屋裏の直下の天井を全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に 準耐火構造の隔壁を設けなければならない。(2級H25)7 患者の収容施設を有する診療所の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕 切壁を防火構造とし、天井を強化天井とする場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなけれ ばならない。(2級H26)8 建築面積350㎡の物品販売業を営む店舗の小屋組が木造である場合においては、原則として、 小屋裏の直下の天井を全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐 火構造の隔壁を設けなければならない。(2級H27)9 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、 準耐火構造とし、天井を強化天井とした場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければ ならない。(2級H28)10 長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、天井を強化天井とする場合 を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(2級H20,H28)11 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下 で、その小屋組みが木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔 壁を設けなければならない。(2級H29)12 有料老人ホームの用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、防火構造とし、天井を強化 天井とした場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(2級H18)13 建築面積400㎡の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下 の天井を全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁 を設けなければならない。(2級H18)14 老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井ではないもの) については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめる ものとした。(1級H16、H25) 15 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井ではないも の)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天 井裏に達せしめなければならない。(1級H21,H30)16 学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)について は、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せし めなければならない。(1級R02)17 準防火地域内においては、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての共同住宅の各戸の界壁(天井は 強化天井ではないもの)は、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。 (1級H28) 18 事務所の事務室で、所定の規定により計算した採光に有効な窓その他の開口部の面積の合計 が、当該事務室の床面積の1/30であるものを区画する主要構造部を耐火構造とした。 (1級H27)19 百貨店の売場で、窓その他の開口部を有しない場合には、売り場を区画する主要構造部を、 耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。(1級H15)20 防火地域以外の区域内における延べ面積1,000㎡、地上3階建の共同住宅の各戸の界壁は、耐 火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(1級H15)21 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下 で、その小屋組みが木造であり、かつ、けた行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の 隔壁を設けなければならない。(1級H17)22 事務所の事務室において、窓その他の開口部で採光に有効な部分の床面積の合計が、当該事 務室の床面積の1/20未満の場合には、当該事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又 は不燃材料で造らなければならない。(1級H17)□ 区画(扉等の規定)1 建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が 加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国 土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定 防火設備」という。(2級H29)2 防火区画に用いる特定防火設備である防火シャッター等は、閉鎖又は作動をするに際して、 当該設備の周囲の人の安全を確保することができる構造のものとしなければならない。 (1級H22)3 老人福祉施設の用途に供する建築物の防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動をする に際して、当該防火設備の周囲の人の安全が確保することができるものとした。(1級H25)4 地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階であ る地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避 難上及び防火上支障のない遮煙性能を有する者でなければならない。(1級R02)5 防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動するに際して、当該防火設備の周囲の人の安 全を確保することができるものでなければならない。(1級H20,H23)6 地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階であ る地上1階から地上3階に通ずる階段の部分については、当該竪穴部分以外の部分との区画に 用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。 (1級H27)7 防火区画に用いる防火シャッター等の特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態 にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものでなければならない。(1級H26,R01)8 屋内に設ける避難階段に通ずる出入り口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、 加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置した。(1級H27)9 防火区画に用いる特定防火設備は、随時閉鎖又は作動を出来る構造のものとしなければ ならない。(1級H16)10 主要構造部を耐火構造とした延べ面積2,000㎡の事務所において、防火区画に用いる特定 防火設備は、閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備の周囲の人の安全を確保す ることが出来るものとしなければならない。(1級H18)11 地階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、階段の部分と その他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有す るものでなければならない。(1級H21)□ 区画(設備・スパンドレル・壁床等の規定)1 配電管が共同住宅の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモル タルその他の不燃材料で埋めなければならない。(2級H16,H22)2 給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋め なければならない。(2級H30)3 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造と し、かつ、通常の火災による防火壁以外の建築物の部分の倒壊によって生ずる応力が伝えら れた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければ ならない。(2級H30) 4 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下としなければならない。 (2級H18,H24)5 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合、当該防火壁は耐火構造としなければ ならない。(2級H36)6 木造平屋建て、延べ面積1.500㎡の旅館に防火壁を設けなければならない場合、当該防火 壁は、通常の火災による当該防火壁以外の建築物の部分の倒壊によって生ずる応力が伝えら れた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければ ならない。(2級H30)7 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設 備で所定の構造であるものを設けなければならない。(2級H27) 8 配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防 火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(2級H28,R02)9 天井のうち、その下方から通常の火災時の加熱に対しその上方への延焼を有効に防止する ことが出来るものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の 認定を受けたものを、「強化天井」という。(2級H29)10 病院の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁を給水管が貫通する場合においては、当該 管とその間仕切り壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。 (2級H18,H20)11 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画 との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(1級H22)12 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、当該風道に設置すべき特 定防火設備については、火災により煙が発生した場合に手動により閉鎖することができるもの としなければならない。(1級H22)13 共同住宅の用途に供する建築物について、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の壁によ る防火区画を貫通することとなったので、当該管と防火区画との隙間を準不燃材料で埋めた。 (1級H25)14 地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁について は、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られて いる場合においては、当該外壁のうちこれれに接する部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火 構造としなくてもよい。(1級R02)15 防火区画における床及び壁は、耐火構造、準耐火構造又は防火構造としなければならない。 (1級H23) 16 防火区画に接する外壁については、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造のひさし、床、 袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁の所定の部分を準耐火構造と する要件が緩和される。(1級H20,H28)17 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合において、当該風道に設置すべき特 定防火設備については、原則として、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急 激に上昇した場合に自動的に閉鎖するもとしなければならない。(1級H28)18 防火区画である準耐火構造の床又は壁に接する外壁については、原則として、当該外壁のう ちこれらに接せる部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火構造としなければならない。 (1級H16) 19 防火区画における床及び壁は、準耐火構造としなければならない。(1級H20)20 給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との すき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(1級H20、2級H24)21 地上15階建ての事務所の15階の部分(床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画すべきも のとする)において、冷房設備の風道が当該防火区画を貫通する場合においては、原則と して、当該風道の当該区画を貫通する部分又はこれに近接する部分には、所定の性能を有 する特定防火設備を設けなければならない。(1級H17)22 延べ面積1,500㎡、木造平家建の建築物である旅館に防火壁を設けなければならない場合、 当該防火壁は、耐火構造としなければならない。(1級H15)23 延べ面積1,200㎡、木造、地上2階建ての小学校において、必要とされる防火壁に設ける開 口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造で あるものを設けなければならない。(1級H18,H23)***************************************************************解説 5-4 法26条(木造等建築物の防火壁等) 令113条(木造等の建築物の防火壁等) 令112条(防火区画) 令114条(界壁、間仕切壁、隔壁) 法35条の3(無窓居室の主要構造部) 令111条1項(法35条の3における無窓居室) □法26条(木造等の防火壁等) 耐火建築物、準耐火建築物以外で延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。 □令113条(木造等の建築物の防火壁等)1項 防火壁等の構造は各号による一号:耐火構造 二号:通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築部の部分の倒壊によって生ずる応力が 伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法三号:通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分から屋外に出た火炎によ る当該防火壁又は防火床で区画された他の部分への延焼を有効に防止できるものとして国 土交通大臣が定めた構造方法 四号:防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、特定防火設備と する2項防火壁等を貫通する給水管、風道等の措置は、令112条20項、21項に準ずる□令112条(防火区画)1項(面積区画)主要構造部を耐火構造とした建築物等は、1,500㎡ごとに1時間準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画しなければならない(スプリンクラー設備等を設けた場合は、3,000㎡)特定防火設備:令109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの4項(面積区画) 主要構造部を準耐火構造(1時間準耐火構造は除く)とした建築物等は、500㎡ごとに1時間準耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画しなければならない(スプリンクラー設備等を設けた場合は、1,000㎡) 一号:強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼 を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるも の又は国土交通大臣の認定を受けたもの) 5項(面積区画) 主要構造部を準耐火構造(1時間準耐火構造)とした建築物等は、1,000㎡ごとに1時間準耐火構造のの床・壁又は特定防火設備で区画しなければならない(スプリンクラー設備等を設けた場合は、2,000㎡) 6項(4項、5項の適用除外)4項、5項の規定は、天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした体育館、工場等は適用しない 7項(高層区画)建築物の11階以上の部分で、床面積100㎡を超えるものは、100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は防火設備(法2条九号の二)で区画しなければならない 8項(高層区画) 建築物の11階以上の部分で、仕上げ、下地共準不燃材料でしたものは、200㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画することができる 9項(高層区画) 建築物の11階以上の部分で、仕上げ、下地共不燃材料でしたものは、500㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画することができる 11項(竪穴区画) 主要構造部を準耐火構造とした建築物等であって、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分とその他の部分とを、準耐火構造の床・壁又は防火設備で区画しなければならない。一号:避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜き等の部分で、壁・天井の仕上げ及び 下地を不燃材料でした場合は区画しなくてもよい 二号:階数が3以下で延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅等の階段の部分等は区画しなくても よい16項(防火区画に接する外壁等) 防火区画に接する外壁については、幅90㎝以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から50㎝以上突出した準耐火構造の庇、袖壁等がある場合はこの限りではない18項(異種用途区画) 建築物の一部が、法27条各項、各号(法別表-1)に該当する場合はその部分とその他の部分を、1時間準耐火の壁・床又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、警報設備を設けた場合はこの限りではない19項(防火設備、特定防火設備の仕様) 一号:イ~ニの規定による二号:階段の部分、竪穴区画、異種用途区画に用いる特定防火設備・防火設備は、遮煙性能を有 すること 20項(給水管等の区画の貫通) 給水管等が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、その隙間をもモルタル等の不燃材料で埋めなければならない 21項(風道等の区画の貫通) 風道が、準耐火構造の防火区画を貫通する場合は、特定防火設備(竪穴区画、100㎡の高層区画の場合は防火設備)を設ける 一号:火災によって温度が急激に上昇した場合に、自動的に閉鎖するもの二号:遮煙性能を有すること 令112条をまとめると □令114条(界壁、間仕切壁、隔壁) 1項(界壁) 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない 2項(防火上主要な間仕切壁) 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く)、児童福祉施設、ホテル等の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない3項(隔壁) 建築面積が300㎡を超える建築物の小屋組みが木造である場合においては、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない4項(渡り廊下の隔壁) 延べ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組みが木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなけらばならない 5項(給水管等が貫通する場合の措置) 界壁、防火上主要な間仕切壁、隔壁を、給水管、風道等が貫通する場合の措置は、令112条20項、21項に準ずる。この場合、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして国土交通大臣が定めた構造方法又は、国土交通大臣の認定を受けたものとする □法35条の3(無窓居室の主要構造部) 政令で定める無窓居室には、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない □令111条1項(法35条の3における無窓居室) 一号:採光に有効な部分の開口部面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上有しない居室 二号:開口部が直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが直径1m以上の 円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上 有しない居室 □ 面積区画 1 〇 法26条一号2 〇 法26条一号 3 〇 法26条一号 4 〇 法26条一号 5 〇 令112条1項 自動式スプリンクラーを設けると面積は倍読みとなる6 〇 法26条一号 7 × 令113条1項一号 耐火構造としなければならない 8 〇 法26条一号 1,000㎡以内に区画 9 〇 法26条一号 令113条 10 〇 法27条3項により準耐火建築物とした、令112条4項、5項に該当するので500㎡又は 1,000㎡で区画 11 〇 令112条により、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用等区画がある □ 高層区画 1 × 令112条7項 耐火構造の床・壁で区画 2 〇 令112条7項 11階以上、100㎡、耐火構造の床・壁で区画 3 〇 令112条7項 11階以上、100㎡、耐火構造の床・壁で区画 4 〇 令112条7項 11階以上、10㎡、耐火構造の床・壁又は防火設備で区画 5 × 令112条8項 仕上げ、下地共準不燃材料 200㎡、耐火構造の床・壁又は特定防火設 備で区画 6 〇 令112条7項 11階以上、100㎡、耐火構造の床・壁で区画 □ 竪穴区画 1 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 2 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 3 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 4 〇 令112条11項 階数3以上に居室がある場合は竪穴区画 5 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれているが、220㎡は竪穴区画 が発生する 6 〇 令112条11項一号 避難階の直上直下のみの吹抜けは、仕上げ下地とも不燃材料とし た場合は竪穴区画は除外される 7 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 8 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 9 〇 令112条11項 共用の階段には除外規定はない 10 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 11 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 12 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 13 × 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 14 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の住宅は除かれている 15 〇 令112条11項 避難階の直上直下には除外規定があるが、この場合は該当しない 16 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 17 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 18 × 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画。不燃材料で造られた壁床はダメ 19 〇 令112条11項二号 階数3以下200㎡以下の共同住宅の住戸は除かれている 20 〇 令112条11項 準耐火構造の壁・床又は防火設備で区画 □ 異種用途区画 1 × 令112条18項 法27条に該当しない(患者の収容施設がない) 2 〇 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 3 × 令112条18項 法27条に該当しない(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) 4 〇 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 5 × 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 6 〇 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 7 × 令112条18項 法27条に該当しない(幼保連携型認定こども園は、3階以上、 2階が300㎡以上) 8 × 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 9 〇 令112条18項 法27条に該当する(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) 10 〇 令112条18項 法27条に該当する(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) 11 〇 令112条18項 法27条に該当する(自動車車庫150㎡以上) 12 × 令112条18項 法27条に該当しない(自動車車庫150㎡以上) 13 〇 令112条18項 法27条に該当する(物販は、3階以上、2階が500㎡以上、3,000㎡以上) □ 令114条の区画(界壁・防火上主要な間仕切り・隔壁) 1 × 令114条3項 建築面積が300㎡超が対象 2 × 令114条2項 準耐火構造 3 × 令114条3項 建築面積が300㎡超が対象 4 × 令114条1項 準耐火構造 5 〇 令114条2項により正しい 6 〇 令114条2項により正しい 7 × 令114条2項 準耐火構造 8 〇 令114条3項により正しい 9 〇 令114条2項により正しい 10 〇 令114条1項により正しい 11 〇 令114条4項により正しい 12 × 令114条2項 準耐火構造 13 〇 令114条3項により正しい 14 〇 令114条2項により正しい 15 〇 令114条2項により正しい 16 〇 令114条2項により正しい 17 × 令114条1項 準耐火構造 18 〇 法35条の3 令111条1項により無窓居室となり正しい 19 〇 法35条の3 令111条1項により正しい 20 × 令114条1項 準耐火構造 21 〇 令114条4項により正しい 22 〇 法35条の3 令111条1項により正しい □ 区画(扉等の規定) 1 〇 令112条1項 特定防火設備の定義により正しい 2 〇 令112条19項一号ロにより正しい 3 〇 令112条19項一号ロにより正しい 4 〇 令112条19項二号ロにより正しい 5 〇 令112条19項一号ロにより正しい 6 〇 令112条19項二号ロにより正しい 7 〇 令112条19項一号イにより正しい 8 × 令123条1項六号 法2条九号の二 ロに規定する防火設備 令109条の2 20分間遮炎性能 9 × 令112条19項一号イにより、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉 鎖若しくは作動をできるもの10 〇 令112条19項一号ロにより正しい 11 〇 令112条19項二号ロにより正しい □ 区画(設備・スパンドレル・壁床等の規定) 1 〇 令114条5項 令112条20項により正しい 2 × 令113条2項 令112条20項によりモルタル等の不燃材料で埋めなければならない 3 〇 令113条1項一号 二号により正しい 4 〇 令113条1項四号により正しい 5 〇 令113条1項一号により正しい 6 〇 令113条1項二号により正しい 7 〇 令113条1項四号により正しい 8 〇 令112条20項により正しい 9 〇 令112条4項一号により正しい 10 〇 令114条5項 令112条20項により正しい 11 〇 令112条20項により正しい 12 × 令112条21項により一号により自動的に閉鎖するものとする 13 × 令112条20項によりモルタル等の不燃材料で埋めなければならない 14 〇 令112条16項により正しい 15 × 令112条により、耐火構造、準耐火構造のみで、防火構造はない 16 〇 令112条16項により正しい 17 〇 令112条21項一号により正しい 18 〇 令112条16項により正しい 19 × 令112条7項によ、高層区画は耐火構造 20 〇 令112条20項により正しい 21 × 令112条21項により、7項の高層区画に該当するので防火設備でよい 22 〇 令113条1項一号により正しい 23 〇 令113条1項四号により正しい 令112条は近年改正され項目も増えより複雑になってきています。4つの区画(面積・高層・竪穴・異種用途)の違い(区画面積、壁床の構造、防火設備の種類)は色分け等で法令集を作り込みましょう! 耐火・防火関連はこれで終わりです。次回からは避難関係に入っていきます。今日はこんな言葉です! 『人間の寿命というのはね、あなたが使える時間のことなの。 その時間をどう使うかは、自分でできることなんですよ。 自分の未来というのは、自分で開発できる。 それはもうあなたの心がけ次第なの。』 (日野原 重明)
Jul 22, 2021
閲覧総数 2467
-
7
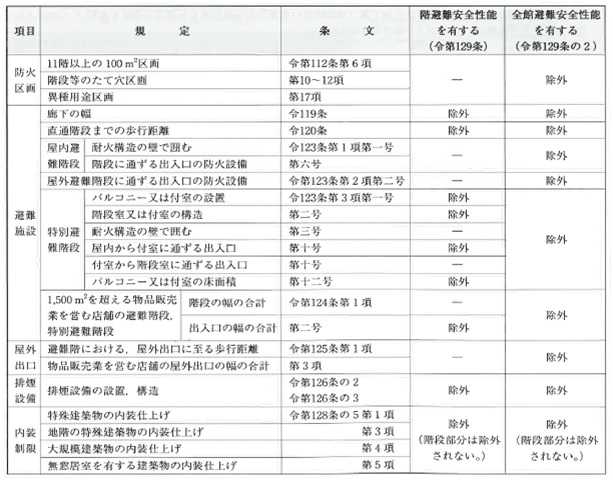
建築士の勉強!(法規編第36回)
第36回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 6.避難施設等 避難施設等は、廊下の幅・出入り口・バルコニー等の手すり、階段までの歩行距離、2直通階段、避難階段の設置、避難階段及び特別避難階段の構造、排煙設備、非常用照明装置、非常用進入口、避難検証法などからの出題がなされます。 今回は、避難検証に関する問題について見ていきましょう! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 6-5 令128条の6(区画避難安全検証法) 令129条(階避難安全検証法) 令129条の2(全館避難安全検証法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 □ 避難検証法 1 主要構造部が準耐火構造の建築物の階のうち、階避難安全検証法により安全性が確かめられ たものには、屋内に設ける避難階段の構造の規定は適用されない。(2級H14)2 主要構造部が準耐火構造である建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであ ることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、排煙設備の設置及 び構造の規定は適用されない。(2級H14,H17)3 主要構造部が準耐火構造である建築物の階のうち、当該階が階避難安全性能を有するもので あることについて、階避難安全検証法により確かめられたものであっても、屋内に設ける避難 階段の構造の規定は適用される。(2級H17,H22)4 主要構造部が準耐火構造である建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであ ることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものであっても、排煙設備の設置 及び構造の規定は適用される。(2級H22)5 階避難安全検証法とは、火災発生時において当該建築物の階から避難が安全に行われること を、当該階からの避難に要する時間に基づき検証する方法若しくは火災により生じた煙又は ガスの高さに基づき検証する方法のいずれかによる方法をいう。(1級H29,H22)6 全館避難安全検証法とは、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われること を、当該建築物からの避難に要する時間に基づき検証する方法若しくは火災により生じた煙 又はガスの高さに基づき検証する方法のいずれかによる方法をいう。(1級H29)7 主要構造部を準耐火構造とした建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を有するもので あることについて、全館避難安全検証法により確かめられたものについては、特別避難階段 の階段室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げ及びその下地を、準不燃材料とすること ができる。(1級H16)8 階避難安全性能を有するものであることが、階避難安全検証法により確かめられたかに階 については、当該階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距 離の制限の規定は適用しない。(1級H22)9 全館避難安全性能を有するものであることが、全館避難安全検証法により確かめられた場 合であっても、「内装の制限を受ける調理室」には、原則として、内装の制限の規定が適用 される(1級H22)10 延べ面積30,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所の用途に供する耐火建築物におい て、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法によ り確かめられた場合(自動式のスプリンクラー設備が全館に設けられているものとする)、 1階において、会議室から地上に通ずる主たる廊下の壁及び天井の室内に面する部分の仕上 げを難燃材料以外のものでし、排煙設備を設けなかった。(1級H15)11 延べ面積30,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所の用途に供する耐火建築物において、 その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確か められた場合(自動式のスプリンクラー設備が全館に設けられているものとする)、3階にお いて、排煙設備を設け、床面積600㎡ごとに防煙壁で区画した。(1級H15)12 延べ面積30,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所の用途に供する耐火建築物において、 その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確か められた場合(自動式のスプリンクラー設備が全館に設けられているものとする)、10階に おいて、事務室の各部分から地上に通ずる直通階段に至る歩行距離のうち最大なものを70m とした。(1級H15)13 延べ面積30,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所の用途に供する耐火建築物において、 その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確 かめられた場合(自動式のスプリンクラー設備が全館に設けられているものとする)、11階 において、防火区画について、その床面積の合計の最大なものを1,200㎡とし、耐火構造の床 若しくは壁又は特定防火設備により区画した。(1級H15)14 延べ面積30,000㎡、高さ60m、地上15階建ての事務所の用途に供する耐火建築物において、 その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確か められた場合(自動式のスプリンクラー設備が全館に設けられているものとする)、15階にお いて、当該階から避難階に通ずる特別避難階段の階段室及びこれと室内とを連絡する付室の床 面積の合計を、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計とした。 (1級H15)15 延べ面積2,000㎡、地上4階建の映画館(各階とも映画館の用途に供する客席を有するものと し、避難階は1階とする)の計画において、全館避難安全性能を有するものであることについ て、全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても、4階から1階又は地上に通ずる2 以上の直通階段を設けなければならない。(1級H15)16 延べ面積2,000㎡、地上4階建の映画館(各階とも映画館の用途に供する客席を有するものと し、避難階は1階とする)の計画において、全館避難安全性能を有するものであることについ て、全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても、客用に供する屋外への出口の戸 は、内開きとしてはならない。(1級H15)17 延べ面積2,000㎡、地上4階建の映画館(各階とも映画館の用途に供する客席を有するものと し、避難階は1階とする)の計画において、全館避難安全性能を有するものであることについ て、全館避難安全検証法により確かめられた場合であっても、通路で照明装置の設置を通常要 する部分には、原則として、非常用の照明装置を設けなければならない。(1級H15)18 延べ面積36,000㎡、地上12階建のホテルの用途に供する耐火建築物(主要構造部を耐火構造 としたもの)において、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避 難安全検証法により確かめられた場合(自動式スプリンクラー設備が全館に設けられているも の)、3階において、床面積400㎡の宴会場の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃 材料とした。(1級H16)19 延べ面積36,000㎡、地上12階建のホテルの用途に供する耐火建築物(主要構造部を耐火構造 としたもの)において、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避 難安全検証法により確かめられた場合(自動式スプリンクラー設備が全館に設けられているも の)、4階において、宴会場に排煙設備を設け、床面積600㎡ごとに防煙壁で区画した。 (1級H16)20 延べ面積36,000㎡、地上12階建のホテルの用途に供する耐火建築物(主要構造部を耐火構造 としたもの)において、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避 難安全検証法により確かめられた場合(自動式スプリンクラー設備が全館に設けられているも の)、8階において、宿泊室の床面積の合計が1,200㎡である当該から、避難階に通ずる直通 階段を2箇所設けた。(1級H16)21 延べ面積36,000㎡、地上12階建のホテルの用途に供する耐火建築物(主要構造部を耐火構造 としたもの)において、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避 難安全検証法により確かめられた場合(自動式スプリンクラー設備が全館に設けられているも の)、11階において、宿泊室の各部分から避難階に通ずる直通階段に至る歩行距離のうち、最 大なものを65mとした。(1級H16)22 延べ面積36,000㎡、地上12階建のホテルの用途に供する耐火建築物(主要構造部を耐火構造 としたもの)において、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避 難安全検証法により確かめられた場合(自動式スプリンクラー設備が全館に設けられているも の)、12階において、防火区画について、その床面積の合計の最大なものを500㎡とし、耐火 構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、その部分の壁及び天井の室内に面する部分の 仕上げ及び下地を難燃材料とした。(1級H16)23 主要構造部を耐火構造とした延べ面積40,000㎡、高さ120m、地上40階建ての共同住宅にお いて、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法によ り確かめられた場合、各住戸及び住戸以外の部分もすべて200㎡以内ごとに耐火構造の床若し くは壁又は所定の性能を有する特定防火設備で区画し(全ての仕上げ下地共準不燃材料とす る)、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段とした。(1級H18)24 主要構造部を耐火構造とした延べ面積40,000㎡、高さ120m、地上40階建ての共同住宅にお いて、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法によ り確かめられた場合、1階にある床面積200㎡の自動車車庫と床面積20㎡の管理人室とは、耐 火構造の床若しくは壁又は所定の性能を有する特定防火設備で区画した。(1級H18)25 主要構造部を耐火構造とした延べ面積40,000㎡、高さ120m、地上40階建ての共同住宅にお いて、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法によ り確かめられた場合、15階以上の居室から地上に通ずる廊下及び階段に設ける非常用の照明 装置は、所定の構造で、直接照明により床面において1ルクス以上の照度が確保することがで きるものとし、かつ、予備電源を設けたものとした。(1級H18)26 主要構造部を耐火構造とした延べ面積40,000㎡、高さ120m、地上40階建ての共同住宅にお いて、その各階が、階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法によ り確かめられた場合、40階の住戸から地上に通ずる廊下及び特別避難階段の階段室の天井及び 壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。 (1級H18)27 延べ面積30,000㎡、地上20階建ての事務所の用途に供する耐火建築物(各階の床面積が 1,500㎡、各階に事務所が設けられている、耐火性能検証法・防火区画検証法・全館避難安全 検証法により確かめられている、自動式スプリンクラー設備が全館に設けられている、避難上 有効なバルコニー・屋外通路等は設けなれていない)で、10階において、こんろを設置した給 湯室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とした。(1級H17)28 延べ面積30,000㎡、地上20階建ての事務所の用途に供する耐火建築物(各階の床面積が 1,500㎡、各階に事務所が設けられている、耐火性能検証法・防火区画検証法・全館避難安全 検証法により確かめられている、自動式スプリンクラー設備が全館に設けられている、避難上 有効なバルコニー・屋外通路等は設けなれていない)で、15階(当該階における居室の床面積 の合計は1,000㎡とする)に通ずる直通階段を特別避難階段とし、当該特別避難階段の当該階 における階段室及びこれと室内とを連絡する付室の床面積の合計を30㎡とした。(1級H17)29 延べ面積30,000㎡、地上20階建ての事務所の用途に供する耐火建築物(各階の床面積が 1,500㎡、各階に事務所が設けられている、耐火性能検証法・防火区画検証法・全館避難安全 検証法により確かめられている、自動式スプリンクラー設備が全館に設けられている、避難上 有効なバルコニー・屋外通路等は設けなれていない)で、12階において、事務室の各部分から 避難階に通ずる直通階段の一に至る歩行距離のうち、最大なものを55mとした。(1級H17)30 延べ面積30,000㎡、地上20階建ての事務所の用途に供する耐火建築物(各階の床面積が 1,500㎡、各階に事務所が設けられている、耐火性能検証法・防火区画検証法・全館避難安全 検証法により確かめられている、自動式スプリンクラー設備が全館に設けられている、避難上 有効なバルコニー・屋外通路等は設けなれていない)で、18階(避難階に通ずる直通階段が2 箇所設けられているものとする)において、事務室、(当該室の壁及び天井の室内に面する部 分の仕上げを難燃材料でしたものとする)の各部分から避難階に通ずる各直通階段に至る通常 の歩行経路の共通の重複区間の長さを25mとした。(1級H17)31 全館避難安全検証法とは、火災発生時において当該建築物からの避難が安全に行われること を、当該建築物からの避難に要する時間に基づき検証する方法と、火災により生じた煙又は ガスの高さに基づき検証する方法及び火災により建築物が倒壊するまでに要する時間に基づ き検証する方法を比較する検証法である。(1級H29)32 各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられ た地上20階建の共同住宅において、最上階の住戸から地上に通ずる廊下及び特別避難階段の天 井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料とし、その下地を準不燃材料で造った。 (1級H24)33 主要構造部を不燃材料で造った地上15階建ての建築物において、全館避難安全性能を有する ものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたので、床面積の合計200㎡ 以内ごとに耐火構造の床及び壁により区画した。(1級H24)34 主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物で、当該建築物が全館避難安全性能を 有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられたものにあっては、特別 避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることができ る。(1級H24,R02)35 主要構造部を耐火構造とした地上8階建て、延べ面積10,000㎡の物品販売業を営む店舗にお いて、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確か たので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び附室のいずれも 設けなかった。(1級R02)36 主要構造部を耐火構造とした地上5階建て、延べ面積5,000㎡の事務所において、最上階が 階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最 上階に、排煙設備を設けなかった。(1級R02)37 各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめら れた地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内 に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。(1級R03)***************************************************** 解説 6-5 令128条の6(区画避難安全検証法) 令129条(階避難安全検証法) 令129条の2(全館避難安全検証法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 令128条の6(区画避難安全検証法) 区画避難安全性能を有するものであることを、区画避難安全検証法により確かめられた場合、令126条の2(排煙設備の設置)、令126条の3(排煙設備の構造)、令128条の5(2項、6項、7項及び階段にかかる部分を除く)の規定は適用しない。(排煙と内装制限(一部除く)は規制されない、という事です!) 令129条(階避難安全検証法)、令129条の2(全館避難安全検証法) 階避難安全検証法、全館避難安全検証法により確かめられ場合をまとめると下表のようになります。このなかでよく問われるのが、直通階段までの歩行距離(令120条)、避難階段の構造(令123条)、排煙設備(令126条の2、令126条の3)、内装制限(令128条の5)などです。条文の脚注等を利用して確認の仕方を覚えてください。 □ 避難検証法 1 × 令129条1項により屋内の避難階段の構造(令123条1項)は、階避難検証規定ではな いので規定は適用される 誤り2 〇 令129条の2 1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の3)は、全館避難 検証規定なので適用されない 正しい3 〇 令129条1項により屋内の避難階段の構造(令123条1項)は、階避難検証規定ではな いので規定は適用される 正しい4 × 令129条の2 1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の3)は、全館避難 検証規定なので適用されない 誤り5 〇 令129条3項一号、二号により避難時間による検証と煙等の高さによる検証のいづれか による方法をいう 正しい6 〇 令129条の2 4項一号、二号により避難時間による検証と煙等の高さによる検証のい づれかによる方法をいう 正しい7 × 令129条の2 1項により特別避難階段の仕上げの規定(令123条3項四号)は、全館 避難検証規定ではないのでで準不燃とすることはできない 誤り8 〇 令129条1項により直通階段までの歩行距離の規定(令120条1項)は、階避難検証規 定なので適用されない 正しい9 〇 令129条の2 1項により火気使用室の内装制限の規定(令128条の5 6項)は、全 館避難検証規定ではないので適される 正しい10 〇 令129条1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の3)、内装制限の規定 (令128条の5 1項、4項、5項) は、階避難検証規定なので適用されない 正しい11 〇 令129条1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の3)は、階避難検証規定 なので適用されない。600㎡区画でもよい 正しい12 〇 令129条1項により直通階段までの歩行距離の規定(令120条1項)は、階避難検証規定 なので適用されない。70mでもよい 正しい13 × 令129条1項により高層区画の規定(令121条7項)は、階避難検証規定ではないなの で適用される。原則200㎡(100㎡区画だがスプリンクラーによる倍読み、9項を考慮 しても1,000㎡)以内に区画しなければならない14 〇 令129条1項により特別避難階段の構造の規定(令123条3項十二号)は、階避難検証 規定なので適用されない(規定でも3/100) 正しい15 〇 令129条の2 1項により2直階段の規定(令121条)は、全館避難検証規定ではないの で適用される。2直階段を設けなければならない 正しい16 〇 令129条の2 1項により屋外への出口の戸の規定(令125条2項)は、全館避難検証規 定ではないので適用される。内開きとしてはならない 正しい17 〇 令129条の2 1項により非常用照明装置の規定(令126条の4、令126 条の5)は、 全館避難検証規定ではないので適用される。非常用照明装置は設けなければならない 正しい18 〇 令129条1項により内装制限の規定(令128条の5 1項)は、階避難検証規定なので適 用されない。難燃材料とすることができる 正しい19 〇 令129条1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の18)は、階避難検証規 定なので適用されない。600㎡区画でもよい 正しい20 〇 令129条1項により2直階段の規定(令121条)は、階避難検証規定なので適用されな い。2直階段を設けなければならない 正しい 21 〇 令129条1項により直通階段までの歩行距離の規定(令120条1項)は、階避難検証規定 なので適用されない。65mでもよい 正しい22 × 令129条1項により高層区画の規定(令121条7項、8項、9項)は、階避難証規定ではな いので適用される。仕上げが難燃材料の場合は、200㎡(100㎡区画だがスプリンクラー による倍読み)以内に区画しなければならない 誤り23 〇 令129条1項により高層区画の規定(令121条7項、8項)は、階避難検証規定ではない ので適用され、8項により200㎡以内ごとに区画しなければならない。また、避難階段 の設置の規定(令122条1項)は、階避難検証規定ではないので適用され、15階以上の 階に通ずる階段は特別避難階段としなければならない。 正しい24 〇 令129条1項により異種用途区画の規定(令121条18項)は、階避難検証規定ではない ので適用される。区画しなければならない 正しい25 〇 令129条1項により非常用照明装置の規定(令126条の4、令126条の5)は、階避難検 証規定ではないので適用される。直接照明1ルクス、予備電源を設けた非常用照明装置 を設けなければならない。正しい26 × 令129条1項により特別避難階段の仕上げの規定(令123条3項四号)は、階避難検証規 定ではないので適用される。仕上げ、下地共不燃材料としなければならない。 誤り27 〇 令128条の4 4項により主要構造部が耐火構造の場合は、火気使用室の内装制限は緩和 される 難燃材料でもOK 正しい28 〇 令129条の2 1項により特別避難階段の付室の規定(令123条3項十二号)は、全館避 難検証規定なので適用されない。30㎡(規定では、1,000㎡×3/100)でOK。避難階段 の設置(令122条)は、全館避難検証規定ではないので特別避難階段を設けなければな らない。 正しい29 〇 令129条の2 1項により直通階段までの歩行距離の規定(令120条1項)は、全館避難 検証規定なので適用されない。55mでもよい 正しい30 × 令129条の2 1項により重複距離の規定(令121条3項)は、全館避難検証規定ではない ので適用される。令120条1項、3項により、歩行距離は50mー10m=40mとなり(居 室の仕上げが難燃材料なので2項は使えない)40m/2=20mを超えてはならない 誤り31 × 令129条の2 4項一号、二号により避難時間による検証と煙等の高さによる検証のいづ れかによる方法をいう。倒壊する時間の検証は含まれない 誤り32 × 令129条1項により特別避難階段の仕上げの規定(令123条3項四号)は、階避難検証規 定ではないので適用される。仕上げ、下地共不燃材料としなければならない。 誤り33 〇 令129条の2 1項により高層区画の規定(令121条7項)は、全館避難検証規定なので 適用されない。8項は全館避難検証規定ではないので適用され、200㎡以内に区画 正しい34 × 令129条の2 1項により特別避難階段の開口部のの規定(令123条3項七号)は、全館避 難検証規定ではないので適用される。屋内に面して開口部を設けることはできない。 誤り35 〇 令129条1項により特別避難階段の付室の設置の規定(令123条3項一号)は、階避難検 証規定なので適用されない。バルコニー又は附室を設けなくてもよい 正しい36 〇 令129条1項により排煙設備の規定(令126条の2、令126条の35)は、検証規定なので 適用されない。 正しい37 × 令129条1項により特別避難階段の仕上げの規定(令123条3項四号)は、階避難検証規 定ではないので適用される。仕上げ、下地共不燃材料としなければならない。 誤り避難検証に関する問題は、基の避難規定や区画規定などがちゃんと理解されていないと難しいと思います。ただ、排煙や内装(火気、車庫、階段以外)は3つの避難検証どれをやった場合でも適用除外になる。直通階段のまでの歩行距離は、階と全館の時には適用除外になる位は覚えておくといいですよ!!避難施設等に関する問題はこれで終わりです。苦手な方が多い分野ではありますが、過去問を1肢づつ紐解いていくと以外に問われているところは単純で、同じところが繰り返す出ているのがわかると思います。次回からは、内装制限に入っ行きます。今日はこんな言葉です。 『一歩踏み出す恐怖を乗り越えるコツは、その「プロセスを楽しむ」こと。そして、せっかく踏み出した一歩をムダにしないコツは、最初の一回で「だめ」だとか「怖い」と思ったとしても、そこでやめずに、踏ん張って数回繰り返してやってみることだ。』 (窪田 良)
Aug 3, 2021
閲覧総数 1909
-
8

建築士の勉強!!(法規編第18回)
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ 解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 3.制度規定 制度規定の問題は、確認申請を中心に、仮使用、定期報告、工事届など法6条~法15条を中心に出題されます。確認申請の中で、仮設建築物・用途変更・建築設備・工作物などは法6条からリンクを貼って飛べるように加工すること。また、用語の定義は確実に覚えておくことが大 事です! 今回は、確認申請(建築・大規模の修繕・大規模の模様替)についてみてみましょう!! 3-1 確認申請(建築・大規模の修繕・大規模の模様替) 法6条 1項、2項(建築物の建築等に関する申請及び確認) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 2級では、全国どこの場所においても確認済証の交付を受ける必要があるか、ないかを問う 問題です。以下、2級で出題された問題ですので、全国どの場所においても、確認済み証の 交付を受ける必要があるものは〇、無いものは×として考えてみてください。 (法改正により一部数値を変更しています。) □ 建築・大規模修繕・大規模模様替(2級問題) 1.木造2階建、延べ面積220㎡、高さ8mの一戸建住宅の新築。(2級H17) 2.鉄骨造平屋建て、延べ面積200㎡の巡査派出所の新築。(2級H17) 3.鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積190㎡の事務所の新築。(2級H17) 4.鉄骨造平屋建て、延べ面積200㎡の一戸建住宅の新築。(2級H18) 5.木造平屋建て、延べ面積250㎡の倉庫の大規模の修繕。(2級H18) 6.鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積200㎡の事務所の大規模の修繕。(2級H19) 7.木造2階建、延べ面積150㎡、高さ8mの巡査派出所の新築。(2級H19) 8.鉄骨造2階建、延べ面積100㎡の一戸建住宅の大規模の模様替。(2級H19) 9.鉄骨造平屋建、延べ面積200㎡の倉庫の新築。(2級H23) 10.鉄骨造平屋建、延べ面積200㎡の自動車車庫の新築。(2級H20) 11.木造2階建、延べ面積220㎡の飲食店の大規模の模様替。(2級H20) 12.文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された木造3階建、延べ面積500㎡ の寺院の大規模の修繕。(2級H20) 13.鉄骨造平屋建、延べ面積200㎡の屋根を帆布としたスポーツの練習場の移転。(2級H21) 14.鉄骨造2階建、延べ面積60㎡の一戸建住宅の移転。(2級H22) 15.鉄筋コンクリート造平屋建、延べ面積140㎡の事務所における50㎡の増築。(2級H22) 16.鉄筋コンクリート造平屋建、延べ面積100㎡の物品販売業を営む店舗の新築。(2級H22) 17.鉄筋コンクリート造平屋建、延べ面積250㎡の飲食店の大規模の修繕。(2級H23) 18.鉄骨造3階建、延べ面積300㎡の倉庫における床面積10㎡の増築。(2級H24) 19.鉄骨造平屋建、延べ面積200㎡の機械製作工場の大規模の修繕。(2級H24) 20.鉄骨造2階建、延べ面積300㎡の工場における鉄骨造、床面積10㎡の倉庫の増築。 (2級H25) 21.鉄筋コンクリート造平屋建、延べ面積200㎡の自動車修理工場の新築。(2級H25) 22.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積90㎡の一戸建住宅の大規模の修繕。(2級H25) 23.木造平屋建、延べ面積210㎡、高さ6mの倉庫の大規模の修繕。(2級H26) 24.木造2階建、延べ面積200㎡、高さ8mの飲食店の改築。(2級H26) 25.鉄骨造平屋建、延べ面積300㎡の自動車車庫の改築。(2級H27) 26.鉄骨造2階建、延べ面積100㎡の一戸建て住宅の新築。(2級H28) 27.木造3階建、延べ面積210㎡、高さ9mの一戸建て住宅における木造平屋建て、床面積10㎡ の倉庫の増築。(2級H29) 28.木造平屋建て、延べ面積250㎡、高さ5mのアトリエ兼用住宅(アトリエ部分は床面積50㎡) の大規模の模様替え。(2級H29) 29.鉄骨造平屋建て、延べ面積200㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の 修繕。(2級H30) 30.鉄骨造平屋建て、延べ面積300㎡の、鉄道のプラットホームの上家の新築。(2級H30) 31.鉄骨造2階建て、延べ面積100㎡の事務所の改築。(2級H30) 32.鉄骨造平屋建て、延べ面積100㎡の一戸建て住宅における、鉄骨造平屋建て、床面積100㎡ の事務所の増築。(2級R02) 33.鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積300㎡の事務所の大規模の修繕。(2級R02) 34.木造2階建て、延べ面積200㎡、高さ9mの共同住宅の新築。(2級R02) 1級では、都市計画区域内(防火地域等内)において確認済証の交付を受ける必要があるのか、無いのかを問われる問題です。以下、1級で出題された問題ですので、都市計画区域内においては(都)、防火地域内においては(防)としますのでその前提で、確認済証の交付を受ける必要があるものは〇、無いものは×として考えてみてください。 2級の問題と違うところは、法6条1項四号建物が対象になるところです。 (法改正により一部数値を変更しています。) □ 建築・大規模修繕・大規模模様替(1級問題) 1.(都)木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建て住宅における床面積12㎡の浴室・ 脱衣室の増築。(1級H21) 2.準防火地域内において、建築物の増築で、その増築に係る床面積が10㎡以内のものを行 う場合。(1級H18) 3.(都)延べ面積200㎡、鉄骨造、平屋建ての事務所の大規模の模様替え。(1級H18) 4.(都)延べ面積200㎡、木造、地上2階建の助産所の屋根の過半を修繕する場合。 (1級H16) 5.鉄道事業者は、鉄道の線路敷地内において、延べ面積50㎡、鉄筋コンクリート造、地上 2階建の運転保安に関する施設を新設する場合。(1級H16) 6.(都)木造、延べ面積500㎡、高さ8m、地上2階建ての事務所の屋根の過半の修繕。 (1級H22) 7.(都)木造、延べ面積10㎡、平屋建ての倉庫の新築。(1級H22) 8.(防)鉄骨造、延べ面積100㎡、平屋建ての事務所における床面積10㎡の増築。 (1級H24) 9.(防)れんが造、延べ面積600㎡、地上2階建ての美術館で、文化財保護法の規定によって 重要文化財として指定されたものの移転。(1級H24) 10.(都)鉄骨造、延べ面積10㎡、高さ6m、平屋建ての倉庫の新築。(1級H25) 11.(都)木造、延べ面積150㎡、高さ9m、地上2階建ての一戸建ての住宅における外壁の 過半の模様替え。(1級H25) 12.(都)鉄骨造、延べ面積50㎡の屋外観覧場の新築。(1級H27) 13.(都)木造、延べ面積300㎡、高さ8m、平屋建ての神社の大規模の修繕。(1級H27) 14.(都)木造、延べ面積500㎡、高さ8m、地上2階建ての共同住宅における、屋根の過半の修繕。 (1級H28) 15.(都)鉄骨造、延べ面積80㎡、平屋建ての一戸建て住宅における、鉄骨造、床面積12㎡、 平屋建ての付属自動車車庫の増築。(1級H28) 16.(防)木造、延べ面積100㎡、地上2階建ての一戸建て住宅における、床面積10㎡の増築。 (1級H29) 17.(防)鉄骨造、延べ面積400㎡、平屋建ての、鉄道のプラットホームの上家の新築。 (1級H29) 18.(都)鉄骨造、延べ面積300㎡、平屋建ての倉庫の屋根の過半の修繕。(1級R01) 19.(都)木造、延べ面積150㎡、高さ8m、平屋建ての集会場の屋根の大規模修繕。 (1級R02) ***************************************************************** 解説 3-1 確認申請(建築・大規模の修繕・大規模の模様替) 法6条 1項、2項(建築物の建築等に関する申請及び確認) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 確認申請の問題は、毎年出ていますので条文で確認しなくても判断できるようにしたい ところです! 法6条1項一号~三号の建物は、建築・大規模の修繕・模様替えをするときは、全国ど こであっても確認申請が必要になります。 四号建物は、都市計画区域等内で建築する場合のみ確認申請が必要になります。 法6条1項 一号:法別表-1に掲げる用途の特殊建築物で、200㎡超 二号:木造で、①3階以上の階を有する ②延べ面積500㎡超 ③高さ13m超 ④軒高9m超 三号:木造以外の建築物で、①階数2以上 ②延べ面積200㎡超 四号:一号~三号以外で、都市計画区域等内における建築物 □ 建築・大規模修繕・大規模模様替(2級問題) 2級の問題は、全国どこにおいても~なので、一号~三号に該当するかを確認します。 1. × 一号~三号に該当しないので不要 2. × 一号~三号に該当しないので不要 3. × 一号~三号に該当しないので不要 4. × 一号~三号に該当しないので不要 5. 〇 250㎡倉庫 一号に該当するので必要 6. × 一号~三号に該当しないので不要 7. × 一号~三号に該当しないので不要 8. 〇 鉄骨造2階建 三号にに該当するので必要 9. × 一号~三号に該当しないので不要 10. × 一号~三号に該当しないので不要 11. 〇 220㎡飲食店 一号に該当するので必要 12. × 法3条1項一号により、建築基準法が適用されないので不要 13. × 一号~三号に該当しないので不要 14. 〇 鉄骨造2階建 三号に該当するので必要 15. × 50㎡の増築後 一号~三号に該当しないので不要 16. × 一号~三号に該当しないので不要 17. 〇 250㎡飲食店 一号に該当するので必要 18. × 法6条2項により、10㎡以内の増築は不要 19. × 一号~三号に該当しないので不要 20. × 法6条2項により、10㎡以内の増築は不要 21. × 一号~三号に該当しないので不要 22. 〇 鉄筋コンクリート造2階建 三号に該当するので必要 23. 〇 210㎡倉庫 一号に該当するので必要 24. × 一号~三号に該当しないので不要 25. 〇 300㎡自動車車庫 一号に該当するので必要 26. 〇 鉄骨造2階建 三号に該当するので必要 27. × 法6条2項により、10㎡以内の増築は不要 28. × 一号~三号に該当しないので不要 29. × 一号~三号に該当しないので不要 30. × プラットホームの上家は建築物ではないので不要 31. 〇 鉄骨造2階建 三号に該当するので必要 32. × 100㎡増築後 一号~三号に該当しないので不要 33. 〇 鉄筋コンクリート造300㎡ 三号に該当するので必要 34. × 一号~三号に該当しないので不要 □ 建築・大規模修繕・大規模模様替(1級問題) 1級の問題は、都市計画区域内~なので、一号~四号に該当するかを確認します。 1. 〇 四号建物の建築なので必要 2. 〇 法6条2項は、防火地域・準防火地域は除外されるので、10㎡以内の 増築でも必要となる 3. × 四号建物の大規模の模様替えなので不要 4. × 四号建物の大規模の修繕なので不要 5. × 鉄道の線路敷地内の運転保安に関する施設は建築物ではないので不要 6. × 四号建物の大規模の修繕なので不要 7. 〇 四号建物の建築(新築)なので必要 8. 〇 四号建物の建築(増築)なので必要 9. × 法3条1項一号により、建築基準法が適用されないので不要 10. 〇 四号建物の建築(新築)なので必要 11. × 四号建物の大規模の模様替えなので不要 12. 〇 四号建物の建築(新築)なので必要 13. × 四号建物の大規模の修繕なので不要 14. 〇 500㎡共同住宅 一号に該当するので必要 15. 〇 四号建物の建築(増築)なので必要 16. 〇 法6条2項は、防火地域・準防火地域は除外されるので、10㎡以内の 増築でも必要となる 17. × プラットホームの上家は建築物ではないので不要 18. 〇 300㎡倉庫 一号に該当するので必要 19. × 四号建物の大規模の修繕なので不要 建築・大規模の修繕・模様替えに関しては、法令集を見なくても判断できるように、 一号~四号は暗記してくださいね! □ 今日はこんな言葉です! 『脳みそが千切れるほど考え、全力投球したときには不可能なことは非常に少ない。 他の人間にできることならば、同じ人間である僕にできないはずはない。 僕はそう思うんです。他の人間ができるのに、同じ人間の一人である僕には できないとか、できないと思わなければいけないとか、そう思うことのほうが不自然 じゃないですか。絶対におかしい。』 (孫 正義) 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Feb 9, 2021
閲覧総数 1564
-
9
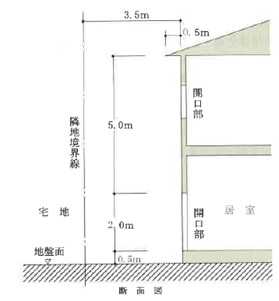
建築士の勉強!!(法規編第23回)
第23回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ 解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 4.一般構造 一般構造の問題は、採光・換気を中心に、便所、階段、床高・天井高さ、遮音性能などから出題されます。二級では、採光・天井高さ・換気などで計算問題も出ています。 今回は、採光の問題を見てみましょう!! (問題文は、法改正により一部訂正しています。) 4-1 法28条(居室の採光及び換気) 令19条(学校、病院等の居室の採光) 令20条(有効面積の算定方法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) □ 採光 1.居室に設ける開口部で、公園に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する 場合、その公園の反対側の境界線を隣地境界線とした。(2級H26) 2.居室に設ける開口部で、川に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場 合、当該川の反対側の境界線を隣地境界線とした。(2級H30) 3.小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、原則として、当該教室の 開口部ごとの面積に、それぞれの採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算出する。 (1級H21) 4.小学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。 (1級H17,H24) 5.中学校における床面積60㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光 に有効な部分の面積は、原則として、12㎡以上としなければならない。(1級H17,H25) 6.小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、用途地 域の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。(1級H18) 7.有料老人ホームにおける床面積50㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口 部を設け、その採光に有効な部分の面積は、5㎡以上としなければならない。(1級H20) 8.商業地域内の建築物(天窓及び縁側を有しないもの)の開口部の採光補正係数は、開口部 が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗 じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。 (1級H22) 9.中学校における床面積70㎡の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光 に有効な部分の面積は、原則として、14㎡以上としなければならない。(1級H29) 10.近隣商業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開 口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を 乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となった場合においては、1.0とする。 (1級R-01) 11.児童福祉施設における床面積60㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口 部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、6㎡以上としなければならない。 (1級H27) 12.高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。 (1級H27) 13.準工業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口 部が道に面しない場合であって、水平距離が5m以上であり、かつ、採光関係比率に8.0を 乗じた数値から1.0を減じて得た数値が1.0未満になる場合においては、3.0とする。 (1級H27) 14.近隣商業地域内の有料老人ホーム(天窓を有しないもの)で外側に幅1mの縁側(ぬれ縁 を除く)を有する開口部の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距 離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が 1.0未満となる場合においては、1.0とする。(1級H27) 15.病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく 算定することができる。(1級H28) 16.準工業地域内の有料老人ホームの居室(天窓を有しないもの)で、外側にぬれ縁ではない 幅1mの縁側を有する開口部(道に面しないもの)の採光補正係数は、水平距離が6mであ り、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7とする。(1級H30) □ 採光計算問題 1.準工業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅1.5m、面 積3.0㎡)の建築基準法上、「採光に有効な部分の面積」を求めよ。(2級H29) 2.第一種住居地域内において、図のような断面を持つ住宅の1階の居室の開口部(幅2.0m、 面積4.0㎡)の建築基準法上、「採光に有効な部分の面積」を求めよ(2級H22) 3.第一種低層住居専用地域において、川(幅4.0m)に面して図のような断面を持つ住宅の1階 の居室の開口部(幅2.0m、面積4.0㎡)の建築基準法上、「採光に有効な部分の面積」を求 めよ。(2級H23) 4.第二種低層住居専用地域内において、図のような断面をもつ幼稚園の1階に教室(開口部は 幅1.5m、面積3㎡とする)を計画する場合、建築基準法上、「居室の採光」の規定に適合 する当該教室の床面積の最大はどれだけか。(2級H20) 5.近隣商業地域内において、図のような断面を持有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5m、 面積3.0㎡)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線か ら後退しなければならない最小限度の距離Xはどれだけか。ただし、居室の床面積は21㎡ とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものと する。(2級R02) ************************************************************* 解説 4-1 法28条(居室の採光及び換気) 令19条(学校、病院等んお居室の採光) 令20条(有効面積の算定方法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) □ 採光 法28条1項により、住宅、学校等政令で指定するものの居室には採光のための窓そのたの開口部を設けなければならない。住宅の居室に関しては、床面積の1/7以上、その他の居室は令19条で、窓の有効面積の算定方法は令20条で指定する。 採光必要面積 ≦ 採光有効面積 令19条(採光に必要な窓面積) 採光必要面積 = 床面積 × 1/5 ~ 1/10 幼稚園・小中高等の学校の教室 1/5 保育所等の保育室 1/5 病院又は診療所の病室 1/7 寄宿舎の寝室等 1/7 児童福祉施設等の寝室、訓練室等 1/7 大学、専門学校等の教室 1/10 病院、児童施設等の談話室・娯楽室等 1/10 令20条(有効面積の算定方法) 1項 採光有効面積 = 開口部面積 × 採光補正係数 2項 一号(住居系) 採光補正係数 = D/H × 6.0 - 1.4 開口部が道に面しない場合、水平距離が7m以上あり、かつ当該算定値が1.0未満 となる場合は、1.0とする。 二号(工業系) 採光補正係数 = D/H × 8.0 - 1.0 開口部が道に面しない場合、水平距離が5m以上あり、かつ当該算定値が1.0未満 となる場合は、1.0とする。 二号(商業系) 採光補正係数 = D/H × 10.0 - 1.0 開口部が道に面しない場合、水平距離が4m以上あり、かつ当該算定値が1.0未満 となる場合は、1.0とする。 D/H:採光関係比率 (対象の窓に複数ある場合は最小の値とする) D:開口部の直上にある建築物の各部分からその部分にに面する隣地境界線までの水平距離 H:開口部の直上にある建築物の各部分から開口部の中心までの垂直距離 ・敷地境界線が、川、公園等に面する場合は、その幅の1/2だけ隣地境界線の外側にある とみなし、Dを算定する。 採光補正係数は、天窓にあっては計算結果の3.0倍、幅90㎝以上の縁側がある場合は計算結果の0.7倍とする。ただし、いずれの場合も3.0を限度とする。 1. × 隣地境界線が公園に面する場合は、反対側ではなくその幅の1/2だけ外側にある ものとみなす。 2. × 隣地境界線が川に面する場合は、反対側ではなくその幅の1/2だけ外側にあるも のとみなす。 3. 〇 採光有効面積は、各窓面積に採光補正係数を乗じて求める 4. 〇 令19条により、職員室には採光は求められていない 5. 〇 中学の教室採光必要面積は、60㎡×1/5=12㎡以上 6. 〇 採光有効面積=採光補正係数×窓面積 採光補正係数は用途地域によって決まる 7. 〇 有料老人ホームの娯楽室の採光必要面積は、50㎡×1/10=5㎡以上 8. 〇 商業地域で、開口部が道に面しない場合、水平距離(D)が4m以上、かつ、採光補 正係数が1.0未満の場合は、1.0となる 9. 〇 中学の教室採光必要面積は、70㎡×1/5=14㎡以上 10. × 天窓の採光補正係数は、数値の3.0倍。この場合は、1.0×3=3.0となる 11. 〇 児童福祉施設等の娯楽室の採光必要面積は、60㎡×1/10=6㎡以上 12. 〇 令19条により、職員室には採光は求められていない 13. 〇 天窓の採光補正係数は、数値の3.0倍。この場合は、1.0×3=3.0となる 14. × 縁側がある場合の採光補正係数は、数値の0.7倍。1.0×0.7=0.7となる 15. × 採光有効面積=採光補正係数×窓面積 採光補正係数は用途地域によって決まる 16. 〇 縁側がある場合の採光補正係数は、数値の0.7倍。この場合は1.0×0.7=0.7となる □ 採光計算問題 1.採光に有効な部分の面積(採光有効面積)=開口部面積×採光補正係数 開口部面積=3.0㎡ 採光補正係数(準工業地域)=D/H×8.0-1.0 D=(3.5m-0.5m)=3.0m H=軒先より1階の開口部の中心までの距離 5.0m+1.0m=6.0m 採光補正係数=3.0/6.0×8.0-1.0=3.0 採光に有効な部分の面積=3.0㎡×3.0=9.0㎡ 2.採光に有効な部分の面積(採光有効面積)=開口部面積×採光補正係数 開口面積=4.0㎡ 採光補正係数(第一種住居地域)=D/H×6.0-1.4 採光関係比率(D/H)が複数ある場合は一番小さい数値となる D1/H1=2.0/2.5=0.8 D2/H2=3.0/5.0=0.6 ∴D/H=0.6 採光補正係数=0.6×6.0-1.4=2.2 採光に有効な部分の面積=4.0㎡×2.2=8.8㎡ 3.採光に有効な部分の面積(採光有効面積)=開口部面積×採光補正係数 開口部面積=4.0㎡ 採光補正係数(第一種低層住居専用地域)=D/H×6.0-1.4 敷地境界線が川に面する場合は、川の1/2だけ敷地境界線が外側にあるとみなすので、 D=(2.0m+0.5m)=2.5m H=軒先より1階の開口部の中心までの距離 4.0m+1.0m=5.0m 採光補正係数=2.5/5.0×6.0-1.4=1.6 採光に有効な部分の面積=4.0㎡×1.6=6.4㎡ 4.採光有効面積から床面積を求める 採光必要面積=A×1/5 採光有効面積=窓面積×採光補正係数 3.0㎡×(D/H×6.0-1.4)=3.0㎡×(3m/6m×6.0-1.4)=4.8㎡ 採光必要面積≦採光有効面積から A×1/5≦4.8㎡ A≦4.8×5≦24.0㎡ 床面積の最大 24.0㎡ 5.床面積からDを求める 採光必要面積=21.0㎡×1/7=3.0㎡ 採光有効面積=3.0㎡×(D/5.0m×10.0-1.0)=6.0D-3.0 採光必要面積≦採光有効面積から 3.0㎡≦6.0D-3.0 1.0m≦D 距離X=1.0m+0.5m=1.5m 二級では計算問題が主流ですから、法令集見なくても解けるようにしたいですね!今日はこんな言葉です!『この世に継続に勝るものは無い。才能も、教育も、継続に勝ることは できない。継続と決意こそが絶対的な力なのである。』 (カルヴィン・クーリッジ)2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Mar 10, 2021
閲覧総数 5683
-
10
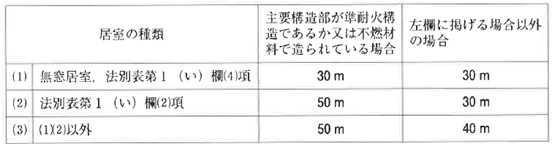
建築士の勉強!(法規編第33回)
第33回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!法規 6.避難施設等避難施設等は、廊下の幅・出入り口・バルコニー等の手すり、階段までの歩行距離、2直通階段、避難階段の設置、避難階段及び特別避難階段の構造、排煙設備、非常用照明装置、非常用進入口、避難検証法などからの出題がなされます。今回は、避難階段の設置、避難階段・特別避難階段の構造、階段・出口までの歩行距離、敷地内通路に関する問題について見ていきましょう!!(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)6-2 令120条(直通階段の設置) 令121条3項(2直階段の重複距離) 令122条(避難階段の設置) 令123条(避難階段及び特別避難階段の構造) 令124条(物品販売業を営む店舗の避難階段) 令125条1項(避難階の歩行距離) 令128条(敷地内の通路) 令128条の3(地下街) 令129条の13 3項(非常用EVの乗降ロビー) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 □ 避難階段の設置 1 主要構造部が準耐火構造である地上3階地下2階の建築物において、地下2階(床面積の 合計が90㎡)に通ずる直通階段は、避難階段又は特別避難階段としなければならない。 (2級H17)2 地上10階建ての建築物の5階以上の階(その主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃 材料で造られている建築物で5階以上の階の床面積の合計が100㎡以下である場合を除く。) で、床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸にあっては、200㎡)以内ごとに耐火構造の床若 しくは壁又は特定防火設備で区画されていない階に通ずる直通階段は、避難階段又は特別避 難階段としなけれなばならない。(1級H19)3 床面積の合計が1,500㎡を超える地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途 に供するものにあっては、各階の売り場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これ を避難階段又は特別避難階段としなければならない。(1級H19)4 地上11階建ての事務所ビルにおいて、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画されていな い最上階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければならない。(1級H27)5 主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同住宅おいて、階段室、昇降機の昇降路、 廊下等が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計が200㎡(住戸以外は100㎡)以内 ごとに防火区画されている場合には、15階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段とし なくてもよい。(1級H30)□ 避難階段・特別避難階段の構造、階段の幅等 1 屋内に設ける避難階段の階段室の天井(天井がない場合は、屋根)及び壁の室内に面する 部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。 (2級H29)2 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が400㎡) においては、原則として、各階における避難階段の幅の合計を2.4m以上としなければならな い。(1級H28)3 地上20階建ての共同住宅の特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこ れと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積の無いものにあっ ては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に8/100を乗じたものの合 計以上としなければならない。(1級R02)4 床面積の合計が1,500㎡を超える物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の各階にお ける避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、原則として、その直上階以上の階(地下にあ っては、当該階以下の階)のうち床面積が最大の階における床面積100㎡につき60㎝の割合 で計算した数値以上としなければならない。(1級H19)5 屋内に設ける避難階段の階段室は、開口部、窓又は出入り口の部分を除き、準耐火構造の 壁で囲み、階段室の壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不 燃材料で造らなければならない。(1級H19)6 屋外に設ける避難階段は、その階段に通ずる出入り口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以 内で、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備ではめころし戸であるものが設けられたもの を除く。)から2m以上の距離に設けなければならない。(1級H19)7 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が400㎡、 避難階は1階、屋上広場はない)において、各階から1階又は地上に通ずる二つの直通階段を 設け、そのうち一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。(1級H21)8 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が400㎡、 避難階は1階、屋上広場はない)において、屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入 り口以外の開口部から2.5mの距離に設けた。(1級H21)9 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が400㎡、 避難階は1階、屋上広場はない)において、各階における避難階段の幅の合計を3.0mとした。 (1級H21,H24)10 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が400㎡、 避難階は1階、屋上広場はない)において、屋内に設ける避難階段について、階段室の窓及び 出入り口の部分を除き、耐火構造の壁で区画した。(1級H21) 11 屋内に設ける避難階段の階段室は、所定の開口部、窓又は出入り口の部分を除き、耐火構 造の壁で囲み、階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び壁の室内に面する部 分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料でしなければならない。 (1級H26)12 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上3階建ての建築物(各階の床面積が600㎡) において、各階における避難階段の幅の合計を3.0mとしなければならない。(1級H30)13 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が600㎡) において、各階における避難階段の幅の合計を3.6mとした。(1級R02)□ 階段・出口までの歩行距離 1 主要構造部を準耐火構造とした2階建の有料老人ホームの避難階以外の階において、主たる 用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の 室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又 は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。(2級R02)2 飲食店(木造2階建(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないもの) 、各階の床面積150㎡、高さ6m、避難階は1階)の計画において、2階の居室の各部分から1 階又は地上に通ずる直通階段の一に至歩行御距離は、30m以下としなければならない。 (2級H28)3 飲食店(木造2階建(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないもの) 、各階の床面積150㎡、高さ6m、避難階は1階)の計画において、1階においては、階段から 屋外の出口の一に至る歩行距離の制限を受ける。(2級H28)4 2階建ての耐火建築物である幼保連携型認定こども園の避難階以外の階において、主たる用 途に供する居室及びこれらから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の 室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又 は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。(2級H29)5 木造2階建の有料老人ホーム(主要構造部が準耐火構造である。)の避難階以外の階におい て、主たる用途に供する居室及びこれらから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、避難階又は地 上に通ずる直通階段への居室の各部分からその一に至る歩行距離を60m以下としなければな らない。(2級H26)6 主要構造部が耐火構造で、避難階が1階である地上10階建てのホテルの客室で、当該客室 及びこれらから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部 分の仕上げを難燃材料でしたものについては、当該客室の各部分から避難階又は地上に通ず る直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなけれなばならない。(1級H20)7 地上3階建の建築物の3階にある飲食店において、新たに間仕切壁を設ける際、飲食店の居 室の各部分から直通階段の一に至る距離を30m以下となるようにした。(1級H21)8 主要構造部を準耐火構造とした地上5階建の共同住宅におけるメゾネット形式の住戸(その 階数が2又は3であり、かつ、出入り口が一の階のみにあるもの)の出入り口のある階以外の 階については、その居室の各部分から避難階段又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距 離を40m以下とすることができる。(1級H21)9 避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入り口(所定の構造の乗降ロビーを 設けた場合には、その出入口)から、所定の通路、空地等に接している屋外への出口の一に 至歩行距離は、40m以下としなければならない。(1級H21)10 主要構造部を耐火構造とした延べ面積6,000㎡、地上15階建ての事務所(各階とも事務所の 用途に供するもので、居室及びこれらから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁 及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)において、15階にある事務 室の各部分から各特別避難階段に至る通路の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるとき における当該重複区間の長さは、原則として、25m以下にしなければならない(1級H18)11 主要構造部を耐火構造とした延べ面積600㎡、地上4階建ての飲食店(各階とも飲食店の用 途に供するもので、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁 及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの)の避難階段においては、階 段から屋外への出口の一に至歩行距離は、40m以下としなければならない。(1級H18)12 主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれらか ら地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを 準不燃材料とした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至歩 行距離は、60m以下としなければならない。(1級H29,R02)13 主要構造部を耐火構造とした地上11階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸につ いて、その階数が2であり、かつ、出入り口が一の階のみにあるものの当該出入り口のある 階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に 至歩行距離は、40m以下としなければならない。(1級R02)14 主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての展示場の避難階以外の階においては、主たる 用途に供する居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を、原 則として、30m以下としなければならない。(1級H30)15 主要構造部を耐火構造とした地上3階建て、延べ面積3,000㎡の飲食店(主たる用途に供す る居室及びこれらから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面 する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の 一に至る歩行距離は、40mとすることができる。(1級R01)□ 敷地内通路 1 主要構造部を耐火構造とした延べ面積5,000㎡、地上8階建ての共同住宅の敷地内には、屋 外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設 けなければならない。(1級R01) 2 主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200㎡、地上6階建ての共同住宅について、敷地内 には、屋外に設ける避難階段及び所定の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅 員が1.5m以上の通路を設けなければならない。(1級H18)***************************************************** 解説 6-2 令120条(直通階段の設置) 令121条3項(2直階段の重複距離) 令122条(避難階段の設置) 令123条(避難階段及び特別避難階段の構造) 令124条(物品販売業を営む店舗の避難階段) 令125条1項(避難階の歩行距離) 令128条(敷地内の通路) 令128条の3(地下街) 令129条の13の3 5項(非常用EVの乗降ロビーの歩行距離) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 令120条(直通階段の設置) 1項 避難階以外の階において、避難階又は地上に通ずる直通階段までの歩行距離は、 表の数値以下 2項 主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、避難上の 廊下、階段等の壁・天井の仕上げが準不燃材料でしたものは、1項の数値に10mを加える。 ただし、15階以上の居室については緩和されない。3項 15階以上の居室は、1項の表より10mを減ずる。ただし、2項の場合(仕上げ準不燃材料) は、1項の表の数値のままでよい。4項 主要構造部を準耐火構造とした共同住宅でメゾネットタイプの場合は、階段までの歩行距 離は40m以下とする。令121条3項(2直階段の重複距離) 2直階段を設ける歩行距離の重複距離は、令120条の歩行距離の1/2を超えてはならない。令122条(避難階段の設置) 1項 5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段は、避難階段又は特別避難階段とし なければならない。ただし、主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られて いる建築物で、5階以上又は地下2階以下の床面積の合計が100㎡以下の場合は除く。 15階以上の階又は地下3階以上の階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければな らない。ただし、主要構造部が耐火構造である建築物で、床面積の合計100㎡(共同住宅 の住戸は200㎡)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されている 場合はこの限りではない。 2項 3階以上の階に物品販売業を営む店舗を設けた場合は、各階の売り場及び屋上広場に通ず る2以上の直通階段を設け、これを、避難階段又は特別避難階段としなければならない。3項 2項の場合、5階以上の売り場に通ずる階段はその一つ以上を、15階以上の売り場に通ず る場合はそのすべてを特別避難階段としなければならない。令123条(避難階段及び特別避難階段の構造) 1項 屋内に設ける避難階段の構造2項 屋外に設ける避難階段の構造 3項 特別避難階段の構造 令124条(物販店舗の避難階段等の幅) 1項 物品販売業を営む店舗に設ける避難階段等の幅及び出入口の幅 一号 各階における避難階段及び特別避難階段の幅の合計は、その直上階以上の階のうち 床面積が最大の階における床面積100㎡につき60㎝で計算した値以上。 二号 各階における避難階段及び特別避難階段に通ずる出入り口の幅は、各階ごとに床面 積100㎡につき、地上階は27㎝、地階は36㎝で計算した値以上。2項 1項の計算に関して、1若しくは2の地上階(2階、3階からのみ)から避難階若しくは地上 に通ずる場合は、その幅が1.5倍あるものとみなす。(3m必要な場合、2mで足りる)3項 2項の規定の適用に関しては、屋上広場は階とみなす。 (2階建の屋上に屋上広場がある場合は3階とみなす)令125条(屋外への出口:避難階においての歩行距離) 1項 ① 避難階の階段から屋外への出口の一に至る距離は、令120条の数値以下とする。 ② 避難階の居室の各部分から屋外への出口の一に至る距離は、令120条の数値の2倍以下 とする。 令128条(敷地内の通路) 敷地内には、屋外の避難階段及び階段から屋外への出口から、道又は公園等に通ずる幅員1.5m以上の通路を設ける。ただし、階数3以下で延べ面積200㎡未満の建築物は90㎝以上。 令128条の3(地下街) 1項四号 長さ60m超の地下街には、直通階段で令23条1項(2)に適合するものを各構えの接 する部分からその一に至歩行距離が30m以下とする。4項 地下街の各構えの居室の各部分から地下道への出入り口の一に至歩行距離は30m以下 とする。 令129条の13の3 (非常用EVの乗降ロビーの歩行距離)5項 避難階においては、非常用エレベーターの昇降路の出入り口から屋外への出口の一に至る 歩行距離は30m以下とする。 歩行距離に関しては、メゾネット40m、地下街30m、非常用EV30mは覚えましょう!! □ 避難階段の設置 1 × 令122条1項により、地下2階が100㎡以下の場合は除外2 〇 令122条1項により、5階以上のに通ずる階段は、避難階段又は特別避難階段としな ければならない3 〇 令122条2項により、延べ面積1,500㎡超で3階以上に物販店舗がある場合は、2階段、 避難階段又は特別避難階段を設けなければならない4 × 令122条1項により、15階以上が特別避難階段。11階なので避難階段でOK5 〇 令122条1項により、15階以上の特別避難階段のただし書きにより正しい□ 避難階段・特別避難階段の構造、階段の幅等1 〇 令123条1項二号 下地・仕上げ共不燃材料で造る 2 〇 令124条1項一号により延べ面積1,500㎡超なので、400㎡×(0.6m/100㎡)=2.4m 以上必要3 × 令123条3項十二号により共同住宅は3/100を乗ずる4 〇 令124条1項一号により正しい 5 × 令123条1項一号により耐火構造の壁で囲まなければならない6 〇 令123条2項一号により正しい7 × 令122条2項により延べ面積1,500㎡超で3階以上なので、2階段で避難階段又は特別 避難階段としなければならないが、令123条2項三号により、屋外に設ける避難階段 は耐火構造としなければならない8 〇 令123条2項一号により正しい9 〇 令124条1項一号により延べ面積1,500㎡超なので、400㎡×(0.6m/100㎡)=2.4m 以上必要10 〇 令123条3項三号により正しい11 〇 令123条1項一号、二号により正しい12 × 124条1項一号により延べ面積1,500㎡超なので、600㎡×(0.6m/100㎡)=3.6m 以上必要。また、屋上広場がなければ3階建なので、3.6÷1.5=2.4mでOK13 〇 令124条1項一号により延べ面積1,500㎡超なので、600㎡×(0.6m/100㎡)= 3.6m以上必要 □ 階段・出口までの歩行距離 1 〇 令120条1項表(2)により50mだが、2項により+10mとなり60m以下としなければ ならない2 〇 令120条1項表(1)により30m以下としなければならない3 〇 令117条により避難規定の適用を受ける建築物なので、令125条1項により令120条 の数値以下となる4 〇 令120条1項表(2)により50mだが、2項により+10mとなり60m以下としなければ ならない 5 〇 令120条1項表(2)により50mだが、2項により+10mとなり60m以下としなければ ならない6 × 令120条1項表(2)により50m以下としなければならない。2項は通路の仕上げが難燃 材料なので緩和されない7 〇 令120条1項表(1)により30m以下としなければならない8 〇 令120条4項によりメゾネット形式の歩行距離は40m以下としなければならない9 × 令129条の13の3 5項により、避難階における非常用EVの歩行距離は30m以下とし なければならない10 〇 令120条1項表(3)、2項、3項により歩行距離は50m以下となり、令121条3項により 重複区間の長さは50m×1/2=25mとなる 11 〇 令120条1項表(1)により、30mだが2項により+10mとなり40m以下としなければ ならない12 × 令120条1項表(2)により50mだが、15階のため2項による準不燃材料を考慮し、 3項による-10mは除外されているので50m以下としなければならない13 〇 令120条4項によりメゾネット形式の歩行距離は40m以下としなければならない14 〇 令120条1項表(1)により30m以下としなければならない15 〇 令120条1項表(1)により30mだが、2項により+10mとなり40m以下としなければ ならない □ 敷地内通路 1 〇 令128条により正しい 2 〇 令129条により正しい 歩行距離や避難階段の設置・構造などはよく条件を確認した上で条文を確認して下さい。歩行距離は、各階での階段までの距離やメゾネットの場合の距離、非常用EVからの距離、地下街の距離などがあるので整理して数値を覚えちゃうといいですよ!今日はこんな言葉です! 『いくつになっても新しいことを始めて、自分なりの花を咲かせることができる。 人生のピークはこれから。』 (松尾 多惠子) 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Jul 30, 2021
閲覧総数 1850
-
11
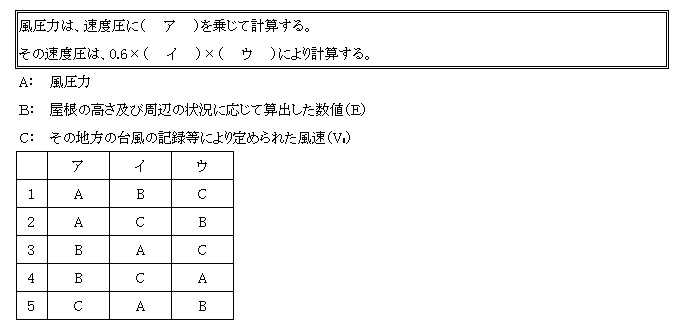
建築士の勉強!第80回(構造文章編編第1回 荷重・外力-1)
構造文章編第1回(荷重・外力-1)建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 構造-2法規に続いては、苦手な人が多い構造を解説します。構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に交互に紹介していきます。 (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)構造(文章) 1.荷重・外力-1(固定・積載荷重、雪荷重、風荷重) 荷重・外力の分野は、二級も一級の1~2問程度出題されます。法規と関連している問題も多いので、施行令(令82条~令86条)と合わせて確認しておくと法規の問題でも活用できます。今回の荷重・外力の分野は2回に分けました。1回目は固定荷重、積載荷重、雪荷重、風荷重の問題です。 (問題は、一部修正しているものもあります。)******************************************************************問題□ 荷重(固定荷重・積載荷重)(2級)1 建築物に作用する固定荷重や積載荷重は、長期荷重と考える。(2級H15)2 「床の構造計算をする場合の積載荷重」と「大梁の構造計算をする場合の積載荷重」は、 一般に、同一の室においても異なった値を用いて計算する。(2級H15,H17)3 一つの部屋の「床の構造計算をする場合の積載荷重」と「地震力を計算する場合の積載 荷重」は、一般に、同じ値を用いる。(2級H16)4 建築物に作用する荷重及び外力として、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力及び地 震力を採用しなければならない。(2級H17)5 瓦葺屋根の固定荷重は、一般に、厚形スレート葺き屋根の固定荷重よりも大きい。 (2級H17)6 住宅の居室における床の単位面積当たりの積載荷重の値については、一般に、「柱の構 造計算をする場合」より「床の構造計算」のほうが大きい。(2級H18)7 固定荷重は、骨組部材・仕上材料等のような構造物自体の重量及び建築物上に常時固定 されている物体の重量による荷重である。(2級H18)8 倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重については、実況に応じて計算した値が3,900N/㎡未 満の場合であっても3,900N/㎡として計算する。(2級H18,H21,H27,R01)9 各階が事務室である建築物において、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、積載 荷重は、その柱が支える床の数において低減することができる。 (2級H19,H22,H25,H28) 10 積載荷重は、一般に、室の種類と構造計算の対象に応じて、異なった値を用いる。 (2級H19)11 同一の室における床の単位面積当たりの積載荷重は、一般に、「床の構造計算をする 場合」より「地震力を計算する場合」のほうが大きい。(2級H20)12 同一の室に用いる積載荷重の大小関係は、一般に、「床の計算用」>「大梁及び柱の 計算用」>「地震力の計算用」である。(2級H21,H25,H28)13 床の単位面積当たりの積載荷重は、一般に、「教室」より「百貨店又は店舗の売り場」 のほうが小さい。(2級H21)14 倉庫等において、積載荷重が一様に分布している場合の応力より、そこから一部の荷重 を減らして荷重が偏在している場合の応力の方が不利になることがある。(2級H21)15 事務室において、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、その柱が支える床の数に 応じて積載荷重を低減することができる。(2級H21)16 床の単位面積当たりの積載荷重は、一般に、「百貨店又は店舗の売り場」より「教室」 のほうが小さい。(2級H24,H29)17 同一の室に用いる積載荷重の大小関係は、一般に、「地震力の計算用」>「床の計算 用」>「大梁及び柱の計算用」である。(2級H26)18 床の単位面積当たりの積載荷重は、一般に、「百貨店又は店舗の売り場」より「教室」 のほうが大きい。(2級H27)19 同一の室における床の単位面積当たりの積載荷重は、一般に、「床の構造計算をする 場合」より「地震力を計算する場合」のほうが小さい。(2級H30) 20 各階が事務室である建築物において、垂直荷重による柱の圧縮力を低減して計算する場 合の「積載荷重を減らすために乗ずべき数値」は、一般に、その柱が支える床の数が多 くなるほど小さくなる。(2級H30)21 同一の室において、積載荷重の大小関係は、一般に、「地震力の計算用」>「大梁及び 柱の構造計算用」>「床の構造計算用」である。(2級R03)□ 荷重(固定荷重・積載荷重)(1級)1 床の構造計算において、単位面積当たりの積載荷重は、実況によらない場合、教室に比 べて学校のバルコニーにおほうが小さい。(1級H15)2 劇場の客席の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、固定席の場合よりその他の場 合のほうが小さい。(1級H16)3 構造計算における積載荷重は、許容応力度等計算を行う場合と限界耐力計算を行う場合 とは同じ値を用いることができる。(1級H16)4 床の構造計算を実況に応じて計算しない場合、所定の規定による設計用積載荷重の大小 関係は、店舗の売り場>教室>住宅の居室である。(1級H17)5 積載荷重及び固定荷重は鉛直方向にのみ作用し、地震力及び風圧力は水平方向にのみ作 用する。(1級H17)6 単位面積当たりの積載荷重の大小関係は、実況に応じて計算しない場合は、「床の構造 計算をする場合」>「大梁、柱又は基礎の構造計算をする場合」>「地震力を計算する 場合」である。(1級H18)7 事務室の柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合において、支える床の数に応じて、 積載荷重を低減することができる。(1級H19)8 百貨店の屋上広場の単位面積当たりの積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、百貨 店の売場の単位面積当たりの積載荷重と同じにすることができる。(1級H19,H24,H30)9 店舗の売り場に連絡する廊下の床の構造計算に用いる積載荷重は、建築物の実況に応じ て計算しない場合、店舗の売場の床の積載荷重を用いることができる。(1級H20,R01)10 倉庫業を営む倉庫における床の構造計算に用いる積載荷重は、実況に応じて計算した数 値が3,900N/㎡未満であっても3,900N/㎡としなければならない。(1級H20,H22)11 鉄筋コンクリートの単位体積重量を算定するに当たり、コンクリートの単位体積重量に 鉄筋による単位体積重量1KN/㎥を加えて求めることができる。(1級H22)12 普通コンクリートの重量を算定するに当たり、単位体積重量については、設計基準強度 Fc≦36N/㎟のコンクリートにおいては23KN/㎥とし、36N/㎟<Fc≦48N/㎟のコンク リートにおいては23.5KN/㎥とすることができる。(1級H22)13 教室に連絡する廊下や階段の床の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、教室の床 の積載荷重と同じ2,300N/㎡としなければならない。(1級H22)14 多数の者が利用する自走式の駐車場において、誤操作による自動車の転落事故を防止す るための装置の構造は、250KNの衝撃力が作用した場合に、装置の部材の塑性変形等を 考慮し、衝撃力を吸収できるようにする。(1級H22)15 単位面積当たりの積載荷重の大小関係は、実況に応じて計算しない場合、教室>店舗の 売り場>住宅である。(1級H24)16 教室に連絡する廊下や階段の床の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、教室の床 の積載荷重と同じ値を用いることができる。(1級H27)17 建築物の各部分の積載荷重は、「床の構造計算をする場合」、「大梁・柱・基礎の構造 計算をする場合」及び「地震力を計算する場合」において、それぞれ異なる値を用いる ことができる。(1級H27)18 一般的な鉄筋コンクリートの単位体積重量は、コンクリートの単位体積重量に、鉄筋に よる重量増分として1KN/㎥を加えた値を用いることができる。(1級H27,H30)19 学校の屋上広場の単位面積当たりの積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、教室の 単位面積当たりの積載荷重と同じ数値とすることができる。(1級H29)20 単位面積当たりの積載荷重は、建築物の実況に応じて計算しない場合、「床の構造計算 をする場合」、「大梁、柱又は基礎の構造計算をする場合」及び「地震力を計算する場 合」のうち、「地震力を計算する場合」が最も大きくなる。(1級H30)21 床の構造計算を行う場合の単位面積当たりの積載荷重の大小関係は、実況に応じて計算 しない場合、住宅の居室>事務室>教室である。(1級R03)□ 荷重(雪荷重)(2級)1 積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重は、多雪区域以外の区域においては、積雪量 1㎝ごとに20N/㎡以上とする。(2級H18,R03)2 屋根の積雪荷重は、雪止めのない屋根の場合、屋根勾配が緩やかになるほど小さい。 (2級H18)3 積雪の単位荷重は、多雪区域の指定のない区域においては、積雪量1㎝ごとに1㎡につき 20N以上とする。(2級H16)4 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合にお いては、零とすることができる。(2級H16,H20,H26,H30)5 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮し て積雪荷重を計算しなければならない。(2級H17,H20,H24,H25,H27,H29,R01)6 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が45度を超える場合にお いては、零とすることができる。(2級H23,H29)7 多雪区域を指定する基準は、「垂直積雪量が1m以上の区域」又は「積雪の初終間日数 の平年値が30日以上の区域」と定められている。(2級H28)□ 荷重(雪荷重)(1級)1 屋根の積雪荷重は、雪止めの無い屋根の場合、屋根勾配が緩やかになるほど大きい。 (1級H15)2 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を 乗じて計算する。(1級H17)3 多雪区域を指定する基準において、垂直積雪量が1m未満の区域であっても、積雪の初 終間日数の平年値が30日以上の区域については、多雪区域となる。(1級H16)4 積雪荷重において、垂直積雪量dは、「その区域の標準的な標高ls及び海率rs」「周辺 地形あるいはその区域での観測資料等」を考慮して特定行政庁が定める。(1級H18)5 雪止めの無い屋根の勾配が45度の場合、屋根の積雪荷重は0とすることができる。 (1級H19)6 多雪区域以外において、積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重は、積雪量1㎝当たり 20N/㎡以上とする。(1級H20,R01)7 垂直積雪量が1mを超える場合、雪下ろしの状況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして 積雪荷重を計算した建築物については、その出入り口、主要な居室又はその他見やすい 場所に、その軽減の状況その他必要な事項を表示しなければならない。(1級H20,R04)8 雪下ろしを行う習慣のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超え る場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの状況に応じて垂直積雪量を1mまで減らし て計算することができる。(1級H29)9 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮し て積雪荷重を計算しなければならない。(1級R04)10 多雪区域以外の区域における大スパン等の一定の条件を満たす緩勾配屋根を有する建築 物では、屋根版の構造種別によっては、構造計算において用いる積雪荷重に積雪後の降 雨を考慮した割増係数を乗じることが求められる場合がある。(1級R04)11 多雪区域を指定する基準において、積雪の初終間日数の平均値が30日以上の区域であっ ても、垂直積雪量が1m未満の場合は、多雪区域とはならない。(1級R04)□ 荷重(風荷重)(2級)1 風圧力の計算に用いる速度圧は、その地方における基準風速の2乗に比例する。 (2級H16,H29)2 風圧力の計算は、原則として、金網その他の網状の構造物についても行う必要がある。 (2級H16)3 暴風時における建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合においては、建築物の実況 に応じて積載荷重を減らした数値によるものとする。(2級H20,H23,H24,H26)4 暴風時における建築物の転倒等を検討する場合においては、建築物の実況に応じて積載 荷重を減らした数値によるものとする。(2級H22)5 風圧力の計算に用いる風力係数は、地盤面からの高さが高い部位ほど大きい。(2級H22)6 風圧力を計算する場合の速度圧は、その地方において定められた風速の2乗に比例する。 (2級H23,H26,H27)7 風圧力の計算に用いる速度圧は、その地方において定められた風速の平方根に比例する。 (2級H24)8 建築物の屋根版に作用する風圧力と、屋根葺き材に作用する風圧力とは、それぞれ個別 に計算する。(2級H26,H28,R01)9 暴風時における建築物の転倒、柱の引抜き等を検討する場合、積載荷重は、築物の実況 に応じて低減した数値によるものとする。(2級H28)10 風圧力を計算する場合において、閉鎖型及び開放型の建築物の風力係数は、原則として、 建築物の外圧係数から内圧係数を減じた数値とする。(2級H29)11 閉鎖型の建築物で風上解放の場合、風圧力の計算に用いる風力係数は、一般に、正の内 圧係数を用いて計算する。(2級R01)12 風圧力の計算に用いる平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erは、同じ地上高さの場合、 一般に、地表面粗度区分がⅢよりⅡのほうが大きくなる。(2級R03)13 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算する。(2級H17,H20)14 速度圧は、その地方において定められた風速の平方根に比例する。(2級H17,H20,H30)15 閉鎖型及び開放型の建築物の風力係数は、原則として、建築物の外圧係数から内圧係数 を減じた数値により算出する。(2級H18,H20,H30)16 ラチス構造物の風圧作用面積は、風の作用する方向から見たラチス面積の見付面積とする。 (2級H17,H30)17 速度圧は、一般に、屋根の平均高さに基づいて算定する。(2級H20)18 金網その他の網状の構造物の風圧作用面積は、風の作用する方向から見た金網等の見付 面積とする。(2級H20)19 風圧力の計算に用いる基準風速V₀は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害 の程度その他の風の性状に応じて、30m/sから46m/sまでの範囲内において定められて いる。(2級H21)20 速度圧の計算に用いる地表面粗度区分は、海岸線からの距離、建築物の高さ等を考慮し て定められている。(2級H30)21 建築物に作用する風圧力に関する下記の文中のア~ウに当てはまる用語A~Cの組合せ として、最も適切なものは、次のうちどれか。(2級H14) 22 図のような方向に風を受ける建築物のA点における風圧力の大きさとして、最も適当な ものは、次のうちどれか。ただし、速度圧は1,000N/㎡とし、建築物の外圧係数及び内 圧係数は、図に示す値とする。(2級H25) 23 図のような方向に風を受ける建築物のA点における風圧力の大きさとして、最も適当なも のは、次のうちどれか。ただし、速度圧は1,000N/㎡とし、建築物の外圧係数及び内圧 係数は、図に示す値とする。(2級H25)□ 荷重(風荷重)(1級)1 風圧力の計算に用いる速度圧qは、その地方における基準風速の二乗に比例する。 (1級H15,H20) 2 基準風速V₀は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性 状に応じて、30m/sから46m/sまでの範囲内において定められている。(1級H17) 3 単位面積当たりの風圧力については、一般に、「外装材に用いる風圧力」より「構造骨 組みに用いる風圧力」のほうが小さい。(1級H17) 4 速度圧qは、基準風速V₀の二乗に比例し、建築物の高さhの平方根に比例する。 (1級H17) 5 ガスト影響係数Gfは、風の時間的変動により建物が揺れた場合に発生する最大の力を 計算するために用いる係数である。(1級H17)6 平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erは、地表面粗度区分(Ⅰ~Ⅳ)に応じて計算す る。(1級H17) 7 風圧力における平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erは、建築物の高さが同じ場合、 一般に、「極めて平坦で障害物がない区域」より「都市化が極めて著しい区域」のほう が小さい。(1級H16,H24,H29) 8 ガスト影響係数Gfは、一般に、建築物の高さと軒の高さとの平均Hに比例して大きくな り、「都市化が極めて著しい区域」より「極めて平坦で障害物がない区域」のほうが大 きくなる。(1級H18,H26) 9 基準風速V₀は、稀に発生する暴風時の地上10mにおける10分間平均風速に相当する値で ある。(1級H18,R01) 10 風圧力を計算するに当たって用いる風力係数は、風道試験によって定める場合の他、建 築物の断面及び平面の形状に応じて定める数値によらなければならない。(1級H19)11 風圧力を算出する場合の基準風速V₀は、地方の区分に応じて規定されている。 (1級H21)12 高さ13m以下の建築物において、屋根ふき材については、規定のピーク風力係数を用い て風圧力の計算をすることができる。(1級H22,H26) 13 閉鎖型の建築物における風力係数は、一般に、その建築物の外圧係数と内圧係数との差 により算定する。(1級H24) 14 風圧力の計算に用いる速度圧qは、その地方における基準風速V₀のに比例する。 (1級28)15 風圧力の計算に用いる速度圧qは、その地方において定められている基準風速V₀の2 乗に比例する。(1級R01) 16 ガスト影響係数Gfは、「平坦で障害物がない区域」より「都市化が著しい区域」のほ うが大きい。(1級R01) 17 風圧力は、一般に、「外装材に用いる場合」より「構造骨組みに用いる場合」のほう が大きい。(1級R01)18 屋根葺き材等に対して定められるピーク風力係数C^fは、局部風圧の全風向の場合に おける最大値について基づいて定められている。(1級R03) 19 屋根葺き材の風圧力に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準は、 建築物の高さにかかわらず適用される。(1級R02) 20 屋根葺き材に作用する風圧力の算出に用いる平均速度圧q ̄については、気流の流れを 表すガスト影響係数Gfは考慮しなくてよい。(1級R02) 21 屋根葺き材に作用する風圧力の算出に用いるピーク風力係数C^fは、一般に、構造骨組 みに用いる風圧力を算出する場合の風力係数Cfよりも大きい。(1級R02) 22 屋根葺き材に作用する風圧力の算出に用いる基準風速V₀は、構造骨組に用いる風圧力 を算出する場合と異なる。(1級R02) 23 図のような4階建の建築物において、各階の風圧力の算定に関する次の記述のうち、最 も不適当なものはどれか(1級H23) 1 高さh2の窓ガラスの検討に用いる風圧力の計算においては、ピーク風力係数を考慮する。 2 高さh1の庇の風圧力は、庇の高さh1のみで検討し、建築物の高さと軒の高さとの平 Hに影響されない。 3 屋根ふき材に作用する風圧力算定においては、ピーク風力係数を考慮する。 4 速度圧は、その地方における基準風速、地表面粗度区分及び建物の高さと軒の高さとの 平均Hに影響され、風力係数は建築物の形状に応じて定められている。 **************************************************************** 解説 □ 荷重(固定荷重・積載荷重) ① 固定荷重・積載荷重の問題は、建築基準法施行令第85条より出題される場合が多いです。 特に、1項表の大小関係はしっかり把握してください。 ② 鉄筋コンクリートの単位体積重量は、コンクリートの重量に鉄筋分1kN/㎥を加えて求める。 コンクリートの重量は設計基準強度により変化する。 □ 荷重(固定荷重・積載荷重)(2級) 1 〇 建築基準法施行令第82条二号の表より、一般の場合、長期に生ずる力(長期荷重) は固定荷重(G)と積載荷重(P)の和となる。 正しい 2 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の構造計算をする場合と大梁の構造計算をする場合では床の方が大 きい。 正しい3 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の構造計算をする場合と地震力を計算する場合では、床のほうが大 きい。 誤り4 〇 建築基準法施行令第83条1項の表より、荷重及び外力は、固定荷重、積載荷重、積 雪荷重、風圧力、地震力を採用しなければならない。尚、2項により、その他に建 築物の儒教に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければなら ない。 正しい 5 〇 建築基準法施行令第84条の表より、瓦葺:640N/㎡(ふき土がない場合)厚型ス レート葺き440N/㎡となり、瓦葺のほうが大きい。 正しい 6 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の構造計算をする場合と柱の構造計算をする場合では床の方が大き い。 正しい 7 〇 建築基準法施行令第84条の表より、固定荷重は、骨組部材・仕上材料等のような構 造物自体の重量及び構造物上に常時固定されている物体の重量による荷重である。 正しい 8 〇 建築基準法施行令第85条3項により、倉庫業を営む倉庫の床の積載荷重は、実況に 応じて計算した数値が3,900N/㎡未満であっても、3,900N/㎡としなければならな い。 正しい9 〇 建築基準法施行令第85条2項により、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算す る場合、支える床の数において積載荷重を低減することができる。ただし、劇場系 の用途の場合は低減できない。 正しい 10 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。 正しい 11 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の構造計算をする場合と地震力を計算する場合では、地震力のほう が小さい。 誤り12 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。 正しい 13 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の単位面積当たりの積載荷重は、教室 (2,300N/㎡)より百貨店又は店舗の売り場(2,900N/㎡)のほうが大きい。 誤り 14 〇 多スパンのの建築物では、積載荷重が一様に分布していると、梁の左右の曲げモー メントが釣り合って、柱に曲げモーメントが生じないことがあるが、荷重が偏在し ている場合は柱に曲げモーメントが発生し不利になることがある。 正しい 15 〇 建築基準法施行令第85条2項により、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算す る場合、支える床の数において低減することができる。ただし、劇場系の用途の場 合は低減できない。 正しい 16 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の単位面積当たりの積載荷重は、百貨店 又は店舗の売り場(2,900N/㎡)より教室(2,300N/㎡)のほうが小さい。正しい 17 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。誤り 18 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の単位面積当たりの積載荷重は、百貨店又 は店舗の売り場(2,900N/㎡)より教室(2,300N/㎡)のほうが小さい。 誤り 19 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。 正しい 20 〇 建築基準法施行令第85条2項により、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算す る場合、支える床の数において低減することができる。積載荷重を減らすために乗 ずる数値は、2項の数値により、支える床の数が多くなるほど小さくなる。正しい 21 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。 誤り □ 荷重(固定荷重・積載荷重)(1級)1 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の単位面積当たりの積載荷重は、教室 (2,300N/㎡)にくらべて、学校のバルコニー(2,900N/㎡)よりのほうが大き い。 誤り 2 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、劇場の積載荷重は、床の構造計算をする場 合は、固定席(2,900N/㎡)より、その他(3,500N/㎡)のほうが大きい。誤り 3 〇 構造計算の種類(許容応力度計算、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐 力計算)によって積載荷重は変わらない。ただし、限界耐力計算においては2次設 計において、積雪荷重を1.4倍、風圧力を1.6倍として計算する。 正しい 4 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の構造計算をする場合の積載荷重は、店 舗の売り場(2,900N/㎡)>教室(2,300N/㎡)>住宅の居室(1,800N/㎡)とな る。 正しい5 × 地震力及び風圧力は、水平方向のみではない。例えば、屋根面の風圧力は屋根面に 垂直宝庫に作用する場合がある。2m超の片持ちバルコニー等は鉛直方向の地震動 を考慮する。 誤り 6 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。 正しい 7 〇 建築基準法施行令第85条2項により、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算す る場合、支える床の数において積載荷重を低減することができる。ただし、劇場系 の用途の場合は低減できない。 正しい 8 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の構造計算をする場合の積載荷重は、百 貨店の屋上広場(2,900N/㎡)と百貨店の売り場(2,900N/㎡)は同じ。 正しい 9 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の構造計算をする場合の積載荷重は、店 舗の売り場に連絡する廊下(3,500N/㎡)と店舗の売り場(2,900N/㎡)は異なる。 誤り 10 〇 建築基準法施行令第85条3項より、倉庫業を営む倉庫は、実況に応じて計算した値が 3,900N/㎡未満であっても3,900N/㎡としなければならない。 正しい 11 〇 鉄筋コンクリートの単位体積重量は、実況による。特に調査しない場合は、無筋コ ンクリートの単位体積重量に、鉄筋による重量増分値1kN/㎥を加えて求める。(鉄 筋コンクリート構造計算基準) 正しい 12 〇 コンクリートの単位体積重量は、②の表の値とすることができる。(鉄筋コンクリー ト構造計算基準) 正しい 13 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、教室に連絡する廊下や階段は3,500N/㎡、 教室は2,300N/㎡なので、同じではない。 誤り14 〇 多数の者が利用する自走式の駐車場において、通常考え得る程度の誤操作による転 落事故を防止するための装置は、250KNの衝撃力を十分吸収できるようにしなけれ ばならない。(駐車場における自動車転落事故を防止するための装置等に関する設 計指針) 正しい 15 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の構造計算をする場合の積載荷重は、店 舗の売り場(2,900N/㎡)>教室(2,300N/㎡)>住宅の居室(1,800N/㎡)とな る。 誤り 16 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、教室に連絡する廊下や階段は3,500N/㎡、教 室は2,300N/㎡なので、同じではない。 誤り17 〇 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用である。 正しい 18 〇 鉄筋コンクリートの単位体積重量は、実況による。特に調査しない場合は、無筋コ ンクリートの単位体積重量に、鉄筋による重量増分値1kN/㎥を加えて求める。 (鉄筋コンクリート構造計算基準) 正しい19 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、学校の屋上広場は2,900N/㎡、教室は 2,300N/㎡なので、同じではない。 誤り20 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、積載荷重は、室の種類と構造計算の対象に より異なる。床の計算用>大梁、柱又は基礎の計算用>地震力の計算用であり、地 震力を計算する場合が最も小さい。 誤り 21 × 建築基準法施行令第85条1項の表より、床の構造計算をする場合の積載荷重は、事務室 (2,900N/㎡)>教室(2,300N/㎡)>住宅の居室(1,800N/㎡)となる。 誤り □ 荷重(雪荷重) 積雪荷重は、建築基準法施行令第86条(平成12年建設省告示第1455号)から出題されます。各言葉の定義、意味はしっかり理解してください。① 積雪荷重は、積雪の単位荷重×屋根の水平投影面積×垂直積雪量 ・積雪の単位荷重は、一般の地域では積雪1㎝当り20N/㎡、多雪区域では特定行政庁が定め た値 ・多雪区域の定義:(ア)垂直積雪量が1m以上の区域、又は、(イ)積雪の初終間日数の平均値が 30日以上の区域 ・垂直積雪量は、(ア)その区域の標準的な標高及び海率、(イ)周辺地形あるいはその区域での 観測資料を考慮して特定行政庁が定める ② 屋根の積雪荷重は、雪止めがある場合を除き、屋根勾配が60度以下の場合、勾配に応じて 低減することができる。60度を超える場合は0とすることができる。 ・積雪荷重による応力は、屋根全体に雪が一様に分布している場合に比べて、その一部が解 けるなどして不均等な分布となる法が不利となることがある。 ・雪下ろしを行う習慣のある地方においては、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mま で低減できる。低減して計算した場合は、出入口、主要な居室又はその他見やすい場所に、 その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。③ 多雪区域以外の区域において、(ア)大スパン建物(屋根の最上端から最下端までの水平投影 長さが10m以上)、(イ)緩勾配屋根(15度以下)、(ウ)屋根重量が軽い(屋根版がRC造又は SRC造でないもの)は、雪荷重に積雪後の降雨の影響を考慮した割増係数を乗じて計算しな ければならない。(平成19年国交省告示第594号)□ 荷重(雪荷重)(2級) 1 〇 建築基準法施行令第86条2項より、積雪の単位荷重は、多雪区域以外の区域におい ては積雪量1㎝ごとに1㎡につき20N/㎡以上としなければならない。 正しい 2 × 建築基準法施行令第86条4項より、屋根の積雪荷重は、雪止めがない場合、勾配が 60度以下の場合は屋根の勾配が緩やかなほど大きくなる。また、勾配が60度を超 える場合は、0とすることができる。 誤り 3 〇 建築基準法施行令第86条2項より、積雪の単位荷重は、多雪区域以外の区域におい ては積雪量1㎝ごとに1㎡につき20N/㎡以上としなければならない。 正しい 4 〇 建築基準法施行令第86条4項より、屋根の積雪荷重は、雪止めがない場合、勾配が 60度以下の場合は屋根の勾配が緩やかなほど大きくなる。また、勾配が60度を超 える場合は、0とすることができる。 正しい 5 〇 建築基準法施行令第86条5項より、屋根面における積雪量が不均等となるおそれのあ る場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。正しい 6 × 建築基準法施行令第86条4項より、屋根の積雪荷重は、雪止めがない場合、勾配が 60度以下の場合は屋根の勾配が緩やかなほど大きくなる。また、勾配が60度を超え る場合は、0とすることができる。 誤り 7 〇 多雪区域の指定の基準は、①垂直積雪量が1m以上の区域、又は、②積雪の初終間 日数(当該区域中の積雪部分の割合が1/2を超える状態が継続する期間の日数)の 平年値が30日以上の区域である。(平成12年建設省告示第1455号) 正しい □ 荷重(雪荷重)(1級) 1 〇 建築基準法施行令第86条4項より、屋根の積雪荷重は、雪止めがない場合、勾配が 60度以下の場合は屋根の勾配が緩やかなほど大きくなる。また、勾配が60度を超 える場合は、0とすることができる。 正しい2 〇 建築基準法施行令第86条1項より、積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影 面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。 正しい3 〇 多雪区域の指定の基準は、①垂直積雪量が1m以上の区域、又は、②積雪の初終間日 数(当該区域中の積雪部分の割合が1/2を超える状態が継続する期間の日数)の平年 値が30日以上の区域である。(平成12年建設省告示第1455号) 正しい4 〇 垂直積雪量dは市町村の区域において、d=α・ls+β・rs+γで求める。ls(区域の 標準的な標高)、rs(区域の標準的な海率)、α、β、γ(区域に応じて定める数値) (平成12年建設省告示第1455号) 正しい5 × 建築基準法施行令第86条4項より、屋根の積雪荷重は、雪止めがない場合、勾配が 60度以下の場合は屋根の勾配が緩やかなほど大きくなる。また、勾配が60度を超 える場合は、0とすることができる。 誤り6 〇 建築基準法施行令第86条2項より、積雪の単位荷重は、多雪区域以外の区域におい ては積雪量1㎝ごとに1㎡につき20N/㎡以上としなければならない。 正しい7 〇 建築基準法施行令第86条6項、7項より、雪下ろしの習慣のある地方においては、垂 直積雪量が1mを超える場合においても、実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らし て計算することができる。その場合、その建築物の出入口、主要な居室又はその他 見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。 正しい8 〇 建築基準法施行令第86条6項、7項より、雪下ろしの習慣のある地方においては、垂 直積雪量が1mを超える場合においても、実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らし て計算することができる。その場合、その建築物の出入口、主要な居室又はその他 見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければならない。 正しい 9 〇 建築基準法施行令第86条5項より、屋根面における積雪量が不均等となるおそれのあ る場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。正しい 10 〇 多雪区域以外の区域における①大スパン、②緩勾配、③屋根重量が軽い等を有する建 築物には、積雪荷重に積雪後の降雨を考慮した割増係数を乗じて計算しなければなら ない。(平成19年国交省告示第594号) 正しい 11 × 多雪区域の指定の基準は、①垂直積雪量が1m以上の区域、又は、②積雪の初終間日 数(当該区域中の積雪部分の割合が1/2を超える状態が継続する期間の日数)の平年 値が30日以上の区域である。(平成12年建設省告示第1455号) 誤り □ 荷重(風荷重) 風荷重は、建築基準法施行令第87条(平成12年建設省告示第1454号)から出題されます。各言葉の定義、意味はしっかり理解してください。① 風荷重=風圧力×風圧力に関する見附面積② 風圧力(構造骨組み用)=速度圧(q)×風圧力(Cf)③ 速度圧(q)=0.6×E×V₀² E=Er²×Gf Er:平均風速の高さ方向の分布を表す係数 Gf:ガスト影響係数) ・ErとGfの傾向(このグラフの傾向がよく問われます!) ErとGfは、建築物の屋根の平均高さと地表面粗度区分によって決まる。 ・速度圧(q)は、各建物で一つの値が決まる。建物の場所によって変化はしない。 ・基準風速(V₀)は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性 状に応じて30m/秒から46m/秒の範囲内で、稀に発生する暴風時の地上10mにおける10分 間平均風速に相当する値。④風力係数(Cf)=Cpe-Cpi (Cpe:外圧係数 Cpi:内圧係数) ・風力係数は、風洞実験によって求めるか、建築物等の形状等に応じて国土交通大臣が定める 値である。風上壁面では、地盤面からの高さ5m(都市化が著しい地域では10m)以上の部 分については、高い部位ほど風力係数が大きくなるが、その他の壁面では、高さに関係なく 一定となる。 外圧係数 内圧係数 屋根葺き材等の構造計算(平成12年建設省告示第1458号)① 屋根葺き材、外装材及び屋外に面する帳壁(窓ガラスも含む)にかかる風圧力は、建築物 (構造骨組)に係る風圧力とは異なる。② 屋根葺き材等に用いる風圧力=平均速度圧(q-)×ピーク風力係数(C^f) (構造骨組みに用いる風圧力より屋根葺き材等に用いる風圧力の方が大きい)③ 平均速度圧(q-)=0.6×Er²×V₀² (ガスト影響係数Gfが入っていない) (基準風速V₀は、構造骨組みに用いる風圧力を算定するときと同じ値) ④ ピーク風力係数(C^f)=C^pe-Cpi (構図骨組みに用いる風力係数より大きく なる) (屋根面の周囲や、コーナー部分の壁のピーク風力係数は大きくなる)⑤ 屋根葺き材は高さに関係なく検討(耐風計算が必要)だが、屋根以外の外装材は、建築物の 高さが13m以下の場合は検討しなくてもよい。 □ 荷重(風荷重)(2級) 1 〇 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。 正しい2 〇 トラス・ラチスや金網など、風が吹き抜ける構造物であっても、見付面積がある限 り風圧力が発生するので計算を行う必要がある。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい3 〇 暴風時における建築物の転倒、柱の引き抜きを検討する場合は、積載荷重が少ない 方が不利になる場合があるので実況に応じて積載荷重を減らして検討する必要があ る。 正しい4 〇 暴風時における建築物の転倒、柱の引き抜きを検討する場合は、積載荷重が少ない 方が不利になる場合があるので実況に応じて積載荷重を減らして検討する必要があ る。 正しい5 × 風力係数は、風上壁面では、地盤面からの高さ5m(都市化が著しい地域では10m) 以上の部分については、高い部位ほど風力係数が大きくなるが、その他の壁面では、 高さに関係なく一定となる。(平成12年建設省告示第1454号) 誤り6 〇 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。 正しい7 × 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。平方根に比例ではない。 誤り8 〇 屋根版(屋根の構造体)と屋根葺き材(外装材)に作用する風圧力は、それぞれ別 の計算方法により算出する。一般的には、構造体に用いる風圧力より外装材に用い る風圧力の方が大きい。 正しい9 〇 暴風時における建築物の転倒、柱の引き抜きを検討する場合は、積載荷重が少ない 方が不利になる場合があるので実況に応じて積載荷重を減らして検討する必要があ る。 正しい10 〇 閉鎖型及び開放型の建築物の風力係数は、原則として、 風力係数(Cf)=Cpe-Cpi (Cpe:外圧係数、Cpi:内圧係数)によって 求める。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい11 〇 風上開放型の風力係数は、風力係数(Cf)=Cpe-Cpi(Cpe:外圧係数、 Cpi:内圧係数)外圧係数に+0.6(正の内圧係数)を用いる。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい12 〇 平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erは、グラフより地表面粗度区分がⅢより Ⅱのほうが大くなる。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい13 〇 建築基準法施行令第87条1項より、 風圧力(構造骨組み用)=速度圧(q)×風圧力(Cf)。 正しい14 × 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。平方根に比例ではない。 誤り15 〇 閉鎖型及び開放型の建築物の風力係数は、原則として、 風力係数(Cf)=Cpe-Cpi (Cpe:外圧係数、Cpi:内圧係数)によって 求める。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい16 〇 トラス・ラチスや金網など、風が吹き抜ける構造物であっても、風圧力が発生する。 風圧作用面積は、風の作用する方向から見たラチスや金網などの見付面積となる。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい17 〇 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²となり、 E=Er²×Gfとなる。ErとGfは屋根の平均高さによって決まるきまるので、速度圧 は屋根の平均高さに基づいて算定する。 正しい18 〇 トラス・ラチスや金網など、風が吹き抜ける構造物であっても、風圧力が発生する。 風圧作用面積は、風の作用する方向から見たラチスや金網などの見付面積となる。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい19 〇 建築基準法施行令第87条2項より、基準風速(V₀)は、その地方における過去の台 風の記録に基づき、30m/秒から46m/秒までの範囲内で、稀に発生する暴風時の地 上10mにおける10分間平均風速に相当する値で決められている。 正しい20 〇 ErとGfの中に出てくる地表面粗度区分は海岸線からの距離、建築物の高さを考慮し て決められており、Ⅰ(極めて平坦で障害物のない区域)~Ⅳ(都市化が極めて著し い区域)で定められている。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい21 1 風圧力は、速度圧に(ア:風圧力)を乗じて計算する。その速度圧は、 0.6×(イ:E)×(ウ:V₀)により計算する。(建築基準法施行令第87条1項)22 2 風圧力=速度圧×風力係数により、 風圧力=1,000N/㎡×(-0.2-(-0.4))=200N/㎡23 4 風圧力=速度圧×風力係数により、 風圧力=1,000N/㎡×(-0.2-0.8)=1,000N/㎡□ 荷重(風荷重)(1級)1 〇 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。 正しい2 〇 建築基準法施行令第87条2項より、基準風速(V₀)は、その地方における過去の台 風の記録に基づき、30m/秒から46m/秒までの範囲内で、稀に発生する暴風時の地 上10mにおける10分間平均風速に相当する値で決められている。 正しい3 〇 外装材に用いる風圧力と、構造骨組みに用いる風圧力では、速度圧と風力係数の値 が異なり、一般に、構造骨組みに用いる風圧力の方が小さい。 正しい4 × 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例するが、建築物の高さの平方根に比例はしない。誤り5 〇 ガスト影響係数Gfは、突風などによる揺れを考慮した割増係数であり、風の時間的 変動により建築物が揺れた場合に発生する最大の力を計算するために用いる係数で ある。 正しい6 〇 平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erとガスト影響係数Gfは、地表面粗度区分 (Ⅰ~Ⅳ)と建物の高さと軒の高さとの平均Hによって決まる。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい7 〇 平均風速の高さ方向の分布を表す係数Erは、グラフの傾向より、地表面粗度区分 (Ⅰ:極めて平坦で障害物がない区域)より(Ⅳ:都市化が極めて著しい区域)の ほうが小さい。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい8 × ガスト影響係数Gfは、グラフの傾向より、建物の高さと軒の高さとの平均Hが大き いほど小さくなり、地表面粗度区分(Ⅳ:都市化が極めて著しい区域)より (Ⅰ:極めて平坦で障害物がない区域)の方が小さくなる。 (平成12年建設省告示第1454号) 誤り9 〇 基準風速(V₀)は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他 の風の性状に応じて30m/秒から46m/秒の範囲内で、稀に発生する暴風時の地上 10mにおける10分間平均風速に相当する値。(平成12年建設省告示第1454号) 正しい10 〇 建築基準法施行令第87条4項より、風力係数は、風洞試験によって定める場合のほ か、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値に よらなければならない。 正しい11 〇 建築基準法施行令第87条2項より、基準風速(V₀)は、その地方における過去の台 風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて30m/秒から46m/秒の範囲 内で、稀に発生する暴風時の地上10mにおける10分間平均風速に相当する値。 正しい12 〇 屋根ふき材の風圧力は、風圧力=平均速度圧×ピーク風力係数で求める。屋根ふき 材は高さに関わらず検討が必要だが、帳壁等の外装材については高さ13m超のみ検 討が必要である。(平成12年建設省告示第1458号) 正しい13 〇 閉鎖型及び開放型の建築物の風力係数は、原則として、 風力係数(Cf)=外圧係数(Cpe)-内圧係数(Cpi)によって求める。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい14 × 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。 誤り15 〇 建築基準法施行令第87条2項より、速度圧(q)=0.6×E×V₀²により、速度圧は 基準風速(V₀)の2乗に比例する。 正しい16 〇 ガスト影響係数Gfは、グラフの傾向より、建物の高さと軒の高さとの平均Hが大き いほど小さくなり、地表面粗度区分(Ⅰ:極めて平坦で障害物がない区域))より (Ⅳ:都市化が極めて著しい区域)の方が大きくなる。 (平成12年建設省告示第1454号) 正しい17 × 構造骨組みと外装材に作用する風圧力は、それぞれ別の計算方法により算出する。 一般的には、構造骨組みに用いる風圧力より外装材に用いる風圧力の方が大きい。 誤り18 〇 屋根ふき材等に対して定められているピーク風力係数C^fは、局部風圧の全風向中 の最大のみで示されている。(建築物荷重指針・同解説) 正しい19 〇 屋根ふき材等の耐風計算において、外装材及び帳壁については建築物の高さが13m 超の部分に適用されるが、屋根ふき材に関しては建築物の高さにかかわらず適用さ れる。(平成12年建設省告示第1458号) 正しい20 〇 平均速度圧(q-)=0.6×Er²×V₀² で求め、ガスト影響係数Gfは考慮していな い。ガスト影響係数Gfは、ピーク風力係数C^fに考慮されている。 (平成12年建設省告示第1458号) 正しい21 〇 屋根ふき材に作用する風圧力の算出に用いるピーク風力係数C^fは、ガスト影響係 数Gfが考慮 されているため、構造骨組みに用いる風圧力を算出する風力係数Cfよ りも大きな値となる。 正しい22 × 屋根ふき材に作用する風圧力の算出に用いる基準風速V₀と、構造骨組みに作用する 風圧力の算出に用いる基準風速V₀は同じ値を用いる。 誤り23 2 1 〇 13m超の部分は、ピーク風力係数を用いて風圧力を計算しなければならない。 正しい 2 × 風圧力の値は、ErとGfに影響される。ErとGfは建築物の高さと軒の高さと の平均Hと地表面粗度区分によって決まる。従って、風圧力は建築物の高さ と軒の高さとの平均に影響される。 誤り 3 〇 屋根ふき材に作用する風圧力は、平均速度圧q-とピーク風力係数C^fとの 積で求める。 正しい 4 〇 速度圧q=0.6×E×V₀²なので、基準風速と地表面粗度区分及び建築物の高 さと軒の高さの平均Hに影響される。風圧力Cf=Cpe-Cpoなので、外圧 係数・内圧係数は建物形状に応じて定められている。 正しい今回は構造の文章問題です。荷重・外力の問題を2回に分けて紹介します。1回目は、固定荷重、積載荷重、雪荷重、風荷重です。この中では、積載荷重表の大小関係、風荷重の言葉・係数の傾向などがよく出ています。最近の傾向として、風荷重の屋根材等の風圧力の計算内容や、雪荷重の一般地域での降雨での割増係数に関してなどが出ています。 今日はこんな言葉です! 『才能があるかないかを決めるのは自分ではありません。やってみて初めて周囲が判断してくれます。自分がやりたいことをまずやってみましょう。 』(瀬戸内 寂聴)
Aug 11, 2022
閲覧総数 3160
-
12
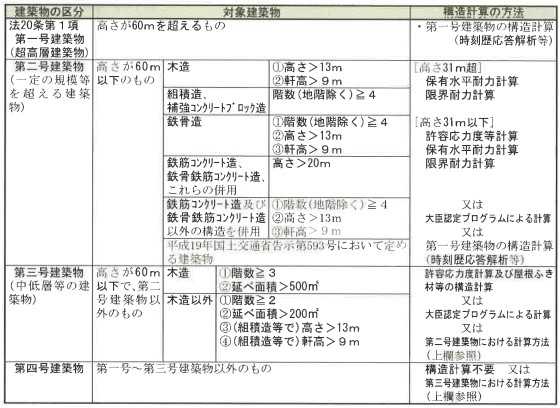
建築士の勉強!第84回(構造文章編第3回 構造計画・耐震計画-1)
構造文章編第3回(構造計画・耐震計画-1) 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!構造-6構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。構造(文章)3.構造計画・耐震計画 今回は、文章問題の構造計画・耐震計画等に関する問題をまとめました。この分野は、前回紹介した荷重外力や、今後紹介する各種構造の分野とも共通する問題がでています。ここでは、敢えて重複する問題も紹介していますのでご了承ください。この分野は、2級でも1級でも必ず数問出題されるところです。特によく出ているのが、構造計算の概要です。2級ではルート2が、1級ではルート3が特に多いので、法規と合わせて学習することをお勧めします!! その他、構造計画一般はとても広範囲から出題されますので、新傾向問題が多く難しい問題も多いいところです。この分野も内容が多いので、数回に分けて紹介していきます。1回目は、構造計算の概要を途中までです。(問題は、一部修正しているものもあります。) ***************************************************************** 問題 □ 構造計算の概要1-1 一次設計・二次設計について(2級)1 建築物の外壁から突出する部分の長さが2mを超える片持ちのバルコニーを設ける場合、 当該部分の鉛直震度に基づき計算した地震力に対て安全であることを確かめる必要があ る。(2級H26)2 まれに発生する地震に対して、建築物が損傷しないようにすることは、耐震設計の目標 の一つである。(2級H27)3 建築物の耐震設計は、稀に発生する地震(中程度の地震)に対して損傷による性能の低 下を生じないことを確かめる一次設計と、極めて稀に発生する地震(最大級の地震)に 対して崩壊・倒壊等しないことを確かめる二次設計から構成される。(2級H29)4 耐震設計の一次設計では、稀に発生する地震(中程度の地震)に対して建築物の損傷に よる性能の低下を生じさせないことを確かめる。(2級H30)5 中程度の(稀に発生する)地震動に耐して、建築物の構造耐力上主要な部分に損傷が生 じないことは、耐震設計の要求性能の一つである。(2級R03)6 耐震設計における二次設計は、建築物が弾性限を超えても、最大耐力以下であることや 塑性変形可能な範囲にあることを確かめるために行う。(2級R03)7 建築物の地上部分について、地震力に対する水平剛性の検討において、各階の層間変形 角が1/200以下であることを確認した。(2級H17)8 各階における層間変形角の値は、一次設計用地震力に対し、原則として、1/200以内と なるようにする。(2級H27,R02)9 極めて稀に起こる地震に対しては、建築物が崩壊や倒壊しないことを確かめる。 (2級H20)10 建築物が、極めて稀に発生する地震動に対して倒壊しないようにするこては、耐震設計 の目標の一つである。(2級R01,R04)1-2 一次設計・二次設計について(1級)1 建築物の一次固有周期は、同じ構造形式の場合、一般に、建築物の高さが高いものほど 長くなる。(1級H15)2 地震地域係数Zは、「許容応力度を検討する場合」と「保有水平耐力を検討場合」とに より異なる値を用いる。(1級H16)3 地表に設置された高さ4mを超える広告塔に作用する地震力については、一般に、水平震 度を0.5Z(Zは地震地域係数)以上として計算する。(1級H17)4 建築物のたわみや振動による使用上の支障が起こらないことを確認するために、梁及び スラブの断面の応力度を検討する方法を採用した。(1級H18)5 床構造の鉛直方向の固有振動数が小さい場合には、鉛直方向の震動によって居住性への 障害が生じないように検討を行う。(1級H19)6 地震時においては、応答加速度が上層ほど大きくなることを考慮して、一般に、地震層 せん断力係数Ciを上層ほど大きくする。(1級H20) 7 高さ30m、鉄骨鉄筋コンクリート造、地上7階建ての建築物において、外壁から突出す る部分の長さ2.5mの鉄筋コンクリート造の片持ち階段について、その部分の鉛直震度 を1.0Z(地震地域係数)として、本体への接続部も含めて安全性の検討を行った。 (1級H21)8 一次設計用地震力によって生じる各階の層間変形角が1/180となったので、別途に、帳 壁、内外装材、設備等に著しい損傷の生じるおそれがないことを確認した。(1級H22)9 鉄骨造の建築物の計画において、張間方向を純ラーメン構造、桁行方向をブレース構造 とする場合、方向別に異なる耐震計算ルートを適用してよい。(1級H23,H30,R04)10 層間変形角の確認において、構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著し い損傷が生じるおそれのない場合には、層間変形角の制限値を1/120まで緩和できる。 (1級H23)11 梁及びスラブの各部分の応力度を検討することにより、構造部材のたわみや震動による 使用上の支障が起こらないことを確認した。(1級H26)12 屋根ふき材において、一つの屋根構面内の中央に位置する部位より縁に位置する部位の 方が、風による吹き上げ力が大きいものとして設計を行った。(1級H26)13 地震力を算定する場合に用いる鉄骨構造の建築物の設計用一次固有周期(単位 秒)は、 建築物の高さ(単位 m)に0.03を乗じて算出することができる。(1級H27)14 平面形状が長方形の鉄骨構造の建築物において、短辺方向を純ラーメン構造、長辺方向 をブレース構造とした場合、耐震計算ルートは両方向とも同じルートとする必要がある。 (1級H27)15 耐震計算を行う場合に用いるAiは、多数の地震応答解析結果の蓄積から、それらをまと めたものに基づき定められた、設計用層せん断力を求めるための高さ方向の分布を表す 係数である。(1級H28)16 鉄筋コンクルート造建築物の設計用一次固有周期Tを、略算法ではなく固有値解析等の 精算によって求める場合には、建築物の振動特性はコンクリートにひび割れのない初期 剛性を用い、基礎や基礎杭の変形はないものと仮定する。(1級H28,R02)17 片流れ屋根の屋根葺き材の構造設計において、風による吹き上げ力は、屋根面の中央に 位置する部位より、縁に位置する部位のほうを大きくする。(1級H30)18 補強コンクリートブロック造の塀の構造設計に用いる地震力は、地表面から突出する構 造物となる煙突に準じたものとなる。(1級R03)19 建築物の屋上から突出する水槽等の耐震設計において、転倒等に対して危険を防止する ための有効な措置が講じられている場合は、地震力を一定の範囲内で減じることができ る。(1級R03)20 高層建築物に設置する設備機器の耐震設計において、設計用水平震度は、一般に、中間 階に比べて上階の方を大きくする。(1級R03)21 一端固定状態のエスカレーターにおける固定部分の設計用地震力の算定において、設計 用鉛直標準震度は、一般に、すべての階で同じ数値とする。(1級R03)22 木質構造の採用や、ハーフPC床版利用による型枠用合板の使用量低減等、地球環境との 共生に寄与した設計が求められている。(1級R04)23 地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表す係数Aiは、一般に、建築物の上階 になるほど、また、建築物の設計用一次固有周期Tが長くなるほど、大きくなる。 (1級R04)2 許容応力度計算(ルート1)(1級)1 高さ10m、鉄筋コンクリート造、地上3階建ての建築物の場合、鉄筋コンクリート造の 柱・耐力壁の水平断面積が規定値を満足しているので、保有水平耐力の算出を行わなか った。(1級H18)2 延べ面積100㎡、高さ5m、鉄筋コンクリート造、平家建ての建築物の場合、仕様規定を すべて満足しているので、保有水平耐力の算出を行わなかった。(1級H18)3 高さ13mかつ軒の高さ9mの2階建て、延べ面積500㎡の鉄骨造の建築物において、偏心 率が0.18となったが、梁スパン長さが6m以下であったので、標準せん断力係数C₀を0.3 として許容応力度計算を行った。(1級H22)4 耐震計算において、高さ10m、鉄筋コンクリート造、地上3階建ての建築物の場合、鉄 筋コンクリート造の柱・耐力壁の水平断面積が所定の値を満足していれば、保有水平耐 力の算出は行わなくてもよい。(1級H23)3-1 許容応力度等計算(ルート2)(2級)1 建築物の地上部分について、高さ方向の剛性分布のバランスの検討において、各階の剛 性率が、6/10以上であることを確認した。(2級H17)2 建築物の地上部分について、平面的な剛性分布のバランスの検討において、各階の偏心 率が、15/100以下であることを確認した。(2級H17)3 偏心率は、建築物の各階平面内の各方向別に、重心と剛心の偏りのねじり抵抗に対する 割合として求める。(2級H21)4 剛性率は、各階の層間変形角の逆数を建築物全体の層間変形角の逆数の平均値で除した 値であり、その値が小さいほど、その階に損傷が集中する危険度が高いことを示してい る。(2級H25)5 偏心率は、各階の重心と剛心との距離(偏心距離)を当該階の弾力半径で除した値であ り、その値が大きいほど、その階において特定の部材に損傷が集中する危険性が高いこ とを示している。(2級H25,H27,R04)6 建築物の偏心率は、計算しようとする方向について、各階の偏心距離を当該階の弾力半 径で除した値である。(2級H26,H29)7 建築物の剛性率は、計算しようとする方向について、各階の層間変形角を建築物全体の 層間変形角の平均値で除した値である。(2級H26,H29)8 地震時に建築物のねじれが生じないようにするため、建築物の重心と剛心との距離がで きるだけ小さくなるように計画する。(2級H30)9 建築物の各階の偏心率は、「各階の重心と剛心との距離(偏心距離)」を「当該階の弾 力半径」で除した値であり、その値が大きいほど、その階に損傷が集中する危険性が高 い。(2級R01)10 建築物の各階の剛性率は、「各階における層間変形角の逆数」を「全ての階の層間変形 角の逆数の平均」で除した値であり、その値が大きいほど、その階に損傷が集中する危 険度が高い。(2級R01)11 建築物の各階における重心と剛心の距離ができるだけ大きくなるように、耐力壁を配置 した。(2級R03)12 建築物の各階の剛性率は、「各階の層間変形角の逆数」を「全ての階の層間変形角の逆 数の相加平均の値」で除した値である。(2級R03)3-2 許容応力度等計算(ルート2)(1級)1 高さ40m、鉄骨鉄筋コンクリート造、地上10階建ての建築物の場合、剛性率及び偏心率 が規定値を満たしているので、保有水平耐力計算によらず、許容応力度等計算を行った。 (1級H18)2 高さ20m、鉄骨造、地上5階建ての建築物の場合、層間変形角が1/200以下であることの 確認及び保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることの確認をおこなった。 (1級H18)3 高さ25mの鉄骨鉄筋コンクリート造、地上6階建ての建築物の構造計算において、塔状 比が4.9であり、剛性率及び偏心率の規定値を満足していたので、許容応力度等計算によ り安全性の確認を行った。(1級H21)4 高さ30m、鉄骨鉄筋コンクリート造、地上7階建ての建築物において、3階の耐力壁の量 が4階に比べて少ない計画とする必要があったので、3階の耐力壁が取りつかない単独柱 については、曲げ降伏先行となるようにせん断耐力を高めた。(1級H21)5 各階で重心と剛心が一致しているが、剛性率が0.6未満の階があると、地震時にねじれ振 動を起こし損傷を受けやすい。(1級H23)6 地上5階建ての鉄骨造の建築物において、保有水平耐力を算定しなかったので、地震力の 75%を筋かいが負担している階では、その階の設計地震力による応力の値を1.5倍して各 部材の断面を設計した。(1級H27)4-1 保有水平耐力計算(ルート3)(2級)1 大地震に対して、十分な耐力を有していることを確かめるために、建築物の地上部分に ついて、保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることを確認した。(2級H17)2 ピロティ階の必要保有水平耐力は、「剛性率による割増係数」と「ピロティ階の強度割 増係数」のうち、大きいほうの値を用いて算出した。(2級H20,H24,H28,R03)4-2 保有水平耐力計算(ルート3)(1級)1 建築物の保有水平耐力を算定する場合、炭素鋼の構造用鋼材のうち、日本産業規格 (JIS)に定めるものについては、材料強度の基準強度を1.1倍まで割増することがで きる。(1級H15,H27)2 構造特性係数DSは、架構が靭性に富むほど小さくなり、減衰が大きい程小さくなる。 (1級H16)3 鉄筋コンクリート構造の建築物において、保有水平耐力を大きくするために耐力壁を多 く配置すると、必要保有水平耐力も大きくなる場合がある。(1級H17)4 鉄骨造の純ラーメン構造の耐震設計において、必要とされる構造特性係数Dsは0.25で あったが、0.3として保有水平耐力の検討を行った。(1級H18,H23)5 構造特性係数Dsが0.3の建築物において、保有水平耐力が必要保有水平耐力の1.05倍と なるように設計した場合、大地震の際に大破・倒壊はしないが、ある程度の損傷は受け ることを許容している。(1級H19)6 各階の保有水平耐力の計算による安全確認において、一般に、偏心率が一定の限度を 超える場合や、剛性率が一定の限度を下回る場合には、必要保有水平耐力を大きくす る。(1級H19,H25)7 鉄骨造の建築物の必要保有水平耐力の検討に当たって、ある階の保有水平耐力に占める 割合が50%となる筋かいを配置する場合は、筋かいのない純ラーメンの場合に比べて、 構造特性係数Dsを小さくすることができる。(1級H19,H25)8 剛接架構と耐力壁を併用した鉄筋コンクリート造の場合、柱及び梁並びに耐力壁の部材 群としての種別が同じであれば、耐力壁の水平耐力の和の保有水平耐力に対する比βuに ついては、0.2である場合よりも0.7である場合のほうが、構造特性係数Dsを小さくする ことができる。(1級H20)9 地上6階建ての建築物(1階が鉄骨鉄筋コンクリート造、2階以上が鉄骨造)の構造計算 において、2階以上の部分の必要保有水平耐力を、鉄骨造の構造特性係数Dsを用いて計 算した。(1級H21)10 高さ31mの鉄筋コンクリート造の建築物において、偏心率が規定値を超えたので、保有 水平耐力の確認を行った。(1級H22)12 構造特性係数Dsは、一般に、架構が靭性に富むほど大きくすることができる。 (1級H24,R04)13 Qunは、各階の変形能力を大きくし、建築物の一次固有周期を長くすると大きくなる。 (1級H26)14 Quは、建築物の一部又は全体が地震力の作用によって崩壊機構を形成する場合の各階の 柱、耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和である。(1級H26)15 Quの算出において、鉄筋コンクリート構造のスラブ付き梁については、スラブの鉄筋に よる効果を考慮して、終局曲げモーメントを計算する。(1級H26)16 Quの算出において、鉄筋コンクリート構造の梁の曲げ強度を算定する場合、主筋にJIS 規格のSD345を用いれば、材料強度を基準強度の1.1倍とすることができる。 (1級H26)17 鉄骨造の純ラーメン構造の耐震設計において、ある階の必要とされる構造特性係数Dsは 0.25であったが、他の階で構造特性係数Dsが0.3となる階があったので、全体の構造特 性係数Dsを0.3として保有水平耐力の検討を行った。(1級H26)18 「曲げ降伏型の柱・梁部材」と「せん断破壊型の耐震壁」により構成される鉄筋コンク リート構造の建築物の保有水平耐力は、一般に、それぞれの終局強度から求められる水 平せん断力の和とすることができる。(1級H15,H27)19 各階の保有水平耐力計算において、偏心率が所定の数値を上回る場合又は剛性率が所定 の数値を下回る場合には、必要保有水平耐力の値を割り増す。(1級H28)20 鉄筋コンクリート造建築物の必要保有水平耐力の計算において、一般に、柱・梁部材に 曲げ破壊が生じる場合は、せん断破壊が生じる場合に比べて、構造特性係数Dsを大きく しなければならない。(1級H28)21 鉄筋コンクリート造において、部材のせん断耐力を計算する場合のせん断補強筋の材料 強度は、JIS規格品の鉄筋であっても、せん断破壊に対する余裕度を確保するために基 準強度の割増しはしない。(1級H30)22 保有水平耐力は、建築物の一部又は全体が地震力の作用によって崩壊機構を形成すると きの、各階の柱、耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和としてもよい。 (1級H30)23 各階の保有水平耐力の計算による安全性の確認において、ある階の偏心率が所定の数値 を上回る場合、全ての階について必要保有水平耐力の割増をしなければならない。 (1級H30)24 構造特性係数Dsは、一般に、架構が靭性に富むほど小さくすることができる。 (1級R01)25 構造特性係数Dsは、一般に、架構の減衰が小さいほど小さくすることができる。 (1級R02)26 各階の保有水平耐力計算において、剛性率が0.6を下回る場合、又は、偏心率が0.15を 上回る場合には、必要保有水平耐力の値を割増する。(1級R02)27 保有水平耐力計算における必要保有水平耐力の算定では、形状特性を表す係数Fesは、 各階の剛性率及び偏心率のうち、それぞれの最大値を用いて、全階共通の一つの値と して算出する。(1級R04)**************************************************************** 解説□ 構造計算の概要 1. 一次設計・二次設計について① 構造計算が必要な建物規模は、法20条1項にて規定されている。② 一次設計:常時及び稀に作用する荷重に対しての検討(許容応力度による安全性の検討、 たわみによる使用上の検討、屋ねふき材等の検討)、建築物の損傷による性能低下をさ せないことを確認 二次設計:極めて稀に作用する荷重に対しての検討し建築物が、崩壊や倒壊をしないこと を確認する③ 一次設計で行う安全性の検討は、応力度により強度の検討を行い、使用上の検討は、剛性 によりたわみの検討を行う。④ 使用上の検討では、床構造の鉛直方向の固有振動数が10Hzを下回る(振動がゆっくりに なる)と、居住性に障害がでる。震動障害を防ぐには、床の曲げ剛性(EI)を高める。 ⑤ 耐震計算ルート2,3を適用する場合は、標準せん断力係数C₀を0.2以上とした地震力によ り生ずる層間変形角(水平方向の層間変位をその階の高さで除した値)を1/200以内とし なければならない。ただし、帳壁、内外装材、設備等に著しい損傷が生じるおそれの無い ことを確認すれば、1/120まで緩和することができる。 ⑥ 一つの建物で、はり間方向、けた行の方向別に異なった耐震計算ルートを適用してよいが、 階ごとに異なるルートを適用してはならない。 1-1 一次設計・二次設計について(2級)1 〇 建築物の外壁から突出する部分の長さが2mを超える片持ちバルコニー等を設ける 場合は、鉛直震度1.0Z以上の鉛直力を考慮して地震力に対して安全性を確かめな ければならない。(平19年国交省告示第594号) 正しい2 〇 耐震設計の目標は、稀に生じる程度の地震(存在期間中に1回以上は遭遇する可能 性のある地震、中程度の地震)に対しては損傷が生じないように、極めて稀に生じ る程度の地震(数百年に一度程度起こる地震、最大級の地震)に対しては倒壊・崩 壊を防ぐことである。 正しい3 〇 建築物の耐震設計は、一次と二次の2段階の安全確認を行う。一次は、稀に生じる 地震に対して損傷しないこと。二次設計は、極めて稀にみる地震に対して崩壊・倒 壊しないことを確かめる。 正しい4 〇 建築物の耐震設計の一次設計では、稀に生じる地震に対して損傷による性能低下を 生じさせないことを確かめる。 正しい5 〇 建築物の耐震設計の一次設計では、稀に生じる地震に対して損傷による性能低下を 生じさせないことを目標にしている。 正しい6 〇 建築物の耐震設計の二次設計では、極めて稀に生じる地震に対して倒壊・崩壊をさ せないことを目標とし、塑性化は許容している。建物が損傷することはやむお得な いが、倒壊はさせず人命等を守る考え方。 正しい7 〇 一次設計用地震力(C₀=0.2)によって生ずる各階の層間変形角は1/200以内としな ければならない。ただし、帳壁、内外装材、設備等に著しい損傷の生じるおそれが ない場合は、1/120以内まで緩和することができる。 (建基基準法施行令第82条の2) 正しい8 〇 一次設計用地震力(C₀=0.2)によって生ずる各階の層間変形角は1/200以内としな ければならない。ただし、帳壁、内外装材、設備等に著しい損傷の生じるおそれが ない場合は、1/120以内まで緩和することができる。 (建基基準法施行令第82条の2) 正しい9 〇 稀に発生する地震には建築物が損傷しないように検討する(一次設計)が、極めて 稀に発生する地震においては建築物が崩壊や倒壊しないことを確かめる(二次設計) 正しい10 〇 極めて稀に発生する地震においては建築物が崩壊や倒壊しないことを確かめるのが 二次設計の耐震目標である 正しい1-2 一次設計・二次設計について(1級)1 〇 設計用一次固有周期は、略算でもとめる場合 T=h(0.02+0.01α)となり、高さ hが高いものほど長くなる。 正しい2 × 許容応力度を検討する場合(一次設計)の地震力を計算する場合の Ci=Z・Rt・Ai・C₀に使うZと、必要保有水平耐力(二次設計)を算出する場合の Qud=Z・Rt・Ai・C₀・Wiを計算する場合のZは同じ数値を用いる。 誤り3 〇 高さ4mを超える広告塔、8mを超える高架水槽等の工作物は、水平震度k≧0.5Z として、地震力(P=k・w)を算定する。 正しい4 × たわみ(使用上の検討)は、剛性(EI)で検討し、強度(安全上の検討)は応力 度で検討する。 誤り5 〇 床構造の鉛直方向の固有振動数が10Hzを下回る(振動がゆっくりとなる)と震動障 害が生じる。そのために、一次設計において、たわみの検討を行う。 正しい6 〇 Ci=Z・Rt・Ai・C₀により、Aiの効果によりCiは上層ほど大きくなる。 正しい7 〇 建築物の外壁から突出する部分の長さが2mを超える片持ちバルコニー等を設ける場 合は、鉛直震度1.0Z以上の鉛直力を考慮して地震力に対して安全性を確かめなけれ ばならない。(平19年国交省告示第594号) 正しい8 〇 一次設計用地震力によって生ずる各階の層間変形角は1/200以内としなければならな いが、帳壁、内外装材、設備等に著しい損傷の生じるおそれがない場合は、1/120以 内まで緩和することができる(建基基準法施行令第82条の2) 正しい9 〇 方向別に異なる耐震ルートを適用してもよいが、階によって異なってはならない。 正しい10 〇 一次設計用地震力によって生ずる各階の層間変形角は1/200以内としなければならな いが、帳壁、内外装材、設備等に著しい損傷の生じるおそれがない場合は、1/120以 内まで緩和することができる(建基基準法施行令第82条の2) 正しい11 × たわみ(使用上の検討)は、剛性(EI)で検討し、強度(安全上の検討)は応力度 で検討する。 誤り12 〇 屋根ふき材や外装材に用いる風圧力は、平均速度圧×ピーク風力係数で求める。ピー ク風力係数は、屋根面の周辺やコーナー部分の壁で大きくなるので、風による吹き 上げ力は、屋根平面内の中央部より縁の方が大きくなる。 (平成12年建設省告示第1458号) 正しい13 〇 設計用一次固有周期は、略算でもとめる場合 T=h(0.02+0.01α)となる。鉄骨 造の場合はα=1となり、T=0.03hとなる。 正しい14 × 方向別に異なる耐震ルートを適用してもよいが、階によって異なってはならない。 誤り15 〇 Aiは、建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の高さ方向の分布を表す係数 であり、設計用一次固有周期Tと高さ方向の建築物重量の分布の影響を受ける。 (建築基準法施行令第88条) 正しい16 〇 設計用一次固有周期を精算で求める場合は、初期剛性(ひび割れによる初期剛性の 低下が生じる前の剛性)を用いる。また、基礎及び基礎杭の変形を考慮してはなら ない。(建築物の構造関係技術基準解説書) 正しい17 〇 屋根ふき材や外装材に用いる風圧力は、平均速度圧×ピーク風力係数で求める。ピー ク風力係数は、屋根面の周辺やコーナー部分の壁で大きくなるので、風による吹き 上げ力は、屋根平面内の中央部より縁の方が大きくなる。 (平成12年建設省告示第1458号) 正しい18 〇 補強コンクリートブロック造の構造計算に用いる地震力(せん断力=Csi×W、 Csi:高さ方向の分布係数 W:固定荷重と積載荷重の和)は、煙突等のせん断力 (せん断力=Csi×W)と同じ。(平成12年建設省告示第1355号、第1449号) 正しい19 〇 建築物の屋上から突出する水槽等は、転倒、移動等による危害を防止するための 有効な措置が講じられている場合は、地震力を1/2を超えない範囲で低減すること ができる。(平成12年建設省告示第1389号) 正しい20 〇 建築物は建築物は上層ほど振動により加速度が大きくなるため、設計用水平震度の 中間階より上階の方が大きくなる。(平成12年建設省告示第1388号) 正しい21 × 建築物は上層ほど振動により加速度が大きくなるため、設計用鉛直標準震度は1階 (0.2)より上層階(1.0)の方が大きくなる。 (平成25年国土交通省告示第1046号) 誤り22 〇 カーボンニュートラルの観点からの木質構造の採用や廃棄物の削減など、サスティ ナブルな社会形成のためにも設計の段階から環境共生を考慮した設計が求められて いる。 正しい23 〇 Aiは、建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の高さ方向の分布を表す係数 であり、建築物の上階ほど、また、設計用一次固有周期Tが長くなるほど大きくな る。 正しい2 許容応力度計算(ルート1)① 二次設計における耐震計算ルート1~3の区別は、建築基準法第20条1項による建物区分によ り、施行令第81条による構造計算により分かれている。② ルート-1(許容応力度計算) 木造(3階建以上、500㎡超、高さ13m軒高9m以下) 木造以外(2階建以上、200㎡超でルート2より小さい規模)) (法20条1項三号、令81条3項) ③ ルート-2(許容応力度等計算) 木造(高さ13m超、軒高9m超、500㎡超) RC造(高さ20m超) S造(4階建以上、高さ13m超、軒高9m超) (法20条1項二号、令81条2項二号) ④ ルート-3(保有水平耐力計算):高さ31m超(法20条1項二号、令81条2項一号) ⑤ S造は、規模によりルート1-1とルート1-2に分かれる。2 許容応力度計算(ルート1)(1級)1 〇 RC造で高さ20m以下の建築物(柱・耐力壁の水平断面積規定値以上)は、ルート1 の規模に該当するので、保有水平耐力計算(ルート3)は行わなくてもよい。正しい 2 〇 RC造で高さ20m以下の建築物(柱・耐力壁の水平断面積規定値以上)は、ルート1 の規模に該当するので、保有水平耐力計算(ルート3)は行わなくてもよい。 正しい3 〇 S造の3階以下、高さ13m以下、軒高9m以下、スパン6m以下、500㎡以下の建築物 は、ルート1-1の規模に該当するため、偏心率の規定は関係ない。C₀=0.3として許 容応力度計算(ルート1)を行うことができる。 正しい4 〇 RC造で高さ20m以下の建築物(柱・耐力壁の水平断面積規定値以上)は、ルート1 の規模に該当するので、保有水平耐力計算(ルート3)は行わなくてもよい。正しい3 許容応力度等計算(ルート2)① 剛性率(各階の層間変形角の逆数/建築物全体の層間変形角の逆数の相加平均):0.6 (6/10)以上 各階の水平変形のしにくさの検討、剛性率の小さい階に変形や損傷が 集中する② 偏心率(偏心距離/弾力半径):0.15(15/100)以下 偏心率が大きい(剛心と重心 の距離が離れている)とねじれ振動を起こし、損傷が生じやすくなる③ 塔状比(高さ/幅):4以下 建築物の転倒の検討 ④ 剛性率、偏心率、塔状比が規定値から外れた場合は、ルート3以上の上位計算を行う ⑤ S造の耐震計算ルート2においては、筋かいの水平力分担率(β)に応じて、地震時水平 力の割増を行う。 Β>5/7(≒71%)の場合、割増倍率は1.5とする3-1 許容応力度等計算(ルート2)(2級)1 〇 剛性率(各階の層間変形角の逆数/建物全体の層間変形角の逆数の相加平均)は、 0.6(6/10)以上としなければならない。 正しい2 〇 平面的な剛性のバランス(偏心率)は、15/100以下とする。 正しい3 〇 偏心率は、重心と剛心の偏りを表し、15/100以下とする。 正しい4 〇 剛性率(各階の層間変形角の逆数/建物全体の層間変形角の逆数の相加平均)は、 0.6(6/10)以上としなければならない。 正しい5 〇 偏心率は、偏心距離を弾力半径で除して求める。0.15(15/100)以下とし、偏心 率が大きい(剛心と重心の距離が離れている)とねじれ振動が生じ損傷が生じやす くなる。 正しい6 〇 偏心率は、偏心距離を弾力半径で除して求める。0.15(15/101)以下とし、偏心 率が大きい(剛心と重心の距離が離れている)とねじれ振動が生じ損傷が生じやす くなる。 正しい7 × 剛性率は、各階の層間変形角の逆数を建築物全体の層間変形角の逆数の平均で除し た値である。 誤り8 〇 ねじれが生じないように、偏心率を小さく(剛心と重心の距離を短く)する。 正しい9 〇 偏心率は、偏心距離を弾力半径で除して求める。0.15(15/101)以下とし、偏心 率が大きい(剛心と重心の距離が離れている)とねじれ振動が生じ損傷が生じやす くなる。 正しい10 × 剛性率(各階の層間変形角の逆数/建物全体の層間変形角の逆数の相加平均)は、 0.6(6/10)以上としなければならない。小さいほど損傷の危険性が高い。誤り11 × 重心と偏心の距離はできるだけ小さくなるように耐力壁を配置すると、ねじれ損 傷が生じにくくなる。 誤り12 〇 剛性率は、各階の層間変形角の逆数を建物全体の層間変形角の逆数の相加平均で除 した値であり、0.6(6/10)以上としなければならない。 正しい3-2 許容応力度等計算(ルート2)(1級)1 × 高さ31m超の建物は、ルート3(保有水平耐力計算)又は限界耐力計算、時刻歴応 答解析を行わなければならない。許容応力度等計算(ルート2)を行う事は出来な い。 誤り2 〇 高さ20m、5階建のS造は、ルート2の規模だが、ルート3(保有水平耐力計算)を 行うことは問題ない。 正しい3 × 高さ25m、6階建のSRC造は、ルート2の規模だが、塔状比が規定値(4以下)を外 れた場合は、ルート3等の上位計を行わなければならない。許容応力度等計算(ルー ト2)を行う事は出来ない。 誤り4 〇 高さ30m、7階建のSRC造は、ルート2の規模なので、耐力壁が足りなく剛性率が 下がる場合は、柱がせん断破壊しないように、せん断補強筋量や断面を大きくする などしてせん断力を高め、曲げ降伏先行型となるように靭性を高める。 正しい5 × ねじれ変形は、偏心率が多きいときにおこる現象であり、重心と剛心が一致してい るときには起こらない。剛性率が0.6未満の場合は、特定の層にせん断力が集中し 層せん断等の損傷が生じる 誤り6 〇 S造ルート2でのβ割増しは、β>5/7(≒71%)の場合、水平力を1.5倍して計算を 行う。 正しい4 保有水平耐力計算(ルート3)① 保有水平耐力Qu(建物の支える力) ≧ 必要保有水平耐力Qun(大地震時の建物に係る 力)を確認する② 保有水耐力の確認は、各階、各方向(X,Y方向)ごとに行う。DsやFesの数値も各階、各 方向ごとに決まる。③ 保有水平耐力Qu:建築物の一部又は全体が地震力によって崩壊メカニズムを形成すると き、各階の柱、耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和④ 必要保有水平耐力Qun=Ds×Fes×Qud Ds:構造特性係数(構造に応じた減衰性及び靭性を考慮した低減係数) (S造0.25~0.5以上 RC造0.3~0.55以上) Fes:形状係数(剛性率、偏心率に応た割増係数1.0~3.0) Qud=Z×Rt×Ai×C₀×Wi(C0=1.0以上)⑤ 構造特性係数Dsは、架構が靭性に富むほど、また、減衰が大きいほど、地震エネルギーの 吸収が大きくなるので、小さくなる。⑥ 形状係数Fesは、偏心率が一定の限度を超える場合や、剛性率が一定の限度を下回る場合 には大きくなる⑦ 同じ規模の鉄骨造で、筋かいがある場合とない場合では、ある場合のほうが靭性や変形能 力が小さくなり、Dsは大きくなる⑧ 同じ規模の鉄筋コンクリート造の建築物で、耐力壁が負担する水平力が大きい(水平力分 担率βuが大きい)ほど、Dsは大きくなる⑨ 保有水平耐力の算定において、鋼材にJIS規格品を使用する場合は、材料強度の基準強度 を1.1倍以下の範囲で割増することができる。ただし、せん断終局強度を計算する場合に は、割増はできない。4-1 保有水平耐力計算(ルート3)(2級)1 〇 ルート3では、保有水平耐力≧必要保有水平耐力を確認する。 正しい2 〇 ピロティ階は壁が少なく剛性が低くなるので、必要保有水平耐力を算出する場合に 割増をする。割増係数が大きい法が安全側の検討となる。 正しい4-2 保有水平耐力計算(ルート3)(1級)1 〇 鋼材をJIS規格品とする場合は、基準強度を1.1倍まで割増することができる。 正しい2 〇 構造特性係数Dsは、架構が靭性に富むほど、また、減衰が大きいほど地震エネルギ ーの吸収が大きくなるので小さくなる。 正しい3 〇 耐力壁を多く配置すると、保有水平耐力は大きくなるが、Dsも大きくなるため必要 保有水平耐力も大きくなる場合がある。 正しい4 〇 Dsを大きくすることは、必要保有水平耐力が大きくなり安全側の設計となる。 正しい5 〇 保有水平耐力計算は、塑性変形を許容した計算であり、Dsが0.3であれば靭性指向 の設計である。保有水平耐力が必要保有水平耐力の1.05倍では、特に大きな余裕を 見込んだ設計ではないので、塑性ヒンジの発生を想定したものといえる。正しい6 〇 偏心率や剛性率が規定値を外れた場合は、Fesを大きくして調整する。Fesが大きく なれば、必要保有水平耐力は大きくなる。 正しい7 × 鉄骨造の場合、筋かいの占める割合が大きいほど全体として靭性が低下しDsが大き くなる。筋かい50%の場合と0の場合では50%のほうがDsは大きくなる。 誤り8 × 耐力壁の水平力分担率(βu)が大きいほど、靭性や変形能は小さくなり、Dsは大き くなる。 誤り9 〇 Dsは各階ごとに各方向別(X,Y方向別)に算出するので、2階以上の部分は鉄骨造の Dsを用いる。 正しい10 〇 高さ31mの鉄筋コンクリート造は、耐震設計ルート2で良いが、偏心率、剛性率、 塔状比が規定値を外れた場合はルート3(保有水平耐力計算)にて確認をしなけれ ばならない。 正しい12 × 構造特性係数Dsは、架構が靭性に富むほど、また、減衰が大きいほど地震エネルギ ーの吸収が大きくなるので小さくなる。 誤り13 × 各階の変形能力を大きくすると、Dsが小さくなるのでQudは小さくなる。尚、一次 固有周期を長くするとRtは小さくなるがAiは大きくなる。 誤り14 〇 保有水平耐力Quは、建築物の一部又は全体が地震力によって崩壊メカニズムを形成 するときの、各階の柱、耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和となる。 正しい15 〇 鉄筋コンクリート構造のスラブ付き梁は、スラブ鉄筋による効果(梁側面から1m 程度の範囲内のスラブ筋)を考慮して終局曲げモーメントを計算する。 正しい16 〇 保有水平耐力の算定において、鋼材にJIS規格品を使用する場合は、材料強度の基準 強度を1.1倍以下の範囲で割増することができる。ただし、せん断終局強度を計算す る場合には、割増はできない。 正しい17 〇 Dsを大きくすることは、必要保有水平耐力が大きくなり安全側の設計となる。 正しい18 × ラーメンと耐力壁では、変形性能が大きく異なるため、両方が混在している建築物 では、ラーメンと耐力壁の終局せん断力の和を保有水平耐力とすることができない。 (建築物の構造関係技術基準解説書) 誤り19 〇 偏心率や剛性率が規定値を外れた場合は、Fesを大きくして調整する。Fesが大きく なれば、必要保有水平耐力は大きくなる。 正しい20 × 曲げ破壊は、せん断破壊より靭性が高い破壊形式なので、構造特性係数Dsは小さく なる。 誤り21 〇 保有水平耐力の算定において、鋼材にJIS規格品を使用する場合は、材料強度の基準 強度を1.1倍以下の範囲で割増することができるが、せん断終局強度を計算する場合 には、せん断は階に対する余裕度を確保するために割増はできない。 正しい22 〇 保有水平耐力Quは、建築物の一部又は全体が地震力によって崩壊メカニズムを形成 するときの、各階の柱、耐力壁及び筋かいが負担する水平せん断力の和となる。 正しい23 × 保有水平耐力の計算は、各階ごとに確認を行うので、ある階が偏心率の規定を外した 場合はその階のみFesによる割増を行う。すべての階を割増する必要はない。 誤り24 〇 構造特性係数Dsは、架構が靭性に富むほど、また、減衰が大きいほど地震エネルギ ーの吸収が大きくなるので小さくなる。 正しい25 × 構造特性係数Dsは、架構が靭性に富むほど、また、減衰が大きいほど地震エネルギ ーの吸収が大きくなるので小さくなる。 誤り26 〇 偏心率や剛性率が規定値を外れた場合は、Fesを大きくして調整する。Fesが大きく なれば、必要保有水平耐力は大きくなる。 正しい27 × 保有水平耐力の計算は、各階ごとに確認を行う。DsやFesは各階毎の数値で、各階 の最大値を用いて全階共通の一つの値ではない。 誤り今回は構造計算の概要をルート3まで紹介しました。この内容は、荷重外力の分野や法規の問題とも重なっています。関連をもって学習して頂けるとより理解できると思います。1級では、保有水平耐力計算の内容(特にDsに関して)は、RC造やS造の中でも出てきますのでしっかり理解が必要です! 次回は、構造計算の概要の続きと構造計画一般を紹介する予定です。今日はこんな言葉です! 『成功するか否かは、その人の「能力」よりも「情熱」による。為すべき仕事に身も心も捧げる人間が勝利者となるのだ。 』(チャールズ・バクストン)
Aug 29, 2022
閲覧総数 2874
-
13
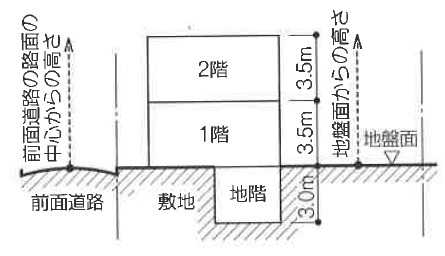
建築士の勉強!!(法規編第13回)
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 2.面積高さの算定 面積高さの算定の問題は、1級では文章問題、2級では具体的な計算問題で出題されます。 過去問で一番多く出題されているのが、塔屋等が高さに算入されるかどうかを問う問題です。 高さは、何処から測るのか、何処まで測るのかを覚えましょう!! 2-1 令2条1項六号(建築物の高さ) 問題 1.避雷設備の設置の必要性を検討するにあたっての建築物の高さの算定について、建築物の屋上 部分である階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/10の場合において は、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。(1級H15) 2.建築物の高さの算定は、地盤面からの高さによらない場合がある。(1級H16) 3.建築物の屋上部分(階段室の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面 積の1/8であり、かつ、その部分の高さが4mである場合であっても、当該建築物の高さに算入 する場合がある。(1級H16、H26) 4.避雷設備の設置を検討する際、建築物の屋上部分にある階段室、昇降機塔等の高さは、当該建 築物の高さに算 入する。(1級H18) 5.北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に おいて定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、 その水平投影面積の合計が当該 建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の 高さは当該建築物の高さに算入する。(1級H18、H25) 6.前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後 退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、地盤面からの高さ による。 (1級H18、H22) 7.道路高さ制限において、建築物の屋上部分に設ける高さ5mの高架水槽の水平投影面積の合計 が、当該建築物 の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高 さに算入しない。(1級H19) 8.避雷設備の設置の必要性を検討するにあたっての建築物の高さの算定について、建築物の屋上 部分である階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/10の場合におい ては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算に入する。(1級H20) 9.前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の 後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路の路 面の中心からの高さによる。(1級H20) 10.「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の 合計が当該建築物の 建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物 の高さに算入しない。(1級H21、H30) 11.第二種低層住宅専用地域内における建築物の高さの限度の規定において、階段室及び昇降機 塔のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合に おいては、その部分の高さは、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。(1級H23) 12.避雷設備の設置の必要性を検討するにあたっての建築物の高さの算定について、建築物の屋 上部分である階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合 においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。(1級H23) 13.前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限において、当該建築物の後退距 離の算定の特例を受ける場合の「軒の高さ」の算定については、前面道路の路面の中心から の高さとする。(1級H28) 14.避雷設備の設置の必要性を検討するにあたっての建築物の高さの算定について、建築物の屋 上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合 であっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算に入する。(1級H29) 15.北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に 関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分 にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについ ては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。(1級R01) 16.前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の 特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路と敷地との高低差にか かわらず、地盤面からの高さによる。(1級R01) ********************************************************************** 解説 2-1 令2条1項六号(建築物の高さ) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 建築物の高さについては、何処から測るのか、何処まで測るのかが、道路斜線、隣地斜線、北側斜線等によって異なるのでまずそこをしっかり覚えましょう! 1.何処から測るのか? ① 道路斜線(法56条1項一号)、前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制 限において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合(130条の12)は、前面道 路の路面の中心からの高さとする。 ② 隣地斜線、北側斜線については、地盤面からの高さとする。 2.何処まで測るのか?(塔屋等の水平投影面積が建築面積の1/8以内の場合の緩和の規定) ① 塔屋等の緩和が無い(避雷設備(法33条)、北側斜線(法56条1項三号)、特例容積率適 用地区内の建築物の高さ(法57条の4 1項)、高度地区内の建築物の高さ(法58条)、 特定用途誘導地区内の建築物の高さ(法60条の3 2項)): 塔屋等の頂部まで高さに 算入される。 ② 5mまで緩和される(第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さ(法55条1項・2 項)、日影規制(法56条の2 )):塔屋等は頂部から5mまでは高さに算入されない。 ③ 12mまで緩和される(①、②以外、道路斜線や隣地斜線等):塔屋等は頂部から12mまで は高 さに算入されない。 ④ 塔屋等の水平投影面積の合計が建築面積の1/8超の場合は、緩和が受けられないのですべ て高さに算入される。 1. × 避雷設備の設置上の高さは、塔屋等の緩和は無い。すべて算入される。 2. 〇 道路斜線は、前面道路の路面の中心からの高さによる。 3. 〇 避雷設備や北側斜線では緩和が無いのですべて高さに算入される。 4. 〇 避雷設備は緩和が無いのですべて高さに算入される。 5. 〇 この問題は、北側斜線のことを言っているので、塔屋等の緩和が無くすべて算入さ れる。 6. × 道路斜線における後退距離の算定の特例を受ける場合は、前面道路の路面の中心か らの高さによる。 7. 〇 道路斜線においては、塔屋等は12mまでは高さに算入しない。 8. 〇 避雷設備は緩和が無いのですべて高さに算入される。 9. 〇 道路斜線における後退距離の算定の特例を受ける場合は、前面道路の路面の中心か らの高さによる。 10. × 北側斜線は緩和が無いのですべて高さに算入される。 11. 〇 法55条の絶対高さは5mまでは高さに算入されない。 12. × 避雷設備は緩和が無いのですべて高さに算入される。 13. 〇 道路斜線における後退距離の算定の特例を受ける場合は、前面道路の路面の中心か らの 高さによる。 14. 〇 避雷設備は緩和が無いのですべて高さに算入される。 15. 〇 北側斜線は緩和が無いのですべて高さに算入される。 16. 〇 道路斜線における後退距離の算定の特例を受ける場合は、前面道路の路面の中心か らの高さによる。 建築物の高さ、何処から測るのか?、何処まで測るのか? 覚えてくださいね!! 今日はこんな言葉です! 『自分がこれだって決めたことは最後まで諦めずにやり切る。 練習でできないことは本番でも絶対にできないから。』 (澤 穂希) 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Jan 3, 2021
閲覧総数 2935
-
14

建築士の勉強!!(法規編第17回)
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ 解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 2.面積高さ等の算定 面積高さの算定の問題は、1級では文章問題、2級では具体的な計算問題で出題されます。 今回は、今までの文章問題を踏まえて計算問題を見てみましょう! 2-5 令2条1項 一号(敷地面積)、二号(建築面積)、四号(延べ面積) 六号(高さ)、八号(階数) 実際の問題は、いずれも択一式で選択肢の中から誤っているものを選ぶ問題ですが、あえて 一つ一つ考えてみましょう! 1.図のような建築物の①敷地面積、②建築面積、③延べ面積を求めよ。(2級H18) 2.図のような建築物の①敷地面積、②建築面積、③建築物の高さを求めよ。(2級H20) 3.図のような建築物の①敷地面積、②建築面積、③延べ面積、④高さ、⑤階数を求めよ。 (2級H17) 4.図のような建築物の①敷地面積、②建築面積、③延べ面積、④高さ、⑤階数を求めよ。 (2級H23) 5.図のような建築物の①敷地面積、②建築面積、③延べ面積、④階数、⑤建築基準法 第56条第1項二号に規定する高さを算定する場合の高さを求めよ。(2級H24) 6.図のような建築物における①容積率算定の基礎となる延べ面積、②避雷針の設置の必要性 を検討するに当たっての建築物の高さ、③階数、④地階を除く階数を求めよ。ただし、図 以外に容積率の算定の基礎となる部分はないものとする。また、階段室の屋上屋上部分の 水平投影面積は建築面積の1/20とし、最下階の防災防災センター(中央管理室)の水平投 影面積は建築面積の1/8とする。(1級H24) ****************************************************************** 解説 2-5 令2条1項一号(敷地面積)、三号(建築面積)、四号(延べ面積) 六号(高さ)、八号(階数) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 1. ①敷地面積 法42条2項道路により道路中心より2mセットバックして (20m-1m)×23m=437㎡ ②建築面積 令2条1項二号より、地階、庇部分は算入されないので 2階の床面積 10m×9m=90㎡ ③延べ面積 令2条1項四号より、各階の床面積の合計 2階:10m×9m=90㎡ 1階:10m×7m=70㎡ 地階:10m×6m=60㎡ 90㎡+70㎡+60㎡=220㎡ 2. ①敷地面積 法42条2項道路により道路の反対側から4mセットバックして (20.5m-1.0m)×14m=273㎡ ②建築面積 令2条2項より平均地盤面を求め、地階は平均地盤面より1.5m出ているので 建築面積に算入される。よって、地階の床面積が建築面積となる。尚庇は地階の床面積 から1mを超えて突き出ていないので算入されない。 10m×10m=100㎡ ③建築物の高さ 令2条1項六号より地盤面より測るため(平均地盤面より) 1.5m+3m+3m=7.5m 3. ①敷地面積 法42条2項道路により道路中心線より2mセットバックして (35m-1m)×20m=680㎡ ②建築面積 2階の床面積が建築面積となるため 20m×13m=260㎡ ③延べ面積 令2条1項四号より、各階の床面積の合計 2階:20m×13m=260㎡ 1階:20m×12m=240㎡ 地階:6m×5m=30㎡ 260㎡+240㎡+30㎡=530㎡ ④高さ 令2条1項六号より地盤面より測るため 3.5m+3.5m=7.0m ⑤階数 令2条1項八号より地階は、倉庫・機械室等で建築面積の1/8以下の場合は算入 されない。 260/8=32.5㎡≧30㎡ 階数は2 4.①敷地面積 法42条1項四号に基づき特定行政庁が指定した部分は道路となるため敷地面 積に算入されない。 16m×25m=400㎡ ②建築面積 令2条1項二号より、2階の床面積+バルコニー先端より-1mの部分 9m×15m+1m×15m=150㎡ ③延べ面積 令2条1項四号より、各階の床面積の合計 PH:4m×4m=16㎡ 2階:9m×15m=135㎡ 1階:8m×15m=120㎡ 16㎡+135㎡+120㎡=271㎡ ④高さ 令2条1項六号より地盤面より測るため 3.5m+3.5m=7.0m ⑤階数 令2条1項八号より地階は、倉庫・機械室等で建築面積の1/8以下の場合は算入 されない。 150/8=18.75㎡≧16㎡ 階数は2 5.①敷地面積 法42条2項道路により道路中心線より2mセットバックして 20m×(15m-1m)=280㎡ ②建築面積 令2条1項二号より、2階の床面積+ひさし先端より-1mの部分 10m×8m+0.5m×8m=84㎡ ③延べ面積 令2条1項四号より、各階の床面積の合計 PH:5m×3m=15㎡ 2階:10m×8m=80㎡ 1階:9m×8m=72㎡ 15㎡+80㎡+72㎡=167㎡ ④階数 令2条1項八号より階段室、昇降機塔等は、建築面積の1/8以下の場合は算入 されない。 84/8=10.5㎡≦15㎡ 階数は3 ⑤建築基準法第56条第1項二号に規定する高さを算定する場合の高さ 隣地高さ制限は、地盤面から測る。PHは建築面積の1/8以下の場合は不算入。 84㎡×1/8=10.5≦15㎡ 高さに算入される 4m+3m+2.5m=9.5m 6.①容積率の算定の基礎となる延べ面積 図以外の容積率の算定の基礎となる部分(地階の老人ホーム等、昇降機の昇降路部分、 共同住宅等の共用の廊下等、自動車車庫等、備蓄倉庫等)はないので 40㎡+800㎡×5+100㎡=4,140㎡ ②避雷針の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さ 令2条1項六号ロにより、地盤面(平均地盤面)より測り、法33条は階段室部分の緩和は ないので階段室の頂部まで高さに算入される 1.5m+3m×4+1.5m+3m=18m ③階数 令2条1項八号より階段室、昇降機塔等は、建築面積の1/8以下の場合は算入 されない。 地階は、防災センターなので階数に算入される。 階数は6 ④地階を除く階数 平均地盤面より上階の床面までが1.5mなので 地下の階数は2 地階を除く階数は4 面積・高さ等の計算は、法令集で確認しなくても出せるようにしたいですね!! 是非解き方は覚えてください。 今日はこんな言葉です! 『明日はどうなるかわからないけれど今日一日は笑顔でいよう。 つらいことは多いけれど今日一日は明るい心でいよう。 いやなこともあるけれど今日一日は優しい言葉をかけていこう。』 (横田 南嶺) 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Feb 2, 2021
閲覧総数 1892
-
15
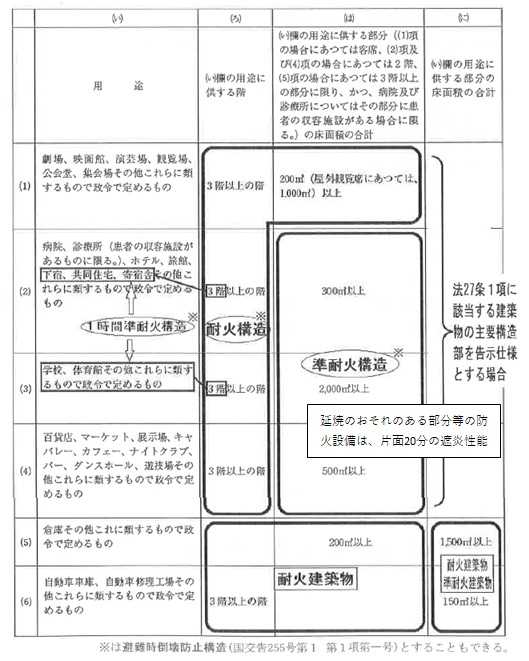
建築士の勉強!(法規編第29回)
第29回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!法規 5.耐火・防火 耐火・防火は、性能規定などからの用語の定義を問う問題、法27条や法61条からの構造を問う問題、法61条関連問題、防火区画などから出題されます。近年法改正も多くされているところですので最新の問題で確認したですね。 今回は、耐火建築物等の構造に関する規定と耐火性能検証法・防火区画検証法について見ていきましょう!! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 5-2 法27条(耐火建築物等)、法別表-1 令110条(法27条1項に規定する性能)、令110条の2(法27条1項の外壁の開口部) 令110条の3(法27条1項の防火設備の遮炎性能) 告示平成27年255号第1 1項(法27条1項に規定する構造方法) 令108条の3(耐火性能検証法、防火区画検証法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 □ 耐火建築物・準耐火建築物等 1.~14.は、建築基準法第27条の規定による耐火建築物等としなければならないものは〇、しなくてもよいものは×を判断しなさい。防火地域・準防火地域以外にあるものとする。 1 平屋建自動車車庫(床面積300㎡)(2級H17) 2 2階建て(各階の床面積250㎡)で、1階を物品販売業を営む店舗、2階を倉庫とするもの (2級H17) 3 2階建て(各階の床面積150㎡)で、1階を倉庫、2階を事務所とするもの(2級H17)4 3階建て(各階の床面積300㎡)で、1階を飲食店、2階及び3階を事務所とするもの (2級H17)5 3階建ての診療所(患者の収容施設があり、延べ面積が300㎡)(2級H21)6 各階の床面積が200㎡の2階建ての有料老人ホーム(2級H23)7 各階の床面積が500㎡の2階建ての飲食店(2級H23) 8 各階の床面積が100㎡の3階建の事務所(2級H23) 9 床面積が200㎡の平屋建の機械製作工場(2級H23) 10 2階建の飲食店で、各階の床面積の合計がそれぞれ250㎡のもの(2級R01)11 2階建ての児童福祉施設で、各階の床面積の合計がそれぞれ150㎡のもの(2級R01)12 2階建の倉庫で、各階の床面積の合計がそれぞれ100㎡のもの(2級R01)13 平屋建ての患者の収容施設がある診療所で、床面積の合計が200㎡のもの(2級R01)14 平屋建ての自動車車庫で、床面積の合計が200㎡のもの(2級R01)15 (防火地域及び準防火地域以外で小学校を計画するに際して)延べ面積2,100㎡、地上2階 の校舎について、主要構造部を耐火構造とし、避難上有効なバルコニーを設置した。 (1級H25) 16 (防火地域及び準防火地域以外で中学校を計画するに際して)延べ面積3,500㎡、地上2階建 の主要構造部に木材を用いたものとしたので、主要構造部を耐火構造とし、その外壁の開口部 で延焼のおそれのある部分に、所定の防火設備を設けた。(1級H24)17 (防火地域及び準防火地域以外で中学校を計画するに際して)主要構造部を1時間準耐火構造 とした地上3階建の建築物の外壁の開口部であって建築物の他の部分から当該開口部へ延焼す る恐れがあるものとして、「延焼のおそれのある部分」のみに、耐火建築物に求められるもの と同じ防火設備を設けた。(1級H24)18 防火地域及び準防火地域外で、地上3階建ての共同住宅において、その耐力壁である外壁に通 常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶 融、破壊その他の損傷を生じない準耐火構造(避難時倒壊防止構造ではない)とする準耐火建 築物とした。 (1級H26) 19 防火地域及び準防火地域以外の区域内における主階が2階にある地上2階建の映画館で、客席 部分の床面積の合計が150㎡、延べ面積が200㎡のものについて、その主要構造部を所定の基 準に適合するものであるについて耐火性能検証法により確かめられた構造とした。(1級H26)20 防火地域及び準防火地域以外の区域内における延べ面積2,500㎡、地上2階建ての学校の校舎 について、主要構造部を木造の準耐火構造とした。(1級H26)21 可燃ガス800㎥(温度が0度で圧力が1気圧の状態に換算した数値)を常時貯蔵する建築物は、 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(1級H17)□ 耐火性能検証法、防火区画検証法 1 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられた場合であっても、延べ面積 2,000㎡、地上4階建ての映画館の4階の主要構造部である柱は、耐火構造としなければなら ない。(1級H23) 2 主要構造部の性能について耐火性能検証法により確かめられたものであり、かつ、当該建築 物の主要構造部である床又は壁(外壁を除く)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検 証法により所定の性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等関係 規定の適用については、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす。(1級H23)3 耐火性能検証法は、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に主要 構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、建築物の周囲において発生す る通常の火災による火熱が加えられた場合に耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を 生じないものであること等を確かめる方法である。(1級H29)4 防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において 発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面 に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。(1級H29)5 主要構造部が、耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を有する ことが確かめられたものであり、かつ、当該建築物の主要構造部である床又は壁(外壁を除 く)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検証法により開口部設備の火災時における遮 炎に関する性能を有することが確かめられたものである建築物に対する防火区画等関係規定の 適用については、これらの防火設備の適用については、これらの防火設備の構造は特定防火設 備とみなす。(1級H16) *************************************************** 解説 5-2 法27条(耐火建築物等)、法別表-1 令110条(法27条1項に規定する性能)、令110条の2(法27条1項の外壁の開口部) 令110条の3(法27条1項の防火設備の遮炎性能) 告示平成27年255号第1 1項(法27条1項に規定する構造方法) 令108条の3(耐火性能検証法、防火区画検証法) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 法27条1項 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、主要構造部を政令で定める技術的基準(令110条)に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法(平27国交告225第1)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、外壁の開口部であって建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令(令110条の2)で定めるものに、防火戸その他の政令(令110条の3)で定める防火設備を設けなければならない。 一号:別表第1(ろ)欄に掲げる階を(い)欄(1)項ら(4)項までに掲げる用途に供するもの (階数3以下で延べ面積200㎡未満は除く(一部の用途に関しては警報設備を設けたものに 限る)) 耐火構造 令110条 一号:避難時倒壊防止構造(平27国交告225第1 1項一号) 二号:耐火性能、耐火性能検証法 二号:別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途でその用途に供する部分の床面積の 合計が(は)欄に該当するもの 準耐火構造 平27国交告225第1 1項二号 準耐火構造又は令109条の3三号:別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途で、その用途に供する床面積の合計が3,000㎡以上の もの 耐火構造 平27国交告225第1 8項 耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号四号:劇場、映画館等の用途に供するもので、主階が1階にないもの(階数3以下、延べ面積200㎡ 未満は除く) 耐火構造 平27国交告225第1 8項 耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号法27条2項 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない一号:別表第1(い)欄(5)項に掲げる用途で、(は)欄に該当するもの 二号:別表第1(ろ)欄(6)項に掲げる用途で、(い)欄に該当するもの 法27条3項 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない一号:別表第1(い)欄(5)項又は(6)項に掲げる用途で、(に)欄に該当するもの二号:別表第2(と)項四号に規定する危険物の貯蔵または処理条の用途に供するもの令110条の2(法27条1項の外壁の開口部)一号:延焼のおそれのある部分 二号:他の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣 が定めるもの(平27国交告225第3) 令110条の3(法27条1項に規定する防火設備の遮炎性能) 20分間防火設備(平27国交告225第2、令137条の10) 片面20分の遮炎性能 平27国交告225第1 1項 三号:地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅又は寄宿舎にお用途に供するもので、防火地域 以外の区域内にあるものでイ~ハの基準に適合するものは、1時間準耐火構造とする四号:地階を除く階数が3で、3階を別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途に供するものはで、前号 ロに掲げる基準に適合するものは1時間準耐火構造とする法27条を別表1にまとめると 別表-1の構成 ① (い)欄(1)項~(4)項までは、主要構造部が、耐火構造(一部1時間準耐火構造)か準耐 火構造の構造規定+延焼のおそれのある部分等の防火設備は片面20分の遮炎性能 (主要構造部の構造規定+片面20分なので、耐火建築物・準耐火建築物の指定ではない)② (い)欄(5)項、(6)項は、耐火建築物・準耐火建築物指定 □ 耐火建築物・準耐火建築物等 NO.1~14は、法27条(法別表-1)に該当するものは〇、該当しないものは× 1 〇 別表-1 (に)欄(6)項に該当し準耐火建築物以上 2 × 別表-1に該当しない 3 × 別表-1に該当しない 4 × 別表-1に該当しない 5 〇 別表-1(ろ)欄(2)項に該当し主要構造部を耐火構造+片面20分防火設備6 × 別表-1に該当しない 7 〇 別表-1(は)欄(4)項に該当し主要構造部を準耐火構造以上+片面20分防火設備8 × 別表-1に該当しない 9 × 別表-1に該当しない 10 × 別表-1に該当しない 11 × 別表-1に該当しない 12 × 別表-1に該当しない 13 × 別表-1に該当しない 14 〇 別表-1(に)欄(6)項に該当し準耐火建築物以上 15 〇 別表-1(は)欄(3)項に該当し、主要構造部は準耐火構造+片面20分防火設備16 〇 別表-1(は)欄(3)項に該当し、主要構造部は準耐火構造+片面20分防火設備17 × 別表-1(ろ)欄(3)項に該当し、主要構造部を耐火構造又は1時間準耐火構造+片面 20分防火設備となる。令110条の2より、一号「延焼のおそれのある部分」と二号 「他の開口部から通常の火災時における火炎が到達するおそれがあるものとして国土交 通大臣が定めるもの」の2か所に防火設備を設けなければならない。18 × 別表-1(ろ)欄(2)項に該当し、主要構造部を耐火構造又は1時間準耐火構造+片面 20分防火設備としなければならない。45分準耐火構造ではダメ。19 〇 法27条1項四号により、主要構造部は耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号 としなければならない。 20 〇 別表-1(は)欄(3)項に該当し、主要構造部を準耐火構造+片面20分防火設備としな ければならない。 21 〇 法27条3項二号に該当し、令116条1項表より700㎥を超えているので、耐火建築物又 は準耐火建築物としなければならない。 □ 耐火性能検証法、防火区画検証法 1 × 別表-1(ろ)欄(1)項に該当し、主要構造部は耐火構造としなければならない。 平27国交告225第1 8項により、耐火構造又は令108条の3 1項一号若しくは二号 でいいので、耐火性能検証法で確かめられたものは、耐火構造とする必要はない。 2 〇 令108条の3 4項により、正しい。 3 〇 令108条の3 1項一号 イ ロにより、正しい。 4 × 令108条の3 5項一号 二号により、建築物の周囲において発生が予測される火災によ る検討はない 5 〇 令108条の3 4項により、正しい。 法21条、法27条、法61条関連の規定は近年改正がされているところで、とても分かりにくくなりました。耐火建築物しなければならない建物については法27条だけに限定されたので、問題の出題形式は以前と変わってくる思います。別表-1は解りやすくマーカー処理等をして工夫をして下さい!! 今日はこんな言葉です! 『考えれば知恵が出る。行動すれば発見がある。人に会えば人脈ができる。 夢を持てば人生が楽しくなる。すべては自分次第。』(福島 正伸) 2級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3410円(税込、送料無料) (2020/11/28時点)楽天で購入1級建築士試験学科ポイント整理と確認問題(令和3年度版) [ 総合資格学院 ]価格:3630円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)1級建築士試験学科過去問スーパー7(令和3年度版) 過去問7年分875問収録 [ 総合資格学院 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/12/31時点)初学者の建築講座 建築法規(第四版) [ 長澤 泰 ]価格:3080円(税込、送料無料) (2020/11/10時点)
Jul 15, 2021
閲覧総数 2753
-
16
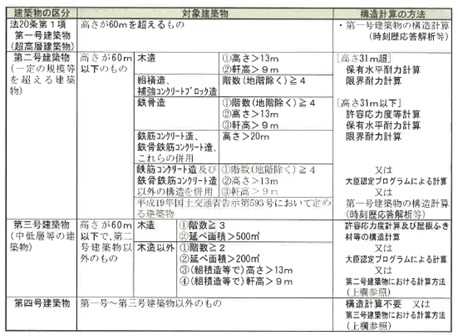
建築士の勉強!(法規編第39回)
第39回建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。過去問を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)法規 9.構造計算・構造強度 構造計算・構造強度の問題は、構造計算、荷重・外力、許容応力度・材料強度、各種構造等に分類されます。1級・2級とも3問ほど出題されます。木造の壁量計算みたいな計算問題もありますので傾向をしっかり押さえてください。特に1級では学科Ⅳ(構造)との関連問題も多いので、法20条の建物分類等は必ず覚えて構造の知識で構造計算の内容を理解すると学科Ⅳでも得点が望めます!!今回は、構造計算に関する問題について見ていきましょう! (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)9-1 法20条(構造耐力)、令36条の2(階数が4以上の鉄骨造に準ずる建築物) 法6条の3(構造計算適合性判定)、法77条の35の9(構造計算適合性判定員) 令36条(構造方法に関する技術的準)、令37条(構造部材の耐久性) 令38条(基礎)、令39条(屋根ふき材等) 令80条の3(土砂災害特別警戒地区内の構造方法) 令81条(構造計算の種類)、令82条(保有水平耐力計算)、令82条の2(層間変形角) 令82条の3(保有水平耐力)、令82条の4(屋根ふき材等の構造計算) 令82条の5(限界耐力計算)、令82条の6(許容応力度等計算) (条文は自分の法令集で確認して下さい。)問題□ 構造計算1 木造3階建、延べ面積250㎡の一戸建て住宅は、所定の基準に従つた構造計算で、国土交通大 臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによりその 構造が安全であることを確かめなければならない。(2級H15)2 鉄骨造平屋建、延べ面積250㎡の事務所は、所定の基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が 定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによりその構造 が安全であることを確かめなければならない。(2級H17)3 屋根ふき材については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して 構造耐力上安全であることを確かめなければならない。(2級H20)4 エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している「高さ が31mを超える建築物の部分」と「高さが10m以下の建築物の部分」については、それぞれ の建築物の部分で必要とされる構造計算の方法を用いることができる。(1級R01)5 保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場 合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重がある場合と積雪荷重がない場合と を考慮する。(2級H25)6 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構 造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなけれなばならない。 (2級H28)7 保有水平耐力計算により、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度 を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。 (2級R02)8 鉄骨造の建築物において、許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、国土交通大臣が 定める場合においては、構造耐カ上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物 の使用上の支障が起こらないことを所定の方法によって確かめなければならない。(1級R02)9 木造2階建、延べ面積400㎡、高さ8mの集会場は、構造計算適合性判定の対象となる(国土交 通大臣の認定を受けたプログラムにはよらないものとする)。(2級H24)10 木造3階建、延べ面積150㎡、高さ9mの住宅は、構造計算適合性判定の対象となる(国土交 通大臣の認定を受けたプログラムにはよらないものとする)。(2級H24)11 鉄骨造2階建、延べ面積200㎡、高さ9mの事務所は、構造計算適合性判定の対象となる(国 土交通大臣の認定を受けたプログラムにはよらないものとする)。(2級H24)12 鉄骨造4階建、延べ面積300㎡、高さ13mの教会は、構造計算適合性判定の対象となる(国土 交通大臣の認定を受けたプログラムにはよらないものとする)。(2級H24)13 補強コンクリートブロック造2階建、延べ面積200㎡、高さ6mの店舗併用住宅は、構造計算 適合性判定の対象となる(国土交通大臣の認定を受けたプログラムにはよらないものとす る)。(2級H24)14 木造平屋建、延べ面積1,000㎡、高さ4mの老人福祉施設は、構造計算によりその安全性を確 かめなくてもよい。(2級H25)15 補強コンクリートブロック造2階建、延べ面積220㎡、高さ6mの長屋は、構造計算によりそ の安全性を確かめなくてもよい。(2級H25)16 鉄骨造平屋建、延べ面積200㎡、高さ9mの倉庫は、構造計算によりその安全性を確かめなく てもよい。(2級H25)17 鉄骨造平屋建、延べ面積250㎡、高さ4mの店舗は、構造計算によりその安全性を確かめなく てもよい。(2級H25)18 鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積180㎡、高さ7mの事務所は、構造計算によりその安全 性を確かめなくてもよい。(2級H26)19 木造平屋建、延べ面積500㎡、高さ6mの建築物は、構造計算によりその安全性を確かなけれ ばならない。(2級H30)20 木造2階建、延べ面積200㎡、高さ9mの建築物は、構造計算によりその安全性を確かなけれ ばならない。(2級H30)21 鉄骨造平屋建、延べ面積150㎡、高さ8mの建築物は、構造計算によりその安全性を確かなけ ればならない。(2級H30)22 鉄骨造2階建、延べ面積100㎡、高さ7mの建築物は、構造計算によりその安全性を確かなけ ればならない。(2級H30)23 補強コンクリートブロック造平屋建、延べ面積180㎡、高さ5mの建築物は、構造計算により その安全性を確かなければならない。(2級H30)24 保有水平耐カ計算において、高さ20mの鉄骨造の建築物の屋外に面する帳壁については、構 造計算によって風圧に対して構造耐カ上安全であることを確かめなくてもよい。(1級R01)25 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物(高さが31m以下のもの)で、高さが13m 又は 軒の高さが9mを超えるものは、許容応力度等計算、保有水平耐カ計算、限界耐カ計算又はこ れらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国上交通大臣が定める基準に従っ た構造計算により安全性を確かめることができる。(1級H20)26 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、「各階の剛性率が、それぞれ 6 / 10以上であること」及び「各階の偏心率が、それぞれ15 / 100を超えないこと」を確かめ なければならない。(1級H20)27 限界耐カ計算において、暴風時に、建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力が、当該構造 耐カ上主要な部分の耐力を超えないことを確かめる場合、建築基準法施行令第87条に規定する 風圧力によって生ずる力に1.6を乗じて計算しなければならない。(1級H20)28 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、建築に関する専門的知 識及び技術を有する者として所定の要件を備える者のうちから選任した構造計算適合性判定員 に構造計算適合性判定を実施させなければならない。(1級H20)29 高さが31mを超え、60m以下の建築物については、限界耐カ計算又はこれと同等以上に安全 性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による場合 には、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土 交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい。(1級H21)30 高さ31m以下の所定の建築物の地上部分について、各階の剛性率を確かめる場合、当該剛性 率は、「各階の層間変形角の逆数」を「当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加 平均」で除して計算する。(1級H17)31 保有水平耐力計算を行う場合、所定の建築物で高さが31mを超えるものについては、地上部 分について、保有水平耐力が、所定の計算による必要保有水平耐カ以上であることを確かめな ければならない。(1級H18)32 限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び 短期(積雪時及び暴風時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する 各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。(1級H18,H22,H28)33 高さが60mを超える建築物については、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的生ず る力及ひ変形を把握し、その力及び変形が当該建築物の各部分の耐力及び変形限度を超えない ことを確かめなければならない。(1級H22)34 鉄骨鉄筋コンクリート造、高さ45mの建築物については、保有水平耐カ計算を行う場合、 「各階の剛性率が、それぞれ6/10以上であること」及び「各階の偏心率が、それそれ15/100 を超えないこと」に適合することを確かめなければならない。(1級H22)35 鉄筋コンクリート造、高さ15m、延べ面積800㎡の建築物については、許容応力度等計算又 はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従 った構造計算により安全性を確かめることができる。(1級H22)36 限界耐力計算を行う場合、構造耐カ上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短 期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に 対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。(1級H26)37 鉄骨造、高さ13m、軒の高さ10m、地上2階建ての建築物については、都道府県知事又は指 定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の対象となる。 (1級H23)38 許容応力度等計算において、建築物の地上部分について各階の剛性率を確かめる場合、当該 剛性率は、「各階の層間変形角の逆数」を「当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の 相加平均」で除して計算する。 (1級H23)39 高さ45mの建築物について、限界耐カ計算を行う場合には、保有水平耐カ計算又はこれと同 等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計 算を行わなくてもよい。 (1級H23)40 高さ25mの鉄筋コンクリート造の建築物の地上部分について、保有水平耐力が必要保有水平 耐カ以上であることを確かめた場合には、層間変形角が所定の数値以内であることを確かめな くてもよい。(1級H23,H29)41 高さが60mを超える建築物で、所定の構造計算によって安全性が確かめられたものとして国 土交通大臣の認定を受けたものは、耐久性等関係規定に適合しない構造方法を用いることがで きる。(1級H24)42 木造、延べ面積200㎡、高さ9m、地上3階建ての建築物は、構造計算をしなければならない。 (1級H25)43 鉄骨造、延べ面積200㎡、高さ4m、平家建ての建築物は、構造計算をしなければならない。 (1級H25)44 高さ45mの鉄筋コンクリート造の建築物の地上部分について、保有水平耐カ計算を行う場 合、各階の層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。(1級H26)45 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、各階の剛性率が、それぞれ 6/10以上であることを確かめなければならない。(1級H26)46 許容応力度等計算においては、建築物の地上部分について各階の剛性率を確かめる場合、当 該剛性率は、「各階の層間変形角の逆数」を「当該建築物についての各階の層間変形角の逆数 の相加平均」で除して計算し、その値がそれぞれ6/10以上であることを確かめる。(1級H29)47 限界耐カ計算を行う場合、地震時については、建築物の地下部分を除き、地震力により構造 耐カ上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないこ とを計算により確かめなくてもよい。(1級H29)48 津波による災害の発生のおそれのある区域においては、津波による外力に対して安全である ことを確かめなければならない。(1級H28)49 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に 生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。(1級R03)50 限界耐力計算を行う場合、所定の地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の 断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確か めなければならない。(1級R03)□ 構造部材等(杭・基礎・その他) 1 地盤の支持層が傾斜していたので、基礎の一部を杭基礎とした。(2級H30)2 限界耐力計算により安全性が確かめられた建築物において、建築物の構造耐カ上主要な部分に 指定建築材料を用いる場合には、その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日 本工業規格若しくは日本農林規格に適合するもの、又は指定建築材料ごとに所定の技術的基準 に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。 (1級H15)3 高さ13m又は延べ面積3,000を超える建築物で、当該建築物に作用する荷重が最下階の床面積 1 ㎡につき100KNを超えるものにおいて、基礎ぐいを使用する場合には、原則として、当該基 礎ぐいの先端を良好な地盤に達することとしなければならない。 (1級H21)4 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は 変形に対して構造耐カ上安全なものとしなければならない。(1級H27)5 建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。(1級H25)6 建築物の基礎は、国上交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全である ことを確かめた場合には、異なる構造方法による基礎を併用してもよい。(1級H29)7 上砂災害特別警戒区域内における建築物の外壁の構造は、原則として、居室を有しない建築物 であっても、自然現象の種類、最大のカの大きさ等及び土石等の高さ等に応じて、当該自然現 象により想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国上交通大臣が 定めた構造方法を用いるものとしなければならない。(1級H30)8 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分を、風圧並びに地震そ の他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。(1級H19,H25)9 構造耐カ上主要な部分で特に摩損のおそれのあるものには、摩損しにくい材料又は摩損防止の ための措置をした材料を使用しなければならない。(1級H30)****************************************************** 解説 9-1 法20条(構造耐力)、令36条の2(階数が4以上の鉄骨造に準ずる建築物) 法6条の3(構造計算適合性判定)、法77条の35の9(構造計算適合性判定員) 令36条(構造方法に関する技術的準)、令37条(構造部材の耐久性) 令38条(基礎)、令39条(屋根ふき材等) 令80条の3(土砂災害特別警戒地区内の構造方法) 令81条(構造計算の種類)、令82条(保有水平耐力計算)、令82条の2(層間変形角) 令82条の3(保有水平耐力)、令82条の4(屋根ふき材等の構造計算) 令82条の5(限界耐力計算)、令82条の6(許容応力度等計算) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) □ 構造計算 法20条(構造耐力)、令36条の2(階数が4以上の鉄骨造に準ずる建築物) 1項 一号 高さ60m超の建築物:国土交通大臣の認定を受ける(構造計算必要) 二号 木造:高さ13m超、軒高9m超 RC造:高さ20m超 S造:階数4以上、高さ13m超、軒高9m超(構造計算必要) 三号 木造:階数3以上、延べ面積500㎡超 木造以外の構造:階数2以上、延べ面積200㎡超(構造計算必要) 四号 一号~三号以外の建築物(構造計算不要)2項 エキスパンションジョイント(令36条の4)のみで接している建物は構造計算上別建物とみ なす 法20条1項をまとめると 法6条の3(構造計算適合性判定) 1項 法20条1項二号に規定する方法又はプログラムによる構造計算、三号に規定するプログラム による構造計算をした場合は、都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない 法77条の35の9(構造計算適合性判定員) 1項 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させな ければならない 2項 構造計算適合判定資格者検定に合格した者又は同等の知識のある者は、国土交通大臣の登録 を受ける。登録を受けたもののうちから、構造計算適合性判定員を選任する 令81条(構造計算の種類) 1項 法20条1項一号建築物の構造計算:一号~四号の基準(時刻歴応答解析) 2項 法20条1項二号建築物の構造計算 一号 高さ31m超 保有水平耐力計算(ルート3)、限界耐力計算のいずれか 二号 高さ31m以下 許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算、限界耐力計算 のいずれか 3項 法20条1項三号建物の構造計算:令82条+令82条の4の計算(ルート1) ※ 上位計算はOK 構造計算をまとめると 令82条(保有水平耐力計算) 保有水平耐力計算は、令82条+令82条の2+令82条の3+令82条の4の計算(ルート3) ※令82条は、項目には保有水平耐力計算とあるが、内容は許容応力度計算の内容が示されている。 令82条の2(層間変形角) 建築物の地上部分について、地震力によって各階に生ずる層間変形角が1/200(著しい損傷が生じるおそれがない場合は1/120)以下であることを確かめなければならない(許容応力度等計算と保有水平耐力計算の場合のみ) 令82条の3(保有水平耐力) 保有水平耐力 ≧ 必要保有水平耐力 (※ここの内容は学科Ⅳの構造でよく問われる!) 令82条の4(屋根ふき材の構造計算) 屋根ふき材、外装材等は国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して安全であることを確かめなければならない 令82条の5(限界耐力計算) 一号 地上部分の一次設計の検討(地震力以外は許容応力計算を行う) 二号 地上部分の二次設計の検討(地震力以外は積雪1.4倍、風圧1.6倍で材料強度により検討) 三号 地上部分の地震力の一次設計(損傷限界の検討) 四号 地下部分の地震力の検討(許容応力度で検討) 五号 地上部分の地震力の二次設計(安全限界の検討) 令82条の6(許容応力度等計算) 一号 許容応力度等計算は、令82条+令82条の2+令820条の4の計算(ルート2) 二号 剛性率:6/10以上(各階の層間変形角の逆数/各階の層間変形角の逆数の相加平均) 偏心率:15/100以下(重心と剛心との距離/ねじり剛心の数値を水平剛性の数値で除した 値の平方根) 1 〇 法20条1項三号建築物なので、構造計算によって確かめなければならない 正しい2 〇 法20条2項三号建築物なので、構造計算によって確かめなければならない 正しい 3 〇 令82条の4により確かめなければならない 正しい 4 〇 法20条2項より、エキスパンションジョイントのみで接している場合は構造計算上別建物と みなす 正しい5 〇 令82条二号表により、長期はG+PとG+P+0.7Sの両方を検討する 正しい 6 〇 令82条の4により屋根ふき材等は、風圧に対して構造計算で安全を確かめなければならない 正しい7 〇 令82条二号表5により、地震時はG+P+0.35S+K 雪を考慮する 正しい 8 〇 令83条四号により、変形等による使用上の支障に対する検討を行う 正しい9 × 法6条の3により、法20条1項四号建物は適合性判定は不要 誤り 10 × 法6条の3により、法20条1項三号建物はプログラムの場合のみ適合性判定が対象 誤り 11 × 法6条の3により、法20条1項三号建物はプログラムの場合のみ適合性判定が対象 誤り 12 〇 法6条の3により、法20条1項二号建物はプログラム、方法どちらも適合性判定の対象となる 正しい 13 × 法6条の3により、法20条1項三号建物はプログラムの場合のみ適合性判定が対象 誤り 14 × 法20条1項三号建築物なので、構造計算によって確かめなければならない 誤り 15 × 法20条1項三号建築物なので、構造計算によって確かめなければならない 誤り 16 〇 法20条1項四号建築物なので、構造計算によって確かめなくてもよい 正しい 17 × 法20条1項三号建築物なので、構造計算によって確かめなければならない 誤り 18 × 法20条1項三号建築物なので、構造計算によって確かめなければならない 誤り 19 × 法20条1項四号建築物なので、構造計算によって確かめなくてもよい 誤り 20 × 法20条1項四号建築物なので、構造計算によって確かめなくてもよい 誤り 21 × 法20条1項四号建築物なので、構造計算によって確かめなくてもよい 誤り 22 〇 法20条1項三号建築物なので、構造計算によって確かめなければならない 正しい 23 × 法20条1項四号建築物なので、構造計算によって確かめなくてもよい 誤り 24 × 保有水平耐力計算は、令82条の4により屋根ふき材等は、風圧に対して構造計算で安全を確 かめなければならない 正しい 25 〇 法20条1項二号建物(高さ31m以下)なので、令81条2項二号により3つの構造計算のうち どれでもよい 正しい26 〇 令82条の6二号イ、ロによりにより、剛性率と偏心率を確かめなければならない 正しい 27 〇 令82条の5二号表により、二次設計では風圧力を1.6倍して検討する 正しい 28 〇 令77条の35の9 1項、2項により 正しい 29 〇 法20条1項二号建物(高さ31m超)は、令81条2項一号により限界耐力計算か保有水平耐力 計算のどちらかでよい 正しい30 〇 令82条の6 二号イにより剛性率の求め方 正しい31 〇 令82条の3により、保有水平耐力≧必要保有水平耐力を確かめる 正しい32 〇 令82条の5一号により、1次設計で令82条一号~三号を確認する 正しい33 〇 令81条1項一号二号により 正しい34 × 令81条2項一号により高ささ31m超は、限界耐力計算は保有水平耐力計算を行う。剛性率や 偏心率は令82条の6二号より許容応力度等計算の場合必要なので関係ない 誤り35 〇 法20条1項三号建物なので、令81条3項の構造計算でOK。許容応力度等計算は上位計算な ので行なってもよい 正しい36 × 令82条の5一号により一次設計では、地震力による許容応力度計算は行わない(短期で地震 力は検討しない) 誤り37 〇 軒高が9mを超えているので、法20条1項二号建物となり、法6条の3により適合性判定の対 象となる 正しい38 〇 令82条の6二号イにより、剛性率の求め方 正しい39 〇 令81条2項二号により、高さ31m超の建築物は限界耐力計算又は保有水平耐力計算のどちら かでよい 正しい40 × 令82条により保有水平耐力計算は、令82条の2の層間変形角の確認を行わなければならない 誤り41 × 令36条により法20条1項一号建物は、耐久性等関係規定は守らなければならない 誤り42 〇 法20条1項三号建築物なので、構造計算によって確かめなければならない 正しい43 × 法20条1項四号建築物なので、構造計算によって確かめなくてもよい 誤り44 〇 令82条により保有水平耐力計算は、令82条の2の層間変形角の確認を行わなければならない 正しい45 〇 令82条の6二号イにより、剛性率の確認を行わなければならない 正しい46 〇 令82条の6二号イにより、剛性率の確認を行わなければならない 正しい47 〇 令82条の5 一号~五号により、地震力による許容応力度の確認は行わない 正しい48 × 令83条1項2項により、津波による外力は検討しない 誤り49 〇 令82条の6一号により、令82条の2(層間変形角)の検討を行わなければならない 正しい50 〇 令82条の5 四号により、地下部分は許容応力度計算を行う 正しい□ 構造部材等(杭・基礎・その他) 法37条(建築材料の品質) 建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材等(指定建築材料)は、一号、二号のいずれかとする 一号 指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格又は日本農林規格に適合す るもの 二号 指定建築材料ごとに国土交通大臣の認定を受けたもの令36条(構造方法に関する技術的基準) 1項 法20条1項一号建物の構造計算を行った場合の仕様規定は、耐久性等関係規定のみ守ればOK 2項 法20条1項二号建物の構造計算を行った場合の仕様規定は 一号 保有水平耐力計算をやった場合は、令67条1項、令68条4項、令73条、令77条二号~ 六号、令77条の2 2項、令78条、令78条の2 1項三号、令80条の2は除外される (守らなくてもOK) 二号 限界耐力計算をやった場合は、耐久性等関係規定のみ守ればOK 三号 許容応力度等計算をやった場合は、すべての仕様規定を守る 3項 法20条1項三号、四号建物は全ての仕様規定を守る 令37条(構造部材の耐久) 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食等しにくい材料又はさび止め等の措置をした材料を使用しなければならない 令38条(基礎) 1項 建築物の基礎は、荷重等を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して安全なも のとしなければならない 2項 建築物には、異なる構造方法による基礎を使用してはならない3項 建築物の基礎の構造は、高さ13m又は延べ面積3,000㎡を超える建築物で、当該建築物に作 用する荷重が最下階の床面積1㎡につき100KNを超えるものにあっては、基礎の底部(杭を 使用する場合は、杭先)を良好な地盤に達することとしなければならない 4項 2項、3項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によ って確かめられた場合は適用しない 6項 建築物の基礎に木ぐいを使用する場合はにおいては、その木ぐいは、平屋建ての木造の建築 物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない 令39条(屋根ふき材等) 屋根ふき材、内装材、外装材等は、風圧並びに地震その他の振動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない 令80条の3(土砂災害特別警戒地区内の構造方法) 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分の構造は、自然現象の種類に応じて、当該自然現象により破壊を生じないものとして国土交通大臣が定める構造補法を用いなければならない 1 × 令38条2項により、異なる構造方法の基礎を使用してはならない 誤り 2 〇 法37条一号、二号により、構造計算に関係なく守らなければならない 正しい3 〇 令38条3項により、基礎杭を使う場合は杭の先端が良好な地盤に達することとしなければな らない 正しい4 〇 令38条1項により 正しい5 〇 令38条2項により 正しい 6 〇 令38条4項により、構造計算によって確かめられた場合は、異なる構造方法による基礎を併用 してもよい 正しい7 × 令80条の3により、居室を有する建築物が対象 誤り8 〇 令39条1項により 正しい9 〇 令37条により 正しい 構造計算の問題は、まず法20条1項一号~四号までの建物規模を必ず覚えて下さい。ここを窓口に、何号の建物なら構造計算は何そして仕様規定は何と言うように繋げる。法規では法令集を見て判断できますが、1級学科Ⅳ(構造)でも同じ内容を問われますので法令集を見なくとも判断できるようにしたいところです!! 今日はこんな言葉です! わたしの人生では、わたしが主役。失敗じゃないよ、成功の途中。心配よりも、応援してね。(三井 明子)
Aug 17, 2021
閲覧総数 2745
-
17
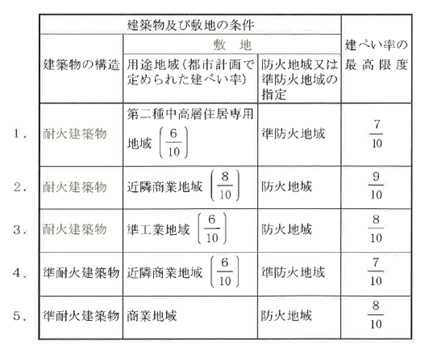
建築士の勉強!(法規編第54回)
第54回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 12.建蔽率 建蔽率の問題は、計算問題と文章問題に分けられます。どちらも、建蔽率の緩和を絡めて問われる場合が多いので、緩和規定はしっかり覚えて下さい。 (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 12-1 法53条(建蔽率) 法53条の2(建築物の敷地面積) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題□ 建蔽率の文章問題1 用途地域の指定のない区域内の耐火建築物は、原則として、建ぺい率の制限を受けない。 (2級H15,H17) 2 都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた際、現に建築物の敷地として使用 されている土地で、この最低限度を下回るものについては、原則として、その全部を一の敷地 として使用する場合においても、その敷地に建築物を建築することはできない。 (2級H15,H18)3 商業地域内において、建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合、その敷地内の建築物の全 部が耐火建築物であるときは、建ぺい率の制限を受けない。(2級H16)4 敷地に接する道路の幅員によって、原則として、建築物の建ぺい率の制限が異なる。 (2級H17,H21,H25,H28) 5 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率の制限を受けない。 (2級H19,H25,R01) 6 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた地域内に巡査派 出所を新築しようとする場合については、その敷地面積を当該最低限度以上としなくてもよ い。(2級H20)7 建築物の敷地面積に関する制限は、景観地区に関する都市計画においても定められることがあ る。(2級H20) 8 準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は6/10)内、かつ、防火地域内で、角地の指定のな い敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は7/10である。 (2級H28,R01) 9 建築物の敷地及び建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該建築物が耐火 建築物であるときは、準防火地域内にある建築物の部分は、建ぺい率の緩和の対象とならな い。(1級H19) 10 工業地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内 の築物の全部が耐火建築物であるときは、都市計画において定められた建蔽率の限度にかかわ らず、建蔽率の限度の緩和の対象となる。(1級H23,H29) 11 都市計画において定められた建蔽率の限度が6/10の第一種住居地域内で、かつ、準防火地域 内にある耐火建築物については、建蔽率の限度の緩和の対象となる。(1級H29) □ 建蔽率の緩和問題1 建築物及び敷地の条件とその建ぺい率の最高限度との組合せとして、建築基準法上、正しい ものは、次のうちどれか。ただし、特定行政庁による角地及び壁面線の指定等は無いものと する。(法改正により正しいものは複数あり)(2級H20) 2 耐火建築物を建築する場合、敷地とその建ぺい率の最高限度との組合せとして、建築基準法 上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地 域、地区等は考慮しないものとし、壁面線の指定等はないものとする。(法改正により正し いものは複数あり)(2級H21) 3 耐火建築物を建築する場合、敷地とその建ぺい率の最高限度との組合せとして、建築基準法 上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地 域、地区等は考慮しないものとし、壁面線の指定等はないものとする。(法改正により正し いものは複数あり)(2級H17) 4 耐火建築物を建築する場合、敷地とその建ぺい率の最高限度との組合せとして、建築基準法 上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地 域、地区等は考慮しないものとし、壁面線の指定等はないものとする。(2級H24) 5 建築物及び敷地の条件とその建蔽率の最局限度との組合せとして、建築基準法上、正しいもの は、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮 しないものとし、特定行政庁による角地及ひ壁面線の指定等はないものとする。(2級H27) 6 「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最局限度」との組合せとして、建築基準法上、正 しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区 等は考慮しないものとし、特定行政庁による角地及ひ壁面線の指定等はないものとする。 (2級H30) □ 建蔽率の計算問題1 図のような敷地において、建築基準法上、建築することができる事務所の建築面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとする。(2級H14) 2 図のような敷地において、建築基準法上、建築することができる事務所の建築面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとする。(2級H16) 3 図のような敷地において、建築基準法上、建築することができる事務所の建築面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとする。(2級H19) 4 図のような敷地において、建築基準法上、建築することができる建築物の建築面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとする。(2級H22) 5 図のような敷地において、建築基準法上、建築することができる事務所の建築面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はないものとする。(2級H18) 6 図のような敷地において、建築基準法上、建築することができる建築物の建築面積の最高限度 は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁 の指定等はなく、図に示す範囲に高低差は無いものとする。(2級H23) 7 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができ る建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除 き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はなく、図に示す範囲に高低差は無いものとする。 (2級R02) 8 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる 建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、 地域、地区等及び特定行政庁の指定等はなく、図に示す範囲に高低差は無いものとする。 (2級H26) 9 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる 建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、 地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差は無いものとす る。(2級H29) 10 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる 建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、 地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差は無いものとする。 (1級H15) 11 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる 建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、 地区等及び特定行政庁の指定等はいものとする。(1級H26) 12 図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができ る建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地 域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。(1級R02) ***************************************************** 解説 12-1 法53条(建蔽率) 法53条の2(建築物の敷地面積) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 法53条(建蔽率)3項 一号 防火地域内(8/10の地域以外)にある耐火建築物等 +1/10 準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等 +1/10 ニ号 街区地で特定行政庁が指定したもの +1/106項 一号 防火地域内(8/10の地域)にある耐火建築物等 10/10(制限なし)7項 建築物の敷地が防火地域の内外に渡る場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築 物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第3項の規定を適 用する法53条の2(建築物の敷地面積)1項 建築物の敷地は、都市計画において建築物の敷地の最低限度が定められたときは、当該最低 限度以上でなければならない。ただし、一号~三号に該当する場合は、この限りでない。 二号 公衆便所、巡査派出所等2項 敷地面積の最低限度を定めるときは、その最低限度は、200㎡を超えてはならない。3項 敷地面積の最低限度が定められ又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている 土地で最低限度に満たない敷地の場合は、その全部を一の敷地として使用するならば1項の 規定は適用されない。 □ 建蔽率の文章問題1 × 法53条1項六号により、用途地域の指定のない区域でも建蔽率の制限を受ける 誤り 2 × 法53条の2 3項により、全部を一の敷地として使用する場合には建築できる 誤り 3 〇 法53条6項,7項により、8/10の地域で防火地域+耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない 正しい 4 × 法53条により、建蔽率は道路幅員による変化はない 誤り 5 〇 法53条6項により、8/10の地域で防火地域+耐火建築物は、建蔽率の制限を受けない 正しい 6 〇 法53条の2 1項二号により、巡査派出所は除外されている 正しい 7 〇 法68条3項により、建築物の敷地面積の最低限が定められる場合がある 正しい 8 〇 法53条3項により、防火地域+耐火建築物で+1/10となり7/10となる 正しい 9 × 法53条3項,7項により、耐火建築物は、防火地域及び準防火地域で緩和を受ける 誤り 10 〇 法53条1項五号により、工業地域は5/10、6/10なので、3項による緩和の対象となる 正しい 11 〇 法53条3項一号により、緩和の対象となる 正しい □ 建蔽率の緩和問題1 1 〇 法53条3項により、6/10に準防火地域+耐火建築物で+1/10となり7/10となる 正しい 2 × 法53条6項により、8/10の地域で防火地域+耐火建築物で制限がなくなり 10/10 となる 誤り 3 × 法53条3項により、6/10に防火地域+耐火建築物で+1/10となり7/10となる 誤り 4 〇 法53条3項により、6/10に準防火地域+準耐火建築物で+1/10となり7/10となる 正しい 5 〇 法53条6項により、8/10の地域で防火地域+準耐火建築物なので緩和なし 8/10 となる 正しい 2 1 〇 法53条3項により、5/10に準防火地域+耐火建築物で+1/10、角地で+1/10となり 7/10となる 正しい 2 × 法53条6項により、8/10の地域で防火地域+耐火建築物で制限がなくなり 10/10と なる 誤り 3 × 法53条3項により、8/10の地域で準防火地域+耐火建築物で+1/10、角地で+1/10 となり10/10となる 4 〇 法53条3項により、6/10に防火地域+耐火建築物で+1/10となり7/10となる 正しい 5 × 法53条3項により、6/10に防火地域+耐火建築物で+1/10、角地で+1/10となり 8/10となる 正しい 3 1 〇 法53条3項により、6/10に準防火地域+耐火建築物で+1/10となり7/10となる 正しい 2 〇 法53条3項により、6/10に準防火地域+耐火建築物で+1/10、角地で+1/10となり 8/10となる 正しい 3 × 法53条3項により、8/10の地域で準防火地域+耐火建築物で+1/10、角地で+1/10 となり10/10となる 誤り 4 × 法53条6項により、8/10の地域で防火地域+耐火建築物で制限がなくなり 10/10 となる 誤り 5 × 法53条3項により、8/10の地域で準防火地域+耐火建築物で+1/10、角地で+1/10 となり10/10となる 誤り4 1 × 法53条3項により、6/10に準防火地域+耐火建築物で+1/10となり7/10となる 誤り 2 × 法53条3項により、8/10の地域で準防火地域+耐火建築物で+1/10、角地で+1/10 となり10/10となる 誤り 3 × 法53条3項により、6/10に準防火地域+耐火建築物で+1/10、角地で+1/10となり 8/10となる 正しい 4 〇 法53条3項により、8/10の地域で準防火地域+耐火建築物で+1/10、角地で+1/10 となり10/10となる 正しい 5 × 法53条6項により、8/10の地域で防火地域+耐火建築物で制限がなくなり 10/10 となる 誤り5 1 × 法53条3項により、5/10に準防火地域+耐火建築物で+1/10となり6/10となる 誤り 2 〇 法53条3項により、6/10に防火地域+耐火建築物で+1/10となり7/10となる 正しい 3 × 法53条6項により、8/10の地域で防火地域+耐火建築物で制限がなくなり 10/10 となる 誤り 4 × 法53条3項により、5/10に準防火地域+準耐火建築物で+1/10となり6/10となる 誤り 5 × 法53条3項により、8/10に防火地域+準耐火建築物は緩和なしで8/10のまま 誤り6 1 × 法53条3項により、6/10に防火地域+耐火建築物で+1/10となり7/10となる 誤り 2 × 法53条3項により、6/10に準防火地域+耐火建築物で+1/10となり7/10となる 誤り 3 〇 法53条6項により、8/10の地域で防火地域+耐火建築物で制限がなくなり 10/10 となる 正しい 4 × 法53条6項により、8/10の地域で防火地域+耐火建築物で制限がなくなり 10/10 となる 誤り 5 × 法53条3項により、5/10に防火地域内外+準耐火建築物なので緩和なしで5/10のまま 誤り □ 建蔽率の計算問題 1 ③ 商:200㎡×8/10=160㎡、準:50㎡×6/10=30㎡ 計190㎡2 ③ 近:200㎡×8/10=160㎡、二:90㎡×6/10=54㎡ 計214㎡3 ③ 商:200㎡×8/10=160㎡、二:40㎡×5/10=20㎡ 計180㎡4 ③ 商:80㎡×8/10=64㎡、一:400㎡×6/10=240㎡ 計304㎡5 ① 商:240㎡×8/10=192㎡、準:120㎡×6/10=72㎡ 計264㎡6 ① 商:100㎡×8/10=80㎡、二:40㎡×5/10=20㎡ 計100㎡7 ⑤ 商:150㎡×10/10=150㎡、準:240㎡×7/10=168㎡ 計318㎡8 ④ 近:60㎡×7/10=42㎡、二:180㎡×6/10=108㎡ 計150㎡9 ⑤ 商:150㎡×10/10=150㎡、準:210㎡×7/10=147㎡ 計297㎡10 ③ 近:400㎡×10/10=400㎡、一:200㎡×8/10=160㎡ 計560㎡11 ③ 商:400㎡×10/10=400㎡、準:300㎡×8/10=240㎡ 計640㎡12 ③ 準:380㎡×8/10=304㎡、一:190㎡×7/10=133㎡ 計437㎡ 建蔽率の緩和規定(法53条3項、6項)の内容は、条文を見なくても判断できるようにしてくださいね。 必ず出る所です!!建蔽率の問題はこれで終わりです。次回は、集団規定の容積率に入っていきます。今日はこんな言葉です。 『ダメならダメでしようがない。 まずは思った通りにやってみよう。 そんな度胸のよさが人生を切り開いてくれることもあるのね。』 (小森 和子)
Sep 9, 2021
閲覧総数 1765
-
18
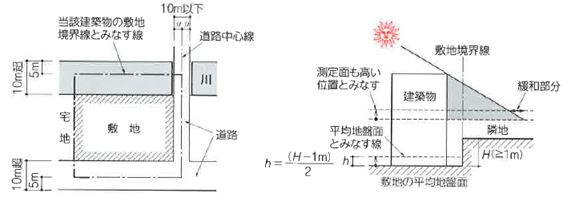
建築士の勉強!(法規編第59回)
第59回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。 (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 15.日影規制 日影規制の問題は、2級では必ず出題されますが、1級では融合問題の中で時々出る程度です。法56条の2や別表4での日影規制の基本的な考え方と政令の緩和規定をしっかり確認して下さい。 (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 15-1 法56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限) 法別表第4(日影による中高層の建築物の制限) 令135条の12(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等) (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 □ 日影規制1 第一種中高層住居専用地域内にある高さが10mを超える建築物は、平均地盤面からの高さ1.5m 又は4mのうちから地方公共団体が条例で指定する水平面に生じる日影について規制する。 (2級H16) 2 建築物の敷地が幅員10mを超える道路に接する場合においては、当該道路の反対側の境界線か ら当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。 (2級H15,H16,H25) 3 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1の建築物とみなし て、日影規制を適用する。(2級H16,H24) 4 建築物の敷地の平均地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、当該平均地盤面 は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなして、日影規制を 適用する。(2級H16) 5 日影規制の対象外にある高さ10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日 影を生じさせるものは、原則として、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制を 適用する。(2級H16,H19,H26) 6 第一種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を 除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。(2級H15) 7 日影規制の対象区域は、地方公共団体の条例で指定する。(2級H19) 8 第二種低層住居専用地域内においては、原則として、平均地盤面からの高さが4mの水平面に生 じる日影について規制する。(2級H19) 9 日影規制において、建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地 境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。(2級H20,H24,H30) 10 日影規制において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地で日影の生ずるものの地盤面(隣地に建 築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合、その建築 物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみ なす。(2級H20) 11 第二種低層住居専用地城内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階 を除く階数が3以上の建築物における、平均地盤面からの高さが4mの水平面に生じる日影につ いて規制する。(2級H21) 12 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物とみなし て、日影規制を適用する。(2級H21,H30) 13 日影規制における「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平 均の高さにおける水平面からの高さをいう。(2級H17,H22) 14 商業地域内にある高さが10mを超える建築物が、冬至日において、隣接する第一種住居地域 内の土地に日影を生じさせる場合は、当該建築物が第一種住居地域内にあるものとみなして、 日影規制を適用する。(2級H22,R01) 15 建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、当該道路の反対側の境界線から当 該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。 (2級H22,H29) 16 建築物の敷地の平均地盤面が隣地(建築物があるもの)又はこれに連接する土地(建築物がある もの)で日影の生ずるものの地盤面より1 m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平 均地盤面は原則として、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなして、日影規制を適 用する。(2級H22) 17 第一種中高層住居専用地域内にある高さが10mを超える建築物は、原則として、平均地盤面 からの高さが4m又は6. 5mのうちから地方公共団体が条例で指定する水平面に生じる日影に ついて日影規制を適用する。(2級H22) 18 日影規制を適用するか否かの建築物の高さの算定は、地盤面からの高さではなく、平均地盤面 からの高さによる。(2級H14,H23) 19 建築物の敷地の平均地盤面が隣地より1 m以上高い場合においては、当該平均地盤面は、当該 高低差から1mを減じたものの1/2だけ低い位置にあるものとみなして日影規制を適用する。 (2級H14) 20 日影規制の対象区域及び日影時間は、都市計画で定める。(2級H14) 21 建築物の敷地が道路に接する場合、原則として、当該道路の反対側の道路境界線を敷地境界 線とみ なして、日影規制を適用する。(2級H14,H18,H28) 22 第一種中高層住居専用地域内にある高さが10mを超える建築物は、全国どの区域内において も、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、地方公共団体が条例で 指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければなら ない。(2級H17) 23 第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階 を含む階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。(2級H17) 24 建築物の敷地が幅10mを超える道路に接する場合においては、当該道路に接する敷地境界線 は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。(2級H17) 25 用途地域の指定のない区域内においては、日影規制は適用しない。(2級H17,H23) 26 第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階 を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。(2級H24,H30) 27 日影規制において、地方公共団体が条例で、用途地域の指定のない区域を対象区域とし、軒の 高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物を指定した場合においては、平 均地盤面からの高さが4mの水平面に生じる日影について、日影規制を適用する。(2級H26) 28 日影規制において、建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずる ものの地盤面(隣地又はこれに連接する上地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれ に連接する土地の平均地表面)より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤 面は、当該高低差から1 mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(2級H26) 29 日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが 10m を超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが1.5mの水平面に生 じる日影について日影規制を適用する。(2級H29) 30 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤 面からの高さによる。(2級H30) 31 商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。(2級H27,H30) 32 第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限が適用さ れる。(2級R01) 33 用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で指定する区域について、日影規 制の対象区域とすることができるが、商業地域においては、日影規制の対象区域とすることが できない。(2級H25) 34 第二種低層住居専用地域内において、軒の高さが7mで地階を含む階数が3の建築物は、日影 規制は適用されない。(2級H27) 35 用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすること ができない。(2級R02) 36 第一種中高層住居専用地域内にある高さ10mを超える建築物において、特定行政庁が土地の 状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可し た場合は、日影規制は適用されない。(2級R02) 37 日影による中高層の建築物の高さの制限に適合しない建築物であっても、特定行政庁が土地の 状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した 場合においては、新築することができる。(1級H17) ***************************************************************** 解説 15-1 法56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限) 法別表第4(日影による中高層の建築物の制限) 令135条の12(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等) (条文は自分の法令集で確認して下さい。)法56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)1項 法別表4(い)欄に掲げる地域等で地方公共団体の条例で指定する区域において、(ろ)欄に 該当する建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時(北海道は午前9時から午 後3時)の間、(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平 距離が5mを超える範囲は(に)欄のうち地方公共団体が条例で定める時間以上日影となる 部分を生じさせてはならない。ただし、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合 等はこの限りではない。 2項 同一敷地内に2以上の建築物がある場合、これらを一つの建築物とみなして日影規定を適用 する。 3項 令135条の12に高低差等の緩和措置をしめす。 4項 日影の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日に対象区域内に日影を生じさ せるものは、当該対象区域にある建築物とみなして日影規制を適用する。 法別表第4(日影による中高層の建築物の制限)(い)欄:商業地域、工業地域、工業専用地域は日影規制は指定されない。 用途地域の指定のない区域でも日影規制は指定される。(ろ)欄(日影規制の対象建物の基準):軒の高さ、高さは地盤面から測った高さ(令2条1項六号 、2項 3mを超える傾斜がある場合は、3m毎の平均地盤面) 一低、二低、田園:軒高7m超又は地階を除く階数3以上 その他:高さ10m超(は)欄(日影の測定面):平均地盤面からの高さ(当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均 の高さにおける水平面からの高さ) 一低、二定、田園:1.5m その他:4m又は6.5m令135条の12(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等)3項 一号 建築物の敷地が道路、水面、線路敷等に接する場合は、敷地境界線はそれらの幅の1/2 だけ外側とする。ただし、当該道路等の幅が10mを超えるときは、当該道路等の反対 側の境界線から敷地側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。 二号 敷地の平均地盤面が隣地より1m以上低い場合は、当該高低差から1mを減じたものの 1/2だけ高い位置にあるものとする。 □ 日影規制1 × 法別表4(は)欄2項により、4m又は6.5mの水平面で測定する 誤り 2 〇 令135条の12 3項一号により、幅員10mを超える場合は、反対側の境界線から敷地側に 5mの位置を境界線とみなす 正しい 3 〇 法56条の2 2項により、同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらを一つの建築 物とみなして日影規制を適用する 正しい 4 〇 令135条の12 3項二号により、高低差の緩和は、当該高低差から1mを減じたものの1/2 だけ高い位置を平均地盤面とする 正しい 5 〇 法56条の2 4項により、対象区域外にある高さ10m超の建物で、冬至日に区域内に日影 を生じさせる場合は、当該区域内にあるものとして日影規制が適用される 正しい 6 〇 法別表4 (ろ)欄1項により、軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上の建築物は日影規 制を適用する 正しい 7 〇 法56条の2 1項により、日影規制の対象区域は、地方公団体が条例で指定する 正しい 8 × 法別表4 (は)欄1項により、平均地盤面から1.5mの水平面 誤り 9 〇 令135条の12 3項一号により、幅員10m以下の場合は、当該幅員の1/2だけ外側にあるも のとみなす 正しい 10 〇 令135条の12 3項二号により、高低差の緩和は、当該高低差から1mを減じたものの1/2 だけ高い位置を平均地盤面とする 正しい 11 × 法別表4 (は)欄1項により、平均地盤面から1.5mの水平面 誤り 12 × 法56条の2 2項により、同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらを一つの建築 物とみなして日影規制を適用する 誤り 13 〇 法別表4 欄外により、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位 置の平均の高さにおける水平面からの高さ 正しい 14 〇 法56条の2 4項により、対象区域外にある高さ10m超の建物で、冬至日に区域内に日影 を生じさせる場合は、当該区域内にあるものとして日影規制が適用される 正しい 15 〇 令135条の12 3項一号により、幅員10mを超える場合は、反対側の境界線から敷地側に 5mの位置を境界線とみなす 正しい 16 × 令135条の12 3項二号により、高低差の緩和は、当該高低差から1mを減じたものの1/2 だけ高い位置を平均地盤面とする 誤り 17 〇 法別表4 (ろ)(は)欄2項により、高さ10m超の建築物は日影規制を適用する。その 場合の測定面は、平均地盤面から4mまたは6.5mの水平面 正しい 18 × 令2条1項六号により、建築物の軒の高さ、高さは地盤面からの高さによる、平均地盤面で はない 誤り 19 × 令135条の12 3項二号により、高低差の緩和は、対象敷地が隣地より1m以上低い場合 が対象 誤り 20 × 法56条の2 1項により、日影規制の対象区域は、地方公団体が条例で指定する 誤り 21 × 令135条の12 3項一号により、幅員が10m以内と超える場合では異なる 誤り 22 × 法56条の2 1項( )書きにより、北海道は午前9時から午後3時まで、全国どこでも同 じ時間ではない 誤り 23 × 法別表4 (ろ)欄1項により、地階を除く階数3以上の建物が対象 誤り 24 × 令135条の12 3項一号により、幅員10mを超える場合は、反対側の境界線から敷地側に 5mの位置を境界線とみなす 誤り 25 × 法別表4 (い)欄4項により、用途地域の指定のない区域も日影規制の対象となる 誤り 26 〇 法別表4 (ろ)欄1項により、軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上の建築物は日影 規制を適用する 正しい 27 × 法別表4 (は)欄4項イにより、平均地盤面より1.5mの水平面 誤り 28 〇 令135条の12 3項二号により、高低差の緩和は、当該高低差から1mを減じたものの1/2 だけ高い位置を平均地盤面とする 正しい 29 × 法別表4 (は)欄4項ロにより、平均地盤面より4mの水平面 誤り 30 〇 令2条1項六号により、建築物の軒の高さ、高さは地盤面からの高さによる(別表4(ろ) 欄の数値) 正しい 31 〇 法別表4により、商業地域は指定されていない 正しい 32 〇 法56条1項三号により、一中、二中は除かれているが、一低は除かれていない、適用さ れる 正しい 33 〇 法別表4により、用途地域の指定のない区域は適用されるが、商業地域は指定されてい ない 正しい 34 〇 法別表4(ろ)欄1項により、軒の高さ7m超又は地階を除く階数3以上の建築物は日影規 制を適用する。地階を含む3階建は対象外となる 正しい 35 × 法別表4 4項により、用途地域の指定のない区域は適用される 誤り 36 〇 法56条の2 1項ただし書きにより、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合 は日影規制は適用されない 正しい 37 〇 法56条の2 1項ただし書きにより、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合 は日影規制は適用されない 正しい 日影規制は、主に2級で出題されます。政令の緩和規定はしっかり理解してください。 次回は、防火地域・準防火地域の規制です。以前2級を中心に紹介して1級を入れていなかったので改めてやります。 今日は、こんな言葉です。 『あなたに出来ること、 出来ると夢見たことが何かあれば、 それらを今すぐ始めなさい。 向こう見ずは天才であり、魔法であり、力です。 さぁ、今すぐ、始めなさい。』 (ゲーテ)
Sep 21, 2021
閲覧総数 1112
-
19
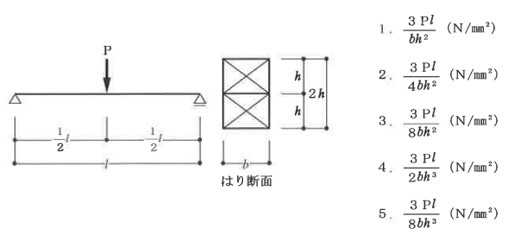
建築士の勉強!第96回(構造力学編第6回 応力度)
構造力学編第6回(応力度)建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に1級問題を見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 構造-18 構造の問題は大きく構造力学(計算問題)と各種構造・建築材料(文章問題)に分かれます。ここでは、計算問題と文章問題を交互に紹介していきます。 構造(力学)6 応力度 今回は応力度の問題です。軸応力度、曲げ応力度、せん断応力度の公式はしっかり覚えて下さい! ************************************************** 問題 □ 応力度(2級) 1 図のような荷重P(N)を受ける長さℓ(㎜)、断面b(㎜)×2h(㎜)の単純ばりに生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、はりを構成する二つの材は、それぞれ相互に接合されていないものとし、はりの自重は無視するものとする。(2級H14) 2 図のような二か所に荷重P(N)を受ける長さℓ(㎜)、断面b(㎜)×h(㎜)の単純ばりのA点に生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、はりの自重は無視するものとする。(2級H15) 3 図のような長方形断面を有する木造のはりのX軸について許容曲げモーメントとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、はり材の許容曲げ応力度は、18N/㎟とする。(2級H16) 4 図のような荷重Pを受ける単純梁にA、Bの部材を用いる場合、二つの部材それぞれの許容曲げモーメントの大きさが等しくなる場合の部材Bの幅xの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材A、Bはともに同じ材料とし、自重は無視するものとする。(2級H17)5 図のような図のような荷重Pを受ける単純梁に断面100㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材が許容曲げモーメントに達するときの荷重Pの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の許容曲げ応力度は20N/㎟とし、自重は無視するものとする。(2級H19) 6 図のような荷重を受ける、スパンが等しく断面の異なる単純梁A及び単純梁Bにおいて、CA点、CB点に生じる最大曲げ応力度をそれぞれσA、σBとしたとき、それらの比σA:σBとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、単純梁に用いる部材はいずれも同じ材料とし、自重は無視するものとする。(2級H20)7 図のような荷重を受ける単純梁に、断面60㎜×100㎜の部材を用いた場合、その部材に生じる最大曲げ応力度の大きさと最大せん断応力度の大きさとの組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の自重は無視するものとする。(2級H21)8 図のような荷重を受ける単純梁に、断面120㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材が許容曲げモーメントに達するときの荷重Pの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の許容曲げ応力度は20N/㎟とし、自重は無視するものとする。(2級H23)9 図のような荷重を受ける単純梁に、断面100㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材に生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の自重は無視するものとする。(2級H24)10 図のような長方形断面を有する木造の梁のX軸についての許容曲げモーメントとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、梁材の許容曲げ応力度は、12N/㎟とする。(2級H25)11 図のような等分布荷重を受ける単純梁に断面75㎜×200㎜の部材を用いた場合、A点の最大曲げ応力度が1N/㎟となるときの梁の長さℓの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。(2級H26)12 図のような等分布荷重を受ける単純梁に断面100㎜×300㎜の部材を用いた場合、A点に生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。(2級H27)13 図のような荷重を受ける単純梁に、断面90㎜×200㎜の部材を用いた場合、A点の断面下端に生じる縁応力度σとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、縁応力度σは下式によって与えられるものとし、部材の断面は一様で、荷重による部材の変形及び自重は無視するものとする。(2級H28)14 図のような等分布荷重を受ける単純梁に断面100㎜×200㎜の部材を用いた場合、A点に生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。(2級H29)15 図のような荷重を受ける単純梁に、断面90㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材が許容曲げモーメントに達するときの荷重Pの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の許容曲げ応力度は20N/㎟とし、自重は無視するものとする。(2級H30)16 図のような荷重を受ける単純梁に断面100㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材に生ずる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の自重は無視するものとする。(2級R01)17 図のような等分布荷重wを受ける長さℓの片持ち梁に断面b×hの部材を用いたとき、その部材に生ずる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の自重は無視するものとする。(2級R02)18 図のような等分布荷重を受ける単純梁に断面120㎜×150㎜の部材を用いた場合、A点の最大曲げ応力度が1N/㎟となるときのℓの値として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の断面は一様とし、自重は無視するものとする。(2級R03)19 図のような荷重を受ける断面100㎜×200㎜の部材を用いた場合、その部材に生じる最大曲げ応力度として、正しいものは、次のうちどれか。ただし、部材の自重は無視するものとする。(2級R04) □ 組み合わせ応力度(1級) 1 図-1のような荷重を受ける鉄骨構造による門形ラーメンにおいて、曲げモーメント及び柱脚の反力が図-2のように求められている。曲げと軸方向力の組み合わせにより、柱の断面A-Aに生じる圧縮応力度の最大値に最も近いものは、次のうちどれか。ただし、条件は、イ~ニのとおりとする。(1級H15)2 図-1のような底部で固定された矩形断面材の頂部の図心G点に荷重P及び荷重Qが作用するときの底部a-a断面における垂直応力度分布が図-2に示されている。PとQの組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、矩形断面材は等質等断面材とし、自重はないものとする。(1級H17)3 図-1のような鉄骨骨組みについて、図-2に鉛直荷重時の曲げモーメントと柱脚反力、図-3に地震による水平荷重時の曲げモーメントと柱脚反力を示している。地震時に柱に生じる短期の「圧縮応力度と圧縮曲げ応力度の和」の最大値として、最も適当なものは、次のうちどれか。ただし、柱は、断面積A=1.0×10⁴㎟、断面係数Z=2.0×10⁶㎜³とし、断面検討用の応力には接点応力を用いる。(1級H22) 4 図-1のような底部で固定された矩形断面材の頂部の図心G点に鉛直荷重P及び水平荷重Qが作用するときの底部a-a断面における垂直応力度分布が図-2に示されている。PとQの組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、矩形断面材は等質等断面で、自重は考慮しないものとする。(1級H26)5 図-1のように、脚部で固定された柱の頂部に鉛直荷重N及び水平荷重Qが作用している。柱の断面形状は図-2に示すような長方形断面であり、鉛直荷重N及び水平荷重Qは断面の重心に作用しているものとする。柱脚部断面における引張縁応力度と圧縮縁応力度との組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、柱は等質等断面とし、自重は無視する。また、応力度は弾性範囲内にあるものとし、引張応力度を「+」、圧縮応力度を「-」とする。(1級H29)6 図-1のように、脚部で固定された柱の頂部に、鉛直荷重N及び水平荷重Qが作用している。柱の断面形状は図-2に示すような長方形断面であり、N及びQは断面の図心に作用しているものとする。柱脚部断面における引張縁応力度、圧縮縁応力度及び最大せん断応力度の組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、柱は全長にわたって等質等断面の弾性部材とし、自重は無視する。また、引張応力度を「+」、圧縮応力度を「-」とする。(1級R03)*************************************************** 解説 □ 応力度 ① 軸方向力による応力度 σ=N/A (N:軸方向力、A:断面積)② 曲げモーメントによる応力度 σc=σt=M/Z (M:曲げモーメント、Z:断面係数)③ せん断力による応力度 長方形断面の最大せん断応力度 τmax=1.5×Q/A (Q:せん断力、A:断面積)④ 代表的な最大曲げモーメント ⑤ 代表的な最大せん断力⑤ 許容曲げモーメント(Ma)=許容曲げ応力度(fb)×断面係数(Z) ここから、荷重を求める問題、部材の長さを求める問題、部材の断面寸法を求める問題など が出題されている□ 応力度(2級)1 σbmax=Mmax/Z Mmax=Pℓ/4 Z=bh²/6×2=2bh²/3 σbmax=(Pℓ/4)/(bh²/3)=3Pℓ/4bh² 正解 2番2 σA=MA/Z MA=Pℓ/6 Z=bh²/6 σA=(Pℓ/6)/(bh²/6)=Pℓ/bh² 正解 1番 3 Ma=fb×Z fb=18N/㎟ Z=120×200²/6=8×10⁵㎜³ Ma=18×(8×10⁵)=144×10⁵N㎟=14400Nm 正解 5番4 A、B材の許容曲げモーメントが等しいとは、Ma=fb×Zb=fb×ZBとなり、A,Bが同じ 材料なのでfbが等しく、ZA=ZBとなるので、ここからxを求める。 ZA(60×400²)=ZB(x×200²) x=240㎜ fa=18N/㎟ Z=120×200²/6=48×10⁵㎜³ Ma=18×(48)×(48×10⁵)=144×10⁵N㎟=14400Nm 正解 2番5 Ma=fb×Z fb=20N/㎟ Z=100×200²/6=2×10⁶/3㎜³ Ma=2P/3×1000=2000P/3N㎟ 2000P/3=20×(2×10³/3)より、P=20×10³N=20KN 正解 4番 6 σA=MA/ZA MA=2.5×1=2.5KNm=2.5×10⁶N㎜ ZA=100×200²/6=4×10⁶/6㎜³ σA=(2.5×10⁶)/(4×10⁶/6)=15/4 σB=MB/ZB MA=7.5×1=7.5KNm=7.5×10⁶N㎜ ZB=100×300²/6=9×10⁶/6㎜³ σB=(7.5×10⁶)/(9×10⁶/6)=45/9 σA:σB=15/4:45/9=3:4 正解 4番 7 σbmax=Mmax/Z Mmax=6×2=12KNm=12×10⁶N㎜ Z=60×100²/6=1×10⁵㎜³ σbmax=(12×10⁶)/(1×10⁵)=120N/㎟ τmax=1.5×Q/A Q=6KN=6×10³N A=60×100=6×10³㎟ τmax=1.5×(6×10³)/(6×106³)=1.5N/㎟ 正解 5番8 Ma=fb×Z fb=20N/㎟ Z=120×200²/6=8×10⁵㎜³ Ma=P×1=PKNm=P×10⁶N㎜ P×10⁶=20×(8×10⁵)=16×10⁶より P=(16×10⁶)/10⁶=16KN 正解 5番9 σbmax=Mmax/Z Mmax=12KNm=12×10⁶N㎜ Z=100×200²/6=2×10⁶/3㎜³ σbmax=(12×10⁶)/(2×10⁶/3)=18N/㎟ 正解 2番10 Ma=fb×Z fb=12N/㎟ Z=100×300²/6=3×10⁶/2㎜³ Ma=12×(3×10⁶/2)=18×10⁶N㎜=18KNm 正解 4番11 σbmax=Mmax/Z Mmax=4×ℓ²/8=ℓ²/2N㎜ Z=75×200²/6=5×10⁵㎜³ 1N/㎟=(ℓ²/2)×(5×10⁵) ℓ²=1×10⁶より、ℓ=1×10³=1000㎜ 正解 1番 12 σA=M/Z M=6000N×500㎜=3×10⁶N㎜ Z=100×300²/6=3×10⁶/2㎜³ σA=(3×10⁶)/(3×10⁶/2)=2N/㎟ 正解 2番 13 σ=N/A±M/Z N=+36KN=36×10³N A=90×200=18×10³㎟ M=9KNm=9×10⁶N㎜ Z=90×200²/6=6×10⁵㎜³ N/A=(36×10³)/(18×10³)=2N/㎟ M/Z=(9×10⁶)/(6×10⁵)=15N/㎟(上からの荷重に対して断面下端の縁応力度 なので、+) σ=2+15=17N/㎟ 正解 2番14 σA=M/Z M=6×4²/8=12KNm=12×10⁶N㎜ Z=100×200²/6=2×10⁶/3㎜³ σA=(12×10⁶)/(2×10⁶/3)=18N/㎟ 正解 4番15 Ma=fb×Z Ma=1.5P×3000-P×1500=3000P fb=20N/㎟ Z=90×200²/6=6×10⁵㎜³ 3000P=20×(6×10⁵)より P=120×10⁵/3000=4000N=4KN 正解 2番 16 σ=M/Z M=5×4=20KNm=20×10⁶N㎜ Z=100×200²/6=2×10⁶/3㎜³ σ=(20×10⁶)/(2×10⁶/3)=30N/㎟ 正解 1番 17 σ=M/Z M=wℓ²/2 Z=b×h²/6=bh²/6 σ=(wℓ²/2)/(bh²/6)=3wℓ²/bh² 正解 1番18 σ=M/Z σ=1N/㎟ M=10ℓ²/8 Z=120×150²/6=45×10⁴ 1=(10ℓ²/8)/(45×10⁴)より、ℓ=600㎜ 正解 2番19 σ=M/Z M=8×2=16KNm=16×10⁶N㎜ Z=100×200²/6=2×10⁶/3 σ=(16×10⁶)/(2×10⁶/3)=24×10⁶N㎜=24KNm 正解 2番 □ 組み合わせ応力度 ① 軸応力度(N/A)と曲げ応力度(M/Z)の組み合わせ□ 組み合わせ応力度(1級) 1 σ=-N/A-M/Z M図より、NとMを求める。 柱右N=-120KN=120×10³N A=6×10³㎟ A点のM=20×2.5=50KNm=50×10⁶N㎜ Z=5.0×10⁵㎜³ σ=-(120×10³)/(6×10³)-(50×10⁶)/(5.0×10⁵) =-20-100=-120N/㎟(圧縮応力度) 正解 5番 2 σ=-N/A±M/Z N=P A=BD M=Qℓ Z=BD²/6 応力度の分布左側-N/A+M/Z=0---① 応力度の分布右側-N/A-M/Z=-σ---② ①+②=2N/A=σ より、Pを求める。2P/BD=σ P=BDσ/2 ①-②=2M/Z=σ より、Qを求める。 (2Qℓ)/(BD²/6)=σ Q=σBD²/12ℓ 正解 5番3 σ=-N/A-M/Z 柱右N=-100+(-100)=-200KN=200×10³N㎜ A=1.0×10⁴㎟ 柱右柱頭M=100+200=300KNm=300×10⁶N㎜ Z=2.0×10⁶㎜³ N/A=(200×10³)/(1.0×10⁴)=20N/㎟ M/Z=(300×10⁶)/(2.0×10⁶)=150N/㎟ σ=-20-150=-170N/㎟(圧縮側の最大値) 正解 3番 4 σ=-N/A±M/Z N=P A=BD M=Qℓ Z=BD²/6 応力度の分布左側-N/A+M/Z=-σ---① 応力度の分布右側-N/A-M/Z=-2σ---② ①+②=2N/A=3σ より、Pを求める。2P/BD=3σ P=3BDσ/2 ①-②=2M/Z=σ より、Qを求める。 (2Qℓ)/(BD²/6)=σ Q=σBD²/12ℓ 正解 3番5 σ=-N/A±M/Z N=120KN=120×10³N A=200×300=60×10³㎟ M=15×2=30KNm=30×10⁶N㎜ Z=200×300²/6=3×10⁶㎜³ N/A=(120×10³)/(60×10³)=2N/㎟ M/Z=(30×10⁶)/(3×10⁶)=10N/㎟ 応力度の分布左側(引張縁)=-2+10=8N/㎟ 応力度の分布右側(圧縮縁)=-2-10=-12N/㎟ 正解 2番6 σ=-N/A±M/Z N=240KN=240×10³N A=200×300=60×10³㎟ M=30×2=60KNm=60×10⁶N㎜ Z=200×300²/6=3×10⁶㎜³ N/A=(240×10³)/(60×10³)=4N/㎟ M/Z=(60×10⁶)/(3×10⁶)=20N/㎟ 応力度の分布左側(引張縁)=-4+20=16N/㎟ 応力度の分布右側(圧縮縁)=-4-20=-24N/㎟ τmax=1.5Q/A Q=30KN=30×10³N τmax=1.5×(30×10³)/(60×10³)=0.75N/㎟ 正解 2番 2級では、曲げ応力度、許容曲げモーメントの公式を理解した上で、それを変形してスパンや荷重を求める問題まで出題されています。1級では、曲げ応力度とせん断応力度の組み合わせ問題が出題されるので、解法手順をしっかり理解したいですね!!次回も計算問題から、座屈を紹介します。 今日はこんな言葉です! 『今度こそ!でも、うまくいかない時は今度こそ!誰よりもたくさん挑戦した人がうまくいく。』 (福島正伸)
Dec 25, 2022
閲覧総数 4205
-
-

- ささやかな幸せ
- 今日も彩雲を目撃しました。週3回ペ…
- (2025-11-23 22:21:24)
-
-
-

- handmadeのある暮らし。
- ☆木の紙でつくる箸置き☆
- (2025-10-15 19:03:58)
-
-
-

- 風水について
- クリスマス・ディスプレイで波動を変…
- (2025-11-24 20:57:21)
-







