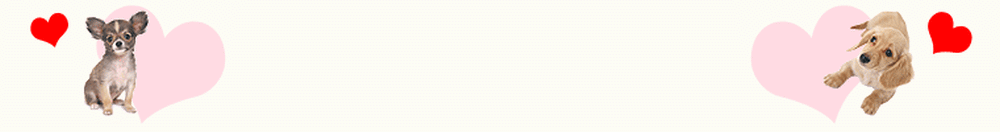60年前の状況で作られた憲法が現代でも通用するなんて考えるほうがどうかしている。平和憲法なんていっても、拉致問題や、中国の領土侵犯や外国人犯罪のように、日本が一方的に犠牲と我慢を強いられてきただけです。
つまり、激変した国際状況に対応できなければ一方的に状況に振りまわされて利用されたり陵辱されるだけなのです。
それを思い知った多くの国民により、日本の行動原則、憲法の改正が求められているのです。
というわけでトラックバックを送ってきた方への反論。
http://anti-yomiuri.seesaa.net/article/1069637.html
為政者の側から「憲法改正」などという声が出てくること自体がおこがましい。主権者は国民であり、国民の中で「憲法を改正して自らの主権を拡張すべき」と考えたとき、初めて憲法改正の必要性が議論されてもよいのである。
この方は知らないようですが、現憲法は公布直後から改正論が議論されてきました。憲法前文の醜い悪文や、回りくどく難解な言い回しをはじめとして数多くの議論が繰り返されてきています。
国家と国民は協力し合うような関係ではない。国家は「全体の奉仕者」である公務員の集合体であり、その行動は国民によって規定される。主権者は国民なのである。国家を国民と同列に置き、「役割分担」を求めるなど誤解も甚だしい。しかし、読売が発表した憲法草案では国民に憲法擁護義務を課すなど、権利制限の方向を明確にしている。このような逆流に我々主権者が押し流されるようなことがあってはならない。
国家を形作っているのは国民です。公務員も権力者も国民なのです。
また、国民と国家は同列です。同列だからこそ国民は国家に物申すことができますし、国家は国民の意見を聞くのです。
国家と国民の関係は上下関係ではありません。互いに権力を負託し、支配したりされたりのフィードバック系を形作っています。
憲法改正も権力
前文の部分で「利己主義を排し、『社会連帯、共助』の観点を盛り込むべき」とある。一見良さそうに見える言葉だが、米国の利己主義に世界一迎合しているのはどこの政府か。自国民が外国で拘束された時、全力で救出にあたらなかった政府が「社会連帯」をいうのは、「国民同士で勝手にやってくれ」という責任放棄ではないのか。
国家とは利己的な存在です。自国の利益を確保しなければ、自国民が犠牲になるからです。アメリカの青年の命によって守られてきた自由市場で莫大な利益をあげてきた日本も同じです。
ていうか、国家戦略は国益をいかに確保するかという面で考えるべきことであり、憲法の内容で拘束されてはいけません。
憲法で国家戦略を拘束した結果が、拉致問題であり、中国へのODAであり、竹島などの領土問題です。
「日本は戦争をしません。」この宣言を聞いた他国はそれならば、とその弱みにつけこもうとするだけです。
憲法とは、国内でのみ力を持つ「法」にすぎません。
「非常事態全般」として災害と有事(=戦争)を故意に同一視する。「公共的な責務」として国家への貢献を要請する。両性の平等を敵視する。社会権(25条、文化的生存権)を守るためと称して国民に責任を負わせ、結果として国家の責任を免罪する。「政治主導の政策決定を徹底」として国民主権を制限。大臣の国会出席義務を緩和し、国会を政府から切り離す。首相の権利を強化し元首的性格を強める。地方自治の推進と称して国家の責任を放棄する。
国家の責任てなんでしょうか?
民主主義では、国民から権利と税金をもらい、国民の意思を実行することが国家の責任です。それ以上の期待は過大というものです。
自分の面倒は自分で見ることが民主主義国家を構成するために必要な人間の資質です。
そして、「改正手続き」の緩和である。現在は国会の2/3が賛成する議決によって初めて憲法改正の提案ができ、さらに国民の承認を得る必要がある。これを、国会の1/2で提案できるように、さらには2/3の賛成ならば国民の意思を問わず改正できる方向を狙っている。もしもこれが実現すれば、「国会で多数さえ占めることができれば」クーデターを起こすことができるわけである。
はい出ました。護憲派の「憲法を改正するのは絶対悪」妄想ですね。国会で多数を占めることができれるなら、クーデーターを起こす必要はありません。通常の手続きで法案を通せばいいのですから。
法律というものは、機械やソフトと同じで実際に使ってみなければ分からない欠陥があるものです。そういった欠陥を素早く修正するには、改正手続きは簡便にしたほうが良いのです。そして多くの国民も選挙で自ら選んだ政治家をそれなりに信頼してもいるのです。
何が「独自憲法」か。憲法改悪を最も望んでいるのは米国ではないのか。改憲に熱心な者ほど対米従属の姿勢が見えるのはなぜか。
あなたの妄想ですよ。ロシア、中国、韓国、アメリカ。日本を囲む国々の中で、法の支配が行き届き、世界最大の軍事力と経済力を持つアメリカの人気が高いのは当然です。
ところで、護憲に熱心な人ほど日本人の自由意志を否定する姿勢が見えるのはなぜでしょうか?
憲法は神聖でもなければ、尊いものでもありません。よりよく便利に楽に生活を送るための道具です。時代や状況に合わせて変更し、国民の行動を豊かに広げていくべきだと思います。
我々が60年も前の人間の意志に縛られる必要は無いのです。
自民党の憲法改正案がひどいって!?
そりゃあ、当然です。ここ数十年間、憲法を作ってこなかったのですから。どのような技術も使われなければ廃れ衰えていきます。60年も経てば、それを引き継ぐ人材も消失してしまうのですから。
憲法改正の手続きを簡易化するのは、日本の法制の開発能力を維持する必要からも重要です。
それでも、現憲法の英文翻訳調の文章よりはマシだと思いますけどね。
子供には正しく美しい文章を教えたいものです。
ま、日本のエスタブリッシュによる威力偵察や観測気球なんでしょうけどね。
もしそうならば、批判ではなく、よりよい案を出す必要があります。「戦前に戻る!」やら「平和憲法の精神が!」とか叫びながら自慰にふけっていてはいけませんよ。 心当たりのある方々>
PR
キーワードサーチ
コメント新着
フリーページ