全50件 (50件中 1-50件目)
1
-

●高音質ライブ録音で聴く! 小澤&SKO、白熱のマーラー「復活」
●高音質ライブ録音で聴く! 小澤&SKO、白熱のマーラー「復活」マーラー:交響曲 第2番 ハ短調「復活」 小澤征爾 指揮 サイトウ・キネン・オーケストラ 菅 英三子(ソプラノ)、ナタリー・シュトゥッツマン(コ ントラルト)晋友会合唱団(関屋 晋:合唱指揮) 録音:2000年1月 東京文化会館(ライヴ) 27歳の時、上野の東京文化会館で初めてこの曲を聴いた。(渡邊暁雄指揮/日本フィル)そのときの感動が忘れられず、レコードやCD、ビデオで数々の異なる指揮者の演奏を聴いてきた。実際に聴いた日本フィルのライブ盤、定番のズービン・メータ、ショルティ、バーンスタイン、アバド…etc。その中で、最高の録音を選べと言われたら、即座にこの小澤/SKOのディスクを挙げる。 第1楽章冒頭のコントラバスの重低音に始まり、90分に及ぶ大曲にもかかわらず、指揮者、オケメンバーの集中力は一時たりとも途切れない。その緊張感と鳴り響く《音エネルギー》に終始圧倒される。ライブ録音だが、音の分離も定位もいい。東京文化会館は、もともと残響が少ないホール。そのため録音された音は混濁することなく実にクリアー。それぞれの楽器音も明瞭に聴きとることがきる。音の分離、定位も秀逸で指折りの超優秀録音に仕上がっている。 聴き所は、まず第4楽章に登場するナタリー・シュトゥッツマンの歌声。コントラアルトの深い響きは曲の雰囲気にぴったりとはまる。この声を聴いてしまうと、どんなにうまいアルト歌手の声でこの曲を聴いても物足りなく感じてしまう。これに続く最終第5楽章はさらに感動的。合唱が入ってくるところから、最終盤、オケ、ソロ歌手、合唱がひとつになって鳴り響く盛り上がりは、まさに圧巻。パイプオルガンが加わり、教会の鐘のようにベルがなる。全身全霊を込めながらタクトを振る小澤さんの姿が目に浮かぶ。情熱的なマエストロの姿を思い浮かべつつフィナーレを聴いていると、思わず涙がこみ上げてくる。音楽が終わるとホールは、拍手と歓声に満ちあふれ、「ブラボ~!」の嵐。この演奏を生で聴いた音楽ファンはなんと幸福なことか。音だけですが、ぜひ、この感動を味わってください。 なお、Youtubeで1995年、長崎の浦上天主堂で行われた小澤さんタクトの《「復活」コンサート》が視聴できます。(オケは新日本フィル)画質は悪いが、こちらも是非ご覧あれ!(YouTube「小澤征爾、長崎ライブ」で検索)
2024/03/02
コメント(1)
-
都合により、しばらくおやすみします。
都合により、しばらくおやすみ致します。復活の時には、またよろしくお願いします。
2004/11/18
コメント(5)
-
●今日は文化の日「太宰の住んでいた町」
●今日は文化の日「太宰の住んでいた町」私の家から脇道を一本入って20メートルほど歩いた場所に、小さな石碑が建っている。戦前、この場所に新婚間もない太宰治が妻・美智子と8ヶ月ほど暮らした家があった。石碑は、その記念として大分前に建てられたものだ。太宰治の命日「桜桃忌」(6月19日)には、近所の神社に太宰ファンが集まるのが恒例になっている。太宰が、新居をこの町に定めた理由は至極単純で、近所に酒屋、煙草屋、豆腐屋という、彼の生活に不可欠な店が揃っていたからだという。酒と煙草は太宰らしくてわかる気がする。では豆腐がどうして欠かせないかというと、実は太宰は歯が悪く、堅い食べ物は苦手だったらしい。そこで好んで豆腐を食べていたという。妻・美智子の回想には、こんなことが書かれている。「太宰は毎日午後三時頃まで机に向かい、それから近くの喜久之湯に行く。その間に支度しておいて、夕方から飲み始め、夜九時頃までに、六、七合飲んで、…ご当人は飲みたいだけ飲んで、ぶっ倒れて寝てしまうのである…」豆腐を肴に日本酒を煽る太宰の姿が目に浮かぶ。酒と煙草と文学と女‥‥。男としては、心のどこかでこういう破滅的な生き方に憧れてしまう。太宰がこの町に住んでいたのは、もう60年以上も前のはなし。町の風景もすっかり変わってしまった。太宰が通ったでいた煙草屋も豆腐屋もいまはなく、跡地は駐車場になっている。酒屋と銭湯は、建物は違うがいまでも商売を続けている。この銭湯には、太宰と親しかった井伏鱒二も一緒に通ったと言われている。おそらく一風呂浴びた後は、豆腐で一杯ということになったのだろう。太宰が住んでいた家の跡地には、いま小さな白いマンションが建っている。我が家の二階から、その建物が見える。私が子ども頃、その場所には確か古い日本家屋が建っていたはずだ。父の話では、その家は戦前からそこにあったようなので、おそらく太宰が暮らしていた家だったのだろう。幼い頃、私は毎日のようにその古い家の前を通って、近所の神社に遊びに行っていた。しかし、その家が古い家だったというだけで、平屋だったのか二階建てだったのかさえよく憶えていない。ましてや、子供だっだから、そこに文豪・太宰治がかつて住んでいたことなど知るよしもなかった。秋の夕暮れははやい。いつの間にか、部屋がオレンジに染まっている。窓の向こうに、はるか遠く八ヶ岳の稜線が見える。-----------------------------------------------◆クイズ◆『さて、この町はどこでしょう?」-----------------------------------------------
2004/11/03
コメント(5)
-
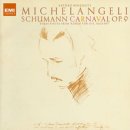
●シューマンの好きの試金石
●シューマンの好悪の試金石クララとの結婚の年を境に、シューマンは歌曲を創作の中心に置くようになり、ピアノ曲はほとんど書かなくなった。ピアニストのコルトーの講演によれば、これはクララがシューマンのピアノ曲の真の価値をほとんど理解出来なかったことが原因らしい。クララの演奏はとてもアカデミックで冷たいものだったというのが、定説になっている。しかし、レコードもCDも世の中に存在しない時代の話だから、確かめようもない。実際、クララが好んだシューマンのピアノ曲はごくわずかだったらしい。それは、「謝肉祭」とシューマンの最高傑作「幻想曲」。ただし「幻想曲」は第2楽章しか理解できなかったと言われている。シューマン好きなら、どうしてと思われるだろう。「幻想曲」の第1、第3楽章はロマン派のピアノ曲の中でも屈指の出来映えの曲のはず。それを理解できないなんて‥‥。実は、私はシューマンのピアノ曲の中で、「謝肉祭」はほとんど聴かないし、「幻想曲」の第2楽は余り好きではない。素人なので音楽理論的にはわかならいが、聞こえてくる響きがどうもシューマンらしくないのだ。あまりにもメロディが立ちすぎているようにきこえる。「謝肉祭」は、確かに派手でピアニストとしては演奏しがいがありそうだが、どうも音楽として単純で薄っぺらい感じがする。「幻想曲」も、第1楽章や第3楽章のシューマン独特の幻想的な雰囲気にくらべ、第2楽章はあまりにもメロディアスだ。《シューマンが本当に好きなら、「謝肉祭」はあまり評価しないだろう。》というのが、独断と偏見による私の個人的意見。さて、あなたはシューマンの「謝肉祭」はお好きですか?◆◆私のお薦め◆◆------------------------------------------ 1.「子供のためのアルバム」op.68~第38曲 冬の季節1/第37曲 水夫の歌2.謝肉祭op.9「子供のためのアルバム」op.68~第39曲 冬の季節2★演奏:アルトゥール・ベネデッティ・ミケランジェリ(ピアノ)---「謝肉祭」の名盤としては、他にルーヴィンシュタイン盤、シュケナージ盤などがある。どちらも持ってはいるが、やはりこのミケランジェリの演奏はスゴい。ミケランジェリは、謝肉祭の前に「子供のためのアルバム」から1曲、そして間に2曲挿入する形で録音している。(意図は不明)----------------------------------------------------------- 1.ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第17番ニ短調op.31-2「テンペスト」2.シューマン:幻想曲ハ長調op.17★演奏:スヴャトスラフ・リヒテル(ピアノ)----リヒテルのシューマンは、「幻想小曲集」「交響的練習曲」など名盤が多いが、この「幻想曲」はすべてのリヒテルの録音の中でも屈指の名演だと思う。特に第3楽章は一度聴いたらリヒテルのシューマンの虜になるはず。もちろん「テンペスト」もすばらしい。リヒテルは苦手という人には、ブレンデル盤がお薦め。
2004/11/01
コメント(8)
-

●日曜日のジャズ~キャノンポールを聴く♪~
日曜日の午後にモダンジャズが相応しいか、はなはだ疑問だが、今日はキャノンポール・アダレイのアルトSAXを聴いた。アルバムタイトルは、“KNOW WHAT I MEAN?”1961年の録音だ。----------------------------------------------------“KNOW WHAT I MEAN?”CANNONBALL ADEERLEY WITH BILL EBANS TRIO〔REVERSIDE〕VDJ-1518_____1961.1.27----------------------------------------------------キヤノンボール・アダレイは、言わずと知れたモダンジャズの巨人のひとり。キャノンボールは、あだ名で「砲弾」の意、スラングで「大食らい」という意味もあるとか。本名はジュリアン・アダレイ。ジュリアンじゃね~。キャノンボールにして大正解でしょう!アダレイは、巨漢の黒人という容貌からは想像できないほど、繊細で知的な男だったという。彼の最高傑作とされるのは、マイルス・デイヴィスと組んだアルバム「サムシング・エルス」。ジャズに詳しくない人でも、このアルバムの第1曲目「枯葉」は一度くらい聴いたことがあるはずだ。マイルスのトランペットがあまりにもすばらしいので、「サムシン・エルス」をマイルスのリーダーアルバムと誤解されている方もいるかも知れない。しかし、「サムシン‥‥」は紛れもないアダレイのリーダーアルバムなのだ。この“KNOW WHAT I MEAN?”も、バックが抒情派ジャズピアノのビル・エヴァンストリオということで、私の街のCDショップでは、エヴァンスの棚に入っていた。しっかり、CDの帯には「キャノンボール・アダレイ with ビル・エヴァン」と書かれているのにね‥‥。まあ、マイルスやエヴァンスに比べればアダレイは影が薄い。しかし、一度、アダレイのサックスを聴けば、その名人芸に即やられるはずだ。“KNOW WHAT I MEAN?”は、アダレイがリバーサイドレーベルに残した名盤中の名盤。モダンジャズのサックスプレイを聴くなら、まずこのアルバムを薦める。アダレイのサックスとエヴァンスのピアノの掛け合いが見事。モダンジャズの巨人2人が、競う合うように白熱の名演を聴かせてくれる。---------アルバムのトップを飾るのは、エヴァンスの十八番“WALTZ for DEBBY”。冒頭のエヴァンスの短いソロに続いて、アダレイの明るいアルトが入ってくる。そのフレージングのうまさ、スイング感は超一級品!さすがのエヴァンスのピアノプレイも、オーソドックスでちょっぴり控え目。エヴァンス作の名曲にもかかわらず、アダレイのサックスの完勝。----2曲目“GOODBYE”はベニー・グッドマンのクロージングテーマ。バーボンとマルボロが欲しくなる、リリカルな大人のジャズバラードだ。こういうリリシズムは、もやはエヴァンスの独壇場。アダレイも負けじといい音で歌ってくれるが、この曲はエヴァンスの技あり1本といったところか。----3曲目“Who cares ?”はガーシュインの名曲。ここでは、アダレイのファンキーなプレイが冴えを見せる。エヴァンスはサポートに徹している感じ。アダレイの勝ち。----4曲目“Venice”。アダレイもエヴァンスもリラックスした軽いプレイで、一時休戦。引き分けというところか。----5曲目“Toy”はアダレイのサックスプレイが乗りに乗っている。サックスプレイの醍醐味を味わうという意味では、このアルバムのハイライトと言ってもいいかも。エヴァンスも後半でいいソロを聴かせるがアダレイのプレイに圧倒されてちょっと控え目。この曲はアダレイの完勝でしょう。----6曲目“ELSA”は、エヴァンス好みのリリカルなナンバー。アダレイもムーディなサックスプレイを聴かせるが、曲のイメージは完全にエヴァンスの世界。ここはエヴァンスに軍配が上がる。----7曲目“NANCY”は、ジミー・バン・ヒューゼンがフランク・シナトラの娘ナンシーの誕生を祝って作曲したバラード。アダレイがしっとりと歌えば、エヴァンスがリリカルに応える。ふりたの演奏は、背筋がゾクっとするほど艶っぽい。いいぞ、いいぞ、サイコ~!シナトラの歌やコルトレーンの名演もあるらしいけど、エヴァンス・アダレイ組の演奏には叶うまい。二人の闘いとしては引き分けってところ。----8曲目、ラストはアルバムタイトル“Know what I mean ?”。アダレイの特別注文に応えて、エヴァンスがこのアルバムのために書いた曲だという。“Know what I mean ?”は「ぼくの言うことわかる?」の意味。アダレイの口癖だという。それをタイトルにするとは、エヴァンスも洒落いている。曲はやはりアダレイのプレイが引き立つように構成されている。最初はバラード風に、途中からラテンの乗りのいいリズム変わる。最後はきっちりリーダー・アダレイに花を持たせて終わるところは、エヴァンスも大人だ!アダレイもお釈迦様の手のひらの上の孫悟空といった恰好。最後は引き分けというところか。-----アルバム“Know what I mean ?”全8曲。どれを聴いてもモダンジャズの醍醐味を堪能できる傑作アルバムだと思う。---------------------------■私が選ぶ、キャノンボール・アダレイのベストアルバム-3-■1.キャノンボール・アダレイ・ウィズ・ビル・エヴァンスノウ・ホワット・アイ・ミーン<CD/洋楽>--私個人としては、このアルバムが一番好き。エヴァンスのプレイが楽しめるというのが大きな理由。-------■2.キャノンボール・アダレイ/サムシン・エルス--超有名、モダンジャズを語るとき必ず登場する傑作アルバム。これからの季節、マイルスのミュートのかかったペットで「枯葉」なんぞ聴いてごらんなさい。一発で痺れます!------■3.キャノンボール・アダレイ・クインテット・イン・シカゴ--アダレイのアルトとコルトレーンのテナー、天才2人のしのぎ合いも聴きどころ。これもお薦め!----
2004/10/17
コメント(0)
-
シブ~い! リストを聴く
今日は、ブレンデルの渋いリストを聴く。-----------------------------------------◆リスト(1811-1886)1)J.S.バッハのカンタータ「泣き、悲しみ、悩み、おののき」のコンティヌオによる変奏曲2)死者の追憶(「詩的で宗教的な調べ」第4曲)3)BACHの主題による幻想曲とフーガ4)孤独の中の神の祝福(「詩的で宗教的な調べ」第3曲)演奏:アルフレッド・ブレンデル(ピアノ)録音:1976年5月------------------------------------------私は、リストの音楽はあまり好きではないし、めったに聴かない。しかし、このブレンデルのリストだけは別。ロマンティックなリスト、あるいは技巧だけの空虚なリストの音楽と言ったイメージとはほど遠い、渋いリストを聴くことができる。ブレンデルは、若い頃リスト弾きとして鳴らしたピアニストである。彼はかつて、自身の著書の中の「高潔なるリスト」と題する論文で、偏見や不当な評価にさられているリストを擁護するような発言している。リストの音楽にあれほど傾倒していたブレンデルだが、最近はまったくリストを取り上げなくなったようだ。確かに70歳を過ぎた巨匠が、自らのテクニックを誇示するために作られたようなリストの曲を今さら弾く必要もないだろう。これから楽壇に打って出ようとする若いピアニストならともかく、評価の定まった演奏家にリストは似合わない。かつてブレンデル自身好んでい演奏したとされる「孤独の中の神の祝福」に関して、彼はある年齢に達した時点で、この曲の世界に入り込めなくなって行き、曲の良さを理解できなくなったために、弾くことを止めたとも言われる。ブレンデルがもう2度と「孤独の中の神の祝福」を弾かないとしたら、この曲の入ったアルバムはなおさら価値がある。「詩的で宗教的な調べ」の中では、3番、4番、7番がよく演奏されうよだが、最近特に人気あるのは、3番の「孤独の中の神の祝福」らしい。どことなく「愛の夢」を思い起こさせる美しい曲だが、宗教色が色濃く繁栄されたこの曲の方が、より音楽としての陰影が深いように思う。静寂の中から生まれる不思議な高揚感は、何とも言えない魅力がある。第1曲目の「泣き、悲しみ、悩み、おののき」のコンティヌオによる変奏曲は、ブレンデルの言葉を借りれば、リストの作品の中で、「ロ短調のソナタ」、「巡礼の年」と並ぶ傑作とされる味わい深い曲だ。単純な半音階で下降するバッハの主題は、変奏になると一転印象派やスクリァビン風になったり、さらにはウェーベル風の無調音楽に聞こえるところもある。もちろん、リストらしい情熱的な変奏も随所にでてくる。リストの後期の作品には、「エステ荘の噴水」や「無調のバガデル」のように、印象派や無調音楽への萌芽が見られると言われる。この曲も、まるでピアノ音楽の見本市のようにさまざまなタイプの音楽が次々に現れ、とても興味深く、面白い作品だ。このアルバムは、リストの音楽を熟知したブレンデルらしい地味な選曲だが、山師あるいはペテン師とまで揶揄される作曲家の違った側面を知るには、もってこいの1枚だと思う。
2004/10/10
コメント(0)
-
グリーグ「抒情小曲集」(ギレリス)
今日は、ギレリスでグリーグの「抒情小曲集」を聴く。---------------------------------------◆エドヴァルト・グリーグ(1843-1907)『抒情小曲集』演奏:エミール・ギレリス(ピアノ)---------------------------------------エミールギレリスは、私がもっとも好きなピアニストのひとり。特に彼の弾くベートーヴェンのソナタは、週に1度はいずれかの曲を聴くほど、惚れ込んでいる。ギレリスのベートーヴェンを最初に聴いたのは、「熱情」だった。それまでケンプの演奏しか聴いたことがなかったので、彼のブリリアントで強靱なタッチから生み出される、エネルギッシュな音楽に圧倒された。「これがほんとうのベートーヴェンだ!」‥‥心からそう思った。「熱情」のあと発売された「ワルトシュタイン」ももちろん聴いた。これもスゴかった。特に第2楽章から第3楽章に入るあたりの幻想的で美しいメロディ。そして徐々にフィナーレに向って疾走する、ベートーヴェン特有の高揚感は、何度聴いてもあきない。「ベートーヴェンはギレリスに限る」これはあの時も今も変わっていない。3枚目に手に入れたギレリスの演奏が、このグリーグ。なんとも素朴で、哀愁漂うグリーグのピアノ曲。透明で美しく愛らしいそのメロディは、あのベートーヴェンを弾く同じピアニストの紡ぎ出す音楽とはとても思えない。しかし、輝くような高音と、豊かな低音は紛れもなくギレリスそのもの。このピアニストは、いったい何ものなのだ。彼の表現力の豊かさと多面性に改めて惚れ直した。その時からこのグリーグも、私の愛聴盤の1枚となった。ライナーノートには、ギレリスのこんな言葉が書かれている。「ロシアではグリーグの『抒情小曲集』は教師と子供たちしか知りませんでした。」ギレリスは、おそらく自分の幼い頃を思い出しながら、この曲を演奏しているに違いない。そう思うと、なお一層ギレリスのピアノが味わい深く聞こえてくる。-------ところで、このグリーグのピアノ曲を聴いたとき、誰でもすぐにシューマンを思い出すだろう。似ている、確かに似ている。グリーグとシューマンと言えば、例の同じイ短調のピアノ協奏曲がカップリングさることが多い。私も持ってる2枚ともその組み合わせだ。この抒情小曲集も、シューマンほど複雑ではないが、曲によっては新しく発見されたシューマンの遺作だと言われれば、信じてしまうほど似ている。たとえば、「あなたのおそばに」「蝶々」など、シューマンの幻想小曲集に紛れ込んでいてもまったく違和感がない。「アリエッタ」「過去」「余韻」なども、『子供の情景』や『森の情景』などのピアノ小品集にありそうな曲だ。シューマン・マニアの私としては、こんな聴き方もできるとこが、この曲集を気に入ってるもう一つの理由でもある。もし、シューマンが好きで、この曲集を聴いたことがない方がいたら、ぜひ一度聴いてみるといい。必ず気に入るはずだ。------------------------お薦めはギレリス盤だが、残念ながら楽天では発見できなかった。アマゾンなら手に入るので、もし興味があるならそちらへ。楽天では、以下のCDを見つけた。抒情小曲集~グリーグ:ピアノ名曲集-----------------------------以下、ギレリス盤に収録されている曲名を列挙しておく。曲名だけでも、イメージが膨らむだろう。1.アリエッタop.12-12.子守歌op.38-13.蝶々op.43-14.孤独なさすらい人op.43-25.音楽帳op.47-26.メロディop.47-37.ノルウェーの踊り「ハリング」op.47-48.夜想曲op.54-49.スケルツォop.54-510.郷愁op.57-611.小川op.62-412.家路op.62-613.バラード風にop.65-514.おばあさんのメヌエットop.68-215.あなたのおそばにop.68-316.ゆりかごの歌op.68-517.昔々op.71-118.パックop.71-319.過去op.71-620.余韻op.71-7
2004/10/09
コメント(0)
-
極彩色のバッハ
今日はアルゲリッチのバッハを聴く。-------------------------------------------トッカータハ短調 BWV-911ハルティータ 第2番 ハ短調 BWV826イギリス組曲 第2番 イ短調 BWV807(録音:1979年)-------------------------------------------グールド・ファンとしては、バッハはどうしてもグールドの演奏を聴く時の方が多い。しかし、時々こうしてアルゲリッチの演奏するバッハを聴くと、その音色の鮮やかさに、グールドのそれとはまったく異なるバッハの魅力を発見する。グールドのバッハがモノクロームの美しさだとすれば、アルゲリッチのそれは色鮮やかな極彩色のバッハだ。チェンバロを意識したグールド違って、アルゲリッチは、そうした拘りを潔く捨て去っている。彼女は、ピアノという楽器が本来持っている能力をフルに使って、バッハの世界を描いてみせる。ダイナーミクやアーティキュレーションの変化から生み出されるのは、躍動感に溢れた自然な音楽である。ストイックで内省的なグールドのバッハに対して、アルゲリッチのそれは自由で、外に向かう開放感がある。グールドか、それともアルゲリッチか。いずれも、紛れもないバッハの音楽であることには違いはない。さまざまなアプローチが許される懐の深さにこそ、バッハの音楽の本質がある。聴く側がバッハの音楽に何を求めるかによって、好みは別れるだろ。あなたはどちらがお好み?
2004/10/08
コメント(4)
-

リヒテルのベートーヴェン 初期ソナタ
今日はリヒテルでベートーヴェンの初期のピアノソナタを聴く。曲目は、「第3番ハ長調作品2の3」と「第4番へホ長調作品7〔恋する乙女〕」の2曲。リヒテルの演奏では、シューマンとベートーヴェンの初期のピアノソナタが好きで、よく聴く。今日の2曲では、第3番の演奏が特に気に入っている。このベートーヴェンの第3番のソナタは、1960年、リヒテルがニューヨークのカーネギーホールで、西側デビューを果たした時のリサイタルの第1曲目に演奏した曲で、よほど自信がある曲目なのだろう。その時、リヒテルはすでに46歳だった。同門のギレリスがすでに西側諸国で演奏会を開き、高く評価されていたことを考えると、リヒテルがなぜこの時まで鉄のカーテンの向こうに閉じこめられていたのか、ほんとうに不思議だ。このニューヨーク・デビューのリサイタルによって、リヒテルは一躍音楽界の大スターへの道を歩み始める。このときのライブ盤もかつて発売されていたようだが、私は聴いたことがない。私が持ってるのは、1975年にウィーンで録音されたものだ。聴いてまず感ずるのは、魅力的なピアノの音である。この録音にはベーゼンドルファーが使われいる。スタインウェイに比べると全体的に渋めで、低音が豊かに響くように聞こえる。(録音自体の残響音も多め)このベーゼンドルファーの音が、ベートーヴェンの初期のソナタにふさわしく、リヒテルの演奏をより一層陰影に富んだものにしているように思う。特にすばらしいのが、第2楽章のアダージョ。初期のソナタでこんなにロマンチックな演奏を他に知らない。ピアノとフォルテのコントラストがもたらす緊張感が、たまらなくスゴい。私の曖昧な表現より、ライナーノートに吉田秀和さんが書いている文章を紹介する。「このホ長調ではじまるこの楽章は、最初の主題の提示の後、ホ短調に入っていく。そこでは、左手に、オクターブで3度上昇する歩みが2回繰り返される旋律が何度も出てくる。‥‥中略‥‥左手のオクターブは、最初は、やさしい暗示的なものとして近づいてくる。しかし同じ歩みが、次にフォルテシモで戻ってくる時には、避けようのない鋼鉄の歩みというか、表情の真実性はきくものを震駭させずにはおかない。しかも、そのどちらの場合も、しっかりとした深いタッチであることは変わらないのである。」このリヒテルの演奏を聴くと、ベートーヴェンの初期のソナタの魅力を再発見することができる。私は、リヒテルの弾く「アパッショナータ」や「悲愴」は、どうも好きになれないが、この初期のソナタ2曲は聞き物だと思う。CDでは、どうも単体発売されていないようで、リヒテル・コレクション BOX [LIMITED EDITION] の中に収録されているのを見つけた。お金に余裕のあるリヒテルファンはぜひどうぞ。
2004/10/06
コメント(0)
-

マーラー『復活』渡邊/日フィル'78
マーラー:交響曲第2番『復活』常森寿子(Sp) ソウクポヴァ(Alt)日本プロ合唱団連合渡辺暁雄(指)日本フィル録音:1978年4月8日 東京文化会館(ステレオ)-------------------------------------------以前日記に書いた、渡邊暁雄指揮日本フィルによる、マーラー『復活』のCD(2枚組)が届いたので、早速聴いてみた。この演奏は1978年4月8日、東京文化会館で行われた、日フィル定期のライブ録音である。この日、私はホールで実際にこの演奏を聴いたので、26年目の再会ということになる。当日の感激はいまでも忘れることができない。特に第4楽章、アルト独唱で歌われる『原光』、そして第5楽章、フィナーレの荘厳な合唱には涙が止まらなかった。後にも先にもコンサートであんなに涙を流したことは、未だかつてない。あの感動がCDで果たして蘇るのか、期待しつつもやや不安だった。しかし、スピーカーから第1楽章冒頭の葬送のテーマが流れ出した途端、私の不安は吹き飛んだ。さすが24bitリマスターリングの威力はずごい。我が家の貧弱な装置でも、地の底からわき出てくるようなコントラバスの響きが見事に再現されている。とても26年前の録音とは思えない迫力だ。私は、すぐにあの日の東京文化会館にタイムスリップした気分になった。それからは、ただひたすら音楽に浸った。やがてあの第4楽章が始まる。ソウクボヴァのアルトはあの時のままだ。どこまでも厳かに響き渡る。この声を私は聴きたかったのだ。そしてあの日と同じように涙が流れてきた。ほんとうにすばらしい、他に言葉を知らない。こんな音楽はめったに聴けるものではない。そして第5楽章。「復活の歌」がppで歌われ、徐々に音楽は荘厳な響きへと変わっていく。指揮者も、オーケストラも、歌手も、合唱も、ひとつになって壮大に歌われるフィナーレ。間違いなくマーラーの『復活』は傑作だ。誰が何と言おうと、私にとって、渡邊/日フィルによるこの日の演奏は紛れもない名演中の名演である。ライブならではの熱気は、何者にも代え難い。私は、日フィルのこの演奏を聴いた日から『復活』のファンになった。そしてメータ指揮による『復活』を長く愛聴盤にしてきた。しかし、今日からしばらくの間、メータを聴くこともないだろう。いま、私はあの日、生演奏でこの『復活』を聴くことができた幸運と、今日あの感激を再び味わうことができた二重の喜びに浸っている。音楽とは何とすばらしいのだろう、心からそう思う。もしマーラーファンの方がいたら、ぜひこのCDをライブラリーに加えて欲しい。余り詳しくない私の意見が信用できなければ、HMVのホームページをご覧になるといい。マーラーや渡辺暁雄について、私よりはるかに詳しい方々のレビューがたくさん載っている。それを読めば、この演奏のすばらしさが多少なりともわかるのではないかと思う。今晩は、もう一度第4、5楽章を聞きながら眠ることにする。★★HMVの『復活』レビューは以下へ★★http://www.hmv.co.jp/Product/Detail.asp?sku=1826646(今ならキャンペーン価格で手にはいるからお得!!)
2004/10/04
コメント(2)
-

シューマンの交響曲
注文してあった、フルトヴェングラー指揮のシューマン/交響曲第4番のCDが届いたので、さっそく聴いてみた。フルヴェンのシューマン第4は、指揮者自身が自らのベストに押すぐらいの名演とのこと。評論家の志島栄八郎さんが、巨匠の未亡人エリザベットさんにスイスで話を聞いたところ、彼女はこう語ったという。「主人が特別に満足した録音は、シューマンの「交響曲第4番」(1953年モノラル盤)、それからシューベルトの「交響曲第9番」。ただしこれは部分的には不満なところもあったようです。それからハイドンの「驚愕」と「第88番」、それにワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」‥‥」フルトヴェングラーというと、あまり詳しくない私など、例のバイロイトの「合唱」を筆頭にベートーヴェンやブラームスの交響曲の名演がまず思い浮かぶ。しかし、巨匠自身はこれらの演奏にはどうも不満があったようだ。「合唱」や「英雄」なんか、ほんとスゴい演奏だと思うのだが、芸術家の感性は凡人にははかりかねる。手許にあるCDには、巨匠一押しのシューマンの「第4番」とともにハイドンの「88番」が入っている。スタジオ録音でしかも巨匠の数ある録音の中でも比較的音質がよいとされている名盤。しかし、如何せん50年も前の録音、しかもMONOだから音は正直良くない。フルトヴェングラーを聴くとき、私の場合、いつもこの音質の悪さに慣れないことには何事も始まらない。この少しこもり気味の渋い響きがいいという意見もあるだろうが、私は慣らし運転で2,3回聴いてからでないと、音楽そのものを楽しむという段階に入れない。これはフルヴェンに限らず、古い録音を初めて聴くときの通過儀礼のようなものだ。さて個人的な感想を書くと、4番はどうも重すぎる。もともとそういう音楽なのか、巨匠の指揮に原因があるのか、はっきりしないが‥‥。私の趣味では、おなじシューマンなら1番「春」のように、透明感のあるもうちょっと軽い音楽の方が好ましい。聞きこんでいけば、また違った感想もでてこようが、いまのところ、これが正直な感想‥‥。それに比べ、ハイドンの「88番」は、威風堂々としたなかにも、明るい開放感が感じられる。特に第4楽章ははねるようなリズムで、フルトヴェングラーらしい高揚感もあり、聴いていてとても楽しかった。私としてはシューマンよりハイドンの方が掘り出し物ような気がする。シューマンの交響曲の私のお気に入りは、ジョージ・セル/クリーブランド管の演奏。「春」と「ライン」の2つ交響曲が入ったCDをどきどき引っぱり出しては聴いている。クリーブランド管の透明感のある弦の響きは、とにかく美しい。特に「春」の第2楽章のラルゲットは、シューマンならではの幻想的でロマンティックな音楽。だからといって決して情緒に溺れたりしていない。このあたりはピアノ曲に見られる「気分屋シューマン」とちょっと違う。第1番「春」は、シューマンがわずか4日で書き上げたという促成栽培のような交響曲。オーケストレーションの稚拙さなど、いろいろ指摘されているらしいが、そんなことは聴く立場からすればどうでもいい。そもそも私にはどこがどう出来が悪いのか、さっぱりわからない。促成栽培だろうが、多少見てくれは悪かろうが、食って旨ければそれで充分満足。シューマン信者の私としては、月の出てない十五夜に、お気に入りのセルのシューマンを久しぶりに聴いてみることといたしましょうか。------------------------------------------------◆シューマン/交響曲第4番、ハイドン/交響曲第88番フルトヴェングラー指揮ベルリンフィル(1953年スタジオ録音盤、MONO)フルトヴェングラーの遺産◆シューマン交響曲第1番変ロ長調「春」交響曲第3番変ホ長調「ライン」序曲*マンフレッド演奏: クリーヴランド管弦楽団 指揮 ジョージ・セル
2004/09/29
コメント(2)
-

モーツァルト ピアノ協奏曲第27番(ラローチャ)
今日はモーツァルトのピアノ協奏曲第27番をアリシア・デ・ラローチャのピアノで聴いた。バックはショルティ指揮のロンドンフィル。ラローチャと言えばやはりスペインものが定番。しかし、モーツァルトもなかなかいい。まろやかな音色はグラナドスなんかよりモーツァルトに適しているかも知れない。コリン・デイヴィスと組んだモーツァルトの協奏曲が何枚も出ているが、このショルティとの27番は比較的ゆったりとしたテンポで、それはそれは典雅な音楽を聴くことができる。特に第2楽章は聴きものだ。ラローチャのピアノにショルティとは思えない控えめなオケが寄り添い、まさに天国的な美しさである。これは一聴の価値あり。演奏全体はやや陰影には乏しい気がしないでもない。この曲によく使われる「諦念」というイメージを期待すると、ちょっとがっかりするかも?しかし、この曲が本来持っている「透明感のある明るさ」はよく出ているように感ずる。ここら辺は好みの問題だろう。ラローチャのピアノは、いつ聴いてもほんとうに美しい。その特徴はこの録音でも遺憾なく発揮されている。録音も優秀だ。素直な気持ちでモーツァルトの音楽に浸りたいのであれば、お薦めできる1枚だと思う。---------------------------------------◆モーツァルトピアノ協奏曲第27番変ロ長調K.595ピアノ協奏曲第25番ハ長調K.503アリシア・デ・ラローチャ(ピアノ)ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団指揮:サー・ゲオルク・ショルティ#:B00005FM2M
2004/09/28
コメント(0)
-
今日はグールドの誕生日
今日は9月25日は、グレングールドの誕生日である。彼がもし生きていれば、今年で72歳になる。50歳でこの世を去ってからもう22年もたつのだ。グールドは25年ほどの間に100枚を越えるレコードやCDを残しているが、その記念すべきデビュー盤は、誰もが知っているあの「ゴールドベルク変奏曲」である。しかし、日本のレコード会社が出した彼の最初の1枚は、「ゴールドベルク」ではなく、ベートーヴェンの後期のピアノソナタ3曲を収めたものだった。いまでは誰も驚かないだろうが、この演奏は当時の常識では枠をはずれた「とてもベートーヴェンとはいえない」変わった弾き方だった。その為、日本の批評家の集中攻撃の対象となった。そのすさまじさに、このレコードをリリースした会社も、グールドのレコードを続けて出す勇気を完全に失ってしまったという。しかし、この演奏を聴いて評価した評論家がいた。それが吉田秀和さんだった。「確かに変わってはいるがおもしろいピアニストだ」と思った吉田さんはすぐにグールドの他の録音を取り寄せたらしい。そして出会ったが、グールドのデビュー盤である「ゴールドベルク変奏曲」だった。後年、吉田さんがある出版社から「私の一枚」という原稿を依頼されたとき、迷った末に選んだのが、グールドの「ゴールドベルク変奏曲」だった。あの吉田秀和さんが数あるレコードの中からたった1枚選んだレコードである。これは聴くしかあるまい。この一文を読んだ私は、すぐにこのレコードを買った。冒頭の主題のアリアが流れ始める。一音一音確かめるように、グールドは弾いている。ピアノの音は耳からではなく、胸からきこえてくるような錯覚に襲われる。一種の酸欠状態にも似た、心地よい息苦しさ‥‥。そしてどこか遠くへ連れて行かれるような気分になり、やがて自然と涙があふれてくる。音楽が胸にしみるというのは、きっとこういう感覚のことをいうのかもしれない。最後の録音となった新盤の「ゴールドベルク変奏曲」ももってはいるが、私は旧盤の方が好きだ。あの胸しみる何とも言えない恍惚感は、新しい盤ではなぜか味わうことができないでいる。-----------------------------------------●旧盤バッハ:ゴールドベルク変奏曲(55年モノラル盤)●新盤J.S.バッハ:ゴ-ルドベルク変奏曲
2004/09/25
コメント(6)
-

ピアノ教師としてのショパン
ショパンがどんな条件で弟子を選び、どのようなレッスンをしたか。「ショパンの遺産」という本を参考にメモ代わりにまとめてみた。◆弟子の採用条件:ショパンは、18年間ピアノ教授の仕事を続けたが、その間生徒不足に悩むことはなく、かえって希望者の多いことに不平を言うほどだった。ショパンの弟子は完璧に2つのタイプに分かれていた。第1は、ほんとうに才能のある弟子。第2は、大して才能はないが金持ちの伯爵夫人、または自分にとって利益となる社交界の淑女。(こちらの方が多かったようだ)生徒の才能をはかる最上の方法として、ショパンは生徒の耳をテストすることを上げている。生徒がたった一度聴いただけでその節を間違いなく歌えたら、その生徒は採ってよいと語っている。また、癖を直すのにムダな時間が必要になるから、新しい生徒はあまり多くを知っていない方が望ましい、とも言っている。◆レッスン時間:レッスンは週2回以上は決してしなかった。各レッスンは45分。ただし、後にレッスンが入っていない時には、数時間に及ぶ場合もあったが、これはほんとうに才能がある弟子に限られていた。◆レッスン室:レッスンは基本的にはショパンの家の専用の部屋で行われた。部屋には2台のピアノがあって、プレイエル(フランスのピアノメーカー)のコンサートグランドは弟子に、小さなアップライトのプレイエルはショパンが弾いた。ショパンは、弟子が貧弱なピアノを弾くことを禁じたという。◆レッスン料:生徒はショパンが窓の外を見ているときに暖炉の上にそっと20から30フランを置いた。直接現金を受け取るような下品なことを、ショパンはしなかったとされる。ちなみに当時のオペラのチケットが12フラン程度だから、1回のレッスンで30フランはショパンなら妥当な額か? 日本でも有名なピアニストのレッスンっていくらくらいするんでしょう?◆レッスン課題:技術的な水準の如何にかかわらず、生徒は指の練習をさせられ、クレメティのプレリュードとエチュードと併用してクラーマーのエチュードを勉強させられた。自作の他、フィールドのノクターン、モーツァルト、ヘンデル、ベートーヴェン、スカルラッティ、シューベルト、メンデルゾーンの曲を弟子に課した。しかし、リストとシューマンは決して与えなかったという。基本的にショパンはリストもシューマンも嫌いだったようだ。また弟子がショパン自身の曲を弾くことも余り好まなかったという。ショパンがピアニストにとって最高の課程としたのは、バッハの「プレリュードとフーガ」で、弟子たちに毎日弾くように指示したという。「(平均律クラヴィア曲集)は最高にして最上の課程。これ以上の理想的な課程は誰も創れるものはない。バッハをおいて真のピアニストはいない。バッハを尊敬せぬピアニストは俗人でいんちきである」とまで、ショパンは言い切っている。ショパンがバッハのプレリュードをよりピアノ的に発展させようとして24の前奏曲を作曲したのは有名な話。◆レッスン風景:ショパンは、弟子のために模範演奏をしなかった。友人に宛てた手紙にも「私は弟子のために決して弾いてやらない」とはっきり書かれている。できの良い生徒とのレッスンは機嫌が良くおしゃべりをしたりするが、できが悪いと途端に怒り爆発、楽譜や折れた鉛筆が飛んでることがよくあったという。この被害にあうのは、大抵伯爵夫人や令嬢だったらしい。何となく気持ちはわかるが、だったらそんな弟子を取るなと、つっこみを入れたい。才能のある生徒には何時間も根気よくレッスンし、弾けるようになるまで同じ箇所を50回も繰り返させた。しかし、ショパンは自分の弟子が何時間も続けて練習する習慣だと知ると、「練習とは集中力と意識をもって行うもので、1日3時間も練習すれば充分だ」と生徒に忠告したという。-----------私見ながら、ピアノ教師としてのショパンはあまりいい先生とは言えそうもない。実際、同時代のリストの弟子からたくさんの有名なピアニストが誕生しているのに、ショパンの弟子にはそういう人物はほとんど見あたらない。しかし、仮にショパンの公開レッスンをいまの日本で開こうものなら、いくら払ってでも受けたいという学生が殺到するだろうなあ‥。
2004/09/22
コメント(0)
-

ショパンの手
ピアノを習っていた頃、先生にまず注意されたのは手の形だった。いわく「卵を軽く握るのようなつもりで‥‥」。確かに、指を立てることで鍵盤を強くたたくことが出来るし、親指を潜らすときもスムーズだ。この手の形は理にかなっており、今も昔も変わらない真理のように思うのだが‥‥、ショパンは違っていたらしい。ショパンは、弟子のクレッチンスキに「手の形について」次のように語ったという。「タッチと音は手の位置にかかってくる、そして鍵盤は指先でたたくものではなくて、指の腹か、肉の付いた部分で打つべきものである。指は鍵盤の上に平たく置くべきで、まるい形になってはいけない。この目的のためには、ニ長調のスケールがもっとも適当である。」もちろんこれを否定する証言もある。同じくショパンの弟子として有名なデュポア夫人は、「ショパン自身そんなに手を平らにしていなかった」と強く否定している。果たしてどちらの証言が真実か。答えはショパンの手の石膏型(図1)を見れば分かるように思う。 写真なので比べようがないが、ショパンの手は比較的小さかったと言われている。この石膏型を見ると、練習の為か関節が大きく突起し、指先の腹は明らかに扁平しているのがわかる(図2)。手をまるくした練習では、こういう形にはならないだろう。ショパンは明らかに手を平らにしてピアノを弾いていたとしか考えられないのではないか? ならば、ショパンはなぜ手を平らにしてピアノを弾いたのか? ホルクマン著「ショパンの遺産」には、こんな記述がある。「水平な指の位置は、レガティシモを弾きやすくして、繊細なニュアンスを出すにはなかなか助けとなるものである。しかし、このような手の位置は、クレッショエンドやフォルティシモには適さないだろう。そしてことに速いテンポで親指をくぐらせるには、それは全然うまくゆきそうもない。」ショパンの手の形は、彼の音楽、そして肉体的特徴と決して無関係でなかった。評伝を読むと、ショパンは肉体的に華奢だったため、ピアノを演奏する際、大きな音がだせなかったことが必ず書かれている。普通のピアニストのダイナミックの幅は、フォルテシモからピアニシモの間にあるが、ショパンの幅はそれより狭かった。そのピアニストとしての肉体的、技術的欠陥を補うため、ショパンはメゾフォルテとピアニシモの間のダイナミックの幅を完璧にコンロールできるように訓練したと言われている。一方で彼は左ペダルをほとんど使わなかった。これはその鈍い効果が不自然だと考えたからだという。(当時のピアノの構造的な問題か?)ショパンが、左ペダルを使わずに弱音を思いのままにコントールするためには、水平な指の位置が必要だったということだろうか?当時のある評論家は『ショパンはピアノとピアニシモの間の濃淡を百も出すことができる』と賞賛したという。この言葉を聞いたショパンはたいそう喜んだらしいが、自らのピアノ演奏に心から満足していたわけではない。ショパンは友人であり同時代の大ピアニストであったリストの演奏を軽蔑しつつ、その力強く豊かな音量を常に恨ましがったと言われる。リストのこんな証言がある。「ショパンは健康的にあまりに脆弱であり、そのため作品を書くということによってその負い目を埋め合わそうとした。彼はそれらと作品が力をこめて演奏されるのを聴きたいと思ったが、彼自身にはそのような力に欠けていた。」もしショパンが現代最高のコンサートグランドで現代のピアニストの弾く自身の作品を聴いたら、どんな感想をもらすだろうか?逆に私のような音楽ファンならば、ショパン愛用のプレイエルピアノで「彼の百のピアニシモ」を一度聴いてみたいと誰しも思うだろう。★注意:素人の推測の部分もありますので、誤解などがあればどうぞ指摘してください。-------------------------------------------------------◆参考資料「ショパンの遺産」ホルクマン著 野村千枝訳(音楽之友社)「ショパン」アルフレッド・コルトー著 川上徹太郎訳(新潮社)
2004/09/19
コメント(7)
-

「9月の雨」(September in the Rain)
雨というと梅雨時が思い浮かぶが、日照時間を較べると6月より9月の方が短いらしい。つまりそれだけ雨の日が多いということだろう。台風は避けたいが、小雨程度なら秋の序曲として風情があっていいものだ。雨は人を感傷的にさせるのか、昔から洋の東西を問わず雨をテーマにした音楽は数多い。クラシックなら、ショパンの「雨だれ」、ブラームスの「雨の歌」、ドビュッシーの「雨の庭」などが思い浮かぶ。ジャズのスタンダードナンバーには、今の季節にぴったりの、そのものズバリ『9月の雨(September in the Rain)』という曲がある。様々なジャズメンが録音しているが、やはりもっとも有名なのは英国生れの盲目のピアニスト、ジョージ・シアリングのものだろうか?「9月の雨」はクールなサウンドでかつて一斉を風靡したシアリングのテーマ曲のようなナンバーである。ジャズ・マニアは「シアリングなんか、カーメンキャバレロと似たり寄ったりで、ありゃジャズなんかじゃない」と辛辣な批評をするファンもいる。しかし、ジャズであろうがなかろうが、シアリングのピアノはとても叙情的で美しい。良くも悪くも甘っちょろいのである。そこが彼のピアノの魅力なのだから、私のように根強いファンも多い。肩肘張らずに気軽にジャズを楽しみたいのなら、シアリングはもってこいのピアニストだ。なかでもこの「9月の雨」はライトでおしゃれ。なかなかのもだと思うのだが‥?「9月の雨」のボーカルなら、一押しはやっぱりサラ・ヴォーンだろう(「At Mr.Kelly's」)。サラ・ヴォーンの歌のうまさは今更言うまでもない。特に、この曲のサラは絶品である。----September In the Rain (Al Dubin/ Harry Warren)----- The leaves of brown came tumbling down, remember, In September in the rainThe Sun went out just like a dying emberThat September in the rainTo every word of love I heard you whisperThe raindrops seemed to play a sweet refrainThough spring is here, to me, it's still SeptemberThat September in the rain ご覧のように、詞の内容は9月のイメージとはとても思えない。私は以前9月のニューヨークに行ったことがあるが、セントラルパークの木立もしっかり葉っぱをつけていた。いくらアメリカが広いとはいえ、アラスカでもなければ9月に枯葉は舞うまい。そもそもジャズのスタンダードナンバーの歌詞など、たいして意味はないものだ。極端な話、歌詞を忘れてしまっても「ダバダ、シュダバ、デゥビダバ‥‥」とやってしまえばジャズになる。だから適当に言葉が並び、韻を踏んでいてメロディに乗りさえすれば、それで一丁上がり。このいい加減さ、自由さがジャズなのだ。スタンダード・ナンバーに「スイングしなけりゃ意味ないね」という曲がある。難しいことを考えず、スイングしながらジャズメンの職人芸にどっぷりと浸れば、これほど楽しい時間はない。シアリングでも、サラ・ヴォーンでも、誰でもいい。秋の夜、お気に入りのジャズメンの取って置きの1枚をじっくりと聴いてみましょうか。-----------------------------------------------------------★シアリング・オン・ステージ/ザ・ジョージ・シアリング・クインテット(楽天のCDは中古しか見あたらなかった、残念)der=0 alt="九月の雨">★サラ・ヴォーン「At Mr.Kelly's」(「9月の雨」含)サラのライブ録音。ジャズボーカルの名盤中の名盤。ジャズファンでなくても充分に楽しめる。ジャズクラブの雰囲気でサラの絶妙なボーカルを聴くことができる。お薦めである。
2004/09/14
コメント(2)
-

ブレンデルと三面鏡
久しぶりに「皇帝」が聴きたくなって、以前録画してあったブレンデルとN響のビデオを観た。ブレンデルは一時期夢中になった演奏家で、今でも好きなピアニストの一人だ。演奏はもちろんだが、私は彼の風貌がともて好きである。牛乳瓶の底のようなメガネ、大学教授のような知的で見るからにきまじめな顔つき。手足の長い彼が、燕尾服を着てステージ袖から歩いていてくる姿は、なんともユーモラスである。巨匠には失礼だが、操り人形のピエロを連想してしまう。しかし、その演奏は現代を代表する巨匠だけにがっちりとしていて、一部の隙もない。背筋をぴっと伸ばし、あまり大きな動作をしない彼の演奏スタイルも、安定感があってとても好きだ。ピアニストの中には、手を振り上げたり、上半身を大きく揺すったり、あるいは天を仰いで恍惚の表情を見せたりと、聴衆の意識とやや遊離したステージを見せる演奏家が少なくない。ステージ演奏だから見せる要素もあって構わない。しかし、それにも限度とうものがある。あまり激しく動かれると、聴く方としてはその動作に目を奪われ、演奏になかなか集中できない。実は、若い頃のブレンデルも、今日の彼自身のスタイルと異なり、大きなジェスチャーで演奏するようなピアニストだったらしい。ある日彼の演奏会を見た友人が、彼にこんな忠告をしたという。「君は、演奏中あまりに激しく動きすぎる。観客は気が散ってしまい、君の演奏に集中できない。そのスタイルは、早く治した方がいい」ブレンデルはこの忠告に素直に従い、すぐに演奏スタイルの改造に取りかかったという。彼の著作『楽想のひととき』の中で、インタビューに答えてその時のいきさつが語れている。インタビュアー「演奏者の動作に音楽的な効果があると感じておられますか?音楽のある瞬間を補うため、あるいはそれに注意をひくために、演奏者は身体の動きを用いるべきだと考えますか?」ブレンデル「ええ、そう思いますね。初めてテレビで自分自身を見たとき、私は自分が音楽的にしたいと思っていたこととまったく相反するあらゆるジェスチャーやしかめ顔をしていたことに気づいたのです。そこで、大きな据え付け用の鏡(三面鏡)を作らせて、ピアノの横に置きました。こうして無意識に、いろいろなことに気づいたのです。それは私が表現したいと思ったことを、実際に現れた私の動作と一致させることに役立ちました。こういうことを必要とする曲は、たくさんあります。-----略‥‥」彼の風貌と三面鏡という取り合わせては、一見ユーモラスな光景にも思える。しかし、実際にその姿を目の当たりにしたら、プロフェッショナルのピアニストの厳しい日常に誰しも感銘を覚えるだろう。三面鏡の話はほんの一例に過ぎない。ブレンデルはいわゆる天才型のピアニストではなく、努力型のピアニストだと言われる。彼自身、自分の思うような演奏が出来るようになるまでに長い年月を費やした、と語っている。ブレンデルの音楽は、徹底した楽譜分析によって築かれたものだ。学究肌の彼は、楽譜から作曲家が残した音楽の本質に迫ろうとする。その掘り下げ方は、確実に一人のピアニストの領域を越えている。ベートーヴェン、モーツァルト、シューベルト、シューマン、そしてリスト‥‥。こうした日々の厳しい鍛錬と弛まぬ探求心の上に彼の芸術は築かれている。ステージ上のブレンデルの後ろには、見えない鏡に映ったもう一人の彼がいるのだ。----------------------------------------------------------◆アルフレッド・ブレンデルの著作私のような素人には、ほとんど馬の耳に念仏のような本ですが、専門に勉強している方にはいろいろ参考になると思います。●「楽想のひととき」岡崎昭子訳(音楽之友社)☆☆目次(主な項目)ベートーヴェン‥‥ピアノ曲、全曲レコーディングに関する覚え書きほかシューベルト‥‥ピアノソナタリスト‥‥誤解されているリストほかブゾーニエドウィン・シュナーベルインタビュー(質問に答えて)●「音楽のなかの言葉」木村博江訳(音楽之友社)☆☆目次モーツァルト演奏家が自らに与える助言クラシック音楽はつねにシリアスであるべきか楽譜とその守護者たちベートーヴェンの新様式シューベルト最後の3つのソナタ大人の演奏家への試金石―シューマンの「子供の情景」高潔なるリストリストの「巡礼の年」第1年・第2年リストのロ短調ソナタリストの心の悩みブゾーニの「ファウスト博士」フルトヴェングラーライヴ・レコーディングについてリサイタルとプログラムピアノにおけるバッハシュナーベルの解釈について
2004/09/13
コメント(4)
-

恋愛神経について
学生時代、好きな女の子ができると、必ずキースジャレットの「ケルンコンサート」をプレゼントする先輩がいた。彼はジャズとサルトル、寺山修司が好きで、私はよく彼の家でキースのピアノと難しいサルトルの話を聞かされた。先輩は、知的好奇心も旺盛だったが、女の子に対する熱心さはそれ以上だった。私の知る限り大学時代に5人の女性と恋愛関係になった。もちろん、モーションを掛けた女性は数知れない。彼はいわゆるプレイボーイではなかった。恋愛はその都度真剣だったし、同時に複数の女性とそういう関係になることはなかった。しかし、なぜか一人の女性と長続きはしなかった。私も先輩を見習って、何人かの女の子に「ケルンコンサート」をプレゼントした。しかし「こんど一緒に聴きましょ!」とか「あなたの部屋で他の音楽も聴かせて」という訳にはなかなかいかなった。自分の思い通りにことが運ぶほど、世の中甘くない。先輩の行状を振り返ると、恋愛はスポーツや音楽と同じで一種の才能だと思う。運動神経があるように、きっと『恋愛神経』のようなものがあるに違いない。自分に好意を持っていない相手を無理矢理口説き落とすのは、至難の業だ。だから、恋人が欲しければ、多少なりとも自分に好意を寄せている相手を見つけ、それにねらいを絞るに限る。恋愛上手な人間を見ると、相手が自分に好意をもっているのか、いち早くかぎ分ける『恋愛嗅覚』のようなものを持っているように見える。そして好意を察知したら、すぐ行動に移す『恋愛瞬発力』も重要な能力だ。テレビの恋愛ドラマではないのだから、普通の人間はいくら若いからといって、四六時中好きだの嫌いだのと考えているわけではない。そもそも人の心は移り気で、躊躇しているうちに熱は冷め、恋の炎もあっけなく消える。だからチャンスを生かし切ることができるかどうか、それが恋愛上手、下手を分ける重要なファクターなのだと思う。どうひいき目に見ても、私は『恋愛神経』が鈍いようだ。以前、俳優のM・Rと20代の画家志望の女性との不倫関係が発覚したことがあった。マンションから出てきたMが、待ち伏せしていた芸能リポーターたちにした言い訳が、テレビで繰り返し放送された。『彼女とはメシ友です。一緒にいたのは、ほんとうだよ。でもね、若い奴らもいっぱいいて、そういう関係じゃないから。ただ、ビデオ見たり、キースジャレットのケルンを聞いて、演劇論とか一晩中語りあっていただけだから‥‥、一種の異文化交流ですよ。いいよね、ケルン、あなた聞いたことある?‥‥云々‥』(彼の声やイントネーションを思い出して読んでください)正確ではないかもしれないが、こんな風なことを言っていたように記憶している。M・Rも、私の先輩と同じように『ケルンコンサート』を恋愛の小道具として使っていたのだろうか?甘くやさしいあの声で若い女の子を口説き落とすMの『恋愛神経』は、年齢に似合わずよほど優れているに違いない。男として人並み以上の「恋愛神経」は、正直言って羨望の対象である。----------------------------------------------------★クラシックピアノファンにもお薦めのキースのケルン-------------------------------------------------------------★★クラシック音楽関連番組放送予定memo★★◆9/12(日)21:00 NHK NHKスペシャル 「アシュケナージ・自由へのコンサート」独裁下の芸術家たちは?▽恐怖の旋律 ◆9/12(日) 21:00 NHK教育N響アワー 名演奏プレーバック▽鍵盤の魔術師シプリアン・カツァリス80年代の名演▽シューマン・ピアノ協奏曲
2004/09/11
コメント(4)
-

ピアニストとピアノ
今日、歯医者の待合室で週刊新潮を読んでいたら、ヤマハの広告にアシュケナージの写真が載っていた。アシュケナージがヤマハを弾くとは知らなかったので、ちょっと驚いた。ヤマハと言えば、リヒテルやブーニンとの関係が有名だ。特にリヒテルについては、NHKの『プロジェクトX』でコンサートグランドCFの開発秘話が紹介されたので、ご存じの方も多いと思う。(今日見た新潮にプロジェクトXの金銭スキャンダルが載っていた)ピアノは、メーカーの違いだけでなく、同じメーカーでも一台一台、音色やタッチが微妙に違うので、ピアノ選びは自ずと厳しくなる。ましてや世界的な一流ピアニストともなれば、限りなくデリケートな世界だ。ミケランジェリのように用意されたピアノが気に入らずに、コンサート自体をキャンセルしてしまうピアニストもいるくらいだから、日本のメーカーが世界の一流ピアニストに気に入られるのは、なかなか難しいことに違いない。国内のコンサートホールでも、やはり国産のピアノは分が悪い。ヤマハのCFもスタインウェイ、ベーゼンドルファーなどの外国のピアノに決して負けないはずなのだが、テレビの中継などを見るとピアニストはほぼ100%スタインウェイを弾いている。ヤマハの広告に出ていたアシュケナージも確かスタインウェイを弾いていたように記憶しているのだが、これからはヤマハを弾くのだろうか?おそらくそういう契約にはなっていないのではないかと思う。その意味では、リヒテルは誠実だ。実際にコンサートでヤマハを弾いている映像を見たことがあるし、CFでショパンのスケルツォ全曲も録音している。このCDは、まとまった形でショパンの曲をあまり録音していないリヒテルとしては貴重な音源だ。77年のレコード芸術誌・レコードアカデミー賞も受賞している。(メロディア盤, 1977年録音)その音は、スタインウェイにも、ベーゼンドルファーにも負けていないように聴こえるのだが‥‥。ちなみに、ヤマハのHPで同社のピアノを賞賛しているピアニストが紹介されていたので、その名前を列挙しておく。故人もいるが、意外と蒼々たるメンバーが並んでいるのに驚いた。コンサート会場やテレビでヤマハを使っていなかったら、つっこみを入れよう!(笑)スヴャトスラフ・リヒテルスタニスラフ・ブーニンウラディーミル・アシュケナージ マルタ・アルゲリッチ クリストフ・エッシェンバッハ アルフレッド・ブレンデル ウィルヘルム・ケンプ マリア=ジョアオ・ピリスデニス・マツーエフエフゲニー・キーシン フランス・クリダ イングリット・ヘブラー アンドレ・ワッツ◆◆『世界のピアニスト、ヤマハを語る』 詳しくはこちらへ◆◆
2004/09/08
コメント(4)
-

ラヴィ・シャンカル『東洋と西洋のはざまで』 -2-
(昨日からの続きです)活動拠点をアメリカに移したラヴィのもとへは、シタール演奏を習いたいという若者が殺到する。彼はインド音楽の学校を創設し、シタールの指導を始める。しかし、それはむなしい行為だったようだ。映像の中でラヴィ・シャンカルは次のように語っている。「(若者たちは)大麻やLSDをやれ、あれをやれとこれをやれと。そうすれば神に出会える。インドでは誰もそうしていると、アメリカの若者たちはそんな言葉を真実と受け止めていたが、それは勿論間違いです。ヒッピー文化が隆盛を極めていく中で、インドに興味をもつ若者が増えていったが、彼らはせいぜいカーマストラやタントラなどのわずかな書物を読んだだけで、インドのすべてを理解したと思っている。何時間もギターをかき鳴らし、陶酔状態の中で『新しい音楽を発見した』『自分にしか書けない曲だ』という。聞いてみればつまらない曲です。絵画でも同じようなことをやっていた。でも、私は彼が好きでした。そこには純真さがあったからです」西洋社会にインド音楽を紹介したいという彼の理想とは裏腹に、集まってくるのは麻薬に溺れた若者たちだった。それでもラヴィは若者たちを受け入れようと努力した。しかし、3年半で学校は閉鎖され、彼は再び伝統音楽の世界に還っていくことになる。閉塞した社会の中で若いアメリカ人たちは傷ついていたが、ラヴィもまた深く傷つけられたように見える。西洋文化と交わることでラヴィ・シャンカルは、莫大な富と名声を手にした。その一方で彼の音楽活動は、常に西洋文化への迎合、商業主義という批判にさらされていた。ラヴィ・シャンカルの半生を見ると、私には『東洋文化を消費する西洋』というの構図が見えてきてならない。ドキュメントの終わり間近で、撮影当時ニューデリーに建設中だった『シャンカル音楽財団』の建設現場が映し出される。80歳を過ぎたラヴィは、年の離れた妻とともに現場を楽しそうに見て回る。彼の残された人生の夢は、ここにインド音楽の研究資料を揃え、一人でも多くの弟子を育成をしていくことだという。彼は、伝統音楽の未来について次のように語っている。「アメリカンナイズとほぼ同じ意味である現代のグローバリッゼーションに危惧を覚えます。古典的なもの、伝統的なものが損なわれる恐れがあるからです。しかし、私たちが演奏する伝統音楽が聞く人の魂に触れることが出来れば、それ(伝統)は失われることなく生き続けるでしょう。」ラヴィ・シャンカルは、ジャンルを超えた多くのミュージシャンと出会い、様々な実験を繰り返してきた。ある物は成功し、ある物は明かな失敗に終わった。そして最終的にたどり着いたのは、結局インドの伝統音楽だった。インドは、いま世界のソフトハウスとして急速な経済発展続けているが、2050年には中国とともにGDPで日本を越える経済大国に成長すると予測されている。ラヴィシャンカルは、インドの伝統文化が失わつつあることに危機感を抱いていると語っているが、それはインドに限ったことではない。近代化という言葉は、欧米化、あるいはアメリカ化とほぼ同義語である。経済的な発展と引き替えに、多くの国や民族が伝統文化を手放してきた。それでもインドは、東洋と西洋のはざまで辛うじて踏ん張っているように見える。インドの伝統文化を支えてるのは何か、私には判らない。身分制度や宗教的戒律、貧富の格差など日本から見ると負の文化遺産があることは認める。しかしインドの文化には魂の根元に響いてくるものを持っている。それに較べて、わが日本はどうだろうか?明治維新以降、日本はいともあっさりと伝統文化や民族としての魂を捨て去ってしまった。これだけ急転換した国は、おそらく世界中さがしても日本だけではないか?日本の、日本人のアイデンティティとは一体何なのかスポンジのように何でも受け入れてしまうのが日本の個性だ、と開き直ることも可能だが、それでは答えにならない。振り返って見れば、私は日本の音楽などまったく聴かず、毎日西洋の音楽をありがたく拝聴している。音楽ばかりではない、映画もスポーツも食べ物もニュースも‥‥。情報化、国際化という言葉に踊らされ、気が付けば日本の外ばかり見るようになっている。日本人の自分とは一体何者なのか?このドキュメント見ながら、そんな問いかけが頭の中を駆けめぐった。しかし、その答えは当分見つかりそうにない。----------------------------------------------------------------★★★ラヴィ・シャンカルのCDが試聴できます★★★
2004/09/07
コメント(2)
-

ラヴィ・シャンカル『東洋と西洋のはざまで』-1-
先週録画してあった、ラヴィ・シャンカル『東洋と西洋のはざまで』(NHK-BS2)というドキュメンタリーを観た。この作品は、2001年、日本のNHK、イギリス・BBCをはじめフランス、アメリカの制作会社などの共同制作による力作である。ラヴィ・シャンカルは、いうまでもなく世界的シタール奏者として、また映画「大地の歌」の作曲家としても知られるインドを代表する偉大な音楽家である。番組は、彼へのインタビューを軸に、生い立ちから、様々な音楽家との出会い、そしてヒッピー文化の中で世界的なスーパースターに祭り上げられ、翻弄される彼の姿が、記録映像やコンサート風景ともに語られていく。映像は、米国・サンディエゴにある彼の自宅から始まる。自宅を出て、豪華なリムジンに乗って何処かに向かう、シャンカル夫妻と娘たちの姿が続く。東洋の精神世界の象徴であるラヴィ・シャンカルが、西洋物質文明の象徴としてのリムジンに乗っている。冒頭から何とも象徴的で皮肉な映像に見えた。ラヴィは、まず自らの生い立ちから語り始める。1920年、彼は北インドのベナレスという宗教色の濃い都市で生まれた。父親はインドで初めて政治学の学位を取ったほどのインテリで、大臣を勤めた後ジュネーブの国際連盟でも活躍した国際人だった。その一方でインドに妻子を残したまま、ヨーロッパ各国に愛人がいるようなプレイボーでもあった。ラヴィは、8歳になるまで父親の顔をみたことがなく、憎むとまではいかないまでも、反感を抱いていたと率直に語っている。ラヴィ・シャンカールの兄・ウダイはインド舞踊の大スターとして有名な人物だった。兄が率いる舞踊団で、ラヴィは9歳からダンスやシタール演奏の修行を始める。そして11歳の時に、舞踊団の一員としてフランスに渡る。パリでの生活は、東洋からやってきた少年にとってとても刺激的なものだったようだ。特に当時の最高の音楽家たちの生演奏は、彼に大きな影響を与えた。ギタリストのセゴビア、ヴァイオリンのクライスラー、指揮者のトスカニーニ、ピアノのパデレフスキー、そしてシャリアピンの歌や街で聴くシャンソン‥‥。西洋音楽はラヴィ少年を魅了し、虜にした。ヨーロッパで成功を納めたウダイのインド舞踊団は、やがてアメリカに進出。ここでも喝采を集め、世界的な名声を獲得するまでになる。ラヴィ自身が世界的に注目されるのは、1960年代に入ってからである。ヴァイオリンのイェフィディ・メニューインやジャズのサックスプレイヤー、ジョン・コルトレーン、そしてビートルズなど、ジャンルを超えた音楽家がラヴィとの共演を望んだ。コルトレーンは、自分の息子に「ラヴィ」という名前を付けるほど心酔していたという。ラヴィ・シャンカールというと、どうしてもジョージ・ハリスンとの関係を抜きして語ることはできない。ラヴィ自身も、共演した多くのミュージシャンの中でもジョージとの関係をもっとも大切に思い、かけがえのない友人だと語っている。番組では、湖かほとりでジョージがラヴィのレッスンを受けるシーンが出てくる。シタールの短いパッセージを何度も繰り返し弾くジョージの姿は、まるでギターをおぼえたての少年のようで、何とも微笑ましいかった。二人が出会った1965年当時のアメリカは、ベトナム戦争がすでに泥沼化していた頃で、厭戦的な気分も手伝って、若者の中に西洋文明を否定し東洋の精神世界に価値を見いだそうと風潮が出始めていた時代である。こうした時代に、ラヴィのインド音楽はまさにぴったいとハマり、ヒッピーたちに熱狂的に迎えらた。ラヴィ・シャンカルは、モンタレー・ポップスエスティバルやウッドストックなどのロックコンサートに次々出演し、一躍スーパースターに祭り上げられてしまう。ラヴィシャンカルは、当時50歳目前。その異常ともいえる熱狂に、彼はとまどいを覚えたという。(長いので、明日に続く‥‥‥‥)---------------------------------------------------------------●The Ravi Shankar Collection-Improvisationsラヴィ・シャンカルのCDが試聴できます●John Coltrane ☆ ジョン・コルトレーン/ジョン・コルトレーンの世界 (国内版DVD)ラーガ・ビヒンパラシィ(ラヴィ・シャンカール)収録●映画『大地のうた』
2004/09/06
コメント(0)
-

モーツァルト 『ピアノ協奏曲23番』
昨日からずっとモーツァルトのピアノ協奏曲を流しながら、仕事をしています。やっぱりモーツァルトは、ピアノ協奏曲がいい。おそらくモーツァルトの音楽の中で、もっとも重要なジャンルは、交響曲でもオペラでも室内楽でもなく、まちがなくピアノ協奏曲だと思います。モーツアルトは全部で27曲のピアノ協奏曲を残していますが、私が聴くのはもっぱら20番以降で、お気に入りは何と言っても第23番です。透明でなんとも優雅な第1楽章。秋の夕暮れを思わせる哀愁ただよう第2楽。そして、明るく躍動感に満ちあふれた第3楽章。この1曲の中に、モーツァルトの音楽がもつすべての要素が凝縮されていると、言ったら言い過ぎでしょうか?それほど、どこをとっても隙のない完成された音楽のように思うのです。特に第2楽章の『高貴な孤独感』(変な表現だが)は、数あるモーツァルトの緩徐楽章の中でももっとも美しいメロディではないでしょうか?この曲がウィーンで初演されたのは、1786年の5月。ちょうどオペラ「フィガロの結婚」が初演されるわずか1ヶ月前のことです。この第23番と一緒に数少ない短調の傑作第24番も一緒に初演されました。言葉は悪くなりますが、モーツァルトは大作オペラの片手間仕事に協奏曲を2曲書き上げてしまったわけです。この事実だけとっても、モーツァルトの天才ぶりには、驚かされます。私たち常人には、想像を絶する驚くべき能力です。さて、この23番の協奏曲はお気に入りの曲だけに、私の手許には3人のピアニストの演奏を収めたCDがあります。最初にこの曲を聴いたのは、ブレンデル、マリナー/アカデミー管盤でした。このコンビのモーツァルトは、かつて一世を風靡し、現在でも彼らの『モーツァルトピアノ協奏曲全集』は、偉大な金字塔と言われています。私が所有している盤は23番と一緒に、モーツァルト最後のピアノ協奏曲となった第27番が一緒に収録されています。レコードの時代に初めて購入し、CDで買い直し、長く愛聴盤として聴き続けてきました。2枚目は、内田光子とジェフリー・テイト指揮イギリス管です。内田さんのモーツァルトも定評のあるところです。こちらのCDを手に入れてからは、ブレンデル盤がどうも平板に聞こえるようになってしまいました。内田さんのピアノは、何といても弱音の美しさが魅力的です。指の先までよく神経の行き届いた、とても繊細な音楽を聴かせてくれます。聞く側にある種の緊張感を強いるような、決してリラックスできるモーツァルトではありませんが、モーツァルトに対する内田さんと指揮者・テイトの思いが、ストレートに心に響いてくる感動的な演奏です。いま一番よく聴くモーツァルトは、内田さんの弾くピアノ協奏曲です。どの曲もとても素敵な演奏だと思います。3枚目は、アシュケナージがピアノと指揮を兼ね、フィルハーモニア管と組んだ演奏です。これは、数あるアシュケナージの録音の中でも、最高ランクに上げられる名盤中の名盤です。特に録音の優秀さは誰もが認めるところでしょう。こんなに美しく輝くようなピアノはめったに聴けません。これもブレンデル盤と同様27番が一緒に収められてますが、圧倒的にアシュケナージの演奏のほうが優れているように思います。このアシュケナージの録音は、グルダの20番とともに永遠の名盤として残っていくのはないかと思います。モーツァルトのピアノ協奏曲を1枚と言われたら、迷わずこのアシュケナージ盤を薦めます。今日はこのアシュケナージのモーツァルトを聴きながら、寝ることにしましょうか。-------------------------------------------------------------------●モーツァルト:ピアノ協奏曲第15番&第21番&第23番指揮: マリナー(ネヴィル)演奏: ブレンデル(アルフレッド), アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ注:現在は23番と27番のカップリング盤は見あたらなかった。●モーツァルト:ピアノ協奏曲23 & 27番指揮: テイト(ジェフリー)演奏: 内田光子, イギリス室内管弦楽団●モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番&第27番演奏: アシュケナージ(ウラディーミル), フィルハーモニア管弦楽団
2004/09/04
コメント(2)
-

アルヴォ・ペルトの世界
今日は、アルヴァ・ペルトの作品集「タブラ・サラ/アルヴォ・ペルトの世界」というアルバムのご紹介。私のライブラリーの数少ない現代音楽の中の1枚である。 アルヴォ・ペルトはご存じの方もいると思うが、バルト海沿岸の国、エストニア出身の現代音楽の作曲家である。現代音楽といっても、彼の作品は自由な形式ながらいわゆるクラシック音楽(調性音楽)に近いため、現代音楽臭くなくとても素直に聴くことが出来る。 彼の音楽の特徴は、繊細で透明な音の響きと深い宗教性にあると言われる。目を閉じて聴いていると、とても心が落ち着く。今はやりの言葉を使えば、一種の「癒しの音楽」ではないかと思う。 このアルバムには、ペルトの呼びかけに応じてキドン・クレーメル、キースジャレット、ベルリン・フィルハーモニー12チェリステンなどのとても個性的な演奏家が参加している。 私は一時キースジャレットに夢中になり、彼のCDを片っ端から購入していた時期があった。このCDもその時の1枚である。正直に言えば、アルヴァ・ペルトなどまったく知らないまま購入したわけだ。だから、最初に聴いたときは正直面食らった。しかし聞きこんでいくと、とても魅力的な音楽であることが実感できるようになった。このアルバムには次の曲が収録されている。 1曲目は「フラトレス」。この曲にはいろいろなバージョンがあって、それぞれまったく違ったイメージの音楽になるらしい。これはピアノとヴァイオリンのバージョン。キドン・クレーメルとキースジャレットの演奏で、印象派のヴァイオリンソナタのような響きをもった美しい曲である。 2曲目は「ベンジャミン・ブリテンへの哀悼歌」。これは、ペルトの代表作と言われる曲で、文字通りブリテンの死を惜しむ鎮言歌である。私もこの曲がもっとも気に入った。鐘の音から始まり、どことなくマーラーを思わせる荘厳な響きをもったオーケストラ曲である。演奏は、デニス・ラッセル・デイヴィス指揮シュトゥットガルト国立管弦楽団。 3曲目は「フラトレス」のオリジナル版。ベルリンフィルの12人のチェリストによって演奏されている。このチェロ合奏版は1曲目とはまったく違ったイメージで、ほの暗いとても宗教的色彩の濃い音楽になっている。チェロの響きもあって、とても重厚な響きで胸に迫るものがある。しかし、私の個人的な好みで言えば、1曲目のピアノとヴァイオリンのバージョンの方が好きだ。 4曲目は「ダブラ・サラ」。これは、ふたつのヴァイオリンとプリペアード・ピアノ、弦楽で演奏される曲である。とても民族色の強い音楽に感じた。クレーメルの鋭いヴァイオリンが印象的な美しい曲である。 ちなみに、プリペアード・ピアノとは、ピアノの弦の部分に木片などの異物をはさんで音を変化させたピアノのことで、ジョン・ケージにより考案された。 ほんとうに偶然に出会ったCDだが、「アルヴォ・ペルトの世界」は私にとってとても大切な1枚になった。ぜひお薦めしたい1枚である。----------------------------------------------------------------「アルヴォ・ペルトの世界」は残念ながら楽天では見あたらなかった
2004/09/01
コメント(1)
-

ベートーヴェンとリストの幸福な出会い
フランツ・リストがチェルニーにピアノを学んだことはよく知られている。そのチェルニーも9歳から15歳までの短期間だがベートーヴェンに師事していた。つまりリストはベートーヴェンの孫弟子と言うことになる。では、リストとベートーヴェンは直接対面したことがあったのだろうか?実は、ちょうどベートーヴェンが第9を書いている頃、たった一度だが、二人が対面したことがあったらしい。リストをベートーヴェンに引き合わせたのは、他ならぬ師匠のチェルニーだった。チェルニーはベートーヴェンに幼いリストの演奏を聴いて欲しいと幾度となく懇願したが、いわゆる天才児が嫌いだったベートーヴェンはなかなか会おうとしなかった。結局、チェルニーの熱心さに根負けしてベートーヴェンはリストに会うことを承諾する。1823年、ベートーヴェン53歳、リスト11歳の時のことである。少年リストは演奏会を前に、チェルニーに連れられて、ベートーヴェンの家を訪ねた。後年、リスト自身が弟子にその時の様子を語った回顧談が残っている。偉大な作曲家の前で少々緊張しているリストを見て、ベートーヴェンはやさしく手招きし、何か弾いてみるように促したらしい。その時のやりとりをリストは次のように語っている。「私はまずリース(ベートーヴェンの弟子で当時の有名なピアニスト)の小曲を弾いた。弾き終わると、ベートーヴェンはバッハのフーガが弾けるかとたずねるのだった。私は『平均律クラヴィーア』からハ短調のフーガを選んで弾いた。『では、そのフーガをすぐ他の調に移調できるかね』と、ベートーヴェンはたずねた。幸い、それもできた。最後の和音を打つと、私はベートーヴェンを見上げた。巨匠の黒ずんだ燃えるような瞳が、刺すように私に注がれている。だが、突然柔らかな微笑が、暗い顔の上をかすめ、ベートーヴェンは私のすぐ近くに来て、腰をかがめ、私の頭に手を置いて、幾度も髪の毛をなぜた。『すばらしいやつだ! ほんとうのトルコ人だ』(確かにハンガリーは長年トルコの支配を受けていたけど)とささやいた。にわかに私はすっかり大胆な気持ちになった。『何かあなたのお作を弾かせていただいてよいでしょうか』と、臆面もなくたずねた。ベートーヴェンも微笑を浮かべてうなずいた。弾き終わると、ベートーヴェンは両手で私を抱き、額に接吻して、穏やかにこういった。『しっかりやれ! 幸運なやつだ! お前は多くの人たちに喜びと幸福とを与えるだろうから! 世の中にこんな立派な美しい仕事はない!』リストは目に涙を浮かべ、深い感情のこもった調子で、このように語ったという。リストは最後に付け加えた。「私の一生のうちこの出来事は、いまだに私の最大の誇りとなっている。私の芸術家としての全生涯の守り本尊なのだ。私はこの話をめったにしない‥‥ほんの仲の好い友だちにしか!」ベートーヴェンは粗野で取っつきにくい人物のように語られることが多い。しかし、周辺の親しい人々の回想録を読むと、彼は本質的にははとても快活で心優しい好人物であったことがよくわかる。孫のようなリストのピアノに感激するベートーヴェン。二人の幸福な出会いは、なんとも微笑ましい。-------------------------------------------------------------参考資料:柿沼太郎訳編「ベートーヴェン回想」 音楽之友社刊
2004/08/30
コメント(2)
-

ファジル・サイのリサイタル
昨日のNHKのBS2「クラシック倶楽部」でファジル・サイという若手のピアニストのリサイタルが放送された。一昨日、りほなさんの日記で放送を知り、録画予約してあったものを今日見た。恥ずかしながら最近のピアニストはほとんど知らないので、サイに関してもまったく予備知識なしで聴いた。その感想を素人なりに書いてみたい。曲目は‥‥1.ハイドン:ピアノ・ソナタ 第48番 ハ長調2.ラヴェル:ソナチネ3.サイ:黒い大地4.ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調 op.57 「熱情」5.モーツァルト : サイ編曲 トルコ行進曲ジャズヴァージョンまず、ちょっとびっくりしたのは、パントマイムを見るようなそのユニークな演奏スタイルである。まるでピアニストが自らタクトを振りながら協奏曲を演奏するように、上半身を前後左右に大きく揺らしながらピアノを弾く独特のスタイルである。実際にホールで見る分には気にならいだろうが、テレビだと表情のアップや正面からのショットも入ってくるので、ちょっとうるさいな思うところもあった。演奏そのもので印象に残ったのは、音の粒だちの美しさだった。特にペダルをほとんど使わないハイドンのソナタにその個性がよく出ていた。放送された曲目の中では、私はこのハイドンが一番良かったように思う。とてもエレガントなハイドンだ。第1楽章は速めのテンポ、切れの良い軽いタッチではねるように歌う。第2楽章は、うってかわってゆったり流れる、思い入れたっぷりの演奏。ナイーブで美しい音楽を聴かせてくれる。彼のハイドンは聴いていてとても楽しい。サイ自身も、一番自由で楽しそうに演奏しているように見えた。彼のモーツァルトならもっと楽しめそうだ。もしCDがあれば、ぜひ聴いてみたいと思った。ラヴェルの「ソナチネ」も良かった。高音部の1音1音の輝くような美しさ、それと対照的に左手で奏される印象派独特の包み込まれるような和音の響き‥‥。音楽としての色彩に富んだ演奏で、彼の才能の一端がかいま見えたように思えた。さて、問題はベートーヴェンである。これはひと言で言えば、「これってベートーヴェン?」と?マークが3つも4つも付くような演奏だった。私はこんなベートーヴェンも聴いたことがない。第1楽章は、低音の響かせ方に個性的なところがあったが、全体としては比較的オーソドックスな演奏に思えた。しかし、第2楽章になるとちょっと変になる。主題の変奏など、独特の節回しで肩すかしをくわされる。さらにテンポの揺れも激しく、どもう落ち着かない。祈りの音楽から光り輝く希望へとつながるベートーヴェンのソナタの中でも、私の一番好きなとことだから、ちょっとがっかりした。第3楽章なると、もはや???のベートーヴェンになる。まず、はじまりからいきなりエンジン全開。そのスピードたるやもはや誰にも止められないといった雰囲気で一気に突っ走る。他のピアニストでもこの第3楽章はスピードとテクニックの見本市みたいなとことがあるが、サイの演奏は尋常ではない。時間は計測してないが、速さだけならメダル確実だろう。さすがに今時の若いピアニストだけあって、テクニックはスゴい。でもちょっとどこか変。よく動くその指に見とれていると、フィナーレの手前で急にブレーキをかけてのろのろ運転になる。これには思わずのけぞった!「オイ、どうしたんだ、サイ?」とまっどていると、再びフルスロットル!ピアノはうなりを上げながらゴールへと向かう。言葉にするとこんな感じの演奏である。これがベートーヴェンといえるかどうか?でも、否定はすまい。たまにはこんなぶっ飛んだベートーヴェンを聴くのも楽しいものだ。ただ、もう一度といわれたら、ご辞退申し上げたい。自作の「黒い大地」とアンコールの「ジャズ風トルコ行進曲」(清水ミチ子を思い出した)については、どうも苦手な分野なので特に感想はない。(失礼)素人の感想でどこまで正確に彼の音楽を伝えられたか分からないが、ユニークで魅力的なピアニストであることだけは確だ。彼の弾くハイドンやモーツァルトならぜひ聴いてみたいと思う。ぜったい、いい演奏が聴けるはずだ。今日の放送を見てそう確信した。ビデオを見終わったあとで、彼のプロフィールをサイトで探してみた。以下の通りである。----------------------------------------------------------------FAZIL SAY Piano グールド以来の独創的な天才ピアニスト(ほんとかいな?) ファジル・サイはグレン・グールド以来の独創的な天才ピアニストかもしれない。ピアノを弾く姿もユニークなら音楽も極めて個性的。しかし、決して奇を衒ってはいない。彼のピアノは何よりも生命感の横溢、音楽が今そこに新しく生まれてくるかのような新鮮さに満ちている。バッハやモーツァルトと共にストラヴィンスキー《春の祭典》のCDをリリースし、その鬼才ぶりを世に知らしめたが、2002年の来日公演でもすばらしい音楽を披露して聴衆を感動と熱狂の渦に巻き込んだ。2003年にはザルツブルク音楽祭にも出演が予定され、今後ますます世界の目が釘付けになるであろう大いなる才能である。 1970年アンカラ生まれ。アンカラ音楽院でピアノと作曲を学び、17歳でデュッセルドルフ・ロベルト・シューマン音楽大学に留学。1992年から95年までベルリン・アカデミーで教える。1995年ニューヨークのヤング・コンサート・アーティスト国際オーディション第1位。同年ベラカーサ財団賞を受賞し、フランスでのデビュー・リサイタルを飾る。新鮮な個性豊かな演奏が衝撃を呼び、CDも『春の祭典』『プレイズ・モーツァルト』などが大ヒットしてブレイク。世界各地で活発な活動を展開している。作曲家でもあり、ピアノ協奏曲《シルク・ロード》《モーツァルトのトルコ風ロンドによる変奏曲》はじめ多くの作品を書いている。◆ファジル・サイの主なCDトルコ行進曲~サイ・プレイズ・モーツァルストラヴィンスキー:春の祭典(ピアノ版)シャコンヌ!~サイ・プレイズ・バッハ---------------------------------------------------------------へ~、トルコ人のピアニストとは珍しい。サッカー選手のイルハンもそうだが、トルコ移民の多いドイツで教育を受け、才能を開花させるトルコ人はたくさんいるのだろう。シューマン音大出身か~、でも彼のシューマンはできれば避けたい気がする。やっぱりモーツァルトのCDはすでに出ていた。しかも評判がいいみたい。これは買わねばなるまい。りほなさん、おもしろいピアニストを紹介してくださって、ありがとうございました。感謝!-----------------------------------------------------------------ちなみに、BS2 クラシック倶楽部、8月30日の放送は、ロナルド・ブラウティガム リサイタルで、曲目は以下の通り。 1. アンダンテと変奏曲 ヘ短調 Hob.XVIII-6 ( ハイドン作曲 ) 2. 厳格な変奏曲 ニ短調 作品54 ( メンデルスゾーン作曲 ) 3. クライスレリアーナ 作品16 ( シューマン作曲 ) 4. アイ・ガット・リズム ( ガーシュウィン作曲 ) どんな「クライスレリアーナ」が聴けるのか、また録画して見なくてはなるまい。「クラシック倶楽部」は、NHKBS2、月曜から金曜、毎朝10時から11時まで。
2004/08/26
コメント(3)
-

ザ・シンガー 「サラヴォーン ベスト3」
今日はジャズのお気に入りのご紹介。私は音楽はあまりジャンルに拘らず聴く方だが、やはりCD棚を見るとクラシックについでジャズの占有率が圧倒的に高い。もちろん、どちらもピアノが中心になる。ジャズはそれほど詳しくはないし、好きなジャズメンも極狭い範囲に限られる。好きなプレイヤーを挙げれば、極々一般的なチョイスになってしまう。ピアノならキースジャレット、ビルエバンス。サックスならキャノンボール・アダレイやコルトレーン。そしてヴォーカルならサラヴォーン、ヘレンメリル、カーメンマックレイ、アニタ・オデイ、トニーベネットといったところになるだろうか。ジャズヴォーカルは、疲れたときに聴くととても癒される。私にとってジャズヴォーカルはモーツァルトよりアルファ波がでる音楽ジャンルのようだ。ヴォーカリストでもっとも好きなのは、やはりサラヴォーンである。古今東西、クラシックも含めてうまい歌い手は数あれど、史上最高の歌手はサラヴォーンじゃないかと本気で思っている。それほどサラの歌はうまい。生前彼女は尊敬を込めて、「ザ・シンガー」と呼ばれた。まさにジャンルを超えた歌手の中の歌手がサラヴォーンなのだ。彼女の歌唱を聴くと、究極の楽器は人間の声であることが分かる。彼女の声域はジャズヴォーカリストの中でも特に広く、柔らかで豊かな低音から、伸びやかで艶っぽい高域まで、まあなんと見事に歌い上げることか。身体全体が楽器のように共鳴し、何とも心地よい歌声を聴かせてくれるのだ。特に50年代のマーキュリー時代の歌声は、ほれぼれする。名盤を3枚挙げると以下のようになる。----------------------------------------------------------●『サラヴォーン・ウィズ・クロフォードブラウン』クリフォードブラウンと組んだこのアルバムは、同じく「ヘレンメリル・ウィズ・クリフォードブラン」とともに、ジャズヴォーカルの名盤中の名盤に挙げられる傑作である。特に1曲目の「バードランドの子守歌」や2曲目「パリの4月」そして6曲目「エンブレイサブル・ユー」など一度聴いたら忘れることはできない。このアルバムのサラの歌唱は、1曲として聞き逃すことはできないと思う。もちろんクリフォードブラウンのトランペットも最高のでき。もし、サラのアルバムを1枚だけ選ぶとすれば、これになる。--------------------------------------------------------------●『サラヴォーン・アット・ミースターケリーズ』これもジャズヴォーカルの歴史に残るライブ録音である。ピアノトリオをバックに、ジャズクラブのリラックスした雰囲気の中でサラのヴォーカルが楽しめる1枚だ。1曲目「9月の雨」、8曲目「ジャスト・ア・ジゴロ」など涙が出るほどいい。またラストの「ハウ・ハイ・ザムーン」のスキャットはこれぞジャズヴォーカルの見本のような歌唱である。-----------------------------------------------------------●『サラヴォーン・イン・ロンドハウス』これもやはりジャズクラブにおけるライブレコーディングである。ミースターケリーズと甲乙付けがたい傑作アルバムだ。いきなりカーメンキャバレロの司会で始まる。といっても当夜のピアノは彼ではなく、ロンネル・ブライト。この夜のバックはピアノトリオではなくトランペット、テナーサックス、トロンボーンが加わったセクステットである。このアルバムのサラは、ミースターケリーズよりリラックスしてるようで、軽快でノリのいいヴォーカルを聴かせてくれる。4曲目「I'llstring along with you」のしっとりした歌唱。それに続く5曲目「You'd be so nice to come home to]は、ヘレンメリルと聞き比べるとおもしろい。◆このCDは残念ながら楽天では見あたらなかった。-------------------------------------------------------このほかにも、サラヴォーンの名盤は数限りなくある。彼女はジャズナンバーに拘らず、ポップスやボサノバ、ミュージカルなど幅広いジャンルの歌を取り上げ、自分のレパートリーを広げていった希有なジャズシンガーである。他のお薦めアルバムにつていは次に機会にして、今日はここまで。
2004/08/24
コメント(0)
-

シューマン 交響的練習曲もいろいろ
久しぶりにシューマンの交響的練習曲のCDを聴いた。私のお気に入りには、ポリーニの演奏である。この曲を初めて聴いたのもやはりポリーニだった。1982年6月のウィーン芸術週間におけるリサイタルの録音で、NHKのFMで放送された時のエアーチェックである。その時のカセットテープはいまも手元に残っている。私は、ポリーニの弾くこのシューマンの傑作を繰り返し聴いた。これが、シューマンの魅力を初めて教えてくれた演奏だった。それから数年して手に入れたCDは、ウィーンのライブに較べると、録音の関係かもしないがより澄んだ響きで、はるかに深い音楽になっている。そのかわり、音楽から伝わる熱気は若干失われてしまったように思われる。特に最後の第12練習曲は圧倒的にライブの方が迫力がある。しかしCDのポリーニの演奏が、交響的練習曲の希有な名演であることにかわりはない。交響的練習曲は、楽譜の出版年や変奏曲の扱いによっていくつかの版があるが、現在主に演奏されるのは1873年にブラームスによって出版された全曲版が多いようだ。全曲版には、12曲の練習曲に1837年版では削除された5つの変奏曲が「遺作」として加えられている。この5曲を12の練習曲のどこに挿入するかは、演奏者に任されているらしい。ポリーニは、第5と第6練習曲の間に一括して5曲の変奏曲を挿入して演奏している。ちなみに、他のピアニストはどのように演奏しているのか調べてみた。シュケナージは第3練習曲のあとに3曲、第8練習曲のあとに2曲。シフは練習曲と5つの変奏をまったく別々に演奏。コルトーは、練習曲間のあちこちに分散して挿入しているようだ。交響的練習曲はリヒテルやブレンデルなども録音しているが、機会があれば聞き比べてみたいと思っている。もし他のピアニストがどのように交響的練習曲を演奏しているかご存じの方いれば、ぜひ教えて欲しい。
2004/08/23
コメント(1)
-

今日は私の誕生日「ボイジャー2号の独白」
いま、私は太陽系を離れ恒星間を飛び続けています。どこに向かっているのか、どこにたどり着くのか、誰も知りません。もちろん、私自身も‥‥。私が外部太陽系の惑星探査のミッションを与えられ、地球を旅立ったのは、地球時間、1977年の今日8月20日でした。人間で言えば、今日は私の27回目の誕生日ということになりますでしょうか?私はいままで外部太陽系惑星、つまり小惑星帯の外側の木星、土星、天王星、海王星を探査してきました。これらの惑星は地球や火星などと違って地殻を持たず、水素やヘリウムなどからなるガス惑星です。実は、この4個の外惑星は175年に1度概ね一列に並ぶのです。そうです、この絶好の機会を捉えて、27年前私は宇宙に旅立ったわけです。打ち上げから2年後の1979年7月9日に私は木星に接近。さらに1981年には土星に。1986年に天王星。そして打ち上げから実に12年後の1989年、ついに海王星に接近することに成功しました。このとき私が撮影した海王星の映像は、地球でもテレビ放映されたのでご覧になった方も多いと思います。この惑星探査のミッションで、私は兄の1号とともに、次々に新しい衛星を発見し、その画像を地球に送り続けました。そして、1990年2月、太陽系の九つの惑星を撮影した写真を最後に、ひとつの任務を終えたのです。私はたった一人、いまも果てしない宇宙の中を飛び続け、二度と地球に帰還することはありません。それが私の運命なのです。太陽系を離れた今も、私にはもう一つのミッションが残されています。それは、地球外の知的生命体に一枚のレコードを届けることです。このミッションは、皆さんもよくご存じの偉大な天文学者、カール・セーガン博士のアイデアです。『地球の音(THE SOUNDS OF EARTH)』と名付けれらたこのレコードには、地球のいろいろな国のあいさつや民族音楽、クラシックの名曲などが録音されています。 音楽のリストには、「ブランデンブルク協奏曲第2番」「運命」「魔笛」のアリアなどとともに、グレン・グールド氏の弾くバッハが入っています。曲は、平均律クラヴィア曲集の第1番です。おそらくセーガン博士の趣味が反映されたのでしょう。私も、グルード氏のピアノの大ファンです。もし許されるのなら今すぐにでもここで彼のピアノを聴いてみたいのですが、大切なレコードですからそれも許されません。私はかねてからグールド氏はひょっとすると宇宙人ではないかと思っていました。ですから、セーガン博士がグールド氏のバッハ、しかも平均律クラヴィア曲集を選んだことは、私には単なる偶然とはどうしても考えられないのです。バッハの平均律は、まさに音楽の小宇宙を表す曲集ですし‥‥。幸運にも私がこのレコードをどこかの星に住む知的生命体に届けることができたとして、彼らはグールド氏の演奏するバッハをどのように評価するのでしょうか。気に入ってくれるでしょうか?私がこのミッションを遂行できるかどうかですか?どうでしょう、それはまさに神のみぞ知る、と申し上げるしかないでしょう。えっ、私の名前ですか?私の名は、ボイジャー2号と申します。 -------------------------------------------------------------●『地球の音(THE SOUND OF EARTH)』について詳しく知りたければ以下のサイトへhttp://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/music.html--------------------------------------------------------------太陽系シミュレーター 時空を超えた惑星間飛行( 著者: Solar System Simulat | 出版社: 講談社 )太陽系内での過去・現在・未来2万年間の天体現象を、あらゆる地点、角度から見ることができる画期的3D・CG。あの日、あの時、あの地点で、星々はどのような瞬きをみせるのか。日食や月食、流星雨はどのように見えるのか。パソコンの中に太陽系がそっくり再現された?!火星に行く?月に降り立つ?土星の輪をくぐる?太陽系内での過去・現在・未来の天体現象を、あらゆる地点、角度から見られるリアルな3Dグラフィックスで再現できる。
2004/08/20
コメント(1)
-

「さよなら子供たち」の音楽
先週のお薦め映画「さよなら子供たち」のラストはやはり泣けた。 ストーリーは、ユダヤ人のボネが学校に転向してからゲシュタポに捕まるまでのお話。 暗めの色調で描かれる中学校の生活や周辺の森の風景はテレビで観ても美しさが伝わってきた。少年の生活と心の交流が淡々と描かれる地味な映画なので、正直だれるところもあるが、最後の別れのシーンは胸にせまるものがある。篠田正浩監督の「少年時代」を思い出した。お薦めである。 さて、この映画には、シューベルト「楽興の時」第2番が重要なシーンで繰り返し流れ、とても印象に残った。 もうひとつ音楽で印象に残ったのは、子供たちがみんなでチャップリンの喜劇を観るシーン。スクリーンの脇でピアノとヴァイオリンの伴奏音楽として、サンサーンスの「序奏とロンド・カプリッチョーソ」演奏される。ご存じの方もいるかも知れないが、映画の歴史上初めて映画のためにオリジナル曲を書いた作曲家は、サン・サーンスである。フランス人のルイ・マル監督はきっとこの事実を意識して、サン・サーンスを使ったのではないかと思う。 サン・サーンスが音楽を提供したのは、1903年に制作された「ギーズ公の暗殺」という歴史的事件を題材にした18分ほどの映画である。サン・サーンスは、別名フランスのモーツァルトとも呼ばれた天才作曲家。しかし、この称号にはどんな大曲でも安易に創ってしまうという、皮肉も込められていたようだ。サン・サーンスの映画音楽がいかなるものか、聴いたことがないのでわからないが、当時すでに78歳だったサン・サーンスが、誕生したばかりの映画という新しい芸術に果敢に挑戦した心意気は、評価されるべきだろう。
2004/08/18
コメント(1)
-

2つの日本・イタリア戦「明と暗」
昨日のアテネオリンピックは、2つ日本・イタリア戦を見ることができた。偶然とはいえ、同日にサッカーと野球で両国が戦うことになったのは、何とも皮肉だ。この2つのスポーツの置かれた現状はあまりにも違いすぎる。昨日の2つゲームは、その明と暗を見せられた気がする。野球は12対0で日本の7回コールド勝ち。サッカーは2対3で日本は敗れ、決勝トーナメントへの道を閉ざされた。試合結果から見れば、野球が「明」で、サッカーが「暗」ということになる。しかし、スポーツとしての未来を考えればまったく違ってくる。昨日の日本・イタリア戦は、皮肉にも野球がオリンピックの競技種目として不的確であることを証明する結果になったと思う。スコアはもちろん、それ以上に両国の実力差は観るスポーツとしての興味を失わせるものだった。イタリア代表の選手には申し訳ないが、守備だけ見ても甲子園で戦っている高校生の方がはるかに訓練されており、うまい。日本のプロ軍団がいまのイタリア代表に勝ったとしても、どれほどの価値があるのだろうか。おそらくイタリアと10戦して1つも負けることはないだろう。オリンピックもプロが当たり前になった今日、戦う前から勝敗の予想がつくスポーツではしらけるばかりだ。(イタリアにも野球のプロリーグがあるらしい)一方のサッカーは野球に較べ、国際間の力の差は確実に縮まっている。オリンピックやワールドカップに出場するような国同士なら、もはや番狂わせという言葉は死語になりつつある。昨日のゲームもイタリアが本調子ではないのに救われたこともあるが、サッカーの試合として充分楽しめる対戦だった。(ただ日本はあまりにも簡単に点を取られすぎ!)リハビリ中の長島監督には申し訳ないが、メダルを賭けた日本野球チームの試合と、サッカーの決勝が同時刻の放送になれば、私は間違いなくサッカーを見るだろう。私は、野球がオリンピック競技としてふさわしいとは思わない。野球はマイナースポーツ故に、国際試合として力が拮抗しゲームとして興味を持つことができるカードは限られている。今回のオリンピックでも出場国はわずか8カ国にすぎない。しかもその中に野球の母国・米国やプロリーグのある韓国は入っていない。両国とも予選で敗れたとはいえ、この2つの国を抜きにして世界1を競う大会に本当に意味があるのか疑問だ。そもそもアメリカ・メジャーリーグは、端からオリンピックなど無視しているに等しい。このような状態が続けば、早晩野球がオリンピック種目から消える日がやってくるのは間違いだろう。北京はどうにかもぐりこめても、それ以降は厳しいだろう。国際化なくして、野球に未来はないと思うが、施設や用具などさまざまなハンディキャップを背負った野球が、マイナースポーツを脱して国際的に発展していくのは容易なことではないだろう。オリンピックの野球の未来も暗いが、1リーグ制でもめている日本のプロ野球の現実はもっと深刻だ。せめて、アテネの長島ジャパンには是が非でも金メダルを獲得し、一時でも明るい話題を提供してくれることを願うばかりである。
2004/08/16
コメント(1)
-

奇病「ピアノリア」
昨日の夜、こんな夢を見た。なぜか、私はある心療内科の医師の診察を受けているのだ。--------------------------------------------------------------医師「やはり、ピアノリアの数値が異常に高いですね」私「そうですか。最近、ピアノ曲以外聴いてないからですかね。でも以前より聴く時間はめっきり少なくなってはいるんですが」医師「あ~、それは症状が大分すすんでいる兆候ですよ。だめですよ、音楽はちゃんとバランスよく聴かないと。でも、珍しいですよね。kaigenjiさんみたいな方がピアノリアに感染するなんて‥‥」私「そうなんですか?」医師「これはある心療内科の臨床研究なんですがね、ピアノリアは子どもの頃からピアノを習っていた女性が感染しやすいみたいです。特に、音大のピアノ科の学生さんは9割以上が発症するという報告もあるんです」私「ほんとうに?実は先生、私も20歳過ぎてから半年だけピアノ習ったことがあるんですよ」医師「あっ、それだ!その時感染したんだ、きっと!なぜ、もっと早く言ってくれなかったんですか?20歳過ぎてからピアノリアに感染するすると治りにくいんですよ」私「ピアノリアの症状が悪化すると、どうなるんですか?」医師「ピアノ曲以外まったく受け付けなくなります」私「でもたかが音楽じゃないですか」医師「確かに、ピアノ曲だけでもまだ聴けるうちはいいです。でも症状がさらに進むと、音楽そのものがつまらなくなって、まったく聴かなくなってしまうんです」私「どういうことですか?」医師「つまりこういうことです。そもそもクラシック音楽というのは限られたレパートリーでなり立っているとても特殊な音楽なんです。もう、新しい曲なんて出てくる可能性はほとんどありません」私「確かにそうですね」医師「ピアノリアに似た病気としては、シンフォニア、オペラニアなんて病気も報告されてはいるんですが、こうした病気の患者さんはあくまでも交響曲好き、オペラ好きというだけで、症状が軽いというか、他のジャンルもちゃんと聴けるんですね。でも、ピアノリアはたちが悪くて、ピアノに異常な執着を持つようになってしまうんですね」私「でも、私は理解できるな、その気持ち」医師「でも問題は、ピアノ曲のレパートリーです。ピアノ曲はたくさんありそうですが、頻繁に演奏される曲となると意外と少ないんですよ。作曲家も、限られてきますしね。おそらく数年かけて、CDや演奏会を聴けば、聞き尽くしてしまうでしょう。未知の曲がなくなると、次はどうなるか」私「聞きくらべですか」医師「そうです。これがピアノリアのステージ2です。正式な音楽教育を受けた方は、ピアノリアに感染してもステージ2止まりです。しかし、危険なのはいわゆる素人のピアノリア患者です」私「まさに、私ですね」医師「そうですね。kaigenjiさんのような素人のピアノリア患者さんは、自分の演奏体験と有名演奏家の演奏を聞き比べるという専門的なスキルを持っていませんよね。だから、感覚的に好きか嫌いかという単純な判断しかできません。そうなると探求も深まっていきません、そこで聞きくらべもすぐに飽きてしまうんですよ」私「私もそういう時がありました」医師「ステージ3に進むのはほとんどが素人のピアノリア患者さんです」私「ステージ3になると、どういう症状がでるんですか」医師「ええ、たいがい作曲家の伝記や裏話に興味を持つようになります。特にショパンやシューマンはいろんな話がありますからね」私「‥‥(ドキっ!)‥‥」医師「芸術家の逸話やスキャンダルを探ることは、音楽とはまったく別の楽しみなんですね。そういう冷静な判断ができないと、とんでもないことになります」私「たしかに、思い当たることがあります」医師「そうでしょう。kaigenjiさん、最近、音楽を聴いても作曲家の私生活がちらちら頭をよぎりませんか?純粋に音楽を楽しめないとか‥‥」私「確かに、先生のおっしゃるような兆候があります」医師「なるほどはっきり申し上げて、kaigenjiさんは重症ですね。音楽を楽しめないことがやがてストレスになって、身体にいろいろな影響が出てきます。そうなる前に、早急に治療が必要ですね」私「具体的にどういう治療法があるんですか?」医師「まず、ショパンとシューマンだけは聴かないでください。ピアノリアの症状を悪化さるだけですから‥‥」私「しかし、私、1日に1度はピアノを聴かないといられないんですけど」医師「そうですか?じゃあ、こうしましょ。どうしてもピアノを聴きたいのであれば、ベートーヴェンかモーツァルトにしてください。ただし、ソナタは駄目ですよ。かならずコンチェルトか室内楽にしてください」私「わかりました。努力します」医師「それと、お薬出しておきましょうね」私「くすり?」医師「ええ、1日3度食後10分、繰り返しこのCDを必ず聴いてください」私「えっ‥‥、これってマツケンサンバ?」医師「強いお薬なんで、多少副作用があるかもしれませんが、重症患者さんにはこれくらいじゃないと、効き目がないんです」私「先生、マツケンサンバは勘弁してください」医師「病気、治したくないんですか。マツケンサンバを聴いたあとで、なんでもいいですから交響曲か室内楽を聴いていください。きっと新鮮な気持ちで聴けるはずですから」私「そんなことで治るんでしょうか」医師「私を信じてください。まあ、暫くこの治療を続けてみて、症状が改善したら徐々にピアノ曲の新しい録音をご紹介しますから、気長に治療していきましょう。そうすれば、また以前のように新鮮な気持ちで音楽が楽しめるようになりますよ、きっと」私「はい、宜しくお願いします」医師「あっそうだ、申し訳ないんですが、マツケンサンバは保険対象外ですから‥‥、ご了承ください」私「はあ~」医師「じゃあ、来週また来てください。予約入れておきますから‥‥。お大事にどうぞ」私「ありがとうございました」-------------------------------------------------------私のピアノリアは、最近ますますひどくなっている。
2004/08/11
コメント(1)
-

音楽家の言葉
今日は、永六輔氏が自分のコンサートの冒頭でいつも読み上げるという、世界の音楽人の言葉の中から、クラシック音楽界の有名人のものをご紹介。それぞれ、なかなか味わい深い。●ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン「音楽は、いかなる知恵、いかなる哲学よりも、さらに高い啓示を与える」●ヨハン・セバスチャン・バッハ「音楽は世界語であって翻訳される必要がない。そこでは魂が魂に話しかける」●アリストテレス「音楽教育の嫌いな子どもはいる。でも、音楽の嫌いな子どもはいない。音楽に忠実なことが楽譜に忠実とは限らない」●ウィルヘルム・フルトヴェングラー「人間的な感動というものは、人間の内側にあるのではなく、人と人の間にあるものだ。」●チャールズ・チャップリン(業界人ではないが)「音と音の間にあるのが、音楽だ」●パブロ・カザルス「私は演奏するたびに違う。でも、それは私が生きている証拠だ」●ヴラディミール・ホロヴィッツ「完全であること自体が不完全だ」●ドミトリー・ショスタコヴィッチ「創造的な芸術家は前の作品に満足していないから、だから次の作品に取りかかる」●レオポルド・ストコフスキー「画家はキャンバスに絵を描く。音楽家は静寂の上に絵を描く。私は音楽をつくる人間で、聴衆は静寂をつくる人間だ」●イーゴル・ストラヴィンスキー「耳を傾けて聴くには努力がいる。ただ聴いているだけならアヒルだって聴いてくれる」----------------------------------------------------------NHK人間講座/永六輔 人はなぜ歌うか(六輔流・日本音楽史)
2004/08/09
コメント(2)
-

ショパン 引き裂かれた肖像
ショパンの肖像画ときいて、どの絵を思い浮かべるだろうか。音楽室の壁や伝記本などで比較的目にする機会が多いのは、ドラクロアあるいはシェフェールの作品ではないだろうか。 ドラクロアの描いたショパンは、28歳の時の肖像。 そして、シェフェールというほとんど無名の画家の筆による肖像は、 37歳の時の姿である。 作者が誰であるかを知らされなくても、どちらが芸術として優れているかは明かで ある。しかし、ショパンはドラクロアの描いた肖像がシェフィールのものより 自分に似ていないという理由だけで、気に入らなかったようだ。 ショパンには画家の深い洞察力など理解できなかったのだろうか。 サンドのこんな証言がある。 ‥‥でも、ショパンは友人(ドラクロア)の絵を見ると文字通り苦しみ、 言う言葉が見つからないのでした。彼は音楽家であり、それ以上のものでない のです。彼のアイデアは音楽にだけ移すことができるのです。彼は奥の深い、 極めて繊細な心情の持ち主ですが、絵や彫刻はまるでわからないのです。‥‥ 何とも辛辣な言葉だが、彼の芸術をもっとも理解し、かつ身近に接した サンドの証言だけに、真実なのだろう。 ドラクロアがこの肖像画を描いたのは、1838年である。 その年の11月ショパンはサンドとともにマジョルカ島に転地療養に旅立つ。 実は、このショパンの肖像の隣にはサンドの姿描かれていた。 つまり、一枚のキャンバスに二人の肖像が一緒に描かれていたのだ。 後年、所有者の経済的理由で、2枚に切り裂き売り払ってしまったらしい。 何とも無茶なことをしたものだ。 ショパンの肖像は現在、パリ・ルーブル美術館に、サンドの肖像は コペンハーゲンのアルド美術館に別々に所蔵されている。 さらに、ルーヴル美術館には、この肖像画の構想と思われる鉛筆スケッチも 残されている。 それには、ショパンがピアノを弾き、サンドがそれに聴き入っている姿が 描かれているという。 しかし、ドラクロアはこの構図を捨てた。 「ショパンのピアノを聴くサンド」というありきたりのアイデアから、 ピアノが削られ、ショパンの横顔のクローズアップ(ピアノの前に座って いるように見えなくもない)と、それを静かに見守るかのようなサンドの姿だけを残した。 一枚の絵に描かれたショパンとサンドは、所有者の身勝手な理由によって 引き裂かてしまった。 ドラクロアには申し訳ないが、この悲劇によって二人の愛憎は、ますます ドラマチックなものに見えてくる。
2004/08/08
コメント(1)
-

音楽が好きな動物、嫌いな動物
モーツァルトの音楽が現代人に安らぎを与えるということで、人気を呼んでいる。純粋に音楽を楽しむのではなく、別の目的で音楽を聴くことにどこまで価値があるのか疑問だが、クラシック音楽のファンが増えることは良いことだと思う。モーツァルトの音楽効果は、取り立てて新しい話題ではなく、過去何度となく取り上げられてきた。人間に限らず音楽のもつ不思議な効果は、いろいろ語られている。乳牛にモーツァルトを聴かせると乳の出が良くなるとか、日本酒の酒蔵でモーツァルトを流すと、酵母が活性化しうまい酒ができる。はたまた、「モーツァルトを聴かせた紅茶キャンディ」なるものまで登場した。小さいとはいえ脳細胞をもった牛は何とか理解できるが、日本酒やキャンディとなると、何とも疑わしい。では牛以外の動物はどうなのだろうか?音楽を好むのか、好まないのか、当然そうした疑問がわいてくる。そこでちょっと調べてみたら、おもしろい話を発見した。時は、第二次世界大戦後間もない1950 年代。ところは、イギリス。クラシックレーベルとして有名なDECCAと思われるレコード会社が、ロンドの動物園で、音楽に対する動物達の反応を調べたらしい。実験には、二挺のヴァイオリンの他に、フルート、オーボエ、ハーモニカという、何とも奇妙な編成の楽隊が用意され、園内を巡回した。その結果は‥‥‥‥。もっとも興味を示したのは、やはり我々人間に一番近いサルだった。とはいえ、これは音楽が好きというより単なる好奇心ではないかと分析された。おもしろいのはサイである。サイは徹底的に音楽を嫌ったらしい。クラシックにもポップスにも激しい怒りをあらわにし、なんと楽隊に襲いかからんばかりの勢いで迫ってきたという。逆に、アシカやオットセイの類は、他のどの動物よりも音楽を好むようだ。アザラシは楽隊の演奏する最初の音を聞くと、すぐに水の中から浮かび上がってきて、うっとりと音楽に聞き入っていたという。猫はなぜかまったく関心を示さなかったらしい。複雑なのは狼とジャッカルと狐である。この同系の動物は、なぜか長調のメロディは皆、落ち着いて聞いているのに、最初の短調の音が響いた途端、鼻面を天に向けて恐ろしい吼え声をあげたらしい。なんとも不思議だ。最後に楽隊がワニの池の前で演奏したときには、まるで命令されたように水から出て、最後の音が消えていくまで頭を上げてじっと耳を傾けていたという。 まるでディズニー映画を見るような光景だ。この実験では、動物がなぜこのような反応を示すのか、納得のいく回答を得られなかったらしい。自然には、科学では解明できないことの方が多い。しかし、この実験結果を宮沢賢治が知ったら、続・セロ弾きゴーシュには、セロを聴くオオカミやワニの群れが登場するのだろうか?‥‥参考資料:関楠生著「世にも不思議?!―信じられない本当の話」(同文書院刊)-------------------------------------------------------------●動物が登場する音楽童話スペシャル・コレクション セロ弾きのゴーシュ ◆20%OFF!<DVD> [GNBA-3002]●ブレーメンのおんがくたい(グリム)●よくわかる幼児のおんぷとりずむ 2/ブレーメンのおんがくたいの巻
2004/08/07
コメント(4)
-

「冬ソナ」「キャンディ・キャンディ」「大映ドラマ」を結ぶもの
「冬ソナ」の女性脚本家が「キャンディ・キャンディ」を参考にしたいう話題は、フジテレビのニュース番組で放送されたので、すでにご存じの方も多いと思う。韓国でキャンディ・キャンディが初めて放送されたのは、日本とほぼ同時期の70年代後半。当時の韓国は日本文化に対して厳しい時代であったが、アニメは別格で唯一見られる日本のテレビ番組だった。「冬ソナ」の脚本を担当したユン・ウンギョンさんも、幼い頃キャンディ・キャンディを見て育った世代だという。今週の週刊新潮には、「冬ソナ」と「キャンディ・キャンディ」の共通点、さらにコラムニスト・丸山タケシ氏の「大映ドラマ」との比較分析が掲載されており、興味深い。簡潔に紹介しよう。●「冬ソナ」と「キャンディ・キャンディ」の共通点★ヒロインの恋人がある日突然事故死し、その後面影はそっくりなのに性格が反対の男性が現れる。★主要な登場人物が重篤な記憶喪失に陥ったまま、支障なく日常生活を送っている。★血のつながりのない大金持ちの親族が、陰から強力にバックアップしてくれる。などの逸話が共通点としてあげられている。これについてのコラムニスト・丸山タケシ氏の解説がおもしろい。氏によれば、以下の点で「冬ソナ」「キャンディ・キャンディ」ともに昔の大映ドラマの作り方に酷似しているというのだ。★舞台設定は違うが、主役の二人に次々に障害を与えて作るストーリー(ほとんどのドラマの基本だと思うが)★悪人、善人の性格を明確に描いている。(これもこの種のドラマの常套手段である)★さまざまな障害を乗り越え、ラストはきちんとハッピーエンドで終わる。往年の赤いシリーズをご存じの年代なら、思い当たるところがあるだろう。赤いシリーズはまさにメロドラマの王道をいく筋立てのドラマだった。それは「冬ソナ」も同じとと言うわけだ。「キャンディ・キャンディ」や「赤いシリーズ」がヒットした70年代後半は、現代の「冬ソナ」人気を支える女性たちの多くが、多感な少女時代を過ごした時とピタリ一致する。いわば彼女たちの眠れるDNAを「冬のソナタ」が呼び覚ました恰好になる。「冬ソナ」は、なぜある年代の女性たちに熱狂的に支持されるのか、私にもやっと納得がいく答えが見つかった気がする。「冬ソナ」第2回『出生の秘密を知ったユサン』では、「テンペスト」が流れるという。そう、あの赤いシリーズでおなじみのベートーヴェンのピアノソナタだ。他の回には、トロイメライ、雨だれ、アルビノーニのアダージョ、ラフマニノフのコンチェルトなど、クラシックのオムニバスアルバムのようなBGMが流れ、ドラマを盛り上げる。クラシックファンなら、何とも恥ずかしくて聴いていられないような選曲だと思うのだが‥‥。先日、私の日記に「僕は冬ソナは妹と2人で見て、笑っちゃってます。」と書き込みをされた方がいた。私も、いままで「冬ソナ」をバカにして見ようとも思わなかった。しかし、今週の新潮の記事を読むにつけ、別な意味で「冬ソナ」に対する変な興味がわいてきている。この夏の再放送は、本気で見てみようかな‥‥?その前に「赤いソナタ」なんてドラマが韓国で始まったりして?キャンディ・キャンディ 愛蔵版 全2巻 いがらしゆみこ・水木杏子/作赤い運命 1赤い絆 1 ◆20%OFF!<DVD> [PCBP-50345]DVD/冬のソナタ DVD-BOX 1TVドラマ「冬のソナタ」で使われたクラシック音楽集★注:これはよくありがちなクラシックのオムニバス盤ではなく、冬ソナで使われた名曲の全楽章、曲集なら全曲がきちんと収められたCDです。値段も安いし、クラシック入門にも最適です。
2004/08/06
コメント(5)
-
「しゅうまん」という菓子を見つけた
きのうの日記の「枕話」は、ご推察のとおり、私の創作である。 しかし、すべてが作り話というわけではない。以前どこかの観光地の土産で、確かにカスタードクリームの入った饅頭をもらったことがある。その饅頭が何という名前だったか憶えていないが、少なくとも「しゅー饅」ではなかった。「しゅー饅」という饅頭がなければ、私の話はまったくの嘘になってしまう。 そこで、ほんとうに「シュー饅」という饅頭がないのか、調べてみることにした。もし世の中にそのような饅頭が存在すれば、私の嘘も罪が軽くなる。早速、検索サイトで探してみた。 さすがに「シュー饅」はなかった。しかし、「しゅうまん」なら1つだけ見つかった。 しかも、なんと「シューマン」というケーキ屋が作っている菓子らしい。(注:スペルは違う)場所は、静岡市高松。有名な登呂遺跡の近くにあるパティスリーとのこと。地元では、シュークリームが評判らしい。 私の想像だが、店主がきっとクラシック音楽のファンなのだろう。果たして、「しゅうまん」なる菓子はいかなるものか? 店舗の写真は、あるサイトで見つけたが、「しゅうまん」の写真は見あたらない。 ただ、別のサイトにはこう書かれている。「シュー皮で包んだロールケーキ『しゅうまん』はなかなか美味しかったですよ」つまり、オリジナルのロールケーキの名が「しゅうまん」と言うらしい。私の創作「シュー饅」とは違うが、「しゅうまん」という菓子は世の中に確かにあった。「静岡市の有名な登呂遺跡の近くには、シューマンとういケーキ屋があり、その店で人気のロールケーキの名は‥‥‥‥‥‥、『しゅうまん』」この「トリビアの泉」的情報に免じて、どうか私の嘘を許して欲しい。** シューマン ・静岡市高松2-1-35 Pあり ・10:00~20:00 火曜定休 ・シュークリームが評判の、可愛いケーキ屋さんです。
2004/08/04
コメント(2)
-

嫌われ者のシューマン
私が「シューマンが好きだ」というと、必ず怪訝な顔をされる。クラシックなど聴いたことのない女の子だと、「あっ、それ食べたことアル~」となる。何のことかと思ったら、どうもカスタードクリームの入った饅頭があるらしい。「シューマン先生と饅頭を一緒にするんじゃ~ねえ、バカ野郎!」それにしてもシューマン・ファンはマイナーだ。辛うじてC1(クラシック1部リーグの意)に所属してはいるが、常に下位を低迷し、C2ながら実力派のマーラー、ブルックナーとの入れ替え戦の危機にさらされている。管弦楽だけなら、ショパンと一緒にC2降格は間違いない。シューマンの不人気は今に始まったことではなく、実は彼の生存中はもっとひどかったようだ。彼ほど作品演奏の機会に恵まれなかった作曲家もめずらしいという。彼の音楽が、当時受け入れられなかったのには原因がある。それは、シューマンがそれまでの音楽形式をほとんど捨ててしまったことだ。彼は音楽史上初の完全な反古典主義者であり、今風に言えば「改革の旗手」だった。しかし、旗は振れども、誰も彼の後を追いてきてくれなかった。友人のメンデルゾーンも、シューマンに天才と賞賛されたショパンでさえ、シューマンの音楽を正当に評価しなかった。唯一リストだけは演奏会でシューマンの作品を頻繁に取り上げたようだが、いずれも失敗に終わったという。極め付きは、奥さんのクララである。天才女流ピアニストだったクララは、内助の功を発揮してシューマンのピアノ作品を演奏会で紹介し続けた。そのクララも、内心では「最高の作曲家は交響曲やオペラの作者だ」と信じ、夫・シューマンにいつかはその種の音楽を書いて欲しいと考えていた。事実、心やさしいシューマンは妻の意向を汲んで、不向きの分野にも挑んだ。彼の最初の交響曲「春」はわずか4日で書き上げられた。「な~んだ、あなたやればでるじゃない!」とクララが言ったかどうかは知らないが、交響曲の1曲くらい楽理に精通したシューマンには朝飯前だったことは確かだ。しかし、自分に不向きとかわっている分野の曲を作るのは、きっとつらい作業だったに違いない。シューマンが狂ったのは、もしかしたら彼の「血」だけではなく、周囲の無理解にもあるのではないか、と私は同情する。さてこのような状態だから、シューマンの音楽は保守的な当時の批評家の恰好の批判対象となった。ある日、ひとりの批評家が、ソナタを書かないシューマンを批判した。それに対してシューマンは、「内容と思想が形式を定めるのであって、その逆ではない」と反論したという。(本当はもっと難しい言い方をしたのだが)「そんなの当たり前ジャン!」と言われるかも知れないが、これはとてもモダンな発想である。同時代の作曲家たちの多くは、形式というある種の呪縛の中で格闘していた。当時の価値観では、形式を逸脱することは、すなわち音楽的価値を失うのに等しい。あのベートーヴェンでさえ、晩年になってようやく抵抗を試みたが、結局その呪縛から完全に解放されることはなかった。シューマンはシューマンであり、他の誰にも似ていない。ある研究家の言葉を借りれば、「モーツァルトやベートーヴェンなどの天才作曲家でも、必ず先人の影響を受けている。天才ショパンでさえ初期の作品ではフィールドやウェーバーの影響が見られる。だが、シューマンは最初から独力で作品を書き、彼の音楽の先例を見いだすのは困難である」となる。「シューマン音楽」の独創性には、彼の育った環境が大きく影響していると思う。シューマンは基本的に音楽を独学で学んだ。「嘘だろ!」と思われるかも知れないが、本当なのだ。。シューマンの生まれた家は、書籍商、つまり本屋だった。彼は、決して音楽一家に育ったわけではない。18歳でライプチッヒ大学の法科に学ぶ傍ら、後に結ばれるクララの父ヴィーク教授についてピアノを学び始めるまで、シューマンは専門的な音楽教育をほとんど受けていなかった。成人するまでアマチュアのままでいた大作曲家は、シューマンぐらいしかいないのではないか。7歳のころには作曲をはじめ、即興演奏も得意だったらしいが、神童ともて囃されたモーツァルトやベートーヴェンなどとは、まったく違った音楽環境にいたのだ。音楽とともに彼のもう一つの興味の対象は、文学だった。物心のつき始めたころから、実家の店先から本を引っ張り出して、片っ端から読みあさったらしい。特に、当時流行のロマン派作家の作品を好んだという。シューマンは、音楽家としてはまれに見る教養人だった。このような過去の音楽とは無縁な環境が、彼を自由な精神をもった音楽家に仕立てたといっても間違いではないだろう。ロマン派の文学を愛し、その影響下で育ったシューマンが、自分の文学への思いやイメージを音楽で自由に表現したいと考え時、過去の音楽形式をいっさい捨てたとしても何の不自然さも感じない。ある時は気まぐれで、予想外の展開で聴く人を驚かす。情緒に溺れ、流されそうになりながら、ぎりぎりのところで踏みとどまる。なんとも不思議な魅力をもった音楽家‥‥。それがシューマンだと思う。どうです、少しはシューマンを見直して頂けましたか?----------------------------------------------------今日の1枚は、シューマンの死後、彼の音楽が認められる切っ掛けとなったピアノ協奏曲イ短調の名演奏を選んでみた。巨匠・」リヒテルとマタチッチの共演。一緒に、人気のグリーグの協奏曲も収録されている。グリーグ&シューマン:ピアノ協奏曲●あまりネタはばらしたくないが、大作曲家の裏事情なら、この本がおもしろい大作曲家の生涯(音楽書)著者・シェーンバーグは音楽史をみっちり仕込んだと、ニューヨークタイムス誌の主席批評家として活躍したその道の権威。とはいっても、楽譜を引用しながら音楽理論や技術を語るのではなく、大作曲家たちがどのような時代を生き、どのうな人生をたどったか、エピソード交えながら、生き生きと書いている。私のような全くの素人でも楽しく読めた。お薦めである。(ネタがバレるので、できたら買わないで欲しい!)
2004/08/03
コメント(8)
-

ドラマ「すいか」DVD-BOXをやっと
遅ればせながら、ドラマ「すいか」のDVD-BOXを手に入れた。予約販売時の在庫残なので、格安で購入できた。購入をお考えの方は急いだ方がいい。(初回特典映像あり)さて、好きな小林聡美主演ということで、放送開始時から毎週楽しみに見続けたドラマである。とても良かったので、DVDが出たら必ず買おうと思っていて、今日まで延び延びになってしまった。久しぶりに見たが、やはりこのドラマは、近年まれに見る傑作である。放送時、視聴率1桁台だったのが本当に信じられない。日本人はいったいこの時間にどんな裏番組を見ていたのだ!しかし、今年4月、脚本の木皿泉が向田邦子賞を受賞したという。分かっている人は分かっているのだ。木皿は過去の受賞者の誰よりも、この賞にふさわしい脚本家ではないかと思う。(拍手!)●脚本がいい(木皿泉)。その巧みさは、賞を受賞したから言うのではないが、まさに向田邦子を彷彿とさせる。それは持ち上げすぎだと、異論を唱える向田ファンもいるかもしれないが、木皿の脚本はそれほどうまいのだ。(第7回のみ、山田あかね脚本)●次に役者がいい。小林はもちろん、同僚の3億円横領犯の小泉。同居人のともさか、市川、浅丘。さらに心憎いのが、脇にもたいまさこ、白石加代子という芸達者な怪女優を配している。脚本と役者だけでも、このドラマの成功は約束されていた。●演出も、なつかしい雰囲気とディテールに拘ったカットとカメラで、脚本の意図を生かした、「行間を楽しむ」ような奥行きのあるドラマに仕上げている。タイトルの「すいか」は、番組宣伝から借りると、【タネなしすいかじゃ何だか物足りない。人生は悩みのタネがつきない。人生もタネがなきゃ物足りない。】こういう意味らしい。物語は、OLの三億円横領という大事件から始まるドラマだが、これを除けばストーリーに取り立ててドラマチックな展開があるわけではない。殺人事件もなければ、ヤキモキするような恋愛もない。舞台となるのは、ハピネス三茶という人食ったような名前のまかない付下宿屋。一昔前のなんともなつかしい雰囲気だ。そこに、浅丘の大学教授とともさか扮する貧乏漫画家が住んでいる。その一部屋にひょんなことから、小林が転がり込んできてドラマが始まる。なさそでありそうな設定は、嘘が嘘でなくなり、本当が本当でなくなる。なんとも不思議な、まさに「大人のおとぎ話」ともいえるストーリーだ。このドラマの楽しいところは、ほとんどの話がハピネス三茶で繰り広げられる一種のシチュエーションコメディになっているところである。限定された空間で展開されるドラマは、場面の切り替え、登場人物の出入り、台詞回しなど、本当に実力がある脚本家でなければ書けない。「やっぱり猫が好き」で鍛えた木皿の筆力は、このドラマにも遺憾なく発揮されていると思う。木皿の脚本がつくづくうまいと思う点は、まず、台詞にリアリティがあることである。OLはこんな話をしているのか、と思わず聞き入ってしまう。たわいもない日常の短い言葉のやりとりに、妙に納得させられ、感動して「そうだ、そうだ」とうなずいていまうのだ。特に小林がふと漏らすひと言には、男の私ですらシンパシーを覚えるのだから、主人公と同年代の女性が共感を抱かないわけがない。このドラマの支持者に、30代独身OLが圧倒的に多いのもうなずける話だもうひとつ、「すいか」における木皿の脚本の特徴は食べ物に対するこだわりだ。私が最初に向田邦子を彷彿とさせると言ったのは、このことである。向田ドラマにも、食卓を囲むシーンが頻繁に登場し、料理やその食い方などへのこだわりがうかがえる。それが、ドラマから漂う空気感、匂いを視聴者に感じさせる重要な要素となっていた。木皿の書く「すいか」にも、ハピネス三茶の食卓シーンが頻繁に登場する。1.2回を見ただけでも、カレー、大トロ、せんべい、デコレーションケーキ、庭でのバーベキュー‥‥。とにかく出るわ出るわのオンパレード。それが決して不自然ではないから不思議だ。丁寧に撮られた食べ物のアップが、人物と人物のショットの間に短く挿入される。(なんというモンタージュの巧みさ)食べ物が、登場人物の表に現れない生活や揺れ動く心理を表現するための、大切な小道具として扱われているだ。その他、生活の中のちょっとした小物やファッションへのこだわりも、女性ファンを増やした要因のようだ。DVDにもしっかり、登場人物の各回のファンションを紹介する特典映像も収録されている。女性ファンにはこれもうれしい。実は、昨日届いたばかりで、まだ1,2話しか見終わっていない。放送時には気づかなかったことも、いろいろ出てきた。そのことについては、その都度ご報告する予定だ。まずは、すいかファンの方は「ぜひお早めに!」とだけ言っておく。また、「冬のソナタ」のDVDを買おうとおもっているあなた、夏は「すいか」に限りますって!---------------------------------------------------★ドラマ「すいか」DVD-BOXはこちらへ(1巻ごとの購入も可能)すいか DVD-BOX ◆20%OFF!<DVD> [VPBX-11978]★木皿泉脚本「やっぱり猫が好き」やっぱり猫が好き 新作’98 <初回限定BOX付き>
2004/08/02
コメント(2)
-

19世紀のワイドショーネタ
ショパンとサンドに関する本を引っ張り出して、久しぶりで読んで見た。読み終わった後で、本質的に下品な私は、ふとこんなことを想像した。もし、19世紀のフランスに日本風のTVワイドショーがあったとしたら、二人のスキャンダルはまさに恰好のネタになっただろう‥‥と。何しろ、子持ちの流行作家と、年下の若いミュージシャンの恋愛関係である。ナジモトも放っては置くまい。しかも、彼らの身近な友人には、ユーゴー、バルザックなどの作家をはじめ、リスト、ドラクロアなどのミュージシャン、アーチストがきら星のごとく並ぶ。彼らへのインタビュー取材を次々重ねれば、ネタ切れになることもない。もちろん、フライデーも参戦する。マジョルカ島の逃避行も、近所の住民の密告ですぐにバレ、二人の同棲生活はパパラッチの恰好の餌食となる。一年後、パリに戻った二人は別々に部屋を借りて生活を始める。すると女性週刊誌はこうなる。「ショパン、サンド、セックスレスで破局か!」刺激的なタイトルが踊る。二人の音楽や小説の話題などそっちのけの、芸能ネタで盛り上がる。しかし、こうした憶測をよそに二人の交際は順調に続く。男女の関係はなくなったが、パリとサンドの邸宅があるノアンを行き来しながら、ショパンもサンドも充実した芸術活動を続ける。しかし、これではワイドショーは盛り上がらない。すると、登場してくるのが、最強のリーサルウェポン、サンドの息子・モーリスだ。サンドが溺愛するモーリスも、すでに20歳過ぎの大人。子供の頃から母親をショパンに奪われたと考えていたモーリスは、ショパンを憎んでいた。ショパンを批判するモーリスのインタビューが、連日放送される。それに対して、ショパンは沈黙を守る。すると当然のようにモーリスに批判が集中する。そのモーリスを、母親・サンドが擁護する側にまわる。ショパン派、サンド派、モーリス派と入り乱れて、ドロドロの愛憎劇が繰り広げられる。そうこうしているうちに、ショパンとサンドの関係がギクシャクし始め、今度は本当に破局!話題は沸騰し、ピークを迎える。しかし、二人が本当に別れたことが分かると、熱は一気に冷める。その後の二人の動向は、サンドのゴシップぐらいで、どうしても盛り上がらない。最後の花火は、ショパンの死だ。マドレーヌ寺院で行われた盛大な葬儀の様子は、大々的に報道される。もちろん、興味の対象は、その葬儀にサンドが現れるかどうか。果たしてサンドはついに姿を現さない。有名人の葬式ネタでもつのは、3日が限度。あっという間に忘れられてしまう。半年後、ショパンが埋葬されるベール・ラシュールの墓地を、密かに訪れる中年女性の姿が、写真週刊誌に掲載される。望遠レンズで撮られたサングラスの女が、ほんとうにサンドかどうかはわかない。----------------------------------------------------日本のワイドショーネタにはいっさい興味はないが、19世紀のちょっと知的なワイドショーなら、見てみたい。●ショパンに関する本なら作曲家・人と作品/ショパン(音楽書)
2004/08/01
コメント(2)
-

続・ふたつの「雨だれ」伝説
前回の雨だれ伝説が正しいかどうか、ずっと気になっていた。まさか私のような素人の書くことをまともに受けとる方もいないとは思うが、不正確のままではどうも気持ちがわるい。そこで、もう一度自宅にあるショパンの資料を見直してみた。その結果、前回の記述は概ね間違ってはいないのだが、説明不足のところや、誤解を招く箇所やもあるので、加筆、訂正したいと思う。●前奏曲出版権、前借りを旅費に充てた事実についてショパンはマジョルカに出発する数年前からすでに24の前奏曲集の作曲を始めており、出発当時には完成間近であった。数曲は実際にマジョルカ島で作曲され、完成をみた。(島で「雨だれ」が実際書かれたかは、私の資料では不明)補足:出版権2000フランうち、500フランを前借りした。●マジョルカ島における住居マジョルカ島到着直後は、最大の町・パルマでホテルが見つからず、下宿屋の2階に一旦間借りした。すぐにパルマの北方7キロのエスタブリメンツに家具付きの質素な貸別荘を借り、「風の家」と名付けた。彼らがこの別荘に移った11月はじめはまだ暖かく、快適だったようだが、中旬から豪雨が続き、別荘内は湿気がひどくなり、ショパンは体調を悪くしたようだ。このため、たびたび医師を呼んだりするうちに、ショパンが肺病ではないかという噂が拡がり、大家から立ち退きを宣告される。(村人との折り合いがわるかったという表現は、正確ではなかった)12月15日には、例のヴィルデモーザ修道院に移る。この修道院は18世紀に建てられた石造りの建物。二人が入る3年ほど前に修道僧が追放され、その後は政府の管理下におかれ、12ほどの庵室が一般に貸し出されていた。(いわば民宿のような感じか?)二人は、この修道院の環境に大分期待をしていたようだが、見事に裏切られ、雨続きの憂鬱な天候と修道院の不気味な雰囲気にショパンは精神的に大分まいってしまったようだ。●「雨だれ」の起源になったサンドの記述「雨だれ」命名の起源は、サンドがショパンの死後に出版した「わが生涯の歴史」の一説である。その箇所の全文はいずれこのHP上で紹介するが、概略は以下のようになる。ある日、サンドは息子のモーリスと一緒にパルマに買い出しにいくが、運悪く大雨に遭い、洪水で帰宅が夜遅くなってしまう。部屋に帰ると、待ちわびたショパンがひとり涙を流しながら、プレリュードを弾いていた。(ショパンは孤独のなかで一種の錯乱状態にあったようだ)その時聞いた屋根の上に落ちる雨音とショパンの弾くプレリュードのメロディをダブらせて、サンドは文学的に表現した。この一説が、「雨だれ」の起源とされている。その夜、具体的にどのプレリュードをショパンが弾いていたのかは書かれていないので、これは想像するしかない。また、この記述が事実であったかも、今となっては何とも言えない。まあ、当夜の光景を想像しながら、プレリュードを聴くのも楽しいと思う。なお、検証には主に以下の資料を参考にした。★「ショパンとサンド」小沼ますみ著(音楽之友社)★「ショパン」アルフレッド・コルトー著(新潮社)
2004/07/31
コメント(0)
-

マジョルカは今日も雨だった~ふたつの「雨だれ」伝説
1838年冬、ショパンとジョルジュ・サンドは、転地療養先にスペイン・マジョルカ島を選んだ。実は、この旅費には「24の前奏曲集」出版の前金が充てられていた。この島で「雨だれ」が作曲されたのには、こんな裏事情もあったのだ。さて、その年のマジョルカ島は、にわか雨が降り続く異常気象に見舞われていたらしい。もしこの長雨がなければ、この名曲も誕生していなかっただろう。一般的に「雨だれ」と呼ばれているのは、24の前奏曲の第15番ということになるが、実は、ショパンはこの曲より先に、この島で「雨だれのイメージ」として曲を書いている。それが同じ前奏曲集の6番目にあたる曲だ。この曲をスケッチとして15番の前奏曲が書かれた。もし、前奏曲集のCDをお持ちなら、ぜひ聴き較べて頂きたい。どちらも、例の雨音をイメージさせる音が絶え間なく鳴り続けるところは、共通している。第6番は、ロ短調の孤独感漂う何とも陰鬱な曲だが、第15番は変ニ長調の哀愁感をたたえた美しいメロディで始まる。しかし、中間部には、第6番をベースにした上でより重く陰鬱にしたような暗いメロディが置かれている。そして、再び冒頭の美しいメロディに戻って、曲は終わる。ここからは素人の推論だが、15番の「雨だれ」を作曲するに当たり、ショパンはまず6番をベースに中間部を書き上げ、その後であの美しいメロディを付け足しのではなかいか。「6番スケッチ」説が事実なら、あながち間違いではない気がする。では、いったいショパンはどんな雨音を聴きながら、曲を書いたのだろか。私としては、こちらの方に興味がある。「雨だれ」命名には、諸説あって、一般的には、二人が宿泊していたヴァルデモーザ僧院の石畳に落ちる雨だれの音を聞いて、ショパンはこの曲を想起した。というのだが、果たして真実だろうか。この話は15番の美しいイメージにはぴったりだが、孤独感や絶望感という、もう一つのイメージからは遠い気がする。おそらく、後付の作り話ではないかと思われる。これとは、まったく違う説もある。実際には二人は島民との折り合いが悪く、借りていた家を追い出され、仕方なく村はずれの空き家で生活を始める。その家は雨漏りがひどく、その音を聴きながらショパンは「雨だれ」を書いたというのだ。夢は無惨にも壊されるが、何となくこちらの方がリアリティがある。そして、あの陰鬱としたメロディの元祖「雨だれ」(第6番)のイメージとも合致する。私は、この説をとるのだが、あなたはどうだろうか?雨漏りのする古い借家で、ひとり曲づくりに励む孤独なショパン‥‥。そんな光景を思い浮かべながら聴き慣れた「雨だれ」を聴くと、別な曲に聞こえてくるから、不思議だ。-------------------------------------------------------●ショパン「24の前奏曲」推薦盤人気のある曲だけに、名演奏はたくさんある。いまさらとう気がしないでもないが、どうしてもこの2人のピアニストのものになる。どちらを聴いても、満足、満足!ショパン/24の前奏曲演奏:マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)ショパン:24の前奏曲 作品28演奏:マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)
2004/07/29
コメント(6)
-

「冬ソナ」より「夏ソナ」?
●今日の1枚フランク、ドビュッシー、ラヴェル/ヴァイオリンソナタ演奏:シュロモ・ミンツ(ヴァイオリン)、イェフィム・ブロンフマン(ピアノ)----------------------------------------------------------異常とも思える冬ソナブーム、韓国ブームである。韓国ドラマを繰り返し放送し続けているNHKはもちろん、ロケ場所を訪ねるツアーまで登場し、すべて完売だと聞く。ブームの仕掛け人たちはさぞやほくそ笑んでいることだろう。女性だけかと思ったが、男性にも「隠れ冬ソナファン」がいるらしい。支持率凋落著しいあのお方も、このブームにあやかろうというのだから、まったくトホホである。そこで、冬ソナファンの方に、私はおたずねしたい。「いったい冬ソナのどこがいいのですか?」実は、私は例のドラマを見たことがない。漏れ伝わってくるストーリーをつなぎあわせると、およそ見たいと思わせる内容ではなさそうだ。そもそも予定調和のようなドラマに、興味はない。メロドラマにありがちなご都合主義の、強引なストーリー展開はしらけるだけだろう。本音を言えば、ブームに乗り遅れてしまったオヤジとしては、その後追だけはしたくないという意地と、一度見たら「ハマりそう」という恐れを抱いているが、偽らざるところだろうか。さて今日の一枚だが、ブームを逆手にとって、冬のソナタならぬ、「夏のソナタ」と題して、真夏に聴きたいソナタを選んでみた。(これこそ、強引な展開とつっこみが入りそうだ)「さあ聴け!どうだ」といわんばかりのドイツ音楽は、蒸し暑い夏には迷惑だろう。そこで、単純な発想で北欧やロシアの作曲家を捜してみたが、手頃なものが見つからない。そもそもこの方面の音楽を私はほとんど聴かないから、CDも数が乏しい。たどり着いたのが、比較的ライトなフランス近代の室内楽である。これなら、夕涼みがてら聴くのにもおしゃれだ。選んだ1曲は、フランクのヴァイオリンソナタである。我が家にあるフランクといえば、あの有名なニ短調のシンフォニーとピアノ五重奏、そしてこのヴァイオリンソナタぐらいである。これぐらい持っていいれば、フランクなら充分だろう。私の所有しているCDは、フランクと一緒に、ドビュッシー、ラヴェルのヴァイオリンソナタが入っている。1枚でフランス近代の3大ヴァイオリンソナタを聴くことができる、お得なCDだ。フランクのヴァイオリンソナタは、第4楽章のカノンでよく知られた曲なので、おそらく聴いたことあると思うが、とても甘美なメロディのロマンチックな曲である。同じロマンチシズムでも国民性の違いだろうか、ドイツロマン派に較べて、フランス近代の音楽はサラっとしている。おそらくフランス人は、ドイツ人のように、音楽に文学や哲学を持ち込まないからだろう。フランス近代の音楽は、心の奥底から根っこそぎ持って行かれるような感動は少ないが、「音楽を音楽として」純粋に楽しみたい時にはふさわしい。もし、フランクのソナタをお持ちなら、今晩あたり早速聴いてみてはどうだろうか。甘さだけなら、かの「冬のソナタ」にも決して引けを取らない。
2004/07/28
コメント(5)
-

ドラマ「逃亡者」を見たが‥‥。
ここのところ、これは見たいと思われるドラマがない。期待していた「逃亡者」は、初回、2回目と見事に裏切られた。江口洋介はあの里見助教授のまま出てきてしまった。申し訳ないがそれだけで、どうしてもしらけてしまう。江口洋介は決して嫌いな俳優ではない。しかし、そろそろ新しいイメージを作らないと、飽きられてしまうのではないかと思っている。それにしても俳優とは恐ろしい商売で、ひとつの役がハマると、次々に同じような役柄が回ってくる。江口の場合は、もちろん医者だ。救命病棟24時の進藤役は新鮮だったし、白い巨塔の里見役は脚本も良かったせいか、まだ行けていた。しかし、逃亡者の永井徹生は、正義漢・江口洋介のままではやや無理がある。もう少し内面の複雑さが表現されないと、ドラマとして深まらない。演出も、ドラマでは珍しいマルチ画面や、望遠レンズを使った不安定なカメラワークで、ドラマの緊張感を高めようと言う意図が見える。志は評価するが、ややあざとい手法に見えるのは、私だけではないだろう。この時間枠は、比較的質が高いドラマを見せてくるので、来週も見るつもりだが、主役の江口がストーリーの中で変容していかないと、今後はもっと苦しくなるような気がする。見所が、阿部寛の妙にハイテンションな演技だけでは、私としては3回目で打ちきりか?
2004/07/27
コメント(4)
-

大発見!黒鍵だけでドビュッシー?
ピアノを正式に学んでいる人には軽蔑されそうだが、私のような「ピアノの弾けないピアノ好き」は、こんなことをして楽しんでいたのだ、ということを今日は恥を忍んで書いてみようと思う。誰でも、一度くらいは学校の音楽室や体育館のピアノを弾いて遊んだ経験が必ずあるはずだ。私も、よく学校のピアノで遊んだ。といっても、当時の私はピアノを習った経験などなかったので、知っている五つくらいの和音を鳴らし、右手で簡単なメロディを弾く程度だった。それでも、楽しくて仕方がなかった。しかし、そんな遊びはいつか飽きてしまう。そこで開発したのが、「ドビュッシーごっこ」である。「ドビュッシーごっこ」とは、私の命名だが、この遊びは全くの偶然から生まれた。ある日、いつものようにピアノで遊んでいた私は、黒鍵だけでピアノを弾いてみることを思い立った。ためしに黒鍵でだけで適当な和音を鳴らしてみた。とても不思議な響きがした。さらに、ペダルを踏んだまま連続して黒鍵だけの和音を積み重ねる。「ムムッ、この響きは、どこかで聴いたことがあるゾ」そう思った。さらに、右手で黒鍵だけの適当なメロディを重ねる。「そうだ、これはドビュッシーじゃないか!」。少年の私はひとりで納得し、世紀の大発見をしたような気分になった。文字だけでは伝わらないので、ドビュッシーの音楽でイメージが近い前奏曲を例に挙げよう。たとえば、和音の響きだけなら「沈める寺」や「霧」、メロディを加えれば「妖精たちはえも得も言われぬ踊り手」や「オンディーヌ」が似ているかしら。まことに馬鹿馬鹿しいと思われるかもしれないが、当時の私はこの「ドビュッシーごっこ」に夢中になり、不思議な不協和音に陶酔感さえ覚えた。それにしても、なぜドビュッシーに聞こえたのだろうか。偶然この日記を読んだ方で、音楽を専門にしている方がいれば、素人でもわかるように教えて欲しい。今日はまったく馬鹿馬鹿しい昔話で、お茶を濁すことになってしまったが、最後に、今日のCDを紹介しておく。ドビュッシーにちなんで、ミケランジェリとベロフの演奏を挙げる。ミケランジェリはきっと好きな方も多いのではないかと思う。気むずかしい完璧主義者で、コンサートをよくキャンセルすることでも有名だった人だ。残された録音も、キャリアや人気の割には少ない。このドビュッシーの映像第1,2集の録音は、もっとも好きな1枚である。というよりドビュッシー以外、彼のモーツァルトもショパンも、生意気だが私の好みではない。しかし、このドビュッシーはいいゾ。とにかくその研ぎ澄まさせたピアノ響きの美しさを、ぜひ聴いて欲しい。前奏曲集もお薦めだ。もう1枚のベロフの演奏する前奏曲集。こちらは、1巻2巻全曲が収められている。フランスのピアニスト、ミシェル・ベロフはドビュッシーの演奏家として定評があり、ドビュッシーのピアノ全作品をレコード5枚にて録音している。このシリーズでディスク大賞5賞を受賞している。私の所有している1.2巻全曲が1枚に収められたCDは現在入手不可能なようだが、各巻ごとに分割されたCDなら入手できる。楽天市場のショップでは、往年の名盤ギーゼンキング演奏の前奏曲集を見つけたので、ホームページの大家さん(楽天)に義理立てし一応紹介しておく。ドビュッシー:[ピアノ曲全集(1)] 前奏曲集 第1巻 & 第2巻ヴァルター・ギーゼキング/ドビュッシー:[ピアノ曲全集(1)] 前奏曲集 第1巻 & 第2巻
2004/07/25
コメント(8)
-
マーラー 「復活」
今日は、ミケランジェリのドビュッシーのことを書こうと思っていましたが、忘れられないコンサートのライブ盤が発売されることを知り、急きょ予定を変更しました。 ------------------------------------------------------- 昨夜、久しぶりにHMVのホームページを見に行ったら、嬉しい案内を発見した。 いまでも忘れることができない、コンサートのライブ盤が発売されるらいしい。 1978年4月8日、東京文化会館で開かれた、日本フィルハーモニーの演奏会。 指揮は日フィルの初代音楽監督だった渡辺暁雄さん。曲はマーラーの「復活」。 当時の日フィルは、フジテレビの不当解雇に抗議する闘争を続けており、経営的に大変苦しい状況にあった。 新宿・河田町の旧フジテレビの局舎の入り口の白い建物の2階の狭い事務所に、日フィルを支援する「ガンバレ日フィル」の事務局があった。私は、1度だけ高校の先輩に誘われて支援者の会合に参加した記憶がある。 その時一度きりで、直接支援運動には参加しなかったが、先輩を通して支援コンサートのチケットだけは購入しつづけ、何回か演奏会に通った。その時のコンサートの中で、特別記憶に残っているのが、マーラーの「復活」である。 ヴィスコンティの映画「ベニスに死す」の影響かどうか定かではないが、日本でもようやくマーラー人気が定着した頃だった。 しかし、私にとってマーラーは未知の作曲家。例の第5のアダージョ程度しか聴いたことがなかった。 当日の「復活」は、まさに私のマーラー初体験であった。 私が感銘を受けたのは、第四、五楽章である。 とりわけ、アルト、ソプラノ、合唱が入ってくる第五楽章の美しさはなんとも形容のしようがない。 「復活賛歌」の歌詞が歌われる部分からクライマックスにかけては、特に感動的である。 ------アルト独唱]----------------------------- 「おお、固く信ぜよ、わが心よ 私が何も失ってはいないことを お前が憧れたもの、お前が愛したもの、お前が得ようとたたかったもの、 それらはすべてお前のものなのだ」 ------------------------------------------------- 私が聴いた日のアルトは、ソウクポヴァという歌手だった。(チェコ人だと記憶している) 彼女の歌声は、格別すばらしかった。その温くふくよかな歌声は、ステージ中央からホール全体を包み込むように響き渡った。 その美しさに、私は涙が止まらなかった。 こんなにすばらしい歌声を聴くことは、もう二度とないのではないか、そう思った。 私はいま、この日記を書きながら、ライブ盤のCDを買おうか迷い始めている。 はたしてあの日の感動を再び味わうことがでるだのだだろうか。 もしかすると、聴かぬまま、記憶の中だけであの日の「復活」を胸の奥にしまっておく方が幸せなのかもしれない。 ◆以下、HMVのホームページの案内をそのまま掲載しておく。 ------------------------------------------------------- 伝説的ライヴが復活! 日フィルと渡辺の復活の日の『復活』 紆余曲折を経た日本フィルが初代音楽監督の渡辺暁雄に原点回帰のため再び音楽監督就任を要請、監督復活コンサートの大変話題となった『復活』。渡辺というとシベリウスのイメージが強い指揮者ですが、マーラーも70年代より熱心に取り上げていたマーラー信者でもあります。食事中も『大地の歌』を口ずさむくらいのマーラー好きでした。そういった特別のコンサートでしたので、大変な熱気ながら品格がにじみ出る稀代の大演奏となっています。マスタリングはアルトゥスが担当。日本語解説付。 ■マーラー:交響曲第2番『復活』 常森寿子(Sp) ソウクポヴァ(Alt) 日本プロ合唱団連合 渡辺暁雄(指)日本フィル 録音:1978年4月8日 東京文化会館(ステレオ) MHVはここをクリック!
2004/07/24
コメント(1)
-

グールド ブラームス「間奏曲」
グレングールドほど、いろいろな逸話が残っているピアニストはいないのではないか‥‥。32歳にしてコンサート活動をいっさい止めてしまったことに始まり、真夏でも手袋にぶ厚いコートを着込でスタジオ録音したとか、自分専用にピアノ椅子の脚を短く切ってしまったとか、演奏旅行中の10日間もほとんど食事を取らなかった、などなど伝説的な逸話には事欠かない。コンサート活動を行わなかったグールドだが、そのせいもあってか、演奏を収録した映像が数多く残されている。これも彼の特徴の一つだろう。それらの映像には、背の低い椅子にすわり、背中を丸めて一心不乱に引き続ける神経質そうな男が映っている。モノクロームの世界の中で、グールドは孤独な修道僧のように見える。さて、グールドといえば、ゴールドベルク変奏曲がすぐ浮かんでくる。彼が世界的な名声を獲得したのもこの曲であり、意識していたかどうかは分からないが、人生の最後の録音も、またこのゴールドベルクだった。因縁めいた話だ。前置きが長くなったが、今日の題目であるブラームスの「間奏曲」は、グールドの数ある録音のなかでも、お気に入りのものだ。ゴールドベルクとともに繰り返し聴き続けてきた。1960年の録音であるから、グールド28歳の時のものである。今日紹介するCDには、ブラームスの小品のなかでももっとも親しまれている作品117から2曲と、118の2曲の間奏曲が収められている。共にブラームス晩年の作品で、素朴で美しいメロディの中に孤独感が漂っている。28歳のグールドはまるで老人が昔話をするように音楽を紡いでいく。ブラームスのピアノ小品には、どこかしらシューマンの香りが漂っているように感ずる。事実、ブラームスはシューマンを尊敬し、シューマンもまたブラームスの才能を高く評価していた。シューマンの死後、彼の残した妻クララと7人の子どもたちの生活を影で支えたのはブラームスだったのは有名な話だ。ブラームスは、一生独身で通したが、彼の心の中には常にクララの存在があったと言われている。そんなことを考えながら、この間奏曲を聴くと、なお一層考え深いものがある。グールドのピアノのなんと美しく、哀しいことか‥‥。グールドの演奏を聴きながら、いつも彼だったらシューマンをどのように弾いただろうか、と考えてしまう。残念なことにあれだけ幅広いレパートリーをもっていたグールドなのに、なぜかシューマンのピアノ曲の録音は残されていない。シューマンの作品としては、ジュリアード四重奏団と録音したピアノ四重奏が唯一が残されているだけである。グールドはなぜシューマンを録音しなかったのか、謎である。●グールドのCDとドキュメント映像(DVD)ブラームス:4つのバラード/2つのラプソディ/間奏曲集J.S.バッハ:ゴ-ルドベルク変奏曲グレン・グールド(ピアノ) <クラシック・アーカイヴ・シリーズ(9)> 【TOBW-3542】 =>2...グレン・グールド 27歳の記憶【KKDS-3】 =>20%OFF!《発売日:01/06/25》
2004/07/23
コメント(6)
-

フランソワのショパン
クラシックを聴き始めた頃、私にとってショパンといえば、サンソン・フランソワだった。ノクターンにはじまり、マズルカ、ワルツ、前奏曲、練習曲、舟歌‥‥。彼のショパンはほとんど聴いた。熱病に取りつかれたように、すでにこの世にいないピアニストの残した録音を追い求めた。フランソワは、どちらかというと異端といえるかもしれれない。後に、ルービンシュタインやアシュケナージのショパンを聴いて、フランソワがいかに個性的なピアニストだったのか、はじめて知った。およそショパンのような通俗的で誰でも知っているような音楽は、ある種のスタンダードがある。その典型がルービンシュタインとするならば、フランソワはまさにその対局にあるピアニストだ。彼の演奏は、全体に即興的で、微妙にテンポを動かしながら、起伏の豊かな表情を見せる。専門的なことは分からないが、時には楽譜に反する解釈も避けなかったとされる。フランソワのショパンを頭に詰め込んだあとで、ルービンシュタインを聴いたとき、ある種の違和感を感じた。私の頭の中で鳴っているあのショパンのメロディと違うのだ。実はルービンシュタインがかわっているのではなく、フランソワがあまりにも個性的過ぎたのだ。私は、フランソワのショパンをすべて肯定するわけではい。際だった個性は、時に「破綻」という結果をもたらす。たとえば、バラードやスケルツォなど音楽としてのトータルな設計を要求する曲には、明らかに破綻している箇所があるように思われる。バラードやソナタは、フランソワには向いていないのかもしれない。それに対して、マズルカのなんと魅力的なことか。彼の残したマズルカ(全曲)は、モノラルという音質的な大きなハンディをもちながら、いまだに色あせることがない。その完成度は、ホロヴィッツの弾くいつくかのマズルカに匹敵するできばえだ。もし、ありきたりのショパンに飽きたなら、フランソワをお聴きなさい。最初は違和感を感ずるかもしれないが、聞き込んでいくうちに、きっとフランソワの魔力にハマるはだ。サンソンフランソワとは、19世紀のサロンの香りがする、最後のピアニストである。◆フランソワのショパン別れの曲[ショパン:ピアノ名曲集]ショパン:ワルツ集ショパン:夜想曲集ショパン:ピアノ協奏曲第1番&第2番ショパン:バラード&スケルツォ集
2004/07/22
コメント(4)
-

ベートーヴェン ピアノソナタ第17番「テンペスト」
ベートーヴェンのピアノソナタは全部で32曲残していますが、私がはじめ聴いたソナタが、この第17番「テンペスト」でした。「テンペスト」とは「嵐」という意味です。この曲が書かれたころ、ベートーヴェンはすでにほとんど聴力を失っていました。弟子にこの曲の名を聞かれたとき、ベートーヴェンはシェークスピアの最後の戯曲である「テンペスト」を挙げたことから、この名で呼ばれるようになったようです。この曲には、人生に絶望し、ある種の諦念、あきらめからから、未来へのかすかな希望を発見しようとする作曲家のこころがうかがわれます。特に美しく印象的なのが、第3楽章です。私は、この第3楽章のメロディが好きで、この楽章ばかり繰り返し聴いていた想い出あります。ある世代の方には、山口百恵の「赤いシリーズ」の中で、使われていたので、きっとご存じの方も多いと思います。私が最初に聴いたのは「ケンプ盤」ですが、いまの愛聴盤となると「ギレリス盤」でしょうか。ギレリスのベートーヴェンについては、いずれもっと詳しく書きたい思います。◆ベートーヴェンの主なピアノソナタが揃うお得なCDベートーヴェン:ピアノソナタ「悲愴」・「月光」・「テンペスト」・「熱情」
2004/07/21
コメント(5)
-

シューマン「子供の情景」
大作曲家の子だくさんランキングトップは、おそらく20人のバッハ。。それに続くのは、果たして誰か。妻クララとの間に、7人の子供をもうけたシューマンもおそらくベスト5入りはまちがいないでしょう。大変子煩悩で有名なシューマンだから、きっと自分の子どもたちのためにこの曲を書いたのではないかと思いがちだが、実際にはこのピアノ曲集が作られたのは、二人が結婚する2年も前のことです。全部で13曲からなるこの曲集には、すべて名前がついています。中でも有名なのが、「トロイメライ(夢)」。クラシックのピアノの小品を集めたCDなどには必ずトロイメライは納められていますが、できれば13曲全曲通して聴きたいところ。とても幸せな気分にしてくれる美しいピアノ曲集です。13曲のタイトルを列記しておきます。1. 見知らぬ国々から 2. 珍しいお話3. 鬼ごっこ4. おねだり5. 満足6. 重大な出来事7. トロイメライ8. 炉端で9. 木馬の騎士10. むきになって11. こわがらせ12. 子供は眠る13. 詩人は語るオススメは、アルゲリッチ盤。一緒に納められたシューマンの最高傑作「クライスレリアーナ」の演奏も評価が高いところ。往年の名盤、ホロヴィッツ盤も捨てがたい。◆推薦盤はこちらシュ-マン/子供の情景 作品15
2004/07/20
コメント(1)
-

シフのモーツァルト
ビートたけしの特番をきっかけに、モーツァルトのCDが売れているらしい。そこで、モーツァルトのピアノソナタの推薦盤を1枚。アンドラーシュ・シフの弾く、ピアノソナタ集。モーツァルトのピアノソナタとしては、もっともポピュラーな第8、10、11、15番の4曲が納められている。トルコ行進曲付の第8番はもちろん、いずれも一度は耳にしたことがあるだろう、なじみ深い曲ばかりだ。独奏のアンドラーシュ・シフは、1953年ハンガリーのブダペスト生まれのピアニスト。彼のモーツァルトは、何のてらいもない無垢な音楽を聴かせてくれる。彼の特徴であるチャーミングで美しい音色はモーツァルトの音楽によくマッチしている。肩のこらない大変心地よい音楽を楽しむことができる。音楽に何か癒しを求めて「モーツァルト聴きたい」と思っている方にもオススメできる1枚である。◆気軽に聴けるモーツァルト
2004/07/19
コメント(2)
全50件 (50件中 1-50件目)
1
-
-

- 洋楽
- ジョ・ジョ・ガン 『ジャンピング・…
- (2025-11-25 04:17:42)
-
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…
- (2025-11-12 00:00:13)
-
-
-

- 今日聴いた音楽
- ☆祝☆乃木坂46♪井上和、1st写真集が年…
- (2025-11-28 07:59:39)
-






