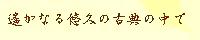【遙かなる紫の物語】若菜の章 その2
藤原鷹通。友雅と同じく、八葉としてあかねを守り、共に戦っていた。あかねに京に残ってもらおう、共に生きようと願っていたが、あかねが天真や詩紋と共に元の世界へ戻ることを選んだことで、恋を失い、それ以来ずっと独り身でいた。
女三宮が龍神の神子そっくりだと聞いて、鷹通はいても立ってもいられない気分だった。帝に、是非自分に御降嫁を賜るようにと幾度も願いを出したという。友雅も、何度か使いをしてやったが、鷹通の家は、藤原の中でも傍流で、他の藤原の思惑もあるし、ということで、友雅に降嫁することに決まってしまったのだった。
友雅も、同じ八葉であり、しかも天地の白虎として共に過ごした仲でもあり、何とかしてやりたい気持ちがないでもなかったが、自分も龍神の神子そっくりの宮に少なからず興味があったので、降嫁を受けてしまったのだ。
そんなわけで、友雅は鷹通に後ろめたさを感じながら、鷹通は友雅にやっかみを感じながら、でも、白虎同士の友情は続いていたのだった。
ある日、鷹通は友雅の橘の館を訪ねた。
女三宮のいる対の屋……。階に腰をかけて、鷹通は友雅が出てくるのを待っていた。
宮は猫が好きらしく、対の屋では多くの猫が飼われていた。
中に1匹、まだ人になれないのか、長いつなをつけられている、真っ白なかわいい猫がいた。 何に驚いたのか、御簾に飛びついて上りはじめた。
瞬間、御簾がさっとあおられ、中がすっかり見えてしまった。
そのとき、鷹通は見てしまったのだ。
宮のお姿を。
猫の動きに気を取られたのか、呆然と立ちすくんで外を眺めている。
(神子殿にそっくりだ……!)
鷹通の胸は高鳴った。もし、鷹通が思慮深くない男なら、踏み込んで抱きしめただろうが、鷹通の理性がぶしつけをとがめた。宮の姿を焼き付けようと必死で見つめる視線に気づいたか、宮の乳母が耳打ちして、宮はさっと奥に入ってしまった。
(なんと言うことだ! あんなにそっくりな……。やはり、あきらめられない。)
しかし、宮はもう、友雅の正室である。人妻となられた方を奪うなど……。せめて、あの猫なりとも自分の傍にいさせることができるなら。
「主上が猫を? 珍しいこともあるものだね。いいとも、宮にもらってこよう。」
気がとがめたが、友雅に嘘をついて猫をもらい受け、一応主上に献上して、まだ人慣れしていないので、と上手に言って、鷹通は例の猫を自分のものにした。
昼も夜も懐に入れ、大事にかわいがっている。
「どこのお姫様にご執心かと思ったら、お猫様ですって!」
女房達にあきれられるほど。宮の身代わりだから……。夜になると、「ね~う、ね~う」と鳴いてすり寄ってくるほど慣れた。
「寝よう寝ようだなんて……。君が私に宮の夢を見せてくれるというのですか?」
身代わりの猫を抱きながら、鷹通は、夢が実現する夜がいつ来るのかとじりじりしていた。
藤姫の体調が悪くなった。
「友雅殿、私、土御門で静養したいと思いますの。」
友雅と結婚してからずっと橘の館で暮らしていたが、藤姫にはやはり、土御門が自分の家だった。想い出がたくさんつまった古い屋敷。あの楽しかった日々に囲まれて、ゆっくり休みたかった。
友雅は、藤姫を土御門に送っていって、そのまましばらく、そこにいることにした。
橘の館は、女三宮がひっそりと留守番することになった。
「友雅殿が土御門に?」
こんな好機がまたとあろうか! 鷹通は、かねて手なずけておいた小侍従と呼ばれる若い女房に手引きさせて、宮の部屋に忍び込んだ。
友雅をがっかりさせた宮の反応のなさは、鷹通には逆に好ましかった。
(奥ゆかしい姫だ……。私が守って差し上げなければ、はかなくなってしまいそうな。こんなに可憐な姫君を、友雅殿はなぜ、一人で置いておかれるのだろう。)
「宮様、さぞお心細いことでしょう。これからは、この鷹通が宮様をお守りしますから、お心強くお持ちください。」
宮は何も言わない。鷹通は、それを、承諾のしるしと受け取った。
女三宮は、実はとてもあわてふためいていた。
感情を決して外に表すことのないようにと厳しくしつけられていたせいで、一見無反応のように見えるのだが、内心は大きく揺れ動いていたのである。
友雅のことは、大人すぎて怖かった。これからはこの人の言うことを聞かなければ生きていけないと思うから、何をされてもじっと我慢していた。
鷹通のことは、以前から少し好ましく思っていた。女房達の噂を聞いても、真面目で一途でと、いいことばかり。降嫁の話が出て、鷹通が願い出ているという噂が聞こえてきたとき、父帝が鷹通を選んでくれたらいいのに、と、ずっと願っていた。
今、こうして鷹通への想いが叶ったのは、宮にとってとてもうれしいことだった。しかし、時はすでに遅すぎた。自分は、友雅の正室になってしまったのに……。今、こうして盗みに来られるのなら、自分がまだ御所にいるうちにきてくれたらよかったのに……。言いたいことは山ほどあった。でも、感情を露わにしてはいけない……。宮は何も口には出さなかった。友雅が知ったら何というか。それだけが怖かった。
宮が身ごもった、と、乳母が友雅に知らせてきた。
友雅は不審に思った。ずっと土御門で藤姫についていたのに、宮が身ごもる? 本当に自分の子だろうか? 相手は誰だ……。
「友雅殿、どうなさったのです?」
藤姫に隠し事はできない。顔色を読まれて、すぐに気づかれる。友雅はふと苦笑して、藤姫に返事した。
「宮が、身ごもられた、と、乳母が言ってきたのですよ。」
藤姫の顔色がさっと変わるのが分かった。長年、無二の姫、北の方、として過ごしてきながら、藤姫が友雅の子を身ごもることはなかった。やはり、龍神の神子様と縁が深かったのだろうか。
「それは……おめでとうございます。お祝いと、お支度をしなければ……」
藤姫の目から涙がふきあがってきた。友雅はそっと抱きしめ、涙を唇で吸い取った。
「運命は皮肉だね。この人にと思う人にはできなくて、思いもよらないところにできるのだから。いとしい人、私の子を産むのはあなただったはずなのに……」
藤姫は、友雅の胸に顔を押しつけた。きつく抱きしめられる感触。愛している、愛されている確かさを感じて、心がほっかりとあたたかくなるのが分かった。
「……乳母が言ってきたから、一度、あちらに帰るよ。すぐに戻るから。」
友雅は、橘の館へ出かけていった。
小侍従の知らせを受けて、鷹通はしまったと思った。
自分の子に間違いない。自分の仕業だと、友雅に分かってしまう。いったいどうしたら!
膝ががくがくふるえ、立っていられない。友雅が今までどれほど自分を引き立ててくれていたか。鷹通は、床に伏したまま、起きあがれなくなってしまった。
「宮様、お殿様がお戻りになられました!」
小侍従が大急ぎで知らせてきたとき、宮は、鷹通からの文をうっとりと読み返しているところだった。どこへ隠そう……! 適当な隠し場所を見つけられず、宮は、とりあえず、自分が座っているしとねの下に文を押し込んだ。
「宮、ご気分がいかがかな?」
友雅がやってきた。当たり前のように御簾をくぐり、当然のようにしとねの横に座る。宮は、文を見つけられないかと、ドキドキして、冷や汗が止まらなかった。
「おや、こんなに汗をかいて……。やはり、気分が悪いのだね。横になっていたらいいのに。御帳台のしたくはどうした? 宮を休ませて差し上げなさい。」
友雅は宮を抱き上げると、御帳台に運んだ。床の上に下ろし、衣をかけ、汗を拭いてやり、など、まめまめしく看病する。宮は、事が露わになったときを思うと、怖くてたまらなかった。
「こんなにおびえた様子をなさるとは……。物の怪でもついているのだろうか? 早速、加持祈祷を……」
「……大丈夫ですから……」
宮はいたたまれず、ついに口を開いた。友雅は、不思議な声を聞いたように宮の顔を見つめた。あかねの声? 声までそっくりだったのか……。
「宮……。本当に、あなたは……宮、ですか……?」
今度は、宮が不思議な顔をする番だった。この人は、何を言っているのだろう? 私は小さい頃から宮だったのに……え? 宮は、自分の小さい頃の事が思い出せないのに気づいた。一番古い記憶は……思い出せない。気づいたら、御所にいて、乳母がいて、母はいなくて、父帝だけだった。
「宮……だと……思います……」
「思いますとは……どういうこと……?」
「思い出せないんです……。小さい頃のこと。おたたさまのこと。気づいたら、御所にいて、おもうさまがいらして……。私、そのとき、そんなに小さくない。もう、ずいぶん大きい私のことしか、覚えていないんです!」
あかねだ! 友雅の勘が叫び声をあげた。時空を越えて、戻ってきたのだ! そのとき、おそらく記憶をなくしてしまったのに違いない。時間をかければ取り戻すかもしれない。友雅の情熱に火がついた。この姫を離したくない。いったい、この姫を盗んだのは誰なのだろう。友雅は、まだ見ぬ相手の事が殺したいほど憎くなった。
次へ
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- REDSTONE
- (確定情報) 武道のアルカナ、パッシ…
- (2024-08-08 08:43:40)
-
-
-

- ゲーム日記
- 【中古】 初音ミク −Project…
- (2024-11-27 17:29:38)
-
-
-

- アニメ・特撮・ゲーム
- 【11/25限定 1等最大100%ポイントバ…
- (2024-11-25 15:39:02)
-
© Rakuten Group, Inc.