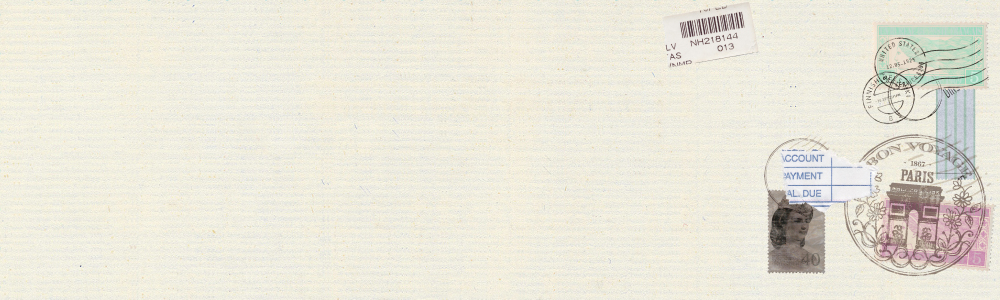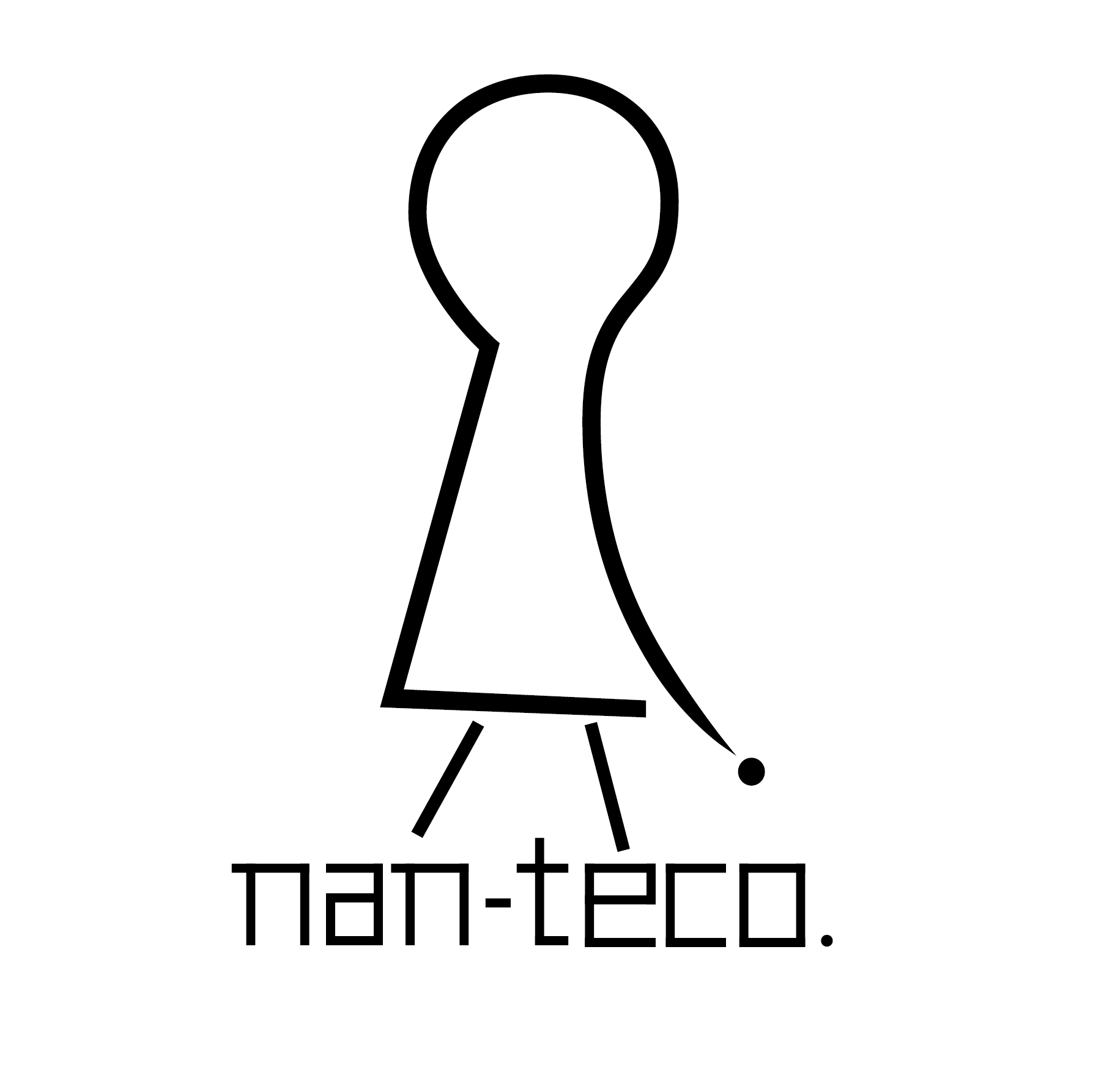PR
X
カレンダー
コメント新着
コメントに書き込みはありません。
キーワードサーチ
▼キーワード検索
テーマ: 哲学・思想(195)
カテゴリ: 哲学
どもどもナンテコです。
私事ですが、最近AIプログラミングを勉強していています。
AIはうまく利用できる人からすれば非常に有能なツールとなりますが、その強力性から、しばしば、シンギュラリティなどという言葉で人々に恐怖を与える対象のように論じられることがありますね。
実際AIの勉強をするとそんなに人間を超越するものでもないことがわかるのですが、、、
なんて思いながらAIと人類の付き合い方で丁度いいところはどこなんだろうと考えたことをメモします。
結論をいうと、AIは放し飼いの家畜という位置付けが丁度いいかなと
家畜は人間が食べ栄養とするために育てられた動物ですよね。そんな家畜にもいろんな環境があり、大量生産のために、ひたすら餌を与えられ強制的に太らされているものや、反対にストレスを少なくするためにできる限り野放しで野草を食べさせるものなどです。
どちらが良い悪いということではなく、どちらも人間の経済圏では必要な活動です。
で、これとAIがどのように結びつくのか。
これに対して、知識は学び吸収して脳を作るものだとします。
家畜と知識をを比べることで、知識にも強制飼育された知と放し飼いの知、さらには野生の知があると考えられますよね。
強制された家畜は安全で、人が生きていくためには最低限必要とされる栄養を得ることができる。放し飼いの家畜は管理が難しく数も限られるが、安全でかつ美味しい。野生の動物は獲得が難しく、安全であるかわからない、それでも他では味わえない旨味や刺激を有することがある。
これと同様に知識にも『強制↔放牧↔野生』の幅があると考えてください。
では、これらを知識で置き換えてみよう。
〇強制された知識
学校の形式的な教育がわかりやすいです。社会の道徳や理想を統一的に知識として吸収しています。システム化された教育体制やつまらない教科書など、正直これらの教育による知は味わうには退屈なものになります。(図集とかコラムはおもしろかったですけどね。)
〇放し飼いの知
書籍やネットなど、誰かが管理している枠組みの中で個人が自由に発言できる場所にある知識です。(この文章もそうです。)今やSNSやYouTubeを利用すれば大抵の情報にはたどり着けますね。ただ、経験的にわかるかとおもいますが、自由度が高いほど粗悪な情報が多く、脳や精神には害を与えるものになります。つまりは出版社が責任を持って発行してい書籍は安全で質が良く、簡単に発言できるSNSでは危険で毒っ気があるケースが多いという感じで、ここにも幅があります。
〇野生の知識
感覚的な説明になるため表現が難しいですが、自分が見聞したものから感じる0,1の知識のようなものです。それが社会的に正しいとか正しくないかということではなく、自分が感じた世界の原理、原則です。雨が降りしきる中に出かけることが億劫になる人がほとんどですが、そんな景色が好きだと自分が感じるなら、それが自分にっとっては快適な経験になるわけです。社会的な動物である人間にとって少数派の意見を持つことは危険であるため、野生の知識を身につけすぎることは必ずしもいいことばかりではないですが、時には自己を知るための刺激的な知を吸収することも必要だと思います。人生の醍醐味ってとこですかね。
現在のAIはまだ強制された家畜の域を出ていません。自動生成で手書きの文字を書く、写真同等の絵を描く、作曲をする。どれも組まれたプログラム上で出力されるため、学習する元のデータを逸することはありません。偶発的な作品が出来上がろうと全て管理されたプログラム通りです。
しかし、昨今、対話が可能なAIの開発から、AI自身がプログラムを書くことができるようになってきました。これが、放し飼いAI時代の序章かなと感じています。それもまだまだ発展途上で、人が欲しい情報を集めて教えてくれるが、こねくり回した誤った情報をパスしてきたりします。これが、会社の秘書やマネージャーといったパーソナル仕事ができるようになったときが、放し飼いAIの完全体に近いかなと、今は感じています。遠い話ですね。
一応シンギュラリティにも触れると、野生AIが発生したときだと思います。対話型AI同士が人間にわからない暗号的な文章でやり取りを始めたら、いよいよですかね。早めに元電源からブッチンしましょう(笑)
てな感じで、知識を家畜(栄養源)として考えるとAIも少しわかりやすく理解できるかなと思いメモしてみました。
誰かの思考訓練の一助になればと思います。
私事ですが、最近AIプログラミングを勉強していています。
AIはうまく利用できる人からすれば非常に有能なツールとなりますが、その強力性から、しばしば、シンギュラリティなどという言葉で人々に恐怖を与える対象のように論じられることがありますね。
実際AIの勉強をするとそんなに人間を超越するものでもないことがわかるのですが、、、
なんて思いながらAIと人類の付き合い方で丁度いいところはどこなんだろうと考えたことをメモします。
結論をいうと、AIは放し飼いの家畜という位置付けが丁度いいかなと
家畜は人間が食べ栄養とするために育てられた動物ですよね。そんな家畜にもいろんな環境があり、大量生産のために、ひたすら餌を与えられ強制的に太らされているものや、反対にストレスを少なくするためにできる限り野放しで野草を食べさせるものなどです。
どちらが良い悪いということではなく、どちらも人間の経済圏では必要な活動です。
で、これとAIがどのように結びつくのか。
これに対して、知識は学び吸収して脳を作るものだとします。
家畜と知識をを比べることで、知識にも強制飼育された知と放し飼いの知、さらには野生の知があると考えられますよね。
強制された家畜は安全で、人が生きていくためには最低限必要とされる栄養を得ることができる。放し飼いの家畜は管理が難しく数も限られるが、安全でかつ美味しい。野生の動物は獲得が難しく、安全であるかわからない、それでも他では味わえない旨味や刺激を有することがある。
これと同様に知識にも『強制↔放牧↔野生』の幅があると考えてください。
では、これらを知識で置き換えてみよう。
〇強制された知識
学校の形式的な教育がわかりやすいです。社会の道徳や理想を統一的に知識として吸収しています。システム化された教育体制やつまらない教科書など、正直これらの教育による知は味わうには退屈なものになります。(図集とかコラムはおもしろかったですけどね。)
〇放し飼いの知
書籍やネットなど、誰かが管理している枠組みの中で個人が自由に発言できる場所にある知識です。(この文章もそうです。)今やSNSやYouTubeを利用すれば大抵の情報にはたどり着けますね。ただ、経験的にわかるかとおもいますが、自由度が高いほど粗悪な情報が多く、脳や精神には害を与えるものになります。つまりは出版社が責任を持って発行してい書籍は安全で質が良く、簡単に発言できるSNSでは危険で毒っ気があるケースが多いという感じで、ここにも幅があります。
〇野生の知識
感覚的な説明になるため表現が難しいですが、自分が見聞したものから感じる0,1の知識のようなものです。それが社会的に正しいとか正しくないかということではなく、自分が感じた世界の原理、原則です。雨が降りしきる中に出かけることが億劫になる人がほとんどですが、そんな景色が好きだと自分が感じるなら、それが自分にっとっては快適な経験になるわけです。社会的な動物である人間にとって少数派の意見を持つことは危険であるため、野生の知識を身につけすぎることは必ずしもいいことばかりではないですが、時には自己を知るための刺激的な知を吸収することも必要だと思います。人生の醍醐味ってとこですかね。
現在のAIはまだ強制された家畜の域を出ていません。自動生成で手書きの文字を書く、写真同等の絵を描く、作曲をする。どれも組まれたプログラム上で出力されるため、学習する元のデータを逸することはありません。偶発的な作品が出来上がろうと全て管理されたプログラム通りです。
しかし、昨今、対話が可能なAIの開発から、AI自身がプログラムを書くことができるようになってきました。これが、放し飼いAI時代の序章かなと感じています。それもまだまだ発展途上で、人が欲しい情報を集めて教えてくれるが、こねくり回した誤った情報をパスしてきたりします。これが、会社の秘書やマネージャーといったパーソナル仕事ができるようになったときが、放し飼いAIの完全体に近いかなと、今は感じています。遠い話ですね。
一応シンギュラリティにも触れると、野生AIが発生したときだと思います。対話型AI同士が人間にわからない暗号的な文章でやり取りを始めたら、いよいよですかね。早めに元電源からブッチンしましょう(笑)
てな感じで、知識を家畜(栄養源)として考えるとAIも少しわかりやすく理解できるかなと思いメモしてみました。
誰かの思考訓練の一助になればと思います。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[哲学] カテゴリの最新記事
-
『成長』は慣れること 2024.07.20
-
ファストアート 2023.08.16
-
字に潜む「幸せ」のヒント 2022.11.30
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.