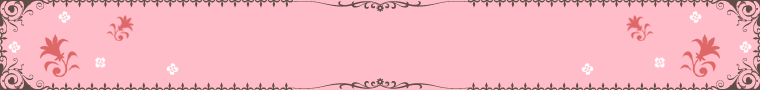第5話 煉獄に荒れる灼熱の風
アリストテレス「金言集」
1
ガシャンッ。
「・・・・・・?」
ヴォルフリートはそこで目を覚ました。鈍い眠りから意識が現実に向かっていく。立ったまま、寝ていたらしい。場所はどうやら街中で路地裏といわれる狭くて暗い場所だった。
空を見渡すと、既に暗闇に包まれようとする時間らしく、オレンジ色の空もその色を薄くしている。
「・・・っ」
不安になって、辺りを見渡した時、張り詰めたピアノ線のような、そんな感覚が襲った。高鳴る心臓、身体中の血が騒ぎ出す、恐怖が頭の中を駆け巡り、緊張が肌を張り詰める。
こうなる時は決まっている。
―異能者が側にいる。
ざわっと肌が粟立つ。
後ろを振り返ると、窓からガラスが割れ、地上に落ちてくる。ヴォルフリートよりも数倍体格のある男が黒装束を地で染めて、地面に落下した。
「ひっ」
大きい音が鳴り響く。人相の悪い男は既に事切れていた。
ジジジ・・・・。バリバリバリッ。
見えない動きで、地面が削り取られていく。まるで鋭い刃物や機械で剥ぎ取っていくようにも見えた。
異能者同士が会えば、それはハント・・・狩りとなる。殺し合いになる。食うか、食われるかの。異能者、歴史の影に生まれる悪魔に愛された、異能の力を持った人々。時代によって魔王の僕だとも、死神の眷属とも言われる。
しかし、特別な才能には当然リスクも異能者本人にとって、どこかに欠陥を齎す諸刃の剣でもある。
ザザザ・・・ッ
突風のせいで、自分の目の前で起きていることがわからない。もう一人の異能者の悲鳴が鳴り響いている。
・・・逃げナキャッ。
心はそう思うのに、足が動かない。何で、何で。表情が恐怖で引きつる。
恐怖で体が動かない。
ビュウッッ
赤い液体が放射状に突風が消えた瞬間、雨のようにヴォルフリートの元に降り注いできた。恐怖で呆然としていたヴォルフリートははっとなる。
「え・・・あ・・」
べとり・・・、とぬるりとした感覚の血糊が自分には不似合いな高級な服についていく。両手を震えさせ、それが人間の血であることに悲鳴を上げそうになる。
ぽつん。
水滴がヴォルフリートの頭に落ちる。本当の雨だ。突風が消え、中身が見え始め、頼りない背中が見えた。まるで少女のように丸く、小さな華奢な肩だった。
着ている服も異国の民族衣装だろうか、刺繍が施されているが、破けて、引き裂かれて、無残な形になっている。中の白いシャツのような服が切り刻まれ、西洋人の肌の白さとは違う、背筋が冷たくなるような、そんな美しい白い肌には銃痕のようなものや切り傷、暴力を受けたような痕があった。
「取り込んでいるところ、ゴメン」
背格好からして、同い年だろうか。いや、自分よりも低い。
「!」
肩を怪我をしている。
・・・外国人か。こちらの言葉はわかるだろうか。
「・・・赤い雨、君が降らせたの?」
乱れた髪は肩まで伸びて、鋭い眼差しの少年は振り返って、驚いたようにヴォルフリートを見た。何故、目をあんなに大きくして、自分を見るのだろう。彼も異能者に会うのは初めてだというのか。ルドルフ様には遭っているけど。
話しかけた瞬間、首に指が食い込んできた。
「・・・・・っ」
白い指がきつくヴォルフリートの首を絞める。
「~~っ」
何、この子!?
「動くな、動けばもっと絞める」
闇の中で獣に似た瞳がヴォルフリートの姿を捕らえる。ヴォルフリートははっ、となる。狼の目だ。
「異能者だな、俺を殺しに着たのか?」
・・・・・怖いっ、怖いよ、この子。
恐怖がヴォルフリートを襲う。
・・・姉さんッ、助けてっ。ぎゅっと涙目をつぶる。
「答えろ、お前は何者だっ」
激しい感情がヴォルフリートを襲う。狩りなんて、ヴォルフリートはした事はない。殺し合いなんてしたくもなかった。次の瞬間、言葉が口を滑った。
「・・・・午後七時、ヴォティーフ教会近くリングシュトラーセ、第3番地、フランツ医院にユリア医師がいる」
「は?」
少年は初めて、すっとんきょうな、子供らしい声になった。
「・・・僕が案内する。その怪我じゃうまく歩けないだろ、途中まで」
「・・・・」
「僕が君を助けるといっている」
オレンジのヒカリが空一面に包み込み、昼と夜が重なり、薄紫色の空になる時間、ルドルフはヴォルフリートの姿を見つけて、話しかけた。
「王宮の庭でボーっとするとはいい度胸だな」
「ルドルフ様、す、すみません!!」
ヴォルフリートは慌てて振り返り、そのまま、豪快に地面に向かって倒れて、額に擦り傷を負った。
「・・・・大丈夫か」
「ハイ、何とか・・・」
手を引いた。異国の少年を強引に掴んで、父親の注意も聞かずに、病院につれていった。病院の前まで言って、初めて、自分の体が自分の意思で動かせた。特に理由もなく、助けた。少年は驚いたように最後まで自分を見ていた。
不思議で仕方ないといったように。
・・・傷つけられるのは苦手だ。血など見たくはない。自分も他の人の血も。
だから、すぐにハンカチで出血が酷い場所を声を荒げられたのに強引にふさいだ。血の感触にぞくりとなった。
ルドルフは、異能者であるヴォルフリートにその力で自分に協力して欲しいと、命令をした。
「協力?」
「勿論、ただとは言わない、僕を守り、君が僕の味方でいれば、その代わり僕が何があろうとも、君やアーディアディトを大切にしてやる」
「仕事の関係って事?」
数秒、ルドルフを見つめた後、柔らかな笑みがヴォルフリートに浮かんだ。それにつられて、ルドルフも頬を緩めて、笑みがこぼれた。騎士と王のように、ヴォルフリートはルドルフに頭を下げた。ルドルフは作ったばかりの花飾りをヴォルフリートの頭に載せて。
「約束します、どこにいても必ずルドルフ様の身はお守りします」
「契約成立だな」
膝を折って、ヴォルフリートは誓いの言葉を立てた。
童話のお姫様か、夢物語でも見ているような気分だった。
シャノンのように綺麗なドレスを着て、おいしいものを食べて、素敵な紳士と恋に落ちて。
まるで、懐かしいものを、まぶしいものを見るようにはじめて、青い尖がり屋根の大きな貴族の屋敷、初めての家に来たとき、レオンハルトはアリスを優しく抱きしめた。
「娘よ・・・」
「お父さん?」
感激やなのか、瞼には涙があった。
辛いものが嫌いなアリスは、今一番の難題に突入していた。父親のレオンハルトは温かい笑顔でそんな娘の健闘する姿を見つめていた。
ジュウウウウ・・・。
「どうですか、アーディあディト様、当店自慢のキー間カレーは赤唐辛子をいつもの数倍入れてみました」
「は、は、はい」
気のせいか、声が震えている。
「メイド長にお前が辛いものが好きだと聞いてね、ぜひ食べてくれ」
「はい、お父様・・・」
緊張のせいか、アリスの表情は暗い。薄暗い室内には、蝋燭の炎が揺らめく。銀の食器など使ったこともない。側仕えのメイドは業務的に、アリスの側にいた。狐の巣のようだ。漆黒の闇の。食べたこともない、一流の食材で作られた料理は喉をうまく通らない。
「お姉様、おなか空いていないのですか?」
砂糖菓子のようなフィネがアリス、ヴォルフリート、ディートリヒ順に並べられた席順の最後で小鳥のような声でアリスに聞いてきた。
「今まで、地方で生活してきたんですから、ウィーンのものは遭わないんじゃないか」
くすり、と嫌味たっぷりにディートリヒが言う。アリスはムッ、となった。であったときからディートリヒはけんか腰だ。
暗闇の中、部屋まで案内役のメイドに連れられながら、パジャマ姿のヴォルフリートをつれて、アリスは始めて会う自分の祖母と廊下で遭遇した。祖母は美しい白い薔薇の束を胸に抱えていた。理知的な氷のような表情で華奢で小柄なアリスを観察するように見ると、メイドを連れてアリスに近づいてくる。
「・・・」
アリスの心臓が震える。
どうしよう、どう声をかければ。ちゃんと敬語で挨拶できるかしら。私のおばあちゃんなのよね。スカートの裾をキュッ、と握った。
「行きましょう」
「はい、奥様」
漆黒のドレスに紫色のショールを腕に纏った老女は好きのない動きで、アリスの横を通り過ぎていく。
「―-」
アリスを無視したのだ。
え?
呆然となった。
お化けでもなったようだ。老女は、まるでメイド以外、誰もいないようにアリスを扱った。そんな扱いは初めてだった。
「・・・・姉さん」
そんなアリスの気持ちを察するように、ヴォルフリートがアリスの手をギュっ、と握ってきた。
「え・・・あ・・・」
じっ、とアリスを見てきた。なぜか、動揺していた自分が恥ずかしくて、視線をそらしてしまった。
「行きましょう、ヴォルフリート」
バーデン家のグレーティアはすっかりルドルフに心を奪われていた。
「全く・・・」
彼女の父は、夢見心地でいる娘にため息をついた。館の方では、ローゼンバルツぁー家の当主の妻とバーデン家の妻がくだらないけんかをしていた。
「残念ですね、親友のエーベルハイト侯爵が来なくて」
「仕方ありませんよ、あの男は皇帝陛下と帝国を守るために生まれた男ですから」
グレーティアの父はにこやかにルドルフに笑う。
「こら、ヴォルフリート、馬にしがみつくな」
「だって、勝手に動くし、怖いよ」
ルドルフの背後では、ラインハルトにヴォルフリートが叱られていた。
エーベルハイト家のアルベルトとアロイス・ツァー・バルツァー侯爵は、両親と共に息子同士で争っているのを不況になりつつある情勢の中、チェコ系の友人と共にエリクはウィーンで目撃している。
「君は、スロヴァニア系やルーマニア系に感情を向けすぎだ」
アロイスは鼻で笑う。
「なぜ、いけない、同じオーストリアの国民だろう?」
「僕たちは皇帝陛下のために、帝国の平和の為に生きなければいけない」
「友達の明日も守れない国にどんな未来があるというのだ」
「皇妃様は、どこの店で今頃、スイーツを食べているのかしら」
「何でも、腰を細くする為に締め付ける機械を自分の部屋に置いてるとか」
「美しい人は大変ね」
参加している貴婦人達が、軽やかな声でそういっているのが、ルドルフの耳にも入ってきた。ルドルフの表情は厳しい。
2
ルドルフの姉、ジゼルはルドルフと共に母親と離されて育った為、エリザベートが母親である事を強く認識していない。頭が悪く、ドジで間抜けで、養子も面食いであるルドルフが選んだ、初めての友達のヴォルフリートにチェスを教えたのも彼女だ。
母親と比べて、明るい太陽のようなジゼルは透き通った声で高らかに、しゅばるつぁん・噛めるという店から取り寄せたティー・エッグ、父親が気に入っているカイザー・シュマーレンというお菓子を横において、アレキサンダーやオカルト、おしゃれの話をヴォルフリートに楽しげに語った。その隣には、ヴォルフリートをがっちり掴んだ、アリスの姿もある。
「噂には聞いた事があるわ、それにしても、君があのローゼンバルツぁー家の子供だったとはね、アリス、母親とは会ったの?」
「はい」
アリスも楽しそうに笑う。
「ずっと会いたかったんでしょう、やっぱり抱きしめてくれた?」
老執事につれられて、歩く赤いじゅうたんの上を緊張しながら、ヴォルフリートと共にアリスは歩いていた。
螺旋階段を上って、ヴィーナスの像が置かれた三階の隠し部屋の鍵がはずされ、扉が開かれると、レースや絹で覆われたパジャマを着た、この世のものとは思えない、女神のような、聖母のような女性が桃色の唇を半開きにして、完璧な肢体を伸ばして、呪いでもかかったように金髪のウェーブヘアを乱して、顔をアリスのほうに向けて、床に寝そべって、ぶつぶつと何かをつぶやいていた。
その肌は、陶器のようにすべすべで白かった。瞳の色はアリスよりこいコバルトブルーで宝石のようだ。
「これは一体・・・・」
「・・・お母さん?」
「エレオノールさま、あなたたちのお母上は13年前から事故のショックで頭がおかしくなったままなのです」
フォルクマたちと別れ、家庭教師やマナーの講師に厳しく教えられている時、急に2人に声がかかった。
「・・・・ごめんなさい、辛い事を聞いたわね」
「いえ、・・・私達は大丈夫です、ねえ、ヴォルフリート」
「うん。僕らは信じています、信じて痛いんです、あの人が僕らの名前で呼ぶのを」
「アリス、ヴォルフリート」
規律やルール、国の国是や正義、周囲の大人たちの抑圧を受け、その上、受けのいい大人しく、控えめで温厚な皇太子を演じなければいけないルドルフの肩には、双翼のわしの紋章がかかっている。元気がいいといえば、聞こえはいいが、ルドルフにはアリスが無作法で無神経に見えた。おせっかいのつもりなのか、皇太子という立場も気にせずに人の懐にずかずかと入ってくる。そのくせ、自分の大事なもののためには一歩も引かない。エリアスにからからかわれたときも双だ。大勢の貴族やくらいを持つ大臣や軍人の前で、紋章の入った懐中時計を見せた。
「言葉を撤回しなさい、私を馬鹿にするのは許すわ、けれど、貴方に私の父さんを、弟を愚弄する権利はないわ」
燃え立つような、生命の力に満ちた青い瞳。発言力のアル家柄のエリアスにも劣らぬ威圧感、その存在感。金色の長い髪は一国の女王のような、彼女の強烈な魅力を引き出していた。
格好は、ジュースで濡れて破けたドレスだというのに、どの少女よりも目立っていた。
「私はアーディアディト、レオンハルトとエレオノールの娘、アーディアディト・フォン・ヴァルフベルグラオです」
「君は一体・・・・・」
背中がざわついたのをルドルフは覚えている。
「剣の練習か、レディーには必要ないんじゃないのか」
宮殿の庭でアリスに遭った時、ルドルフはアレキサンダーを連れて、アリスに言った。
「いいじゃない、私が見せて欲しいと頼んだんだから」
「姉上、いくら、ローゼンバルツァーがお受けを守る軍人の家柄だからといって、公私を分けていただかないと」
はぁ、と息をついた。
ジゼルがアリスを抱き寄せた。
「いいじゃない、アリスは私のお友達なんだから」
「え・・・」
かぁぁとアリスは頬を赤らめた。
「お、おおおお、お友達!?私が?ジゼル様の?」
「耳元で大声を出すな、女性は人前で声を荒げないものだ」
「固いわよ、ルドルフ、そんなんじゃ、女の子にモテないわよ」
ちっちっ、とジゼルは指を揺らした。
「姉上・・・・」
ふと、足元を見た。
「姉上、アーディアディトはわかりますが、何故、これを貴方の所にいるんです」
アレキサンダーが、赤毛が混じったダークブラウンの髪の背が低い少年の手をかんだ。
「あいてててて!!」
ウーッ
「痛い、地味に痛い!!」
「何故って、可愛い弟の可愛い初めてのお友達と、弟思いの私が仲良くなりたいと思うのは当然でしょう?」
ジゼルはにっこりと微笑んだ。
「・・・・ずるいです、姉上」
ルドルフはうっ、となった。
「アーディアディト」
「・・・ナ、何です」
「お前、にあわないな、そのかぼちゃパンツ」
アリスの顔が赤くなる。
「なぁぁぁぁ!?」
意地悪な笑みをルドルフはアリスに向ける。
「それに相変わらず、発音が悪い、まるで壊れたバイオリンだ。お前、弦が全部外れてるんじゃないか」
「ななな・・・」
「外れてるな、決定だ」
「何を勝手な!!」
「ルドルフ!!」
いさめるような声が向けられたが、ルドルフは無視をした。
3
闇の中で何かがざわついた。
一歩。
また一歩。
ルドルフの豪華で高級なつくりのベッドに近づいてくる。子供には不似合いの大きなベッド。柔らかい絹の寝着。冷えた空気の中で時計がカチ、カチと動く。
魔物がルドルフを襲う。
「・・・・っ」
拳をぎゅっと握る。しゃっくりが出そうになるのをルドルフは必死に抑える。いつもの発作だ。息が苦しい。息が途切れる。
大丈夫。
大丈夫だ。
夜が来るゴトに襲う不安、孤独、思い知らされる圧倒的な絶望。
支配者に人間の心は必要ない。降伏も何もかも、国民の明日のために。
頼るな、気を許すな、甘えるな。お前の人生は帝国のもの。ルドルフ、お前は軍人となり、誰よりも賢く、導くものとなる。
父親の言葉が浮かぶ。闇の中で目を大きく見開く。正直言って、9歳かそれくらいの子供の姿にしては異様だった。必死にシーツにしがみついた。
昼間ははしゃぎすぎた。自分らしくもない。あのきゃんきゃんと騒ぐ女のせいだ。秘密を隠してくれるのはありがたい。
・・・・何故。
今、アーディアディトの顔なんかが思いついた。
―きゃっ。
発作を出したルドルフが思わずしがみついた時、アリスも反射だったのだろう。ルドルフの小さな手を弾いた。
―あ、すみません。
からかった後、すぐのことだ。
誰にも弱みを見せてはならない。そう、自分は全ての幸福の為に子供でいてはいけない。
旅立つ前、エリザベートは珍しくルドルフの部屋を訪れた。家庭教師や司祭は慌てて、エリザベートの元に駆け寄った。
「すみません、王妃様、お部屋にこられるとは」
「すぐにイスを持ってこさせます」
つややかな黒髪が揺れる。ダークブラウンの瞳には、深い知性が漂い、高貴な空気が自然と皇妃の体からあふれ出る。
「いいのよ、旅立つ前にルドルフのかくぉを見たかっただけだから、顔色はよさそうね」
白い手がルドルフの頬に触れる。ルドルフに緊張が走る。
「・・・お忙しいのに、わざわざお越しをありがとうございます、母上」
ルドルフは子供らしく、美しく笑みを浮かべる。
「・・・息子ダモの、当然でしょう、相変わらず可愛い子」
エリザベートは優しくルドルフの頬に挨拶のキスをした。アレキサンダーも珍しそうにその光景を見ていた。
「それじゃ、フランツを頼むわね、ルドルフ」
「はい・・・・」
2人の間に微妙な空気が流れる。
「そうそう、ルドルフ、今度、ヴォルフリートを乗馬に連れて行くから、貴方もそのつもりでね」
「・・・え?」
ルドルフは顔を上げた。
「私、あのオッドアイの瞳が気に入ったから、素直そうで可愛いわ、姉の方は美人だけど・・・少しだめね、貴方のお友達なら私も楽しくおしゃべりできそうだわ」
女神のような笑顔で、エリザベートはそれだけ言うと、女官をつれて去っていった。冷たい風が通り過ぎていった。
ヴォルフリートはあからさまに緊張していた。笑顔の皇妃がヴォルフリートの前にいる。その光景を、ルドルフの姉、ジゼルがテントの中で見守っている。
・・・荒れるわね。
ルドルフのご機嫌を取るのがまた、難しくなりそうだわ。
「はぁ・・・」
ジゼルが心の中でため息をついた。
「それじゃあ、いきましょう」
「はい・・・!」
ヴォルフリートは黒い馬に乗せられ、エリザベートの白馬についていった。爽やかな風が通り過ぎていった。
「ばっかじゃないの!!もう!」
「止めろ、貴様、ふざけるな!!」
アリスがルドルフをお暇様抱っこした。
「アーディアディト様、ルドルフ様が私たちが」
「そうよ、無理して」
「お医者様はどこなんです!!」
「止めろ、離せ!!」
顔を赤くして、ルドルフはじたばたと暴れた。
「子供なら、頼ることも覚えなさいよ!!」
「キサマァァ!!」
ルドルフもカッとなった。
「僕を誰だと思っている、無礼者!!」
「助けて欲しいなら、素直に言えばいいじゃない!!」
アリスの頬は赤い。
何故、泣くんだ、この女・・・!!
ルドルフの顔がさらに赤くなる。
「誰がお前なんかに言うか、アホが!!」
「行くわよ!!」
「2人とも落ち着いて」
2人の間でヴォルフリートはおろおろとしている。
アリスは王宮へと走り出した。
4
教会の賛美歌か。
そう思って、ルドルフはベッドの中で意識を取り戻した。医者や女官は既にいなかった。
「起きたの?」
「・・・ああ」
ふぅん、とヴォルフリートは姉の美しい歌声に聞きほれるルドルフの整った顔を額に置くタオルを絞りながら、見た。
「ヴォルフリート様、ちょっと・・・」
「あ、はい」
ルドルフはヴォルフリートが去っていくのを視線で追っていた。ヴォルフリートは気付かない。
「はっさは収まったみたいですよ」
柔らかな笑みがルドルフに向けられる。
・・・可愛い。
一瞬だけ、そう思ったが、はっとなる。
「ルドルフ様?」
首を傾けて、アリスは不思議そうにルドルフを見る。
「・・・育った村で習ったのか?」
「はい、よく行く教会で、孤児院ではよくそれで起こられましたけど、なぜか」
「暢気なものだな」
「そりゃア、ルドルフ様の艦橋に比べれば、ですけど」
アリスは視線をそらした。バカ正直というか、真っ直ぐな気質だ。怒られて、といっても周りに愛されて育った結果だろう。
彼女と親しくなれば、自分も同じようなものになるんだろうか。
「いつも、ああ、何ですか、無理して」
「―負けてはいけないんだよ」
「僕は間違わない、民や国のために、父上やエリザベートの息子として、常に前を進む、証明しなければいけない」
「僕はオーストリアの皇太子として生まれた、だからこそ勝たなければいけない」
背筋が凍えそうになる。
「勝たないといけないんだよ、アーディアディト」
「僕は歴史に僕という存在を証明する」
ガラスのような、何のヒカリもない瞳が夕闇が迫る時間の中、異様な光を輝かせていた。不安のような感情がアリスに走る。
何か、ひとつのことがあれば、目の前の少年は壊れてしまいそうだ。
なぜか、アリスはそう思った。
「証明する・・・・んだ・・」
「ホラ、小鳥が死んだ、あの小鳥は運命に負けたみたいだよ、アーディアディト。馬鹿だよね」
5
慌てて、アリスが去っていくのをヴォルフリートは見かけた。
・・・何かあったのかな?
「・・・・」
けんか腰だからな、ルドルフ様も姉さんのこと、気に入ってるだろうに、何ですぐ喧嘩するかな。
「挨拶して、僕も帰ろうっと」
扉の前には、アリスを警戒したアレキサンダーが寝ていた。アリスを見て、敵だと判断したのだろうか。頭を撫でると、顎を摺り寄せてきた。
許してもらえたらしい。
「失礼します、ルドルフ様」
「入れ」
扉を開けると、ルドルフは広い窓の外の景色を見ていた。
・・・なんか、不機嫌そうだな。空気が重い。
「ええと、それじゃ、お元気そうなので、僕も家に」
ヴォルフリートは扉の方に下がりながら、ゴマするような笑みでそういった。
「・・・・無様だと思ったか」
「は?」
ヴォルフリートは教育を受けていない。アリスもだが。育った村でも無能だと、ドジでトロイとからかわれていた。のんびりして、変わっている。
頭の中も姉より鈍いのだろう。自分の話も半分は理解できていない、恐らく意味はわかっても聞き流している状態だ。痛められても、笑っていたらしい。泣き虫で甘えん坊で、姉の後ろに隠れて。
「女に弱いところを見られて、男なのに運ばれて、病気になって、・・・馬鹿だと思ったのだろう?」
弱みなど見せてはいけないのだ。ルドルフはヴォルフリートの方に顔を向けようと思わなかった。
「ええと?え?」
「僕は大丈夫だ、今日はヘンな所見せたな、下がれ」
「ええと・・」
う~ん、と首を傾ける。
「・・・・変な子ですよね、ルドルフ様って」
「は?」
「僕にはわからないんですが、何故恥ずかしいんです?病気になるのは、普通のことでしょう。病気になったら、誰だって頼りますよ。だって、怖いじゃないですか、そのまま死んだら」
「・・・あのナ、僕は皇太子だぞ。オーストリアのハプスブルクの。帝王は上に立つものだ、見本となる存在だ」
「身体が弱くてもですか?」
「貴様、侮辱罪だぞ、それは!!」
「ごめん・・・でも、9歳ですよ。甘える年齢だと思うんですが」
「僕は君と同じ子供じゃない、皇族だぞ。同じでいてはいけない、弱みは見せないものなんだよ」
「同じなわけないですよ、だって、僕とルドルフ様は他人、全くの他人ですよ。同じ人間なんて、僕はつまらないよ。いいじゃないですか、ルドルフ様が身体が弱くても、誰も責めてないんでしょう?」
6
「サルヴァトール公、本当にやるんですか?」
「無論だ、今挑戦しなくてイツ挑戦するというんだ、行くぞシュテルンバステル伯」
陽光のせいで、今年で14歳になる次期シュテルンバステル伯候補のヴォルフリートの顔はよく見えない。美丈夫といわれ、ルドルフに比べれば健康的なハプスブルクの問題児は、ロレンツ銃を手に新しく作られた小型爆弾に銃弾を放った。
パァン、スパパパン・・・・・!!
ドォン!!
空に煙が待った。
「・・・・・あの、花火みたいなんですが」
「よし、お前、見て来い」
「エーッ、俺ですか」
助けを求めるように、隣のヴォルフリートを見る。
「僕が行くよ」
これで、賭けは自分の負けとなるのか。
・・・僕、事務系というか、情報を集める方なんだけどな。
ハプスブルク家の紋章をイメージした飾りがついた帽子を整えて、大きめの軍服を揺らしながら、ヴォルフリートはそれに近づいた。
ダークブラウンの髪が乾いた風で揺れた。
「聞きまして、コンラート様」
美しく着飾った娼婦夜ダンサーに囲まれながら、サロンでイギリスから持ち帰った紅茶を飲みながら、中年を思わせない前髪がウェーブのダークブラウンの髪の貴族が耳を傾けた。
「ある修道院にそれは美しく、神のように清らかな司祭様がいるということを、いつもある異国の司祭の見習いをつけているのですって」
「へえ、あなた方のようなヴィーナスのような女性より美しい男ですか、それは見てみたいものだ、どんな男なんです?」
「私の同僚のシャルロッテから聞いた話では、スウェーデンとイギリス人のハーフで、祖父にアイルランドの伯爵様がいる、彫刻のように美しく、さながらクールなアポロンのような方なんですって、年は20代で、司祭長の一人だとか」
「私は、その司祭様の言葉を聴くために若い貴婦人やお医者様、・・・それにここではいえない身分の方もその集会で集まってるとか」
「どちらにせよ、それは・・・・」
「名前は何と言うのです?」
「だんな様!」
扉が開き、コンラートの妻でエルネストの母親であるフリーダが漆黒のドレスに身を包んで、顔を紫色のベールをかぶって、長身痩身の体で、入ってきて、女性達を無視して、コンラートに突進してきた。
「お前、今日は病院じゃ・・・・」
「うちの子の家庭教師の女から聞きつけたのです、あなたはまたこのような、いかがわしい場所で、アンナに今日は占いの出が悪いといったのに」
フリーダは身体を震えさせた。
「フリーダ、落ち着けよ」
「貴方は、わたくしの苦労を何もわかっていないのね、この前はボーイでその前は花屋の女をうちに入れようとして・・・・、私の顔が醜いから、この火傷のあとがそんなに気に入らないのね・・・」
フリーダがコンラートに扇を顔に向かって投げつけた。
7
姉上に結婚の話?」
皇帝フランツから、ルドルフはそうきかされた。13歳になった皇太子は幼さは年相応に残しながらも、母親と父親から受け継いだ美しさを実が聞けていて、誰もが見惚れる少年となった。
「そうだぞ、お前の所にも話があったと思うが」
「いえ・・・、今、初めて、知りました」
「そうか、あの子も大分困惑してるようだから、お前が落ち着けなさい」
「ハイ、父上」
「それでは、下がっていい」
「はい」
ルドルフが頭を下げて、部屋を出て行くと軍人や政治家、貴族や司祭が代わるように部屋の中に入って言った。
アレキサンダーが、耳をピクリと動かした。
「アレキサンダー?」
ルドルフが歩くのを止めると、衛生係といわれる女性と女官が廊下を歩いているのが目に入った。ルドルフを見ると、こびるような笑顔を浮かべた。
「・・・・・」
笑顔を浮かべながら、ルドルフは舌打ちを誰にも気付かれないようにした。
・・・大バカものめ。
ルドルフの姿を見て、ヴォルフリートは息を整えて、服装にへんなことがないか、確認をした。前とは違うのだ、身分が違う。しかし、だからこそ一国の皇子様に挨拶をしなければいけない。
「皇太子殿下!!」
ルドルフは、ヴォルフリートを見て、あからさまに誰に声をかけられたのか、わからないといった表情を浮かべた。
青い瞳は湖底を思わせる色合いに染まり、緑色の右目は濃く高貴さを滲み出してきており、日に焼けている右手には刻まれたような、十字架のような痛々しい傷跡があり、額にも同じような小さすぎる傷跡があるが、よく見ないと気付かない小ささだ。
「こんばんは!!今日はどのような気分でしょうか!挨拶が遅れてすみません、こちらに付くのが少し遅れてしまって・・・・」
「・・・ヴォルフリートか?」
薄暗さと日の光に中和されて、はっきりとその顔が見える。
そばかすが消えているが、その素朴さは変わっていないように見えるが、かなり整ってきている。柔らかく、可愛い印象だ。
「え、今、気付かれたんですか?」
今日は何なんだろうか、家に帰っても同じ事を何回も聞かれるし、街では変な目で動物のように女の人に見られるし。
「お前、化けたな、さすがはエレオノールの子供というわけか、血ってのは怖いな」
何故、ジーット見ているのだろう。
「それ、姉さんにも言われました、別に前と変わらないと思いますが」
「変わってる事に気づかないのか?」
「そういわれても、かがみ見るのが少ないですし」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- がんばれ!地方競馬♪
- 11/21名古屋の1点勝負
- (2025-11-20 21:41:05)
-
-
-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)
- 阿倍野にて
- (2025-11-20 19:22:08)
-
-
-

- 模型やってる人、おいで!
- EF58(その13) サンダーバー…
- (2025-11-20 20:40:42)
-
© Rakuten Group, Inc.