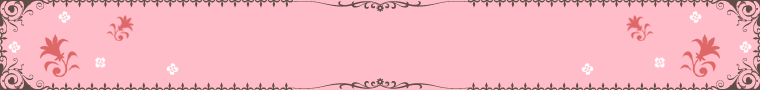第19章Poison Ivy
恋の苦しみほど嬉しいものはなく、恋に苦しむほど幸福なことはない。
(by アルント)
1
赤いヘッドドレスには濃い緑の紐とピンク色の薔薇の飾りがつけられていた。赤と黒を貴重にしたドレスはアンティークドールの衣装のように見える。人形のように小さな顔立ち、輝くような黄金の髪のツインテールはカールがかかり、瞳は高貴なブルーグレーの瞳をしていた。すぐ側にいるのは保護者だろうか。
ヨハン・サルヴァトール公のところに来た幼女は、貴族の令嬢らしい。
少女の前には、アリスの姿もある。ヨハンの恋人、ミリーは戸惑ったように二人を見ていた。
「ブレーズ侯爵のお孫様だそうです・・・それと、ローゼンバルツァーの残した・・・・」
「・・・・・アリスとディートリヒ、エルネスト3人以外の生き残った血族か。守る為に保護していたわけか。親は誰だ?」
すたすたと歩き出す。高貴さと幼さを見せる顔立ちはきりり、と引き締まっていた。
「サルヴァトール公、わたしのお父様はどこですの?」
「お父様?」
少女はきょろきょろと辺りを見回す。
「おかしいわ、ここにいるときいたのに」
「アーデルハイト!!」
わぁぁぁんと銀灰色のツインテールに青と琥珀色のオッドアイの瞳を持つ同じ姿の少女が現れる。
「犬が犬が!!」
「なぁに、アーデルハイト、情けないわね。レディーはむやみに感情を出すものではなくてよ」
「だって、犬が犬が!!」
「全く・・・」
家庭教師のエルザ・ブラルは、ハンガリーの血とラテン系の血を持つドイツ系18歳を迎えたばかりで、臨時の家庭教師として、今回の皇族のたびにも出ていた。担当する科目はピアノであり、チェコ語やスペイン語だった。得意なのは出会ったばかりの人と仲良くなること。性格はおせっかいで慌てん坊でどこか頼りなさ下で好奇心が強くなると、周りが見えなくなることだ。
「ウィーンの女性は美しいですね」
「困ります・・・」
専用の世話係である女官や護衛官、医者に囲まれたルドルフ皇太子を待つ待機室で外交官の役を負かされた成立前はプロイセンと呼ばれたらしいドイツ帝国の将校、ハルトヴィヒ・ベッテンドルフに口説かれていた。黒髪の美丈夫で、区二元では発言権もあるらしい。
「先生!」
蕩けるような笑顔の皇太子が乳母を連れて、エルザに駆け寄ってきた。初めて、会った日からルドルフはエルザを気に入ったらしく、何かと話しかけてくる。
「まぁ、どうなされましたの、殿下」
素直で内気で、世間の皇太子の性格とは随分違う。
「父上が、先生もお茶会に誘ったらどうだって」
お目付け役の女性の目が光る。エルザはぎくりとなった。
「まあ、それは、上のものに聞いてみませんと」
おほほ、とエルザは困ったように笑う。
「・・・・貴方がローゼンバルツァーの人間を手下にしているとは知らなかった」
マザー・アリエスはたよらかに笑う。アロイスやローザリンデの姿もある。
マフィアのボスとその腹心エリクがヴォルフリートと話していた。間には情報屋で交渉やのモニカの姿もある。
「私は一匹狼でうちにもなかなかいつかない貴方が、宿敵と私たちのダブルスパイしているとは思わなかったわ」
「目的を果たすためだ」
「・・・それでは、何故、ヴィルフリートに深入りしたのかしら」
「ヴィルフリート?あいつの名前はヴォルフリートだろう」
「いいえ、ヴィルフリートよ」
「・・・何、皇太子の友人?」
「ああ、来ているらしいよ、ハルトヴィヒ。オーストリア・ハンガリー帝国で割りと有名な実力者の子息らしくて、好みに細かい皇太子殿下もその友人は重宝して、他の取り巻きとは区別してるとか」
「カール、皇太子殿下の明日のスケジュールを聞いているか。明日、お前、大臣や陛下たちのお付きを負かされてるんだろ」
紅茶の匂いが部屋の中を漂っていた。
「・・・ハルトヴィヒ、仕事か?それともいつものニンゲン観察かい?悪戯を過ぎると、いくら僕でもかばえないことが」
「カールは口が多いな」
「一応、上司に聞いてみるけど、行動には責任を持てよ。今は大事な国同士の話し合いなんだから」
はぁとカールはため息をついた。
「君の友情に感謝するよ」
穏やかな太陽の下で、お茶会のように長いテーブルで、お偉方の話し合いが開始され、周りの警護をハルトヴィヒ浜かされ、退屈極まりなかった。老人や軍人が多い席でただ一人の子供、皇太子は政治の話に耳を傾けていた。木の匂いや草の匂い、花の匂いがハルトヴィヒの鼻腔をくすぐる。
「寝るなよ、ハルト」
「悪い、悪い」
悪戯めいたり、冗談を言って期限を取って。時折、照れたり。
さすがは皇太子と大人顔負けの表情や発言をして、そこらの子供と違うという振る舞いを見せる。
・・・さすがは有名なエリザベート様の息子ということか。美しい。
視線が偶然重なった。
・・あ。
にこり、とルドルフは可愛らしく微笑んだ。
ただのガキかな、やっぱり。
2
数人の貴族の子供がルドルフに話しかけ、ルドルフも楽しそうに笑っていた。
「リヒャルト、それではこの場は任せるぞ」
「はっ」
中には、ギルバートの父親の姿もあった。嫌味な視線を浴びて、しょげている鳶色の柔らかそうな髪のギルバートも。
「見て、あの肌の色・・・」
「アレでは、殿下にゴマをすっても意味がないわね」
妙齢の貴族の婦人が扇越しに笑っていた。
「・・・・君もこっちに来る?」
「イエッ、僕はいいです」
柔らかく透明感のアル笑顔を向けられ、ギルバートは赤く染める。
「でも」
「結構です」
ギルバートは顔をそらした。
そんな時、白いレースの服を着て、白い帽子を被ったアリスが登場した。春の花のかぐわしい匂いと太陽に輝く笑顔がそこにはあった。
・・・エレオノール。
その少女はハルトヴィヒの初恋の人によく似ていた。誰でも優しく包み込み、勇敢で、自分を曲げない輝いている美しいウィーンの聖母に。
「殿下、お医者様が読んでいます」
「もう、そんな時間か」
「おいそぎを」
信頼した笑顔がそこにあった。他の子供達とは対応が明らかに違った。
「彼女ですよ、殿下の親友は」
「・・・名前は何と言うんだ」
「え、ええと・・・」
「すみません、将校様」
そばかすの目立たない赤毛の少年が声をかけてきた。
「ルドルフ殿下が夜の会食にドイツ帝国の貴方達も席を同じにするようにと」
田舎にでもいそうな、いもな少年だった。ハルトヴィヒはしたうちをした。オーストリア側の宮廷仕えの貴族の少年なのだろう。それらしい衣装を着ている。ロシアの血でも持つのか、片方の目は深い新緑のような深い味わいの色をしていた。反対の青い目は、以外にも金髪の先ほどの少女と同じ色だった。
「俺、少し抜けるわ」
「え、あ、あの」
11歳くらいの少年は戸惑ったようにハルトヴィヒを見上げている。
「でも、僕、それまで、将校様達のお相手をするようにと」
「ふん」
ハルトヴィヒは少年を突き飛ばした。
「ああ、時間までには戻ってこいよ」
「・・・ああ」
ツェツィーリア・フォン・ベルギャントは取り巻きに囲まれながら、ヴォルフリートから皇太子殿下の情報を聞き出していた。父親には皇太子に取り入るように言われ、人のよさそうなお付きのヴォルフリートに目をつけたのだ。
「・・・そうですか、それではエルザ女史は特別な女性ではないのですね」
「よかったですわね、ツェツぃーリア様」
「ルドルフ様は誰にでもお優しい、ただそれだけのようですね」
賛同者の少女たちは嬉しそうな声を出す。
「わたくしはアルベルト様の為です。アルベルト様が、殿下をお守るする立場になられるから」
頬がかすかに染まる。その時、扉が乱暴に開き、ツェツぃーリアは突き飛ばされる。
「ヴォルフリート、大変、大変!!」
「・・・・アーディアディト~」
「あら、どうなされたんですの、ベルギャント侯爵の令嬢様」
嫌味な言い方だ。
「人のことを突き飛ばしておいて、この愚か者!!」
「それはごめんなさい」
2人の間で火花が散った。
「2人とも落ち着いて・・・」
2人の間をオロオロとヴォルフリートは歩いていた。
「「貴方は黙ってて!!」」
アリスとツェツぃーリアの声が重なった。
3
部屋で偶然、ルドルフと話す機会があり、お連れの女官がくるまで話すこととなった。
「ルドルフ様に変なことを言わないでくださいね」
「しませんよ」
エルザは警戒心を浮かべた瞳でハルトヴィヒを見た後、足早く去って言った。
「・・・・」
2人の間に沈黙が走る。
「夕べはよく寝られました?」
「はい、陛下が貸してくれた施設は充実していて」
「父上は王たるものは下のものの感情も大切にすべきという考えですので、まだまだ修行中の僕としては父上の足の先を掴むのも大変でして」
「偉大な父君をもたれるというのは、どこの国の王族も同じですよ」
ルドルフが立ち上がり、バイオリンを持った。
「ベッテンドルフ殿、貴方は音楽に興味は?」
「嗜む程度には」
「それではひと時、子供の演奏を聞いてくれませんか?僕の近くのニンゲンは教本どおりの評価しかくれないので」
「貴方がひかれるのですか」
「はい、たまに開いた時間に父上が教えてくださるので、僕も開いた時間に紀を鎮める為に引くんです」
「・・・・」
「見事な演奏でした」
「良かった、少し店舗がずれたり、音が微妙になったと思ったのですが」
ドタッ
階段でアリスが転んだ音が聞こえた。
「何だ」
ハルトヴィヒが廊下に出ると、アリスだった。近くにいた使用人は機械的にアリスを助け、一方目立たない位置でさげすむようにアリスを見下ろしていた。
「ドジね」
「ふふ・・・」
上の階のツェツぃーリアもくすくすと笑っている。
「ここには殿下も折られます。ご自分の振る舞いに気をつけてください」
かぁぁとアリスは頬を染める。
「はい・・・」
ハルトヴィヒはてを差し出す。
「君、大丈夫かい?」
アリスが体を起こすと、足に痛みがはしった。
「・・・あ」
「どうした」
「足が・・・」
痛めたのか。
「誰か、この令嬢の元に医者を連れてきてくれ」
「いえっ、そんな」
ルドルフが膝を折り、心配そうにアリスを見る。
「・・・大丈夫か」
声が今まで聞いたものと違う。どこか不器用な声だった。
・・・特別ね。
「大丈夫、私が何とかしよう」
「・・・・」
アリスは戸惑い、ツェツぃーリアは苦々しい表情を浮かべた。
4
花びらが舞う中で、花園の中で青空の下、アリスは笑うルドルフと共にくるくると回り、元気よく笑う。最初の印象とは違い、おてんばで元気な少女のようだった。
「困る行動をするな」
ルドルフはため息をついた。
「あら、遊ぶことは子供の特権でしょ?」
「僕は時間が限られてる」
「私は殿下の相手をするのが、仕事ですよ」
アリスはにっこりと笑う。
「足を痛めてるんだから、ここは弟に任せろよ」
「大したことありません。・・・私では駄目ですか」
アリスがじっとルドルフを見る。ウッ、とルドルフがなる。
「・・・・性格が悪いな、お前、ナルシストか」
「酷いですよ、殿下」
その光景を見ながら、弟とハルトヴィヒはくびを傾けた。
音楽会で、皇帝フランツは言った。
「では、任す」
「それでは」
ここで、ハルトヴィヒは奇妙なことに気付く。フランツとルドルフが近くの席でありながら、全然会話をしていない。それどころか、ルドルフは視線を父に向けようとしない。ただ緩やかに力なく笑みを浮かべている。
廊下で、エリアスにあった。
「エリアス」
「・・・・ハルトか」
「久し振りだな、・・・本当にオーストリアの人間になったんだな、ドイツ帝国の宰相の息子だったお前が」
「外の子供ですから、それに自分はもう家を捨てた人間です。ハルト、貴方もよくあの家にまだいられますね」
「酷いな、こう見えて、おれ、愛国者よ?」
「そうでしょうか、貴方はいつもご自分をごまかされるので」
ぞろぞろと周りのものをつれて、ルドルフは移動していたが、ギャラリーの中にアリスの姿はいなかった。
「おい、エリアス、今日はローゼンバルツァーの人間はいないのか」
「何故、そのナを・・・まあ、皇帝陛下やその後子息の殿下の護衛ならば有力な家のものならいくつかいますから、・・・また、女ですか、ハルト」
「はい?」
「その家のもの出来ているのは、レオンハルト様やエレオノール様ではありません」
「しかし、宮廷仕えでその道では有名なんだろう、エレオノーるさまも后妃様のご好意があるとか」
とん、と腕に何かぶつかった。
「すみません、失礼を」
二日前に会った少年だった。少年は頭を下げると、ルドルフの元によって言った。
「そういや、誰だ、あの子供は、エリアス。取り巻きの一人か?側仕えの貴族の子息か?」
「ルドルフ様のご友人です」
「は?」
「ですから、殿下の友人です。名前はヴォルフリート・フォン・ヴァルフベルグラオ、貴方が助けた少女の実の弟君です」
「・・・・にていないじゃないか。それに殿下なら、自分のレベルに合う、容姿も家柄もいい同い年の少年や少女なら友達がいくらでも」
「私もそう思いますが、・・・殿下が気に入られているので」
5
森の中を仕事の合間に散歩に誘うと、エルザ、ルドルフの後にヴォルフリートはついてきた。
「おお、森苺。あ、こっちはリスかな、足跡が」
「違うな、これはイノシシか、もっと大きい動物の足跡だ」
大人びた、それでいて意地悪に見えるような、そんな表情を浮かべて、ハルトヴィヒとエルザの前を歩いていた。
「小さい瓶でももって来るべきだったかな、土の成分とかわかったかも」
「それなら、薬品を使った方がいいんじゃないか」
「はぁ・・・」
「馬鹿だな、お前」
「はぁ・・・」
エルザも驚いたような表情をしていた。
「エルザ、殿下はいつもあの感じなのか。前と印象が違うような」
「いえ、私もヴォルフリート君が来るときは席をはずされるので。ですが、もっと殿下を知ってる人だと、ヴォルフリート君といる時が殿下は一番安心しているとか」
湖の側でエルザとルドルフが話をしていた。爽やかな風が森の中をはしっていた。
「ヴォルフリートと呼んでいいかな」
「え?はい、構いませんが」
「君が殿下の友人と言うのは本当かい?」
「はい」
「殿下は君の何を気に入って、お側においておられるのかな?」
「え」
う~ん、と首を傾けた。
「よく言われるのはバカとか、役立たずとか、ぼけっとしてるから良く歩いて歩けとかだから、からかうのにいいとか?姉さんといると、意地悪を言われるし」
「その程度で、あの頭がよく、将来が有望な殿下が側に置くと?」
「いつも高いグランドピアノばかり相手より、手作りで雑なピアノもたまには相手にしたいんじゃないですか。僕、いつも失敗ばかりで姉にも殿下にも母にも怒られますし」
「何か、得意分野があるのだろう、殿下に役に立つような。君にあるはずだ」
「得意分野ですか、・・・ええと」
いらいらする。何なんだ、この普通の子供は。しかも頭が悪そうでとろそうなガキは。
ルドルフがヴォルフリートの頭を叩いた。
「いつまでくだらない話をしている、行くぞ」
「え~っ、僕、もう少し、ドイツの話も聞きたいんですよ~」
「駄目だ」
ルドルフが靴を投げ捨てた。
「靴が汚れた、気持ち悪いから僕を背負え」
「え~」
「僕の命令が聞けないのか?阿呆が」
冷たい視線だ。ちろり、とヴォルフリートを見ている。
「足が痛いんだよ、僕は」
「ルドルフ様、私が」とエルザが申し出る。
「僕はこいつに背負えといったんだ」
凄い我儘だ、とハルヒヴィヒは思った。
「僕、体力ないのに」
そういいながらかがみこみ、ルドルフは背中にしがみついた。
「丁寧に持てよ、落したらお前の父親を首にするから」
「はい~」
6
自分と弟と態度が違いすぎやしないだろうか。
「随分暴れ回って、あの煩い雀どもを混乱させたそうだな?ナァ、アーディアディト」
意地悪な上から目線だ。肘盾に膝を預けて、足を組みながら、ルドルフは口元をゆがませた。ルドルフは乱暴に汚れた足をアリスの手の上に預けた。
「きゃっ」
「綺麗にふき取れよ、使用人」
「誰が貴方の使用人・・・、会談の時は優しかったのに」
「当たり前だ、あの男はドイツ帝国でも重鎮だぞ。いい態度を見せるのは当然だ。出なければ、誰がお前のような女を助けるか」
「ヴォルフリートをこき使ったのは、何の為よ」
「勿論、将来、僕の側で働かせる為だ。あいつは僕のものだからな」
「勝手に決めないで、ヴォルフリートのミライはヴォルフリートのものよ」
扉が開いた。
「姉さん、女官のリーザさんがそろそろ出発の用意を殿下にって。・・・なんで、タオルを持ってるの」
振り返ると、ルドルフは既に服を着替え、新しい靴を履いていた。
「アーディアディトは少し慌ててたんだよ」
「ちょっと・・」
ルドルフが後ろでアリスの服のすそをつかんで、つねった。
「頭を撫でろ」
「は?」
「撫でろ、かさついたてで。出来れば白い洗練された手がいいが」
ヴォルフリートがルドルフの頭を撫でた。
「たまにルドルフ様はわからないことを言いますね、本当に。こういうのはお母さんにしてもらうんですよ」
「寝る前に本を読め、フランス語の絵本だ」
「自分、まだスペルを間違うんですが、・・・いいんですか?」
「僕がお前にケーキを食べさせてやる、十分だろう?」
「・・・ええ、それなら、姉さんの方がいいな~、って、顔をすりスリしないで下さい、気持ち悪い」
馬車の中では、ヴォルフリートがいびきを書いて、ルドルフの肩にもたれかかりながら寝ていた。重箱のような本を持ちながら、窓ギシにハルトヴィヒと会話をした。
「そんなの、ヴォルフリートだからに決まってるだろう」
「・・・・」
品がなく、つばをたらしながら気持ちよさそうに寝ている。赤毛っぽいダークブラウンの髪を優しく撫でていた。
「僕が守らなければ、こいつはどうやって生きていけるんだ」
7
「ウヴァ、私、きらぁい」
「駄目よ、アーデルハイト、好き嫌いしちゃ。約束したでしょ、外にでたらもう、おじい様のところみたいにいてはいけないと」
「アーデルハイトはでたくなかったもん。外に出たらお父様が絵本を読んでくれるんだもん、・・お父様ぁ」
頭が混乱しそうだ。
「・・・・あの、あなた達のお父様って誰なの?」
「その前にどっちが姉でどっちが妹なんだ」
ヨハンが長いソファーに手を置き、身を乗り上げて、2人のアーデルハイトに聞いた。
「・・・・黄金のアーデルハイトが姉、銀のアーデルハイトが妹」
「私達、一つ違いなの」
「・・・双子ではないの?」
アリスは若干戸惑いながら、聞いた。
「私とこの愚図妹と同じにしないで頂戴。この私がこんなのと同じなわけないでしょ」
手を腰に当てながら、9歳の少女はそういった。
「・・・ごめんなさい」
なぜかアリスが過った。
「父親は誰だ?母親は?」
「そうね、苗字も名前も言わないのは相手に無礼だわ。私達の父はヴォルフリート・フォン・ローゼンバルツァー、母はアンネローゼ・フォン・レーヴェクロイツ。そこにいるアーディアディト伯母様の弟よ」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・え?」
アリスは何を言われたのか意味がわからなかった。
雨が降り注いでいた。空気も大分乾燥している。
ヴォルフリートは正直、困っていた。
・・・・狭い。何故、エレクは、友となった少年は自分にこんなに近いのだろう。
「あの、狭いんだけど」
「相談に乗るんだろ」
「・・・姉さんは、君のこと知らないよ」
最近の姉の人気ぶりは何なんだろうか。
ディーターは8月12日に珍しく白いドレス姿に包んだエルフリーデの艶姿を見た。恥ずかしげに戸惑った表情で。
「にあうかな?僕は本当はこんな格好・・・変だよね?」
「そんなことはない!!」
思わず声を上げてしまった。クスクスとエルフリーデの母、ブリジットとその夫カールスの姿があった。
「ラインハルト様は今日来ていないのですね」
「これはブレーズ侯爵、来てくださったのですか」
「それはもうお美しい奥方にお可愛い娘さんがおられるカールス殿のいる所なら、どこでも」
「ま、うまいこと・・・」
くすくすとブリジットは扇を広げて笑う。
「クリストとヘレーネ様はまた喧嘩をなさっているようですな」
「放っておいているのです、あの2人は昔からああなのですから」
はぁ、とブリジットはため息をついた。
「今日は音楽科の賓客もおおいようですな。コンラート殿がさっき、バイキングの衣装を着ていましたが」
エレオノーるは優しく穏やかにきびきびと客に対応しており、側にはディートリヒやフィネの姿もある。
フォルクマがきょろきょろしていた。客の間を歩いていたブレーズとヴォルフリートが気付き、声をかけた。
「どうしたんです?何か、お探し物でも」
「ああ・・・、君の姉君はどうした?乾杯の音頭を頼んだんだが」
「そういえば、会場にいませんね、散歩でしょうか?」
客たちは楽しそうに話をしていた。
アリスは塔の中にいた。
「鍵を内緒でとってきちゃった」
「・・・・」
扉の向こう側にいるアンネローゼは沈黙している。
「こんなにすばらしく晴れた日だもの、アンネローゼが自分のお父さんの誕生日に出ていてもおかしくないわよ」
硬く閉ざされた扉の前に、使用人部屋からカギを貰ってきたアリスが白いドレス姿で弾んだ声でそういった。扉の隙間から、アンネローゼの声が聞こえる。
「ありがとう・・・、アーディアディト」
8
「全く、どこに言ったんだ」
エルネストとフォルクマはいつの間にか立ち入り禁止エリアまで来ていた。
ザァァァ・・・。
「青い薔薇?」
花びらが舞い、見上げると古い塔が聳え立っていた。視界の隅ではエルフリーデが黒い服の男と会話をして、馬車に白いドレス姿で乗り込む所だった。
自分の父親の誕生日に??
「行こう、エルネスト」
「ああ」
最上階まで行くと、奥の部屋の扉は開けられていた。
「薔薇がこんな所にまで・・・」
「部屋に入ってみるか、アリスがいるかもしれん」
「止めようよ、幽霊や物取りがいるかも」
ふっ、とフォルクマが笑う。
「子供だな、エルネストは」
その時、部屋の中から呆然とした表情のエルフリーデの姿があった。服は着ておらず、布で身体を覆っている。
「・・・・・エルフリーデ?」
「その格好は・・・・」
「お前、フォルクマね。ヨハネスの孫の」
声の調子もいつもと違う。雰囲気がなんだかいつもと。
「それは君もだろう、エルフリーデ、君に何が」
エルフリーデが歩き出す。エルネストの身体に緊張が走る。
「・・・・貴方」
「―-」
エルフリーデがフォルクマの胸に手を当てる。
「お前でちょうどいいわ、フォルクマ、お前、あの人のために死んで!!」
女神のようにエルフリーデは微笑んで、フォルクマの胸を貫いた。
「―--え?」
その20分後、アリスは再び塔へと向かう。アンネローゼが来ないことに不安を感じたのだ。
どうしたのかしら、ドレスも髪飾りもあげたのに。
着れないという事はないだろうけど。
・・・・仲良くできるかしら。
仲が悪い両家だけど、私と彼女とで・・・・アロイスもヴォルフリートもきっと。
ふふ、と笑いながら、アリスは階段を上り、最上階に向う。
角を曲がると、信じられない光景が広がっていた。
「・・・え?」
きゃああああ、と悲鳴が聞こえた。会場の方からだ。
「・・・・アリス、早く皆の所へ、あのバケモノが・・・・・」
エルネストはアリスにそういった。
ブリジットの城や会場となった庭は炎の中で、目の前の会場は地獄絵図だった。全て喉を引き裂かれ、目をつぶされて、殺されていた。
「これは一体・・・・」
すぐ側には、フィネの姿があった。
「・・・・その声はお姉様?」
「フィネ、これは一体・・・」
「あの人が・・・」
フィネがアリスに抱きかかえられながら、ある方向を指を指す。
炎の中で、ヴォルフリートはエレ区の手を振り払った。
「オイ!ヴォルフ!」
「アンネローゼを助けに行く!!」
「友情に熱いのはいいけど、行かせてくれ!!」
「失踪したんですよ、昨日、アンネローゼ嬢、貴方の伯母の娘が」
「え?」
馬車に同席した刑事の言葉に、足を止めた。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- GUNの世界
- Browning Hi Power【Commercial】HW…
- (2025-11-20 12:30:22)
-
-
-

- 競馬予想
- 11月270%回収率稼働中!今週は3…
- (2025-11-20 20:25:30)
-
-
-

- 動物園&水族館大好き!
- 千葉市動物公園 しずかちゃんのご飯…
- (2025-11-21 00:00:21)
-
© Rakuten Group, Inc.