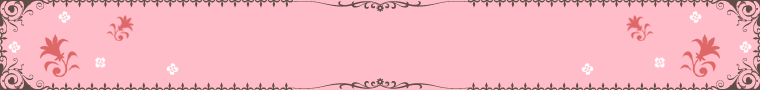第20章アンダーラインに惑わされるな
あたりまえのことを心をこめてすることだ。
(by ヴァニエ)
1
アレクシスの元に、アロイスとアルベルトの決闘のニュースが飛び込んできた。先日は、家の中でエルフリーデがエドガーと共に心中未遂の事件でざわついていたというのに。格式と伝統に囚われたこの高貴な貴族の家柄は、王族とのつながりがある。だからこそ、彼らからしたら事件続きで頭の中が混乱しっぱなしだ。
暑さと気温の変化が苦手なアレクシスは、重い空気の中、事件後のヴォルフリートに出会った。ヨハネスの子供で生き残ったのは、エレオノールやブリジット、ディートリヒやフィネ、エルネストだった。テロリストに襲われたとも、ローゼンバルツァー家に恨みを抱くものが起こした反抗だとも聞いていた。誕生日パーティーの会場はまさに惨劇のあとであり、死体は爆発物でも使われたのか、目を大分痛くなるくらいの惨状だったらしい。
お金に少々だらしない一面を持つヴォルフリートは下品な笑いを浮かべ、野性味のある表情でコインをベッドの上で数えていた。普段とはまるで、がらりと違う。別人だ。病院の壁は切り刻まれ、看護婦や医者もその代わり用に恐怖を隠すことが出来ない。
「くく・・・、きゃははははははははっ」
「・・・・・・」
あの現場にいたんだ、仕方ないか・・・・。あんな・・・・。
踏み込んだ会場の光景がアレクシスの脳裏に浮かぶ。おかしくなるのも無理はない。
「サルヴァトール公」
息を切らして、ヨハンが駆け込んできた。
「アーディアディトの家が襲撃されたというのは本当か」
・・・わざわざ、着たのか。護衛の役割を持つ、お受けともつながりがある家柄とは家。アレクシスはそう思ったが口に出すのをぐっと押さえた。
「親戚だそうです」
「・・・・そうなのか」
「はい」
事件から数週間後、警察と病院、裁判所を廻っていたヴォルフリートは職場復帰をしていた。親しげに、リヒャルトと話すヴォルフリートを、皇太子派を擁立する派に入っているデュドネは心配そうに見た。同じ皇族派で純血主義、皇太子を押す立場である先輩が娼婦の母親を持つ庶民上がりの男などと。
「大丈夫かな、あいつ・・・」
「酷い有様だったんだろ・・・」
「全く、許せませんわ」
「アーディアディト様も今は入院中だとか・・・」
宮殿の中で、ヴォルフリートは様々な人に囲まれて、けなげにも笑みを浮かべている。
相手の顔は見えないが、医者と中年の上流階級のニンゲンだった。
「そうですか・・・ありがとうございます」
「君の親に伝えるべきかな・・・」
「いいえ、このことは自分と先生だけで・・・明日、その人に会いに行きます」
ローゼンバルツァー家の暗闇が常にあの笑顔を包み込んでいる。デュドネは恐ろしさとどうしようもない不安を感じてしまっていた。
わざわざ、皇帝陛下に勲章を頂くとは、実力はないが権力のアル大貴族に甘い言葉を吐くだけはある。アリスの弟は演技の才能と女性をかどわかすこと、気難しい相手を口説き落とすのに長けておられるようだ。
「出世したんだよな・・・ここ最近の好成績の影響で」
家と格式にこだわり、身分の低いものを受け入れないウィーン宮廷ではありえない。実力者の孫というのが生きているのだろう。
とんだ狐だったということか。大人しそうに、出世に興味ないと振舞いながら、影では太いパイプと手を結んでいたとは。控えめで、慎ましやかな笑顔で遠慮がちにそういった。
「まさか、おじいさまのお力の賜物ですよ」
柔らかい笑顔で包み込むように言った。その時、ヴォルフリートを慕う皇女マリー・ヴァレリーやフランツが現れた。
「ルドルフを出世の道具にして、だろ?」
暖かい手でヴォルフリートはヴァレリーを包み込み、笑みを浮かべる。ヴァレリーは嬉しそうな表情を浮かべた。
「クリスマスですね。もうすぐ」
窓辺に視線を映す。
「ヴォルフリート、お前は何を望む?地位や名誉か?」
雪が降りそうだ、ヴォルフリートはそう思った。真っ白い手。けれど、自分の知っているあの手は血で汚れている。漆黒の長い髪を血でぬらして。
「聞いているのか?」
「すみません、ですが、その質問はヨハン様には悪いのですが、次回ということにさせていただけませんか?」
「何」
「約束します、この胸にかけて」
胸に手を当てて、静に目を閉じて、涼やかな声でそういった。
2
煙をまくように、皮肉交じりに馬鹿にするようにアリスを笑う。
「はっ」
「何よ。馬鹿にする気・・・」
くすり、とどこか毒が混じったような笑みが浮かぶ。まだほんの16歳の少年だというのに容貌のせいか、酷く大人じみているように見える。帝国の敵である反政府勢力とつながりが発覚したマフィアとの戦闘中、一緒に逃げる形となったエレクと廃墟の中、偶然という形で離すこととなった。
「別に、ただ弱者を救う志はそんなにむやみに言うものかなと思ってね。なま温い環境におかれた平和主義者らしい言葉だ」
切れ長の瞳はアリスを見据えているようで、アリスの心を大人しくさせない。妙な不安を感じさせる。
帽子を被り、仮面をかぶり、闇のオシオキ人で腐敗をくじく。あの皇太子の趣味にしては随分少女趣味だ。エレクはどこかアブナカッ示唆と胡散臭い雰囲気であり巣を恵刑させていた。闇に属する存在。
「女性をだますやり口でお金を巻き上げるあなたに、そんなことを言われる筋合いはないわ」
足元には闇金や裏の世界のスないパー、ごろつきが転がっていた。エレ区の手には、ハンドガンが握られていた。エレ区が全て打ち抜いたのだ。
敵を殺す時の表情はまさに冷酷で人をだますことをいとわない狐。軽やかに人を惑わす手口は狸だ。エレクは誰にも属さない。世話になっている裏の世界の重鎮にも、心を寄せる同僚にも、近づくものを全て切りつけ、陥れるならず者だ。先ほども仲間としていた男を自分の立場が危うくなった瞬間、銃で残酷に殺した。
切り裂き魔、歩く火薬庫といわれるだけはある。エモノを得たときの死の天使のような狂気じみた笑みは、強靭そのものだ。
「力は誰かを守る為に存在するものよ」
真っ直ぐで清らかで、熱い炎のような射抜くような目がエレクに向けられる。
「自分を守る力もない正義の味方気取り不在がこの俺に説き伏せる貴下、笑わせるな。俺に命令するな、俺に逆らうな、この偽善者やろうが!!」
威張りやなエレクの短所がでた。
「私の貴店がなかったら、貴方は助からなかったわ」
凍りついた表情に赤みが差す。プライドが高い男なのだ。
「たまたまだろ、お前が余計なことをしなければ、俺は喉元をすぐに引き裂けた」
「へそ曲がりで意地悪・・・人の命を何だと思っているの」
「お前が言うことではない」
冷たく突き放された。
事件を聞いたのは、数週間後だ。
速達で王宮には送ったが届いただろうか。満面の笑顔で喜ぶ皇太子を想像したが、・・・見たくはないな。女子にはちょうイケメンなんだろうが。
「金や株に対して、厳しくないか?アレクシス」
「お前がヘンな入金するからだろ。裏からなら、ご自慢の甘い台詞や顔使えば?お前、立派な結婚詐欺師になれるぞ」
「うわ、この倍率は厳しい・・・」
脳裏に、カールとしてのアリスとのあるときの会話を思い出しながら、トルコ人?ギリシャ人の従者の青年を連れながら、スロバキア人の自由民主化運動を人ごみの中、眺めているヴォルフリートの背中を見た。
恨まれて当然の悪魔の一族だ。惨劇が起こることはエレクでも容易に想像できる。軽快すべきは自分も同じだ。いつか失われた命の為に、敵の陣地にもぐりこみ、信頼させ、帝国を恨む同胞の冷たい視線を浴びながら、いつかローゼンバルツァーの病巣をえぐる為にこの男に近づいた。
誰も信じるな、愛するな、油断するな。それが信念でこれからも変える事はない。いざとなれば、利用しているこの男だって自分はこの手で殺して見せるだろう。これは最優先時事項だ。
・・・本当に帝国に自由を勝ち取りたいならば、生ぬるい方法だ。
男達の生々しい感触が身体に蘇る。手にはじめて感じた銃の重み。異能者として始めて人間を殺した嵐の日。弱気になるな、ひるむな。
エレク・ビーネアイト、お前はその程度ではないはずだ。
チェスの駒のように目の前のダークブラウンの髪の男を見る。彼と自分の立場を置き換えれば、ヴォルフリートにとって自分こそが危険な存在だ。間違いはない。自分の存在が発覚すれば、皇太子の前にヨハネスの牙がこの男の喉元を引き裂きかけない。
「どうした?」
恩は感じている。今までなら離れるか、殺すか、その二択を選んだだろう。誰にも寄り付かず、自分だけで目的に向っていくだろう。だが、あの表情の答えも自分への友情の正体も自分は知らない。
「いや・・・」
何を考えている。面倒なことは関わらない。貴族がどうなろうと、俺には関係ない。殺されようと、どんな目に合おうと。
ここにいるのが、あの時、自分の目の前にいたのがヴォルフリートの姉。一度たりともこの自分の心を乱し、許した、愛とも恋とも呼べない感情を齎した彼女ならば、今、切り捨てるだろうか。この姉弟は危険だ。
近づけば、自分は恐らく今以上に、今の自分を否定され、自分ではない何かが認めたくないものがさらされ、傷をえぐられる。予感ではなく、確定だ。
だが、だからこそ、目を背けてはならない。
ヴォルフリートは自分から、異能者ではない、自分に近づいたのだから。その意味の大きさから、行動から、何より自分の言葉から逃げてはならない。
「・・・・無愛想な男だな、こいつ」
「そうか?アレクシスが思うよりは意外と普通だけど」
「せっかくの休日に男だけとは、あーっ、女に障りたい」
「女好きだね、アレクシスは」
「・・・リーダーがしゃべるぞ」
エレクがぼそりといった。アレクシスも視線を目の前のスピーチに向ける。エレクはヴォルフリートが血のような夕焼けに一瞬向けたことに気付いた。たった一瞬だが、置いていかれた子供のような感情が青い瞳に浮かんでいた。
3
エルフリーデの病室にアリスは訪れていた。
「・・・・・・アリス、来てくれたんだね。・・・・馬鹿なことをしたと思ってるだろ」
その表情はアンネローゼに似ているが、双子でも異能者とニンゲンではここまで違うのか。エルフリーデはニンゲンだ。自分と同じ。
「・・・本気だったんでしょう」
「・・・・・ああ。彼はね。僕も・・・・・」
か弱い。親衛隊であろうエルフリーデが。
「こんなこと言ったら、君は僕を見損なうかもしれない」
「エルフリーデ?」
ふっ、とどこか自嘲するように、切なげに笑う。
「アロイス・バルツァーのこと、好きなんだろ?」
どきん、とアリスの胸が脈を打つ。
「私は・・・・」
「僕は・・・いえ、私は、ずっと、皇太子殿下が好きだった。だから、親衛隊に入ったんだ」
衝撃の告白だった。
「・・・・え?」
「セルビア人やスロヴァキア人のほうでは相変わらず」
「家々、外ばかり我的ではありませんぞ。政治家の腐食問題に巻き込まれて、家をつぶされたものも」
「うちの娘を有力者の下に」
ガラス窓に背を預けながら、白い軍服を模したパーティー用の礼服に身を包みながら、ルドルフはワイングラスを片手に大臣や司祭、貴族たちの会話を聞いていた。
「ルドルフ様、ダンスを」
勇気を出した白いドレスの令嬢が手を差し出した。ルドルフもにこやかに答える。
「はい・・・」
優しい声だった。優雅な音楽のナがルナか、女性の視線を一身に浴びながら、ルドルフは美しい女性達と踊る。
胸やわざと男を引くようなき方をしている。地位や名誉、財産を求めて。
皇太子という看板を求めて。
胸は痛まない。自分も同じように彼女達を利用しているのだから。
帝国のミライ、それがルドルフの存在する意味だ。その意味を側にいるアリスは理解していた。
「・・・・・でも、貴方と殿下は」
「ローゼンバルツァー家は代々、軍人の家で帝国の政治にも関わってきた家柄だ。母は反対してたけどね、僕が父に銃を習うことを、けれど、一度、狩場で殿下のお姿を見て以来、一人で国民のミライを背負う小さな背中を見て、僕は・・・・」
美しい。その横顔は女神のように美しい。
大人しく、おしとやかで気弱な少女。ヴォルフリートとの付き合いの中、性格が変わったとアリスは思っていた。
仲のいい二人を複雑な思いを抱いていた。
「本気なのね・・・では、エドガーは」
「利用したんだよ、彼の思いを。今回の事件のことも利用してね。・・・僕はやっぱり呪われたローゼンバルツァーの人間だ。自分が自分で恐ろしい・・・・・あんな、皆、恐ろしい死に方したのに」
エルフリーデは拳をギュっと握る。
「・・・・そんな事ない、・・・・私だって」
「・・・・・僕は言う資格はない。でもアリス、頼むからアンネローゼを恨むのは止めてくれ、彼女は許されないことをした・・・でも、僕の双子の妹なんだ」
切なげな目がアリスに向けられる。
「・・・・無理よ、だって、彼女はあんな・・・・・、それに私の前でヴォルフリートを・・・、いくら、嫌っていたからってあんな・・・」
「アリス・・・・」
何かを考えた後、エルフリーデが口を開く。
「それは違うよ、アリス」
「え?」
もう一度、シーツを握る。
「・・・・ヴォルフリートとアンネローゼは君が思うような憎悪の関係じゃない。僕と君の家が険悪でも」
エレオノールやブリジット、両家は会うたびに争い、喧嘩し、刀傷沙汰で上から注意されていた。
「会うたびに罵声を浴びせあって、殴ったり、けったり、骨を折ったって・・・私は見てきたわ。お母さんたちだってあの二人を合わせるのを避けていたわ、犬猿の中だって。首を絞めた事だってあるじゃない」
エレオノールの悲鳴をアリスは忘れたことがない。
イギリスの宰相が令嬢たちから解放されたルドルフに声をかけてきた。
「いつ見ても華やかでうらやましい限りですな」
「そうでもありませんよ」
「いやいや、我がイギリスもここ最近落ち着いたとはいえ、民衆の反乱や不況、女王陛下に媚びる人間もいるので、気疲れが多くて」
「ですが、イギリスは私には恵まれているように思えますが」
「外では無敵の艦隊を持つ王国といわれていますが、・・・まぁ、殿下の帝国の抱える問題に比べれば、私の言葉など気休め程度ですが。フランツ陛下は多くの民を持たれているから」
「ルドルフ様、どうか、お近づきになりたい一新で数々の無礼を働いたこと、お許し下さい」
「どうか、ヴィクトリア様ご同様の語慈悲を私にもおあたえくださいませ」
「決して、ルドルフ様を退屈させませんわ」
「・・・・」
ローザリンデが恋人のために近づいている事は、エルフリーデも知っていた。親衛隊の中マトと共に宮殿の中で、街中で密やかに行われているのを目撃していた。
「―付き合っているんだよ、ヴォルフリートとアンネローゼは」
エルフリーデは口を開いた。アリスの目が大きく開く。かなり驚いているようだ。
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・え?」
僅かに口元がゆがむ。
混乱して、微妙な表情になっている。
「まさか、・・・ヴォルフリートは年頃で女の事も付き合いがあるのは知ってるけど。ありえないわ、だって、ヴォルフリートが好きなのは可愛い女の子で、エルフリーデとアンネローゼは美人じゃない」
「猫の足音を追いかける会、科学部、青い薔薇、このキーワードで思い当たる節はないかい?ヴォルフリートは時々文通しているのは知ってるだろ」
思い当たる節が合ったらしい。
「・・・でも、そんな、・・・恐ろしい人を・・・・」
声が震えている。
「ヴォルフリートが私に内緒を造るわけがない。だって、ヴォルフリートは私が好きだもの。聞いたこともないわ」
「まさか、私を嵌めたのですか、ルドルフ様!!」
「ローザリンデ嬢、私かその男か、お決めになったのは貴方だ」
「卑怯者!!」
「この道しかなかったわ!!」
部屋に戻ると、たくさんのクリスマスプレゼントがおかれていた。ルドルフの好みではなく、気を引く為に、自分の得のために誰か知らないものが。
異能者を守るのは、皇帝陛下の父は認めない。優先順位は帝国市民と帝国のミライだ。様々な民族を一つにまとめ、歴史と文化を守る。羽の飾りがついたコートはスロヴァキア人の血がついた。自分が、殺した相手の。
ふと、忘れられたらしい白い包装紙に地味な緑色のリボンのはこが目に入った。たくさんのプレゼントの中でそれだけが雑な扱いをされていた。
女官だろうか、苛立ちが駆け巡る。何気なく、それを床から拾い上げると、レオンハルトのいえのものからだった。差出人の名前は。
「殿下、ヴァレリー様がルドルフ様にお話しが」
ノックをして、女官が入ってきた。ルドルフは女官を突き飛ばし、ぎゅっと箱を抱えこみながら、コートを脱ぐことなく、艶やかな髪を揺らしながら、走り去っていった。
「殿下?」
4
雨が降っていた。
厳重に警備された塔の中では、冷たい兵士の視線や銃、濡れた草の匂い、湿った匂いが混ざっていた。ピンクや白を基調に、柔らかな色彩で彩られた部屋の中には、銀縁のタンスや触台が置かれた小物入れ、人形が置かれた漆黒の小さいサイズの家具があり、反対方向には、イスや写真、本棚とものを書く為の机が並べられていた。中央には巨大なベビー用を思わせる天蓋、その上には星やら天使が釣り下がっている。
「ブレーズ、ホラホラ、この青いリボンのドレス、どうかしら?お父様は気に入ってくれるかしら」
キャミソール姿のアンネローゼは楽しそうにドレスを広げていた。執事はドレッサーのかわりをさせられている。
「・・・・さぁ、あのお方は年に数回しか会わないので」
「もう、頼りないわね」
珍しく、子供じみた表情をしている。原因はわかっている。あの異能者の子供だ。
「・・・どこをそんなに置きに召したのです、オッドアイの少年を」
「嫉妬?気にしなくても、あんなの、ただのお人形の一つよ」
幼い少女にふさわしくない酷く大人びた女の表情で怪しく笑いながら、指先を舐めながらそういった。
・・・・・重い。そう思いながら重箱のような厚さの本を顔から外して、近づいてくる足音に耳を済ませた。王宮の図書館は静まり返って、薄暗い。
司祭様の言葉を聴くか、・・・今日は冷えるし、墓参りは止めるか。
・・・アンネローゼ。
目を開けると、華美なつくりの儀式用の礼服を着たルドルフが立っていた。肩を揺らし、白い息を吐いて、表情が引き締まっていた。駆けつけてきたようだ、まるで。
何を怒っているんだ、この人。
「・・・おそようでございますね」
まだ、意識がぼんやりする。頭をこきこきと整えながら、ヴォルフリートは立ち上がった。そういえば、服が乱れて、襟元もゆるいままだ。ボタンも外れている。
・・・恥ずかしい。
「すみません、こんな格好で、すみませんが少しお待ちしていただき・・・」
妙な視線に気付いた。
「・・・・・・・何か?」
何と言うか、女の子の恥ずかしい格好で胸やスカートが見えない男のそれのような。
考えて、血の気が引いた気がした。
「・・・相変わらず美しいと思って、・・・可愛い」
・・・嘗め尽くされてみるなら、美形や女性の領域だろう。細まっちょで青年らしくない少年を感じさせる体型だと踊り子に言われたことはあるが。しかし、視点を変えると嫌味な体型だな、顔まで気持ち悪いくらいすばらしく美しいとか。
誰だよ、こんな人外作ったのは・・・・皇帝陛下と皇妃様か。
「・・・ほめていただいて、嬉しいんですが、自分、男ですよ」
「・・いや、お前は綺麗だ」
「いやいや、筋肉ありますよ、・・・・体毛は薄いですが。殿下は自分に余計な幻想を抱いているみたいですが」
「性別を超えた魅力がお前にはあるぞ、ヴォルフリート」
・・・・・・・・・・どういう意味だ、こら。
「魅力って・・・」
手首を捕まれ、本棚に背中を預けられた。
「って、いきなり、何を」
2人の頭が重なった。硬い、優美で程よく洗練されたからだがこすりついてきた。
ヴォルフリートは目を見開かせた。
「こら、其れをこすりつけるな!!ここ、公共、公共!!」
「・・・シリアスがにあわない男だな、お前」
ポケットから小さいこづづみを出して、ルドルフがヴォルフリートに渡す。
「これは?」
「お前の誕生日だろう」
イヴは昨日なんですが・・・。感情に流されるな、交渉、交渉。ビジネスパートナー、それに愛人(出来ればなりたくないが)が加わっただけじゃないか。異能者のため、異能者の。
「ありがとうございます・・・殿下、何かありましたか?顔が少し青いのですが」
自然に額に手を当てた。自分の額と比べる。
「熱はないようですね」
「馬鹿が!!」
「は?いきなり、何を」
「私を子ども扱いするな!!」
「してないですよ」
「・・・・殿下?」
「心が荒れている、だから、私を慰めろ、お前ならばできるはずだ」
迫られたらしい。ヒロインみたいな表情をするな。なるほど、こういうのに皆だまされるんだな。
「慰めなさい」
嫌な信頼だな。
マナーや乗馬、一般教養。貴族の子息として徹底的に教育されているヴォルフリートはルドルフとも宮殿とも関係なく、家庭教師に銃や剣の訓練をしていた。もうすぐ12歳となる。近頃、夢遊病で医者にかかっていた。
「神経症の類ですね」
屋敷に招かれたかかりつけの医者は笑顔でそういった。
「・・・それで頭痛や痺れが。でも、先生、何故寝てるのに包帯を巻くような怪我を。それにメイドのマーサは何故、僕にあんな・・・」
「仕事のしすぎでしょう、彼女はプライベートで金銭的な問題を抱えていたようですからな」
「令嬢のツェツぃーリアの家に姉さんと父さんだけが・・・いいな、ご馳走が食べれて」
あーあと子供らしい声を出す。
「・・・近頃、お姉様との時間が減って寂しいのですね」
「はい・・・」
しゅん、とうなだれる。
「環境の変化で神経が参っているのでしょう。ヴォルフリート様。貴方が宜しかったら私の知り合いの病院で見てもらえますが」
「いや、そこまでは・・・」
「そうですか・・・」
医者はなぜか複雑な表情を浮かべた。
「?」
おかしいといえば、今日の一日だ。いつもどおり、家庭教師と勉強をして、母親の買い物につき合わされて。病気のせいで一緒に行けるはずだった舞踏会にいけなくて。
午前中は、二コルとチョコレート店の前で呼び止められて知らない女の子に叩かれて。昼前には、ヘンリーと呼ばれて、泥棒扱いされて、危うく刑事に捕まりそうになった。泉の前では、褐色の肌の少年にアルバートと乱暴な挨拶をされて、一方的に切れられた。
午後は人間違いはないものの、12歳の誕生日にやるという儀式の為に司祭やら著名人やら偉い立場であろう紳士や淑女の前に見世物のように扱われ、着せ替え人形とされた。3時には、ボランティア組織だと目に赤い化粧と紫のアイシャドーがついた琥珀色の瞳の白い、金の刺繍が施された服を見る巫女の北欧を思わせる優しい品のある高貴な少女となぜか2人きりにされ、自分は次世代の女神を生み出す器だと手を何回も触られた。
・・・・・大貴族で凄い金持ちで様々な国と貿易をしている大一族だとお母さんからは聞いているが、何かが変だ。
自分をかつて苛めた貴族の兄妹、カールやエリザベート、優しくしてくれるロッテもシャノンもローゼンバルツァーは特別待遇だといっていた。軍人でものすごい古い血筋と聞いているが変だ。
はっきりとはいえないが。人間の敵を狩る処刑人。ハプスブルクを守る帝国の盾。
・・・・何故、僕やアンネローゼはこの家に迎えられているのだろう。
「・・・・・」
駄目だ、考えるな。その先は考えてはいけない。
5
彼女と会えるのは、彼女が外に出ることを許される狩りの水曜日と医者が来る土曜日だった。どういうわけか、いがみ合う両親とブリジット夫妻の間では、自分や姉の扱いは妙だった。ブリジットと母は自分を息子や甥だけの理由なのか、会うと、取り合いをしてた。エルフリーデとアンネローゼの父は姉を父のレオンハルトと直接的ではないものの、取り合っていた。
父はどんな時も姉を自分の側に置きたがった。二人きりで遊んでいると、時折、怖い目で見られる時もあった。
「また、見てるよ」
「そう?」
おおらかなアリスはまるで気付いていない。
父に理由を聞くと、頭を撫でられ、優しく笑われた。
「父親は娘が可愛くて仕方のない生き物なんだよ」
「・・・」
まただ、また、何か、ごまかされたような気がする。のどの中がザラリトする。
「・・・飲み物、持ってきます、お父様」
「ああ、イっておいで」
僕も父親というものを触れたこともない。けれど、いい父親だと思う。僕らを外に置いたのもきっと家の事情で。
空気は冷え切っていた。背中に伝わるベッドの感触も硬く、湿っていた。
ルドルフの異能者の力は、自分のものとまるで異質なものだ。ブラックホールのような、全てを飲み込む為の。すべてのものをひれ伏す為の王の力だ。系統としては、エモノとなった人間を切り裂くアンネローゼのものと似ているだろう。
何が起きたのか、わからなかった。
指一つ動かさず、ただルドルフは階段のしたの異能者同士の殺し合いを見ていた。冷たい氷のような目で。支配者には冷酷さも必要だろう。
「おおお・・・」
崇拝者の男の目が合った。さっきまで敵だった男の目がルドルフと言う少年の崇拝者の目に。異能者はこの世にいてはいけない悪魔の祝福を受けたものなのに。
背筋が凍りついた。
・・・・美しい。
破壊的に美しいと思った。人間とは違う、支配者の美しさだった。天使というよりは悪魔的な美しさだった。
・・・勝てるのか、自分は。殺し合いに、この競争に。
柱の影でヘンリーは体の震えを抑えていた。相手は自分よりも年下の子供だというのに。
薄暗い部屋の中で温かいそれに身を預けながら、ヘンリーはぎらついた目をどこか不安げに揺らしていた。
・・・アンネローゼ。
輝くような、笑顔。
・・・アンネローゼ。
漆黒の揺れる髪。
俺様がお前の居場所を作る。あいつらからも解放するから。
だから。
・・・待っていろ、すぐに行く。助けに行くから。
「わかりました、坊ちゃま、すぐに飲み物をお持ちします」
「ああ、頼むよ」
メイドに内容を伝えると、機械的に対応される。視線は相変わらず厳しいが少なくともこの家の子息や令嬢としては扱うことにしたようだ。最も、自分についてはまだ疑いがあるようだ。
「坊ちゃま」
振り返ると、ナースメイドの三人組が悪戯を思いついた猫のような表情で立っていた。
「お忙しいと思うのですが、数分だけ、私どもと会話してくれませんか?」
「―-」
記憶の一部があやふやだった。
・・・甘いもの、食べたいな。ぺろりと口元を整えた。
「転職するかな」
いつもハードだが、前よりもハードすぎるな。
「・・・ま、仕事は終わったから言いか」
深夜に宮殿付きの護衛とヨハンはヴォルフリートとであった。
「クリスマスにまで巡回の仕事か、お前の部隊もこき使われるな」
「人手不足ナモノで」
襟元がゆるくなったままだ。ヴォルフリートは襟元を調えて、息をついた。頭には羽根布団に使う羽がついていた。
「ここで働く時は服装を整えろといつも言ってるだろ」
「すみません」
ヨハンはヴォルフリートの軍服を調えた。
「・・・お前、まさか抜け出して、女と会ってたんじゃないか」
「まさか、そんな暇などありませんよ、こんな忙しい時に」
「頭の其れは」
「・・えっ、あっ、すみません」
遠くの方で呼ぶ声が聞こえた。
「それじゃ、失礼します」
「ああ・・」
狭い部屋の中でヴォルフリートは意識を取り戻した。
「それでは、坊ちゃま、私どもはこれで仕事に戻りますので」
「失礼します」
リボンは首からゆっくり垂れ下がっていた。柔らかい素材の白いシャツは貴族の子息らしくひらひらしていて、茶色のズボンは濡れていた。日に焼けた肩にはアイロンでつけたような小船方の焼いたあとがあった。擦り傷や切り傷もあった。押さえている腹は叩き疲れた後があった。
お湯をかけられた頭はぐっしょりしていた。
「・・・・」
「・・・・」
ヴォルフリートは嵐が過ぎたことに気付かず、数分間自身を失っていた。
扉が閉じた時、カチッと音が頭の中で鳴り響いた。
「え?あれ?」
周囲を見渡すと、来た事のない衣類をしまう小部屋の中のようだ。アイロンや洗濯物を干す為の紐が地面に散らばっていた。
「・・・・ええと、何だ、ここ」
頭が少し痛む。格好を見ると、苛められた後のようだ。
だが、誰に?
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
あれ?
「覚えてないや」
ぞぉぉとなった。
「ヤダ、気持ち悪い・・・部屋にかえろ」
身体を起こし、肩を抑えながら、ヴォルフリートはその場を立ち去った。
「・・・え?」
「ヴィクトリアさん」
「ヴィクトリアでいいわ」
ヴィクトリアは真っ直ぐにアリスを見ていた。
「今、なんて」
「貴方の弟は、家族に暴力を受けているといったのよ」
「・・・何を言っているの?」
ルドルフはヨハネス公にお願いをした。
「・・・・・どうか、アーディアディトやヴォルフリートに危険なことは」
杖を持った老人は威厳と気品のアル笑顔をイスに座りながら、ルドルフに向ける。
「なるべくは私も苦労してきた孫に銃は持たせたくはないですが、一族のものはペンより剣を、力を重要視するものが多いですから。当主とはいえ、私には一族のもの全てを押さえつける力はないのですよ」
「・・・・」
信じていいのだろうか。
ルドルフは複雑な表情になった。
「彼らも我が一族の血を持つものですから、いずれ己が何をすべきか、理解すると思いますが」
「・・・そうですか」
廊下で皇帝である父とエリザベートに出会った。
「ルドルフ、元気そうね」
「陛下、この件は」
「ウム、任す。ルドルフ、失礼するぞ」
「じゃあね、ルドルフ」
「はい・・・」
ローゼンバルツァーの存在は父の中でどうなっているんだろうか。だが、確認することはなぜか戸惑いがあった。
「・・・・」
「・・・ブランが死んだ」
「いや、あいつに殺されたんだ、エレク」
「皇太子ルドルフに」
6
ブリジットが買い物の最中に見かけたダークブラウンの髪の少年は間違いなく、ヴォルフリートだった。
ヴォルフリートはスラヴ人とクロアチア人、るてにア人の少年少女とオセロで遊んでいた。メイドや使用人は不安そうに、アリスも戸惑ったようにヴォルフリートを見ていた。
「もう、買い物寸断だから、帰ろうよ」
「もうちょっと」
母国語のドイツ語の発音は前よりも綺麗となり、自分のものとなり、方言は少なくなっている。クロアチア人の少女は、セルビア語に似た言葉を喋っている。
その首元にはカトリック系の十字架が下がっている。奇妙なのは周りのクロアチア人やセルビア人の大人たちである。
クロアチア人と話すのはいい。だが、純粋なオーストリア人であるブリジットは部下を連れながら、不安を感じた。オーストリア・ハンガリーに銃帝国の国民なら、セルビア人と積極的に近づかないはずである。
ハンガリー人の商人や職人は無視を見るような目で、ヴォルフリートを見ていた。
「君、止めなさい」
結城アル中年のハンガリー人の富裕層の男がヴォルフリートの肩をつかんだ。
「はい?」
のんびりとした表情だった。恐らくは庶民育ちでのんびりとした環境の静だろう。人種にこだわらず、また、浅はかな考えを持つ彼には、目の前の大人の複雑な感情はわからない。
スラヴ人の大人が、恐らくは子供同士の遊びに大人がつっこむなと注意を促すようにハンガリー人の男の前に出る。
「・・・お前は関係ない。大人が子供同士のじゃれあいに口を出す気か」
「何だ、貴様、私に逆らう気か」
「その杖をこの少年から離せ。お前にこの少年を罰する権利はない」
ヴォルフリートは立ち上がり、大人たちが喧嘩しそうな気配に気付き、とめようとした。
「あの、喧嘩は止めて下さい」
スラヴ人の男はヴォルフリートをかばうように、ハンガリー人の前に出る。
「暴力に訴える気か」
ブリジットが前を出るよりサキに、アリスが前に出る。
「喧嘩は駄目!!」
アリスはリビングでため息をついた。フィネは不思議そうに、姉の横顔を見ている。
前から行動を深く考えずに、誰にでも懐くというか、ある意味ではその行動が裏ましイが、弟の軽はずみな言動や行動は、自分の起こす問題異常に複雑さを本人の無意識で生んでいるのだから頭が痛い。
「はぁ・・・・」
「お母さんに怒られたの?」
「いや・・まぁ」
はぁ、とヴォルフリートはため息をついた。
「通りがかりの子がカタコトで暇つぶしに付き合ってくれるかと聞いたら、いいと答えたから暇つぶししただけなのに。言葉はドイツ語だからいいじゃないかよ」
すねた。
「でも、中には変な人や怖い人もいるかもしれないし、お母さんも心配になると思うよ」
「でも・・・」
「強情なんだから」
アリスは仕方ないな、と声を出した。
「姉さんはどうなの?」
「え?」
「言葉や姿が違うだけで、遊んではいけないと思うの?同じニンゲンで同じ子供だよ」
意味のない言葉だろう。
「私は、私だって、本当は仲良くしてみたいと思うわ。でも、・・・私には難しいわ、言葉無難しいし、ヴォルフリートはあの子達の言葉、わかってたの?笑って、話してたけど」
自分と違う文化を持ち、言葉を持つ。当たり前のことだが、アリスには苦手意識がある。だが、弟は?
村に住んでいた時だって、自分と同じように、クロアチア人やセルビア人の他国の人間を見てきたはずだ。見知らぬ人間が怖くないのだろうか?
ヴォルフリートも目や動作でむらの中の子供にいじめられたことがある。
「近づいて、怖くないの?」
教育を受けておらず、畑仕事やにもつ運び、基本的な言語しか習っていない環境だった。
「・・・・怖い?」
「言葉はわかってたの?」
「ううん。でも、手の仕種とか表情で何となくわかったかな、相手に敵意はなかったから大丈夫かと思って」
「ヴォルフリート・・・」
「・・・ア、ごめんなさい、姉さん」
© Rakuten Group, Inc.