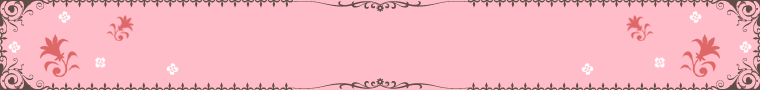第22章ゴールデン・ローズ
ギルバートとアリスは信じられない光景を見た。ヨハネスにヴォルフリートが膝まづいていた。
「お願いです・・・、ヴィクトリア嬢の結婚、あなたの力で何とか・・・」
声も揺れていた。
「ならぬ・・・」
「僕は結婚など、気持ちのない結婚など・・・」
「諦めろ、所詮お前が思う相手は、お前とは結ばれぬ相手だ」
「お願いです・・」
布をギュっ、と掴む。
・・・・そこまで、ヴォルフリートはアンネローゼのことを。
アリスの胸がざわついた。
「扉を締めますよ」
メイドがそういって、固い扉を閉じた。
アポロ・ホールで豪華なダンスパーティーが行われる中、ルドルフの眼前では帝国主義と自由主義、民主主義を歌う若者や学生、洗濯女の姿があった。
パレードのようだ。
「皇太子様が陛下に提言したそうだ」
「今回は都市計画の改装か」
「殿下は新しいものが好きだからな」
閣議のあと、口々に細やかに大臣たちは言った。
「プロイセンやロシアでの問題が大事になっている現状で」
「殿下はこの国の現実が何もわかっていない」
リヒャルトやヨハネス、ディーターの父の姿もあった。
「どうかされまして?新聞やさん?」
花の匂いを漂わせて、踊り子達が胸を見せるような薄い衣装で美形のルドルフに近づいてくる。
「知っています?最近、自由主義者が掲げる新聞が出回っていることを」
「へえ、そうなんですか」
理解者ではない、と美しくなったヴォルフリートは言った。子供の頃は野暮ったいというか目立たない方だったのに、今では女達が彼を見ると食いついてくる。
「ヴォルフリート」
「すみません、殿下、リヒャルト様とヴィヴァリー夫人とのお茶会に誘われていまして」
旧市街で富豪の館が襲撃された、と仕事もあるといって去って言った。恐らくは彼は何故だ、と思っているのだろう。最近理解してきたが、ヴォルフリートは美形コンプレックスのようだ。綺麗な美術品のようだ、といっていたがその裏には強烈な劣等感があるようだ。
宿泊上の中に、13歳のギルバートは管理されていないピアノを見つけた。周りにはオルガンやバイオリンが合った。兵士たちの精神の急速の意味もあるのだろう。士官たちの話では、以外にもこの音楽室を使うものはほとんどいないのだという。記憶の中の父は音楽や自由な考えが好きだった。
愛、平等、自由。人は信頼しあうもの。
光り輝くものを教えてくれた。僕は自分が貧しいなんてちっとも思わなかった。パンの匂いや草花の匂いや笑い声。友達と遊んで、勉強をして、喧嘩をして。あそこでは自分の肌の色も髪の色も、母がジプシー出身だということも何も重要ではなかった。安らかで穏やかな、涼しい生活。水車の音や匂いやロバ。穏やかな時間。
ポロンと鍵盤を振るう。
「すまない、少年、邪魔するぞ」
振り向くと、外交官らしい背の高い黒髪のドイツ人の青年がいた。後ろには上司らしい男がいた。
「大尉か、上の仕官や左官、将官はいるか」
「はっ、い、いえ、ええと、すぐに探してきます」
かぁぁ、と頬を赤くして、ギルバートは、楽譜を散らばせて、慌てて、軍人のハルトヴィ火の元から駆け出す。急に自分の姿を思い出したのだ。
「ああ、すまない。驚かせたか、・・・君、もしかして、ジプシーか?ここにいると言う事は貴族のせがれなんだろうが」
「いけませんか」
「いや・・・」
その時、仕官が通りかかった。
3
恥ずかしい、格好悪いと思われただろう。軍の学校に行けば姿形で戸惑うこともないだろうに、双思ったのに。ここも家の中と同じか。父はあからさまに自分を家の中から追い出しガっていたけど。
時間は、球技の時間となっていた。その次は砲術や戦術、歩行訓練だ。
「大丈夫かい、ギルバート」
大人しい同じ部屋のフランツが心配そうに自分を見ていた。
「大丈夫だよ」
「そう、今日は、尾に教官が担当する反と戦うんだって、イヤだなぁ。ギルバートはスポーツや格闘技が得意だからいいけど」
「はは、でも座学では君はトップだろう」
その時、同じ反の意地悪三人組が声をかけてきた。
「よう、ギルバート、今日も元気そうだな。侯爵様の三男貌さ魔でもこんな子供じみた授業にはでるんだな」
手下らしい少年がにやにやと笑っている。
「サボると、先生が厳しいからね。それに僕は任された仕事や作業はちゃんと受ける主義なんだ」
「さすがは入学式で子爵や完了の子息の先輩に決闘を申し込んだだけはアル。でも、君の正義感はここでは通用しないこともおぼえたほうがいいけど」
「くだらない価値観に囚われたニンゲンに僕の友人を貶めることを受け入れるくらいなら、僕はいつでも決闘を申し込むよ」
「なっ」
「お前、朴達を誰だと思って、妾のこのクセに」
「よせよ」
「!?」
珍しい。いつもはしつこく迫るというのに。
「せいぜい、いい子を演じるんだな。だが、お前のカードを見てみろよ。そんな事、いってられなくなるぜ」
「?」
メヌエットを踊りながら、結婚式は昼下がりに行われた、男女が一緒になって集団で踊るダンスだった。
「っちえ、アリスの奴、あんな仮面のどこがいいんだか」
アレクシスは参加者の中で一番豪華な素材で作られた服を着ていた。周囲は祝福の日を心から喜んでいた。グライン一対で行われた結婚式は密やかに、友人と親戚だけで行われた。岩屋まで川が挟まれ、高波、渦巻、酒巻と呼ばれ恐れられる三つの岩があり、川床には花巌石の岩石がごろごろとしていた。
「川で洗礼があったようだ、アレクシス」
ヴィルフリートが結婚式の警護に当たっていた。
「バケツ一杯をかぶる洗礼式だそうだ、非効率な行為だ」
「40キロ下ると、ヴァッハウだな。お前もいたんだろ、ヴォルフリート」
「ああ、つまらない任務だった」
「ヴァッハウか、ワインのみてぇぇ」
空に向って、アレクシスが叫んだ。
リヒャルトとヨハネスが手を組む光景が視界の隅に入った。
「金持ちはまた金儲けを成功させたようだな」
ヴィルフリートは目を閉じる。
「すまない、一時フランツの所に戻る」
音楽が鳴り響く。花びらの中、アロイストアリスがウインナ・ワルツやレンとラーを踊る。
ヴィクトリアとペアを組むヴォルフリートを微笑ましい気持ちで会場の隅で眺めていた。リヒャルトが戻ってくる。
「・・・お前の友はなかなか、使える奴だな」
ギルバートは顔を上げた。
「え・・・」
ヴィクトリアは恥ずかしそうに、得意なはずのウインナ・ワルツも動きにくい気持ちがあるのか、なかなか体を密着しようとしなかった。優しげに穏やかに、清らかな瞳や声、宝物のように優しく触れてくる手、女性の扱いに慣れた動作を見せ、優しくリードするヴォルフリートは反対に落ち着いている。
その光景をローザリンデはギルバートを待ちながら複雑な気持ちで見ていた。
「それなら、私が相手してあげましょうか?」
「ヴォルフリート、冗談でしょう」
「どう思います?」
「退散、これまでのようですね」
・・・・危険な人だわ、あの人は。
足腰が立たない。
ガタガタと震えながら、フランツに方を支えられながら、ベルクウェインとディーターの背中を見た。
「相手にもならなかったな」
「やっぱり、生まれが粗野だからな。思考も対決方法も見えやすい」
「・・・・」
ギルバートは愕然となった。冷たい同級生や先輩の視線が突き刺さる。
「どいてよ、ボール拾い」
ディーターがすぐ側のそばかすの少年を突き飛ばした。あははは、と残酷に笑う。
「劣等生が独りいると、この俺たちまで同じレベルに見られるから困るぜ」
「だよなぁ」
わざと足をぶつけられ、みんなの前でさらし者にされた。
・・・・アレが、あの反のやり方なのか。砂をぎゅっと掴んだ。
いつか、見返してやる。
「ギルバート・・・」
フランツは心配そうにギルバートを見る。
4
夕暮れ時、アリスは花嫁の役から解放され、休憩室に戻ってきた。入れ替わるようにヴォルフリートが頭を抱えながら、アリスの前を通りかかった。
「ヴォルフリート、どうしたの?」
「少し頭痛が・・・頭もふらふらして・・・」
「まぁ、大丈夫?」
アリスはヴォルフリートに詰め寄った。
「え・・・うん」
「また、無理して・・・・、今日は無理しなくていいといったでしょう」
「・・・・ゴメン、姉さん」
「部屋に戻って」
「はい・・・」
別れた後、甘く切ない琴の様な音がアリスに聞こえてきた。
「どこから・・・」
その音楽は2階から聞こえてくるようだった。ドレスのすそをめくって、アリスは二階に向かい、二階の二番目の部屋に向い、扉を開ける。
愛らしいアーデルハイトが竪琴で音楽を引いていた。月光に照らされ、何とも美しい光景だ。
綺麗・・・・、本物のお姫様だわ、この人。
指先が止まり、音楽が鳴り止む。
「あら・・・」
「あっ、ごめんなさい」
慌てるアリスに、一歩ずれた調子でゆっくりと首を傾けて、不思議そうにアリスを見た後アーデルはハイトは反対方向に首を小さく傾けて、右手を白い頬に添えた。ゆっくりとした動きだ。
「まぁ・・・」
ピンク色の唇から愛らしい声がでた。そして、アーデルハイトはにっこりと笑って、ロシアンブルーを抱き上げて、ドレスのスカートの上に置いた。
「アーディアディトさん、よかったら、わたくしとしばし、ゲームでもしません?お時間、今、開いています?」
「え?ゲームですか?」
「式の当日にはだんな様と初夜を過ごされるのでしょうが、ほんのひと時、駄目ですか?」
「でも・・・」
アーデルハイトはにっこりと笑う。
ゲームの結果、アリスの勝利だった。
「・・・・・あら」
「ごめんなさい」
「いいんですのよ、対等に勝負したんですもの、まあ、面白い手で駒を操りますのね」
アーデルハイトはニコニコと笑っている。メイドはお茶を用意していた。
洗練されているな、一つ一つが輝いている。アーデルハイトの瞳は清らかで何の苦労も哀しみも知らないようだった。
「どうかなされたの?」
「・・・・いえ、アーデルハイト様は綺麗だなって」
「まぁ、今日のアーディアディトさんに比べたら私なんて、まだ未熟者で」
「お見合いや今、付き合っている人はいるんですか?それくらい可愛くきれいだったら」
「それが全然。わたくし、お父様に兄弟の中で一番愛されてるのか、全然とのがたと関わる機会を与えてもらえないんですの」
「そうですか」
「でも・・・」
「?」
カップを持ちながら、アリスが顔を上げる。
「アーディアディト、私、ヴォルフリートが好きですわ。ヴィクトリアさんとの縁談、つぶすのを手伝ってくれません?」
「え?」
空気が変わった。笑顔は優しい、柔らかい。
「宮殿や皇族の狩猟でたまに付き添いを担当されていますよね。あの凛々しい横顔、優しい眼差し、平等な優しさ・・・わたくし、人目で心が奪われてしまいましたの。・・・ヴォルフリートが欲しいですわ、他の女性に誰にも奪われたくありません」
「いきなり、何を」
「・・・貴方は、ご自分の弟様の価値を理解するべきですわ」
彼女は何を言っているんだろう。
「・・・わたくし、家柄や血筋にこだわり、媚を売るだけの美男子が大嫌いなんです。皇太子殿下が一番人気で、皇妃にと思う方が宮殿には多いようですが、わたくしは違う。男に媚びるだけの女になる気はありません。わたくしが夫とするのは平等たる関係、かつわたくしが負けてもいい、この人なら何もかも捧げてもいいという方としか、私は私を与えませんわ」
愛らしい外見からがらりと人が変わったようだ。
ハルトヴィ人であったのは、里帰りして、父に連れられたお茶会の席だった。中には、皇太子の家庭教師、エルザの姿があった。
金色の髪の眩しい少女が食べ物でぐちゃぐちゃに汚れたギルバートに優しく手を差し伸べた。白いヘッドドレスと白いドレスに身を包み、慈愛に溢れた少女に似た母親と使用人を背後に連れて。
「大丈夫?」
「は、はい・・・」
柔らかな日の光に照らされた、優しい笑顔。澄んだ青い、大きな瞳に輝く金色の髪。白い肌は良く手入れがされ、よどみなど少しもない。
ギルバートがそっと手を差し出そうとすると、ローザリンデが父親と共に屋って、貴婦人や紳士、使用人の愛情がこもった視線を浴びながら、颯爽と登場した。すぐ近くには、ローザリンデの親友であるヴィクトリアとその母親の姿がある。
「まあまあどうしたんですの」
スローペースで話すのが彼女の口癖だ。白いリボンと編んだ三つ網をロール上にしてまとめており、その手には彼女が得意な氏が書かれたノートやヴァイオリン専用の楽譜がある。
「ローザリンデ、久し振りね」
「アーディアディト、会いたかったわ」
真っ先にローザリンではアリスに抱きついた。
アリスに渡されたレースのハンカチはまだ、ギルバートの手の中に在る。午後三時にアップルティーを飲む瞬間の或ローザリンでは、アリスから話されると、食べ物を供給している使用人にブルーベリーソースがかかったスコーンを頼んだ。
「今度はどんな詩を書いたの」
「ゲーテの詩を少し変えたものよ」
「ヴィクトリア、貴方は剣術がまた上達したんですって」
「あら、私の特技は武術や剣術だけじゃなくてよ」
ヴィクトリアは優雅な仕種と笑顔で、周りの子息を魅了していた。
「大立ち回りしたそうですね、ヴァルベルぐラオ中尉の令嬢は」
ギルバートははっとなった。
「ハルトヴィヒ・・・さんですよね」
「覚えてくれていたとは光栄だね」
ハルトヴィヒがギルバートの存在に気付いた。
「へえ、君もこのお茶会に参加してたのか、親の付き添いかい?」
「はい」
5
厳しい訓練と周りの差別やいじめに似た環境に身をおきながら、友人との時間を重ねていたギルバートは廊下である日、自分と同じ学年に皇族とつながりのある生徒顔に教官やディーターの近くにいると友人達から聞いた。
「しかも、あの名門中の名門のローゼンバルツァーの嫡男らしいよ」
廊下では、たくさんの研究生が比し決め合っていた。そこへ、教師にほめられているエルネストの優雅な姿が現れた。
「あの人は?」
「彼だよ、ヨハネス・フォン・ローゼンバルツァーのお孫様は」
漆黒のウェーブヘアが風に揺らめく。光の中にエルネストはいた。同級生達も尊敬のまなざしをエルネストに向けていた。
「馬術のテストでトップの成績で、昌ももらったことがあるんだよ、歴史や数学もフランス語も得意だとか」
「まあ、いわゆる優等生って奴だな」
「へぇ・・・」
眩しい目でギルバートはエルネストの横顔を見た。あっという間にエルネストは廊下を全貌の眼差しを受けながら去っていく。
アリスとアロイスは幸せな一夜を過ごした。窓辺に垂れ下がりながら、
・・・・・子供ではないんだな、僕らは。
ヴォルフリートはそう思いながら、月を眺めていた。
脳裏には、図書室での学校での13歳の時の思い出が蘇る。
場所は狭い図書室。
「は、ディーターと同室ですか?」
苗字を呼び合う関係は学校内ではなく、上官以外の生徒は親しくなくても、名前で呼び合うのが自然なこととなっていた。
「そうだ、ディーターは、どのルームメイトにも同室を嫌がられる我が学年の問題児だ。ヴァるべるぐらお、お前の部屋は今お前だけだろう。いいか?」
「僕はいいですけど、彼は?」
「話は通している、伝えた直後は反論していたが、温厚なお前なら融通を図るといったら了承した」
「はぁ・・・」
図書室を訪れたギルバートは、教官と話すヴォルフリートに帰し感のような感覚を覚えた。頭の片隅が傷む。
・・・いてて、いつもの頭痛?
頭痛もちのギルバートは双思った。視線をヴォルフリートを向ける。すると、警戒心を向けるディーター脳で組んだ姿がある。同じ反の生徒もなぜか、地味なその少年に蔑むような、からかうような、悪意に満ちた笑みを向けて、ニヤニヤしていた。
「あの子、いつも同じクラス・・同じ反の子に無視や嫌がらせされているんだって」
「フランツ、いつの間に」
「ディーターやベルクウェインと同じ反で、親同士が関係の或家柄の子らしくて、家も変なトラブルがあるとか、僕と同じように動作も鈍くて、頭の回転が遅くて、標的にされやすいとか」
「班長や教官は助けないのか?」
「それは・・・、この学校は基本的に地位がある貴族には甘いし、ただの承認や金持ちの庶民の子には基本的に放任なんだ。お互い、面倒ごとは関わらないのがルールというか」
「ああ、お前個人の家のトラブルは奴に話すなよ」
「それは勿論」
ざわざわ・・・・
「緊張するな、どうしよう、上級生と合同の馬術の訓練なんて」
「大丈夫だよ、朴達か急性は今日は先輩の乗馬のサポートするだけだろ」
学校と寮に入って、二ヵ月後、多くの教官と訓練生との反に別れて、上級生の馬術試合のサポートをギルバートたちはすることになった。場所は、宮殿の中の馬術の学校と森林公園の中の馬の為の施設だった。
「アルベルト先輩、大丈夫ですよね」
貴公子アルベルトが爽やかで優しげにギルバートたちに微笑む。
「本気の訓練ではないよ、今日は馬術の技術を競い合うだけの練習試合だ」
その時、多くいる訓練生から歓声が上がる。
「見ろよ、ライゼエルフ、カイザーライヒ第12近衛隊、将官を多く輩出する帝国の看板的、英雄の兵団、シュヴェーアトクロイツ連隊、早くから優秀な仕官や左官、将官候補の部下をスカウトしに来たって事か。上につながりのある、すぐ出世コースの貴族様は将官様を見て、いい点数を取ろうとそわそわしているぜ」
「ライル・・・」
出世欲丸出しのライルというクラスメイトの目はぎらついていた。彼もそのうちの一人だ。強いスポンサーがいるらしい。
「見ろよ、ライゼエルフ隊所属の帝国の死神、トップの成績で学校を卒業した先輩、皆が憧れの少佐ノア・ジークハルト・アイヒベルクとエドガー・エドムント・ミーケ・フォンノイブルク男爵、大佐殿だ」
「本当にあの二人、行動を共にしているんだな」
周囲のものも憧れのまなざしを向けている。観衆が嫌いなのか、小柄で華奢な印象のノア大佐は舌打ちしていた。あこがれるものの中には、エドガーやベルクウェインの姿があった。今日は観客なのか、複数の部下は連れていないようだった。
ギルバートの後ろを遅れてきた上級生のアルヴァー先輩とヴォルフリート、ディーターの姿があった。
「あーっ、ノア少佐、もう行っちゃうのか」とアルヴァー。
「お前のせいだぞ、ヴォルフリート」とディーター。
「チッ、愚図が」再び、アルヴァー。
「・・・・でも、でも、先輩が今日着る服を何度も確認させるから」
声が震えている。おびえているようだ。
「あ?先輩の俺様にたてつく気か」
ヴォルフリートが胸ぐらをつかまれた。
「ひいい、すみません」
ギルバートが振り返ると、デジャヴが襲ってきた。
・・・・あ。
「どう思う、お前、この新聞・・・」
結婚式から帰ってきて、偶然ヨハンと出会い、呼び止められた。
部屋の中は貴重な調度品がいくつも置かれていた。
「投稿者はルドルフ様ですね」
「わかるのか」
「ええ、このもったいない今わしとか、わざとらしいくどい表現とか、かつ労働階級の現実を微妙な具合で掴んでいる感じとか、さすがにペンネームをつかっているようですが」
「そうか・・・」
ヨハンがヴォルフリートの横に座った。
「・・・・アイツはこのところ、閣議で意見書を出している。そのせいか、皇帝陛下の機嫌は不安定なものとなっている。息子が意見するなんて思ってもないからな」
「・・・自分にそのようなことを言って、大丈夫ですか?」
「仕事には忠実だからな、お前は。今の話を聞いても、口外はしないだろう」
「・・・殿下はあせっておられると、ヨハン様は思っているということですか?自分は殿下がそれほどペースを崩されて、自分から和を乱し、結果を出さないとは思えませんが」
「・・・老人たちは、皇太子のアイツの立場や感情がわかっていない。帝国が足元から崩れていく過程にあることも。俺は立憲主義や帝国主義は否定しない、わかるか?だが、それにこだわり続ける現状ではないんだ。新しい改革をあせる気持ちを俺やあいつは持つのは自然だというのに」
「―ですが、焦れば結果が出るとは思いません。ヨハン様は一度、肩の力を抜くべきと自分は思います。それに殿下はいつまでも病弱な皇太子ではなく、オーストリアの皇太子です、あの人は強いから心配する必要はありません」
「・・・・お前、あいつのこと」
ヨハンがなぜか驚いたようにヴォルフリートを見ている。
「何です?」
「理解者だと俺は思っていたが、お前もなのか。・・・ヴォルフリート、違うんだな、お前は。お前はあいつの事何一つ理解していない、それでは他の奴らと同じだろう」
「?」
「・・・聞いていいか、何故、ルドルフはお前が最大の理解者と思いこんだ?・・・お前がそう思い込ませたのか?」
「最大の?まさか、殿下の最大の理解者は貴方です、ヨハン様こそ何を言ってるんです?」
あの日の会話を思い出した。
「あ・・・ああ・・・」
「思い当たることがあるのか」
「実は・・」
上級生の練習試合を森の中のコースを使って、アルベルトを補佐しながら、ギルバートは確認することとなった。サポートする動機の訓練生の中でも、上に取り入ろうとするもの、純粋に先輩のサポートするものの姿があり、ギルバートはその校舎の中にいた。アルベルトの白馬のひづめを丁寧に拭き、フランツは餌の草を専用の箱の中に入れていた。
「お似合いの姿だな」
「君のところはあんな色の黒い使用人を使うのか」
「まさか、うちはハンガリー人の色の白い娘だよ、武器商の息子君」
いじめっこ3人組みはせっせと手馴れた様子で優雅に先輩の機嫌を取り、サポートしながら、ギルバートを評した。
「お前ら、いい加減にしろよ、あいつ、将来の侯爵様だろ」
「・・・・ライル、あのリヒャルト侯爵が本気で、あいつを後取りにすると」
「可能性はなくはないだろ」
ふっと、リーダー格の少年が笑う。
「ありえないさ、そんな事」
6
加害者(?)の弁明を聞いて、ヨハンは頭を抱え込んだ。
「おかしいんですよね。あそこであの言葉を聞いたらプライド高く、敵は容赦なく殺してきた殿下だから処分するか、外へ追い出すと自分はふんだんですが」
ヴォルフリートは肝心のシーンはなかったことにした。
「・・・死んだら終わりだろうが。ま、なんだ、結局事にいたったのか」
「・・・・・・・・そこ、聞きますか?」
気付かれた。
「・・・・・だが、大事な部分だ。つまり、アレだ、お前はルドルフを愛してしまった、で、契約したんだろう?」
「それは違います。僕が殿下と関係を結んだのは僕の恋人と僕の同胞の居場所のためです」
違うのか・・・。
「だが、それでルドルフが傷つくと思わないのか?相手はお前に本気だぞ」
「どうなんでしょうね」
「何?」
「友達の時から疑問だったのですが、僕にはどうも崇拝とか恋愛とかの感情を僕に向けるのはポジション的に違うんじゃないのかと思うのですが。僕は姉さんの方が好きだと思っていましたし、殿下の今までの交際の相手を見ても僕と似たタイプはいませんでしたし。一番近い感情でじゃあ、自分が恋愛の意味で見れるかといったら、違うんですよね。特に憎んでもいないし、すきでもないし、苛めたいとか縛りたいとか支配したいとか彼女のように思わないですし。あ、男ということは今重要視してないので誤解しないでくださいね」
「・・・お前が面倒くさい男ということはわかった。それでいつ居場所が作れそうなんだ」
ひーふーみーと数え始めた。
「全体で500・・いや、600人だから五年か、10年ですかね」
「あいつを縛るつもりか?下手したらアイツが陛下に今の立場を奪われる可能性も」
「だから、僕が出世したんですよ、異能の力も使って。僕は皇太子という立場からしたらネックですからね。表向き、殿下の忠臣で殿下を出世の道具にするなり上がり物の方が都合がいいですから、色々と。後は偽装結婚ですかね」
「いきなり、大事だな」
ギルバートは変色した緑色の日記を多くの上客の中で囲まれながら読んでいた。皇太子ルドルフがエリザベートから送られたもので、ヴォルフリートに渡した赤い日記とは違うものだ。
ザバァァ・・・ン。
そういえば、初めて、オーストリアに渡ったときもこんな船の中だったか。白いゴスロリをきたアンジェラはきゃっきゃっと弾んでいた。近くには人形を彫る黒髪の少年が頬に傷を追いながら、機嫌よさそうに鼻歌を歌っていた。
思考は、過去へと13歳の時に戻る。
尊敬の眼差しをアルベルトに向けながら、アルベルトの洗練された馬術を見惚れながら、次の先輩の為の馬をギルバートは連れてくる。
「じゃあ、僕、次のオイゲン先輩、次の担当の先輩の所に行くから」
瞬時の対応も勉強のうちらしい。或程度の社交性は軍人といっても、求められるらしい。バトンタッチ制の授業では、班ごとではなく、動機だけで2人一組で一人の先輩と馬に当たる。
「ああ」
上流階級の少数の観客は訓練生に興味はなかった。将官や左官、尉官などは訓練生を値踏みしていた。ライルが戻ってきた。
「次の相手、尾に教官の所のあの劣等生らしいぜ。ちゃんと面倒見てやれよ」
「え・・」
「ほら」
振り返ると、次の次にもうベルクウェインのアトにヴォルフリートの姿があった。穏やかで優しげな、弱々しい緊張した顔をしていた。
―被告リヒャルトを殺人未遂、婦人に起こる暴行容疑でただいまより抗議を行う。
被害者のリヒャルトからは顔から血の気が引いていた。
「な・・っ」
―被害者はユリア・バズール、ホーフブルク付きの女官であり、医者。本人は亡くなっているため、彼女の親族が受けるものとする。
「ギルバート、これはどういうことだ、私はアイツに地位や家を奪われた被害者だぞ!!」
「・・・・」
「何故、答えない」
かつてのような生命力に満ちた優しい光はギルバートの目にはない。妻の写真をギルバートは握り締めていた。
「・・・もう誰もいないんです、アーデルハイトもローザもディーターもベルクウェインもエドガーも・・・。皆、死んでしまった」
「私は女を辱めていない!!私は言い寄られただけだ!」
「被告、法廷を辱めるような発言はおやめ下さい」
「・・・・」
「それでは、続けます」
リヒャルトは振り返る。
「私はニンゲンのためにあの化け物を殺そうとしただけなのに・・・こんな・・」
劣等性は、ヴォルフリート・フォン・ヴァルベルぐラオ。レオンハルト中尉のご子息で、軍人と貴族の家柄らしいが、姿はオッドアイのメイ外は背が低く、体も細い、可愛らしい少年だった。
「うわわわっ」
「草が」
「いててっ」
「水が」
「革が」
「きつく閉めすぎたっ」
遠くから見ると地味で普通の少年だが、近くに見ると可愛い顔をしているが動作が鈍い。これでよく、軍の学校に入れたものだ。同じような境遇だとフランツは行った。
「ちっ、愚図や牢が、次の順番が控えているんだから早くしろよ。てめえの静で、将官殿にマイナスの評価を貰ったら、お前のせいだからな」
「まあまあ」
なだめつつも、笑えるレベルなのかとギルバートは悩んだ。
セットしながら、ヴォルフリートをサポートしつつ、先輩をなだめながら、ギルバートは素早く馬の腰や首に専用の皮や紐をセッティングしていく。
「ごめんなさい・・・」
弱々しい声で、肩もしょげている。
「・・大丈夫だよ」
僕がサポートしてあげないとナ、同じ訓練生だし。能力の差は誰でもある。
「ふん、庶民上がりにしては欲やるな、乗ってやるよ」
「はい!」
ギルバートは元気よく答える。あまりの元気に上級生はずり落ちる。
「・・・・調子が合わない奴だな、行くぞ、もう」
「はい!」
その時、視界の隅でフランツが控えようの馬に上級生達に乗せられていた。
フランツは馬に乗れない。ギルバートは慌ててフランツの方に向き、駆け出そうとしたその時、多くいる観衆にぶつかり、いじめっ子が馬の腹を殴った。
「ひひぃぃん・・・!!」
「やぁ?な、何?」
馬が前足を大きく上げて、逆コースへと走り出す。
「やばい、あっちは前の上級生達がゴールへと戻っていく、逆のコースだ!!」
「何!?」
ギルバートが声を上げ、驚く。
フランツ!!
7
ルドルフの従兄弟にあたるフランツは、寝るのが趣味(だと思う)で、王宮の図書館に入ることが許されている、イギリスに行ったルドルフに取り残された、尊敬するルドルフの寵愛を受ける親友というヴォルフリートとの接触を試みようとしていた。
「・・・・本当に僕が話しかけるの?」
「私が起こしたら可哀想じゃない」
憧れのルドルフは、自分で行動し、世界に自分の意思を反映させている。いかに皇帝にふさわしい人間になろうと、努力を怠らず、輝く姿にフランツは尊敬を抱く。同時に、美しいエリザベートには憧れの女性のような感情があった。ヨハンとは親戚であり、おしゃべりな兄のような印象で、ルドルフの崇拝者達へは苦手意識もあった。ルドルフは才能や実力があるものが好きだ。選ばれた人間しか、ルドルフの側に置かれない。
「ヴォルフリート」
身体をゆすると、額の髪が揺れて、鞭で打たれたような傷跡があった。幼い頃にルドルフにつけられた傷だという。手には、バンソウコや切り傷がいくつかあり、銃を握ることで出来るたこのようなものがあった。
ルドルフ兄様のような綺麗な手ではない。フランツはヴァレリーを通して、かかわったことはあるが、この青年と親しいわけではない。アリスのように優しく勇敢で人を包む手ではない、美しくだれもが惹かれるそういう派手さはない。
「ヴォルフリート、おきて」
「・・・んっ?・・・え、うわわわっ」
素っ頓狂な声を上げて、軍人とは思えぬドンくささでイスから転げ落ちて、床に崩れ落ちた。子供のような表情を浮かべた。
「大丈夫?ヴォルフリート」
頬がかすかに上気している。・・・顔は割りに整っているんだけど、崇拝者のエリアスに比べると、どうも種類が違う。調子が狂う人だ。
「ヴァレリー様?フラン様?」
戸惑った声だけ聞いていると、ルドルフ兄様より年上とはとても思えない。
「本、床に落としましたよ」
「すみません・・・」
かぁぁと頬を赤らめた。
馬は、逆方向から来る馬の間を抜けて、林の中に入っていく。教官たちも事態に気付き、上級生達を叱ったアト、すぐ側にいたエルネストとアルベルトに頼んだ。
「フランツを救出に向ってくれ」
「は、はい」
「行こう、エルネスト」
ギルバートの胸は不安で揺れる。
「教官、自分も、自分もフランツの救出に向わせてください」
「君は訓練生で下級生だ。・・・馬術も習ったばかりの未熟者が今手を出した所で、事態を悪化させるだけだ、控えていろ。友情や重いだけではどうにもならないこともあるのだ」
「できません!!」
教官がたじろいだ。
「・・・君」
「友達が危険にさらされているのに、待っているダケなど、自分には出来ません」
真っ直ぐな目が教官を捕らえる。
「行きます!!」
アルベルトはハッとなった。観客席のノア証左も視線をギルバートに向ける。氷のような、表情の少ない鋭敏な顔立ちがかすかに驚きの表情を浮かべていた。鋭い刃のような目がギルバートの姿を捕らえる。ヴォルフリートの持つ、控えていた次の黒い馬の手綱を手に取ると、あっという間に飛び乗り、フランツがいる林へとかけていく。
「行くぞ、エルネスト」
「あ、ああ」
「・・・・彼は意外と強情で、感情が激しいタイプのようだ」
残されたヴォルフリートに、ライルやギルバートの同級生が群がってくる。
「・・・ヴァルベルぐラオ、大丈夫か」
「・・・え、ああ、何と言うか、激情かだね、直情型というか。温厚そうだと思ったけど。自分にはないなぁ、激しい、ああいう感情」
「そうですよ、ジャパンの血を持つサブローと友達の弟のジークヴァルトに剣の稽古していますよ」
笑うと、アリスによく似ていた。草の匂いをかぎながら、軍服からかすかにミントの匂いが漂ってきた。始めて、会ったとき、ヴァレリーは既にヴォルフリートが気に入ったようだ。穏やかで陽だまりのような、新緑のようなヴォルフリートは今、地位を登り、国を動かすポストの親衛隊監察のような立場であり、小隊を動かす地位があり、ローゼンバルツァー家の広告塔であり、剣や銃の達人だという。
「そっかーっ、ヴォルフリート、何でもできるものね。異例の出世なんでしょ」
「いやぁ、完璧な人が僕の上にまだまだたくさんいますし、僕なぞまだ未熟者で、それに僕は本当は上に立つリーダーとかは向いてないんですよ」
「まァ、冗談がうまいのね」
「冗談ではないんですが、・・・何故でしょうね、僕はどうも本当のことを言うと、皆信じてくれないのは」
はは、と苦笑いを浮かべる。
「何故、ルドルフ兄様についていかなかったのですか?」
「フラン?」
「親友で、貴方はルドルフ兄様を守ると誓ったのでしょう、それなら側にいるべきだ」
ヴォルフリートがきょとんとした表情になった。
「フラン様はお優しいのですね」
ふっ、とヴォルフリートは笑う。
「ヴォルフリート、僕は真剣に・・・・!」
「フラン様、親友だからといって常に側にいるとは限りませんよ。それにルドルフ様は、公私をきっちり分ける方です。そのルドルフ様の下で働く私がそのような部を超えたことが出来るとお思いですか?」
「けれど、それはさびしいことじゃないんですか?」
この人は控えめで、自分からルドルフの前に出ようとしない。
「人はそんなに自分を曲げることなんて出来ないと僕は・・・」
「大丈夫・・・」
ヴォルフリートが優しくフランの手に触れた。
「フラン様が心配なさることは何もありませんよ、僕は殿下を信じていますから」
「ヴォルフリート・・・」
ヴァレリー達が去った後、議員や大臣達が通りかかり、ヴォルフリートは頭を下げる。
「ヨハネスの七光りが・・・・」
「いい気になるなよ、男妾が」
「ここはお前のようななりあがり者が普通なら立ち入りできぬ場所だからな」
汚らしいものを見るように、引き捨てた口調で大臣たちは顔をゆがめてそういった。
「・・この先には酷いぬかるみが出来ているので、足元にはお気をつけてください」
ヴォルフリートは表情を変えない。静に大臣たちの動くのを待っている。
「ふん・・・」
言葉が見つからなかったのか、大臣たちは去っていく。ヴォルフリートは静かな笑みを浮かべていた。
「ヴァルフベルグラオ上官、何故あのようなやからに道を譲るんです」
部下たちが駆けつける。
「何故って、そりゃあ、身分が上であの人たちが国を支える立場だからだよ。僕の上司の同僚でもあるしね」
「でも、でも、上官は皇太子側の人じゃありませんか、それなのに、何で皇帝陛下の保守派のしたなんかに、ヴァルフベルグラオ上官にはもっとふさわしい場所が」
「辞令だから仕方ないでしょ、司祭や公爵のように宮廷内で皇族と渡り合う立場ジャないン出し。家のくらいは重要視されるものだろ」
「だったら、上官の家でしたら・・・」
「いいんだって。それよりさ、君たちと僕は同い年なんだからそんなに畏まらなくても、同い年で敬語もないだろ」
「できませんよ!!」
部下の一人が大声を上げた。
「だって、ヴァルフベルグラオ上官は強くて、格好良くて、優しくて、剣も銃も出来て、ルーマニアで功績を上げた英雄じゃないですか!」
「そうですよ、アルバニアでは、一人で大尉をクーデターのさなか、単身で救ったとか」
「セルビアでは人買いの少女達をマフィアから救ったとか」
「・・・いや。それ、誤解だから、全部上司の作戦通り、動いただけだから。大体セルビアでは、マフィアとあっていないし、・・・まあ、国側の役人と上司との間で話し合いに付き添ったけど」
「僕らは信じません!!」
「・・・・」
8
フランツの馬の手綱をつかもうと、近距離に迫るが、初心者レベルのギルバートの言うことなど、乗馬している馬は聞いてくれない。
「ギルバート、辞めて、止めて、怖い!!」
フランツは完全に混乱し、馬の首にしがみついている。
「くそっ、いうことを聞け、フランツ!!」
テ綱を握り、片方はフランツの方に手を伸ばし、あと数センチというところで届きそうなのに、馬はギルバートに合わせず、鳴き声を上げて、フランツの馬から離れ、近づくを繰り返している。
「・・・・・ぅぅぅ」
「フランツ、落ち着いて、僕が必ず、助けるから、お前、いいから僕のいうことを聞いてくれ」
「ギルバート、もう・・・」
「近づくんだ、ホラ!!」
テ綱をきつく、締め上げると、なおも馬は抵抗する。
「もう、いいかげんに・・・!!」
馬は手足をばたつかせ、興奮している。
その時、二人の前に巨大な影が一瞬、通り過ぎる。馬が悲鳴を上げる。
「なんだっ」
「ギルバート、馬が何か、変」
馬の鳴き声が鳴り響いた。
ベルクヴァインが結婚し、エドガーはバイキングの血を引く娘と結婚し、ブレーズが湖のボート部屋で心中を起こしたというニュースはディーターの耳にも届いた。
「アロイス、お前は知っていたのか?」
ヴォルフリートを通じて、ディーターはアリスの夫であるアロイスと知り合う形となり、サアラはルドルフをキーパーそんにして、のし上がる形となった。結局、アリすのこともルドルフにとってお遊びに過ぎないらしい。
「ええ・・・相手はセルビアの女性だとか」
仮面を外すと、火傷の後がある。
「・・・そっか、真剣だったんだな、あいつも」
「貴方こそ、婚約者がいるのでしょう?」
「帰ったら勝手に親が決めてたんだよ、俺は家のために結婚する気はないから」
「では、だれと?父親が納得すると思わないけど」
ぐっ、とディーターが感情を抑える。
「エルフリーデ・・・」
「ああ、従兄弟の、でも、彼女は親衛隊でしょう?止めさせるんですか?」
「・・・これからだよ。まだ相手にもされていない」
「お前の浮気性は宮廷じゃ有名だからな」
意地悪じみた笑みをアロイスは浮かべる。
「俺の家も大変なのよ、オヤジが外に産ませた子や母さんが不倫して生んだコとかで」
「ぐちゃぐちゃですね」
「その上、権威やら家にこだわるし、もう、息が詰まるというか」
アロイスの父親は速やかに処罰され、表向きは病死とされた。
「不自然だわ・・・」
「アリス・・・」
「家に行きましょう、こんな急になくなるなんて、ありえないわ」
アロイスがアリスの手を取る。
「いいんだ、俺はあいつを父と思っていなかった。血のつながりもないし」
「でも、私の義理の父でもあるじゃない!!」
真っ直ぐな目でアリスはアロイスに言った。なんて眩しいんだ。
アロイスはそう思った。
「わかった、行こう」
「アロイス・・・!」
アリスの表情が明るくなる。
階段を下りながら、社交界で結婚相手を探す形となったヴォルフリートとであった。ヴィクトリアとの事は様子見という形で、ヨハネスが家のための結婚相手をお目付け役の取るこの青年をつけて、本人に探させているらしい。
「おかえり、ヴォルフリート」
「ただいま、兄さん」
・・・不自然なしだ。この男が関与したのだろうか、あの皇太子に命じられて。
「相当疲れてるね」
「参るよ、任務の合間に連日社交界でダンスを踊ってるから」
先に寝るよ、とヴォルフリートが階段を上っていく。
「ヴォルフリート、君はこの家を出たいと思わないのか?」
「は?」
ヴォルフリートがアロイスに顔を下げる。
「この家は君を幸せにしてくれているのか?」
「当たり前だろ」
「アンネローゼのこと、散々拒まれたらしいね、君の叔母さんに」
「知ってるのか」
「アリスが教えてくれた」
「・・・」
「彼女はいつも君に気を配っている。君が笑顔でいられるように。けれど、この家が君をそうさせていると思えない。12歳のときからなんだろ、ある仕事をしてるのは・・」
「仕方ないことだ、それが帝国に必要なら」
「君は利用されているに過ぎない、それでもか?だれもエルフリーでも真剣に君たちを守らなかった。だからアリスはこの家の当主となって、皇太子殿下のスパイとなった」
「でも、過去だ。終わったことだ」
「アリスはこっちが焼けるくらい、君が大好きで大切なんだ。兄弟愛か、うたがうくライに」
「アーディアディト姉さんがアンネローゼと?何を」
「本当だよ、嫉妬してた」
「・・・・」
9歳の時の記憶だ。ルドルフの思考はふとした時、暗闇のひとりきりの部屋から始まる。たくさんの教育係や祖母のゾフィー、唯一の温かさは姉のギーゼらだが、ルドルフがほしいものとは微妙に違っていた。
―お前は母親似捨てられたんだ。
小さな身体を小さくして、魔物のけたたましい声を聞こえないように自分で耳をふさいだ。冷え切った豪華で他人行儀ナ部屋。
自分を必要といった司祭さえ自分を利用していた。そんなことは一から知っていた。何もかも手に入れている人生に見えるだろう。
ギルバートの読む日記には、最初に私の人生は、死と孤独が付きまとう。光はあの神しかいなかった。自分だけのあの最低な神だけが、この世であり、全てであったと。
・・・・だれも、一緒に死んだマリーでさえもこの世のものではなかったというのか。ギルバートは複雑な心でいた。
王は孤独なものだ。
だれも同等の位置に座れず、常に命を狙われ、理想を求められる。最初は10歳から書き始めたのだろう。日々の暮らしで、箇条書きのように書いている。だが、ページを進めて、夜の女性や貴族の女性との色恋や政治、戦争となり、文章もクールな感情となっている。だが、自分の家でおきた最大の事件、地位を上り詰めた異能者が逮捕され、刑務所に送られている間、ルドルフの感情は揺れていた。ヴォルフリートと何があったのか、エンを切り、ただの主従であり、たくさんいる軍人という扱いをしていた。
ヨハンは言った。
異能者に頼んで、ルドルフの中のある人物との関係性を変えて、王者にしたのだと。
「・・・・」
第3者となったはずの異能者としてのヴォルフリートの行動や生活、女性との付き合い、食べ物や家を細かく記していた。逆に噂となった愛人と思われていたアリスのことはすっかり名前さえ書かなくなっている。最初から関係さえしていなかったように。時系列もめちゃくちゃだ。
逮捕前、・・・・記憶が戻っていた?
しかし、何故、そこまで、皇太子は彼にこだわって、記憶をなくしていて、尚、彼を求めたのか。相手はルドルフの事などサンプル程度にしか思えず、ベクトルが違っていたのに。
9
ギルバートとフランツの馬は悲鳴を上げたアト、さらに興奮し、コースの中の林を抜けると、一般の散歩コースに入った。ギルバートも全速力の馬にさすがに対処できず、しがみついた。
周囲の人間はあわてて、避ける。その時、目の前にノア少佐やエドガー大佐が馬と共に現れ、フランツとギルバートの間に入っていく。
「合図を送る、1、2のさんで俺たちの馬に飛び移れ」
「フランツ、合図を送る、息をゆっくりはテ、目をつぶって、私の胸に飛び乗るんだ」
「はいっ」
上の人間が来て、フランツは安心したらしい。
「来い、下級生」
「は、はいっ」
その時上流階級の母と娘の親子連れ、・・・妹のアーデルは意図とギルバートの義母が突如目の前に現れる。ギルバートは慌てて手綱を掴むが、反動ではねてしまい、その動きで馬は混乱し、ノア少佐から離れていってしまう。
「あっ」
「馬鹿が、何をしている」
ギルバートは公園内の馬車、無人の馬車に衝突しそうになる。ノアは慌てて追いかけるが馬がいうことを聞かず、間に合わない。
その時。
「え・・・」
エドガー大佐のすぐ横を一筋の俊敏な風が一瞬のうちに通り過ぎた。早すぎて、姿を確認するのに数秒か買った。日の光に照らされた、赤毛かかったダークブラウンの髪。見事な手さばきだった。
「!」
茶色のまだらな馬と13歳の少年が一秒だけ、ノアを超えて、あっという間にギルバートと馬の近距離に迫る。
「―-」
「行け、リア」
ヒヒィィン。
ドドドドド・・・・。バッ。
飛び上がった茶色のみすぼらしい馬がギルバートの馬の前にいきなりたち、乗っていたダークブラウンの髪の少年が声を出す。すう、と息を吐く。
「静まれ!!愚か者がっ!!」
つりあがったオッドアイの瞳。表情がギルバートと話していたときとがらり、と違う。全く、違う別人が目の前にいるような感覚にギルバートは襲われた。怒気、いや激しいうねりがギルバートの身体を、馬を、硬直させる。
「?」
ガタガタ・・・。
暴れていた馬を見ると、前足が震えていた。カタカタ、と本人の意思に反して、ギルバートの体も小刻みに震えていた。全てを圧する濁流のような激しさがその場にいるものを完全に圧迫していた。
「君、大丈夫かい」
「は、はい・・・」
乗馬前のこの少年、ギルバートの感情を真似して演じてみたが、どうもこの反応だと演技が過剰らしい。伯母のヘレーネやブリジットの一喝に比べれば優しいのだろう、恐らく。
「そう・・・よかった」
ノアもエドガーも呆然と少年を見る。
「怖いものはいないよ、僕が追い払った、もう大丈夫だから、お前は落ち着きなさい。落ち着け」
優しく穏やかな、見慣れたとろそうな笑顔にギルバートが目を閉じた瞬間、戻っていた。涼やかな、清涼とした声で動揺の色はない。
「恐怖は去った、大丈夫、ホラ、息を吐いて、もう、大丈夫だから、おびえなくていい。お前を苛めた人間はここにいないよ」
一瞬、馬が動きを止めて、少年の姿を見る。
ノアもギルバートも驚いたように少年を見る。馬は急速に動きを平常に戻し、動きを止めた。
「大丈夫・・・」
赤毛かかったダークブラウンの髪、オッドアイの瞳、そばかすのある可愛げな顔立ち。
「大佐や少佐殿もご無事だったのですね、安心しました」
ゆっくりとした動きで視線をノアたちに向ける。
「貴様・・・」
「君は・・・」
二人の視線に気付くと、とろそうな少年は不思議そうに2人を見る。
「何ですか?」
やばい。二人には、変に思われたか。姉さんやルドルフ様、家のニンゲンには目立たないように注意されていたのに。擬態の演技をもう少しあげないと。人の他人の気持ちが読めない、理解できない以上、僕には真似して、その情報を理解し、入っていくと頭にマインドコントロールさせないと。今は2人から自分という存在をほかのものに向けないと。
「エルネスト先輩、言われたとおり、馬をとめましたよ~」
散歩コースをエルネストと馬が歩いてくる。
「ありがとう、ヴォルフリート」
「もう、先輩が止めてくださいよ、優等生でしょう」
「馬術の成績では君も一番だろ」
ギルバートの脳裏に、森の中で吸血鬼のように血をすっていたヴォルフリートの姿と今の姿が重なった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 競馬全般
- 11/23 テラステラ(32)~東京 2勝C 休…
- (2025-11-27 19:11:02)
-
-
-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
- 我が家にもSwitch2がやってきた!が…
- (2025-11-28 10:34:46)
-
-
-

- 美術館・展覧会・ギャラリー
- あと3日!
- (2025-11-28 06:57:07)
-
© Rakuten Group, Inc.