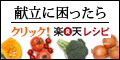「今年、記録的大雨による土砂災害が各地で起こりました。筆頭となるものは伊豆大島に降りかかった台風26号ですが、去来してから1か月も経っていません。しかし、再び台風27号が襲来し、すでに次の台風が近づいています。
なぜ、季節外れのこの時期に台風が連続で襲うのか、土砂災害は全国でどれくらい起こりうるのか、そのリスクと対策は。」
といった段取りでした。 →番組情報は コチラ
あああタメになるお話...と思い整理したくなったので以下にダイジェストを( ..)φメモメモ ※注 大幅にうp主が改竄しています。これまでの比じゃなくうろ覚えなので、噂話レベルだと受け止めてください;;;
●温暖化に備える
今年の気候は、地球全土の温暖化から気団の位置が北にずれ、日本は各地で最高気温を更新する酷暑に。一方、気圧配置のずれから台風は中国にぶつかっていた。
秋になっても海水温度は下がらず、10月になった今でも雨雲をたっぷり含んだ台風が発生。気温は少し下がったため、日本に襲来するようになった。
→過去20年のデータから、年によってばらつきはあれど日本における降水量は増加中
→温暖化はこれからも進むだろうから、秋に日本への台風直撃や連続、記録的豪雨はこれからも起こり得る。異常気象ととらえず、常時あることとして対応策を練るよう自治体に意識変革が必要
●土砂災害は起きるのか
伊豆大島の被害からわかることがある。火山灰の堆積地は容量を超える雨水が降ると地面が滑り落ちること、泥を含むぶん押し流す力が強いこと、流木が土砂とともに流れ込むため被害が拡大すること、橋に溜まった流木が土砂の流れをせき止め川から土砂が溢れだして地上に氾濫させてしまうこと。
→日本全土の2/3は、火山灰からなる土地。伊豆大島のような土砂災害が起きる可能性は高い(中部以北はほぼ該当でした)
→土砂災害警報の70%は空振り。そのため、自治体の腰は重い
●土砂災害に対応する自治体
過去に土砂災害の被害に遭った経験のある2つの自治体を取り上げた。
1つめの自治体は、土砂災害が発生したら職員に自動的にメールが届く装置を危険個所に設置。また、大雨注意報が出たら避難準備情報を流し、大雨警報になったら避難勧告、といったマニュアルを作成した。
→予定よりも大雨注意報の発令がはやく、早朝のため職員が揃っていなかった。職員がいないと避難所が開設できない
→深夜や早朝に発令した場合どうするかなど、考えるべき事例が多い
2つめの自治体は、「タイムライン」という手法を採用した。タイムラインとは、アメリカのハリケーン被害から編み出された行動規程で、ハリケーンが襲来する96時間前から避難準備行動を開始する。自治体、住民などのすべきことが細かく定められており、素早い非難につながる。この自治体では、96時間前に非常用電源の動作確認を行い、××時間前には過去に被害のあった地域を点検。兆候がないかをチェックした。
→台風の進路が逸れたため、それ以上タイムラインは進まなかった。4日前から動くことで、気象の予想外の動きにも柔軟に対応できる余裕がありそうだ
●コメンテーターのまとめ
土砂被害を防ぐのは素早く避難すること。自分の住んでいる土地が危険なのか、どれくらいの降水量だと危ないのか、住民の認識と自治体の情報公開が求められる。また、避難勧告や避難指示などといわれても、切迫感が伝わりにくい。自治体側は、いきなり避難勧告を出すのではなく、このまま雨が降り続けたら避難勧告を出しますよ、などと段階をふまえた情報を小出しにするとよい。そして、住民は防災してもらうのではなく、自分で防ぐ意識をもつこと。災害情報を確実に手に入れる環境にしておき、近所の川や道路に変化があれば、報告すること。住んでいる人の情報は、とても重要な災害情報です。
おまけ。
土砂災害についてわかりやすいな~とおもったサイトです_(._.)_
PR
キーワードサーチ
カレンダー
October , 2025
September , 2025
July , 2025