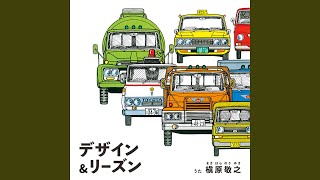ビハーラ活動論 レポート
私はビハーラ活動論の講義を受けることによって、過去を振り返ったり、今取り組んでいることにヒントを与えてもらったり、将来、死という課題とより向き合う手がかりを得たように思えた。
まず、死を前にした人の願いについて“日常性の延長”、“願いの継承”、“再会の希望”の3つを教えていただいたことは大きな収穫だった。私は福祉を学ぶ者として、いかなる時もQOLを高められる生活への支援に関心を持っているので、以上の3つの願いを叶えることがQOLを高める鍵だとヒントを得たと思う。告知を受けていない人に比べて、死期が迫ってきていると把握している人や緩和医療を受けている人でも、死の受容が出来ているわけではなく、やはり完治したい、生きたいという希望を持っているものだと思う。しかし、その希望を叶えたくても叶えられない状況にある人も少なからずいるのが現状だと考える。その完治したい、もっと生きたいという身体の治癒としての希望を叶えられないのなら、せめて心に起こり得る葛藤を癒してもらいたいという希望を持っているのではないかと思う。あくまでそれら心に起こる葛藤を解決するのは患者その人であるが、葛藤と向き合えるように、そして乗り越えられるように環境を整える、つまり痛みのコントロールや宗教の2つの働きを生かして人生の舵取りや前進する力を持ってもらうこと、家族関係の調整や社会資源の情報提供や利用を促すのは医療や宗教、福祉の役割であると考える。そして、医療や宗教、福祉はそれぞれが個別に働きかけるよりも、協働した時、死を前にした人の願いを具体化できるのではないかと思う。その具体化が生の完遂を支えることであり、その場としてビハーラやホスピスが発展してきたように思える。
ビハーラやホスピスと他の医療機関や施設の違いにはまず、真実の共有ということが挙げられるのではないかと思う。ホスピスや緩和ケア病棟に転院する際には他の医療機関と治療目標の違いがあるため、告知の有無が関係する。告知に対してはメリット・デメリットの両面があるが、残された時間のためには告知を通して、真実を共有することが望ましいのではないかと思われる。そうすることで患者が自分自身と向き合うだけでなく、家族もより自分自身や患者とも向き合い、人生の振り返りなど自主的な内観が自然と双方で行われると考える。そして、死の意味やいのちの尊さを感じることができ、家族は残された時間をより有意義に、患者は最期の跳躍として人間的な成熟が遂げられるのではないだろうか。すべての患者と家族が真実を共有することによって理想的なプロセスをたどるわけではないと思うが、ホスピスやビハーラは他の医療機関よりも生の完遂を支える場として理想に近い援助が提供できるという感想を持った。
また、医療職の死に対するイメージの違いも挙げられると考える。急性期病院や高度先進医療を掲げる病院などでは、治療が第一であり、死を敗北と見なす傾向が未だにあるのではないだろうか。確かに医療職に代表される医師は冷静沈着な判断が求められ、公私混同が許されない専門職である。そして、死を敗北として疾病に取り組んだ過去があるからこそ、医療技術は目覚ましい勢いで進歩し、平均寿命を延ばすことが出来た。しかし、死を敗北と見なす価値観を持っているのとそうでないのでは大きな違いがあると思う。死を敗北だとするために、治療目標を根治から緩和へとギアチェンジすることに抵抗感を持ち、患者の死を第三人称の死として終わらせてしまうきらいがあるのではないだろうか。根治から緩和へ治療目標をギアチェンジしたからといって、医療との関わりが終わるわけではなく、むしろ、医療のよりよい関わり方が望まれる。その際、死が敗北とするなら、患者・家族と医療職は納得のいく関わりが持てず、双方がどこかに違和感を持ち、死を迎える切なさを助長しかねない。死は決して敗北ではなく、どのような人にもいつか必ず訪れるものだということを、誰もが理解しなくてはならないと思う。
そして、病院で死を迎える人が大半を占める病院死時代に同じ施設で迎える死であっても、ビハーラやホスピスで迎える死はまた意味合いが違ってくるように思える。それは患者、また患者家族の主体性を重んじた治療が図られていることで人生を最期まで自己決定によって生き抜けるように思うからである。インフォームドコンセントの概念が日本でも普及してからは、医師が主導権を握るお任せ医療ではなくなってきただろうが、まだ完全になくなったわけではないと思う。また、治療に対する説明において同意はなされても、治療方法や今後の生活を自主的に選択し、描けるところまではまだ到達していないと考える。さらには環境が整わないままに平均在院日数の短縮化が図られてしまえば、現在の医療システムに不信感を抱くことが予想され、自己決定による最期が守られるとは思えない。その中で、生の完遂を支えようとするホスピスやビハーラは患者や家族の個別性と自主性を尊重し、患者はもちろん、見送る家族にとっても人生に納得できる環境を作り出せると思う。また、今後、超高齢社会を迎える中で単身者世帯が今まで以上に増えてきていることから、家族の看取りがなく、医療現場で死を迎える人が増えると予想されている。医療と福祉、宗教の連携による援助が行われるビハーラやホスピスの活動は何も施設で行われるものばかりではないと思う。在宅ホスピスの流れもあることから、施設を飛び出したビハーラの活動にも関心を寄せていきたいと思った。
さらに、医療機関とビハーラ・ホスピスの違いには患者・家族が宗教的援助を自由に受けられるという点が大きいと思われる。疾病によって死を目の前に感じると身体的・心理的・社会的・精神的な苦痛を経験することになる。それを全人的苦痛としているが、とりわけ精神的苦痛にとっては個人差が予想されるものの宗教的援助が効果的ではないかと考える。精神的苦痛は、こんなはずではなかったと後悔の念や、生きる意味を問うなど、なぜ・どうしてに通じるものでスピリチュアルな痛みであり、対応したケアを要するものだと思う。スピリチュアルな痛みとは何らかの出来事によって、自分自身の中に拠り所が失われてしまった時、人間存在を支える時間軸、関係軸、自律軸のどれかを失うことが要因の一つとされている。その時に自身の外や内に新たな拠り所を見つけようとするために起こる反応のことであり、対応したケアは新たな拠り所を見つけようとする生きる力を支えることだと思う。そのケアには折れてしまった軸を構築することも挙げられるが、死をもうすぐ迎えるターミナルにある人は残された時間がわずかという時間軸が折れた状態であるため、時間軸を再構築することは困難だと思われる。その場合は折れてしまった軸を補えるように他の軸を太くすることが必要とされる。さらに、信仰によって死後もなお、将来があると思えるなら時間軸は再構築が可能であると思う。宗教は古くからその中心に死を主題として発展してきた。死が身近に溢れている時には社会不安が増大し、死や苦しみに意味を与えるべく宗教が必要とされたが、死に場所の変遷や核家族化によって死が日常の生活から遠ざかってしまった現在、また宗教を必要としているのではないかと思う。
そして、スピリチュアルな痛みは死を前にしたときにのみ起こると限らないのではないだろうか。人間存在を支える拠り所を失うのは何も死に対面した時だけでなく、今現在の持ちうるものでは乗り越えられない壁に直面した時でもあると思う。その際に宗教という全てを俯瞰したような大きな視野で壁を捉えると、意外に早く壁を乗り越えられたり、乗り越えられる試練や壁が新たな世界への扉だったと気付いたりするように思える。数ある宗教の教えの中でも、授業で学んだ“自灯明・法灯明”や“自らを島とし、法を島とせよ”という言葉には深く考えさせられた。そこには何かの出来事に遭遇して生きる力が弱くなったとしても、それぞれに歩んできた道のあることやそれを支えてきてくれた数々の人やもの、また深い慈悲で包んでくれる見えない存在があることを感じさせる。また、全人的苦痛の中でも、スピリチュアルペインに答えを見出し、解決するのはその人以外の誰でもないと考える。信仰の力はその問題に自らが立ち向かうことを示唆し、また支えるものでもあると思う。スピリチュアルな痛み全てを宗教で解決できるものではないだろうし、区別しなければならないところもあると思う。だが、宗教による可能性を捨ててはならないと思えた。また、信仰のあるなしに関わらず、スピリチュアルペインを乗り越えた人には優しさやあたたかさが生まれると思う。そして、人の痛みを理解できるようになるのではないだろうか。そして、以前では見えなかった、見つけられなかった喜びを発見できるように思える。
ここで、宗教のもたらすものをもう一度振り返りたい。多種多様なものがあると考えられるが、授業で教わった生きる意味、行くべき方向性を与える役割と前進する力強さを与える役割に加えて、無常と死を超えた絆を享受できることが大きいと思う。現在の生活がどれだけ見えるもの、形あるものに執着しているかを仏教における無常観においても知ることができた。先生が体験された桜物語は、自然に満ちている無常を示唆し、競争社会のストレスに答えを出すものではないかと思えた。日本はいつの頃からか自分に競争意識を持つのではなく、他者に競争意識を持つようになったのではないだろうか。そのために現在では競争社会の勝ち負けのみが表面化し、ストレスの多い時代になったように思う。桜のお話によって誰かと比べるのではなく、ありのままの自分に今日一日、できる精一杯のことを心がけることの大切さを考えさせられた。もし、同じ状況に置かれたとしても仏教による縁起思想を持ち得なければ、桜のメッセージを感じ取ることができないと思う。宗教によってすべての人やものとの出会いが偶然ではなく、意味があるとするから無常に溢れる自然に学ぶ姿勢がもたらされると思う。
また、仏教による無常観は日常に当たり前などないと無常に溢れていることを感じさせることによって、無常を超える絆について考えるきっかけを与えてもくれる。それは死を前にした願いの一つである、“再会の希望”を叶えるものであろう。無常を何より感じさせる死を目の前にした時、その切なさ、侘しさは無限に膨らむと思う。仏教による倶会一處としての極楽やキリスト教における天国とはまた再会できる希望の象徴であろう。また、宗教による死後の世界を持っていなくとも、日本には仏教国としての死にまつわる文化があるように思える。日本人は多宗教であり、特定の宗教による信仰を持っていないと言われる昨今でも、多くの日本人は死後、どのように残っているのかという問いには答えられなくとも、完全に無になり、ゼロになって何も残らないとは考えていないように思える。やはり、そこには仏教国としての浄土に対する概念が残っているのではないだろうか。日本の文化を見直すことによって、生死にヒントを与える何かがあるように思えた。
死と生の関係は正反対の関係でも、どちらかが隔離されるものでもない。ただ、よりよい生を考えるには死の問題を考えるのが不可欠だと思う。今もどこかで新たな命が生まれると同時に生を終える人がいる。命あるものはすべて死に向けて、歩んでいるという事実は変えられない。死ぬために生きているようなものであるが、生死を繰り返して人類の歴史は今まで続いており、これからも続くであろう。私は今この世に生きている私たちは過去と未来を繋ぐ存在であると思う。死ぬために生きているような何十年かで次世代へバトンタッチを行う。その営みを通して自分の命がいずれなくなることを実感できれば、人は自身の唯一性、一回性を認識することになり、無常に裏打ちされた輝きを放つ何かを残せるのではないかと思う。また、自身の唯一性、一回性を認識することは他者の存在の唯一性や一回性をも認識することになる。そのように認識できれば、今、ここで出会えたことに感謝の気持ちが起こったり、出会う意味を考えさせられたり、お互いの受容や尊重に歩を進めるのではないだろうか。それらの認識や尊重は人間関係だけでなく、ものを大切にする意識を育む。ふと、昨今、環境問題を考えるためにふさわしいと流行ったもったいないという思想にも影響をもたらしたのではないかという考えが浮かんだ。
死を通して生を見つめ、よりよく生きることを考えるプロセスに宗教を必要とする人もいれば、そうでない人もいると思う。しかし、人々の予想以上に宗教は波及効果があると思う。その影響の広がりをこの講義を通して実感できたように思う。また、前にも増して人との出会いと別れは人を成長させるものだと実感させてもらった。最期の瞬間まで生き抜いていただく援助を通して、自分自身の成長を続けたいと思う。かねてからの夢である、誰かに生きていてよかったと思ってもらえる日を夢に生の完遂を支える援助に携わりたいと思う。授業で聞かせたもらったマザー・テレサには到底及ばないと思うけれど、先生の桜のお話を胸に努力したい。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 【2025年11月】楽天市場ブラックフラ…
- (2025-11-20 12:50:09)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 「Rocker? ロングスリーブ」 折れた…
- (2025-11-20 16:45:29)
-
© Rakuten Group, Inc.