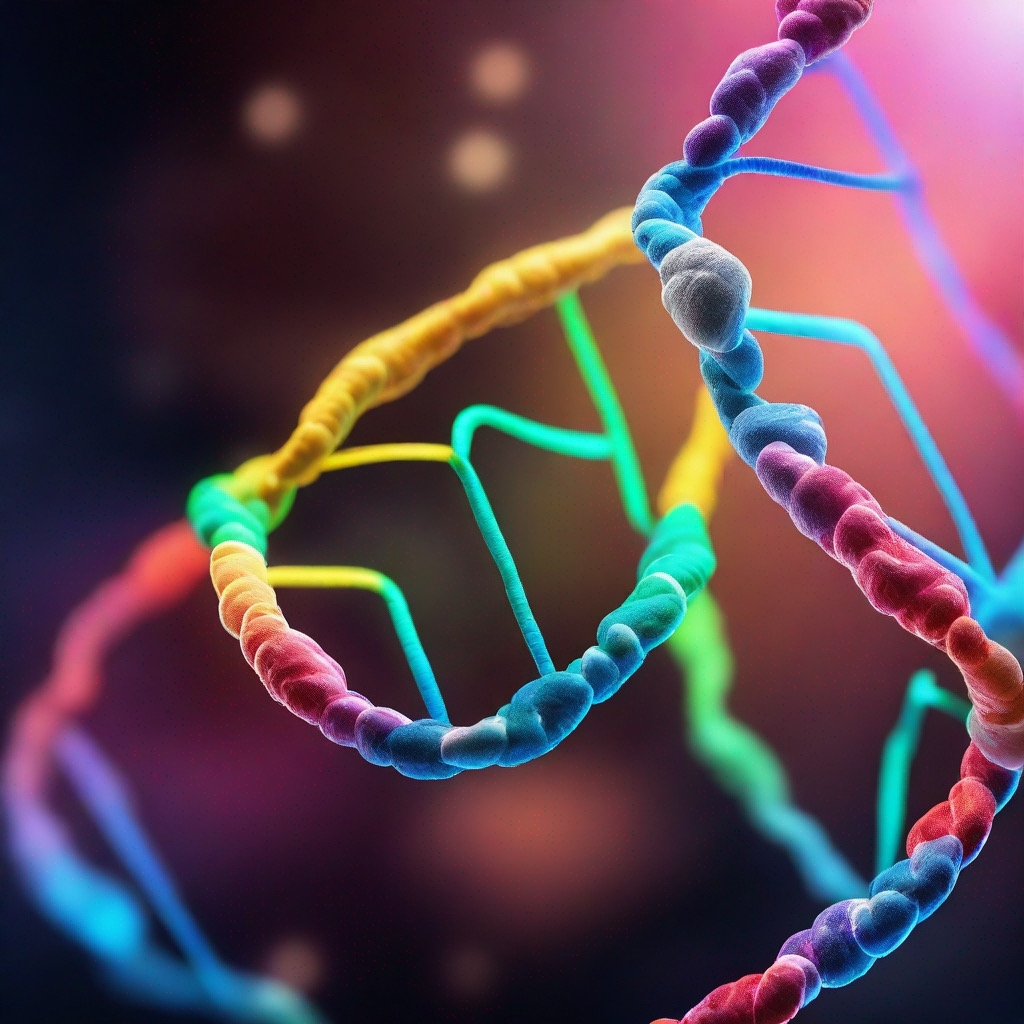PR
カレンダー
キーワードサーチ
コメント新着
サイド自由欄

狐に食われる足、舞に宿る魂──兼好が遺した不気味な風と智慧を探る
心の静寂の中で綴られた『徒然草』後半は、表面的には些細なエピソードの羅列に見えます。しかしその奥には、現代の我々の生き方や感情にも深く響く、皮肉と警句と、そして風刺の刃が光っています。
目次
- 1. 不気味な日常の裏にある真実
- ・狐に足を食われるという寓意
- ・妖怪や化物に託された人間の無意識
- 2. 賤しきものに宿る誇り
- ・辺境の芸能と都の誇り
- ・祭と放免に見る「賤しさ」の再評価
- 3. 知識と無知の本質を問う言葉たち
- ・「知らず」と言える勇気と品格
- ・万の咎を避けるための「まこと」
- 4. 和歌と舞に込められた精神
- ・舞の「手の中」にある興の選び方
- ・釈迦念仏と法然の教えの系譜
- 5. 月のように欠けてゆく人の心
- ・「望月」の円満とその崩壊
- ・父への問いと仏への距離感
1. 不気味な日常の裏にある真実
狐に足を食われるという寓意
狐に足を食われるという話は、怪談ではありません。舎人という身分の人間が、堀川殿にて狐に足を噛まれる──この描写は、日常の秩序が一瞬で壊されることを暗示しています。「狐」は、古くから変化(へんげ)を司る存在であり、人の心の隙を狙う象徴でもあります。日常がいかに脆く、無意識に侵食されるかを、兼好は淡々と記しています。
妖怪や化物に託された人間の無意識
さらに、五条内裏に現れた「妖物」の話や、藤大納言殿の語りもまた、人が見えない領域にあるものへの畏れと畏敬を示しています。兼好は、超自然的な存在を否定するのではなく、逆にその存在が人間の心の奥深くとつながっていると示唆しているのです。
2. 賤しきものに宿る誇り
辺境の芸能と都の誇り
「辺土は賤し」という言葉の背後に、兼好は深い問いを隠しています。社会の中心である都から見下されがちな地方や辺境。しかし、そこにある舞楽が「都に恥じず」と記されることで、表面的な身分や地位では測れない芸術の尊さが浮かび上がります。
祭と放免に見る「賤しさ」の再評価
また、放免という庶民の存在や、彼らが参加する祭りの中に宿る霊性も無視できません。兼好は、権威と伝統に囚われる都よりも、時に「賤しい」とされる場所に真実の美を見出すのです。
3. 知識と無知の本質を問う言葉たち
「知らず」と言える勇気と品格
「すべて、人は、無智・無能なるべきものなり」という断定的な表現は、非常に挑発的に響きます。知識社会の現代においてはこれほどまでに逆説的な言葉はないでしょう。しかし、兼好が言いたかったのは「無知を恥じず」「知を飾らず」「知らずを語るな」という、自己抑制の倫理だったのではないでしょうか。
万の咎を避けるための「まこと」
また、「まことありて、人を分かず」という言葉には、知識や論理を超えた、誠実さや共感の重要性がにじみ出ています。この視点は、SNSで分断と対立が深まる現代にこそ必要なものかもしれません。
4. 和歌と舞に込められた精神
舞の「手の中」にある興の選び方
通憲入道による「舞の手の中に興ある事どもを選びて」という言葉は、芸における真の価値が、目立つ部分ではなく「手の中=構造の中」に宿ることを示しています。見える部分だけで判断する浅薄な視点を戒めているのです。
釈迦念仏と法然の教えの系譜
また、釈迦念仏や六時礼讃に表れる仏教儀式も、ただの形式ではありません。法然の弟子である安楽の名も登場し、兼好が見ていたのは、儀礼の中にこそ宿る精神性でした。人が集い、声をそろえ、念仏を唱える──そこにあるのは信仰というより、共感と秩序、そして癒しの機能です。
5. 月のように欠けてゆく人の心
「望月」の円満とその崩壊
「望月の円まどかなる事は、やがて欠けぬ」──この短い一節に、兼好の死生観と時間感覚が凝縮されています。完全に見えるものでも、やがて欠けていくのが自然の理。人間関係や感情、そして人生そのものも、こうして崩れていくと彼は見抜いていました。
父への問いと仏への距離感
さらに、幼少期の兼好が父に「仏は何者か」と問いかけた場面は、宗教へのまっすぐな探究心を物語ります。兼好は仏を抽象的な対象としてではなく、「生きている自分の実感」に照らして見ようとしていました。その感性こそが、『徒然草』全編を貫く根本精神です。
最後に
『徒然草』の後半は、一見すると取るに足らない記録や逸話の集積に見えるかもしれません。しかし、その裏には、現代人が見失いがちな「感受性」や「畏敬」「沈黙の意味」が、濃密に漂っています。
狐や妖物は、心のどこかにある見たくないものの化身です。無知を肯定する言葉は、知識や正しさに振り回される時代への批判です。そして、円満な月がやがて欠けていくように、どんなに整った人生にも揺らぎや空虚があることを、兼好は知っていました。
この世の表と裏──その両方を静かに見つめるまなざしこそ、『徒然草』を読む意味であり、私たちが自分自身を深く掘り下げるヒントになるのです。
生きづらさに役立つ情報はこちらのメルマガから
人気ブログランキングでフォロー
ブログ村でフォロー
すべてのリリース情報が載っているLINEVOOMはこちら
私の楽天ROOMはこちら
引きこもりや生きづらさの相談はこちら
思ったことを深掘りするブログ
アニメを観た感想ブログ
叶えてみたい夢ブログ
自叙伝ブログ
お金にまつわるブログ
料理に関するブログ
ビジネスのブログ
ダイエットのブログ
ファッションのブログ
スピリチュアルのブログ(英語)
私が作っている引きこもりYouTube動画はこちら
私が作っている音楽のYouTubeはこちら
私が運営しているメルカリはこちら
(楽天ランキング)
生きづらさに役立つ情報はこちらのメルマガから
人気ブログランキングでフォロー
ブログ村でフォロー
すべてのリリース情報が載っているLINEVOOMはこちら
私の楽天ROOMはこちら
引きこもりや生きづらさの相談はこちら
思ったことを深掘りするブログ
アニメを観た感想ブログ
叶えてみたい夢ブログ
自叙伝ブログ
お金にまつわるブログ
料理に関するブログ
ビジネスのブログ
ダイエットのブログ
ファッションのブログ
スピリチュアルのブログ(英語)
私が作っている引きこもりYouTube動画はこちら
私が作っている音楽のYouTubeはこちら
私が運営しているメルカリはこちら
-
陰謀論はなぜ生まれるのか|権力の不透明性… 2025.11.21
-
税金・地方交付税から行政法まで!国の「… 2025.11.19
-
知恵と芸の追求:本当に大切なものを見極… 2025.11.16