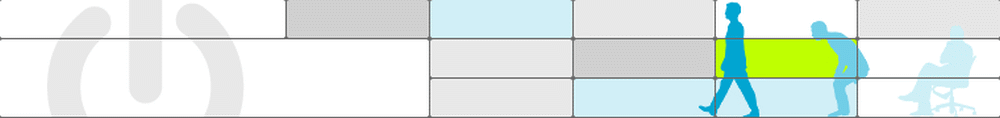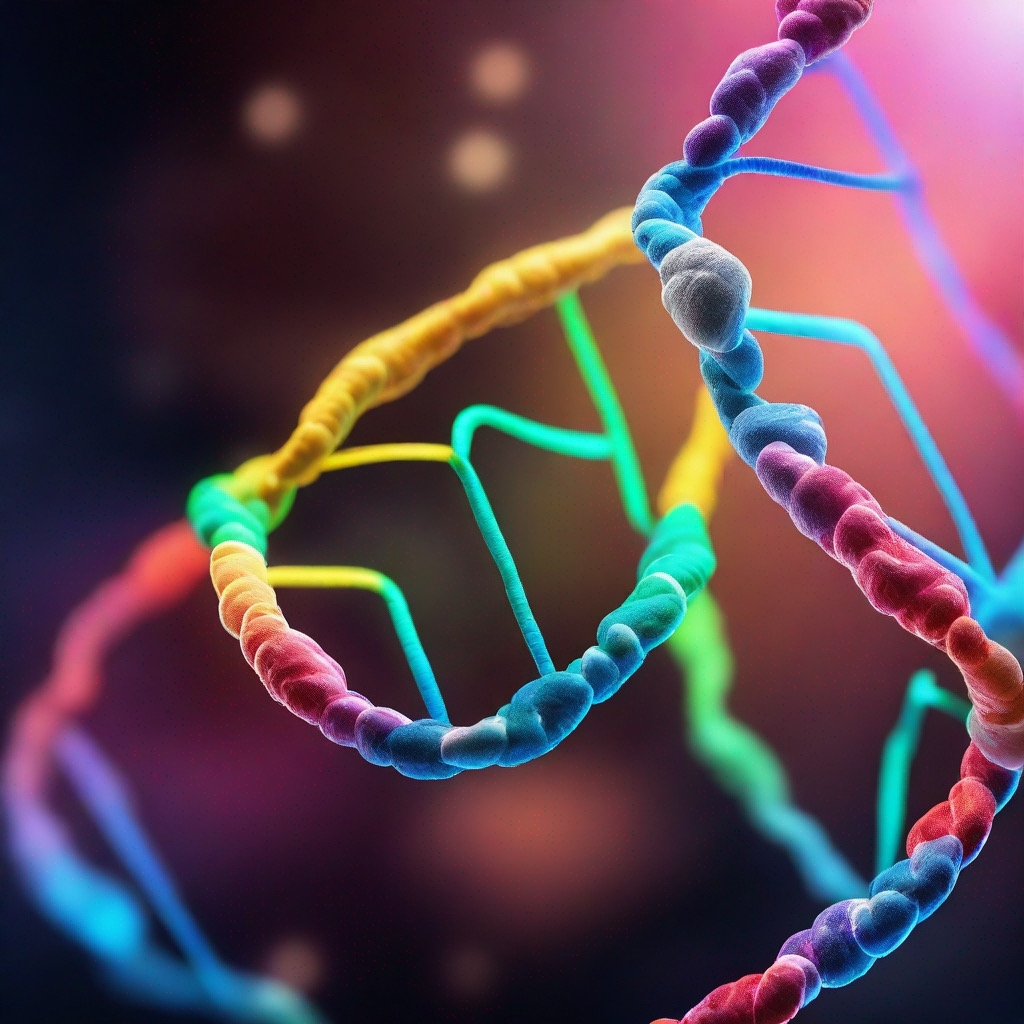PR
カレンダー
キーワードサーチ
コメント新着
サイド自由欄
人間の本性と世の虚実を照らす:吉田兼好の鋭き眼差し

人間の愚かさや賢さ、そして人の世のはかなさを、吉田兼好は飾らぬ言葉で私たちに語りかけてきます。
第六十段から第百二段までには、目をこらさなければ見逃してしまうような鋭い真実が隠されています。
そこに宿る知恵と皮肉を、現代に照らして掘り下げていきます。
目次
- 1. 智恵ある者の孤独と気高さ
- 2. 世の虚実を見抜くまなざし
- 3. 人間の心に巣食う弱さと欲望
- 4. 美と芸に宿る人のあり方
- 5. 日常の些細に宿る人生の教訓
- 6. 最後に
1. 智恵ある者の孤独と気高さ
・真乗院の智者が示した沈黙の重み
第六十段で語られる盛親僧都の在り方は、現代の知識人像をも照らします。
彼は「やんごとなき智者」と称されながらも、多くを語らず、行いによって人を導きました。
智慧を持つ者ほど、言葉に頼らず、行動の端々に品格を宿すということを、我々は忘れてはならないのです。
・虚名に惑わされぬ慎みの精神
第七十段では、権勢を振るう者の遊宴の席に招かれた玄上が、それを潔しとせずに辞退する姿が描かれています。名誉や誘いに飛びつかず、己の節を守ることが、いかに尊いかを物語っています。
2. 世の虚実を見抜くまなざし
・語り継がれる話のほとんどは虚言か
第七十三段に「世に語り伝ふる事、まことはあいなきにや」とあり、民衆の語り継ぐ話の多くが真実ではないことが示されています。歴史や伝承、ニュース、SNS──すべてに共通するこの構造は、今こそ再考が必要です。
・見た目に囚われず、事の本質を見極める
第七十一段では、噂で聞いた人の顔を想像し、いざ会うとまるで違うことの驚きが語られます。この感覚は、現代のSNSのプロフィール写真や肩書きに対する幻想と重なります。
3. 人間の心に巣食う弱さと欲望
・人はなぜ名声や虚飾に走るのか
第七十九段では「何事も入らぬさましたるぞよき」と記され、知識や経験を鼻にかけぬ慎みが美徳とされています。一方で、現代では自己アピールが求められる時代です。
・愚かなるこだわりが生む執着
第七十五段では「つれづれわぶる人」について述べられ、孤独の中で何も手につかず、物思いに沈む姿が描かれます。現代人もまた、孤独に耐えられず、SNSや買い物で心を埋めようとします。
4. 美と芸に宿る人のあり方
・絵や書に現れる人格と趣味
第八十一段では、屏風や障子の絵や文字に人の趣味や人格が映し出されることが語られています。美意識は、持ち主の精神の深さを映す鏡であり、それは服や所作にも通じます。
・古典と流行の間にある断絶と懐疑
第七十八段にて、流行する「今様」の珍しさをもてはやす風潮に対し、深い疑問が投げかけられています。「古りたるまで知らぬ人は、心にくし」という言葉には、伝統に目を向けぬ者への批判が滲みます。
5. 日常の些細に宿る人生の教訓
・猫またから牛の売買までが語るもの
第八十九段には「猫また」が人を食うという噂が登場し、第九十三段では牛を売る話が淡々と語られます。一見ばかばかしいような話のなかにも、慎重さや人間の疑い深さ、信頼の難しさが浮かび上がります。
・矛盾に満ちた営みのなかにある真理
第九十七段では、「その物に付きて、その物を損ふ物、数を知らずあり」と述べられます。つまり、役に立つものほど、時にその役割によって不具合や不幸を招くという逆説が語られています。
6. 最後に
徒然草の第六十段から第百二段までは、表面的には些細な事象の羅列に見えるかもしれません。しかし、その奥には人間の本質、社会の矛盾、そして生きる上での美意識と慎みがしっかりと描かれています。
現代の混迷した社会にこそ、吉田兼好の視点は価値を増してきます。
表層の情報に振り回されるのではなく、一度立ち止まって、深く、静かに、自分と社会を見つめ直す。
それが徒然草の教えではないでしょうか。
物語や寓話に耳を澄まし、自分の内側を磨き続ける姿勢を、これからも大切にしていきたいと思います。
生きづらさに役立つ情報はこちらのメルマガから
人気ブログランキングでフォロー
ブログ村でフォロー
すべてのリリース情報が載っているLINEVOOMはこちら
私の楽天ROOMはこちら
引きこもりや生きづらさの相談はこちら
思ったことを深掘りするブログ
アニメを観た感想ブログ
叶えてみたい夢ブログ
自叙伝ブログ
お金にまつわるブログ
料理に関するブログ
ビジネスのブログ
ダイエットのブログ
ファッションのブログ
スピリチュアルのブログ(英語)
私が作っている引きこもりYouTube動画はこちら
私が作っている音楽のYouTubeはこちら
私が運営しているメルカリはこちら
(楽天ランキング)
生きづらさに役立つ情報はこちらのメルマガから
人気ブログランキングでフォロー
ブログ村でフォロー
すべてのリリース情報が載っているLINEVOOMはこちら
私の楽天ROOMはこちら
引きこもりや生きづらさの相談はこちら
思ったことを深掘りするブログ
アニメを観た感想ブログ
叶えてみたい夢ブログ
自叙伝ブログ
お金にまつわるブログ
料理に関するブログ
ビジネスのブログ
ダイエットのブログ
ファッションのブログ
スピリチュアルのブログ(英語)
私が作っている引きこもりYouTube動画はこちら
私が作っている音楽のYouTubeはこちら
私が運営しているメルカリはこちら
(楽天ランキング)
生きづらさに役立つ情報はこちらのメルマガから
人気ブログランキングでフォロー
ブログ村でフォロー
すべてのリリース情報が載っているLINEVOOMはこちら
私の楽天ROOMはこちら
引きこもりや生きづらさの相談はこちら
思ったことを深掘りするブログ
アニメを観た感想ブログ
叶えてみたい夢ブログ
自叙伝ブログ
お金にまつわるブログ
料理に関するブログ
ビジネスのブログ
ダイエットのブログ
ファッションのブログ
スピリチュアルのブログ(英語)
私が作っている引きこもりYouTube動画はこちら
私が作っている音楽のYouTubeはこちら
私が運営しているメルカリはこちら
-
欲望と知恵のバランスを考える 2025.11.22
-
時間の尊さを見失わない生き方 2025.11.07
-
【夢の中の「探す」とはなにか】超ディー… 2025.10.26