全270件 (270件中 1-50件目)
-
Re:よき指導者
朝の坐禅会でのできごと。博識の男性が曹洞宗の禅と、臨済宗の禅の違いについて、質問されました。老師はすぐに、「違いを探すのではなく、同じものを探す」ことが大切ですと、おっしゃいました。宗教が戦争をおこすのは、、こういう表面的な違いへのこだわりや、道徳性からおこっている、、、大切なのは、なにかに頼らず(理解をいれないレベルで)直にそれに触れることなのだとも。大変難しいことですが、頭で考えるな、、とおっしゃているのだと思います。男性の質問にそのまま、答える方も多いでしょうが、今日は、この質問のおかげで、またひとついいお話が聞けましたよ(^^)質問好きの方は、聞きたいことがあるというよりも、自己アピールの場として使う人、知識を披露したい人も、結構多いように感じます。老師のひとことは、禅の本を片っ端から読んで、知識を知ろうとしていた男性の読書をとめ、、ただ坐ることへのきっかけになったようにも思ったことです。相手の意図を、くつがえしてあげることも、大きなプレゼントになる。なかなかこの境地にはいかないけれど、、、。
2008年07月06日
コメント(2)
-
Re: ぼた餅を買って感じたこと。
先日、差し入れ用にと、百貨店で「ぼた餅」を買いました。差し入れ先で、すぐに食べられるようにとお箸をお願いしましたが、ヘラが入っていますからと言われ、あけてみると、1箱にたったの1個!!せめて、「何人分ですか」と聞いてくれる、心配りが欲しかったな~と思ったことです。小さなことですが、この小さなことでしか、今は他社と差がつけられません。爪楊枝一本、箸一本にもこだわりがなければ・・・なんてね。ところで、ぼた餅とおはぎは、同じものです。ぼたんの花が咲く頃には、ぼた餅と呼び、萩が咲く頃にはおはぎと呼ぶのだとか。昔、こんな話をしながら、特大のぼた餅を家でつくり、仏壇にお供えした後に、お昼ごはんとして皆で頂いたことを懐かしく思い出したりしました。もし、人数を聞かれ、人数分のお箸を入れてくれたら、、、。お客様の言葉のなかにはいっぱいサービスのヒントが隠されています。
2008年06月14日
コメント(6)
-
Re: 年神さまをお迎えして。
新年 あけましておめでとうございます。 毎年感じることですが、大晦日の何ともいえない閉塞感から 一気にトンネルを抜けだしたような、、、。 まだ庭の木々は枯れ果てて、、どこもかしこも、命が終わっていく かのような寂しい風景ですが、 実は、その枯れた木々の幹の下や、霜のおりた土のなかには 新しい命が日々育まれているのだそうです。 もうすぐ・・・です。 だから、春は一見まだまだ先のようですが、春の気配は むくむくと胎動を始めているそうな。 年神さまを新年のおうちにお迎えして、今年は節目ごとの 行事を大切にたいせつにしようと思っています。 竹の節のように、 わが身を振り返る時間。弱虫な自分や、おごっている悪い自分を 振り返るきっかけをつくる。 一月は睦月ともいいますが、家族や親しい人が集まって「睦みあう」 そんな所以があるのだとも。 今年もどうぞ宜しくお願いします。 年神さまに一年の無事をお願いしながら。
2008年01月01日
コメント(12)
-
Re: 秋の実りの季節です。
季節には色がある・・・。秋は、黄色や茶色の季節。そしてそんな色の食べ物を食べていれば、夏の疲れをとり、きたる冬の蓄えの時期にあわせて体を整えてくれる、、、そうですね。柿や栗、、キノコや、みかん。今日はひさしぶりにのんびりした気分を味わっています。母の病気のことや、目の前の仕事の多さについつい追われて気がつけば、秋。疲れが一日でとれる年代ではなくなったことを肝に銘じ、今日はキノコ料理や、デザートに柿でも食べることにしましょう(^^)
2007年10月13日
コメント(6)
-
Re: ひとを動かすことば。
単純ゆえに、純粋、、そして真理。そんな言葉だと思いました。「さぼるな」 「草とり 励め」 「悩める人の友となれ」ある雲水さんが禅の修業が終わってその寺を去るとき、老師から頂いた言葉だそうです。禅のすべてがある、、、初心者のわたしでさえそれはわかりました。ちょうど、茶の湯の世界にも、~茶の湯とはただ湯をわかし茶をたててのむばかりなる事と知るべし~という有名な千利休さんのことばがありますが、余白を読むことが好きな日本人にとっては意味深いものです。知識としての言葉ではなく、感じさせる言葉。そしてそれは一度ストンと心に入ると忘れることがありません。言葉とはスゴイものですね。
2007年08月26日
コメント(9)
-
Re: ラグジュアリーホテルの魅力
東京のホテル見学をしてきました。カテゴリーでいうと、高価格に位置するラグジュアリーホテル。今回の目的は、春にオープンしたリッツカールトン東京です。東京ミッドタウンという導線からか、おそろしく人でごった返していました。人が多いのは、いいのでしょうが、本来のリッツカールトンホテルのよさは、裕福な層 数パーセントを対象にした、余白と余裕に満ちた空間です。やっと席を確保して、紅茶を注文。ティーバックをくくりつけたティーポットがなぜか、ファーストフード店のそれとだぶってしまい、そうそうに退散しました。ティーバックは決して悪くありません、、、そして、わたしが宿泊者であれば、この喧騒から離れて、本来の優雅なステイを楽しんでいたことでしょう。ただ、人気がありすぎて、あまりに混み合っていたようです。翌日は、横浜のホテルでランチをとりました。最後の紅茶は、お皿がなんと二枚がさね、、、老舗のホテルです。食べたり、飲んだりすることは本能、、、食欲を満たせばいいことですが、ひと手間加えることによって、「おもてなしの心」が伝わります。テーブルから直(じか)にではなく、クロスをかけ、美しいお皿を重ねることで、上へ上へと目線があがり、わたし達自身の背筋もすっと伸びるようです。外資系ホテルばかりが話題になりますが、日本の老舗ホテルもなかなかラグジュアリーですよ。是非お試しを。
2007年07月21日
コメント(4)
-
Re:人を元気にするもの。
何をするのも面倒くさいと、某男性はつぷやきます。 ホテルの仕事中のことです。 聞いてみると、それは奥さまを亡くされてからひどくなり、 ご飯もお風呂も、最低限のことで済ませ、 ただ仕事だけはいつもどおりにしているのだとか。 逆に考えれば、湯気のあがる食卓、掃除の行き届いた部屋の匂い 、、、、、なんていうのは、しあわせの象徴なのかもしれません。 野菜はしっかり、、、タバコはほとほどにネ! おせっかいな女性ふたりが、口で言ってはみたものの、 その後どうなっているのか、、、、、実のところ心配です。 昔、「民藝運動」というのが、にぎやかだった時代があります。 暮らしのなかから生まれた美に注目する、、、そんな運動だったような 気がします。 民藝の特徴は、「健康的な美しさ」です。 日々の暮らしで使う、食器や家具、敷物など、、、名のある職人さんでは ないけれど、長く使うのに耐える丈夫さと過不足のない機能性が、 「健康である」とされる美しさ・・・の由縁とか。 愛する人と離別した悲しみが、日々の暮らしと向きあうことを拒否している のかもしれない男性。 暮らしのなかには、健康的なことがあふれいます。 高級レストランの食事より、数倍、自分を元気にしてくれるなにかがあります。 コンビニのおかずもおいしいものが増えましたが、それをそのまま箸をつける のでは、食事とはいえません。 そのおかずが映えるような色のさらに移してはじめて、食事の準備が整う ようにも。そして、そんなことの繰り返しが人を健康にしてくれるのかな~とも 思います。
2007年06月02日
コメント(7)
-
Re: いやされるとき。
癒し、、といえば、アロマテラピーや、森林浴など、受け身のイメージが強いものです。癒してもらう、、、。JR尼崎事故から2年がたった先日、事故の被害に遭われた方をテレビ各局が特集で、クローズアップしていました。某私大の女子学生、、Mさん。事故のことを誰にもしゃべりたくない2年だったそうです。2年たって、、やっと彼女は実家に戻り、自分から「メンタルケア」に行ってみようと前に進み始めました。心は、自分の心でしか癒すことができない、、、。まわりは、寄り添って、その人が自分の足で進むのを応援することしかできないのだ、、、。事故のことを語るMさんを見ながら、少し癒されてきたのかな、、、としゃべることができた彼女を見ながら思いました。Mさんを取材してきたテレビ局の一人がたまたま親しい女性。彼女は記者生命をかけて、真摯に作ったと、、、メールで知らせてくれました。最近、わたしも母が突然検査入院することになり、なんともやるせない日々を過ごしていましたが、つらいときの「心のつかいかた」、、癒されるということの意味など、自分のことと重ねながら、考えることの多い日々でした。癒しという言葉を使うとき、様々な角度があることを覚えておきたいこの頃です。終><配信停止URL http://my.plaza.rakuten.co.jp/index.phtml?func=diary&act=push
2007年05月04日
コメント(6)
-
Re: もうひとつのホテル
ホテルの中の「もうひとつのホテル」とも呼ばれるクラブフロア。すこし割高ではありますが、専用ラウンジで、こだわりの朝食やティータイムなどのおもてなしがあり使い方によっては、とてもお得。大阪の老舗ホテルとして有名なリーガロイヤルホテルの「ザ・ナチュラルコンフォートタワー」は、器や使う紙一枚にもこだわった、さすが!のクラブフロアでありました。まず、五感を刺激する音、、香り、、色彩。洗練された身のこなしのコンシェルジュ。エレベーターを降りた瞬間から、もうひとつのホテルの扉がひらかれたような期待感が高まります。ポイントは、「お客様が何をもとめているのか」という原点に徹底的にこだわったこと。社長の強い意志のもと、優秀なスタッフが、楽しみながら、時には生みの苦しみを味わいながら「もうひとつの非日常」を創造していく過程が垣間見えるようです・・・。何もない箱だけの空間に、家具を入れ、リネンを選び、照明を調整して、花を飾る、、、そして、お客様の喜ぶ顔を唯一の働き甲斐にしているスタッフが登場する、、と、いつのまにか、ホテルのテイストが浮かび上がってきます。ホテルとはやはりひとつの舞台だと感じるクラブフロア視察でした。
2007年02月18日
コメント(4)
-
Re: さもないことに・・・。
某編集者のご両親は、かなりのホテルフリーク。 関西を中心に一流ホテルのスイートルームはほとんど、長期ステイ でご経験済みです。 で、、、最終的に落ち着いたのが、神戸の、、、とあるシティホテル。 決め手はスタッフのフレンドリーな対応にあったようです。 孫のような若いスタッフが、「おかえりなさい」と、名前を呼んでくれる、、、 お土産を買っていくと、行く先々でお礼をいってくれる、、、 もう、お爺ちゃんの心はわしづかみにされているそうなのです。 同じように、お土産を買っていっても、ホテルの対応はずいぶん違うのだとも。 ほんの「小さなこと」が、お客様の心を掴むのですね。 料理研究家 栗原はるみさんの成功の要諦は、 主婦として日常の「さもないこと」を大切にしてきたこと、、、だそうです。 ・・・先日、お客様にお礼状を書いたら、後日お電話をいただきました。 (大体、お礼状に返事がくるのは稀です) 携帯電話でとれなかったため、、、その返信をしようかどうか悩んでいると その2、3日後にもう一度、お電話が。 有名企業の会長さん。 「さもないこと」を大切にする方でした。
2007年01月27日
コメント(13)
-
Re: お茶会で・・・。
新年、いかが御過ごしですか。 新年といえば、お茶会です。 今年はじめてのお茶会に行ってきました。 ホテルのバイキングマナーと同じくらい、お茶会では「譲りあう心」 が必要!? とされますが、行くたびに勉強になります。 なぜなら「我さきに、、」と、順番待ちの列が、ちょっとした小競り合いになった り、 「どうぞお先に、、」なんて言おうものなら、最後の方に追いやられてしまいます。 でも、たまに「お先にどうぞ」と云ってくださると、なんて素敵な方だろうと、 なります(^^; お茶をやっていてそんなこともできないなんて、という声も聞こえそうですが、 会費を払っていたり、自分の権利が主張できるときには、 なかなかどうして、譲れない気持ちになるようです。 そんなお茶会の帰り道、、「江戸しぐさ」という本を読みました。 今は少なくなりましたが、「銭湯つきあい」にも、社会で人と上手に つきあうためのエッセンスがたっぷり、、詰まっているのですね。 マナー教室にわざわさ行かなくても、昔は身近な生活のなかに、 大切なマナーの見本があったようです。 ~先ず隗より始めよ~ と、いうわけで、今年のわたしの目標は、もういちど、そんなところから 点検してみたいな~と思います。 どうぞ今年も宜しくお願いします(^^)v
2007年01月03日
コメント(8)
-
Re: 放下著(ほうげじゃく)
久しぶりに茶事の亭主をしました。前日まで、バタバタしていて、買物などの準備はしたものの、心の準備は、まったくできていなかった・・・、何とも後悔の残る茶事でした。掛物は、「放下著」 ~禅語で「投げ捨ててしまいなさい」一年の余計なものをすぺて、きれいにしましょう、、そんな気持ちも込めて、選びました。後日、禅寺の老師さまに、この話をしたとき、いいことは、投げ捨てたくないものです、これではだめですか、、と訊いてみました。…よかったことはとっておきたい、その気持ちはわかります。でも、すべては表裏一体。愛情も、裏返せば愛欲に変わります。何もないことが一番です。一点でも、曇りをつくると、それがいつか逆のものに変化するのですよ、と。サダム・フセインも、最初は正義の心をもっていた、、、そんな話を訊くうちに、やっと、自分自身が作った茶事のテーマに、「。」を打っていただいたような気持ちになれました。えいっ、、と投げ捨ててしまいましょう(^^)よかったことも、わるかったことも……。浮かんでは消え、消えては浮かぶ、、自分の作ったスクリーンには保存ファイルは、なしとして。今年も一年、、ありがとうございました。いっぱいの感謝をこめて(^^)
2006年12月31日
コメント(6)
-
Re: 心のリセット日
友人達と温泉にでかけてきました。 山あいの鄙びた温泉郷の中にあって、ここだけはリピーターが ひきもきらないと評判の宿。 何がリピーターの心をそんなに惹きつけているのか、 ホテルウーマンとしては、経験してみるしかありません(^^; 宿の部屋は、ごく普通。 到着したときも、期待に胸ふくらむような、空気は感じられなかった・・・。 でも、そのあとから、小さなサービスが次から次へ。 それは、プロのサービスというよりは、親戚のおばちゃんが 親切にしてくれているような、「温かくて」ここちよいものでした。 久しぶりに石焼イモを食べたり、里山の野菜が、やさしいサラダや お浸しになって、なんと50種類も。 個性の強い料理を食べるより、体のすみずみが元気を取り戻して くれそうな、滋味あふれるお料理でした。 暖炉の前で、おじいちゃんがたててくれた珈琲を飲んだり、 窓の外でおばちゃんが温泉卵を作っているのを見ていると レベルの高い優秀なスタッフに囲まれたサービスではなくて、 心がゆったりとする「大家族」のサービスなんだな、と感じた次第です。 人は人に癒されるんですね。 「ホスピタリティ」 色々な定義はありますが、体感できる宿でした。
2006年12月22日
コメント(11)
-
Re: 風がふいています
~大いなるもののあることを 今日吹く風の涼しさに知る~ 山田無文外にでるのが、毎日楽しい・・・。木陰と日向が同じくらい気持ちがいいのは、春と秋の特権かもしれません。テレビをつけていると、ありし日の山田無文老師のインタビューが流れていました。それまでずっと病気に苦しんできた老師・・・。ある日感じた風に、いつもと違う感覚をあったそうです。この風は、「空気」が存在するから、流れてきているのだな、空気というものは、自分が意識するしないにかかわらず、存在してくれる、あぁ、なんとありがたいと感じたそうです。 その日を境に老師は毎日散歩にでるようになり、食事もとれるようになって、すっかりお元気になられたのだとか。禅の生活は一言でいうと、「最低の生活に最高の感謝をささげること」最近は、簡単に夢をかなえるとか、ラクをして大きな成功をおさめるというマニュアル本が流行っていますが、不用のものはなるべく持たないかわりに、見えない心の修養を積み重ねた人が、一瞬の風に気づかされた話には、なにか順番が逆であったな~と感じたことです。
2006年10月28日
コメント(10)
-
Re: 余白、余韻、隙間・・・。
昨夜は各地で観月会が催されたようですね。満月、、完璧な美しさでしたが、桜が散る前のような一抹の寂しさも感じてしまったのは、肌寒い秋風のせいでしょうか。(それとも、歳のせい!?)久しぶりにのんびりと、過ごしています。「自然の営みののんびりさ」と違って、日々の生活はいつもせわしなくあいている隙間や余白を次から次へと合理的に埋めていっているようにも。放っておいても、隙間や余白はできてくるものなんですが、あえてそれはゆるされないような、そんな厳しさも感じます。月の満ち欠けと同じように、人の身体のエネルギーにも、きっとリズムがあるのでしょうね。連休は、自然の中で過ごします。コントロールしすぎた心と体をすこしゆるめて、恐れたり、泣いたり、笑ったり、、、できたらいいな~。
2006年10月07日
コメント(8)
-
Re: 禅寺の鐘は、ならない。
もう何年も通っているというのに、最近やっと気がつきました。 ・・・禅寺の鐘はならないもの。 なぜなら、こちらから聞かなければ、老師はわたしの聞きたいことには 答えてくれません。 わたしは福岡に行きたいのか、、それとも東京に行きたいのか。 まずそこがスタートです。 体が行きたい方向にむけば、次はそこに行くための、 方法を探ります。 そのためのヒントを教えていただく、、場。 逆に、ホテルではこちらから鐘をならして、お客様の心にできるだけ 近くなろうと努力します。 禅では言葉(知識)がときに、理解(気づき)のさまたげになりますが、 サービス業では、言葉はとてもよい働きをしてくれます。 たとえば、あいさつ。 そんなことを考えているから、わたしの坐禅はいつも騒がしい。。。 心の鐘が鳴りっぱなし、です。
2006年09月10日
コメント(8)
-
Re: サービスあれこれ・・・。
先日立ち寄ったレストランで、アルバイトらしき女性に、「水をおそそぎしてよろしいでしょうか?」と聞かれました。「お注ぎ」の間違い?とも思いましたが、そうでもない様子・・・。なんとなく、気持ちがすっきりせず、、そんなことを考えていると、お客様との雑談で、レジでお釣りを渡すときに、両手でしかも、ちょっと手にふれるように渡してくれるレストランが多くなったいうお話。「それは、うれしいんですか??」と聞いてみると、他人にされると案外「気持ち悪い」ものなんだとか・・・。きっと、お店の責任ある立場の方が考えたサービスやマニュアルなのでしょうね。もし、わたしが上司から今日からそういう風にサービスしなさいと言われたら、どんな言葉で「拒否」しよう、、、とかどう言えば波風が立たないんだろう等、余計な心配をしてしまいました。。。これも時代を反映しているのでしょうか、ね。
2006年09月01日
コメント(6)
-
Re: 女が畳をかえるとき・・・。
今、昼寝から目が覚めました。い草のまくらに頭を載せた途端、、数秒で、眠りに入ったようで・・・。疲れていたんですね~。畳には、日本人の体をちょうど癒してくれる程よい硬さがあるようです。それは、西欧人のペッドへのこだわりに匹敵する、、と私は思います(^^)最近、二人の女性が畳をかえた話をききました。ひとりは、敬愛する高級料亭の女将さん。さるVIPが世間の騒ぎから隠れるように、お泊りにこられたときのこと。かなり心労の激しい顧客のその方に何をして差し上げようと考えたそうです。いろいろと考えた末、客室の畳をすべてかえて差し上げたのだとか。畳の清々しさに、すぐに気づかれ、何よりも喜ばれたそうです。女将いわく、「新しい旅立ちをイメージして」プレゼントしたそうです。もう一人は、お茶の仲間。自宅でもあるお寺で、茶道のイベントがとり行われることになり、わずかばかりの室料はかたちとしていただき、自費で茶室の畳をすべて取りかえたとか・・・。お金に換算すれば、どちらも割には合いませんが、、、さすが!!と声をかけたくなりました。
2006年08月13日
コメント(10)
-
Re: 軽井沢の休日
去年オープンしてから、ずっと行きたかった「星のや 軽井沢」ちょっと贅沢な宿泊になりましたが、緑と水と「モダンな日本」が共鳴しあった 心にしみるリゾートでした。心に残ったのは、「名札」です。全員、名前のわかるものをつけていないのです。もちろん支配人も。普通は、フロントあたりで、そのホテルの人間関係を感じることもあるくらいです。かっぷくのいい支配人がエントランスで、偉そうに仁王立ちし、フロアをやたら動きまわるマネージャーの姿。スタッフは、それら上司の顔色も伺いながら、一生懸命接客に励んでいる・・・。(あくまで、イメージです(^^) )でも、「星のや」さんには、支配人らしき人影も感じられず、ひとりひとりが責任をもって、サービスに努めている、、そういう雰囲気がとても心地よかったのです。あとで、スタッフに名札のことを訊いてみました。ホテルの中を「フラットな組織」にするためと、社長の方針であえてつけていないとのこと。星野社長は、ホテル再建で、今 最もホットな存在の方。宿泊するお客様の五感をひらき、呼吸をとりもどす・・・。語源に忠実な「ホスピタリティ」を感じた旅行となりました。
2006年07月20日
コメント(12)
-
Re: 禅の魅力
久しぶりに老師のお話をきき、禅の魅力を再認識しました。 わたしたちはいつも、心を使いすぎて疲労している・・・。 その原因は、対立にあると。 次々とおこること、、、はどんなものでも「頂く」気持ちが肝要です。 病気やトラブルなど、できれば遠慮したいことの方が多いけれど、 ままならないのが世の常です。 まずは、素直に受け入れて、そのことで必要以上に心を使いすぎない、、 ことが肝要、、、そんなお話でした。 それには、坐禅で体の腹筋と背筋を鍛えていると、体も自分を助けて くれるとか。 腰を入れる、、、という言葉がありますが、片手間ではなく、全力であたると いうことだそうです。 坐禅では、腰をいれて坐ること。
2006年07月09日
コメント(8)
-
Re: 鴨川で夕涼み
京都 鴨川に大きな床がはられる季節です。昔の鴨川は、葦や草がおい茂っていたそうで、こういう遊びは今だからできることかもしれません。まして、川の傍で食事をすれば、蚊の大群に襲われそうですが、床の下には大きな蚊を集める装置があるそうで、心配無用。「幾松」という、粋な名前の旅館で、しばし京都の贅沢を味わいました。女将の挨拶がまた、秀逸でした。心をつかんで、コミュニケーションするというプロの挨拶。ひとりひとり、違う言葉で、ほんのすこしだけ、心が通ったな~という気にさせる会話。料理より、ロケーションより、、、記憶に残りました。後日、大阪の某所の窓口で、ずいぶん待たされるので、何事かと耳をそばだてていると、「アイスクリーム」の差し入れが溶けるから、早く食べてこいと催促しているのでした。雲泥の差です。「主人公」という言葉が頭をよぎりました。どうふるまっていくのか、、自分の居場所は自分が決めてきたんだな~と思ったことです。
2006年07月01日
コメント(6)
-
Re:実った稲穂のような人
たまたま、そこに居合わせたご縁で、イエローハット 鍵山相談役とお目にかかることができました。去年お世話になった、禅寺のトイレ掃除のことなどご報告し、にこやかに、きさくにお話してくださいました。「実った稲穂のように」、、ほんとうに、謙虚で実直なイメージの方。わたしが尊敬する方の共通点でもあります。帰り際、全員たってお見送りしましたが、人は一人で輝くのではなく、まわりに引き立てられて、なお一層輝くのだな~と感じ入りました。「自己顕示欲」という悩ましい欲に、ふりまわされたりする日常ですが、いい出会いをいただきました。「忘己利他」おのれを忘れ、他を利するこれも、わたしのまわりで活躍されている方の共通点。にぎっている掌をゆるめるように、少しずつ力をぬいていければと思います。今日はかえるの合唱を聴きながら、ひさしぶりに深呼吸、、、。
2006年06月17日
コメント(13)
-
Re: 灯火ゆれる静寂の茶事
京都のなかでも御寺として格式ある泉湧寺。 「浄敬庵」は、そこから歩いて数分の風情ある茶室です。 ちょうど黄昏の刻々と暮れていく時間にそって進行する 「夕ざりの茶事」は想像以上にロマンチックで、非日常的。 なんと、うれしいことにこの日、わたしは正客をおおせつかり、 冷や汗と、感動を両方体験した一日でした。 いわゆる初座は、まだ明るく、このときに、懐石料理をいただきます。 「和の作法」の原点ともいえる食べ方、問答。 料理も、亭主が手作りしたもので、さすがに旬を先取りして、美しい。 お腹もそろそろ満たされて、フッと外をみると、もうとっぷりと日が暮れていました。 まるで、「壷中の天」 再び、露地へとうながされ、いよいよ後座のスタートです。 和ろうそく独特の力強いゆれを見ていると、そこに座らせていただいた 四人の心がすっと寄り添うような感じがして、 ほの暗さの中にも、温かさが伝わるような、なにかとても懐かしい、 不思議な感覚におちいりました。 そして何といっても「静か」なのです。 音のない静けさと、わたし自身の心の静けさ。 波だつ心がすっーと落ち着くような心地良い呼吸をとり戻すことができました。 「浄敬庵」は、亭主であるKさんが、ひとりでおもてなしの準備から、茶事までこなす ひときわ贅沢な空間です。 ホテルのおもてなしの原点は、この茶事の中にこそあると感じたひとときでもありました。
2006年05月21日
コメント(12)
-
Re: アンティークに囲まれて
天皇家ゆかりの料亭。「荒手茶寮」で食事をする機会に恵まれました。菊のご紋が入ったお部屋で、次の間がふたつあり、ひとつは脱いだ着物に香を焚きしめる部屋、もうひとつは家来が警護のために隠れている部屋なのだとか。100年、時代をさかのぼるだけで、ずいぶんタイムスリップしたような気分になります。まるで骨董美術館のような重厚感。この建物が建てられた時代を聞いてまた、びっくり!!戦争で消失しまい、戦後に立て直されたのだとか。わざわざ古材を各地から集めて、何百年も前に建てられたような風合いにしているのだそうです。茶室によくある「わび・さび」が効いているというのか、なんとなくどんよりした空気感に、昔泊まって眠れなくなった京都の古い旅館を思い出しました。ぜいたくなことですが、すべてが古いとかえって落ち着かなくなるのです。こういう施設を利用するとき、好みはふたつに分かれるようにも思います。その時代に合った快適性をさりげなくとりいれて、本来の雰囲気をうまく崩しているところがいい人と、頑なまでに細部にこだわるほんものを愛する人。白洲正子さんのような方がいらっしゃったら「この馬鹿者が!!」とお叱りを受けそうですが、、、。ともあれ、食事は時間が止まったような非日常的な空間のおかげで、ゆっくりと楽しむことができました。そして何より、お料理を運ぶ係りの方の気さくなサービスが建物と対照的でほっとなごんで、食事も数段おいしくなったことでした。
2006年05月05日
コメント(4)
-
Re: コーチング体験記
コーチングを体験しました。 親しくしているMさんが新しくコーチングビジネスを 始めるというので、ラッキーなことにクライアント役として 白羽の矢をあてていただいたのです(^^) 受けてみて感じたことは、「心がさわやかになれる」こと。 電話の最初は、忙しさで頭も体もドロドロ?している のですが、Mさんのリードにつられて、「そういえば」とか 「そっか」なんて、思っているうちにあっという間に1時間。 自分のことだけで、1時間たっぷりしゃべれることが、 こんなに気持ちのよいものだとは思いませんでした。 そして、自分のことを知らない、、、ということも今回知りました。 私らしさって何?と聞かれて、いまだにわからないのです。 カウンセリングとも似ているようですが、 未来の自分と対峙できるという意味では、べつものなのでしょうね。 迷子の話をおもいだしました。 迷子は、自分のいる場所、これから行く場所、道を聞く人を知らない、、、 のが条件とか。 そういう意味では、わたしもまだちょっとした迷子かもしれません。
2006年04月22日
コメント(12)
-
Re: ウォーク・ジャパン
奈良を一日歩いてきました。 ちょうどお釈迦さまの誕生日にあたり、お寺はどこも 「灌仏会」という、甘茶をかける行事でにぎわっていました。 もうっ、、、人が多く、、、鹿でさえ、観光客からもらう「鹿せんべい」に うんざりといった様子。 どこへ行ってもこんなもんだと思いがちですが、穴場はまだまだ残っています。 先日も五街道のひとつ、「中山道」を歩いて旅するツアーの主催者と お話する機会に恵まれました。 旅するのは、みんな外国人。 しかも、歩き旅。 日本人が行きたい場所には、彼らは向かわず、 自然のエネルギーや、土地の日常生活の匂いをかぎながら、 日本を感じて、旅しているのだとか。。。 とても人気のあるコースで、外国人のみるガイドブックでは有名なんだそうです。 「ウォーク・ジャパン」 次回は、そんなコンセプトで歩いてみたいものです・・・。
2006年04月08日
コメント(6)
-
Re: 季節の移ろい。
今日も雨が降っています。 冬から春へ 自然をみていると、すべては変化している、、そして自分も春や夏をへて、 秋、冬へと移っていくのだな~と思えます。 その小さな単位、一年のなかで、体は冬の間に蓄積した毒素を排出しようと 自然界の「苦い食べ物」をほしがるのだとか。 ふきのとう、菜の花など、旬の野菜はみな苦い・・・。 おもてなしの食卓でも、この「はしりの食材」は、とっても日本人好みです。 先日、漢方の先生から「病気にならない生き方」という本を薦められて 読んでみました。 ベストセラーになっているのですね。 牛乳、マーガリンなど、体によくない食材のことがかかれてあり、 乳製品好きなわたしなど、戸惑うほどでした。 でも、牛乳には推進派と反対派がいて、白黒つけるのは難しいとも。 体にきいて判断する、、、そんな自然な体でありたいと思うこのごろです。 春の雨もまた、恵み。。。
2006年03月18日
コメント(17)
-
Re: プロのおもてなし
久しぶりの日記です。 今日はお客様と一緒に、高級料亭の下見に同行してきました。 ここの女将さんを紹介するのが、わたしの役目。 敷地2000坪の「桂山荘」は、裏六甲という立地もあって、雪がお庭に まだ少し、残っていました。 お客様と女将さんの気もあって、食事後も話がはずみ、 ついつい私も個人的な好奇心からこんな質問を・・・。 「こういう高級料亭にくるときの、客の心得を教えてください」 まず、玄関で脱ぐ靴が大切です。(かならず、磨いてくださいね) 二番目は、仲居さんなど、今日お世話になる人への「お世話になるよ」と いう挨拶。 三番目は、「客」だという一方的な気持ちではなく、お世話してくれる人へ 、、、どんなもてなしを望んでいるのか、それを伝えるちょっとした気配り(サイン) 襖(ふすま)一枚に、とても意味があるのだそうです。 お料理をもって入ってくるときは、話に夢中になって無視するのではなく、 視線を少し寄せるだけで、お世話する人も、だんだん息が合ってくるのだとか。 その後、帰り道に茶室をいくつか見学して帰りましたが、最初の「あまりに行き届いた」 おもてなしの空間を体験したせいで、どこも、行き届いていないのに、 敏感に反応してしまいました。 「落ち葉一枚でさえ、今日掃除しようか、明日まで残しておこうか悩むのよ」 そんな女将さんの言葉に敬服です。
2006年03月04日
コメント(9)
-
Re: 見られ力。
自分のことが一番わかっていないのは、自分自身かもしれません。見ることはあっても、「見られる」ことはあまり意識していないもの・・・。先日、お茶の先生がテレビに取材されることになりました。ドキュメンタリー風に、日々の生活を追っていくのですが、お茶の稽古のようすも取材していただきました。わたしも、ちょっとだけ、映っているかもしれません。お客様を迎える場面では、あるく位置をまちがえ、炭を直す場面では、ナント「お香合」をころりん、、、と落としてしまいました。恥ずかしいこと、この上ありません。ある女優さんと写真をとったときに、どの写真も決まっているので、一緒にとってもらった社長さまが、どうしたら、そんな風にとれるのですか? と聞いたそうです。「いつも見られることを意識していますから」、、とお答えになったとか。 なるほど。。。意識を少しかえることで、人は変わるものなんですね。もう少し、「見られ力」を鍛えて、出直したいと思います(^^;
2006年02月14日
コメント(8)
-
Re: 上質のコミュニケーション
時間がなくて読めなかった資料や、パソコンに定期的に配信される情報、、、 地下鉄などの移動中に、やり残した宿題でもするように、必死になって読みますが、 読んでしまえば、自分には必要のない情報も多くて、がっかりすることも・・・。 情報過多で、本当に自分に必要なものがみつけにくくなりました。。。 量ではない、、 質が大切といえば、「コミュニケーション」もそうではないか、と。 時間があって、沢山おしゃべりしても、親しくなれない人がいます。 反対に、すき間のような時間をぬってしゃべった一言で、生涯の親友になることも。 そのヒントをわたしはいつも茶室のなかに発見します。 「非日常」と「礼儀作法」 コミュニケーションには心をひらくことが前提だと思うのですが、 実はわたしはこれが苦手。 相手を意識しすぎて、壁をつくってしまうのです。 サービス業を意識しすぎるせいか、相手の心をひらくことを考えすぎて、 自分の心がひらけない・・・。 そんな自分を変えてくれたのが、「茶室」という非日常性でした。 仕事をはなれ、「礼儀作法」に終始する愚直なトレーニングのなかで、 まずお茶の仲間との「上質なコミュニケーション」を体験。 お客様の心をひらくためには、まず自分の心から、、ということを 教えられました。
2006年02月04日
コメント(8)
-
Re:お客様からのご依頼。
女性の営業って、得することが多いでしょ、、、と言われます。 わたしは、損か得かといわれれば、半々としか、、、。 なぜなら、女性は女性のお客様に嫌われると元も子もなくなりますから。 先日、ホテル取材でお世話になった記者の方から プライベート旅行のご依頼がありました。 「妻がよろこぶ旅行」をコーディネートしてほしい、、とのこと。 もう一度取材してほしい、、、なんて下心もありますから(^^; 「おまかせください!!」と高らかにお答えしました。 とくに男性の場合、奥様とか、同伴した女性が満足してくれることが、 結構大きなポイントになっているような気がします。 高級クラブに女性と同伴で行くと、ママさんは男性にはかまわず、 隣の女性のサービスに全神経を傾けるのだとか・・・。 (友人に聞いた話です) 主導権をもっていると勘違いして、ご主人に「熱い視線」など おくろうものなら、あとで痛い目に合うのは必至のようです。 お互い気をつけましょう(^^)
2006年01月27日
コメント(6)
-
Re:営業の楽しみ
人と会うことが好きで、仕事も好き、、、。これはわたしの口癖です。でも、お世話になっている東洋医学の先生が、わたしを長年診ていてどうしていつもこんなに疲れているのだろう、、、と不思議に思われたようです。特に上半身の疲れ方が異常とか・・・。そういえば、肩がこり、目を中心に疲れます。人と会うことは、楽しいと思いながらも、いつも緊張感を背負っている自分。先生は、自分の経験をあげ、毎日病人を診ていると、病気をもらうのではと思われがちだけど、毎日自分は元気をもらっている、、、。 考え方を少し変えるだけでも、疲れ方が変わると思うよ、、と言われました。たまたま今朝の日経新聞に料理研究家の「栗原はるみ」さんの記事を見つけました。毎日の主婦の仕事の単調さに心がすさみそうになったとき、「さりげない」楽しみをみつけて、「自分をリセットする」うち、気分がかわってきたそうです。好きこそものの上手なれ、、というものの、日々の仕事のやり方に、さりげない楽しみをみつけることも、大切なんだな~と思ったことでした。
2006年01月21日
コメント(8)
-
Re: 「見た目が9割」とは・・・。
新年の挨拶まわり、、、互例会など、1月も毎日いろいろな方と お会いしています。 そんな折、「人は見た目が9割」という新書が面白いと、複数の友人から聞きました。 読みたい本が沢山あるので、またにしようと思っていたのですが、 買ってしまいました。 挑発的なタイトルに負けたようです。 参考になる部分があるとページに折込を入れるのですが、 結局2ページくらいしか、折込ませんでした。 決して参考にならなかったわけではなく、この本のタイトルはすごいと 関心しています。 以前、備前焼のお店に偶然入り、留守番をしているおじいちゃんを発見。 おじいちゃんならと、安心していると、「今日は冷えますね~」と 話しかけられました。 その絶妙な間合いに、わたしも引きづられ、とうとう、新幹線に乗る前に、 紙袋2つ分も、備前焼を買ってしまったことがあります。 カリスマ販売員のおじいちゃんの見た目にだまされた訳です・・・。 さて自分はどんな「見た目」で勝負するのか、、、考えてしまいました。
2006年01月16日
コメント(4)
-
Re: 今年の運勢
年末の閉塞感から、ぬけだし、 新しいことが始まる開放感にひたるこの頃です。 休みがあると風邪をひくのが、関の山。 ふだんのペースが一番ですね。 ふだん占いなどに興味がなく、ほとんど知らないのですが、 何かの拍子に「大殺界」に入るらしいと知りました。 ありゃ~と、思っていたら、 これが「勘違い」であることを友人から教えられ、 ちょっとばかり、「ほっ!」としております。 見れば気になるし、占いとは「やっかいな」ものですね~。 というわけで、今年もわたしはこの方のお話を実践することにした次第です。 禅寺の老師さま。 念頭のお話は、「呼吸のめんどうをみる」でした。 あたりまえ過ぎて、ていねいな呼吸をする人が少ないですね。 吸う息は、天からの贈りもの、吐く息は、自分の責任なのだそうです。 長い息を心がけて、「下半身」にエネルギーがたまるよう、 一年間やってみようと思います。 みなさまは、占い、お好きなのでしょうかね。>
2006年01月06日
コメント(6)
-
Re: 「無事」
母の入院、自分の病気と、体調は今いちだったにもかかわらず、 年の後半からは、スイスから近場の京都まで、まぁ、色々な ところにでかけることができました。 旅行というのは、自分の条件が整わなくても、まわりのサポートで、 思わぬところにいけるもの、、、たまたま今年の私はそうだったようです。 稼いだお金は、旅行と薬代に。 気がつけば、スーツなど自分の洋服は買わずじまいの一年でした。 何よりも大切なことは、「健康」でした。 サービスの基本も「健康」、、、。 明日からまた新年がスタートですね。 あと数時間ですが、今年一年「無事」であったことに感謝。 どうぞよいお年を(^^)
2005年12月31日
コメント(12)
-
Re: 京都三昧の日々。
目がさめると、外は雪景色。茶人好みの宿として知られる京都「炭屋」に一泊。しんしんと、ふんわりと雪化粧された、坪庭をながめながら、朝食の前に準備された梅干とお茶を一杯。「炭屋」は、全室趣きの違う数寄屋造りで、たまたま出かけた日には「釜がかかり」、お茶のご接待がありました。一般の観光旅館とはひと味違う、京風の静かなおもてなしが魅力です。売店やロビー、レストランなど、本来、人が集まるスペースがほとんど省略されていることで、互いに顔をあわすことが少なく、こういう静寂が醸しだされるのかも・・・。作家が長期滞在して、作品を仕上げるのも頷けます。・・・友人が急に「雪の金閣寺」が見たいと言いだしました。一瞬少ないかも、、、と思いましたが、大きな間違いで、進路にそって、ぞろぞろ歩くだけ。早々に引き上げ、ランチのために、「上七軒」へ移動。祇園とはまた違う「花街」の家並みを散策し、こちらは人もまばらでした。一行の掛け物、、、ひと群れの水仙を求めて、冬の京都を、とかっこよく企画したつもりが、誰もがそう思ったようでなかなかうまくいかないものです。
2005年12月18日
コメント(10)
-
Re: 心に残るお茶会スタイル
少し前になりますが、 紀宮さまの結婚式は、ほんとうに評判がよかったですね。 なんでも「お茶会スタイル」の結婚披露宴。 一瞬、抹茶でも出されるのかと思いましたが、 簡単なお食事とお茶とお菓子のパーティをそう呼ぶのだそうです。 「心は厚くつかい、軽くさらっともてなす」 そのバランスが絶妙で、お手本にしたいと思った女性は多かったはず、 そんな風に思いました。 結婚式といえば、なにかアッというような演出も楽しみのひとつですが、 ロイヤルとか、セレブといったイメージとかけ離れた 「心のこもった温かさ」が、「サプライズ」でもあったような。 ずっと心の残っていたので、今さらですが、書いてみました。
2005年12月07日
コメント(10)
-
Re: なにやらホテル三昧
ここのところ、なにやらホテル三昧の日々。 ディナーショー、研修旅行、ホテル研修など。 ホテルを仕事にするものには、よそのホテルを体験することが いちばんの勉強。 いろいろな話を聞き、ショーを鑑賞し、高級なディナーや 快適な客室を体験させていただいいて、 さて、思い出そうとしたときに、 記憶に残っているのは、なんでもない感覚的なことばかり・・・。 われながら、悲しくなりますが、 とくに残るのは、そこで感じた「温度」のようなものでありました。 あそこは、なんとなく感じよかったな、とか、 ホテルは立派だったけど、なんとなく冷たい空気が流れていたな~とか。 宴会場から客室まで、隅々まで見せていただいたのに、 フロントの親切だったホテルウーマンの笑顔の方が記憶に残るものなのです。 そして、普段は口にすることのないディナーさえ、今では当日のメニューさえ 思い出せない始末。 美味しかったかどうか、とホテルスタッフのサービスの手際のふたつ位しか 思い出せません。 これは個人的な資質によるのかもしれませんけど・・・(^^;
2005年12月01日
コメント(6)
-
Re: ちょっと疲れ気味です。
クレーム発生。 ホテルの現場と、旅行社さまとの板ばさみになりながら、 「からみあった糸をほどいていく」ような作業をくりかえしています。 「もう二度と使わないからな」なんて、言われても、「めげない」のです。 そう啖呵をきっても、よくしたもので、お客さまから、またそのイヤなホテルに リクエストがあがる可能性だってあるのです。 だから、基本的な問題点はもちろん改善して、相手が次回も声を かけやすい状態にまでリセットしてみる。 まあっ、そんなに上手くはいきませんが、気は心ですから。 でも正直いって、疲れます。 わたしだって、言いたい放題で、プイッと横むいてみたい~。
2005年11月17日
コメント(12)
-
Re: 控えめの美学。
先日、やっとトイレ掃除ツアーにでかけてきました。 大阪からは、12名参加。 人が人を呼び、「なんで、高いお金を払ってまで、そんなことするの?」と いわれそうですが、感動のトイレ掃除になりました。 何が良かったのか、後でアレコレ考えてみました。 まず、無言の気配りが随所にあったこと。 着替えの部屋に「そっと置かれた」タオルと石鹸。 掃除をする前から、周辺の掃除をして待ってくれていた 「掃除に学ぶ会」のみなさん。 方丈で、抹茶を点ててくださり、 銘々に色紙を準備してくださった禅寺の老師さま。 「下座の行」といいながら、にぎにぎしいツアー。 楽しく、にぎやかで、「押し付けがましさ」のないところが 今回のトイレ掃除の魅力でした。 ひとりですることが「控えめ」ではない・・・。 なにか良いことをするときは、こういう風に楽しんですることが 相手の負担にもならず、互いが気持ちよいことを 改めて知ったことでした。
2005年11月11日
コメント(6)
-
Re: 和のたしなみ
チップの渡し方や、お礼状の書き方、、、浴衣の紐の結び方から、 お茶の飲み方まで。 和のたしなみを知らない人が増えているのかもしれません。 もちろん、わたしも含めてです・・・(^^) 雑誌やカルチャースクールでも、最近クローズアップされているのを よく目にします。 わたしもお茶を始めたのは、坐禅の後にいただく抹茶を 上手に飲みたいのがきっかけでした。 その後、お箸の持ち方から、お道具の扱い方まで、ついでに いろいろと身につきました。 でも、「和のたしなみ」とかマナーは、やっぱり実践で失敗しないと 身につかないように思います。 美しい本を何度読んでも、結局、忘れますから。 「千家十職」のお道具をひとつでいいから、手にいれなさいと いわれました。 それらしく扱っても、写しは写しの扱い方にしかならないようです。 本物に触れたいものです。
2005年11月03日
コメント(11)
-
Re: 記憶にのこるパーティとは・・・。
大きな予算を使う企業のパーティは、主催側の腕のみせどころ。 でも、欲張りすぎて「焦点がぼやけて」しまうこともよくあります。 某新聞社の移転記念パーティは、社長さまの挨拶も 来賓の挨拶もない、、、いたってシンプルなものでした。 お料理はビュッフェ料理を最小限にして、ほとんどは屋台で提供。 「松茸の炭火焼」「フォアグラのステーキ」「ふかひれラーメン」など、 抜群の素材がならびます。 主催者の方にきくと1500名ほど来られていたそうです。 足して、引く、そのバランスが絶妙でした。 なにより、1時間はかかる「挨拶」をカットして、鏡わりだけにする「潔さ」。 屋外パーティというリスキーな計画は、花火、文楽などのアトラクションも、 充実していて、「こころの残る」ものでした。 すごいな~・・・。
2005年10月28日
コメント(10)
-
Re: どうみても・・・。
どうみても、「高齢者」にちがいない、わたしの母ですが、納得がいかないようす・・・。さる「敬老の日」に、母あてにきた「高齢者」向けのイベント。紅白のおまんじゅうがもらえるらしいのですが、、、。「高齢者の方」というひとことが気にいらないようなのです。たとえ娘であっても、「だって、どうみても高齢者よ」なんて、いえないのです。それくらい、デリケート。同姓ゆえにわかるのかもしれません。以前、お客様をよぶときに、親しみをこめて「おばあちゃん」と呼んでしまった担当者がずいぶん、お叱りをうけた話も聞きました。「最近どこのツアーに参加してもお年寄りが多くて、ウンザリするのよ」とお客様。「そういうわたしも、年寄りだけど、だから、イヤなの」とも。みじかで、母をみているだけに、「妙に納得」して、お話をききます。それくらいのことで、と笑いそうになった母の態度でしたが、案外、あなどれない問題です。
2005年10月20日
コメント(8)
-
Re: スイスからのお客様
スイスで友達になったCさんが、彼女とふたりで、ホテルに泊まりにきてくれました。スイスから、4週間の休みをとっての旅行です。身動きのとれないわたしにかわって、友人やホテルの仲間が連日フォローしてくれ、とてもうれしかった(^^)もつべきものは、友と仲間です。自分がスイスでうけた「おもてなし」のなかで、一番うれしかったのは、沢山の人とのふれあいでした。車で送ってもらう行為よりも、車の中でかわした他愛のない会話。地元の人達がランチをとっているお店に連れていってもらい、旅行者であることを忘れて過ごす時間。そんな旅行者のくせに、在住しているかのように過ごす時間が楽しかったものですから。彼らが、帰るときにも、来たときよりも友達が2、3倍に増えている、、、そうなれば、うれしいのです。ツアーのときには、そういうチャンスが少ない(ほとんどないかも)のが残念なところです。
2005年10月15日
コメント(14)
-
Re:だから女は・・・。
「だから、女は嫌なんだ・・・」ひさびさに言われてしまいました。お客様との打ち合わせ。わたしの作った見積書にどうも納得がいかなかったご様子です。「堅い、融通がききにくい・・」など、一般的によく言われます。実は、ちょっとばかり、、この後、傷つきました。「○○様からの紹介ということで、誠意をもって作ったつもりですが、どこが、ダメなんでしょうか?」紹介者の顔を立てる、、、最終的に満足していただく、、そんなことをグルグル頭のなかで、考えながら、こんなこと、言ってしまいました・・・。まだまだ、甘い、、ですね~、私は。
2005年10月07日
コメント(16)
-
Re: 陰陽五行とサービス業
阪神タイガースが優勝するかもしれないという晩、 ミナミの某所で、噺家さん数人とお食事をする機会に恵まれました。 といっても、私は記録係、、、のようなものです(念のため・・) ふだんあまり落語はきかないため、、話についていけないな~と思っていました。 、、、でも、師匠が「陰陽がね~」いわれた瞬間、わたしの耳が反応しました。 寄席で、前座の噺家がにぎやかめなネタをしたら、自分は少し静かなネタをする。 陽、陽と続くと、聞く方もだんだん疲れてくるから、 ひとつの寄席の中で、陽、陰、陽というように、変化をつけるのだそうです。 お茶事(4時間くらいかかる正式なお茶席)がまさにこれの連続なのです(^^) わが意を得たり、、。 そうか、落語もお茶事も、そしてホテルのサービスも似てるんだな~と 少しうれしくなりました。 人を退屈させない心遣いは、どんな世界でも共通性があって、 日本人特有のものかもしれません。 タイガース優勝の美酒に酔うミナミの端っこで、そんなこじんまりした 会合もあったようで、、、。(オチなくて、スミマセン)
2005年09月30日
コメント(10)
-
Re: 茶道ライブ
予定していた「京都の茶道ライブ」、、、なんとか無事、おわりました。500名分のお茶をたてる、、、という規模の大きさに不安もよぎりましたが・・・。お茶の師匠は、「500名分をたてると思うな、いつも1人のためにお茶を点てなさい」そのように言われました。準備段階で、気がたって!? (^^; いるときは、決してそのようには考えられませんが、 終わってみれば、この言葉のおもみが、ズシリときます。そういえば、ホテルの上司も、先日似たようなこと、言ってたな~と思ったりしたわけです。いわく「思いつきのサービスはするな、、、1人でも100人でもあっても同じものを提供しなさい」「いましめ」にしたい言葉です。京都の商業施設で行われたイベントは、買物客の方対象で、ほとんどの方がお抹茶は、始めてのようでした。「お茶の味はいかがでしたか?」いちいち声をかけるのは、大変でしたが、1人にかけて、他にかけないワケにはいかないと、一応皆さんに話しかけてみました。「始めてだけど、すごくオイシイかった」と皆、返してくれて、あ~っ、これが「一座建立」、、、場のつながりができた瞬間だなと思ったことでした。
2005年09月26日
コメント(10)
-
Re: すてきなキャリアウーマン。
また一人、すてきなキャリアウーマンを紹介していただきました。 なかなか双方のスケジュールが会わず、土曜日にやっと訪問。 思っていたとおり、「あまり余計なものを身につけない」 ごくごく普通のイメージ。 でも、ふだんのエネルギッシュな仕事ぶりが想像される わくわくするようなオーラを身にまとっていらっしゃいました。 お仕事は、ゴルフ練習場オーナー。 行き帰りのタクシーの運転手さんもおっしゃってましたが、 いつ行ってもお客様で満員の、関西でもNO.1の練習場。 紹介してくださった業界新聞の社長さま曰く、 アイデアあふれるイベントを数々うって、地域に愛される コミュニティスポットのようになっているそうです。 アットホームな雰囲気が随所に工夫されていて、ゴルフの練習にきているというより 「第二の我家」で寛いでいる、、、そんな感じを受けました。 ホテルもうかうか、できません。 うちはホテルなんだから、、、というこちらサイドで勝手に考えた固定観念は、 そろそろ捨てた方がいいのかも。。。
2005年09月18日
コメント(8)
-
Re: ホテルウーマンの雑記帳
~ 和顔施 wagense ~体調も戻りつつあり、さあ~っ、エンジンを巻き直してがんばろう!!とはりきっていたのですが、油断がたたったのか、、がくんと不調の毎日です。鏡に映る、元気のない顔をみるうち、せめて自分自身に対して、微笑んでみよう、と思いました。坐禅をするとき、、、背筋まっすぐ、手を丹田の前で組み終わったら、最後に口元の口角(こうかく)を少しだけ上にあげるのですが、こうすると、こころなしか、「顔か心か、体のどこか」が一瞬「ひらく」ような気になります。すると、体もゆるんで、少しだけ気持ちがゆったり。ほとけさまと同じ御顔、、、を一応つくる訳です。和顔施、、、もともとは「仏教の布施」のひとつとして使われる言葉ですが、まずは自分自身に対して。
2005年09月13日
コメント(6)
-
Re: ホテルウーマンの雑記帳
わたしのお茶の先生はカナダ人です。 ときどき、雑誌などにも取材されていますが、 ハートでお茶の精神性を理解している、「真のお茶人」だと わたしは尊敬しています。 そんな先生のもとで、またお茶の大きなイベントを受けることに なりました。 去年は、某ホテルで300名分のお茶席をつくる、、、そんな話が とある社長様から舞い降りました。 そんな無謀なとその時も思いましたが、今年は500名分とか、、、。 今も電卓をたたきながら、シュミレーションしていましたが、 主催者が望む一時間ではどう考えても無理、、。 私も嫌いな方じゃないから、ますます足を突っ込んで、抜けなくなる、、、。 墓穴をほってるな~、いつもながら(涙) 電卓と紙をにぎりしめながら、、解けない方程式と格闘している所であります。
2005年09月06日
コメント(10)
全270件 (270件中 1-50件目)
-
-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…
- 奥只見湖♫
- (2025-11-27 21:51:41)
-
-
-

- ぶらり、歴史の旅、歴史探訪(歴男、…
- 仙台の旧町名「保春院前丁」(今の住…
- (2025-11-22 00:00:15)
-
-
-
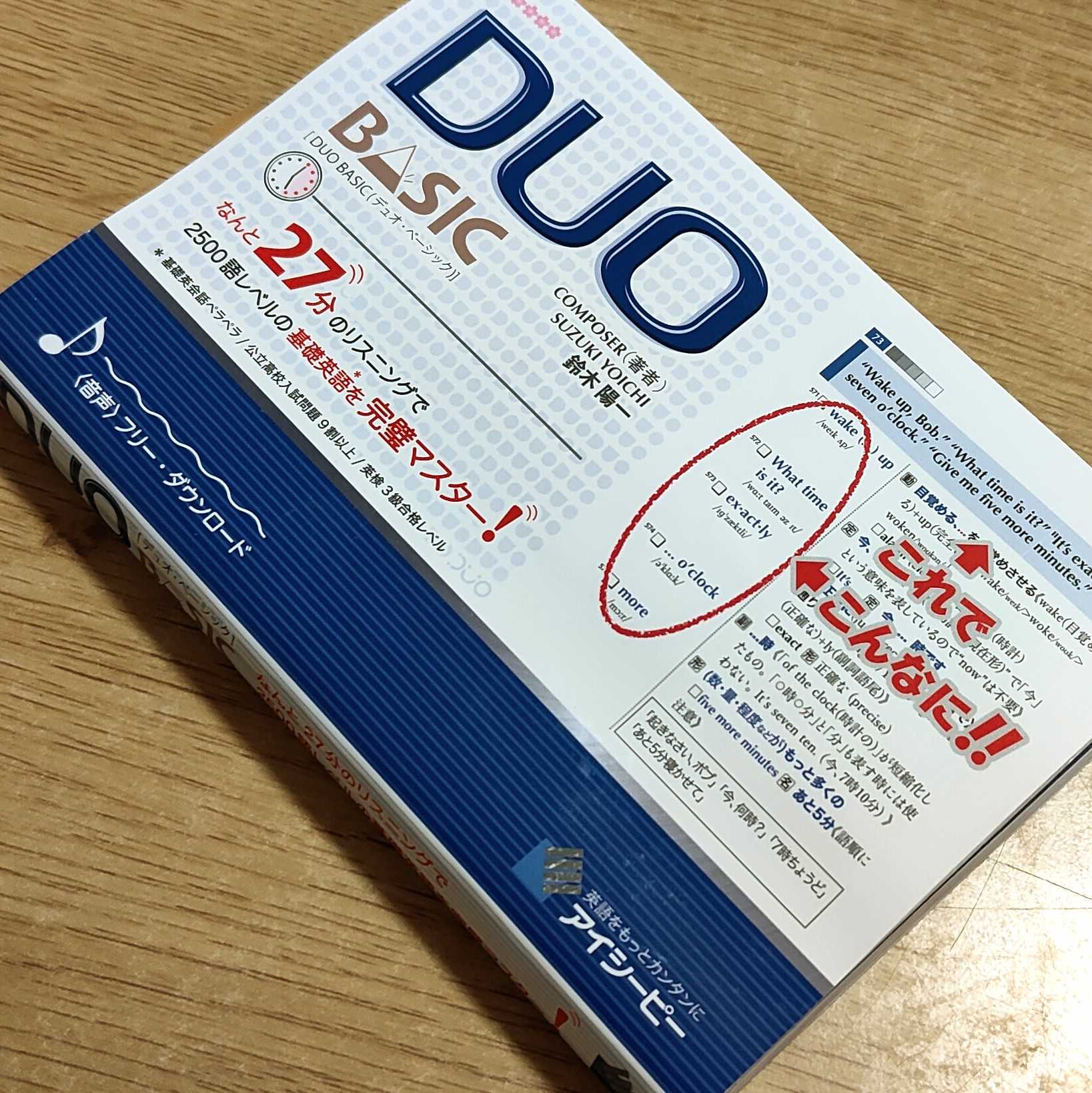
- 海外旅行
- 🇺🇸 My English and My Dream! Part 3
- (2025-11-28 10:08:35)
-








