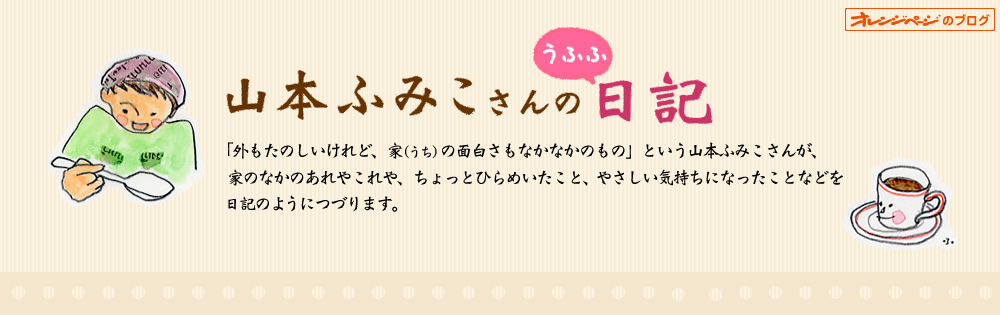サイド自由欄

随筆家。1958年北海道生まれ。つれあいと娘3人との5人暮らし。ふだんの生活をさりげなく描いたエッセイで読者の支持を集める。著書に『片づけたがり』 『おいしい くふう たのしい くふう 』、『こぎれい、こざっぱり』、『人づきあい学習帖』、『親がしてやれることなんて、ほんの少し』(ともにオレンジページ)、『家族のさじかげん』(家の光協会)など。
カレンダー
2025/10
2025/09
2025/07
キーワードサーチ
「家族水入らず」というコトバがあるが、わたしの気持ちのなかには、それが、ない。ないことはないのかもしれないが、そういうことは言わずに暮らしたいと思って、言わずに暮らしてきた。
昨日も深夜、末の子が寝ぼけ眼で、わたしの枕元にやってきて、
「追いだされたから、泊めて」と言う。
どうやら、長女が、終電に乗りそこねた友だち2人を連れて帰ってきて、蒲団が足りなくなり、ひとりを末の子のベッドに寝かせたものらしい。やれやれである。
しかし、ほんとうは、こういう展開をわるくないな、と考えている。
あの家に行けば、寝床くらいはみつけられる、と思ってもらえるのが、うれしいのだ。
姉さんたちが勝手に泊まっていくのなんかは、もう慣れっこだが、もっと小さいひとが、親御さんの仕事の都合で、何日かつづけて泊まるようなときには、こちらもちょっと身構える。身構えるといっても、身構えていることを気取られないように身構えるという程度のことだが。
ふだん通り騒がしくしていれば、まあ寂しい思いをさせてしまう心配もなかろうが、こういうとき、わたしは自分とふたつの約束をしている。
ひとつめは、小さいお客さん(仮にハッパチャン)の名前をいちばん最初に呼ぶこと。
「ハッパチャーン、ごはんですよー」という具合。
この家に暮らしているひとを呼ぶのは、そのあとだ。
もうひとつは、ハッパチャンのお箸を用意すること。
「これ、ハッパチャンのお箸だから、おぼえてね」と、箸を紹介する。こうしておくと、ハッパチャンは、お膳立てを手伝ってくれるときにも、
「これが、ふんちゃん(わたしだ)ので、これが上のお姉さんので、これが、わたしの」という風に、みんなと同じ感覚で食卓につける。んじゃないかな。
ときどき、お泊まりの小さいひとが帰ってしまったあと、末の子どもと目を合わせ、「なんか、久しぶり」「うん、久しぶり」と言い合って、ぎゅっと抱きあうことがある。
だけどね……。
何もかもを、あとまわしにされたこの家の子どもが、ひがんだり、ふくれることは、一度もなかった。もっとも、わたしにしたところで、ほかのことで、子どもがしょんぼりしているときにはわかってやりたいと思うが、この種の文句には、耳を貸さないつもりでやってきた。
うちに「自分の箸」を持つひとがふえたので、紙で小袋をつくり、お名前を書いて、専用のひきだしにしまっている。
このひきだしをあけるたび、自分たちが、一緒に愉しくごはんを食べる仲間をもっていることがひと目でわかる。
ありがたいなあ、としみじみ思う。
「また、ごはん、食べにおいでね」

「ごはん、食べにおいでよ」の箸の一部です。

こういう、「袋貼り」みたいな内職が大好きです。
型紙と名前つけのシールを、箸と同じひきだしに
しまっています。
これさえあれば、同じ長さ、幅の袋がつくれるって
もんです。

箸のほかに、茶碗もそれぞれに用意できるといいんですが、
そこまでは、なかなかね……。
ときには、家の者たちが、ごはんを食べに来てくれたひとに
合わせ、みんなでそろいの茶碗を使うことがあります。
これが、その茶碗です。
(ふたも付いてます)。
私もいれて~とお願いしたいです!!!
一緒にごはんを食べると、
なんだかうれしい。
私の今年の目標は、
ひと月に一客(家族)を迎えることです。
はりきっていろいろ作り、
どしどし出し続けていたら、
「田舎のおばさんみたいだ」(好意的に振る舞うがやりすぎといういみらしい)
と夫に言われました。
(2008/04/18 12:41:04 PM)
まゆさん
はじめまして。
ふみこさんのようなお母さんになりたい、
なんて、娘たちが聞いたら、
何て言うだろ。
「そんなおそろしいこと!」とか。
「もっと、おちついたお母さんめざしてください」とか。
「大変ですよ、あのひとの子どもやるのは」とか。
あ〜。
自覚してるんだ、アタシってば。
そんなことより。
これからも、よろしくお願いします。
ぺこり。
ふ
(2008/04/10 09:59:55 AM)
はこさん
こんにちは。
わたしも、身構えてた。
ひとを招く。
掃除しなくちゃ。
何、つくろう。
あ、こんなもの着てちゃ、おかしいか。
とかって。
でも、わたしの「ふだん」に来てもらう、を
練習しました。
ね。
ふ
(2008/04/10 09:52:28 AM)
のりぃさん
いらっしゃいませ〜。
保育園生活、たのしいでしょう。
わたしも、保育園生活の先輩に肩を押してもらいました。
そうか、わたしものりぃさんの肩、押せたんだな。
うれし。
のりぃさんも、誰かの肩を、そっと……。
ふ
(2008/04/10 09:49:37 AM)
ふみこさんの本を読んで、暮らしぶりに憧れて憧れて。
今日、新刊が出ているのを偶然本屋さんで発見し、
ブログの存在も今日知って・・・
もっと早く知りたかったですー!
とても嬉しいです。
ふみこさんのようなお母さんになりたい!!といつも思ってます。
(3人の子育て奮闘中です!)
これから毎日の楽しみが増えました。
(2008/04/09 10:11:24 PM)
こんにちは。先日はお返事いただけてうれしかったです~。
また遊びにきますね。
最近、私もブログ作ったので、よかったら見てみてくださいね。
http://kokotiyosa.blog62.fc2.com/
です。
では、また。
(2008/04/09 10:25:56 AM)
「ご飯食べにおいでね」ってなかなか人に言えない私です。
つい身構えちゃうのですよね。
なに作ろうとかどんな風にもてなそうとか・・・。
そんなこと考えず、ふいっと気軽に人を誘える人になりたいです。
誘われたお宅に自分専用のおはしがあるって
より身近になれたようで嬉しいと思います。
(2008/04/08 06:12:30 PM)
えいっ!決心し、子どもを預け、働いています。
あのエッセイにどんなに励まされたことか!
その後も、くらしのこと、ごはんのこと・・・etc.
いつもふみこさんの文章を励みにして、そして楽しみにしてきました。
新刊の案内を読むまで、このブログの存在を知らず・・・
今はこのようにやりとりができるようになり、とってもうれしく思います!
お客さん、大好きです。
なかなか頻繁にとはいかないのですが、呼んだり呼ばれたり。
これからも、気軽に楽しんでいきたいと思います。
(2008/04/08 04:04:52 PM)
自分専用のお箸が食卓に並んでいたらとても感激します。
わー私も山本家に歓迎されている。こんな嬉しい事ないなー。
その思いやりが素晴らしい。私なんか考えた事もないです。
自分ではいつも遊びに来て欲しいし、泊りに来てほしいと思って
いますが・・・来ませんね。心はいつも全開しているのに。
(2008/04/08 01:30:18 PM)
娘の春休みが終わり、新学期が始まりました。
この春から娘も六年生!
いよいよ小学生最後の年です。
「ごはん、食べにおいでね」って娘が幼稚園の頃は親も子どももにぎやかに
食卓を囲んだものです。
このごろはあまりそんな機会がなかったのですが、
ふみこさんのブログを読んだら、「ごはん、食べにおいでね」って友達を誘いたくなりました。
そうそう、今朝の「山本さんちの台所 53」を読んで、心新たになりました。
私がまかされている食卓に、ささやかながらもいろんな気持ちをこめようと…。
なんだか新学期の気分がぐんぐん身体にしみこむようです。
ふみこさん、ありがとう!
(2008/04/08 11:44:11 AM)