2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004年12月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
ヨハン・シュトラスII 喜歌劇「こうもり」
今年も暮れようとしています。 8月17日からプログを始めて、リンクを貼っていただいた方々やご訪問いただいた皆様に、改めてここにお礼を申し上げます。独断と偏見の音楽と花の日記ですが、来年も皆様方にお付き合いをしていただけるように、頑張って日記の更新を続けていくつもりですので、どうかよろしくお願い申し上げます。どうぞ良いお年をお迎え下さい。本当にありがとうございました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ヨハン・シュトラウスII作曲 オペレッタ「こうもり」今日は1年の締めくくり「大晦日」。 この「大晦日」の夜に欧米のオペラ劇場で上演される回数が圧倒的に多いのが、ウイーンのヨハン・シュトラスII(1825-1899)が作曲したオペレッタ「こうもり」です。今日はその「こうもり」を採り上げました。ヨハン・シュトラウスIIは、「ワルツ王」と呼ばれたほどウイーンで絶大な人気を誇っていましたが、オペレッタ(喜歌劇)の作曲は45歳(1871年頃)になってから着手したそうです。 フランスのオッフェンバックのオペレッタなどに刺激されて書くようになったと言われています。彼はその生涯に16作のオペレッタを書いていますが(「ジプシー男爵」など)、最も有名で今尚人気のあるこの「こうもり」が代表作となっています。この「こーもり」は全3幕の構成で、当時のウイーンの上流社会を舞台にして繰り広げられる喜劇で、或るパーテイでこうもりの扮装のまま、友人アイゼンシュタインに路上に置き去りにされて恥をかいたファルケ博士が、その友人アイゼンシュタインを騙して大恥をかかせるという物語で、劇中にはウインナ・ワルツがふんだんに使われており、陽気で楽しさこの上ないオペレッタです。 第2幕の仮面舞踏会では「ガラ・パーフォーマンス」が用意されていて、オペレッタとは関係なく、大物ゲスト歌手の声の競演という豪華な一場面もあります。1年の締めくくりを賑やかで、楽しい舞台で過ごして新年を迎えようということなのでしょうか、初めに書きましたように欧米ではよく大晦日に上演されて新年を迎えています。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウイーン・フィルハーモニー ワルデマール・クメント(テノール) ヒルデ・ギューデン(ソプラノ) ワルター・ベリー(バリトン)他(ガラ・パーフォーマンス出演歌手) レナータ・テバルディ ビルギット・ニルソン ジュリエッタ・シミオナート テレサ・ベルガンサ ジョーン・サザーランド レオンタイン・プライス マリオ・デル・モナコ フェルナンド・コレナ エットーレ・バステイアニーニ ユッシ・ビョルリンク(LONDONレーベル POCL 2278-9 ウイーン録音)カラヤンがウイーンフィルの藝術監督をしていた頃の録音で、ウイーン情緒いっぱいで、ウイーンフィルの極上のアンサンブル、豊麗で優美な音色を楽しめる演奏です。 カラヤンとウイーンフィルの蜜月時代の遺産です。 ガラ・パーフォーマンスでは当時のイギリスDECCAの大歌手・看板歌手が友情出演して、軽妙に歌う様はウイーンでの帝王カラヤン時代の全盛を偲ばせる豪華さです。 またカラヤンと録音では絶妙のコンビだったジョン・カルーショーの遺産の一つでもあり、当時のDECCA録音技術の優秀さを物語る盤でもあります。DVDでは極め付け、カルロス・クライバー指揮 バイエルン国立歌劇場での舞台上演録画があります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月31日
コメント(14)
-
カヴァレフスキー 組曲「道化師」 / 何故「年越しそば」を食べるの?
『今日のクラシック音楽』 ドミトリー・カヴァレフスキー作曲 組曲「道化師」1904年の今日、旧ソヴィエトを代表するドミトリー・カヴァレフスキーが生まれた日です。 そこで今日は彼の代表作である、組曲「道化師」を採り上げました。 子供向けの児童劇の付随音楽として書かれたこの曲は、作曲者自身によって演奏会用組曲として編集されて、今日ではこの組曲がポピュラーになっています。一つ一つの曲はは短く親しみやすい旋律で、平明簡潔な全10曲で構成されています。 特に、第1曲目の「プロローグ」は有名でラジオ番組などのテーマ音楽としてよく使われています。 また「ギャロップ」は学校の運動会では必ずと言っていいほど流され、誰もが「あ~、あの曲!」というほど超有名曲です。 カヴァレフスキーは特にこどものための音楽を数多く書いており、短いピアノ小品集(子供のための35のピアノ曲集)などを残しており、子供のための音楽教育にも貢献した作曲家でした。愛聴盤 キリル・コンドラシン指揮 RCAビクター交響楽団(BMGビクター JMXR24014 1958年 ニューヨーク録音)非常に古い録音ですが、最近BMGが最高のリマスタリングで古い録音をデジタル処理によって素晴らしい音質に蘇らせるXRCDというシリーズで発売しているCDの中の1枚です。カップリングはハチャトリアンの「仮面舞踏会」です。1961年、まだ高校生だった頃だと記憶しているのですが、当時のビクターレコードから「Living Stero」というシリーズで発売されたLP盤で、擦り切れるくらいに聴いていた懐かしい録音盤です。『今日の音楽カレンダー』1877年 初演 ブラームス 交響曲第2番1884年 初演 ブルックナー 交響曲第7番1904年 生誕 ドミトリー・カヴァレフスキー(作曲家)1905年 初演 レハール オペレッタ「メリー・ウィドウ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『年越しそばを何故食べるの?』大晦日には『年越しそば』を食べる習慣がありますが、何故大晦日に食べるのでしょうか? 今まで疑問視しなかったのですが、誰からもその理由を聞いたことはないし、蕎麦屋には年越しそばのポスターが貼ってあって、店に来る客や出前で食べる客で賑わう年越しそば。それで色々と調べてみると、諸説が多くどうも明確な説はないようです。 大体以下の由来に基づくそうです。1.そばは長く伸びるので運や寿命、身代が細く長くのびるようにと願って、縁起をかついで食べた。2.江戸時代に金銀細工師が、そば粉を練り飛び散った金粉をそばに着け、水にそばを浸けると金が水底に貯まることから「金が貯まる」と縁起をかついで晦日に食べた。3.鎌倉時代に博多地方のお寺で「世直しそば」といってそばがきを皆に振舞ったところ、運が向いてきたという事で「運そば」といって大晦日に食べる習慣が始まった。4.そばは切れやすいことから、悪いことの縁を切ると言い、出来の良いそばは、良くつながることから良いことが長続きすると言って食べた。こんなところが「年越しそば」の由来だそうです。明日は午後1時から神社の社務所詰めになるので、昼食に「鰊そば」を作って食べて行こうと思っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月30日
コメント(8)
-

朝比奈 隆を偲ぶ / ドビッシー 弦楽四重奏曲 / 年末の掃除
『朝比奈 隆を偲ぶ』2001年12月29日、大阪が世界に誇る名指揮者朝比奈 隆が93歳の生涯を閉じた日でした。 訃報を知ったのは翌日の30日でした。 その年の秋に名古屋に住むクラシック音楽を好きで、アマチュア合唱員としてベルデイの「レクイエム」などに出演されていたメール友達が、楽しみにしていた朝比奈 隆のコンサートが体調不良のために中止になった旨のメールを送ってきました。 その時から私は嫌な予感をしていたのですが、訃報を聞いてカラヤンが亡くなった時以上のショックを受けました。かねがね、先生のお年を考えると大阪でのコンサートがあれば聴きに行かねばと思いながらも、結局あまり足を運ばずにいたことが悔やまれてなりません。 お年を召していても指揮台での立ち居姿は、恰幅がよくて背が高いことから、背筋をピンと伸ばしている指揮姿には後光さえ射しているかと思うくらいのオーラのある姿でした。私が高校生の頃はドイツ音楽の色々な作曲家の曲を演奏なさっていましたが、晩年になるにつれて3B(ベートーベン、ブラームス、ブルックナー)ばかりのプログラムに限定されていましたが、日本人指揮者ながら最も重厚で、分厚いハーモニーの伝統的なドイツ風の音楽を作りだす指揮者でした。今日はその朝比奈 隆を偲びながら、1975年の東京文化会館で行なわれた大阪フィルの東京定期演奏会でのライブ録音で、ベートーベンの「英雄」交響曲を聴こうと思います。 このLP盤で初めて朝比奈 隆という指揮者の凄さを知った想い出の1枚です。 これがCDに復刻されて私のライブラリーに収まっています。 もうこういう指揮者ー職人肌のーは出てこないと思います。 音楽大学にも行かず、京都大学でサッカーを楽しみ、卒業後は阪急電車の運転手をしていた人が、アメリカのシカゴ交響楽団から客演指揮者として招かれて、ブルックナーの交響曲第5番を指揮して、聴衆総立ちのスタンディング・オヴェーションで評価されたのです。 そういう色々なエピソードを思い出しながら75年録音の「英雄」を聴いてみようと思っています。独断と偏見の記事にお付き合いいただいて、ありがとうございました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 クロード・ドビッシー作曲 弦楽四重奏曲1893年の今日(12月29日)、フランスの作曲家クロード・ドビッシーが書きました弦楽四重奏曲へ長調が、名ヴァイオリニストで作曲家イザイが主宰するイザイ弦楽四重奏団によって初演されています。ドビッシーの唯一のこの弦楽四重奏曲は、ドイツの室内楽作品の伝統と形式を踏襲しながら、フランスの作曲家セザール・フランクの創始しました同一主題がまた他の楽章で表れるという「循環形式」を用いて、大胆な和声と色彩豊かな音楽に仕上げており、第2楽章、第3楽章などの繊細な詩情に溢れた美しい曲です。この翌年には名作「牧神の午後への前奏曲」が書かれており、ドビッシーの充実した時期の作品です。 ラヴェルの弦楽四重奏曲と共に、近代フランス室内楽の傑作です。愛聴盤 アルバン・ベルク弦楽四重奏団(EMIレーベル TOCE59062 1984年4月スイス録音 ドイツ輸入盤)完璧無比なアンサンブルと美しい音色に魅せられる演奏です。『今日の音楽カレンダー』1876年 生誕 パブロ・カザルス(チェロ奏者)1882年 初演 ブラームス 弦楽五重奏曲第1番1893年 初演 ドビッシー 弦楽四重奏曲1906年 初演 シベリウス 交響詩「ポピョラの娘」1965年 逝去 山田耕作(作曲家)2001年 逝去 朝比奈 隆(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『年末の掃除』午前10時ごろ病院で診察してもらって帰宅すると妹が遊びに来てくれた。 「掃除せないかんやろ。 手伝うわ」。仏壇の中を掃除して家中に掃除機をかけてくれてきれいにしてくれた。 台所もレンジあたりや換気扇などをきれいに洗剤で洗ってくれたおかげで、随分ときれいな台所になった。大晦日は神社の社務所詰めになるので、明日家の中を掃除しようと思っていたので助かった。 手際よくやってくれたので、12時半には終って昼食。 随分と楽な年末になった。夕方には従姉妹の花屋から正月花が届く。 ようやく迎春モードが高まってきた今日の我が家でした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月29日
コメント(6)
-
ラヴェル 「夜のガスパール」 / 今日は「御用納め」(追記) / また実子殺し
『今日のクラシック音楽』 モーリス・ラヴェル作曲 「夜のガスパール」1937年の今日(12月28日)、フランスの作曲家で「オーケストラの魔術師」「スイスの時計師」とか呼ばれた精緻で、華麗な音楽を書残したモーリス・ラヴェル(1875-1937)が62歳の生涯を閉じた日です。 今日は彼の命日に因んで数多く遺された名曲の中からピアノ独奏曲「夜のガスパール」を選んでみました。この曲はラヴェル33歳の1908年に書かれており、この時期はラヴェルにとって充実した頃であったようです。 ピアノ曲では「ソナチネ」「鏡」「マ・メール・ロワ」、オーケストラ曲では「スペイン狂詩曲」などが書かれた時期です。「夜のガスパール」は「アロイジス・ベルトランの3つの詩による」と副題が付けられているのですが、19世紀初めのフランスの詩人ベルトランの散文詩集「夜のガスパール」から3篇を選んで、そこから得たイメージとかインスピレーションで書いているようです。第1曲「水の精」人間に恋をしたオンデーヌ(水の精)が、恋に破れて雨の中に消えていく物語ですが、水音のさざ波のような開始音楽と水の精を表す美しい旋律に魅了される曲です。第2曲「絞首台」絞首台の「死」の様相を音楽にしており、引導を渡すかのような鐘の音が不気味に響く、鬼気さえかんじられ、ピアノ音楽をとことん追求したようなラヴェルの面目躍如といった曲です。第3曲「スカルボ」スカルボとは悪戯好きの小妖精のことで、幻想的にスケルツオで書かれており、暗い陰惨なイメージの「絞首台」のあとだけに、この軽妙さが活きています。 3曲中一番長い曲で、技巧に富んだ、ラヴェル独特の精緻なピアノ音楽の魅力を味わえる曲です。愛聴盤 パスカル・ロジェ(ピアノ)「ソナチネ」「高貴で優雅なワルツ」「クープランの墓」「プレリュード」「マ・メール・ロワ」「亡き王女のためのパヴァーヌ」などラヴェルの主要ピアノ作品を収めた2枚組CDです。(DECCA レーベル 440 836-2 1974-75年録音 ドイツ輸入盤)もう1枚はラヴェルの主要作品を収めた2枚組CDです。(ドイツ・グラモフォン 469184 ドイツ輸入盤)収録曲は以下の通りです。 1.ボレロ(カラヤン指揮ベルリンフィル) 2.ラ・ヴァルス(ブーレーズ指揮ベルリンフィル) 3.ピアノ協奏曲ト長調(アルゲリッチ・ピアノ、アバド指揮ロンドンフィル) 4.スペイン狂詩曲(小澤征爾指揮ボストン響) 5.水の戯れ(アルゲリッチ・ピアノ) 6.亡き王女のためのパヴァーヌ(小澤征爾指揮ボスト響) 7.ダフニスとクロエ(アバド指揮ボストン響) 8.夜のガスパール(アルゲリッチ・ピアノ) 9.ピアノ3重奏曲(ボザールトリオ)10.ツィガーヌ(アッカルド・ヴァイオリン、アバド指揮ロンドンフィル)まさに名曲名演揃いです。 『今日の音楽カレンダー』1937年 逝去 モーリス・ラヴェル1963年 逝去 パウル・ヒンデミット(交響曲「画家マチス」で有名な作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日は「御用納め」』今日は「御用納め」とされている日です。 これは民間企業を指すのではなくて、官庁・地方自治体の所謂「お役人」社会の慣わしから来ているのものです。この「御用納め」の由来は遠く江戸時代4代将軍家斉の時代に遡るそうです。 この家斉時代に与力。同心たちの政務を12月25日をもってその年の仕事を終える慣わしが出来たそうです。 そして「御用納め」を済ませてから、呑めや踊れやのドンちゃん騒ぎを繰り広げたそうです。一方江戸城では、毎月の1日、15日、28日が各大名の将軍謁見日であり、これが粛々として行なわれており、1年最後の謁見が12月28日であることから、江戸城の「御用納め」は28日と定められていたそうです。 その日は将軍から大名たちに扇子などの引き出物が贈られたそうです。明治政府になって、明治2年にはまだこの幕政の慣習を踏襲して25日を「御用収め」と定めていましたが、明治6年になって28日を「御用納め」とされて今日に至っているそうです。市井はというと、それどころではなく掛取りやら返金の金繰りなどで町民は大晦日除夜の鐘が鳴るまで走り回って年越し準備の金繰りに奔走していたそうです。 大晦日の夜遅くまで掛取りや金繰りに走る人たちの提灯が行き交うさまを「大晦日の蛍火」と呼んだそうです。ちなみに「御用納め」後の宴会はドンチャン騒ぎで、それが現代の「忘年会」を生んだようです。「御用収め」由来の一席でした。 おあとがよろしいようで。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『また実子殺し』毎日新聞ネット記事によると27日長野県松本市で、37歳の母親が9歳長女と3歳長男の二人の実子の頭を石で殴って殺したと自首してきたニュースが報じられている。殺した理由やいきさつは報じられていないし、夫がいるのかどうかも不明だが、どうして我が子を殺すようなことができるのかと暗澹となる記事だ。 自首した時には自家用車で出頭しており、その車の中に殺された子供二人を乗せていたらしい。自家用車があるくらいだから、生活苦でもないのかなと思ったり、夫がいるのかなと思ったりしているが、最近両親から虐待されたり、殺されたりする子供の事件が続発しており、親に信頼を寄せている子供たちが虫けらのように扱われていることに無性に腹が立ち、人の生命の尊厳を考えない親に対して殴り飛ばしてやりたいくらいの憤りを覚える。この母親の殺人に至る動機は定かではないが、1回きりの人生を与えられて生まれてきた実の子供を殺すことは、動機、理由を問わず、絶対に許されることではないはずだ。インド洋沿岸10ヶ国で22,000人以上(27日現在)の死者が出たり、災害で多数の人たちが亡くなっていることも併せて、ほんとに暗澹とした年の瀬になってしまった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月28日
コメント(12)
-
ショーソン 「詩曲」 / スマトラ沖大地震 / 富岳園 椿の花写真
『今日のクラシック音楽』 エルネスト・ショーソン作曲 「詩曲」1896年の今日(12月27日)、フランスの作曲家エルネスト・ショーソン(1855-1899)が書きました「詩曲」が初演されています。この曲はヴァイオリンとオーケストラのために書かれた曲で、12月22日の日記で紹介しましたフィビヒの「詩曲」よりもこちらの方が有名で、ゆったりと響くオーケストラをバックに、独奏バイオリンが甘美で切ないメロディを朗々と歌う印象的な作品です。コンサートや録音などでヴァイオリン曲としては演奏される頻度が遥かに高い曲です。 約15分ほどの長さの曲ですが、瞑想的な雰囲気のある美しい旋律と、ヴァイオリンの重奏音と歌う部分がとてもきれいな詩的な佇まいの曲です。 フランスの作曲家ドビッシーも「この曲の終わりのところほど夢のように優しく感動的なものはない」と絶賛したほどの名曲です。 初演は1896年の今日12月27日、フランスでショーソンと親交のあったベルギーの大バイオリニスト、ウジェーヌ・イザイ(1858-1931)の独奏で行なわれています。彼は他に交響曲や室内楽曲などを書残していますが、ショーソンと言えばまずこの「詩曲」が浮かぶほど有名なヴァイオリンの名曲です。しかし、彼は44歳の時に自転車に乗って車との接触事故でまだ若き命を散らしてまっています。 ジャン・ガロワという人がそのショーソンの亡くなった日のことをこう書いています。『六月十日午後六時半頃、もうすぐ出来上がるばかりの楽譜を脇にやって、彼は長女のエチエネットを呼び、一緒にいつもの道を回ってから、パリから着く夫人と子供たちを迎えに、近くの駅に行くことにした。より敏捷だった若い乗り手の方が先に立ち、しばらく行って振り向くと、父親の姿が見えなかった。そこで引き返すと、恐ろしい光景が彼女を待ち受けていた。正門の柱の根元にこの音楽家がこめかみを砕かれて倒れていたのである。彼は即死していた。この馬鹿げた事故は、過労に、その午後の暑さが加わったことに因るものであったのだろうか。ショーソンが自転車に乗ることが上手でなかったために起こったのであろうか。この道路に彼は慣れていたし、それは皆の言い分とは反対に、比較的穏やかな傾斜で下っていた。何が起こったのであろう。それは誰にも分からず、この作曲家は、彼の秘密を墓場の中に持ち去っていった』「ショーソン」(ジャン・ガロワ著 西村六郎訳 音楽之友社 1974)より愛聴盤 諏訪内晶子(Vn) シャルル・デュトワ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 (Philips レーベル UCCP-1086 2004年2月2~4日 イギリス録音)カップリングされている曲は 1. サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソ 作品282. サン=サーンス:ハバネラ 作品833. ラロ:ギター 作品284. ショーソン:詩曲 作品255. クライスラー:シチリアーノとリゴードン(フランクールのスタイルによる)6. クライスラー:才たけた貴婦人(L.クープランのスタイルによる)7. ベルリオーズ:夢とカプリッチョ 作品88. ラヴェル:ツィガーヌ『今日の音楽カレンダー』1869年 初演 スーザ 「星条旗よ永遠なれ」1896年 初演 ショーソン 「詩曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『スマトラ沖大地震>』インドネシア・スマトラ沖でM8.5クラスの大地震が発生、その後も周辺でM5~7クラスの地震が続発したと報じられている。地震による大津波がインド洋沿岸諸国をすぐさま襲い、インド・チェナイ、タイ・プーケット、バングラデシュ、マレーシャ、インドネシアなどに甚大な被害発生と報じられて、毎日新聞ネット記事26日付け20時56分のニュースでは死者10,000人に達しようとしており、タイ・プーケットでは日本人観光客20人の安否が確認されていないという。 被害の詳細がもっと判明するにつれて使者・行方不明の数も増えてくることが予想される。今年は、「年の言葉」通り「災」の年で、特に天災による死亡者の数が多かった。 一体地球に何が起こっているのかと考えてしまう災害発生の多い年であり、1年の終わり近くでこの大地震。亡くなられた各国の人々の冥福をお祈り申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『富岳園 椿の花』いやあ~、驚きました。 このサイトで初めて知りましたが椿にはこれだけの種類があるとは! 一目見て名前の違う花の区別がつかないのが多いこと。 そういうのは葉を見て区別するのだと思いますが、山茶花も椿の種類に入れられているようにも見えます。それにしても、よくぞこれだけの椿の花を撮ったものだと感心するのと、体系的にまとめ上げたものと感服せざるを得ません。しかも日本の椿、外国の椿と分けて紹介されています。 一度は見ておかれたらと思い、ここにご紹介いたします。 先日この日記に書きました「伝統文化コミュミニティ 椿 わびすけの家」に紹介されていたサイトです。 富岳園 椿をクリックすれば飛びます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月27日
コメント(8)
-
シベリウス 交響詩「タピオラ」 / 境内の楠にしめ縄
『今日のクラシック音楽』 ヤン・シベリウス作曲 交響詩「タピオラ」1926年の今日(12月26日)、フィンランドの作曲家ヤン・シベリウス(1865-1957)が書きました交響詩「タピオラ」が作曲されています。 この曲はニューヨーク交響楽協会の依頼で書かれており、1926年にニューヨーク交響楽団の演奏で初演されています。「タピオラ」というのは彼の祖国フィンランドの叙事詩「カレワラ」に出てくる森の神「タピオ」の領土のことだそうです。 シベリウスは人一倍祖国を愛した作曲家で、この「カレワラ」という叙事詩についての曲を他にも書残しています。 初期の作品「クレルヴォ交響曲」などもこのカレワラとの結びつきが深いそうで、生涯を通じてこのカレワラのテーマを書いているそうです。シベリウスの作品には、祖国への愛着と自然への愛情・賛歌という想いが色濃く描かれているのが多いのですが(代表的なのが「フィンランデイア」)、この「タピオラ」もフィンランドの森の神をテーマにして、森と湖の祖国を象徴する自然を描き出そうとしたのでしょう。 曲全体にそういう自然を描いた趣に溢れた名品です。私が40歳の頃、北欧を訪れた際にフィンランドにも立ち寄り、森と湖に囲まれた息を呑むような素晴らしい自然の美しさに触れた時の感動を思い出す曲です。愛聴盤 ユージン・オーマンデイ指揮 フィラデルフィア管弦楽団(BMGジャパン BVCC38123 1976年フィラデルフィア録音)カップリングはシベリウス交響曲第5番、4番です。『今日の音楽カレンダー』1830年 初演 ドニゼッテイ オペラ「アンナ・ボレーナ」1831年 初演 ベッリーニ オペラ「ノルマ」1926年 初演 シベリウス 交響詩「タピオラ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『境内の楠にしめ縄』以前このページの日記に掲載しましたが、村の神社境内にある樹齢推定400年の古い大木の楠木に、今年からしめ縄を着けて大晦日、新年の参拝の村の人たちを迎えることに先日神社役員会で決まり、今日そのしめ縄が納入されてきて、お化粧をすることになっています。境内に入ってすぐにこの大木が迎えてくれますからこれで神社境内の見栄えが良くなります。 またひとつ、神社を守る張り合いができました。来年は神社の会計を預かるともさん、もっと村の人たちが神社に参ってもらえるような企画を来年は考えていきたいと思っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月26日
コメント(6)
-
J.S.バッハ 「クリスマス・オラトリオ」 / 夕焼けエッセイ「クリスマス」
『今日のクラシック音楽』 J.S.バッハ作曲 「クリスマス・オラトリオ」今日はキリスト教社会では「クリスマス」です。 西洋クラシック音楽はキリスト教文化と深く結びついています。 オルガンなどの楽器や、声楽・合唱曲・ミサ曲・鎮魂歌(レクイエム)・オラトリオ・カンタータといった宗教曲はもとより、絶対音楽・標題音楽などでもキリスト教の「神」への崇拝から書かれている曲が多く、またオペラなどでも「神」としてキリスト文化が影を濃く落としています。そのキリスト教の年中行事で最も大切な一つに「クリスマス」があります。 クリスマスとはイエス・キリストの生誕を祝う教会行事です。「今日のクラシック音楽」では、今日がクリスマスにちなんでJ.S.バッハが「クリスマス物語」に基づいて作曲しました「クリスマス・オラトリオ」を採り上げました。聖母マリア、眠る幼子イエス、天使の群、羊飼いたち、東方3人 の博士たち、聖書に書かれたこれらの挿話は私たちの想像を刺激し、感動を与えてくれるクリスマス物語。バッハはこの<クリスマス>のために6つの独立した音楽を一つにまとめた「クリスマス・オラトリオ」を1734年、49歳の時に作曲しています。 曲は6部構成で初演は全曲をまとめて演奏されたのではなくて、以下のように披露されたそうです。第一部が12月25日、第二部が26日、第三部が27日。第四部は年が明けた1月1日、第五部が1月2日、第六部が1月6日にそれぞれ演奏されました。私たちにとれば12月25日が<クリスマス>というわけですが、当時の<クリスマス>とは12月25日から翌年1月6日(「顕現節」と呼ばれています)までをお祝いしていたそうです。イエス降誕に関する話は第一部から第三部に描かれています。 この時期、6部から成るこの「クリスマス・オラトリオ」を前半部(第一部~第三部)だけ取り上げる理由がここにあります。楽曲構成は、シンフォニア(器楽曲)、合唱曲、レチタティーヴォ(話すように言葉の抑揚をつけて歌われる曲)、アリア(レチタティーヴォに対して旋律的に歌われる曲)、コラール(ドイツ賛美歌)から成ります。各部は下記のようになっていて、福音史家という語り手が筋を物語っていきます。[第1部:声を挙げてよろこび、その日々を讃えよ] (ベツレヘムにおけるイエスの誕生)[第2部:その地方で羊飼いたちが] (野にある羊飼いたちへの天使のお告げ)[第3部:天の支配者よ、舌足らずの祈りを聞き入れよ] (羊飼いたちの幼子イエス訪問)[第4部:感謝し、讃美してひざまづけ] (幼子イエスの命名)[第5部:栄光あれと、神よ、汝に歌わん] (東方の博士たちの到来とヘロデ王の不安)[第6部:主よ、高慢な敵かいきまくとき] (博士たちのマリア/イエスとの巡り会い)音楽は平明ながらこれら全曲を聴きとおすにはおよそ2時間30分かかりますから、よほど覚悟して聴かないと最後まで聴き通すことは容易ではありません。 私も聴いているうちに電話などがかかると、そこで緊張が途切れて聴くのをやめたり、聴いている途中で最後まで聴く気力を失くすことが何度もあり、全曲を聴きとおしたのは数回だけです。でも、今日はクリスマスにちなんで「キリスト生誕」にまつわる第1部~第3部までは是非聴こうと思っています。愛聴盤 ペーター・シュライアー指揮 ドレスデン国立歌劇場管弦楽団・合唱団(Philipsレーベル PHCP20198/200 1987年録音)『今日の音楽カレンダー』1870年 初演 ワーグナー 「ジークフリート牧歌」1885年 初演 ブラームス 交響曲第4番1910年 初演 ラヴェル 「亡き王女のためのパヴァーヌ」(オーケストラ版)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『クリスマス』幼い頃、息子はクリスマスが近づくと、毎日のように「サンタさんはいつくるの、どこからくるの」と一日中聞いていた。 枕元に靴下を置いて寝たのは何年続いたでしょう。小学三年生になった年のクリスマス。 「お母さん、サンタクロースなんかいてへんで。 お父さんとお母さんがプレゼント買ってきたんやろ。 クラスの皆が言ってたわ。 僕もサンタクロースなんかいてへんと思ってたわ。 エントツから入るわけないやん、エントツのある家、見たことないわ」子供の成長がうれしいやら、寂しいやら、複雑な気持ちだった。中学生になった年のクリスマス。 「お母さん、僕サンタクロース信じてるよ。 絶対いるよ。 プレゼント何かな。 ゲームソフトだったらいいな」と自分の欲しいソフトの名前を言う。 頭脳作戦できたか。 でもなぜか嬉しくて、ソフトの発売日、朝早く買いに行った。あれから何年もサンタクロースの話をしなかった。 ある朝、歯磨きしながら息子が「今年はお母さんのところにサンタクロースが来るかもしれへんから、靴下、用意しときや」とぶっきらぼうに言う。予想もしない言葉に胸がキュンとして涙をこらえるのに困った。また何年かしたら息子に「サンタクロースはいると思う?」と聞いてみようと思う。 どんな言葉がかえってくるか楽しみだ。-産経新聞2004年12月24日付け夕刊「夕焼けエッセイ」 大阪府堺市 女性ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月25日
コメント(12)
-
ヴェルデイ オペラ「アイーダ」 / 叔父の愛犬が亡くなった
『今日のクラシック音楽』 ジュゼッペ・ヴェルデイ作曲 オペラ「アイーダ」1871年の今日(12月24日)、ジュゼッペ・ベルデイ(1813-1901)の大作オペラ「アイーダ」が初演された日です。このオペラはスエズ運河開通を祝って建てられたエジプト・カイロの大オペラ劇場のこけら落とし公演のために作曲されました。オペラは、古代エジプトとエチオペアの争いを背景にして、エジプトの王女アムネリスが恋する将軍ラダメスと、戦いで捕えられてアムネリスの奴隷となっているエチオペア王女アイーダの悲恋物語です。 結末は死刑を宣告されたラダメス、彼と共に死ぬことを選んだアイーダの二人が死んでいくところで幕切れとなる暗い悲恋を扱っていますが、第2幕での将軍ラダメスの凱旋を祝う場面はで、「アイーダ・トランペット」と呼ばれるトランペットが活躍する一大スペクタクルで、「凱旋行進曲」として有名な場面は、まさにこけら落とし公演にふさわしい舞台となっています。将軍ラダメスの愛するアイーダはエチオペアの王女。 それと知らずに戦勝してエチオペア兵士などを奴隷として連行して凱旋するラダメス。 その奴隷たちのなかに父エチオペア王を見つけて驚愕するアイーダ。 凱旋の褒美としてエジプト王から王女アムネリスとの結婚を許されるが、ラダメスはアイーダを愛しているがために、後にエチオペア王と判明しても逃がしてあげて死刑宣告を言い渡される。 ラダメスが受ける生き埋めの刑場に先回りして忍び込むアイーダ。 二人の愛は死をもって永遠に結ばれるという物語です。「清きアイーダ」(ラダメスのアリア)、「勝ちて帰れ」「おお私の故郷よ」(アイーダのアリア)など美しいアリアと東洋風のリリカルな旋律が随所に奏され、凱旋の場では爆発的なスペクタクルと化すところなどは、ヴェルデイの面目躍如たるグランド・オペラの傑作です。愛聴盤 アンナ・トモワ=シントウ(アイーダ),ブリギッテ・ファスベンダー(アムネリス),プラシド・ドミンゴ(ラダメス),ジークムント・ニムスゲルン(アモナズロ),ロバート・ロイド(ランフィス),他 リッカルド・ムーティ(指)バイエルン国立歌劇場管弦楽団,バイエルン国立歌劇場合唱団(ORFEO原盤 C583 0221 録音:1979年3月22日,ミュンヘン)1979年3月22日、ムーテイ指揮によるバイエルン国立歌劇場でのライブ録音。 ドミンゴを除くとほとんどミュンヘンのメンバーで固められていますが、ムーティのラテン系指揮棒に炙られたようなゲルマンたち。 第2幕『凱旋の場』での強烈な高揚(終幕後は冷静と言われるドイツの聴衆をしてブラヴォーの嵐・)などなど、ムーティとしてもこの時期ならではの直裁な熱狂ぶりがとにかく聴きものです。絶頂期の若きドミンゴは昨今とはまるで違う全力投球で、得意のラダメスで艶々の美声を聴かせており、素直にその格好良さを認めざるを得ない熱唱、名唱だと思います。情感のこもった、こまやかな心情を歌い上げるアイーダ役で、イタリアのソプラノとはまた違った味わいを醸し出すトモワ=シントウ。 きわめてドラマティックなファスベンダーの王女アムネリス。ドイツ・バイエルンで炎と化したイタリア・オペラの名舞台のライブ録音です。 その他の愛聴盤 カラヤン指揮 ウイーンフィル ミレッラ・フレーニ(アイーダ)、 ホセ・カレーラス(ラダメス)、 アグネス・バルツア(アムネリス)、 ピエロ・カップッチルリ(アモナスロ)、 ルッジェーロ・ライモンデイ(ランフィス)、 ヨセ・ファン・ダム(エジプト王)、 カーティア・リッチャレルリ(巫女の長)(東芝EMI CE22-5951-52 1979年5月ウイーン録音)よくぞこれだけの豪華歌手を揃えたと敬服以外にない、まさに帝王カラヤンがウイーンフィルを指揮して繰り広げる一大絵巻のようなオペラ演奏。 とりわけフレーニのアイーダがリリカルな表現でカラス、テバルディなどと一味ちがう表現が聴きものです。『今日の音楽カレンダー』1871年 初演 ベルデイ オペラ「アイーダ」1888年 初演 チャイコフスキー 幻想的序曲「ハムレット」1935年 逝去 アルバン・ベルク(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『叔父の愛犬が亡くなった』12月20日母の弟(83歳)が可愛がっていたゴールデン・リトルバーが癌で亡くなりました。 ペットショップで買ってきたのが4年前。 小さな犬でしたが、ものすごい食欲で見る見るうちに大きくなり、叔父も散歩に連れて歩くのが大変なくらいの大きな犬に成長していきました。 私が叔父の家に行くと喜んで飛びかかってくるのですが、何度も押し倒されそうになるくらいの大きさでした。今月に入ると私を見てもじっと寝そべったままなので、おかしいなあ、体調が悪いのかなと思ってましたが、亡くなった叔母のお通夜で叔父から「癌」だと聞きました。 医者に診察をしてもらった時は、手の施しようのない末期癌で手術も出来ない状態だったらしい。20日には応接間で叔父と一緒に居た犬が、前足を伸ばして叔父の脚をとんとんと叩き、応接間の扉を叩きに行ったので小便でもしたいのかと叔父は思って外に出してあげたそうです。 それから30分後に戻ってこない犬を庭の隅の灯篭の傍で死んでいるのを見つけたそうです。 犬は一人寂しく死んでいくということを聞いていましたが、まさにその通りで、叔父を叩いたのはお別れの言葉だったのでしょう。 叔父の落ち込みようはひどいもので、傍目にも可哀想でならない愛犬の死でした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月24日
コメント(12)
-
ベートーベン ヴァイオリン協奏曲 / 伝統文化コミュニテイ 椿 わびすけの家
『今日のクラシック音楽』 ベートーベン作曲 ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品611806年の今日(12月23日)、ベートーベン(1770-1827)が書きました「ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品61」が初演された日です。バッハ、モーツアルト、パガニーニなどのベートーベン以前の作曲家、またベートーベン以降の作曲家たち(ブラームス、メンデルスゾーン、チャイコフスキーなど)が書残した数多くのヴァイオリン協奏曲がありますが、私はこのベートーベンの協奏曲が最高峰に聳え立つ曲だと思います。この曲が書かれた頃は、後に「傑作の森」と呼ばれる彼の作曲活動の中期に当たる時期で、作品番号からするとピアノ協奏曲第4番、交響曲第4番、ラズモフスキー弦楽四重奏曲などがあり、作品57の「英雄」交響曲で成功を収めたあとの曲です。 おそらくベートーベン自身の最も幸せな時期であったと思います。 4番シンフォニーの清楚な、静的な美しさ、優美で柔和な響きの4番のピアノ協奏曲と、どこか共通しているものを感じさせるこのヴァイオリン協奏曲を聴くとそう感じます。伝統的な3楽章形式で書かれていて、アクロバットのような名人芸を披露するような華麗なパッセージは書かれておらず、ヴァイオリンを豊かに歌わせることに集中して書かれたような曲です。 のびやかに、豊麗に響く歌に溢れ、旋律楽器としてのヴァイオリンの特性を高度な芸術的気品にまで高めており、格調の高さ、崇高な美しさと、男性的な情熱をも兼備えている傑作です。1806年の初演では楽譜が完全な形で演奏者に渡されておらず不評に終わり、この初演後38年を経て名ヴァイオリニスト・ヨーゼフ・ヨアヒムがメンデルスゾーンの指揮によって再演されて曲の真価が世に認められたそうです。愛聴盤 カール・ズスケ(Vn) クルト・マズア指揮 ライプチッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団(ドイツ シャルプラッテン 発売=徳間ジャパン 25TC-287 1987年9月録音 現在は廃盤)キョン・チョン・ファ(Vn) クラウス・テンシュテット指揮 ロイヤル・コンセルトヘボー管弦楽団(EMIレーベル 東芝EMI発売 TOCE13021 1989年11月 ライブ録音)『今日の音楽カレンダー』1806年 初演 ベートーベン ヴァイオリン協奏曲ニ長調1834年 初演 ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」1893年 初演 フンパーディンク オペラ「ヘンゼルとグレーテル」1946年 誕生 エディタ・グルベローヴァ(ソプラノ歌手)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『伝統文化コミュニティ椿 わびすけの家』このサイトは日本の伝統文化・故事などを画像を掲載して紹介しています。 HPオーナーの多種にわたる知識と造詣の深さに敬服しながら読ませていただいていましたが、このたび私のページ「プレリュード」がこのHPにリンクされて掲載されています。 私にとって大変光栄なことと喜んでいます。 皆様方も是非このサイトを訪問されて「伝統文化」に触れてみられたらいかがと思い、ここに紹介させていただきます。 URLは椿 わびすけです。 私のページはこのサイトのトップページの一番下のsearch伝統文化コミュニテイをクリックすると多種のカテゴリーがあって、その中の『音楽』をクリックすると紹介されています。プレリュードで直接飛びます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月23日
コメント(8)
-
ブラームス ヴァイオリン・ソナタ 第3番 (カレンダー追記あり) / 今年もあとわずか
『今日のクラシック音楽』 ヨハネス・ブラームス作曲 ヴァイオリン・ソナタ第3番 二短調 作品1081888年の今日(12月22日)、ヨハネス・ブラームス(1833-1897)が書きましたヴァイオリン・ソナタ第3番がハンガリーのブタペストで初演されています。ブラームスはオリジナルの形で書いたヴァイオリン・ソナタは3曲あります。 現在ではこれら3曲をヴァイオリンとピアノのためのソナタとして呼ばれています。 それ以外にもソナタとして書いているのがあるのですが、クラリネット・ソナタを編曲したもので、これら3曲とは一線を引かれてます。一聴してわうかるのはブラームスのヴァイオリン・ソナタは技巧を誇示した高音を要求しているわけでもなく、重音で演奏される部分も少なく、華麗な効果もなく、旋律を歌わせてピアノとの和音処理の程よいバランスを備えているのが特徴です。とりわけこの第3番は、彼の晩年に書かれた曲で(1886年)、他のこの時期に書かれている曲などと同じように(クラリネット五重奏曲や交響曲第4番など)「人生の秋」「人生のたそがれ」を感じさせるような、渋い内省的な音楽となっています。 この頃は短調の作品が多く書かれていることから「たそがれ」に近づいた自分の生涯の行く先を見つめていたのかも知れません。 和声は重く厚く書かれており、より深い精神性を感じさせる曲で、第1番や第2番の持つのどかさから一転して深い情感と寂寥感の滲む曲です。冬の寒い夜に暖をとりながらしっとりと聴くにふさわしい曲ではないでしょうか。愛聴盤 アンネ=ゾフィー・ムター(Vn) アレクシス・ワイセンベルク(ピアノ)(EMIレーベル 5747252 1982年9月パリ録音 輸入盤)『今日の音楽カレンダー』1789年 初演 モーツアルト クラリネット五重奏曲1808年 初演 ベートーベン 交響曲第5番「運命」1858年 誕生 ジャコモ・プッチーニ(作曲家)1888年 初演 ブラームス ヴァイオリン・ソナタ 第3番1894年 初演 ドビッシー 「牧神の午後への前奏曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今年もあとわずか』 もう今年も終ろうとしている。 早い。 また、年を重ねてと思いながら、腰を伸ばす。 今年五月の連休半ば、息子にインターネットの使い方を教えられた。 私は手紙が好きだ。 メールは好きではない。 漢字を出すのに時間が掛かりそう。 ローマ字を探し出して文字に換えるのも手数がかかるだけけ・・・・・と。 だが、息子は本気だ。 メモ用紙と鉛筆を持って、電源を入れてくれるところから教えてくれた。 孫は学校で使ったローマ字のプリントをくれた。 教えられた通り、ゆっくり本を写し書きしてみた。 美しい文字が並ぶ。 思ったより面倒でもない。 私は、やってみるかと思った。 息子は、音楽の聴き方やEメールの使い方をパソコン画面からコピーして、順序よく教えてくれた。 メールの取り出し方も。 面白くなってきた。 メッセージが出来ると宛先を探し出しドキドキしながらクリックする。 足の悪い私はポストに行かなくてよい。 断然気に入った。 まず、娘に。 心配で、「メール行くよ」と。 返事がすぐ来る。 遠くの孫にも。 すぐ返事。 へぇーと私。 会ったことのない娘の友だちにー。 もう夢中。 朝、ウトウトしている私の耳に息子の大声。 「おばあちゃん、メール」。 ガバッと起きて読む楽しさ。 一本指で一生懸命綴って送る私は、まだ写真や模様を入れたりはできないが、この1ヶ月で一本指を卒業したい。 幸せだった今年。 拍手で迎えたい85歳。 大阪府 84歳 無職女性 ー産経新聞2004年12月21日付け夕刊 「夕焼けエッセイ」-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月22日
コメント(10)
-
フィビヒ 「詩曲」 / 今日は冬至(追記あり)
『今日のクラシック音楽』 ズデニェク・フィビヒ作曲 「詩曲」1850年の今日(12月21日)、チェコの作曲家ズデニェク・フィビヒ(1850-1900)が生まれています。フィビヒはスメタナ、ドヴォルザークと共に、チェコ国民楽派草創期における、最も重要な作曲家の一人です。これまで国内ではあまり耳にすることもなかったフィビヒではありますが、ここ最近はCDも流通するようになりました。フィビヒ はその50年の生涯のうちに、叙情に溢れるロマン派風の美しい作品を数多く遺したそうです。しかし、チェコ国民楽派といえば、スメタナ,ドヴォルザーク,ヤナーチェクの3人の名前が挙がりますが、彼らと共にフィビヒの名が並ぶのは希です。 プラハで活躍し、チャンスがあったにも拘わらず、敢えて楽壇の要職に就かなかったこと、また、彼ら3人と同時代のチェコの人でありながら、彼の音楽がドイツ・ロマン派に近いものを持っていたことも、その原因の1つではないかと言われています。フィビヒの作品は、旋律の美しさもさることながら、重厚で複雑な彩りの和声の豊かな響きも大きな魅力であると感じています。 その彼の作品の中に「気分・印象・思い出」(全部で4集)というピアノ曲集の作品41に含まれている一曲に「詩曲」があります。 ロマン溢れる曲想でヴァイオリンにも編曲され、ショーソンの有名な「詩曲」と並び賞されている曲です。彼の誕生日にちなんでこの「詩曲」を今日は聴こうと思います。(CHANDOSレーベル CHAN9381)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日は冬至』今日は「冬至」。 1年で一番日の短いです。 秋のつるべ落としからすぐに冬至になってしまった感があり、今年もいつの間にかあと10日間で暮れようとしています。 年齢を重ねて来ると日が経つのが早く感じるのは私だけでしょうか?冬至には「ゆず湯」に入る慣わしがあります。何故、冬至にゆず湯風呂なのでしょう?「とうじ」という言葉にあるそうです。冬至の読みは「とうじ」。というわけで、湯につかって病を治す「湯治(とうじ)」にかけているそうです。更に「柚(ゆず)」も「融通(ゆうずう)が利(き)きますように」という願いが込められているのだそうです。 5月5日に「菖蒲(しょうぶ)湯」に入るのも、「(我が子が)勝負強くなりますように」という、ゆず湯と同じ「願かけ」だそうです。 今日はゆずを買ってきて「ゆず湯」に入ろうと思っています。(追記)かぼちゃを食べると中風(脳卒中)にならない、夏の患いを防ぐなどという言い伝えがあり、それらのものを食べる風習などがあります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月21日
コメント(6)
-
ベートーベン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」 / レナータ・テバルディ死去
『今日のクラシック音楽』 ベートーベン作曲 ピアノ協奏曲第5番変ホ長調 作品73 「皇帝」1982年の今日(12月20日)、20世紀を代表する偉大なピアニスト、アルトゥール・ルービンシュタイン(1887-1982)が亡くなった日です。 同世代のもう一人の不世出のピアニスト、ウラジミール・ホロビッツと共に一世を風靡した大ピアニストで、ビクターレコードにおびただしい録音を残しています。彼の紡ぎ出すピアノの音色は常に大らかさに溢れており、聴き手を自然に音楽の楽しみに浸らせてゆく愉悦感溢れるピアノ音楽を創りだしている演奏家でした。 11歳の頃から天才と呼ばれ、その後80年間天才であり続けたピアニストでした。 その彼が1975年3月に88歳で録音したベートーベンの「皇帝」協奏曲が遺されています。 彼はショパン弾きとしても数多くの録音を残しており、いずれも素晴らしい演奏なのですが、88歳にして溌剌とした「皇帝」を遺した偉業に敬意を表して採り上げました。「皇帝」は、それまでの単にピアノの技を聴かせるピアノパートを際立たせていたスタイルから、深い精神性を秘めたオーケストラ部分に強い意思を持たせた「ピアノ付き交響曲」とでも言える様な威風堂々とした協奏曲です。 まさに雄渾無比な世界を創り出している作品です。ルービンシュタインは、かなり遅めのテンポでじっくりと弾いており、80歳を超えているとは思えないほど瑞々さで、しかも豪華、華麗に弾き上げています。 メロディの歌わせ方にかなりの癖がありますが、雄渾な世界を創りだす老齢ピアニストの至芸に酔える演奏です。1982年に95歳の生涯を閉じたルービンシュタインを偲んで聴こうと思います。(BMGレーベル BMCG37220 1975年3月ロンドン録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『レナータ・テバルディ死去』12月19日世紀のソプラノ歌手、イタリアのレナータ・テバルディがサンマリノの自宅で死去したとANSA通信(イタリア)が報じています。マリア・カラスと人気を二分したテバルディは大指揮者トスカニーニに認められてデビュー。 1950-1960年代のイタリア・オペラ黄金時代を支えたソプラノでした。 1961年にNHKの招きでイタリア歌劇団のメンバーとしてマリオ・デル・モナコ、ジュリエッタ・シミオナート、アルド・プロッテイ、ガブリエルラ・トゥッティなどと来日して、デル・モナコと共演した「アンドレア・シェニエ」は今でもオペラファンの語り草となる名舞台を見せてくれました。また十八番の「トスカ」でも最高の歌唱と演技を見せてくれて、アリア「歌に生き、愛に生き」の素晴らしい歌唱では拍手が鳴り止まず、15分間も中断したという前代未聞のオヴェーションがありました。 「天使の声」と絶賛されたテバルディの声は、清らかに澄み渡り、実に清楚で、しかもドラマテイックな表現も充分に歌える歌手でした。この人の62年の舞台をTV中継ながら観れたことは幸運でした。 高校2年生だった私が、マリオ・デル・モナコの歌唱と共に、オペラ狂いにさせた張本人の一人がテバルディでした。61年来日の舞台の「アンドレア・シェニエ」「トスカ」をNHK映像によるDVDで彼女を偲びたいと思います。『今日の音楽カレンダー』1823年 初演 シューベルト 劇音楽付随音楽「ロザムンデ」1982年 逝去 アルトゥール・ルービンシュタイン(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月20日
コメント(8)
-
チャイコフスキー オペラ「スペードの女王」
『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 オペラ「スペードの女王」1890年の今日(12月19日)は、チャイコフスキー(1843ー1894)が書きましたオペラ「スペードの女王」が初演された日です。このオペラは旧ロシアのプーシキンの詩文小説を題材に書かれており、18世紀末のペテルブルグを舞台に繰り広げる人間模様で、台頭する市民社会のゲルマンという男がリーザという女性に恋をして、彼女の寝室に忍び込み、リーザに貴族で金持ちの婚約者がいることを承知で愛の告白をしたところ、彼女自身もゲルマンに心が傾いていることを知る。リーザの祖母の伯爵夫人がトランプ遊びの名手で「スペードの女王」と言われていたが、市民社会出身のゲルマンは富を築こうと伯爵夫人にスペードの3枚の秘密を教授してもらおうと夫人に迫るあまりに、夫人はショック死してしまう。 夫人の死の真実を知ったリーザは入水自殺して果てる。ゲルマンはリーザの婚約者とトランプの賭けに出る。 スペードの秘密を死ぬ間際に夫人から聞いていたゲルマンは、勝負に勝ったと思うが婚約者の勝ちと知り、自殺をしてしまう。人間の運命を描こうと書いたこのオペラは、チャイコフスキーらしい、美しい旋律に彩られていて、彼独特の甘美な音楽を楽しめるオペラです。愛聴盤 ワレリー・ゲルギエフ指揮 キーロフ歌劇場管弦楽団・合唱団 マリア・グレギナ(ソプラノ) ゲガム・グリゴリアン(テノール) オルガ・ボロディナ(Ms)(Philips レーベル PHVP-2013/4 VHSビデオ 1992年収録)『今日の音楽カレンダー』1888年 誕生 フリッツ・ライナー(指揮者)1890年 初演 チャイコフスキー オペラ「スペードの女王」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『危ない自転車』最近自転車の乗る人が多くなり、駅前などは放置自転車で歩けないほどに増えています。 そうなるとマナーの問題が出てきます。 歩道いっぱいに広がって走る登下校の生徒。 自転車で走りながら携帯電話メールを入力している人や電話で話をしている人。 先日、買い物に出かけて見た光景ですが、30歳代の主婦風の女性。 車道を自転車で走りながら電話で通話中。ちょっと右方向に走ったので後ろから来たタクシーと接触しそうになりました。 自転車を停めて運転手を睨んでいました。 悪いのは自転車の方なんですが、それがわかっていないかったようです。 タクシーの運転手に携帯電話のことを咎められて初めて気がついた風でした。 危ないですね。私も以前に自転車に乗りながら4回連続のくしゃみをしたために前が見えず、電信柱に衝突しました。皆さん、自転車と言えどもマナーを守りましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月19日
コメント(6)
-
ブルックナー 交響曲第8番 / 今日でお別れ
『今日のクラシック音楽』 アントン・ブルックナー作曲 交響曲第8番 ハ短調アントン・ブルックナー(1824-1896)の創作ジャンルはほぼ交響曲に限られていると言っても過言でないほど、現代では彼の作品を演奏する再現芸術家は指揮者とオーケストラにほぼ限られています。 彼は、生涯に11曲のシンフォニーを書いていますが(9番は未完)、世に認められたのは7番であり、やっとこの8番の初演で何度も何度もステージによばれるほどの圧倒的な成功をおさめたそうです。 1892年の今日(12月18日)は、その交響曲第8番のウイーンでの歴史的な初演日にあたります。初演の成功を物語るように、この8番は彼の遺した11曲の交響曲の中でも最高の傑作と呼ぶにふさわしい曲だと思います。 最も美しい、またもっとも壮大な伽藍のような、まるでアルプスを仰ぎみるようなスケールを誇る作品です。 楽器編成は大きな規模に拡大されて、ハープが3台要求されていたり、ホルンが8本要する大交響曲です。彼自身「私が書いた曲のなかで最も美しい音楽」と語っており、第3楽章「アダージョ」は特に美しさが際立っています。 彼は敬虔なカトリック教徒だったそうですが、この曲(他の交響曲にも言えることですが)には禁欲的な深い精神性と、パイプオルガンのような広大な音楽宇宙と重厚さが備わっている傑作です。ブルックナーの交響曲はオルガンを使って書かれていたそうですが、全ての交響曲に共通しているのは曲の「書式」です。 混沌とした宇宙の創造を思わせるかのような弦のトレモロで始まる第1楽章。 まるでアルプスの巨峰を仰ぎ見るかのような、宇宙的なスケールを感じさせる終楽章。 そして中間楽章は寂しさ、哀愁を湛えたアダージョと、「野人」「自然人」と呼ばれた彼の素朴さを伝えるスケルツオなどで構成されています。 ほぼ全曲がこのスタイルで8番もその例に漏れません。 おそらくこれほど一貫したスタイル・書式を貫き通した交響曲作曲家は、他に誰一人としていないと思います。 それほど頑固に「スタイル」を守った人でした。その彼がウイーンで最初に熱狂的に迎えられたのが、この第8番の交響曲でした。 大器晩成型の典型で、そのときブルックナーは68歳。 その4年後に死が忍びよっていたのです。愛聴盤 朝比奈 隆指揮 大阪フィルハーモニー交響楽団(Exton レーベル OVCL-00061 2001年7月23、25日東京サントリーホールでの演奏会ライブ録音)2001年12月29日に逝去した朝比奈 隆最後のブルックナー演奏となったコンサートのライブ録音。 この曲を何度も録音している朝比奈ですが、私はこの演奏を聴いて深い精神性、広大なスケール、アダージョの美しさなどに感動して涙を流した盤です。 私たちにブルックナー音楽の素晴らしさを伝えてきた朝比奈先生にお礼を言いたくなった演奏です。「ありがとうございました。 もうゆっくりとお休み下さい」『今日の音楽カレンダー』1892年 初演 ブルックナー 交響曲第8番1908年 初演 ドビッシー 組曲「子供の領分」1962年 初演 ショスタコービチ 交響曲第13番(バビ・ヤール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日でお別れ』今日は叔母の告別式。 ほんとに今日でお別れとなりました。 この人が人の悪口を言っているのを聞いたことがありません。 いつも人のいいことばかりを言ってた人で、それでもお人好しではなくて、40歳ごろから商売を大阪市内で一人で始めて、居並ぶ大阪商人と互角あるいはそれ以上に張り合って50年店を守ってきた人でした。後年は糖尿病との闘いで、両足の指が壊疽にかかり切り落としていましたから、自宅マンションの階段の上り下りや、商店街を毎朝、毎夕その足で歩いていました。 店を手伝う娘二人にはそれでも愚痴を言わずに、何をしてもらっても「ありがとう」と言ってたそうです。 「感謝を忘れたらあかんで。 すみませんとありがとうを言えたら、人間どんなことでも耐えて生きていけるから、忘れたらあかんで」が口癖のど根性の座った大阪商人で、優しい叔母でした。「叔母さん、お疲れさまでした。 もう手を休めてゆっくりお休みください」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月18日
コメント(10)
-
アーサー・フィドラーを偲ぶ
『今日のクラシック音楽』 想い出のスクリーンミュージック~アーサー・フィドラーとボストン・ポップスオーケストラ1894年の今日(12月17日)は、セミ・クラシックの人気指揮者だったアメリカのアーサー・フィドラー(1894-1979)が生まれた日です。フィドラーはボストン交響楽団のヴァイオリン奏者でしたが、1930年にボストン・ポップスオーケストラの指揮者となり、セミ・クラシックと呼ばれるクラシック音楽のポピュラーな小品だけを指揮して人気を集めた人で、1960年代のセミ・クラシックLPと言えばこの人を指すほどに人気を不動のものにしていました。 映画音楽、オペラの序曲や間奏曲、オペラのバレエ音楽、管弦楽の小品などを次々にレコーディングを重ねていました。 軽妙で、お洒落で、時にはゴージャスなムード音楽まで幅広く手がけた指揮者でした。ボストン・ポップスオーケストラはボストン交響楽団と同一楽団で、クラシック音楽のオフシーズンにポップスと名を変えて活動していました。今日は彼らの数あるレコーディングから「想い出のスクリーンミュージック」というタイトルの映画音楽を聴いてみようと思います。若い方には馴染みがないと思いますが、主に60年代の映画音楽がラインナップされています。 「栄光への脱出」「慕情」「真昼の決闘」「ベン・ハー」などが収録されており、これらをフルオーケストラによるサウンドで美しい映画音楽を聴かせてくれています。(BMG レーベル BMGファンハウス発売 BVCC3054)『今日の音楽カレンダー』1864年 初演 オッフェンバック オペレッタ「美しきエレーヌ」1865年 初演 シューベルト 交響曲第8番「未完成」1894年 誕生 アーサー・フィドラー(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月17日
コメント(4)
-
サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲第3番 / 叔母が亡くなりました
『今日のクラシック音楽』 カミーユ・サン=サーンス作曲 ヴァイオリン協奏曲第3番1921年の今日(12月16日)はフランスの作曲家カミーユ・サン=サーンス(1835-1921)が亡くなった日です。サン=サーンスは、フランクやフォーレなどと近代フランス音楽を確立した作曲家で、交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽、それにオペラも手がけた多才な人でした。 ピアノの演奏家としても活躍したらしくて協奏曲のうち半分の5曲がピアノ協奏曲が書かれています。またヴァイオリンでも優れた作品を残しています。 「ハバネラ」「序奏とロンド・カプリチオーソ」などがそうです。 これらの2曲のヴァイオリンのための作品と並んで「ヴァイオリン協奏曲第3番」がつとに有名です。 1880年の1月2日に名手サラサーテを得てパリで初演されています。 サン=サーンスは3曲のヴァイオリン協奏曲を書いていますが、あとの2曲はほとんど演奏されないでこの第3番のみが取り上げられています。旋律がとても美しく、全体の構成もすぐれており、第1楽章の開始からフランス風で、まるで春の午後の美しさを感じさせるような音楽です。 第2楽章は舟歌風の抒情が漂う詩的な、田園情緒のような色彩の美しい楽章です。 私はこの曲では第1楽章の開始部分と第2楽章のヴァイオリンのフラジョネットがクラリネットが音を重ねていく部分にいつも魅かれています。今日がサン=サーンスの命日にちなんでこの曲を聴こうと思います。愛聴盤 チョン・キョンファ(Vn) ローレンス・ファスター指揮 ロンドン交響楽団 (Decca レーベル 460008 1975年5月 ロンドン録音)キョン・チョンファ若き日の録音ですが、流麗に紡ぎ出される美音としっかりとした構成、しっとりとした第2楽章のため息がこぼれるようなフラジョレット、LP以来の長年の愛聴盤です。『今日の音楽カレンダー』1877年 初演 ブルックナー 交響曲第3番1893年 初演 ドボルザーク 交響曲第9番「新世界より」1921年 逝去 カミーユ・サン=サーンス1921年 初演 プロコフィエフ ピアノ協奏曲第3番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『叔母が亡くなりました』今朝早く叔母が病院で息をひきとったそうです。 享年93歳。 昨夜近所に住む叔母の次女を訪ねたときは、病院からもう控え室で待機することはないでしょう。 ICU病室の決められた面会時間に来て下さいという、少しはいい知らせだったのですが、高熱を出して肺炎を併発して亡くなったそうです。 叔母の回復を願って、書き込みをしていただいた皆様にはご報告いたしますと共に、改めてここにお礼を申し上げます。 ありがとうございました。亡くなる前に会えなかったのが心残りです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月16日
コメント(6)
-
タルレガ 「アルハンブラの思い出」 / 叔母が倒れた!
『今日のクラシック音楽』 フランシスコ・タルレガ作曲 「アルハンブラの思い出」1909年の今日(12月15日)は、スペインの作曲家で偉大なギタリストのフランシスコ・タルレガ(1852-1909)が亡くなった日です。彼は近代ギター音楽を確立した偉大な作曲家であると同時にギター音楽を数多く遺した人です。 ギターは「リュート」というアラビアを起源として発展してきた楽器で、ヨーロッパで広まったのですがスペインの作曲家ソルが18世紀に現れてギター音楽を多く遺しました。 それによってギターは楽器として確立したのでした。 そのあとこの楽器はスペイン音楽では欠かせることができないものとなり、踊り(フラメンコ)などの楽器として庶民に親しまれています。「小さなオーケストラ」とも例えられる、多彩な表現を可能にした功績はタルレガに引き継がれて現代に至っています。今日の話題のフランシスコ・タルレガ(タレガとも呼ばれています)は、19世紀にギター音楽を更なる高度な音楽に高めた人で、この『アルハンブラの思い出』は最も有名なギター音楽の一つです。 タルレガ自身がスペインのグラナダ郊外にあるアルハンブラの宮殿を訪れた時の印象を書いた音楽で、私自身でこの宮殿をイメージしながらいつも聴いています。 月の光が降り注ぐテラスで奏でる、静かな弦のトレモロの美しさが漂うような音楽です。 愛聴盤 ナルシソ・イエペス(ギター)(グラモフォン レーベル UCCG3393/4 1970-1989年録音)アンドレ・ゼコビアという不世出のギタリストの後継者ナルシソ・イエペスの録音盤から名曲を2枚組みにまとめたCDで、1枚目はスペインの作曲家が書いたギター名曲集、2枚目が「アランフェス」などのギター協奏曲集です。『今日の音楽カレンダー』1909年 逝去 フランシスコ・タルレガ(作曲家・ギタリスト)1944年 逝去 グレン・ミラー(ジャズ作曲家・トロンボーン奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『叔母が倒れた』今朝8時半ごろにいつも行く珈琲ショップで町会役員や神社役員などと歓談していると1本の電話が携帯電話に入りました。 母からの電話でした。 大阪市内に住んでいる叔母(母の姉)が昨夜遅く倒れて意識不明のまま病院に担ぎ込まれて、まだ不明のままという知らせでした。この叔母は今年93歳で、戦後すぐに大阪市内で花屋を経営して花の師匠、官庁、師匠の教える会社などへ花を配達して着実に経営してきた人で、現在は二人の娘が叔母に替わって経営をしていますが彼女はまだ現役で、先週10日に店を訪れた時はまだびしゃこを束ねているほど、毎日店に出て仕事をしていました。母と母の兄弟二人(90歳と81歳)を引率してすぐに病院へ駆けつけたところ、救急病棟の集中治療室で意識不明のままベッドで寝ていました。 ここ数日が山だと医師が言ってました。 面会制限時間が設けられていたので長居は出来ずに、心配ですが夕方帰宅しました。帰宅して間もなく一緒に行った叔父(90歳)の長男(60歳)から、男の子の孫が生まれたと知らせがありました。 輪廻転生を思わずにはおれません。無理かも知れませんが、叔母の意識回復を祈るばかりです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月15日
コメント(12)
-
ベルク オペラ「ヴォツェック」 / 今年の言葉 / 椿 / 紅葉便り(完)
『今日のクラシック音楽』 アルバン・ベルク作曲 オペラ「ヴォツェック」1925年の今日(12月14日)、アルバン・ベルク(1885-1935)が作曲しましたオペラ「ヴォツェック」がベルリンで初演された日です。ベルクは世に言われるところの「新ウイーン楽派」3人(シェーンベルグ、ウエーヴェルン、ベルク)のうちの一人で、ウイーンで活躍した、音楽の基本和声を無視して無調音楽や十二音技法などの手法を生み出した作曲家で、この曲もオペラ史上初めて無調音楽で書かれたオペラです。19世紀ドイツの劇作家の未完の戯曲を題材としており、この戯曲はドイツ文学史上初めてプロレタリア階級が登場した問題作と言われたそうです。音楽(オペラ)によって貧しい一兵士が社会に取り残されて、やがて破滅へと奈落の道を転がり落ちて行く男の生き様を描いています。床屋だった金なし、地位なし、お人よしの兵卒のヴォツェック(バリトン)にマリー(ソプラノ)という愛人がいて、二人には子供ができている仲だったが、お金がないために結婚できないでいるところに、荒んだ心になっていったマリーが軍楽隊長の誘惑に負けてしまう。 それを知ったヴォツェツクはマリーをナイフで刺し殺し沼に沈めるが、捨てたナイフを探しに再び沼に戻ってきて深みにはまって死んでしまいます。 幕切れはマリーが沼で死んでいると人々が駆けて行くのと一緒にマリーの子供が一緒に駆け出すところで終演となるオペラです。ベルクはこのオペラで疎外された人間による、現代社会での人のあり方を問いかけたのでしょう。 それにしても戦後間もなく製作されたビットリオ・デシーカの映画「自転車泥棒」に似たような、聴き終わったあとは何ともやりきれない気分になる非情の幕切れです。愛聴盤 フランツ・グルントへーバー(バリトン)、 ヴァルトラウト・マイヤー(ソプラノ) ダニエル・バレンボイム指揮 ベルリン州立歌劇場管弦楽団・合唱団(テルデック原盤 ワーナーミュージック発売 WPCS-5649/50 1994年4月 ベルリン ライブ録音)『今日の音楽カレンダー』1924年 初演 レスピーギ 交響詩「ローマの松」1925年 初演 ベルク オペラ「ヴォツェック」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今年の言葉』その年の世相を一字で最もよく表現する言葉が今年も選ばれました。 選ばれた言葉が京都清水寺住職によって筆で大きく書かれて発表されました。その言葉は「災」。今年日本本土に上陸した台風が10個。 それによる風雨での被害、中越地震の被害等の甚大な被害状況から選ばれた言葉でしょう。 被害による農作物への影響によって高騰した野菜の被害を受けた消費者の「災」もあるでしょう。 今年の世相を表現したぴったりの言葉だと思います。私なりに考えたもう一つの言葉があります。 「道」です。 今年は弱者が殺された、誘拐された、虐待されたという事件が顕著でした。 小学生が殺された事件。 誘拐されて不明になっている事件。 あとを絶たない親からの幼児虐待事件。 イラク武装集団に殺された、あるいは誘拐された外国人市民。 「おれおれ詐偽」の高齢者の被害等、枚挙に暇がありません。逆に権力側に座る人たちの「暴挙」も顕著でした。 強い立場にある者からの「暴挙」。 教師の生徒へのセクハラ事件。 警察官の電車内痴漢事件。 警察、地方公務員の組織ぐるみの公金着服(裏金作り)。 相も変らぬ自民党派閥の献金隠し。 これらも枚挙するに余りあります。こうした「人の道」を外した事件が多かったのも今年の世相の特徴で年々増加しているようです。 来年こそは「正義の道」が世の中を堂々と渡れるようになって欲しいという意味もこめて「道」を選びました。皆さんにとって「今年の言葉」は何でしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月14日
コメント(10)
-
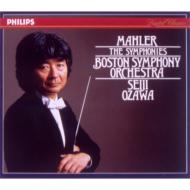
マーラー 交響曲第2番「復活」 / 亡父25回忌
『今日のクラシック音楽』 グスタフ・マーラー作曲 交響曲第2番 ハ短調「復活」1895年の今日(12月13日)、グスタフ・マーラー(1860-1911)が作曲しました交響曲第2番 ハ短調「復活」が、ベルリンでマーラー自身の指揮で初演された日です。 この交響曲は管弦楽とソプラノ、メゾ・ソプラノと合唱団によって演奏される曲で、マーラーはこの2番のほかに、3番、4番、8番それに「大地の歌」という交響曲に声楽を加えています。5つの楽章から成る、演奏時間が約1時間20分を要する大作で、声楽部分は彼の歌曲集「少年の不思議な角笛」の旋律が使われており、これは続く第3番、第4番との三部作のような関連もある曲です。この曲の副題「復活」は、終楽章にドイツの詩人の詩が、(一部マーラーによって書き直されていますが)、引用されており、その詩が「復活」という題名に由来しているそうです。 曲は第1楽章が葬送行進曲という従来の交響曲形式とは異なる書き方で始まっています。 マーラーの有名な言葉 : 「人が永遠に生きるためには、まず死ななければならない」 これは死後の世界に永遠の命を授かり、理想郷を夢見ているマーラーを表している言葉ですが、この第2番「復活」は死のあとにくる永遠に生きながらえようと憧れを歌った彼の作品の中でも代表的な曲です。 終楽章に用意されたアルト、ソプラノ、合唱と管弦弦楽の音楽曼荼羅は、荘重でスケールの大きな音楽によって「復活」を高らかに歌い上げています。愛聴盤 (1) 小澤征爾指揮 ボストン交響楽団 キリ・テ・カナワ(ソプラノ) マリリン・ホーン(メゾ・ソプラノ) タングルウッド音楽祭合唱団 (Philips レーベル 420 824-2 1986年ボストン録音)(2) エリアフ・インバル指揮 フランクフルト放送交響楽団(DENON CREST1000シリーズ COCO70471 )(3) オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 エリザベート・シュヴァルツコップ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1895年 初演 マーラー 交響曲第2番「復活」1928年 初演 ガーシュウイン 「パリのアメリカ人」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『亡父25回忌』12月13日は父の命日で今年は亡くなって25年になります。 25回忌の法要は昨年済ませていました。 妹夫婦と妹の息子夫婦が昨日の午後墓参りに来てくれました。 驚いたことにまだ2ヶ月の赤ちゃんを連れてきていました。 静かによく寝ていましたが、風邪をひかないかハラハラしました。母を含めて皆で、自宅から徒歩5分くらいのところにある墓地へ車で行ってお参りを済ませてきました。 きっと父は驚いているでしょう。 生まれて2ヶ月のひ孫まで行ったのですから。帰宅してから宅配ビザを注文してひとしきり赤ちゃんの話題で話に花が咲き、楽しい午後の日曜日のひとときとなりました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月13日
コメント(10)
-
ブラームス 「クラリネット五重奏曲」(追記あり) / 町内の清掃
『今日のクラシック音楽』 ヨハネス・ブラームス作曲 クラリネット五重奏曲偶然の出来事ですが有名作曲家とクラリネット奏者との邂逅の機会が,そのクラリネットの名曲を生んでいるのです。 モーツアルトからはあの「クラリネット協奏曲」や「クラリネット五重奏曲」がシュタットラーという奏者との出逢い、ウエーバーからはやはり2曲の「クラリネット協奏曲」や「クラリネット五重奏曲」が書かれています。1891年の今日(12月12日)、ヨハネス・ブラームス(1833-1897)が書きました「クラリネット五重奏曲」が初演されています。 この曲も彼がマイニンゲンの宮廷オーケストラの首席クラリネット奏者リヒャルト・ミュールフェルトに出逢い、その音色に魅せられて書いたという有名なエピソードのある曲です。ブラームスにはベートーベンという偉大な先人が残した曲のために、作曲には非常に慎重になったようです。 ベートーベンの9曲の交響曲が彼の前に聳え立つように遺されていたために、ブラームスは第1番のシンフォニーを完成させるのに20年の歳月を費やしています。 ベートーベンと並び賞される、あるいは超える曲を書くのに苦労したのでしょう。室内楽曲でもやはりベートーベンの偉大な作品群の前に筆が鈍ったのでしょうか「弦楽四重奏曲第1番」を書いたのは40歳になってから、「弦楽五重奏曲」にいたっては57歳になってようやく作曲しています。音楽評論家の故門馬直美氏の畢生の大作「ブラームス」(春秋社刊)を読みますと、この「弦楽五重奏曲」を完成した57歳の頃(1890年)にはもう作曲意欲を喪失している 頃だったそうで、非常に寡作になっていた頃でした。そんな彼に創作意欲を奮い立たせたのが前述のクラリネット奏者ミュールフェルトでした。彼の美しい音色に魅かれて彼はクラリネットのための曲を書き始めました。 そして現代ではモーツアルトのそれと2大名曲として輝いています。 (追記)ベートーベンが書かなかったクラリネットという楽器を得て創作意欲が湧いてきたのでしょう。 そのごクラリネットソナタも書いており、華やかさはありませんが、夜に聴くとしっとりとした滋味深い曲を遺しています。(追記終わり)すでに「人生の秋」が訪れていた頃ですから、非常に美しい旋律の中に、「諦観」めいた哀愁漂う曲となっていて、第2楽章などはジプシー風の音の響きが東洋的な渋みのある 雰囲気を漂わせています。 彼の交響曲第4番と同じように「人生のたそがれ」「人生の秋」を感じさせるクラリネットの名曲中の名曲です。 今日の初演日にちなんで聴いてみようと思っています。愛聴盤 アルフレート・プリンツ(クラリネット) ウイーン室内合奏団員(オイロディスク原盤 DENONレーベル 1980年4月ウイーン録音)プリンツのクラリネットに魅せられる演奏です。 最高音から低い音までピッチはびくとも揺れることのない一貫した音色を保ち、ゲルハルト・ヘッツェル(Vn)などのウイーンフィルの弦楽奏者による、柔らかいウイーンの響きともいえるアンサンブルが聴く者をひきつけます。 カップリングはモーツアルトのクラリネット五重奏曲で、天国的な明るさの名曲をも味わえる極上の演奏・録音です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『町内の清掃』昨日(12月11日)は町内をあげての清掃を行いました。 町内会運営委員やボランテイアの人たちの手で、公園や集会所周りの枯葉やビン・缶などのゴミを拾い集め、見る見るうちに美しくなりました。 自宅前なども個人でやってもらい町内が綺麗になりました。普段逢えない人たちとも会話が出来て、コミュニケーションにも最適の場となりました。 嬉しいのはPTAの働きかけで子供たちも大勢参加をしてくれたことです。 自分たちが毎日遊ぶ場所を丁寧にゴミ拾いをしてくれていました。出来る限り続けていきたいものです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月12日
コメント(2)
-
ベルリオーズ 幻想交響曲 / 花画像差し替えました / 今度は薬師さん
『今日のクラシック音楽』 ベルリオーズ作曲「幻想交響曲」ベートーベンが57歳で亡くなったのが1827年、その翌年1828年にシューベルトが亡くなっています。 今日の話題の「幻想交響曲」はベルリオーズによって、これら先人の偉大な作曲家の死後からのすぐの1830年に書かれています。 このことが凄いことなんです。1803年の12月11日は、このへクトール・ベルリオーズ(1803-1869)が生まれた日です。 今日は彼の誕生日にちなんでこの「幻想交響曲」を採り上げました。何が「凄い」のか? 彼がこの曲を書くまでは絶対音楽の象徴のような存在だった交響曲に、標題と物語性を表したことです。 音楽史上、交響曲を「標題音楽」とした最初の作曲家で、現代でもオーケストラ作品として最も人気の高い曲の一つです。この曲を書いた当時、パリ(彼はフランス人です)にシェイクピア劇を公演する劇団が英国から訪れていて、彼はその劇団の花形女優ハリエット・スミスソンに強烈に恋心を抱いたのですが、彼女からは鼻もひっかけてもらえぬままにパリから劇団は次の公演地に行ってしまって、ベルリオーズは失恋をしました。その時の失恋感情を音楽に表したのが、1830年に完成した「幻想交響曲」です。 ある芸術家が恋に狂い、失恋して人生に飽きてしまってアヘンの毒物自殺を図るが、致死量でなかったので重苦しい夢を見て異常な幻影に悩まされてしまい、その幻影の中で常に現れるのが「固定観念」のようになった恋人の旋律である、と彼自らが書残しているように、この曲は「ある芸術家の挿話」と副題が付いています。第1楽章 「夢と情熱」 狂おしい恋の情感を描いており、ここで表れる「恋人の旋律」は以降の楽章にも出てきます。第2楽章 「舞踏会」 華やかなワルツの調べで舞踏会に現れてくる恋人を予感しています。 交響曲にワルツを用いる発想がベルリオーズの異才たる面目躍如といったところでしょうか。第3楽章 「野の風景」 夏の夕暮れに田園で休む芸術家の胸によぎる恋人の姿。 雷鳴と孤独が暗い将来を暗示しています。第4楽章 「断頭台への行進」 とうとう彼は彼女を殺してしまい、処刑場へ進むさまを描いています。 ここでの行進もあくまでも不気味です。 ギロチンの降りる前にちらっと恋人が脳裏をよぎるかのように「恋人の旋律」が現れます。第5楽章 「ワルプルギスの夜の夢」 彼を弔う魔女の饗宴の模様がグロテスクに描かれています。 審判の鐘と魔女のロンドが交錯するフィナーレです。これほどの曲をベートーベンの死後3年ばかりで書いたベルリオーズはやはり「鬼才・奇才」なのでしょう。 この曲を聴いたリストが交響詩を創始するきっかけになったと言われています。ちなみにこの曲の成功で、ベルリオーズはやがてスミスソンと結婚することができたのですが、二人の生活は10年くらいで破綻をして、その後ベルリオーズは2度結婚しますが妻に先立たれて、最後は一人寂しく67歳の人生を終えたそうです。愛聴盤 チョン・ミュン・フン指揮 パリ・バスティーユ管弦楽団(ドイツグラモフォン 445 878-2 1993年10月録音)どのフレーズにも輝かしい生命力が感じられて、生き生きとした音楽の精彩が始まりから終わりまで一貫しており、所謂楽譜が透けてみえるという演奏で、熱に炙られる若き芸術家の心情を見事に音で表した演奏。 不滅の名演奏のシャルル・ミンシュの豪快なスケールとフランスらしい明るさと輝きのある録音盤とは、少し違う趣きがあるミュン・フュンの素晴らしい名演奏だと思います。『今日の音楽カレンダー』1803年 誕生 エクトール・ベルリオーズ(作曲家)1925年 初演 ニールセン 交響曲第6番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今度は薬師さん』先日の夜、入浴してパジャマに着替えてPCに向かっていると電話。 同級生の女性が経営している居酒屋からの電話でした。 現在の神社役員と元役員の各1名が呑みにきているから来ないかという誘い。 大先輩でもあるので断われず、パジャマの上にセーター、ジャンパー、ズボンを着けて徒歩5分の店まで行くと赤ら顔の二人がカウンターに座って呑んでいました。両名とも11月23日の信州旅行に同行してくれたので、話題はそっちの方に。 ひとしきり話が終ると、一人が切り出しました。 「薬師さんの役員を来年9月で終るから、後任にあんたを推挙しておいた。 頼むよ」「えッ! ちょっと待ってください。 来年は私は神社の会計をまかされる身です。 それに神社と薬師さんの祭礼は、同じ日で重なりますから会計を担当していると重なる日は薬師さんの方には列席できないですよ。 無役なら問題ないかも知れませんが。 やらないとは言いませんから2年待って下さい。 神社の会計を来年から2年やります。 それが終って・・・・」と言っても聞く耳持たぬの様子。こういう役は自分の方から頼んでできるものではないから、頼まれているうちが華かとも思うのですが、お金を管理しながら他所の祭礼のため神社を離れることもできないから、ここはひとつ断って2年先に勤めようと思っています。 その話し合いが12日(日)です。 しっかりと断らなければ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月11日
コメント(10)
-
スクリャービン 「法悦の詩」 / 年末ジャンボ宝くじ
『今日のクラシック音楽 』 スクリャービン 「法悦の詩」1908年12月10日は、旧ロシアの作曲家スクリャービン(1872-1915)が書きました「法悦の詩」(交響曲第4番)がニューヨークで初演された日です。スクリャービンには「神聖な詩」とか「火の詩」とかの「・・の詩」とかのタイトルのついた曲が多いのですが、これらの曲は交響曲として分類されています。 この「法悦の詩」も交響曲第4番と呼ばれていますが、むしろ「交響詩」にちかい単一楽章で書かれた曲です。音楽は彼独自の「神秘和音」という手法で書かれており、「法悦」とは宗教的に使われる言葉ですが、彼は精神的、肉体的恍惚(エクスタシー)を描こうとしており、官能的な響きの曲です。 演奏時間約20分ほどの曲ですが、初演されたあと、ロシア正教会はこの曲の官能性に異議を唱えて上演禁止を申し入れたといういわくつきの曲です。スクリャービンはピアノの名手だったそうで、彼が遺したピアノソナタは「ロシアのショパン」と呼ばれたほどの名手が書いただけに、美しい響きのソナタが多く、最近私はよく取り出して聴いていますが、スクリャービンを知る上にこの「法悦の詩」は忘れることのできない作品の一つです。愛聴盤 ウラジミール・アシュケナージ指揮 ベルリン放送交響楽団(DECCA レーベル 49061 1990年5月録音)『今日の音楽カレンダー』1822年 誕生 セザール・フランク(フランスの作曲家 代表曲 交響曲ニ短調)1908年 誕生 オリヴィエ・メシアン(フランスの作曲家 代表曲 「トゥーランガリラ交響曲」)1908年 初演 スクリャービン 「法悦の詩」1910年 初演 プッチーニ オペラ「西部の娘」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『年末ジャンボ宝くじ』今朝仕事で出る前に例の珈琲ショップへ立ち寄ると、マスターから大阪駅方面に出るなら宝くじ(年末ジャンボ)をまとめ買いを頼まれました。 バラが100枚 連番20枚。 近所の連中が集まってまとめて買うらしい。 大阪駅なら特設宝くじ売り場があります。 全国の売り場でダントツの1等当選確率の売り場で、九州や四国方面からも買いに来る名物売り場です。仕事の帰りに寄って頼まれた枚数を買ってきました。 自分の分は10枚(バラ)も買いました。 渡したうちで当たり券があれば、10,000円以上1等までの場合は20%もらえる約束です。 以下の当たりであればもらえません。でも、当たった人が申し出てくれないと番号を控えているわけではありませんから、私にはわかりません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月10日
コメント(8)
-
ラロ チェロ協奏曲 / 今年の紅葉
『今日のクラシック音楽』 エドゥアール・ラロ作曲 チェロ協奏曲ニ短調1877年の今日(12月9日)は、スペイン系フランス人作曲家エドゥアール・ラロ(1823-1892)が書きましたチェロ協奏曲ニ短調が初演された日です。ラロはヴァイオリオン協奏曲の形式の「スペイン交響曲」やオペラ「いすの王様」などで有名ですが、もう1曲彼を有名にしているのがこのチェロ協奏曲です。 曲は「スペイン交響曲」と同じくスペイン情緒に溢れた作品で、ローカル色の強い旋律が親しみと美しさ、楽しさに満ちたチェロと管弦楽のための協奏曲として出色の出来映えです。 ただこの曲は独奏チェロのための「カデンツア」がないので他のチェロ協奏曲と少し趣きが違います。愛聴盤 ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ) スタニスラフ・スクロヴァチェフスキー指揮 ロンドン交響楽団(マーキュリー レーベル PHCP-10326 1962年7月録音)35mmマグネットフィルム・レコーデイングによりダイナミックレンジが驚異的に広くなった録音で、、LP発売当初から話題になった盤。 シュタルケルの卓越した技巧と、スケールの大きな、豪快な表現で聴く者を圧倒する演奏です。カップリングはシューマン、サン=サーンスのチェロ協奏曲で1枚のCDでロマン的な3曲を聴ける徳用盤でもあります。『今日の音楽カレンダー』1877年 初演 ラロ 「チェロ協奏曲」1905年 初演 R.シュトラス オペラ「サロメ」1915年 誕生 エリザベート・シュヴァルツコップ(ソプラノ)1942年 初演 ハチャトリアン バレエ音楽「ガイーヌ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今年の紅葉』今年は所謂紅葉の名所と親しまれている所には一度行ったきりなので間違いかもしれませんが、近くの公園の「いろは紅葉」なども「色づき」が悪く、紅くなってくると葉が痛んでしまい、落葉するケースが多いようです。 名所にしても遠景から眺めると美しいのですが、近くで見ますと色が悪く葉も悪いという印象でした。 静岡に住んでいる家内も「今年の紅葉は色がおかしい」と電話で言ってました。 京都の名所を訪れた人たちも異口同音に同じことを言っています。やはり温暖化の影響なのでしょうか? 名所のもみじはしっかりと手入れをされているので、余計にそう感じます。 人が知らず知らずの間に自然の摂理を壊していってるのでしょうか? 悲しいことです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月09日
コメント(2)
-
ベートーベン 交響曲第7番 / 神社前にゴミを置かないで
『今日のクラシック音楽』 L.V.ベートーベン作曲 交響曲第7番イ長調作品作品921813年の今日(12月8日)は、L.V.ベートーベン(1770-1827)が作曲しました、彼の7番目の交響曲第7番が初演された日です。この曲は前作の「田園」交響曲が標題音楽的に書かれ、自然への愛と感謝に溢れた曲であったのに対して、曲全体を支配しているのは強烈なリズムです。 フランツ・リストは「リズムの神化」と形容し、ワーグナーは「舞踏の神化」と形容したそうです。 全楽章が力強いリズムで貫かれています。「バッカスの饗宴」という言葉がありますが、この曲はまるでギリシャ神話の酒の神さまのバッカスの狂乱に例えられるほど、強烈なエネルギーの爆発が大きな魅力です。彼の時代の前、ハイドンやモーツアルトの交響曲は勿論のこと、ベートーベン自身としてもこれほどにリズムを大切にして、絶妙に展開させた曲を書いたことがありません。 終楽章のたたみかけるような終結部は、非常にスリリングな楽想で締めくくっています。愛聴盤 レナード・バーンスタイン指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(ドイツ・グラモフォン 423 481-2 1980年録音 輸入盤 ベートーベン交響曲全集)『今日の音楽カレンダー』1813年 初演 ベートーベン 交響曲第7番1849年 初演 ヴェルディ オペラ「ルイザ・ミラー」1865年 誕生 ヤン・シベリウス(フィンランドの大作曲家)1915年 初演 シベリウス 交響曲第5番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『神社前にゴミを置かないで』最近、神社の鳥居のそばに生ゴミや粗大ゴミを置いていく人があり困っています。 今日も電気製品の不用となった物が置かれていました。 そこで神社としてもこれを放置するわけにはいかず、小さなたて看板を作り「ここはゴミ置き場ではりません」と書いて住民の注意を喚起することに決めて、昨日の午後に看板製作業者に神社に来てもらって看板の大きさ、書く言葉などを打ち合わせました。 神社にそういう看板を立てたくないですが、これ以上ゴミ投棄を放置できないので立てることにしました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月08日
コメント(6)
-
マスカーニ オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」 / 不断桜
『今日のクラシック音楽>』 ピエトロ・マスカーニ作曲 オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」1863年の今日(12月7日)は、イタリアの作曲家ピエトロ・マスカーニ(1863-1945)が誕生した日です。 マスカーニといえばこの曲、オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」です。マスカーニ25歳の時の作品で、ローマの楽譜出版社が募集したオペラ作品に応募して賞金をもらい、初演は1890年の5月17日にローマで行なわれています。 この初演は大成功をおさめ、マスカーニは一躍有名作曲家となったオペラです。このオペラは同名小説をオペラ化したもので、開放的で感情的なところのあるシチリアを舞台にした一幕オペラで、「カヴァレリア・ルスティカーナ」とは「田舎の騎士道」という意味です。 謂わば「男の道」みたいなものでしょう。 シチリア人は激情的なところがあり、すぐに感情を露にする傾向があり、「シチリアの決闘」という言葉があるほど熱しやすい気質の地方です。物語はシチリアのある村の青年トリッドゥが兵役から免除されて帰ってくると、恋人だったローラが馬車屋のアルフィオと結婚していました。 そこで彼は、村の女性サントッツアと交際をするのですが、ローラのことを諦めきれず昔のようによりを戻します。 所謂「不倫恋愛」です。 このことを知ったサントッツアは嫉妬のあまり馬車屋に告げ口をしたために、二人の男の決闘となりトリッドゥは殺されて幕となる暗い話です。このオペラは「ヴェリズモ・オペラ」と呼ばれており、それまでのヴェルディの「椿姫」に代表される上流社会を舞台にしたオペラではなく、イタリアのどこの村にでもいる青年男女を主人公にして、「夢想的」な世界でなく、「現実的」な生活の中で起こることを描写したオペラです。 「ヴェリズモ」とは『現実』という意味です。音楽はシチリアの甘く美しい旋律に溢れており、幕が上がる前奏曲の途中でトリッドゥの甘い、激情的なアリア「おー、ローラ」から始まり、合唱曲はシチリアの風情を的確に表しており、有名なアリア「ママも知る通り」(サントッツアのアリア)や、コンサートで単独で採り上げられる美しい「間奏曲」、それにトリッドゥのお母さんとの別れの決闘前に歌う「母さん、あの酒は強いね」など、70分あまり聴く者をシチリアへと誘うオペラです。 旋律は美しく、哀愁もあり、アリアも素晴らしいオペラです。 マスカーニの誕生日にちなんで今日はこのオペラを楽しみます。愛聴盤 マリオ・デル・モナコ(テノール) ジュリエッタ・シミオナート(メゾ・ソプラノ) コーネル・マックニール トリオ・セラフィン指揮ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団・合唱団(Decca レーベル UCCD 3341 1960年7月ローマ録音)もう44年前のステレオ録音ですが、デル・モナコの感動的な「黄金のトランペット」最盛期で、シミオナートのあたり役サントッツアは、未だにこの録音を凌駕する歌唱がないと思えるほどの激情に溢れた名唱です。 もう数え切れないくらい聴いていますが、『母さん、あの酒は強いね』のモナコのアリアは今でも涙が溢れてくるほどの迫真の歌唱、シミオナートの「ママも知るとおり」の切ないサントッツアの心情のアリアなど、色褪せない名演奏です。1962年にNHKの招きで来日した「イタリア歌劇団」は日本中のオペラファンを熱狂させて去って行きました。 モナコとテバルデイの「アンドレア・シェニエ」モナコの「道化師」アルド・プロッテイの「リゴレット」 テバルデイの「トスカ」 モナコの「アイーダ」 それにシミオナートのこの「カヴェレリア・ルスティカーナ」とまさにオペラファンを完全にKOした秋でした。幸運にも私は大阪公演でモナコの「道化師」 シミオナートの「カヴァレリア・・・・」をフェスティバルホールの指揮者の真後ろの最前列で観ることができました。 高校2年生でした。 あの夜の名舞台が昨日のように蘇ってきます。 NHK映像DVDであの夜の感動を味わっています。(NHK DVD キングインターナショナル KIBM1016 1962年 東京文化会館での公演ライブ)最近の映像で凄いのがあります。 ゼッフィレッリが演出したオペラ映画「カヴァレリア・ルステイカーナ」がそれです。 プラッシード・ドミンゴのトリッドゥ、オブラソッワのサントッツア、ジョルジョ・プレートルの指揮で演奏されるこの映画は、ゼッフィレッリ抜きでは話せない映画です。 オペラ音楽を忘れて映像、映画として見事な出来映えです。 ドミンゴ、ストラータスのオペラ映画「ラ・トラヴィアータ」と双肩の出来映えです。『今日の音楽カレンダー』1863年 誕生 ピエトロ・マスカーニ(オペラ作曲家)1873年 初演 チャイコフスキー 幻想曲「テンペスト」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『不断桜』先月末に大阪長居植物園・公園で「10月桜」という桜の花を撮影して「桜」に興味を持ち、調べてみると桜には色々と種類というか名前があるのを知って、先日も「10月桜」をこのプログで掲載しました際に「冬桜」を紹介しましたが、その後「不断桜」という名前があるのも今日の毎日新聞朝刊で読みました。「不断桜」とは、9月になると葉の中に一つ、二つと花を見つけるようになり、葉が落ちてしまうと次第に花が多くなってて11月に満開となる。 12月になると寒さのせいか花の数は減っていくけれども、春までぽつりぽつりと咲き続けて、4月になると他の春桜と同じようにパッと満開になる、そういう桜のことを指して呼ぶらしいです。花びらは一重でなくて八重の種類だが、せいぜい二重くらいの花が多いそうです。 10月桜と同じように花びらは小さく、色は桃色になっていき、小さい黄緑のがくがあるのが特徴だそうです。国指定の天然記念物の「不断桜」が三重県鈴鹿市の子安観音境内にあるそうです。 こちらをクリックして下さい。不断桜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月07日
コメント(10)
-
チャイコフスキー 「くるみ割り人形」 / 冬宮祭
『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 バレエ音楽「くるみ割り人形」1892年の今日(12月6日)、チャイコフスキーが書きましたバレエ音楽「くるみ割り人形」が初演された日です。「白鳥の湖」「眠りの森の美女」と共に「3大バレエ音楽」といわれる曲で、初演されたペテルブルグのマリンスキー劇場では今でもクリスマスの夜にこのバレエが上演されている様子がNHKで放映されていました。原作はドイツの作家ホフマンの「くるみ割り人形とねずみの王」で、マリンスキー劇場の依頼で作曲されたそうです。クリスマスの夜、クララの家でパーテイが開かれてグロッセルマイヤーという老人から、クララはくるみ割り人形をプレゼントされます。 その夜、クララが目を覚ますとくるみ割り人形が大勢のネズミと闘って負けそうだっと。 クララはネズミたちにスリッパを投げつけると、なんと醜い人形は凛々しい王子さまに変身して、クララをお菓子の国へ案内します。 クララはそこで歓待されて、幸せな気分に浸っているのですが、それはクララのクリスマスの夜にみた夢だったというお話です。お菓子の国で遊ぶクララの幸せな気分に溢れた曲の数々で、可愛らしい曲など楽しい音楽でいっぱいです。 私は特に「こんぺい糖の踊り」が大好きです。愛聴盤 アンドレ・プレヴィン指揮 ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団(EMIレーベル TOCE59031 1986年録音)その他『今日の音楽カレンダー1841年 初演 シューマン 交響曲第4番1880年 初演 チャイコフスキー 「イタリア奇想曲」1929年 誕生 ニコラス・アーノンクール(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『冬宮祭』昨日(5日)はこの町の神社の大例祭のひとつ「冬宮祭」があり、朝の9時から夕方まで社務所に詰めて参拝される方たちへの応対と、大晦日の新年参拝客への準備をしていました。 毎年大晦日にはお札・絵馬や三宝など神事に使った廃棄物を持ってこられる参拝客のために「とんど」を境内で炊いているのですが、今年はその薪が少なくなっているので薪割りをしたり、大晦日に販売する新しい干支の絵馬の整理をしたりして時間を過ごしていました。昨日は「弥生ロマンウオーク」という催しがあって、町にある弥生文化博物館を出発した人たちが次々と神社を訪れてくれて、神社の歴史などを説明する一幕もありました。 こういう機会があると改めて神社の歴史を振り返るということが出来るのと、普段は知っているつもりでも体系的には歴史をあまり知らない自分にがっくりでした。 勉強になりました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月06日
コメント(6)
-
ディヌ・リパッティのモーツアルト / 法隆寺に行けなかった
『今日のクラシック音楽』 W.A.モーツアルト ピアノソナタ第8番 イ短調 K.3101791年の今日(12月5日)は、W.A.モーツアルト(1756-1791)の命日です。 彼は今日、わずか35歳の若い生涯を閉じています。 遺作「レクイエム」の未完の部分を弟子のジェスマイヤーに細かく指示をした数時間後に息を引き取ったそうです。 彼の命日にちなんでその「レクイエム」を聴こうかと思いましたが、もう一人若き命を白血病で散らしていった天才ピアニストがいます。 彼が遺したピアノ録音の中で、私に強烈な印象を与えたモーツアルトのピアノソナタの録音があります。 曲はソナタ第8番イ短調、ピアニストはルーマニア生まれのディヌ・リパッティ(1917-1950)。 高校2年生のとき、ラジオのクラシック番組から流れてきたモーツアルトの演奏に驚きました。 それまで聴いていたピアノの音と違って、まるで蝶々が舞うように鍵盤上を軽やかなタッチで動き回るかのような音に耳を澄ませました。 それがこの第8番のピアノソナタでした。 以来私はこの曲が忘れられないものとして心に残っています。あとになって、この曲はモーツアルト22歳の1778年パリ滞在中に書かれたこと、それも同行していた母の体調がどんどん悪くなって亡くなってしまったのですが、その死の直前に書かれていたことを知りました。 曲はイ短調という暗い調性で書かれており、おそらく母の死をすでに覚悟をしていた彼の心情が書かせたかのように、悲劇的な色合いの音楽です。一方、ディヌ・リパッティは白血病に冒されており、主治医からは演奏活動をも禁止するよう勧告されている状況の中で、フランスのブザンソン音楽祭のリサイタルへの出演を「約束を守らなければ」という思いで、医師のギリギリの説得を振り切ってこのリサイタルを行なったそうです。誰もが彼の最後のリサイタルになるだろうと考えており、その夜の聴衆も「告別のリサイタル」と知っていたようです。そのステージで演奏された曲の一つが、このモーツアルトのイ短調のソナタでした。 モーツアルトの、母との永遠の別れへの「レクイエム」だったかもしれないこの曲を採り上げたリパッテイの心情は、察するに余りあるものです。その演奏は見事という他のない、自分の死期が近いことを知ったリパッテイのモーツアルトへの深い共感が、美しい表情を湛えた演奏にならしめているのでしょうか、バッハのパルテイータ第1番、シューベルトの2つの即興曲、ショパンの13のワルツなどと同じように、鍵盤を駆け巡るタッチは軽やかですが、このイ短調ソナタはことのほか美しく輝くような演奏で、何度聴いても涙を禁じ得ません。コーチゾンという注射を打ちながらの演奏で、ショパンのワルツでは最後に残った第2番を弾く気力、体力はもう残っていなくて、13番までの演奏でやめざるを得なかったと、後にリパッテイ夫人が書いています。モーツアルトがジェスマイヤーに「レクイエム 二短調」の未完部分に細かく指示をした数時間後に息を引き取ったの同じように、リパッテイもこの告別演奏会の2ヶ月後の1950年12月2日に、あまりに若すぎる命を散らしていったのです。「リパッティ ブザンソン音楽祭における最後のコンサート」(EMIクラシックス TOCE-3159 1950年9月16日のリサイタル録音)『今日の音楽カレンダー』1830年 初演 ベルリオーズ 幻想交響曲1837年 初演 ベルリオーズ 「レクイエム」1946年 誕生 ホセ・カレーラス(テノール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『法隆寺に行けなかった』4日は先日日記に書きました奈良 法隆寺の若草伽藍の壁画を証明する破片や瓦の破片についての現地説明会と出土品展示を見られる日でしたが、母の血圧が高くなっていたのと、大晦日に神社で販売する「絵馬」が入荷するのと、鳥居と神木に掛ける『しめ縄』の業者との打ち合わせがあったために、現地へ行くことが出来ませんでした。 出土品に描かれているという「蓮」や人物のスカートの断片などを実際に見たかったのですが、残念でなりません。 今日も同じ催しが現地でありますが、明日は神社の「冬宮祭」なので、朝から夕方まで社務所詰め。 今回は縁がなかったと諦めます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月05日
コメント(12)
-
チャイコフスキー ヴァイオリン協奏曲 / ヨーグルト
『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 ヴァイオリン協奏曲1881年の今日(12月4日)、チャイコフスキー(1840-1893)が書いた「ヴァイオリン協奏曲」が初演された日です。 クラシック音楽の好きな人たちの間で「メン・チャイ」という言葉がありますが、メンデルスゾーンの流麗かつ美しいヴァイオリン協奏曲とチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲の二つを指して言う言葉なんですが、それほどにこの二人の協奏曲はポピュラリティを確立しており、レコード会社も新進気鋭の若手を売り出す録音にはよほど勇気がいる2曲とまで言われているくらいにポピュラーな曲になっています。ところがこの曲の初演当時は、オーケストラの楽員からでさえも不評を買うほど惨めな初演での批評だったそうです。 それでもこの曲の初演者であるブロッキーというヴァイオリニストが何度も、何度もこの曲を各地で弾き続けたお陰で今日の評価を得たそうです。曲は「ロシア」の香りがいっぱいで、開始楽章の冒頭からもうロシアの大地に投げ出されて、その大地に包み込まれるような強烈なチャイコフスキー節満載の旋律、音楽です。 どうしてこの曲が初演時に不評だったのか不思議です。第二楽章は「カンツォネッタ」と題されている「歌」の楽章で、哀愁に溢れた美しい旋律が聴く者の心を捉える、チャイコフスキー独特のスラブ的な美しさいっぱいの音楽です。一言で形容するなら「ボルシチ」料理といったロシア色濃厚な、ロマン的な音楽です。愛聴盤 アンネ=ゾフィ・ムター(Vn) アンドレ・プレビン指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(グラモフォン 00289 474 5152 2003年9月録音 輸入盤)カラヤンとの共演から15年、今回は夫君 プレビンとのおしどり共演で、夫婦となってから2枚目のCD(1枚目はプレビン作曲の「愛妻に捧ぐ」Vn協奏曲)です。第1楽章からムターのVnは、表情づけが濃厚で、熱く歌いこんでいます。 スケールの大きな表現と、スラブ色を超えた、もっと濃厚なロマン的な演奏で、彼女が年を重ねるごとにこの傾向が強く表れており(クルト・マズア指揮ニューヨークフィルの'97年ライブ録音のブラームス、同じ共演で2002年のライブ録音のベートーベン)、今回の演奏では前作のブラームス、ベートーベンを上回るほどの濃厚な表現で、妖艶なまでの美音・表情に圧倒されました。カップリングはコルンゴルド(1897-1957)のVn協奏曲。 アンドレ・プレビンがぞっこん惚れこんでいる作曲者で、ドイツを追われてアメリカ・ハリウッドで映画音楽に従事した後に書かれた曲で、プレヴィンにとって3回目の録音。 まるで映画音楽の中に入り込んだような曲、演奏で、ムター節全開です。私はこのコルンゴルドを聴きたくて買ったのですが、チャイコフスキーの素晴らしさに圧倒されました。 この曲を見直したと言っても過言ではない、強烈なインパクトでした。『今日の音楽カレンダー』1976年 逝去 ベンジャミン・ブリテン(イギリスの作曲家 有名曲 「青少年のための管弦楽入門」)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『ヨーグルト』私は好き嫌いという食べ物が無いのですが、何故かヨーグルトだけは料理に使われている場合を除いて嫌いで食べません。 ヨーグルトだけを食べるのがダメなんです。 インドへ仕事でよく行きました。 ほぼ全土の主要都市を訪問しました。 あそこは言語が13-14くらいあって、方言ではなく、全く違う言葉が話されています。 例えばニューデリーの人とチェナイ(前のマドラス)の人が会話ができません。 それで共通語の「英語」を使っています。言語が違うと文化、風俗も違ってきますから食生活も違います。 一般的にインド料理は「カレー」という概念が定着しています。 それは正しいのですが、日本のようなカレーではなく、香辛料(スパイス)が100種くらいあって様々なカレー料理のある国です。 このカレー料理が彼らの基本で、日本のように外国料理店がずらりと軒を並べていることのない、自分たちの伝統的な料理を大切にしている国民です。言語が異なると食生活も違います。 まづ、カレー料理の「辛さ」が北と南では違います。 インド人10億の人口で「菜食主義者」がほぼ8割から9割とも言われていても、その料理に違いがあります。 南から2000km離れている北に転勤になった人(これは異例のことなんですが)、ニューデリーでの生活を「外国生活」と呼んで、マドラスに出張するたびに南の独特の食材を持ち帰っていました。 一般的にニューデリーの主食は「ナン」とか「チャパティ」という小麦粉を練った竈焼きのパンですが、南は米です。 料理の味付けも異なります。そういうインドで共通しているのがヨーグルトです。 機内食には必ずヨーグルトが付いています。 辛いカレー料理のあとに食べられています。そんなインドで覚えましたのが、白ご飯にヨーグルトを混ぜ合わせて食べることです。 最初これを見た時は気持ちが悪くなりましたが、インド人の強引な薦めで一口食べてみました。 美味しい! ヨーグルトとご飯のマッチングが絶品なんです。 特に、スプーンを使わずに指のなかでご飯を丸めてそのまま手で食べると美味しいのです。 それからはインドでの食事には、「ナン」を食べない時は、ご飯にヨーグルトを混ぜて食べていました。 そのヨーグルトは食べますが、今でも単体では食べられません。 但し、ご飯は冷や飯です。 温かいご飯ですとヨーグルトの臭みで食べられません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月04日
コメント(6)
-
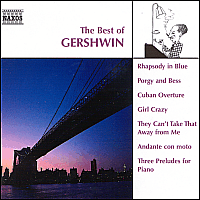
ガーシュウイン 「ピアノ協奏曲 へ長調」
『今日のクラシック音楽』 ジョージ・ガーシュウイン作曲 ピアノ協奏曲 ヘ長調1925年の今日(12月3日)は、アメリカの作曲家ジョージ・ガーシュウイン(1898-1937)が書きました「ピアノ協奏曲 ヘ長調」がニューヨークのカーネギー・ホールで彼自身のピアノ独奏で初演された日です。この曲は前作「ラプソディ・イン・ブルー」(ピアノと管弦楽の協奏曲風な音楽です)の成功のあとに書かれていて、完成までに相当の力の入れ方であったようです。 依頼は当時の指揮者ウオルター・ダムロッシュによるもので、彼の指揮、ニューヨーク交響楽団の演奏で初演されたそうです。前作の出来で自信を強めて作曲に力をいれて、オーケストレーションなどは何度も自腹を切ってホールを借り切って、楽団員を集めて音を確かめつつ完成していったそうです。この協奏曲は前作「ラプソディ・イン・ブルー」に較べると古典形式の色合いが濃い作品ですが、アメリカン・ジャズフィーリング、瑞々しいメロディ、スイングや洒落た和声などが聴かれるアメリカらしさのある洗練された感性と感覚が閃いている曲です。 ウイスキーグラス片手に聴くのもオツなものです。愛聴盤 ザ・ベスト・オブ・ガーシュイン (Naxos レーベル 8.556686) 「ラプソディ・イン・ブルー」や「ポギーとベス」などが収録された盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1883年 誕生 アントン・ヴェーベルン(オーストリアの作曲家 代表作「管弦楽のための五つの小品」)1934年 初演 ヒンデミット 交響曲「画家マティス」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月03日
コメント(4)
-

サン=サーンス オペラ「サムソンとデリラ」 / 法隆寺に最古の壁画
『今日のクラシック音楽』 サン=サーンス作曲 オペラ「サムソンとデリラ」1877年の今日(12月2日)は、フランスの作曲家シャルル・カミーユ・サン=サーンス(1835-1921)が書きましたオペラ「サムソンとデリラ」がドイツ・ヴァィマール大公歌劇場で初演された日です。旧約聖書のヘブライの英雄豪傑「サムソン」物語を題材に3幕にしたオペラで、現在では彼の書いたオペラで唯一世界で上演してされているオペラです。サムソンはヘブライ人の豪傑ですが、ヘブライはペリシテに征服された民族で 彼はヘブライのために数多くの戦いで勝って同族から英雄として崇められていますが、ペシリテの妖艶な美女デリラの誘惑に勝てず、彼の強さの秘密を彼女に教えてペリシテ人に捕らわれ盲目にされて処刑場に引き出されるのですが、神から最後の力を得て宮殿の柱を倒して全て崩壊させるという筋書きです。 劇中第3幕で踊りの場面がありますが、これは「バッカナール」として単独でコンサートや録音などに採り上げられる曲です。 弦と太鼓で刻むリズム、ヘブライ風の東洋的な旋律で、華やかさをふりまく音楽です。第2幕ではデリラが誘惑するアリア「あなたの声に心は開く」はメゾ・ソプラノ(デリラ役)の名曲の一つで、アリア・コンサートなどでよく採り上げられます。旧約聖書を題材にしている物語、現在の中東を舞台にしたエキゾチックな旋律、第3幕の神殿破壊という劇的なところがあっておもしろいオペラです。1950年代にセシル・B・デミル監督でビクター・マチュアが主演の映画がありました。 「サムソンとデリラ」というとこの映画、特に神殿破壊のスペクタクルなシーンを思い出します。愛聴盤 ホセ・クーラ(テノール) オルガ・ボロディナ(メゾ・ソプラノ) コリン・ディビス指揮 ロンドン交響楽団(エラート レーベル WPCS10004/5 1998年録音)このオペラは2001年5月19日にびわ湖ホールでニューヨーク・メトロポリタン歌劇場の引越し公演があり、ドミンゴのサムソン、ボロディナのデリラ、 ジェームス・レヴァイン指揮だったのですが、S=62,000円 A=52,000円、B=42,000円 C=32,000円 D=22,000円 E=14,000円で、とても切符を買えるものではない高嶺の花の公演でした。 両歌手のあたり役だったのですが、残念でした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『法隆寺に最古の壁画』世界最古の木造建築で世界遺産に登録されている法隆寺(奈良県斑鳩町)で、7世紀前半の壁画の破片が数多く(約60点)見つかったと、新聞やTVで報道されました。これは聖徳太子(574-622)が建立した初代法隆寺とされている若草伽藍の金堂か塔に描かれていた壁画の可能性が高く、現在保存されている法隆寺金堂壁画(8世紀前後)を約1世紀近くさかのぼる国内で最古の壁画と確認されたそうです。加えて、見つかった多数の破片に焼けた痕跡も見つかり、「日本書紀」に記されている「法隆寺焼失」の記述が歴史的事実に基づいていることを証明・裏づけするものだそうです。若草伽藍の金堂か塔に描かれていたと推測する根拠は、今回同時に出土された「瓦」からの推測であるらしい。先日の「池上曽根弥生遺跡」の『ミニ都城』と並んで、これは第1級の発見で、歴史に興味を持っている私にはこういう発見には、古代へのロマンをいっそうかき立てられ、今回の出土とその意味に鳥肌立つ思いです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1877年 初演 サン=サーンス オペラ「サムソンとデリラ」1883年 初演 ブラームス 「交響曲第3番」1903年 初演 シベリウス 「悲しきワルツ」1923年 誕生 マリア・カラス(ソプラノ歌手)1931年 逝去 ヴァンサン・ダンディ (フランスの作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 枇杷(びわ)の花 撮影地 大阪府和泉 2004年11月薔薇(ばら)科開花時期 11月ー12月下旬中国・日本原産葉の形が楽器の「琵琶」に似ているので名付けられている「枇杷」の字は中国漢名から花は白く、なかなか気付きにくい花葉は厚くて固いが薬用として使われてきた。 関節の痛みに効くらしい枇杷の実を漬け込んでおくと虫刺されに効く
2004年12月02日
コメント(8)
-
バルトーク 「管弦楽のための協奏曲」 / 師走
『今日のクラシック音楽』では、ベラ・バルトークが書きました「管弦楽のための協奏曲」が1944年12月1日にアメリカ・ボストンで名指揮者クーゼビッキーによってボストン交響楽団で初演されています。 この曲についてはすでに9月26日の日記で紹介しておりますので、今日はその他の音楽カレンダーのみの掲載とさせていただきます。『その他今日のカレンダー』1867年 初演 ブラームス 「ドイツ・レクイエム」1935年 初演 プロコフィエフ 「ヴァイオリン協奏曲第2番」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『師走』今日から「師走」月。 何となくせわしくなるような語感のある月名です。 昔は「師走」の意味は先生が走ると教えられた記憶があるのですが、どうもこれは間違いのようです。 かと言ってはっきりとした定説がないようです。 以下に挙げました説があるのですが、これも明確ではないようです。1.「師駆月」(しはせづき) 昔は坊さんはお盆だけではなく、暮れにも各戸にお参りに来てくれたことから訛ったらしい。 師はここでは僧職を意味する言葉。2.「為果つ」(しはつ)が訛った。 農作業や年中行事が終った意味から訛って「しわす」となった。3.「四極」(しはつ)が訛った。 四季の終わりということから「しわす」と訛ったという説。4.「年果つ」(としはつ)が訛った。 年の終わりを「年果つ」と言って、これが「しわす」と訛ったという説。いづれにしてもこの「師走」という言葉はじっと座っていることから、人を立たせて慌しくさせる言葉には間違いないようです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年12月01日
コメント(2)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 人気歌手ランキング
- 第76回 NHK紅白歌合戦 全出場歌手…
- (2025-11-15 04:58:28)
-
-
-

- クラシック、今日は何の日!?
- 鼻が詰まってるので花粉症に良いとさ…
- (2024-09-21 22:11:23)
-
-
-
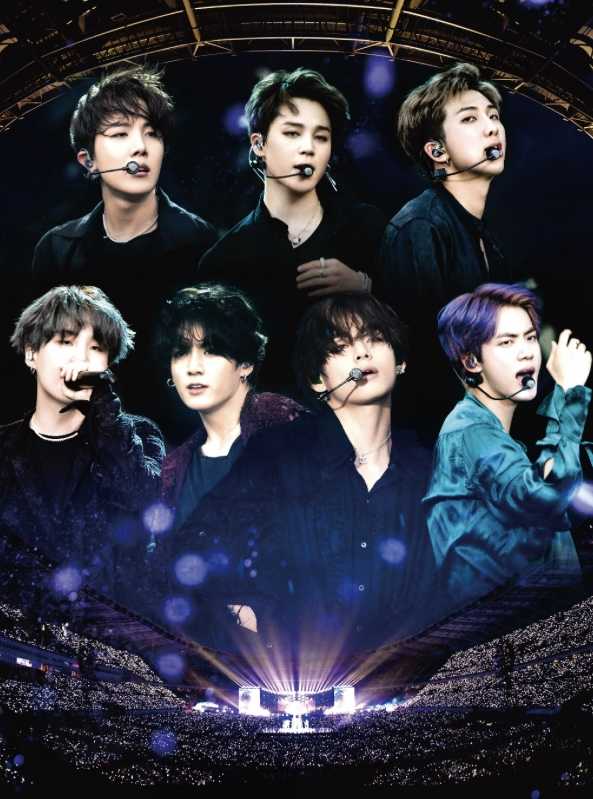
- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF のDVD…
- (2025-11-21 18:37:01)
-







