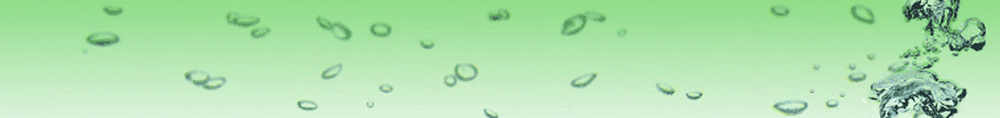カテゴリ: ガーデンデザイン
築山庭造伝 前編後編、石組園生八重垣伝、芥子園樹石画譜、芥子園風景画譜、山水並に野形図・作庭記、南坊録抜萃・露地聴書、余景作り庭の図・他三古書、都林泉名勝図会、園冶は、江戸時代後期の作庭の指南書といわれている。この書が日本の庭を画一化し、堕落せしめた原因の一つではないかと指摘される方もいる。
一方では、七代目小川冶兵衞のように各寺々を回り、それをモデルに庭造りしているのも事実。むしろ、そのような庭つくりの出来るデベロッパーとしてのプロデュースの方が突出していたという。純粋に「好い所」を組み合わせる構成の意味合いではデザインの一つといえる。何処かの先生のように「緑のデザイン」をするなどと訳のわからないデザインより判り易い。
様式や型はどの国にもあり、伝統芸能には無くてはならない伝え方の一つとして捉えてもよいのではないかと思っている。確かに、パターンとして認識してしまうと画一化され面白いものにならないという捉え方もあるが、国内の古典(あえて現代の庭と対比した時の表現)に関して扱っている石や造形物には「規格」が無い。無いからこそ「型」としての基本が理解出来き、批判もまた出来る。そしてそこには不易の域も存在する。
よい例が竹垣だ。竹垣の材料が変化しても物理的な変化に乏しい。この国の国民性が作り出したものとして最も機能的で豊富なデザインであってもその昔、新しい竹垣のデザインとして紹介された竹垣がシュロ縄で模様を凝らし、鯉を振り下げる程度が進化であり、矢来垣が既に在ったこの国の竹垣が木製のラティスに成り代わる程度の問題だ。
庭つくりの進化は住生活に伴って日々変化しているものだ。新たな素材を探し、新たな景色を求める。「そこでどの様に過ごす」のかを追求することで庭つくりの未来はバラ色だ。これまでの庭つくりの技術や要素を活かして新たな庭を作り出そう。
粗末なようでそうでないという意味合いで「侘び・寂び」の表現として露地庭書にはよく使われる歌に次のようなものがあります。
「見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮」
この歌は『新古今集』で歌われている藤原定家の歌です。一般的にこの歌は、
「浦の苫屋の秋の夕暮れ、見渡しても花も紅葉も見あたらない」
見渡せば花もモミジもない。だけど、浦の苫屋には秋の夕暮がある。
一方では、七代目小川冶兵衞のように各寺々を回り、それをモデルに庭造りしているのも事実。むしろ、そのような庭つくりの出来るデベロッパーとしてのプロデュースの方が突出していたという。純粋に「好い所」を組み合わせる構成の意味合いではデザインの一つといえる。何処かの先生のように「緑のデザイン」をするなどと訳のわからないデザインより判り易い。
様式や型はどの国にもあり、伝統芸能には無くてはならない伝え方の一つとして捉えてもよいのではないかと思っている。確かに、パターンとして認識してしまうと画一化され面白いものにならないという捉え方もあるが、国内の古典(あえて現代の庭と対比した時の表現)に関して扱っている石や造形物には「規格」が無い。無いからこそ「型」としての基本が理解出来き、批判もまた出来る。そしてそこには不易の域も存在する。
よい例が竹垣だ。竹垣の材料が変化しても物理的な変化に乏しい。この国の国民性が作り出したものとして最も機能的で豊富なデザインであってもその昔、新しい竹垣のデザインとして紹介された竹垣がシュロ縄で模様を凝らし、鯉を振り下げる程度が進化であり、矢来垣が既に在ったこの国の竹垣が木製のラティスに成り代わる程度の問題だ。
庭つくりの進化は住生活に伴って日々変化しているものだ。新たな素材を探し、新たな景色を求める。「そこでどの様に過ごす」のかを追求することで庭つくりの未来はバラ色だ。これまでの庭つくりの技術や要素を活かして新たな庭を作り出そう。
粗末なようでそうでないという意味合いで「侘び・寂び」の表現として露地庭書にはよく使われる歌に次のようなものがあります。
「見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮」
この歌は『新古今集』で歌われている藤原定家の歌です。一般的にこの歌は、
「浦の苫屋の秋の夕暮れ、見渡しても花も紅葉も見あたらない」
見渡せば花もモミジもない。だけど、浦の苫屋には秋の夕暮がある。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[ガーデンデザイン] カテゴリの最新記事
-
山縣有朋の庭園観 2010年11月11日
-
京都に行ってきました。 2010年10月31日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年07月
コメント新着
玉川造園・庭師の風…
yamituki64さん
香り&ハーブ・アー… ハーブクマさん
岐阜・愛知・滋賀で… hirokun0204さん
バカボンのお庭 バカボンのお庭1077さん
佐賀の植木屋みどり… みどり活動さん
香り&ハーブ・アー… ハーブクマさん
岐阜・愛知・滋賀で… hirokun0204さん
バカボンのお庭 バカボンのお庭1077さん
佐賀の植木屋みどり… みどり活動さん
カレンダー
キーワードサーチ
▼キーワード検索
© Rakuten Group, Inc.