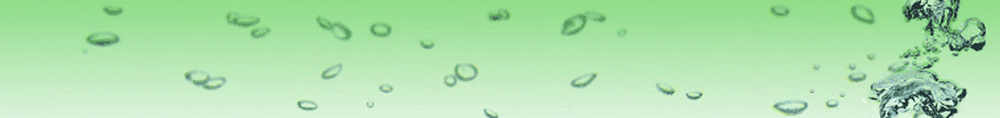カテゴリ: ガーデンデザイン
昨日は、今年一年を振り返って総括をしました。それぞれの持ち場の中で技術的な指摘や成長など勉強会での応用などです。今回は、「崩し」についてです。

とくに、私どもスタッフに延べ段の崩しについて理解が足りないことや、何故ジグザグなのか、また、延べ段の役割など確認の意味で各々に忌憚の無い意見を求めました。この文章では判りにくい部分ですが私たちスタッフには大切な事です。まず、延べ段はデザイン上の形だけではないこと、時折、雑誌で見よう見真似で造られた物を見る。形はそれなりに出来てはいるが、何故崩しているかは明らかに理解できていない。
怖い事は、それが形となって表れてしまうこと。既に景色を持つ鎌倉などではあえて特別景色(水場やオーナメント)を設けない現場もある。「何故そこを歩かせるのか、何故、欠け張りがあるのか、」禅問答のようにしつこく追求します。
スタッフ間の禅問答です。
問 、「写真は、形としてみれば旨く貼れているように見えるが、歩く部分が通っているように見える。また、欠け張りを出しているが崩しといえ、欠け張りの意味が無い様に見える。それについては如何か?」

答 、「崩しといえども安全に歩行する」ことが大事。」
問 、「それも一つの答え」 「それでは安全な延べ段であればまっすぐな形が理想か?」

「崩しの欠けや張りは何故あるのか?」
「また、設計者の意図を何とする。」
答 、「・・・・・・・」
と、この様にあっと言う間に楽しく2時間が過ぎていきます。
明日は、珍しく古典の現場とリノベーションされた現場2例です。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[ガーデンデザイン] カテゴリの最新記事
-
山縣有朋の庭園観 2010年11月11日
-
京都に行ってきました。 2010年10月31日
Re:崩すということ(12/27)
フィトライフ
さん
上記のような講義?勉強会?は外部の者でも参加させて頂けるのでしょうか?
(2006年12月28日 15時30分18秒)
Re[1]:崩すということ(12/27)
nek1113
さん
フィトライフさん
本当はネット通信教育をやっているのですがあまり知られていません。
ただ、本業が忙しく塾の企画もあるのですが開講出来ず開店休業状態です。ブログでも少しですが流していきますので宜しくお願いします。 (2006年12月28日 18時44分04秒)
本当はネット通信教育をやっているのですがあまり知られていません。
ただ、本業が忙しく塾の企画もあるのですが開講出来ず開店休業状態です。ブログでも少しですが流していきますので宜しくお願いします。 (2006年12月28日 18時44分04秒)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年07月
コメント新着
玉川造園・庭師の風…
yamituki64さん
香り&ハーブ・アー… ハーブクマさん
岐阜・愛知・滋賀で… hirokun0204さん
バカボンのお庭 バカボンのお庭1077さん
佐賀の植木屋みどり… みどり活動さん
香り&ハーブ・アー… ハーブクマさん
岐阜・愛知・滋賀で… hirokun0204さん
バカボンのお庭 バカボンのお庭1077さん
佐賀の植木屋みどり… みどり活動さん
カレンダー
キーワードサーチ
▼キーワード検索
© Rakuten Group, Inc.