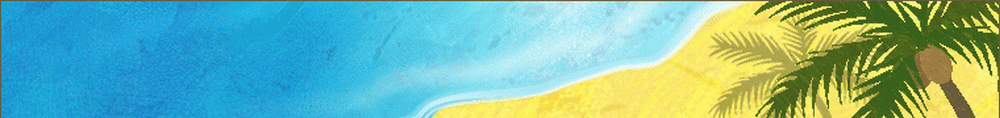僕が稲村ジェーンを見れない理由。
「僕が稲村ジェーンを見れない理由。」
「ビッグウェンズデー」や「ノースショア」が好きだった。
その映画を見るたびに、僕の身体はじんわりと夏の匂いを思い出す。
でも「稲村ジェーン」も同じようなサーフィンの映画だったけど
どうしても見ることができないままだ。
きっとそれは、あの夏が置き忘れていった思い出が、まだ僕の胸に残っているからだろう。
置き忘れた思い出。
忘れることのない、22歳の夏。
サングラス越しに見たサイドシートのカナコは、思わず息をのむほどキレイだった。
ペプシのタブを左手の薬指にはめてはしゃぐ姿が
窓越しに流れる白い海岸線にとても映えていた。
2年ぶりに訪れた、静かで暑い夏。
僕のミニクーパーの灼けつくような背中の上で
ミモザイエローのサーフボードがガタゴト揺れていた。
僕は波乗りをしていた。
大学一年の時、悪友に誘われるままに何気なく始めた波乗りだったが
こうして就職活動を控えた今も、引き寄せられるように真夏の太陽の下にやって来ている。
突き刺すような日差しが恋しくなると僕はステアリングを決まって「東」の方角にまわした。
そして9月の扉をノックするまで
チョコレート色の肌に潮風の匂いを染み込ませた。
今年も会社の内定が取れるよりも早く、僕はこの場所へ帰ってきた。
ただひとつ、いつもと変わっていたこと。それは助手席にカナコがいるということ。
仲間たちの集うセプテンバーカラーズのシーサイドカフェテリアには、いつもの笑い声が響き、
二人で買ったチキンフィレサンドを並んで頬張った。
波乗り仲間からはからかわれたけど、アイスティーの氷をストローでくるくる回して遊ぶ彼女を素直に愛していた。
「疲れた顔して海から上がってくるときのあなたがいちばん好き。」
カナコがデッキチェアに腰掛けながらそう言う。
「2番目に好きなのは、楽しそうな顔をして海に向かっていく時のあなた。」
キョトンとして佇む僕に、2つ年上の彼女は少し照れたように微笑む。
「だって、海から上がってきたら、あたしを愛してくれる番でしょ?」
そしてシャワールームに隠れてキスをした。
でも僕は知っていた。
季節がやがて僕達を引き裂いてしまうということを。
夏に出会った恋は、やがて二人の日焼け跡が消えていくのといっしょに終わっていくものだと。
僕とカナコの座るシートの距離が少しずつ近くなっていくのにつれ
8月の恋は消え去ろうとしていた。
「ねぇ、南十字星って北半球じゃ見れないんだよね。」
「あぁ。いつか見てみたいな。」
「・・・あたしも」
でも一緒に見ようという言葉は、なぜか言えなかった。
やがて僕達は別れた。
やっぱり1枚のサーフボードには二人じゃ乗れなかった。
恋は海のようにいつまでもそこにあるものではなく、
例えば夏のように、いつしか過ぎ去ってしまうものなのだ。
カナコは海じゃなかった。
カナコは夏だった。
夏の恋だった。
その年の秋はいつものようにやってきた。
ただひとつ変わっていたこと。
それはサイドシートにカナコがいないこと。
そこには彼女が置き忘れていったサザンのMDがポツンと置かれてあるだけだ。
それを聞くたびに僕は戻れない夏と、22歳の自分を思い出す。
僕が「稲村ジェーン」を見れない理由はこんなところだ。
© Rakuten Group, Inc.