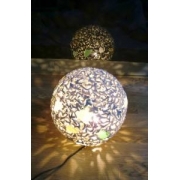PR
Calendar
Oct , 2025
Sep , 2025
Jul , 2025
宮古島に移住して
黒糖作りの工程
今日は朝から出かけてきました。
行先は沖縄電力宮古支店の敷地内にある野球場です。
宮古・八重山の少年野球チームが一堂に集まって毎年行われている野球大会です。
その様子は、後日報告したいと思っています。
さて、今日の話題ですが、
昨日の黒糖シロップ作りに続いて、今日はいよいよ黒糖作りの紹介です。
13日のブログで、≪サトウキビを絞って、大きな鍋状の容器に入れて、窯の上に乗せて、火を付けて、煮詰め始める≫所までは紹介しました。
その後ですが、
絞り汁が多かったからか、窯に火を入れてから小1時間経っても沸騰しません。

どうしてかな?と思っていると、作業をしておられるご主人とお友達が何やら話されていて、
鍋の底のすすを落とし始めました。
すすが底に付着していると、液の温度が上がらないんだそうです。
落としたとたんに沸騰して、ブクブクと泡立ち始めました。
すすは炭素そのもので、熱を通しにくい性質があります。
なので、地球へ帰還時のスペースシャトル外壁を空気との摩擦熱から守るためにに塗布してあるほどです。
そうした炭素の性質を経験からご存じのお二人の知恵に感心してしまいました。

湯気が立ち始めてからも、火加減を見ては材木をくべていきます。
先日の台風8号で折れた木の枝はたくさんあるんですが、火力が弱いそうです。
そのため、家屋の解体があると廃材をもらってきて貯めておくんだそうです。
沸騰が続くと、たくさんのアクが出てきます。

そのアクをすくっては取り、すくっては取り、何度も々繰り返します。
上の写真の釜も小屋も全てご主人の手作りです。
「手作りシートー屋」「ンマイ窯」と書いた表示がぶら下がっています。
これは「手作り砂糖屋」「おいしい(黒糖ができる)窯」といった意味合いで付けたと言っておられました。
表示板の下にコップと小さな皿があるのが分かるでしょうか?

窯の字の下です。
お神酒とお供えです。
窯に火を入れる前に、「火の神様」に安全をお祈りして供えるのを欠かさないとおっしゃっていました。
ガスコンロのスイッチを何気なくひねっている私たちが忘れた事を、いろいろと大切に守っておられる気持ち・姿勢に接して、背筋が伸びる思いでした。
更に材木をくべて煮詰めていきますと、泡が盛り上がってきます。
そうすると、

大きな柄杓でかき混ぜます。
空気に液を触れさせて温度を少し下げ、泡立ちを押さえます。
これも、泡立ちの状況を見ながら、何度も繰り返します。
と同時に、液の温度を見ているんだと思います。
120度強まで液温を上げるんですが、

最終段階に近くなると、温度計で確認します。
(手に持っておられる棒状の物が温度計)
いよいよ、最終段階です。

最初の液量の半分以下になっています。
温泉のxxx地獄そっくりの泡が、ブクッ・ブクッと出て、いい匂いがしています。
温度計で最終確認して、長かった煮詰め作業が終わりました。
窯に火を入れてから、約4時間の作業でした。
この後に固める作業が待っているんですが、ブログが少し長くなってしまいましたので、以降は明日の紹介とします。
沖縄の海辺 うみばたさん
pinpon. の気ままに… pinpon.さん
刺繍大好き♪のぞみの… のぞみ☆*⌒さん
石垣島♪母ちゃんのス… bluenaさん
Comments
Keyword Search