ニュース メディア
2018/3/2現在新聞の購読料は全国紙(朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、産経新聞)で朝刊と夕刊と合わせて4037年です。
地方紙も夕刊を発行している場合、だいたいそれぐらいの価格です。
1日あたり130円です。
決して安くはありません。
ところで日本経済新聞は2017年秋に値上げしました。
4509円から4900円(朝刊,夕刊セット)への値上げで約400円の値上げです。
日本経済新聞の場合は金融機関に勤めているサラリーマンなど、購読者層がほぼ決まっているので、多少値上げしても、購読者が大きく減ることはないと踏んだ値上げなのかどうかはわかりませんが、日本経済新聞は全国紙でも別格という感じもあるので、値上げしたんだなという思いぐらいです。
ところで他の全国紙ですが、購読者の減少に悩まされています。
様々な要因がありますが、ネットの普及によってネットによるニュース記事に押されていることもありますし、1990年代のバブルが弾けてからは、賃金が上がらないというか、上がらないどころか下がった方も少なくないので、生活防衛のために新聞を取るのをやめた方も少ないないと思われます。
ですから今の時代、値上げするならば、さらに購読者減少を加速させることになりかねず、新聞社にとっては自滅行為のようなので、当分は値上げすることはないだろうと考えていました。
値上げどころか購読者数を増やすために、値下げもアリかなとさえ思っていたのですが・・。

自分を高く売る技術 なぜ「値上げ」をしてもお客さまが離れないのか? [ 島田弘 ]
ところが
水面下では読売新聞が値上げを検討
しているようです。
値上げ幅は200円程度なんだそうですが、もし値上げが実施されれば4237円になることになります。
しかし今回は朝日新聞が値上げに合意していないようです。
ということで読売新聞以外の全国紙3社すべてが値上げするかどうかは不透明ですし、読売新聞は他社が値上げしないとなれば、値上げを断念するかもしれません。
いずれにしても、近い将来、値上げが実施されるのかどうか見守る必要がありますし、読売新聞が値上げしたからといって他社も追随して値上げするかどうかもわかりません。
購読者としては200円でも値上げしないほうが助かるのですが。

50円のコスト削減と100円の値上げでは、どちらが儲かるか? 読むだけで「儲かる会社の秘訣」がわかる本! [ 林総 ]
2018/2/2
梅毒といえば昔は、歓楽街などを中心に拡大する怖ろしい病気として知られていました。
進駐軍などは、軍のうちに梅毒が広まるのを怖れて、歓楽街とかかわりのある婦人の梅毒検査などを強要したことは知られています。
その後、梅毒と医学のとの闘いで、ある程度、梅毒を抑えることに成功した時期もあったようですが、しかし最近になって再び梅毒が増えてきているようです。
産経新聞2018年1月23日よると
梅毒の患者が急増している。症状に気づかずに進行してしまうことが多く、放置すると脳や心臓に合併症を引き起こすことがある。国立感染症研究所によると、平成29年の患者報告数は現行の集計となった11年以降で初めて5千人を突破。専門家は注意を呼びかけている。と報じました。
もしも治療もせずに放置するならば、致命的ともいえる病気です。
早期治療ならば治ることも可能ですが、再発すること多く感染してしまうと厄介な病気であることにちがいありません。
さらに日本では許可されていない薬で効果的に治すことができるともいわれていますが、副作用も怖ろしいものなので日本では認可されないようです。
いずれにしても自分とパートナー双方が感染しないような生活を送っているならば、何ら心配することのない病気です。
清く健全な生活を送っているならば、心配のあまり精神的に落ち込むことはないでしょう。

伊東毒性病理学 [ 高橋道人 ]
2018/1/26
近年、慢性的な財政難が続くなか、政府もなんとかして税収アップを図ろうとしています。
そこで増税のターゲットになるのが嗜好品ということになるわけですが、嗜好品のなかには、たばこがあります。
そしてたばこ増税は、いつも議論されることになるわけですが、一部の意見では、
たばこ増税をしても税収アップにはつながらない
という意見もあります。
その意見の根拠は、たばこ増税を行っても、その機会にたばこをやめる人や吸う本数を減らす人があらわれて、たばこの消費数が減るために税収もアップしないというのです。
たしかに、その通りなのかもしれませんが、しかしその意見には次の事実が見落とされているように思われます。
産経新聞2018年1月15日夕刊に掲載された記事ですが、それによると
たばこが原因で平成26年度に100万人以上が、がんや脳卒中、心筋梗塞などの病気になり、受動喫煙を合わせて1兆4900億円の医療費が必要になったとの推計を、厚生労働省研究班が15日までにまとめた。国民医療費の3・7%を占めるという。
と書かれていました。
つまりは、たばこが原因で1兆5000億円の医療費が費やされているのです。
もしこの1兆5000億円がかからなくなるならば、健康保険料もそれに応じて安くなることでしょう。
さらに医療費の約30~40%は税金が投入されていますので、税金投入額が軽減されることにもなります。
ということで、たばこ増税によって、たばこの消費本数が減って 結果的には税収アップにはならなくても、医療費の軽減にはつながり、保険料負担の軽減、さらには税金投入額の軽減効果があるということになります。
ということで、たばこ増税には行えば、それ相応の効果があるということになりそうです。

日本の地方財政 / 神野直彦 【本】
2018/1/8
昨年、日経新聞社本社において火災事件が発生しました。
本社ビルの一部が燃えたようですが、日経新聞社の業務そのものには大きな支障はなかったようです。
ところでこの火事の原因ですが、どうやらただならぬ事柄が原因のようです。
産経新聞2017年12月27日の記事によると
日本経済新聞社東京本社ビル(東京都千代田区大手町)で今月、2階の男子トイレから出火し男性1人が死亡した火災で、警視庁丸の内署は28日、死亡したのは西東京市芝久保町、無職、水野辰亮(よしあき)さん(56)と判明したと発表した。日本経済新聞社によると、水野さんは11月上旬まで練馬区内の同社専売店で所長を務めていた。同社広報室は「目立ったトラブルはなかった」としている。
と報道されていました。
さらに火災の原因について産経新聞の同じ記事には
火災は21日午前10時50分ごろ発生。トイレの床や壁など約30平方メートルが焼け、水野さんが倒れていた個室付近からは油の反応があった。遺書などは発見されていないものの、同署では現場の状況から自殺の可能性が高いとみて捜査している。
と報道し、元日経新聞専売所の所長(約1カ月前に辞職)による焼身自殺の可能性が高いとのことです。
新聞の記事には
同社広報室は「目立ったトラブルはなかった」としている。
と日経新聞側の広報では目立ったトラブルではないと述べて、新聞社による専売所いじめを否定していますが、しかし気になります。
そもそも今の時代、新聞販売店経営は厳しい舵取りの求められる事業です。
以前に書いた記事
新聞販売店の経営 今はとても厳しい時代
にも書いたとおりです。
しかも新聞社の意向に従わなかった専売所の所長が新聞社によって解職されることは珍しくありません。
今回の事件も「目立ったトラブルなかった」と日経新聞社は述べていますが、何かがあったのではないかとふと考えてしまいます。
いずれにしても所長不足の時代、所長になるための門は広く開かれていますが、しかし安易にその門をくぐらないほうが良いように思います。

【中古】 40歳からのキャリアチェンジ 中高年のための求職・転職術 / 楠山 精彦 / 日本経団連出版 [単行本]【ネコポス発送】
2017/8/18
一括借り上げによるアパート経営が2000年以降増えるにつれて、地主が建設会社に騙されたと訴えることが多くなりました。
空室になっても家賃は保証されるという魅力的に思える提案にのってしまったのでしょう。
またなんとか相続税対策を行わなければならないと考えていた地主さんにとってもアパート経営、しかも一括借り上げによる、手のかからないアパート経営は魅力的に思えたことでしょう。
しかし、一括借り上げによるアパート経営によるデメリットも、認知されるようになり、それとともに「こんなはずではなかった」と悔やむ地主さんも増えてきました。
一方で大手の一括借り上げ業者にとっては、巧みに勧誘し、地主さんを取り込むことができたことで、多くの場合、罪に問われることはありません。
あくまでも合法的にビジネスの一環として行っているからです。
ということで、どんなに地主さんが、騙されてと感じていてもどうしようもありません。
ところで今回は、
一括借り上げも行っている、あの積水ハウスが騙された
というニュースです。
2017年8月上旬は積水ハウス関連のニュースは、この件でもちきりです。

アパート経営はするな! 賃貸経営の落とし穴 / 須田忠雄 【本】
そもそも事件の内容とは、積水ハウスがマンション建設のために、土地を購入しようとし、地主(後に偽の地主だということが発覚する)さんに63億円という大金を支払ったものの、支払った相手が偽の地主なので、購入手続きができなくなったというものです。
そして大金を受け取った偽地主も大金を持ったまま姿をくらまし、積水ハウスにしてみれば、
まるまる大金を奪われてしまった状態です。
今回の事件は立派な犯罪行為ですが、偽地主を見つけ出して大金を取り返すことができるのかどうかはわかりません。
一説によると積水ハウスが今回の不動産取引を依頼した司法書士に損害賠償を請求するとのニュースもありますが、もしそうなると、その司法書士、破産宣告をするしかないとのことです。
いずれにしても大金の絡む不動産取引、1つの過失で大きな損失を被る可能性のある、怖い取引でもあります。
アパートマンション経営地主さんの騙されたという訴えも深刻かもしれませんが、積水ハウスの今回の事件はもっと深刻です。
いずれにしても、アパート経営を含む不動産取引、1つの過失がおおきな損失へとつながる取引なので慎重でありたいものです。

【送料無料】 私のアパート経営“失敗”物語 成功の秘訣はトラブルにあり!? / 仲村渠俊信 【本】
2016/1/31
日本は医療については、比較的安心して向き合える国です。保険制度があって過度の高額医療費負担の心配もそれほどありません。医療機器、設備についても外国と比較してもトップレベルにあるともいわれています。また献身的に勤勉に働く医師、看護士たちも数多くおられます。しかし問題がないわけではありません。
その1つが輸血です。日本の病院の多くが一定のヘモグロビン値よりも数値が下がると、当たり前のように輸血を施します。しかしこの輸血は 驚くほどリスクの高い治療法 であることを一般の患者は知りません。もちろん一部の医師たちは輸血の高リスクを認識しているようですが、様々な事情から声高に意見を述べることがなく、決められたルール―に従っているようです。なかには輸血拒否患者を最初から受け入れようとしない私からすれば残念な病院もあるようです。私が思うにはそういう病院は病気の治療には向き合っていても患者の心や信念とはまともに向き合っていないのか、それとも輸血しないことによって生じるかもしれない様々な厄介な問題を回避したいのかはわかりませんが・・
ところで2016年1月24日産経新聞には「輸血で慢性肝炎新たに3人疑い」という記事がありました。他にも報道している新聞社があるかもしれません。つまり輸血を施されることは、スクリーニング処理をくぐり抜けた細菌、ウィルス等も施されてしまうことを 覚悟しなければならない治療です。 しかし問題が発覚すればスクリーニング処理を強化する、しかし新たな細菌、ウィルス等がスクリーニング処理をくぐり抜ける。するとまた強化する。いわばイタチごっこのような状態です。
しかもネット検索で「輸血 免疫力の低下」で検索すると恐ろしいほど情報がヒットします。これほどの情報があるということは、明らかに輸血=免疫力低下は事実といわざるを得ません。
さらに 輸血は高コスト治療 ともいわれています。(日本の場合は事情が異なります)もちろん患者は保険制度のおかげでそのことをあまり実感することはありませんが、外国ではそのように考えられている国もあります。
そう考えると輸血ありきの日本の医療制度も見直しを行うべきではないかと思うのですが・・良識のある医療関係者のみなさん、ぜひ事実と向き合ってください。
「輸血は受けてはいけない」こんな本があるんですね。

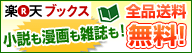
2016/1/10
2015年12月29日の産経新聞には「出版物販売落ち込み最大」という記事が載せられていました。平成8年に書籍と雑誌の販売額が2.5兆円だったのが1兆5000億円ぐらいとかなり落ち込んでいるとあります。つまり出版物不況の根深さが浮き彫りになったかたちです。
ところでなぜ書籍や雑誌が売れなくなったのでしょうか。
記事によると1つの要因は少子化とあります。少子化により購買力のある若年、中年層が減少し、高齢者が増える。高齢者は年とともに目が悪くなると、新聞こそ購読しても読むのに努力がいる書籍や雑誌を読まなくなっていく、結果として出版物販売が落ち込むということが生じるのかもしれません。
もう1つの要因はスマートフォンの普及とあります。確かに今の世の中、わざわざ出版物を買わなくても、スマートフォンやタブレットでも同じ情報を得ることができるようになっています。いわゆる電子書籍の普及が印刷物を押しやっている感があります。しかも電子的な方法で読むほうが、リーズナブルだとすると節約志向から印刷物を買わなくなるのかもしれません。しかも電子版だとスマートフォン、タブレットに書籍、雑誌内容が収まるので、印刷物のように処分する手間が省ける、家の中に保管するスペースも必要でないといったメリットがあります。
ところで印刷版のメリットにもふれておきたいと思います。
・書き込みができる。
・迅速に読む記事の変更を行える。ページをめくることが電子版よりも容易。
・電子機器の手触りよりも紙の印刷物の手触りのほうが良いと感じることもある。
もちろん書籍や雑誌の印刷版にするか電子版にするかは、メリット、デメリットをよく考えたうえで、どちらにするか選ぶことができると思います。
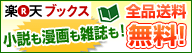

2015/12/6
最近は新聞をとらなくなっている人も増えています。ニュースや情報はインターネット、テレビでも見ることができますし、購読料が高いということで新聞を取らない人もいると思います。
それでも高齢者世帯を中心に新聞を購読している人は少なくありません。私も購読しています。実際インターネット版のニュース記事にはない情報が紙の新聞には豊富に掲載されていますし、正直、インターネットをタップしていくよりも紙の新聞をぱらぱらめくるほうが読みたい記事を素早く見つけることができると思います。
ところで近年、夕刊を読まない人が増えています。夕刊配達地域で夕刊をとらないで朝刊のみにしている人も少なくありません。しかし夕刊配達地域で夕刊を取らない方かたは、次の事実を見落としているかもしれません。
その1 夕刊のある地域の価格は朝刊と夕刊のセット価格の公式価格は決められていますが、朝刊だけの価格はありません。つまり各販売店によって価格が決められています。多くの場合セット価格よりも100円~500円程度安く販売店が設定し、価格的にはあまり差がありません。
その2 朝刊だけの地域は朝刊に1日のすべてのニュース記事が掲載されますが、夕刊のある地域で夕刊に掲載されたニュース記事は朝刊には掲載されません。(朝刊のみの地域とセットのある地域において同じ新聞社の提供する新聞の朝刊は内容が異なります)
その3 夕刊のみで提供される広告、チラシがあります。
その4 欧米で発生するニュースは朝刊には間に合いません。夕刊に掲載されます。(例えばニューヨーク市場の株式、商品の終値など)
このように夕刊には夕刊なりの役割があり、本当に新聞を読むならば夕刊も見逃すことはできないように思います。 実際に価格的にも数百円程度しか違いがありませんので、夕刊のある地域では夕刊も購読してみるのはいかがでしょうか。

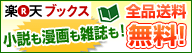
-
-

- 楽天市場
- オルナオーガニック シャンプーセ…
- (2025-11-23 05:05:02)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「三木谷さんが来てないって聞いた時…
- (2025-11-23 09:00:05)
-




