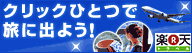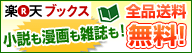サブリース契約(一括借上げ)
2017/5/12 【大和ハウス大阪ビル。建設業界では売上高かトップのメーカー。2016年の業績は好調だった。】
【大和ハウス大阪ビル。建設業界では売上高かトップのメーカー。2016年の業績は好調だった。】
建設業界において積水ハウスとトップシェアを競っている大和ハウス工業ですが、このほど新築戸建て住宅においてもサブリース(家賃保証)を行うと発表しました。
どういうことかというと、新築戸建て住宅を購入しても、転勤等などで引っ越しをせざるをえなくなる場合、そのあと自宅を売却するか、賃貸住宅として貸すかの選択を迫られるかもしれませんが売却するのも大変となると、賃貸住宅として貸すことになるかもしれません。
しかし入居者が見つかって家賃収入が入るかどうかの不安も生じることと思います。
もし入居者がずっといなければ、固定資産税や建物の維持費等は支払い続けなければならないので、まさにその物件そのものが家計にとって大きな負担になってしまいます。
そこで新築戸建て住宅を大和ハウスで購入した後、50年間は、その間に賃貸することになったとしても、入居者募集を開始して6カ月間入居者が見つからない場合は、6ヶ月後は最低保証の賃料を支払ってくれるというものです。
大和ハウスの狙いとしては、新築戸建て住宅の販売促進のために考え出した制度のようで、購入後の安心をセールスポイントにしているようです。
 【自宅を賃貸にしても入居者がいなければ、家計の負担になるだけである。】
【自宅を賃貸にしても入居者がいなければ、家計の負担になるだけである。】
一見、この制度とてもマイホーム購入にとても良い制度のように思えますが、不安な要素も残ります。
まず最低限の家賃を保証するということですが、その金額はどれぐらいになるのでしょうか。
通常、サブリースでない賃貸の場合、家賃の5~10%が不動産管理会社に手数料として支払われます。
サブリースになると15%前後ですが、最低保証となると家賃の30~40%が不動産管理会社に支払われることになります。
となると最低保証金額が支払われるとしても、その金額は、すずめの涙ほどしかないのかもしれません。(家賃保証制度は空家リスクをヘッジすることはできても、サブリース企業の事業がそのことによって収益が圧迫されることがないようにサブリース企業が調整を図ってくることがあります)
さらに支払われる賃料の見直しがあるのかどうか、というてんも抑えておくべきでしょう。
いわゆる賃料減額というものですが、賃貸住宅オーナーの多くが経験している事柄です。
最低保証額が当初の3年は7万円だったとしても3年後からは6万円になるという事にならないのでしょうか。
いずれにしてもサブリースにもデメリットがあることをよく認識したうえで、住宅購入を検討するのが賢明なことでしょう。

【中古】 これからの土地活用のための家賃保証の実務 / 西峰 猛史 / 税務研究会出版局 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】
2016/2/10
2月8日のブログではサブリース企業(私の場合は大東建託)が一旦、借上賃料の減額要求をしたのならば頑として要求を曲げないことについて書きました。今回は彼らの借上げ賃料の基準となる家賃査定について書きたいと思います。
減額要求で合意してしまったのは残念でなりませんが、この協議の時に、大東建託側は私を説得するために家賃査定部門の責任者を連れてこられました。この責任者との話し合いから様々なてんを勉強させてもらったのは、収穫であったように思います。
彼の話からわかったことは、大東建託の家賃査定の方法は 周辺の家賃相場を調査して、私の物件と類似した物件の相場の平均値を割り出し家賃を決定するという方法 です。今回対象となった物件は1階テナントですが、周辺テナントと家賃を拾い上げて説明し、テナントの場合は特に坪単価が幾らになるかを説明していかれました。そして「平均値の単価が今はこれになるので、あなたの物件の家賃は今の価格で適正です」ということです。
2016/2/8
 もともと弱小大家には交渉力がなく田村次郎著「16歳からの交渉力」の本などを読んで交渉力を身に着けていかないかもしれませんが。
もともと弱小大家には交渉力がなく田村次郎著「16歳からの交渉力」の本などを読んで交渉力を身に着けていかないかもしれませんが。
いずれにしても、どうしても大家への支払いを増額させたいならば、弁護士さんなどと相談することが必要かもしれません。
ただしこれはあくまでも大東建託が相手の場合ですが、これで署名しなけば解約をちらつかせたり、署名を強制させるようなことはありませんでした。彼らはあくまでも大家を粘り強く説得させる方法を取るようです。
また2月12 日頃のブログでは彼ら(この場合は大東建託)がどのようにして家賃を査定しているのか、そのことも今回、勉強になりましたので、勉強になった事柄のその2として書いてみようと思います。
 羽成守著「民事調停の実務」とても難しそうな本ですが、大家であるならばある程度、調停についての知識があるほうが、よいかもしれませんね。
羽成守著「民事調停の実務」とても難しそうな本ですが、大家であるならばある程度、調停についての知識があるほうが、よいかもしれませんね。
2016/2/5
1月29日、2月4日のブログで大東建託との借上賃料協議について書きましたが、ついに協議がまとまりました。結果は賃料面では完敗といったところです。
いきさつは今回はテナント部分の賃料改定協議だったわけですが、入居者家賃が20%下がったので、大家に支払う借上賃料も20%下げるというものです。1回目の協議の時はそもそも家賃が20%も下がること自体、おかしいのではないかと言って合意を拒否しました。それで今回は、大東建託の賃料査定の責任者と大東建託建物管理の担当者と2人で来られ、賃料査定の責任者がどうして20%も下げざるをえなかったかの説明に来られました。ある程度の誠意は感じましたが、結局は事業として成り立つためには20%の減額を受け入れてほしいと懇願されました。(内心は大東建託は相当儲けているのに、まけてくれても全然大丈夫じゃないのとも思いましたが・・)
まったく一歩も引きそうにない態度を取られたので、しぶしぶ減額を受け入れることにしました。(調停、訴訟に持ち込むのもしんどいですし)しかし口約束ですが、次のてんも確認しました。大家にとって大きな出費になる大規模改修工事を築15年以降に行う。通常10年~13年頃に行われることが多いですが、建物管理の担当者から15年以降の確認をとり、しっかりとその場でメモを取りました。
マンション管理大損のからくり 管理費、大規模修繕費は四割安くなる! / 須藤桂一【中古】afb
大東建託さんついでに4割安くしてくれないかな↑
それから来年は住居部分の借上賃料改定協議が行われますが、住居部分の家賃はあまり下がってないので、来年の賃料改定は大きな減額はまずないとの確認を取りました。まあしかし、しぶしぶ合意した最大の要因は12年頃に行われると想定していた大規模改修工事が想定より3年以上先になったというてんです。いくらかの時間的な余裕ができたのでその間に今後のマンションの経営のことなどを考えていこうと思います。
 「おいしい話には裏がある」と本に書かれていますが、まさにアパート経営は、甘くないということを今回の賃料改定協議から実感しました。
「おいしい話には裏がある」と本に書かれていますが、まさにアパート経営は、甘くないということを今回の賃料改定協議から実感しました。
2016/2/4
2016年1月29日のブログで借上げ賃料改定協議の1回目について書きました。結局その日は決まらずまだ2回目の日程の連絡も来ません。
サブリース契約大家にとって、最も緊張し嫌なのがこの借上げ賃料改定の協議かもしれません。今日はこのてんについて幾らか詳しく書きたいと思います。
私の物件は大東建託とのサブリース契約で建てられたものですが、築8年になります。大東建託のサブリース契約では、住居部分の賃料改定が10年、そして後は5年毎に行われます。一方でテナント、店舗部分は3年毎に賃料改定が行われます。
それで今回の賃料改定はテナント部分の9年目以降の賃料改定協議ということになります。もうすでに2回テナント部分の賃料改定は行われていますが、当時は父が協議に参加したのでどういう話し合いが行われたかは知りませんが、1,2回目はテナント入居者もあり家賃は当初設定されたままの家賃でしたので、大家に支払われる借上げ賃料も変わりませんでした。しかし2回目の協議のあと入居者が退去され、その後のテナント募集家賃がなんと20%も下げられたのです。この下げ方にも大いに疑問がありましたが、当時は父が大家でしたので、何も言いませんでしたが、その後、大家だった父が亡くなり私が引き継ぎました。そして遂にそのままの状態で3回目の協議がやってきたのです。借上げ賃料改定協議は初めてだったのでとても緊張しましたが、正直、愕然としました。大東建託建物管理の担当者は借上げ賃料も20%下げた金額で署名、捺印をせまってきたのです。テナント部分の賃料なので、金額も半端ではありません。とても署名、捺印する気になれなかったので、どうして家賃をこんなにも下げたのか理解に苦しむと言って断りまりました。担当者も「私もなぜこんなにも下げたのかわかりません。家賃の審査部にいきさつなど聞いて、また来ます」と返答しました。
 こんな本があるほどですから家賃は下がってもしょうがないですかね。
こんな本があるほどですから家賃は下がってもしょうがないですかね。
それから1週間が経過したわけですが、悶々とした日々、なんともいえない苛立った日々を過ごしています。ネット検索などで今後どう対応していけばよいのか模索していますが、サブリース契約トラブルの相談を受け付けている弁護士会などもありますので、そちらに相談することも視野にいれています。
今後、どうなるのやら、また経過をブログしたいと思います。

2016/1/29
先回、先々回とサブリース契約(一括借上げ)についてブログしました。ところでこの契約において30年、35年の一括借上げで契約したとしても大家に支払われる賃料が契約期間一定であるわけではありません。提供する企業によって期間は異なりますが、周期的に大家に支払われる賃料の見直しが行われます。
実のところ1月21日、大東建託建物管理の担当者が来られました。大東建託の場合、テナント部分は3年毎に大家に支払われる賃料の見直しが行われます。8月1日が改定日なので、そのための協議で来られました。残念ながらテナント家賃はかなり下げられていたので、覚悟はしていましたが、やはり大家に支払われる賃料もダウンしていました。
担当者はこの金額での署名、捺印を迫りましたが、 私はどうしてこんなにもテナントの家賃を下げたのか理解に苦しむと主張して署名、捺印を拒絶しました。担当者も「確かにこの家賃の下落は乱暴ですね、」と言い「審査部が家賃設定をしているので、わたしもどうしてかわかりません」と言われました。
結局、次回、審査部の担当者と一緒に来て説明させるということになりましたが、大家に支払われる賃料は変わりそうにありません。まあそれでももう少し粘れば、多少は上げてくれるかなあ、とも思ったりもしましたが、決定は次回以降になりました。またそのてんについてはブログしようかと思います。
ところで一括借上げの場合、空き部屋による家賃収入の減少は避けられますが、大家に支払われる賃料の見直しは周期的に行われ、家賃が下がっていれば、大家に支払われる賃料も下げられます。これがなんといっても一番嫌なところです。
今の時代、大家になるならばサブリース契約のほうが無難だとは思いますが、しかし甘くはありません。この大家という立場は、物件が古くなるにつれ、多くの場合、収入がだんだんと減っていくという悲しい現実に向き合わなければならないのです。

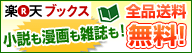
2016/1/28

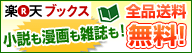
2016/1/27
最近では一括借上げの契約(サブリース契約)を行なわないようにとの指摘の文章をよく目にします。しかし私の考えはサブリース契約で大家にならないのなら、大家にはならないほうがよいと思っています。つまり大家になるならば、特に不動産の素人であるならばサブリース契約をしたほうが無難だと思います。(無難といってもサブリース契約大家で深刻な状況になっている大家も少なくありません)
以前、りそな銀行の担当者が来られた時も最近、アパートマンションの経営はほとんどがサブリース契約になっていると言われていました。その理由は私もわかります。サブリース契約をしているならば、空き部屋が生じても賃料は支払われる、つまり空き部屋のことで過度に心配することがないからです。
ところで私の物件は大東建託との30年の一括借上げです。亡き父が契約しました。
ところで30年間、大東建託は私の物件の査定家賃の15%ほどを収入にして維持管理業務(入居斡旋、家賃回収等を含む)を行ってくださっていますが、正直この維持管理業務自体は赤字ではないかと思います。なぜならば大家には大東建託から空き部屋の有無にかかわらず当初設定された査定賃料の15%を引かれた賃料が支払われていくからです。(大家に支払われる賃料は周期的に見直しが行われる場合があります)例えば私の物件で1年8カ月、空き部屋になっていたテナントがありましたが、その間、大東建託からずっと賃料を支払ってもらいました。仮に月額20万円として計算しても(実際はもっとたくさんもらっていました)合計400万円を空き部屋だったにもかかわらず賃料をいただいていたことになるのです。つまり大東建託は大家に400万円を支払ってその分、まるまる損失が生じていたのです。
それでは維持管理業務だけでは赤字になるは当然だと考えられますが、大東建託などサブリースを売りにしている企業はどうやって経営が成り立っているのでしょうか。このてんについては、次回のブログで書きたいと思います。