高齢者の問題
高齢者社会になり、年老いた親の世話が多くの家庭で課題になってきています。
このようなななか、私の家でも妻の親、田舎で一人暮らしをしていたのですが、様々な事情を考慮して、引き取ることになりました。
全体的に体力が衰えていますので、なんとか体を動かしてほしいものですが、そのためにも近所にディサービスの施設があるので、そこに通わせたいのですが、そうするためには、要介護認定を受けなければなりません。
田舎では、ケアマネージャーはついていたのですが、介護認定は受けていなかったので、引き取ってから要介護認定を受けたほうがよいでしょうということで、早速、手続きに入りました。
この要介護認定について厚労省のホームページには
介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。 と書かれています。
このように 家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態になった時に、要介護認定の要支援1の認定を受けることができます。
そして状態の重症度に応じて要支援2~要介護5と認定されます。

新・要介護認定調査ハンドブック第4版 74項目のポイントと特記事項の記入例 [ 東京都介護福祉士会 ]
ところでこの要介護認定を受けるためには、ケアマネジャーのサポートや主治医の先生の書類が必要となってきます。
そこでケアマネジャーの選任と、かかりつけの病院の先生に一筆書いてもらわないといけないのですが、その後、市役所の担当の方が審査に来られます。
様々なテストを行われますが、その審査後に、しばらくしてから認定の通知書が市役所から送られてきます。
私の義母の場合は市役所の担当者による審査の
3週間後
に通知がきました。
結果は要支援2でしたが、これでディサービスに通わせることができます。
ところで人によっては1カ月ないしは3カ月もかかる方もおられるようですが、待っている期間にお年寄りが、どんどん弱っていくこともあります。
もう少し早く手続きを進めてもらいえないかとも思うのですが。
幸い義母の場合は、自分でできる限り体を動かしていたので、待っているうちに弱くなってしまうことはなかったのですが。

要介護認定調査員 調査・判断の重要ポイント [ 今田 富男 ]
2017/11/24
元気に仕事をしているならば、睡眠時間は6~7時間ぐらいでしょうか。
私も大家なのでアパートローンを銀行から借りていますが、そのためか銀行の担当者がしばしば来られるます。
まだ入行して2年ほどの若い行員さんですが、通勤に1時間半以上かかるので、毎朝5時に起きて出勤しているんだそうです。
おそらくは通勤中に上手に睡眠を取っておられるのかもしれませんが、就寝時間が11時としても6時間程度しか寝ていないことになります。
このように仕事を元気にこなしている間は睡眠時間が少々短くても、やっていけている方も少なくないと思うのですが、
年をとっていくとなぜか、
睡眠時間が長くなるようなのです。

4時間半熟睡法 世界一の「睡眠の専門医」が教える! [ 遠藤拓郎 ]
というのも私の妻の母が、田舎で1人暮らしをしていくのが、難しくなったので、私の家で引き取ることになったのですが、とにかくよく寝ます。
80歳を超えてはいますが、晩は9時ごろには寝て、朝は7時まで寝ています。
さらに昼食や夕食のあとには1時間ほど寝ます。
一日に少なくても12時間は寝ているのではないかと思います。
まるで乳幼児と同じほどよく寝ているような感じですが、なぜそんなにもよく寝るのでしょうか。
そのことを調べてみますと厚労省のe-ヘルスネットのページには
睡眠が浅くなることです。睡眠脳波を調べてみると、深いノンレム睡眠が減って浅いノンレム睡眠が増えるようになります。そのため尿意やちょっとした物音などでも何度も目が覚めてしまうようになります。
と書かれています。
つまりは年とともに睡眠が浅くなっていくので、その分、睡眠時間が長くなるということのようです。
しかしそれでも、むやみやたら寝ることもよくないようです。
同じ厚労省のページには
早寝早起きは結構ですが、眠気がないのに「やることがないから寝床に入る」ことはやめましょう。寝つきは悪くなりますし、中途覚醒が増えてしまいます。・・高齢者ほど寝床に入っている時間が長いことが分かっています・・。睡眠時間が短くなるのに寝床にいる時間が長くなる…。結果として眠れぬままに寝床でうつらうつらしている時間が増えて睡眠の満足度も低下してしまいます。
とも書かれているからです。
やはり年をとってからも、だらだらと時を過ごすのではなく、できる限り有意義な活動を行うことによって、睡眠の質の改善を図り健康的な生活を送ることができるようです。

疲れとり首ウォーマー つけて深睡眠 (レタスクラブムック) [ 小林弘幸(小児外科学) ]
2015/12/13
産経新聞2015年12月1日に高齢者が1人で食事をとる孤食の記事が掲載されていました。今は昔と比べて、多くの人が長生きできるようになっています。確かに長生きできることはよいことだと思います。しかし一方で配偶者が亡くなって一人暮らしになり、一人で食事を取る人が多いというのです。
もちろん2世帯住宅などで、子供家族と一緒に暮らしているならば、いつも孤食になることはないと思いますが、すべての高齢者がそういう恵まれた環境にいるわけではありません。
ところで孤食になると何が問題になるかということですが、記事によると1人きりのために栄養バランスがおろそかになり、食への楽しみが薄れがちになり、結果として体力が衰えていき、やがては 介護が必要な状態に陥ることがあるということです。
もちろん同居家族がいても3度の食事を一人でとる孤食の人もリスクが多いとあります。鬱傾向になるリスク、低栄養になるリスクが高いということです。
高齢者が介護状態、あるいは鬱病になると本人のみならず家族も大変です。老人性鬱病で自殺することも少なくないようです。
できるならば高齢者がいつも孤食にならないように社会で考える必要があるかもしれません。
考えてみると私も母が隣に住んでいるとはいえ、父を亡くし孤食になっていることが多いように思います。これからは、できるかぎり一緒に食事を行えるように配慮していきたいと思いました。
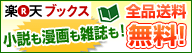

© Rakuten Group, Inc.





