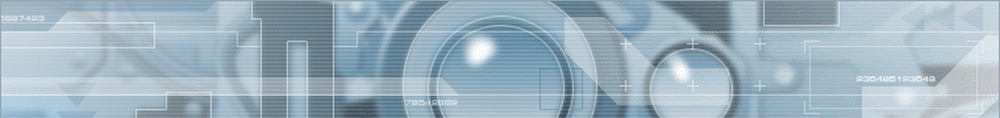PR
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
フリーページ
残念ながらわたしはアンジェイ・ワイダの善き観客ではなかった、機会にめぐまれてこなかったということもあったが(名画座にはあまりまわってこなかった)。
昨日とおなじくNHKETV特集にてアンジェイ・ワイダの特集をビデオで観ていた(昨日は中間試験の採点日ということで、ふたつのNHKのビデオを観ていたことになる、そのつぎはお待ちかね(?)ヨシモトさんの出番であるはず)。
ポーランドはナチス・ドイツに侵攻されたことはよく知られている。
しかしじつはポーランドはソ連にも侵攻されていたのであった。
それでもポーランド、とりわけレジスタンス勢力はソ連軍を解放軍とみなし、強力関係にあった。
だがソ連軍にはうちわの事情があり、しかもスターリンのもと、エゴイスティックな面もみせ、呼びかけられもしたレジスタンスによるワルシャワ蜂起は結果として敗北におわる。
それが描かれているのが「地下水道」(未見)。
河の向こうにはソ連軍がひかえているというのに、眼の前で見殺しにされるレジスタンスの生き残りたち。
のちにソ連軍はワルシャワに進駐、しかしレジスタンス勢力を弾圧、レジスタンス側はいまだ大戦終了まえなのにソ連軍を敵とみなし、抵抗する。
他の東ヨーロッパ諸国とことなり、ポーランドの場合は大戦中から反ソ空気が濃厚であった。
したがってこのような事情を理解していれば、「灰とダイヤモンド」(これは観た)の見方ががらりとかわるはずである。
ソ連系のコミュニスト政権に抵抗する暗殺者、原作では政権の人間が主人公なのにワイダは暗殺者のほうに視点を置き、それによりポーランドに連綿とつづく自由への戦いを謳う。
そしてその視点の巧みな置き換えにより、政府の検閲をたくみに乗り越え、制作、公開に踏み切れたワイダの知恵にも感心される。
もちろんわたしはずっとずっと昔に見たとき、そんなことには気がつかなかったことを告白しておく。
おなじく「大理石の男」(未見)でも、国家建設にはげむ労働者の姿への政府の恣意性をきびしく追求、これにより制作・公開を許可した文化大臣はポストを失うにいたるシビアさ。
労働者のストに軍が銃を向け、死傷者までだす1970年の事件(メキシコの1968年も思い出す)。
政府とかかわりをもたないはじめての労働者組合「連帯」とワイダの関係。
そしてこの番組のメーンであった、大戦中にポーランド領内にてポーランド将校がソ連軍に大量虐殺された「カティンの森」事件。
ああ、ポーランドがいかに生きのび、自由をもとめてきたか。
表現の自由のとぼしいくににて、ワイダのような監督がいかに自分の表現をもとめてきたか。
自分の無知さを悔いることしかできない。
http://
(05 of March, 2009)