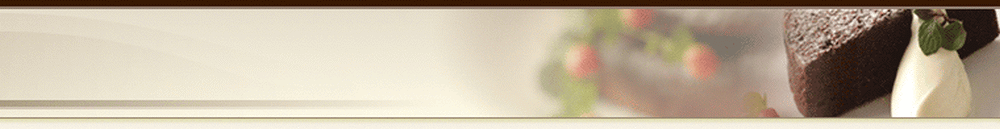たまには税法ネタを。
土地などの不動産は時価が算定の目的によって異なることからモノは1つであっても価格がいくつも考えられるということで一物多価といわれています。税法の中でもさらに税法別にこの時価の考え方が異なるので注意が必要です。この考え方はおおむね次の3グループに分かれるようです。
1.所得に関する税金・・・所得税、法人税、住民税
ここでは「もうけ」を算定するのに「いくらの利益が発生したのか」というアプローチをしますから土地の時価は 第三者間で通常取引される価額 ということになります。
2.無償での権利移転に関する税金・・・相続税、贈与税
ここでは無償で権利が移転した「そのモノ自体はいくらなのか」というアプローチをしますから土地の時価は評価方法を独自に定め 相続税評価額 ということになります。
3.行政手数料や自治体からの利益享受などに関する税金・・・登録免許税、不動産取得税、固定資産税・都市計画税など
ここでは、登記や登録手数料や不動産の取得・保有により自治体から得られるべき便益の享受の対価といった意味合いが濃いものですがその対価を合理的に算定することについては簡便で客観的な基準が必要ですから市町村が評価した 固定資産税評価額 が土地の価額として用いられます。
以上、3つの時価をご説明しましたが登録免許税以外の国税における土地評価のタブーがあります。それは 国税で固定資産税評価額を使ってはいけない ということです。これには2つほど理由があり、一つは「固定資産税評価額はこの地域は単価いくら、という評価であるため個々の土地の事情が織り込まれていない」ということです。もう一つは「下級役所である市町村役場が評価したものを上級役所である国税当局が斟酌することは国のプライドが許さない(?)」というものです。
後半部分の理由は定かではありませんが、固定資産税評価額は最も身近で簡単に入手できる評価額ですからついついこれで評価しがちですが特に贈与などのときにこれを使うとアウトとなることが多いですから注意が必要です。
-
総選挙と消費税 September 8, 2008
-
相続税が変わります。 July 8, 2008
-
タバコ1箱千円になる? June 10, 2008
カレンダー
 New!
保険の異端児・オサメさん
New!
保険の異端児・オサメさん『今時の勉強方法』 所税仲間さん
キャッシュフロー 社… 公認会計士天野隆さん
10年後の自分に向け… taka-maruさん
輝く私であるために にゃこ姫さん
コメント新着