PR
X
2025.11
2025.10
2025.09
2025.08
2025.10
2025.09
2025.08
2025.07
2025.06
2025.05
2025.04
2025.06
2025.05
2025.04
テーマ: 最近観た映画。(40986)
カテゴリ: 映画の話
2006年最後に観た映画は、この一本でした。
この映画を観て、
「本当に米国人が撮った作品なのか」
と、舌を巻いた観客は多かったことでしょう。
むしろ邦画として普通に見られてしまうほど、“日本人の物語”としての完成度は高く、それだけに多くの人々をのめりこませているのだと思います。
ただ、忘れてはいけないことは、
「日本軍の戦いをハリウッドが忠実に描いた」
ということがすごいのではなくて、
「一つの戦場を、争った双方の側から捉える」
もちろん、古代ローマの英雄もソ連の狙撃兵も日本の芸者も、皆英語を喋るのが当然のハリウッドにおいて、オール日本人キャストの「日本語の」映画を撮ったことは、本当に快挙だと思います。
これを実現させたイーストウッド以下製作陣に、改めて敬意を表します。
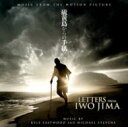
米軍側の兵士たちを描いた「父親たちの星条旗」では、何度も何度も、唐突に戦場の場面に引き戻される演出方法が、平穏な暮らしに戻ってもなお、硫黄島の記憶から逃れられない「生き残った者の地獄」を体感させるのに非常に効果的でした。
対してこの作品は、演出は直球勝負。
その分、従来の米映画では単なる「やられ役」だった日本兵が、それぞれ人格を持ち、家庭を持ち、生活を持っていた人間だということを、世界中の観客に伝える力を持っていると思います。
戦場という状況下で、尊厳を守った者も、堕落した者もいる。
一人の人間の中でさえ、両極端の感情がせめぎあい、思いは激しく揺らいでいく。
勝者と敗者に分かれても、人間という存在の普遍性は共通であるというメッセージは、痛いほど伝わってきました。
物語の語り部役となる二宮和也くんの演技が評判となっていますが、私はむしろ、加瀬亮が演じた清水という兵士のキャラクター造型に、すごいリアリティを感じてしまいました。
かつて、憲兵として叩き込まれたマニュアルに沿って、他人を「非国民」「卑怯者」「~すべきだ」と非難するときは雄弁な彼が、自分の命の瀬戸際に立たされたときには、内面の弱さを露呈しなかなか決断ができない。
押し付けられ、盲従していた借り物の価値観を捨てて、彼が自分の頭で考え、自分の目で運命を見つめるようになっていく。
「父親たちの星条旗」を観終わって、私の胸によぎったのは
(そしてこのあと、ベトナムがあって、イラクがあって…)
という、アメリカという大国に対する漠然とした嫌悪感でした。
今回、「硫黄島からの手紙」を観て、その時の感想を思い出し
(じゃあ、日本はどうなの?)
戦場で、戦争で、人の命が失われることの愚かさ。それを、常に誰もがちゃんと理解していなければいけないのだということを、教えてくれた二作品でした。
なお、両方併せて見てこその作品だと思うので、配給側が二本を並行して見られる興行スケジュールを組まなかったのは非常に不満です。
【関連ブログ】
「父親たちの星条旗」を観た。
ある映画広告から。
この映画を観て、
「本当に米国人が撮った作品なのか」
と、舌を巻いた観客は多かったことでしょう。
むしろ邦画として普通に見られてしまうほど、“日本人の物語”としての完成度は高く、それだけに多くの人々をのめりこませているのだと思います。
ただ、忘れてはいけないことは、
「日本軍の戦いをハリウッドが忠実に描いた」
ということがすごいのではなくて、
「一つの戦場を、争った双方の側から捉える」
もちろん、古代ローマの英雄もソ連の狙撃兵も日本の芸者も、皆英語を喋るのが当然のハリウッドにおいて、オール日本人キャストの「日本語の」映画を撮ったことは、本当に快挙だと思います。
これを実現させたイーストウッド以下製作陣に、改めて敬意を表します。
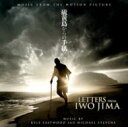
米軍側の兵士たちを描いた「父親たちの星条旗」では、何度も何度も、唐突に戦場の場面に引き戻される演出方法が、平穏な暮らしに戻ってもなお、硫黄島の記憶から逃れられない「生き残った者の地獄」を体感させるのに非常に効果的でした。
対してこの作品は、演出は直球勝負。
その分、従来の米映画では単なる「やられ役」だった日本兵が、それぞれ人格を持ち、家庭を持ち、生活を持っていた人間だということを、世界中の観客に伝える力を持っていると思います。
戦場という状況下で、尊厳を守った者も、堕落した者もいる。
一人の人間の中でさえ、両極端の感情がせめぎあい、思いは激しく揺らいでいく。
勝者と敗者に分かれても、人間という存在の普遍性は共通であるというメッセージは、痛いほど伝わってきました。
物語の語り部役となる二宮和也くんの演技が評判となっていますが、私はむしろ、加瀬亮が演じた清水という兵士のキャラクター造型に、すごいリアリティを感じてしまいました。
かつて、憲兵として叩き込まれたマニュアルに沿って、他人を「非国民」「卑怯者」「~すべきだ」と非難するときは雄弁な彼が、自分の命の瀬戸際に立たされたときには、内面の弱さを露呈しなかなか決断ができない。
押し付けられ、盲従していた借り物の価値観を捨てて、彼が自分の頭で考え、自分の目で運命を見つめるようになっていく。
「父親たちの星条旗」を観終わって、私の胸によぎったのは
(そしてこのあと、ベトナムがあって、イラクがあって…)
という、アメリカという大国に対する漠然とした嫌悪感でした。
今回、「硫黄島からの手紙」を観て、その時の感想を思い出し
(じゃあ、日本はどうなの?)
戦場で、戦争で、人の命が失われることの愚かさ。それを、常に誰もがちゃんと理解していなければいけないのだということを、教えてくれた二作品でした。
なお、両方併せて見てこその作品だと思うので、配給側が二本を並行して見られる興行スケジュールを組まなかったのは非常に不満です。
【関連ブログ】
「父親たちの星条旗」を観た。
ある映画広告から。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[映画の話] カテゴリの最新記事
-
「モテキ」を観た。 2011.11.30
-
「コクリコ坂から」を観た。 2011.08.01
-
「ブラック・スワン」を観た。 2011.05.21 コメント(4)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.












