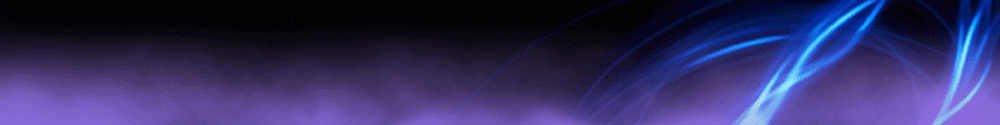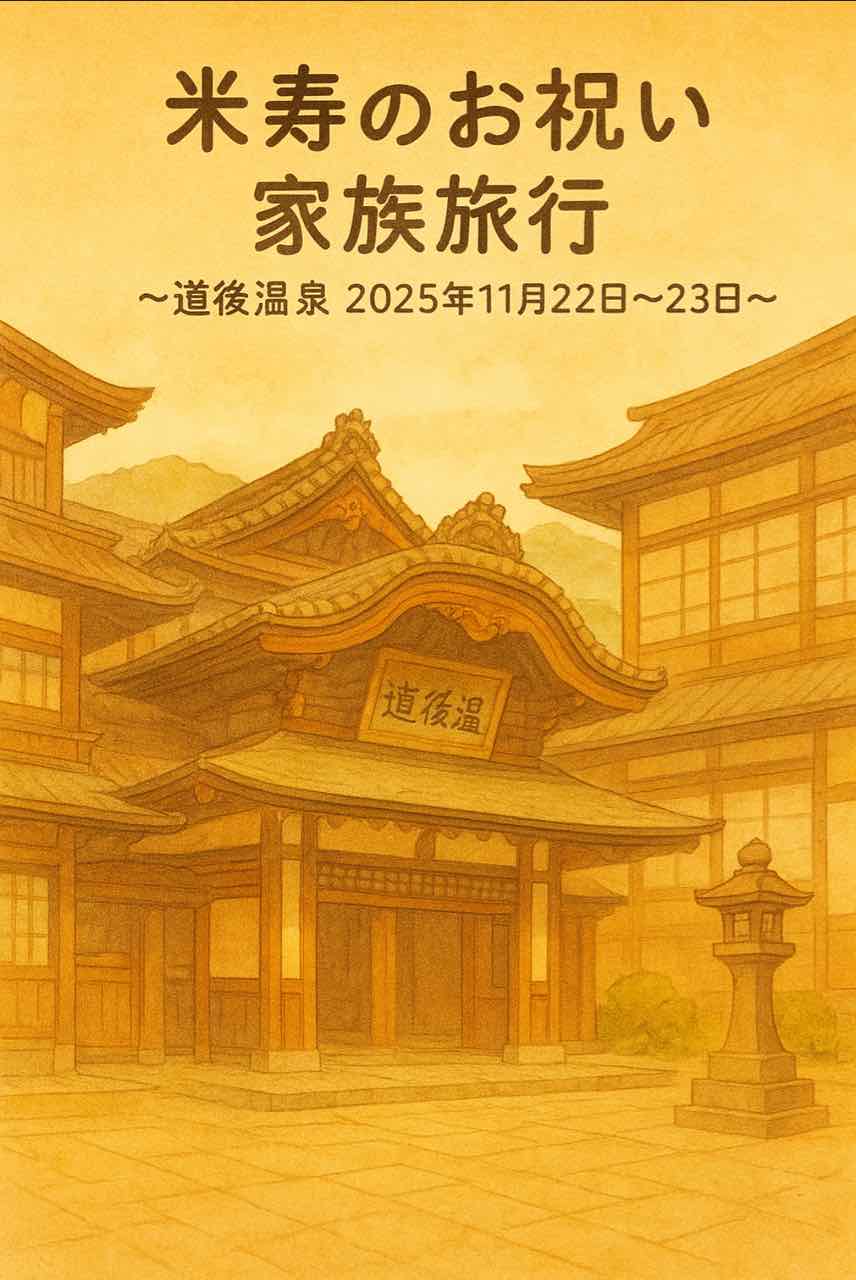小説ひめ(仮題)第1章ノ1 平常
相手は高校生くらいの男、ガタイは並、鼻ピアスが実に似合ってないその顔に青筋、、はたってないがたっ
ていてもおかしくない怒りの形相、それも当然だろう、今俺の足元に倒れている男はこの男の友人らしく、そ
してそれを俺がつい今しがた殴り倒したところなのだから。
「死ねコラァ!!」
男が大きく腕を振りかぶって俺に殴りかかってくる!
しかし動じることなど何もない冷静に静かに対処、相手をしっかり見る。
距離推定2m強、大きく振りかぶった右腕を振り下ろしつつ突進中
胸部・頭部それに首筋ガラ空き、さっきのやつより雑魚確定。
男が振り下ろしてきた腕を動きに合わせて体勢を変えながら右腕で受け流し、そのまま隙だらけの喉元に右
腕で手刀一閃、もちろん雑魚用手加減試用。
我ながらなかなか様になった一撃、男は体勢を崩されてた上に予想を上回る一撃についてこれずそのまま首
に手刀をブチこまれる。
「ぶぇッ」
「ふぅ……多分峰打ちだ、安心せぃ」
男は突進してきた勢いそのままに喉を抑えながら倒れこむ、これで終い、二人この調子で俺が倒した、次の
敵がいないことを確認し少し離れたところにいる平を見る。
俺よりも多い三人を相手にしていたはずなのだがそんな程度では平はなんともない様子で息も切らさず埃を
払うかのように手を叩いていた。
アレは平の悪いクセ。
足元には相手していたであろう三人の男がうずくまっている。
「平ぁ!さっさと退くぞッ!」
「わかってますよ、秋悟」
蹲っている男達を見下ろしている平に声をかけさっさと走り出す、警察が来るまで今までの経験からだいた
い後2~3分、余裕が無いので振り返らないが後ろから平が着いてくる音をしっかり確認しつつ野次馬の間を
すり抜けて一気に現場を離れ街の喧騒から抜けていった。
一度も止まらず一気に走り抜けることおよそ10分、人通りも多く明るかった街から離れて裏路地を抜け、
住宅街に入りさらに住宅街の中にある少し大きな公園に着くまで後ろを振り向くことさえなかった。
普段は犬の散歩や遊んでいるこども達でけっこうな喧騒に包まれているこの公園もこの時間は静寂に包まれ
俺達以外の人は誰一人いない。
「はぁはぁはぁ……」
「ふぅはぁはぁ……」
二人で木製のベンチに腰かけながらしばし肩で息をして酸素を補給する、そろそろ冬も近いからか吸い込む
空気が冷たく走って火照った体には心地いい。
「はぁはぁはぁ……平ぁ」
俺は息が少し整った頃を見計らってベンチにもたれ、上を見上げたままで平に声をかける。
「何ですか?秋悟」
「今日はなんだったんだ?」
「大したことじゃありません、彼らに肩がぶつかったって因縁つけられたんですよ」
しれっとした顔でさも当たり前のことのように言う平、その顔は別に悪びれた様子もなくただ淡々と事実の
みを語っているのだ、と物語っていた。
「そうかぁ、、肩がぶつかったのかぁ……ハハそりゃ納得……」
少しおおげさに肩をすくめる動作をしつつ俺は横を向き、平の耳をつかみ、大きく肺に息を吸い込んで、、
それを一気に胸の筋肉を使い吐き出す。
「出来るかっ!!つまらん理由で考えなしにケンカすんなっつってんだろバカヤローー!!」
「―――ッ、あまり耳のそばで大きな声を出さないで下さい。三半規管が痛くなります」
平が耳を押さえながら当たり前のことを抗議してくる、が当然そんなことに耳を貸す気は毛頭ない、俺は怒
っているのだ。
「そうなるようにしたから当たり前だ、全く、、お前にこれ言うの何回目だと思ってるよ?」
心底飽きれた様子を態度に隠さず出しながら平に不満の目線を送る。
「しかし私にも言い分はあります。彼らは最初からケンカ腰でした、あの状況ではケンカになるのは避けれま
せんよ」
平は平でこちらの不満に大して意義を申し立ててくる、しかしコイツはいつもこうなのだからもはやその言
い訳を聞く気になどなれない。
「それ以前の問題だっての、普通の人はそんな怖い兄さん方と肩ぶつけるような歩き方しません。歩き方を気
をつけ事故を未然に防ぎなさい……と警察庁も言ってるぞ」
ビシっと言ってやるはずだったのに早くも声のトーンが落ちだしてる俺、、ダメだなと思いつつも性分なの
かどうしても強く言い続けることに慣れない。
「努力はしてるんですけどね、私にソレはなかなか難しいようです」
こちらの考えが見抜かれてるのかわずかに微笑みながら平が返してくる、あぁダメだ、既にいつものパター
ンと化してしまっている、はぁっと一つため息をつき俺は立ち上がる。
「全く、、ほとんど変わらないなお前」
「私は随分貴方に変えられたと思ってますよ?」
「まだまだ真人間にはほど遠いよ」
そう言って本当に飽きれたように態度で表してやるがそれを見せても平は何が面白かったのか笑っていた、
失礼なヤツだ。
「帰る、全く手助けして損した。言っておくけど次は絶対助けないからな」
と口だけ言っておく、もう何度も繰り返したやりとり、このセリフも既に何度か言ってるだろうがそれでも
言う、毎回こう言いながら助けてはいるがこう思っていることも事実だから。
既に夜遅い、街頭の灯りがわずかにあるものの暗闇に沈んだ公園を家に向かって歩き出した俺の背中に後ろ
から平の声が届く。
「秋悟、助けに来てくれた事、感謝してます。でも妹さんを家で心配させてまですることじゃありませんよ」
「一応知り合いだからな。それと後半はよけいだっての」
平の珍しい言葉にどう反応していいか分からずとりあえずそれだけ返して俺はそれだけを言って、平が苦笑
する様子を背中で感じながらそのまま振り返らずに片手を振って公園を出て行った。
平と別れ、暗い住宅街の道を家まで歩く間、俺は家に一人でいるはずのアゲハにどう言い訳するかを考えて
いた……。
空は一面の星空
街は静かに
闇はただ深くそこに在り
平と俺もいつも通り
それは全くなんでもない
ただの俺達の日常だった。
10月13日 早朝
ぎぃ……と遠慮がちに扉を開ける音と誰かの気配が部屋に人が入ってきたことを告げる。
「――――んっ」
眩しい……カーテンが開けられたのだろうか、朝の気持ちいい光がまぶたを閉じていてすらその存在感を発
揮してくる。
「お兄ちゃん起きた?」
カーテンを開けた人物が布団に近寄ってくる足音が聞こえる。
「あぁ。ふぁ……おはよう、アゲハ」
「おはようお兄ちゃん」
目をこすりつつ顔を向けると、そこにはアゲハの笑顔があった。
我が妹ながらアゲハの顔立ちは整ったものだ、その笑顔と朝の光が眠気を吹き飛ばしてくれすぐに俺は頭が
覚醒してくるのを感じる。
「お兄ちゃん、まだ時間あるけどいつまでも寝てると静音さん来ちゃうよ?」
「ん……悪いなアゲハ、起こさせてしまって」
「気にしてないから大丈夫だよ、いつもは自分で起きてくれるから。それにたまにこういうことがあるとダメ
なお兄ちゃんを養う妹って感じがして楽しいから♪」
そう言ってアゲハはおかしそうに笑った。
たまにあるこういう日というのは毎回決まっていて、昨日のように平と一緒にケンカしてきた時……その意
味でダメ兄貴というのは間違っていないためにちょっと後ろめたかった。
「いや本当にありがとう、静音に起こされると何やられるかわかったもんじゃないからな……アゲハに起こし
てもらえるととても助かるよ」
そう言いつつ俺は布団から抜け出す。
「はい、どういたしまして、それじゃご飯の用意しておくから先に下居間に行っておくね、お兄ちゃんも服着
替えて来て、もうすぐミナミさんも来ると思うよ」
「う……」
「ミナミ」という単語に俺は大きく反応する、まだ完全には覚醒しきってなかった頭が一気に覚醒していく
のを感じる。
そういえばあの人がいるんだった……もう何週間もたっているのに未だにあの状況に完全には慣れていない。
普段ちゃんと理解している時であれば大丈夫だがこうやって不意打ちのように名前を出されると急に意識し
てしまうために言葉に詰まってしまう。
そんな状態に気付いているのかいないのか、、アゲハはそのまま部屋から去って行った。
「は~……何やってんだろ俺」
気持ちを落ち着かせるために一気に窓を開ける、外は雲のほとんどない快晴の空、ほどよい冷たい空気が部
屋に流れ込んできた。
窓のそばでその空気に浸っているとさっきまでの高揚感も消えてほどよく体もほぐれてくる。
「ふぅ、さて行くか」
居間に入ると朝食はもう出来上がっているのか、パンが焼けるいい匂いがしてきた。
台所からはアゲハがスクランブルエッグを作りながら鼻歌を歌いつつ肩を揺らしているのが見える、その髪
ではアゲハのお気に入りのアゲハ蝶の髪留めが踊っている。
クセなのかアゲハが料理する時よほど機嫌が悪くない限り常に鼻歌を歌っている、ということは昨夜のこと
を特に怒ってるということはないようだ。
昨夜は帰った時には既にアゲハは寝ていて今朝が帰ってから最初に見たのが今朝だったために怒っていない
か気にしていたのだけど……そもそもバイトで帰りが遅いのはいつものことなのでそうアゲハは気にしてはい
ないようで助かった、怪我もしてないしこれなら多分気付いていないのだろう。
席に着こうと居間に足を踏み入れる―――、
「おはよう~、秋悟」
とその時真後ろから声がした。
「―――うわっ!」
全く油断していた俺は思わずマヌケな声をあげつつ後ろを振り向く、そこには足まである長い金髪・大きな
赤い眼の美女……TVで見る世界のTOPモデルもかくやといった女性が、俺の背中から10cmもないとこ
ろにその姿からは想像できないような無邪気な笑顔を浮かべて立っていた。
「ミ、ミナミ、後ろから急に声かけないでくれよ、心臓に悪い」
「あら、私はさっきからここにいたけど秋悟がずっと気づいてくれなかったから仕方なく先に声かけたよ?」
「さっきからってどのくらい?」
「秋悟がここに来た直後に私も来てたわよ?なんで気づいてくれないのかな~?」
う、、そんな時からいて気づかなかったのか俺は、、ほんの30秒くらいの時間に過ぎないはずだがこんな
真後ろにいて気づかなかったなんて自分の鈍感さに自分で少し呆れる。
「ごめん、ちょっと考え事してたから、悪かったよ」
「どうしようかなぁ~?ねぇ秋悟、人は本当に悪いと思った時は態度で表すものじゃない?」
そう言いながらミナミが流し目を向けてくる。
その仕草はわざとやっているのだろうけども本当に艶っぽくてまともに顔を見続けていられなくなる。
顔が赤くなりそうだったので思わず眼をテーブルの方へ背ける、そこには出来上がったばかりの朝食が湯気
を上げていた。
「ッ、わかったよ。じゃあウィンナー1本で」
「2本で手を打とう!」
俺の言葉に最初からそう言うつもりだったかのように即答で返してくるミナミ、その顔には笑みが浮かんで
いて全く悪気がある様子がない。
「あぁもうわかった、じゃあ二本でいいから」
渋々といった様子で言ってみせる俺、だがあんな顔で言われて断れるほど俺は強い男じゃなかった、という
のが本当のところだ。
「あはッ♪ありがと~秋悟」
俺の返事に気をよくしたミナミは満面の笑みを浮かべてくる、この笑顔が朝から見れたのならウィンナー二
本はむしろ安いだろうと自分を納得させる。
「おはようミナミさん。二人で何してるの?」
と、そこへ食事を作り終えたのかエプロン姿のアゲハが声をかけてくる。
「なんでもないよっ♪アゲハちゃんもおはよ~」
そうアゲハに挨拶しつつミナミはすぐに居間へ入って行き自分の席に着席する、ちゃっかりしているところ
や切り替えが早いところは実に猫っぽい。
このブロンド美女のミナミ、当然ながら自分達兄妹の血縁というわけでもなんでもない。
うちは兄妹の二人暮らしなのだがそれに対して家が実に広いのだ、どれくらい広いかというとこの母屋とは
別に離れまであるくらいである。
当然二人暮らしでその広さを活用しきれるはずもない、なのでしばらく離れは放置されてきていたのだがせ
っかくあるものをもてあますのももったいない、何かと生活費で金は入用だしどうせなら貸家としてはどう
か?
といことになり借家人を募集したところこのミナミが来た、というわけなのである。
最初は外国人ということだけでも驚きだったが会ってみてさらに驚かされることとなった、女性ということ
は事前に聞いていたのだが実際に来たミナミは会った人誰もが言葉を失ったくらいの美女だったのだから。
これが原因でミナミが来てしばらくは静音や友にからかわれる破目となったくらいだ。
ちなみにまだ会って一ヶ月もたってないのにミナミと呼び捨てにしているのは本人からの意向だった、最初
は俺も大家として接していたのだがミナミの方から呼び捨てでいいと言ってくれたのだ。
当初は俺もアゲハも遠慮していたのだが、何度もそう言ってくれるので外国の人だからアットホームな方が
いいのかも?と偏見丸出しな結論を2人で出し呼び捨てで呼び合うようになった、という次第である。
この一緒にとってる朝食もその延長だった。
かくして、今日も結城家の朝餉の場には3人が揃っているのであった。
朝食も終わり、ミナミは離れに戻り後片付けを俺とアゲハがしていると玄関からチャイムが鳴る音が聞こえ
た。
「あ、静音さん来たよ」
いつも来る時間は同じ、相手も同じなので出るまでもないことはアゲハも俺もわかりきっていた、タオルで
手を拭き居間に置いてあったかばんを手に取る。
「んじゃ行くか」
「うん」
火の元を確認してから二人で家を出るとそこに長い黒髪に大きなリボンをつけた一人の女の子が立っていた。
「やっ秋悟、アゲハもおはよう」
「おはよう静音」
「おはようございます、静音さん」
彼女の名前は支倉静音、俺の幼なじみでありアゲハにとっても姉のような存在だ。
家が近く昔からの腐れ縁もあり今でも一緒に学校に一緒に通っている。
「アゲハ、火の元確認した?」
「うん、ちゃんとしてあるよっ」
「じゃ鍵しちゃうね」
そう言って静音はポケットから鍵を取り出し扉に鍵をかける、この家の鍵は俺とアゲハと静音も持っている、
支倉家とは静音だけでなく家族ぐるみでお世話になっているために静音が家に来ることも珍しくなくいつから
か静音にも鍵を持ってもらうことになったからだ。
静音が鍵をかけたことを確認した後3人で学校へ向けて歩き出した。
まだ朝も早く他に登校してる生徒もほとんどいない静かな住宅街を3人で他愛もない会話をしながら歩いて
いく。
「そういえばさ、秋悟。昨日あんたバイトだったでしょ?夜変なこととかなかった?」
「なんだよ急に……特に変わったことはなかったけど」
急に脈絡もなく言われて少し焦ってしまう、静音は昨日のケンカの話を知っててわざと聞いてるのか?と思
ったが静音の顔を見る限りそういった感じはしない、本当に聞いてみただけなようだ。
「秋悟、ニュース見なかったの?またあったんだよ、あの事件」
「あの事件ってなんだ?なんかあったのか?」
あの事件と言われても心当たりのない俺はそうマヌケに返してしまう。
「秋悟あんた知らないの!?」
「お兄ちゃん知らなかったの?」
う……静音とアゲハが全く同時に声をあげてくる。
なんだか自分がものすごくマヌケになった気分だ……静音とアゲハは動物園で奇妙な動物でも見るかのよう
な眼でこちらを見てくる。
しかしこっちとしても知らないものは知らないのだ、こう返すしかない。
「はぁ~……あんた本当に情報に疎いわねぇ。今この街に住んでてこの話知らないのって秋悟くらいじゃない?」
「仕方ないだろ、知らないものは知らないんだし。最近バイトも忙しかったからニュースとかも見てないよ」
「お兄ちゃん、最近街で変な事件が起こってるんだよ。事件現場に被害者がいなくて一応失踪事件ってことに
なってるんだけど、血が大量に残ってたりしてどう見ても人が殺されたとしか思えないような状態になってる
んだって」
俺と静音の言い合い(というほどのものでもないが)にアゲハが横から助け舟を出してくれる。
「それってイタズラかなんかじゃないのか?その血も何か別のモノを代用した偽者とか」
「そんなんだったら警察が見破ってるっての。ちゃんと警察で確認したけど本物の人間の血液だったらしいよ。
それも輸血用血液をバラまいた、とかじゃなく同一人物の血液」
静音が、、怖がらせようとしてるつもりなのかちょっと雰囲気をつけたおどろおどろしい言い方で言ってく
る。
「それで、その事件が昨日もあったのか?」
「そうそう、今回で確か4件目だっけ?」
「3件目だよ、静音さん」
わりと物事に大雑把な静音をアゲハがダメ出しする、これは昔からの構図でもある。
「3件目か、さっきアゲハも言ったけど事件現場なのに死体が見つかってないのよ、今まではね」
静音が思わせぶりな言い方をしてくる、いつものことだがコイツはもったいぶった言い方が好きなのだ、こ
こで突っ込んで聞いてしまうと静音の思うツボなわけだが、、悔しいが俺はここまで言われてそのまま流せる
ほど大人な人間ではなかった。
「今ままでは、ってことは今回は死体があったのか?」
俺と静音は長い付き合いだけに俺が聞き返してくることなどお見通しだったのだろう、静音はしたり顔で続
きを話だした。
「ふふん、今まで無かったものが今回だけはいきなり出てくるなんて都合よくはいかないわよ」
いや、都合よくいくとかいかないとかそもそも殺人事件のことだから俺もお前もわからんはずだけどな、と
思ったがあえて言わないで先を続けさせる。
「今回あったのは体の一部、確か手足が1本づつだったかな」
「うっ……」
今まで黙って話を聞いてるだけだったアゲハが思わず声をあげる、想像力のいいやつだから想像してしまっ
たのだろう、、合掌。
「おいおい、物騒だな……」
「しかもこの事件、アンタのバイト先の近くで起こったみたいよ?」
「えぇ!?」
それまで聞いててもどこか他人事だった俺だが流石に自分の身近な話だということを言われて少し驚く、間
もなく真横で声が上がった。
思わず横を見るとアゲハがビックリした顔をしていた、顔色も少し青ざめてる。
「お兄ちゃん……大丈夫なの……?」
「おいおい……バイト先の近くで起こっただけだから大丈夫だって。それに帰りもほとんど明るいところを通
ってるから危ないこともないよ」
「う……うん……」
そう言いながらアゲハの頭を撫でてあげる、こうすると昔からアゲハは落ち着くのだった、今日も少し撫で
てやってると落ち着いてきたのか顔にも血色が戻ってきた。
と、その様子を横で見ていた静音がクスクスと笑いだした。
「あははは、やっぱアンタ達仲いいわ~」
「おいおい、アゲハをあんまり虐めすぎるなよ」
「虐めてなんかいないわよ、ね~アゲハ?」
「う、うん……静音さんは優しくしてくれてるよ?」
うわ……完全に静音に陥落してるなアゲハ……。
それからは事件の話題は全く無くなり、静音にからかわれながら学校に到着するのだった……。
いつもの学校いつもの教室、アゲハとは学年が違うので途中で別れたが静音とは同じ学年同じ教室なので道
は一緒、というか静音とは小学校から違う教室になったことがないという筋金入りの幼なじみなのだ。
教室に入り自分の机まで行く、とそこには明らかに俺の机に突っ伏して寝ている明らかに俺じゃない男がい
た、日の光を浴びながら物凄く気持ちよさそうに寝ている。
「……友」
「ん~……?」
「こら起きろ」
と言いながら頭にチョップを打ち込んでやる、するとモソモソと動きながらようやく起き上がる。
「お、秋悟おはよう。今日もいい朝だな」
「いい朝だな、じゃない。寝るなら自分の机で寝ろ」
「いや俺の机廊下側で寒いんだよ。秋悟のはホラ、窓際でちょうどいい気持ちよさだし」
「じゃあもういいだろ、ホラもう席開けろ」
「はいはい、どうぞお座り下さい」
そう言いつつ友が席を空ける。
この俺の席で寝ていた男の名は北里友、静音と同じくずっと同じ学校同じ教室という幼なじみだ、その縁あ
って俺と静音と友は常に一緒に育ってきた。
同じ男ということもあって友とは静音以上に色々とバカなことをしてきた仲だ、しかし静音と違って家が少
し離れていたために普段会うのは学校で、となるのが普通だ。
「そういえばさ、秋悟聞いた?事件あったんだってよ」
「あぁ、死体がないっていう事件だろ?今朝静音から聞いたよ」
「そうそう、嫌な事件だよなぁ。死体が無いもんだから誰が死んでたのかもわからないらしいぜ、性別・年齢
もわからないもんだから警察も失踪者をしらみつぶしに探してるとさ」
なんだか今日は朝から物騒な話題ばかり聞いてる気がするな……そんなことを考えながら友と話をしている
と教室に平が入ってくる。
教室の大半の人はなるべく目を合わせないようにしているのがよくわかる、それもそうだろう、平は鮮やか
な金髪に身長180以上の長身、さらにはケンカで学校全体でももっとも有名な男なのだ、むしろこれは自然
な光景とすら言えるものだろう。
昨日は夜だった上に色々と焦っていたため確認出来なかったが今見てみても平は無傷のようだった。
「やぁ、二人とも。おはようございます」
「おっす、平」
「お前少しは反省したか?」
俺と友とで別々の反応をする、普段はよくかぶるだけにこうなることは珍しい、そしてこういう場合どうい
うことなのか友は知っている。
「なに?お前らまたケンカ?」
友はこちらを向いて飽きれたような顔をしてくる。
「誤解されるようなこと言うなよ、ケンカしてたのは平で俺は巻き込まれただけだって」
「よく言うよ、お前自分から突っ込んでくクセに。だいたい平に援軍なんていらないだろ~。お前目でしかケ
ンカできないんだし」
「仕方ないだろ、お前だって何度か助っ人に来てくれたことあるじゃないか。それに目の事はいいだろ、ある
もんは有効に使うもんだ」
と言ってみるものの友の言ってることはほぼ正しい、平が助けてほしいといったわけでもなく見かけたら自
分から飛び込んでいるのもその通りだし、実際平に助っ人はいらない、平は俺とは比べ物にならないほど強い
のだ、5人程度の相手で負けるはずもなく、平自身が喋らないので真偽は不明だが15人を相手に1人で勝っ
たという話もあるくらいだ。
もちろん俺もそういったことは理解している、理解しているのだがしかしどうしても考えるより先に体が動
いてしまうのだ。
「俺ならちゃんと判断するさ、勝てるケンカにわざわざ野暮なことはしない、相手が強そうな時も手を出さな
い」
「薄情だなオイ」
さりげなく言う友に思わず突っ込んでしまう、そんな様子を平はおかしそうに笑いながらみていた。
「でも秋悟の助けは本当にありがたいと思ってますよ、私もいつでも万全というわけにはいきませんから」
「それ以前にケンカするなっての」
しかし何度言っても平の周りからケンカが無くなる様子がない、血の気が多いというわけではないと思うん
だが、、そういう星の下にでも生まれてきたのだろうか?
「これでも秋悟に会う前と後ではかなり減ってますよ、それも秋悟のお陰です」
なんともうやうやしく頭を下げてくる、その仕草は本当に上流階級の人間のようだ。
外見もよく言葉遣いも丁寧で物腰も良い、これだけ見たら誰もコイツがケンカしまくりの不良男だとは思わ
ないだろう。
「だといいけどな、、とにかく次がないように気をつけてくれよ」
平が助けてくれと言ってきたわけでもないのに助けに入ってる俺としては、こう謝られたりするとあまり強
くは出られなく、この話はここで終わりになった。
「全員席につけ、ホームルームを始める」
話をしていて気づかなかったようだがいつの間にか教壇には担任が立っている。
「っと、もう来てたのか松永。じゃ俺は戻るわ」
「では私もこれで」
友は自分の席へ、平は平然と教室の外へと出て行く、平の教室が別の教室というわけではない、平はいつも
こんな感じでホームルームが始まると教室を出て行き、だいたいは終業まで戻ってこない。
その平が出て行く様子を担任は眼で追っているようだが結局注意はしなかった、多分もう諦めているのだろ
う。
俺達とは普通に話しているも、結局平の一般的な扱いは不良、皆が好き好んで接するようなことはない、そ
れは先生達も一緒だった。
とはいえこの件については平自身の問題ということで俺も口出しはしない、俺が平に怒るのはケンカの時だ
けだ。
出欠で自分の番が過ぎたのを確認すると俺は机に突っ伏した、バイトの疲れが出ているのか最近よく昼は寝
ている、今日も眠気が出てきていたので寝る用意、授業聞いてないのはまずいかもしれないがあとで友か静音
にでも聞くことにしよう……そんなことを考えてるうちに意識が遠のいていった……。
「…………ろ」
……
「…………きろ」
……ん?
「……ご……きろ」
何か誰かが言ってる気がする……、この声は確か静……、ゆったりとしたまどろみの中に聞こえてきた声の
ことを考えてると急に目の前に否妻が走った。
「った~~~」
頭を押さえながら体を起こす、無理な体勢で寝ていたためか体中が微妙に痛い、しかしそれよりも頭のズキ
ズキとした痛みが目立つ。
どう考えても殴られた痛み、そしてこの痛みの原因は目の前で仁王立ちしている女なのは間違いあるまい。
「なんだよ静音……」
「なんだじゃない!いつまで寝てるつもり?もう昼休みよ!」
そう言われてあたりを見回してみると、なるほど、クラスの大半が弁当を広げて昼食をとっている。
もう食事を終えてるヤツも少なくない、よほど疲れが溜まっていたのかホームルームから一気に昼まで寝て
しまっていたようだ。
「それにあんた図書委員でしょ?なんだか知らないけどさっき呼び出しされてたわよ」
「えっ、あそうか。今日は確か委員会がある日だ」
うちの学校は定期的に図書委員で会議みたいなことやっていて今日もその日だ、しかし今静音に言われるま
で完全にそのことを失念していた。
「はぁ、まぁあんたのことだから忘れてると思ったけどね……。ほらさっさと行ってきなさい」
「ん、悪いな静音。あと起こしてくれてありがとう」
「はいはい、いいから早く行きなさい」
静音に礼を言って教室を飛び出る、我ながら夫婦漫才のようなことしてるなと思う。
静音はアレで外見がよく、学校でもかなりモテるのだがいつも人にかまってその世話ばかりしているので特
定の彼氏を作ったことがない。
面倒見もいいから彼氏を作っても不思議じゃないのだが、、まぁこれも俺がどうこう言うことではないので
静音には特に何も言わない。
教室を出て一気に階段を駆け下りる、図書委員会は図書室であってるので図書室へ直行、昼休みだけあって
人は多いが人ごみの間を走り抜けるのには慣れている。
スピードを落とすことなく走り抜けて図書室に入る。
いつもと同じの本の匂い、喧騒に包まれていた廊下や教室とは別世界のような静けさがあるこの部屋。
進学校というわけでもないうちの学校は昼休みも図書室はわずかの人しかおらずいつも静かだ。
さらに今日は委員会もあるので一般の生徒はおらず全くの静寂……というか静かすぎる。
委員会があってるならもう少し人の気配や声がするはずなんだが……少し嫌な予感がしつつも図書室の奥へ
進んでいく。
しかし中にも誰もいない、委員会がいつも使っているテーブルには誰も座っておらず、逆に使い終わった後
のように椅子が少しごちゃごちゃしている。
「あっちゃあ……」
今更になって時計を確認すると昼休みが始まってから30分は過ぎている、この状況と時間からするともう
とっくに委員会は終わったのだろう。
これはちょっとまずい、、授業なら友や静音に聞けるが委員会の内容はそうはいかない、いくら疲れている
からとはいえ委員会あったことまで忘れてしかも昼休みを半ば以上まで寝て過ごすとは、我ながらかなりのグ
ウタラぶりだ。
少し途方に暮れているとコツコツと本当に耳を澄ませてないと気づかない程度の音が書庫の方から聞こえて
きた。
誰かいるのか?
音がした書庫の方へ歩いていく、図書室の入り口周辺はテーブルや椅子などもあり比較的ひらけているが奥
の方は書庫となっていてずっと書架が続いているだけである。
書架の方を覗き込んでみると一列目には誰もいなかった、二列目にもいない……順番に見ていくこと三列目。
その通路に一人の女生徒が立っていた。
肩まである髪をかきあげつつ書架を見ながら歩いている、その目には大きな円眼鏡、胸には三年であること
を示す青いリボン、そして手には多数の本を抱えてそれを一冊づつ書架に直していく。
そしてその人物は俺もよく知る人だ。
「依子先輩」
と声をかけると女生徒はなんともノンビリした動きでこちらを向き――、
「あ、サボリの人です」
といきなり言われた。
「すいません、ちょっと寝坊してしまって……」
「ダメじゃないですか。もう委員会終わっちゃいましたよ?」
「そうみたいですね、何か連絡事項とかありました?」
「特になしです、だから今日はいつもより早く終わったくらいですから」
にっこりと笑ってそう答えてくれる、図書委員の会議は他の委員会に比べると頻繁にあるためかこうした得
になしで終わることも決して珍しくはない。
ということはもうここには用事はないのだがさすがにこのまま帰るのは気が引ける、なにより先輩一人でこ
の作業をするのは大変だろうし、男としてはこういうとこで手伝わないわけにはいかない。
「じゃあお詫びと言ったらなんですが、それ手伝いますよ。先輩一人で全部直すの大変でしょう」
「あ、いいんですか?じゃあそれお願いしますね」
と言って先輩が指差した先にはまるで辞典かと思わせるほどの分厚い本の山……が30冊ほど。
一瞬ゲッと思ったが自分から言った以上撤回するつもりもない、先輩に言われるまま10冊ほど持ち上げ一
緒に並んで片付けだす。
ラベルを見ながら正規の場所へ本をしまうだけの単純作業、しかし本の重さがネックでかなり体力を使って
しまう、特に辞書クラス10冊分ともなるとかなりのものだ。
だがこんなことで弱音をあげるわけにもいかないので腕に力を入れてただ黙々と本を直していく、先輩も喋
らずに本を直していっている。
ラベルを確認して書架に直す……「和英・英和辞書」勉強に使ったのだろう。
ラベルを確認して書架に直す……「世界動物百科」誰か動物好きが借りていったのだろうか。
ラベルを確認して書架に直す……「世界の兵器一覧」マニアックだなおぃ。
何も喋らずにただただ本を直しているだけなのだが特に退屈とは感じなかった、意外な本が借りられててそ
れを見るのが面白いということもあったのだが、それよりもたまに依子先輩を見た時の先輩の仕草のせいだろ
う。
たまに依子先輩の方を見てみると、先輩は書架と本を見比べながら頬に指を当てて小首をかしげていたりし
ている、その仕草はなんとも愛らしくこれだけ見るとこの人が先輩だということを忘れてしまう。
と、そうして先輩の方を見ていると先輩と目が合ってしまう。
「?どうかしました?」
「いや、なんでもないです」
「??」
まずいまずい、ジロジロ見るなんて失礼すぎだ俺、、。
その後は余計なことをしないで本を直すことに専念する、その甲斐もあってか昼休みが終わる直前には全て
直し終えることが出来た。
「はい、秋悟君お疲れ様でした」
そう言って先輩がペコッと頭を下げてくる。
「いや俺が勝手に手伝っただけなので。それに先輩にはお世話になってますし」
今日も自分のせいで委員会に遅れたところを何も無しとはいえ内容を教えてもらったのだから、これくらい
の礼は当然だろう。
「それはそれ、これはこれです」
がしかし先輩はこちらの意見をバッサリ斬り捨てるようにそう言ってにっこり笑った。
「さぁもう昼休み終わりますよ、教室に戻りましょう秋悟君」
と言いながら先輩は俺の背中を押して歩き出す。
「ちょっと先輩、ちゃんと自分で歩けますって」
「じゃあちゃんと歩いて下さい」
そう言って先輩は手を離し、ニコニコしながらこちらを見ている。
前々からそうだがこの先輩はどこか変わったところがあるな……、それがある意味先輩のいい所でもあるの
だけど。
そう思うも口にすることはなくそのまま二人で図書室を後にし、図書室の鍵を先輩が閉めた時ちょうど予鈴
がなった。
昼休みももう終わり、だったのに今になって俺は昼食をとってないことを思い出していた。
時刻は15時15分、全ての授業が終了し皆が帰宅・部活に散っていくこの時間。
「う~……」
俺は死にかけていた。
「腹減った……」
「なんだ秋悟、お前結局昼食食えなかったの?」
結局昼食を食べれなかった俺はそのまま昼食抜きでこの時間まで過ごした、5現目は空腹をやり過ごすため
に寝て過ごした、5現終わってから休み時間中に食事を取ろうと思っていた。
しかし今日は何事もうまくいかない日なのか、、起きたらそこは既に6現目真っ最中で食事などできるはず
もない。
さらには寝まくったせいで眠気が無くなっており、眠ってやり過ごすことも出来ず6現目の間ずっと悶々と
空腹に耐えていたのだ。
永遠とも思えるほど長い時間が過ぎ去り、ようやく6現が終わって食事にありつける!と思ったのもつかの
間、今度はそもそも弁当を家に忘れてきていたことが判明、結局今日は昼食無しとなり気力も体力も失って机
に突っ伏していた、という次第だった。
「友~……」
机に突っ伏したまま我ながら情け無い声で目の前の友人に話しかける。
「なんだよ」
「なんかオゴってくれ……」
「だが断る」
「なにィッ!?」
「この北里友の好きなことは自分を頼ってくれる友人にNOと、、っておいおい本当に辛そうだな」
「あぁ辛い……、すまんがボケに付き合ってやれそうもないわ……」
普段はバカばかりやってる仲なのだがさすがにこちらの緊急事態には気づいてもらえたようだ、友は頭をか
きながら――、
「仕方ないなぁ、普通なら購買行け、と言うとこだが……。ほれ」
と言ってアンパンを渡してくれた。
「うぉぉ!食い物だッ!!」
一気に袋を開けると一口、あんこの甘さが口いっぱいに広がる、俺はかつてアンパン一個にこれほど感動し
たことがあっただろうか!?いや無い!
貪るようにアンパンを食う、二口三口、ほんの3度かぶりついただけでアンパンは綺麗サッパリ消え去りき
っちり俺の腹へと納まった、そんな俺の横で友は大笑いしている、がそんなことは気にしない、今は目の前の
パンに集中。
「ご馳走様でした」
アンパンとアンパンをくれたよき友人に感謝。
「いや~、アンパン一個でそこまで感動してくれるとは、、空腹になると人間性が出るってのは本当みたいだ
な」
友は涙目になりながらまだ笑っていた。
「いや本当にそれほど空腹だったからな。とにかくお前には感謝、今度なんかで埋め合わせするさ」
そう言って友に手を合わせ拝むようなポーズをとる。
「いいって、アンパン一個でそこまで感謝されると逆に気持ち悪い」
手をひらひら振りながら友は断ってくる、見返りを求めてこないのはこいつのいいところだ。
俺もそういうとこはある程度理解しているので借りを返す時はそうと言わずに返してやるのが常だった。
「んじゃ俺は帰るわ。秋悟は今日もバイト?」
「そうだよ、最近仕事量が増えて忙しくてかなりこき使われてるさ」
「ははっ、大変そうだな~。ま、体壊さん程度に頑張れよ大黒柱!アゲハちゃんとミナミさんのためになっ」
「ミナミは関係ないだろッ」
そう言い返すも既に友は教室を出て行っていた、妙な時にすばしっこいやつだ。
全く、いいヤツと思って感謝しても直後にああいうマイナス面が出るから困るやつだ、しかしだからこそ友
は憎めないヤツでもある。
さて、腹も落ち着いたことだし早速バイトに行くことにする、がその前に一度一年教室へ。
かばんを持ち教室を後にする、カバンの中は多少のノートがあるだけで余計なモノ(主に教科書類)は机に
しまいっぱなし、だからカバンは軽い。
一年教室は一階下の階なので階段を下っていく、作りは同じだが自分たちと比べると多少幼さが見える学生
達が多い通路を歩き目的の教室前へ。
知らない教室を覗く、それも学年まで違う教室を、となると抵抗があるものだがそこはもう勝手知ったる他
教室といったところ、すぐ目的の人物を見つける。
「アゲハ」
と呼びかけながらアゲハの元まで寄っていく。
アゲハは友達と話していたようでポニーテールの女の子と向かい合って座っていた、俺の呼びかけに反応し
てこちらを向いてくる。
「あ、お兄ちゃん。どうかしたの?」
「今日もバイトで遅くなると思うから夕食先に食べておいてくれ。あと今日弁当家に忘れてきたみたいだか
ら、夕食にはそれを食べるよ。だから夕食はアゲハの一人分な」
「うん、わかった。でもお兄ちゃんそれだと昼食食べてないんじゃないの?」
アゲハが少し心配そうに見てくる。
「いや友に食事分けてもらったから大丈夫、夕飯までは十分もつさ」
そう答えるとアゲハはわりと簡単に納得してくれた、聞き分けがいい妹をもつと助かる。
「っと、話の邪魔をしてごめんね」
それまで俺とアゲハのやりとりをじっと見ていたアゲハの友人らしき女の子に声をかける、がしかしその子
はじっとこっちを見ながら僅かに首を振るだけだった。
なんだか小さな子だなぁ…、座っているのでわからないが多分150cm無いんじゃないだろうか?
解いたら肩くらいまであるであろう髪を後ろでポニーテールにしている、だがそんな外見より印象になった
のはその表情だった。
無表情。
ただただじっとこっちを見ているだけで何の表情も浮かんでいない、嫌われているのかいないのかもわから
ないのでなんとも話しづらい……。
「あ、ごめんね七十七(なづな)ちゃん、この人は私のお兄ちゃんだよ。お兄ちゃん、私のお友達の柳七十七
ちゃん」
気まずそうな俺の様子を見てかアゲハが間を取り持ってくれる。
「結城秋悟、アゲハの兄やってます。よろしく柳さん」
と俺もアゲハに合わせて挨拶をする、微妙にかしこまってしまってるがそれは俺の性格というよりこの子の
雰囲気のせいもあるだろう。
「知ってます」
そんな俺を見つめながら柳さんはそれだけ返してきた、顔はやはり無表情。
知ってるって……、俺はこの子と会った覚えがないのだけどな?もしかしてどっかで会ってて俺が忘れてる
だけなのだろうか?
にしてもこの子ほど印象深いと忘れることはないと思うのだけど…。
同じことをアゲハも疑問に思ったのかちょっとキョトンとした顔をしていた。
「あれ?七十七ちゃんお兄ちゃんに会ったことあるの?」
「無い、でも知ってる。先輩は有名だから」
う……二人の会話を聞くに俺が有名だから会ったことはないけど名前は知っていたというところのようだ。
そしてこの有名というのは十中八九、平との関係のことに違いない。
「へぇ~、お兄ちゃんって有名なんだ。うんうん、それは妹としても鼻が高くていいことです」
と、アゲハはなぜか得意そうな顔をしている。
いやアゲハ……有名たってその内容次第だと思うんだが……まぁあまり突っ込んで聞かれてどこからか昨日
のケンカのことがバレるよりはマシだろう。
しかし我が妹ながら少しズレてるな。
「じゃあ俺は行くから。アゲハ、柳さん、邪魔して悪かったね」
これ以上この場にいては墓穴を掘りかねないと退散することにする。
「うん、仕事頑張ってね」
アゲハの声に手を振って答えるとそのまま教室をあとにする。
教室を出た後にもう一度教室を覗いてみると、アゲハと柳さんが入ってきた時と同じように話をしていた。
ニコニコ笑いながら話をするアゲハと、アゲハと話している間もずっと無表情な柳さん、なんとも対照的な
二人だった。
学校から家とは違う方向、繁華街を抜けて人通りがまばらな道を通りさらに少し歩いたところで俺のバイト
先へ到着。
広い敷地内にデカデカととある長方形の建物は少し薄汚れていて年代を感じさせる外見をしており、壁の一
部にはツタがからみついているところもある。
そしてその横にある駐車スペースには数台のトラックが停車している。
この古い倉庫が俺のバイト先、ここで倉庫内作業をするのが俺のバイトだ。
知り合いのツテで教えてもらった仕事で、けっこうな重労働になることもあるがバイト代がよく俺は気に入
っている。
「おはようございます!」
「おぅ、坊主。今日も一日頑張れよ」
と、出会う人に挨拶をしながら建物内へ入って行く、既に他のおっちゃんとも顔見知りなので向こうもしっ
かり返事を返してくれる。
従業員用の入り口から中に入り、荷物が雑然と置かれた通路を通り抜けて更衣室へ入る。
中に入ると数人のおっちゃんたちに混じって眼鏡をかけた青い眼で金髪の背の高い明らかに外国人風の青年
が混じっていた。
少し前からバイトに入った人で一応は俺は先輩ということになるが、すぐに仕事を覚えていったおっちゃん
達曰く期待の星。
「おはよう、エース」
俺の声にぱっとこっちを振り向いてくれ、その眼鏡の中から青い眼がこちらを捉える。
「やぁ秋悟、昨日ぶり。筋肉痛はなおった?」
「いや筋肉痛になんてなってませんて」
「昨日あれだけ重労働だったのに?秋悟、君はタフだね~」
まだ会って間もないが既にかなり軽いやりとりをしてる俺とエースさん、ミナミもこともあるし俺が外国人
と打ち解けやすいのか、それとも外国の人は皆こうなのか……。
「何言ってんだか、エースなんか昨日俺より働いてたのに全然平気じゃないか」
そんな俺の声にエースはニヤリとしてボディビルダーのようなポーズをとってみせる。
着替えの途中で上半身裸だったために筋肉がはっきり見える、割れた腹筋に厚い胸板、ゴツいとまでいかな
い程度のスリムでいながら筋骨隆々としたバランスのよい体つきをしている。
う~ん、マッチョになりたいとは思わないがこのくらいの体つきは同じ男としては憧れるな。
「そういえば街でかなり凄惨な事件があったらしいね」
着替えをしているところにエースから声がかかる、やはり俺が知らないだけでかなり街でも話題になってい
るのだろう、今日はこの話題ばかり聞いている気がする。
ていうかなんで俺はこの話題知らなかったんだろう?
そうして事件について雑談をしながら服を着替えて、エースと一緒に職場に入る。
最近は仕事が一気に増えて忙しいらしく俺達が入った時にはもう何人ものおっちゃん達が忙しそうに動き回
っていた。
俺は夜で上がりなのだがどうも徹夜に近い状況になってる人もいるとかいないとか……。
早速俺たちも指定の場所へ散る、荷物の運び入れは午前中に終わっているので今日の仕事は明日出す分整理
となる。
忙しく動き回るおっちゃん達に混じって俺も荷物を運び出し、所定の場所まで持って行きまた戻って別の荷
物を持ち移動させ、を繰り返す。
昼食がアンパンだけだったのですぐ空腹になってきたはずだがそれを感じる間もなく動き回り、そして時間
も過ぎていった。
「お疲れ様でしたッ!!」
「はいお疲れ~」
「お疲れ様~」
「秋悟またね~」
上がりの時間となり着替えをしてまだ忙しく動き回ってるおっちゃん達に声をかける、エースもまだ残って
いてこの時間に帰るのは俺一人だ。
学生ということで色々と融通をきかせてもらっているのである。
倉庫を出るともう完全に日が暮れていた、この場所自体が閑散とした場所にあるため回りも真っ暗で静かで
なんとも寂しい感じがする。
「は~……腹減った……」
昼と同じセリフを吐き歩き出す。
バイト中は忙しくて感じる暇もなかったがそれはそれ、バイトを終えるととたんに空腹感を感じてきて今は
それがピークに達していた。
人によっては一食くらい抜いても全然平気という人もいるが、俺の場合は一食抜くだけでもかなりのダメー
ジを受ける。
消化が早いのか、空腹になるのが早いのだ、今日もアンパン一個ではやはりもつはずもなくこうしてふらふ
らになりながら帰宅している。
どこをどう歩いたかもはっきりしないまま歩き続け、繁華街の外れにさしかかったあたりで遠くで鳴ってる
サイレンの音が聞こえてきた。
サイレンの音はじょじょに近づいてきて、道路をパトカーが通り過ぎたと同時に遠ざかっていった。
なにか事件でもあったのか?と思ったその時になって朝の会話を思い出す。
――最近街で変な事件が起こってるんだよ。一応失踪事件ってことになってるんだけど、事件現場血が大量
に残ってたりしてどう見ても人が殺されたとしか思えないような状態になってるんだって――
自分とは遠い、自分には関係ない話と思っていたが今俺が歩いてきた道の途中、襲われる可能性がある場所
は何箇所もあった。
しかも自分は今空腹のせいでふらふらだ、この状況でもし襲われたら相手が1人でも勝てるとは思えない、
それが事件の犯人だったりしたら何かで武装しているだろう、そうなると余計に勝ち目はない。
自分の現在の状況を冷静に考えてみると、自分はただ襲われていないというだけである、ということに気づ
かされ、その迂闊さにわずかにだが恐怖した。
今もあたりにはほとんど人はいない、この後の道はさらに人が少なくなる、いや住宅街に入ると大半の道は
誰も通ってないのが普通だ。
「ふぅ……、もうちょっとしっかりしないとな……」
一度深呼吸をして気を持ち直す、事件があったからといってそう神経質になりすぎることもない、しかしぼ
けっと歩いていてもいいわけではないのだ、と自分に言い聞かせる。
気持ちが落ち着き、空腹感も耐えれる具合になったところで歩き出した、今度はフラつくこともないしっか
りした足取りで。
小説ひめ(仮題)第1章ノ2 平常
© Rakuten Group, Inc.