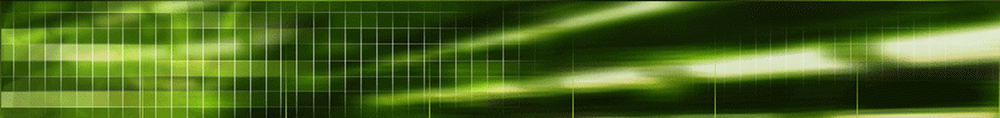第一話「輪廻転生」
それは、人の歴史に名を列ねし英霊達の第二の故郷…。
彼の者は戦国の時代を生き、数多の兵を切り伏せた将。そして、またある者は持てる叡智を振るいて歴史を操りし賢者。
時を越えて集いし彼等の魂は、死した後もこの世で鎬を削る。
記憶も無く、己が何者かも知れぬというのに、英霊達はその本能に従い幾千年を再び生きる。
この世界には、基本的に寿命という概念が存在しない。
一度死した魂は、既に肉体を失っているからだ。
だが、それでもこの世が存在するのは、戦の中で生きた者達の強念が具現化されているからなのかもしれない。
力への飽くなき探求心。
果たされる事のなかった約束。
犯した罪への想念。
人が「まだ生きたい」と願う理由は数知れない。
生に執着する思いの強さが、きっと…この世界を形作る真理なのだろう。
…だが、それだけなのだろうか?
本当にそれだけならば、この世に安息の場所などありはしない。
こんなにも人の心が穏やかでいられる理由がないのだ。
そんな事を考えながら、私は高く何処までも広い天(そら)を見上げていた…。
「飽きないなぁ…、この景色…」
キラキラと煌く星空のような蒼穹。
日の光を反射する独特な空の輝き。
何故、こんな奇妙な空を見て、何の違和感も覚えないのだろうか。
きっと、何もかもが新鮮で、真新しくて、だから、感動ばかりが先走っているせいなのかも知れない。
「そうか?オレはもう、いい加減見飽きたけどなぁ…」
ヴァンハルト・ベルフ・ヒューイット。
この世界に落されて、初めて出会ったヒト。
本当の意味で、初めて出来た「友達」と呼べるヒト。
この人が隣に居てくれる。ただそれだけで、今をこうしていられる事が、何より楽しく思えた。
「…もう三百年以上も見てるからな。今更って感じだ」
ココに来て、もう一月余りになる。
その間、ずっとこの人と生活を共にしている。
ヴァンは、この世界について色々な事を私に教えてくれた。
この「空の海」もその一つだ。
「そういうもの?」
「そういうもの」
目も合わせず、私達は、ただただ天を見上げていた。
この世界の空は奇妙だ。
大気のずっと上には、世界全体を覆う広大な海が広がっていて、その更にずっと向こうに、太陽のような輝きが在る。
だから、波打つ海面が陽光を乱反射させ、キラキラと煌いて見える。
物理法則など完全に無視したファンタジーな現象だ。
「…フゥ~。そろそろ行こっか」
私は立ち上がると、スカートについたホコリを両手でパンパンっと叩き落とし、隣に座ったままのヴァンに微笑みかける。
「もう、いいのか?」
「うん。もうお昼でしょ?家に帰ろ」
キトラという街の郊外。そこに広がる高原で、私達二人は休息をとっていた。
芝の香りを含んだ優しい風が心地良いこの場所は、私のお気に入りだった。
ここを見付けてからは、毎日のように同じ場所に座り込んで空を眺めている。
それが、もう日課のようになっていた。
「んじゃ、帰るか」
私が差し出した手を握り、ヴァンもスクッと立ち上がる。
にぎられた手に重みは感じない。女の私に対するこのヒトなりの優しさだ。
高原の街キトラ。
アウカトーラと呼ばれる大陸の南方に位置するこの街は、気候も穏やかで年中暖かい。
国家という枠組みから外れた土地だからか、他国からの侵攻を受ける事もなく、日々平穏な暮らしが人々の心までも穏やかにさせている。
住み易いいい街だった。
だからなのか、ヴァンは私をこの街に招き入れてくれた。
「お昼、何が食べたい?」
「なんでも。ショウコの作る料理…ワショクっていったっけ?アレは美味いからな」
二人並んで広い石畳の街道を歩きながら、そんな日常的な会話を交わし、道の両端に並ぶ雑貨屋や八百屋の店主から声をかけられてはニッコリと笑って挨拶を返す。
時折「若夫婦」なんて冷やかしの言葉もかけられるが、そんな極普通?の人の営みさえ、今の私には楽しくて仕方が無かった。
こんな幸せが続くのなら、永遠の命も悪くない。
だが、そんな事を考えながら、何時も通り昼食の材料を買い込んで、家路につこうとしていた時だった。
「…ヴァン!ヴァンハルト!」
「…?」
唐突に呼び止められ、私達は振り返った。
木造住宅街の一角。その石畳の街道を全力疾走してくる鎧姿の男性。
一直線に私達の所へ向けられた足が、呼び止めた相手である事を示していた。
「ハァ…ハァ…、探したぞ、ヴァン…ッ」
苦しそうに肩で息をしながら、今にも咽て詰まりそうになる言葉を無理矢理に吐き出す男。
そんな彼を見て、ヴァンは言葉を返した。
「クリフじゃないか。…どうしたんだ?そんなに慌てて」
どうやら、彼はヴァンの知り合いらしい。
ヴァンよりは少し若く、年の頃は私と同じくらいだろうか。
短めに切り揃えられたツンツンとした逆立つ髪型が特徴的な、気の強そうな青年だった。
「どうしたもこうしたもない!突然姿を消したと思ったら、女連れで幸せそうな顔しながら…ケホッケホッ」
何か急ぎの話しでもあったのだろうが、呼吸が整わずに結局咽るクリフと呼ばれた青年。
余りに苦しそうだったので、私は買い物籠の中から飲み物を取り出すと、思わず彼に手渡していた。
「だ、大丈夫…ですか?」
「わ、わりぃ、頂くよ…っ」
半屈状態で差し出した果物のジュースを手に取ると、クリフがゴクゴクと喉を鳴らしながらそれを飲み干す。
そして、一息つき、ようやく落ち着いたのか、彼は再びヴァンの方を向き直って話し始めた。
「フゥ~…。ヴァン、ローレンスがアンタを探してるぜ」
「ローレンスが…?」
「あぁ。…クーヤンが落ちた」
クリフのその言葉を聞いた瞬間、ヴァンの顔色がガラリと変わった。
「なんだって!?」
怒気にも似た何かを孕んだ驚きの声が街中に響き渡る。
会話の内容がいまいち良くつかめないが、それが重大な話しである事は直ぐに分かった。
焦りともとれる複雑な表情。
ヴァンのそんな顔を私は見た事がなかった。
二人の会話は、そんな私を置き去りに、どんどん進められて行く。
「…まさか、こんなに早く…っ」
「あぁ、ローレンスも予想外だったみたいだ。けど、ウチの諜報部がグランスレイの紋章付きを何機か確認してる。…間違いない」
「クーヤンが落ちたとなると、ここも…。マズイ状況だな」
「頼む、ヴァン。戻ってきてくれ…。アンタが居てくれなきゃ、アレを動かす事も儘ならないんだっ」
ヴァンは何かを迷っている風で、その返事に困っているようだった。
そして、「戻ってきてくれ」と言ったクリフのそんな言葉が、私の中の不安を煽っていた。
彼が…ヴァンが、何処か遠くに行ってしまいそうで、それが怖くなったのだ。
「…ヴァン…」
思わず、私は彼の服の袖をつかんでいた。
「ショウコ…。いいや、そうだな…。わかってるさ」
私の気持ちを察したのか、それとも、何かを決意したのか、ヴァンは微笑みながら私の頭をクシャクシャっと撫でると、キリッと真剣な顔に戻ってクリフの方を向き直った。
「クリフ、飛行艇を用意してくれ。出来るだけ早くだ」
「それじゃあっ」
「あぁ、お前は先に戻って、ローレンスにこの事を伝えてくれ」
「わかった!…そう言ってくれると思ってたぜ、ヴァン!」
今にも飛び跳ねそうなほど喜びに満ち溢れた表情。
だが、そんなクリフとは対照的に、私の中の不安は大きくなってゆく一方だった。
それを察したのだろうか。クリフは急に大人しくなって、私の方を見ながらヴァンに尋ねる。
「…彼女の事、どうするんだ…?」
その質問の答えを待つ私は、正直、気が気じゃなかった。
きっと、何が起こっているのかを、彼は説明してくれるだろう。でも、その内容次第では、私とヴァンの距離が遠く離れてしまう。そんな予感がしていたからだった。
しかし、ヴァンは予想外に穏やかな表情でクリフに答えを返す。
「今から話し合ってみる。…少しだけ、時間をくれないか?」
「わかった。でも、あんまり時間はないぜ」
「あぁ。すなまい」
フゥ~っと呆れたような笑顔を浮かべ、クリフは私の方を向いた。
「そんな不安そうな顔しないでくれよ。オレがまるで、悪者みたいじゃないか」
「ご、ごめん…なさい…」
「うわっ、泣くなよ!?簡便してくれっ」
何故だろう。
涙が溢れてきて、感情を抑えられなかった。
前はこんな事なかったのに…。
孤独に慣れてしまっていたからだろうか。
でも今は、孤独という物を知っていて、一人じゃない事の幸せを知ってしまったから?
考えれば考える程、涙が後から後から溢れ出してきた。
「た、助けてくれよ、ヴァン。女は苦手だ」
「ハハハッ」
クリフがお手上げと言わんばかりにヴァンに助けを求める。
すると、ヴァンは豪快に笑って、私の頭をスリスリと撫でた。
「心配するなよ。一人になんてしやしないから」
その瞬間、突然、私の中の不安が吹き飛んだ。
凄く苦しかった筈なのに、たった一言だけで、私の涙はスッと止まっていた。
現金な奴。そう思われるだろうか。でも、本当にそれだけの事で、私の中のモヤモヤした気持ちはスッキリとして消えてしまっていたのだ。
「…うん…」
泣き止んだ私を見て、ホッとした表情でクリフが続ける。
「流石だね。女の扱いに慣れてる」
「オイオイ、誤解を招くような事言うなよ」
困り顔でそう返したヴァンに、クリフは笑いながら片手を振って踵を返した。
「ハハハッ、そんじゃ、先に戻ってるぜ、ヴァンッ」
「あぁ、ローレンスによろしくなっ」
再び走って来た方に向かって駆け出すクリフ。
返事こそなかったものの、走りながらしばらく手を振ってそのまま人込みの中へと消えて行く彼に、私はヴァンとは違う心地良い気持ちを抱いていた。
結局、二人の会話の意味は分からず終いだったが、それでも、気持ちを落ち着かせる事が出来た。
これから一度、私達の家に戻り、ヴァンが説明をしてくれるのだろう。
まだ多少の不安はあったが、それでも受け止める心構えは出来ていた。
木造の借家。
なんと表現すればいいのか、それは私の住んでいた国にはなかった様式の家だった。
中世ヨーロッパを題材にした映画などで屡登場する一般家屋…とでもいうのだろうか。
天井、床、壁。テーブルもイスも、家具も何もかもが木造品で、室内に入った途端に心地良い木の香りが鼻腔を擽る。
私の実家にも似たような香りの和室があるが、こことは漂う風情が違う。
そんな洋間へと辿り着いた私とヴァンは、早速話し合いを始めた。
ドッカとイスに腰を下ろしたヴァンは、テーブルを挟んで座る私に向かって少し真剣な表情で語り始めた。
…それは、信じられない話しだった。
ヴァンは、とあるレジスタンス組織のトップで、さっきの会話に出てきたローレンス・アーンスラントという人物が代理を勤めているらしい。
クリフはローレンス直属の部下で、剣の腕もたつ信用出来る男。…なのだそうだ。
そして、ヴァン達が長年反抗を続けている相手というのが、やはり先程の話しの中に登場したグランスレイ王国という軍事国家らしい。
このグランスレイという国は現在幾つもの周辺諸国を相手に戦争を繰り広げているらしく、その圧倒的軍事力によって次々に他国の統一化を果たしているのだそうだ。
だが、余りに非道な行いを平然とやってのける彼等に反発する組織や国は少なくなく、各地で大規模な戦闘が毎日のように繰り返されているらしい。
この世界に来てから、初めて住んだのがこんな平穏な街だったせいか、私はすっかり忘れていた。
こ世は、群雄割拠。
英雄達が己が血肉を賭け、命と鎬を削り合う戦国の乱世。
弱肉強食が罷り通る、力こそが全ての世界だという事を。
それを、まざまざと思い知らされた…。
「…じゃあ、ヴァンは戦争に行くって事…?」
「そう…だな。そういう事になるんだろう」
私は多分、また不安そうな表情をしていたんだろう。
そんな私を見て、ヴァンは何処か済まなさそうに言葉を返した。
「こんな風になるなんて、思ってもみなかった…」
何十年か昔なら、戦争に友達や家族を奪われるなんて普通の事だったのかも知れない。
でも、私が育った時代は平和で、戦争なんて言葉とは無縁の毎日を送っていた。
確かに、勉強として学校でならった史上の事実。
そういう時代があった事は知っていた。だけど、まさか自分が体験する事になるなんて…。
正直に言って、悩んでた。
ヴァンは私を一人にはしないと言ってくれた。
だけどそれは、「自分は死なない」という意味ではなく、「私も連れて行く事が出来る」という意味だった筈だ。
だって、あの時にはまだ、戦争なんて言葉を口にはしていなかったんだから。
じゃあ、私はこの人と共に戦場に立てるの?
人と人との命のやり取りを目の前にして、耐えられるの?
剣の腕には覚えがある。だけど、だからといって、それが実践で通じる保障はない。
ううん。むしろ精神的な物の影響を受けて、実力さえまともに発揮出来ないかも知れない。
足手纏いになるんじゃないだろうか。
それ以前に、戦えるのだろうか。
戦がどんなものであるのかは知っているつもりだ。
でも、知っているのと経験があるのとでは雲泥の差がある。
私は返答に困っていた。
「そんなに悩む事はないさ」
「え?」
私は、本当に馬鹿正直な顔を持ってるらしい。
ヴァンには、私の心境なんて全てお見通しだったみたいだ。
だから彼は、今まで見せたどんな笑顔よりも優しく、微笑みながら続けてくれた。
「ショウコがどんな生き方を選ぼうと、オレが守ってみせるさ。だから、何処に居たって、それは永遠に変わらない」
歯の浮くような臭いセリフ。
でも、こんなにも頼り甲斐のある言葉を聞いた事なんてなかった。
けど、それを正直に口に出すのは恥ずかしくて、だから私は、少しだけ皮肉を込めてこう返した。
「…キザだよ」
「そ、そうか?」
「やっぱり、クリフさんの言った通りなんだ」
「ん…?」
何が?って感じで最短の疑問文を返すヴァンに、私はジト目でクリフの言葉を繰り返す。
「女の扱いに慣れてる…」
「ブッ!お、お前までそういう事言うかっ!?」
誤解だ。と言わんばかりに立ち上がって抗議するヴァン。
そんな彼が可笑しくて、私は堪え切れずにお腹の底から笑ってしまった。
「ヒデェな…。人が恥ずかしいの我慢して、折角本気で言ったってのに…」
拗ねるヴァン。でも、お陰で吹っ切れた気がした。
実際やってみないとわからない。でも、やってみないとわからないんだ。
だから、私の心は決まっていた。
「ねぇ、ヴァン」
「ん…なんだよ?」
「私、ついてく事に決めた」
未だ拗ねていたが、その言葉を聞いた瞬間、ヴァンは何時もの笑顔に戻って承諾してくれた。
だが、そのヴァンの言葉が出る前に、突如として直下型地震のような地面から突き上げてくる振動と轟音に私達二人は襲われるのだった。
ゴォォ~ンッ!!
家中の家具が揺れ動き、ギシギシと音を発てる。
直後には、食器棚から陶器のお皿やカップが落下し、床に落ちて割れた音が私を驚かせた。
「キャッ」
耳を塞ぎ、蹲った私の肩をヴァンの逞しい腕が抱いて包み込むのを感じる。
その直ぐ後に、彼の声が耳元から響いた。
「家の中は危険だ。外に出るぞっ」
「う、うんっ」
グラグラと揺れ動く私達の家。
このまま地震が続けば、おそらくは物の数秒で倒壊してしまうだろう。
ヴァンに促されながら、私は耳を塞いだまま外へと駆け出した。
そして、家から飛び出した直後、メキメキっと強烈な音を発して家は崩れ始める。
「あ…あぁ……」
私はただ、唖然とその光景を凝視していた。
本当に一瞬の出来事で、まだ状況が飲み込めていなかったのだ。
だが、ヴァンの視線は、既に他の場所へと移っていた。
「冗談だろ…。手際が良過ぎるっ」
「…え?」
その言葉の意味が理解出来ず、私は慌ててヴァンの視線の先を追った。
そして、信じ難い現実を目の当たりにするのだった。
「な、なに…?なんなの、アレ………っ」
モクモクと黒煙を噴出し、炎上する無数の家屋。
逃場を求めて惑い、悲鳴をあげる人々。
夕方でもないというのに茜色に染まる空には、幾つもの電光が散っていた。
その中で、最も信じられなかった物。それは、人のような形をして空を駆け抜ける幾つもの物体だった。
「グランスレイの鎧甲機…チッ、もう嗅ぎ付けてきたってのかっ」
グランスレイ?
それは、ついさっきヴァンの口からも聞いた名だった。
ヴァン達レジスタンスが戦っている相手。
…そう。これは、戦争だったんだ。
「ど、どうしようっ!ねぇ、ヴァン、どうしたらいいのっ!?」
やっぱり、私はダメだ。
混乱して、こんな時にどう対処していいのかまるで解らない。
私に出来た事なんて、ただヴァンに頼って、耳を塞ぎながらしゃがみ込む事だけだった。
「ショウコ………コッチだ。ついて来い!」
それなのに、ヴァンは私の手を強く握って駆け出してくれた。
絶対に離さない。そんな気持ちが痛いほど伝わってくる。
この人は、本当に私の事を守ってくれようとしてるんだ。
なのに、私は…。
「…ゴメンね…ヴァン…」
この喧騒だ。聞こえている筈がない。
でも私は、前を走る大きな背中に、小さくそう呟いていた。
ついさっきの自分の言葉を悔いていたんだ。
ついて行くなんて言っておいて、こんな様だもんね…。
そんな事を思いながら、覚悟の甘さを痛感していた。
それから、どれくらい走り続けたんだろう。
切迫した状況だからだろうか。疲れとかそんな物を感じている余裕さえ、私にはなくなっていた。
気付いたら、街を襲う轟音が遠くなっていて、そこには見慣れた景色が広がっていた。
「ここ…何時もの…」
透き通るような芝生の香りが風に運ばれて私の五感を刺激する。
今朝だってここに来たんだ。見間違える筈がない。
…そう、ここは、何時もの休憩場所だ。
どうして、こんな所に?そんな下らない疑問が頭を過ぎる。
でも、それには大きな理由があったんだ。
「…クソッ、早く動いてくれ、このポンコツッ」
ヴァンはズボンのポケットから取り出した小さな鉄板のような物を握り締め、何かを苛立ちながら待っているようだった。
早く逃げなきゃ。そう思っても、ヴァンはそこから動こうとはしない。
だから、何を待っているのか尋ねようと口を開きかけた。
でも、次に目の前で起こった不思議な現象に、私の口は開きっぱなしになってしまった。
「トビ…ラ…???」
突如目の前に開け放たれた扉。
うん、そうだ。トビラとしか言いようの無い物だ。
でも、そのトビラの向こう側には建物なんて建ってない。なのに、そこには扉だけがあって、ポッカリと開かれたその奥には何処までも深く長い階段が続いていた。
地下へと続いているんだ。でも、ここに逃げ込むの?
入り口から数メートル先は、暗くて階段の段を確認する事も出来ない。
そんな場所に逃げ込むのが、少し怖かった。
でも、ヴァンは私の手を引いて、その中へとズンズン突き進んで行く。
「ね、ねぇ、ヴァン。暗くて何も見えないよ…っ」
手を握っているだけでは足りなくて、彼の声を聞きたくて、そんな事を言った。
そんな怯えた声に私の心境を察したのか、ヴァンが優しげな声を返してくれる。
「大丈夫だ、オレがついてる。それにホラ、目も慣れてきただろ?」
「…………………」
手探りで進む内にそんな事を言われ、半信半疑で目を凝らす。すると、真っ暗だとばかり思っていたそこには、何処からか差し込んだ光で微かに白んで見えた。
良く見れば、ちゃんと階段だって見えて来る。
それに気付いた私の足は、徐々に歩行速度を上げていた。
そんな私の変化を知ってか知らずか、落ち着いた頃を見計らうようにヴァンが口を開いた。
「連中の狙いは、十中八九この奥の代物だ」
「…ここの奥?」
だが、その問いの答えを聞く前に、突然視界が開けた。
「うっ」
暗闇の中を歩き続けたせいで、目が急激な光量の変化に対応出来なかった。
地下だというのい、まるで太陽の日の光のような眩しい明りが天井から降り注いだのだ。
蛍光灯?最初はそんな風に思ったが、この世界にそんな画期的な技術は存在しない。
つまりは、別の何かが発光しているせいなんだろう。
だが、それを考える間もなく、私の目には自身の視覚を疑うような光景が映し出されていた。
「…石…像?」
冒険物の映画でも見ているような気分だった。
そこには、神殿か何かなのか、石造りの遺跡のような物が広がっていて、部屋の両脇に立ち並ぶ欠けた石柱や剥がれ掛けた石壁のヒビがこの場所の長い歴史を物語っているようだった。
天井は高く、砂埃の積もった床の上は、意外にしっかりとしている。
その石畳の向こうを真っ直ぐに見据えると、祀られるように人型の巨大な石像が鎮座していた。
私は、その巨像に目を奪われてしまっていた。
「…ヴァルシード…」
「…えっ?」
唐突にヴァンが発した言葉。
その言葉…というより、単語の意味を聞き返そうとすると、その前に彼の方から語ってくれた。
「それが、この鎧甲機の名前らしい」
「がい…こう…き?」
さっき、空を飛んでいた人の形をした物を見た時も、ヴァンはそんな言葉を口にしていた。
「がいこうき」とは、いったい何なのだろう?
目の前にあるソレは、石で出来たシンプルなデザインの木人形のようにも見えるけど…。
そんな事を考えていると、ヴァンは説明を続けてくれた。
「鎧甲機ってのは、乗り込む人間の意志に反応して動く機械仕掛けの兵器の事さ」
「乗り込む…って、アニメや漫画みたいなのに出てくる、ロボットみたいなモノなの?」
「ん…あにめ?まんが?…いや、その「ろぼっと」って物がどんな物なのかは知らないが、要は人間が操縦する兵器と同じだ」
忘れてた…。この人は、もう三百年以上も前にこの世界に落されてるんだ。つまり、私の生きていた時代から三百年前の人って事。
そんな人が、アニメや漫画、ましてロボットなんて言葉を知ってるはずがない。
私は、自分で口にした言葉を馬鹿馬鹿しく思い、少し苦笑する。
「まぁ、いいや。ショウコ、これから言う事を、しっかり聞くんだ」
「え…う、うん…?」
急に真面目な顔で両肩を正面からつかまれ、少しドキッっとした。
でも、期待していた言葉とは裏腹に、ヴァンの口は思い掛けない言葉を紡ぎ出す。
「…今からお前を、コイツに乗せる」
「うん…って、ちょっと待ってよ!これ、兵器なんでしょっ?まさか…私に、これで戦えっていうのっ!?」
突然の話しで気が動転し、口調が荒くなる。
しかし、それでもヴァンは話しを止めようとはしなかった。
グッと肩をつかんだ手に力が込められ、押さえ付けられる。
「落ち着けって!」
「あぅっ」
「何も戦えなんて言う気はない。…いや、正確には、コイツは動かせないんだ」
「…?」
「だが、今そんな事はどうでもいい。重要なのは、動かせないって事なんだ」
「どういう…事?」
「動かす事が出来ない。つまり、コイツの中にさえ居れば、安全って事なんだよ」
「えっと…」
ヴァンが言いたいのは、こういう事なのだろうか?
動かない石像の中に隠れていれば、グランスレイの兵隊達に見付かっても私に手を出す事は出来ない。
だから、この中に居れば安全。
つまり彼は、私に安全な隠れ家を用意してくれたという事なんだろう。
「じゃあ、これの中に入ってるだけでいいの…?」
「そういう事だ」
そう言うなり、突然背後の階段を気にし始めたヴァンは、私の手を強く握って鎧甲機というその石像の裏側まで引っ張って行った。
石像の裏側には石造りの階段が崖のように聳えていて、そこをやはり手を引かれながら上って行く。
十メートルも無かったが、それでも落ちればただでは済まなかっただろう。
それを思い、下を振り返ると身震いしてしまう。
「で、でも、動かせないんでしょ?どうやって中に入るの?」
すると、ヴァンは先程の物と同じ鉄板のような物をポケットから取り出して見せた。
「コレさ」
私はそれを手渡されると、その圧倒的な軽さに驚かされた。
金属に見えるその板は、想像以上に軽く頑丈そうだった。
しかも、外枠には美しい彫り物までされていて、何か古代の象形文字にも似た模様も削り込まれている。
十字架…と呼ぶには少し幅広なソレを手に、私は再び聞き返す。
「これを…どうするの?」
「至って単純。…念じるのさ。「開け」ってね」
胡散臭い。なんて言ったら怒られそうだけど、確かにそう思った。
でも、現にさっきは、何も無かった筈の空間に扉が開け放たれた。
あの時だって、ヴァンはコレを握り締めていただけだったんだから、信じるしかなかった。
「念じる…。開け…」
ついつい、~ゴマって言いそうになる自分を馬鹿らしく思い、心の中で笑いながら念を込めてみる。
勝手なんかわからないから、そこは適当だった。
でも、それは思いの外簡単に開いてしまう。
キュィ~ン…パシュッ
壁面のヒビかと思っていた亀裂が上下に裂けるように広がり、機械的な音を発していた。
「あ…開いた…」
「ショウコ…お前って、案外平気そうなんだな…」
「えっ?」
そう言われて気付く。
何故だろう?ここに入り込んでから、急に気持ちが楽になったような気がする。
神殿のような造りのこの部屋に漂う神聖な空気のような物がそうさせているのだろうか。
ただ、確かに言えるのは、懐かしさのような不可思議な感情が胸のずっと奥の方にあるって事だけだった。
だが、次の瞬間には、そんな気持ちさえ吹き飛ばされてしまっていた。
『…周囲を隈なく探せ!早急に目標を確保せよ!』
『ハッ!』
その声は、私達が降りて来た階段の方から響いて来た。
グランスレイ軍の兵士達の声だ。
巨像の裏手に居るので、もし彼等が部屋に入り込んで来ても直ぐに見付かる事はないだろう。
だが、それでも私は、両手で口を塞いで身を屈めてしまっていた。
「…早く中へ入れ。見付かっちまうぞ…っ」
私の耳元で、小声でそう囁くヴァン。
私は無言で首を縦に振ると、鎧甲機の背中にポッカリと開かれた穴蔵の中へと滑り込んだ。
「…ヴァンも早く…っ」
穴蔵の底に辿り着いた私は、入り口の方に向かってヴァンにそう言った。
しかし…
「ワリィな…、ショウコ。コイツは、一人乗りなんだ」
「…え?」
一向に飛び込んで来ようとしないヴァンに、私は手を伸ばそうとした。だが、その手が彼の下へと届く前に、急にヴァンの姿が遠退いて行く。
「え?えっ??どうしてっ!?」
私は困惑気味の頭でそんな事を口走りながら、周囲をグルグルと見回していた。
何とかこれを止めないと。そんな気持ちだったんだろう。
でも、その思いに反して、ヴァンは遠くからコチラを見下ろしていた。
「オレには、まだやらなきゃならない事がある。…お前とこの鎧甲機を守らなきゃいけないんでな…」
「…なに…それ…。なに格好付けてるのよっ!?ヴァンには似合わないよ、そんなのっ!」
「ハハッ、ヒデェなぁ。…けど、サヨナラだ…」
「ウソ…。ヤダよ…。待ってよ、待ってってば!」
だけど、どんなに叫んでも、ヴァンは何時もみたいに優しく微笑んでくれるだけだったんだ…。
ドンドン遠くに行っちゃって、姿が小さくなって行って、また一人ぼっちになっちゃうんじゃないかって、不安で押し潰されそうだった。
十分?三十分?…ううん、もしかしたら、たった数秒の出来事だったのかも知れない。
孤独感の中で膝を抱えていたら、そこは真っ暗な何もない世界だった。
私は一言だけ、呟いてみた。
今、一番会いたい人の名前…。
「……ヴァン……」
期待なんて、これっぽっちもしてなかった。でも、その瞬間、私の願いは聞き届けられた。
「ウソ……、ヴァンッ!?」
いきなり広がる色付いた世界。
私の目には、確かにヴァンの姿が映っていた。
だけど、決して楽観出来る状況とは思えない光景だった。
「ヴァンハルト・ベルフ・ヒューイット…。やはり、貴様だったか」
「へぇ~、オレも有名になったもんだ。末端の飼い犬にまで名前を覚えられているなんてな」
「なっ、貴様ぁ…私を侮辱するかっ」
私の足元。…ううん、巨像の足元だろうか。そこで、ヴァンは両手をロープのような物で縛られ、身動きを封じられてグランスレイ軍の兵士に剣を突き付けられていた。
一人や二人ではない。複数人の剣で武装した兵士達に取り囲まれている。
ヴァンは、その中の一人…一番派手な鎧を来た仮面の兵士と何かを言い合っているようだった。
「やるのか?だったら、好きにしなよ」
「…いいや、まだ殺しはしない。処刑命令は下されているが、生け捕りにしたとなれば、陛下も私の実力を認めてくれるというものだろう?」
「甚振ろうってか…。アンタ、趣味悪いぜ」
「ぬかせっ!」
突然剣を振り上げる兵士。
「っ!!」
私は声にならない声を発し、両手で目を覆っていた。
「ゥグッ!」
ドッと鈍い音が響いた。
幸い、剣で斬られたのではなく、その柄の部分で殴り付けられただけのようだった。
だが、それは一度だけでは済まなかった。
「…グッ!…カハッ!」
「私を侮辱した罰だ!タップリと後悔させてくれるわっ」
「グアッ!」
何度も何度も殴り付けられ、地面に倒れ込むヴァンの姿は痛々しかった。
「ヴァン!ヴァンッ!」
私がどんなに叫んでも、その声が彼等に届く事はなかった。
助けたい。今直ぐにでも飛び出していって、あの兵士達を斬り殺してやりたい。
でも、どんなに嘆いても、今の私には何も出来なかった。
この巨像の中から外に出る手段さえ見出せなかったのだ。
初めて出来た、大切な友達。
その友達が目の前で苦しめられているというのに、自分には何一つ出来る事なんてなかった。
無力さを呪わずに、何を呪えというのだろう。
非力さを嘆かずに、何を嘆くというのだろう。
「私…なんて無力なの…っ」
涙が後から後から溢れ出してくる。
悔しい。
剣道の試合で負けた時よりも何十倍…ううん、何百倍も。
だけど、私が悔やんでいる間さえ、グランスレイ兵士のヴァンに対する暴行は止まりはしなかった。
「陛下に背く愚か者が!己が分を弁えよっ」
「グァーーーッ!」
床に倒れこんだヴァンの腹部を容赦なく具足の尖った先端で蹴り込む兵士。
耐え兼ねたヴァンは、口から多量の血を吐き出し、地面を赤黒く染め上げた。
「フンッ、殺してしまっては元も子もないからな。この辺で許してやろう。…フッ、感謝するんだな、ヴァンハルト・ベルフ・ヒューイット」
剣を鞘に収めようとする兵士。
だが、これで終わってくれればと、私が安堵した時だった。
「…こんなもんかよ…」
「なに…?」
顎に伝う血糊を肩で拭い、ヴァンは上体を起こして嘲笑うかのような表情でその兵士を見る。
「何迷ってやがる?そんなにオレが怖いのか?」
「怖いだと?ハッ、馬鹿な事を…」
「だったら、ロープを解いてその剣でオレを斬ればいい。殺した後での理由付けなんざ幾らでも出来るだろうが」
兵士の声色が変わったのを、私は見逃さなかった。
このままでは、ヴァンが殺される。
どうして?なんであえて挑発するような事を言うの?
だが、そんな気持ちさえ、言葉にして直接尋ねる事も出来ない。
「…何が言いたい?」
「一対一の剣の勝負でケリつけたって言やぁ箔も付くってもんだろうが。そんな程度の事にまで考えが及ばないって事ぁ、最初から弱腰になってんじゃねぇのかって聞いてんだよっ!」
「き、貴様ぁ…言わせておけばっ!!」
一度は戻しかけた剣を再び引き抜き、兵士は思い切りその刃を天高く掲げる。
「ならばいっその事…、思い通りにしてくれるわぁーーーーーーーーっ!!」
眼前に迫る白銀の刃。
その刹那、オレは思っていた。
これでいい…。
コイツがオレを殺し、その体を外に持ち出してくれれば、クリフのヤツが気付いてくれる筈だ…。
それで、ショウコの命は助かる…。
悪かったな、ショウコ。約束を守ってやれなくてさ…。
「死ねぇぇーーーーーーーーーーぃっ!!」
ヴァンの頭上へと振り下ろされる狂気の刃。
もう止められない。
ヴァンが死んでしまう。
そう思った時、私の中で何かが弾けた。
『ダメェェェェェェーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーッッッ!!!』
「っ!?」
地下全体が揺らぐほどの強烈な声が響き渡り、その声に驚いた兵士の剣が一瞬鈍る。
だが、彼等を襲ったのは、その声だけではなかった。
「ぬぉあっ!?!?」
兵士達を一瞬で薙ぎ払う一陣の突風。
凄まじい勢いで吹き荒れたそれは、しゃがみ込んでいたヴァン以外の兵士達全てを数メートルは吹き飛ばしていた。
「な、なんだっ!?」
驚きに目を丸くしていたのは、その突風に命を救われたヴァンだった。
彼が振り返ったそこに在ったのは、片膝を床に減り込ませ、右腕を振り払ったかのような体勢で動きを止めていた鎧甲機ヴァルシードの姿だった。
「冗談…だろ。コイツは…ヴァルシードは、千年王にしか扱えない筈じゃ…っ」
けど、誰よりも驚いていたのは、当の本人である私自身だった。
「…動い…た…?」
思わず振り払った自身の手を見詰め、ニギニギと力を込めて見る。
するとどうだろう。十数メートルはあろうかという巨体が、まるで自分の体のように指の細かな動きに至るまで反応しているではないか。
自由自在。というよりは、むしろ自然に馴染んでいる感触があった。
「これが、…鎧甲機…」
動かしてみて初めて解る。
この子は、私の事を知ってくれているんだ。
だから、理解してあげればいい。
そうすれば、この子はきっと、応えてくれる。
何故かそう思えた。
『ヴァン、今の内にっ!』
私は自分の手を差し出すように、ヴァルシードの手をヴァンの所へ下ろす。
だが、ヴァンはというと、未だ呆けた顔でコチラを見上げたまま、何かを呟いていた。
「…ショウコ…、お前が、本当に動かしてるのか…」
聞き取れないほど小さな声だった。だから私は、急かすように手の甲で地面を打ったのだ。
ズンッと沈み込む石畳。
その直ぐ脇で、ヴァンも飛び跳ねていた。
「おわっ!」
『早く乗って!』
「わ、わかったって!」
半ば強引にヴァンをその手に乗せた私は、ヴァルシードに心で尋ねてみる。
(ヴァルシード…。外に出られる…?)
ヴォン…ッ
その音は、この子の返事だったのだろうか。
ヴァンを抱えたヴァルシードの足元に奇妙な紋様が浮かび上がると、次の瞬間には光に包まれて空を舞っていた。
「え…、ウソ…?」
急に全身を襲う浮遊感。
飛んでいる…というよりは、落ちているといった表現の方が適切な状況。
私は無意識の内に悲鳴をあげていた。
「キャーーーーーーーーーーーーーーッ!!」
数百メートルはあっただろうか。
ジェットコースターに乗った事はなかったが、きっとこんな感じのスリルなんだろうと思う。
徐々に近付いて来る地面。
ジェットコースターとの違いは、このまま着地してしまう事だろう。
地面に叩き付けられる。そんな恐怖に駆られて忘れていた。
自分の体とヴァルシードの体との比率だ。
「あ…れ…?」
地面にぶつかる。…と、目を閉じかけた時には、もう着地してしまっていた。
案外衝撃もなく、すんなり降りられてしまった事に若干の驚きを感じる。
それで安心してしまった私は、一つ重要な事を忘れていた。
「シ、ショウコッ!お前、オレを殺す気かぁーーーーーーっ!?」
手に握ったままのヴァンは、生身だったって事。
『ゴ、ゴメン…』
そう言ってはみたものの、ヴァンには私の苦笑が見えていない。
コチラからは、彼の怒り顔が良く見てとれるのに…。
でも、今はそれに構っている場合じゃなかった。
「…助けなきゃ…っ」
ヴァンは私にとって大切な人。だけど、大切なのは、ヴァンだけじゃなかった。
私の事を快く受け入れ、優しく支えてくれた人達が、この街には沢山居る。
そんな人達が、何の罪もないのに惨たらしい蹂躙を受けている。
見過ごす事なんて出来ない。
見捨てる事なんて出来やしない。
『ヴァン…。私、行って来る』
キトラの街からは少し離れた山岳地帯。そこに着地した私は、ヴァンを地上に降ろしてそう告げた。
でも、ヴァンは怒ったような口調でそれを止めようとする。
「無茶言うな!いくら鎧甲機を操れるからって、いきなり戦って勝てるほど実戦は甘くない!」
わかってた。
でも、この街には、グランスレイの鎧甲機部隊に対抗出来る力がない事も知っていた。
だから、たとえ勝てなくても、みんなが非難出来るだけの時間が稼げれば十分。
『…ヴァンだって、私の為に命を捨てようとしてくれたもの…』
「なっ、それとコレとは話しが…っ」
解ってた。ヴァンがどうしてあんな無謀な事をしようとしたのか。
だから、私は彼の言葉が言い切られる前に背中を向けた。
「…同じだよ。私にだって、守りたい人達が出来たから…」
膝を屈め、飛び立とうとするヴァルシード。
それが、私の意志。
ヴァンにも生きて欲しかったから。
「ま、待てショウコッ!…ぶわっ」
ヴァルシードから放たれる不思議な衝撃。
それが体を持ち上げてくれて、ヴァンにもそれ以上の言葉を言わせないでくれた。
「…行くよ、ヴァルシードッ」
ジャンプすると同時に空を駆けるヴァルシード。
ヴァンの姿は直ぐに木々に隠れて見えなくなってしまったけど、それでよかった。
戦うって決めたんだ。
誰かを守ろうとする気持ちを、あの人に教えられたから。
だから、守る為に戦う。
どんなに非力でも、脆弱でも、気持ちが大事なんだって思えるようになったから。
「馬鹿だっての…クソッ」
飛び立つヴァルシードの背を見上げ、オレは悔しさに地面を殴り付けた。
「生きて帰って来いよ…。絶対、死ぬんじゃないぞ、…ショウコォーーーーーーーーーーーーーーッッ!!」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- うろ覚えに漫画を紹介するぜ
- (2024-09-22 03:52:28)
-
-
-

- 読書日記
- 書評【 化粧品を使わず美肌になる! …
- (2024-09-29 00:00:22)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- 太陽と月の邂逅 ハプスブルク夢譚 …
- (2024-08-27 12:00:52)
-
© Rakuten Group, Inc.