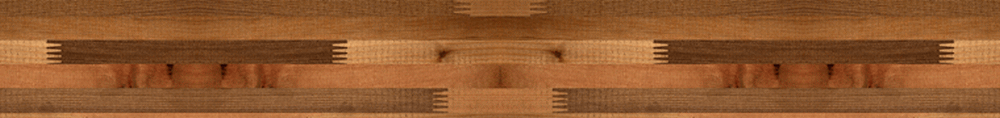ジャックと豆の木
足取りが重いのには、二つ理由があった。
一つは、牝牛の歩みがのろいのと、もう一つは、子牛の頃より共に育った、牝牛との別れが辛かったからだ。
牝牛は、少年とその母親の二人きりの家計の糧となっていた。
しかし、乳の出なくなった老牛はもうその役割を果たせない。
母親は少年に、牝牛を市場で売ってくることを命じた。
「いいかい、ジャック、よくお聞き。必ず1000ゴールド以上で売るんだよ。ほんとはそんなに高くは売れないけど、お前を不憫に思って買ってくれるお客がきっといるからね。それから、はじめから1000ゴールドといってはダメだよ。2000ゴールドとお言い。お客は必ず値切るから、はじめは高く言うもんだ。わかったね!」
子供ごころにも、この指令はかなり難易度の高いものだと感じた。
市場までの道程は、果てしなく長いものに変わっていった。
朝早く出たはずが、もう陽が傾きかけている。
このままじゃ、どこかで野宿するようだなと思い始めたとき、道端の岩に腰掛けている老人が目に映った。
灰色のガウンに身を包み、身の丈より長い杖を携えている。
声をかけられなければいいなと思いながら、傍を通りすぎようとしたら、案の定しわがれた声がジャックを呼び止めた。
「おい、子供。どこへ行く」
“子供”と呼ばれて、ちょっとムッとした。
ジャックは子供と呼ばれるほどは幼くない。
「ひゃっひゃっひゃっ、言わんでいい。市場へ行くのじゃろ。その老いぼれ牛を売りに」
―解ってるなら聞くなよ―
ジャックは、不愉快なのと、気味が悪いのと、少し怖いのとで、無視してさっさと行きすぎようとした。
「これこれ、待ちなさい。今から行っても市場はしまっておるぞ」
―その通りだけど、関係ないだろ―
「どうじゃ、その牛、わしが買ってもいいぞ」
「えっ?」
ジャックは改めて老人を見た。
ガウンは思いのほか埃がかっていた。
灰色に見えるが、本当は黒かったかもしれない。
妙に見開いた左目と、大きく曲がった鼻が不気味で、その口から歯が3本ほど欠けているのが見て取れた。
「ひゃっひゃっひゃっ、気味の悪い年寄りだと思っとるな。それも間違いではないが、大事なことを教えよう。わしは魔法使いなのじゃ」
「魔法使いだって?」
「そうよ。魔法を使って、人間にいたずら―じゃなかった、困っている人間を助けとるのじゃ」
「聞いたことがあるような気がする。たしか、母さんが…」
「そうじゃろそうじゃろ。で、いくらで売るのじゃ、その乳の出ない役立たずの牝牛」
「せん…じゃなかった、2000ゴールド」
「2000ゴールド?そりゃまたずいぶん高いな」
「だったら、1000ゴールドに負けてあげるよ、特別だよ」
「ひゃっひゃっひゃっ、1000ゴールドでも高すぎるぞ。まあ良い。いくらでも払ってやるぞ、ほれ!」
老人は小さな布の袋を差し出した。
思わず受け取ったが、その袋はとても軽く、1000ゴールドの感触には程遠かった。
戸惑うジャックの様子を見て、それまでにこやかだった老人の表情が急に険しくなった。
「よく聞けよ。この袋の中には、魔法の種が入っておる。その種を蒔けば、たちどころに天に昇る木が生える。後はその木を登って天に行けばよい。お前の望むだけの金貨がそこにある。すきなだけもっていけばいい。母親もきっと喜ぶだろう」
厳しく見据えた目でそう言うと、また柔和な面立ちに戻った。
「おっと、言い忘れたが、巨人には気をつけろよ」
「巨人?何ですか巨人って―」
「うひゃっひゃっひゃっひゃっ…」
奇妙な笑い声を残して、老人は煙と共に消えてしまった。
呆然と立ち尽くすジャックが、我に帰って振り向くと、そこに牝牛の姿はなかった。
あわてて手の中の袋を開けると、老人の行った通り、小さな種が五粒埋もれるように入っていた。
ジャックには、とにかく現実を受け止めるしか、選ぶ道はなくなっていた。
家路に向かうジャックの足取りは軽いものではなかった。
すでに陽はとっぷり暮れている。
頭の中で、今日起こったことを必死に反芻していた。
母親に納得の行く説明をするためだ。
問題は、自分の言うことを果たして信じてもらえるかということだ。
魔法使いが言ったこと。
判らない。
でも、信じてもらえることにした。
そうしないと、家に入れない。
ジャックは勇気を振り起して、きわめて快活に、家の扉を開けた。
「母さん、ただ今!」
「ジャックかい。遅かったねえ。どうだった。売れたのかい」
「うん。売れたよ、母さん」
「えっ、売れたのかい。そうかい、おまえは商売の才覚があるかもね。で、いくらで売れたんだい?」
「う~ん、1000ゴールド。でもいくらでもいいって…」
「1000ゴールド!でかしたねえ。まさか、あの牛が1000ゴールドだなんて、ほんとにいい商売人になるかもしれ…、いくらでもいいって、どういうことだい」
「実はね―」
ジャックはポケットから小袋を出した。
笑顔を絶やさないようにして、大きく息を吸ってから、今日の出来事の説明を一気呵成にした。
話が進むにつれ、母親の眉が、段階を踏んで険しくなり、そのたびにジャックのほほがひきつっていった。
「ね、すっ、すごいでしょ。あした、僕が天に行って、摂ってくるよ、待っててよ」
母親は、ジャックの手から小袋を引ったくり、中を覗き込んだ。
唇がわなわなと震えている。
「母さん、ゴメンよー。でも大丈夫だよ。きっと。僕、騙されてないよ。明日になれば―」
母親は、勢いよく窓をあけ、思いっきり小袋を外へ投げ出した。
あっと口を開けて驚くジャックの髪の毛を掴み上げ、
「この、能無しの馬鹿息子!」
と怒鳴った。
「騙されてないだと!魔法使いってのは、ろくなもんじゃないんだっていつもいってるだろ。お前の父さんも爺さんも、みんな騙されて、我が家はこんなに落ちぶれちまったんだ。大事な牛を豆粒と交換して1000ゴールドだと!この大馬鹿野郎!どうしてくれるんだい。うちにはもう何にもないんだぞ!」
そういえば小さい頃、魔法使いに騙された話を聞いたことがあった。
「だから、明日になれば…」
「明日だと!今行って来い!いま、いんちき魔法使いを探して牛を取り返して来い!」
髪の毛を掴んだまま、ドアまで引きずり、そのままジャックを外へ放り出した。
「牛を取り戻すまで帰ってくるな!」
今まで聞いた事のないような激しい音で、ドアは閉められた。
魔法使いの話は信じてもらえたようだが、こんな展開になるとは想像してなかった。
暗闇の中で、泣いているうちに眠ってしまった。
目覚めたときは、朝だった。
騙された自分が招いたことだ、とにかく魔法使いを探しに行こう。
ようやくそう決心をして、立ち上がったとき、朝もやの中に不思議な、緑色のロープのようなものがみえる。
地面から立ち上がり、空高く雲の中につながっている。
近くによって見ると、豆のつるが束になって連なっていた。
魔法使いの言った通りだった。
「母さん!母さん!母さん!見てよ!本当だったんだよ!本当に天まで繋がってるよ!」
ジャックの大騒ぎに、目をこすりながら母親が家から出てきた。
「母さん、僕、行ってみるよ。魔法使いの言ったことが本当なら、あの雲の上に1000ゴールドがあるんだ」
母親は、何度か頷き、
「ジャック、気をつけておゆき。下を見ちゃいけないよ」
「うん、待っててね。僕、木登りは得意なんだ」
ジャックは勢いよく登り始めた。
昨夜のどん底状態から、一転して上昇気分に包まれた。
こんなにワクワクしたのは初めてかもしれない。
一手一足登るごとに、自身の未来や希望が広がっていく感覚があった。
何時間も掛かったはずなのに、無我夢中だったので、あっという間にたどり着いた。
雲の上に立つと、美しいハープの音が聞こえる。
音のする方向に、ちいさなやしろが見える。
ジャックは、そこが間違いなく目的地だとわかった。
走っていって中を覗くと、まばゆいばかりの金貨が溢れている。
金貨の山の上のほうを見ると、黄金に輝くハープがあり、ハープが音を奏でると、音が金貨に変わって落ちてくるのだった。
ハープの音色も、金貨の輝きも素晴らしいものだった。
ジャックは夢見心地で呆然としていたが、我に帰って足元の金貨を拾い集めた。
―10ゴールド金貨だから、1000ゴールドは100枚か。でもいくらでもいいって言ってたから、ずるして2000ゴールドもってっちゃお。母さん喜ぶぞ」
ポケットにぎっしり金貨を詰め込んで、天にも昇る気持ちとはこのことかと感動を噛み締めた。
そして、さあ戻ろうとして下を覗いたとき、ジャックは背筋が凍る思いがした。
母さんが、下を見ちゃダメだといった意味が今わかった。
自分の居るところが、どんなところか忘れていた。
小さく見える家や木を見て、あまりの怖さに足が震えた。
でも、戻らねばならない。
登ってくるときは、上ばかり見ていたので全く気がつかなかった。
そういえば、風も吹いていたが、さっきより強くなっている気がする。
金貨をポケットに詰め込んだぶん、重たいし動きにくい。
でも、そんなことを言っていてもしょうがない。
意を決したジャックは、生涯一番の勇気を振り絞って降り始めた。
その頃、豆の木のふもとでは異変が起きていた。
突然現れた天に続く豆の木を見つけて、村人が何事かと集まってきたのだ。
心配そうに空を見上げている母親に、村人が声をかけた。
「いったい何なんだい。この木は」
「いいえ、何でもありません。なんでもないから、どうぞお引取り下さい」
「なんでもないわけないだろ。こんなもんはじめて見た。誰か登ってんかい」
「いいえ、誰も登ってなんか居ません。雲の上には何にもありません。お願いですから、皆さん帰ってください」
母親の態度に、村人達がいぶかしんでいると、空からきらきら光るものが降ってきた。
地面に落ちたそのものを見ると、金貨ではないか。
ジャックのポケットから零れ落ちた一枚だった。
「なんで、空から金貨が…」
「あれっ、あそこに人がいるぞ。もしかして、ありゃジャックでないか?」
村人が見上げた先には、てんとう虫のように小さく見えるジャックの姿があった。
途中まで降りたものの、疲れと寒さで足がすくんで動けなくなったジャックの耳に、かすかに人の声が届いた。
「がんばれージャック」
誰かが僕を応援している。
それも一人じゃない。
大勢の声だ。
下が見れないジャックは、とにかくその声を励みにして、又、一歩一歩降り始めた。
小一時間ほどそれが続き、疲労困憊ようやく地上に戻った。
「母さん、母さん、僕、行ってきたよ、ほら、金貨がこんなに―」
ポケットから金貨を出して見せると、村人から歓声が上がった。
「ジャック!どうしたんだこれは!金貨があるのか、雲の上に!」
「うん、たくさんの金貨が降ってくるんだ」
あわてて口をふさごうとした母親だったが、遅かった。
ジャックの言葉を聞くが早いか、村人が次々豆の木を登りだした。
「あ~だめだよ、皆さん、雲の上にはなんにもありませんよ~。この子はちょっと頭がおかしいんです~」
村人はそんな声にはかまわず、次々と上っていく。
「あ~ばかだねこの子は。みんなに盗られちまうじゃないか」
「大丈夫だよ母さん、金貨はすんごくあるから。それに、金色に輝くハープが、次々と金貨を降らしてるんだ」
「金色に輝くハープだって?」
「そうだよ、金貨も降らすけど、いい音も出すんだ。金貨はその音に合わせて、踊るように降り注ぐんだ」
「ジャック!それは、爺ちゃんが言っていた魔法のハープだよ!悪い魔法使いに騙されて盗られちゃった我が家の家宝だ」
「え~、うちにあったの?」
「そうだよ。確かに爺ちゃんに聞いた。そんなところにあったとは…。ジャック!もう一度上って行って、魔法のハープを取り返しておいで!」
「え~!!もう一度登るの~?」
「あたりまえだろ、うちの宝なんだよ。あのばかどもに横取りされちまうじゃないか」
「だって、母さん、僕もうくたくただよ。それに登るのはいいけど、降りるときはめちゃくちゃ怖いんだ」
「ジャック!いくら怖いって、今の母さんより怖いものはないはずだよ!」
ぐっと近づけてきた母親の顔は、言葉通り怖かった。
すると、一転、にっこり微笑んで、
「おまえが頼りなんだから。母さんにはお前しか居ないんだよ。おねがいだよ~」
猫なで声で頼んできた。
と思ったら急に、
「お~いおいおい…たった一人のかけがえのない母さんが、こんなに頼んでも、おまえって子は…こんな恩知らずだったなんて…」
今度は泣き落としに来た。
「わかったよ母さん。僕行くよ。がんばるよ」
泣き伏せていた母親が、にっこり笑ってジャックを抱きしめた。
「いい子だ。おまえは、やっぱりいい子。私の子。がんばって来るんだよ―」
ジャックは大きく頷いて、颯爽と登り始めた。
雲の上は大騒ぎだった。
村人が、手に手に金貨をつかみ、よだれを流して喜んでいる。
その歓声の渦の中に、ジャックはようやくたどり着いた。
と、なんとひとりの村人が、金貨の山を登り、金色に輝く魔法のハープに、手をかけようとしているではないか。
「あっ、ダメだ、さわるな~」
と言おうとしたら、
「やめて~たすけて~」
それはすさまじい金切り声が、四方に響き渡った。
声の主は、金色に輝くハープ自身だった。
手にかけようとした村人は、驚いて金貨の山を転がり落ちた。
同時に、なんとハープも転がり落ち、ころころ転がって、ジャックの足元で止まった。
ジャックとハープは目があった。
すると、今度は地の底から響くような太い大声が、あたりに響き渡った。
「だ~れだ~!だ~れが、そこに、いるのだ~」
ほこらの奥の大きな扉が、地鳴りと共に開き、そこに身の丈十倍ほどの巨人が立っていた。
村人は、恐怖に目を見開き、悲鳴を上げて逃げ始めた。
「こら~!まてい~!」
待て、と言われると、人はますます逃げ足が速くなり、一斉にもと来た豆の木にしがみついた。
そこで、村人は、ジャックがそうであったように、あまりの高さに怯え、立ちすくんだ。
が、今度は後ろからどんどん人が押してくる。
押された村人は、豆の木に掴まることも出来ず、つぎつぎ空中へ投げ出されていった。
投げ出された人々は手足をばたつかせたが、急に鳥のように飛べるようになるはずもなく、地上に向かって、かき集めた金貨と共に、ひらひらと落ちていった。
ジャックは一人、逃げ出さずに立ち止まっていた。
勇気があったわけではない、ただ逃げ遅れたのだ。
「だ~れだ~おまえは~」
巨人はジャックに向かって言った。
「ジ、ジャック、―ジャックです」
「なぜ、ここに、いる~」
「あっ、あの木を登って来たら、ここに来ました―」
巨人は雲をつきぬけそそり立つまめの木を見た。
「こんな、わるさを、しおって―。よからぬまほうつかいの、しわざだろうー」
「あの、僕は、魔法使いに、牛を売って、その代金を、取りに来ました。そして、貰いました、金貨を。だから、それは、牛の代金だから、いいはずですけど―」
巨人は長く垂れ下がった前髪の奥の目で、ぎろりとジャックを見た。
「そんな、うしのことは、しらん。このきんかは、まほうつかいのものではない。きんかをかってにもっていたのなら、かえしなさい」
「え~、だって、魔法使いが……。それに、このハープは、もともと、うちのものだって、うちの家宝だったんだって…」
「かほう?だれが、そんなことを」
「僕の母さんです」
「それも、ちがうな。このはーぷは、わしのものだ。むかし、いっときだけ、まほうつかいにぬすまれたことがあったが、おどかしてとりもどした。そのとき、なにかおもいちがいをしたのだろう」
「でも、母さんが…、どうしよう…」
「きんかは、はーぷがかってにだすもので、わしには、なんのかちもない。―ここまで、のぼってきた、おまえのゆうきにめんじて、くれてやる。―だが、はーぷは、だめだ。きんかをだすはーぷが、ちじょうにあったら、どんなことになるか。さっき、おちていった、ものどもをみればわかるだろう。よくふかき、にんげんには、わたせない。―これは、おまえを、しあわせにはしない―」
巨人の言うことは、真実味があり、騙したのは、魔法使いの方だとジャックにも解った。
だけど、ジャックは、目の前のハープをどうやって持って帰るかしか頭になかった。
「お願いです。このハープを、母さんに見せたいんです。一目見せたら、必ずまた持ってきます。だから、少しの間、貸してください」
巨人は、すこし黙っていた。
お願いです、お願いです、両手を合わせ、目をぎゅっとつぶり、ジャックは祈った。
「ははおやに、みせたら、すぐもどすのか―」
「はい、一目母さんに見せて、僕が嘘をついてないって解ってもらったら、今の説明をして、返します」
「ははおやが、かえさないといったら?」
「僕が、母さんを説得して、ちゃんと返します」
自信はなかった。
「それなら、できるかどうか、やってみるがいい。にんげんが、よくにかてるか、どうか、みてやろう」
ジャックの目が輝いた。
ハープを背中にくくりつけ、母の待つ地上へ向かう。
今度は二度目だから、怖さも半減している。
頭の中で、母親に言う台詞を考えていた。
このハープは、天に住む巨人のもので、我が家の家宝ではない。
たまたま何かの都合で、我が家にあったのかもしれないが、それは、魔法使いが巨人を騙して盗ったもので、結局その魔法使いは巨人に返した、我が家の家宝は、魔法使いに騙されたのではなく、返したのだと。
説明の段取りを考えてみたが、あの母親がそれで納得するとは思えない。
かといって、ハープを持って帰らなかったら、さらなる悲劇がジャックを襲うはずだ。
やはり、ここまでの行動は、間違っていないと信じよう。
あれこれ考えていると、ハープが不意に話しかけた。
「お前の家の家宝だったってのは、うそだな」
「えっ?何でそういえるの?」
「おいらが居たのは、王様のお城だ。お前の爺さんは、その家来だ。誰かが、話しを作り変えたんだな」
言われてみると、ジャックのお爺さんが王様だったなんて話は聞いたことがない。
王様でもないのに、魔法のハープを持っているのはやっぱり変だ。
母さんは、騙されてたか。
それとも、母さんはそれを知ってて、僕に嘘をついたのか。
「それから、言っとくけど、おいら地上では金貨をだせないからね。天上だと気持ちよく音が金貨に変わるけど、地上だと人間の欲が邪気を出すから金貨にならないんだ」
あ~又説明しなくちゃならないことが増えてしまった。
「それと、巨人がさっき、おいらは巨人の物だって言ってただろ。あれも、ちょっと違うんだな」
「えっ?どういうこと?」
「おいらを作ったのは、魔法使いで、欲がない人間の前では金貨を出すように魔法をかけたんだ。だけどそんな人間は居なかった。おいらは純粋に音楽を奏でたいんだけど、欲に駆られた人間に試されてばかりで、うんざりしてるところを、あの巨人が助けてくれたんだ。天上に行ったらあんなふうに好きなだけ奏でられたから、おいらにはよかったけどね」
ジャックの頭はこんがらがってきた。
結論が出ないまま、ジャックは地上にたどり着いた。
母親の怒り狂う姿が、脳裏に映っていたが、そこには、ジャックが初めて見る母親の姿があった。
なんと、あの母親の目から、ぼろぼろと涙が零れ落ちているではないか。
「おおジャック。よく戻ってくれたねえ。空からたくさん人が落ちてきたよ。母さんが悪かった。怖い思いをさせてしまって」
自分の生還を、涙を流して喜んでくれる母親に、ジャックは戸惑いもあったが、今まで感じたことのない喜びを味わった。
「母さん、僕ね―」
ジャックの声がつまり、言葉が続かなくなった。
すると、聞き覚えのあるしわがれた声が、
「ほほう、魔法のハープを盗んで来たのか。見かけによらずたいした奴じゃ」
魔法使いだった。
「違うよ、盗んだんじゃない。巨人に借りたんだ。母さんに見せるため」
今、涙を流して自分を抱きしめている母親が、魔法のハープと聞いてどう反応するか不安がよぎった。
しかし、あんな嘘までついて、ジャックに危険な思いをさせた母親が、意外にも興味を示さない。
「おい、どうした。お前が欲しがっていた、金貨を出す魔法のハープじゃぞ」
「ジャックごめんよ。母さんが悪かったよ。ハープなんて要らない。お前が無事に帰ってきてくれれば。欲に駆られて、自分をなくしていた母さん恥ずかしいよ」
「母さん、僕こそゴメンよ。母さんのこと、ちょっと信じてなかった」
魔法使いは二人の様子を見て頷いた。
それから、長い杖を空に向かってまわし、呪文を唱えた。
ハープに閃光が走り、それが豆の木に伝わり、共に消えた。
豆の木が消えると、あちこちで人の声が聞こえた。
空から落ちた村人が、頭を振り振り起き上がった。
「村人は何も覚えていない。今日のことはお前達親子の秘密にしておけ。ちょっといたずらが過ぎたかも知れんので、お詫びに贈り物じゃ」
魔法使いが杖を振った先に、牝牛が立っていた。
昨日売ろうとした老いた牛ではなく、若い、これから何年も乳の出る牝牛が。
驚くジャックが、我に帰ってお礼を言おうとしたときには、すでに魔法使いの姿はなかった。
© Rakuten Group, Inc.