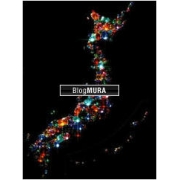PR
Keyword Search
 New!
Pearunさん
New!
PearunさんMちゃんママから長… New! flamenco22さん
^-^◆ 学びの宝庫・…
 New!
和活喜さん
New!
和活喜さんWリーグトヨタ紡織チ…
 クラッチハニーさん
クラッチハニーさん風に向かって クリス…
 千菊丸2151さん
千菊丸2151さんComments
Freepage List
Calendar
![]()
![]()
![]()
「河井継之助の没後」
(二)
山本帯刀が斬首された日が、慶応四年九月八日である。
この日をもって明治元年と改元された。こうしてみると惜しい人物を
なくしたもの思われる。
孤軍奮闘した会津が、若松城を開城降伏した日が九月二十二日である。
長岡藩主の牧野忠訓は、若松城の切迫する状況により、八月二十三日、
建福寺から城北の小荒井に移り、各地の長岡藩兵を召集し、翌、二十四日
に集まった藩兵二百名を会津の援軍として赴かせた。
この後、忠訓は藩士の家族、婦女子、幼童など二千名を率い、八月二十六
日、会津より米沢に移った。会津で転戦していた長岡藩兵も、おいおい米沢に
退いたが、米沢藩が降伏におよび、九月十二日に米沢を発ち、山形、基石を
経て十四日に仙台城下に達し、隠居の雪堂と忠訓は北山の光明寺に入った。
藩士と家族、領民等は本吉(もとよし)、東山、登来(とめ)の三郡に別れて
宿泊したが、会津藩の降伏を知り二十五日、奥州追討平潟総督の本営に降伏
書を提出した。新政府は十月十三日、藩主忠訓に対し東京に至って謹慎し裁
きを待つように命令を下し、隠居の雪堂と家臣一同は、藩地である長岡に戻
り、そこで謹慎するよう、お達しがでた。
こうして長岡藩諸隊と家族、領民等は河井家の姻戚の森源三が引率し、
折からの豪雪をいとわず百里の悪路を辿り、藩地へと帰投することとなった。
彼等の行く手には酷寒と飢餓が待ち受け、未知で困難な旅が始まった。
こうして立ち戻った墳墓の地は、戦火で荒廃し折からの豪雪で悲惨極まる
光景が現出していた。
記録によれば、城下の士族、卒族の戸数は一七〇七軒あったと云うが、
このうち焼失したもの、一〇一四軒に及んでいたと云う。
また町屋の焼失は一四九七軒、近郊の農家は一〇八二軒にもおよび、惨憺
たる有様であった。
それに折からの積雪で、雪は平均、七尺余りも積った一面の雪景色であっ
た。この情景を藩士婦人の小金井きみ子は、次ぎのように詠んでいる。
「立ちかえり 雪ふるさとを 来て見れば 今朝、白妙(しろたえ)に 埋もれけり
庭やいずこ まがきやいづち 家居(いえい)さえ 唯(ただ)しら雪の つもるのみ
にて」 こうした長岡の状況を長岡の本富栗林は、会津藩の悲劇と比べ、
このように述べている。
「世人戊辰の事を言う者、かならず会津を説く。曰(いわ)く白虎隊なり、曰く
娘子軍なり、その事、その人と共に、壮は即ち壮なりといえども、死は易くして、
生の更に難きものあり、この歳五月、戦始まるや、白刃を堤げて弾雨の下に
立ち、もとより父子あい顧るの暇なく、いわんや兄弟妻子をや。
各々ただ力を尽くして戦うあるのみ。故に弾丸黒子(こくし)の小城をもって、
西国雄藩の大兵に抗し、いったん敵手に委ねたる城塞は、再びこれを回復し、
その破るるに及んでは遠く去って会津に会し、会津また敗るるや去って米沢に
入る。米沢すでに降る。即ち去って仙台に至れば、仙台もまた既に降伏せり。
敗残の兵をもって百里を流離す。或は老若病弱を扶助し、飢寒を冒(おか)し、
困苦を忍びの状、今日とうてい想像の及ばざるものあり。ことに婦女子の身を
もって、難を未知の山中に避け、幾度か死生の間に出入して、わづかに其の
夫の残骸を求め得たるがごとき、惨事は一にして止まらず。これを会津藩が、
君臣、親子、一城にこもり、流転曝露(るてんばくろ)の苦もなく、ただ坐(い)
ながらにして暫時、囲みを受けたるに比すれば、わが藩士が君臣、父子、夫
婦、兄弟みなあい失し、半歳のあいだ山野に曝露し、百里に流寓したるの苦
は、もとより同日の論にあらず。今日これを想うも、じつに慄然たらしめるもの
あり、ああ三河武士の後裔は、かくの如くに終われりといえども、いわゆる武士
の意気、千歳のもと懦夫をして起たしむるものなからずやは」
「山本五十六伝」
続きます。