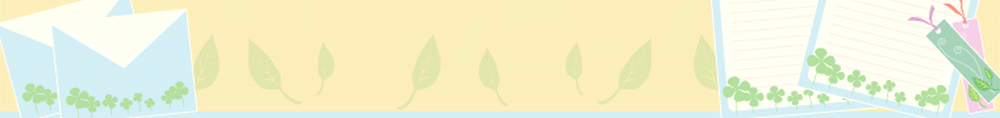PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
コメント新着
テーマ: さだまさしさん(107)
カテゴリ: さだまさし
さだまさしさんの音楽、その49は「修二会」
ちょっと時期がずれてしまいましたが、まあ同じ3月ということで。
この曲は、アルバムに収録されているものと、コンサートで演奏されるもので、アレンジが全く異なります。正直アルバムに収録されているものは、あまり印象に残らないものでした。さださんも「消化不良」ってどこかで言っていたことがあるような...でもコンサートで演奏されるこの曲は、迫力、訴える力ともに、すごくしっかりしたものがあります。パーカッションがしっかりしているからこそ、なんでしょうね。
『春寒の弥生三月花まだき
君の肩にはらり 良弁椿
ここは東大寺 足早にゆく人垣の
誰となく独白く南無観世音 折から名残り雪』
修二会(お水取り)は、東大寺の二月堂を中心に、2月中旬から様々な行が開始されます。一般には、3月に入ってから12日の「お水取り」の神事を指すことが多いようです。先日の日記にも書きましたが、この時期、関西は寒さがぶり返します。今年もそうでしたが、12日前後は雪がちらつくことも多いです。
『もはや二月堂 天も焦げよと松明の
松明(おたいまつ)は、3月1日から14日に二月堂で行われる行法です。通常の日は、午後7時に「おたいまつ」が点火され、1本に1名の練行衆がついて二月堂本堂に上堂されます。5-7日と12-14日は「走りの行法」というものが行われます。二月堂からおたいまつが降られるという、有名なシーンですね。また12日は午後7時30分から、14日は午後6時30分から「しりつけタイマツ」といって立て続けに10本の松明があがります。特に12日は「篭たいまつ」が使用されますので、一番勇壮に見えます。また12日深夜に、お水取りの儀式も行われます。TVで放映されるのは、たいがいこの12日の「篭たいまつ」による「走りの行」です。
『過去帳に 青衣の女人の名を聴けば』
青衣の女人は、鎌倉時代に過去帳を読み上げているところへ青い衣をまとった女性が現れ「なぜ私の名前を読まない」と恨めしそうにいうので、とっさに「青衣の女人」と読み上げたところ、すうと消えていったといういいつたえに基づいたものです。今でも過去帳に青衣の女人の名はのっています。(少し小さい声で、早口で読み上げるそうです)この過去帳の読み上げは5日と12日にあります。
『ここは女人結界 君は格子の外に居り
息を殺して聴く南無観世音 こもりの僧の沓の音』
これらの行はすべて「女人禁制」で行われます。例え子供であっても、籠堂の女人結界を越えることは、許されません。
『水よ清めよ 火よ焼き払えよ この罪この業』
穢れを、水で清め、火で焼き払う。壮絶な行法が「修二会」です。12日の「走りの行」は、すごい人出で、「きれいだなあ」と思う余裕もありません。二月堂の前って、そんなに広くないですし、下手すると(例えば今年のように、土曜日に重なるなど)木々の上に微かに炎を眺めることが出来るだけという状況になります。
本来のお水取りの神事や、五体投地、達陀などの行法は、夜間に行われますので、私も参詣したことはありません。が、そこにこそ修二会のすべてが、現れているのかも知れません。さださんの描く、修二会の世界。一度体験してみたいものです。
ちょっと時期がずれてしまいましたが、まあ同じ3月ということで。
この曲は、アルバムに収録されているものと、コンサートで演奏されるもので、アレンジが全く異なります。正直アルバムに収録されているものは、あまり印象に残らないものでした。さださんも「消化不良」ってどこかで言っていたことがあるような...でもコンサートで演奏されるこの曲は、迫力、訴える力ともに、すごくしっかりしたものがあります。パーカッションがしっかりしているからこそ、なんでしょうね。
『春寒の弥生三月花まだき
君の肩にはらり 良弁椿
ここは東大寺 足早にゆく人垣の
誰となく独白く南無観世音 折から名残り雪』
修二会(お水取り)は、東大寺の二月堂を中心に、2月中旬から様々な行が開始されます。一般には、3月に入ってから12日の「お水取り」の神事を指すことが多いようです。先日の日記にも書きましたが、この時期、関西は寒さがぶり返します。今年もそうでしたが、12日前後は雪がちらつくことも多いです。
『もはや二月堂 天も焦げよと松明の
松明(おたいまつ)は、3月1日から14日に二月堂で行われる行法です。通常の日は、午後7時に「おたいまつ」が点火され、1本に1名の練行衆がついて二月堂本堂に上堂されます。5-7日と12-14日は「走りの行法」というものが行われます。二月堂からおたいまつが降られるという、有名なシーンですね。また12日は午後7時30分から、14日は午後6時30分から「しりつけタイマツ」といって立て続けに10本の松明があがります。特に12日は「篭たいまつ」が使用されますので、一番勇壮に見えます。また12日深夜に、お水取りの儀式も行われます。TVで放映されるのは、たいがいこの12日の「篭たいまつ」による「走りの行」です。
『過去帳に 青衣の女人の名を聴けば』
青衣の女人は、鎌倉時代に過去帳を読み上げているところへ青い衣をまとった女性が現れ「なぜ私の名前を読まない」と恨めしそうにいうので、とっさに「青衣の女人」と読み上げたところ、すうと消えていったといういいつたえに基づいたものです。今でも過去帳に青衣の女人の名はのっています。(少し小さい声で、早口で読み上げるそうです)この過去帳の読み上げは5日と12日にあります。
『ここは女人結界 君は格子の外に居り
息を殺して聴く南無観世音 こもりの僧の沓の音』
これらの行はすべて「女人禁制」で行われます。例え子供であっても、籠堂の女人結界を越えることは、許されません。
『水よ清めよ 火よ焼き払えよ この罪この業』
穢れを、水で清め、火で焼き払う。壮絶な行法が「修二会」です。12日の「走りの行」は、すごい人出で、「きれいだなあ」と思う余裕もありません。二月堂の前って、そんなに広くないですし、下手すると(例えば今年のように、土曜日に重なるなど)木々の上に微かに炎を眺めることが出来るだけという状況になります。
本来のお水取りの神事や、五体投地、達陀などの行法は、夜間に行われますので、私も参詣したことはありません。が、そこにこそ修二会のすべてが、現れているのかも知れません。さださんの描く、修二会の世界。一度体験してみたいものです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.