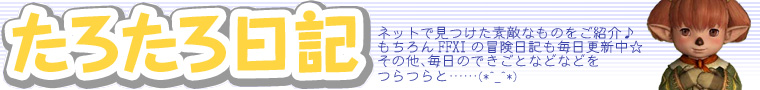PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
マリアと元黒騎士部隊の男たちは次々と問題を起こしまくる⁉️
救命団団長に転身を遂げたローズの壮絶な過去⁉️
このままでは静かなセカンドライフ計画が詰んでしまいます⁉️
マーリンとの模擬戦が噂になり学院内にいられなくなってしまう⁉️
遂に世界の壁を超え、リゼルの“一番大切な人”が登場⁉️
半グレの手先・信に誘拐された零花と無事、再会を果たした哲雄⁉️
前人未踏の第98階層へと潜った「夜蜻蛉」のパーティメンバーたち⁉️
異世界召喚されたバナザは存在を隠すためフリオと名前を変え⁉️
学年トップ3のリアーナからパーティに誘われたウィルは⁉️
天才勇者・クルスや、博識の剣士・ルカとともに、村の平和を護れ⁉️
救命団団長に転身を遂げたローズの壮絶な過去⁉️
このままでは静かなセカンドライフ計画が詰んでしまいます⁉️
マーリンとの模擬戦が噂になり学院内にいられなくなってしまう⁉️
遂に世界の壁を超え、リゼルの“一番大切な人”が登場⁉️
半グレの手先・信に誘拐された零花と無事、再会を果たした哲雄⁉️
前人未踏の第98階層へと潜った「夜蜻蛉」のパーティメンバーたち⁉️
異世界召喚されたバナザは存在を隠すためフリオと名前を変え⁉️
学年トップ3のリアーナからパーティに誘われたウィルは⁉️
天才勇者・クルスや、博識の剣士・ルカとともに、村の平和を護れ⁉️
コメント新着
パナソニック 電子レ…
 Leppardさん
Leppardさん
Pink-topaz Kilala-topazさん
Dreaming in Vana'di… ミスティ☆さん
Zenetekia@FF11 ゼネさん
魔戦士? OzwanのFF11… Ozwanさん
下手な考え休むに… … BergKatseさん
リントパ リンたん♪さん
ヤマトタケルの旅日… Takelさん
お気楽ヴァナ日記 Nekopiさん
オキバハウスR おきばさん
 Leppardさん
LeppardさんPink-topaz Kilala-topazさん
Dreaming in Vana'di… ミスティ☆さん
Zenetekia@FF11 ゼネさん
魔戦士? OzwanのFF11… Ozwanさん
下手な考え休むに… … BergKatseさん
リントパ リンたん♪さん
ヤマトタケルの旅日… Takelさん
お気楽ヴァナ日記 Nekopiさん
オキバハウスR おきばさん
サイド自由欄
設定されていません。
テーマ: 暮らしを楽しむ(400585)
カテゴリ: フード&ドリンク
男たちの大和、イイ曲ね~♪
長渕さんの曲も聴いてるウチに
「まぁ、いいかな」ってw
これ、曲作る前の言葉らしいの
先に曲聴いちゃったですけど、なるほど~って思ったです☆
いやいやいやいや
歌はやっぱり、稲葉さん最高です~♪
浮気はしないぉ (*^-^*)
あ、そうそう
セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ
全部そらで言えたですか?
普段はスズナ、スズシロくらいしか食べないよね(^_^;)
一応今夜は
それらしいのつくって食べたですよ~☆

春の七草がゆ
冬季限定商品(12月~3月)
いつでも、お手軽に七草がゆを
お召し上がりいただけます
価格 3,150円 (税込) 送料込
長渕さんの曲も聴いてるウチに
「まぁ、いいかな」ってw
これ、曲作る前の言葉らしいの
先に曲聴いちゃったですけど、なるほど~って思ったです☆
『男たちの大和 / YAMATO』主題歌を長渕剛が - 株式会社 角川春樹事務所
長渕「この大和に立って、悲しくもたまらない気持ちになった。多くの犠牲の上で今の豊かな日本があることを実感しました。戦争という舞台を借りて、壮大な愛を描く映画だと思います。今までの自分にない最高の曲を作りたい」
いやいやいやいや
歌はやっぱり、稲葉さん最高です~♪
浮気はしないぉ (*^-^*)
あ、そうそう
セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ
全部そらで言えたですか?
普段はスズナ、スズシロくらいしか食べないよね(^_^;)
一応今夜は
それらしいのつくって食べたですよ~☆

春の七草がゆ
冬季限定商品(12月~3月)
いつでも、お手軽に七草がゆを
お召し上がりいただけます
価格 3,150円 (税込) 送料込
●フリーズドライ七草×7袋
常温保存(冷凍不要)
期間限定商品(12月~3月
●レトルトのおかゆとフリーズドライの七草のセットです。
●お米はヒノヒカリ100%を使用しています。
レトルトのおかゆなのでいつでも手軽に食べられます。食べすぎで胃もたれに なっているとき、体調を崩しているときもすぐに調理ができるため便利です。
梅干をのせて、夜食に食べるのにもお腹にやさしくいいですよ。
七草について
1歴史
(中国と日本の風習が併合 もともとは『願掛け』行事)
七草粥の由来は諸説があり、どれも決定的ではないということですが、一般的とされるのが以下のような説です。6世紀頃に著されたとされる中国の楚の国の風俗、伝統行事を記した『荊楚歳時記』に、「正月七
日、人日(じんじつ、五節句のひとつ)となす。七種の菜をもって羮(あつもの、熱い汁)をつくる」とあります。また古来より中国では、春先に若菜を食べる習慣が多くみられます。
一方、日本では宮中行事として、正月十五日に供御の粥として、米やアワ、ヒエ、キビ、小豆等で粥を作り、食したという記録が残っています。
(あずきがゆの原型という説があります。)
そして、中国で行われていた伝統行事が日本に伝わり、日本独自のアレンジが加わって、七草粥という習慣が生まれたとされます。
七草粥あるいは七草は宮中で行われた行事で、平安時代の初期、嵯峨天皇の御膳に健康長寿を祈り、ナナを入れたものを出したのが最初だといわれています。そして約1世紀後の延喜年間には正月七日に7種の若菜を入れた七草粥が朝廷の行事として行われ、以後、朝廷の行事として定着したようです。
このとき天皇の健康長寿を祈るほか、魔除け、招福、病気予防、豊作を招くといったことが、併せて願掛けされていました。ある意味、まじない的な色合いが強かったようです。 その後、室町時代後半から江戸時代にかけては、庶民の間にも広がりました。そして全国に広がりを見せたことから、後世になるにしたがって地方色が豊かになったといわれています。
また、一般的な風習によれば、前日の6日の夜から七草粥を作り始めます。まず7種の野草を用意し、まな板、薪、包丁、火箸、すりこぎ、しゃくし、菜箸、の七つ道具を準備します。そしてまな板を清め、〈七草ナズナ唐土(とんど)の鳥が日本の国に渡らぬ先にストトントントン七草ナズナ〉と唱えながらまな板を叩き、七草粥を作りました。
2栄養について
(『粥』だからこそ七草の栄養を余さず得られる)
七草粥に使われる野草は、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ(カブ)、スズシロ(ダイコン)の7種類。正月料理や年末年始の酒浸りがたたって胃腸が弱った時期や、青菜等野菜類が不する冬場には格好の食事だといわれています。
ではどうして7種類の野草が選ばれたのでしょう。これについて、薬草・漢方薬局「漢方堂」(茨城県竜ヶ崎市)を経営し、漢方、薬用植物研究家でもる薬剤師の佐藤成志氏は、「いわゆる七草にあげられる野草はすべて、冬の間は雪の中、あるいは氷の下に埋もれながらも、ちょっと日当たりがよくなれば、青々と芽を出して繁茂していきます。氷や雪の下に埋もれていながらも、すでに春の芽生え、いわゆる命というものをきちんと蓄えているわけです。このパワー、エネルギーをいただくという意味が、まずとても大きいことなんです。」
個々の野草の効能は別項を参考にしてほしいのですが、これにもう一つ共通していることは、どれも強い解毒作用を持つこと。「冬の間に、あまり体を使わず運動することも減り、しかも囲炉裏やこたつなどじっとして正月を過ごすことが多いですが、このときにたまった毒素をいち早くだし、春に向けて体調を整える準備をするために必要なのが七草なんです。七草はいずれも解毒作用を持つものが多いですが、そういうことを日本人は食文化の中に、うまく取り入れてきたということですね。」
そして『粥』であることにも意味があるといいます。「そもそも冬の時期というのは胃腸の働きが弱り、まして年末年始はお酒を飲む機会が多いですよね。そんなときに粥であれば消化吸収されやすく、しかも七草の効能が粥の中に閉じこめられていますから、それらの栄養素も吸収されやすいというわけです。」
※平成12年2月1日発行
(株)日本ジャーナル出版 「自然と健康」2月号より
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[フード&ドリンク] カテゴリの最新記事
-
食べられるしゃぼん玉⁉️ 2025年10月27日
-
ギフトやご自宅での飲みくらべに人気の TH… 2023年06月18日
-
下部に楊枝でひとさしするとつるんと表面… 2022年09月20日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.