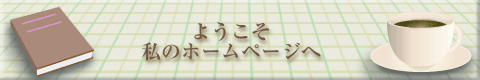孫子に学ぶ勝利への道!2
(1)人を動かすには指導理念をもて(哲学者であれ)
「動いて、迷わず、挙げて、窮せず」
経営者・指揮官は、自ら人生論、職業観、世界観、歴史観、そして使命感をもつこと。そして、これらは部下・選手の共感を呼ぶことが必要である。また哲学者としての一面をもつことが必要であり、そうして始めて部下・選手を動かしていけるし、困難・危急に際しても、ふんばりをきかせることができる。高い価値観を掲げて、生きがいをその中に見出す努力をする。
(2)指揮官は組織のビジョンを持て(哲学者であれ)
「人、すでに専一なれば、勇者も、ひとり進むことを得ず、怯者も、ひとり退くことを得ず。」
人間は魅力ある目標を示されるならば、その達成を目指して努力するものである。指揮官は、そういう考えのもとに行動すべきである。そして、この目的ないし、理想というものは、「心の鍛錬」とか「自分づくり(身心相即・物心相即)」に基づいたひとづくりという精神的・教育的なものでなければならない。使命感、他人や自分の言動に対する責任、部下・選手を成長せしめる情熱、これらが多くの部下・選手を動かすことになる。
(3)すぐれた組織(チーム)は「偉大なる教育機構」(哲学者であれ)
「道を修めて、法を保つ」
指揮官は、たけだけしく逞しいだけではなく、人生をどこまで信念を以って貫くか、正正堂堂の人生を自らのものにできるかが重要なことである。
(4)指揮官は志をもて「勇を斉しくして、一のごとくするは、政の道なり」
今日「志」とは、理想を求め、高い目標に挑戦する推進力、行動を起こすときの活動力の源泉、自己との戦いの課題、そして困難、苦境のときの支える力である。
(5)功績は部下に、失敗は自分に「進んで、名を求めず、退いて、罪を避けず」
組織(チーム)に対する忠誠心と義務感は、自らに高らかな理想と誇りある使命感があるかどうかに左右されるもの。それが感動を呼ぶのだ。また、真の勇気は、そこから生まれるものであろう。
(6)健康な心をもて「高さを好み、陽を貴ぶ」“高きを好んで、下きをにくみ、陽を貴んで、陰をいやしむ”
1 使命感をもつ。人のため、組織のためを考え、自己中心ではない。
2 ストレスから逃げない。ストレスはむしろ、ロマンと目的をもっていることの証左である。乗り越えることに生きがいをもつ。
3 感激性をもつ。毎日のくり返しや平凡なことにも新鮮さを見出す。
4 達成感と喜びを積み重ねる。チャレンジと達成が、自分の成長であること実感する。
5 蓄積に努める。自分以外から常に何かを学ぼうと努力する。
(7)疲れないチームをつくれ「高陽に居りて戦えば、利あり」
仕事・鍛錬をする以上、そういう環境に自らを置く人の方が成長するということ。進んで高い目標にチャレンジし、ほめられ、表彰されることに物質面よりも精神面の満足を見出す、そういう積極性が大切だというのだ。
(8)人の心を知れ「囲めば欠く。窮には、迫るなかれ」
1 善意、親切の押しつけ。自分勝手な「善意の基準」を設けようとする。
2 楽しみ、趣味の押しつけ。他人の楽しみを「自分の物さし」で測ろうとする。
3 意見の押しつけ。世の意見の「画一性」を期待する。
4 経験、知識の押しつけ。相手の「無経験」を酌量しない。
5 完璧の押しつけ。相手の「弱点」を斟酌しない。
6 頑固さの押しつけ。重要でない「些細な事柄」について譲らない。
以上のことは、相手を追いつめることであり、自分の心のゆとりのなさ、自己中心を見せているようなものである。人間関係とはこれを知った上で、自分を押しつけるよりも、相手のこの意識を受け入れることから始まり、この理解、認識、信頼関係を生むことになる。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 楽天イーグルスにアツいエールを送ろ…
- 2004年に発生した中越地震から10月23…
- (2024-10-24 00:22:47)
-
-
-

- ヴィッセル神戸
- 天皇杯準決勝 神戸2-0広島さん パナスタ…
- (2025-11-17 14:50:35)
-
-
-

- スキーのコト、雪のコト、はなしまし…
- ★南月山に雪★
- (2025-10-29 17:07:47)
-
© Rakuten Group, Inc.