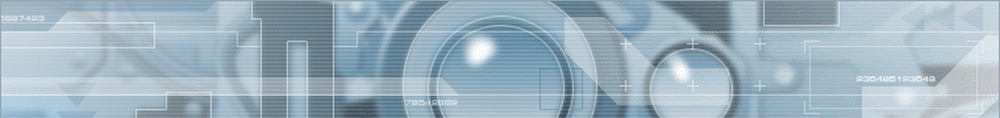昨年9月のドイツについての最後の大作にとりかかります。ワインの感想はないので味を忘れることを気にしなくてよいので後回しにしていました。
ドイツのワイン産地に踏み入れた初日の午前中は ザールSaar
の葡萄畑の散歩をしました。
早朝に夜行列車でザールブリュッケンに到着しトリアーに移動しロッカーに荷物を預けてスーパーで朝食と水を買い(8時なのに開いていました)電車でまたザールへ移動しました。
ヴィルティンゲンWiltingen
で下車して、たしか4時間後に隣駅の カンツェムKanzem
から電車に乗ってトリアーに戻ったと思います。
このくらいの距離なら歩けるという事と折り返さなくてもよいルートだと思ったのでこの周辺を選び、この付近に詳しくそして歩いたこともあるだろうと思われた北嶋氏にルートなどを相談し歩くルートを決めていきました。

ヴィルティンゲンの駅を降りた時にカンツェム方面を撮ったものです。後にこの葡萄畑の尾根をずっと歩いていったのです。
朝は霧が一面を覆っていました。この霧が葡萄に影響を与える寒さを和らげる作用があります。
カンツェム方面へ向かう前に訪れるところがありました。
オルツタイルラーゲに定められている シャルツホーフベルクScharzhofberg
の畑です。この方面に一度は行ってみたいということもあってスタートをヴィルティンゲンに決めたということもあります。僕自身はこの畑に対してそんなに想い入れはないのですが、ドイツで最も有名な畑のひとつなのでこの目で見なくてはと思っていました。
シャルホーフベルクの畑はザール川から直角に(おおまかですが)奥へ続いていく丘の畑です。
ヴィルティンゲン村から30分くらいシャルツホーフベルクの畑沿いを歩いたところにこの地で最も有名な エゴンミュラーEgon Müller
の醸造所があって、そこまで行って折り返してくることにしていました。
思ったことなどを書いていきますが、正確、明確な情報な情報ではなく推測な部分が多いのでシャルホーフベルクを知る、という観点ではあまり参考にはならないと思います。

これは戻ってくる時に斜面の上のほうに登った時にヴィルティンケン、ザール川の方向を撮ったものです。写真の左が上流でアイル、ザールブルク、右がカンツェム、トリアーの下流側です。
こういう丘がこの後ろにもずっと続いています。水は川ではなく沼みたいなところで丘に沿ってずっと続いているわけでなくシャルホーフベルクは川沿いの畑ではありません。

かの有名なエゴン・ミュラーの邸宅兼醸造所です。ワインのラベルにもなっている光景です。
シャルホーフベルクの畑に入って20分くらい歩くとここに辿り着きます。この先にも畑は続いていてシャルツホーフベルクの畑の真ん中くらいに位置していると思われます。

家の近く畑の手前にはプチ農園が広がっていました。

ここも家の近くから撮ったものです。しっかりは確認していませんがエゴン・ミュラーが所持する区画はこの中に必ず含まれているはずです。
機会があればどこらへんを所持していてアウスレーゼはどこからとかとかそういう事を聞ければなあと思っています。

行きは斜面の下にある小道を歩いていったのですが(茂った木の先に車道もあります)、帰りは斜面の中腹まで登ってみました。下から見るより実際に登るとけっこう急で踏み外して落ちないように気をつけながら登らなくては危ないといった状況です。

これは上のほうを撮ったもので少し見切れているのでわかると思いますが、斜面は3ブロックに区切られていてそこには平らな道が造られています。
一番下のブロックにはシーファーはあまり転がっていないのですが、上の方のブロックは表面からがっつりとシーファーでした。でも北嶋氏に訊いてみたら下の方も土壌は同じようです。
昼にシーファーを触ったらとても熱くなっていたのでシーファーによる保温効果というのがよくわかりました。
また、シャルツホーフベルクの畑はとても長く続いていて広いのですが、1971年の法改正により区画が広がっていてオリジナルはこの続く丘の全てではなくエゴンミュラーを中心とした途中までの区画のみだそうです。
土壌も違うようなのですが土壌の違いなどは一見見ただけではわかりません。もしかしたらここからは違うと説明されて観察したら違いがわかるかもしれませんが。
また、エゴンミュラーは樹齢100年以上の葡萄からもワインを造っているとのことですが、エゴンミュラー周辺はかなり細くてとても黒い葡萄の樹だったのですが、100年は経っていないかもしれませんが明らかに古樹だというのがわかりました。途中からはもっと太い他の畑でもよく見かける樹でした。

この地区がオリジナルの最良の区域の土壌かどうかもわからないのですが、消費者はそこまで気にしないし専門家、マニアでないと違いは分からないと思うので、所持する醸造所としてもシャルツホーフベルクの畑を所持さえできればよいと考えている造り手もいるのではないでしょうか。もちろんトップどころの造り手ではそういう違いの部分にもこだわっているところもあるとは思いますが。
次回はヴィルティンゲンの畑についてです。
-
ザールのヴィルティンケン周辺のぶどう畑… 2013.03.26
-
ザールのヴィルティンケン周辺のぶどう畑… 2013.03.24
-
今回のドイツで食べたもの、飲んだドイツ… 2013.02.23
カテゴリ
カテゴリ未分類
(54)ラーメン
(60)ドイツワイン
(119)東京ドイツワイン協会(ケナー関係含む)
(42)役にたつであろうワインの知識
(17)ドイツワイン 2010年ヨーロッパ旅行編
(29)2010年 ヨーロッパ旅行ドイツワイン以外
(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 土地
(14)ベスト3 ヨーロッパ旅行 体験
(10)ヨーロッパ旅行 08年12月編
(8)ヨーロッパ旅行 08年1月編
(3)ヨーロッパ旅行 実践編
(11)2012ヨーロッパ旅行 ドイツワイン編
(22)2012ヨーロッパ旅行 (ワイン以外)
(6)日本の土地
(28)ベルギービール
(17)その他酒
(10)音楽
(48)プロレス
(18)日本で買えるおすすめドイツワイン
(7)sakae
(3)2013年ヨーロッパ旅 ワイン以外
(3)2013年9月ヨーロッパ ドイツワイン
(4)2014年9月ヨーロッパ
(2)・2025.10
・2025.09
・2025.07
キーワードサーチ
コメント新着
モーゼルだより mosel2002さん
ドイツワインならメ… 店長@ユースケさん
Loving PURORESU hirose-gawaさん
youi's memo youi1019さん