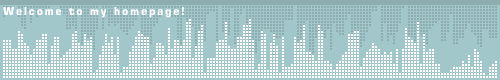JOE LEE WILSON
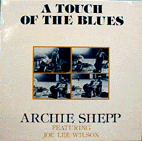
1978年のことだったか?
クラブでのK原君の研究会でのこと。
そのジョン・リー・ウィルソンのレコードをかけると自然発生的にクラブのメンバーによる合唱がはじまったのだ。
最初は遠慮がちに、次第に各人の声は大きく、最後の頃には、絶叫に近い感じで、大合唱になった。
K原君がかけたレコードは「ジョー・リー・ウィルソン/シャウト・フォー・コルトレーン」(Why Not)のA面1曲目「モード・フォー・トレーン」。
ロフトジャズシーンでその名前はスタジオ主宰者としてサム・リバースとならんで知ってはいたけど、歌はその時に初めて聴いたのだ。
コルトレーンの名前を反復するその歌はわれわれの世代にとってそれだけで興奮させるものがあったのだろう。
酒も入っていないのに異様にハイテンションな状態で盛り上がったのだ。
このアルバムは当時のロフトシーンの断片がうかがえる、そして最も初期の藤原清登のベースが聴ける力作である。
それから、しばらくしてまた、K原君がアーチー・シェップの特集かなんかでジョー・リー・ウィルソンの歌声が聴ける一作として紹介したのが、この「A TOUCH OF BLUES」 ARCHIE SHEPP FEATURING JOE LEE WILSON(FLUID)
前作も素晴らしかったが、このアルバムはそれをさらに上回る出来だとその時直感した。
アーチー・シェップの名義になっているが、実質、ジョー・リー・ウィルソンのリーダー作といっても良いと思う。
ジョー・リー・ウィルソンの声は、黒人男性独特の中低音域はややいがらっぽいビターテイストな声質で、それが高音域になると、粘りをもった甘く、ソフトさとハードさ、刺激性をもちあわせたよく伸びる音と形容したらわかるか?とにかく聴いていて特徴のある個性あふれる声。
深い陰影、ブルース感覚、私たち日本人が絶対表現できないなにかが、ジョーの歌にはDNAとして刷り込まれている。
おそらく、何を唄っても底辺にはそのテイストというか、ブルース成分が本人も無意識のうちに表出されるのではないだろうか?
努力や練習だけでは踏み越えられないものの何か。
それこそ、歴史であり、血であり、本能であり、因子なのであろう。
ブルースという精神の。
アーチー・シェップのテナーサックスとジョー・リー・ウィルソンのボーカルが一卵性双生児のように同じテイストで、絡み合い、反応しあう。
二人の深いエモーションが固まりとなって投げかけられる。
私たち聴者は唯、それを享受するだけでよい。
A TOUCH OF BLUES
それだけで、祈り、触れられるのだ。
真のブルースの精神に・・・
このアルバムは、1977年10月19日 パリで録音された。
メンバーは、
ARCHIE SHEPP(TS,SS,FL,P) JOE LEE WILSON(VO)
SIEGFRIED KESSLER(P) CAMERON BROWN(B)
CLIFFORD JARVIS(DS)
この後、ジョー・リー・ウィルソンは、次のアルバムをリリースしている。
・THE SHADOW(AGHARTA)1990年
・ACID RAIN IT`S BEEN RAININ`(BLOOMDIDO)1992年3月
などをリリースしていて、新作を最近イタリアのPHILOLOGYからリリース。
シェップと同じくますます元気で活躍している。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治サインポスター掲示2『FUK…
- (2024-01-22 04:00:09)
-
-
-

- ☆モー娘。あれこれ☆
- 【石田亜佑美・横山玲奈・櫻井梨央(…
- (2024-11-27 21:58:28)
-
© Rakuten Group, Inc.