-
1

帳消し?
今朝、教会で福音書の朗読をきいていて、「そうか?」と思った。さて、あるファリサイ派の人が、一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席に着いておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持って来て、後ろからイエスの足もとに近寄り、泣きながらその足を涙でぬらし始め、自分の髪の毛でぬぐい、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、「この人がもし預言者なら、自分に触れている女がだれで、どんな人か分かるはずだ。罪深い女なのに」と思った。そこで、イエスがその人に向かって、「シモン、あなたに言いたいことがある」と言われると、シモンは、「先生、おっしゃってください」と言った。イエスはお話しになった。「ある金貸しから、二人の人が金を借りていた。一人は五百デナリオン、もう一人は五十デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。」シモンは、「帳消しにしてもらった額の多い方だと思います」と答えた。イエスは、「そのとおりだ」と言われた。そして、女の方を振り向いて、シモンに言われた。「この人を見ないか。わたしがあなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙でわたしの足をぬらし、髪の毛でぬぐってくれた。あなたはわたしに接吻の挨拶もしなかったが、この人はわたしが入って来てから、わたしの足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから、言っておく。この人が多くの罪を赦されたことは、わたしに示した愛の大きさで分かる。赦されることの少ない者は、愛することも少ない。」そして、イエスは女に、「あなたの罪は赦された」と言われた。同席の人たちは、「罪まで赦すこの人は、いったい何者だろう」と考え始めた。イエスは女に、「あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい」と言われた。(ルカ7:36-50)二人とも、返す金がなかったんでしょ?で、半額免除とかじゃなく帳消しにしてもらったんでしょ?はたから見れば、「多く帳消しにしてもらったほう」と「少なく帳消しにしてもらったほう」がいるけど、当人にとっては自分が帳消しにしてもらったことに変わりない。他人とくらべれば、多い少ないがあるかも知れないけど、自分にとっては自分がゆるされることだけが問題で、ゆるされてうれしかったら、ゆるしの大きさに応じてじゃなく「とにかく自分にとって精一杯」、感謝するんじゃないか?いや、福音書にケチつけるわけじゃないんですが。罪深いほど、赦される必要があるだろうし、そういう人を退けず、うけいれるイエスはえらいけどね。
2007.06.17
閲覧総数 15
-
2

従順の意味
昨日きた教区新聞に、シスターの生活のことが書いてあって、それを読んでつらつら考えたこと。神にささげる修道生活の三本柱は「清貧、貞潔、従順」。20代前半で洗礼をうけた当時、教会の若者たちはみな、男性は司祭になることを、女性は修道女になることを一度はきちんと祈って考えなさいと言われていた。そんなこと言われても他にやりたいことがいっぱいあったし、生意気盛りだった(過去形で言っていいものか?)年頃。ある先輩が「清貧と貞潔は、できる。もうやってる。でも、私に従順になれったって、無理だよ。」というのを聞いて、「私もだ!」と思った。昨日ふと、従順ってシスターだけのものじゃないな、と思った。私は日曜日以外にはいっさい教会によりつかない、けっこうさめた信者なのだが、ある時期、2年近く毎週日曜日の昼食を神父さまとともにする特権にあずかっていた。(もちろん、教会の仕事のお手伝いをしていたから。)食事しながらいつも「先週はどんなことがあったの?」と聞かれて答えるのは自分の一週間をふりかえるよい機会になった。(ごはん食べながら告解してるみたいだったけど。)ある日、「先週は研究発表のしかたの件で上司と意見があわなくてやりあった。」と言うと、「で、最終的に合意に達したの?」と聞かれた。「いいえ、合意したわけではないけど、結局上司に従いました。(We didn't agree, but I obeyed.)」と言うと、70歳をすぎたその神父さまは急に食欲なくしたような表情になって「なんてこと言うんだ。神学校時代を思い出すじゃないか。」と言った。そばにいたおばさんが、「最近obeyなんて言葉、聞かなくなりましたね。」と言った。日本の神父さまがたはあまりそういう話をしないけれども、アメリカの神父さまがたはみな、神学校は楽しいとか懐かしいというよりも、厳しくしぼられた思い出ばかりだという。で、神学校でobeyすることもたたきこまれたそうだ。ところでこの時私は、英語のobeyというのは日本語の「従う」よりももっと深刻な意味があるのだと知った。単に自分の判断を放棄するとか「まあしょうがないから、この場は言うこと聞いておこう。」ではなく、受け入れることがほとんど不可能と思えるようなことを、十字架にかかるまえのイエスのように徹底的に祈って、自分と戦って、その結果うけいれることをobeyと言うのだと知った。いざという時に、神に従順になれるか。わたしたち全員に、問われている。そして従えることは幸いなのだと今は思う。
2006.11.08
閲覧総数 39
-
3

今朝思ったこと;正統的じゃない聖書解釈
ヨハネによる福音書2章:1-11三日目に、ガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスも、その弟子たちも婚礼に招かれた。ぶどう酒が足りなくなったので、母がイエスに、「ぶどう酒がなくなりました」と言った。イエスは母に言われた。「婦人よ、わたしとどんなかかわりがあるのです。わたしの時はまだ来ていません。」しかし、母は召し使いたちに、「この人が何か言いつけたら、そのとおりにしてください」と言った。そこには、ユダヤ人が清めに用いる石の水がめが六つ置いてあった。いずれも二ないし三メトレテス入りのものである。イエスが、「水がめに水をいっぱい入れなさい」と言われると、召し使いたちは、かめの縁まで水を満たした。イエスは、「さあ、それをくんで宴会の世話役のところへ持って行きなさい」と言われた。召し使いたちは運んで行った。世話役はぶどう酒に変わった水の味見をした。このぶどう酒がどこから来たのか、水をくんだ召し使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで、言った。「だれでも初めに良いぶどう酒を出し、酔いがまわったころに劣ったものを出すものですが、あなたは良いぶどう酒を今まで取って置かれました。」 イエスは、この最初のしるしをガリラヤのカナで行って、その栄光を現された。それで、弟子たちはイエスを信じた。最初のしるしは、水を酒にかえることだったのか。死にかかっている病人をなおすとか、飢えているおおぜいのひとに食べ物を配るとかじゃなく?日照りに雨をふらせるとかじゃなく?いったいどういう重要な婚礼だったのだろう。ぶどう酒なんて、たりなくなれば飲むのやめればいいと思うんだけど。もしかして、のんべー集団で手に負えなかったの???まあ書いてないことを想像してみてもしょうがないが、なんか意外な最初のしるしだよなぁ。私がここからイエスにならうとすれば、まあ私たちの生活のなかで、大きく人助けをしたり社会に貢献できるチャンスはそうそうない。でも、そこにある小さな問題を、解決する、私がしなくちゃいけないことでなくても、みつけたらすっと解決する、そういうところから始めよう、そんなことだろうか。みんながそうすれば、たしかにそれは大きな変化になるしね。ひとりひとりの「私」が実行すれば、みんながしてることになるしね。それにしても、(これを言ったら殴られるかもしれないが)ほんとに水がぶどう酒にかわったのかなぁ。世話役、もうさんざん飲んでて水がすごくおいしかったんじゃない?
2007.01.15
閲覧総数 17
-
4

「帳消し」パート2
前回の「帳消し」の話、まあ重箱の隅つついてるようなものかも知れないけど、私がなぜ「当人は帳消しにしてもらった額の多少に関係なく自分が帳消しにしてもらったことに精一杯感謝するはずだ」と思ったかが次のネタになるな、と思いました。帳消しにするほうにしてみれば、多く帳消しにする決心をするほうがあきらかにエネルギーいりますね。では帳消しにしてもらうほうにとってはどうか?借金が期限までに返せないってことは、信用をなくすことなんですよね。たとえばサラ金から借りた金を返すために別のサラ金から借金し、それが雪だるまのようにふくれて多額の借金になったとしたら、それはそれで問題だけど、小額の借金すら返せない、そんな額も工面できないほどに困窮してるってことが取引先や世間にわかってしまうってのも、すごーく困ることなんじゃないだろうか?だから私個人的には、そういう小額の借金を返せないようなときに帳消しにしてもらうほうがありがたいかもです。借金が多額になっていたら、感覚がマヒしてて、帳消しにしてもらったありがたさもあまり感じないかも。んで、私たちはそんなにしょっちゅう殺人とか盗み、不倫とかする機会はないけれども、神のみむねにそわないことはけっこうちびちびしてるかもです。そういう小さな罪を日々くいあらため、赦していただくこと、そしてその赦しに応えていくことは、けっこう重要だよね、きっと。小さな罪に気づかず悔い改められないのって、けっこうまずいんではないか。神様って、私たちの罪の大きさを区別して、それぞれの罪の赦しに別の量のエネルギーつかってるかな???じつは最近、私の父がなくなりました。父には私をふくめて5人こどもがいたので、そのなかで一番「できのいい」子と一番「できのわるい」子がいたわけです。何をもってできがいいとするかは問題なので、5人それぞれに別の観点からのコンプレックスはあったと思うのです。でも、そういう順位はどうでもいいことなんじゃないだろうか?みんな、自分なりにせいいっぱい親孝行したい気持ちはあったんだ、だからみんなそれぞれ泣いたんだ、父だってそれはわかっているんじゃないかな?多く学費を出してもらった子と少なくもらった子がいたけど、どれだけ出すにも「その子の幸せ」のために親はしてくれたんじゃないだろうか?というようなことを最近考えていました。そんな流れで、私たちの罪の大きさ、与えられた赦しの大きさ、それに対する感謝の表現、というのも、他人と比較することじゃないんじゃないだろうか?と思えたのです。神様を自分の父親と同じレベルで論じるのは失礼だったかも知れないけど。
2007.06.21
閲覧総数 18
-
5

はぐ記念日
ハグ(抱擁)、というのは日本にはあまり無いあいさつ、愛情表現の形式ですね。アメリカに来てから時々されるようになったけど(さすがにまだ自分からはできませんな)、いままで相手はいっつも女性だった。見てるとやっぱり異性でハグするのはそれなりの関係なんですな。で、今日、はじめて男性にハグされた!相手、引退したおじいちゃんの神父様だけど。ま、彼にとっては私は孫みたいなもんなんでしょう。あははは。このおじいちゃん神父は、まだまだ元気だけど、やっぱり訪ねていくと喜ぶ。なつかしい顔をみるのはだれにとっても嬉しいんだろうけど(ってひと事みたいに言うけど、私もうれしい)、歳とると、特にうれしがるようになるよね。うちの親にもそろそろ顔みせに行かねばなー。しかし、ハグするには覚悟がいるよ。お互いどれだけぜい肉ついてるか、とってもよくわかるんだもん。
2005.10.09
閲覧総数 7
-
6

自分のことを棚にあげて言えば(創世記3章1-12)
主なる神が造られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。「園のどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。」女は蛇に答えた。「わたしたちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも、園の中央に生えている木の果実だけは、食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないから、と神様はおっしゃいました。」蛇は女に言った。「決して死ぬことはない。それを食べると、目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存しなのだ。」女が見ると、その木はいかにもおいしそうで、目を引き付け、賢くなるように唆していた。女は実を取って食べ(神よりもどこの馬の骨とも知れない蛇の言うことを聞くのか、このバカ女は。)、一緒にいた男にも渡したので、彼も食べた。(こら、食べちゃだめだって言われてただろ!女をいさめず何でも渡されたら食べるのか、このトンマ。)二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はいちじくの葉をつづり合わせ、腰を覆うものとした。(胸は隠さなかったのか。)その日、風の吹くころ、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が、主なる神の顔を避けて、園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。「どこにいるのか。」彼は答えた。「あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり、隠れております。わたしは裸ですから。」(隠れてるのに返事するんだね。頭かくして、、、。しかしロジックぶっとび。恐ろしくなったのは裸だからじゃなくて、神に逆らったから、その報いを恐れてるんじゃないの?うそつくと、あとでもっと言い訳必要になるよ。それにしても、聞かれもしないのに自分から裸を自覚していることを認め、墓穴ほっている。)神は言われた。「お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。」アダムは答えた。「あなたがわたしと共にいるようにしてくださった女が、木から取って与えたので、食べました。」(聞かれたことに対して必要十分なことを答えなさい。あなたが云々の言い訳はまったく余計だろ。)
2007.01.09
閲覧総数 17
-
7

週末のつれづれ
週末なので、一週間分のごはんをつくってます。まとめてつくったものを小分けして弁当箱にいれ冷蔵庫に保存し、毎日一つずつもっていきます。週の間にはほとんど料理しません。あ、念のためにいっておくと、週末にはがんばって2-3種類のものを作るので、一週間まったく同じものを食べ続けるわけではありません。さらに、たとえばカレーをつくっても、弁当箱にいれる時に、わざと肉のかたよった箱と野菜のかたよった箱をつくったりします。そして、ピクルスやチーズを入れたりいれなかったりすれば、まあ毎日少しずつ違う弁当を食べることができる、、、、と本人は思っているのだからよいでしょう?!で、英語のcookっていう言葉は、「料理する」って日本語に訳されるけど、cookは加熱する調理のことなんだよね。野菜きったりつけものつけるのは、cookではないのだ。コンビニ弁当を電子レンジで温めるのはcookなんだろうか???知らん。日本にはイモを海水で洗って塩味をつけて食べるサルがいますが、食べ物に火を通して食べる動物は人間だけじゃないかな?火を通すと、柔らかくなったり、おいしくなったり、ナマでは消化できないものが消化できるようになったり、食べ物についている寄生虫やばいきんを殺すことができたり、保存がきくようになったりします。それから食べ物に火をとおしている間に、あたりにいい匂いがただよって、食欲をそそったり懐かしい気持ちになったりしますよね。火を利用することを最初に発見したひとは、えらいな~。火があれば、明かりにもなるし、暖をとることもできる。(ついでに、都合のわるいものを燃やしてなくしてしまうこともできる。)でもマッチの発明される以前には、火をおこすのはとても手間がかかった。だから人々は種火をたやさないようにした。いっぽう火が大きくなりすぎると、ものを破壊し、命をもうばってしまう。だから、火を安全な大きさに保ち、でも絶やさないようにすることは重要だった。ところが火を24時間体勢で管理するのは、一人では無理。そんなわけで、人間は火を使うために共同体を形成していったんじゃないか。火は共同体の中心。だから、神が火のなかにあらわれたり、神の霊が炎の形になって人々に下ったりするんじゃないの?で、いまもって、集まって祈るときにはろうそくに火をつける。カトリックのミサのときには2本以上ろうそくをともすって決まってます。で、司教ミサのときには4本とかもっとたくさんろうそくつけることが多くて、それは司教ってたいてい年とってて、より明るくしないとミサ典書が読めないからだろうと思ってたけど、もっと別の意味あるのかも。んじゃ、この便利な電気やら電磁調理器やらにあふれた文明社会は、人のつながりを弱めてしまうんだろうか?う~~~~む。使い方次第だよね。昔だって、火を使いたい時だけつかって共同体のために働かない輩はいただろうし。
2006.11.05
閲覧総数 11
-
8

ゆるしの秘跡
私はいわゆるcradle Catholic(カトリック信者の親から生まれた、赤ん坊のときからのカトリック信者)ではないけれども、自我が確立する前に教会に行くようになり、いろいろ教え込まれたので、教会が教えていることをしないのはなんとも落ち着かない。そういうわけで、こんどの日曜日のイースターを迎える準備として「ゆるしの秘跡」をうけた。私が教会に行くようになった頃にはもう、その習慣は廃れていたが、昔は土曜日ごとに、罪を告白して新たな気持ちで日曜日を迎えようという人の長い列が教会にできたのだそうだ。私は、大祝日の前、特にクリスマスとイースターの前には悔い改めるように教えられた。この秘跡は4つのステップからなる。1.自分が神とその共同体である教会に対してどういう罪をおかしたかふりかえる2.神のまえに罪を告白し、心から悔やみ、悔い改めを決意する3.教会(の代表者である司祭)に罪を告白する4.教会(の代表者である司祭)から指示された償いを実行するステップ1、2は自分が神と直接むきあう場である。聖霊の助けをもちろん受けるのだが、それでもどう神とむきあうかは自分次第と言える。これについての解説書やウェブサイトはいろいろあるのだが、概ね、旧約聖書の十戒と、それに付随した教会のルールにそって自分の罪を具体的にふりかえるというものである、と言えると思う。十戒に文字通り反する罪といったら、殺しとか盗みとか、かなり深刻なもので、通常の善良な市民には機会のないようなものにも感じられるし、もともとこの儀式はとんでもなくまずいことをして教会共同体から交わりを絶たれたひとが、共同体に戻るためのものだったとも聞く。それでも十戒の意味を咀嚼すれば、自分のなかにもそういった重罪に通じる罪、失敗というのは1つや2つ、思い出すものだ。そういうことや、自分が気にしていたことを何ヶ月かに1回ずつ告白していたのだが、今回、自分の教会のスケジュールが都合悪かったのでいつもと違う場所に行き、いつもと違う司祭に告白をきいてもらった。短い儀式が終わって、「これは便利だから、持っていきなさい。」とわたされた小さなカードを帰宅してから読み、目からうろこが落ちる思いをした。それは「ゆるしの秘跡の手引き」、といったカードだったのだが、罪の糾明のしかたが今まで私の読んだことのない方法だった。1.神を愛する2.隣人を愛する3.平和のためにはたらくという3部だてだった。そしてどう神を愛するか、どう隣人を愛するか、この世にどう平和をもたらすか、といった項目の解説がされていた。たしかに、これがイエスさまの教えであり、十戒よりも自分にとってしっくり来るものだった。さらに、この小さな儀式の最後に唱える祈りの文例がのっていた。これも今まで使っていた手引書とはおもむきがやや異なっていた。「いつくしみとあわれみの神、私を優しくみつめ、私の罪をゆるしてください。私に清い心をつくり、キリストに心から従う望みを私のなかに強めてください。あなたの教会、そして世界のなかで、あなたの永遠の愛を証しすることができますように。主キリストによって。アーメン」こんどはこれを使ってみよう。こんどは何ヶ月もあけないで行こう。この小さなカードを手にいれ、とても儲けた気分だ。
2006.04.11
閲覧総数 11
-
9

りんごの皮
今まで寒いところに住んでいたけど、こんどの所は暖かいので、柿がりができる、ということがわかった!これがプリンに続いて2番目にみつけた、この街のよいところだ(笑)。日本人は柿がすきなんだよ~とアメリカ人の友達に教えたら、「柿ってそのまま食べるのか、皮をむくのか?」と聞かれた。たぶん、人にもよるし、どれだけなじんでいるかにもよるんではないか、と答えた。うちの親は私が小さいとき、柿も梨もりんごも桃もむいてくれたが、学校で友達の話をきくと、どうもむかない家もかなりあるらしいということを知った。アメリカでは、もっとも普通のりんごの食べ方は、皮をむかずに丸かじり。洗って櫛形にカットしてパックされたりんご、というのも売ってるが、これにも皮がついている。アメリカ人にとって、りんごの皮はむかないものらしい。でも、アップルパイにするときは、むく。なんでかな。りんごを必ず皮をむいて食べる習慣があったら、皮をむいているうちに思い直して、というか皮をむくのがめんどくさくなって、アダムは食べるのやめたかも。そーか、だからあの知恵の木の実は、まるごと食べられる「りんご」ってことになってるんだw。ザクロとかだったら、めんどくさくて、、、。
2006.10.08
閲覧総数 6
-
10

よい、わるいの定義
某所で議論があったようなので。私流、よい、わるいの定義。よい;神様からいただいた本来のすがた、それを感謝して生かせている(以上は自己だけでなく他に対しても)、結果としていきいきと輝くわるい;上記よいに反すること♪神の御旨を行うことは私の心の喜び♪てかまあ、私は何を良しとし何を悪しとすべきかのよりどころがほしかったから神を求めたかも知れません。循環理論w。んで何が神の御旨か知るは、やっぱり常に耳をすませないとだめですね。だけど、それでもこの循環を選んでとりあえず良かったと思う。選ぶまで、どうやって生きていけばいいんだか、でも生きるのやめることもできなくて、途方にくれてたから。
2006.02.03
閲覧総数 18
-
11

神への不平
レントの聖書の学びとディスカッションのてびき、今日の聖書の箇所は民数記 14章 2−3節。イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して不平を言い、共同体全体で彼らに言った。「エジプトの国で死ぬか、この荒れ野で死ぬ方がよほどましだった。どうして、主は我々をこの土地に連れて来て、剣で殺そうとされるのか。妻子は奪われてしまうだろう。それくらいなら、エジプトに引き返した方がましだ。」モーセとアロンのリーダーシップのもと、イスラエルはエジプトでの奴隷生活からのがれて約束の地へと旅するが、いろいろな困難にであい、なんどもモーセとアロンに文句をいう。ここにきて、神にも文句を言っている。生きていれば、だれしも自分の思い通りにいかないことをたくさん経験する。そんな時、私たちは文句を言いたくなるが、自分の思い通りになっていない部分をみて神に不平を言うのではなく、自分に与えられている部分にもっと目をむけ、神に感謝するためにはどうしたらよいか、というふうにこの教材はディスカッションに導いている。それはそれでよいのだけど。しかし、私の思いはまったく別のほうにむいてしまった。神に不平をぶつける、というのは、それだけ神を身近に感じ、あてにしているということじゃないかと思った。私も、いやなことをたくさん経験するのだが、神に不平をいったおぼえがない。文句を言うべき、恨むべき対象は、いつも神以外にとても具体的にみつかってしまい(上司とか、同僚とか、親とか、自分とか)、そこに文句を言うことで満足してしまうのだ。つまり、私はふだんあまり神をあてにしていないのか?いや、たいして苦労してないってことか?うーむ。
2006.04.07
閲覧総数 15
-
12

求めなさい、そうすれば与えられる。
6ヶ月宿題コース、今週のお題はこれなんですが。1.求めて与えられる2.求めて与えられない3.求めず与えられない4.求めず与えられるどれが一番うれしいか?3は、気にもしませんね。2は、普通のクリスチャンなら「まだ時でないかも知れない」、くらいは思うでしょうね。考えてみると、私は人間に対してはほとんど必ず「○○までに」って期限付きでお願いするけど、神様に対してはお願いに期限を示してないかな。だって神様にお願いするようなことって、もう今この瞬間にどうにかしてほしいようなことだもん(^^)。4は、よくありますが、予想外のものでうれしいことより、いらないものでうれしくないことのほうが多いかな。だって、本当に必要だと思うなら、すでに手に入れるか求めるかしてますもん。1が一番うれしいですよね。神様は、私たちが求めるまえから、私たちが何を求めるかご存知。さらに、私たちに何が必要かご存知。だから、求めたものではなく必要なものを与えてくださることもある。でも、私たちに「求める」という余地を残してくださっている。なぜかうまく説明できないけど、求めに応えてもらえるって、私たちにとってうれしいですもん。何を求めるべきかわかっている時のほうが、何を求めるべきかわからない時よりはるかに健康ですし。求めることは、自分にとって必要なものを見いだす練習かも知れません。
2007.09.21
閲覧総数 46
-
13

また会う日まで
「今朝、Fさんがなくなりました。」お手伝いしている老人ホームのチャプレンからメールがきた。大きい老人ホームだから、毎週のようにだれかかれかなくなるんだけど、こういうお知らせがきたのは初めて。そしてたしかに、Fさんは私にとって特別だった。日曜日の朝、老人ホームのなかでミサがある。車椅子のお年寄りたちが長い廊下をチャペルに移動するのを手伝ってくれるひとを大募集していたとき、ああ、私でもできるな、と軽い気持ちで始めたお手伝い。出会った当時96才だったFさんは、ちょっと気難しそうに見えて、私は最初こわかった。最初のころ、よく「私をおしてくれてるのは誰?」と聞かれた。それからほどなく私のことをおぼえて、朝食のあと、いつも私が迎えに行くのを待っていてくれるようになった。とてもかわいがってくれたので、私も自分のおばあちゃんのように思うようになった。先週は、私がむかえに行くと、"This is my special friend."といってにっこりした。最近少しオーバーワークで、このボランティアもいつまでできるかな、と思っていたのだけど、その時、「このおばあちゃんがいるうちは、お手伝いやめられないな」、と思ったばかりだった。このおばあちゃんのひとり息子は神父様。こうやって愛情を注ぎはげましながら、わが子も神父様に育てあげたんだろうか、なんて考えていた。今週は、いつもみんなが朝食をとるお部屋にいなかった。寒くて調子わるいのかな、また来週あえるかな、と思っていた。 新聞にでた死亡記事を見ると、私だけでなく、たくさんの人に愛を注いでいたんだ。年とって体が動かなくなっても、ひとを愛することはできる。その愛はひとを動かし、世の中をかえることができる。少なくとも、私は Fさんの愛に動かされた。おばあちゃん、もう体もどこも不自由じゃないね。日曜日に会えなくなるのはちょっと寂しい。でも、この世の生活がおわっても、私達のためにお祈りしてくれるんだよね?そのうち、また会えるし。
2006.02.22
閲覧総数 9
-
14

Have a nice day, Have a nice week
先日書いたように、月曜の朝、忘れ物をとりに教会に立ち寄った。私の教会は、毎朝8時15分からミサがある。しかしこれに参加すると仕事に遅れるので、出ているのはだいたいご隠居さんばかり。(日本の教会は、平日ミサはもっと早い時間のところが多いのではないか?アメリカでは数十年前までは、子供はミサに出れば学校の1時間目に遅れてもオーケーだったのだそうだ。)私は8時5分前に教会の鍵があくのを待って、忘れ物をそそくさととり、ミサは失礼した(当然!)。笑いながら忘れ物をわたしながら、神父さんは「これから仕事?いってらっしゃい。(Have a nice day)」と言ってくれた。そういえば、親といっしょに暮らしていた頃は、毎朝「いってらっしゃい」と送られたものだが、一人で暮らすようになって、もうずいぶんこの「いってらっしゃい」を聞いていなかった。この神父さんだって、一人で暮らしているのだから、何年もだれにもそんなことは言われていないだろう、、、、あ、この教会以外の仕事もかけもちしているから、教会からでかけていく時に、秘書さんに言われているだろうか?まあとにかく、こういう一言はありがたいものだな、と思った。なんか今日一日、守られそうな気がする。毎週、日曜日にお手伝いしている老人ホームで、私はお年寄りに別れ際に、最初のころ「じゃあ、また来週 See you next week」と言っていた。「さようなら Good bye」だともう会えないみたいだから。それに英語でいちばんふつうの毎日の「さようなら」はSee you ,,,なのだ。でも、ある時ふと、必ず来週会えるわけじゃないな、と思った。それから私は「Have a nice week」と言うことにした。普通の一週間でも、今週天国に行くんでも、これならOKだろう。
2006.04.19
閲覧総数 5
-
15

クリスチャンは仏教徒のお葬式で焼香してもよいか?
ご要望により、他所に書いた私見をコピペします。単独の読み物として完結するように、一カ所だけ表現をかえました。注;私は宗教学者や神学者ではありません。教役者でもありません。==========まだわたしが大学生で洗礼をうけていなかったころ、教会にも定期的には行っていなかったころ、大学で、KGK(キリスト者学生会)という、たぶん福音派だったと思いますが、カトリックではないクリスチャン学生の集会にさそわれたことがありました。東京から招かれた主事のお話のトピックのひとつが、「マスターベーションは罪か、それともして良いか」というものでした。ずいぶん何年も昔のことなので、細かい表現はたしかではありませんが、その要旨は「罪の意識のなかにマスターベーションをするなら、それは罪である。」というものだったと思います。19歳だった私は、ずいぶん奥歯にもののはさまったような言い方をするな、だめって言って若い人が離れていくことを恐れているけど、結局するなって言いたいんでしょう?と思ったものです。年齢が当時の倍以上になったいま、あの主事のおっしゃったことはもっともだと思います。また、これはクリスチャンのすべての行動、たとえば他宗教の行事に参加してもよいかどうか、仏教の葬儀で焼香しても良いかどうか、ということにも通用するロジックだと思います。最初に、神は愛であるということを思い出してください。神様が、あるいは神様の代弁者として教会がなにかを私たちに禁じるのは、すべて、私たちを救いと反対の方向にむかわせないためです。私たちが自分自身を傷つけ不幸になるのを防ぐために、神様をちゃんと見つめていられるために、いろんなことをしろとかするなとか言っているだけです。偶像崇拝というのは、単純につくった像を拝むことではないと思います。唯一まことの神以外の存在を、一時的にではあっても、自分のなかで唯一まことの神以上に大切にすることだと思います。だから、最初に禁じられていることなのです。教会で、焼香はいけないと教えられたひとも、OKだと教えられたひとも、どうしていけないのか、どうしてOKなのか、ある程度の年齢になったら、自分で考え咀嚼する必要があると思います。そして教会の教えに同意するなり、納得できなければ聞くなり、自己責任で教会の教えには従わないことを選ぶけれども神様に申し開き(他人のせいにするのではなく、その結果も自分が負う)ができるようにするなり、選ぶのです。それをしないと、いつまでたっても借り物の、自分の体にあわない服をきる思いをするのです。私は洗礼をうけた後も焼香はしていますが、それは現在の日本の葬式で行われる焼香はほとんど宗教的意味がない、文化的習慣である(そもそも仏教には神という概念がないし)と理解しているからです。僧侶はどう思っているか知りませんが、仏教徒である私の家族もそういう理解です。ですから私が焼香しても、だれも、私が私の信じる神と別のほうをむいたとは思いませんし、私の心も痛みません。私にとっては、仏教徒の葬式で焼香するのは、英語しかわからない人には日本語で「ありがとう」って言っても感謝が通じないし、たまたま私は英語がしゃべれるから英語で”Thank you”と言うのと同じことです。でも英語をまったく知らない人にはそんなことができるわけもないのと同じように、 焼香の作法をよく知らない、異文化で育った人が焼香しないのは、相手の文化を尊重しないといって非難されるようなことではないはずです。私が相手の文化を尊重できるのは、せいぜい仏教(それも自分の実家の宗派に近い限られた宗派)まででしょうね。世界に五万とある諸宗教の文化全部を尊重はできないです。知らないものは知らない。そうしたら、へたに首をつっこんでおかしなマナーでまねをするよりも、「知らないので失礼しますね」と外に立っているほうがスマートだと思うのです。もし私が焼香はいけないと教え込まれていたとしましょう。そのいけない意味を自分が咀嚼する機会をもつ以前に、焼香するかしないか選ばなければならない状況になったとします。とりあえず、教えられたことによれば、すべきではないと思う自分。でも、まわりに違和感を与えないため、まわりをほっとさせるために、「本当はいやだけれども」焼香する。これは、自分のなかで神様(あるいはその代弁者としての教会)の教えよりも「まわり」を上においていることになりませんか?これこそ、自分と神様の関係を傷つけることになりませんか?それでも赦しを願えば神様は赦してくださるけど。そういうわけで、すっきりとお焼香できたら、神様に感謝すれば良いし、すっきりしない気持ちがあったのなら、神様に赦しを願えばよいと思います。
2006.08.29
閲覧総数 4315
-
16

創世記
ちょっとつかれたのでバカ話かきます。なんでヒトクローンをつくっちゃいかんとかって教会はいまさら騒ぐんだろ?イブがアダムのあばら骨からつくられたらなら、イブはアダムの体細胞クローンじゃんかw。アダムを先に作ったのは正解だよね。それ以後、いつも女から男が生まれるわけだから、1例くらい、男から女ができるケースをつくって、バランスとっておかないと。
2006.06.06
閲覧総数 15
-
17

イエス様に子供がいたら?
では雹(ERBM)さんが来てくださるということなので、今日は前から考えていたイエスさまに子供がいたらどうなのか、ということを書いてみます。(ほんとはこのブログはもっとあほなこと書くようにつくったんだけど。)ICFは一応、使徒信条、ニケア信条にそった正統信仰の超教派キリスト教サイトで、ひよこちゃんも見てるので、あんまり一般的じゃないことを書いてひとを惑わせないほうがいいと思いました。ここは、無責任ないち小娘のサイトなので、そのつもりでどうぞ。でも、私は正統信仰を否定するつもりはなく、むしろ擁護する立場のつもりなんです、これでも。改革おじさんもここに来てくれないかなw。改革おじさんが何を根拠にあんなに自信をもってイエス様は結婚も離婚もして子供もいるって言ったかはまだ聞いてませんが、雹さんは、イエスさまが妻子もちだったら、どのへんがまずいんですの?もうネタばれもなにも考えなくていい時期だと思うから書きますが、ダヴィンチコードというのはまさにイエスの子孫がこの現代のフランスに生きていて彼等が不思議な運命のなかでであう、という話しですよね。ま、これはちょっとばかばかしい部分もあるフィクションなので、ほんものの正統信仰の教会で映画のロケをするのはどうかと私は思うけど(教会がその考えを支持してるって勘違いするヒトがいるだろうから)、イエスさまに子供がいること自体はべつに神であり人であるイエス像をこわすことにはならない、かえって、もしその子孫が今の世にまだいたら、イエスさまが人としてたしかにあの時代を生きた存在だったのだ、イエスさまの話はおとぎ話ではないんだ、ということを強調する助けになるぞい、と私はあの本を読んだときに思いました。 なんか、まずいことでてきます?イエスさまに子供がいたら?カトリック要理にもべつに何も書いて無かったのでは?で、私はイエスさまに子供がいたって主張するには証拠がたりないんじゃないかと思うけど、そういうヒトに目くじらたてるほどのことでも無いんじゃないか、と思います。でも、妻子がいるなら、自分が殺されるときになんで腹心に妻子をよろしくな、じゃなくて母さんよろしくな、しか言わなかったんだろう?カトリックの場合は聖職者が独身であることについて時々「イエスさまが独身だったから」という説明がされることがあるけど、私はそれ以外に聖職者が独身であることに意味があると思うので、べつにイエスさまが妻子持ちでも困りません。
2005.10.07
閲覧総数 32
-
18

二人称
病人のためにどう祈ったらよいか考えるにあたり、googleで「病人のための祈り」を検索した。たくさんでてきたが、そのなかで爆笑フレーズが。「心と体をいやしてくださる主イエス・キリストに結ばれて 苦しむ人々に約束されているあんたの慰めと励ましを得ることができますように。」いや、単にタイプミスでしょうが。ローマ字入力で、Aをひとつ打ち損なったんでしょう。しかし神に「あんた」とは思いもよりませんでした。これだから日本語はおもしろいよ。英語ではこうはいきません。だれかれかまわずyouです。ちょっとつまんない。日本語では、どういう代名詞を使うかで、関係を確認できるんですね。
2007.02.08
閲覧総数 18
-
-

- ☆ ひ・と・り・言 ☆
- 高市首相、台湾有事での 「集団的自…
- (2025-11-27 19:41:44)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 京セラ_ペッパーミル_毎日のことだか…
- (2025-11-27 14:05:08)
-
-
-
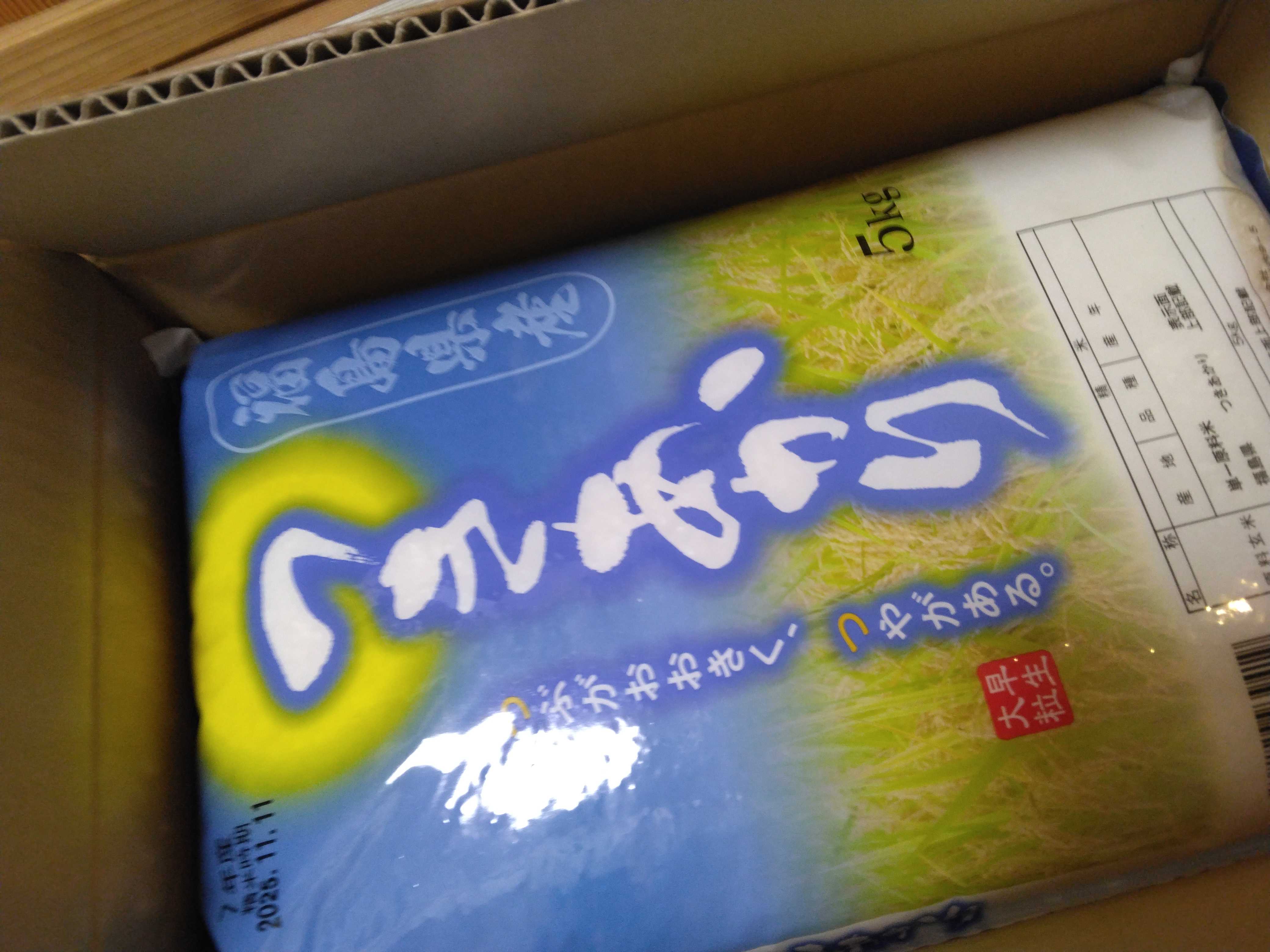
- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 米届いた 福島つきあかり8980円
- (2025-11-27 14:17:51)
-







