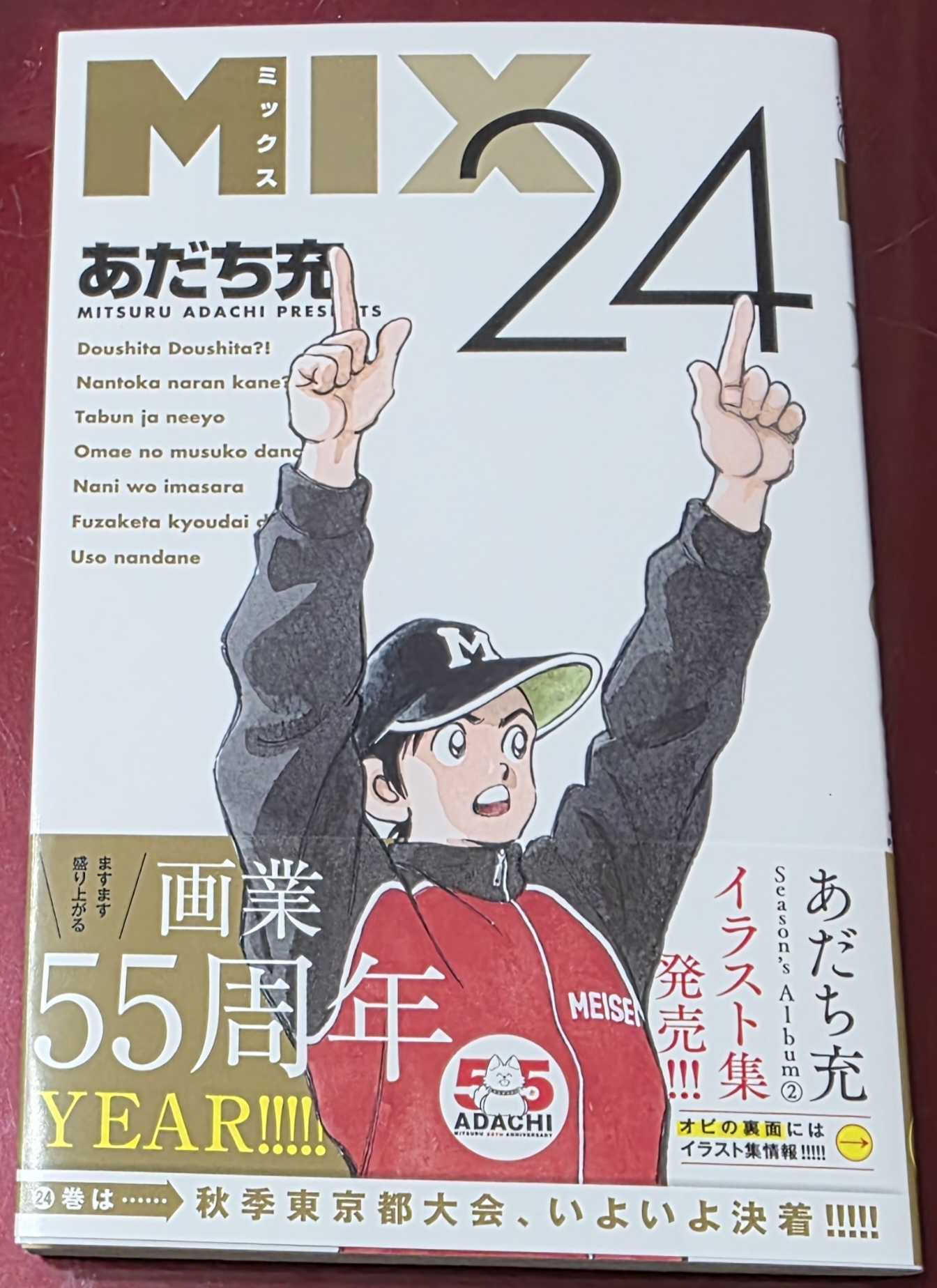2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2008年01月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

最短で結果が出る超勉強法 荘司雅彦
著者の荘司雅彦は81年、東京大学法学部卒業、日本長期信用銀行入行。85年、野村證券投資信託入社。86年9月末に退社し、翌10月、ゼロから司法試験の勉強を始める。独自の勉強法を考案して、88年、当時としては最速のペースで司法試験合格。91年、弁護士登録。その卓越した独特の、しかし十分な実績のある勉強法を惜しみなく書き下ろしているお勧めの一冊。この本の主なポイントは以下のとおり。第1部 スタートはモチベーションアップが大切だ! 一冊の基本書にすべての 情報を集中させよう 分量が少なく わからない部分は気にしない 何回も回転させる 読んでわからなければ著者が悪い 合格体験記は常に手元に 行き詰まったら読む 情報は基本書の余白に書く 問題を解くときに基本書の該当箇所に戻る 道具選びは機能性と オシャレ性を重視しよう A4サイズ30穴のクリアファイルに入れる 酸素エアチャージャー 速読ソフト 瞑想用CD 強力な勉強仲間を作ろう 最も効果的な勉強法は「誰かに教えること」 人に教えることにより自分の理解度は伸びる 勉強仲間と協力関係を築いた方が合理的 ダメな人と傷をなめ合うのは論外 「試験を目標にする」のは とても効果的だ 人間は簡単に決意し、簡単に挫折する 試験を受けると決めてしまう 勉強の最大の妨げは「自分が設定する限界」 自分に限界があると思ったら伸びない 有名大学の出身者は、効率的な勉強を知っているだけ 「成功のイメージ」を潜在意識に刷り込もう 潜在意識の活用で効率アップ 科学的に証明されていないものを否定するのは傲慢 天動説を信じていた人と同じになるかもしれない 脳は無意識に課題に取り組んでいる 具体的なイメージを潜在意識に送り込む ベンツに乗る 大邸宅に住む 毎晩思い浮かべる 重要なポイントはとことん考える癖をつける そうすれば、ふとアイデアが浮かぶもの 勉強こそ若返りに最適である 自己投資の勉強をすれば、「脳力」向上につながる 効果もツールを使った場合に比べ何倍も大きい 勉強することにより脳が活性化する 学校等へ行けば環境の変化と 交友関係の広がりができる 試験の結果により感情に大きな弾みができる 目的を達成のポジティブな心は老化を防ぐ 「勉強は絶対的な善である」 自分で自分の限界を設定するな しっかりした習慣があれば、 学習効果に年齢は関係ない カーネルサンダースは60歳で起業 忙しい、いつかやるは「うそ」 いつかは永遠にやってこない 今始める以外に勉強はスタートできない 限界を決めれば、後は死を待つのみ第2部 続ける秘訣は「楽しく勉強すること」にあり! 自分の心に「ご褒美」を与えよう 学んだことを「長期記憶」 として定着させよう 記憶保持作業 覚えてから数時間以内 記憶喚起の復習 1日、1週間、1カ月後と空ける 学習後5分間反芻する 黄金の記憶保持作業 就寝前の見返し 前々回のことを復習 10個まとめてよりすきま時間に少しずつ 複数科目を織り交ぜる 記憶作業を続ければ記憶力は良くなる 記憶作業はやればやるほど効果があがる 詰め込みと丸暗記は「善」だと思え 暗記が進めば理解が後から着いてくる 暗記した翌々日に復習 一週間後に二度目の復習 問題をひたすら解くうちに記憶と理解がついてくる 勉強の時間帯は気にするな! 眠気をこらえる⇒全く頭に入らない 勉強をしている間は脳を活性化させる 脳がベストコンディションの時に行うべき 不調の時でも簡単な問題をやるなどして ペースを乱さないようにする マトリクス計画表が効果を倍増させる 「総必要時間」と「処分可能時間」を計算する 低優先度のことを捨てる 計画表を作れば「勉強の浮気心を封じる効果」がある 気分のムラを防ぎ、やることの「迷い」を排除できる 試験勉強は少なくとも3回転 3か月であれば 長期回転;2か月 中期回転;3週間 短期回転;約10日 記憶が保持できる 見直しにより、全体像が把握できる 右脳のパワーを徹底的に利用しよう 人の目は無意識にヴィジュアル化 それにより右脳は絶えず活性化 活字情報を読み手が右脳でヴィジュアル化 右脳経由でヴィジュアル的にインプットされれば長期間記憶が定着 右脳を活性化する方法 絵画、デザインを意味を考えずに見る 歌詞のない音楽を聴く第3部 一気に成果を上げる最強のヒント 「突っ込む癖」で論理力を養おう 何かに対し自問自答を行う 常に「なぜ?」と突っ込み考える習慣をつける 論理力は自分の頭を使わなければ伸びない能力 五感をフルに使って勉強しよう 暗記、詰め込みだけでなく、アウトプットも重要 「他人に教える」のは優れた口頭でのアウトプット 人に教えることにより、自分の理解不足がわかる わかりやすく説明することは、 本当に内容を理解していなければ できないこと 問題を解くことは手を使うアウトプット あれこれ書いて試行錯誤する 勉強;頭脳労働 理解 定着 試行錯誤 作業;頭を使わない 線を引く マーカーする 教材は「迷ったら買い」を肝に銘じよ 時間と効率のために金を出し惜しんではならない 買わない本が何かの拍子に必要になることはよくあること 資格や学歴は取れるときに取っておこう
2008/01/31
コメント(0)
-

レバレッジ・リーディング 本田直之
本田直之氏躍進のきっかけとなったレバレッジシリーズ第一段のレバレッジ・リーディング。ビジネス書は、成功者の体験やノウハウを短時間で疑似体験できるツールであり、その多読こそが最高の自己投資であるとし、著者独特の読書術を紹介。コンセプトは「多読」である。この本と出合い、自分なりにレバレッジメモ(本書参照)を作成し始めた思い入れのある一冊。そうこのブログにはいろいろな書評を書いているが、皆この本がきっかけなのだ。この本のポイント(レバレッジメモ)は以下のとおり。・汗水たらし、血のにじむような努力をした人の数十年分の試行錯誤の軌跡が、ほんの数時間で理解できるようにほんの中には情報が整理されている。・他人の経験や知恵が詰まった本というのは、とんでもなく安価で割安なもの・レバレッジをかければ少ない労力で、大きな結果を出すことができる・本を読んで、そこに書かれているノウハウを自分流に応用し、実践で活用すること・インプットだけでは、自己満足にすぎない。いかにアウトプットするかが勝負である・本を読む時間がないのではない。本を読まないから時間がないのである。本を読めば読むほど時間が生まれる。・世の中が変化し続ける以上、読書で身につけた知識も常に古びていく運命にある。・意識して自分に新しい刺激を与えていかないと、自分のやり方に固執したり、視野が狭くなってしまう・柔軟な精神を維持し、新しい知識や考え方を吸収し続けるためにも、多読を習慣にするべき・無理して難しい本を選ぶ必要はない。とっつきやすい、わかりやすそうな本を読めばよい・多読には、たくさんの本を読むことで、複数の意見を同時に参考にできるメリットもある・アマゾンの中見検索で、読みたいキーワードの本を探す・読み始める前に、この本から何を得たいかを予めイメージしておけば、たとえ読み飛ばしても大事なところに差し掛かったとき、何かひっかかることを感じる・目的があると、自分の持っている課題や目的と照らし合わせて、役に立つことを要領よく拾うことがでる・100項目すべて抜き出し、1つも身に付かないよりは、重要な1つの項目だけ抜き出してそれを実践する方がリターンが得られる・レバレッジリーディングは投資活動。単に本を多く読みこなすのではなく、自分の課題や目的、目標にとって必要な情報だけ得られれば、それで十分。完璧主義を捨てること。それが第一歩。・本は万人向けに書かれているもので、自分1人だけに書かれているものではない。100%自分にとって必要なことがかかれているとは限らない。・まず本全体を俯瞰する(1)著者をチェック(2)帯、カバーの表ソデ、まえがき、目次、そしてあとがきを読む(3)そして本を読む目的を再確認する・1ページ目から読み始めず、この一手間をかけることで、格段に効率的な読み方ができるようになる・良い本をじっくり読むためには、無駄な部分は切り捨てる・速読ではなく、読むスピードに緩急をつける(重要な箇所はゆっくり、それ以外は猛スピードで)・複数の本の中に、どこかで読んだような手法や考え方が何度も出てくることがある。多くの人がそのノウハウや考え方について述べるということは、それが原理原則であるということの証拠。(これも多読して初めてわかる)・せっかく投資した読書の時間とコストを回収するには、「読書後のフォロー」を行うことが絶対に必要・メモをすることで記録に残し、実践に使う。メモの内容を自分の中に刷り込み習慣化することで正しいやり方を身につけたり、実践のプロセスでメモしたことがそのまま使えるか使えないかも把握できる・そうした反復をしながら、自分に現実に合うようにアレンジし、その洗練されたノウハウが結果を伴うようになる・良書との出逢いが特別な体験で終わらないよう、条件反射的に現実のビジネスの場で生かせるよう、読書をシステム化すること・自分の課題、目的を絞り込む⇒読むべき本を絞り込む⇒重要な箇所に印⇒レバレッジメモに要点抽出⇒実践で試す⇒レバレッジメモをブラッシュアップする⇒実践で条件反射的に対応できるようにする・このような行為の積み重ねを「パーソナルキャピタル(自分資産)」を増やすこと。・同じような課題をかかえる人にメモの内容を伝える(言葉をおごる)・知識労働者は、自ら教えるときに最もよく学ぶ(P・F・ドラッカー)本を読む時間がないのではない。本を読まないから時間がないのである。私の一番気に入っているフレーズである。
2008/01/30
コメント(0)
-

レバレッジ・シンキング 本田直之
本田氏のレバレッジシリーズ第三弾である「レバレッジシンキング」。「努力するのに成果が上がらない人」と「余裕を持ちながら大きな成果を上げる人」の違いはレバレッジの考え方にある。必要なのは「労力」「時間」「知識」「人脈」の4分野への自己投資。スポーツ・経営・投資・脳科学の方法論をベースに自己啓発に応用した仕事術を紹介する。訓練不要で誰にでも実践できるノーリスクのシンプルな方法論が書かれている。以下は主なポイント。第一章 常にレバレッジを意識せよ・レバレッジ・シンキングとは「労力」「時間」「知識」「人脈」にレバレッジ(てこの原理)をかけ、”Doing more with less"(少ない労力と時間で大きな成果を獲得する「DMWL」)を実現するというもの・パーソナルキャピタルを増やすと同時に、マインドも高めていかなくてはいけない・注意が必要なのは、パーソナルキャピタルには目もくれず、マインドだけ高めてしまう人がたくさんいるということ。・ビジネス書を多読したり、読むのが好きでも、成果が上がらない人がたくさんいる。・その理由は、マインドが高まってもパーソナルキャピタルを増やす努力をしないから思うような成果が上がらない。マインドは資産ではない。残念ながら空回りするだけ。思い切りアクセルを踏み込んでいるのに、「労力」「時間」「知識」「人脈」というタイヤが4つとも外れているため、前に進んでいないのだ・パーソナルキャピタルとは、「労力資産」「時間資産」「知識資産」「人脈資産」。ビジネスパーソンが仕事で成果をあげるよう自己投資することで構築される・パーソナルキャピタルを増やし、これにレバレッジをかける。少ない労力と時間で大きな成果を獲得する。これがレバレッジ・シンキングの基本的な考え方。・ゴールを明確に描く最大のメリットは、選択力が身に付くこと。自分にとって何が大切で、何が大切でないかがわかるようになる。余計なことをしなくなり、時間、労力、お金の無駄が無くなる・チャンスは誰にも均等にあり、それに気づけるか、気づけないかは、どれだけ明確にゴールを描けたかにかかわってくる・パッシブ(受け身)でなくアクティブ(能動的)に行動せよ第二章 労力のレバレッジ・労力のレバレッジのポイント(1)仕組化;再現性があり、繰り返せる。次回から行動するときに一から考える必要がない(2)無意識化・習慣化;精神力が弱かったりしても、いちいち考えなくても行動でき、継続しやすくなる(3)KSF(キー・サクセス・ファクター)を見つけ出す(4)二毛作、言葉のレバレッジ、エクササイズのレバレッジ等その他のレバレッジ・うまくいった方法を仕組化すれば、いつでも誰でも再現することができる・仕組化には、余計に時間、労力がかかるが、それによって先々継続してリターンを生むことになる・マニュアルの本来の目的は、一定の仕事レベルにまですべてのスタッフの能力を引き上げること・時間を短縮し、最短ルートを通るためのツール・仕組化する部分は仕組化し、それ以外のことに頭を使えるようにする・チェックリストが重要なのは、それに沿って仕事をしていけば抜けがないし、やらなくてはいけない全体の作業ボリュームもわかる・時間の節約にもつながり、誰かに仕事を依頼する場合も、全体像とやるべきことがわかっているので時間の無駄がなくなる・うまくいっている人を見ると、良い行動を無意識に行っている。いわば習慣化している・習慣化という方法は、自分をコントロールすることが苦手な人や、飽きっぽい人間には便利・考えると行動に移らない。習慣にしてしまえば、自動的に身体が動くようになる・人間の行動の、実に95%は無意識のうちに行われている・いきなり大きな習慣を身につけようと思わず、小さなことからやり始める、あるいは意識する・小さな習慣を身につけていくと、良い流れが生まれる。「良くしていこう」という意識がベースに生まれると、やがて大きな習慣もできるようになる・小さな雑用を毎日積極的に片づけていると、その程度のことなら面倒くさいとは感じなくなってくる。同時にイライラも抑えやすくなる。これは脳の中で、感情系に対し思考系の支配力が強くなったことを意味している。・そうしたら、もう少し困難な問題に取り組んでいけばよい。そうやって脳の体力を高めることから始めていくと、無理なく、問題解決能力の高い人になっていくことができる・よい習慣を身につけるために、習慣チェックリストを作成し、習慣を常に意識し、定着させることが必要・効率が悪く、成果が上がらず時間がかかってしまうことの原因の一つは、ポイントがずれていることにある。・ずれていることを必死にやっていても成果にはつながらない・成功へのカギを握る要素=KSF;キー・サクセス・ファクターを見極める能力が必要・KSFの見つけ方は、始める前にどうすれば良いか、その最短距離を考えて行動する。これこそが成果を上げるために最も重要な能力の一つ・労力のレバレッジでは、一つの物事をするときに、同時に何かできないか考える。これが二毛作でのさらなる効率化である・歩きながら耳勉する。会議の空いた隙間時間で簡単な仕事をこなす、、、等・労力のレバレッジは、「自分はできる」と思うことが重要。「できない」とか「無理だ」と思ったり、言葉にしたりするとマイナスのレバレッジがかかる・いくら疲れていても、土日にごろごろしていては、かえって月曜日はだるくなり、効率が落ちる。第三章 時間のレバレッジ・時間があるから成果が上がらない。意図的に時間を短くして成果を上げるようにする・知識労働社会では、時間を積み重ねれば積み重ねるほど成果につながるということはほとんど無く、実際にはある程度までは達するが、その後は一定になる・時間をためることはできないが、レバレッジをかけて増やすことはできる。時間を投資することで時間資産を増やす・これが軌道に乗ると、そこから不労所得的に生まれる余裕時間で更に再投資し、DMWLを実現し、成果を拡大することができる。・俯瞰逆算思考;まずゴールを決め、現状からゴールまでを俯瞰し、逆算思考でタスクを決める・ビジネスで成功している人は、その殆どがまずゴールを設定している・はっきりしたゴールがないと、「やるべきこと」「やらなくてよいこと」というタスクの選択ができなくなる・すべての仕事が大切に思え、あれも、これもやらなくてはいけないという状況になる・TODO;「やらなくてはいけないこと」・タスク;「自発的に請け負った仕事」・時間投資のもうひとつの方法は、時間割をつくり、時間のルーチン化を図ること・無駄な時間を過ごさないために、すぐに行動を起こさず、この仕組みづくりに時間を投資することがポイント・時間割のおかげで、次に何をやろうかという雑念が入ることなく行動に集中力を増し、常に平常心で、自分の持っている力を発揮させるベースになる・時間割を作ると「この仕事をやるのに○時間かかる」という発想から「この時間の中でこの仕事をやる」という発想に変わる・逆にい言えば、時間割なしでは、その日の出来事に流されてしまう・給与天引きの積立と同じように、時間割をつくってブロックして、自己投資の時間を決めてしまえば、残った時間で仕事をしようという発想になる・自由時間<全体の時間-固定時間(ルーチンワーク、mtg、睡眠、食事、通勤等)>を削って仕事をするということは、自己投資に費やす時間を減らすということになる・すると固定的にかかる時間が増えていくことになる。それではいつまでたっても楽にはならない第四章 知識のレバレッジ・労働人口6542万人に対し、年間ベストセラーとなるビジネス書はだいたい30万部。労働人口のうちビジネス書を読んでいる人は0.64%にすぎない・知識への投資は単なる勉強ではない。あくまでも投資であるから、リターンを得るために行う行為。常にリターンを追及するROI(投資収益率)意識が必要・ノウハウがなぜ必要かというと、現代が時間不足時代に突入しているからである・なぜ多くの成功者の前例に学ぶのか。実は、現状からゴールまでを俯瞰し、逆算すると、多くのやるべきことが見えてくる。・限られた時間の中で成果を上げるには、他者から学ぶのが一番よい・一冊や二冊読んだだけでは足りない。できるだけ多くの本を効率よく読み、多くの人の成功のプロセスを吸収することが大事・これにより累積効果が出て、パーソナルキャピタルの「含み資産」がどんどん増えていき、条件反射的に実践で必ず活用できるようになる・読書を始める前には、まず読書は問題解決のために行うものと意識する・たとえば、「自分の人生の目標は何か」「現状の課題は何か」という目標を持つ。すると今の自分に必要な本がわかる・大事なのは、本から得たノウハウをレバレッジメモにまとめ、繰り返し読んで条件反射的に行動できるようにし、実践でどんどん活用すること・読んだだけでも実行しなければそれで終わり。インプットするだけでは、ただの自己満足にすぎない。いかにアウトプットするかが勝負第五章 人脈のレバレッジ・人間一人ができることは限られているが、人脈によってレバレッジがかかると、自分一人で出せる成果の何倍もの大きな成果を生み出すことができる・相手にお願いだけではだめ。大切なのは相手にどんなバリューを提供しているか。また誰を知っているかではなく、誰に知られているかである。・人脈づくりは短期ではなく長期投資である・人脈をつくるうえでの基本は、相手にコントリビューション(貢献)すること・人にあう前に、まず相手に興味を持つ。相手のことをきちんと知らないのに、会ってもらおうとするのは間違い・自分よりマインドの高い人、マインドの高いネットワークに加わることによって、それに影響され、自分のマインドも上がる
2008/01/30
コメント(0)
-
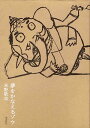
夢をかなえるゾウ 水野敬也
「変わりたい」と願う主人公の「僕」が、インドの神様「ガネーシャ」が出す課題を、毎日ひとつづつこなしていくストーリー。ガネーシャの出す課題の一つ一つは一見簡単なものばかり。しかしこれらは人生を変えるだけの大きな効果を持つという。自己啓発書を読みあさるものの、今ひとつ実行できなかったり、成果に結びつかない私向きの本だ。(しかしガネーシャの課題は未だやっていない。だからだめなんだ...とわかっているのだが)ガネーシャの課題は以下のとおり。原文はほとんどが大阪弁。・靴をみがく自分を支えてくれるものを大切にしなさい・コンビニでお釣りを募金する世の中の人を喜ばせたいという気持ちを素直に大きくしていくことが大事。だから寄付をする。自分はとにかく人を喜ばせたい、助けたい。そういう人間になることだ。・食事を腹八分目にする食べたいと思っても腹八分目で必ずおさえる。そうやって自分をコントロールすることが楽しめるようになったら、生活が変わってくる。・人が欲しがっているものを先取りする「ビジネスの得意な奴は人の欲を満たすことが得意な奴」。人はどんな欲があって、何を望んでいるか、そのことが見抜けるやつ、世の中が何を求めているかが分かるやつは、事業を始めてもうまくいく。・会った人を笑わせる笑わせるということは、「空気を作る」ということ。場の空気が沈んでいたり暗かったりしても、その空気を変えるだけの力が笑いにはある。いい空気の中で仕事をしたら、いいアイデアも生まれる。・トイレを掃除する人がやりたがらないことをやるからこそ、それが一番喜ばれる。一番人に頼みたいことだから、そこに価値が生まれる・まっすぐ帰宅する会社が終わったら自由だから遊んでもいいというわけではない。むしろ逆で、自分が成功していくための「自由に使える使える大切な時間」である。・その日頑張れた自分をホメる毎日寝る前に、自分がその日頑張ったことを思い出して「よくやった」とホメる。そうやって頑張ったり成長することが「楽しこと」だと自分に教えてあげることだ。・一日何かをやめてみる時間がぱんぱんに入った器から何かを外に出す。そうしたら空いた場所に新しい何かが入ってくる。人生を変えていくというのはそういうイメージだ。・決めたことを続けるための環境をつくる本気で変えようと思ったら意識を変えようとしたらだめだ。意識でなく「具体的な何か」を変えなければダメ。・毎朝、全身鏡を見て身なりを整える意識や内面を変えるのは難しい。でも外見は変えられる・自分が得意なことを人に聞く自分の仕事が価値を生んでいるかを決めるのはお客さん。つまり自分以外の誰かだ。・自分の苦手なことを聞くこの世界に闇がなければ光も存在しないように、短所と長所も自分の持っている同じ性質の裏と表になっているものだ。人に会うのが好きな奴は、一人の作業に集中することが苦手。またその逆もしかり。・夢を楽しく想像する誰に言われるまでもなく、勝手に想像してワクワクするのが夢だ。考え始めたら楽しくて止まらなくなるのが夢だ。・運が良いと口に出して言う自分にとってうれしくないことが起きても、嘘でいいから「運が良い」と思うこと。そうしたら脳みそが勝手に運が良いことを探し始める。自分に起きた出来事から何かを学ぼうと考え出すのだ。そうやって自然の法則を学んでいくのだ。・ただでもらうどんな小さなことでも、安いものでも、とりあえず何でもいいからただでもらってみること。それを意識していたらコミュニケーションが変わってくる。言い方とか仕草一つとっても気を使うようになる。・明日の準備をする一流の人間はどんな状況でも常に結果を出すから一流だ。常に結果を出すには、普通に考えられるよりずっと綿密な準備がいる。・身近にいる一番大切な人を喜ばせる人間は不思議な生き物だ。自分にとってどうでもいい人には気を遣うくせに、一番世話になった人、つまり自分にとって一番大事な人を一番ぞんざいに扱う、例えば親だ。・誰か一人の一番いいところを見つけてホメる成功したければ誰かの助けをもらわないと無理だ。それがわかっていれば、人をホメるということは、大事かというレベルを超えて呼吸をするレベルでやること。二酸化炭素を吐くのと同じくらいナチュラルにホメ言葉を使うこと。・人の長所を盗むマネをするのはお客さんを喜ばせること。それを考えたら恥ずかしさなんか感じない。早く成長し早く技術を覚えてもっと多くの人を喜ばせたいと思うことが何より大事。・求人情報誌を見る自分で「これだ」という仕事を見つけるまで探し続けなければいけない。仕事を間違えたら、それこそ一生を棒に振ることになる。・お参りに行く成功したいと思う人は何でもやってみることだ。可能性があることは何でも実行することだ。馬鹿馬鹿しいとか意味がないと言ってやらない人は結局そこまでして成功したくないということだ。・人気店に入り、人気の理由を観察するお店は優れたサービスを学ぶ場所でもある。その店がどんなことをしてお客さんを喜ばせているか観察せよ。・やらずに後悔していることを今日から始めるみんなやりたいことをやって後悔しない人生を送った方が幸せになると知っている。でもやらない。収入、世間体、不安。人を縛る鎖はみんな同じだ。今まで無理だったらこれからも無理。変えるなら「今」だ。「今」何か一歩踏み出さないと。でなければ、やらないまま死んで行くだけだ。・サービスとして夢を語る多くの人が聞きたい夢は、世の中がそれを実現することを望んでいるということ。であればその夢をかなえるのは簡単だ。みんなが応援してくれる夢だから。・人の成功をサポートする自分が本当に成功したかったら、その一番の近道は、人の成功を助けること。・応募する可能性を感じるところにどんどん応募すれば良い。そこでもし才能が認められたら、人生なんてあっという間に変わる。・毎日、感謝するお金も、名声も、地位も、名誉も自分で手に入れるものではない。お金は他人がくれるもの。名声は他人が認めたからくれるもの、全部他人が与えてくれるものだ。世の中を形づくっているものに何でもいいから感謝する。足りていない自分の心を「ありがとう」という言葉で満たす。ありがとう、ありがとう、みんなのおかげで私は満たされています、そうやって感謝するのだ。
2008/01/28
コメント(0)
-

続ける技術 石田 淳
英会話、各種試験勉強、日記・手帳術、禁煙、ダイエットと継続しなければ意味がないものばかり。ある時「やるぞ!」と決意するが、なぜか長続きしない。三日坊主も100回続けば300日だが、あまり意味はないだろう。本書にある「行動科学に基づいた『物事を継続させるための』セルフマネジメント手法」は、意志の弱さや性格、精神論や根性とはまったく無縁のもの。 ・ある行動を増やす・ある行動を減らすこの「行動のコントロール」をすることで、ものごとは継続していくとのこと。 本書では、物事が長続きしない理由を解き明かし、行動のコントロールのポイント、さらに継続のためのコツを紹介している。 本書のポイントは以下のとおり。 続かない理由 やり方はわかるが継続の仕方が分らない やり方がわからない ターゲット行動 増やしたい行動 減らしたい行動 行動の二つのパターン 不足行動を増やす 英会話 筋力トレーニング 過剰行動を減らす 禁煙(たばこ) ダイエット(甘いもの) 不足行動 増やしずらい理由 すぐに成果を確認できない 長く続けなければ成果を得られない 邪魔する行動 ライバル行動 TVを見る とても魅力的 マンガを読む なぜ負けるか すぐ望む結果が得られる とても簡単 習慣化されていない 過剰行動 減らない理由 努力なく簡単に継続できる たばこを吸う 甘いものを食べる 快感やメリットがすぐ確実にとれる 邪魔する行動 残念ながらない 行動に着目する 条件を整える ターゲット行動の発生をコントロールする ライバル行動の発生をコントロールする 行動の構成要素 A先行条件(直前条件) B行動 C結果条件(直後条件) ターゲット行動を増やす 行動のヘルプを作る ターゲット行動が発生する可能性を高める いつも本を持つ トレーニングウエアを用意する 動機付け条件を作る 行動したときのメリットを考える ほめられる ご褒美を与える 行動のハードルを低くする ターゲット行動を行いやすくする マンガをしまう ターゲット行動を減らす 行動のヘルプを取り除く 煙草を捨てる コンビニに寄らない 動機付け条件を取り除く 飴などのチェンジ行動を探す テレビを録画する 行動のハードルを高くする 煙草を捨てる 買わない
2008/01/27
コメント(0)
-

無理なく続けられる年収10倍アップ勉強法 勝間和代
無理なく続けられる年収10倍アップ勉強法/勝間和代これは著者の勝間氏が新入社員から本作執筆時の38歳までに年収を10倍にした勉強法が書かれている。大卒の新入社員なら年収は500万位とすると5,000万円か。すごいものだ。勝間氏は史上最年少で公認会計士に合格するなど、もともと地頭はいいのだろうが、勝間氏ならではの工夫が懇切丁寧に書かれている。なによりも関心するのはこだわり。とことんより良いものを追及する姿勢は大いに見習いたい。本作の主なポイントは以下のとおり。 はじめに 勉強で大事なのは 続かせる仕組みづくり 意識づくり 勉強するほど幸せになる という成功体験をつくる 勉強に共通する5つのコツ (1)基礎を最初に徹底的に学ぶ (2)先達から勉強の仕方をしかり聞く (3)学ぶ対象の基本構想を理解する (4)学んだことを自分の言葉でアウトプットする (5)勉強をわくわく楽しむ 勉強へ自分を自然と追い込み、 習慣化させる仕組み 人間の仕組みは、 目先の緊急を優先させる 収入の5~10%を勉強に投資しよう「基礎編」 1.なぜ勉強るすのか 自分が幸せになる ために勉強しよう 格差社会を 生き延びるため 親が勉強すると子供も それを見て育つ 2.なぜ勉強が 続かないのか? 勉強しないツケは確実に回ってくる 必然性に基づく続く仕組みをつくる 勉強の成果をまめにアウトプットする 3.まずは道具を揃えよう 「書斎を持ち歩く」 仕組みを作る ノートパソコンを用意する 速読術で成果を5倍速く出す マインドマップで頭の中を整理 4.勉強の基本的なコツを知る 基礎を最初に徹底的に やれば後が早い 半年間、基礎学力を つけることに集中する 短期間に結果を 出す人に共通 今やっていることを 将来ビジョンとつなげる 先達から、勉強の仕方を聞く 勉強の仕方を聞く 内容を聞くのではない まず「マネ」から入る 学ぶ対象の基本理念 を理解する 何のために存在するのか 英語は異文化の人たちがコミュニケーションを 交わすことができる言語 したがって文法は簡略化され、 日本語より文法が大事 仕事の基本思想を理解し、 求められる能力を要素分解するスキル 学んだことを自分のことばでアウトプットしてみる インプットとアウトプットに 勉強時間を半分ずつ使う アウトプットして初めて、 本当に理解してるかわかる 言葉に表現できなければ、 実はまだよく分かっていない 勉強をわくわく楽しむ 世の中のパズルを埋めている実感 これからは自分で勉強のスキルを 身につけないと生き残れない 5.目でする勉強 本・新聞・雑誌・ネット 本は乱読でよい。 量が勝負とひたすらインプット 一定量を超えた瞬間、 ある日突然にわかるようになる 問題意識を持って、 質の良い情報を乱読する テレビは時間当たりの情報量が 少ないので時間の無駄 6.耳でする勉強 隙間時間には耳での勉強 耳は使える時間も長い 7.目と耳で勉強する 8.学校に行ってみる 9.「勉強の仕組み」を 投資しながら組み立てる 勉強法で差別できるのは道具とやり方 すぐに現れなくても、ある日突然、成果が出る ITを使った効率的な方法を準備 基礎を強化し、成果を確認することで 自分の成功体験にする「実践編」 10.何を勉強すればいいのか? 明日から仕事に使えることを勉強する 最新セールス手法をより早く 身につけるにも英語が必須 アメリカの方がマーケティング、 セールスでは進んでいる 共感や感動を軸にした エモーショナル・マーケティングが発達している 問題意識を持って仕事をしていれば、 勉強のテーマは自然に出る 自分の仕事のリテラシーを 高めるために勉強する 理解する能力、知識 資格試験が大事なのは、 学歴と同じ役割を果たすから 11.英語 目指せTOEIC860点 英語ができると、 全世界が市場になる 1.2億人⇒65億人へ 日本だけ扱う会社に 比べ顧客数が違う ボキャブラリー力を上げる 読めないものは聞けない 英字新聞や雑誌を読みあさる ヒアリング力を上げるには、 ボキャブラリーを上げる必要あり 発音は、リスニングで直す 量が大事 12.「さおだけ屋」を 超える知識とは? 会計はビジネスの言語 財務諸表はサラリーマンの必修科目 会計の構造がわかっていると、 ビジネスの本質がつかめる 会計は、英語よりハードルが低く、 強力な武器となる 13.IT みんなに 頼られるエキスパート 生産性の高い企業は、 IT投資額が高い 創造的な仕事も、ITをいかに 使いこなすかにかかっている ITは現代の読み書きそろばん 14.経済 日経新聞の 裏を読める 経済学はライバルが少ない 東大に商学部がない 15.転職 身につけたものを お金にしよう 16.資産運用 勉強内容が 収入に直結する 資産運用の方法を知らない人が多い やり方がわかれば誰でもできる 17.さぁスケジュール帳に 予定を入れましょう あとがき無理なく続けられる年収10倍アップ勉強法/勝間和代
2008/01/26
コメント(0)
-

破壊的トレンド 渡辺弘美
ニューヨーク在住の著者が、アメリカIT分野の動向や技術動向を調査する仕事の中から、日々膨大なニュース、ブログを読み、全米各地で行われるカンファレンス参加、シリコンバレー、ニューヨークの注目企業の訪問の中から蓄積したIT界のトレンドを紹介。ネットによるボーダレス化を背景に、IT分野の新たな潮流が日本にも迫っているという危機感と新たな潮流を生み出せるという可能性に期待し記した渾身の一冊である。日本のこれからの姿でもあるかも知れないアメリカのIT界トレンドを知る内容の充実した本。記述も平易であり写真も多く読みやすい。文末にも記載しているが、アメリカだけでなく日本からもこのような先端技術を世界に先駆けて発信できる技術者の育成も急務であろう。 0.破壊的トレンドとは何か 数多くの破壊的なイノベーションの登場 その背景にあるユーザー・エンパワーメントへの時代変化 1.ダイレクト ユーザーを直接つかみ、ロックイン ユーザーがネット中の情報と直接つながることを好み、 またネット側もユーザーと直につながることを求めている ユーザーが欲しい情報を探してウェヴサイトを さまよっていた環境を塗り替える可能性を秘めている 企業とユーザーを直結する「フィード」feed 米国でホットなウィジェット(Widget) 顧客のもとへ出向くためのツール 2.フリー 「潤沢経済」時代のビジネス 情報技術(IT)の資源当たりの 単価が無料(フリー)に近くなり、 「潤沢時代」の時代に突入した DVDレンタル→オンラインDVD配信 ウォルマート→アマゾン 情報技術資源が限られていいた 「稀少経済」の時代が終焉を迎え、 ユーザーへ主導権が変移 原則禁止→原則自由へ 自分(企業)でなくあなた(you)が 最も良いものを知っているという ボトムアップの立場 管理不能 とりあえず製品をリリースするという β版的なアプローチに舵を切った方が良い 3.クラウドソーシング みんなの知恵を利用する 他人任せになるならば、必然的にアウトソーシングという概念に帰結する 「潤沢経済」下では豊富なインフラを生かし、 面識がない多くの人の知恵や知識を 活用することが可能になる 大衆の知恵をビジネスにとりこむ クラウドソーシング(crowdsourcing) 大衆から知識や知恵を調達する クラウドソーシングの典型技術;ウィキ(Wiki)技術 ウィキペペディア;ウィキ技術の応用例 コンテンツ・レーティング;大衆からの評価を集める 集合知を取り入れるほどサービスが賢くなる サービスが賢くなればユーザーが増え、 情報が増えて集合知が集積する という好循環を形成する 4.プレゼンス リアルタイムな情報を生かす 新聞社のDBはストック型の情報 配信されない、されていても垂れ流しになっていたリアルタイムのプレゼンス情報が価値を持ち始めようとしている 今の私を伝えるプレゼンス情報 米国でホットなプレゼンス情報は2008年の大統領選に向けたキャンペーン 候補がリアルタイムに今を伝えている 位置情報を元に都市交通システムの 効率化を図ることができる 駅の入場者数に応じて 列車の本数を変える 従量制の自動車保険料 (GPSを使い、距離、時間帯、危険地域の有無で保険料高低) 5.ウェヴ・オリエンテッド すべてのサービスをウェヴ上で提供できるか ネットの登場でコミュニケーションやソーシャルネットワーキングのあり方が変容 知識習得や知の集積が国境を越えて容易に行われるようになった 更に手元のコンピューターで行っていた情報処理をネットワーク側で済ますことが可能に 開発が激しWEB OS PCは昔のダム端末(メインフレームから流れる文字列の表示機能のみ) WEB オフィス スイート戦国時代 グーグル ゼンター 6.バーチャル&リアル 「仮想」は「非現実」にあらず セカンドライフで火がついた仮想世界 3Dだけでなく、360度方向デジタル写真、3Dプリンター、拡張現実感(AR) 仮想と現実を橋渡しするテクノロジーが続々登場 デジタル・ネイティブ世代には非常にポピュラー 3Dプリンタ-で仮想世界からリアルな「モノ」を生む 7.ビデオ 映画やTVの行く末は ユーザーが製作した動画がIPに乗って世界を駆け巡るようになった 映画、TVの配信手段もネットを選択 大量に流れる膨大なコンテンツはメディアを、そしてユーザーをどこへ連れて行くのか IPTVアプリの開発競争は進む TVよりも携帯の日本の若者 8.インターフェース よりわかりやすく、使いやすく 人間の視覚に直接訴えるインターフェースが開発 文字情報中心の入出力インターフェースが破壊的に塗り替えられようとしている 人間とコンピュータをもっと近づける 情報の視覚化技術 IBM メニューアイズ データを16種類にビジュアル表現 電話による音声認識サービス 3次元加速度センサー Wiiリモコン Wiiリモコン+セカンドライフで訓練シュミレーター構築 マルチタッチスクリーン iPhone アナログデバイスのデジタル化 スマートペン レーザー光による仮想キーボード モノつくりは「ソフトウェア中心」の発想が必要 9.サーチ ポストグーグルの潮流 グーグルの「全世界のあらゆる情報を整理する」という野望は道半ば 次世代検索の3つのアプローチ 自然言語で可能な検索 検索結果の視覚化による「より良いUI」 特定分野の情報検索を得意とする「垂直型検索エンジン」 10.セマンティック・テクノロジー 意味を理解し始める時代へ コンピュータ-は入力情報の意味を理解していない 情報の意味や関連性を理解、それに基づいた処理を行うのがセマンティック技術 データの統合、情報検索、情報共有分野で大きな変革をもたらすと期待 「情報化社会」から「関連性社会」へ 11.破壊的トレンドの対処法 市場を塗り替えようとしている大きなうねりをとらえておくことが大事 海の向こうの出来事では済まされない 破壊的トレンドをつくり出すエンジニアの育成も重要
2008/01/26
コメント(0)
-

人に好かれる話し方 和田裕美
人に好かれる話し方/和田裕美著者の和田裕美氏は株式会社ペリエ代表取締役。営業コンサルタント。著書に「人に好かれる話し方」(25万部)、「売れる営業に変わる本」(20万部)などベストセラー多数。外資系教育会社日本ブリタニカで世界2位の成績を収めた。2001年のブリタニカ日本撤退に伴い独立し、株式会社ペリエを設立。現在は営業コンサルタントとして多業種での営業組織作りに携わる。今回はベストセラー「人に好かれる話し方」。とても丁寧な書きっぷりで、文章も平易なので気持ち良く読めた。最近は著者のCDを買うなど、和田裕美にはまってしまっている。人に好かれる話し方/和田裕美本書の内容は以下のとおり 第1章 基礎づくりから始めよう! 「やさしい空気にする」が基本スタイル 人には悪気はなく、無意識に相手に プレッシャーをあたえてしまう人がいる 本人は気付いていないことが多い 「売りたい」、「自慢したい」、「自信がない」心も ちょっとだけ深呼吸してから、そのことばかり意識 しないようにする 重要なことは安心の空気は信頼を生む 人が発する空気は、 ・第一印象 ・笑顔と動作 ・心 でできている 笑顔をいうのは口角をしっかり あげて「にこ―」ってすること マラソンより簡単に誰でもできること 「話せる人」ということは「一緒にいて楽しい人」 「共感ワード」を使うこと 思いやりのある嘘もあるかもしれない ちょっとだけ嘘も必要な時がある 第2章 トークはテクニックじゃない 大切なのは相手の話を聞きたいという気持ち 「共感していますよ」ということを いかに相手に伝えるか 相手が海の話をしたら、あなたも海を見る イメージの中で、相手と一緒に 海辺にいるのです 口に出して言うことで、お互いの イメージの中で共感してリンクする 謙遜している人の心理を読み、 本当に相手がほしい一言を返す 相手のほしいものは、他人の評価 からもらえる自信なのです 悩むような微妙な質問を するときは、遠慮がちにしてみる この遠慮感覚がとても大事 話す時には目的を決めてからスタートする スタートとゴールが決定していれば、 主軸から少々それても、中心軸に 戻ることができる 波縫い話法 TVで人の話を聞いてメモをとる習慣をつくる それを箇条書きで要点をまとめるトレーニングをする 人は自分を好きな人が好きである 一緒にいて楽しいと思ってもらえること 人は自分の話を聞いてくれる人が好きである 話せるということは、ちゃんと相手の話が聞けること 聞いて、聞いて、聞いて、話す こんな聞き方では相手がムッとしてしまう (1)たくさんのことが頭にあって集中できない (2)ついつい相手の話をさえぎって話したくなる (3)他の人の議論や意見に 反論したくなってしまう 否定と反論は簡単に誰でもできる (4)相手の話に興味が持てない 目の前のその人に興味を持つ (5)専門すぎて理解できない まずメモをとる (6)なんだか気が散る 必ず顔に出る 集中できない時は切り替えるしかない (7)最後まで聞かないで 結論を言いたくなる 相手の欲求不満状態を引き起こす (8)熱心に覚えようとして要領悪く聞いてしまう まずは八割理解から (9)人で判断して聞いてしまう 話の中身に耳を傾けた方が器が大きい 第3章 目の前の人のファンになる 「話すこと」が「幸せの種」になる 自分が相手からどう思われるかを気にするということは、 自分にベクトルが向いていて「自分を思う」気持だっていうこと 笑顔でいい空気をつくれば、少なくとも嫌われることはない 交友関係がスムーズに築けるひとは、 共通項を探し出すことができるってこと 会話に共通点を引き出すために、 ちょっとした知識があればいい 自分に向けてもらった関心というものがとても嬉しい 自分に向かってくれる人の方がやっぱり好きなんです 人から褒められればすごく自信が持てる 人から賞賛される意見を聞きたいと願っている 相手のすごさを無条件で認めることも、ほめ上手には大事なこと 素直に感じたままを表現すること 単純思考になるということ 相手をハッピーにする言葉が使えているか 相手のマイナスに目がいってしまうと絶対に損 話すと言い訳が多くなる人 今の状態を正当化するときに使う話し方 否定的な考え方をするせい 自分の都合に合わせようとすると絶対にダメ 自分の使う言葉には感謝を添えてみる 電話くれると「嬉しい」 怒る時は危険性と可能性を同時に見せる 第4章 話の内容をリンクさせていく 相手が楽しくなる言葉、テーマを選ぼう ボキャブラリーを増やすには、まず本、文字を読むこと 言葉には意味がある 「海」は「うみ」ではなく「広くて青くて深い、、、 暖かくて、冷たくて、塩辛いと五感の表現が必要 相手に「言葉」を「映像」で伝えることができる人は、 そうでない人よりも、明らかにボキャが多い たまには普段読まないジャンルの本や雑誌を 読むと新しいボキャブラリーが増える 話す時に一番大切なことは難しいことを簡単に話すこと 「知らないです。教えてください」って 言える人の方が本当はかっこいい もっと凄いのは、知っていることを知らないと言えること 聞き上手になってから話をするということは、 相手の聞きたいことを話すという構造が 出来上がるまでのステップです 第5章 声のトーンとリズムを変える 知らず知らずに「声」で損してませんか 早口は自分の回転のよさを 披露しているように見える人 頭の回転は早くても、思いやりや 機転が利かないってことです 語尾マシュマロ 最後の語尾をふわっとさせることで、 やさしくふわっとした感じになる 第6章 仕事のプロとしての話す力 「思いやりの松竹梅」で人とつき合う 事実は事実であっても事実だけでは人は納得しない 機械と話しているのではない 会話の中で大切なことは、相手への自分の気持ちを 会話の中にどうやって入れていくかっていうこと 人と人との空気、人の感情などを読み取る 能力が落ちてしまうのは、「人と話す機会がない環境」が そこに存在してしまうことに問題がある 話すということを「口」を使うだけだと思わないこと 目を使って観察し、耳を使って声のトーンを感じ、 身体を使って「言葉と動作」を組み合わせてみること 自分が何をしてほしいかよりも、 相手が何をしてほしいかに気が付く ことっていうのは、思いやりを持つという 意味です 思いやりの三段階のステップ 梅;自分がしてほしくないことを 相手にはしないという思いやり 竹;自分がしてほしいことを、 相手にしてあげる思いやり 松;相手が欲しいとことを してあげる思いやり 自分の思いではなく、 相手が中心なのが松の思いやり 相手が幸せになることを考える大前提に、 自分がハッピーであることが必要です 話し方というのは本当はノウハウではなく、 やはり「人間力」が大きな要素になる 否定的なことを否定する マイナスとマイナスを掛けるとプラスになる 第7章 もっと伝わる言葉の使い方 あなたの話し方にみんなが耳を傾けるようになる スピーチは、相手の話を聞く必要もなく、 「あいつは自分ばっかり話しやがって」と 思われることもない 今日伝えたいこと、それを伝えること によっての最終目的を明確に書き出す 今日伝えたいこと;わくわくすることの大切さ 今回の最終目的;聞いた人が元気になること 相手が幸せになってほしいと思う気持ちがあれば、 笑わせようと努力したり、面白い冗談を入れたり するわけです 説得力のある話し方 信頼される人であること ロジカルに話せること 事実はこう 中身はこうで 問題はこれで こうやればこういう根拠で解決できる 表現すること その場にいなくても目でみているような 視覚的イメージを言葉にのせて情景を話す 相手にとって得なことを相手の人が 自ら選ぶことを促すような「背中を押す言葉」です 相手の感情がむくむくと動いて、 あくまでも相手の意思で前に 動くことを選択すること 結論が先に来ると、これから相手に説明することが明確です人に好かれる話し方/和田裕美
2008/01/26
コメント(0)
-

印傳屋名刺入れ とんぼ
印傳屋名刺入れ とんぼ今月のJAFメイトに山梨の印傳屋の特集があった。そこに出ていた とんぼ模様の名刺入れにほれ込んでしまった。しかし名古屋では売っている店がなかったが、今日大阪のセミナーに行く時に心斎橋の直営店で名刺入れを購入した。とんぼは、前へ前へとまっすぐに進むことから、「勝利を呼び込む虫」と縁起がいいとされてるそうだ。印傳とは16世紀頃に印度(インド)から伝来し、日本人の美意識と創意工夫により育まれてきた染め革工芸。その技法は、戦国時代は鎧や兜、江戸時代には革羽織、莨(タバコ)入れ、巾着などに用いられ、粋なステータスシンボルとして持て囃されてきた。中でも甲州印伝は、厳選された最高級の鹿革を使用し、この柔軟で軽く強靭な鹿革に漆付けする独自の技法で、個性豊かな紋様を表現している。手触りもなかなか良い。品質の割には値段も手ごろ(名刺入れが4,725円)で、はっきりいってお勧めだ。買ったのと同じ色の名刺入れ財布も良い小銭入れも良いな
2008/01/20
コメント(0)
-

ファイナンシャルアカデミースペシャルライブ2008 本田直之×泉 正人
1/20(日)、日本ファイナンシャルアカデミー主催のファイナンシャルアカデミースペシャルライブ2008に行ってきた。場所は名古屋でなく大阪だったのだが、ベストセラー「レバレッジシリーズ」の著者である本田直之氏が登場することでもあったので参加した。(本田氏の著作はすべて読んでいる)ライブの最初は、(株)ピークパフォーマンス 代表取締役 平本相武氏の「ハイパワー・モチベーションLIVE!」。早稲田ラグビー部の中竹監督のメンタルサポートをやっていると言っていた。早稲田の強さはこんなところにもあるのだろう。続いて山根亜紀子氏の知識ゼロからのまるわかりFX講座。そして最後に「マネーの教養 スペシャル対談 泉正人&本田直之」であった。泉氏は写真で見た印象と違い、スマートな感じ。これは本当に意外だった。左足を昨日ねんざしたとか。髪型は小泉元首相のような感じ。本田氏は雑誌で何回か見たが、レバレッジシリーズを書いている印象はない。この寒さの中、グレーのTシャツにGパン。長髪を後ろで縛るヘアスタイルで登場。ここでは成功するための10のファクターについて泉氏と本田氏が対談というよりは、それぞれが解説するというスタイル。10のファクターは以下のとおり。(1)お金に働かせる考え方を持つ労働収入=会社依存⇒個人サバイバルの時代、労働収入以外の収入が必要な時代に(2)勉強して自分で判断できるようになる本を読む習慣を持つお金の勉強は、その必要がでてきてからでは遅い。今から始めるべき(3)小額でいいから実践して経験する勉強では得られない、自分の投資にあたっての性格を知るということ自分を客観的に分析する(4)家計簿とバジェット(予算)をつける自分のお金の流れを分析するこれをやらないとお金にアバウトになってしまうバジェットが資産が増える仕組みに(天引預金)(5)ストック型(B/S)の思考を持つフロー型=労働収入ストック型=積み上げればよりリターンが得られる(勉強もこれ)パーソナルキャピタル 自分資産を増やす⇒余裕ができる(6)自分に向いている投資を探す性格にあったもの本田氏;REIT(流動性が高い)泉氏;不動産おおきなうねりで投資を判断1~5年後は今からよくなるか、悪くなるか、の大雑把なレベル(7)良いアドバイザーを見つけるこれも必要になってからでは遅いもらうだけではダメ。相手に提供できるバリューは何か。アドバイザーが正しいか見極めることも大事(8)素直さ素直に学ぶ意識が重要である(9)明確な目標を持つ行き先を決めるプロセスが決まる行動が決まる意志が動く目標は大きく持つ「何のために」目的も必要(10)時間を効率的に使う時間は貯める、借りる、稼ぐことができないしかし平等に与えられたもの効率的につかうことはできる時間に対する考え方を変える本を読む時間がない⇒本を読まないから時間がない可処分時間=自分で使える時間⇒自己投資に充てるお金で買えるもの(1)自由(2)余裕考え方を変えれば複利の効果で効いてくる。こんな感じであった。最近まではあまり知らなかったのだが、WEBで調べるとこのようなセミナーは意外と多く開催されている。やはり名古屋よりは東京が圧倒的にチャンスが多いのだが、これからも積極的に参加していきたい。なぜなら周りにいる人たちの意識がとても高く、良い刺激になるからである。今日、隣に座った人と話したが、ジェームス・スキナーのセミナーにも参加したことがあると言っていた。実は私も参加したいと思っているセミナーなのだ。名古屋での数少ないチャンスを少しでも生かしていきたい。
2008/01/20
コメント(0)
-

「もうひとりの自分」とうまく付き合う方法 石井裕之
心のブレーキのはずし方、心のDNAの育て方に続く第三弾。人間の潜在意識との上手な付き合い方について明快に解説。何となく無意識に感じていることも、こうして書面で読めば一層理解が深まる感じがする。主な内容は以下のとおり。 もう一人の自分 いつもの自分とは違う 損得を考えない 二人の自分が矛盾 当たり前の事ができなくなる 潜在意識 もう一人の自分 上手く付き合うことが必要 ひっくり返っている 心の支点 目標の明確化 通訳になる⇒英語の勉強をする 自己暗示 ひっくり返っている 主客の関係 人を徹底的に褒める 自分に自信がつく 人を褒める=自分を褒める 逆順 ひっくり返っている 時間の流れ 潜在意識は意識と逆 意識を潜在意識の流れと揃える 逆からやる 逆読書術 逆ノート術 毎日生まれ変わる 睡眠により生まれ変わる 休む=潜在意識に任せる アファメーション 肯定的な自己暗示の文章 繰り返しのリズム 無条件に潜在意識に入り込める 習慣こそが最強のアファメーション 振り回される 決断ができない人 小さな決断を軽んじない どうでもいいことも 自分で決める 言霊 言葉だけではダメ 言葉と結果のセットを繰り返す できないこと、やる気のないことは口にしない 私の言葉は実現する 実現することを言葉にする 潜在意識にわからせる 実現できる目標を実行する 目標+実現の繰り返しのリズムが生まれる アファメーションが構成される
2008/01/14
コメント(0)
-

きっと、よくなる!2 「お金と仕事」編 本田 健
世界的カリスマコーチであるアンソニーロビンスの著作の翻訳で有名な著者書き下ろし。2005年に続き第二弾。今回は副題にもあるとおり「お金と仕事」に焦点を絞っている。全般に亘り良いことが書いてあるが、特に印象にのこったのは以下の内容。「運をコントロールする方法」意識してツキのある状態を保っておくための五つの秘訣1.自分のまわりを大好きなもので満たすこと2.自分の好きなことをやって時間を過ごすこと3.運のいい人とつきあう4.人を日常的に喜ばせること5.感謝すること'08/1から東京、名古屋、関西で本田健氏の講演があるとのこと。興味あるかたはここを参照。
2008/01/14
コメント(0)
-

雨がふってもよろこぼう!~人生が良い方向に向かう!心を鍛える25の習慣~ 嶋津良智(しまづ よしのり)
子供は大人を見ている。最近キレ子供が増えているというが、悪影響を与えているのはキレやすい大人なのではないか?雨がふっても喜ぶ、そんなおおらかな人生を歩んで行きたい。本書のポイントは以下のとおり 心を変える 人生が変わる 受け取り方を変える 考え方を変える 過去も変わる 怒らない 心や感情のコントロールができる 怒らないを選択する 3つのルール 命と時間を大切にする! 怒りは時間の無駄 怒っても結果は同じ 人生は思い通りにいかない! 思い通りにいかないのは楽しいこと 妥協は悪いことではない しかし一つでも減らしていく 苦悩と喜びはパッケージ 後年の活躍は苦労と失敗のおかげ 苦労の経験が成長させる 怒る人は早死する 胃潰瘍、高血圧、糖尿病、 不眠、膠原病、ガンにつながりやすい 結果よりプロセスが大切 輝きをえるために苦労や困難が必要 人はプロセスから学ぶ生き物 人生の免疫力 早い段階での失敗、挫折 免疫力がついてくる 子供には失敗させよう! ゴネ得はイヤな思いをする プロセスを省略しても得るものは少ない 人間はプロセスから学び、成長する 一つ一つの積み上げが大事 怒ることを決めるのは自分 目の前の出来事に意味はない 人の心を左右するのは受取り方 意志決定の質が人生の質を変える 感情はコントロールできる 価値観の違いを受け入れる 自分の受け止め方を変える 怒りは脳の老化現象 心の老化が怒りの原因 人生の成果 考え方、心構えによって変わる 根の部分;ものの見方、考え方、心構え 幹の部分;知識、スキル、テクニック 枝葉の部分;行動、態度、姿勢 実の部分;成果 何のために生きているか どう生きるか その考え方によって人生が変わる 何があってもよろこぼう 目先の損得で考えない 全体的、グローバルな視点で考える これが自分の繁栄につながる 他人は変えられない 自ら動こうとする環境をつくる 一流と二流の違い 成功者は感情コントロールの達人 怒りは無謀をもって始まり後悔をもって終わる 他人のせいにしない 物事は何も解決しない 自己責任、当事者意識 49対51の法則 良い悪いはギリギリの感覚 善の心を養う訓練 赤信号を渡らない 子供の見本になる 余裕のある人生を送る 自分の欠点を利用する 自分なりの解決策を持つ 目標は低く設定 やり遂げるという達成感を味わう 小さな習慣から始める 脳の体力を高めることから始める 三合主義 助け合い 分かち合い 譲り合い 価値観メガネ 事実の見方を変える 物事の捉え方を変える
2008/01/06
コメント(0)
-

カモメになったペンギン ジョン・P・コッター (著), 藤原和博 (著), 藤原 和博 (監修)
カモメになったペンギン ジョン・P・コッター (著), 藤原和博 (著), 藤原 和博 (監修)本書は、コッター氏のベストセラー『企業変革力』のエッセンスである「変革を成功させる8段階のプロセス」をペンギンの寓話にしたもの。温暖化によりペンギンが住む氷山が崩壊の危機を迎えようとしている事態に直面し、ペンギンがいかに危機的状況を乗り切るかを組織の変革という観点から物語にしたもの。会社で仕事を回すうえで、基本的な事項が良くおさえられていて読んでいて痛快である。書かれているポイントは以下のとおり。好奇心を持って観察するキーマンに話す現地現物で確認する危機意識を共有する視覚に訴える対策チームを組成する適切なメンバーを選定するチームをまとめるビジョン・戦略を考えるビジョン・戦略を周知する障害を取り除く短期的な成果を出す更に変革を進める変革を根付かせる新しい文化を築くこんな感じ。なかなかの良作と思う。カモメになったペンギン ジョン・P・コッター (著), 藤原和博 (著), 藤原 和博 (監修)
2008/01/06
コメント(0)
全14件 (14件中 1-14件目)
1