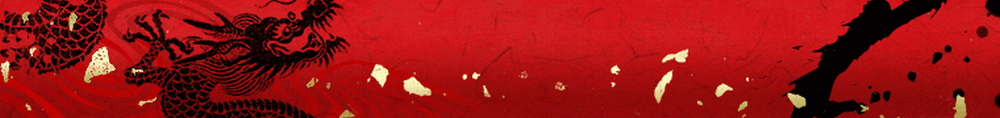カテゴリ: カテゴリ未分類
一言で沖縄民謡と言っても、(よく言われることだが)沖縄本島の音楽と、八重山の音楽では大いに違う。
だから、いわゆる「沖縄民謡」というくくりで聞きにきた人に八重山民謡を聞いてもらう時、演奏する側もとまどいが生じる。
やちまた道、あることに気づいた。(たいしたことではないけれど…)
八重山民謡には「月」の唄が多いということ。一般に南国沖縄をイメージさせる太陽(ティダ)とは、ここに大きな違いがある。
「とぅばらーま」もそう。「月ぬ真昼間(まぴろーま)」しかり。そして「月夜浜」、「月ぬかいしゃ」…。(う~ん、みんな心に響くいい唄やね。「まぴろーま」という語感だけでしびれてしまう。ぜひ月夜に聞いて欲しい。)
日本人(あえて「日本人」と言わせてもらいます)の心音(心根)にある「月」とは何か。(やちまた道、最近この心音(=心根)という造語が自分で気に入っている。)
ひとつには、「夜の静寂(しじま)」の象徴であること。
人生には昼もあるが、夜もある。この当たり前のことを心の奥深くに示してくれるのが、「月」の存在である。
ふたつ目には、「はかなさ」である。
みっつ目には、なにか「霊的なもの」。
「つくぃ」とは「憑く」から来ているとか…。 本当がどうかわからないが、結構気に入っている。なにかに取り憑かれ、なにか降りてきていると言う感覚か…。
さらには、「満ち欠け」。
陰と陽。片割れを恋い求める半欠けの月。100%全きものではなく、ちょっと欠けた十三夜に美を求める感覚。大海の満ち引きのように、生と性をつらぬく大いなるうねりとリズム。
そして、「反照」であるということ。
「自ら」輝くのではなく、「我」を主張するのではなく、「他」から照らされた時だけ、その美しい姿を現す。厳しい搾取の歴史の中でじっと自分を押さえ耐えながら生きてきた八重山の人々の慎ましい心音(心根)を、「月」の唄たちはやさしく静かに奏でてくれる。
八重山民謡を唄う唄者たちは、「月」を唄う心があるか…。
これは、とても大切なことだと思う。
だから、いわゆる「沖縄民謡」というくくりで聞きにきた人に八重山民謡を聞いてもらう時、演奏する側もとまどいが生じる。
やちまた道、あることに気づいた。(たいしたことではないけれど…)
八重山民謡には「月」の唄が多いということ。一般に南国沖縄をイメージさせる太陽(ティダ)とは、ここに大きな違いがある。
「とぅばらーま」もそう。「月ぬ真昼間(まぴろーま)」しかり。そして「月夜浜」、「月ぬかいしゃ」…。(う~ん、みんな心に響くいい唄やね。「まぴろーま」という語感だけでしびれてしまう。ぜひ月夜に聞いて欲しい。)
日本人(あえて「日本人」と言わせてもらいます)の心音(心根)にある「月」とは何か。(やちまた道、最近この心音(=心根)という造語が自分で気に入っている。)
ひとつには、「夜の静寂(しじま)」の象徴であること。
人生には昼もあるが、夜もある。この当たり前のことを心の奥深くに示してくれるのが、「月」の存在である。
ふたつ目には、「はかなさ」である。
みっつ目には、なにか「霊的なもの」。
「つくぃ」とは「憑く」から来ているとか…。 本当がどうかわからないが、結構気に入っている。なにかに取り憑かれ、なにか降りてきていると言う感覚か…。
さらには、「満ち欠け」。
陰と陽。片割れを恋い求める半欠けの月。100%全きものではなく、ちょっと欠けた十三夜に美を求める感覚。大海の満ち引きのように、生と性をつらぬく大いなるうねりとリズム。
そして、「反照」であるということ。
「自ら」輝くのではなく、「我」を主張するのではなく、「他」から照らされた時だけ、その美しい姿を現す。厳しい搾取の歴史の中でじっと自分を押さえ耐えながら生きてきた八重山の人々の慎ましい心音(心根)を、「月」の唄たちはやさしく静かに奏でてくれる。
八重山民謡を唄う唄者たちは、「月」を唄う心があるか…。
これは、とても大切なことだと思う。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.